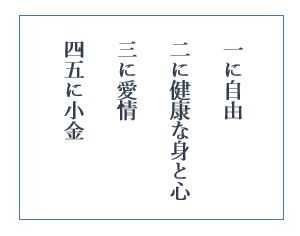2006年04月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
ハナミズキ
何度も欲しいと思っていたハナミズキの苗木を、鎌倉の市場で見つけたとき、それが花開いた様を想像し、わたしは嬉しくてたまらなかった。 元気良くすっと上に伸びた苗木は、いかにもちゃんと根付きそうに見えた。 でも抱えて電車に乗るには、少々憚られる背丈をも持っており、やはりわたしは断念せざるをえなかった。 それでも後に、あの時買っていたならば、と何度臍をかんだことだろう。 それほどハナミズキは、わたしの好きな花なのであった。 昔住んでいた家の、小さな猫の額ほどの庭は、それこそ雑多に植栽されていた。 今様のガーデニングには程遠く、食べた柿の種から育った柿の木や、義母がところ構わず増やした沈丁花、近所の人たちと交換し合った一年草の草花、そして食用のニラなどが、にぎやかにひしめき合っていた。 だから一体、どこにハナミズキを植える場所があったのか、と苦笑してしまうのだけれど、わたしは庭にハナミズキを植えたかったのだ。 そこから最寄り駅まで行く途中に、ハナミズキの大木を持つ家があった。 偶然散歩の途中で見つけてからは、花の季節には必ずその道を通ったものである。 更に枝垂桜を持つ家や、モッコウバラを玄関先に咲かせる家もあり、わたしはその通りをひそかに花の道と呼んでいた。 そもそもハナミズキを植えたいと思い、好きになったきっかけが、その大木にあった。 ゆうに塀を越えたハナミズキは、堂々と枝葉を伸ばし、凛とした樹木の美しさを感じさせた。 まさにわたしは、樹木の美しさにほれたのであった。 ところが、そのほれた木は、花をつけたのである。 白い、まるでつばの広い帽子のような花をつけて、悠然としていた。 あまりに気品に満ちた花にわたしは足を止めて、じっと眺めた。 生まれて初めて、ハナミズキに遭遇した瞬間であった。 人間世界の、雑多なわずらわしいことなど無関係とでも言いたげに、その気品に満ちた花は咲いていた。 花が終われば、夏の陽射しを和らげる葉が茂り、家の軒先を強い日差しから守った。 なんて素敵な空間を提供してくれるのか、とその家の前を通る度に、我が家の庭にハナミズキという願望が膨らむのであった。 (続く)
2006年04月21日
コメント(3)
-
携帯メール
高校の友人からメールが届いた。 「近くの桜が満開になりました。今年は母の桜を見に帰らないのですか?帰ったら連絡をください」と結んであった。 この時季になると、わたしが書いたエッセィ『母の桜』を思い出すらしい。 リクエストに応えて掲載してみた。 故郷には、まだわたしのことを思い出してくれる友達がいる。
2006年04月09日
コメント(2)
-
棘(些細な出来事)
ほんの些細な出来事だけど、母を思い出した。 その時の、母の気持ちを知るまでに、わたしはこんなにも多くの時間を費やしたのかと思った。 まだ母が生きていた頃。 久しぶりに帰った実家で、母が悲しそうにこう言った。 「腐らせてしまうのなら、どうして声をかけてくれなかったのだろう。別に食べたいわけじゃないけど、なんだか悲しい」と。 実は、当時未婚だった末の妹のことである。 カビの生えた和菓子が無造作に、彼女の部屋のくず入れに入っていたのだった。 わたしは、こんなことを気にする人だったかしら?と、まるで意に介さなかったのだけれど、なぜかこの母のセリフが胸に残っていた。 時は経ち、場所は我が家へと移った。 本当に些細なことである。 「あら。スープがある。飲もうっと」 いきなりお湯を沸かしているわたしの背後から、 「それは駄目。わたしのだから」 次女の一声がかかった。 「あら、そう」 わたしはお湯を沸かすのをやめて、冷蔵庫を覗き込んだ。 「あ、シーマだ。飲んでいい?」 これも次女が持ってきたものだった。 でも二本あったからその一本を飲みたいと思った。 「あたしの好物だから買ったきたのに、駄目」 実は次女との間に、こういう些細なことがずっと続いていたのである。 言葉に暖かさが微塵も感じられなかった。 余りに、一晩泣いてしまった夜もあった。 こんなことに引っかかってしまう自分の気持ちの弱さに、とても腹立たしいのである。 そんな折、母のあの日のシーンが浮かんだ。 母は、こういう気持ちを表現したかったのだ、と。 食べたいものがあれば買ってくれば良いのだし、そんなに大したことではなかったのに、その背後に潜む小さな無意識という棘に、傷ついていたのだった。 あの時の母の気持ちは、今でも末の妹には通じていないだろう。 その場にいなかったのだから…。 次女にこの気持ちが分かるまで、また多くの時間がかかるのか、とわたしはひとり苦笑する。
2006年04月09日
コメント(4)
-
桜(母の命日)
今日は大好きな母の命日。 母が桜の花びらと共に散って、もう17年の歳月が過ぎた。 生きていたら90歳はゆうに超えているのだけれど、わたしの中の母は、やはりあの階段をとんとんとんと一気に駆け上る若き日の姿が浮かぶ。 働き者で、貧乏のどん底にあっても弱音を吐いたことがない。 『貧乏人の子沢山』とはよく言ったもので、七人の子供を持てば稼いでも稼いでもお金が足りない、という日々だったに違いない。 それでも一度も嫌な顔を見せたことがないのだ。 見るに見かねた親切な隣人に、養子に出してはどうかと打診されたこともあったそうである。 でもは母きっぱりと断った。 一人娘で何不自由なく育った母は、その寂しさを誰よりも知っていたからだった。 二人の娘の子育てにさえ、時折息切れをするわたしは、母ならどうしたであろう、あの時どうしてくれたっけ、といつも母の姿を思い浮かべるほど、今でもわたしの人生のバイブルだ。 それにしても、やはり母には手が届かない思いがしている。 些細なことで揺らぎ、娘の恋愛でおたおたしてしまう自分がいる。 母が生きていたなら、なんていうだろうか? 「ケイちゃん。娘を信じなさい」って、笑うだろうか。 「母さん、わたし美人?」って聞くと、 「美人じゃないけど、あなたは可愛いよ。性格がとっても可愛いよ」 と笑った。 「嘘でも良いから、一度で良いから、美人だと言ってよ」 「だから、美人じゃないけど可愛いってば」 こんな調子で、絶対に美人だとは言ってくれなかったけれど、わたしは母の深い愛情を感じていた。 母のまっすぐな気持ちは、いつもわたしのハートに届いていたことを、今懐かしく思い出す。 母に一度もけなされたことのない自分の人生を振り返ると、偉大だった母にどこまでも頭が下がる。
2006年04月02日
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1