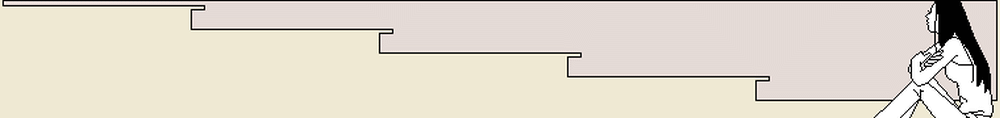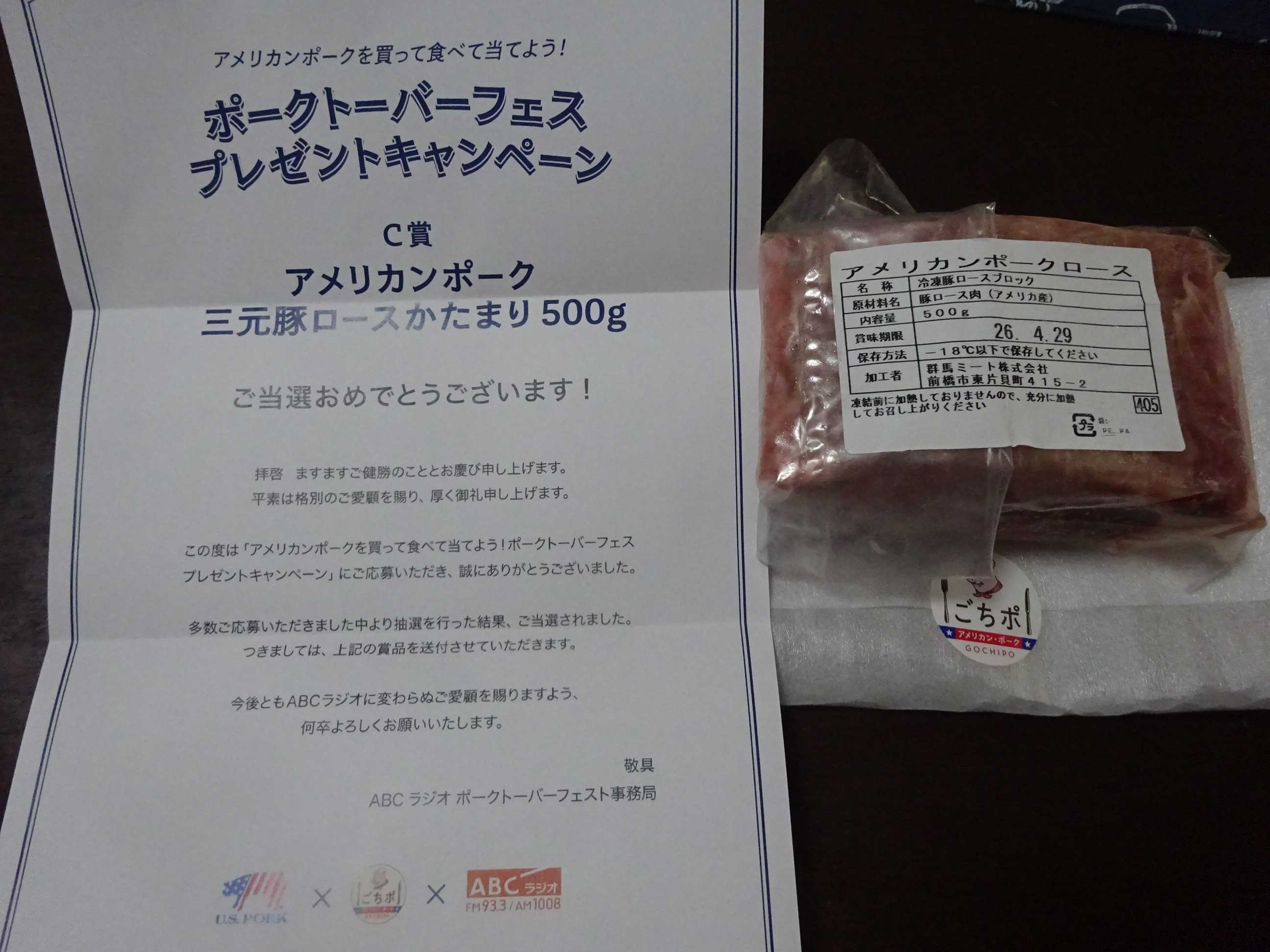2019年07月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

烏瓜の花
「ウリ科の蔓性多年草。山地に生える。雌雄異株。夏、白色で縁が糸状に避けた美花を夜に開き、晩秋、実が赤く熟す。果肉は荒れ止めの化粧水を作り、種子は薬用・食用。塊根から採った澱粉は天花粉の代用、生薬の土瓜根(どかこん)として利疸・利尿・催乳剤として用いられる。」初めて烏瓜の利点を知って驚いている。此の花を見る度、艶やかな夜会服の様に思うのは私ばかりではあるまい。 夜会服のやうなからすうりの花 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、烏瓜の花
2019年07月31日
コメント(0)
-

百日紅
百日紅は幹の皮が滑らかなので猿でも滑るという意味がある。夏から秋に紅色または白色の小花が群がり咲く。漸く梅雨が明け、百日紅の似合う暑さとなった。暑いのは好きではないが寒いよりは我慢できるのは京都の盆地で育ったゆえんである。百日紅を見ながらハンカチで汗を拭き野川沿いを散歩している。昨日みんみん蝉が鳴いた。 日矢を吸ひ紅を増したる百日紅 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、百日紅(さるすべり)
2019年07月30日
コメント(0)
-

灸花
「子供たちが灸に擬して遊ぶところからこの名がついた。」と辞書にある。ヘクソカズラの別称。アカネ科の慢性多年草。葉は楕円形。全体に悪臭がある。私の子供の頃は両親は肩凝りや腰痛に灸を据えていたが、今の子供はこのことは知らないだろう。 肩凝りの母でありしよ灸花 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、灸花・屁屎葛(ヘクソカヅラ)
2019年07月29日
コメント(0)
-

祭
昨日野川沿いを散歩していると浴衣の子を自転車に乗せて駅方面へ向かっている家族連れに出合った。駅近くには太鼓の音がかすかに聞こえてきた。これは見に行くしかないと、駅へ向かった。果たして駅前の北口、南口の広場には大勢の人が集まり、かき氷や綿菓子のテントに列ができていた。踊り櫓も組まれ、踊子(中年の女性)も30人ほど控えていた。中でも少女達の着物姿が美しく目に焼き付いた。 をみな子の髪結ひあげし祭かな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・宗教、祭・商店街祭
2019年07月28日
コメント(0)
-

空蝉
4日ほど前から野川沿いの桜並木に蝉が鳴き出した。にいにい蝉である。夕風に乗って蝉の声は涼しげである。この空蝉はマンションの植え込みに落ちていたものを拾ってきて夫の愛車に乗せた。色がブルーなので、CB92かCR71であろう。空蝉のハンドルさばきは上々である。 空蝉のハンドルさばき夫に似し クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、空蝉
2019年07月27日
コメント(0)
-

プール
子ども達は夏休みに入った。マンションの敷地内のプールが開かれ子ども達が水飛沫を上げ、黄色い声を上げている。今日は珍しく朝から日が差し絶好のプール日和である。 子ども等のプールの声を網越しに クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・人事、プール
2019年07月26日
コメント(0)
-

赤楝蛇
へびの一種。全長70~120センチメートル、水辺に普通にカエルなどを捕食する。毒牙を持っているので深く咬まれると、腫れることや血が止まらないこともあり、時に致命的なので注意。野川沿いを散歩していて発見。未だ子どもの様で細い。 赤楝蛇人の気配に動きたる クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、赤楝蛇(やまかがし)、野川
2019年07月25日
コメント(2)
-

飛蝗生る
野川沿いを歩いていると日ごとに何かが消え、何かが現れる。昨日も葉っぱの上に負飛蝗が生まれていた。傍に未だ殻が残っていたので生まれたところであろう。 少し日の差して来(きた)る日飛蝗生(あ)る クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、飛蝗生る
2019年07月24日
コメント(0)
-

ブーゲンビレア
オシロイバナ科イカダカズラ属植物。南米に分布。枝にはとげがつき、卵形で先がとがった葉を互生し、先端に3枚の苞をつける。紅色のは知っていたが、マンション1階にある花屋に桃色のものが出ていてびっくり。 晴れよかしブーゲンビレア咲きたれば クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、ブーゲンビレア
2019年07月23日
コメント(0)
-

緋鯉
昨日は選挙と句会、その後の暑気払いと忙しなかった。しかし、雨にならなかったのが何よりもの救いとなった。そして句会は楽しく、暑気払いは賑やかに過ごせた。睡蓮と河骨の池には釣台があり、そこから池を見渡していると緋鯉が悠然と姿を見せ大きく翻って行った。 釣台に来て翻る緋鯉かな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、緋鯉
2019年07月22日
コメント(2)
-

河骨
スイレン科の多年草。沼沢などに自生。根茎は太く横臥、水上に露出する。夏に長い花柄を水面に出し、黄色の1花を開く。睡蓮が沢山咲いている池に一つの島が出来河骨が咲いていた。まるで人の握り拳の様で思わず拳を高々と上げてみた。 河骨や思はず上ぐる我が拳 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ今日は句会の前に選挙、句会後に暑気払いと忙しい。 俳句・夏・植物、河骨(こうほね)
2019年07月21日
コメント(0)
-

梅雨茸
とある杜を歩いていて梅雨茸を発見、渡邉和夫さんのブログによれば針金落葉茸とのこと。なるほど傘は針金が集まったように見え、この茸の回りは落葉を敷き詰めた様に拡がっている。 梅雨茸を数へ数へて二三百 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、梅雨茸・針金落葉茸
2019年07月20日
コメント(0)
-

藪甘草
7~8月咲き道沿いや土手や明るい草原に生えるユリに似た半八重のオレンジの花。花径10cm大1日花で翌朝にはしぼむ蕾をたくさんつけ次々と開花する。同属のヘメロカリス野甘草も同様で一重の花。ようやく雨が上がり日が差してきた。室温27度、湿度80%と蒸し蒸ししていたのでエアコンを1時間ほどかけたら気温25度、湿度59%とになり快適になった。 耀うて藪甘草の雨しづく クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、藪甘草
2019年07月19日
コメント(0)
-

向日葵
向日葵は日に向かって咲くと書く。雨の向日葵はどこを向いて咲いているのであろう。午後1時頃の室温は26度、湿度83%とと蒸し暑い。 雨かづき向日葵の咲く小径かな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへニュースで祇園祭が報道されないので、以前録画した祇園祭を見て懐かしんでいる。 俳句・夏・植物、向日葵
2019年07月18日
コメント(0)
-

梅雨深し
当地はこのところ日差しがない。しかし雨が降るといっても雨脚は強くないので夕方傘を差したり、手に持ったりしながら散歩をしている。その後ろからジョガーが追い越していく。彼等・彼女等は帽子をかぶり濡れながら走っている。 梅雨深し神明橋を往き還りところで昨日は我が故郷の祇園祭の宵山、今日は山鉾巡行。祇園囃子が恋しくうずうずしている。 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・天文、梅雨深し、野川神明橋
2019年07月17日
コメント(0)
-

青鷺
昨日は青鷺を三羽見た。一羽は野川の真ん中に彳ち餌を狙っていた。あとの二羽は野川の上空を飛んでいた。番か、恋鳥かともと思って見送った。一時間の散歩を終えて青鷺を見たが未だ同じ処に彳っていた。傍にいた軽鴨はもうそこにはいなかった。 青鷺やそんなに野川棲みよいか クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、青鷺、野川
2019年07月16日
コメント(2)
-

木苺
とある家の垣根に木苺がなっていた。大粒で紅く色づいている。もう少し熟れると黒紫色になる。子どもの頃、野の木苺を食べたことがあり、家に帰ると「あんた木苺食べたやろ」と、「何でわかるの」と訊ねると、「かがみ見てみ」と言われた。幼い頃の思い出である。 木苺を盗るには少し歳とりぬ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、木苺
2019年07月15日
コメント(0)
-

梅雨晴
神明橋の上流で男性が網を翻しながら何かを採っていた。ふと川沿いの柵を見ると東京都の「特別採捕許可」の幟がはためいていた。男性は河川の生物の調査員と知れた。こうして野川の生態系が守られているのだと理解した。 梅雨晴や野川を漁る調査員 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・天文、梅雨晴、野川、特別採捕許可
2019年07月14日
コメント(0)
-

守宮
有鱗目ヤモリ科の爬虫類の総称。多くは夜行性・食虫性で、鳴くものもある。壁や天井などに貼りついて移動する。夜出て、昆虫を捕食。毒はない。野川沿いを散歩していた時川沿いの柵に守宮が貼りついていた。午後5時過ぎ、未だ回りが明るいのでカメラを向けても動く気配はなかった。 逆さまに貼りついてゐる守宮かな クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、守宮(やもり)、野川沿い
2019年07月13日
コメント(0)
-

五月雨
昨日の散歩の時間は雨だったので径を変えて国分寺崖線沿いを歩いた。かっては螢が飛んだ神明の森三ツ池から野川へ注ぐ小さな川に沿って歩いていると檜扇水仙が今を盛りと咲いていた。檜扇水仙はアヤメ科の多年草。夏に6弁の花を多数、花穂につけ、花穂はややジグザグになる。モントブレチアともよぶ。 五月雨や濡れそぼちたる朱き花 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・天文、五月雨、檜扇水仙
2019年07月12日
コメント(0)
-

夏萩
昨日の暑気払いは男性1人、女性8人。女性はご主人の夕食の準備をすませての参加なので、どっしりと構えておしゃべりに夢中。ビールを飲めない女性2人も楽しそう。蕎麦屋と意っても酒の肴が豊富なのが良い。この時季決まって水茄子の漬物がでる。写真はきたみふれあい広場の夏萩。風がなくても揺れているが、風が吹けば尚風情がある。 夏萩の揺るる呼吸に合はせ撮る クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、夏萩、きたみふれあい広場
2019年07月11日
コメント(0)
-

紫式部の花
室温24度、湿度76%とと何となく肌寒い。こんな日が続くらしい。梅雨寒である。今日は野川句会の日。野川沿いもさぞ寒いことであろう。句会後には場所を移動して暑気払いもあり、この寒さでは盛り上げに欠ける。でも女三人よれば何とかで心配は無用かも知れない。野川沿いに紫式部が咲いていた。 雨ほつほつ式部の花のほつほつと クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、紫式部の花・式部の花・花式部、野川
2019年07月10日
コメント(0)
-

黄金虫
7月7日は小暑だった。その二日後の今日は室温24度湿度74%と過ごしやすい気温である。外は曇りで風がある文部屋の中より涼しい。外階段に黄金虫がいて手を伸ばしたら動いたので、草叢に逃がしてやった。 黄金虫に手相いかにと問うてみん クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、黄金虫
2019年07月09日
コメント(0)
-

睡蓮
我が家から徒歩5分のところにきたみふれあい広場がある。平日の昼間はほとんど人がいないが、平日の夕方や土日には幼児を連れた家族連れで賑わう。象さんの形に滑り台は子ども達に人気である。またとんぼ池には紅白の睡蓮が咲き、時々鯉が睡蓮を揺らして過ぎる。もちろん水馬もいる、時には川とんぼも飛んでいて此処も子ども達の格好の遊び場でもある。 睡蓮の睡らぬ刻を私す クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、睡蓮・羊草、きたみふれあい広場
2019年07月08日
コメント(0)
-

草刈
一泊二日の大山(だいせん)の旅を終えて帰ってきた。野川は草刈りの真っ最中。上の写真、草刈りの職人が女性なのは珍しい。 膝折りて鋏遣へり草刈女 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・人事、草刈、野川
2019年07月07日
コメント(0)
-

六月
弓ヶ浜妻木晩田遺跡(晴天なれば)次に訪れたのは鳥取県西伯郡大山町妻木115ー4にある鳥取県立むきばんだ史跡公園。入場無料なのがよい。ボランティアの方にガイドしてもらた。この方も無料。 中国地方の最高峰・大山の麓に甦った弥生時代の国邑、それが妻木晩田遺跡です。 遺跡のひろがりは鳥取県米子市・西伯郡大山町にまたがる晩田山丘陵全域におよび、弥生時代 に大山山麓に存在したであろうクニの中心的な大集落であったと考えられます。 現在、全体のおよそ1/10が発掘調査されています。その結果、弥生時代中期末(西暦1世紀前 半)~古墳時代前期(3世紀前半)にかけての、竪穴住居跡約450棟、掘立柱建物跡約510棟、 山陰地方特有の形をした四隅突出型墳丘墓などの墳墓36基や、環壕など、山陰地方の弥生時代 像に見直しをせまる貴重な資料がたくさん発見されました。(とりネットより)入り口の板に頭を打ち付けないように竪穴住居に入る。中は広々(20名位は入れそう)としていて雨が入らないように回りに盛り土がしてある。茅葺きなので、茅に虫がこないように燻す小さな炉があった。息を深く吸い弥生時代の香しい匂いに酔いしれた。四隅突出型墳丘墓は、土で覆われていて、その下に実際の墳丘墓があるとのこと、子どもの小さな四隅突出型墳丘墓もあった。そこを西へ向かって進むと右手に弓ヶ浜が弓なりに拡がっていた。弓の先は美保神社のある美保湾である。晴天なら遙か彼方に隠岐の島が見えるとのこと。この日は海霧(じり)が立ち籠めていて残念ながら見ることが出来なかった。 俯瞰して六月果の弓ヶ浜 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・時候、六月、妻木晩田遺跡、弓ヶ浜
2019年07月06日
コメント(2)
-

苔茂る
大山寺へは長い石段を登り、お参りをした。大神山へは登らずに左手の脇道を下った。途中「無名の橋」があり、仲間が無名ではなくちゃんと「無名」と名がついているなどと皆を笑わせた。坂の敷石は濡れて滑りそうであったが無事下ることができた。坂が終わった左手に「暗夜行路」の碑が建っていた。碑はご覧の様に苔が茂り、背景の山毛欅林は夏霧に包まれていた。『暗夜行路』は志賀直哉の唯一の長編小説である。大正10年に、雑誌・「改造」に前編を発表してから16年たった昭和12年にやっと奈良の自宅で書き上げた。 主人公の時任謙作は、祖父の妾だった女性と分家住まいをしながら気ままに暮らす作家志望。旅先の尾道で自分が祖父と母との間に生まれた不義の子であることを知らされ衝撃をうける。その重い心は京都で見初めた直子との結婚で和らぐのだが、留守中にその直子が幼なじみの従兄弟と過ちを犯したことがわかってまた悩む。許すべきであるのに許しえないことへの葛藤。謙作は山陰の旅に出る。大正3年のひと夏、志賀は大山で過ごした。その思い出が「暗夜行路」のヤマ場として描かれる。小説にも実名で登場。志賀が滞在した宿坊「蓮浄院」を訪ねたかったが時間の都合で断念した。その蓮浄院の裏手に登山口があり、謙作たちが登った大山への登山道である。 苔茂る「暗夜行路」の碑にまみゆ クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・植物、苔茂る、・大山寺・志賀直哉『暗夜行路』
2019年07月05日
コメント(0)
-

夏の霧
「木曾路はすべて山の中である」の書き出しで知られるのは島崎藤村の『夜明け前』である。大山寺に参拝し「大山路はすべて夏霧の中である」などと呟く。 夏霧に浮かび尊き大山寺 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・天文、夏の霧・夏霧、大山寺
2019年07月04日
コメント(0)
-

草清水
末次雨城句碑中里神社に、「鶴」の女流石橋秀野の山陰生活を手助けした末次雨城の句碑が建っている。末次雨城は中山町の町長で、鶴の飛鳥集作家でもあり、鶴山陰支部を束ねていた人でもある。また、私が鳥取市に住んでいたとき氏に手紙を出し教えを請うた師でもある。書肆で昭和45年2月に刊行された角川書店の『石田波郷追悼特集号』を買い求め、波郷の生き様に共感し、鳥取県で「鶴」で活躍している雨城氏を選んだいきさつがある。それ以来、鳥取市から米子の句会へ幼児3人を連れ汽車で通っていた。中里神社へはすっかり無沙汰を重ねていたが、今回図らずも〈藪縫つて春立つ濁りやまぬなり〉の句碑にまみえることができた。句碑の回りは草清水で潤っていた。 草清水雨城の句碑の匂ひたち クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・地理、草清水、末次雨城句碑、中里神社
2019年07月03日
コメント(0)
-

露涼し
石橋秀野句碑次に訪れたのは中山町の中里神社。「鶴」で活躍した女流秀野の句碑がある。句碑には石田波郷の筆で〈風花やかなしびふるき山の形〉と刻まれている。秀野の句碑は地に蹲るように置かれ美しく、大山に連なる船上山へ向いている。*補足 「船上山は山岳霊場として、和銅年間に赤衣上人か智積上人によって、智積寺として開基されたと伝えられる。南北朝時代の初めには、隠岐を脱出した後醍醐天皇を伯耆の豪族、名和長年が迎え、船上山に行宮を築いた。後醍醐天皇方の名和長年と鎌倉幕府方の佐々木清高との間で激しい戦い(船上山の戦い)が繰り広げられた古戦場である。山頂付近の蒲ヶ原には行宮碑がある。1932年(昭和7年)に国の史跡に指定された。」秀野が夫山本健吉とともに山陰の地に移り住んだのは、昭和20年4月から翌21年7月まで。肩身の狭い疎開者として窮乏生活の極みを経験したようである。〈火桶抱けば隠岐へ通ひの夜船かな〉の句に、寒々とした情景を読み取ることができる。病弱な秀野一家にには厳しい生活だったが、鶴山陰支部とのあたたかい交流があった。21年7月、健吉の京都新聞社への転勤に従い京都へ転居。疎開地の無理がたたり結核を発症。22年9月26日、三十八歳の短い生涯を終えた。(『定本 石橋秀野句文集』参照) 秀野句碑に触るる縁や露涼し クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・天文、露涼し、秀野句碑、中山町中里神社、船上山の戦い
2019年07月02日
コメント(0)
-

時鳥
この度鳥取県の名峰大山へ行ってきた。大山は鳥取砂丘と並ぶ鳥取県の自然遺産。標高1,709mを誇る中国地方最高峰である。野鳥保護区、自然林保護区にも指定されており、西日本最大級のブナ林や特別天然記念物に指定されるダイセンキャラボク、様々な動植物や昆虫など、多様な生態系を形成している。写真は大山寺からバスで訪れた「ほととぎす橋」。橋から下を眺めると山毛欅林が拡がり少し夏霧がかかっているのが解る。橋を行き戻りしていると、文字通り時鳥が鳴いた。 吹きおこる風を総身に時鳥 クリックしてね ↓ 人気ブログランキングへ 俳句・夏・動物、時鳥、大山、ほとぎす橋
2019年07月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 💡 Aqua-Terrarium Lighting Setup …
- (2025-11-21 09:32:24)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-