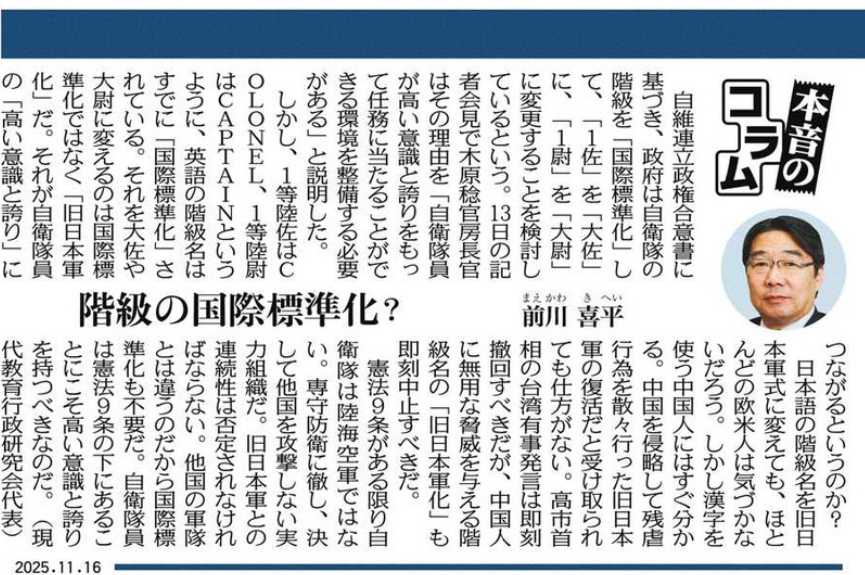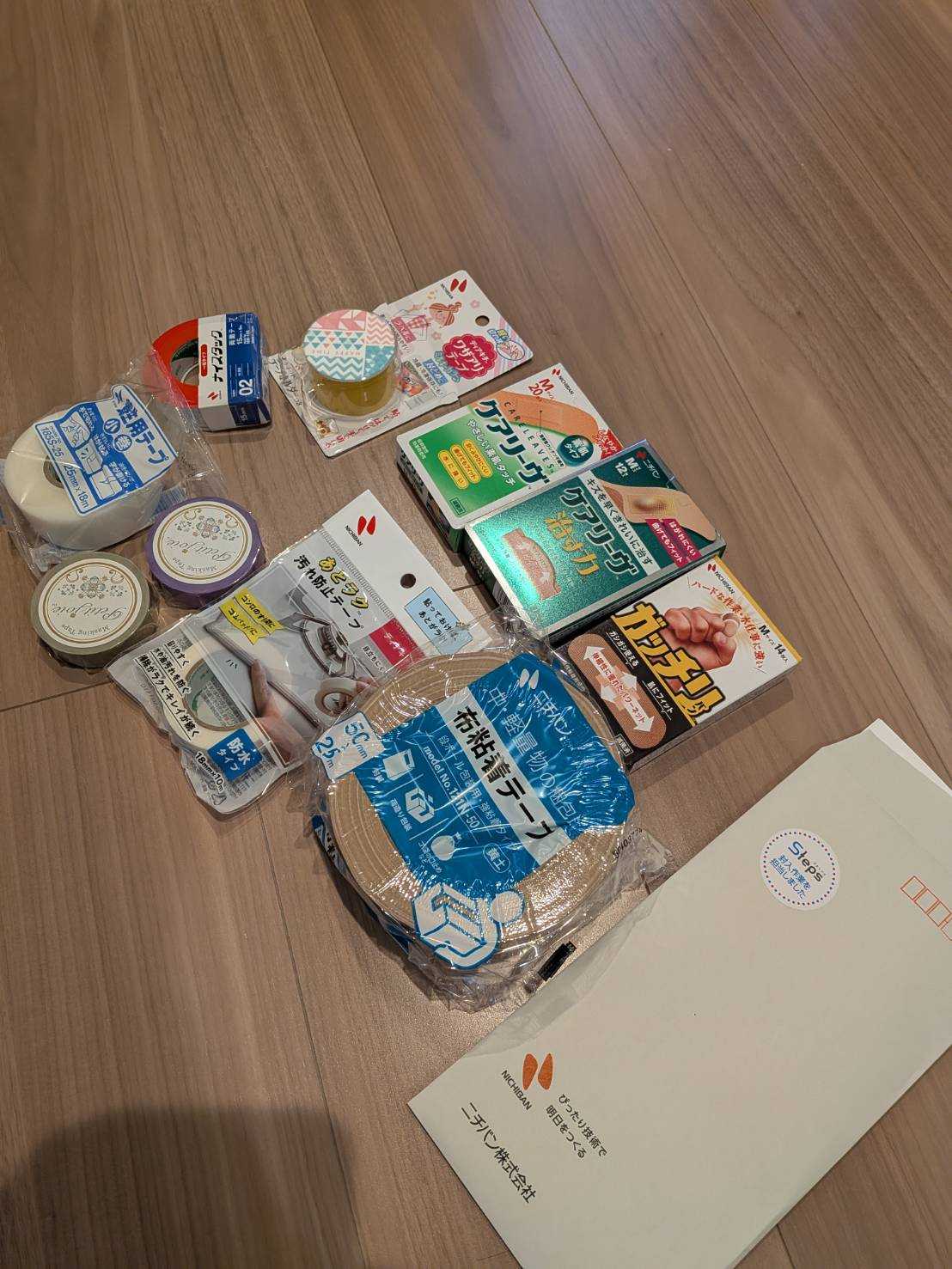2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年01月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
待てない男
ハニーと食事に行く車をレストランの駐車場にバックで留めるドアを開け車から降りるとハニーはなかなか降りてこない松 いや 待つ女性は車を降りるのにも段取りというものがあるのだ車をロックしレストランへドアを開けハニーを先に入れるフツーですウェィトレスが喫煙か禁煙か聞く勿論 禁煙店の入り口に背を向けて腰掛けるのはハニー僕は入り口方向を向いて腰掛けるこれもフツー入り口が遠ければ奥の席にハニーを座らせるセオリーレストランは家庭ではないいつ何事が起きるか解らない男はいつでも入り口に注意している必要がある何を食べるのかは、ハニーより早く決めるハニーに告げるここは待ってはいけないハニーに注文させるためにではないハニーが自分の食べるものを決めやすくするためだハニーの食べるものが決まったらウェィトレスを呼び注文は男がする食事中に携帯をいじらない会話は聞いているふりはいけない聞くだけもいけない他愛のないことでも話す話を聞いていない男が多いドリンクバーがあればスープやコーヒーは男が用意する使わなくてもクリームと砂糖は用意する食事が終わりレジへ行く代金をハニーが払っている間に車に行き、エンジンをかけておく・・などはもっての他並んで一緒にレジをすませるレストランのドアを開けハニーを先に通すフツー車までは並んで歩く車のドアを開けてやったりしてはいけないやりすぎはいけないその代わりに乗車させずに待たせ車を半分だけ前進させてから乗車させるとなりの車にドアを当てないように気をつける必要がないようにと解っているが全部出来ているわけではない男は待てない動物なのである女はどうかやっぱり待てない動物である
2010.01.31
コメント(24)
-

30日の日記
着陸時に見た水平方向の満月が綺麗でした出雲はあまり寒くなく助かりました今回はちょっと疲れました首の付け根が張ってしまって振り向けません明日 針でも行こうかな日曜日だからだめかなそうそうF邸の模型を作るのだったっけ皆さんお返事書けなくてごめんねPS出雲で 少し時間があったので宍道湖の北側をドライブしました運転してくれたかじくんありがとう住宅革命の高山邸のあるあたりです冬の山陰特有のあまり強くない太陽の光が湖面に反射して綺麗でした
2010.01.30
コメント(4)
-

それでは宿題を出します
国土交通省も東大の某教授もNEDOも勘違いしている熱橋を定義しましょうたぶん彼らはこんな現象を見て木部は断熱部よりも熱伝導率が高いから伝達された熱で濡れたものが乾いた断熱部は熱を伝えにくいから濡れたものが乾きにくいと思ったたぶん検証もせずに木部の熱伝導率と断熱部の熱伝導率の差を資料で調べ結論を導き出した木部は《熱橋だ》とそもそも熱橋とはなにか熱伝導率の差はあれ、それぞれの伝導速度の差の何パーセント以上ならば熱橋とするのかはたして木部の熱橋でドライヤーのように濡れた外壁を乾かす事が本当に出来るのか熱橋に対して外壁の通気層の存在をどう評価するのか熱橋では無い部分の濡れた状態を是とするのか通気層があれば内部結露しないなどと思っているのだろうか現場を知らない優秀な学者が数少ない事例だけで結論を導く事に大きな不安を抱きます日本の建築はまだまだ黎明期ですねいや衰退期なのかも・・・さてこの問題は卒業試験より難しそうですねみなさんの卒論のテーマにいかがですか熱伝達をどう止めるかが建築物の省エネ性のに多大な影響を与えるのですからとても有意義なテーマのひとつです
2010.01.29
コメント(8)
-
推理と真実
いろいろな現象を見てそれはなぜかと疑問を持ち仮説をたて検証するここまでは誰でもする仮説と検証が一致しなかったら再検証するこれを何度も何度も繰り返し真実に辿り着く世界で初めて証明される真実も始めは推理からそして仮説~実験~証明となる世界で初めてでなければたぶんどこかに既に結論がある先人の研究がある先人の研究を利用出来る資料の蓄積があるから人類は効率よく進化したしかし先人の研究が間違っていてそれを信じたがために途方もない遠回りをしてしまうことも少なくない科学に信じると言う要素はない先人の誤ちは地雷のように息をひそめている結論を出す前に検証しよう僕の結露の研究は開始してから15年経つけれどまだ続いてるその中で気付いた先人のミスがたくさんあります例えば熱橋国土交通省の仕様書さえ熱橋を勘違いしている先人を信じたのだろう
2010.01.28
コメント(6)
-
さーて出雲だ
出雲の物語はいずもで書くベーか行って参ります
2010.01.28
コメント(0)
-
イノベーション
イノベーションってどういう意味?と聞かれたのでググッてみた 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 イノベーションとは、新しい技術の発明だけではなく、新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革である。つまり、それまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすことを指す。 それって僕ら?
2010.01.28
コメント(4)
-

ブログ研究所その5
皆さんの応援でがんばることの出来るfsですそれにしても年齢が露骨に数字になっている蝋燭というもなんだかなー思い切り吹き消したらケーキのパウダーが飛び散って家族から非難ごうごうでした加減というものを知らないって・・さて研究課題が山積みでぜんぜん解決しないブログ研究所ですが予てからS組さんに調査を依頼されていた某住宅の壁のシミSさんのカビではないかという問いかけにそれではと壁のシミ部分を削り取り培養してみる事にしましたシャレーに寒天を作りその上に壁のシミを削り取った小さなカケラを乗せますシャレーは100℃で30分煮沸後電子レンジで5分殺菌電子レンジは便利ですかなり高い殺菌力がありますからたすかります寒天は例のスポンジ状で棒状のあれですやはりきちんと殺菌した鍋で煮とかしちょっとさめてからシャレーに入れ蓋をして冷蔵庫へ寒天が冷蔵庫で冷たくなってから検体を乗せます熱い時に乗せると検体の元気がなくなってしまいますからねシャレーは気温22℃で安定な暗所に保存2010年1月26日 午前7時現在で培養1週間です下の写真が今朝のものです白い砂状のものが検体ですが未だにカビは出ていませんこの観察はもうしばらく続けます
2010.01.26
コメント(2)
-
25日の日記
皆さんありがとう 嬉しいです また 泣きました
2010.01.25
コメント(5)
-

ブログ研究所その4
ひそかに誕生日を迎えていたfsです全然ひそかじゃないですが・・・今夜はハッピーバースデイを家族で合唱しますいつも涙がちょちょぎれます(はい、古いです)じょうしゅうのメンバーは既にはじめている筈の吸放湿実験ですがぼくは全然やっていなかったので今日始めましたといっても事務所の亀ちゃんにやっといてねって命令しただけです(面目しだいもありません)このはぎれが8月頃にはどうなっているのか楽しみですいろいろ考えたのですが生っぽい材では乾燥し続けるような気がしたのでおもいっきり古い材料で開始しましたもう、カラッカラッですちなみに杉3寸5分角 L200mm1月25日現在 1100グラムです2205ccですから1ccあたり0.4988662グラムですかりーもんだ
2010.01.25
コメント(7)
-
ブログ研究所3の3
窓ガラス [普通のペアガラス]の内側にアルミはくを貼って測定 測定機器 放射温度計、通常のアルコール温度計、ケストレル気象計 部分的に マーカーで黒赤緑に塗った物と塗らない物を用意した 測定時刻 午前6:00 外気温 プラス2℃ 室内気温 ブラス22℃ 外壁の室内側表面温度 21℃ ガラス面 9.4℃ ガラス面アルミ黒 16.2℃ ガラス面アルミ赤 17.6℃ ガラス面アルミ緑 17.2℃ ガラス面アルミ 18.5℃ 樹脂サッシフレーム 9℃ ガラス面屋外 マイナス1.2℃ 外壁面屋外 マイナス2.7℃ 判った事 ペアガラスは ちゃんと暖房すれば 暖かいぞー 以上
2010.01.24
コメント(5)
-
プログ研究所その3の2
ブイマライダーさんからカキコでちなみに窓の放射温度を正しく測る場合はどうするんですか?裏紙(反射率の良い色?)を外側にペタン、として放射温度計で計測すれば誤差無いのでしょうか?やってみたいのですが、補正の仕方とかさっぱとありましたので考察そうですねガラスは透明だから放射温度計だと難しいですね反射率が良い紙を貼ると室内の放射を反射してしまいますから反射せずに熱伝導率の良い薄いものをガラスの内側に貼ってみましょうか外側だと外気温になってしまいますからねデライトに付属のアルミテープを茶色かグレーに塗って測ってみましょうガラスを直接着色するのが一番正確かなー忘れなかったら明日の朝実験です放射温度計をお持ちの方はぜひ、御自分でもやってみてください
2010.01.23
コメント(2)
-

ブログ研究所その3
以前紹介した我が家の脱衣室の窓の結露ですが湿流の速度に興味があったので計測してみました朝6:00起床 室内気温22℃ 湿度35%いつもの様にシャワーを浴びる前に脱衣場にストップウオッチを準備シャワーは給湯器の温度設定42℃で最高温で噴射外気温マイナス2℃シャワー室を出るときにシャワー室のドア開放シャワー室から窓まで約4メートル窓は曇っていません窓に向かって歩くと身体の周りの水蒸気を引き連れて窓に接近してしまうのでシャワー室の入り口の前で観測計測開始から窓ガラスの曇り初めを目視で確認するまでの時間11.5秒秒速347.8mm自然拡散の速度ということだけれど分子量と気温で大体決定することですシャワー室のドアを開いたときの風圧がかなり影響するはずだけど我が家のシャワー室ドアは折れ戸でかなりゆっくり開いたからとりあえず無視します結論想像通りの早さでした
2010.01.23
コメント(3)
-
あいた口がふさがりません
某市役所の建築指導課の建築主事に「24時間換気装置の吸気口は、各居室の外壁にそれぞれ穴を開けなきゃいかん!」と言って譲らない御仁がいるそうなこの省エネが求められる時代にヒートショックで死亡者が後を絶たない時代にドアのアンダーカットでの吸気経路を国土交通省が認めているのに室内の静粛性もピアノの音が外部に漏れる問題も寒くなってしまうから換気装置のスイッチを切ってしまう居住者が多いと言う問題も自分の法理解に問題があることを省見ず権力を振りかざして真剣に建築に取り組む建築家をいたぶっているとしか思えません何とかならないのだろうか主事(個人)にあらゆる決定権を与えている行政は・・・建築主事という資格は法を曲げられるのかあっいいこと思いついた
2010.01.19
コメント(4)
-
ブログ研究所その2の2
セキロ君から正解が出たのでとりあえずホッとしているfsです断熱無しというところが肝心ですね断熱が無くて木部がぬれている事の不条理を感じますねーこの家寒いでしょうねー
2010.01.18
コメント(4)
-
住宅革命その70
高山は建築端材を壁の中にしまいこむという僕の提案を快く承諾してくれた。このごろの高山は、僕が意表をつく提案をするのを待っているかのようだ。僕が何かを語りかけると目を輝かせて、「今度は何だ?」と聞いてくる。今回も、普通のユーザーなら端材とはいえ建築廃材が壁の中に入っているなんて嫌がるところだろうけれど、根っから理系の友は躊躇無くメリットを優先したようだ。「そりゃあ良い考えだ。やろうやろう。」と、二つ返事で身を乗り出してきたものだった。端材を壁に入れる作業は結構手間がかかる。適当に入れただけでは、蓄熱や吸放湿性能は良いけれど防音効果や耐震補強にはならない。サイズを統一し簡単に接着をしながら収めていく。殆どの端材は床から90cmくらいの高さまでに収まってしまうが、壁はびっくりするほど頑丈になる。少々蹴飛ばしたくらいではプラスターボードは破損せず、蹴ったほうが痛い思いをするだろう。僕たちは三日間で端材を入れ終わり、七日間かけて間仕切壁のプラスターボードの取り付けを完了した。驚いた事に間仕切壁の内部空間に余裕を残して家一軒分の建築廃材は全て壁中に納まってしまった。このことだけで約10万円の産業廃棄物処理費が浮いた事になる。もっとも三日間の人件費がかかっているからコストダウンにはならないけれど・・・。間仕切壁にプラスターボードを張る工程でもう一つ工夫した事がある。それは、間仕切壁の上部(天井に近い部分)に通気止めという処理をしたのだ。通気止めとは壁の中の空気と天井裏の空気を隔てる為の処置である。壁の中の空気は暖房したときに暖められて上昇気流となり、天井裏へ流れ込んでいく。壁にはコンセントボックスやスイッチボックスといった電気設備があるからそれらの隙間から室内空気が吸い込まれて天井裏まで流れ込んでしまう。この現象は外壁の断熱に不備がなければ熱損失とはなりにくいけれど、室内空気に含まれているカビの胞子やダニの死骸などのアレルギー物質が天井裏に蓄積する事になってしまうのだ。“ちりも積もれば山”というけれど文字通りアレルギー物質の山ができてしまう。通気止め処理は空気層を分断することで断熱性能を若干向上しつつアレルギー物質の蓄積も少なくしてくれるのだ。この効果に、僅かだけれど先に詰めた建築端材も壁内部の空気量を少なくすることで貢献してくれている。 通気止めをしている家はとても少ない。なぜかといえば、その効果が絶大である事をプロの建築家たちも知らないからだ。稀に知っている人がいても、工程を変えなければならないとか手間がかかるとかいってやらない場合が多い。通常の在来建築は壁のプラスターボードよりも天井を先に仕上げるから、どうしても壁上部に通気する穴が開いてしまう。この穴を一つ一つ塞いでいくとしたら莫大な手間隙がかかってしまい、プロたちはその事を知っているから通気止めをやりたがらないのだ。しかし、実際はそれほどの大作業とはならない。壁のプラスターボードを先に張るだけでよいのだ。プラスターボードが梁まで到達しているだけで実質、通気止め処理は完了する。しかもそのことでプラスターボードという面材が途中で途切れることなく床から梁まで両面に貼られているから、僅かだけれど家全体の剛性も増してくれるという効果もある。新築ならば通気止め処理をしたからといって余計な手間がかかるということは無いといって良いのだ。一年が終わろうとしていた。出雲の冬は寒い。高山邸の周辺は山間の南斜面だが、すでに積雪が30cmほどになっている。しかし、家の中はたった三つの工事用の電球で汗ばむほどである。作業をしているからなおさらだが、この家に人が住むようになって生活廃熱が出るようになったらどれほど暖かい家になるのか、楽しみで仕方ない。もちろん無暖房で暮らせるほどではないだろうけれど、居住者の健康維持のために室温を22℃程度で維持し行く事を少ないエネルギーで実現してくれるだろう。
2010.01.17
コメント(4)
-

ブログ研究所その2
今日は住宅革命をアップする予定なのですぐに更新してしまいそうですが研究所シリーズでお題をひとつ下の写真は一昨日岐阜で撮影したものですサイディングは鉄板天気は時々雪 気温0℃午前7:30撮影さてさてこの結露はどうして起きたのか忌憚の無いコメントをお待ちいたします
2010.01.17
コメント(8)
-
ブログ研究所
ビトウ君のところで白熱した議論が展開していますね楽しいですよそ様の家のことなのでなかなか真相はわかりませんがプロとしての推理はだんだん深くなっていきますね屋根断熱か天井断熱かはたまた桁上か下屋はどうして解けているかまあ高窓があることがヒントになりそうですね断熱位置よりも工事の精度のほうが重要でしょうからそこそこわかろうというものです1階に(下屋以外にでも)ダウンライトがあれば下屋が解けるのはありですね推理は知識の総動員でやっととんとんですまだ読みが足りないかもしれませんUB周辺は?軒天に換気口はあるか?とかも考慮し別の視点で同じ分譲地で3物件に同じ物置が置かれているので同じ建築会社が建築したのか?とか1物件だけ高窓があるから設計者は違うのか?とかたんに屋根勾配がきつくて解けなかったとかこの家の夫婦は3年くらい交渉が無いとか(さっ寒い!)
2010.01.17
コメント(7)
-
地球環境に貢献した量
僕の事務所が昨年一年間で消費削減し地球環境に貢献した熱量を計算してみました約1950000キロカロリーでしたひゃくきゅうじゅうごまんきろかろかろりーたいしたことありませんね僕が販売している全国のデライトが一冬で節約するカロリー量は1000台稼動していると仮定して1728000000キロカロリーじゅうななおくにせんはっぴゃくまんきろかろりーってなことになりましたやっぱりたいしたことないねあと二桁上げたいね!と思いますもちろん僕は社会的に認められることが目的でやっているわけでもないからISOなんてものにもまったく興味がありません余計な経費をかけてISOを取得する気もありません人の評価なんてどうでもいいんです結果がすべてですがんばっている理由は自分の生活費を稼ぐことにほかなりませんまあ、ちょっとだけ未来の子供たちに出来るだけ良い環境を残したいとは思っていますが・・・
2010.01.16
コメント(3)
-
帰宅
四日間の出張から帰宅し、真っ先に体重計に乗る 1.5Kg増加 しかたがない 今日から三日で落とせばいい 出張中はどうしても体重が増えてしまう 見方を変えれば 普段の食事はよくコントロールされていると言える ハニーのおかげです 出張中に悪戯をしたからゴマを摩っているわけではありません 地元に居るときは体重が下がります それだけよく動いているとも言えますが やはり食生活は大切です 体重は健康のバロメータですからね アラカン親父は 節制せにゃなりませぬ
2010.01.15
コメント(4)
-
美濃の隠し子
岡崎は暖かいのに 岡崎製材の会議室は網走より寒い と感じる一日を終え 今日は美濃太田-美濃加茂のT邸を尋ね 午後には岐阜にもどります 名古屋駅始発のひだ3号は後ろ向きで出発し岐阜までは後ろ向きのまま走ります 岐阜駅で高山線に入る時に進行方向が変わり、前方に進みます かざはなの舞う岐阜駅で進路を変えた富山行き、ひだ3号は銀世界を走って行きます T邸は 僕が設計してビトウ君が建築した たぶん 現時点で 日本一省エネな住宅です 工事中は何度か行ってみたのですが 完成後は初めて訪れます すごく愉しみです そのわけは T邸は 生活排熱を蓄熱したり再利用する仕組みを持たせましたから、住む事でより暖かくなっているはずだからです 里子に出した自分の子供に 初めて会う気分で電車に揺られるfsです 早く逢いたい
2010.01.14
コメント(6)
-
13日の日記
岡崎は昨日、雨でした 今朝のいらご岬は良い天気ですが 風強く波高し 寒いです
2010.01.13
コメント(2)
-
12日の日記
東京駅で お約束の深川飯を買い 発車も待たずに包みを広げる 美味いんだなーこれが 2010年も遂に始動し 景気や政治はお寒い状況が相変わらずですが 状況が悪いと言うことは 勝ち抜く材料を持っている人にはラッキーと言うことで おっと 豊橋だ
2010.01.12
コメント(8)
-
住宅革命その69
深夜電力利用がエコだと宣伝されてもなかなか信じることは出来ない。深夜電力料金が安いのは原子力発電所が夜になっても稼動していて、しかし、大企業の工場は夜になって停止するから、電力が余ってしまう。その余った分を無駄に放電している状態が現状としてあるから、安くして少しでも売りたいというのが電力会社の考えだ。そもそも初めから深夜に放電してしまう分の料金まで昼間の料金で稼ぎ出していたのに・・。だから安く売る事が出来る。1970年代にオイルショックというのがあった。OPECの原油価格引き上げ宣言や中東の戦争による原油高騰で世界中がパニックに陥った。全て人為的な原因によるものだった。この時日本ではテレビ局が深夜放送を自粛したりしたものだ。現在では地球規模の温暖化が人類の破滅に繋がると危惧する報道が相次いでいるにもかかわらずテレビは朝まで放送され、深夜電力をどんどん使えという。地球の温暖化が人類の廃棄する物質や熱によるものだと主張している面々の意見では、間違いなく温暖化に貢献してしまう行為なのではないか。温暖化の原因が人類起源のものかどうかはさておき、省エネルギーを進めることは良いことだ。ただし、正しい省エネルギーをするべきだ。正しい省エネルギーとは当たり前のことだけれどエネルギーの消費を減らすことでしかない。高山邸の間仕切壁の中に仕込む蓄熱材料は全くお金がかからず、効果的で、安全で、社会貢献度がとても高いものとなる。それは何かというと、内装下地材として使用するプラスターボードの端材、柱や梁の端材、床板や下地合板の端材などである。これらの端材は、通常は産業廃棄物として、最終処分場へ運ばれ、処分される。産業廃棄物の処分にはお金とエネルギーがかかる。産廃処理業者はガソリンを消費して廃棄物を処分場へ運び、賃金を稼ぐ。処分場では重油を消費して廃棄物を処分する。廃熱と排気ガス(CO2やSOxやNOx)の発生を伴う。捨ててしまえば有害ガスや熱を出しお金を浪費する建築廃材も、蓄熱・吸放湿材料として壁の中へ仕舞い込めば、永久に働く蓄熱・吸放湿材となり、排気ガスも出ないし、産廃処理費もゼロになる。まさに三方良し。一石三丁も四丁も働く。しかも材料代は捨てるものとして考えればただと言ってもよい。通常ならば空洞の間仕切壁に質量の高いものが入ると蓄熱・吸放湿だけでなく、防音効果が増し、隣室の音が漏れにくくなる。若干コストをかけて、旨く接着してやれば住宅の耐震強度を増すことにもなるかもしれない。まさに良い事尽くめなのだけれど、一般の工務店や大工さんたちはこんなことはやらないはずだ。壁の中にごみを捨てたと揶揄される事を恐れるから・・。50年後、いや100年後にその家が解体され、壁のなかから建築廃材が出てきたら、未来の建築家たちは正しい評価をしてくれるかどうか・・・その頃の建築はどこまで進歩しているのか興味は尽きない。幸か不幸か、間仕切壁の中の空間を全て満たすだけの端材は発生しないので、完全満タンは蓄熱・吸放湿材としての資材を購入しない限り不可能だけれど、仮に満タンとした場合をざっと計算してみると、その容積は40坪の家で、なんと15立方メートルに及ぶ。これを建築物の構造体の容積と合計すると優に30立方メートルを超えてしまう。いったいどれほどの蓄熱と吸放湿を期待できるだろう。ああ、そんな家を創ってみたい。
2010.01.10
コメント(11)
-

窓の実験室
出雲のこげんぱさんのまねをしてみましたわかりにくくなると意味不明になってしまいそうですから実験はシンプルに複雑な要素を排除しました今朝のことです朝まだ暗い6:00シャワーを浴びみましたシャワー室のドアを開けっぱなしで脱衣室で身体を拭いているとオール樹脂の脱衣室の窓(プラマード)はペアガラスですが約10秒ほどで全面結露ですおっ これだっ! とすっぽんぽんのまま寝室に走り愛用の液晶の壊れ始めたCANONのコンデジを取り出し脱衣に戻りすっぽんぽんのまま撮影したのがこの写真です外気温は-2℃ですさて日課の起床時の体重を量りパンツを履きTシャツを着たところで2枚目をパチリ(デジカメはパチリといわないけれど・・・)上のほうから乾き始めていますなぜか・・・こたえはシンプル使用13年の樹脂サッシのパッキンは隙間ができ始め隙間風が流れているからですなぜ上から傷むのかは不明ハックショイ !(>
2010.01.09
コメント(3)
-
2010年の抱負
今日から仕事始めなのに昨日から仕事をしているfsですうちの事務所は寒いです薪ストーブをがんがんたいても寒いですさて、今年の抱負です〔住宅革命を完結します。特許を最低2つはとります。〕こんなところで勘弁してくださいはい
2010.01.06
コメント(12)
-
住宅革命その68
しばらく文章を書かずにいたら文章力が落ちてしまっていましたお恥ずかしい表現が在りましたので少々訂正を加えました訂正したところからはじまり、はじまりーたかだか2~300kgの蓄熱物を800℃程に熱しても蓄熱体として脆弱なものでしかない。しかも暖房の対象となる室内空気は22℃にもなれば十分な暖かさなのだ。蓄熱物が800℃という高熱では室温が25℃でも30℃でも、温度差がありすぎて放熱が止まらない。太陽光を暖房の手助けとして利用できる昼間になっても蓄熱暖房機は意味もなく放熱を続けてしまう。結果、室温が上がりすぎて熱いと感じてもどうすることも出来ず窓を開くかエアコンを冷房運転する破目になる。これでは残念ながら省エネとはいえない。物体が持つ熱量はその物質の比熱×比重×容積で現される。もしもその物質の容積が少なければ、その物質に求めるだけのエネルギーを与えるためには必要なだけ高温にしなければならない。しかし高温にすると放熱が早いのだ。本来、蓄熱による暖房を考えるならば、目標室温よりも2~3℃高い設定で巨大な蓄熱体に蓄熱させる事が望ましい。蓄熱温度が低ければ放熱速度がゆっくりし、熱が長持ちする。しかも太陽光などのおかげで室温が蓄熱温度よりも高くなれば放熱は転じて蓄熱となり熱を蓄え始め、無駄なく自然エネルギーを吸収する。このことから蓄熱体の質量は大きければ大きいほど良い。しかし、そんなに巨大な蓄熱体を作ることはスペース面でもコスト面からも個人住宅には無理があるように思える。しかし、よく考えてみるとそうでもないのだ。40坪程度の住宅には250枚ほどのプラスターボード(石膏ボード)が使われていて、その重量は5トンにも及ぶ。そのほかにも断熱材の内側にある建材は全て蓄熱体として機能する。数十本の柱や梁、構造用合板などを集めると約10トンそのほかにも、居住者が持ち込む家財道具一式が約3トン。住宅にはこれら約18トンの蓄熱材が存在する。これらを全て蓄熱体として利用するのに7キロワットもの深夜電力は必要ない。500ワットそこそこのエアコンを深夜電力を利用して運転しておけばよいのである。誰でも一度や二度はエアコンのスイッチを切るのをうっかり忘れて寝てしまった事があるだろう。翌朝、異様に暖かかった事を覚えている。ただ、もったいない事をしたと後ろめたい気持ちになったものだ。不思議なもので深夜電力利用の蓄熱暖房機が7キロワットも消費してもエコだと言われると納得し、たかだか500ワットでもエアコンの消し忘れは後ろめたいものだ。その消費量がたった1/14であるにもかかわらず・・・。暖房のキモは建物そのものを冷やさないことなのだ。 北海道以外では就寝時に暖房を切るのが当たり前だった。そのせいで脳梗塞や心不全などの循環器系の発作を住宅内で起こし倒れる人の数は北海道より本州のほうが多い。なぜなら北海道では就寝時も暖房を切ることは無く、起床時も設定温度を維持しているからだ。 空気よりもずっと重い物体が(建物そのものが)とても低温になってしまったとしたら暖房のコストは莫大なものになってしまう。たとえば40坪の家の中にある空気の量は約450kgであり、この空気の気温を20℃上昇させるためには2160kcalのエネルギーを必要とする。しかし、建物そのものが冷えていたら空気だけを暖めてもなかなか暖かくならない。それは、建物が暖房の熱を奪ってしまうからだ。建材の質量が仮に空気の1000倍(いろいろな建材が含まれているので平均として)として、建材を目標暖房温度に上昇させるには空気の約45倍のエネルギーを必要とする。これでは暖房費がかさんでも仕方がない。しかもなかなか温まらないから、家族は寒い思いをするし、健康にも悪影響を及ぼす。せめて、オール電化契約をした家庭は、深夜電力を利用して、弱い暖房をするべきだ。断熱が適正であれば、500ワット程度の消費で暖かい朝を迎える事が出来る。 エコロジーの世界では「モッタイナイ」という単語が日本の美しい言葉として世界中に知られるようになった。化石燃料のように限りのある貴重な資源だけでなく、あらゆる物に対する感謝を知る事が必要だと教えている。モッタイナイの心から見ても、人の命を守るための暖房は消費を許されるプライオリティーのもっとも高いところに位置していると思う。適正な暖房をすることは家族の健康を守る上で必要な投資なのだと考えるべきなのだ。北海道の人々は年間暖房費を15万円も投じて家族の健康を守っているのである。関東ならばその1/3以下の投資で十分な暖房が出来る筈なのだ。そして、それをもっと上手にやろうというのが蓄熱暖房という事になるのだけれど、しかしそれは、7キロワットもの大電力を投じて蓄熱暖房気を使うことではないと言うことなのだ。
2010.01.05
コメント(7)
-
住宅革命その67
蓄熱とエンタルピー僕は工事に復帰し、3日程で外壁に面したエンタルピー断熱の工事は完成させることが出来た。そしてすぐに間仕切壁の工事に取り掛かる。普通、間仕切壁というものは外気に面していないから断熱をする必要がない。ということは当然内部は空洞になっている。断熱の必要がない部分だから空洞でよいのだけれど、僕は以前からこの空洞部分を有効利用できないものかと考えていた。そして、思いついたのが蓄熱と湿度調整のための吸放湿をさせたら良いのではないだろうかということだった。地球の温暖化が、人類が排気するCO2に由来するものとして省エネルギーのためのアイテムがいろいろと開発されている。温暖化が本当にCO2のせいで起きているのかどうかは別にしても、省エネすることは良いことだ。エアコンや冷蔵庫の効率が上り、消費する電力が少なくなる事が良い事なのは言うまでもない。しかし、そんな省エネ機器の中に蓄熱型暖房機というものがある。一時的にエネルギー(深夜電力などの価格の安いエネルギー)を大量に投入し、質量が多く比熱の大きな物質に蓄熱し、深夜電力の時間外にゆっくりと放熱させることで暖房コストを下げようとするものだ。僕は以前からこの方法に疑問を感じていた。深夜電力といえども貴重な資源を利用して作り出したエネルギーである。それを平均的な物で7kw/hもの電力を投入する。そして蓄熱体は数百度という高温に達する。高温の物体からゆっくりと放熱させるためには高度な断熱が必要になる。しかし、ここに無理が生じる。熱というエネルギーは例外なく高温側から低温側へ移動する。その温度差が大きければ大きいほど移動速度が速い。0℃の水を100℃のお湯にするために200℃の熱源で熱するよりも1000℃の熱源で熱したほうが早いことは誰でもわかることだ。これは、熱い物ほど放熱が早い事を意味する。たかだか2~300kgの蓄熱物を800℃程に熱しても蓄熱体として脆弱なものでしかない。しかも暖房の対象となる室内空気は22℃にもなれば十分な暖かさなのだ。蓄熱物が数百度という高熱では室温が25℃でも30℃でも、熱源が800℃もあっては温度差がありすぎて放熱が止まらない。太陽光を暖房の手助けとして利用できる昼間になっても蓄熱暖房機は意味なく放熱を続けるから、そのせいで室温が上がりすぎて熱いと感じても熱源が高温すぎて放熱を止める事が出来ない。物体が持つ熱量はその物質の比熱×比重×容積で現される。もしもその物質の容積が少なければ、その物質に求めるだけのエネルギーを与えるためには必要なだけ高温にしなければならない。しかし高温にすると放熱が早いのだ。本来、蓄熱による暖房を考えるならば、目標室温よりも2~3℃高い設定で巨大な蓄熱体に蓄熱させる事が望ましい。蓄熱温度が低ければ放熱速度がゆっくりし、熱が長持ちする。しかも太陽光などのおかげで室温が蓄熱温度よりも高くなれば放熱は転じて蓄熱となり熱を蓄え始め、無駄なく自然エネルギーを吸収する。このことから蓄熱体の質量は大きければ大きいほど良い。
2010.01.03
コメント(2)
-
住宅革命 2010連載再開
正月休みともなれば多少の時間が得られ執筆も出来ようというものですさて長い間筆を休めていました「住宅革命」を再開したいと考えています。さてさてどうなりますか・・・・
2010.01.01
コメント(1)
全28件 (28件中 1-28件目)
1