2010年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
県アンコン終わりました
本日は県アンコンでした。今回は打楽器とフルートの2チームが出場……。結果は打楽器が県代表、フルートが銀賞でした。フルートチームは、もう少しで金賞だっただけに惜しかったです。でも、秋以降このパートは急成長しました。講師の先生の熱心な指導と、メンバーのがんばりがあったらこそです。よくがんばりました。打楽器は、2週間後の北陸大会に駒を進めます。ここまでは昨年と同じですが、今後もし、本気で全国大会を狙うというのなら、しなければならないことはたくさんあります。目標が高ければ高いほど要求が高くなるわけで、それに応えることができるかどうか……、今まで体験したことのない未知のゾーンですから、かなりの精神力が要求されるはずです。できるでしょうか?高いレベルで見るのなら、まだ完成度は70%程度……。2年かけて同じ曲に取り組んでいますが、音楽は奥深いです。よりよいものを求めたら、キリがないです。それだから大変、それだからおもしろいのかもしれませんね……。1月は推薦入試などがあって、部活にはほとんど行けませんでしたが、クラスの推薦入試組も、すべて合格しました。これからは少し余裕ができるでしょう。部活の方にも顔を出して、打楽器チームの行く末を見守りつつ……Y中吹の進むべき方向を考えたいですね。では、また……。
2010.01.31
コメント(0)
-
感謝の気持ちをもって取り組んでいきましょう。
県アンコンまであと一週間になりました。今日は、午後はフルートチームの音程合わせに付き合いました。なかなか合わないし、合わせようとすると音は響かなくなるし、ある程度のところまで来ていると、なかなか目に見える進歩は出てこないようです。しかし、このチームは、アンサンブル練習を始めた当初は県大会まで進めるとは、あまり思っていなかった(自分たちも思っていなかったらしい)ので、正直、よくやっていると思います。その後、打楽器チームの演奏を聞きました。4分48秒……、危ういですが、タイムも収まるようになってきました。打楽器チームは昨年、北陸大会まで行きましたが、今年はどうでしょうか? 期待半分、不安半分……という心境です。(あまり自信があるという感じではないですね……)2チームとも、よく頑張っているとは思います。でも、自分たちだけではここまで来られないし、これからも、楽器運搬や文化会館練習で多くの方の世話になるということを忘れてはいけません。自分たちが輝くために、多くの方の支えがあること……、それを忘れたら、いい結果にはならない……と私は思っています。吹奏楽やアンサンブルは自分たちだけでは出来ない。多くの方の支えがあってこそ、成り立つものだから、周りへの感謝を忘れてはいけない……何度も言ってきましたが、本当に部員達の心の底にそういう気持ちがあるのか……と言われますと、ちょっと自信が揺らぐ残念な場面を何度か見てしまいます。みんな上手になりました。努力もたくさんしています。でもね……、自分たちが努力して上手になって、そして音楽が楽しくなって……、そういう環境を与えられていることに、まず感謝ですね。私も、部員達がいて、最近はあまり行けないけど、それでも、一緒に楽しく音楽作りが出来る……。そういうことに感謝したいです。ありがとうとか、感謝の気持ちを本当に根付かせるのは、なかなか難しいことだと、最近はつくづく感じます。県アンコン……、キーワードは「感謝」です。特に2人の講師の先生に対して、この気持ちが強くなければ、いい演奏はできません。がんばってほしいものです。
2010.01.24
コメント(0)
-
1月は休みなし……
久々に書きます。いろいろと忙しくて、更新する暇がありませんでした。3年生の進学関係の仕事が、いよいよ佳境に入るのもあり……、そんな忙しいのに、先週はN地区のアンコンの審査員などに出かけていたり……、1月4日に働き始めて……、今月は1日も休んでいないことに気づきました……。今日は久々に部活に行けました。県アンコンが1週間後に迫ってきました。アンサンブルチームは、講師の方が毎週来てくださるので、ほぼそちらにお任せしています……。とはいうものの、やはり関わる必要があるようで、来週もほとんど行けないことを考えると、明日のアンサンブルチームだけの強化練習で、音程など、やばいところを見てあげないといけないと思っています。今日はアンサンブルチーム以外、要するにフルート、打楽器抜きで合奏を行いました。基礎が1時間ほど……、卒業式の練習が1時間ほど(かなりネチネチと……)、そして新曲(入学式やスプリングコンサートで演奏したい曲)の合奏が1時間ほど……という感じでした。息をしっかり吸うことが大切だと思います。息をしっかり吸って、安定した音を出す……。そして周りと自分の音を、よく聞いて合わせる……、単純だけど、今はその2つを徹底的に言います。それと、今後も2週間ほどは合奏が出来ないので、パート練習やセクション練習の課題も与えておきました。パート練習やセクション練習が円滑に出来る環境は、特に大切だと思います。今日、聞いた限りでは、結構、パート練習はしてあるようです。ただ、セクション練習となると、低音の音が甚だしく合わなかったり、旋律もよくそろっていなっかりで、まだまだ不十分です。特に低音パート(木管低音、弦バス、テューバ)には、曲練習の時は、なるべく一緒にやるようにと指示をしました。「顧問は来んモン」(?)状態が、3月半ばぐらいまでは続くでしょう……。逆に顧問が来ないおかげで、自分たちでやるという自主性は育っていくかもしれません。Y中吹のサウンドは、合奏ではなく、各パートや各セクションでの地道な取り組みがベースとなります。指示を待つのではなく、一人ひとりが主体的に音楽作りに参加してほしいです。(その方が楽しいはず!)
2010.01.23
コメント(0)
-
全く部活に行けない平日……
昨日は、面接の練習の後、調査書、推薦書……計10人分……書き上げて、ヘトヘトになり、……今日は雪の中、会場練習に向かいました。久々の大雪です。いつもは50分ほどで行ける道ですが、今日は1時間20分ぐらいかかりました。でも、市内を抜けF市に入れば、雪の量も全然違います。「かなり少ない!」アンサンブルチームは、今週は全然見ることができませんでした。ただ、この2チームには強力な講師がついているので、ほぼ2人にお任せという感じになってきました。1人は長年の友人、1人は教え子……。2人とも熱心に教えてくれますし、メンバーも全幅の信頼を寄せているようです。フルートチームを教えているK先生(教え子)が、「毎日、見に来たいチームです」と言ってくれました。本当にうれしいことです。K先生のおかげもあって、秋口から急に伸びたパートです。まだまだ県で通用するようなレベルではないと思いますが、一生懸命やっていると思います。今日の最後の通し練習はメロメロでしたが、それでも、K先生のやろうとしていることが見えてきました。勢いのあるアンサンブルとは違う、何か気品のある優雅なアンサンブルを目指しているようです。本番まであと3回、レッスンをして頂く予定です。昨年、北陸まで進んだ打楽器チームはメンバーが4人も残っていますが、それだけに県大会で負けられない……というプレッシャーが感じられるようになってきました。昨年のような大胆さが薄れ、無難にまとめよう……という雰囲気になっています。ちょっと危険な傾向です。結果をおそれず、自分たちの良いところを出してほしいと思います。2チームともよく頑張っているだけに、少しでも練習を見てあげたいと思うのですが、平日は3年生の進学関係の仕事のため、ほとんど顔を出せません。来週もほとんど行けないと思います。前、3年生を担任した時はこれほどではなかった……と記憶しているのですが、今年はかなり忙しいです……。私が忙しいだけに、今回の2チームについては、本当に2人の講師の先生に感謝しないといけません。県アンコン出場の皆さん、せっかくの機会です。素晴らしい音楽を聴かせてください。
2010.01.15
コメント(0)
-
小学生と合同練習
近くのS小学校の金管バンドの子たちが、今度の県アンコンに出場するということで、練習をしに来ました。いわゆる合同練習ですが、夏の演奏会では一緒にやったりしているのですが、練習を一緒にやるのは、今回が初めてです。部員達が基礎を教えたり、小学校の子が取り組んでいる曲を見てあげたりしました。教えてみると、自分たちも基礎があまり出来ていないということに気づくようです。また、私の方でも金管楽器については、一人ひとり見てあげましたが、もっと音をスムーズに出す方法を教えてあげるといいのかな……と思いました。そうなると、やはりアンブッシャー(口の形)が大切だと思います。いい口の形の子もいるのですが、そうでない子の方が多いようです。小学校の最初の段階では、バジング遊びやマウスピース遊びで入るのが有効だと思っています。「バジング」演奏会とか「マウスピース」発表会をやると面白いかも……。さて、うちの金管の生徒には、バジング(唇を振動させて音を出すこと)をよくさせます。その時に上唇が下唇に重ならないにして、なるべく高い音を出させます。これをマスターさせておけば、音の詰まりはなくなり、高い音もスムーズに出るようになってきます。(だいたい、1年でハイG、2年でハイB♭ぐらいは出るようになります。)よくアンブッシャーは、その人に合ったもので……と言われますが、私は自然な形で……、すなわち、その人の口の形と同じようになるように、アンブッシャーを作れと言っています。楽器を吹くときだけ、口の形を無理に変えているのなら、それは無理な吹き方で、疲れやすいし、スムーズには音が出ません。金管楽器やフルート奏者のアンブッシャーが悪いのは、悪いリードで木管楽器を吹くようなものですから、決していい音は出ないと思っています。今日の合同練習ですが、最初のうちは、どうやってよいか戸惑っていましたが、終わりの方は上手に教えることができたようです。今年は金管が県に出場することが出来なかったので、こちらの方も少し時間があるので、今度は小学校で取り組んでいる曲を練習して、曲の指導をしてあげられると良いと思いました。ほとんどが6年生で、今春入学予定です。何人かは入部(できれば全員がうれしいけど……)してくれるはずですから、今のうちから教えておいても損はないはずです。このような交流は良いものだと思います。今回は向こうから来て頂きましたが、もう少しこちらの方から、校区の小学校に積極的に出向いて行った方が良いと思いました。少し活動を見直していきたいです。
2010.01.09
コメント(0)
-
久々に合奏……
今日は久々に合奏をしました。やはりというか、基礎合奏1時間、曲15分……でした。あんまり、いい音はしませんね。(もう少し期待したのですが……)ブレスの浅いのが気になります。道険し……ですね。例年と比べると、木管がややアップ、金管がややダウン……。打楽器は何でも来い……、こんな感じでしょうか……?よって、今年のサウンドは、今までとはかなり違うものになりそうです。それだけに、自由曲はかなり悩んでいます……というか、ぴったりの曲が見つかりません。私が指揮をするのなら、邦人作品の方がいいように思いますし……。友人のT君に勧められている曲……、これが一番良いようにも思うのですが、中間部のソロパートが気になります。あとは、課題曲との絡みもあるので、(沖縄の曲があったような……。今年はマーチに行かない可能性もあり……)何とも言えません。2曲合わせて、キャラクターを生かせることが出来れば、言うことがないのですが……。もう一つ、中部日本(中部地区だけの限定)も今年はアクトシティ(浜松)の開催なので、狙ってみようかなと思っています。(今日のような音では無理でしょうけど……)5年かけて、オーボエ、弦バスそしてファゴット……と、大編成吹奏楽の体制は整いましたから、やはり今年は勝負!ですね。がんばらないといけませんね。
2010.01.07
コメント(0)
-
今日から部活始動です
冬休みもあと2日……なのですが、うちの学校では、昨年のインフルエンザの影響で学校閉鎖などがあったため、本日から授業をしています。午前中は授業、午後は部活です。本日は、冬休みの宿題点検もあって、やっていない者は残しになってしまいました。数名の者が残しになってしまい、2010年の始動は全員で始めることができませんでした。これは、とても残念でした。現在1,2年部員は46名です。昨日も書いたように、この46人全員で演奏することに、「吹奏楽」部としての意味があります。「吹奏楽=全員でやる音楽」なのですから、現部員46人で一丸となって頑張っていくことに値打ちがあるのです。そういう自覚をもって、一人ひとりが取り組んでほしいと思っています。外は雪が降っています……。寒いです。「息で音をつくる……とは、どういうことか? 考えてみよう!」今日、部員達に投げかけた言葉です。アンコンでフルートチームが県大会に残りましたが、今思うと、フルートチームと他のチーム、勝敗を分けたのは、「息」だったように思うからです。「息で音をつくる」ということは、もちろん、息を吸うことが大切で、これがしっかり出来ているチームが、この前のアンコンでは県大会に残ったように感じました。うちのフルート、N中のフルート、金管、S中のサックスは、そういうことが良く出来ていたようです。(残り2チームは打楽器ですが、打楽器チームもしっかり息の合っていたチームが残ったように感じます。)この前の大会では、高校生チームがどのチームも素晴らしい演奏をしましたが、どのチームもしっかり息が入り、楽器が豊かに響いていました。うちの地区の高校のレベルも、数年前と比べると、格段にレベルが上がりました。うれしい限りです。こういう高校生の演奏を生で見ていたわけですから、見習ってほしいと思います。今日の練習を見ていますと、うれしいこともあります。今年はどのパートも仲が良く、円く輪になって練習している姿があちこちで見られました。(T山商業の練習みたい?でした。)これは、良い兆候です……。部員達が何を感じ、今後、どのように音を作っていくのか、期待して見守っていきたいものです。
2010.01.06
コメント(0)
-
みんなでがんばれ! 吹奏楽部!
日記をネット上に書くようになって、もう9年目に入りました。長く続いてきましたが、やはりいろいろな失敗がありました。特に、最初の頃は、思いをそのまま書いてしまい、いろんな人を怒らせたり、迷惑をかけたり……で、難しいものだと感じました。でも、当時は今ほどは普及していなかったので、そのせいで大事にならなかったと思われます。今なら、ブログ炎上!ぐらいのめに遭っていたかもしれませんね。日記を書き始めた当時、一学年2クラスの小さな学校にいました。その中で何とか部員を集めて、それでも部員数がある程度いる時(2学年で30人を超えるとき)はA部門をやっていました。(周りからは無理している……と思われていたでしょう。)とにかく全員で、そして全力で、コンクールに出る……というバンドでしたので、そういうバンドから見て、Y中のような部員数が多い学校が、どんな事情があるかは知りませんが、人数を30人に落として、……(メンバーを精選してるように見えます)……、B部門で賞をかっさらっていくのは、特におもしろくなくて……、いろいろ辛辣なことを書いていたように思います。(そういう自分が数年後にY中に赴任することになるとは知らずに……)私は「吹奏楽は部員全員でやるべき……!」という信念を貫いてきました。吹奏楽部が他の運動部と違うところ……それは、補欠がないこと!です。でも、2学年で40人以上いた場合、B部門に出てしまえば、明らかに10名以上の補欠を作ることになります。5年前、Y中に赴任したとき、前年まで出場していたB部門に出るか、A部門に出るかで、かなりもめました。当時、部員(2,3年)は45名……、人数だけなら明らかにA部門です。3年生を中心に話し合いましたが、B部門に出た時、落とす15名は誰がどうやって選ぶのだろう……という話になりました。部員達は「それは先生が決めてください」と言います。私は、「この年に来たばかりの者が、何も分からずにそんなことが出来るわけがない!」と言い返しました。「そんなことは、コンクール前になればわかるはずだから、その時、決めればいいじゃないか」と言って来ましたが、「45人で練習してきて、いきなり30人に落とすのか。そんな計算の出来ないことは難しい……。30人でやるつもりなら、今ここで30人に落とすべきだ」……こんな問答があったように思います。……吹奏楽部、皆でがんばる道を選ぶべき!……結局、3年生部員達は、15人の2年生をメンバーから落とすのは難しいし……、実はメンバーの約半数が前年に、コンクールメンバーから外された悔しさをもっており、あんな悔しさは後輩には味わわせたくない……という者も出てきて、赴任一年目からA部門に出場できることができました。今のメンバーにはわからないでしょうが、この話し合いは4月いっぱい続いたわけで、当時の3年生には、私の信念のせいで、とても苦労をかけたことだと思います。しかし、この年、いきなりのA部門挑戦で金賞、翌年からは県代表になれました。それからは、コンクールは部員全員で(……と言っても、入部早々の1年生には技術的に厳しいので、基本的には2,3年全員で!)という状態になり、今は、A部門出場が当たり前ということになっています。さて、1月はアンコン県大会出場の者と、それ以外の者に分かれるので、一番不安定な時期です。でも、みんなでがんばる!……ということなので、Y中吹を背負って出場するチームに対しては、部員全員で支援することになっています。特に今年のように打楽器チームが残っている場合、他の部員の協力がなければ、楽器運搬もセッティングもスムーズに出来ません。「私らのチームは終わったし、後は残っているチームが勝手にやればいいわ……」では、部員全員でがんばる姿勢は生まれません。とにかく、部員個々の力をつけて、そこに一丸となって頑張る姿勢を加えて、少しでも良い音楽を届けることができるように……、そうありたいものです。部員一丸、みんなでがんばる姿勢を忘れないでほしいものです。
2010.01.05
コメント(0)
-
仕事始め……。部活は6日から……
今日から仕事です。今年は日の周りが悪く、4日から仕事始め……。年末年始の休暇も6日しかありませんでした。いつもの年なら、のんびり旅行なんかをしているタイミングなのですが、今年は3年生を受け持っていることもあり、今日から学校に出勤です。なお、本日より3年生の補習も始まっています。部活は1,2年の登校日の6日からとしました。年明け早々……3年生の受験準備……、そしてフルートチームと打楽器チームのアンサンブル練習……、結構忙しくて、腰が痛いなんて言っていられないです。今日は少し時間もあったので、部活ノートの中の部員達のアンコンの反省を読んでいました。まだ半分ほどしか提出されていないのですが、(こういうのは早く出した者の方がしっかり書けているものです。催促されて出すようなものには、ろくなものがありません。)なかなかしっかりした内容ばかりでした。特に1年生の反省がしっかりしており、この学年は先々楽しみだなと感じました。それに比べて……というのもありますが、今日読んだノートの中には、自分たちが無事に演奏できたことについて、感謝の気持ちを書いてあるものもあり、今後の活動にも期待がもてそうです。吹奏楽は一人ではできません。また、楽器演奏はいろんな方のサポートがないと成り立ちません。楽器が壊れても自分たちで直すことはできませんから、いつも楽器を調整してくださる楽器屋さん……に感謝。どこでやるにしても重い楽器を自分たちで運ぶことはできませんから、いつも笑顔で楽器を運んでくださるK運送の皆さん……に感謝。この前の会場のスタッフの皆さんは寒いといけないと思って早くから暖房を入れてくださいました……感謝。一生懸命演奏を聞いてくださった審査員の先生方……に感謝。そして、いつも演奏を楽しみにしてくださって会場に来てくださる皆様……に感謝。こういう方たちのサポートがあってこそ、我々の演奏は成り立ち、我々は楽しみを味わうことが出来るのです。忘れてはいけません。一生懸命練習して、それを発表する機会(コンテスト・コンクール)があること……。幸せなことです。それを支えてくださる皆様に感謝。感謝を言い出したらキリがありませんが、我々の活動はそれだけ多くの方に支えられて成り立っているのです。さて、その多くの方のサポートに応えるために、一生懸命練習して、良い音楽を届けたいものですね。県アンコン、卒業式……と吹奏楽部は3学期も忙しいですね。がんばっていきましょう。(しかしながら、顧問は、しばらくは来んモンです?)
2010.01.04
コメント(0)
-
坂の上の雲
年末にNHKで放映されていた「坂の上の雲」……なかなか面白いドラマでした。日露戦争当時の海軍参謀、秋山真之が主人公に、真之の兄の好古、幼なじみで俳人の正岡子規の3人を軸に展開される物語で、明治という時代を生きた人たちは、日本の未来に希望を抱き、そして、自らの可能性に大いに挑戦していたということが、実感できるドラマです。坂を一気に駆け上るようなスピードがあり、スケールの大きさを感じます。しかしながら、このドラマ、昨年末から始まり、年末だけの放送で、3年がかりで全話をやるという予定らしく、せっかく面白くなってきたのですが、この続きは今年の年末ということで、1年近くも待たないといけません。もちろん、終わりの方は、バルチック艦隊を破った、日本海海戦も描かれるでしょうから、とても楽しみなのですが、それは来年の年末……、気長に待つしかないですね。続きが今年の年末ということなので、その間に原作を読んでしまおうと、司馬遼太郎の原作を購入しました。司馬遼太郎の傑作として有名な作品ですが、大作です。文庫本で8巻……、それでも少しずつ読んでいけば、今年の年末、いや遅くとも来年の年末ぐらいには読み終えているでしょう。司馬遼太郎の作品と言えば、よく大河ドラマの原作になって、映像化されてきましたが、この「坂の上の雲」だけは、スケールが大きく、絶対に映像化は無理だとされてきたらしいです。生前の司馬遼太郎もこの作品の映像化だけは許さなかったようです。明治の40年間は、維新に始まった日本が、列強の一つであるロシアに勝利するまでに駆け上るのですから、それは世界史上でも奇跡に近いことです。それを今まであまり取り上げることが出来なかったのは、近隣諸国への配慮でしょうが、やはり、しっかりと描いておく必要はあると感じます。約40年で、小さな島国に過ぎなかった日本が列強の仲間入りをするわけですから、それを成し得た人たちは、とても頑張ったでしょうし、我々が思いもしなかった知恵を巡らせたはずです。私も歴史は結構好きなのですが、明治を扱った作品は、あまり知りません。確かに、日清、日露と続く戦争への道は、その後の太平洋戦争の敗戦につながるのでしょうが、列強の侵略を防ぎ、そして日本が坂を駆け上るがごとく、押し上げた人物たちを描く今回のドラマは、私にとっては興味があります。ドラマの第2部は年末なので、それまでに司馬遼太郎の原作を読んで、しっかり予習したいと思います。
2010.01.03
コメント(0)
-
新年ですね
新年明けましておめでとうございます。もう21世紀に入って10年目になってしまいました。子供の頃は、21世紀なんてまだまだ……と思っていたのに、あっという間に時が過ぎていきます。新年は、ちょっと腰痛に苦しんでいます。(かなり痛いです)それと、年末年始の暴飲暴食のせいで、血糖値も不安定(これは自業自得ですが……)で、次回の検診が怖いです。さて、Y中吹ですが、アンコンの惜敗(地区代表3を狙ったのに、2つに留まったので……)をどう受け止めるかから、2010年がスタートします。もちろん、県大会に進む2チームについては、行けるところまで行ってほしいと思うので、力一杯支援はしたいものです。……とはいうものの、打楽器とフルートは、どちらかというと、講師の方にお任せの部分が多いパートですので、あまり私の出る幕はないかもしれません。打楽器パートは、友人のT君が、しっかりと曲を作ってくれています。T君とは、20年来のパートナーで、打楽器のことだけでなく、バンド指導全体にわたってサポートしてもらっています。今年は、全国大会も考えられるチームなので、T君の指導にも熱が入っています。フルートも、今シーズンから、私の最初の学校の教え子、Kさんが、顔を出してくれるようになりました。Kさんは、高校・短大でフルートを専門的に勉強したので、ポイントをしっかりおさえて指導してくれます。この2人の講師の方の尽力が、打楽器チームとフルートチームの躍進につながっています。ありがたいことです。あと、クラリネット、サックス、オーボエ、ファゴットにも、講師の先生がつきました。さらに現在は弦バスも探しています。この前のアンコンで、オーボエ、ファゴットの2重奏が、すこぶる審査員に好評でしたが、これも、ファゴットH先生の力によるところが大きいです。このような体制作りは、今までの反省にたったものです。北陸大会で全く通用しないのは、個々に技量がついていないからだとT君に言われたこともありますが、考えてみると全くその通りで、今年度は、部員達の技量を精いっぱい伸ばして勝負したいと考えています。私も気がつけばY中で5年目が終わろうとしています。やり残したことがあるとすれば、北陸大会でしょうね。金賞とは言わないですが、せめて銀賞をとって終わりたい……そんな思いがあります。今年はメンバーもそろっているので、チャンスのような気がします。今年も、がんばらないといけませんね……。
2010.01.01
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-
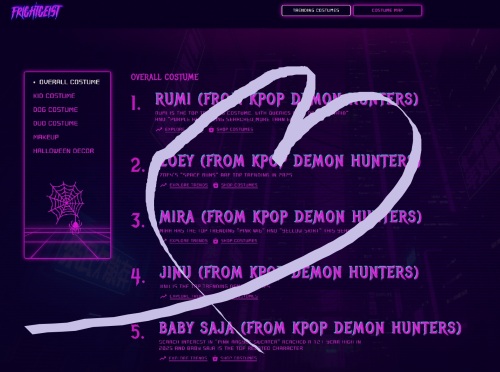
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-







