2010年06月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』7 ~ 楽しむ。
『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)今回が、第7回です。==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ7 (p146~p153)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・よい結果を出したい時ほど楽しむ・早く走りたいときほど、リラックスするのです。・陸上のボルト選手は、走ることを心の底から、楽しんでいる。・「自然体になる」ことが大切・「楽しむ」と決めてしまうことで、無駄な力が抜けていく・楽しもうと決めたら、後はやるべきことをやり続ける。・続けるコツは、楽しむこと・「すべてを楽しむ」#これができたら、最強、無敵ですね♪ ・「一生懸命に努力すること」が 「しなければならないこと」から、 「したいこと」になっていく・なかなか結果が出ないからこそ、 ものごとは楽しい。・実は、人は結果が見えないことが大好き。・すべての趣味というのは、うまくいかないことを楽しんでいるだけ。(p153まで)==========================「楽しむ」ということが極意のようにして書いてあります。本当にそうです。今日、新たな仕事が増え、忙しい1週間になることが確定しました。要は、楽しめるかですね。ただ1点に集約して、シンプルに現状をとらえ直すことができたので、これでまたやる気がバババッと出てきました。うれしくなってきました。「楽しむ」「楽しむ」でやっていきます。 ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.28
コメント(0)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』6 ~ 自分の仕事を「作品」にする
続きものの「読書メモ」の続き。 『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)今回が、第6回です。==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ6 (p138~p145)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・商品に魂が入ると 作品になる・企画のどこかに「想像を超えたこだわり」が、あるかどうか・やりたい企画の内容が、さも実現しているかのように 細部まで描かれている。・その企画が実現したときに、お客さまが得られる感動が 物語になっている。・普通ならばやらないところまで、 とことんやっている。・妥協せずに細かいところにこだわってモノづくりをする。・もはや商品ではなく芸術作品です。・つくり手の魂が入ることで、モノの価値がまったく違ってくる。・自分の仕事を「作品」にする・少しの差をつくるために、つくり手たちは、 強い思いを持って取り組む。・お客さまは、わずかでも、よりいいものに対して、殺到していく。・わずかな差を真剣に検討する。 (例)・あいさつの仕方 ・電話の受け答え など・一流といわれるホテルなどでは、 設備以上に、働く社員の意識、身の振る舞いが一流。・自分の意識を変えると、自分がかかわったことの価値が変わる。(p145まで)==========================昨日、「おそすぎないうちに」という歌の録音ファイル、およびオリジナル写真を取り入れたフォトムービー動画をネット公開しました。これも、ささやかかもしれませんが僕の「作品」です。自分が感動したことを、どう作品化するか。そういうモノづくりに挑戦するとき、自分のこだわりが問われています。教師としての「授業づくり」のときもそうです。どこまでできるか、いつも、自分との勝負が繰り広げられています。授業のことでは、算数だけでなく、「水害に関する防災学習」について、調べてきたことを教材として組み立て、授業として仕組もうと計画を進めています。水害学習は7月5日ですが、この日まで、せいいっぱい用意します。強い思いを持って取り組みます。そのために必要なことは、何でもやっていきます。 こういった本から学んだ「姿勢」を、実生活でも生かして、自らの取り組みを進めていきたいです。 ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.27
コメント(0)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』5 ~「やりたいことは、できること」
続きものの「読書メモ」の続き。 『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)今回が、第5回です。==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ5 (p96~p137)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・出会えたこと自体が奇跡のようなもの・なにごとも当たり前に思わないことで、 他人との関係がうまくいくようになったり、 自分自身が優しく、強くなったりすることができる。#「おそすぎないうちに」という歌を知って以来、 なにごとも当たり前に思わないようになってきました。 この歌のマイ録音を、本日公開しました。 歌詞の出るフォトムービーがYouTubeで見られます。・「今日が、私の人生で、最後の講演会」 このように考えて行う講演会は、疲れるどころか、 どんどん体の調子も良くなり、会場が一体感に包まれ、 本当に楽しく盛り上がります。・人生最後と思って、大切にいきたい。・コミュニケーションで最も大切なことは、 テクニックではなく、相手に好意を持つことです。・腹が立つのは、自己中心的になっているから。・「電話の取り方で世界が変わる」と思うと、楽しくなる。・「世界を変える打ち合わせだ」と思うと、楽しくなる。・外出するときには、 「世界を、ちょっと変えてきます」と言うようにしています。・「やりたいことは、できること」・なかなか結果が出ないのは、他人と同じやり方をしようとするからです。 自分らしいやり方を見つけていけばいいのです。・一流の人たちは、成果が出たからといっておごらず、 出なかったからといって投げやりになることはありません。・人を信じて、その夢を支援すれば、 自分もまわりからの支援を得られるようになり、 どのような壁にぶつかったとしても、必ず乗り越えられます。・「遅かれ早かれ、あなたは将来、世の中を変える人になると思うので、 自分のペースでやっていけばいいと思います。 私は、あなたを信じます」・壁を感じる地点 = 過去の限界 その先の挑戦する時間はすべて、 新しい自分になることができる素晴らしい時間になる・どんなに頑張っても結果が出ない時間を、 上司や先輩も経験している。・すべての限界は、過去の限界であり、 これからの限界ではありません。(p137まで)==========================この本、学ぶことが多いので、引用が多くなっています。名言のめじろおし。これでもかなり厳選しているのですが・・・。次回の更新も、お楽しみに。(^0^) ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.26
コメント(0)
-

合奏アレンジの初歩を学ぶ ~てっちゃんの楽しい合奏編曲講座
電子黒板の授業に役立つ電子教材を探して「東書eネット」に会員登録したら、「音楽」の合奏編曲の初歩を大変丁寧に解説しているサイトを紹介してもらえました。 ▼てっちゃんの楽しい合奏編曲講座これが、かなり凝っています!楽譜を見ながら、演奏を聴けます。しかも、どの音符を演奏しているのか、音楽ゲームのように音符がでっかくなって教えてくれます。読譜の勉強にもなりますね。作曲・編曲を学びたい僕のような初心者には分かりやすいサイトです。僕は趣味で曲作りもやっているので、自分の役に立つように、ブログにこのサイトのメモを残しておきます。=============================「てっちゃんの楽しい合奏編曲講座」 Vol.5 その2までのサイトメモ・メロディーの三度下でうまくハモれないときは、六度下で。 (ラならば下のドですね。)・「メリーさんの羊」、 前半は明るく長調でテンポ速め、 後半は暗く短調でテンポ遅めにアレンジしてみる。 #僕が今改良を加えようとしている 「HOME」という曲があります。 ちょうど、テンポをさわろうとしていたので、 参考になります!・コード進行の改良例 F→D7→G7と変える。 D7からGへ行った方が、より「劇的な効果」を生む。 D7はG(G7)へ解決する「終止形」の役目をしていて、よく使われる手法。 同じ理由で、C→C7→F もあり。・C(I)→Dm7(IIm7)→G7(V7)→C(I)という進行(終止形)は、 非常に良く使われる。#D(レ)もG(ソ)もC(ド)に行こうとする性質があるので、 レ → ソ → ド と、両方使おうとするのですね。 こういう理屈はよく忘れてしまうのですが、 覚えておきたいと思います。・こういう「香辛料」は、時々ちょっと使うから効果がある。 頻繁に使ったら、かえって単調になり、曲の印象がつまらないものになる。#理屈がわかって「おお、こりゃあいい!」と思っても、 多用すると逆効果、ということですね。 シンプルな中に、ちょっと混ぜてあるからいい、と。(^^;)・コードを変更することで、ベースラインをメロディックにする。 ファ(Fのコード)→ ミ(Cのコード)→ レ(D7のコード) ド(C)→ミ(C7)→ファ(F)→ファ♯(F♯dim)→ソ(C/G)→ソ(G7)→ド(C)# こういう、経過をスムーズにするためのコードの微修正は 「常套手段」らしいですが、 僕にはこのあたりが難しいです。 メロディックなベースラインは大好きです。 ドーシーラーソーとか降りていく順次下降のベースとかは 特に好きで、使えるときは使おうとします。・ペダルポイント: ソ、ソー、ソ、ソー のように、ひとつの音を長く持続するやり方 少し不安定な感じがしますが、前奏や間奏、場面転換等に多く用いられる。 その「不安定な感じ」から本編に戻ったときの安堵感や、充足感が とても心地良い。・中間部に鍵盤ハーモニカのソプラノ・ペダルポイント。 いっそ、ベースラインもペダルポイントにしてしまいましょう。# こういう編曲があるのは知っていましたが 「ペダルポイント」というのは初めて聴きました。 なるほど。実際にその編曲を聴いてみると、 もとへ戻ったときの感じが、確かにいい感じです。 曲1曲の中で変化をつけて戻ってこさせるときに 知っておきたい技法です。=============================作曲・編曲は大好きですが、最近ほとんどできていません。でも、作曲途中、編曲と中の曲がわりとあるので、時間がかかったとしても、チャレンジは続けていきたいです。曲ができたら、ネット上で公開しますね。(^^)ちなみに今までの公開曲は、いろんなところで公開していますが主としては僕の音楽のページで聴けます。 ▼にかとまの音楽のページ ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.26
コメント(0)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』4 ~「来てくれてありがとう」と思いながらあいさつする。
ちょっと空きましたが、続きものの「読書メモ」の続き。 『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)今回が、第4回です。==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ4 (p84~p)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・信頼されたとき、 人は信頼に応えたいと努力する。・「その社員を信頼する勇気を持つこと」・リーダーや上司になる人は、 人を信頼して、受け入れる勇気が必要・たとえば 「今日も会社へ来てくれてありがとう」 と思いながら、 朝のあいさつをするかしないか#ドキッとしました。 そんなこと思いながら、あいさつしてません。 というか、人によって、自分が避けられていそうな人には あいさつをするのを自分から避けています。 それに対して、 「今日も来てくれてありがとう」とか 「今日も出会えて、よかった。/ありがたい。」といった 感情・・・ これは、対極にありますね。 これを読んで、そう思いたい、そうありたい、 と思いました。 "To be, or not to be." そうあるか、それともそうあらないか、 そういう、あり方が大切である。 「あいさつをする」という行為の裏側にある、 感情のあり方が、試されている、と思います。 (誰に?(^_^;))・自分が成長することの楽しさがわかってくると、 他人の長所からひとつでも多くのことを学びたくなってきます。 そして、「ありがとう、教えてくれて」というふうに、 自分が学ぶべきことに気づかせてくれる他人に、 感謝したくなってくる。・相手の欠点からも、学ぶことができるようになる・ 部下を育てる =やる気にさせる ↑ 上司が部下から学ぶ・新入社員が話す内容を聞いて、 上司は、自分が新入社員だったころのことを思い出して 「おれも、そういう気持ちで、この会社に入ったんだったなあ」 と、志を新たにする。・若い社員の持っている情熱や純粋さ、吸収力などを見て、 上司が自分に足りないところを反省し、成長につなげます。 そういう上司がたくさんいる会社ほど、 若い社員も学ぶ姿勢を持つ#学校も同じ。 教師が学ぶ姿勢を持つなら、 子どもは学ぶ姿勢を持つだろう、と思います。 子どもから学んでいたか。 今日も、反省です。(>。<)△上司が教えることばかりを意識していると、 部下の欠点ばかりが気になってしまいます。◎相手の長所を見ても、短所を見ても 学ぶことができると考えると、 それぞれに個性を認め、尊重し合うことができるようになる。(p95まで)==========================この本、学ぶことが多いので、引用が多くなっています。これでもかなり厳選しているのですが・・・。まあ、それはそれとして、このままこの本の読書メモは続けていきます。次回の更新も、お楽しみに。(^0^) ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.24
コメント(0)
-

最近、将棋にこっています。
今日はクラブがありました。僕は、今年から新設された「囲碁・将棋」クラブを担当しています。担当を熱望して、叶えてもらいました♪で、そこに参加している子どもで一番将棋の強い子と今日やりました。前回、もう一人の担当の先生がまさかの惜敗を喫したので僕まで負けては先生の面目に関わるとヒミツで必死に特訓していました。そのかいあって、からくも、勝ちを拾わせてもらいました。いやあ、最近の子供は強いです。まだルール習いたての子はもちろんまだまだ強いとはいえないのですが、趣味でずっとやってきていて、大会とかにも出ている子は、すごい強い。今回は偶然勝てましたが、次回はどうなるかわかりません。また、特訓をしておきます。(^^)ちなみに、特訓はインターネット将棋道場の「将棋倶楽部24」でやっています。無料でネット将棋ができて、同じレベルの全国の人と戦ってその戦績に応じてレーティングという持ち点が上下する大人気サイトです。参加している方の中で一番弱いグループ、レーティング200~300ぐらいのところを行ったり来たりしています。本も買いました。まだ注文したばかりですが。 『将棋1手詰入門ドリル』(椎名龍一 、池田書店、2007、980円)僕みたいな初級者には、いい訓練になりそうな本です。今回はコンビニ受取を指定したので3日ぐらいしたら、通勤途中のコンビニに受け取りに行きます。(^。^)6月いっぱいなら、サークルK・サンクスで受け取るとポイント3倍!というキャンペーンをやっているのです。(笑) ブログ王ランキング
2010.06.21
コメント(0)
-

「読書メモ」リストを更新
「読書メモ」のリストを更新しました。過去に読んだ本にかかわっている部分で新しい話題を書いたときは、過去のところに黄色いセルで、追記部分を目立たせています。今回更新部分の中では『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』が一番心に残っています。続編も読みたいです。 ブログ王ランキング ▲よければ1クリックお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.06.20
コメント(0)
-

子どもが輝く「魔法の掃除」「自問清掃」のヒミツの講座(神戸 6/26)
ヒミツの講座なのですが、案内します。(情報元は「Teachers Online会員制メールマガジン「先生生活」第61号」)このブログでもかなりオススメの本としてとりあげていた「自問清掃」。その著者による「自問清掃」の講座が神戸市勤労会館にて開催されます。日にちは、来週の土曜日。▼講座要項は、こちらです。「自問清掃」の取り組みには本を読んで本当に感動したのでぜひ生のお話を聴いてみたいところです。ただ、都合により僕はちょっと行けない見込みですが。おそらくすばらしい講座になると思います。興味のある方は主催の「神戸おもちゃばこ」さんにぜひ、お問い合わせされはいかがでしょうか。先着順で、36人限定らしいですよ~。(^。^)『「魔法の掃除」13カ月 ~「Iメッセージ」を語れる教師』(平田治、三五館、2007、1400円)『子どもが輝く「魔法の掃除」~自問清掃のヒミツ』(平田治、三五館、2005、1400円) ↑ この本の読書メモは、こちら。 その1 その2 その3 その4 その5 ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.06.20
コメント(0)
-

シエナ・ウインド・オーケストラ 舞鶴公演♪
舞鶴に行ってきました。今が旬だという、岩がきやとり貝を食べました。(^^)メインは、シエナのコンサートです。この演奏が、とにかく正確!ジャン、ジャン、ジャン、など、全体演奏で短く切る音を続けるところなど、全体があまりにも正確にそろっているので、感動しました。「うまい演奏」とはどういうものか、というものを考えますに、・正確であるというのはかなり大きいな、と改めて思います。例えば自分の演奏だと、自信を持ってできたと思っても、客観的に見れば8割できていて、ええとこです。シエナはプロの吹奏楽団ですが、プロでも、本当に正確な演奏、というのはなかなか難しいと思っています。とくに、オーケストラになると集団でタイミングを合わさないといけない。出だしを合わせるだけでなく、音の伸ばしや、休符のタイミングまで合わすとなると、やっぱり若干ずれが出てくるのが、普通です。シエナの演奏は、最初聞いたとき、DTMみたい、と思いました。(DTMとはDesktopMusicのことで、コンピュータによる打ち込み音楽です。)それぐらい、人間わざと思えないぐらい正確な演奏に感じました。「迷走するサラバンド」での複雑なリズムや、「スターウォーズ」のラストのジャン、ジャン、ジャンなど、あまりにもきれいにそろってびっくりしました。ただ単に正確さだけを追求しているのではなく、思いっきり音を鳴らして、周りの音を気にしないかのごとく思いきりよく自分ペースで鳴らしている・・・ように見えて、実は合っている、というそのバランスがよかったです。例えばグロッケンの音はかなりよく聞こえてましたが、この楽器は目立ちすぎるだけに、合わせようとすると音が控えめになりがち。それが、全然控えめにならずに、気持ちよくでっかい音でとにかく鳴り続けてました。僕の経験でいうと、これってけっこう勇気のいる演奏だと思います。さて、シエナの最後は、会場の有志も楽器を持ってステージに上がります。僕も上がりました。楽器なしで。(笑)おそらくただ1人、歌を歌って参加しました。とにかく大人数での合奏。客席からは全然聞こえていなかったと思います。僕の歌を聴いてくれていたのは、そのときちょうどお休みになる、周りの演奏者たちくらい。客席からスネアドラムやシンバルをもって上がってこられた熱意あるパーカッションの方々、そしてすぐ前のトロンボーンの方々、あのとき歌っていたのは、僕ですよ~。(^0^)演奏が終わったあとで、シエナのバスドラム奏者の方と少しお話をしました。そしたら、「先生ですか?」って。一個人として参加していたのに、なんでばれたのかな?ステージには中学生や高校生がたくさん上がっていたので、もしかして引率の先生だと思われたんじゃないか、と思います。(笑)ステージでは、かなり気持ちよく歌えました。シエナと同じステージに立てる、というのが、立ってみてわかりましたが、これだけですごいメリット。プロの方が出す音を間近で聴ける、間近でその演奏を見れるんです。隣のバスドラムの音、僕が今まで聴いてきた音と、全然違ってました。音の深みがすごい。いや~、勉強になりました。プロの方や、熱意ある多くの皆さんと一緒に歌って、僕の歌のレベルが少し上がった気がします。技能って、うまい人と一緒に演奏すると、1ランク上がるんです。 楽器は関係なしに、パートの壁を越えて、演奏者としてのレベルが伝わってくるんです。 うまくなりたい方、シエナのアンコールのように、演奏のうまい人と一緒のステージに立てる機会をぜひ見つけて利用しましょう!(^0^) ブログ王ランキング
2010.06.19
コメント(2)
-

明日はシエナ・ウインド・オーケストラ 舞鶴公演♪
今日は気持ちよく授業できました。この調子で、明日はとっても楽しみにしていたコンサートに行ってきます。吹奏楽のコンサートですが、演奏団体が、すごい。吹奏楽のプロ集団、シエナ・ウインド・オーケストラ。佐渡裕さんが育てた吹奏楽のプロフェッショナルチームです。CDでは聴いたことがありますが、生で聴くのは初めて。今からとても楽しみです。アンコール曲目は、楽器を持ち寄って会場の人も参加するんだとか。こういう企画は大好きです。僕も参加するぞ~!でも、楽器がない・・・。そういうわけで、鍵盤ハーモニカか、「歌」で参加することになりそうです。曲目は、マーチ「星条旗よ永遠なれ」。僕がこれを初めて演奏したのは、広島大学吹奏楽団にいたときです。パーカッションだったのですが、大変気持ちよくシンバルを鳴らせる曲。大好きでした!今回、シンバルは持ち寄れないのが、残念。(^^;)鍵盤ハーモニカはうまく吹けないので、ちょっとは自信があるのは歌だけですが・・・楽器を持って演奏するのに、歌っていていいんでしょうか。歌の歌詞と楽譜は苦労してネットで探し当てました。歌詞はWikipediaに出ていたので割と早目に分かったのですが、その歌詞を歌う楽譜や、歌っている演奏が全然出てこなかった!英語検索でアメリカにまで行っちゃいました。▼歌の楽譜▼歌の演奏(The Stars and Stripes Foreverfrom American Revolutions by M Ryan Taylor )テンポが速いのと、英語がよくわからないので、やっぱり歌の方も難しそう。明日は行く前に自宅練習しておきます。(^^;)では、明日、行ってきます!(^0^) ブログ王ランキング
2010.06.18
コメント(4)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』3 ~「役に立ちたい」
今週は、かなりへばっています。元気出して、行こうと思います。明日の授業は、3年生の「かさしらべ」第1時と第2時、4年生の「垂直と並行」第2時と第3時。いろんなクラスに入っている都合上、授業内容が錯綜しています。今年度はおもしろいといえばおもしろいし、忙しいと言えば忙しいです。(^^)まちがいなく、勉強になる1年です。それでは、続きものの「読書メモ」の続き。今回が第3弾。書名は、これです。↓『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ3 (p64~p83)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・あなたのまわりにいる人が、 あなたのことを、すべて教えてくれます。・私たちにできることは、自分の器を大きくすることしかありません。・相手に期待する気持ちを切り替えて、 その相手に感謝できることを見つけ出す。・その人にどうしたら好意を持つことができるのかを考えてみる。→・自分の相手に対する意識を変える・やる気にさせる支援を行うコンペ 「メンタリング・コンペ」 (1)経営者から本音で、困っていることを話してもらう。 (2)質疑応答の時間を取った後、 全員でその経営者に対して、 やる気にさせる支援の内容を、紙に書いて渡します。 (3)経営者に、 自分をやる気にさせてくれたコンサルタントのベスト3を選んで、 その理由とともに発表してもらう。 (4)互いにコピーを取って共有する。#実際に福島さんが経営コンサルタントの方向けに行っているそうです。 「なるほどなあ」という仕組みが見えます。 広く、他の会議・ミーティングでも、使えそうです。・「その人の役に立ちたい」という気持ちを持つほど、 伝わる。・お互いにみんな助け合う:「相互支援」・社員がみんな一緒に成長する。・まずは、相手にしてほしいことを、自分からしてみましょう。 相互支援の関係をつくるためには、 はじめはこちらから、支援することが大切です。(p83まで)==========================「相互支援」の関係づくりは、以前のブログでも、「僕が目指している教育のありかた」といったものにつなげて書かせていただきました。福島さんの本を読むと、「相互支援社会」をめざして、自分から動こう!というやる気にさせられます。では、また。次回の更新も、お楽しみに。(^0^) ブログ王ランキング ▲よければ応援のクリックをお願いします。感謝します!
2010.06.17
コメント(0)
-

(算数)3年 かさしらべ ~「リットル」の話
算数の教材研究の話です。そろそろ3年生で「かさしらべ」の授業をします。そこで、「リットル」について調べてみたら、面白いことが分かりました。・デシリットルは、実際に使われている。・筆記体での「?」という表記は、国際的には認められていない。・欧米での飲み物には、CL(センチリットル)が使われる。など。参照元は、Wikipediaです。デシリットルが使われている写真も、見ることができます。 ブログ王ランキング
2010.06.15
コメント(2)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』2 ~「うまくいかなくても応援したい」
元気は、いろいろなところでもらえます。こういった、読書からも。(^^) 『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)この本の中身を、読み返していきます。今日はその第2回。==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ2 (p46~p63「第1章 やる気がぐんぐん出てくる法則」の終わりまで)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・本当にやりたいことをやる#ここ2年くらいの僕の生活コンセプトは、 「やりたいことをやる」です。 「やりたいことは、全部やってみようかな」 という気持ちで、何でもやっています。 やりたいことがある、ということが、 すべての出発点です。・困難に立ち向かっている姿、一生懸命に生きている姿が、 他人に勇気を与える。・「うまくいくだろうから応援する」のではなくて、 「うまくいかなくても応援したい」という人を集める必要がある。#今度選挙がありますが、 選挙に出る方など、社会の中で多くの人に応援してもらって 世の中を変えることを志しておられる方には、 こういった要素が一番必要なんだろうと思います。 もちろん、具体的な成果とか、結果は大事ですが、 それよりも、努力とか、想いとか、やっていることの過程を知って、 「たとえうまくいかなくても応援したい」と思えるかどうか。 現代社会は一見すると成果主義の世の中かもしれません。 しかし、生き様や行動力・意志の強さから魅力を感じ、 人が人を応援しようとする社会が、確実に来ていると思います。 僕も、人と関わることをやっていく限りは、 成功や失敗以前に、応援される人物でありたいと願います。・プレゼンテーションにおいて大切なものは、 「人の心を動かす感動と共感」・発表者がプレゼンテーションをつくる過程で、 本気で自分の弱さや過去と向き合い、 それでもあきらめず夢に向かって進む姿を周囲の人に見せること(p63まで(「第1章 やる気がぐんぐん出てくる法則」の終わりまで))==========================元気出してがんばります!次回の更新も、お楽しみに。(^・^) ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ありがとうございます。
2010.06.15
コメント(0)
-

誕生日
11日(金)が誕生日でした。今日、子どもから、思いがけなくプレゼントをもらいました。(お手紙と、手作りの首飾りが入っていました。)算数の教科だけ教えに行っている3年生からです。金曜は行事の関係で授業に行けなかったので当日渡せなかったと言っていました。担任でもないのに、おぼえてくれていて、とてもうれしいです。(^^) 年齢は、35歳になりました。サイコーの1年にしていきます。(^-^)よろしければ、応援してください。僕も、皆さんのお役に立てたら、と思います。今後とも、よろしくお願いします。(^0^) ブログ王ランキング
2010.06.14
コメント(2)
-

福島正伸『1日1分元気になる法則』1 ~思い出してみよう!
どうも最近、元気がない。(>。<;)そういうときには、こういう本を読みます。『1日1分元気になる法則』(福島正伸、中経出版、2010、1300円)==========================【内容情報】(「BOOK」データベースより)2万5000人の人々を毎朝一通のメールで励まし続けている著者が語る、人生が変わる考え方24。==========================福島さんの本は、かなり元気をもらえます。発売後すぐに読んだ本ですが、元気になるために、もういっちょ、読み返します。(^。^)それでは、恒例の読書メモ、いってみよう!==========================『1日1分元気になる法則』読書メモ1 (p45まで)(・は本の記述の抜粋、#の緑文字は僕のコメントです。)・なにごとも当たり前と思わないこと。・すべてに意味があること。・そこから何を学ぶかが大切であること。#先に紹介した本『生きがいの教室』と ちょうど、つながる部分ですね。(^^)・応援することは、応援されることだ。・思い通りにならない他人が、 自分を成長させてくれる。・成長するほど、他人の長所が見えてくる。・話す言葉を選ぶ前に、話す気持ちを選ぶ。 ・はじめに考えてみてほしいのが、 自分の体験を振り返ること。・小さいころに、すごく楽しかったことやうれしかったこと。#僕の場合、何かなあ。 音楽は、今でも好きです。 子どものころから、音楽の時間は好きでした。 学校で習う歌も好きだったし、 ラジオから流れてくる歌も好きだった。 FMラジオの放送曲をたくさんテープに録音して、 3000曲ぐらいは、カセットに集めました。 たくさん集まったので、リスト化したり、 ベストセレクションテープを作ったりしました。 ビックリマンシールを集めるのも、楽しかった。 自分でお話を作るのも、楽しかった。 うんと小さい頃は、 チラシの裏などの裏紙に、 好きなように、お絵かきするのが、とても楽しかった。 忘れてしまっていたけど、 自分には「楽しむ」才能がある、と思い出せるのは、 うれしいことです。(^0^) おお、なんだか、気分がよくなりました! これは、すばらしい効果ですね!・使命を持って果敢に行動している人たちに、出会うこと。#今までも出会ってきました。 そのたびに、元気と勇気をいただきました。 同僚の先生、本の著者、セミナーの講師・・・etc. だんだん、身近な人も、何かしらに果敢に挑戦し、行動しているんだな というのも分かってきました。 元気は、そういった気づきからも、分けてもらえますね。(^0^)(p45まで)==========================このあとも、かなり、かなりいいことが、書いてあります。福島さんの言葉は、本当に人を元気づけます。ネット動画で、福島さんの言葉を使った「宝地図ムービー」も見ることができます。これもまた、元気づけられます。本当に!ぜひ、見てみて下さい。(^0^)【宝地図ムービー】「夢」が「現実」に変わる言葉音楽も、いい感じなんです。これがまた。僕は何度も視聴しています。作ってくださった方、ありがとう!! ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ありがとうございます。
2010.06.13
コメント(0)
-
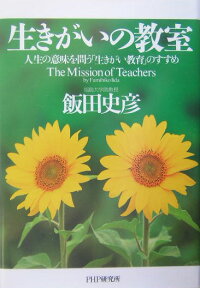
飯田史彦『生きがいの教室』4
今日は「あとがき」についてふれまして、この本の読書メモの最終回とします。といっても、著者の他の本と、著者のサイトの紹介だけです。 『生きがいの教室 ~人生の意味を問う「生きがい教育」のすすめ』 (飯田史彦、PHP研究所、2004、1400円)==============================『生きがいの教室』読書メモ4 (p277~)『愛の論理 ~私たちは、どこまで愛せばゆるされるのか』(飯田史彦、PHP文庫、2002,700円)↑スピリチュアルな内容は出てこないが、 旧来の学問分野の範囲内で、同じ主張を展開。 多くの学校図書館に置かれている。 最も安心して生徒に紹介できる本として、教育上の効果が期待される。・著者サイト 飯田史彦研究室へようこそ! http://homepage2.nifty.com/fumi-rin/==============================『愛の論理』もぜひ読んでみたい本です。評判もいいらしいです。買うにしても、文庫だと安いのがうれしいですね。 飯田先生のサイトは、たま~にのぞきに行きますが、そのたびに様変わりしています。けっこう更新されているようです。(^^)音楽活動もされているのが興味深いです。僕と一緒ですね。(^。^)僕の音楽活動はほぼ休止中ですけど・・・。 ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.06.10
コメント(0)
-
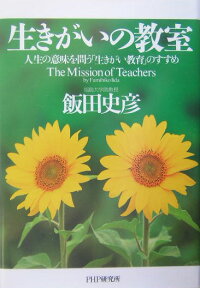
飯田史彦『生きがいの教室』3 ~子供たちに対する気持ちや見方の変化
忙しい。かなり忙しいです。でも、昨日読み返した『生きがいの教室』の中の記述、・いかなる状況にあっても幸福を実感できるように・「自分の人生を生ききること」に徹するということを大事に、忙しいことに感謝したいと思います。では、今日は「小学校の試み」のところを具体的に引用します。『生きがいの教室 ~人生の意味を問う「生きがい教育」のすすめ』 (飯田史彦、PHP研究所、2004、1400円)==============================『生きがいの教室』読書メモ3 (p217~)(福島県 大室圭次郎先生より)・子供たちに対する気持ちや見方の変化・生きがい論を知る前まで、 あまり良い印象を持っていなかった子供ほど、 「自分よりもよほど魂のレベルの高い方で、 これほど困難な人生計画を立てていらっしゃる、 すばらしい方なのだ」という、 180度違った見方になりました。・自分の方が、「子供たちから貴重な学びをさせていただいている」・自分が担任した子供たちは、(略) いわゆるソウルメイトなのだという認識に立つことができてからは、 自然に子供たちへの愛情や感謝の気持ちがわいてくるようになりました。(『親子で語る人生論』の中で) ・この本の中のお父さんは、 「死にたくなるほど人生について悩むということは、 大切なことだ」と言って、喜んだ。 (参考リンク「・「親子で語る人生論」(飯田史彦著 PHP研究所)を授業する」)(p276 まで)==============================『親子で語る人生論』、楽天では売り切れですが、この本を読んで、読みたくなりました。出版社サイトに詳細が載っていました。『親子で語る人生論』(リンク先:PHP研究所 書籍紹介)============================親に聞きたくても、聞けなかったこと。子に伝えたくても、伝えられなかったこと。数々のベストセラーを送り出した著者が画期的手法で世に問う、時代を変える人生論。 ============================出版社サイトでも売り切れ表示だったので手に入りにくいかもしれませんが、手を尽くせば、手に入るかな?さて、いよいよ次回、最後の「あとがき」のところを引用して、この本の読書メモは終えたいと思います。それでは、また次回! ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.06.09
コメント(0)
-
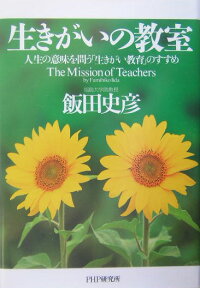
飯田史彦『生きがいの教室』2 ~「生きがい論」の特徴
『生きがいの教室 ~人生の意味を問う「生きがい教育」のすすめ』 (飯田史彦、PHP研究所、2004、1400円)この本の紹介、部分抜粋を続けます。(第1回はこちら)==============================『生きがいの教室』読書メモ2(p43~75 #の緑文字は僕のコメントです。)(「生きがい論」の特徴) ・すでに幸福であることに気づくための人生論・「いかなる状況にあっても幸福を実感できるようになった状態」 に至ることが人生の目標・「人生は思い通りにならないからこそ価値がある」という前提・「喜びや楽しみだけではなく、苦悩や悲しみを含む あらゆる体験・感情・思考を通じて成長し、 精神性を高めていくべきである」という観点・物質的成功とは無関係に、 「人生における全ての体験に価値を見出すための精神性」 を身につけようとする人生論#スピリチュアルな観点をとる意義がいろいろと語られます。 小林正観さんや斎藤一人さんなど、 他の「幸せになる考え方」を語られている方と かなり共通する部分が多いです。・他人をうらやましく思うことが、 いかに無意味なことであるのか・私たちは、他人の人生と比べないで、 「自分の人生を生ききること」に徹すれば、それで良い。・「自分の人生に恋すること」が、大切。 自分の人生に恋をしている人は、 「人生の中で起きてくる出来事を、全て楽しんでやろう」という決心が できあがっている。 だから、嫌なことがあったり失敗しても、 「やれやれ、またお出ましになったか」という感じで、 大らかな気持ちで対処することができる。#この表現はおもしろいな、と思ったので引用しました。 「恋をすれば、すべてがハッピー」みたいなことがありますけども(^^;)、 そういうワクワク・ドキドキ、それから 「心の余裕」、 そういったものが、生活を彩る。 こういう考え方・精神状態にいる人にとっては、 「つまらないことなんかない」ということになるのではないでしょうか。(p75(第1章終了)まで)==============================第2章は、ちょっと飛ばしまして、次回は「小学校の試み」の書いてあるページから引用します。(ページで言うと、p217~です。) それでは、また! ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。
2010.06.08
コメント(0)
-

楠桂『不育症戦記 ~生きた赤ちゃん抱けるまで』
『不育症戦記 ~生きた赤ちゃん抱けるまで』(楠 桂、創美社コミックス、創美社/集英社、2010、980円)==============================お腹の中で、赤ちゃんが育たず流産・死産をくりかえしてしまう『不育症』年間患者数7万人以上妊娠女性の2~5%が直面している現実です。 ==============================我が家に赤ちゃんが来て、7か月になります。赤ちゃんを抱けるってしあわせ!ありがたい!っていうことが、本当に実感できる本です。著者の体験に基づくエッセイマンガ。現実にこういったことあるのだ、ということを知ってよかったと思います。本を読むことで、自分だけのことだけでなく、他の人の人生も知ることができること、それによって自分の人生やその周りを取り巻くすべてが、ありがたいものに変わってくるということ。知らなかったことを知らせていただけるありがたさをかみしめながら、楠桂さんや、不育症で悩まれている多くの方々に、思いをはせたいと思います。楠桂さんの絵柄は久しぶりに見ました。男性でも抵抗なく読める、マンガです。「不育症」という言葉はこのマンガを読むまで知りませんでした。こういったことがあるのだということを知ってもらうためにも、広くいろいろな人に読んでもらいたいと思います。 ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。 (「おすすめ本」のブログランキングに新しくジャンル登録しました。 まだ登録したてで実績がないので、ぜひ、クリックお願いします!(^0^))
2010.06.05
コメント(0)
-

『エンゼルバンク』12巻~「目標」と「計画」を混同するな!
最近、PCの調子が悪く、システムのリカバリばかりしています。新しいPCにデータと設定を全部引っ越さないとダメかな・・・。今日、学校でおこなった電子黒板での授業も映像の投影がなかなかうまくいきませんでした。モニタケーブルの接触不良によるもの。原因は分かっているのですが、授業開始時間になってもまだ映像がうつらないのであせりました。準備が授業時間に食い込んだらだめですね。さて、話は変わりまして、マンガ『エンゼルバンク』第12巻を昨日読んで「なるほど」と唸ったので、今日はそれを書いておきます。(『生きがいの教室』の読書メモがまだ途中ですが、それはまた改めて。)『エンゼルバンク ドラゴン桜外伝』(12)(モーニングKC、三田紀房、講談社、2010/4、560円)=============================『エンゼルバンク』第12巻 読書メモ・目標がゴール地点だとすれば そこへの行き方を示す地図が計画書になる。 常に最短ルートで行けると期待するのではなく、 道に迷ってもゴールまでいく準備をするのが計画だ。#「目標」と「計画」を混同するな、という話が語られます。 思い当るところがあり、興味深いです。 「常に最短ルートで行ける」と期待して その通りに行かないだけで失敗するというのは 今までによくあった経験です。 それを見越して計画を立てなければならない。 「失敗」込みの、地図のようなものが、「計画」。 なるほど!・どんなことも決めつけて考えるな。・その直線的な思考回路が問題なんだ。 あまりにも単純で、視野が狭すぎる。・他にも色んな方法がある・・・ それに気づくことが大事なんだ。・今の時代、 満足いく人生を手に入れるための方法は山のようにある。 自分に合った乗り物に乗り換えて たどりつけばいい。 焦る必要はない。=============================12巻、出たばかりなのにもう13巻も出たそうです。はやっ!『エンゼルバンク』(13)(モーニングKC、三田紀房、講談社、2010/5、560円)このマンガは、表面的には見えていなかったものの裏側に気づかせてくれるので、おすすめです。 ブログ王ランキング ▲応援のクリックをお願いします。ブログ継続の力となります。 (「おすすめ本」のブログランキングに新しくジャンル登録しました。 まだ登録したてで実績がないので、ぜひ、クリックしてください!(^0^))
2010.06.03
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1





