2010年12月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

『教師とSCのためのやさしい精神医学』12~「選択制緘黙(かんもく)」
大みそかですね。僕が住んでいる丹波市では昨日、今日ときれいな雪が見られました。今日はだいぶ積もって、すっかり雪国です。今年1年、ありがとうございました。最後に、ずっと続いている「特別支援」関係の読書メモ、第12回(最終回)を書いて、区切りよく終わりたいと思います。 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)第12回(最終回)。最終章、「青年期までに診断されるその他の精神障害」から、特に「選択制緘黙(かんもく)」のところを 取り上げます。昨日登場してもらった「カントク」のキャラクターに再度登場してもらい、本書の内容をえりぬきでしゃべってもらいます。(笑) ================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』 12 (p171~。緑文字は僕のコメントです。)今日は、<選択制緘黙>についてとりあげるぞ。アイアイサー!<場面緘黙>という名前のほうがおなじみだな。 ある特定の場面(たとえば学校)において、 まったく(あるいはほとんど)言葉を発しないものをいうんだ。別に心配することはない。 たっぷりと、そしてゆったりとかかわってあげなさい。ブリーフセラピーの研修では、 よくこの<選択制緘黙>の話を取り上げるんだ。 <しばしば問題の周辺にリソースがある>という話をする際に。リソース、つまり、問題解決につながる資源、ということですね。「しゃべれない(口)」という問題の周辺とは何だ? そう、それは「見る力(目)」であり、「聴く力(耳)」だ。 実際、彼らは非常によく周りのことを見ているし、 周りの話を聴いている。僕自身も、あまりしゃべらない子どもだったので、 よくわかります。 しゃべってコミュニケーションしないからといって、 周りを気にしていないかというと決してそうじゃない。 かえって、目や耳でコミュニケーションを図ろうとしているようなところは 強かったですね。何か返答を彼らから期待するのでなく(ここ重要!)、 ただただ声をかけたり、話したりしてあげる。選択制緘黙だけでなくて、言葉の遅れがある子どもさんでも、 そうですよね。毎日毎日、一滴ずつでもいいから、 いいメッセージを彼らに送り続けてあげてください。あとは、彼らの得意な「発信チャンネル」を見つけてあげること。 「書く」あるいは「描く」というチャンネルは非常に得意だという子もいる。 あるいは「造る」が得意な子もいるし、「奏でる」が得意な子もいる。 この子はどの「発信チャンネル」が優勢なのか、 それが見つかれば、コミュニケーションもかなりスムーズなものに なっていくぞお。 僕も、「しゃべる」ことより、「書く」ほうが好きです。 だからこうやってブログを書いているわけですが。 絵を描くのも好きでしたし、レゴブロックを組み立てるのも、 音楽を演奏するのも好きでした。 音楽は今もですが。 そういう「発信チャンネル」があると、 自分自身が、とてもラクになれます。 人それぞれ、「発信チャンネル」はちがっていいですね。 それを認め合える社会を作りたいと思います。 ===============================これで、 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』の読書メモ、そして年内のブログを終わります。ここまで読んでくださって、ありがとうございました。来年は、飛躍の年にするべく、ブログもパワーアップを図っています。新キャラクターとして、「てんちゃん」に登場してもらい、さらにブログを明るく楽しくしていきたいと思っています。(素材工房Engel Heart さん作成のフリー画像素材から拝借します。) また来年もよろしく。よいお年を。 (^0^)アクセスなう、感謝! 応援クリック! ブログ王ランキング
2010.12.31
コメント(2)
-

『教師とSCのためのやさしい精神医学』11~自尊感情や自己効力感を高める対応(^0^)
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)学校教育に対するお役立ち情報満載のこの本。おかげでとりあげるのが今日でもう第11回目。本の中身も、終盤を迎えています。 さきほど、「読書メモをおもしろくしたい」と書いたばかり。今日は実験的におもしろくアレンジしていきたいと思います。本書の内容に対するリアクションを工夫していきます。本書の内容は、「DB」の監督画像を拝借して、今までの ・ の代わりに でいきたいと思います。(笑) 内容は「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」 の後半、学校での対応について の第3回です。 下の(3)ですね。(1)(2)は過去ログを参照してください。 (1) ADHDの認知特性に合わせた対応 (2) 一貫した対応 (3) 子どもたちの自尊感情や自己効力感を高める対応================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』11(p163~170より。緑文字は僕のコメントです。)5.<子どもたちの自尊感情や自己効力感を高める対応>通常、ADHDのある子どもたちは 「自己コントロール感」が非常に低い。ほう!なるほど! ★まずは、「自分はやれる!」あるいは「やれている!」という感覚を 子どもたちにもってもらうこと。ふむふむ。 そのためには・・・ ・タイムリーにほめる。・「増やしたい行動」をしたならば、 そのときその場でほめる。・具体的にほめる。 「今日の授業態度はよかったよ」 ではなくて、 「○○の時間は、ちゃんと席について○○を一所懸命やってたね」 のほうがいい。漠然としたほめ方ではなく、 ちゃんと見ていないとできないほめ方をする、ということですね。そして、「例外」にかかわるこれについては、 ブリーフセラピーの本にめっちゃくわしく書いてありますね!「ああっ、たたいちゃう! と思って、 先生ハラハラして見てたけど、 今○○くん、たたかなかったよね! すごい、すごい!」 と、まずは ほめる。 ・そして 「どうやったの!?」 または 「どうして今 たたかずにすんだの?」 と言葉を続ける。 ・少なくとも、うまくやれた理由を本人に考えさせる。本人の言った答えに対しては全部支持! です。答えられたことについて、またほめる。◎こうした「例外」へのかかわりを通して、 本人の中の 「自分は衝動をコントロールできている /何かに集中していることがある」 「自分はその力を持っている」 という感覚を育てる「例外」は必ず存在します!一般的に、ADHDのある子に対してほめる際には、 こちらがびっくりしているという感じを伝えるような、 何らかの表情やアクションを含ませた方がいい。そうなんだ!あんまり言葉は多くしないほうがいいなんとっ!!Vサインを送るとか、頭をなでるとかで伝えるだけのほうが よいこともある。(やったね!) 言葉を主に使うのは、先ほどの 「どうやってやったの?」 の部分。「○○がよくできたね」 とほめるよりは、 「○○してくれて、ありがとうね」 と言ったほうが入る子も多い。 (ありがとう!)その子ばかりでなく、ほかの子のことも、 普段から十分にほめておいてください。 みんなすごいぞ~!!ほかには、役割を与える。「自分は周りから評価されている」 「自分は周りによい影響を与えることができる」 といった感覚を育てていきたいですね。同感です!(p170まで) =============================== リアクションを入れて、読書メモを明るくしてみたつもりですが、どうだったでしょうか。 これで第6章は終わりです。イラスト無料素材 子供や赤ちゃんのイラストわんパグさんの画像をお借りして、楽しくリアクションをしてみました。次回は最終章、「青年期までに診断されるその他の精神障害」を参照します。特に「選択制緘黙(かんもく)」のところを取り上げる予定です。 ↓僕も 「自分は周りから評価されている」 「自分は周りによい影響を与えることができる」 と思いたいので、よかったら、クリックしてください(^0^)↓ ブログ王ランキング
2010.12.30
コメント(0)
-
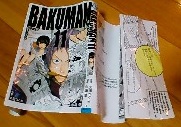
ブログリニューアル予告!
おかげさまでブログのアクセス数は去年の同時期に比べて格段に上がっています。だいたい、毎日500アクセス台です。これを 1日10000までもっていきたい!(オイオイ)そのためには、もっとおもしろくしないといけない。『バクマン。』11巻が昨日出ました。僕が読んだ後、1歳の娘が読みたがるので渡したらもぅすでにカバーはボロボロです↓ このマンガの主人公は、マンガをおもしろくするためにとにかく真剣です。主人公の一人が気づきました。「ストーリーはいい。 でも、絵が暗い。 もっと 明るくないと!」このブログも同じです。ためになる、しかもおもしろい。このシンプルなことを目指していきます。何より、書いている本人が楽しいものを! 「読書メモ」もアレンジしていきたいと思っています。来年の「読書メモ」はおもしろくしますよ!ま、今日は予告だけということで・・・。 (^0^)アクセスなう、感謝! 応援クリック! ブログ王ランキング
2010.12.30
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』10~学校での「一貫した対応」
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)上の本の読書メモの第10回。う~む、年内に、終わるかな。「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」 の後半、学校での対応について の第2回です。 (1) ADHDの認知特性に合わせた対応 (2) 一貫した対応 (3) 子どもたちの自尊感情や自己効力感を高める対応 を順に、参照していっています。 今日は <一貫した対応>のところです。前回はこちら。 ================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ10 (p156~163より)4.<一貫した対応>・「問題行動」というものは、 チグハグな対応をしていると、拡大していく傾向がある。・基本的な対応方針については、 きちんとスタッフ間で話し合って、共通認識をもっておきましょう。○対応の基本方針策定にあたって ・「当面の目標」にからんだものであること ・学校からその子を排除するようなものではないこと・ADHDの場合、「最終」ゴールは、 「落ち着いて、皆と仲良く過ごせるようになること」・「誰が」「どこで」「いつまで」ということに関して、 コンセンサスをつくっておきましょう 「どのように」というのは、細かく決めないほうがいいかもしれない。 それぞれのスタッフが、それぞれの持ち味を活かしたかかわりを 自由にした方がよい場合が多い。 どうやるのかはその人に任せた方がいい、という考え方、賛成です。 僕もその方が動きやすい。・個々自由にやって、 「こうやったらうまくいったよ」ということの情報交換は 頻繁に行われるべきケース会議を何のために開くかといったら、 一番のメリットはこれじゃないか、と思います。 うまくいっていることを、広げていく。 うまくいったかかわりを、知ってもらう。・保護者も参加していることが望ましい。 最低でも、方針について了解が得られていなければならない。・学生ボランティアが関わる場合、 (共通理解への)時間的コストはかけなくてはならない。★問題行動の程度がひどくないのに、つい強く叱責してしまったり、 かなりひどいことをやっているのに何も注意しなかったり・・・ 介入ラインがそのときどきで動いてしまっているような対応は、 決してよい結果を生みません。 「ここまでのことはうるさく言わないが、 ここを超えることをしたらきちんと注意する」 といった問題行動のラインを明確に設定しておき、 それを動かさない。自分はなかなか守れていません。 大いに反省するところです。 特に自分が疲れていたり、時間がなかったり、 「とにかくもう大変!」って状況の時は、 問題に気づいても見過ごし・・・ということも。 だから、そもそも「基準」を守れるように、 自分の感情や忙しさがどうであろうと守れる「基準」を最初から 設定しておかないと、破たんしますね。 そういう意味では、介入ラインは甘めでもいいと思っています。 厳しくいろいろ言い出したら、こっちが守れなくなるので。 ○3つの行動分類とそれへの対応 a 絶対許されない行動・・・・・・断固たる対応 b 減らしたい行動・・・・・・無視 c 増やしたい行動・・・・・・ほめる・細かいことをアレコレ注意しても改善しない。こちらが疲れるだけ。 注目は c に対して与えましょう。○本人がよいことをした → 本人が得をする●本人が悪いことをした → 本人が損をする というパターンに一貫性をもたせる・口でほめてあげるだけでなく、 何か残るものをあげられるなら、それもしてあげたほうがいい。(p163の途中まで) =============================== (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.29
コメント(0)
-

医療費控除は1家族で10万円を超えればOK!
行きつけの整体で、帰りに「医療費控除の対象です」という張り紙を見て、一応今年分の領収書をもらってきました。整体って保険がきかないので高いのですが、医療費控除の対象になるならお金が戻ってきそうです。医療費控除って、病院での治療費だけでなく、整体での施術や薬局で買ったお薬代、移動にかかった交通費まで対象なんです。けっこうカバーする範囲が幅広い!しかも、自分だけでなく家族全部が対象なので、どうやら計算すると10万円を超えているようです。通常の年収がある方なら10万円を超えるかどうかが基準の模様。対象は1年間の医療費で、今年の1月から12月まで分です。気づいていないだけで実は控除対象になっている人は意外と多いかと。せっかくなので今年分の医療関係の領収書を見直してみましょう!▼参考サイト:医療費控除の解説 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.28
コメント(0)
-

山崎まさよし『COVER ALL-YO!』~素材の美味しさをそのままに
山崎まさよし/COVER ALL-YO!最近の一番のお気に入りCDです。発売は3年前ですが、知ったのは2週間前。(^^)洋楽の有名曲のカバー集なのですが、ただのカバーに非ず。アレンジの聴かせ方が絶妙!ジャケットからしてしゃれています。曲目は以下の通り。==============================1. Englishman In New York ~ロイヤルストリングスとボサノヴァを一緒に 2. Superstition ~野趣味あふれるアコースティックで 3. Your Song ~素材の美味しさをそのままに 4. True Colors ~その雰囲気に包まれて 5. Respect ~極上グルーブをレアのままで 6. Raindrops Keep Fallin’ On My Head ~南国風プレート乗せ 7. Daydream Believer ~ウクレレの音色を添えて 8. When You Gonna Learn ~このリズムをお好きなだけどうぞ 9. Just The Two Of US ~サルサソース仕立て 10. All My Loving ~シェフの家ごはん==============================ちなみにamazonの評価は10人が評価して平均が★5つの満点です。1曲目の出だしからしていいですが、3曲目の「Your Song」は泣けます。 邦楽カバー版もあります。こちらの「M」も絶品です。こんなアレンジがあるのか、って感じです。 邦楽CD 山崎まさよし / COVER ALL-HO!============================1. M ~BLUESを逢わせてみました 2. ケンとメリー~愛と風のように ~料理長のお任せ仕込み 3. Sweet Memories ~声のミルフィーユ仕立て 4. 月 ~和の頂きを目指して 5. さらば恋人 ~デトロイト風に 6. トランジスタ・ラジオ ~厳選した素材の二点盛り 7. 大きな玉ねぎの下で ~あの頃の涙を添えて 8. アンダルシアに憧れて ~アツアツに炊き上げました 9. あなたに会えてよかった ~気まぐれディレイをふんだんに 10. いかれたBaby ~音楽の恵みをこの曲に ============================カバー曲って、「結局、原曲のほうがいいや」という印象を持ちがちなのですが、これらのアルバムだけは別で、原曲と全く違った曲に仕上がっており、比較できません。おそるべきカバーアルバムです。ここのところ、こればかり聴いています。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.28
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』9~ADHDの認知特性に合わせた対応
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)上の本の読書メモの第9回。「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」 の後半、学校での対応についてです。 (1) ADHDの認知特性に合わせた対応 (2) 一貫した対応 (3) 子どもたちの自尊感情や自己効力感を高める対応 順に、参照していきます。 今日は <ADHDの認知特性に合わせた対応>のところです。================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ9 (p150~:「第6章」の後半)3.<ADHDの認知特性に合わせた対応>・ADHDのある子どもの席は、 一番前の中央(あるいは廊下側)・席を前にして、視覚刺激量を減らしてあげる・教室の前の壁には、極力、掲示物を貼らない。物も置かない。○記憶への定着は視覚刺激で ・大人のADHDの方は、覚えておかなければならないことを よく手の甲に書いておられる。 ・再想起するきっかけさえ与えられればいい。○体感覚に関する反応性は非常に高い。 ・友達のひじがちょっと触れただけで、 その友達にパンチをみまわすということが、しばしば起こる。 ・興奮しているADHDのある子を落ち着かせる場合にも、 しばしば体感覚刺激が最も有効。 (すっと後ろから肩に手をのせてあげる等) ・ADHDのある子は、すごく身体接触を求めてくる。 それにはできるだけ応じてあげて、落ち着かせてあげる。 ・本人を落ち着かせる「肌触り」を持っている「物」とは何か? これを探ることは役に立ちます。○注意持続時間内でできる課題を渡す ・どういった課題にはどのくらいの時間、 注意を持続できるのかをよく観察して把握しておく。 ・できたらよくほめてあげる。 それから次の課題を渡す。 これを繰り返す。 ・これを集団授業と並行して進める。 その子向けの課題を集団授業向けのものとは別につくっておく。○ADHDのある子には、みんなでかかわる。 ・1人の先生がクラスもその子も全部みるなんていうことは、 土台無理な話。 (p156の途中まで)=============================== (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.27
コメント(0)
-

PC野球ゲーム「DB」をバージョンアップしました。
僕の趣味はいろいろありますが、そのうちの1つに、オリジナルゲームの開発があります。あまり聞かない趣味ですね。(笑) 代表作は、ずいぶん前に制作した、エクセルを使った野球シミュレーションゲーム「ダイナミックベースボール」。ずっとほったらかしでしたが、世間がWindows7だ!と騒ぎ出したので最新環境に対応させるべく、バージョンアップしました。また、今までは7回制の野球ゲームでしたが9回制に変更しました。大きな変更だったので、野球ゲームに興味がある方はぜひプレイしていただいて、不具合があれば報告していただけると助かります。 ▼ダイナミック・ベースボールのページこのゲーム、これまでに10回ぐらい雑誌で取り上げていただき、前のバージョンでのダウンロード総数はVectorで13000に上りました。自分の好きな選手を登録して、成績の推移を楽しむゲームです。好きな人はけっこうハマるみたいですよ。「アウト!」「セーフ!」などの声は、10年ほど前、中学校の指導補助員をしていたときに関わりのあったお子さんに声の出演をしていただいています。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.27
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』8~ADHDの薬物療法
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)上の本の読書メモの第8回。「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」に入っていきます。今回は前半の、薬物療法のところです。 ADHDの定義や診断、どういった障害なのか、ということについては、前回に書きました。 ================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ8 (p135~:「第6章」の前半から)「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」 1.ADHDの薬物療法・「対症療法」的な薬物・状況が困難なものである場合には、 薬物療法の導入は躊躇されるべきではありません。・メチルフェニデート(リタリン) 精神刺激薬(通常、突然眠ってしまう睡眠障害の治療薬)の1種 ADHDの症状である<不注意><衝動性><多動性>のすべてに 効果がある。 通常1日量10mg。朝と昼に半分ずつ飲む。 効果は4~5時間。 朝、学校に来る前に家で飲む。→午前中いっぱいはもつ →お昼休みにまた飲む。→下校まではもつ 夜は飲ませてはいけない。眠れなくなる。 ・ADHDのある人は精神刺激薬を飲むと落ち着き、 そうでない人は活動性が高まる。 ※ADHDのある人とそうでない人で、 この薬物に対する反応が違う・朝ちゃんと薬を飲ませたかどうかの確認を保護者から受ける。 飲んでいる場合と飲んでいない場合の本人の様子の違いを確認するため。 ・お昼の薬は保健室で管理しておいて、 担任の先生が毎日、本人に指示して保健室に行かせ、 そこで飲むようにするのが普通。 ・精神刺激薬の副作用は、不眠、食欲低下など。・身体依存性はない。精神依存もほとんど発生しない。 飲んだからといって、別に気持ちよくなるわけでない。・ADHDによる日常生活上の困難は、 多くの場合成長とともに克服できたり、 コントロールできるようになる。 薬は、最も困難な時期を少しでも落ち着かせるために用いられるべき。 2.薬物療法について最低限の知識をもつ必要性・抗てんかん薬(カルバマゼピンやバルプロ酸ナトリウム)も、 ADHDのある子に対して処方されることがある。・抗てんかん薬には、<衝動性>を抑える効果がある。 ただし、副作用に注意。 カルバマゼピン:傾眠やめまい、吐き気や嘔吐 バルプロ酸Na:鎮静作用(眠くなる、頭が回らない感じ)、手指の震え、脱毛症 ・かかりつけの病院名、担当医名を控えておく。 子どもに変化が現れたとき、または緊急の事態に遭遇したとき、 その病院や担当医からの指示を仰ぐことができる。・かかりつけでない病院にとりあえず運ぶ時にも、 病院のドクターに 「○○病院の○○ドクターが担当で、 ○○という薬を○○グラム飲んでいます」 と明確に伝えることができる。・(公立中学校 木原先生の話) 「自分のクラスにいる子が、 どのような疾病に対して、どのような薬をどのくらい服用しているのか を知っていると、私はとても安心できます」 「突然の出来事というのが一番驚くわけですが、 その突然に出合わないように、また出合ったとしても その驚きを最小限にとどめておくことができるのです」(p149まで) ===============================メチルフェニデート(リタリン) については、最近はほとんど処方されていないような気がします。メチルフェニデートはコンサータにも入っています。 コンサータなら、1日1回の服用でいいようです。持続時間はなんと12時間! 詳細は ▼メチルフェニデート - Wikipedia森先生は本書の中で、依存性はほとんどないと言われていますが、Wikiによると、依存症はあるようです。 次回は、ADHDの学校での対応に入っていきます。本書では大きく3点にまとめられています。(1) ADHDの認知特性に合わせた対応(2) 一貫した対応(3) 子どもたちの自尊感情や自己効力感を高める対応次回、詳しく参照します。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.25
コメント(0)
-

終業式~そして忘年会(^^)
24日は終業式でした。 夜は忘年会。 1年を振り返って、 「たくさんがんばりましたよね。よい1年でしたね」と 職場の先生方と話しました。(^^) 最後はカラオケに行って、運動会のダンス曲や音楽会の歌を歌って 盛り上がりました。 そろそろ1年を総括する時期です。 そして来年が飛躍の年になるよう、準備していきます。 来年はうさぎ年。年男です。 うさぎのように、ぴょ~んとはねて、一気にジャンプしたいと思います。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.24
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』7~「ADHD」
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)上の本の読書メモの第7回。本日は、「ADHD」についてです。ADHDの定義や診断、どういった障害なのか、ということについて。 ================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ7 (p120~134:「第5章」の全部を部分的に抜き出しながら参照します。)「第5章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)」 1.2.略3.ADHDは小さい頃からその兆候が認められ、 また複数の状況において問題が存在する・先天的な脳機能の障害・診断には、成育歴に関する情報が必要・場面限定性のものではない・保護者からの情報が必須 4.PDDとの関連・PDDとの重複があれば、ADHDの診断は付されない (DSM-IVにおいて)・実際はPDDのある人たちのうち、 かなりの人たちがADHD症状を併発 5.ADHDの疫学 ・ADHDの診断は、ICD-10だと <不注意><多動性><衝動性>の3つ全部が揃わないと 診断がつかない・DSM-IVの場合、<不注意>か<多動性-衝動性>の どちらか1つあれば、ADHDの診断がつく 6.7. 略8.ADHDの予後・<多動性-衝動性>は、なくなるとは言わないまでも、 年齢が上がるにしたがって基本的には落ち着いてくる。 そのコントロール・スキルも向上していく。・<不注意>のほうは結構しつこく続く ただこれも、自分の傾向を自覚して、 それなりの対処法を開発していけば、 社会生活上それほど支障が出ない程度には コントロールしていけるようにはなる。・<多動>は、活動性が高いということでもあるので、 障害というよりもむしろ「リソース」だとさえ言える。(p134まで) ===============================最後の、「障害」と見ずに「リソース」と見る、という考え方、かなり大事だと思います。世の中の大仕事は、積極的に活動するエネルギーなしではまわっていきません。ADHDで大きな功績を残しておられる有名人の方はかなりおられます。あるブログ記事によれば、エジソン、レオナルド・ダビンチ、アインシュタイン、トム・クルーズ、マイケル・ジョーダン、黒柳徹子・・・。そうそうたるメンバーです。(情報元:▼ADHDと診断された子どもへの教師としての対応の仕方) 次回は、「第6章 注意欠陥/多動性障害(ADHD)への対応」を参照します。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.23
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』6~PDDのある方が、親友を持てるようになる
やる気が復活しましたので、一度消えたブログ記事の再開です。 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』 (森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)上の本の読書メモの第6回。PDD(広汎性発達障害)の方だけでなく、すべての人がコミュニケーションを楽しめるようになるための秘訣が書いてあります。================================ 『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ6 (p100~「第4章」の途中から。)10.<変化を楽しめるようになること>・対人関係がなぜこうも楽しく、ワクワクする、刺激的なものかというと、 それは例えば会話などの中に「予測不可能性」があるから。 そこでどんどん「新しい」ことが起こり、 「新しい」発見があり、それが「創造性」につながっていく。★「意外性」があるからこそ「面白い」(「変化を楽しむ」力をつける、具体的実践例)・トンチンカンなことをし始めるというゲーム (例)・汽車のおもちゃ(あるいは絵カード)を取り上げて、 「まあ、おいしそうなケーキ!」 パクパク食べる真似をして、一緒に笑い合う。 ・「ああ、頭がかゆい!」と言いながらお尻をかく。 ・「わあ、このケーキおいしそう!」と言いながら 目で食べようとする。関西の先生では、ボケて子どもたちのツッコミを誘う方が、 割合多いかと思います。 「子どもの自主的な発言・思考を促す」点でも、 こういった「いかにボケるか」の研究は欠かせません。(笑) 僕の経験上でも、「言葉が出にくい子」や「コミュニケーションが苦手な子」が、 「トンチンカンなことに対して思わずツッコミを入れたくなる」という手法で、 かなり効果のある「学習」ができています。 自発的表現のないところに、学習は成り立ちませんからね。 「授業とはボケとツッコミである」 と言ってしまっていいかもしれません。 ・RDIの様々なエクササイズは、変化をつけるということを 視野に入れて構成されている。・変化をつけて、それについていける能力を伸ばす。 ・PDDのある子は、しばしば正しすぎる。・ユーモア:必ず何かしらの「間違い」の要素が含まれている。・まずは「間違える」から始めて「楽しい」につなげていく。・PDDのある子どもたちに限った話ではなく、 今の日本の教育全般の中で、もう少し考えられてもよいこと。同感です。 「正しすぎる」ということは、人間関係や社会生活の上で かなり「問題」になってきます。 僕自身も「正しすぎる」ことを主張して、 人間関係で困ったことが山ほどありました。(>。<;) 「間違えること」を学ぶ。 「ユーモア」を学ぶ。 「楽しい」ということを学ぶ。 自分が本当に大事だと思った勉強が、ここにあります。 ・ゲーム感覚でどんどん変えていく。・子どもたち自身にいろいろと考えてもらって、 アイデアを出してもらう。 11. 12. 略 13. RDI、そのほか、あれこれ・RDIの最終目標の一つが 「PDDのある方々が 親友を持てるようになること」・「楽しかった思い出」をたくさんつくりたい。 いつでもそれを思い出せるような環境を与えてあげたい。 ・「メモリーブック」: 活動の記録をきちんと残しておいて、それを振り返る作業が大事・ 友人関係における未来のスケジューリング ・一言で「友達」って言っても、 実際はそこにはいろんな形態や関係がある。(p118(第4章の終わり)まで)================================ 一度消えてしまったブログ記事を、こうやってもう一度書くことができました。支えてくださった皆様方に感謝です。次回は、第5章「ADHD」の章に入ります。よかったら次回も読んでくださいね。それでは! (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.22
コメント(2)
-

正面のボールがとりにくい理由は「斜視」にあった
(※本文中の「ビジョントレーニング」を、間違えて表記していたので 翌日付で訂正します。(^^;)どうも最近ミスが多いです。ごめんなさい。) 僕は、普段メガネがなくてもよく見えます。でも、職場ではメガネをかけています。その理由は「斜視」だからです。左右の視力は、それぞれ1.2と0.2。視力差があるだけでなく、見えている像が少しずれている、と眼科医にお聞きしました。片目の視力が良ければ日常はその眼を使って見るので、全然支障はないのですが、眼科医の勧めに従ってメガネをかけるようにしました。でも、そもそも「斜視」についてよくわかっていませんでした。(^^;)土曜日のビジョントレーニング講座でいろいろとお話をお聞きした中に「斜視」についての説明もあり、自分自身の「目」の勉強にもなりました。ビジョントレーニングでは、真正面にだんだん近づいてくる物をどこまでぼやけずに見られるか、という指標があります。(輻輳(ふくそう)、と言います。)近づいてくるものをじっと見ていると、寄り目になってきます。 ( ●)(● ) __ 斜視の場合、これが非常に苦手のようです。ビジョントレーニングにより、改善されることがあるようですが、プリズム入りのメガネでも改善します。現に、僕の場合、メガネをかけて見ると、かなりしっかりと近づいてくるものを見ることができました。メガネをかけだしたのは大人になってからなのですが、子供時代に野球のボールを正面で取るのが苦手で、特にフライをとるのは全然できなかった、その理由は、この「目」にもあったようです。(単に運動神経が鈍かったのもありますが・・・。)僕と同じように「野球のフライがとれない」と悩んでいる野球少年の少しでも助けになれば、と思って書きました。専門のビジョントレーニングを受けるか、即効性を期待するなら眼科医にきちんと見てもらってメガネを処方してもらうと、そのフライ、とれるようになるかもしれませんよ!(^0^)視力的には見えていても、メガネやコンタクト、ビジョントレーニングで あなたの「困っていること」が解決することもある。こういうことも、ぜひおぼえておいてほしいと思います。ちなみにWikipediaによると、「斜視」は「片方の目は視線が正しく目標とする方向に向いているが、もう片方の目が内側や外側、あるいは上や下に向いている状態のこと」と説明されています。治療については、「眼鏡やコンタクトレンズなどで屈折矯正を行うことにより、斜視を治療することができるケースもある。 また物を見る力をつけさせる(視能訓練)ことにより斜視を治療できる場合がある。 プリズム眼鏡等を用いる方法もある。」とあります。(引用元:斜視 - Wikipedia )ビジョントレーニングについてはまだよくわからないのであまり書きませんでしたが、今後も学んでいきたいと思っています。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.20
コメント(0)
-
SENS(特別支援教育士)最終試験
今日はSENS(特別支援教育士)資格認定最終試験でした。さすがに SENS の資格はなかなか楽には取れませんね。(^^;)簡単な問題はほとんど出ませんでした。これから受けられる方のために書きます。勉強はちゃんとしておいたほうがいいです。(笑)まあ、直前の勉強だけでなく、それまでの勉強の蓄積がやはり大事ですね。テスト時間90分のうち、回答に80分かかりました。最後までやり終えてすぐに見直しをする気力はなく、ちょっとぼーっとしてました。周りが一生懸命やっている雰囲気におされて、見直し開始。選択肢のうち「やっぱりこっち!」と選びなおしたのが何点かありました。後でテキストを確認したら、それで正解になったものもあり、誤答になったものもあり・・・。いちおう8~9割はできてると思うんだけどなあ。受からなければ、また来年です。いや、受かっているとだけ、考えよう。 何人かの方と、なつかしい再会を果たしました。SENSを受講していると、仲間ができるので、それが一番のメリットですね。※2011/10/24最終試験の問題内容が推測できるような記述について削除しました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。
2010.12.19
コメント(10)
-
大阪オリエンタルホテル
今日は神戸でビジュアルトレーニングのお勉強。その後、大阪のホテルで明日のSENS(特別支援教育士)試験に備えています。SENSの教科書はかなりよくできているのですが、3冊もあるので、一夜漬けで覚えるにはかなりの分量です。(^^;)ちょっと小休止。泊まっているのはここです。↓ニューオリエンタルホテル最安値で、シングル1泊3900円とお安いホテルですが、大浴場がついています。しかも、楽天ポイントが10倍ついたり、1000ポイントすぐにもらえたりする宿泊プランがあり、楽天ブックスですぐに本を買う僕みたいなものにはとてもお得です。僕は5100円で、ポイント10倍アンド1000ポイントつき朝食つきで宿泊しています。大浴場は男女交代制。「お風呂は何時から何時まで~!」と決められています。修学旅行みたい。さっき入ってきましたが、シンプルなジェットバスが、気に入りました。腰や肩に当たって、かなり気持ちよかったです。今はフロント近くの10分間100円のインターネットでブログ書いています。(^^;)さて、かなり気分転換できたので、試験勉強再開!(^0^)受験生の皆さん、明日お会いしましょう! (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.18
コメント(0)
-

『ハーバード白熱教室』 今週末にはNHKで再放送!
昨日の反省を踏まえ、今日はfirefoxでブログを書きます。明日は特別支援のビジュアルトレーニングの講座、あさっては特別支援教育士の最終試験です。明日から特別支援づけになるので(?)、今日は全く関係のない本の紹介です。『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業(上)』(マイケル・J.サンデル/日本放送協会、早川書房、2010、1400円)けっこう今はやりですか?DVDで講義が見られるようで、見てみたいです。「哲学」「道徳」系の本はけっこう好きなんですよ。上巻は勢いに乗ってサクサク読めました。下巻も読みたい! では、個人的に「なるほど」と思った、カント哲学のところを引用します。==============================『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業(上)』読書メモ・カントはこう推論した。 私たちが動物のように喜びや満足や欲望を追い求め、 苦痛を避けようとするとき、本当に自由に行動しているとはいえない。 なぜか。 実際には、私たちは欲望や衝動の奴隷として行動しているからだ。・カントはこう言っている。 行動を道徳的に価値のあるものにするのは、 そこから生じる帰結でも結果でもない。 動機、意志の質、そして行為がなされる意図である。 重要なのは動機だ。 重要なのは、その人が正しい行いを正しい理由ですることだ。・自分の利益や要求、特別な状況が ほかの人のそれよりも重要であるという理由で、 自分の行動を正当化するべきではない。・私たちは、自分たちのプロジェクトや目的、利益のために他人を使うとき、 彼らの尊厳を尊重するやり方で接すれば何も問題はないのだ。 ==============================いろいろな哲学者の考えが紹介され、興味深い事例や仮定が出てきます。僕としては本の後ろのほうで出てくるカントの考え方が一番勉強になりました。速報!今度の日曜日、NHKで 本書にも載っている東京大学での著者の講義が再放送されます!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12月19日(日)教育 午後6時~6時58分 「イチローの年俸は高すぎる?」(再) ハーバード白熱教室@東京大学 「イチローの年俸は高すぎる?」 イチロー、オバマ大統領、日本人の教師、3者の年俸を比較しながら、富の分配の公正について議論をしていく。果たして、イチローはオバマ大統領の42倍もの年俸に値するのだろうか。さらには東大への入学資格をお金で買うことの是非についても考える。 (情報元:NHK)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 本の下巻はこちら。【送料無料】ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業(下) 世間では、DVDのほうが人気らしいです。 【27%OFF】[DVD] NHK DVD ハーバード白熱教室 1(販売価格 2,146円) (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.17
コメント(0)
-

「書きかけのブログが消えてしまった!」を防ぐオドロキの対処法!!
実は、今日のブログは『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』の第6回をほとんど書き終えていました。非常に調子よく、たくさん書きました。ところが、これがよくあるのですが、キー入力の時に間違ったキーを押してしまったか、エンターキーを2回押してしまったかで、ページが移動してしまいました。こうなると、いくら「戻る」で戻っても書きかけの記事は戻ってきません。空白の入力画面を見て、唖然。再び入力する気にはならなくて、やる気を失ったまま、風呂に入っていました。最近では「日記のプレビュー」で別ウインドウで表示させるクセもつけていたのに。どういうわけか今回はその別ウインドウに残っていた記事も初期の内容のまま。30分ぐらいかけた記事が水の泡です。その消えてしまった記事の中身、 前回の次回予告をお読みの方なら分かりますね?そうです、<変化を楽しめるようになること>です。(笑)ブログ記事でさんざん <変化を楽しめるようになること> の大事さにふれておきながら、突然書きかけの記事が消えるというアクシデントに対して楽しめませんでした。(笑)まだまだ修行が足りません。 さて、転んでもただでは起きない、という主義なので、対策がないか調べてみました。するとおもしろいことが分かりました。書きかけのブログ記事が消えてしまうのはIE(インターネットエクスプローラ)にありがちなんだそうです。Operaやfirefoxなら、間違ってページ移動しても、戻ってきたら書きかけの内容が残っているらしいです。 ▼ITmedia Biz.ID:「書きかけのmixi日記を消してしまった!」を防ぐすばらしいです。僕のようにブログを書く人にとっては、耳寄りな情報ではないでしょうか。Operaやfirefoxは昔使っていましたが、今は使っていません。さっそく、IE以外のブラウザも試してみたいと思います。 ▼Operaのダウンロード ▼firefoxのダウンロード (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.16
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』5~「ボールを用いたゲーム」
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』(森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)この本の読書メモ、今日が第5回です。昨日の最後に紹介した、RDIのいくつかのゲーム。すっごくいいです!「自閉症」のことについて、ちょっと勉強しただけだと、人とのかかわりは無理なのかな、個別に別室で勉強したほうがいいのでは・・・という理解もされやすいのですが、なんのことはない、大勢のクラスメイトと楽しくやっていくことも十分可能です。そのカギが、昨日の「ゲーム」に代表されるような「単純な遊び」を、周りの人たちと楽しむ、その積み重ねにあると思っています。特別支援学級に在籍していても、その生活のほとんどを「交流学級」(原学級)で過ごしている子どもたちの場合、「自閉症」または「自閉傾向」であっても、低学年から高学年になるにつれ、周囲の友達や先生との「笑顔の交換」が増え、本当に楽しく「人間関係」が結べています。そういうすてきな実践が、全国のどこにでも広がるといいな、と思っています。前置きが長くなりました。今日はその続きです。================================『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ5(p96~「第4章」の途中から。)8.<周囲の人々の動きを参照して、 それに合わせられるようになること>の続き以下、「ボールを用いたゲーム」の例・「ドッジボール」: スポンジボールやビニールボールを使用。 当たっても痛くない。子どもに恐怖感を与えない。 まずはこちらが子どもに向かって何回か(柔らかく)投げる。 子どもは当たらないように逃げる。 次に攻守交替。 何度か繰り返し、やり方がわかってきたら、 次に こちらが投げるときに、フェイントを使い始めましょう。 こういう表情や仕草の時は投げる、 こういう場合は投げないとか、 何か非言語的な合図を事前に子どもに送っておいて投げる。 → 子どもがそれを察知して、上手に逃げられるようになればしめたもの!・「ツー・ボール・トス」: 1つずつボールを持って、 それを「せえの」で同時に相手にトスする。・より高度なボールゲーム(バスケットやサッカー): RDI的には、その主眼は「パス」の上達にある。 相手が受け取りやすいように上手にパスを出していく練習。★楽しく盛り上がってやることです。以下、ロープを用いたゲーム・「シーソー綱引き」: 片方が引っ張ったら片方は緩め、 今度はさっき緩めたほうが引っ張り、片方が緩める。 これを繰り返す。 =ロープがゆーらゆーら往復しているような感じ できるようになったら、今度はロープ(あるいは棒)を2本にし、 右と左に1本ずつ持ち合う形で、 左右交互に引き合ってみるのもいい。・「大縄跳び」: まずは大縄を2人で上手に回せるようになる練習★こちらが子どもに合わせてあげてはいけない! こちらが合わせてばかりいると、 子ども自身の「協調」能力はいつまでたっても伸びてはいきません。 子どもがこちらに合わせられるようにならなければいけないのです!・子どもたち同士でペアを組ませるならば、 どちらがどちらに合わせるのか、 その役割を明確にしておいてあげることが大切。★これらの活動は、活動を成功させることが主眼なのではなく、 活動を人と一緒にすることが楽しくて、 その楽しさを人と共有できるようになることが主眼 9.略(p99まで)================================「こちらが子どもに合わせてあげてはいけない」という一言、ドキッとします。でも、確かに、いろいろと配慮して相手に合わせてあげる時期よりも、それを過ぎてお互いに慣れ、こちらのペースに相手を合わせさせようとする(?)時期のほうが、子どもの成長はいちじるしかった気がします。 「協調運動」のゲームの例示を見ると、サッカーなどのボールゲームも「人と合わせる」要素が非常に強いことに気づきます。引用したこの本の例示以外でも、・ペアトーク ・合唱 ・合奏なども、「相手」がいるからこそ楽しい。「相手」なしでは成立しえない活動です。特に僕の場合、音楽や演劇が大好き。もともと人とかかわるのは苦手なほうなのですが、大学の時に演劇をやったり、音楽をやったりして「人と一緒に活動することの楽しさ」がわかってからは、積極的にそういった活動を楽しむようになりました。結果的に、人とかかわることについての能力も、伸びていったように思います。特に、とっかかりとして「演劇」というのはかなりいいと思います。この本の中でも「PDDのある方でも演劇は結構できたりする」(p101)と書かれていますが、「演劇」は、シナリオや状況が決まっていて、事前に予習ができるので、やりやすいのです。そして、結果としての「人と共にある楽しさ」は、しっかりと享受することができます。小学校でも、「道徳」の時間にロールプレイをしたりします。そういうところから、対人関係能力を伸ばしていくことは大いに期待できます。 次回は、やっぱりこの章の続きで、<変化を楽しめるようになること>のところをとりあげます。PDDの方は、決まりきったことにこだわりがあり、レールをはずれることを嫌います。でも、「変化を楽しめる」からこそ人生は面白い、という側面にも気づいてもらいたい!そこで、どんな取り組みがあるかを、具体的に紹介したいと思います。面白いですよ。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.14
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』4~人間関係を楽しむためのRDI
特別支援教育関係で、今まで勉強してきたことを振り返っています。その中の一つが、この本です。『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』(森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)今日は第4章。「PDDへの新しい取り組み-療育プログラムRDIへの誘い」についてです。================================『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ4(p68~95「第4章」の途中まで。)1.今まで「対人的相互反応における質的な障害」は どう扱われてきたか・PDDへの対応 ・行動療法(応用行動分析が代表的) ・TEACCH:個別アセスメントに基づいた包括的教育プログラム ○空間や時間(スケジュール)をわかりやすく「構造化」 ○コミュニケーションにおいて視覚的手がかりを多用する ○TEACCHの「精神」は、「自閉症の文化」を理解すること 目標は、彼らがもっている能力を最大限に発揮して、 彼らなりによりよく自律的な生活ができるようになること ・感覚統合 ・薬物療法 2.RDI(対人関係発達指導法)の登場 ・RDI:「PDDのある人たちも人間関係を楽しめるようになること」 を最終目標にする、ユニークな療育プログラム 3.対人的相互反応の発達を促進させるポイント 1)非言語的コミュニケーションを発達させること 2)人と一緒にいて何かをすることを「楽しい」と感じられるようになること 3)周囲の人々の様子を観察・察知できるようになること 4)「協調」を楽しめるようになること 5)「変化」を楽しめるようになること 6)「白か黒か」ではなく「灰色」の部分を認められるようになること 7)相対評価/文脈的評価ができるようになること・とにかく、人と一緒にいること、人と一緒に何かをすることを 「楽しい」と感じてもらうこと その体験をたくさんつくってあげること・まずは一緒に「遊ぶ」こと・「笑い」が命。 「興奮」が命。・かなりこちらのテンションを上げてやらなくちゃならない。 4.<非言語的コミュニケーションを発達させること>・コミュニケーションに占める非言語的コミュニケーションの果たす役割は、 7割以上・まずは非言語的コミュニケーションを鍛えることが大切・まずは非言語的メッセージを受け取る力を伸ばすこと →こちらは最大限に言語の使用を控える。言葉数を少なくする。・非言語的に、オーバーに伝える。 どれくらいかというと、おそらくそれは 幼稚園の先生くらいに、あるいは赤ちゃんをあやすお母さんくらいに・RDIだけやっていればよいというものではないし、 RDIの方法論で他の領域をすべてカバーできるわけでもない。 学習指導は学習指導で、きちんとやらならなくてはならない。 だから「分けて考える」のです。 RDIだけで「授業」はできません。 RDIは基本的に「遊び」です。 ただ、「授業」の中にもRDI的要素を取り入れることはできます。 5.<人と一緒にいて何かをすることを「楽しい」と 感じられるようになること>・ただ一緒に歩いたり、ユ~ラユ~ラしたり、 跳んだりはねたり、倒れたり、道具を用いない遊びのほうがいい。・情動の共有 emotion sharing 一緒に笑い合う。笑顔の交換。 6.公立中学校でのRDI的要素の実践○まなざし: 生徒を指名するとき、名前を呼ばずに「まなざし」を向ける。 あらかじめ「目で合図する」旨を伝えてから繰り返し行う。○シーッ: 入室する際に「シーッ」をしながら、抜き足差し足で入る。 声を出したり、音を立てたりした生徒をオーバーアクションで指さし、 さも大変なことが起こったように振る舞う。 (他にも事例多数)→生徒が「この人は次に何をするのだろう?」という表情になってくる。・「笑い」の環境を常時提供し続ける。・笑いをとるためには、まずはボケることだ。 7.略8.<周囲の人々の動きを参照して、 それに合わせられるようになること>・「一緒にピョン」: 2人で同時に、ちょっとした段差の上からピョンと飛び降りるだけのゲーム ・最後は、言葉を使わないで、非言語的手がかりだけで こちらと同時に飛び降りられるようにもっていく。年少のお子さんなら、・「一緒にバタン」: 大きなクッションあるいはクッションの山に一緒に倒れこむというゲーム。 倒れこんだら、子どもをコチョコチョとくすぐったりして、2人で大笑いする。・「並んで歩くゲーム」: 2人、横に並んで一緒に歩くだけ。 2人で真横に並んで、ゴール地点までそのまま一緒に歩きましょう。 上手にできたら、ゴール後に、2人で喜びあいましょう。 最初は普通のペースで。 → 足早あるいはゆっくり → 途中でペースを急に上げたり下げたり★これはゲームです。楽しくやりましょう。(第4章8の途中まで)================================「協調運動」のゲームの例示は、まだまだ続きます。この後、「ボールを用いたゲーム」「ロープを用いたゲーム」が登場します。でも、長くなったので今日はこの辺で。 非言語的コミュニケーションを意識的に使うって、かなり大事だと思います。そして、「情動の共有」ということ。これらは、PDDへの取り組みである以前に、「楽しく学校生活を送る」という、すべての子どもたちに保障すべき最低限のことを提供する具体的プログラムのような気がします。子どもも楽しくなるし、もちろん教師も楽しくなる。「学力をつける」こととは別かもしれませんが、大事なことです。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.13
コメント(0)
-

『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』3(広汎性発達障害(PDD)の定義)
特別支援教育士(SENS)の試験まで、あと1週間となりました。特別支援教育関係で、今まで勉強してきたことを振り返っていきます。『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』(森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)この本の読書メモは、今日で第3回。今回は、第3章。「広汎性発達障害(PDD)」についてです。================================『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ3(p42~67「第3章」より。)1.自閉的傾向○広汎性発達障害(PDD) :自閉症スペクトラム障害(ASD) ・DSM-IVにおける<自閉性障害>の診断基準のうち、 少なくとも(1)と(3)が該当。 (1)対人的相互反応における質的な障害 ※量ではなく質の部分の障害 ・非言語的なやりとり、および、 人(自分も含めて)の「気持ち」を把握し表現することの困難 (2)コミュニケーションの質的な障害 ・言葉の発達の遅れ、「オウム返し」(「反響言語」)等 (3)行動、興味、活動の限定された反復的で常同的な様式 ・非常に強いこだわりがある・ 何らかの目的のために人とかかわることはできるが、 (「道具的相互反応」) 人と一緒にいること自体を楽しみ、 その楽しさや充実感の体験を相手と共有すること (「体験共有的相互反応」)が難しい ★でも、真の「仲間関係」を築くためには、 この「体験共有的相互反応」が不可欠!2.自閉性障害・情緒障害児通級学級井上薫先生の話 「自閉症圏のお子さんの中に、授業中教室から飛び出していく子がいる。 追いかけながら「止まれ!」と叫んではいけない。 彼らは走っている最中に「止まれ」と言われると、 「止まれ」という言葉の意味を「走れ」だと思い込んでしまう。 だから、走って追いつき、抱きしめて止める。 そして「止まれ」と優しく言う。 止めてから「止まれ」。そうすると「止まれ」の意味を正しく覚えてくれる。」・DSM-IVでは、ADHDと自閉性障害の重複を認めていない。 ADHDの診断は付けずに、自閉性障害を優先させる。3.のアスペルガーについては今回は略します。(第3章「広汎性発達障害(PDD)」より)================================第4章は「PDDへの新しい取り組み―療育プログラムRDIへの誘い」です。いよいよ、第4章は、障害への「具体的な手立て」の部分に入っていきます。そこが一番、肝心な部分ですよね。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.12
コメント(0)
-

喜多川泰『手紙屋 蛍雪篇』2~「勉強する権利」を大切にしていこう!
「勉強」する意味がよく分かる本、『手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙』(喜多川泰、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2008、1500円)その読書メモの続きです。=============================『手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙』読書メモ2(p196~)(ネタバレになりますので、純粋に物語を楽しみたい方は 読まないで下さい!)・想像力を駆使して「人」を見ていると、 必ずその人に興味がわいてくるものです。 そしていつの間にか、その人の生み出した「もの」に対する 興味もわいてきます。「人」と「もの」はつながっていますね。 逆に、「もの」に興味を持って、「人」につながることも、ありそうです。・勉強という道具は、 「自分を磨くため」 「人の役に立つため」 という2つの目的のために使ってはじめて、 正しい使い方をしたといえるのです。僕の尊敬する人たちも、そのように役立てている、と思います。・人間は人のためにこそ、 より強い意志を持って行動できるようにできています。 これが人間のすばらしいところだと私は思います。・あなたが勉強しなければ困るのは、 あなたではなく、将来あなたと共に生きる人なんです。・あなたが勉強を続けた結果、○○に成功したとしたら、 あなたのおかげで数多くの人が幸せを手に入れることになります。 その人たちのために、 今あなたは勉強をするんです。・「勉強」をして大成した人たちは、 ある点で共通しています。 小さい頃から 「世の中のためになる人になりなさい!」 と言われて育ったということです。 本文からの引用はここまでですが、 最後に「あとがき」から引用しておきます。 この本の中心テーマだと思いますので。・僕は、僕たちの持っている「勉強する権利」を大切にしていくべきだと 思っています。 みんなで上手に使って、大切に使っていかなければならない、と。 そして、「勉強を上手に使うとはどういうことか」という僕なりの考えが、 「その経験を自分という人間を磨くために使う」 「その経験を他の人の役に立つために使う」 ということ。 (この2つは根本的には同じこと)=============================僕たちは恵まれすぎて、「勉強する」ことが権利であることすら、 忘れてしまいがちです。 でも、歴史上、勉強することは明らかに「権利」でした。 (もちろん今もそうです。) この本の中で手紙屋は、「勉強する」ことをあえて「禁止」しました。 「勉強する権利」に気づかせる、大変効果的なアプローチだと思います。 「しなくてはならないこと」になった瞬間、権利としての魅力にあふれていた 「勉強」が、途端に色を失ってしまいます。 勉強を楽しむ心を取り戻しましょう! 僕たちは、最初はみんな、勉強が大好きだったはずです。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.11
コメント(2)
-

喜多川泰『手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙』
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』の読書メモを書いている途中でしたが、唐突ながら別の本の読書メモを差し挟みます。すっごくいい本です。喜多川泰さんの『手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙』(喜多川泰、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2008、1500円)===============================【内容情報】(「BOOK」データベースより)何のために勉強するんだろう?何のために大学に行くんだろう?進路に悩む女子高生、和花が「手紙屋」から学んだ、勉強の本当の意味とその面白さ。ベストセラー『君と会えたから...』『手紙屋』の著者が贈る渾身のメッセージ。===============================受験生のヒロインと手紙屋のやりとりが物語の軸。「何のために勉強をするのか」といった人生の核になる疑問に真っ正面から答えてくれる本です。教師としての目から見ても、大変意義深い本です。ちなみに、11月28日のブログでは、この前作を紹介しています。 ▼喜多川泰『手紙屋』~あなたが成功した後に出会う大応援団セットで読むと、かなりいいです。=============================『手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙』読書メモ(ネタバレになりますので、純粋に物語を楽しみたい方は 読まないで下さい!) 「勉強する」とはどういうことなのか、 作中では、「ピアノの練習」や「サッカーの練習」との比較がされるなど、 身近でわかりやすい例を引きながら、 様々な「勉強」の持っている側面が語られます。 その中の一つが、こちら↓・『今までこの地球上に存在した人々が経験し、 発見しては次の世代へと伝えてきた すばらしい知識や知恵を、 今度は自分が受け継ぎ、自分のものにすること』 この主張が出てくるまでの過程が、すばらしいです。 こうやって、この部分だけ抜き出して書くと伝わらないのですが。(^^;)・「将来の不安」が行動の原動力になるのは事実です。 しかしそういう人は、残念ながら幸せな人生を送ることなどできません。 追いつめられなければ動けない人は、 常に追いつめられた状態の人生に甘んじるしかないのです。「追いつめられないと動かない」タイプなのですが、 これを読んで反省しました。・「やるべきこと」というのは、 決して「やらなければいけないこと」ではありません。 それは、本当は 『将来の自分が、今の自分にやっておいてほしいこと』 なんです。「やらなければならない」と思うと気が重いのですが、 そう思うと、心が軽くなります。 将来イメージ、将来から現在の自分を見るイメージができると いいですね!・有名な講師の授業を数多く受ければ、 勉強ができるようになると勘違いしている人がいます。 でも、本当にできるようになるのは、 あくまでも「自分で練習をくり返したとき」 だけなのです。 ピアノのレッスンと同じです。これまた反省。 けっこう「有名な人」のおっかけみたいなところがあるので。(^^;) 著名人ですごい方はたくさんおられますし、 著作やDVD、音声などでその方の考えに直に触れることもできます。 直接足を運んでセミナーなどに参加すると、確かに学びは大きいです。 でも、「自分の普段のおこない」がないところで、 結局は他人頼みみたいないい加減な学び方なら、 本当に成長するまではいかないでしょう。 やりたいことがあるなら、 「自分はそのために、毎日何をくり返しているかな」 と自問自答しなければなりませんね。(p195まで)=============================まだ本の途中までですが、いったん置きます。 後編は明日に続く! (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.10
コメント(0)
-

森俊夫『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』2(MR,LD等の定義)
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』(森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)読書メモの第2回です。今回は精神遅滞(MR)やLDについて。もろに、「お勉強」ってかんじです。ま、試験勉強を兼ねているので。================================『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ2(p31~41「第2章」より。)1.精神遅滞(MR) ・IQ70以下 (IQ71~84は境界知能)・IQは決して固定的なものではなく、変動するもの・長尾圭造「精神遅滞も治ります。(中略) 訓練や環境調整により社会生活上、 自立することは可能となります。 そうなれば精神遅滞とは呼びません」 2.LD・DSM-IVで言うLDは、 「読字障害」「算数障害」「書字表出障害」「特定不能の学習障害」 の4つだけ。 「読み」「書き」「算数」のどれかの発達が特異的に遅れているもの・文部科学省の定義では、 「聞く」「話す」能力の発達の遅れ(DSM-IVでは<コミュニケーション障害>) 「推論する」能力の発達の遅れが付け足されている。 3.運動能力障害 (発達性強調運動障害)・元来、運動というものはどれも「協調運動」 4.コミュニケーション障害・「話す」ことに遅れがある場合=<表出性言語障害>・「話す」「聞く」両方に遅れがある場合=<受容―表出混合性言語障害>・子どもの場合、「聞く」能力が障害されていると「話す」能力も発達しない(第2章より)================================ADHDやPDDは別章でくわしく取り上げられています。今回はここまで。次回は、第3章「広汎性発達障害(PDD)」についてです。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.09
コメント(0)
-

震災に関する授業研究(写真提示時の留意点)
今日は職員会議でした。1月17日の取り組みと、それに向けての「震災に関する道徳授業」についての提案・呼びかけなどをさせていただきました。震災授業については、昨日有意義な研修を受けてきたところです。「良いと思ったことは皆さんに広める」というスタンスのもと、研修でお聞きしたことのうち、「写真を見せる」場合の留意点を、特に2つにしぼってお伝えしました。1つは、震災当時の写真と、復興した後の今の写真を並べて提示することで、子どもたちに気づきを促す方法。 講師の方は「比較することは学習の基本だ」とおっしゃられていました。僕もそう思います。もう1つは、「子ども達の目の高さから見た写真と、そうでない写真」についてです。震災被害の写真には、いろいろな角度から撮影されたものがまじっています。空から撮影したもの、民家やビルを正面からアップにしたもの、被害の様子を遠くから広く捉えたもの・・・。子どもたちに写真を提示するときに、こちらのねらいとしては、「想像力をはたらかせてもらいたい」と思っています。壊れた建物や広い範囲の焼け跡を見せることも場合によってはありますが、「こわい」「かなしい」「かわいそう」といった以上に想像を働かせることがなかなかしにくいことが多いです。これが、子どもの目の高さから見た写真であれば、想像力を働かせやすい。また、モノだけでなくヒトがうつっていると、「あの人はどうしたのかな」と想像を働かせることになる。たとえ人が写っていなくても、建物の写真を見せた後で、「じつはこれは病院なんだよ」と知らせると、途端に、「お医者さんは? 患者さんは? 看護師さんは?」と、人がどうなったかが気になり始めます。「モノから人へ」大変大事な視点を提供していただきました。 震災関係の取り組みについては、僕の方で1月17日当日の追悼集会の司会と、映像や画像の提示を行うことになりそうです。全校生の貴重な時間をいただいての取り組みになります。去年同様、しっかり準備していきたいです。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.08
コメント(0)
-

1.17を考える
今日は防災担当の研修がありました。神戸市での震災教育の今を、お聞きしました。大変有意義な研修でした。講義を受けた後は、少人数での授業案立案。16時までのところを、20分オーバーして、学習指導の流れを考えました。教材は『明日に生きる』の中の、黙とうに関する小学6年生(当時)の作文です。同じ地域の他の先生方の考え方にふれ、大変刺激になりました。研修後、学校にとんぼがえりし、さっそく校長先生と相談しました。「震災に対する学校をあげての取り組み」についてです。僕の中では案はあったのですが、今日の研修が具体的に動き出すきっかけとなりました。勤務校では初めてになる「1.17追悼集会」を明日の職員会議で提案します。震災を風化させないために、経験されてきた先生方の協力を呼びかけ、学校をあげての取り組みをしていきたいです。 今年は、希望して「防災」の校務分掌を持たせてもらいました。防災担当としての初めての1.17を来月迎えます。兵庫県での震災教育の取り組み、他校での実践もぜひお聞きしたいです。コメントお寄せください。よろしくお願いします。 (震災関連過去記事 ▼震災当時の様子をお聞きする(2010年01月24日) ) (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.07
コメント(0)
-

森俊夫『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学』1~教師になぜ精神医学の知識が必要か?
『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1) (LD・広汎性発達障害・ADHD編)』(森俊夫、ほんの森出版、2006、2100円)僕の敬愛する森俊夫さんの本です。特別支援教育の対象と言われているLD,広汎性発達障害(アスペルガー等)、ADHDについての基本的な知識を学べます。発達障害に対する理解が「なぜ必要か」ということも、わかりやすく書いてあります。特別支援教育士の試験が近いので今日からこの本を読み返していくことにします。今日は第1章「精神障害とは何か?」のところだけ引用します。================================『教師とスクールカウンセラーのためのやさしい精神医学(1)』読書メモ1(p30まで #以下の緑文字は僕のコメントです。)・「事例性」においては、 「<誰が><何を>問題にしているか」が主要なポイント 「疾病性」より「事例性」のほうが大事です。#「問題はつくられる」ということ。 森先生の本では、よく出てくる考え方です。Q:教師になぜ精神医学の知識が必要か?・教職25年目の小学校の先生の回答 (森先生絶賛!) (1)個に合った教材の開発に努めていける (2)指導方法の工夫改善により個への配慮ができる (3)組織としての指導体制づくりをし、 多くの教師の目で子どもを見届ける必要性を理解できる (4)子どもをなるべく正確に見取る力になる 等 ↓ ○教師側に「精神医学の基礎知識」があれば 少し心のゆとりが生まれ、 個人を理解するうえで役立つ・森先生の設定していた模範解答の要素(抜粋) ○対応によって、その予後は大きく変わってくる。 ○対応の中身は、各精神障害によって、しばしばまったく違ってくる。 ○多くの精神障害は、早期に発見され、早期に適切な援助を受けられたならば、 その予後はよい。 ○教員は早期発見・早期介入の可能な立場にいる。 ○障害への偏見等を改善するためにも、子どもたちへの教育が重要。 ○まず教員が精神障害に対する正確な知識を持ち、 偏見を解消しておかなければならない。(第1章「精神障害とは何か?」まで)================================赤字にしまくりですが、どれも、忘れてはいけない大事なことだと思います。僕は忘れていました。(てへっ)思い出せてよかった。特別支援教育の必要性の原点は、子どもたちの事実にあります。「その個に合った対応」をすることで、変わっていった子どもたちを、何人も見てきました。今まで出会った子どもたちが教えてくれたことを、忘れずにいたいです。 そうそう。森俊夫さんといえば、ブリーフセラピーです。最初に読んだ本が、めちゃめちゃおもしろくて役に立つ本でした。ほんの森ブックレット『“問題行動の意味”にこだわるより“解決志向”で行こう』(森俊夫、ほんの森出版、2001、680円)ブログでも絶賛し、他の先生方にも勧めました。森先生の本の内容は、その他の本も含め、過去記事に詳しく書いています。未読の方はぜひご覧ください。あなたの現状を変えるパワーがあります。▼ブリーフ・セラピー(短期療法)は知る価値アリ!! (最初に紹介したブログ記事です。)▼『先生のためのやさしいブリーフセラピー』 ▼『解決志向ブリーフセラピー』 1 2 3 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.06
コメント(0)
-

おすすめ旅行先 京都府北部 福知山市
最近、ブログのアクセス数が急増しています。 11/29 → 11/30 → 12/1 → 12/2 → 12/3 → 12/4 483 → 467 → 448 → 514 → 583 → 678 訪れてくださっている方々、ありがとうございます。今日は、福知山まで行ってきました。舞鶴・若狭自動車道が無料になったので、阪神間の方とか、ぜひ行ってみてください。おすすめです♪三段池公園です。すごく広い公園で、いろいろな施設が併設されています。今日のように天気のいい日の散策には、もってこい!池を見て、なごみました。今日は行きませんでしたが、ここの動物園が小さい子どもさんにおすすめ!小さい動物園なのですが、動物とのふれあいが楽しめます。えさをやるのも、そこらじゅうの動物にやり放題。(笑)最近は、イノシシに子ザルが乗る、ということで話題になっているようです。僕らは、公園の後、ランチと温泉のために、ホテルロイヤルヒル福知山に行きました。僕らは隣の丹波市からの旅行なので泊まりませんでしたが、遠くから来られる方は、ここに宿泊して旅行の拠点にするといいです。広くて豪華なホテルで、天然温泉もついています。そのわりに、安めの料金で利用できます。楽天トラベルでの口コミ評価も、5点満点でクチコミ・お客さまの声: 4.43と高評価です。僕らはレストランと日帰りでの温泉利用。まず、和食倶楽部 「山葵(わさび)」というところで食事しました。ロハス定食とかあって、とっても健康的。店内の雰囲気も良いです。大きな窓からは、庭の景色。これがまたすばらしい。僕が頼んだのは中華ランチ。 1300円で、食後にはデザートとコーヒーもついてきました。おいしかったです。 食事の後は温泉へ。土日だけ、お昼も営業しています。日曜でしたが、14時頃に行ったので、すいていました。 僕の半径5m以内には、人がいない、という状態です。ゆったり入れました。(画像引用元:楽天トラベル「ホテルロイヤルヒル福知山」より) (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.05
コメント(0)
-

LD学会機関誌No.3より (特別支援教育推進にかかわるヒント満載!)
LD学会の機関誌を読む、第3回目です。 (過去記事) ▼第1回 ▼第2回今回は、さらに部分的に、自分のアンテナにひっかかったところを、引用・紹介していきます。▼が元記事のタイトル、・が元記事の部分的内容#は僕の意見・感想です。=================================▼柘植雅義「高校生に発達障害の授業をしてみたら」・自分でできる具体的なサポートをポストイットに書き(1人3枚)、 黒板に貼って・・・4~5つほどの観点に分類し協議#現場のケース会議でも使えそうです。(^0^)・発達障害の高校入試における配慮の事例 ・別室受検 ・試験時間の延長 ・集団面接を個人面接で実施 ・問題用紙の拡大 ・前日に試験会場の下見 等#他にも多数紹介されていました。 自閉症やLDなどの障害に合わせて、様々な配慮事例があることがわかります。 ▼上好 功(NPO法人特別支援教育ネットワークがじゅまる副理事長) 「高等専修学校における実践」・子どもと同じ年齢(発達年齢)になり、 遊び心をもって、一緒に楽しむ。 また、自分のカラーを変えることなく、 独自の方法で実践する。・手立ては用意しておいて、 本当に困って助けを求めてきたときに初めて、 具体的に支援する。・毅然とした態度を示す 悪いことは悪い#上の3つ、赤文字を使いましたけれど、 すっごく大事だと思います。 この3点は、どこの教育現場でも、共通ですね。 ▼島貫 学「特別でない特別支援教育」(高等学校の実践)・基本は教職員の情報交換・担任会や分掌連絡会、教科担任会等で 生徒の様子を必ず交流する。・提出された「気になるカード」への記入内容を一覧表に。 教科によって「気になったり」「気にならなかったり」というのが みえてくる。#「ポストイット」も「気になるカード」も、 「書いて交流する」という点で、同じですね。 勤務校のケース会議ではやっていないですが、 非常に効果的な方法だと思います。 ▼上野一彦「高等学校における特別支援教育の動向」・大学入試センター試験における 「発達障害」の特別措置について ・センター試験出願時に受検特別措置を申請する。 ・審査にあたっては、希望する措置の必要性、妥当性を判断するために、 (1)受験特別措置申請書 (2)医師の診断書 (3)状況報告・意見書等 の書類の提出が求められる。 ・(3)については、 個別の指導計画や個別の教育支援計画等によって 明らかにされる可能性も高く、 今後の特別支援教育の一層の推進を求めることにもなろう。#以前、竹田先生からお聞きした、 「センター試験における配慮」の実像が、 この記事によって、大変よくわかりました。 センター試験は、毎年1月でしたっけ? もうすぐですね。 今年は「発達障害」への配慮が具体的に示されたということで、 実際にどうなるのか、注目しています。 高等学校での特別支援教育をぐぐいっと進めるきっかけに なりそうです。================================= (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.04
コメント(0)
-

(DS)スタジオジブリ+久石譲『二ノ国』
今日、電気屋さんに寄ると、スタジオジブリ+久石譲+レベルファイブ、という文字が目につきました。レベルファイブというのは、DS「ドラゴンクエスト9」の制作会社です。ジブリがDSでのゲームソフトに進出するとはびっくりしました。知っている人は、かなり早くから知っていた情報だと思いますが。テレビで流れていたゲームのムービーを見ましたが、まんま、ジブリのアニメ映画そのものでした。ジブリは大好きだし、ファンタジーが舞台のRPGも好きなので、とてもおもしろそうだと感じました。「魔法指南書」という本が同梱されていて、その謎解きを並行して行うようです。かなり心惹かれます。音楽が久石譲というのも、ポイントが高い。演奏は東京フィルハーモニー交響楽団です。ムービーのBGMをちょっと聴いただけですが、これまた、ジブリ映画そのもの、って感じでした。発売は来週の12月9日。現在予約を受け付けています。子どもたちのクリスマスプレゼントでかなりの本数が売れそうです。↓楽天ブックスでは、今ならポイント7倍のキャンペーンもしています。(^^)【送料無料】二ノ国 漆黒の魔導士 【魔法指南書 マジックマスター 同梱】ポイントに弱いので、楽天で今さっき予約してしまいました。届くのが楽しみです。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.03
コメント(0)
-

日本が変わるスイッチが入っている映像 - 裸の男とリーダーシップ
ネットワーク地球村の会報で、高木善之さんが紹介されていました。(YouTube動画)日本が変わるスイッチが入っている映像 - 裸の男とリーダーシップ 1人の裸踊りが、1人のフォロワーを得ることで、次第に人数が増え、最後には大人数でのムーブメントに発展。「ムーブメントを起こす」とはこういうことか、と分かります。仲間や賛同者を得るには、まず、一人で、本気の裸踊りをはじめることですね。折に触れて何度も見たい動画です。 (^0^)いつも読んでくださって、感謝します! ブログを応援してくださる方はクリックしてください!(^^;) ブログ王ランキング
2010.12.02
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1





