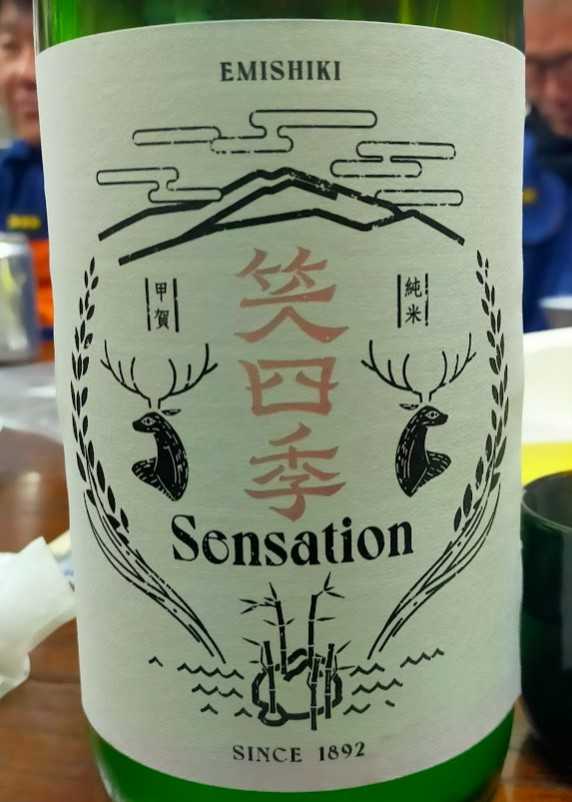2018年04月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
一筋縄ではいかないカセットテープ
今春、就職して独り立ちしたムスメの部屋を整理していたら、CDラジカセが出てきた。この機械もそれなりに古いシロモノで、CDが再生できなくなっている、ということは以前ムスメから聞いていたので、機械が出てきたところでさほどの期待感は無かった。そのまま数日放っておいたのだが、ある日ふと、カセットテープなら聴けるんじゃないか、と思いついた。そこに思い至るまでに時間が掛かったのは、私が音楽をCDに焼くということを覚えて以来、もうかれこれ10数年、カセットテープとは無縁の生活を送っていたからに他ならない。その間、過去に録り溜めたテープも、目につかないところにしまい込んだままだったのだ。そういういきさつで、10何年か振りにカセットテープを引っ張り出してきた。恐る恐る1本のテープを機械にかけてみると...おぉ、ちゃんと作動するではないか!しばらくすると、音も問題なく聞こえてきた。現在わが家ではCDデッキも壊れていて、まともに動くのはレコードプレーヤーだけなので、カセットテープが聴けるというのは、嬉しいニュースだ。ところが使い出してからわずか数十分後、新たな欠陥が発覚した。このCDラジカセ、早回しと巻き戻しのボタンが機能しなくなっているのだ。もっとも一本のテープを初めから終わりまで、表裏と順序通り聴く分には問題ない。ただ私はテープの途中で放っておくのが嫌いな性質なので、昔からの習慣で、片面聞き終わったら必ず全部巻き取るようにしている。ところが早回しが出来ないので、例えば片面30分のテープに24分しか録音されていない場合、聴き終わったら6分の間は再生し続けなければいけない。で、先日初めて聴いたときも、テープをそのように再生のまま放っておいた。その間一時部屋を離れていて、そろそろ終わったかなというタイミングで部屋に戻った。なのにまだ廻っている....!?おかしいなと思い、停止ボタンを押してテープを取り出してみたところ、最後まで巻き取ったあと、勢い余ってテープが根元からちぎれてしまっているではないか!おそらくは古いテープ故に劣化していたんだろう。テープの劣化といえば、ワカメ状になって音がおかしくなるのが定番のイメージだが、こういうケースもあるんだなあ。こんなことで掛けるテープが片っ端からお釈迦になってはたまったものではない。そういうわけで、またまた満足に音楽の聴けない生活に逆戻りだ。
2018年04月14日
コメント(0)
-
伝統とは
伝統とは何だろう?とにかく変わらないこと、変えずに続けることを伝統だと思っている人は多そうだ。そうすると、そうした行為こそが「伝統を守る」ということになる。ただ私は、「伝統を守る」というのはあくまでも「結果」でしかないと考える。あえて言えば「伝統」とは、数多の人々の営みが連綿と続いてきた過程であり、それが“結果として”「伝統」となっていくのではないか、と思っている。その過程においては、様々な障害や葛藤もあるだろう。そしてその中には、過去に例の無い事象にぶち当たることもあるだろう。その度ごとに適切な判断を下した者のみが、伝統を引き継ぎ得るのではないか。「変えない」という意識ゆえに思考停止になるのは、本末転倒だ。あらゆるものは変わりつつあるものだ、という前提で考えれば良いだけのことだ。たとえば日本酒の酒蔵。100年以上続いている蔵は全国でも珍しくないが、もちろんそれらの蔵が皆、100年前と全く同じ酒造りをしているわけではない。機械化すべきところは機械化して、合理化、省力化を図っている。でもそのことが酒蔵の伝統を汚しているわけではもちろん無い。思考停止に陥って、頑なに変わらずに凝り固まっているものを、「因習」と呼ぶ。早いハナシが、今の相撲界が大切にしているモノは、「伝統」ではなく、「因習」でしかない。その「因習」も、合理性が明らかなものであればまだいいと思う。ただ、「土俵上は女人禁制」という因習に、どれだけの合理性があるのだろうか?見方を変えよう。どれだけの人にメリットがあるのかどうか。「土俵上は女人禁制」という因習を堅持することで、メリットのあるのは誰か?他方、この因習を撤廃することで、不利益を回避し得る人は多いのではないか?要は何の合理性も持たず、誰のメリットにもならない因習を頑なに堅持することに、どれだけの意味があるのだろう、ということだ。結論。「土俵上は女人禁制」という因習は、即座に撤廃すべきだ。私は門外漢ではあるが、それが相撲界の「伝統」を損ねることにはならないと考える。
2018年04月05日
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1