2006年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
島田荘司『天に昇った男』
島田荘司『天に昇った男』~光文社文庫~ 昭和51年、九州O県の星里という街で、事件が起こった。 星里は、星が美しいことで有名で、観光客でにぎわう街であった。その街の、伝説とも実話ともつかない言い伝えにより、昇天神社の境内に、桜の季節に高い櫓(やぐら)を建てる。そこで繰り広げられる昇天祭は、有名な祭りとなっていく。 古くからあった街だが、洋風の建物が増えてきた。昔ながらの、街一番であった旅館「ほしのや」の経営は火の車となる。その経営者三人が殺された。櫓に、ロープでつるされていたのだった。 容疑者は、「ほしのや」近くの料亭の板前であった、門脇春男。彼には、異例の速さで死刑が宣告された。 それから、17年の歳月が経った。10時10分前。拘置所の死刑囚棟に、看守の足音が響く。門脇の死刑が執行されるときがきた。 上の内容紹介では最後に書いた、死刑囚棟のシーンから、物語ははじまります。門脇さんに死刑が執行されるのは、平成5年(1993年)。日本に、死刑がそぐわなくなってきた-そういう様子が描写されます。法務大臣の署名により、死刑が執行される。大臣は、自分の手で殺人を犯す苦痛から逃れる。殺す側は、大臣の署名によって処刑されるんだからね、と、責任から逃れようとする。 ちょっとナイーヴな話題になりますが、中世ヨーロッパでは死刑執行人は蔑視されていました。そんなことを連想します。すすんでしたい人はいない、けれども、遺族のため、秩序のため、その存在が必要とされているのでしょう。 もちろん、死刑囚には、そうなってしかるべきことをしたという過去があるのでしょう。彼らは死んで罪を償うべきだからこそ、死刑囚となっている。けれども、彼らが殺されるとき、殺す側も、殺される側も、様々な思いにとらわれる。最初にいくつか、死刑囚の心情描写というか、死刑場に連れて行かれる前の言動が紹介されていますが、複雑な気分にならずにいられませんでした。 主人公の門脇さんは、しかし冤罪を主張しています。物語を読んでいくと、本当に苦しい人生で。といって、それは私が生まれてからの社会と、周囲の環境、それによって形成された私の考え方から「苦しい」と言っているのであって、当時を生き抜いた方々から見れば、本当に私などあまちゃんだと思うのですが…。こんなことを言っていると話がすすまないのでいきますが、覚せい剤の使用の件など、あきれてしまったというか…(門脇さんは覚せい剤もしていないようですが)。人の考え方を、いかに社会が規定しているか、というのをあらためて思います。そしてその社会を都合のいいように変えていくお上。…島田さんの作品からは、どうしても権力、お上への批判をはらんでいるようなので、こういう感想が出てくるという面も考慮しておきましょう。 ともあれ、門脇さんはやっと星里で落ち着けたかと思ったのですが、そこで出会い、彼を慕ってくれた女性が、また不幸な境遇で。そして事件が起こり、十七年の歳月が流れるのです。 ラストはへこみました。途中感動させられて例によって涙していたので。あっ、まさにラストで書かれているようなことを、私も体験させられたことになってしまいます。胸が痛むエピソードが多いです。高圧的な警察官。読んでいていらいらします。 そんな中、星里に伝わる話は、面白い(笑えるという意味ではないです)オチもあって、印象に残っています。天に昇るために、大きな櫓を建てる男の話です。
2006.02.28
コメント(0)
-

秋月涼介『消えた探偵』
秋月涼介『消えた探偵』~講談社ノベルス~ 入ってきた扉から出て、出てきた扉から入る。そうしなければ、異世界に飛んでしまう。そう信じ込み、生活のルールとしているスティーヴン。彼は、その能力を理解できない周りの人間たちから、強迫神経症と烙印をおされ、症例蒐集家アンソニーの経営する診療所に入所することになる。 解離性同一性障害のクリス、統合失調症のアリー、不眠症のリー、心気神経症のエルザ、「多重恐怖症」のガイ、前向性健忘症のシルヴィ、躁鬱病のメイ。これらの患者のみならず、職員も精神的な疾患を抱えた人間ばかりが集められた診療所。 ある夜、スティーヴンは、三階の一室で倒れた人間と血痕を目撃する。その直後、犯人に襲われ、彼は窓から転落した。命に別状はなかったが、入ってきた扉とは異なる場所から建物の外に出てしまったため、スティーヴンは、異世界に飛んでしまったと考える。 その後、事件の現場を調べたが、血痕もなく、さらに調査を進めたものの、一向に加害者も被害者も浮かんでこない。異世界にきてしまったために、事件の性格が変わってしまったのではないか。自分が体験した事件は、窓から出てしまった後のこの世界では、将来起こることなのではないか。そう考え始めたスティーヴンは、被害者と加害者の見当をつけ、事件を未然に防ごうと奮闘する。 あらすじはこのような感じです。んー、ふーんっていう読後感です。320頁、4時間ほどですね。正直残念です。 上で書いたように、いろんな症状の方々がいる診療所。スティーヴンは被害者(あるいは加害者)の目星をつけるため、患者全員に話を聞いていきます。その中で、患者たちの症状、彼らが過去に体験した事件のエピソードなどが語られていきます。一人一節(一章)かけていくので、エピソードとしては興味深いし、症例もしっかり調べておられるんでしょうけれど、冗長な感じは否めません。 不安神経症はいまはともかく、私の記憶には特別な意味をもって残っている言葉ですし、先端恐怖症は若干ありますし、私は高所恐怖症ですし。そのほかいろいろ思い出して、考えるところはありました。 スティーヴンにとって、出入り口の問題は自己同一性…というとおかしいですね、彼は異世界を超えても、彼自身は変化なく、周りの人間が見た目は同じだけれど変わってしまう、という考え方ですので、世界の同一性とでもいうのでしょうか、とにかく世界が変わってしまう問題です。他人が妄想と言おうが、彼にとってそれは真実です。 本書に書いてあったわけではないですが、自分を誹謗中傷する、もっとひどい言葉を投げかける声が聞こえる、というのは、本人以外にその声が聞こえなくても、本人には本当の体験として感じられているのです。ですから、「幻聴」という言葉自体に疑問を抱いている方もおられるそうです。 …などなど、自分の体験を他人は共有しえない、とか、少数派を迫害する多数派、とか、こういった問題については興味深く読みました。死期を予知できる魔女の理論や、人形遣いの悪魔の理論などを読んでいると、運命論についても考えるきっかけになるでしょう。 ミステリとしても、たしかに伏線があるといえばありますし、終章の出だしではやられた、と思いました。でもオチが…。唐突な感じが否めません。傍点がついていますが、読み進めている中で、そんなことは全く考えませんでしたし、全体の中の位置付けとして、傍点つけて強調するようなところかな、と思ってしまいました。 被害者も加害者もわからない中、その両者を探り、事件を防ごうとする。こういう物語は私にとってははじめてですし、読んでいて不思議な感じがしました。
2006.02.26
コメント(0)
-
漢字バトン
研究室の方から、またまた挑戦してみて、と紹介されたバトンです。前の人から課題にされた漢字としては、同室某氏が提案された漢字に挑戦することにします。1.前の人が答えた漢字に対して自分が持つイメージは?【牧】…おおらか、のんびり。ふむ、次の漢字とあわせると牧歌風の「牧歌」になりますね。そこからの連想もあるかもです。統制しようとする存在が、司牧の担い手となるわけですね。説教師ジャック・ド・ヴィトリ万歳。でも私は牧の存在でいたいです(最初に答えたイメージと私はそぐわないですが)。【歌】…言葉は人を救うこともできます。歌。言葉を旋律にのせてつむぐ。ときに落ち着かせてくれ、考え込ませてくれ、感動させてくれる存在。(宗教の)教えを伝える手段にもなりますね。グレゴリオ聖歌万歳。【高】…手が届かない存在。こちらを圧倒してくる存在。場合によっては、だからこそ挑み、がんばろうとする活力を与えてくれます。場合によっては、というのは、人には得手不得手がありますから。自分の行く道にそれがあれば乗り越えたいし、目指す地点は、きっと高いところでしょう。…ふむ、なんかノリで書いてしまいました。付け加えておきますが、私はキリスト教徒ではありません。2.次の人に回す言葉を三つもし後に名前を挙げる方々がしてくださるなら、【繊】【教】【和】でお願いします。上記のように、1番の項目でお答えください。3.大切にしたい言葉を三つ【直】馬鹿正直でもいい、まっすぐ、素直に生きていければいいと思います。実際は歪みだらけなので、考えるところが多いわけですが。【敬】「われ以外、みな我が師」-吉川英治さんの言葉だそうです。私以外の誰もが、私にない長所を持っています。人を敬う気持ち。これは大切にしていきたいです。【温】ほんわかあったか。落ち込んだときでも、微笑んでしまうような心のゆとりをくれる、そんな雰囲気。私のまわりにそういう空気を感じられる場がいくつもあることに、幸せを感じています。4.漢字のことをどう思うこのバトンを答えるにあたり、参考にしている方の答えにもありますが、表意文字にして表音文字、ということが浮かびます。いままでに答えてきたように、漢字一文字に対して、いろんな意味を感じ、いろんな印象がもてる。その奥が深いところが好きです。5.最後にあなたの好きな四字熟語を3つ教えてください【諸行無常】それでも、ひたむきに生きようかと思います。【信賞必罰】がちがちだったら息苦しくなりますが、それでもなるたけ世の中はこうあってほしいです。【温故知新】歴史を学んでいる者として、頭にとどめておきたい言葉です。6.バトンを回す人6人とその人をイメージする漢字をなにしろ、バトンをまわすなんてのは初めてですから緊張します。以下に名前を挙げる方々は、もしお時間があれば、バトンを受け取ってくださると幸いです。勝手なイメージも書いてしまって恐縮です。それから六人はしんどいので、楽天ブログからお二方、その他のブログからお二方、お願いしたいと思います。・あっくん先輩さん イメージ:「技」叙述トリックを織り交ぜた日記に「やられた」と思い、またその日記にはしばしば笑わせてもらっています。・torezuさん イメージ:「誠」日記や、こちらにいただけるコメントなどを拝読している中で、誠実な方だという印象を抱いております。・でこぽんさん イメージ:「姉」私がいろんなブログに出かけて、コメントなどをするようになったきっかけを作ってくださったので。・聖月さん イメージ:「豪」日記を拝見するたびに、豪快さに感嘆しております。ご家族の方との温かいエピソードも好きです。ほとんど勢いで書いてしまいました…。四名の方、勝手に紹介してしまってすみません。ーーーバトンをまわしてくれた方、こんなところでよろしいでしょうか。久々にのんびり考えることができて、楽しめました。ありがとう。
2006.02.26
コメント(4)
-
アンリ・ピレンヌ『中世都市-社会経済史試論-』
アンリ・ピレンヌ(佐々木克巳訳)『中世都市-社会経済史試論-』~創文社、1970年~2005年9月8日に紹介したアンリ・ピレンヌの著作です(その、『ヨーロッパ世界の誕生』についての記事はこちら)。目次は以下のとおり。序文第一章 八世紀末に至るまでの地中海商業第二章 九世紀の商業の衰頽第三章 シテとブール第四章 商業の復活第五章 商人第六章 都市の形成と市民第七章 都市の諸制度第八章 ヨーロッパ文明に対する都市の影響第一章、第二章は特に、先述の『ヨーロッパ世界の誕生』を読んでいたので、よりよく読めたように思います。ローマ帝国は地中海的性格をもっていた。ゲルマン人がその性格を変えてしまったのではなく、彼らの侵入後もローマ帝国の商業の動きは連続している。この古代世界を破壊するのはイスラームの侵入であり、これによって西方は地中海的性格を喪失し、重心を北方(内陸)へと移すというのです。九世紀、カロリング朝の商業活動はとるにたりないものであり、市場は地方的な小市場にすぎなかったと指摘されます。この時代、経済の基盤は動産から不動産(土地)となり、ピレンヌによれば、カロリング帝国は、「内陸国家であったと同時に、本質的に農業的な国家」だったということです。荘園も、従来は商業活動に従事していましたが、商業の衰退により、消費経済(自給自足的)へ移っていくということです。以上、第一章から第二章までの整理です。第二章の後半では、カロリング帝国と中世のロシアが対比されていて、興味深かったです。第三章、シテとブール。ここはもう少し整理しておきたいところです。…が、メモ程度にここにも書きましょう。戦争時などに避難するための囲い地。ここは、住民たちが儀式などで集まる場になり、やがて宗教上、行政上の中心となります。これがシテです。シテには、司教が管理するものもあり、そうしたシテでは司教の権力が強くなっていきます。シテは、宗教行政の中心となるのです。ブールも、城壁によって囲まれた場所(通常は円形)でした。これは軍事的な施設でした。第四章、商業の復活。重要なのは、10世紀からの人口増加です。これにより、開墾の時代をむかえることになります。そして、商業の復活に大きな役割を果たすのは、ヴェネツィアによる地中海商業と、フランドル地方のノルマン人との交流です。つまり、外の商業との接触が、商業の復活につながっていくというのです。こうして、商業、そして工業がさかんになってくると、それは農業にも作用し、都市と農村の間に相互関係がうまれるのです。第五章では、職業商人の誕生と、その地位について。職業としての商人はヴェネツィアから生まれていくと指摘されます。また、先にもふれた人口増加。これにより放浪者が生まれ、その中から商人が出てくるという指摘は、興味深く読みました。商人は、自分たちの利益のために集団を形成し、遠隔地商業によって各地を放浪します。この動きが、農業社会、あるいは既存の秩序に衝撃を与え、商人は貴族や聖職者から批判の目で見られることになります。ところが、公権力によって保護もされ、彼らは自由民にして特権者となるのです。第六章では、先にふれたブールに並んでつくられたフォブール(新しいブール)の重要性が指摘されます。ここが商人の定住地とされていきます。ブルジョワは、この新しいブールの住民のことだという指摘(古いブールの住民にブルジョワという名称は決して与えられなかったという指摘)が、実に勉強になりました。さて、疲れてきたのではしょります。第七章は、最後でまとめてくれているので、引用します。「中世の都市は、12世紀に入って現れてくるところでは、防備施設のある囲いの保護の下に、商工業によって生活を営み、都市を特権的な集団的人格とするところの特別の法、行政、裁判を享受する、コミューンである」(181頁)。要は、ここでは市民の特権的な性格が指摘されています。第八章で興味深かったのは、農民が余剰収穫物を売ることで利潤を得る、その前提には商業の発展があった、ということですね。技術の改良で生産量が増えるわけですが、このように農民が勤勉に労働するのは、商業によって自分が快適になっていく可能性が開けたから。興味深かったです。ピレンヌの本は、論の展開がうまくて、読みやすいです。読んでいて面白い、と思いました。
2006.02.18
コメント(0)
-

倉知淳『占い師はお昼寝中』
倉知淳『占い師はお昼寝中』~創元推理文庫~ 昼寝が大好きの占い師・辰寅叔父のもとに、見習いアルバイトとして通う美衣子。占いでは嘘八百を並べ、口先で客をまるめこむ。それでいて、事件(事態)は解決、あるいは良い方向に向かっていく-。叔父のぐうたらぶりにあきれながら、その洞察力や要領のよさに一目置き、そして訪れてくる「お客さん」を観察して社会勉強をする-。そんな美衣子が関わった、六つの事件。「三度狐」一番目の「お客さん」は、一流会社の課長補佐。引っ越しをし、また社内で昇進の話が出た頃、身の回りで不審なことが起こった。ゴルフクラブの紛失、書類紛失、そして、枕もとにおいていた本の紛失。「水溶霊」二番目の「お客さん」は、かっこいい女性。彼女のマンションで、ポルターガイスト現象が起こったという。「写りたがりの幽霊」三番目の「お客さん」は、軽薄な男子学生。彼が写っている三枚の写真は、いかにも心霊写真のようであった。「ゆきだるまのロンド」四番目の「お客さん」は、明るい主婦。自分が二人いるのではないか、そう疑問を感じずにいられない出来事が起こっているという。「占い師は外出中」五番目の「お客さん」たちは、二人の老人。片方の老人の家に、血まみれの幽霊が出るという。「壁抜け大入道」六番目の「お客さん」は、小学生の男の子。父親に盗難の疑いがかけられているが、自分は事件の夜、現場に、一つ目の大入道を見たという。 面白かったです。辰寅さんの口調が、どこか猫丸先輩に似ているなぁと感じてしまうのは仕方ない…? まったく予備知識のないままに読みました。「三度狐」の真相編で、そうとう引き込まれてしまいました。話を聞きながら、漠然と答えを導き出す。その後考えると、論理的な思考の道筋が見える。こういう、辰寅さんのやり方が面白いなぁと思ったのも大きいですが、彼の心配りもよいですね。「三度狐」があたたかいお話で、この短編集は私にとって当たりだ、と思いました。 第四話「ゆきだるまのロンド」も、あたたかくて素敵な物語でした。 お客さんたちが語る事件は、日常離れした、不思議な事件、現象。それこそ幽霊だの、ドッペルゲンガーなど、超自然的なものを感じるからこそ辰寅さんのところへ相談にくるわけですが、当の辰寅さん自身は一切そういうものを信じておらず、さらに占いさえも信じていない。このギャップ。そして、非日常が、生臭い、あるいはあたたかい、ともかくあまりにも「日常」のこととして説明されていく過程。面白くて、わくわくしながら読みました。 好奇心いっぱい、ちょっと直情的なところもある美衣子さんと辰寅さんのやり取りも、ほのぼのしています。ものすごく面倒くさがりの辰寅さんですが(客が長居しないために、冷暖房も設置せず、ソファを粗雑にするなんて)、ときどきかっこよく思われるのです。 あたたかい物語を読みたい気分だったのもあり、良い読書体験でした。
2006.02.16
コメント(0)
-
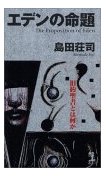
島田荘司『エデンの命題』
島田荘司『エデンの命題』~カッパノベルス~「エデンの命題」アスペルガー症候群のぼく-ザッカリ・カハネは、アスピー・エデンという教育施設に入れられていた。ここは、アスペルガー症候群と診断された中でも、学力が高い人々を集めた施設である。多くは、ここに入るまでに、いじめなどを受けていた。ぼくもその一人。しかし、この施設では、勉強に運動に、充実した生活が送ることができた。ここで知り合ったティアと、ぼくは親密になった。しかし、ある日、ティアが手術のために施設を出てから、ぼくは大きな陰謀に巻き込まれていくことになる。「ヘルター・スケルター」頭部を怪我し、記憶に障害をもっているらしい俺。俺の脳には、異常があるようだった。女医に、脳を活性化するという薬を飲まされ、その薬の効果の続く時間-五時間以内に記憶を戻さなければ、俺は生涯ベッドの上での生活になる可能性があると宣告される。女医の言葉にうながされながら、俺は少しずつ過去を思い出していく。 以下、それぞれの作品について感想を。「エデンの命題」。 私は学生の頃、アスペルガー症候群と診断された子どもたち、線引きは難しいのですが、自閉症、高機能自閉症と診断されている子どもたちの、託児のボランティアをしていたことがあります。本書の中でも言われていますが、「自閉症」とは、自分の中にひきこもる-いわばひきこもりのように誤解されることもあると思うのですが、決してそうではありません。すごく活発ですし、元気ですし。周囲の人にあわせるのが苦手で、周囲の人には、そこが受け入れがたく感じてしまう。正直、私も一緒に遊ぶ中で、対応に困ってしまうこともありました。思うところがあったのもありますが、自閉症について、ほとんど勉強もしていなかったのもあるのでしょう。 ともあれ、この中編は、そのアスペルガー症候群の少年、ザッカリによる一人称で話が進みます。旧約聖書の解釈-創世記の蛇、禁断の木の実、アダムの肋から作られたイヴ、これらについての話を、興味深く読みました。私は中世のキリスト教関係の勉強をしていますが、聖書の解釈などは不勉強でして、カインの妻の話については、なるほどと思いました。まったく、矛盾がありますね。 クローンや脳について、島田さんはずいぶん詳しいようで、既にいくつかの著作の中で、これらを題材にした物語を書いておられます。それらの作品を連想しながら、本作を読みました。「ヘルター・スケルター」 いろいろと違和感を感じながら読みました。最後は、あぁ、なるほど、と納得。こちらは、脳の仕組みについて、詳しく書いてあります。また、「エデンの命題」の主題がアスペルガー症候群と旧約聖書の二本立てとするなら、こちらの作品は、脳(の異常)とヴェトナム戦争の二本立てといえるでしょうか。ES細胞、インシュリンなどなど、最近よく耳にする言葉がよく出てきて、勉強になります(私はあまり分かっていませんが…)。勉強しなくては。 全体を通して、やっぱり島田さんの小説は面白いなぁ、と思いました。吉敷さんのシリーズはほとんど読んでいませんし、御手洗さんシリーズ以外の短編集ではあんまりぱっとしないと感じる作品もありますけれど…。
2006.02.16
コメント(2)
-

佐飛通俊『円環の孤独』
佐飛通俊『円環の孤独』~講談社ノベルス~(記事は、16日に書いています) 2050年、宇宙空間に浮かぶステーションホテル。ここに、招待客など、 15人の客が宿泊していた。 名探偵として有名なH・Mは、3年前に起きた事件の真相がわかった、と、吹聴してまわっていた。今回の客の中には、三年前の事件の関係者たちも集められている。その犯罪を、H・Mは皆の前で暴露しようとしていたようなのだが-。 H・Mは殺された。首のうしろを刺されており、自殺とは考えられなかった。しかし、現場には不可解な点があった。ステーションホテルの鍵は、全てDNA識別によっている。内部でH・Mは死んでいるというのに、彼の部屋の鍵はロックされていた。 三年前の事件にも、密室状況があったという。殺人鬼と呼ばれた男、時計に飾られたどくろ、そのどくろの紛失、闇夜を移動するどくろ…。その事件にも、不可解な点がいくつもあった。 ステーションホテル内の事件、そして三年前の事件について、宿泊客として居合わせた日本の刑事、鈴木新が謎を解き明かす。 私は、SFものは苦手なのですが、それでもなんとか読めました。しかし、ステーションホテルの機構の細かいところや、宇宙服を着てホテルから(万が一)出た場合でも、ホテルからそう離れてしまうことはないといったことなど、細かいところの説明は、登場人物の口を借りてなされており、「もっとも僕はそれ以上詳しいことは分からないけど」なんて言葉で濁されております。ステーションホテルの仕組みが本書の主題ではないにしても、主要舞台なのですから、せっかくこういう舞台にするんなら、もっと深めた設定にしておく方がよいのでは、と思いました。もっとも、私はあまりに物理学的な話になってついていけるわけじゃないですが、たとえば、分かる分からないは別として、竹本健治さん『匣の中の失楽』や乾くるみさん『匣の中』を興味深く読みましたので、細かい話を書いてもらっても楽しめたかな、と思いました。 本書の設定では、2050年の日本は大変なことになっております。んー、どうなるんでしょう。 がちがちに古典的な本格ミステリを意識されているようなので、正直、2050年で宇宙に浮かぶホテル、という設定がミスマッチのような印象を受けました。そういう意味で、三年前に起こった事件の方は、<文字反転>1980年の事件ですので<ここまで>比較的面白いと思いました。どくろの紛失なんて、なかなか魅力的です。 なお、作者の名前は、さびみちとし、と読むようです。ーーートラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。ーーー ちょっと日記も。 火曜日に風邪をひいてしまい、午前中は大学に行っていたのですが、あんまり具合が悪くなったので、昼過ぎに帰宅して、寝込んでいました。水曜日もほとんど寝込んでいたのですが、夕方くらいに少し落ち着いたので、なんとか本書を読了できた次第です。
2006.02.15
コメント(2)
-

のぽぽん☆
のぽぽんです!二つまとめて撮ったのですが、小さいコが不鮮明になってしまいましたね。またあらためて撮ろうかな…。先日ある方にいただき、とても嬉しかったのです。研究室においています。これで、通学時も、バイトから研究室に戻るときも、わくわく感じが増すというものです。もともと、いま使わせてもらっている研究室はとても居心地がよいと思っていたのですが、さらに癒しグッズもいる、楽しみな場所になりました。私のハンドルネームはのぽねこですが、これはのぽぽんとねこが好きだから、という理由からです。ハンドルネームに一部使わせてもらうのが恐縮なくらい、のぽぽんはかわいいです。写真の方ですが、大きな方が背もたれと腰のあいだにはさんだり、座布団にしたりという用法のものです。座布団にするのはなんだかもったいないので、背中にいてもらっていますが、ときどきぎゅっとして遊びます。横になるときは、枕にもなってもらえますね。ふかふかしていて気持ちいいです。小さな方は、手でふにふにして遊びます。むかしのこんにゃくボールみたいな感じですね(こんにゃくボールでは、仙台で会った方々には通じなかった覚えがありますが)。のぽぽんはなかなかお店にいないので(足指用やら目を冷やすのなどはあるのですが)、本当に嬉しく思っています。
2006.02.13
コメント(0)
-
コレット(堀口大學訳)『青い麦』
コレット(堀口大學訳)『青い麦』Gabrielle Colette, Le Ble en Herbe~新潮文庫~ 夏休み、例年のように海岸の別荘を訪れたヴァンカとフィリップ。二人は兄妹のように育ち、恋仲にあった。不器用で、喧嘩もしながら、それでも二人はお互いに愛していると思っていたのだが。 ある日、フィリップは白衣のマダムに出会う。後日、お使いに行った帰り、フィリップは彼女-カミル・ダルレーと再会した。そこでオレンジエードをご馳走になった彼は、その後ダルレーへの思いを募らせていく。 …ところが、ある日、ダルレーは彼に告げないまま別荘を去り、ヴァンカはフィリップの浮気に激怒する-そういう話でした。 その、ヴァンカの激怒のシーンは、さすがに訴えてくるものがありました。それに対するフィリップの反応に、どこかいらいらしながら読みました。 海外の名作ということで、普段なら長めに内容紹介をメモするのですが、本作はとりわけ細かく内容紹介もしづらいので、この程度で。 興味深かったのは、ヴァンカとフィリップの親たち-大人が、「影」と表現されていること。地の文では、大人たちの名前は一切出てこなかったように思います。
2006.02.13
コメント(0)
-

本多孝好『真夜中の五分前 side-B』
本多孝好『真夜中の五分前 five minutes to tomorrow side-B』~新潮社~ 一卵性双生児の姉妹の一人、かすみと付き合い始め、二年が経った。 その間。 かすみは、妹のゆかりとともにスペインに旅行に行っている際、事故で死亡した。 上司の小金井さんは仕事をやめ、僕も仕事をやめ、温泉地の町おこしの件で知り合った人物-野毛さんのもとで働き始めた。僕がもと勤めていた会社は、大手の広告代理店に併合された。 ある日、ゆかりの夫、尾崎さんから連絡があった。いまの自分の妻が、ゆかりなのか、かすみなのか、分からない-。そういう話だった。 僕は野毛さんの、いわば道楽ともいえる事業で、経営不振の店を建て直させる仕事をしていた。いままで出かけた店は四軒。全て、成功していた。そして僕は、また新たな店を手がけることになる。 今回もやはり、メモ程度にあらすじは書きましたが、本当にメモ程度です。 本書も素敵でした。かすみさんと付き合い始める中にも、僕とかすみさんの間にはいろいろな痛みがあったわけですが、うまくいき始めたときの、かすみさんの死。事故には姉妹とも巻き込まれており、生き残った方がかすみさんなのかゆかりさんなのか、それは尾崎さんにも僕にも、そして生き残った本人にもわからない。どうしようもなく苦しい状況だと思います。 僕は、久々に小金井さんと再会したとき、ある忠告をうけます。そしてある行動を起こし、それから、少し-それまでとは違った、スタートを切ることになります。 小金井さんも素敵だし、野毛さんも素敵です。渋谷のバーのオーナーもバーテンも素敵です。オーナーが回していた、どんぐりのこま。なぜかとても印象に残っています。学生時代、僕が水穂さんとよく通っていた喫茶店のマスターも素敵だし、水穂さんのお父さんも、どこか不器用で、とても素敵です。 今年の12月末にも、きっと私は「今年読んだおすすめの10冊」を選ぶでしょう。本作-side-Aとあわせて、『真夜中の五分前』はその中にいれよう、と思いました。 そう、結局、僕の名前は一度も出てきませんでした。*追記。読んでいるときには、ここにはふれておきたいと思いながら、書き忘れていました。僕は、大学時代の恋人、水穂さんの影響で、目覚まし時計を五分遅らせています。水穂さんが亡くなってからも、その習慣は変わっていません。私事になりますが、私はむしろ少し進めています。最近では、目覚ましは携帯電話の機能を利用していますので、実際に起きたい時間より2,3分前に目覚ましをセットするようにしています。つまり、時計を遅らせる、というのは、私の感覚ではありえないのですが、それがとても素敵なことに思われる描写がありました。その部分を引用しますが、一応文字色を変えておきます。「僕は枕もとの時計を見た。もう少しで日づけが変わるところだった。とするなら、世界の日づけはもう変わっているのかもしれない」(90頁)。こんな風に思えるのは、なんだか素敵だな、と。時間に厳格で時間に追われている私ですが、たまにはこんな風に思えるようなゆとりももちたいものです。といって、別段、ゆとりなく暮らしているという感覚はありませんけれど。ーーートラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。
2006.02.12
コメント(0)
-
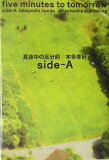
本多孝好『真夜中の五分前 side-A』
本多孝好『真夜中の五分前 five minutes to tomorrow side-A』~新潮社~ 広告代理店につとめる僕の上司、小金井さんは、非常に有能なのだが、組織とはあわず、彼女を嫌う人間は多かった。僕の属する部署は、北陸の温泉地の町おこしにたずさわっているところだった。 仕事に忙しく、最近微妙な空気を感じ始めていた恋人とも、久々の食事。それからしばらく二人の間で連絡をかわすことはなく、次にあったときは、二人の関係が終わった。 僕は暇になった終末、プールに行くようになる。そこで、自分の会社が扱った口紅を使っている女性に、ふと目がとまった。二人は目があい、どちらからともなく声をかけることになる。 素敵な物語でした。メモ程度にあらすじを書きましたが、そんなのどうでもいいと思うくらい。 一卵性双生児。似すぎている二人には、自分とはなんなのかが分からなくなってしまう。ふるまいもそっくりで。相手の話を聞くと、その場でどう感じたかがわかってしまうような。私は一卵性双生児の一人として生まれたわけではないので、実感がわかりません。ただ、アイデンティティだのなんだのいう悩みごとが、まったく別のレベルの話なんだ、というところに、少しずきっとしました。 僕と水穂さんの出会いの話も、よかったです。そして、ラストがとてもよかったです。そこへ収束する物語の流れ。語彙のなさに困りますが、素敵でした。 また、近いうちに『side-B』も読もうと思います。ーーートラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。
2006.02.10
コメント(2)
-
新倉俊一訳『結婚十五の歓び』
新倉俊一訳『結婚十五の歓び』(Les Quinze Joyes de Mariage)~岩波文庫、1979年~ いつものように、内容紹介、感想の順ではなく、つらつらと書こうかと思います。本書からの引用も、内容の紹介も詳しくすることにします(自分の勉強とも関わるので、メモの意味もこめて)。 本作は、中世フランス文学です。その方面で有名な、新倉先生の訳です。本作の作者、成立年代など、不明な点も多く、定説はないようですが、解説をまとめると、成立年代は14世紀末から15世紀初頭、作者は、(田舎の)聖職者であろう、というのが有力なようです。 さて、この物語は、一言でいえば(ひどい)奥さんにふりまわされる(気の毒な)旦那さん、といったところ。 内容に入る前に、タイトルについても一言。本書の構成は、序文、第一の歓び~第十五の歓び、結論、となっているのですが、序文にこのようにあります。「我身は(中略)ついぞ結婚の経験はないものの、これを経験せる者から聞いたこと、ならびにこの目で目撃したことから察するに、結婚には十五の難儀があり、しかも、結婚をなせる人々はこれを以て歓喜、快楽、至福とみなし、無双の歓びと信じ込んでいる、と考えるにいたった。しかしながら(中略)これら結婚の十五の歓びこそは、思うに地上最大の責め苦、苦悩、悲哀、不幸で」あるというのです。作者は結婚を、魚梁(やな:川魚をとるしかけの一種)にたとえているのですが、その魚梁にひっかかった者は、苦難の状態にあってもそこから出ようとせず、歓びと考えている、というのです。だから、あえて歓びと呼ぶ、と結論で言っています。 第一の歓びは、結婚してそう年月が経っていない男性に起こります。奥さんは、豪華な服を欲しがっています。夜、床につき、夫婦の営みをしたがる旦那さんですが、奥さんは具合が悪いといいます。理由を聞いてもなかなか答えてくれません。奥さんは、旦那さんがあんまり言うから答えるけれど、と、理由をいいます。旦那に言われてお祭りに行ったけれど、自分の服装が一番みすぼらしかった。決して高い服が欲しいから言うんじゃないけれど、私がみすぼらしいと、あなたのことを思えばこそ恥ずかしいのです、と。旦那さんは、家計で手一杯なのに、なんとか服を買ってあげようと、お金に苦しむことになります。 んー、書くのに時間かかりますね。あとは流しながら書くとしましょう。 第二の歓びは、奥さんがお友達や従兄弟(それが本当に従兄弟がどうかはわからないとのこと)と祭りや巡礼に行こうとする場合。第一の歓びのように、巧みに旦那さんをいいくるめます。第三の歓びは、妊娠した場合。妻はそう具合が悪くないのにとても具合が悪いように言い、お医者さんもそのようにいいますから、旦那さんは奥さんのかわりに家事で手一杯なのに加えて、奥さんを心配するあまり食事もろくにとれなくなります。ところが、旦那さんが留守にしているあいだに、友達たちが家にやってきて、当の奥さんも一緒に食事を楽しむのです。 第四の歓びは、何人か子どもができて、適齢期になった娘たちを嫁に出す場合。結婚するとき、女性は嫁資金といって、持参金を持っていかなければなりませんでしたから、出費がかさみます。これに、旦那さんは苦労することになります。 第五の歓びは、奥さんの方が身分が高い場合。ここでも奥さんは高い晴れ着をほしがり、浮気もします。 ところで私は、小説を読むときに、面白いと思ったところ、関心をもったところに付箋をはるのですが、本書には原語や言葉を説明してくれる注もついていて、勉強につながるところにも付箋をはりました。研究室の方に付箋をはっている理由を聞かれ、そのように答えたのですが、「神かけて、ジャンヌ(使用人の名前)、この私は夫から何も買ってもらえない。あの人ときたら、本当に馬鹿だ」というところから何を学んだのかとつっこまれてしまいました。笑ってしまったから貼っていたのですが。 とまれ、この奥さんのセリフは第五の歓びに登場する方のもの。旦那さん、口答えをしようものなら、奥さんの家柄の方が立派なわけですから、その話をされてしまい、逆らうことができないのです。 第六の歓びは、好人物が、若くて邪険な妻をめとった場合。奥さんはやたらと口答えをしますが、旦那さんは彼女をいたく愛していて、できる限り機嫌をとろうとするので、大変なようです。 第七の歓びは、結婚してしばらく年月が経った場合に起こります。一般論として、若い頃はまだしも、年を経るにつれて、旦那さんの精力は衰えていきます。奥さんは浮気をし、その噂が旦那さんの耳にもはいるのですが、奥さんはうまくやりこめます。 第八の歓びは、子どもがまだ小さい場合。子育てのことで、もめるわけですね。子どもが本当は元気なのに、とても弱っているという奥さんや乳母たち。旦那さんは心配しながら、いろんな仕事をして疲れるわけですが、そんなことを言おうものなら、出産のときに自分がどれだけ弱っていたか、どれだけ聖女さまたちにお祈りしたか、あなたはもうお忘れになったのね、といわれるのです。 第九の歓びは、旦那さんが年をとったり、病気なりで弱ったりしまったとき。長男はそれなりの年齢になっていて、まるで家長のようにふるまいます。家族の誰も旦那さんをいたわらないのですね。 第十の歓びは、なんかもう離婚手前までいっている事例です。 第十一の歓びは、若い貴公子が国中をふらふらしているときに、ある娘さんを妊娠させてしまった場合。娘さんの奥さんは、なんとかその男と娘を結婚させようとします。男は男で、結婚できて大喜びなのですが、結婚後にできちゃった婚だったことがばれ、両親から嘆かれてしまう、というものです。 第十二の歓びは、めちゃくちゃ尻にしかれる場合。 第十三の歓びは、旦那さんが戦争に行き、捕虜にされるなどして、しばらく帰ってこられなくなった場合。旦那さんが妻のことを強く思っているあいだにも、奥さんは夫が死んだものとして、新しい夫を見つけ、楽しんでいるのです。 第十四の歓びは、とても気立てのよい女性と結婚したものの、妻に先立たれてしまい、邪険なバツイチ女性と再婚する場合。その女性は結婚の経験があり、旦那をどう扱うかこころえているので、しばらくは本性を見せずに、夫の性質を見抜いたあと、どんどん邪険にふるまうというのです。 第十五の歓びは、願いかなって結婚したものの、相手の女性が遊び好きで、この世の快楽をむさぼるタイプだという場合です。作者によれば、これは「地上最大かつ極度の苦しみ」です。 * 結局全部紹介してしまいました…。私が専門に勉強にしている時代よりも、成立年代はあとなのですが、興味深い一次史料ですし、細かくメモをとっても困りますまい(ほとんど遊びで書いていますが)。 以上、途中から「歓び」と書くのが痛ましいほどの物語を紹介してきましたが、新倉先生は、ここに反女性主義が見られる、と指摘しています。同時に、本書は、そんな苦しみの中に入り、それを歓びと感じている愚かな男性たちへの風刺の性格をもっているとのことです。 史料として読む場合には、こういうことも考えなければなりませんが、ここではひとまず一つの物語として楽しく読みました。旦那さん気の毒だなぁ、と思いながら。 私は古本で購入しましたが、絶版になってはいません。私が通っている大学の生協にも並んでいます。
2006.02.09
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1










