2006年08月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
8月19日は箱根→東京観光でした
8月18~20日と、箱根→東京旅行をしてきたのですが、前回の記事からずいぶん時間が経ってしまいました…。18日は箱根を観光し、箱根で一泊しました(記事はこちら)。19日。温泉宿の朝は、温泉に入らなきゃ、というんで少しのんびり入浴。朝食はバイキングでした。美味しかったです。それから、箱根湯本駅周辺でおみやげなどを見ました。あるおみやげ屋の二階が喫茶店になっていて、そこで私は和菓子とお茶をいただきました。こちらも美味でした。なんやかやとおみやげも見たあと、箱根から東京に向かいます。箱根湯本駅から新宿駅まで、ロマンスカーというのが走っています。外の景色がよく見えるように、座席が数度外側に向いていたり、いろいろ趣向を凝らした素敵な電車でした。ロマンスカーも指定席をとっていたので、のんびり旅です。そして、新宿。覚悟はしていましたが、人混みに疲れました…。ここで先輩と合流しました。まずは新宿から汐留に向かい、日テレタワーに行ってきました。一時期、「ズームイン朝」を好きで見ていたので、汐留ラーメンのことは知っていたのですが、あまりに並んでいたので食べるのは断念。前日、箱根で昼食にラーメンを食べていたので、まぁいっか、という気持ちでした。昼食をとって、宿へ。いったん荷物を置いて、また汐留に戻り、東京観光の目的地だったお台場に行ってきました。目覚ましくんをバックに記念撮影。旅行者満喫です。そのあたりで、私はもう人混みで疲れてしまい、フジテレビの建物の中までは入らず、自由の女神を見ながらのんびりしていました。しばらくして、大江戸温泉物語へ。利用者はいったん浴衣に着替え、浴衣姿でいろんな出店をまわったり、お風呂に入りに行ったりという形式でした。全員浴衣というのは、なかなか良い趣向だと思います。一緒にいた友人の受け売りですが、屋内夏祭りみたいな感じでした。足湯も試してみたのですが、楽しかったです。お台場から、宿へ。旅行二日目は、こんな感じでした。私にしては夜更かしして友人たちとお話できたのも良かったです。*最初にこの記事をアップした際、先日の8月18日の観光について書いた記事へのリンクをはり忘れたままでした。お詫びして訂正します。
2006.08.29
コメント(2)
-

島田荘司『水晶のピラミッド』
島田荘司『水晶のピラミッド』~講談社ノベルス、1994年~ 1986年、アメリカ・ルイジアナ州に、ビッチ・ポイントという岬がある。そこから日本橋と呼ばれる橋を渡ったところに、エジプト島と呼ばれる島がある。この島には、ギザのクフ王のピラミッドそっくりのピラミッドがあった。大きさは同じ。ただし、下半分は本物のように石で作られているが、上半分はガラスで作られていたのだ。 このピラミッドを舞台に、レオナ松崎主演の映画のあるシーンが撮られることになった。ピラミッドの設計者の弟、リチャード・アレクスンがレオナに出会い、その映画の話を聞いて、この場所を提供したのだった。 シーンの設定のため、激しい嵐の夜、撮影が行われた。その際、レオナは、まるでエジプトの「死者の書」に出てくるアヌビスのような、犬のような頭をした人間を目撃していた。そして翌日。水晶のピラミッドのすぐそばに建っている塔の最上階で眠ったリチャードが、なかなか部屋から出てこなかった。部屋は、内側からドアがかけられており、窓からもも出入りはできず、その部屋は密室状態だった。さらに日付が変わろうとする頃、映画スタッフの判断で部屋をあけると、リチャードが奇妙なかっこうで死んでいた。後の検死により、彼は溺死していることが分かった。塔の最上階―七階―で、密室状況の部屋の中、男が溺死していたのだ。 警察の捜査は難航し、映画撮影も停止させられた。そこでレオナは、一刻も早く事件を解決すべく、御手洗潔のもとへ解決の依頼へと訪れる。 数年ぶりの再読。いやはや、面白かったです。御手洗さんかっこいいですね。 本書は、いわゆる文明時代のエジプト、タイタニック号事件が交互に語られ、やがて現代(1986年)の事件についての描写、となるのですが、エジプトのシーンが良いです。人間の汚い面も十分に描かれているのも含めて。タイタニックは…そういえば、私は結局映画を観ていません。 最上階密室での溺死事件の謎も素敵でした。そして、本書の主題でもあるピラミッドの謎でしょうか。昔はピラミッドに関する本でけっこうテンション上がったものですが、今回はそんなでもなかったです。御手洗さんの冷静な指摘はおぼろげに覚えていて、そのせいもあったかもしれません。 どんな事件だったかも覚えていなかったのですが、読んでいるうちになんとなく思い出して、それでもやられた、という気分になれました。面白かったです。 好きなセリフがあるので、引用を。文字色は変えておきます。「われわれが知る歴史とは、たいてい時の為政者によって公認することを強制された創り話なんだ。権力者の身のまわりで起こる殺人事件なんて、歴史の流れにあってはほんの片隅の出来事でしかない。真の歴史は、民衆の営みの中にある。それらは決して、歴史書には表れることがない」(389頁)
2006.08.28
コメント(2)
-

ミシェル・パストゥロー『悪魔の布―縞模様の歴史』
ミシェル・パストゥロー(松村剛・松村恵理訳)『悪魔の布―縞模様の歴史』Michel Pastoureau, L'Etoffe du Diable : Une histoire des rayures et des tissus rayes~白水社、1993年~ 西洋中世の色彩、紋章、図像の歴史の権威ミシェル・パストゥローの多くの著作の中で、最初に邦訳が出された著書です。13世紀から現代までの縞模様の歴史を、服飾の技術の歴史などともからめながら、特にその価値体系について描いています。 簡単な目次は以下なとおり。ーーー 縞の秩序と無秩序 第一章 縞模様の衣装をつけた悪魔(13-16世紀) 第二章 横縞から縦縞へ、そして逆転(16-19世紀) 第三章 現代の縞模様(19-20世紀)ーーー はじめに、ともいうべき「縞の秩序と無秩序」のところで、パストゥローはこの本を短いものにしたいと書いています。縞模様の歴史というのは新しい領域であり、その段階では、詳細な研究よりは総括的な論の方がよいだろうというのですね。 第一章は、私の専門が中世史ということもあり、特に興味深く読みました。最近、彼の論文を何度か記事で紹介していることもあり、最初に本書を読んだときよりは、よく理解もできたように思います。 まず、カルメル会のスキャンダルについてふれられています。カルメル会は12世紀にパレスチナで誕生し、ヨーロッパにやってきて、 13世紀に托鉢修道会に分類されることになります。 托鉢修道会というのは、主に都市に住み、民衆への説教に従事した修道会です。民衆の懺悔(告解)を聞く役割も果たしたようです。 13世紀の四大托鉢修道会としてドミニコ会、フランシスコ会、聖アウグスティノ隠修士会、そしてこのカルメル会があります。 さて、どういうスキャンダルだったのか。彼らはもともとパレスチナにいたのですが、聖王ルイが十字軍からパリに戻ったとき、カルメル会修道士を連れていました。そして彼らが、縞模様の外套を着ていたことが、スキャンダルだったのです。人々は彼らに「縞の坊主」というあだ名をつけてあざ笑いました。さらに付け加えれば、当時完全に修道女になるわけではなく、俗人としての資格のまま修道的な生活を営むベギンと呼ばれる女性たちがいたのですが、カルメル会修道士はベギンの女性たちと交流があまりに密接だ、と非難されたのだとか。ベギンは私の研究とも関わってくるので、興味深かったです。 とまれ、ではなぜ縞模様が非難されたのか。教会会議では、聖職者が(縞であれ市松模様であれ)二色の衣装を着ることを禁じています。また、世俗の慣習法や規則の中で、縞模様は排斥された者たち―私生児、農奴、受刑者、ハンセン氏病患者、異端など―に着せられるように規定されています。また、文学作品の中では、不実な騎士や姦通する女、貪欲な召使いなどは縞模様の服を着ているといいます。このように、縞模様は、なんらかの理由で社会秩序の外部におかれた者たちに結びつけられていたのです。なので、東方からやってきた修道士が縞模様を着ていた、というのは、スキャンダラスなことだったのですね。 さて、本書ではその後紋章について言及されますが、そこは割愛するとして、一つの指摘を紹介しておきます。想像上の紋章の中では、先にふれたように、縞模様をもつ紋章はほとんど全て否定的です。しかし、現実には縞模様を含む紋章は無数にあり、威光を誇る紋章もあった、というのです。たとえばアラゴン王国の紋章は、赤と金の縦縞をもっていたといいます。 第二章では、中世では軽蔑的・「悪魔的な」意味をもっていた縞模様が、次第に肯定的な意味をもつ過程が論じられます。縞模様はまず、召使いの身分・従属的な役割の第一の記号になったといいます。 さらに近代には、肯定的な価値をもつ縞模様が普及します。貴族や上流階級の若者たちが着始めるというのですが、重要なのは、それが社会から除外された者たちが当時課せられていた横縞ではなく、縦縞だったということです。たとえば、16世紀のフランス王フランソワ1世、イギリス王ヘンリ8世は縦縞の服をきた姿の肖像を描かせています。 18世紀には、ロマン主義的・革命的な縞模様がはじまります。興味深かったのは、シマウマに対する評価の変化です。シマウマは、16-17世紀の学者には、危険で不完全な、あるいは不純な動物とみなしていました。しかし、18世紀のビュフォンという人物は、シマウマをもっとも調和のとれた動物の一つに数えているのです。 そして、アメリカ独立革命、フランス革命でみられる縞模様について。アメリカ国旗の紅白の縞は、自由にイメージと新思想の象徴として現れたといいます。フランス革命では革命に関するあらゆる舞台に縞の装飾なされました。三色帽章は遠くからよく見える「記章」としての役割を果たし、急速に国民軍の記章となります。また縞模様は共和制や愛国主義のイデオロギーを示すものとなり、縞模様を着ることは、そのイデオロギーに賛同することを誇示することでもあったといいます。 ところでここで興味深かったのは、フランスの赤、青、白の三色の説明として、白=国王の色、青・赤=パリの色、という説明は不十分だという指摘です。フランス革命のはるか以前から、パリは紋章的な色として赤、青を使わなくなっていたそうで、パストゥローはこの三色はアメリカ独立革命から継承したものと考えています。フランス革命がはじまる頃には、この三色が自由の色として十分認められていた、というのです。 一方、悪い意味の縞模様も存続しています。たとえば、囚人服ですね。ところで、囚人らの縞模様はアメリカから渡来したそうで、また、フランスでは徒刑囚に対して縞模様が用いられたことはなく、赤い上着を着せられていたのだそうです。 また、面白かったのが語彙について。たとえば、近代フランス語のレイエ(rayer)という動詞には、「縞をつける」という意味と、「削除する」などの意味があります。縞をつけるとは除外することであった、というのです。そして長い間、縞模様の衣装をつけた人々は社会から排除されていました。ところが、この除外は、権利や自由の喪失ではなく、一種の保護と考えられたかもしれない、といいます。中世社会が狂人や愚か者に与えた縞模様は、彼らを社会から疎外する記号でしたが、同時に悪魔などから彼らを守る柵や格子の意味をもったのではないか、というのですね。 第三章については、笑える意味で興味深い、あるいはへぇーっと思った話を紹介します。 今までに何度か記事にも書きましたが、日本でいうアクアフレッシュなど、縞模様の歯磨きがあります。フランスではシニャル社の歯磨きが有名らしいのですが、パストゥローは、なぜチューブからきれいな縞模様が出てくるのか、チューブを分解したのです。引用しましょう。「シニャルの歯磨きチューブを分解し、解体しさえした(「めちゃめちゃにした」というべきだろうか)とはいえ、あのように二色の歯磨きがどのようにチューブから出てくるのか、私にはわからなかったと告白せざるをえない。シニャルの歯磨きは、私にはその謎を完全に保持しているのである。そのほうがよいのかもしれないが」(139頁注21)。さらに次の注で、彼はこう書いています。「…この歯磨きを称える文章を書くにあたって、シニャル社は私の「スポンサー」になってはいない。しかしながら、もしも本書の出版の後、縞模様の歴史についての研究に助成金を出してくれるというのなら……」(同頁注22)。パストゥローの茶目っ気が大好きです。 それから、パストゥローのお父様はアンリ・パストゥローという方で、シュールレアリストです。ピカソとも交流があったそうです。あるときピカソと衣料店に行ったとき、ピカソは「尻に縞模様をつける」ために縞模様のズボンをほしがったが、縦縞のズボンがなかったので買わずに出てきた、というエピソードが紹介されていました。 さて、またパストゥローのお茶目な文章があります。縦縞はシルエットを細く見せる効果がありますが、「太り気味で苦しむ人のなかには、あえて横縞を着て、視覚的に太って見えるのは縞のせいであり、体のせいではないと見る者に思わせようとする者もいる。現代の微妙でひねくれた策略である」(137頁注7)。 それから、縞模様は服飾の上で男性的な含みをもち、男性の縞の装飾と女性の散らし模様の装飾とが対比される場合がある、という文脈で、しかしこのことは体系的ではない、と。「水玉や花柄の下着をつけた男性―それは違反に近いものがある―に出会うのは稀だろうが、その逆は事実ではない。なぜなら、繊細で女性的な、きれいな縞のはいったパンティやブラジャーをつけている女性はおおぜいいるからである」(92頁)。違反に近いものがある、って…。面白かったです。 そのほか、縞模様と境界の関係など、興味深い指摘も多々ありました。短く、上で紹介したような面白いエピソードも多くあり、とても読みやすい本です。 私は単行本で持っていますが、現在は新書版も出ていて、そちらの方が入手しやすいかもしれません。新書版の画像はこちら↓。
2006.08.23
コメント(0)
-

8月18日は箱根を観光しました
あいた時間を見つけてぼちぼちと、18日~20日の旅行の記録をつけておこうと思います。本当に日記ですね。 学部生の頃仙台にいたのですが、そのとき所属していたボランティアサークルの同期たちと、箱根&東京旅行に行ってきたのです。みなさまと会うのは二年ぶりで、どきどきでした。 地元の駅を始発で出発し、新幹線で神奈川県は小田原へ。ここで同期二人と合流し、箱根登山鉄道で強羅駅に向かいました。実際には、その一駅前の彫刻の森駅で降りたのですが。 箱根登山鉄道は、けっこうな勾配のところを上っていきます。途中、三度スイッチバックしました。はじめての経験ではないかと思います。 さて、彫刻の森駅の近くにある箱根・彫刻の森美術館まで行ったのですが、私ともう一人は美術館に入らず、箱根強羅公園というところへ行きました。ガイドブックによれば、1914年に開園した、フランス式の庭園です。中央の噴水あたりは洋風なのですが、割と和風のところも多かったです。 ↓箱根強羅公園の噴水の写真です。 さて、その後強羅駅でさらに一人も合流し、四人で大涌谷へ向かいました。強羅駅から早雲山まではケーブルカー、早雲山から大涌谷まではロープウェイです。私は高所恐怖症なので、ロープウェイは怖かったです…。などと言いながら、それなりに景色も見ることができました。 大涌谷に到着すると、少し遅めの昼食です。ここは黒タマゴが有名で、昼食には温泉たまごの入ったラーメンをいただきました。黒タマゴは、温泉でゆでることで、温泉の成分によって殻が黒くなるのだそうです。細かいところまでメモすればよかったのですが…。 ↓黒タマゴの写真です。 その後、きたのと同じ通路で箱根湯本駅まで戻り、ここで同期五人が集まりました。温泉街をぶらぶら歩き、予約していた宿へ。玉簾の瀧というのが有名な宿に泊まりました。温泉でのんびりまったり。 楽しい一日でした。旅行二日目、三日目は、また別の記事に書くとします。
2006.08.21
コメント(0)
-
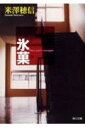
米澤穂信『氷菓』
米澤穂信『氷菓』~角川文庫、2005年(再版)~ 神山高校一年生の俺―折木奉太郎に姉から届いた手紙。それは、今年部員が入らなければ廃部になってしまう古典部に入るよう促す手紙だった。やらなくていいことはやらない、やらなければならないことは手短に、がモットーの<省エネ>志向の奉太郎だが、姉の手紙で、古典部に入ることにする。ところがその年は、彼以外にも新入部員がいた。それが、名家の令嬢千反田えるだった。奉太郎の旧友にして好敵手、福部里志も入部することになる。 千反田との出会いのときに起こった、千反田閉じこめ事件(わずか数分の間に、千反田がいた部室が何者かに鍵をかけられていた)、別の旧友であり図書当番の井原摩耶花が疑問に思った、毎週金曜日に学校史が借りられ当日返される「愛なき愛読書」事件など、身近な謎を折木はいくつか解決した。そこで、千反田に相談を持ちかけられる。33年前に古典部に所属していた千反田の伯父―関谷純から古典部の話を聞いたとき、彼女は泣いてしまったという。泣いてしまったのは覚えているが、何を聞いたのか思い出せない。自分は伯父から何を聞いたのか、考えてほしいというのだ。古典部の過去の文集など、資料を集める中で浮かび上がる、33年前に起こった事件。それがどんな事件だったのか、事件の中心人物であった関谷に何があったのか。そして、関谷が決めた古典部の文集『氷菓』のタイトルの意味は。新たに古典部に入部した井原も含め、古典部一同は謎解きに挑む。 本作は米沢さんのデビュー作です。面白かったです。 長編の中に、いくつか日常の謎系ミステリの短編が収められている構成、といえばよいでしょうか。連作短編集とはいえないと思います。 なにが面白かったといって、33年前の事件の真相解決のために、四人の部員がそれぞれ資料を集め、分析し、仮説をたて、議論します。その過程が、まさに私もしているような研究の過程なのです。それこそ、彼らは過去の事件の復元をしようとしているのですから、歴史学をしている者としては面白く読みました。…自分の研究より実りがありそうだな、と苦笑しながらですが…。 内容紹介でも少しふれましたが、千反田さんが部室に入ったときは鍵が開いていたのに、数分後に折木さんが来たときは部室に鍵がかかっていた、という事件など、日常の謎系ミステリの短編としても読める章も面白かったです。物語の流れとしては、<省エネ>志向の折木さんが、少しずつ変わっていく過程もよいですね。 本作のシリーズとして、『愚者のエンドロール』があるのだそうです。また見かけたら読んでみたいと思います。注)この記事は8月21日に書いています。
2006.08.20
コメント(2)
-

島田荘司『ら抜き言葉殺人事件』
島田荘司『ら抜き言葉殺人事件』~光文社文庫、1994年~ マンションの一室で、日本語教師にしてピアノ教師である笹森恭子が首を吊って死んでいた。笹森はまっすぐな性格で、しかし厳しく刺々しいところがあった。彼女を知る人々は、自殺するような人ではないと口をそろえて言う。 吉敷竹史は、この事件を担当することになった。 時を同じくして、別の女性が飛び降り自殺をした。二人をつなぐ人物として、笹森周辺を調べていた吉敷たちは、作家の因幡沼耕作にたどりついていた。笹森は因幡沼に対して、その作中に使われた「ら抜き言葉」に対する痛烈な批判の手紙を送り、これに対して因幡沼が反論したため、二人の中では激しいやりとりがあったのである。そして、飛び降り自殺の女性は、因幡沼の熱烈なファンだった。 その因幡沼が殺されていた。二人目の女性の死の知らせを受けた直後、吉敷たちはそれを知る。笹森が因幡沼を殺し、そのあげく自殺、女性は因幡沼の死を嘆いて自殺した、という構図が、捜査の中では一般的な構図と考えられた。 しかし、なぜ「ら抜き言葉」なのか。先のように考えられた事件の構図に釈然としない吉敷は、笹森の過去を調べていく。 吉敷さんシリーズの長編を読むのは、これで二冊目になります。御手洗さんシリーズが、多少極端に言って、風変わりな事件→御手洗さんの思考をぼかした調査の過程 →意外な真相→その真相に至る御手洗さんの思考の解説、という構造だとすれば、吉敷さんシリーズは、(風変わりな事件)→吉敷さんの思考の過程も描きながらの調査の過程 →意外な真相、という構造だといえると思います(吉敷さんシリーズは二冊しか読んでいませんが…)。いわゆる探偵役の思考を追いながら読む感覚ですね(特に何も見ずに記事を書いていますが、解説かなにかで同じようなことが書かれていればすみません。少なくとも本書の解説では、それぞれのシリーズの叙述の構造についてはふれられていないはずです)。本書には大がかりなトリックがあるわけではありませんが、まさにその思考の展開、吉敷さんの捜査の展開自体が面白いです。 そして本書の読後感ですが、気持ち悪さ、ある種のいたたまれなさが残ります。笹森さんがなぜ「ら抜き言葉」に激しいこだわりを持ち、ら抜き言葉を使う人々には生きる資格がないというくらいの勢いでそういう人々を批判するのか。一つの答えは明かされます。しかしでは、(以下反転)なぜそのきっかけとなった国語の教師は、「ら抜き言葉」にだけこだわったのか。教師としての威厳をたもつため、なんでもよかった、ということではあるのでしょう。それこそが、本書の一つの主題である権力をめぐる歪さにつながっているのだと思います(反転ここまで)。 タイトル通り、「ら抜き言葉」が一つのメインテーマであり(これはその裏にある、日本語の構造、さらには日本人の思考スタイル、権力維持のありかたにつながっていくのですが)、そのため日本語の文法について詳しくふれられています。笹森さんの感情的な意見と因幡沼さんの(比較的)冷静な意見では、やはり後者に説得力を感じるのですが、二人の議論が興味深いです。そして文法について詳しく書かれているせいで、本書を読む中で文法が気になってしまうのがトラップですね(笑)。文法の話あたりでなるたけ気にしないようにしましたが、そのあとはいつも通り文法には気にせず読みました。 本書に登場する学校は、ことなかれ主義を地で行く学校で、読んでいていらいらしました。もっとも、自分にもことなかれ主義的な考え方がないとはいえないので、そういう態勢に一方的に批判ばかりするのはフェアではありませんが、やはりいらいら…。島田さんは、そういう権力を、すごく単純明快にむかむかする存在として描いていらっしゃる気がします(御手洗さんが小馬鹿にしている警察などもそうですね)。 で、話を戻しますが、気持ち悪さ、いたたまれなさというのは、そういう、日本人のあり方の歪さが描かれているから感じるのだと思います。ら抜き言葉は、それを描くための一つの手段かなと思いました。それこそ、因幡沼先生が指摘している他の文法ミスでも、お辞儀の仕方でも、なんでもよいのだと思います。ですが、『ら抜き言葉殺人事件』というタイトルは、それだけでわくわくしますし、どうして笹森さんがそんなにら抜き言葉にこだわるのか、というのは魅力的な謎でした。 * 岡山から神奈川県小田原に向かう途中に読了しました。今日はもう眠いので、旅行のことや、東京から岡山に帰る間に読んだ米沢穂信さんの『氷菓』の感想は、また後日…。注)この記事は8月20日に書き、21日に一部修正しました。
2006.08.18
コメント(2)
-
筒井康隆『くたばれPTA』
筒井康隆『くたばれPTA』~新潮文庫、1986年~ 24編のショート・ショートが収録されています。全部は大変なので、面白かった話をいくつか紹介します。 まず、最初の「秘密兵器」。優秀ではあるものの、いまひとつ力が足りない野球部に、ソフトボール部に所属している女子が助っ人として迎えられます。彼女を男子ということにして、その高校の野球部は甲子園に勝ち抜いていく、という話。あ、これは面白い、と思って、この本を読んでいくのが楽しみになりました。 第二話の「遊歩道」も、とても短いですが怖くて面白かったです(笑えたという意味ではなく)。たとえば黒と白のタイルが交互にあって、黒のとこしか歩いちゃいけないんだ、ということは私もしたことがありますが、ただそれだけのことをネタに、こんな風なホラーができるんだなと思いました。「酔いどれの帰宅」。これは意味がわかりませんでした。もしこの記事を読んでいる方で、この話をご存じの方がいれば、教えていただきたいです…。ミステリで「読者への挑戦」というのは目にしていますが、こんな「挑戦」(?)を本で読んだのは初めてのような気がします。「落語・伝票争い」。これは笑えるという意味で面白かったです。二人の婦人がお会計のとき、自分が支払いますから、と何かと理由をつけて払おうとするのですが、最初は丁寧な口調だったのにどんどん罵倒の言葉に変わっていく、という話。罵倒の言葉が笑えました。「かゆみの限界」。これもホラーで、面白かったです。ノミの研究をしている大学院の学生のもとへ、学部時代の友人が訪れます。友人は、顔をなにかで真っ白に塗っていました。その友人は、ノミをくれ、すぐにノミを肌着につけて行く、というのです。よく見てみると、その友人の頭にはシラミがいっぱいいたのです。もっとひどいことも友人はしているのですが、その理由にもぞくぞくしました。 表題作の「くたばれPTA」は、SFまんが作家が、PTAの婦人たちにつめよられ、不健全なまんがを描くなと言われ、それに対して反論するのですが、話になりません。次元が違うのですね。次第にその漫画家には仕事の依頼がこなくなり、子どもたちにも遠ざかられていく、それならば…と行動を起こそうとする物語です。これも痛快ですね。先の「落語・伝票争い」など、本書には女性風刺の話がいくつかありますが、それについては解説で幸森さんがきれいにまとめておられます。本書は、この解説も読んでいて面白かったです。 順番は表題作より前にありますが、「猛烈社員無頼控」は豪快な話でした。なんだか痛ましいものも感じましたが。 痛ましいといえば、「最後のクリスマス」も痛ましかったです。タイトルからして悲しいお話だろうと察しましたが、思わぬかたちで放射能の後遺症をからめて描かれていて、印象的でした。 * 全体的に、面白かったです。あまりショート・ショートは読まないのですが、良いですね。 仙台のサークルの同期生との旅行に向かう電車の中で読みました。また旅行の話も記事に書きたいと思います。注)この記事は8月20日に書いています。
2006.08.18
コメント(0)
-

加納朋子(文)/鈴木健(絵)『ななつのこものがたり』
加納朋子(文)/鈴木健(絵)『ななつのこものがたり』~東京創元社、2005年~ 加納朋子さんのデビュー作『ななつのこ』の主人公、入江駒子さんが、はじめてファンレターを出した相手、佐伯綾乃さん。佐伯さんの作品のタイトルが、『ななつのこ』です。加納さんの作品は、作中作の『ななつのこ』という短編集とリンクした、日常の中の謎を描いた作品です。 『ななつのこものがたり』は、作中作の『ななつのこ』を絵本にしたものです。それぞれのお話自体は、加納さんの『ななつのこ』で紹介されています。この絵本は、全部で七つのお話を、お母さんが子どものはやてくんに聞かせてあげる、という構成になっています。物語の主人公の名前も、はやてくんです。 今回は内容紹介は書かなくてもいいかな、と思っていたのですが、簡単に謎の部分を。 「すいかの涙」 はやてくんの家の庭に、すいか泥棒が入っていました。はやてくんは、自分が夜に見張りをする、と言いだし、一晩中番をしました。それでも翌日になると、すいかが盗まれているのが分かったのです。 悔しくなったはやてくんが家を飛び出し、めちゃくちゃに走っていると、白い建物がありました。その中には、あやめ色のカーディガンを着た女性がいました。だからはやてくんは、彼女にあやめさんというあだ名をつけました。はやてくんをみたあやめさんは、どうしたの、と声をかけてくれました。それではやてくんは、出来事を話したのです。あやめさんは話を聞いて、出来事の真相と、一つの解決策を示してくれます。 「金色のねずみ」 はやてくんが住む村のお寺には、こんじきねずみという宝が伝わっていました。夜になるとそのねずみが動き出す、という言い伝えもありました。はやてくんは、本当かどうか確認しようとします。そして、ある夜、ねずみが置いてあった場所にないことが分かったのでした。 「空の青」 夏休みの宿題を、友達の家にしにいったはやてくん。友達もおおぜい集まっていて、絵の宿題を終わらせるつもりでした。ところが、みんなの絵の具の中から、青い絵の具だけがなくなってしまったのです。 「水色のチョウ」標本として、水色のチョウを作ってきた友達がいました。みんなが<水色アゲハ>と呼ぶようになったそのチョウを、はやてくんは自分もつかまえたいとがんばります。そして森の中で、はやてくんはついに<水色アゲハ>を見つけたのでした。 「竹やぶ焼けた」 和歌友達だった、おじいさんとおばあさんがいました。ある日おじいさんは、おばあさんに抱いていた恋心を、和歌によんで送りました。しかし、それに対するおばあさんからの返事がなかったらしく、おじいさんは悲しそうでした。はやてくんがこのことをあやめさんに話すと、あやめさんは、話してもいないおばあさんの背の高さを言い当てたのです。 「ななつのこ」こんじきねずみの事件の後、お寺には三匹のねこが住むようになったのですが、その中のシロが七匹子どもを生みました。七匹の子ねこは、それぞれ村の人にもらわれていったのですが、翌日、子ねこをもらった全ての家から、子ねこがいなくなっていたのです。 「あした咲く花」 はやてくんは、あやめさんにお父さんから聞いた話をします。お父さんが子どもの頃、お父さんはおもちゃの拳銃をもっていました。お友達が、海賊ごっこをするとき、宝箱の中にその拳銃もいれようと提案しました。ところが、そのお友達は宝箱を隠しに行ってから帰ってこず、それからすぐに引っ越してしまったのでした。 あやめさんは体が弱くて、はやてくんが訪れたときも、体を起こすことができない方です。だから、はやてくんから話を聞くのを楽しみにしているのでした。 菊池さんの絵も加納さんの文章もとても優しくて、本当に素敵な絵本でした。 なかなか眠ろうとしないはやてくんに、お母さんは一晩ごとに、物語の中のはやてくんの話を聞かせます。だから、ときどきはやてくんへの呼びかけの言葉もあって、そちらも良かったです。お母さんは「きみ」と呼びかけるので、なんだか不思議な感じになります。明日から旅行に出る都合もあり、今日は明るいうちに最後の二話を読んでしまいましたが、やっぱり寝る前に一話ずつ読むのが良いですね(昨夜までそうしていました)。 読み終わってしまうのがもったいないと思えるくらい素敵でした。これからも、疲れたときなど、読み返していこうと思います。(追記) いったん記事を書いてから、思っていたのに書いてないことがあったと思い返したのですが、さらに考えて、思うところがありました。一応、文字色を変えておきます。 回文の話が出るときに、お母さんの名前も回文になっていることが明かされます。そして最後に、はやてくんに聞かせていたお話が、お母さんの大好きな本に載っているお話ということも明かされます。そうすると…。このお母さんは駒子さんなのかな、と思ったのでした(本を読むときはほとんど何も考えないので、読み終わってしばらくしてから思い至りました)。そしてそう思ってみると、物語がずっとずっと深く感じられるのでした。 素敵な本です。大切にしたいです。
2006.08.17
コメント(0)
-

森博嗣『探偵伯爵と僕』
森博嗣『探偵伯爵と僕』~講談社、2004年~ ある日、公園で出会った一人の男性。夏というのに背広を着てネクタイをしめ、ブランコに乗った怪しい人物。彼が、探偵伯爵だった。 僕は、小学生。その出会いから、伯爵と出会っては話すようになっていた。 僕は伯爵から、過去に解決したという事件をいくつかクイズ形式で出してもらっていた。銀行から金塊が奪われたという事件、人質が密室状態で見つかったという事件…。 密室事件のクイズについて考えている頃、僕の身近で事件が起こる。夏祭りの準備の日に会っていた友人が、その日から行方不明になっていたのだった。 僕がそのことについて伯爵に話すと、伯爵は事件の捜査に乗り出した。僕も、助手として動くことになる。 おおまかなあらすじはこんなところです。伯爵の秘書のチャフラさんと伯爵の掛け合いや、僕が巻き込まれるスリリングな光景など、印象に残るシーンも多いです。 本筋に入る前―導入というか、横書きで、僕の考えと、それに対する伯爵の言葉があるのですが、その時点でこれは面白いと思いました。 それから、僕の一人称の形式で物語が進みますが、そこに描かれている価値観など、興味深く読みました。印象に残っているのは、怪獣映画の怪獣について。怪獣は悪いことをしようと思って街を壊すのではない、動物なのだから遊んでいるだけ。だから、すぐに殺したりするのではなくて、怪獣が楽しめるような場所を提供してあげればよいではないか―というんですね。 同じく、虫を殺しても罪悪感はないのに、なぜ犬や猫を殺したり傷つけたりするとかわいそうと言われるのか(思ってしまうのか)。本書の中でも決定的な答えが出されているわけではないですが、考えるきっかけになります。ときどき考えることではあっても、そういうテーマについて四六時中考えているわけではありませんから。 死刑のことについても、考えさせられました。そして、事件が終わりを迎えるところでは、あるいは事件の背景が語られるところでは、もう涙でした。 僕は、いわば伯爵に対するつっこみ役的なところがあって、二人の掛け合いはとても面白いです。笑えるし、そして泣けたし。とにかく、読んでいて飽きませんでした。 細かく読んでいたら、ラストの手紙の意味も分かるのかもしれませんが、ラストは、私にはよく分かりませんでした。ですが、それはともかく、とても面白い物語でした。「かつて子どもだったあなたと少年少女のためのミステリーランド」のシリーズの一冊です。このシリーズは高いからと、手に取らずにいたのですが、今回読んでとても良かったです。素敵な読書体験でした。
2006.08.17
コメント(0)
-

佐飛通俊『アインシュタイン・ゲーム』
佐飛通俊『アインシュタイン・ゲーム』~講談社ノベルス、2006年~ 1922年、来日していたアインシュタイン博士は、奈良県のある村で、事件に遭遇する。道に迷ってしまった博士のもとへ駆けつけてきた、言葉が話せない男。男は、博士を蔵の前に連れて行き、鍵がかかっていることを示した。そこへ出てきた、男の家族。家族が蔵を開けると、そこには男が倒れていた。事態をさとり、、博士が警察を呼びに出た。警察とともに博士が蔵に戻ると、男が血まみれの斧を持っていた。蔵にはばらばらの死体があった。 * ザナドゥ鈴木は、1922年にアインシュタインが遭遇した事件について、真相を文章にするつもりでいた。自殺した男を、言葉の話せない男―被害者の召使い―が恨みにまかせてばらばらにしたと思われたが、博士が、「あれは自殺ではない」というメモを残していたのである。 一方、依頼を受け、相対性理論によって若返ろうという怪しげなセミナーに参加する。そこに居合わせた団体職員の白冷とともに、ザナドゥはいんちきを暴露する。いんちき主催者の一人―南無井新二とともに、三人で酒を飲むことになるが、新二に飲み逃げされる。 後日、奇人として有名な新二の父親、存在が新理論を発表するということで、南無井家が経営する旅館でパーティーが開催される。存在と、その二人の子どもたちはいがみあっており、その機会に存在の遺言が発表された。遺言の発表に居合わせなかった存在は、殺されていた。遺言発表の場であったコロシアムにつらなる二つの塔。塔の上の部屋に存在はこもったのだが、一度女性が確認したときには、そこには死体はなかった。しかしその後、ザナドゥたちが部屋を確認したときには、絞殺された存在の死体があったのだった。 いやはや、どうにも疲れがたまっているようで、ずいぶん昼寝しながら読んだのもあり、ぱっとしなかったというのが感想です。ミステリとしては面白いかもしれませんが、別段目新しさはありませんし(存在殺人の真相はたしかに面白いと思いましたが)、著者の言葉で、「笑い」がコンセプトとしてあげられていますけれども、残念ながらそんなに笑えませんでしたし。笑わせようと思われるくだりが、むしろ歪でした。同じくメフィスト賞作家の石崎幸二さんの方がはるかに面白いと思います(謎解きの過程も笑いの要素も)。石崎さんが、しばらく作品を出してないのが残念ですが…。 表紙は、ポップな感じを出そうとしていながら基本的に歪で不気味だと感じますが、本作の感想もそんなところです。残念でした。
2006.08.13
コメント(0)
-

真梨幸子『女ともだち』
真梨幸子『女ともだち』~講談社、2006年~ 20階建ての大型マンションで、殺人事件が起こった。二階の独身女性―吉崎満紀子は、性器とともに子宮を持ち去られていた。二十階の女性―田宮瑤子は、その満紀子の血液が付着したナイフで死んでいた。 満紀子は、売春で有名だった。彼女と関係をもっていた男性が逮捕され、裁判が開かれる。しかし、男の逮捕に疑問を抱いたフリーライター、楢本野江は、独自に調査を進めた。 被告人、山口啓太朗。エリートコースを進んでいた彼は、結婚後家庭内暴力などを起こし、離婚。仕事の方もうまくいかなくなっていた。 被害者、吉崎満紀子。負けず嫌いで、正直なところが強く、売春をする姿はどこかいびつで、普段の性格とのギャップがあった。 被害者、田宮瑤子。スキャンダルに彩られた満紀子とは対照的で、大衆の関心はあまりひかなかったが、彼女にも暗い過去があった。 検察側は、山口が二人を殺した、と主張した。非常階段の入り口の問題など、検察の主張に矛盾を見いだす野江は、記事で検察側をひどく攻撃した。しかし、やがて自分も過ちを犯していたことを知り、あらためて事件を見直していく。 描かれているのは、とにかくどろどろした人間像。嫌なリアリティがありました。「ブラディータワー」と形容されるマンションの近くに、そこよりも低価格で好条件のマンションが建つ。それを受けて、タワー最上階の値段も、当初の半額に。瑤子さんは、半額でそこを買ったのですが、小さなことでも住人たちから嫌がらせを受けることになります。瑤子さんの人柄から、次第に彼女に好印象を抱く住人もできますが。 幼少期の田宮さんについての描写は、嫌な気分にしかなりませんでした。 劇団員のファンとして、お金を注ぎ込む満紀子さん。そのために売春をしたり、下着を売ったりするわけですが、痛ましさを感じました。 というんで、どろどろ重たい気分になるものの、ミステリとしては割とオーソドックスで、わくわくしながら読みました。被告人山口氏と、満紀子さんには関係がありましたが、山口氏と田宮さんにはまったく接点がありません。検察官の主張の矛盾を崩していく楢本さんの記事や、その取材活動は、だからとても面白かったです。第二章で登場する老婆。老婆は、住民から何度苦情を受けてもマンションの緑地に石を積み上げるのですが、その理由として口にする言葉が意味深で、それもずっと気になったままの読書でした。 前作『えんじ色心中』は、ラストでなにがなんだか分からなくなってしまいましたが、本作は割とわかりやすく ―というか、前作の印象が残っていた分、安心した気分で読了しました。 どろどろした部分も含め、面白かったです。ーーー 最近夏バテ気味で、今日も研究がまったく手につかなかったため、読書を進めることにしました。しばらく暑さも続くようですし、体調管理に気をつけなくては、とあらためて思います。生活リズムは整っているつもりですが、夏バテの心当たりもいくつかありまして…。
2006.08.10
コメント(0)
-

浦賀和宏『八木剛士 史上最大の事件』
浦賀和宏『八木剛士 史上最大の事件』~講談社ノベルス、2006年~ 松浦純菜・八木剛士シリーズ第四作。あらすじはなんとも書きにくいのですが…。 以下、ざーっと話をなぞるので、先入観なしに本書を読みたい方はご注意ください。 河野くんがDVDを買ったので、いつもの四人―河野、松浦、小野、八木―で観よう、という話になります。しかし、八木さんは興味がなく、いろいろ考えたあげく、約束をすっぽかすのです。そんな八木さんに、松浦さんから電話。その後、思いがけないことに、松浦さんが八木さんのところに遊びにくるのです。自分のお気に入りのDVDを持って。二人は、楽しく時間を過ごしますが、八木さんは松浦さんに嫌われているのではないかと、不安で不安で仕方ない。そしてついに、自分の気持ちが伝わるような発言をするのです。 その夜、八木さんは松浦さんを彼女の家まで送ります。ところが帰り道、八木さんをいじめる人たちと出くわします。さんざん悪口を言われますが、松浦さんは彼らに言い返します。その後、彼らとは別にちょっとしたアクシデントがあるのですが、それを見ていた彼らは、二人に中傷の言葉を浴びせるのです。 数日後、八木さんはクラスで、これまでにないほどのいじめを受けます。その日、松浦さんからかかってきた電話。彼女は意を決して、ある提案を八木さんにもちかけるのでした。八木さんは、とても喜びます。松浦さんも、八木さんに同意してもらって、嬉しそうです。しかし―。 本書の中でも、八木さんは妹のお見舞いに行くのですが、そこで、以前彼と妹を撃ったあの外国人が現れます。スナイパーは八木さんを狙いますが、ここでも八木さんには銃弾一つも当たりませんでした。 松浦さんとの約束の当日。待ち合わせの少し前。瀧先生から電話がかかってきます。スナイパーに、人質にされているというのでした。そして、ガールフレンドの命が危ない、と八木さんに伝るのです。 まず、あれ、目次がないな、と思いました。章題も、「一週間前」「三日前」という感じ。最後の方は、「六時間前」「三時間前」といった感じで、どんどん気を引きつけられます。本当にわくわくしながら読みました。それはひどいいじめの描写もあり、不快な気分にもなりますが、いったい「史上最大の事件」とはなんなのか、気になってたまらないのです。どんなオチになるのか、と。 …気の毒でした。そうとうテンション下がりますね。 他のことについてもいくつかふれておきましょう。 前作で、ちょっとした伏線が描かれていましたが、それがどうつながってきているのか、まだはっきりとは明かされていない感じです。本書の中でも、「私」の一人称によるパートがあるのですが、その「私」が「八木剛士」とどういう関係があるのか、やはりよく分かりませんでした。 面白かったのは、南部さんが松本楽太郎を読んでいることですね(松本さんは、前作『上手なミステリの書き方教えます』に登場する作家です)。 とまれ、楽しい読書体験でした。わくわくしながら読めるのって素敵なことだと思います。
2006.08.10
コメント(2)
-
ミシェル・パストゥロー「中世紋章の軽蔑的な色と形」
Michel Pastoureau, "Figures et Couleurs Pejoratives en Heraldique Medievale"dans Michel Pastoureau, Figures et Couleurs, Paris, 1986, pp. 193-207 ミシェル・パストゥロー「中世紋章の軽蔑的な色と形」を読了。史料の種類、中世紋章の中の軽蔑的な色と形の紹介、そして研究の手続きが紹介されるという構成で、方法論を提示してくれる論文です。 以下、小見出しに沿って紹介を。1.資料体 この研究では、「悪い」人間に与えられたおよそ300の紋章が史料となります。これらの紋章の出所として、(1)文学テクスト(武勲詩など)、歴史・叙述テクスト、(2)図像資料、(3)特定の紋章(サラディンなどの)が区分されています。 そして、「悪い」人間の類型化が紹介されます。(a)サタン、反キリストなど、(b)人物化された悪徳、(c)悪評高い聖書の人物、古代あるいは初期中世の人物、 (d)異国の王や人間(想像の人物も)、(e)ユダヤ人、(f)キリスト教と戦う王や君主(イスラーム)、(g)騎士道物語の人物(不実な騎士など)、です。2.要素a)盾の形 紋章は主に盾に描かれたのですが、盾の形をもたない紋章もある、それには意味がある、ということです。たとえば、外周が丸いものは軽蔑的であり、イスラームや東方の王には丸い盾があてられたとか。b)色 この節が一番面白かったです。紋章の中の主要な七色は、金、銀、赤、黒、青、緑、紫。この中で、銀だけは軽蔑的な意味をもたなかったそうです。このうち、特に軽蔑的な色は赤と黒ですが、この二色に対する態度は時代によって変わります。赤が次第に悪く見られないようになり、逆に中世末期になると、黒はつねに赤よりも悪い、というんですね。 他の色について。金色は黄色としてみなされ、価値が落ちていきます。これは、貪欲、裏切り、ユダヤ人を示します。 緑は、イスラームにわりあてられるときなどは軽蔑的な意味をもちますが、それは例外的で、特に宮廷文学の中ではいつも良い色であるとか。若さ、愛、喜びなどを示します。ところで緑は、想像の紋章のうち18%、現実の紋章のうち2%を占めるそうです。 一方青は、想像の紋章のうち15%、現実の紋章のうち23%で、緑と逆の現象が認められます。青は中立的に用いられ、良い青は誠実さを示し、悪い青は喪の感情を示すそうです。 紫は、紋章のなかできわめてまれだそうです。その希少さこそに意味があり、外国人の盾に紫が用いられたとか。c)形 軽蔑的な役割を果たす形は多いのですが、一番多いのは動物の図像です。その中でもっとも悪いとされたのがレオパール(豹)。これについては、先日紹介した「動物の王は何か」でふれましたので割愛します。その他、悪、サタンなどのアトリビュート[象徴的な持ち物]とされたのが、蛇、蛙、猿、猫などなどで、多く列挙されています。 植物(野菜)の中で軽蔑的な意味をもつのは、りんごしか確認できないそうです。これも、原罪でのりんごの役割のため、軽蔑的な意味を持たせたにすぎない、といいます(ラテン語名も原因にあげられていますが、ここでは省略します)。 続いて、身近なもの。斧や短刀など刃物、鈴や鐘など「騒々しい」ものが軽蔑的な意味をもつといいます。 そして、幾何学模様について。等間隔の仕切りや交互に配置される色は、常に悪い意味を示したといいます(市松模様、等色二分など)。こうした面の地ではなく、その上に描かれる「可動図形」の中で悪い意味をもつのは、星と月。星は東方を、月はイスラームを示しました。 また、黒人、老人なども、こうした機能をもったそうです。d)紋章の構成 無地(=単色)が、軽蔑的な意味を示すもっとも単純な方法だったといいます。先述の色の話とも関係しますが、特に赤一色と黒一色が軽蔑的な意味を示したそうです。過剰に色を使うのも同じ意味をもったとか。 また、歯や角を強調したり、巨大に描かれたりした姿は好意的でない意味を示したそうです。 兜飾りについての言及も面白かったです。現実の紋章では、盾の中に描けなかったものを、兜飾りの中で示した。つまり、兜飾りは「安全弁」の役割を果たした、というのですね。ところが、想像の紋章(文学作品内など)では、この安全弁の機能は必要なかったということです。3.手続き 研究上の手続きが(a)~(g)まで紹介されますがここでは省略します。おおむね、これまで述べてきたことの整理です。最後の、(g)「聴覚的に好意的でない印象を引き起こすために、言葉あるいは表現の響きに頼ること」というのが面白かったです。これは、文学にみられる想像の紋章に固有の領域です。視覚ではなく、聴覚が問題となるのですね。ーーー どういう図形や色が軽蔑的な意味をもった、という羅列がメインなので、それ自体は興味深いのですが、そこから広がっていきにくい(というか、広げていない)という感じがしました。ですが、最後に紹介されている、「聴覚」の問題は興味深かったです。この紹介の冒頭でも書きましたが、方法論の提示ですので、示唆に富む論文だといえると思います。
2006.08.08
コメント(2)
-
ミシェル・パストゥロー『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』
Michel Pastoureau, Figures et Couleurs : Etude sur la symbolique et la sensibilite medievales, Paris, 1986 ミシェル・パストゥローによる論文集『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』(訳は、『王を殺した豚 王が愛した象』の、松村剛先生による訳者解説から)に収録された論文について、これまで紹介の記事を書いています。この記事は、この書物の目次と、それらの紹介の記事へのリンクの意味のための意味もあって作っています。 既訳論文については、そのタイトルの試訳も示した上で、紹介の記事にリンクしています。(もともと、既読論文へのリンクのみ書いていましたが、未読論文の原語タイトルも加え、目次だけでも全体を示そうと思います)。ーーーAvant-proposReference des articles reproduits<人間と色>(L'Homme et les Couleurs)・「次に青がきた」(Et puis vint le bleu)・「無秩序の色と形:黄と緑」(Formes et couleurs du desordre : la jaune avec le vert)・「中世の色:価値体系と感性の様式」(Les couleurs medievales : systemes de valeur et modes de sensibilite)・「色彩、装飾、紋章」(Couleurs, decors, emblemes)<紋章と社会>(Emblematique et Societe)・「国家とその紋章のイメージ」(L'Etat et son image emblematique)・「中世の印章」(Le sceau medieval)・「紋章の普及と紋章学の起源」(La diffusion des armoiries et les debuts de l'heraldique)・「紋章の図像」(L'image heraldique)・「『紋章は衰え、標章は栄える』標章の起源に関する覚え書き」(Arma senescunt, insignia florescunt. Note sur les origines de l'embleme)・Du masuque au totem : le cimier heraldique et la mythologie de la parente <印と空想>(Les Signes et les Songes)・「動物の王は何か」(Quel est le roi des animaux)・「アルテュール、ランスロ、ペルスヴァル、その他の英雄」(Arthur, Lancelot, Parceval et les autres)・「アーサー王物語の紋章―ノルマンディ地方の紋章か?」(L'heraldique arthurienne : une heraldique normande?)・「中世紋章の軽蔑的な色と形」(Figures et couleurs pejoratives en heraldique medievale)・Soleil noir et flammes de sable. Contribution a l'heraldique nervalienne : El Desdichado・「緑色の側と灰色の側―国立図書館に座り、仕事し、読書し、書き、眠り、夢を見、愛したことを思い出す」(Cote vert et cote gris. S'asseoir a la Bibliotheque nationale, travaillier, lire, ecrire, dormir, rever, se souvenir d'avoir aime)Table des matieresーーー 本書の体裁上の特徴を一点、指摘しておきます。それは、収録されている諸論文が、初出の形のまま掲載されているということです。たとえば、1頁に1コラム(普通の体裁)の論文もあれば、2コラムに分かれた論文もあり、註の形式にしても、脚注の形にしている論文もあれば、末尾にまとめて掲載している論文もあり…。フォントサイズもばらばらです。このあたり、整理していれば、本全体としても見やすいのに、と感じます。*なお、この点は、3年後に出版された『色彩・図像・象徴―歴史人類学研究』(Couleurs, Images, Symboles. Etudes d'histoire et d'anthropologie, Paris, Le Leopard d'Or, 1989)では、改善されています。
2006.08.06
コメント(0)
-
ミシェル・パストゥロー「動物の王は何か?」
Michel Pastoureau, "Quel est le Roi des Animaux?"dans Michel Pastoureau, Figures et Couleurs : Etude sur la symbolique et la sensibilite medievales, Paris, 1986, pp. 159-175 ミシェル・パストゥローの論文集『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』所収の論文「動物の王は何か?」を読了。仏語のゼミで最初に読んだテキストで、思い入れがあります。数年ぶりに再読。 ここでは、三つの動物―ライオン、熊、鷲が、歴史的にどういう位置にあったかが示されています。 以下、小見出しに沿って紹介していきます。 ライオンの前進 ライオンは、中世の紋章の中でもっとも頻繁に現れる図像でした。紋章の中の15%を占めるそうです。その次の動物は鷲ですが、その割合は3%です。 地理的には、フランドル地方、低地地方に多く、山がちの地域では少ないとのこと。 年代的にはどうか。古代や初期中世にライオンの人気は見られますが、鷲やイノシシもまた人気でした。 6-11世紀には、ライオンは少し後退します。そして11世紀半ばから12世紀初頭、ライオンは図像や文学の中で急増することになります。これについては、十字軍の役割が指摘されています。十字軍によってスペインや東方から織物や美術品がもたらされることになりますが、そこにはしばしばライオンが描かれていたというのですね。ともあれ、このライオンの急増の時期が、紋章の誕生の時期にもあたります。ライオンが描かれた盾は、キリスト教騎士の典型的な盾となるのです。なお、ゲルマン地域ではライオンの急増への抵抗がみられ、ここではイノシシが英雄のアトリビュート[象徴的な持ち物、しるし]となるそうです。 悪いライオンの存続:レオパール(豹) 中世の象徴の中では、全ての動物は両義的である―ということで、ライオンにも二面性があります。たとえば聖書の中では、ライオンはキリストであると同時に反キリストでもあるというのです。 11世紀から良いライオンが急増する一方、悪い側面を引き受けるライオンが作られます。これがレオパール(豹)ですが、現実の豹とは無関係だといいます。とまれ、ライオンの悪い面がレオパールに引き受けられることで、ライオンは決定的に動物の王となるのです。 さて、面白いエピソードが紹介されているので、ここでも紹介します。イギリスの王に、リチャード獅子心王という人がいました。彼の盾には、三匹のレオパールが描かれていました(なお、紋章では、レオパールは顔は正面で体が横向き、ライオンは横顔でされます)。ところが紋章官は、「レオパール(豹)」という言葉を使うのを避け、「正面向きの頭を持つ歩行姿のライオン」という言葉を使うようにしました。百年戦争のときには、フランスの紋章官たちはイギリスの「レオパール(豹)」を、悪いライオン、私生児だ、といって軽蔑したとか。それでもイギリスでは、結局デザインを変えることなく、自分たちの紋章を呼ぶのにレオパールではなくライオンという言葉を使うようになり、今日まで続いているとのことです。 熊の価値の低下 古くから、熊は北半球で崇拝されていました。熊は、口頭伝承の動物であるとここでは言われています。熊は、野蛮な人間であると同時に、森の王、動物の王でした。ところが、キリスト教の影響により、熊は次第にその地位を低下させます。悪魔的な存在、暴力的で悪意をもち、淫乱で愚かな動物だとされるのです。 熊は、紋章の中では非常に少なく、パストゥローによれば1000のうちの5つもないそうです。ところが、人名や地名など、固有名詞には多く認められるといいます。たとえば、アーサー王の名前は、熊を意味するケルト系の言葉がもとだそうですが、しかしアーサー王は決してその紋章として熊を持たないのだとか。 紋章体系ができる時代に、熊は動物の王であるのをやめ、ライオンが動物の王になった、ということです。 ここでも面白いエピソードが紹介されています。1140年頃から1170年の間に、ザクセンのハインリヒ獅子公(Henri le Lion)と、ブランデンブルク辺境伯アルベルト熊伯(Albert l'Ours)が対立していたのですが、前者が勝利します。これ以後、ドイツの王家は「熊」というあだ名を持たなくなったというのですね。時代的にも、紋章の上でライオンが熊に勝つ時期です。面白い話もあるものだと思いました。 最後に紹介される(王立)動物園について話も興味深かったです。12-13世紀、動物園は熊の収容をやめて、ライオンを集めるようになるそうです。一方、熊は大道芸人やジョングルールの動物となり、見せ物、「サーカス」の動物となるといいます。 ここで、ライオンと熊について整理すると、ライオンはローマ的、キリスト教的な動物。熊は、ゲルマン的な動物です。したがって、熊に対するライオンの勝利は、ゲルマン的感性に対するローマ的感性の勝利、「野蛮な」ヨーロッパに対する「キリスト教的な」ヨーロッパの勝利、だとパストゥローは述べています。 鷲の問題 ところで、12世紀から鷲がライオンと対立するようになります。カール大帝は、エックス・ラ・シャペルの宮殿の頂に鷲を置かせたそうですし、神聖ローマ帝国シュタウフェン朝のフリードリヒ・バルバロッサは、その軍旗や盾に鷲を用います。鷲は皇帝の動物、ライオンはその対立者の動物なのです。14世紀半ばまで、鷲が多く認められる地域には、ライオンが少なく、その逆も認められるとも指摘されています。 15世紀の著述家は、鷲は鳥の王であるだけでなく、全ての動物の王であると書いているそうです。また、鷲は、ライオンに比べ、ゲルマン的な感性と衝突しませんでした。熊のかわりに鷲を用いることは、熊のかわりにライオンを用いるよりも受け入れられたというのです。 こうして、パストゥローは次のように結論します。「熊は、動物の長にすぎなかった。ライオンは王となった。しかしライオンは、王の中の王である鷲の前で、その道を譲らなければならなかった」(p. 168)ーーー 面白く読みましたが、引っかかった部分があります。熊に対するライオンの勝利が、ゲルマン的感性に対するキリスト教的な感性の勝利と説明されていますが、ではなぜそれが11-12世紀、紋章体系ができてくる時期に起こったのか。短い論文ですから仕方ないかもしれませんが、いささか説明不足かと。 なお、最後には、良い/悪い、知的な強さ/肉体的な強さ、という二つの軸による、動物チャートが作られていて、こちらも興味深かったです。(参考文献)・ミシェル・パストゥロー(松村剛監修)『紋章の歴史-ヨーロッパの色とかたち』創元社、1997年・ミシェル・パストゥロー(松村恵理・松村剛訳)『王を殺した豚 王が愛した象-歴史に名高い動物たち-』筑摩書房、2003年・アラン・ブーロー(松村剛訳)『鷲の紋章学―カール大帝からヒトラーまで』平凡社、1994年
2006.08.06
コメント(0)
-

たかの宗美『まりといっしょ』
たかの宗美『まりといっしょ』~宙出版、2005年~ 主人公は、西洋メルヘン雑貨店のオーナー<人形の夢>にして唯一の店員さんである、美幸さん。そして、ペットの柴犬・通称まり(本名マリアテーゼ)です。最初は番犬には心許なかったまりですが、いまでは立派に番犬の役目や商売のために美幸さんのフォローをしたりとしています。 美幸さんは、西洋メルヘン大好きですが、実はとても和風のことを好みます。結婚式には十二単を着たいとか、クリスマスツリーに書いた願い事は無病息災…。外見もメルヘンチックですが、とても現実的な一面も。 そして、美幸さんのお店の隣で喫茶店を営むキリタさん(もうお店の名前なのか彼の名前なのか…)。キリタさんは、毎日美幸さんとまりに昼食とおやつを届けています。どこか美幸さんに恋心を抱いているようですが、ツッコミ役ですね。 たかのさんのマンガは好きで、『有閑みわさん』『派遣戦士山田のり子』『夏乃ごーいんぐ!』などなど読んできています。その中でうすうす気づいていましたが、たかのさんはあまり登場人物に名前をつけません。このマンガでも、人物紹介があるのですが、美幸さんについて、「名字がまだない…」と書いてあるのにスゴイと思いました。キリタさんなど、「名前がまだない…」です。だから先にキリタさんの紹介を書いたとき、かっこで注意書きをつけたのです。お店の名前が、喫茶「キリタ」なのです。 ほのぼの面白い4コマ漫画です。のんびりできました。
2006.08.04
コメント(0)
-

二宮宏之『マルク・ブロックを読む』
二宮宏之『マルク・ブロックを読む』~岩波書店、2005年~ 20世紀後半の歴史学会に大きなインパクトを与えたアナール学派第一世代、その名の由来である雑誌『アナール』の創始者の一人であるマルク・ブロックについて、(1)その生涯を歴史的に位置づけ、(2)その著作についての二宮さんの読み方を示す本です。 1998年に行われた講演がもとになっています(岩波セミナーブックスの中の一冊です)。 本書の構成は以下の通りです。ーーー第一講 時代に立ち向かうブロック 一 ブロックとの出会い 二 過去の重荷 三 歴史家ブロック 四 試煉のとき第二講 学問史のなかのブロック 一 新しい学問の胎動 二 『アナール』誌創刊 三 三位一体―ベール・フェーヴル・ブロック 四 『封建社会』の構想へ第三講 作品の仕組みを読む 一 三つの主著1 『王の奇跡』 二 三つの主著2 『フランス農村史の基本性格』第四講 作品の仕組みを読む(つづき) 一 三つの主著3 『封建社会』 二 歴史家の仕事―『歴史のための弁明』第五講 生きられた歴史注あとがき略年譜・関連地図図版出典一覧主要著作・参考文献ーーー 上で、ブロックの生涯の位置づけと書きましたが、これは二つの面から述べられます。一つは、第二講にあるように歴史学の歴史の中で、ブロックがどのように位置づけられるか。第二に、第一講と第五講でなされるのですが、ユダヤ系の家庭に生まれ、フランス人として二つの世界大戦を経験した歴史家としての生涯の位置づけです。 先に、マルク・ブロックの生涯を本書に沿って簡単に整理します。 マルク・ブロックは1886年、リヨンに生まれます。父のギュスターヴ・ブロックは古代ローマ史の専門家で、リヨン大学、パリの高等師範大学、ソルボンヌ大学の教授を歴任した人物です。さらにさかのぼり、マルク・ブロックの男系の祖先は高祖父のバンジャマン・ブロックまでさかのぼれるといいます。そして、その子でありマルクの曾祖父であるガブリエル。彼らはユダヤ教徒でしたが、1791年の「ユダヤ人解放令」で、フランス市民権が与えられることになります。 マルク・ブロックは名門校で学び、第一次世界大戦に従軍した後、戦後ストラスブール大学の一員となります。『王の奇跡』などを執筆し、後にソルボンヌ大学に移ります。 そして第二次世界大戦。フランスはドイツに敗北し、ブロックはユダヤ系だったために「ユダヤ人公職追放令」にひっかかります。結局、フランス国家への貢献が認められるということで、適用免除の申請をして受け入れられることになるのですが、このことが他のユダヤ人を裏切ることになるのではないかという「良心の危機」があったと指摘されています。フランスの状況に危機を感じ、アメリカに移る計画もたてるのですが、これは果たされませんでした。マルク・ブロックはリヨンに移りレジスタンス運動に参加し、地下活動を展開するのですが、ゲシュタポにより逮捕され、 1944年6月16日、ドイツ兵に銃殺されました。 第五講では、マルク・ブロックが立ち向かわなければならなかった二つの問題について、検討がなされます。一つはユダヤ人の問題。もう一つは、上の略歴ではふれませんでしたが、アルザスの問題です。 ユダヤ人の問題について、二宮さんはマルク・ブロックの遺書をもとに考察します。ブロックは遺書の中で、葬儀ではユダヤ教の儀式をしないように要求しています。一方、自分がユダヤ人として生まれたことは否認しないといいます。しかし自分をフランス人と感じており、ユダヤ人であることはその障害にはならない。自分はよきフランス人として死ぬのだ、と言うのです。 このようにブロックは、自分がユダヤ人であるということについて、強調しています(公職追放令など、そういう時代背景があったのも大きな理由です)。一方、フランスとドイツの中間にあたるアルザスの問題について、ほとんどふれていません。父のギュスターヴまで、ブロック家はアルザスに定着していました。地理的な問題上、ドイツ領になったりフランス領になったりと、アルザス地方の住民の言語やアイデンティティも大きな問題となるわけですが、ブロックはアルザスについてほとんど特別な感情を示していない。では、なぜ示していないのか、ということが考察されます。ここでは、ブロックは、その研究の中では国民主義的な感情を示していないけれど、現実にはフランス共和主義の普遍的価値こそを問題としていて、アルザス固有の地域文化に固執することがなかったのではないか、と二宮さんは指摘しています。 学問史の中のブロックについてもふれておきましょう。 いわゆる「近代歴史学」の特徴として、実証主義、厳密な史料批判という点があげられます。もちろん、これらの性格は基本的には現代の歴史学の基本でもあるのですが、当時は史料から何を読み取るのか、という部分が弱く、考証に終始する傾向があったといいます。この傾向への批判として、ブロックらに影響を与えた三つの潮流が起こります。「ヨーロッパの学問運動・芸術運動は、雑誌を旗印にして展開されることが多い」(53頁)のですが、ここでも三つの雑誌が紹介されます。第一に、ポール・ヴィダル=ド=ラ=ブラーシュが中心となった『地理学年報』。ヴィダルは「人文地理学」を提唱し、これは人間と自然との交渉過程を重視する見方なので、歴史的アプローチが基本的な性格となります。第二に、エミール・デュルケムが中心となった『社会学年報』。その主張の根幹は、「人間の営みをなによりも集合的な過程ととらえ、人間社会を諸要素の密接な関連から生まれる全体構造と見る」(57頁)ことでした。第三に、アンリ・ベールが中心となった『歴史学総合評論』。ベールは、この雑誌を新たな問題提起と議論の場にしようと企てました。 これらの影響を受けて、マルク・ブロックはリュシアン・フェーヴルとともに『社会経済史年報(アナール)』を創刊することになるのです。 そして、『アナール』の大きな特徴として、二点指摘されています。第一に、人間事象をすべて相互連関のうちに捉えようとする立場。第二に、諸専門分野の相互乗り入れの提唱です。先にはふれませんでしたが、「近代歴史学」への批判として、歴史学が細かい専門領域に分化しているということが挙げられていたのです(先日読んだ、『いま歴史学とはなにか』という本でも、現代歴史学の問題点として、専門領域への分化が指摘されていましたっけ…)。 第三講、第四講では、マルク・ブロックの主要な研究書『王の奇跡』『フランス農村史の基本性格』『封建社会』、そして歴史学の方法論に関する『歴史のための弁明』について、その概略の紹介と、特徴の指摘や評価がなされています。ここでは詳しく書かないことにしますが、とても興味深く読みました。本書を参考にしながら、ブロックの著作をあらためて読んで勉強したいと思いました。 それから、上では省略しましたが、第一講で、マルク・ブロックが日本の学会でどう受け入れられてきたか、ということが紹介されており、こちらも興味深く読みました。 ・西洋史関連(邦語文献)一覧へ
2006.08.02
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-







