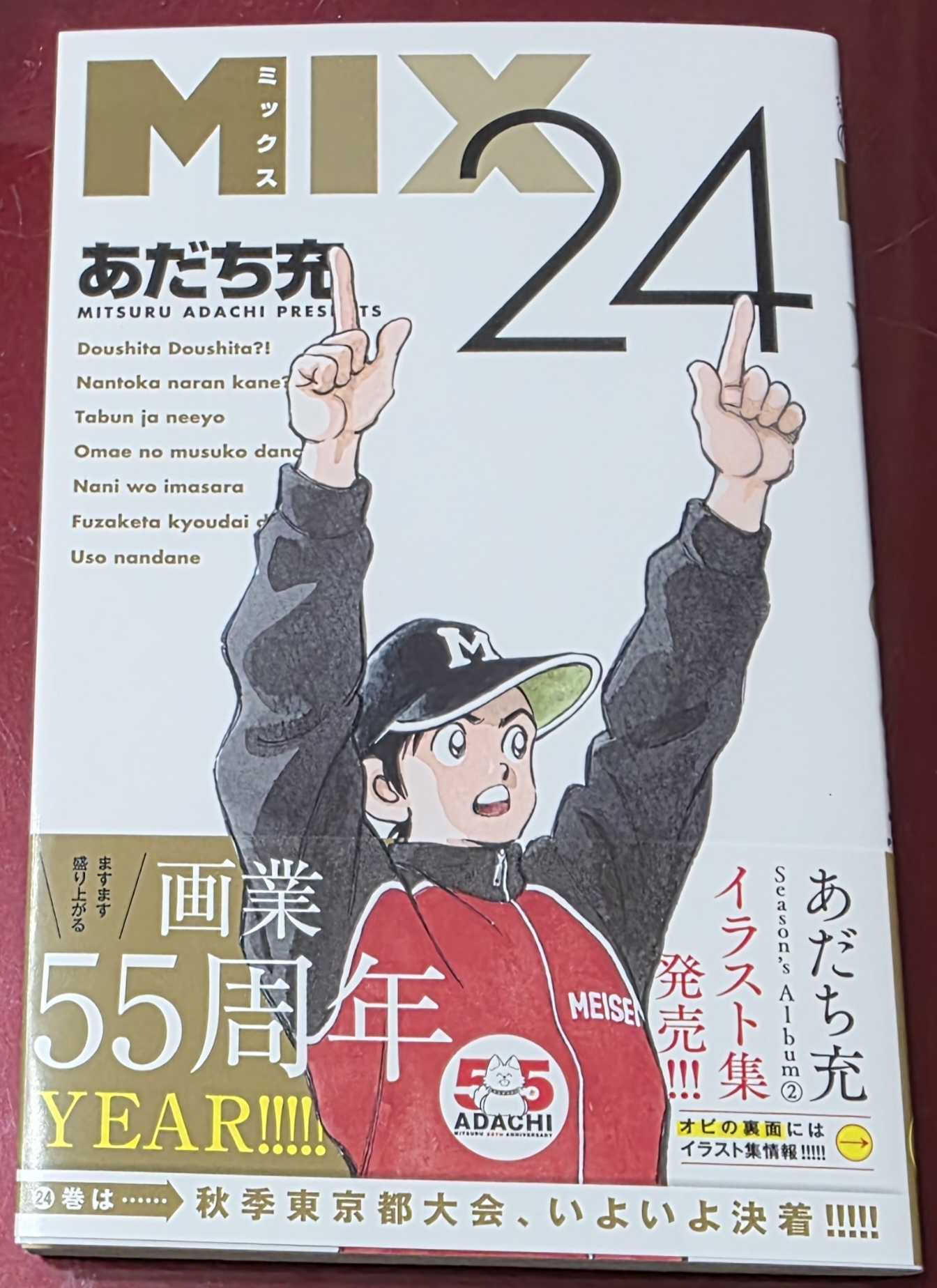2006年04月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

鷺沢萠=文/稲越功一=写真『奇跡の島』
鷺沢萠=文/稲越功一=写真『奇跡の島』~角川文庫、2001年~ 短い物語です。1ページあたりの文字数も少なく、写真も多いので、すぐに読めるかと。 南米のある島で、彼と見た太陽。南米にとどまりながら、自分には二度とあの太陽を見ることはできないと嘆くマリア。奇跡が起こることを祈る。奇跡は決して起こらないから奇跡なのだと、考えながらも-。 彼と過ごした過去。その、哀しい終わり。一つの幸せな人生(その後の「マリア」さんが不幸かといえば、そうとばかりも読めないのですが)を自ら終わらせるシーンも、どこか淡々と描かれていました。 その後、マリアさんと暮らしているホセさんが、素敵な人だなぁと思いながら読みました。過去のことを決して話さず、自分の具合が悪い理由も話さない、そんなマリアさんに理由を問うことなく、ただそばにいる。ドライブ中、突然の大雨の音にびっくりして(恐怖を感じて)泣き出してしまったマリアさん。彼女の肩を、両手でやわらかく包むホセさん。その後の二人のやりとりには涙でした。 今日はあまりじっくり写真を見ていないのですが、写真も素敵だと思います。あぁ、久しぶりに銀色夏生さんの写真詩集を眺めたくなってきました…。
2006.04.28
コメント(1)
-

辻村深月『ぼくのメジャースプーン』
辻村深月『ぼくのメジャースプーン』~講談社ノベルス、2006年~ 『冷たい校舎の時は止まる』で、第31回メフィスト賞作家としてデビューした辻村さんの、第四作です。いつものように、内容紹介と感想を(内容はつっこんで書いています)。 二年前-小学二年生の頃、「ぼく」は自分の「力」を知る。言葉によって、相手を「呪う」力。母親には、それを決して使わないように言われていた「ぼく」だが、四年生になったある日起こった事件をきっかけに、その「力」を使おうと決意する。 賢くて、優しいふみちゃん。同級生の彼女を、「ぼく」は慕っていた。彼女はうさぎが好きで、四年生になってうさぎの当番をするのをずっと楽しみにしていたのだった。 いつも早く教室に行き、クラスの子が当番をできないときには、いつも自分でするふみちゃん。その朝は、「ぼく」が具合を悪くし、当番に行けなくなった。かわりに早く学校に向かったふみちゃんは、うさぎ殺しの犯人と、ばらばらにされたうさぎたちの第一発見者となる。 その日から、他人の言葉に反応を示さなくなったふみちゃん。ふみちゃんをそんな風にした犯人を許せず、ぼくは「力」を使って犯人に近づこうと試みる。 母親は、同じ「力」を使える親戚のもとで、勉強するように「ぼく」に言った。ここで「力」について勉強しておくことも、決して無駄ではないと。 犯人と会って話すまで、一週間。「ぼく」は、「先生」-秋山先生のもとで、多くのことを勉強する。 前作『凍りのくじら』で、数日ひきずるくらいに心を揺さぶられたのですが、本作でも、うさぎたちの状態や、ふみちゃんがうさぎたちを抱えて先生たちに「助けてあげてください」というシーンでは、相当ゆさぶられました。その後も、とりわけ復讐について考えるあたりになると、もやもやと考えてしまいました。 主人公が十歳の男の子のせいもあるのでしょうが、「説話」のように感じながら読みました。「ぼく」や秋山先生が使える「力」をめぐって、・生き物の尊厳(どの程度の虫までなら殺せるか、しばらく飼っていた動物を食べられるか、人間以外の動物に「気持ち」はあるのか、などなど)、・復讐のありかた(復讐は復讐を引き起こすということ、許せないほどのひどいことを受けたにも関わらず、それを忘れようとすること、復讐して何を得られるのかということ、などなど)…、とにかくいろんなテーマについて、秋山先生は「ぼく」に考えさせます。四六時中考えつづけていたら、生きるのがしんどくなってしまうようなテーマ(これは私の主観です)について、これでもかと考えさせられるのです。 そして、それらについて、いくつかの考え方も示されます。もちろん、正解はないでしょう。紹介された考え方を読みながら、またあらためて考えさせられます。 つねづね考えていたことも、ストレートに描かれていました。人間は他人のために涙を流すことはできない。たとえば、誰かが死んでしまったとしても、それは相手を失ってしまった自分がかわいそうだから、人は涙するのだと。ただ、それはそれとしても、そう思えるだけの相手がいる、ということは、その相手のことを思っていることになるのでしょう。すごく安心する言葉でした。 とまれ。こうしたメッセージ性の方に心が奪われ、「仕掛け」には(違和感を感じながらも)気づきませんでしたが、いわゆるミステリ的な要素はどうだっていいのだと思います。 いろいろと考えるきっかけになりました。 * 秋山先生は、『子どもたちは夜と遊ぶ』に登場されている先生ですね。中盤まで気づかなかった自分が恥ずかしかったです。本作で、前作では描かれなかった言葉がわかったのですが、やはり秋山先生の言葉は、描かれない部分もありました。
2006.04.15
コメント(2)
-

綾辻行人『びっくり館の殺人』
綾辻行人『びっくり館の殺人』~講談社、2006年~ 大学生、永沢三知也が古本屋で手に取った一冊の本-鹿谷門実『迷路館の殺人』。彼は、いやおうなく、小学六年生の頃に関わった、「びっくり館」での密室事件を思い出す。 館シリーズ第八作にもあたる、講談社「かつて子どもだったあなたと少年少女のためのミステリーランド」書き下ろし作品です。以下、簡単に内容紹介と感想を。 三知也は、父親とともに神戸市A**町に引っ越してきた。まもなく、クラスメートたちから、「びっくり館」についての噂を聞く。館の中にはとにかくびっくりすることがあるだの、びっくりユウレイが出るだの…。 ある日、英会話スクールの帰り道、三知也は「びっくり館」に古屋敷という標識があるのに気づく。いつもはしっかり閉ざされている門扉も開いており、敷地内に足を踏み入れた。 そこで知り合った一人の少年-トシオ。亡くなった兄と同じ名前でどきっとしたのだが、二人は次第に仲良くなっていく。 体が弱いというトシオを、その祖父の龍平はきびしく監視しており、三知也が一緒に遊ぶ時間も制限された。そんな古屋敷氏が、三知也やその友人のあおい、トシオの家庭教師を招いて、トシオのための誕生会を開く。そこ招かれた三人は、不気味な腹話術ショウを披露された。「人形」には、トシオの亡くなった姉、リリコの名がつけられていた。 やがて、トシオの周囲に起こる異変。三人は、古屋敷氏に問いただすべく連絡をする。古屋敷氏があらためて三人を招いたクリスマスの夜、密室状態の中で、古屋敷氏が殺されているのを三人は発見した。 正直、『暗黒館の殺人』が冗長な割にあまり面白くなかったので、今回の作品には満足。ミステリはミステリなのですが、やはり館シリーズは、そこに流れる独特の不思議な雰囲気がいいですね。本作のラストも、事件の謎自体は納得なのですが、全てが明らかにされておらず、余韻が残ります。 いままでの作品の多くが、標題になっている館の中で(一定の期間の)集団生活→殺人事件発生、という流れなのに対して、本作は、主人公が「びっくり館」の外にいる時間の方が長いです。そういう意味でも、ちょっと異色かな、と。 活字も大きく、読みやすかったです。読了に二時間もかかりませんでした。 先にも書きましたが、『暗黒館』がちょっと不満だったので、綾辻さんに対する評価が変わりそうだったのですが、本作で安心しました。 館シリーズは、十作で完結の予定だとか。完結まであと二作…。次回の作品は楽しみですが、終わりが近づくと考えると、ちょっと寂しいですね。そういえば、本作の中で、「不気味な仮面をモチーフにした館」について言及されています。『奇面館の殺人』というのが構想にあるそうですが、第九作はそうなるのでしょうか。 老人の腹話術のシーンはかなり不気味でしたが、何枚もある挿絵もけっこう不気味でした。 *「かつて子どもだったあなたと少年少女のためのミステリーランド」のシリーズを買ったのは、これが初めてです。作家読みという意味では、森さんや島田さんが同シリーズで出している作品も、文庫化(するのかな?)を待てばよいのですが、綺麗な装丁という意味では、他の好きな作家のも欲しくなったり…。とはいえこのシリーズは少々高いですから、なかなか買うふんぎりがつかないでいます…。
2006.04.15
コメント(4)
-

嶽本野ばら『下妻物語-ヤンキーちゃんとロリータちゃん』
嶽本野ばら『下妻物語-ヤンキーちゃんとロリータちゃん』~小学館文庫、2004年~ ものすごく面白かったです。大笑いしながら、涙ぐみながら、涙ぐんできたところで笑わされながら、とても素敵な読書体験でした。 主人公はロリータに生きる竜ケ崎桃子さんと、ヤンキーに生きる白百合イチゴさんの二人です(これは、ほとんど、固有名詞のメモのつもりです)。 兵庫県尼崎で生まれた桃子さんは、しかし地元が好きではありませんでした。尼崎を馬鹿にした描写、そしてその後住むことになる茨城県下妻を馬鹿にした描写、笑いながら読みました。古今東西、田んぼ。森羅万象、田んぼ。だなんて、面白い表現だなぁと思い、冒頭から繰り広げられるロココ・ロリータ論に続いて、このあたりからどんどんひきこまれていました。 尼崎でバッタ物を売っていた駄目親父。ユニバーサルスタジオジャパンのバッタ物を作り、しかしそれが売れてしまったがためにばれ、下妻に引っ越すことになる二人。東京まで出るのはきわめて不便なものの、桃子さんはロリータ服を買うため、お金を必要とします。そこで、余っていたバッタ物を売ることにして、個人広告に出します。そこに連絡をくれたのが、イチゴさん。 お互い、服装を馬鹿にしあいます。イチゴさんは、数ヶ月生まれているからと、姉御ぶり、桃子さんはイチゴさんの馬鹿なところを指摘していきます。そこで、素直に恥ずかしがり、しばらくへこんだりするところが、イチゴさんの素敵なところだなぁ、と思いました。 私のなかで、本作の中で誰が素敵って、もちろん桃子さんもかっこいいところはあるのですが、イチゴさんです。でもそれは、桃子さんがイチゴさんのよさをしっかりと見て取っているからこそ、伝わってくるのでしょう。 以後、いくつかネタにふれますね。 イチゴさんが所属しているレディースの暴走族。そのリーダーが結婚して、暴走族をぬけるというので、イチゴさんは特攻服に刺繍をしたいと考えます。桃子さんがよく行っている代官山に、腕の良い刺繍職人がいるというので、一緒に行くのですが…。そこで残念な結果になってしまうのですが、イチゴさんはちゃんとした対応をしています。そして、刺繍は桃子さんが手がけることになるのですが、完成した刺繍を見たときのイチゴさんの言葉。それを聞いた桃子さんの感情を読んで、泣けてきました。文字色変えて、引用しておきます。「シブいとか、イカツいとか、カッコいいとか、イカすとか、そんな単語しかイチゴの頭の中には入っていないと思い込んでいましたが、イチゴは刺繍を見て、綺麗だと言ってくれました。誉め言葉として、その言葉を使ってくれました。私は少し、泣きそうになりました」(232頁)。 それだけイチゴさんのことを馬鹿だと見ているわけですが(馬鹿の一面は間違いなくあるでしょうけれど)、けれどもしっかり良いところを見つけているなぁ、と感じます。先にふれた、代官山での刺繍は実現されませんでしたが、そのときのイチゴさんの対応を誉めているのも桃子さんです。逆に、桃子さんがそこを指摘していなければ、私は読み流していたでしょう。 そして、イチゴさんが慕っていたリーダーの送別会の翌日。イチゴさんは、同時に失恋を経験していました。そのとき、公園で二人は会ってお話するのですが、このシーンもとても素敵です。 また引用してしまいます(先の引用と同じく、ここを読み返すだけで、話の流れも思い出して泣けてきます…)。「なぁ、桃子。女は人前で泣いちゃいけないんだよな」「うん。でもここには今、誰もいないよ」(241頁) もっともっと、感動して、素敵だなぁと思って、笑えたところは多々あるのですが、感想はこのくらいで。ものすごく面白かったので、書いていればきりがありません。また再読して、感動を味わいたいです(そして、楽しい気分になりたいです)。 しばらく前から気になっていたのですが、知人との話の中で嶽本さんの話になったので、これをきっかけにと思って買って読みました。本当に読んでよかったです。
2006.04.09
コメント(8)
-
ミシェル・パストゥロー「色彩、装飾、紋章」
Michel Pastoureau, "Couleurs, Decors, Emblemes"dans Michel Pastoureau, Figures et Couleurs : Etude sur la symbolique et la sensibilite medievales, Paris, 1986, pp. 51-57. ミシェル・パストゥローの論文集『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』より、「色彩、装飾、紋章」を紹介します。注もついていない短い論文です。簡単に内容紹介を。まず、装飾の三つの価値について。(1)紋章としての価値。紋章は、個々人を識別する役割を果たします(後述)。(2)イデオロギーを伝達する装置としての価値。(3)図像的価値。装飾の中で、色が最も重要な役割を果たします。中世の人々にとって、色は、人間や社会の分類、価値付けなどの役割を果たすものでした。以上が前文です。以下、小見出に沿って。<布etoffeという媒体の優位性>11世紀の間に、西洋文明は毛織物の文明となりました。布産業が中世経済の原動力だったといいます。布は、紋章の価値を強調する手段でした。以下、布の模様について紹介されます。ちりばめ(スメ)-単色の背景に、水玉、星、ひし形などを配置。これは、13世紀の後半からまれになっていくそうです。普通の模様は、線模様です。また、格子模様が人気だったとか。<灰色の人間、赤い壁>中世の図像に関する資料は、現実の人間の衣服を研究するにはあてにならないといいます。現実には、(衣服の)色はいくつかの例外を除いて長持ちしなかったからです。はっきりした染色、貴族たちが着ていた色鮮やかな服-こうした現象が認められるのは中世末であって、12-13世紀の人間は、「灰色の人間」hommes grisだったといわれています。ところで、教会は色を賛美していました(12世紀を生きた修道士クレルヴォーのベルナールなど、色鮮やかな教会について不平を述べる人々もいますが)。その中で、赤が支配的な色だったといいます。赤は卓越の色であり、人間が暗闇への恐れに打ち勝つようにする色だ、ということです。青が次第に優位になってくるのですが、17世紀半ばまで、室内の壁では、白や赤が優位だったそうです。他のパストゥローの論文では、青が優位になっていく過程が強調されるのが印象に残っているので、この指摘は印象的でした。<紋章をつけた人間>12世紀、「個」(個人、個性)が出現し、個人を識別する動きがうまれます。まず、家族が紋章の最初だそうです(個人を識別する役割という意味で、でしょう)。11-14世紀に、姓が普及していく過程も指摘されています。紋章は、まず戦争やトーナメントの中で出現します。かぶとやくさりかたびらのせいで、個人の識別が難しくなる。そこで登場するのが紋章です。12世紀末から急速に広がり、軍事の領域だけでなく、印璽、貨幣、建築物などでも紋章が利用されるようになります。また、地理的にも拡大し、13世紀には全ヨーロッパに広がったそうです。紋章を使う人々も、戦士にはじまり、貴族女性、聖職者、市民、ブルジョワなどなど、だれでも使えるようになっていきます。やがて、古代の英雄や神話の人物など、想像上の人物にも紋章が使われます。<記章marqueの文明>この節は長いのですが、メモはあまりとっていないので、短めに。紋章学により、紋章には厳格な規則が設けられます。紋章官が、紋章の作成などに責任をもつことになります。中世の文明は「記章の文明civilisation de marque」だと指摘されます。ここまでに何度もふれていますが、紋章(記章、印signe)がもつ、対象、場所、人を識別するはたらき(さらに、階層だて、対立させ、協力させる、などのはたらきもあります)が強調されています。ーーーパストゥロー『図柄と色彩』Figures et couleursからの論文紹介も、これで三度目。次から別の論文を読むので、パストゥローの論文を読むのはしばらく先のことになりそうです。
2006.04.05
コメント(0)
-

倉知淳『幻獣遁走曲』
倉知淳『幻獣遁走曲-猫丸先輩のアルバイト探偵ノート』~創元推理文庫、2004年~ 30歳にもなるというのに、ふらふらとアルバイトに明け暮れる。童顔なので見た目では年齢も不詳。そんな猫丸先輩がアルバイトの中で関わった五つの事件を描く短編集です。簡単に内容のメモと感想を。「猫の日の事件」2月5日。東京フレッシュペットが猫の日と定め、猫好きの人々を集める「日本良い猫コンテスト」が行われる。責任者の部長は、大の猫嫌い。それでもVIPの猫を褒め称えていた。そのVIPの一人・早崎婦人が、部屋を少し空けた間に、彼女がテーブルの上に置いていたという指輪がなくなっていた。お客様対応のためにその場に居合わせていた猫丸先輩が、犯人をつきとめる。「寝ていてください」新薬モニターのバイトに参加した誠。綺麗だが事務的な看護婦に、やる気のなさそうな医師。「バイトの期間はどんな理由があっても外出禁止」。薬や度重なる採血のせいか具合が悪くなり、何度もこのバイトをしている男性から怖い話を聞き、不安を募らせていた誠。そのとき、モニターの一人が採血に行ったきり帰ってこなくなり、看護婦は血相をかえてそのモニターの荷物を部屋から持ち去った。 これは、読んでいてちょっと嫌な気分になりました。もっとも、誠さんの視点で描かれているからそう感じたので、同じくモニターとなっていながらこの状況も楽しんでいる猫丸先輩の視点で見れば、ちっともそんな気分にはならなかったのかもしれませんが。「幻獣遁走曲」幻獣アカマダラタガマモドキを探す、という意味不明のバイトに、猫丸先輩の紹介もあり、彼とともに参加した鼬沢。バイトを集めた鬼軍曹の長ったらしい演説を聞き流し、過酷な草刈を強いられ、バイトのほぼ全員が嫌気がさしていた頃、小火が起こる。鬼軍曹が、幻獣の証拠として読み上げた、その祖母に送られた幻獣発見について書かれた書類が燃やされていたのだ。 この話は、比較的はやくに犯人がわかりました。そんなことより、鬼軍曹がしゅんとしていくのが爽快でしたね。最後のエピソードは余興程度に受け取っておきました。それにしても、ツチノコやら雪男やら、はやりましたねぇ。小学生の頃はよくそれ関係の番組をわくわくしながら見ていたものです。「たたかえ、よりきり仮面」八月四週目。炎天下の中、デパートの屋上で催された「爆裂戦士よりきり仮面」のアトラクション。司会のお姉さん、夏樹は、数少ない観客に向かって、笑顔で声をあげる。気ぐるみの悪役、その二人の手先、そしてよりきり仮面。彼らの動きは見事なものだった。主催者側がけちっているので、しょぼいけれど…。そのアトラクションを、毎度見に来てくれている子どもがいた。裏方で夏樹たちがくつろいでいるところへ、よりきり仮面に会いに来た、という子ども。子どもからの差し入れをありがたくいただいた彼らだが、すぐのちに事件(?)が発覚。よりきり仮面の気ぐるみ-その足のところに、ガムがくっつけられていたのだ。 主題歌がなかなかすごいです…。戦隊ものは、もう十数年も見てないですから、懐かしい感じがしました。一人で熱心にステージを見る子ども。彼がどうしてこれだけよりきり仮面に熱心なのか、そちらの方からも日常の謎風の物語ができそうだな、と感じました。「トレジャーハント・トラップ・トリップ」小さな広告の、松茸刈りに目をとめた啓太。妻の茂美を誘い、二人は参加することにする。二人はマイホーム購入計画のため、お金を節約しためることを最大の課題としていた。松茸をたっぷり取って、ご近所に配り、お返しを期待する-。山奥まで歩いた甲斐はあった。大量の松茸が見つかり、参加者たちは喜んでいたが-事件が発覚。みんなで集めていた松茸の量が減っていたのだ。 ほのぼのできる話です。おじいちゃんおばあちゃんのペアがすごくかわいかったです。二人ともすごい実力者だし。人間の欲の深さがどうとか、そういうことも考えられますけれど、二組の夫婦のやりとり、婿養子で苦労している方のお話など、なんだかいいなぁ、と思いながら読みました(婿養子の方は大変そうですが…)。このお話では、猫丸先輩は松茸の山への案内役のバイトとして登場します。 以上、おおむねほのぼのできるお話が多くて、満足でした。
2006.04.02
コメント(2)
全6件 (6件中 1-6件目)
1