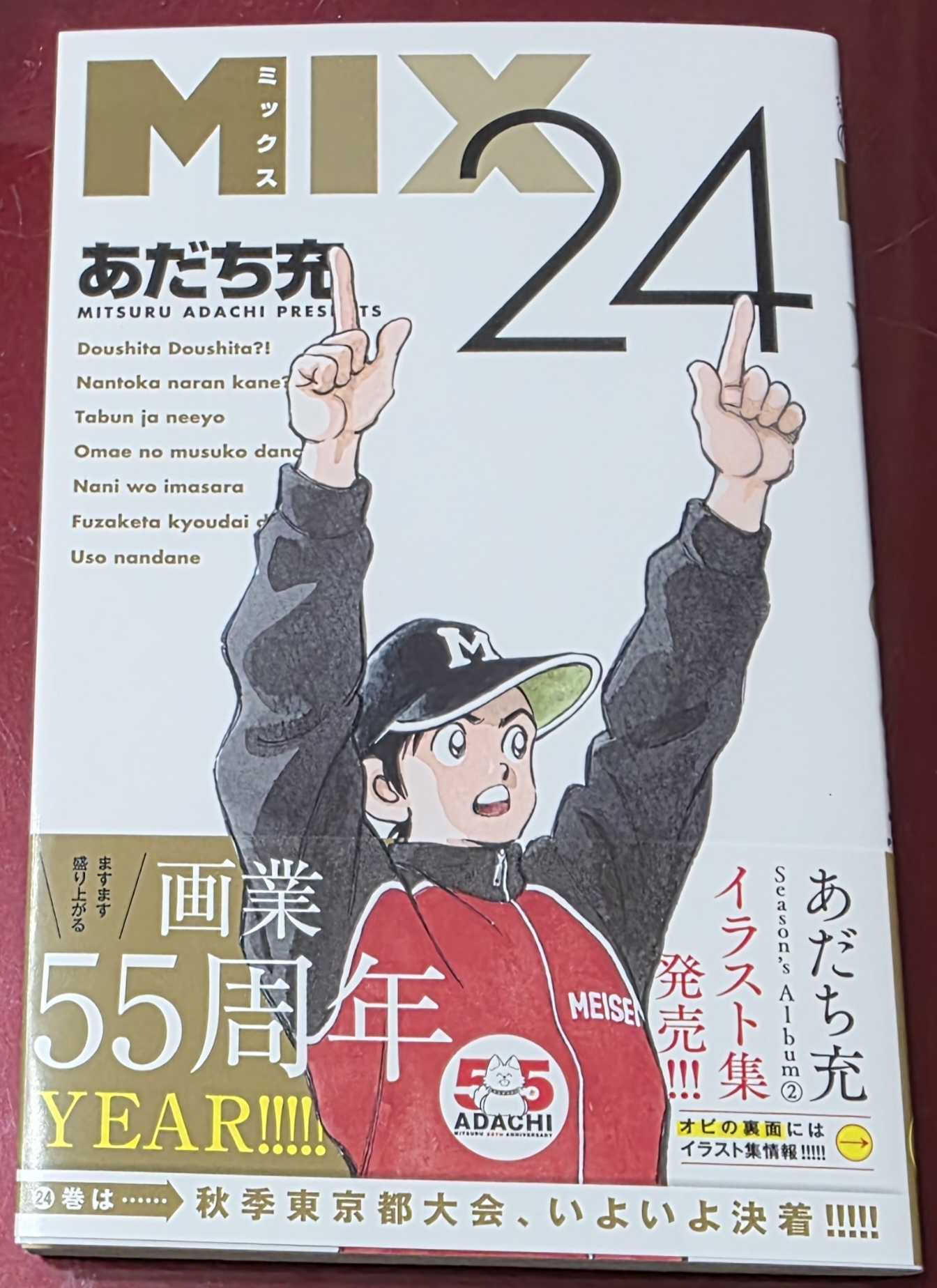2006年06月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

デイヴィッド・キャナダイン編『いま歴史とは何か』
デイヴィッド・キャナダイン編(平田雅博他訳)『いま歴史とは何か』~ミネルヴァ書房、2005年~ ゼミで読んだ本です。 E・H・カーという著名な方が『歴史とは何か』というこれまた著名な本を書いておられます(私の感想はこちらです)。 いきなり脱線します。久々に自分の記事を読み返したのですが、カーの『歴史とは何か』を読んでいろいろ考えたなぁ、ということを思い出しました。もうちょっとカーがどういう方だったかメモしていればよかったなぁとも思いますが…(そして今日も妥協します…)。 とまれ。カーの『歴史とは何か』出版40周年記念のシンポジウムが2001年に開かれたそうです。本書は、そのシンポジウムでの講演をもとにした論文集です。 で、さきほどの脱線ともつながるのですが、本書を読んで考えるところが、別段なかったなぁ、ということです。あとでまたふれますが、アマゾンに寄せられた書評でも相当指摘されていますが、本書の訳はひどいです。私が敬愛する歴史家ジャック・ル・ゴフの本をひどい訳で世に出した鎌田氏という方がいますが、あれよりひどいかもしれません。で、私も西洋史をやっているので外国語を読んでいるわけですが、じゃあお前の訳は大したもんなのか、と問われたら、それは違います。読み返して恥ずかしくなる試訳が多々あります。ですが、せめて出版するときは考えていただきたいです。それでご飯を食べるんでしょう。私は人の批判は好きではありませんが、ひどい訳なので言わせていただきました。ひどい訳には目を瞑りながら出版するのですかね。…また脱線しました。要は、訳がひどいので読むテンションが下がったというのも、あんまり考えるところがなかった一因なのかな、と思った次第です。 本書の目次は以下のとおりです。 第一章 プロローグ-『歴史とは何か』のいま- 第二章 いま社会史とは何か 第三章 いま政治史とは何か 第四章 いま宗教史とは何か 第五章 いま文化史とは何か 第六章 いまジェンダー史とは何か 第七章 いま思想史とは何か 第八章 いま帝国史とは何か 第九章「いま」歴史とは何か[*のぽねこ注:「いま」は、本書では傍点です] 自分が専門にしている領域を直接扱っていることもあり、そして論の流れがスムーズなこともあり、第四章がもっとも面白かったです。著者が何を言いたいのかよく分からない章もいくつかありました(私は第二章で特に感じました)。この記事では各章の紹介は省略します。興味をもったところだけ。 第七章は、「言語論的転回」について論じていました。これは、言語が現実と世界を構成する、という考え方です。たとえば、単純な例ですが、「わたしは今日ケーキを食べました」という文章があるとします。いちごのショートケーキを思い浮かべる方もいるかもしれません。私がチーズケーキが好きだということを知っている方なら、あるいはチーズケーキを食べたのかな、と思うかもしれません。裏をかいてロールケーキかもしれません。そもそも、「わたしは今日ケーキを食べた」のでしょうか。このように、文章で表現された裏にある「真実」には到達しえない、という考え方です。歴史家はいっぱい文字資料を読んでいるかもしれないけど、君らに真実なんて分からないよ、という主張ですね。 こうしたことを言う方々の目的と歴史家の目的は違うのだから、歩みよりは難しいだろう、ということをゼミなどで話しています。「言語論的転回」の主張も、それはそうだと思います。それでも、史料を批判的に読んで、ある事象をある特定の時代・社会に位置付けることが歴史学だと私は思っているので、もちろんその中ではいろんな解釈が生まれてきますが、それでいいし、それが大事だと思っています。…「言語論的転回」の話とかみあってませんよね。こうなってしまいます。なお、「事実」と「真実」を区別し、事実にもいくつかのレベル(ある時代のある地域の人口や物価という「事実」、あるときある人間がある事件を起こしたという「事実」、など)を分けて、言語論的転回に反論している方がおられます。 章の順番は前後しますが、先にもふれた第四章。宗教史(キリスト教史)を扱った章ですが、主にアナール学派の研究が紹介されます。それも主に中近世に関する研究が中心で、私が読んでいる著作も多々紹介されていますので、興味深く読みました。特に、エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリの『モンタイユー』、ジャン・ドリュモーの『罪と恐れ』、そして邦訳はないミシェル・ヴォヴェルの『バロック的信仰心と非キリスト教化』の三冊の意義が簡潔に整理されていて、個人的にとても勉強になりました。 結局、自分が担当した章の紹介になってしまいました…。 さて、訳の話にまいります。特に気になったところ。第八章「いま帝国史とは何か」より、一節を引用します。「やむをえず短くなった本章で、私が帝国史へのアプローチについて網羅的に概略していないことが明々白々なのは、繰り返しに耐えることである」(231頁) 文脈を無視してここだけとりあげるのは乱暴かもしれません。それでも、この日本語は…。 では、まとめましょう。ここ40年で、歴史学の研究の対象はひろくなり、個別専門化している、という現実があります(そんなことはずっと以前から指摘されている、というお話も聞きましたが)。本書は、その中のいくつかを特にとりあげた、ということですね。最近のテレビと歴史学のこともなんだかんだと論じられていました。というんで、たしかに「いま歴史とは何か」を考えるたたき台にはなると思いますが、先にもふれたように、別段考えさせられるようなことはありませんでした。個人的には、先に紹介した二つの章が特に勉強になったなぁ、というところです。むしろ、これをたたき台にしたゼミでの議論の方が、考えさせられるところがありました。 そして、繰り返しますが、訳のひどさがきわめて残念です。これまた先にふれたことですが、何を言いたいのかはっきりしないような章もあり、要は全体的に読みにくかったです。 E・H・カーの『歴史とは何か』へのオマージュというには、いささか残念な本でした。もっとも、ここまでここで書けたのは、ゼミなどでの議論でいろいろ考えることができたからなので、ゼミの時間を振り返り、先生をはじめ、学生のみなさまと話せた時間をありがたく思う次第です。なんだか感傷的ですね…。
2006.06.30
コメント(0)
-

西尾維新『ザレゴトディクショナル 戯言シリーズ用語辞典』
西尾維新『ザレゴトディクショナル 戯言シリーズ用語辞典』~講談社ノベルス、2006年~ 『クビキリサイクル』から『ネコソギラジカル』まで、戯言シリーズ全6作(9冊)の用語辞典です。作成秘話など、裏話も満載です。というんで、本書は袋とじになっています。 ○○辞典、というのを頭から最後まで読み終えるという、私にははじめての経験ができました。 読む前は、ためらいもありました。シリーズ全て読んでいるとはいえ、細かい人名や設定まで覚えていませんし、大丈夫かなと。最初の項目「哀川潤」を読んで、そうした心配は消えました。泡坂妻夫さんの亜愛一郎さんへの言及がそこにあり、ちょっとしたミステリの紹介にもなっていたからです。他の項目にも、森博嗣さんや京極夏彦さん、笠井潔さん(特にその矢吹駆シリーズ)らに言及があり、興味深かったです。 さらに面白かったのは、西尾さんの、まだ単行本になってない作品も項目として載っていること。私は雑誌までカバーして読んでいないので、短編の状況を把握していないのです。『零崎双識の人間試験』の続編や、『ダブルダウン勘繰郎』に続く(といって内容に関連はないそうですが)JTCトリビュートの作品、さらにそうした既に出版されているシリーズ以外の作品など……要は全てが気になります。 西尾さんの作品の関連でいえば、シリーズ第三作『クビツリハイスクール』の項目を読んでいて、そういえば『クビツリハイスクール』は密室本だったなぁ、と思い出しました。 そう、ツンデレなんて項目もありました。昨年の夏頃にはじめて耳にしましたが、もちろんそのときは意味なんて分かりませんでした。いまでは漠然と認識はしていますが、辞典と銘打っているわりに、ここでは定義がなされていませんでした。それだけ一般化したということ、あるいは少なくとも戯言シリーズ読者については知っていて当たり前、ということでしょうか(苦笑)。先日紹介した浦賀和宏さんの『上手なミステリの書き方教えます』(感想はこちら)で散々萌え文化が批判されていましたし、私もそういった文化からは距離をおいておこうと思っているわけですが、無駄にくいついてみました。 戯言シリーズの舞台は京都ですので、京都にまつわる事項も紹介されます。八橋とおたべの違いなど、聞いたことがあるとしても人に説明できるほど覚えていませんので、興味深く読みました。 全体をとおして、面白かったです。
2006.06.24
コメント(1)
-

浦賀和宏『上手なミステリの書き方教えます』
浦賀和宏『上手なミステリの書き方教えます』~講談社ノベルス、2006年~ 松浦純菜さんと八木剛史さんシリーズ第三作です。ハウツーもののようなタイトルですが、上手なミステリの書き方は分からないような…。むしろ、ミステリへのアンチテーゼの一つの形として読みました。 主人公の八木さんは、趣味(特技)といえばガンプラ作りくらいで、学校ではほとんどの生徒からいじめられている、という人。レストランで、妹と食事しているとき、外国人に発砲され、妹さんは入院、しかし八木さんは奇跡的に助かった、という過去があります。 第一作で、純菜さんと八木さんは出会います。純菜さんは、八木さんのその《力》を重視して、二人は仲良くなるのです。女性の友達がいなかった八木さんにとって、純菜さんは大きな存在になっていきます。そして、第一作、第二作の中で二人は事件に巻き込まれ、そして事件を解決するのです。 本作は、既刊の二作を読んでいないと全く意味不明だと思います。二冊とも読んでいて文脈は分かっているつもりでも(だからこそ?)、「彼女と出会わなければ俺は脳内で幸せに生きていられたのに!」という帯の文句に失笑してしまいましたが…。 いつものような感想の書き方はしづらいので、つらつらと書きます。 メインは、八木さんの苦悩です。純菜さんが好きな八木さんですが、最近は二人で出会うことより、女友達の小田さんと、男友達の河野さんも一緒に四人で会うことが多いのです。自己卑下の気持ちがあまりに大きい八木さんは、純菜さんは河野さんと話している方が楽しいんだ、とか、もっと一般的に、自分以外の男といる方が純菜さんは楽しいに違いない、とか考えます。ガンダム関連の妄想とかいじめの描写とか…。濃いですね…。 萌え文化を嫌悪するエロ萌え小説家の独白も、本書で大きな部分を占めています。私は何を読んでいるんだろう…という気分になりました…(苦笑)。 ひたすらにオタク文化、萌え文化が批判されます。それらの文化は資本主義社会にあって、お金になる分野だからマスコミから非難されないが、実は日本を堕落させている、というんですね。 妙な話だな、どうつながっていくんだろう、と思いながら読むわけですが、びっくりなつながり方をしてくれました。ミステリテイストの事件も起こります。その小説家の妹が、一見不可解と思われる状況で殺されるのです。 なにやら奇妙な話でしたが、ラストの爽やかさが良かったです。勧善懲悪はいいですね。 トラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。(追記) 作家批判やいくつかのエピソードについて、『浦賀和宏殺人事件』を思い出しました。自分の感想を読み返してみると、あまり好きになれないと書いていますが、作品を読み返してみるとまた別の印象を抱くかもしれない、と思いました。
2006.06.18
コメント(2)
-

岡崎隼人『少女は踊る暗い腹の中踊る』
岡崎隼人『少女は踊る暗い腹の中踊る』~講談社ノベルス、2006年~ 第34回メフィスト賞受賞作です。作者の岡崎さんは岡山県在住だそうです。本書の舞台も岡山です。ものすごくうちの近所のような気がするのですが…。あぁ、でも本書の舞台に出てくる学校の数を考えると、違うような気もします。 バイオレンスな作品です。以下に、内容紹介と感想を。 父親を継いでコインランドリーの管理をしている俺-北原結平。最近、岡山市で乳児誘拐事件が続いていた。つい先日、四回目の事件は、俺が住んでいる穴見で起こった。 事件から三日経った日のこと。コンビニに立ち寄っていた俺は、駐車場にとめた原付きに、少女が近づいているのに気づいた。少女に近づくと、少女は走り去る。開けっ放していたメットインの中に入れていたトートバックは原付きのそばに置かれていた。かわりに、メットインの中には両足のちぎれた赤ん坊の死体が入っていた。 九年前。俺が見殺しにしてしまった女性と、少女が俺の中で重なっていく。俺は少女を探し、乳児誘拐事件に一つの解決を作り上げようと画策する。 その頃、俺に近づくウサガワという男。ウサガワは、マスコミによる乳児誘拐事件の扱いをしのぐほどの大事件を-一家惨殺事件を繰り返していく。 ミステリーテイストのところもあるのですが、とにかくバイオレンスです。 ウサガワが起こす事件もひどいですが、俺が事件に別の形を与えようと動く過程でも、暴力のオンパレード。あんまり読まないジャンルです。装丁と本書の体裁(一段組み)もあってか、どことなく舞城王太郎さんの雰囲気を感じます。でも文体はずいぶん違いますし、やはり方向も違いますかね。 冒頭でもふれましたが、舞台は岡山県です。馴染み深い地名や学校名がたくさん出てきます。岡山弁も自然に読めました。岡山弁を文字にしたら読みにくい、という思いはあるのですが、本作ではあまり気になりませんでした。勢いがあるからでしょうか…。 えげつない設定ですが、それほど気分がふさぐこともありませんでした。あんまり深く考え込むとどつぼにはまりそうなので、あまり考えないで読んだのはあるかもしれません…。
2006.06.18
コメント(0)
-

森博嗣『臨機応答・変問自在2』
森博嗣『臨機応答・変問自在2』~集英社新書、2002年~ 先日紹介した『臨機応答・変問自在』の続編です(感想はこちら)。前回は、森さんが授業の際に学生から受けた質問とそれへの答えなのに対して、一般の方々から募集した質問と、それへの答えという形になっています。前書きで森さん自身もおっしゃっていますが、質問する方は、その質問が本に載る可能性がある、と知っていて質問してきているので、どうもそこを意識したような質問が見受けられます。だからこそ面白い質問もありましたが…。回文がよかったです。 今回はあまり付箋をはりませんでしたし、パソコンに向かう前から薄々感づいていましたが、たいした感想が書けそうにありません。 面白い(?)と思ったのは、新書の分類記号。前作は、Gで「科学」の枠組みなのですが、本作はF「文芸・芸術」のくくりになっています。話がふくらみません、それだけでした。 読みながらこれは書こうと思っていたことを。174頁、森さんから読者に質問があります。「本書はあなたにとって何の役に立ちましたか?」と。 私の目下の答えは次のようなところです。「他人の価値観や考え方にふれる一つのきっかけになりました。小説を読むのと同じ動機、あるいは小説を読んだあとに抱く感想と同じです。森さんの小説や日記などを拝読していて、森さんの価値観を興味深く感じていることもあり、Q&Aの形で様々な問題(?)に対する森さんの見解をうかがえたのは楽しい時間でした」 問う力、簡潔に答える力を磨きたいものです。
2006.06.17
コメント(0)
-

「桃太郎」ゆかりの場所めぐり
(記事は12日に書いています)日曜日は、桃太郎のモデルとされる吉備津彦命と、彼が退治した鬼のモデルである温羅(うら)にまつわる神社などをめぐってきました。高田崇史さんの『QED 鬼の城伝説』(感想はこちらです)をざーっと読み返して、予備知識をつけた上でのお出かけです。まずは吉備津彦神社へ。駐車場は、鳥居に向かって右手(西側)にあります。夏至の日の太陽が、鳥井の真正面から上るように設計されているとか。拝殿、祭文殿、本殿が一列に並んでいます。さて、次いで西側、吉備津神社に向かいます。途中、左手に「鼻ぐり塚」というのがあります。ここには、牛の鼻輪が700万個も置かれているそうなのですが、入場料を節約、今回は見送りました。100円ですから、決して敷居は高くありませんが…。吉備津神社に到着。本殿へと上がる階段の手前に、矢置岩というのがあります。吉備津彦命が鬼ノ城に住む温羅に向かって矢を投げるのですが、その際矢を置いていたところだとか。この神社でとても好きなのは、長い回廊です。この回廊を通って、有名は御竈殿(おかまでん)に行けます。退治された温羅は、その首を切られ、しばらく首村というところに置かれたそうなのですが、ずーっと唸り続けたといいます。そこで、その首を埋めたのが、御竈殿の下。それ以来、竈が鳴るようになったといいます。これが、鳴釜神事の起源です。また、回廊を歩いていくと、(入った側から見て)左手にあじさい園があります。まだ時期が早かったようですが、もう少しすると綺麗になるそうです。そのあじさい園にある階段(割と長くて急)を上がったところに、岩山宮というのがあります。そこから、階段を見下ろして撮った写真がこちら。ところで、現在本殿と拝殿は修復中でした。ここは、「比翼入母屋造り」といわれる独特の造りをしていて、他に例がないところから「吉備津造り」といわれます。入母屋造りの本殿と切妻造りの拝殿があわさった形をしています。さて、吉備津神社の次に、矢喰神社へ向かいました。吉備津彦命が投げた矢と、鬼ノ城から温羅が投げた岩がぶつかり、矢が落ちた場所だそうです。矢が落ちた岩というのが五つありました。まわりは割と整備された公園になっていて、なかなか良い場所だなぁと感じました。最後に向かったのが鯉喰神社です。吉備津彦命と温羅の勝負はなかなかつかなかったわけですが、吉備津彦命はアドバイスを受けて、矢を二本同時に放ちます。片方は、例によって温羅が投げた岩とぶつかったのですが、もう片方が温羅の左目に刺さりました。温羅は雉に姿を変えたりするのですが、結局鯉に姿を変え、血吸川に入ります。その鯉を、吉備津彦命が鵜に身をかえてとらえたという場所が、この神社です。『QED 鬼の城伝説』の中で、棚旗姉妹や小松崎さんが訪れた場所をトレースしていると考えると(高田さんも取材にいらしたかと考えると)少しどきどきしたのが妙なファン心理とでもいうのでしょうか。肝心の鬼ノ城を訪れなかったのは、体力に自信がなかったからです…。またいずれ、道もちゃんと確認して、あらためて訪れたいなぁと思います。
2006.06.11
コメント(6)
-

森博嗣『臨機応答・変問自在』
森博嗣『臨機応答・変問自在』~集英社新書、2001年~ 国立M大学・N大学で授業をされている森博嗣さんは、学生の成績を、毎回授業の度に学生に質問を書かせ、それによって評価しているそうです。その考え方は、12頁の「重要なのは答えることではない、問うことである」の部分から、詳しく紹介されます。 そして本書は、その授業の中で学生から出された質問と、それに対する森さんの答えを紹介する構成になっています。質問の約95%は授業に関する質問であり、本書では残りの約5%、一般の読者の興味も持てるような質問が抽出されている、ということです(このあたりの数字は、続刊『臨機応答・変問自在2』を参考にしました)。 森さんは、質問の全てをワープロで打ち込み、それぞれに答えるそうですので、それぞれの答えはとても短く、ウィットがきいています。質問に質問で返す、など、答え方のテクニックも紹介されています。 目次は次の通り。1.いろいろな質問2.建築に関する質問3.人生相談?4.大学についての質問5.科学一般についての質問6.コンクリートに関する質問7.森自身に関する質問 読みながら付箋をつけましたが、3のところにけっこう貼りました。 短い答えというので面白かったのが、Q.部屋をうまく換気する方法はないでしょうか。A.ある などですね。いまのは、1からの引用です。 私はがちがちの文系ですので、2,5,6などは純粋に勉強になりました。他のところでも、森さんの考え方に感化されるところは多々あります。森さんの考え方が好きだから、私はその作品を多く読んでいる、ともいえます。 久々に読み返したのですが、とても興味深く読みました。(追記) 153頁に、アクアフレッシュという歯磨きは、チューブの中で三色が分かれているのか、という記述があります。これに関する脚注で、どのような仕組みでこのようになっているのか、切り開いて内部を覗く人がいるらしい、とありました。 いるんです。昨日の記事で紹介したフランスの歴史学者ミシェル・パストゥローです。彼は色彩や紋章の歴史の分野で有名な方なのですが、『悪魔の布-縞模様の歴史』という本を書いています。別の本の紹介ですが、『悪魔の布』についてふれた記事はこちらです。リンクをはった記事でも書いているとおり、パストゥローは、フランスの「アクアフレッシュ」にあたる歯磨きチューブを、分解したそうなのです。学術書で大笑いするという珍しい経験を与えてくれたパストゥローは尊敬する歴史家です。ーーーもともとフリーページに感想をリンクしていましたが、書いていないに等しい感想だったので、この記事にあらためるとします。
2006.06.11
コメント(0)
-
ミシェル・パストゥロー「次に青がきた」
Michel Pastoureau, "Et puis vint le bleu", dans Michel Pastoureau, Figures et Couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilite medievales, Paris, 1986, pp. 15-22. ミシェル・パストゥローによる論文集『図柄と色彩―中世の象徴と感性に関する研究』より、「次に青がきた」を紹介します。この本の論文を紹介するのは今回で四回目になります。パストゥロー氏のことは記事のたびになにかしら言っていますし、青についてもいろいろふれてきてますので、簡単にいこうと思います。 この論文が収録されている本が1986年と、20年前のことには注意しなければいけませんが、当時の段階で、ヨーロッパ人のお気に入りの色は以下のとおりだそうです。一位は青で約半数、二位の緑が25%、三位の黒が10%だそうです。では、昔はどうだったのでしょうか。1.パストゥローは、紋章の色について統計的な研究を行っています。結果が次のとおりです。<azur-紋章の青>1200年頃:5% 1250年頃:14% 1300年頃:20% 1350年頃:25% (その後しばらく安定、少し低下した時期を経て)1650頃:35%<gueules-赤>1200年頃:65% 1350(1250の誤り?)年頃:45% 13世紀末:35% その次に、地理的分布が指摘されますがそれは省略するとして、興味深かったのが、青が多い地域では黒が少なく、逆に黒が多い地域では青が少ないという指摘です。ここから、紋章の観点からいえば、青と黒が同じ役割を果たしていた、と言われます。2.次いで、文学史料(特にアーサー王伝説)を分析し、色のもつイメージが紹介されます。まとめると次のようになります。(以下、騎士の服の色、13世紀までのイメージ、13世紀末からのイメージという順番で紹介します)・赤 13cまで:悪い考えに駆り立てられた 13c末~:軽蔑的なニュアンスなくなる・緑 13cまで:一般に若く、無秩序 13c末~:(本文に言及なし)・黒 13cまで:善or悪の英雄 13c末~:常に悪い側・白 13cまで:英雄の友人 13c末~:(本文に言及なし)・青 13cまで:まれ 13c末~:王権、忠実な愛、聖母マリアの色3.文学以外の領域の青についてです。 (a)美術史 13世紀から、ミニアチュール(細密画)やステンドグラスに青が多くなっていくことは、美術史家たちも価値をおいている点だそうです。 (b)衣服 青い服は、普段着から盛装になるそうです。布の染色技術が高まり、明るい青の色が出せるようになったため、貴族の服に青が流行するようになるとか。アカネ職人が青の権威を貶めようとして、悪魔を青く描かせたという話は、以前紹介したこちらの論文にもふれられています。やがて、青は王室の色となっていきます。もともとはフランス王カペー家の家系を象徴する色だったのが、次第に王の色となる、と指摘されています。面白かったのは、アーサー王がほぼいつも青い服を着ている、という指摘です。アーサー王物語も読まなければと思いながら、未読です…。4.こちらも既に紹介している論文でもふれられていますが、色の対立についてです。青が登場しその地位が高くなる時代まで、白-赤-黒という三色の図式が支配的だったとされています。ここで興味深いのが、黄色が白と同一視され、緑あるいは青は黒と同一視されたという指摘。 後、紋章の中で、色の使い方が規制されるのですが、これは色の数を六つとし、それを二つのグループにわけます。 (a)白、黄 (b)赤、黒、青、緑 そして、同じグループの色を並べることが禁止されたというのです。たとえば、地が赤なら、他の(b)グループの色を並べてはだめで、白か黄しか並べられない、というのですね。このグループは、つい先に指摘された色の同一視がふまえられていて、興味深かったです。この同一視と同じことだと思いますが、1.のところでふれた青と黒の関係のように、白が多い地域では黄色が少なく、黄色が多い地域では白が少ないという関係があったそうです。なお、緑は非常にまれだとか。2.の文学のところで、13世紀末からのところに緑についての言及がないのも、そのためかもしれません。 ともあれ、青が大きく価値を増大させる頃、従来の白-赤-黒という三色の図式は崩壊に向かいます。5.青の急速な進出は、三色の図式の崩壊の結果であろうと、パストゥローはこのときは考えています。『青の歴史』という本が2005年に邦訳されて出ているのですが、こちらを読むともっと確定的に書いているかもしれません。英訳版はざーっと読んでいるのですが、邦訳はまだ読み終わっていません…。 ともあれ、三色対立の図式は、色の直線的・ヒエラルキー的な序列にとって変わられる、といいます。 別の論文でも図で示されていますが、本論文での指摘を図式すると以下のとおりです。<ヒエラルキー>上:白、青中間:赤下:黄、黒 最後は、色の歴史が、人類学的な歴史につながっていくといった指摘をされています。ーーー パストゥローの本はいろいろ読んでいますし、本論文は20年前の論文ですから、内容としてはほとんど聞いたことがありました。青の歴史について簡単に整理されているのがよいですね。個人的には、フランス語の勉強になりました。
2006.06.10
コメント(0)
-

朝暮三文『ダブ(エ)ストン街道』
朝暮三文『ダブ(エ)ストン街道』~講談社文庫、2003年~ 第8回メフィスト賞受賞作です。石田衣良さんによる解説にもありますが、ミステリが多いメフィスト賞の中、本作は異色であると感じます。私はほとんど読まないファンタジーです。 ハンブルクで私-ケンが出会った女性、タニヤ。彼女には夢遊癖があり、ケンのもとを離れてしまった。そして、ケンに届いたタニヤからの手紙。彼女は、地球のどこにあるかもわからない(太平洋上にあるようですが…)ダブ(エ)ストンという場所にいるという。 ケンはさまよい、島にたどりついた。そこが、ダブ(エ)ストンだった。島の人々は、だれもが道(?)に迷っている。なにかを探して、さまよっている。 …なんていう話でした。 メインは、ケンさんによる一人称。ダブ(エ)ストン近くを漂流する幽霊船の中の幽霊たちや、裸の王様ご一行など、ときどき別のシーンも織り交ぜられます。 なんだか最近辛口になってきているような気がして不本意ではありますが、本作は冗長な感じがしました。あまり読まないジャンルだから仕方ないのでしょうか…。 ああ、ここは泣かせどころなんだろうな、普段のテンションだったら泣くかもしれない、と思うようなシーンも、ぼんやり眠たいまま読みましたし。 もともとの単行本の本は、本当になかなか見つからないようで、やっと読めたわけですが、あまりテンションは上がらなかったです…。
2006.06.07
コメント(1)
全9件 (9件中 1-9件目)
1