PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1167)戦国
(1098)江戸後期
(134)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(608)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
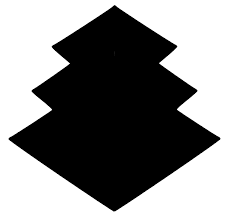
(おがさわら まさやす)は、
室町時代
の
武将
、
守護大名
。
信濃
守護
[1]
。
小笠原長基
の3男で
長将
、
長秀
の弟。
宗康
、
光康
の父。
小笠原氏 は曾祖父 貞宗 が 足利尊氏 に仕えた功績で信濃守護を世襲したが、隠居した父の後を継いだ次兄長秀が 国人 衆の反感を買い、 大塔合戦 に敗れて 応永 8年(1401)に信濃守護職を取り上げられ、信濃は一時 斯波義将 の支配に置かれた後、翌応永9年(1402)には 室町幕府 の直轄領となった。 政康は 嘉慶 2年(1388)に13歳で元服し、応永12年(1405)に兄から家督と小笠原氏の所領を譲られた。
応永23年(1416)に 関東 で発生した 上杉禅秀の乱 鎮定に 駿河 守護 今川範政 や 越後 守護 上杉房方 と共に出陣し、また応永30年(1423)には 鎌倉公方 足利持氏 と対立した 京都扶持衆 山入氏 ・ 小栗氏 ・ 真壁氏 らを救援するため、幕府代官細川持有と共に 常陸国 に出陣するなど、 足利将軍家 に反抗的な関東足利氏への抑え役として4代 将軍 足利義持 から重用され、応永32年(1425)に信濃守護職に任命された。信濃の幕府直轄化は元々は守護による統治を嫌って幕府直臣化を望む信濃村上氏ら国人の動きに応えたものであったが、自立志向が強い彼らは幕府の命令にも従わず関東足利氏に通じて反抗することもあったため幕府にとって直轄支配のメリットがなかったこと、関東足利氏に対抗する軍事的再編の中で守護による軍事指揮権の再構築が図られたことによるとみられている。
正長 元年(1428年)の 正長の土一揆 に対して上洛し一揆勢の鎮圧にあたった。また、この年に足利持氏が越後守護代 長尾邦景 や同国の国人を寝返らせようとして邦景から告発を受けると、政康を急遽帰国させて越後出陣の事態に備えさせている。
永享 4年(1432)には6代将軍 足利義教 の弓馬師範に推挙された(『 林羅山 撰 将軍家譜』)。永享8年(1436)には持氏と通じた 村上頼清 と 芦田氏 討伐を果たし、義教から感状を授かった。
村上氏は永享9年(1437年)に幕府に降伏し、小笠原氏の信濃支配は一応達成することになる。
これに先立つ応永24年(1417)、在京していた 武田信元 の 甲斐 帰還を手助け、 守護代 として 跡部氏 を派遣している。甲斐では持氏の支援を受けた国人・ 逸見有直 が勢力を強めており、その対抗的意味があったと考えられている。
永享10年(1438)の 永享の乱 では 上野国 に出陣し 平井城 に向けて北上する持氏方の軍勢を討ち破った。永享12年(1440)の 結城合戦 にも信濃武士を統べて参戦しており、『結城陣番帳』にその諸将の名が見える。嘉吉2年(1442)、 小県郡 海野で死去。 享年 67歳。長男の宗康が後を継いだ。しかし、正式な譲状を作成しなかったことから、この継承に異論を挟む余地を生んだ。
その後、 嘉吉の乱 で義教が 赤松満祐 に 暗殺 された後に 畠山持国 が台頭、甥で長兄長将の子の 持長 が持国の支持を背景に相続を主張、国人も2派に分かれて抗争、小笠原氏は お家騒動 で混乱、信濃の支配に動揺をきたし 漆田原の戦い を起こすことになった。
信濃の支配権確立にも取り組み、 広沢寺 や 筑摩神社 を開基した。】
*「小笠原 長秀」 (おがさわら ながひで)は、 室町時代 の 武将 、 守護大名 。 信濃 守護。 小笠原長基 の次男。 長将 の弟、 政康 の兄。幼名は豊若丸。
初めは上洛して将軍 足利義満 に出仕した。 明徳 3年 / 元中 9年(1392)、 相国寺 の落慶供養では先陣随兵を務めている。 応永 6年(1399)の 応永の乱 では 畠山基国 に従って 堺 を攻め、同年、信濃守護に補任された。入部に先立ち、将軍 足利義持 は 水内郡 太田荘領家職について、押領人を退けるよう 御教書 を発した。
応永7年(1400年)、京都から下向し、 国衙 の後庁のあった 善光寺 に入部したが、 国人 に対する排斥と守護権力の強化は大いに反感を買い、有力武将や大文字一揆勢との 大塔合戦 へと発展し、大敗して 大井光矩 の仲介によって京都に逐電した。応永8年(1401)に信濃守護職を解任され、信濃は幕府の直轄領(料国)となった。応永12年(1405)に弟政康に家督と小笠原氏の所領を譲渡した。
応永31年(1424) 筑摩郡 で死去(『豊前豊津小笠原家譜』)。享年59歳。著書に「犬追物起源」がある。
*「小笠原 政康」 (おがさわら まさやす)は、 室町時代 の 武将 、 守護大名 。 信濃 守護 [1] 。 小笠原長基 の3男で 長将 、 長秀 の弟。 宗康 、 光康 の父。
小笠原氏 は曾祖父 貞宗 が 足利尊氏 に仕えた功績で信濃守護を世襲したが、隠居した父の後を継いだ次兄長秀が 国人 衆の反感を買い、 大塔合戦 に敗れて 応永 8年(1401)に信濃守護職を取り上げられ、信濃は一時 斯波義将 の支配に置かれた後、翌応永9年(1402)には 室町幕府 の直轄領となった。 政康は 嘉慶 2年(1388)に13歳で元服し、応永12年(1405)に兄から家督と小笠原氏の所領を譲られた。
応永23年(1416)に 関東 で発生した 上杉禅秀の乱 鎮定に 駿河 守護 今川範政 や 越後 守護 上杉房方 と共に出陣し、また応永30年(1423)には 鎌倉公方 足利持氏 と対立した 京都扶持衆 山入氏 ・ 小栗氏 ・ 真壁氏 らを救援するため、幕府代官細川持有と共に 常陸国 に出陣するなど、 足利将軍家 に反抗的な関東足利氏への抑え役として 4 代 将軍 足利義持 から重用され、応永32年(1425)に信濃守護職に任命された。
信濃の幕府直轄化は元々は守護による統治を嫌って幕府直臣化を望む信濃村上氏ら国人の動きに応えたものであったが、自立志向が強い彼らは幕府の命令にも従わず関東足利氏に通じて反抗することもあったため幕府にとって直轄支配のメリットがなかったこと、関東足利氏に対抗する軍事的再編の中で守護による軍事指揮権の再構築が図られたことによるとみられている。
-
「千葉氏一族の群像」千葉氏の逸話。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」長尾景春の乱。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」千葉孝胤。 … 2024年06月30日










