PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1167)戦国
(1098)江戸後期
(134)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(608)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
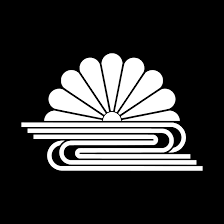
/
観応
元年(1350)10月、北朝での進退が極まった直義はついに南朝側に寝返ることを決意した。
11月20日に河内国石川城に参じ、北朝重臣 畠山国清 も離反に加わり、さらに南朝准大臣 北畠親房 と謁見して投降の意を伝えた(『 園太暦 』正平5年11月25日条)。これが 室町幕府 の内紛である 観応の擾乱 (かんのうのじょうらん)の始まりである。
なお、直義と親房の折衝地の石川城は、城そのものは北朝の畠山国清の居城であったが、地域としては正儀の本拠地である 東条 内にあり、この後しばらく正儀も直義と協調路線を取ることから、藤田精一は、直義の投降と観応の擾乱の勃発には正儀からの 調略 も一枚噛んでいたのではないかと推測している。
国清も離反に加わったことについては、 亀田俊和 の推測によれば、直義の養子(実は尊氏の実子) 足利直冬 が有能な武将であるのに、尊氏が冷遇していることに、国清が同情したのではないかという。
正平6年 / 観応 2年(1351)1月3日ごろ、正儀は楠木党のひとつ和田氏( 河内和田氏 か 和泉和田氏 かは不明)を直義の腹心 桃井直常 に貸し与え、桃井は和田氏を率いて坂本( 比叡山 周辺)を攻めた(『 園太暦 』)。
2月10日、正儀も自ら擾乱に加わり、河内国 大饗城 の北朝軍に示威行動を取る(『和田文書』)。
その後、観応の擾乱は直義側有利に進み、2月17日 摂津国 打出浜の戦い でも直義勝利、2月25日もしくは26日に 高師直 ・ 高師泰 兄弟が 上杉能憲 に殺害されたことで、一旦の決着を見た。
和平交渉(1351年初)
南朝からの援軍のおかげで尊氏・師直に勝利できた直義は、見返りとして、北朝と南朝の和睦交渉を取り持つことを提案した。
正平6年 / 観応2年(1351年)2月初頭、直義は銭一万疋を南朝に献上するなど、積極的に友好関係を深めようとした(『 房玄法印日記 』同年2月6条)。
しかし、 楠木氏 同族 河内和田氏 の棟梁 和田正武 (わだまさたけ)は主戦派の支持者であり、直義の言を信用していなかったらしく、同2月には 常陸親王宮 令旨として 諏訪部助直 ら 中国地方 の南朝武将たちに戦闘準備を執達していた(『三刀屋文書』)。
亀田俊和の推測によれば、直義が北朝の年号である観応を使い続けていたことも、南朝主戦派からの不信感を買ったという。
一方、同僚・同族の正武らとは異なり、正儀は和睦に前向きであり、南北朝間で初の本格的な和平交渉に臨んだ(第一回はだが、短期間で打ち切られた)。
そもそも、南朝は当時逆境にあり、北朝の側から和平を持ち込むとは、実利的に考えれば千載一遇のチャンスだったのである。
また、当時、足利直義は、相次ぐ政治的混乱や実子 足利如意丸 の急死などもあって、政治への興味を失いつつあったが、なぜか和平交渉だけには熱心で、このことも追い風となった。
とはいえ、前述したように当時南朝はまだ強硬的な主戦派が多く、3月時点で既に交渉には困難の影が見え始めていた。
まずは2月ごろに室町幕府の 二階堂行通 が南朝の穴生行宮( 賀名生行宮 )への使節に選ばれ、交渉を行っていたが、(南朝の側から京に使節を派遣すると決まったためか)3月2日に使節を辞任している(『房玄法印日記』観応2年3月2日条)。
3月11日、正儀は神宮寺将監某と入道某の二人( 神宮寺正房 と 八木法達 ?)を和平交渉の南朝側特使として京に派遣し、 足利直義 と交渉を進めた(『 房玄法印日記 』)。
3月12日ごろ、 臨済宗 の北朝高僧 夢窓疎石 もこの交渉に関心を示していた(『園太暦』)。
北朝の 山名氏 の山名俊行から正儀の側近の 和泉和田氏 に宛てた3月14日付の書状でも「御合体」について触れられており(『和田文書』)、楠木党総出の和平交渉だったようである。
4月初頭に入っても和平交渉は継続中であったことを、天台宗の高僧 恵鎮 が証言している(『 園太暦 』観応2年4月16日条)。
後半に入り、25日にも和平の会談があった(『園太暦』)。
4月27日、直義は南朝の糾弾から兄の尊氏をかばって、武家は公家を助けることが本分なのだから、南北朝が合一しても、尊氏の将軍の地位はそのまま安堵して欲しい、という書状をしたため、正儀の両特使に託している(『吉野事書案』『 房玄法印日記 』同年4月27日条)。しかし、5月中旬、南朝の主戦派はこの提案を拒絶し、尊氏の政界からの完全追放を望んだ(『房玄法印日記』同年5月15日条)。
この南朝と幕府の交渉は『 吉野事書案 』という記録が残され、格調高い政治議論として古来より名高い。
両朝の議論の結果、南北朝に分かれた主な原因が、天皇親政か幕府主権か、恩賞の分配方法をどうすべきか、という二点に集約されることがわかった。
しかし、この二点の双方において、両陣営の意見は余りに隔絶しており、和睦が締結されるにはまだ遠く、結局は内戦の継続が決定された。
南朝内の誰が正儀の和平交渉に横槍を入れたのかは、はっきりしない。足利氏を糾弾する文書『吉野事書案』の署名や、『 房玄法印日記 』という一次史料で親房が和平を拒絶したとする記述から、伝統的には、 准大臣 北畠親房 が主戦派の首魁だったとされ、現実を見ようともせずに、北朝の提案を無碍に却下したと言われてきた。
しかし、21世紀初頭以降の研究では、実際には親房は中立派であり、主戦派と和平派の間の調停役を務めていたと考えられている。
亀田俊和によれば、このころの主戦派代表は、公家の 洞院実世 、そして他ならぬ 後村上天皇 自身だったという。
身内の非現実的な強硬路線のせいで交渉破断を伝えざるを得なくなったことに、正儀は激しく怒り狂った。
-
「千葉氏一族の群像」千葉氏の逸話。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」長尾景春の乱。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」千葉孝胤。 … 2024年06月30日










