PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1167)戦国
(1098)江戸後期
(134)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(608)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
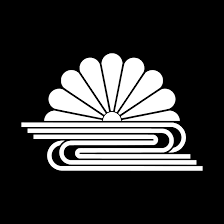
/
応安
元年7月19日までは努力が続いていた形跡が確認できる(『河野文書』重綱(判)
河野通堯
宛書状同年7月19日付)。
しかし、後村上天皇・足利義詮という両首脳を立て続けに失ったことにより、交渉は以前にも増して困難となった。しかも、次節で述べるように、後村上天皇の長子で主戦派の長慶天皇が即位することとなり、やがて交渉は打ち切られた。
長慶天皇即位
正平23年 / 応安 元年(1368年)、和平派の熙成親王(後の 後亀山天皇 )ではなく、北朝に対して強硬だったと言われる主戦派の 長慶天皇 が即位し、和平派の中心であった正儀は南朝内で孤立することになってしまった。
長慶天皇 は、現実路線よりも理想論を奉じる強硬派だったが、決して無策な愚君ではなかった。
『 源氏物語 』の日本最古の辞書形態の注釈書『 仙源抄 』を著すなど、文人・学者としての優れた素養もあり、芸術の怪物的天才だった祖父・ 後醍醐天皇 譲りのカリスマを受け継いでいた。
のち、 二条派 の大歌人でもある 宗良親王 が 36 年もの長征から戻ったこともあって、長慶天皇は歌合・和歌会を盛んに催した。現代の感覚からすれば公務を放棄して遊戯に興じたように一見思えるが、当時の歌合・和歌会は高度に政治的な場であり、王権を権威付ける公的な文化装置の役割があった。
また、このような歌合を通してわかるのは、長慶天皇政権が、人員的にも政治・訴訟制度的にも、それなりのものを維持できていたということである。
長慶天皇が主宰する文学サロンによって、この後、 弘和 元年 / 永徳 元年(1381) 12 月 3 日 、宗良親王を撰者とする 準勅撰集 『 新葉和歌集 』という傑作が生み出されている。
実際、長慶天皇のカリスマ向上政策は功を奏しており、のち正儀が北朝に寝返ったときも、棟梁の正儀の決定に唯々諾々と従った楠木氏とその同族の武将は楠木正直ぐらいしかおらず、他はほぼ全て長慶天皇のもとに留まった。
特に 河内和田氏 と 和泉橋本氏 は楠木氏の同族だが、その棟梁と思われる 和田正武 と 橋本正督 は、正儀不在中、長慶天皇の股肱の臣として活躍した。
しかし、長慶天皇にどのような政治的ビジョンがあろうとも、そして同族がどれだけ長慶天皇を支持しようとも、それが戦乱の継続を意味する限り、正儀とは全く相容れるものではなかった。
細川頼之と協同する
一天平安
南朝へ帰参
弘和 2年 / 永徳 2年(1382)閏1月、正儀は南朝に帰参した。正儀の出奔で空位となった室町幕府の河内国守護職は、 畠山基国 が引き継いだ。
南朝帰参の契機となったのは、直接的には幕府での後ろ盾である 細川頼之 を失ったからである。
これに加えて、 林屋辰三郎 は、正儀の長年の努力が実り、南朝内で和平派を支持する層が増えたからではないか、としている。
幕府の報復措置は速やかで、裏切った正儀に対し同月内に 山名氏清 を派遣した。
弘和 2年 / 永徳 2年(1382)閏1月17日ごろ、正儀は山名氏清と対峙し、24日、河内国平尾で交戦(『三刀屋文書』所収『出雲国須波郡新左衛門入道軍忠状 永徳2年3月日』)。
正儀は野戦で敗退したため、「旧居之要害」(平尾城?土丸城?)に籠城し、河内国の南朝軍を招集した。
なお、 徳川光圀 『 大日本史 』は『和漢合運暦』を引いて、このとき正儀は氏清に大敗し、宗族6人、家人140が死亡したとし、『 南方紀伝 』等も同様に伝える。
しかし、これらは 江戸時代 初期の著作のため、数字が正確かどうかは不明である。
また、前記一次史料では、正儀が野戦で敗北したことまではわかるが、平尾城に立てこもった後の籠城戦の勝敗まではわからない。
この後、 軍記物 『 後太平記 』は、 元中 5年 / 嘉慶 2年(1388)に嫡子の 楠木正勝 が河内国平尾で氏清に大敗したとしている( 平尾合戦 )。後世の軍記物のため、日付や戦闘内容をそのまま鵜呑みにしてよいかは疑問である。
しかし、 一次史料 である元中7年 / 康応 2年(1390) 3 月 7 日 『尼妙性等売券』(国会図書館編)には、「平尾合戦」のとき山名氏の乱入によって荘園の 券文 (土地書類)が失われたとあるから、1380年代のどこかで楠木氏が氏清から手痛い打撃を受けて平尾城が陥落し、幕府の報復が成功したことは事実と考えられている。
参議昇進
その後、 弘和 2年 / 永徳 2年(1382)2月28日までには、北朝側に離反する前に南朝で任じられていた 左兵衛督 の官職に復帰した(『渡辺文書』弘和2年2月18 8 日付下知状)。
同年12月24日までに 参議 に任じられ、 公卿 (国政を司る 太政官 の最高幹部)となった(『観心寺文書』河野辺兵庫頭宛書状12月24日付 [13] )。
楠木氏 は 四姓 (源平藤橘)のひとつ 橘氏 の後裔を自称・公言し、これはおそらく父の正成が若かりし頃に兵衛尉に任官するために系図を捏造したものと考えられているが、少なくとも『 建武記 』など当時の政府の記録でも公的に橘氏として扱われている。
橘氏 は 永観 元年(983)に参議 橘恒平 が没したのち没落して公卿が絶えていたため、(実態はともかく公的な書類の上では)正儀は実に399年ぶりの橘氏公卿ということになる。
-
「千葉氏一族の群像」千葉氏の逸話。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」長尾景春の乱。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」千葉孝胤。 … 2024年06月30日










