PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(290)時代の事変・変貌
(256)幕末
(104)中世
(1167)戦国
(1098)江戸後期
(134)近世
(40)古代史
(254)江戸時代
(608)安土桃山時代
(346)明治維新
(86)大正・昭和
(360)温故知新
(0)魏志和人伝
(4)王朝伝説の群像」
(3)徐福
(0)江渡泰平の群像
(1)「傘連判状
(5)室町管領の攻防」
(20)徐福・桃源郷に消え」
(1)江戸泰平の群像
(294)石徹白騒動
(7)大名のお家騒動
(64)信西と信頼の興亡
(5)嘉吉の乱
(43)応仁の乱の群像
(46)戊辰戦争の群臣
(69)幕藩一揆の攻防
(55)ジョン万次郎の生涯
(2)太閤の夢の夢」
(79)平治の乱
(43)西南戦争
(42)保元の乱
(38)天正壬午の乱
(43)小牧長久手
(42)治承寿永の乱
(43)高杉晋作
(49)コメント新着
キーワードサーチ
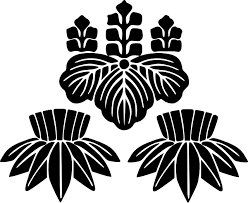
山名氏 (やまなうじ、やまなし)は、 山陰地方 を中心に勢力を持った 武家 ( 守護大名 ・ 戦国大名 )である。
鎌倉時代
山名氏の 本姓 は 源氏 。 家系 は 清和源氏 の一家系 河内源氏 の 棟梁 ・ 鎮守府将軍 ・ 源義家 の子・ 義国 を祖とする 名門 ・ 新田氏 の一門。 新田義重 の 庶子 ・ 三郎義範 (または太郎三郎とも)が 上野 多胡郡 ( 八幡荘 )山名郷(現在の 群馬県 高崎市 山名町周辺)を 本貫 として 山名三郎 と名乗ったことから、山名氏を称した。
*「山名 義範」 (やまな よしのり)は、 平安時代 末期から 鎌倉時代 初期にかけての 武将 ・ 御家人 。 山名氏 の祖。
新田義重 の庶子として誕生。 上野国 多胡郡 八幡荘 の山名郷 [2] を与えられ、山名氏を称した。
承安 5年 / 安元 元年(1175)から安元3年 / 治承 元年(1177)頃には 豊前国 の 宇佐八幡宮 を勧請し、 山名八幡宮 を建立している。他の兄弟と比較されて義範のみ 新田荘 内の所領を分与されず、また、極端に少ない所領しか相続しなかったことから、新田氏の庶流の中でもかなり冷遇されていたと見られる。
父・義重は治承4年(1180)8月に挙兵した 源頼朝 の命になかなか従おうとしなかったために、頼朝から不興を買って 鎌倉幕府 成立後に冷遇されたが、逆に義範はすぐさま頼朝の下に馳せ参じたため「父に似ず殊勝」と褒められ、 源氏 門葉 として優遇された。治承8年(1184)2月の 源義経 率いる 平氏 追討軍に参加。 文治 元年(1185)8月には 伊豆 守 に任じられる。文治5年(1189)7月の 奥州合戦 に従軍。 建久 元年(1190)、頼朝の上洛に供奉。建久6年(1195)の2度目の上洛では 東大寺 供養の際に頼朝に近侍し、その嫡子・ 頼家 の参内にも従っている。
いち早く頼朝のもとに参陣したのは、早くから 足利氏 との縁があったためであると伝わる。】
山名氏の祖の義範は 鎌倉時代 には早くから 源頼朝 に従って 御家人 となり、頼朝の知行国( 関東御分国 )の一つである 伊豆 の国主に推挙され伊豆守となる。
源伊豆守の公称を許され 源氏 の 門葉 として優遇された。逆に本家の 新田氏 は頼朝へ参上することが遅れたこともあり、門葉になれなかった。
通説では山名義範の嫡男 重国 の長男の 重村 が山名郷を継承し、山名氏の嫡流になったとされている。
系譜上においては通説通りで問題はないものの、実際には重村の弟・ 朝家 の系統と重国の弟(すなわち、重村・朝家の叔父にあたる) 重家 の系統が鎌倉時代における山名氏の中心的存在であったとみられている。
朝家の子孫は鎌倉幕府の法曹官僚、重家の子孫は 六波羅探題 の奉行人を務める家柄であったが、朝家の曾孫の 俊行 が 正安 3年(1301)に謀反の疑いで滅ぼされ、残った重家の子孫も鎌倉幕府滅亡と前後して没落したため、結果的に鎌倉時代を通じて不振であった山名重村の子孫だけが残ったとみられている。なお、重家の子孫とみられる山名氏が丹波国・出雲国・備前国などに所領を有していた可能性があるものの、重村の子孫である守護大名の山名氏による支配との連続性は確認できないため、別物とみなされる。
-
「千葉氏一族の群像」千葉氏の逸話。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」長尾景春の乱。 … 2024年06月30日
-
「千葉氏一族の群像」千葉孝胤。 … 2024年06月30日










