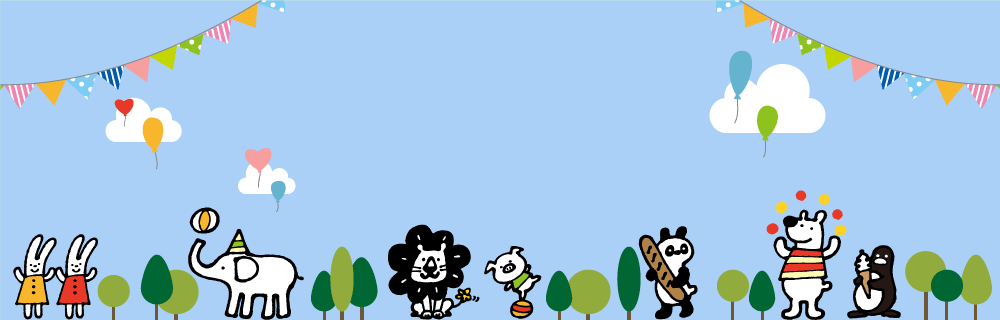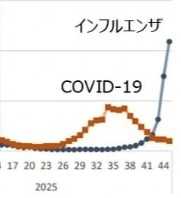2011年02月の記事
全58件 (58件中 1-50件目)
-
チュニジアからエジプトへ…(31)
チュニジアからエジプトへ…(31)バーレーンに戻り、歴史を振り返りながら、今日の状況を見ることにします。この国は、国土面積がアラビア半島で最小の島国です。しかし、ペルシャ湾の入口に近く、ペルシャ帝国の海上交通を担う要衝に位置していましたので、海のシルクロードの十字路にある、大事な拠点だったのです。イスラム教の登場以前、ネストリウス派のキリスト教(中国では、景教と呼ばれています)徒が多かったことからも、この地を通っての東西交易が活発に行なわれていたことがわかります。こうしたいきさつから、イスラム世界の拡大のなかで、この地の人々はペルシャ(イラン)やメソポタミア(イラク)南部の人々と共に、シーア派の信仰を持つに至りました。やがて時移りて、バーレーン島は、喜望峰を経由してアラビア海からインド洋に至る航路を開発したポルトガルが、支配するに至りましたが、そのポルトガルの支配も80年程柄で衰え、再びイランの支配下に戻ります。イランの支配が200年えお経過した18世紀末、アラビア半島のスンニー派の勢力が、カタールを経由してバーレーンに進出、軍勢を率いたハリファ家の当主が、力の衰えたイラン系の王朝を圧倒して、バーレーンの統治を始めました。この王朝が今に続くバーレーンの王家です。こうしたいきさつで。バーレーンは人口の2割弱のスンニー派が支配層となり、国民の8割近くを占めるシーア派住民の大部分が貧困層を形成しているのです。やがて第一次大戦後、イギリスの支配下に入り、1971年の独立後も、国内の治安維持に関しては、国王の私設顧問という形で、イギリス人が務めるなど、スンニー派の王位と権力を維持するために、多数派のシーア派を警戒する体制をとって来ました。歴史的、伝統的にはペルシアの影響を強く受けていながら、そのペルシア(イラン)系の人々はずっと冷遇され、2割の征服者が君臨する体制が続いている。ここにバーレーンの問題があります。しかも油田はありますが、埋蔵量は少なく、やがて枯渇することも分っている状態のため、財政的に豊かとはいえない状態にあります。度重なるシーア派住民の反逆で、今世紀に入って、ようやく議会制が取り入れられましたが、二院制の議会の下院のみの選挙制で、国王の任命制をとる上院の権限が優越しますから、住民の声をある程度ながら反映する下院の声が、認められることはありません。下院を通過しても、国王や王族さらには富裕層の気に入らない法案は、全て上院で否決されてしまうからです。内閣は国王が指名した首相が組閣し、国王に対して責任を負う内閣です。首相以下ほとんどの閣僚を王族が占めますから、まさに明治憲法体制以上に、名ばかりの立憲君主制に過ぎません。それでも、議会すら存在しないサウジアラビアやクウェートなどに比べれば、マシとされているのです。2003年の米軍らのイラク侵攻は、結果的に失敗に終わり、フセイン政権下で抑圧されていたシーア派が、イラクの政権を握るようになりました。そしてイラクのシーア派は、特にイラク南部に集中しています。ペルシア湾岸の2大国、フセイン時代には、深刻な対立関係にあったイランとイラクが、今やシーア派連合を形成して、バーレーンのシーア派を密かに支援する、こういう体制を、米国の介入が作ってしまったのです。こうしたバーレーンでは、昨年10月に下院選挙が行なわれ、シーア派の政党ウェファク党が40議席中18議席を占め、他のシーア派系政党を合わせて過半数を握ったのですが、その主張は全て上院で潰され、シーア派系住民のみの失業率が15%を越える状況のなかで、何の成果も打ち出せずにいたのです。そうしたところに起きたのが、チュニジアのジャスミン革命であり、アラブ世界に影響力の強いエジプトの革命だったのです。ここに、一握りのスンニー派に、200年以上にわたって牛耳られてきたシーア派住民の怨念が、堰を切って溢れ出したのです。住民の決起に触発されたウェファク党の議員や、他のシーア派系議員は、「選挙で選ばれた議員の主張が認められない議会は、無効である。」と宣言して、議員を辞職し、デモの隊列に加わりました。 続く
2011.02.28
コメント(8)
-
オバQ誕生 28日の日記
クロニクル オバQ誕生1964(昭和39)年2月28日1964年は、10月に東京オリンピックが開かれた年でした。そして47年前の今日、発売された漫画週刊誌『少年サンデー』誌に、新連載漫画として。藤子不二雄さんの「おばけのQ太郎」が初めて登場したのです。ユニークでちょっとドジでだけれど、気が良くて犬が大の苦手という、お化けらしくないキャラクターのQちゃんは、子どもたちに愛され、Qちゃんのおかげで、お化けが怖くなくなった子ども達が、大勢誕生したのでした。
2011.02.28
コメント(14)
-
チュニジアからエジプトへ…(30)
チュニジアからエジプトへ…(30)バーレーン問題の途中ですが、リビアの動きがきな臭いので、今日はリビアの続報です。リビア、解決に時間がかかりそうです。反カダフィ派に就いた正規軍に戦略家がいないようですね。首都の空港をカダフィ派が抑えています。そしてカダフィは、金でブラックアフリカの内戦地帯から、内戦で精神を破壊された少年たちからなる傭兵隊を集め、トリポリに空輸しています。これで数を揃えて、必死の抵抗をしているのです。やられても次が来るわけですから、空港を占拠しない限り、イタチゴッコが続きます。武器もカダフィ派の方が、質の良いものを揃えているようです。しばし、内戦は続きそうです。またCNNの情報では、トリポリ周辺になお10トンの化学兵器(マスタードガス)を貯蔵しており、外国航空機のトリポリ空港への着陸を阻んで、少数ながら残っている各国の外交官を、実質的に人質にしています。それで、どこも迂闊に手を出せずにいます。CNNの記事によれば、「米軍縮協会(ACA)の核不拡散専門家ピーター・クレイル氏によると、リビアの武器庫には今も約10トンのマスタードガスが残存するという。その大半は、首都トリポリの南に位置するラブタの化学兵器製造工場に保管されている。」というのです。今のところ、このガスは使われていないようですが、平気で国民を空爆するカダフィのことです。いつ、マスタードガスを撒き散らすか。分らないのが怖いところです。しばらく、激戦が続くのでしょうが、最も早くケリが着くとすれば、身内か側近の誰かが、至近距離からカダフィを暗殺することしかないでしょう。人民裁判で撲殺されるよりも、その方が彼には良いかもしれません。そして何よりも、権力者が庶民を平気で抹殺する悲劇を、1日も早く終らせる方法は、残念ですが、カダフィの死しかないようです。 ザビ
2011.02.27
コメント(16)
-
ドイツ国会議事堂放火により全焼 27日の日記
クロニクル ドイツ国会議事堂放火により全焼1933(昭和8)年2月27日今から78年前の事件です。1929年の10月に、アメリカに発した世界恐慌の発生から3年4ヶ月、この年、1月にはドイツにヒトラー政権が誕生したばかりの時でした。首相になったヒトラーは、政権基盤を固めようと、すぐに議会の解散に打って出、3月5日を投票日に、選挙戦の最中でした。そんなこの日、午後9時30分頃、ドイツ国会議事堂が放火により出火、全焼したのです。放火犯として、附近にいたルッペという少々気のふれたオランダ人青年が逮捕されたのですが、事件の背後関係や真相は、今日まで明らかになっていません。分っていることは、選挙戦の最中にあったヒトラーとナチスが、政権政党の特権を生かした、この放火事件を、政敵の弾圧のために、徹底的に利用したということです。ヒトラーは、事件の報を聞くと、ただちに「事件は共産党の組織的な犯行である」との談話を発表、共産党勢力を一網打尽にひっ捕らえて、同党に壊滅的な打撃を与えたのです。社会民主党もまた、無傷では済みませんでした。
2011.02.27
コメント(0)
-
チュニジアからエジプトへ…(29)
チュニジアからエジプトへ…(29)バーレーン王制は、湾岸戦争後に米国と軍事協定を結び、米国にペルシャ湾岸における重要な軍事拠点を提供しています。バーレーン島南部の25%が、米軍基地となっており、ここには米国第5艦隊の司令部が置かれています。ですから、バーレーンが反米化し、米軍基地の存続が危なくなるとすると、これは米軍にとっても大きな痛手となることは、間違いのないところです。ブッシュ政権が始めたイラク戦争は、フセイン独裁の下で、スンニー派支配を保ってきたイラクに、「民主化」するつもりで、シーア派に明け渡したのです。結果として、イラク戦争で最も得をしたのは、かつてのペルシア帝国の末裔イランということになったのです。イラン・イラク戦争でも分るように、国境問題を抱えて犬猿の仲だった、イランとイラクは、アメリカの失策のおかげで、手を組むことが出来るようになったのです。そこへ、スーダン紛争の終結と、南スーダンの独立に始まる、地鳴りのような中東革命が始まったのです。チュニジアからエジプトに飛び火した革命の嵐は、今まで顕在化することの少なかった民衆の声を、一挙に噴出させました。8割近いシーア派住民が立ち上がり、スンニー派王制にノーを突きつけたのです。中途半端な内閣改造で収まることはないでしょう。バーレーンに、シーア派内閣が誕生するようなことになると、そのバーレーンにとって、イランやイラクは、脅威ではなくなります。それゆえ、米軍の基地など不要になります。米国の好きな「民主化」が、エジプトに次いでここバーレーンでも、米国の不利益に繋がって行くという、何とも皮肉な現象が広がっているのです。 続く
2011.02.26
コメント(6)
-
東京高裁女性の定年差別に違法判決 26日の日記
クロニクル 東京高裁女性の定年差別に違法判決 1975(昭和50)年2月26日36年前の今日のことです。この日東京高裁は、「女性の定年を男性よりも低い年齢とすることは、憲法の男女平等並びに労働の権利の規定に照らして、違法である」という、画期的な判決を下しました。今だ男女雇用機会均等法が準備もされず、話題にもなっていない時期でしたから、この判決は働く女性たち、とりわけ働き続けたい女性たちを。大いに勇気付けました。裁判闘争は、地味で息の長い戦いになります。大変な費用と労力、そして時間を必要とします。その上日本の裁判は政治や大企業に著しく有利で、庶民には不利に働くことが多いのです。そうした中で勇気をもって問題を提起し、定年差別の現実を静かに訴え続けた女性たちの勇気と信念が,遂に定年差別違法判決を引き出しました。そして、こうした努力が、やがて男女雇用機会均等法を、生み出すことに繋がりました。私は、この日は、日本女性史の輝かしい1ページだと、受け止めています。
2011.02.26
コメント(4)
-
チュニジアからエジプトへ…(28)
チュニジアからエジプトへ…(28)リビアを先に記しましたが、湾岸に位置するバーレーンも燃えています。バーレーンは大小33の島々からなる島国で、人口は79万人。主島のバーレーン島は、隣国サウジアラビアと1本の橋で結ばれています。バーレーン王家は、サウジやクウェートの王家に近く、スンニー派の信仰を保持しているのですが、国民の多くはシーア派であるため、王家と国民との間で、宗教的軋轢が絶えない国です。石油収入があるため、国民に税は課されずにいますが、油田は枯渇傾向にあるため、産油量は減少しつつあるため、ここ数年失業率が増加傾向にあります。バーレーンは、イランやイラクとも近く、1990年代の湾岸戦争頃から、シーア派住民が政治的に目覚め、当時専制的であった王権に対する民主化闘争が断続的に続き、次第に大規模化しました。この状況に王権は譲歩するしかなく、2002年に、立憲君主制へ移行することとなりました。二院制の議会を設け、内閣制度も設置されましたが、首相は国王の任命であり、内閣は国民ではなく、国王に責任を負う、明治憲法体制に近い制度となっています。このため、内閣のメンバーは、いずれもスンニー派で、しかも主要ポストは、全て国王の一族で占められています。このため、国民の80%近くを占めるシーア派住民は、極めて不利な状態に置かれており、チュニジアやエジプトの革命運動は、バーレーンのシーア派住民を大いに刺激し、首都はシーア派住民の様々な要求の坩堝と化したのです。 続く
2011.02.25
コメント(8)
-
『夕刊フジ』創刊 25日の日記
クロニクル 『夕刊フジ』創刊1969(昭和44)年2月25日1969年というと、もう42年前になるのですね、1月に東大安田講堂を占拠する学生たちを排除するために、機動隊が動員された、あの年です。全共闘運動がまだまだ頑張っていた時期。日本の学生の目が、天安門事件当時の中国の若者のように、そして現在のエジプトやリビアの若者のように、輝いていた時期でした。そんな最中のこの日、日本で初めての駅売りのタブロイド版夕刊紙、『夕刊フジ』の創刊号が発売されました。今では駅の外にコンビニなどにも置かれていますね。販売の中心は、関東と関西で、公称の発行部数は194万部とされています。発行元はサンケイ新聞社。
2011.02.25
コメント(10)
-
チュニジアからエジプトへ…(27)
チュニジアからエジプトへ…(27)リビア西部でも、正規軍のカダフィ離反が相次ぎ、トリポリ周辺の諸都市で、次々反政府派の覇権が確立しているようです。首都から100~200km圏と言いますから、丁度、小田原や静岡、宇都宮、水戸といった一帯が、革命派の手に落ちたことになります。私自身は、カダフィの狂気に、1989年12月、東欧革命の年の最後を彩ったルーマニアのチャウシェスク体制の崩壊を、重ね合わせています。折りしもカダフィの娘が、マルタへの亡命を企てて、着陸を拒否されたという情報も入りました。本人は、自宅前で報道を否定したということですが、火のないところに煙は立ちません。独裁者家族の右往左往する慌て振りが想像できる逸話です。カダフィは、なお彼に忠誠を誓う親衛隊(傭兵部隊)に、首都に通じる道路を閉鎖させて、トリポリ市内で、反対派の大量粛清を進めているのでしょうが、周辺を固めた革命派が、首都への反撃を開始したらどうなるでしょうか。傭兵部隊は、人材派遣会社から派遣されています。特に質の高い将校は、おいそれと確保できません。彼らは契約の手前、あるところまでは頑張るでしょうが、そこから先については、契約にないとして、危地を脱出して逃げ出す訓練も受けています。難民主体の兵士は置いていかれるでしょうが、上官を失った彼らは、戦意をなくして降伏するか、武器を捨てて逃げ出すでしょう。カダフィ政権は、長くは持たないでしょう。リビアの問題はその後に来ます。リビアは、アルジェリアのように、長い独立闘争を戦い抜いて、150万人を越える犠牲者まで出す血みどろの戦いを経て、フランスからの独立を達成したアルジェリアのような経験を持ちません。また、エジプトのような高い教養を持つエリート軍人の層も、持っていません。リビアにあるのは、アフガニスタンのような部族社会です。そうなんです。リビアは砂漠の民、ベドウインの世界でした。今でも各地の部族長が一定の力を持つ世界です。カダフィは、こうした部族の首長の支持の下に独裁体制を築き、やがては独裁的強権によって、不満を抑え込み、一定の安定を保ってきました。カダフィという独裁者のいないリビアは、当然四分五裂します。部族連合政権が上手く機能するためには、部族間の経済的並びに政治的利害が一致することが必要ですが、(25)で指摘したように、元油は東部で産出し、西部にはありません。カダフィは、この元油収入を、ほとんど西部の経済発展に投下し、東部は貧しいままに放置されてきました。ここから想像できることは、今度は油田を抱える東部が、西部の要求を拒否することです。これで平和が保てるでしょうか。強力な独裁者がいなくなったリビアで、部族間紛争による内戦が続く事態が予測できます。国際消費市場での元油価格の上昇は、当分続く可能性が高いかもしれません。 続く
2011.02.24
コメント(10)
-
フランス 二月革命成る 24日の日記
クロニクル フランス二月革命成る1848年2月24日163年前ですね。この9年後に黒船がやってきました。この日、前々日22日に本格化した、革命派の動きはさらに高まり、軍部も離反して孤立無援の状態になった国王ルイ・フィリップは、遂に退位を決断、辛うじて馬車での亡命を許されました。2日間、蜂起した民衆の退位要求に応えず、軍による鎮圧を目指したのですが、そうした行動が火に油を投じて、民衆の怒りを増幅してしまい、結果として亡命せざるをえないことになりました。18年前の1830年7月の革命で、国民の歓呼の声に迎えられて、市民王と親しまれ、立憲君主として王位に就いたルイ・フィリップも、18年間の国王生活を通じて、次第に民意に鈍感な国王に変貌してしまった、その成れの果ての姿でした。長すぎる施政は、腐敗と堕落を生み、結果として民の声に疎くなる。そのサンプルの1つがここにもありました。
2011.02.24
コメント(4)
-
チュニジアからエジプトへ…(26)
チュニジアからエジプトへ…(26)政府要人の反カダフィ陣営入りも続き、ベンガジを中心とするリビア東部は完全に反カダフィ派の支配下に入ったようですね。これに対して、トリポリでは、カダフィ一派に動員された人たちのデモが中心街に繰り出しているとの情報もあります。今のところ、リビア西部の様子はなお混沌としているようです。カダフィ一派は、独裁者の本領をあらわにして、反旗を翻した民衆は人間として扱う必要がないと、言っているようです。そのやっていることは、イラクやアフガンで、米軍兵士がやっていることと同じですが、施政者が国民を相手に実行している点が、決定的に違っています。イラクやアフガンで、そしてイラクやアフガンの人たちを同胞と考えるイスラム世界で、倍軍が嫌われ者になっているのは、このためですし、住民がゲリラの味方はしても、米軍の味方にならないのは、このためです。デモ隊に対する殺戮をほしいままにしたリビア民衆は、カダフィやその一派をどう受け止めるでしょうか。当然、米軍に対する憎しみ以上に強い憎しみを、カダフィ一派に対して抱いているに違いありません。狂気に取り付かれた独裁者、長期政権で政治的感度を錆び付かせてしまった独裁者の支配が、長く続くことはありえません。問題はリビア軍部の力量です。エジプト軍と違って、リビア軍部には、権力にしがみつくカダフィに引導を渡すほどの、力量がないことにあります。そのためカダフィは、傭兵で固めた大統領親衛隊を頼りに居座りを策しています。トリポリを中心とした西部の民衆が、カダフィー打倒に立ち上がり、それに呼応する形で、東部に結集したリビア世紀軍が、トリポリに向かって進撃を開始するとなると、ことは内戦にならざるをえません。内戦は不可避なのか、何とか回避されるのか。ギリギリの緊張は刻一刻と高まってきている気がします。そしてこの事態は、世界経済にとっても、大きなマイナスの要因となります。 続く
2011.02.23
コメント(6)
-
荒川静香選手金メダル獲得 23日の日記
クロニクル 荒川静香選手金メダル獲得2006(平成18)年2月23日あれから5年ですか。荒川選手のイナバウアー、有名になりましたね。そうなんです。トリノ・オリンピックの女子フィギュアで、荒川選手が1位となり、男女を通じてフィギュアスケートで、最初の金メタルを獲得しました。荒川選手の凄い所は、この時のスコア(得点)が、彼女のフィギュア人生での最高得点だったことです。あの大舞台で、生涯最高の演技を披露した。その精神力は素晴らしいですね。ここから、日本のフィギュアスケート界、男女共に活気づいていますね。
2011.02.23
コメント(12)
-
チュニジアからエジプトへ…(25)
チュニジアからエジプトへ…(25)そしてバーレーン、リビアへチュニジアからエジプトに拡大したアラブ革命の狼煙は、イエメンからバーレーン、リビアへと広がりました。エジプトほどには、イスラエル寄りではないリビアで、内戦状態と表現されるほどに、革命の火が燃えさかるとは、自分の迂闊さに腹を立てているところです。とりあえず、緊迫度の高いリビアのことを先に記します。リビアの革命の発火点は、東部のベンガジでした。そしてリビアの油田は、この東部に集中しています。リビアの独裁者カダフィは、首都トリポリを核とする西部の出身です。政権を掌握したカダフィは、東部の油田から得られる収入の大半を、自らの出身地である西部地域に投じて、東部地域を貧しいままに放置して来ました。それゆえ、1969年の政権掌握後40年を越えるカダフィ独裁の下で、東部は何度も反旗を翻し、その都度鎮圧されてきました。そして今回、2月15日に始まった東部の決起は、東部地域の民衆蜂起に対する備えとして派遣されていた軍部を巻き込み、油田地帯を含む東部地帯の支配権を握るまでになっています。従来とは様子が違ってきています。西部のトリポリでも、職のない若者中心にハンカダフィの動きが広まり、出動命令を受けた空軍による、市民に対する空爆が行なわれるという、事実上の内戦状態に立ち至っています。チュニジアやエジプトにはなかった事態が起きているのです。これには、チュニジアやエジプトにはなかった2つの事情が絡んでいます。1つは前述した西部と東部の対立です。リビアは基本的に部族社会が強固に残っています。しかも東部にしかない油田から得られる収入のほとんどを我が物としてきた西部が、油田収入の全てを東部に取り戻されて、黙って引き下がるとは考えられないことです。ここにカダフィ政権側の付け入る隙が残っています。そして二つ目は、カダフィの親衛隊は、リビアの正規軍ではなく、豊富な原油収入の一部を使って、彼が高給で雇い入れた傭兵部隊だという事実です。各地で情け容赦なく、リビア民衆を銃撃したり空爆したりと、殺戮をほしいままにしているのは、この傭兵部隊(=外人部隊)なのです。こうした事実に反発した正規軍部隊は、次々に反カダフィの陣営に移っているようですが、装備の点で最も優れているのは、カダフィ親衛隊の傭兵部隊なのです。しかもその傭兵部隊にとって、雇い主であるカダフィの失脚は、自分たちの失職を意味します。リビアは厄介なお荷物を抱えているのです。そしてカダフィは、最近はおとなしくなっていたとはいえ、反米、反イスラエルの立場を堅持してきました。ですから、欧米から何を言われても馬耳東風でいられます。従って、最悪の場合、リビアは長い内線に突入することも、ないとはいえない状況にあると言えます。平然と民衆の殺戮を命じる独裁者、その命令を忠実に実行する大統領親衛隊という名の傭兵部隊、彼等に対するリビア正規軍と部族社会の怒りの大波がカダフィ一派を、ここ数日のうちに飲み込まない限り、リビアは大変なことになりそうです。 続く
2011.02.22
コメント(10)
-
吉野ヶ里遺跡 22日
クロニクル 吉野ヶ里遺跡1989(平成元)年2月22日昭和が平成に切り替わったばかりの時でした。22年前です。来月には、初めて平成生まれの大卒が誕生するという事実が、分りますね。そんな22年前の今日、佐賀県の吉野ヶ里遺跡で、国内最大級の弥生時代後期の環濠集落が発見されました。スワ卑弥呼の邪馬台国かと、大きな話題になりましたね。邪馬台国論争は、永遠の謎、永遠のロマンであってほしい、この頃はそんな気がしています。
2011.02.22
コメント(18)
-
チュニジアからエジプトへ…(24)
チュニジアからエジプトへ…(24)スエズ運河を航行する船舶は、「スエズ運河会社」に航行を申し出。許可を得ることが必要です。そして「スエズ運河会社」はエジプト政府の方針に従い、経済封鎖対象国の船舶や、エジプトと対抗関係にある国の艦船については、政府の許可がない限り、航行許可を出さないのが通例でした。こうしたいきさつから、イラン革命後に、イラン海軍の艦船がスエズ運河を航行したことは、1度もなかったのです。サダト時代は、イラン・イラク戦争と重なっていましたから、エジプト政府は当然のこととして、ペルシア帝国の末裔ともいえるイランではなく、アラブ世界に属するイラクを支持していました。そしてムバラク時代になると、親米路線を堅持しましたから、当然親イスラエルの路線が採られ、イラン敵視政策が続けられましたので、イラン艦船のスエズ運河航行が、許可されることはなかったのです。それがどうでしょう。ムバラク退陣から僅かに1週間で、見事に覆されたのです。イランのメディアは、1月26日に「イラン海軍の士官候補生たちが、1年間の訓練のために、スエズ運河を通過して地中海に向かう」、「彼らは、イランの船舶をソマリアの海賊から守るための訓練に参加する」と報じていました。この報道に敏感に反応したのがイスラエルでした。イランの艦船が、レバノンのヒズボラ向けの武器を、大量に積んでいるのではないかと、騒ぎ出したのです。こうしたイスラエルの過剰反応に対し、2月12日に政権掌握を発表したエジプトの軍評議会は、極めて冷静でした。エジプト外務省は、17日に、イランの艦艇2艘がスエズ運河の通過申請を提出している事実を明らかにした上で、「通過を認めるか否かは、国防相が最終判断することになっている」と発表しました。そして翌日18日には、「エジプト政府は、イラン艦艇のスエズ運河通過を認める」と発表したのです。エジプト新政権が、これまでに締結された国際条約を遵守する旨を宣言したからといって、従来のような米国の思い通りに動く、傀儡のような政府であり続けることは、国民との関係からして、もはやありえないのです。イラン艦艇のスエズ運河の航行許可が、あっさりと認められたことは、エジプトの新政府が、もはやイランを脅威と受け止めていないことを示しています。この点で、米・イスラエルのイラン封じ込め戦術は、トルコの離反に続いて、ここでも破綻したのです。イスラエルの慌て振りが眼に見えるようですが、イスラエルの政治指導者や軍幹部には、昭和前期の日本の指導層に近い好戦派が揃っているだけに、第5次中東戦争勃発の危険性が、高まってきているように感じられます。要注意ですね。 続く
2011.02.21
コメント(6)
-
東京日日新聞創刊 21日の日記
クロニクル 東京日日新聞創刊1872(明治5)年2月21日139年前の今日、今日の毎日新聞の前身、「東京日日新聞」が、東京で最初の日刊新聞として、創刊されました。事実上日本最古の日刊新聞が、この日誕生しました。やがて、関西系の「大阪毎日新聞」と合併し、次第に全国紙の体裁を整えて行くのですが、毎日新聞としての新聞の発行は、1943(昭和18)年の1月1日号からです。出発は、朝日や読売よりも10年以上早かったのですね。
2011.02.21
コメント(16)
-
チュニジアからエジプトへ…(23)
チュニジアからエジプトへ…(23)ムバラク体制に、最終的に引導を渡したエジプト軍部の思考と行動にも目が離せません。憲法改正を焦点とする、政権の行方を占う点では、革命の引き金を引いた若い世代よりの対応が目立ちます。そしてもう一つの焦点は、ムバラク以後のエジプトの外交政策の方向にあります。エジプト革命が始まり、ムバラク政権の延命が難しそうなことがわかってからというもの、オバマ政権は、米国にとって30年来の盟友であった、ムバラク政権を見捨ててまで、エジプト新政権が親米政権であり続けることに、期待を寄せています。2月10日、ムバラク大統領が辞任を拒否する演説をした直後にオバマ大統領がエジプト情勢について発表した声明には、エジプト国民に向けたこんな一文があります。大統領は、エジプト国民よりの姿勢を鮮明にして、ムバラク大統領に辞任を迫った後、エジプト国民を讃え、さらに「エジプトの皆さんは、いつまでもアメリカ合衆国が、皆さんの友人であり続けるということを、知っているべきです。」オバマ政権は、今後のエジプト政権の一翼を担うであろう反政府勢力に、秋波を送り、米国との関係を維持するように求め、対話を始める用意のあることを、表明していることが、この声明から読み取れます。サダト大統領は、キャンプデービットでイスラエルとの平和条約を結んで、シナイ半島を取り返しました。そのサダト大統領の暗殺後に登場したのが、ムバラク政権でした。ムバラク政権は、その30年に及んだ支配の間、イスラエルとの平和条約を揺らぐことなく維持してきました。これは、イスラエルにとって大きなことでした。この30年の間、イスラエルは、エジプトの脅威を意識することなく、シリアやイラク、そしてパレスティナやレバノンに対置することが出来たのです。イスラエルは、エジプトとの戦争はもうないという前提で、安全保障政策を構築してきたのです。エジプト新政府が、イスラエルとの平和条約を見直すのであれば、』イスラエルの安全を巡る環境は激変します。米国とイスラエルは、このことを畏れて、24時間体制で、エジプト情勢を見守っていました。2月12日、政権を掌握した軍部が、従来からの国際関係を維持する、国際条約は変わらず遵守すると発表したことで、欧州や日本を含め、米国、イスラエル寄りの国々は、一葉に安堵のコメントを流しました。しかし、イラン海軍の練習船のスエズ運河航行問題で、状況はガラリと変わりつつあります。変化は日々に続いています。 続く
2011.02.20
コメント(4)
-
大阪ドーム完成 20日の日記
クロニクル 大阪ドーム完成1997(平成9)年2月20日14年前になるのですね。この日大阪ドームが、大阪市西区に完成しました。東京ドーム、福岡ドームに続く、日本で3番目のドーム球場の誕生でした。97年のプロ野球、丁度南の地方でのオープン戦が間もなく始まろうという頃でした。大阪ガスの工場跡地に、94年7月に着工し、この日完成を見ました。ドームは近鉄バッファローズの本拠地として建設され、3月1日に正式にオープンしましたが、近鉄球団が2004年のシーズン終了後、近鉄球団がオリックス球団に吸収合併されることになり、2005年からはオリックス・バッファローズの本拠地となりました。なお、現在の球場名は、命名権の売却により、京セラドーム大阪となっています。
2011.02.20
コメント(14)
-
チュニジアからエジプトへ…(22)
チュニジアからエジプトへ…(22)現在のエジプトでは、軍評議会が暫定的に権力を握っています。表面的には内閣がありますが、この内閣の役割は、敗戦後すぐの時期の日本の内閣のようなもので、実質的な権力主体はGHQにありました。同じように現在のエジプトは、軍評議会の意向に従って、内閣が動いていると言えましょう。その軍は、制定する憲法について、大規模デモを組織して、ムバラク政権や治安警察のウラを掻くことに成功した若者連合と、何度もの会合をもって、彼らの意向を取り入れる積りのように見えます。そして、大統領選に就いては、軍部から候補を出さないことも表明しています。一方で、穏健なムスリム原理主義の道を歩むムスリム同胞団も、候補を出さない旨をひょうめいしています。エジプト国内で、支持基盤の広い、2つの勢力が候補を出さない形で、果たして実力ある政権が組織できるのか否かは、大変興味あるところです。一方で、軍は既成政党の代表を重視する姿勢は見せておりません。国際原子力機関(IEA)前事務局長として、世界的に名を知られたエルパラダイ氏も、軍部には無視された形です。軍は、若者達を引き立てる積りなのでしょうか。それとも何か別の狙いがあるのでしょうか。そしてまた、米国やイスラエルの今後の動きはどうなのでしょうか。 続く
2011.02.19
コメント(2)
-
大浦天主堂完成 19日の日記
クロニクル 大浦天主堂完成1865年2月19日(元治2年1月24日)146年前のことです。時期は幕末。3年後が明治維新。この日、長崎に大浦天主堂が完成しました。現存するキリスト教の建造物としては、日本で最古のものです。正式名称を日本二十六聖殉教者堂と言います。その名の通り、二十六聖人に捧げられた教会堂です。そのため御堂は殉教地の西坂の方向を向いて、建てられています。長崎市への原爆投下で被爆し、破損したのですがが、爆心地から比較的離れていたために焼失は免れました。戦後の復興と共に修理が行なわれ、1952年に修理が済み、翌1953年3月31日に国宝に指定されました。大浦天主堂の建築は、フランスのカトリック教会の外国宣教部日本支部が、資金と設計を担当し、長崎の棟梁の手で行なわれました。宣教師たちの狙いは、「外国に対して開かれていた長崎周辺には、密かに信仰を伝えるカトリックの信徒が残っているのではないか。そうした信徒を見つけ出したい」という1点にありました。宣教師たちの期待は、御堂の完成から1ヶ月後の3月17日に現実のものとなります。この日近在の住民10数名が、教会に赴任したブディシャン神父を訪ね、自分たちが神父と同じ信仰を持つことを、告白したのです。信者たちは、御堂に聖母像があること、神父が独身であることから、御堂がカトリックの教会であることを確信し、この日の訪問となったのでした。やがて、長崎周辺の各地で多くのカトリックの信徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことがわかります。天主堂の建設は、大きな成果を生んだのです。この「信徒発見」のニュースは、喜ばしき大ニュースとして、ローマ教皇ピウス9世のもとに届けられます。教皇は感激して、「東洋の奇蹟」と叫んだと記録されています。
2011.02.19
コメント(6)
-
チュニジアからエジプトへ…(21)
チュニジアからエジプトへ…(21)こうしてムバラクは、軍部に詰め腹を切らされる形で、辞任を表明しました。ドラクロワの「民衆を率いる自由の女神」でお馴染みの、1830年7月のフランスの七月革命は、栄光の3日間と称されるように、7月27日~29日の3日間で決着のついた革命ですが、革命派の要求した内閣の交代を、国王シャルル10世が渋ったために、彼は全てを失って亡命する破目になりました。28日の午前中までに、内閣の更迭と革命派による組閣に踏み切っていれば、彼が立憲君主の地位に留まることは、情勢からいって不可能ではなかったのです。読みの甘さが命取りでした。ムバラクもまた、閣僚の一部更迭や副大統領職の復活などの手は打ちましたが、この時点で名誉ある辞任に踏み切らなかったことが、晩節を汚すことに繋がりました。さて、ムバラクを辞任に追い込んだ軍部の、その後の動きは早かったですね。25日のデモを成功に導いた若者たちの動き同様、こちらも見事なものでした。おそらく、1月末以降、何度もムバラク辞任後の姿をシュミレーションして、軍幹部の意志を統一していたのでしょうね。遅くも、「大統領支持派」をタハリール広場から一掃した頃には、ムバラク辞任不可避で一致していなければ、あの素早い行動はありえないでしょう。タハリール広場を埋め尽くした若者を含む群集が、勝利の美酒に酔っている間に、暫定政権の方針が7ヵ条として打ち出されたのです。そこに書かれたおよその内容は、既に指摘しました。新憲法に基づく民主的選挙で、新政権が誕生するまで、軍指導部が暫定政権を担う旨が、ここに表明されました。軍は先手を打ったのです。この点も、七月革命派の勝利が決まった7月29日夜に、勝利に酔いしれる民衆を横目に、徹夜でオルレアン公ルイ・フィリップの王位就任を待望するビラを印刷し、パリの街中に掲示したオルレアン派の勝利に、相通じていました。 続く
2011.02.18
コメント(4)
-
札幌雪祭り始まる 18日の日記
クロニクル 札幌雪祭り始まる1950(昭和25)年2月18日北海道のブログ仲間の皆さんが、道内各地の雪祭りの写真をアップしてくれています。おかげで、雪国の祭りの雰囲気を、いながらにして味わわせていただいています。そんな北の国の雪祭りの始まりの話です。61年前ですね。昭和25年の日本は、戦後の悪性インフレ対策として提案された、シャウプ勧告を実施して、深刻なデフレに耐え初めていた頃です。朝鮮戦争の特需景気が神風となって、奇跡的ペースで復興が軌道に乗り始めるのは、この1年4ヵ月も後のことですから。この年、道民を元気付け、観光客の誘致につなげようと、札幌観光協会と札幌市が主催して、「第1回札幌雪祭り」が開かれました。今日がその初日でした。アイデアを出したのは、後援団体に名を連ねた「北海タイムス」の編集局だったそうです。戦前の札幌には、いくつかの雪の祭典があったようですが、戦争中に全て途絶えました。この第1回の雪祭りでは、市民の雪捨て場となっていた大通公園の西7丁目に、札幌市内の中学校や高等学校の生徒たちが合わせて6基の雪像を制作しました。。また、雪祭りに合わせて、札幌鉄道管理局が国鉄の札幌駅前に雪像を作って展示しています。祭りは好評で、市民たちから、来年以降も継続して欲しいという要望が相次ぎ、今日に続くことになったのですね。「北海タイムス」さんの大ヒットでした。
2011.02.18
コメント(8)
-
チュニジアからエジプトへ…(20)
チュニジアからエジプトへ…(20) 1月25日のデモ発生当初から、反体制派はタハリール(解放)広場の制圧に成功しました。カイロの中心部、日本に例えると霞ヶ関の中央に位置する広場を反体制派が制圧したのです。当初の数日間は、治安機関が出動していましたが、やがて彼らは姿を消します。治安機関の隊員の多くは、一部幹部を含めて下層階級の出身です。彼らは公安警察官としての任務を教え込まれる過程で、学生や大卒のエリートに対する徹底した憎悪の感情を叩き込まれます。ですから、彼らは広場に集結したデモ隊が、いつものように社会のエリートを中心とした人々で埋め尽くされていたのなら、例え数が多くても、躊躇なく至近距離から催涙弾を打ち込むなどして、暴力的に排除することをためらわなかったでしょう。その結果が失敗に終ったとしてもです。しかし、タハリール広場に集まった人々の多くは、彼らと出自を同じくする下層の貧しく人々でした。それを知ったヒラの隊員たちには、大きな動揺が走ります。貧しき者同士の紐帯が作用して、彼らは上官による暴力の行使命令をためらいました。これが、治安機関の行動を中途半端なものにした原因だったように思います。ムバラクやその側近たちは、忠誠心を示す治安機関員を私服に着替えかせ、彼らとムバラク政権に寄生して利益を得ていた人々、さらには金で集めた烏合の衆を動員して、大統領支持派をでっち上げ、タハリール広場の反体制派を襲撃する行動にでました。これが最終的に、ムバラク一派の命取りとなりました。子飼いの治安機関員でさえ、一致団結した鎮圧行動が取れない状況にある時に、暴力的鎮圧はもはや不可能です。それにも関わらず力で圧殺しようと試みることは、なお形勢を見ていた人たちを、決定的に反体制派支持に向かわせる効果しか持たないからです。この点は、歴史を紐解けばいくらでも史実を挙げることが出来ます。程なく、ムバラク政権を見限った軍が登場し、烏合の衆に過ぎなかった大統領派を排除します。2月上旬のことでした。ここから2月11日(日本時間12日)までの動きは、ムバラク前大統領への惻隠の情を持つ軍指導部が、彼の自発的辞任を促し、そのリミットに指定した11日まで、説得を続けたということだったようです。勝負の行方は、1月25日のデモ隊が、広いタハリール広場を埋め尽くした段階で、はっきりしていたのかもしれません。 続く
2011.02.17
コメント(12)
-
ロシア宮殿爆破事件 17日の日記
クロニクル ロシア宮殿爆破事件1880(明治13)年2月17日131年前の今日のことです。当時のロシア帝国の首都ペテルスブルグで、今で言う過激派による宮殿の爆破事件が起きました。それも皇帝一家が食事をされる、宮殿内の食事の間が爆破されたのですから、大変センセーショナルな事件として、世界的な話題となり、日本でも大きく取り上げられました。当時のロシアは、ツアーリ(皇帝)による独裁体制の下で、欧米諸国に追いつき追い越せとばかりに、工業化=資本主義化が進められていたのですが、その結果貧富の差が広がり、貧困層の不満が多いに高まっていた頃です。この頃のロシアの反体制派の主力は、農民を主力とした社会主義を掲げるナロードニキと呼ばれるグループでしたが、この派は権力による徹底的な弾圧を受けて、組織的には崩壊寸前に追い込まれていました。コノグループの一部が過激化し、皇帝を暗殺して、そのどさくさに乗じて、革命を成し遂げようと考えたのです。「人民の意志」党を名乗ったこのグループは、「皇帝アレクサンドル2世の死刑宣言」を発表して、ツアーリ暗殺を宣言、厳しい弾圧を受けたのですが、仲間の1人で、腕の良い指物師だったハルトゥーリンが、偽名で宮廷の指物師として採用されたのです。腕が良くしかも実直なハルトゥーリンは、宮廷の担当者に信用され、冬宮(殿)の地下室に住み込むことを許されます。こうして宮殿にもぐりこんだ彼は、調査を続け、皇帝が来客と共に食卓につく、食堂の位置を特定します。こうして彼は、外出のたびに、道具箱にダイナマイトを潜ませては、地下室に持ち帰りました。こうした準備の据えに、彼は131年前の今日、来客と昼食を共にするという情報を掴んだのです。食堂の下部にダイナマイトを仕掛け、長い導火線に火をつけてから、ハルトゥーリンは悠々と冬宮から脱出します。食堂は過たず爆破されました。5人の死者と58人もの負傷者も出ました。しかし、皇帝は難を逃れました。一緒に食事をする来客の到着が遅れたため、まだ食堂に姿を見せていなかったのです。こうして暗殺は未遂に終りました。しかし、世界は「人民の意志」党の名を、記憶することになりました。
2011.02.17
コメント(4)
-
チュニジアからエジプトへ…(19)
チュニジアからエジプトへ…(19)20ヶ所を公開して1ヶ所を秘密にしただけではありません。治安機関がネット情報をチェックしていること、発信者も特定されているだろうことを、予測した若者達は、メールの情報交換に登場しないメンバーたちによって、数日に渡ってデモのシュミレーションを行い、予測しうるさまざまなケースについての、検証を行なったのです。秘密地点でデモが始まった場合、どのくらいのスピードで、20もの地点に散らばった治安部隊が到着するか。治安部隊の到着以前に、デモ隊が集合地点を離れるには、どのくらいのスピードで動き出す必要があるのか。どのくらいの時間で、集まってきた群衆をデモに加えて、制御不可能な大きな流れとすることが出来るか。さらには、治安部隊の移動で手薄になった20の地点に、いわばおとりとして集まった人たちは、いつ頃動き出すことにするか。こうしたことが、ひっそりと準備されたのです。こうした綿密な計画を立てた上で、運命の25日がやってきました。この日、治安機関はデモ側の予測どおり、公開された20ヶ所の地点に分散配置され、デモを封じ込める体制を敷きました。この20の地点にもデモ参加者は集まってきましたが、あらかじめ耳打ちされていたメンバーは、これらの地点には赴かずに、秘匿されていた21ヶ所目の地点に集合したのです。こうして、治安警察が全く無警戒だった21ヶ所目の地点に、突如300名のデモ隊が登場したのです。この日革命が始まると聞かされ、それを待ち望んでいた貧民窟の住民たちが、続々とデモ隊に加わります。こうして瞬時にして、数千人のデモ隊が出来上がり、さらに10分もするうちには、数万人のデモにまで増殖したのです。不意を突かれた治安機関は、すぐにデモ地点への移動を各所に流したのですが、既に奔流の如くに勢いを増していたデモ隊を、制御することはもはや不可能だったです。こうして秘匿場所からのデモ隊は、無傷でタハリール広場に到着したのです。続いて、治安部隊の移動で、警戒の緩んだ20の地点に結集した若者達も、周辺の労働者や貧民たちを加えて、雪だるま式に増殖しながら、次々にタハリール広場にやってきました。その規模は、治安機関にコントロール不可能を悟らせるに、十分な規模を、はるかに超えていたのです。普段はデモに参加しない貧しき住民たちの動員に成功したこと、これが今回の成功の鍵となったのです。若者達の行動力、知力には、侮りがたいものがあるように思います。
2011.02.16
コメント(6)
-
北海道拓殖銀行(拓銀)創立 16日の日記
クロニクル 北海道拓殖銀行(拓銀)創立1900(明治33)年2月16日111年前の今日、北海道拓殖銀行が「特殊銀行」として、創立されました。特殊銀行というのは、戦前の日本で、長期にわたる設備投資や対外貿易上の必要や、植民地政策上の必要などから、一般の普通銀行とは別の法律に基いて設立された政府系金融機関です。具体的には、重化学産業振興を担う日本興業銀行(興銀)、植民地に設立された台湾銀行や朝鮮銀行、そして北海道開拓を経済面で援助する拓銀などが、これにあたります。雪深い2月中旬に設立されたというのが、いかにも北海道開拓への貢献を期待された拓銀らしいですね。こうした特殊銀行は、債券(金融債、1年満期の割引債と5年満期の利付き債がありました)を発行して資金を調達し、長期の投融資を行いました。こうして拓銀は、北海道開拓に大きく貢献したのですが、戦後になって、所期の役割は達したとして、普通銀行に転換します。この時、長期金融部門は切り離され、日本長期新銀行に移されました。普通銀行となった拓銀は、その後昭和の経済成長の波に乗り、北海道の経済発展に大きく貢献し、「拓銀さん」と親しまれたのですが、バブル期に幹部が経営の舵取りを間違え、1997年に破綻に至ったことは、御存知の通りです。
2011.02.16
コメント(20)
-
チュニジアからエジプトへ…(18)
チュニジアからエジプトへ…(18)エジプト革命の発端となった反政府デモを組織したのは、若者達のグループでした。30歳以下の年齢層の多い国では、若者のエネルギーが、しばしば社会変革の起爆剤となります。60年安保から全共闘運動までの60年代の日本もまさにそうでした。79年の朴正熙大統領暗殺前後の韓国もまた似たような状況にありましたし、天安門事件(1989年)当時の中国も同じでした。現在のエジプトは、まさにその状態にあります。かくして若者を主役とした反政府デモが大きなうねりとなって噴出しました。彼らの計画した1月25日のデモは、何故成功したのかを見たいと思います。エジプトの治安機関は、デモや暴動の鎮圧には、相当の自信をもっています。過去に何度もこうした反政府運動を封じ込めてもいます。その治安機関が、今回は何故封じ込めに失敗したのでしょうか。ここに問題の鍵があります。どうやら若者達は、作戦を練りに練り、治安機関の裏をかく巧妙な戦術をとったようです。以下は、ウオールストリート・ジャーナル(以下WSJ)が、メンバーの1人にインタビューした記事です。若者達は、先ずバラバラな自分たちの組織を大同団結させることからはじめ、相異なる6つの組織の連合体を作ります。反体制各派の政治組織、労働団体、そしてムスリム同胞団など、6派の青年部が、10日頃から連日代表者会議を開いて、「革命青年運動」(仮称)という連合体をまとめ、綿密に戦術を練りました。彼らは、デモ決行日を25日と定め、その日に向けて21ヶ所のデモのスタート地点、即ち集合場所を決めました。選ばれたのは、主に労働者階級が密集して住む地域のモスクのある場所でした。同時多発的な大型デモを組織することで、治安機関の警備を分散させ、、カイロ中心部のタハリール広場まで、突っ走ろうという計画でした。彼らの計画の優れていた点は、この21ヶ所の集合地点のうち、なんと20ヶ所をインターネットを通じて、事前に明らかにしたことです。25日はエジプトの祝日でした。彼らは最後の1ヶ所の地点を秘密にしていたのです。治安当局は、20ヶ所もの地点に集合するというインターネットの開催予告に、眼を剥きます。今までこれほ沢山の場所で、同時多発デモが組織されたことなどなかったからです。公表された開催地が3ヶ所とか5ヶ所であれば、治安機関もより慎重になったかもしれません。20ヶ所もの公表が、まんまと治安機関のウラをかくことに繋がったのです。若者達やりますねぇ。公表しなかった21ヶ所目の開催地点は、カイロ市内でも指折りの貧民地区で、住民はインターネットや携帯電話とは、全く縁のない人たちでした。青年グループはネットで予告した次の日から、入れ替わり立ち替わり現地に足を運び、絵入りのビラとクチコミで、住民にデモへの参加を呼びかけたのです。インタビューに応じた若者は、「1月25日に革命が始まるという印象を、もって貰うことが目的だった」と語っています。彼らの計画はこれで終ったわけではありません。まだ続きがあります。 続く
2011.02.15
コメント(8)
-
さよなら日劇 15日の日記
クロニクル さよなら日劇1981(昭和56)年2月15日丁度、今年が30年の節目にあたるのですね。1933(昭和8)年に竣工、同年のクリスマスイヴに、盛大な開館披露でオープンした日劇は、入場人員4千人という、当時としてはケタ外れの大劇場でした。日劇は、大空襲でも焼失を免れ、GHQの接収もかいくぐり(所有者の東宝は、東京宝塚劇場を提供して、日劇の接収を免れたそうです)、この日あで、48年の間、芸能人の登竜門の役割を果たしてきました。しかし、老朽化が激しく、他に日劇を凌ぐ大劇場も誕生したことなどから、取り壊しが決まり、この年1月28日から2月15日までの「サヨナラ日劇フェスティバル」を最後に、取り壊されることになりました。跡地に建設されたのが、有楽町マリオンです。
2011.02.15
コメント(6)
-
チュニジアからエジプトへ…(17)
チュニジアからエジプトへ…(17)ムバラク辞任後の様子を見ると、前大統領ムバラクは、軍部に辞任を迫られ進退に窮したというのが、真相に近いようですね。自ら辞任したのではなく、解任という不名誉を避けるために、自ら辞任することを選んだのでしょうね。前内相外、彼の腹心は、いずれも出国を禁じられ、事実上軟禁状態に置かれているようです。辞任を表明したムバラクが、権限を委任したのは、腹心の副大統領スレイマンではなく、軍評議会という軍の最高機関でした。個人ではなく軍幹部会という集団に委任することは、自らの処遇がどうなるかも定かでないということになります。事実、ムバラク自身も出国を禁止され、スレイマンにいたっては、その消息すら明らかにされていません。おそらく、彼もどこかで身柄を拘束されているのでしょう。さて、その軍評議会ですが、権力掌握後、矢継ぎ早に将来計画を発表しております。「新憲法は案作成後、ただちに国民投票で可否を決する」という項は、誰でも予測のつくことです。外交関係は、当面現状維持というのも、治安の維持と改革案の具体化までの暫定政権という立場からすれば、これも当然でしょう。私が、お!やるなと思ったのは、昨秋のインチキ選挙によって選ばれた議会を即時解散したことです。これでムバラク派は、よって立つ基盤を悉く奪われたことになります。残された課題は、非常事態宣言の解除と、全ての政治犯の釈放でしょう。サダト大統領の暗殺後に布告された非常事態が30年も続くということは、そもそもおかしなことです。30年も非常事態が続くというのは、その間内戦が継続したとでも言うのでなければ、説得力を持ちません。そして、もう1点、早期の治安回復によって、観光客を呼び戻すことが急務です。エジプトにとって、外国からの援助を除くと、2大収入は、スエズ運河の通行料と、観光収入です。ピラミッドやスフィンクスに代表される古代エジプト王国の遺跡は、現代人の想像力を掻き立て、古代史のロマンを夢想させる人気スポットです。治安の回復なくして、観光客の呼び戻しは不可能です。こうした発想が、軍部に革命派よりの路線を取らせているようですが、そのことの背後に、革命の主力勢力の構成の問題が、隠れているようです。明日はその点に踏み込んで見たいと思います。別件ですが、本日はe-taxソフトを使っての電子納税の書類を一気に仕上げました。宿題が1つ終って、明日からしばし伸び伸び出来ます。 続く
2011.02.14
コメント(10)
-
自動車保険事始 14日の日記
クロニクル 自動車保険事始1914(大正3)年2月14日最初にお断りしておきますが、これは日本のケースです。自動車の発明は、ドイツとフランスが先行して開発、アメリカで量産化に道を開きましたから、当然自動車保険も欧米が先行しています。日本では、97年前の今日、東京海上保険(4年後の1918年に東京海上火災保険へ名称変更)が、自動車保険の事業免許を取得し、営業認可を受けました。先見の明があったというべきでしょうが、この時期どのくらいの契約が取れたのでしょうね。因みに現在の「東京海上日動火災保険」の最大の主力商品は、海上保険で、取扱高はダントツの世界首位。トーキョー・マリンの名は、世界的に知られています。
2011.02.14
コメント(14)
-
チュニジアからエジプトへ…(16)
チュニジアからエジプトへ…(16)ムバラク辞任から、1日経ちました。この間に分かってきたことがあります。日本時間の11日(現地の10日夜)、ムバラクが辞任せずに大統領職に留まると発表した時、怒った民衆が一斉に靴を脱いで両手に掲げました。イラク戦争中に、イラク訪問中のブッシュが、聴衆から靴を投げつけられた事がありました。アラブ世界では、足に履く靴で頭を打つことは、最大の侮辱とされています。脱いだ靴を両手で掲げた姿は、民衆のムバラクに対するストレートな怒りの表現でした。そして、怒りに燃え脱いだ靴を掲げた大群衆は、ほとんど携帯電話など持たない、素手の人たちでした。ネット世界やケータイ電話は、やはりエジプト革命の主役ではなかったのだ。広場を埋め尽くした民衆の映像から、私はこの点を確認しました。1月25日、エジプトでデモの始まった当初、治安警察はデモの封じ込めに失敗しました。この謎がようやく解けました。若者の運動はかなり手が込んでいたようです。そして治安警察は、ネットやケータイで流れた情報はしっかり掴み、虱潰しの要領で、潰していたことも明らかになってきました。若者達や、隠れたデモの計画者は、治安警察の浦を掻きました。ネットで情報が流されると同時に、若者達は労働者街や貧民靴に散りました。そこで、彼らはケータイなど持たない人たちにビラを配り、さらにビラの内容を読み聞かせ、仲間たちへの連絡を依頼して歩いたのです。伝統的な、ビラとクチコミの人海戦術が、勝ちを占めたのです。そして後手に回った治安警察は、遂に最後まで劣勢を跳ね返すことが出来ず、親分のムバラクは、出身母体の軍からも見放されたと、概略を辿ると、事態はこういう経過で、進行したようです。 続く
2011.02.13
コメント(10)
-
平民にも苗字が 13日の日記
クロニクル 平民にも苗字が1875(明治8)年2月13日、明治は遠くなりにけりですね。もう136年前ですね。「沖のプリンター」の宣伝で、○○のという所属科の下に苗字を呼ばれ、「好きです」とか「支えたいです」とか囁かれている姓、全国的に苗字のベストテンに入るのだそうですが、中村さんとか、鈴木さんとか、斎藤さんといった姓が大量に登場したのが、この日のことでした。そうなんです。136年の今日まで、支配階級を除く平民には、名はありましたが姓はなかったのですね。「○○村の平吉」とか呼ばれるのはこのためです。この日、明治政府は、「平民苗字必称義務令」を布告、国内全戸に苗字をつけ、姓を名乗ることを命じたのです。許可したのではないことがミソですね。許可では全員が名乗るとは限りませんんで…
2011.02.13
コメント(12)
-
チュニジアからエジプトへ…(15)
チュニジアからエジプトへ…(15) エジプト時間の昨夜宵の口(日本時間本日未明)に、ムバラクが辞任しましたね。どうやら軍幹部に詰め腹を切らされたようです。予想外に展開は速かったですね。カイロのデモ以上に、各地に広がった労働者のゼネストの威力が大きかったようです。スエズ運河会社の従業員まで、ストに入りましたから、影響は甚大でした。何しろ運河がストップすると、国家としての収入減は、大変深刻ですから…。 今朝、この事実を知り、時間がありましたので、英語圏と仏語圏のニュースペーパーを拾い読みしてみたのですが、どこも連日1面のトップ記事がエジプト関連に当てられ、さらに3ページ、4ページと記事が続きます。知人に問い合わせた所、ニュース番組に占めるエジプト関連ニュースのウエートは、フランスでも4割、アメリカでは6割に昇るというのです。欧州は勿論、アメリカでの関心の高さは、想像以上でした。ムバラク失脚で、中東情勢がどうなるかに、注目が集まっているという所でしょう。ところで、ムバラクの退陣で事態は解決に向かうのかというと、そうはいえません。確かにムバラク政権に抗議の声を上げた人々は、目標の一つを達成しました。しかし、ムバラク退陣は、旧体制の象徴であるムバラクに焦点を当て、旧体制を一掃するためのスローガンとして掲げられた目標です。ムバラクは退陣した、しかし旧体制は温存されたという結果になったのでは、元も子もありません。まだ、旧体制を一掃するための運動は、最初の1歩を踏み出したに過ぎないのです。ここから、ムバラクなきムバラク派=旧体制死守派と反対派のせめぎあいが、本格的に始まります。激動の日々は、まだ始まったばかりですね。89年の天安門事件、同年秋の東欧諸革命以来の革命の年の本格化、20余年の歳月を経て、久し振りに血が騒ぐ日々を味わっています。というわけで、このところ、極めて元気です。 続く
2011.02.12
コメント(14)
-
バレンタインフェアの誕生 12日の日記
クロニクル バレンタインフェアの誕生1958(昭和33)年2月12日明後日14日がバレンタインデー。今やどこもかしこもバレンタイン商戦で賑やかですね。記憶が定かではありませんが、日本でバレンタインデーが賑うようになったのは、1980年代ではなかったでしょうか。当時から「チョコレートメーカーの陰謀ではないか」という説が、唱えられたりもしていましたが、それはどうやら事実だったようです。しかし、仕掛けの起源は、バレンタインデーがメジャーな存在になるはるか前でした。何しろ53年前ですから…。仕掛け人は、当時創業6年目の小さなチョコレート会社だった、メリーチョコレートの原堅太郎社長の次男、原邦生氏です。邦生氏は、入社を控えた大学4年生でしたが、パリ在住の先輩から、「バレンタインデーには、チョコレートに花を添えてカードを交換する」習慣があると聞き、当時出店が認められていた伊勢丹新宿店のコーナーに、この日2月12日から14日までの3日間、バレンタインフェアの看板を掲げたのです。しかし、当時の日本では、バレンタインデーを知る人もなく、初年度の試みは、見事な空振りに終ります。3日間の売り上げは、僅かに板チョコ3枚にカード1枚だったというのですから…。ここで邦生氏が挫折していたら、日本のバレンタインデーの今日の隆盛は、ありえなかったのでしょうね。成功する実業家というのは、失敗を糧に成長するというのは、本当ですね。邦生氏は、この失敗を糧に、翌年2月、今度は愛のイヴェントに相応しいハート型のチョコレートを考案し、表面にto~from~の文字を入れ、注文を受けたらその場で名前を入れて包装する作戦に出たのです。今では珍しくないハート型のチョコレートですが、初めて見る女性の足を止めるには十分すぎる効果がありました。まして名前まで彫ってくれるというのです。この試みは当りました。義理チョコという発想はなかったのですが、バレンタインデーとチョコレートというイベントは、新宿伊勢丹の地下売り場から、メリーチョコレートによって小さな灯を灯されたのでした。
2011.02.12
コメント(14)
-
チュニジアからエジプトへ…(14)
チュニジアからエジプトへ…(14) ここで、ムバラクに変わって、エジプト政府の事実上の代表を務めている副大統領のスレイマンの人物像を瞥見することにします。AFP通信の記事から知りえたことを記すことにします。彼は、1980年代はじめに、米国北カロライナ州にある、ジョン・F/ケネディ特殊戦センターで、テロ容疑者に対する尋問方法(具体的には、拷問による自白させる方法)を学び、帰国後に情報局長官に就任しました。以後アメリカは、自国やグアンタナモ基地で尋問し、自白させるのが憚られる人物については、密かにエジプトに移送し、スレイマンに尋問を委ねることになったというのです。その具体例も、AFP通信の記事は指摘しています。当時の米大統領ブッシュが、勝手にサダム・フセインのイラク攻撃を始めた時、パウエル国務長官が開戦すべき根拠として、国連に提出した証拠なるものは、スレイマンが尋問によって引き出した自白調書だというのです。尋問された人物は、イブン・シェイク・アル・リビ容疑者。彼は、サダム・フセインとアルカイダの繋がりを知る人物としてアメリカで拘留され、エジプトに護送されています。カイロで執拗な拷問を受けたリビは、イラク政府がアルカイダに対し、生物・化学兵器を提供する方向で動いていると自白しました。パウエルは、このリビの自白を詳細に説明して、イラクの持つ大量破壊兵器の発見と破棄を、開戦の根拠に据えました。しかし、リビ自身は、後にこの自白を「拷問によって、強制的に言わされた」として、撤回しています。ここから、スレイマンが、アメリカの忠実な同盟者として、アメリカの期待する通りの偽情報を作りあげたことが、理解できます。実際に、イラクには大量破壊兵器は、影も形もなかったことが、現在では明らかになっており、リビの自白が偽作であったことも明らかになっています。米国上院が、関係諸国に派遣した調査団の報告書が、2006年に上院に提出されていますが、そこにはっきりと、エジプト当局による拷問と、偽の自白の強要の事実が指摘されています。なお、米国が自国での拷問を避け、エジプト当局に尋問を委ねる人物についての、引渡しプログラムの存在については、スレイマンの果たした役割と共に、先般公表されて周知のこととなった、ウィキリークスのリークによって、疑問の余地なく明らかになっています。こうした面で、スレイマンは、アメリカにとっても、イスラエルにとっても、今のところいろいろな意味で都合の良い人物なのです。しかし、彼は野心家であり、情報局長官を長く勤めただけに、一筋縄でいかない人物でもあります。形勢如何によっては、大きく立場を替えることもありえます。その点で、今後の動きを予測することの、難しい人物でもあります。 続く
2011.02.11
コメント(6)
-
松竹キネマ設立 11日の日記
クロニクル 松竹キネマ設立1920(大正9)年2月11日今朝から、この地域にも初雪が降っています。新年になって、初めてのまとまったお湿りに、空気は冷えていますが、乾燥は和らぎ、些かホッとしているところです。いまのところ、地温が下がりきらないのか、まだ降り積もってはいませんが、降り止む気配もありませんから、明朝は雪かきが必要になるかもしれません。さて、91年前の話です。この日、当時の東京市京橋区の築地3丁目で、「松竹キネマ合名会社」が産声をあげました。これが現在の「松竹」の前身です。設立当日に、新聞紙上に大きな広告を出し、映画の製作と配給を行なう旨を発表するとともに、「2-3万坪の撮影所用地」と「人材」を求む旨を公示しました。実際に、3月には小山内薫を校長に据えて、松竹キネマ俳優学校を設立、公募によって36名を研究生として採用、俳優の養成に努めました。撮影所としては、蒲田に9千坪の用地を取得、蒲田撮影所(後大船に移転)を建設しています。さらに京都下加茂に、京都撮影所を設立、東京で現代劇、京都で時代劇を撮影する体制を築きました。
2011.02.11
コメント(12)
-
チュニジアからエジプトへ…(13)
チュニジアからエジプトへ…(13)現在のエジプトでは、反体制派を加えて、政権移行に関する協議が行なわれていると、大真面目に報道されています。協議が行なわれているのは事実ですね。しかし、この移行協議、実は茶番劇です。体制と反体制というなら、反体制側は当然政権の転覆を目指す勢力ということになります。反体制勢力に分類できるとすれば、ムバラク政権によって非合法化された事実をもって、「イスラム同胞団」を上げることは可能ですが、同胞団のスポークスマンは、移行協議からの離脱を表明していますから、残りは体制内反対派に過ぎません。ムバラクは、30年間空席にしておいた副大統領職を復活して、情報機関を監督してきたスレイマンを据え、「民主的選挙」と改憲、そして自身の不出馬を約束して、事態を収束させようと目論んでいます。これで、民主化になるかというと、まずなりません。事実上体制内野党にまで、高いハードルとなっている被選挙権規定(=立候補規定)や、選挙権の範囲を多少見直すことくらいで、終息させたい意図がみえみえです。完全な民主化、年齢以外に制限のない、敢然普通選挙では、民衆の支持が厚い「イスラム同胞団」外の、反体制派の圧勝が見えていますから、それでは体制内野党にメリットはないのです。その点で、「野党」はムバラク政権の幹部だったスレイマンらと、同じ穴の狢です。その連中を取り込んでの、「はい、こういう改革をしました。チャンチャン」では、改革になどならない。それが分っているので、それじゃダメだよと、デモは終息の気配を見せないのですね。そして明日が、エジプトが燃え出して3度目の金曜礼拝の日です。キリスト教(正教を含む)にとっての日曜日にあたる日ですね。何かが起こるのでしょうか。事態はまだ続いています。 続く
2011.02.10
コメント(10)
-
北九州市発足 10日の日記
クロニクル 北九州市発足1963(昭和38)年2月10日48年前になるのですね。この日、福岡県の北九州5市(門司市・小倉市・戸畑市・八幡市・若松市)が合併し、北九州市が誕生しました。合併により政令指定都市となる、最初のケースでした。最近はさいたま市とか、相模原市とか、こういうケースが増えてますね。
2011.02.10
コメント(22)
-
チュニジアからエジプトへ…(12)
チュニジアからエジプトへ…(12)エジプトは、古代メソポタミア文明の中心地だったイラクと並んで、古代文明の発祥の地です。しかも1950年代の前半という早い時期に、革命によって王政を打倒し、アラブ世界をリードした自負を持つ誇り高い国です。そんな国の若い士官や士官候補生たち、さらには軍籍にない若者達が、いつまでもパレスティナの仲間たちを虐げ続けている、イスラエルに便宜を与え続けているムバラク政権を、許容し続けるでしょうか。兵役によって入隊してくる兵卒たちと接し、彼らの暮らしぶりや思いを知るのも、こうした若き将校たちです。兵士との接触によって、より強く彼らが改革の志を持ったとしても、不思議はありません。1月下旬からの反政府デモのうねりを、軍部が取り締まらず、デモ隊と治安警察の間に入って、デモ隊の安全を確保したのも、軍幹部がこうした若手将校の意識に配慮したからに外なりません。良く言われることですが、積極行動分子は一部であり、大多数の民衆は行動していないと、主張する方が大勢います。こういウ主張は、事実を言い当てているようで、実は大切なことを見落としています。確かに行動はしていないのですが、この行動に消極的な人たちの潜在的意識が、どちらを向いているかにこそ、大事なポイントがあるからです。彼等彼女らは、自分は参加しなくても、反政府派を心情的に応援しているのか否かです。現在は、軍によって、デモ隊の安全が一応確保されていますが、当初は違っていました。デモの計画も命がけでしたし、計画者たちには、デモ終了後に逮捕を避けるために、身を隠す必要もありました。そしてその多くが成功し、治安警察のデモ封じ込めは悉く失敗に終りました。私はここに、デモ隊に参加したわけではない、物言わぬ市民たちの、デモ隊に寄せる心情的な共感の厚さを感じます。10人のデモ隊の背後には、100人を大きく越える心情的支持が存在した。だからこそ、デモの指導者、計画者たちは、人民の海に溶け込むことによって、治安警察の追及をかわすことが出来たのです。そして、今なお事態は動いています。 続く
2011.02.09
コメント(6)
-
女性最高裁判事誕生 9日の日記
クロニクル 女性最高裁判事誕生1994(平成6)年2月9日もう17年経つのですね。この日、細川首相は、 高橋久子元労働省婦人少年局長を、最高裁判所判事に任命しました。こうして、この日女性初の最高裁判事が誕生しました。女性の社会進出は、1980年代から活発化してきており、そうした事情に鑑み、男性優位の職場のだった法曹界にも、女性の進出が求められていた時期でしたから、このビッグニュースは、各方面で好意的に受け止められました。
2011.02.09
コメント(10)
-
チュニジアからエジプトへ…(11)
チュニジアからエジプトへ…(11)では今後の展開は、どうなるのでしょうか。エジプト軍の動向が、今回も大きな鍵を握っていることは、間違いありません。何故軍なのか。エジプトは国民皆兵制を、現在も採用しています。ですから身体検査に合格した男性は、全員兵役を経験しています。しかもエジプト軍は、世界10位とされる軍事力を要しています。1952年の革命で、国王ファルーク1世を追放した自由将校団も、その名の通り軍内の若手将校たちの秘密組織でした。軍こそが革命の担い手であり、現在でも、軍部に対する国民の信頼は厚いのです。だからこそ、52年の革命後の、短期のつなぎ役だったナギブを含めて、ナセル、サダト、ムバラクと続く、4代の大統領は、全て軍人出身でした。これはエジプトに限りませんが、経済が離陸期に入り高度経済成長を続けるアジアの国々や、ブラジルなどを除く途上国では、留学などを経て高い教養を身につけた若い世代は、かつての『赤(軍人)と黒(聖職者)』の時代ではないですが、幹部候補生として軍に迎えられるが、常なのです。それゆえ、政界のリーダーになるのも、この層に限られる傾向が強いのです。ムバラクも軍人です。彼も30年にわたって独裁政権を維持したツワモノです。政治的弾圧にマルマル軍を使って、国民的人気に支えられていることを誇りとする、軍人のプライドを傷つけることは慎重に避けました。弾圧や拷問などの仕事は、治安警察に担当させて来ました。これが、現在のエジプトにおける軍の人気と、警察の不人気の背景です。さて、その軍はどう動くのでしょうか。 続く
2011.02.08
コメント(10)
-
黒部トンネル全通 8日の日記
クロニクル 黒部トンネル全通1959(昭和34)年2月8日黒部トンネルは、1956年に着工し63年に完成した、関西電力の黒部ダム(水力発電所用)の建設工事のために作られたトンネルです。計画が動き出した1956年当時、日本経済の復興と共に、工業用電力の不足が目立ち、特に関西地域では、停電が頻発する事態が生じていました。今では考えられないことですが、当時は夜10時~朝4時頃まで、家庭などへの電力供給が停止されてもいました。曽根史郎の『若いおまわりさん』の歌詞に >そろそろ広場の灯も消える<とあるのは、この状態を指していました。この事態に対し、関西電力は、戦前に一部調査を行なったことのある、黒部川上流でのダムと発電施設の建設に、社運をかけて取り組むことを決めたのです。当時の社長、太田垣士郎の決断によるものでした。建設予定地は山奥でしたから、当初の工事は建設材料を徒歩、馬、ヘリコプターで輸送する原始的な方法で行なわれました。このため、作業がはかどらず、困った関西電力は、予定地までトンネルを掘ることを決断しました。こうして着工されたのが、大町トンネルと黒部トンネルでした。大町トンネルを担当したのは間組、黒部トンエルを担当したのは熊谷組と佐藤工業でした。工事は、破砕帯から大量の冷水が噴出し、多数の犠牲者を出すなど、大変な難工事となりましたが、当時の最新鋭の技術を動員して、苦境を切り抜け、1959年に相次いでトンネルの貫通に成功したのです。そして、52年前の今日が、黒部トンネル貫通の日だったのです。結局黒部ダムは、総工費513億円(当時の関西電力の資本金の5倍でした)を要し、投入した作業員は、延べで1千万人を超え、工事中の殉職者171人という難工事の末に、1963年に完成をみたのでした。
2011.02.08
コメント(6)
-
チュニジアからエジプトへ…(10)
チュニジアからエジプトへ…(10)10時頃から外出して6時頃に戻りましたら、本日の夕刊に、政権側(スレイマン副大統領)と反政府勢力との交渉が行なわれ、一定の合意に達したとの報道が出ていました。政府側からすれば、いままで非合法化していた「ムスリム同胞団」を含む勢力と交渉を持ったのですから、大幅な譲歩をしたつもりでしょうね。しかし、政治犯の釈放は「全員を無条件に」ではなく、部分開放に留まっていますし、非常事態宣言の即時撤廃要求に対しても、事態の沈静化後と、時期をぼかしています。そして何よりもムバラク大統領の即時辞任要求には、応じていません。交渉は合意に達したとされていますが、とてもそうとはいえないようです。反政府側にもいろいろな勢力がありますから、反政府側の分裂を図る作戦なのか、とりあえず様子を見ているのか、駆け引きが始まったという所でしょうか。民衆のエネルギー、そして若者の変革にかける情熱が本物であれば、近いうちに再度の大きなうねりが出てくるものと思います。分っていることは、ムバラク政権がアラブの大義に背いて、イスラエルとアメリカの忠実な僕に堕していたことを、エジプトの人たちが、決して快くは思っていなかったという事実です。イスラエルは、その土地から追い出して、ユダヤ人の占有地にしてしまったパレスティナ難民に対して、ガザとヨルダン川西岸という、2ヶ所の限られた地域に限って、難民たちによるパレスティナ国家の建設を認めました。PLO(パレスティナ解放機構)は、ここに自治政府を樹立し、国際社会から国家として承認を受けました。こう説明されてきました。しかし、その実態はどうだったでしょうか。ガザ(元来はエジプト領で、第3次中東戦争でイスラエルが占領した土地です)とヨルダン川西岸(こちらは元々ヨルダン領で、同じく第3次中東戦争でイスラエルが占領しました)は、かたやエジプトとイスラエルに囲まれ、かたやヨルダンとイスラエルに囲まれた土地です。しかも、この2地区の土地全てが、パレスティナ人に渡されたのかというと、そうではありません。ガザでもヨルダン川西岸でも、肥沃な土地、住みやすい土地はユダヤ人の入植者が、占有したままで居座っているのです。両地区とも、限られた狭い地域です。その中の一等地とも言えるかなりの面積を、少数のユダヤ人が占領し、広い農地と広大な屋敷を所有しているのです。対するパレスティナ人は、狭い地域に押し込められているのです。そして、ヨルダン川に接する西岸はともかく、ガザは水がありません。水はイスラエルが止めてしまえば、手に入らないのです。ユダヤ人入植地にはふんだんに送られているのに…。同じアラブのエジプトから、分けてもらう手があるはずですよね。普通に考えれば…。ところがムバラク政権は、イスラエルの要求を入れて、自国とガザとの間に、ベルリンの壁のような壁の建設を認め、ガザとの交流や物資の運搬を止めているのです。昨春、1週間か10日ほど、ガザの政権を担当するハマスが爆破し、通路を作った壁の通行を自由としたことが、大ニュースになりました。これが実情です。実質はガザもヨルダン川西岸も、イスラエルが作り、エジプトとヨルダンが協力者となっている、パレスティナ人を閉じ込める巨大な檻、牢獄と化しているのです。そこから外に出るには、イスラエルの許可が必要で、パレスティナ人は日常的にイスラエル兵士の監視下で生活しているのです。パレスティナの仲間が、このような屈辱的な状態に留まることを強いられているのは、エジプトやヨルダン政府が、イスラエルの言いなりに、イスラエルに協力しているからです。このことは、日本人は知らなくても、エジプトやヨルダンの人々は良く知っています。特に知識層では、知らない人は先ずないでしょう。彼等が、こうした政府の姿勢を快く思わないだろうことは、想像に難くありません。1度火がついた思いは、奔流のように溢れ出し、簡単にはとめることはできません。まだまだアラブの情勢は、流動的なように思います。 続く
2011.02.07
コメント(6)
-
スイスで女性参政権承認 7日の日記
クロニクル スイスで女性参政権承認1971(昭和46)年2月7日丁度40年前のことです。これは欧米諸国では、異例の遅さになります。遅かったフランスも、日本とほぼ同じ1946年には、女性参政権を認めているのですから…。この日の国民投票で、婦人参政権の導入を定めた憲法改正が承認され、スイスも婦人参政権の導入が、可決成立を見ました。しかし、スイス憲法は、参政権に関する主権は、国ではなく州が持つとも定めているため、71年に婦人参政権が認められた後も、アッペンツェル・アウサーローデン準州では、1990年まで婦人参政権は、制限されたままでした。
2011.02.07
コメント(10)
-
チュニジアからエジプトへ…(9)
チュニジアからエジプトへ…(9)チュニジアからエジプトに飛び火した、アラブの変革への動きは、イエメン、ヨルダンなどに飛び火し、政権交代を実現しています。イエメンでは独裁政権が崩壊し、ヨルダンではイスラム教の開祖ムハンマドに連なる王家こそ存続しましたが、国王は反政府派の主張を全面的に取り入れ、政権の顔ぶれは一新されました。しかしです。アラブの独裁政権の中で、最も長く政権の座にあるカダフィ政権のリビアでは、小規模なデモはありますが、政権は安泰です。またアルジェリアでは、1991年の選挙で圧勝したイスラム原理主義政党のイスラム救国戦線(FIS)による政府の誕生を嫌った軍部が、1992年1月にクーデタを起こし、以後、世俗主義に基づく軍人による独裁政治が続いています。92年の軍クーデタ後に発令された「国家非常事態宣言」の下で、軍人中心の民族解放戦線(FLN)による一党独裁体制が敷かれ、やがて多党制に移行したのですが、イスラム主義政党は認められず、非常事態宣言も解除されていません。そんなわけで、イスラム過激派によるテロも、続いていました。そんなアルジェリアのブーテフリカ政権(現在3期目の大統領職にあります)に対する打倒運動も、今のところ活発化する傾向を見せておりません。違いはどこにあるかと言いますと、リビアとアルジェリアの共通項は、反米、反イスラエルの姿勢を貫き、パレスティナ人やパレスティナ難民に対する連帯と支援の姿勢が、揺るがないことにあります。アラブの誇りを失わない政権に対する反発は、例えそれが長期の独裁政権であっても、今のところ強いとは言えないのです。それが今後も貫かれるかどうかは、分りません。あくまでいまの所です。それでもここから見えてくることがあります。それは、エジプトで親米、親イスラエルの政府が継続する可能性は、大変難しくなっているということです。パレスティナ人を虫けらか奴隷の如く扱い、民族の誇りを踏みにじり、驕り高ぶった態度をとり続けたイスラエルが、頭を抱える時が近付いているようですね。 続くそれでも、
2011.02.06
コメント(8)
-
エリザベス2世即位 6日の日記
クロニクル エリザベス2世即位1952(昭和27)年2月6日59年前のことですから、イギリスのエリザベス女王、このままお元気なら、来年は即位60周年ということになるのですね。凄いなぁ。59年前のこの日、エリザベス現女王の父君、イギリス国王のジョージ6世が肺がんに起因する衰弱から発した、冠状動脈血栓症により死去したことを受け、即日長女で、王位継承者だったエリザベスが王位を継いだのです。
2011.02.06
コメント(12)
-
チュニジアからエジプトへ…(8)
チュニジアからエジプトへ…(8)そして、今年の1月15日、チュニジアで「ジャスミン革命」が始まり、あれよあれよという間に、独裁者ベン・アリが亡命する事態に至りました。ジャスミン革命の詳細について、私は詳しい情報を持ち合わせていません。理解できていることは、ウィキリークスが暴露した情報の中に、チュニジア支配層の贅を凝らした、贅沢三昧の暮らしぶりが入っていたことです。この事実を知って、怒り心頭に発した人たちが、画像をコピーして流した結果、広い範囲の人たちの知るところとなり、twitter やFacebookで始まった街頭行動の呼びかけが、ラジオやクチコミを通じて広がった結果が、ベン・アリ追放に繋がったのですね。ウィキリークスも、twitter やFacebookも、米国で生まれたものです。米国生まれの技術やサービスを使って、アラブの人たちが親米政権を倒したのです。その原因にまで遡れば、米国発の世界大不況がバックグラウンドになっていることは、明らかです。これは何とも皮肉ですね。さて、エジプトに話を戻すと、エジプトの知識層は、自国こそアラブの盟主という意識を、今ももっています。確かに8千万人という人口は、アラブ世界でひときわ目立っていることも事実です。チュニジアに出来たのなら、自分たちもと、考えたとしても不思議ではありません。ここまで記したように、ムバラク政権による反対派の弾圧と圧政は、目にあまりました。そして、金持ち優遇の経済自由化で、貧富の差は拡大し続けていました。そして生活に窮した多数の貧困層。きっかけさえあれば、一斉蜂起が起きる条件は熟していましたから、事態の広がりに時間はかからなかったのです。しかし、ここで考えるべきことがあります。ムバラク圧政は取り除かねばなりません。ただし、ここで弾圧されていたのは、ムスリム同胞団など穏健派ムスリムを含む、ムバラク一派にとって、目障りなムスリム組織と原理主義過激派でした。その他大勢のムスリムの人たちにとっては、言論や信仰の面で、不自由なことはなかったのです。それなのに何故、その他大勢の人たちが反ムバラクで団結したのでしょうか。エジプトの人々にとって大切なことの1つに、アラブの盟主エジプトというメンツの問題があります。そうであれば、アラブの大義にソッポを向いて、親米・親イスラエルの路線をひた走る、ムバラク政権は許せなかったのです。 続く
2011.02.05
コメント(4)
-
コインロッカーに嬰児の死体 5日の日記
クロニクル コインロッカーに嬰児の死体1973(昭和48)年2月5日あれから38年ですか。嫌な出来事でした。この日渋谷駅のコインロッカーから、嬰児の死体が発見されました。以後、この年いっぱい同種の赤子の遺棄事件が続き、当時大きな社会問題となりました。
2011.02.05
コメント(16)
-
チュニジアからエジプトへ…(7)
チュニジアからエジプトへ…(7)ルクソール事件後、ムバラクはさらにムスリム過激派への弾圧を強化すると共に、最大野党である穏健派ムスリム、「ムスリム同胞団」の幹部をも拘束して、組織の弱体化を測りました。こうして、21世紀の到来と共に、ムバラク独裁体制は、ほぼ完成の域に達したのです。このムバラクの支配に翳が射したのは、ブッシュの戦争であるイラク戦争でした。アラブ世界の支配層、とりわけサウジなどの王侯やUAEなどの首長らにとって、フセインの失脚と処刑は望ましいことだったでしょうが、アラブの民衆にとって、イラク民衆を無差別に殺傷する米英などの軍隊は、憎むべき敵であり、反米感情は益々強まったのです。ムバラク政権のエジプトには、イスラエル承認と、イスラエルとの協調の見返りに、毎年15億ドルの経済援助が、米政府から与えられていました。ムバラクはこの金を操作して、軍の近代化を進めると共に、経済自由化を進めました。その結果、彼とその側近、そして1部の超富裕層が大いに懐を肥やしたのです。ここに、国内における貧富の差は益々拡大を見たのです。こうした経済的不満が高まっている所で、イラクやパレスティナの同胞を虐げる米英とイスラエル。その米国とイスラエルの言いなりになっているムバラク政権に対し、国民の怒りが高まらないはずはありません。何よりも、ガザ地区(ここはシナイ半島とイスラエルに囲まれた地域です)のパレスティナ人を、出口のない大型の檻に閉じ込めたような封鎖壁を築き、イスラエルの言いなりに封鎖に協力するムバラク政権は、エジプト国民にとって、許しがたい存在にほかならなかったのです。ここに、2004年頃から、雨後のタケノコのようにあちこちで、反政府蜂起が起きるようになり、ムバラク政権とSSIは、その鎮圧に忙殺されるようになっていたのです。この傾向は、2008年のリーマンショック以後特に激しくなり、インフレ率の上昇と経済不況によって、失業率の上昇と食料品価格の大幅値上がりの二重苦に苦しむ民衆の、反ムバラク感情は、いつ暴発してもおかしくない状態になっていたのです。 続く
2011.02.04
コメント(0)
-
ヤルタ会談始まる 4日の日記
クロニクル ヤルタ会談始まる1945(昭和20)年2月4日もう66年も前のことになるのですね。第二次世界大戦も、ドイツの敗色が濃厚都なり、日本も本土決戦に備えるしかない状況に、追い詰められていた頃です。この日、ソ連の黒海に面した保養地、クリミヤ半島のヤルタで、米大統領ローズヴェルト、ソ連最高指導者スターリン、英首相チャーチルの3名による、ヤルタ会談が始まりました。この会談は、ドイツの戦後処置を相談する目的で開かれ、ドイツ降伏後、東からのソ連軍と西からの米英軍が、夫々の軍を展開して治安維持にあたること(事実上の占領を続けること)、ただしベルリンは、東西に二分し、分割統治とすることが決められました。このドイツ分割案が決着を見た後、ローズヴェルトはスターリンに対し、ドイツ降伏後に、ソ連が日ソ中立条約を破棄して、日本に宣戦布告し、対日戦線に加わることを強く求めたのです。対独戦が終了すれば、後方の憂いを除くための日本との条約は、役割を終えます。この国際政治の当然の常識を踏まえての誘いでした。さらにローズヴェルトは、スターリンの気を引くために、南カラフトの回復の外に、千島列島の領有などを容認する姿勢も示したのです。ここに、ヤルタ会談の席で、ドイツ降伏後3ヶ月後までの間に、ソ連が対日戦線に参加することが決まったのでした。対米戦に頭がいっぱいの当時の出来の悪い軍人や政治家、気骨のある官僚を排除して、イエスマンばかりで固めた高級官僚は、冷徹な国際政治の現場では、常識として考えておくべきことすら、見落としていたのですね。ヤレヤレ…
2011.02.04
コメント(8)
全58件 (58件中 1-50件目)