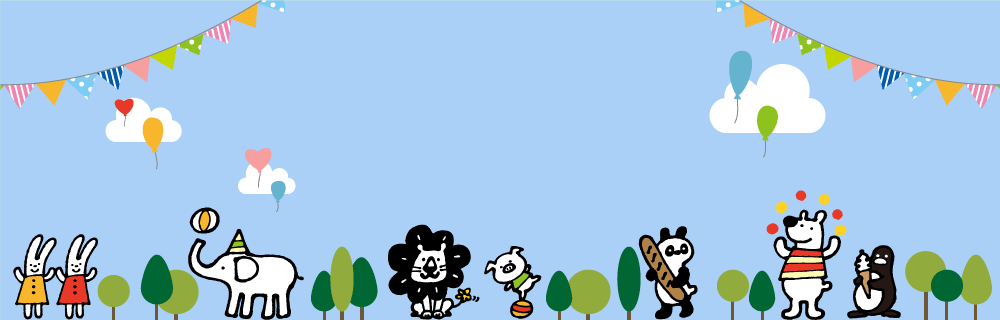2011年01月の記事
全62件 (62件中 1-50件目)
-
チュニジアからエジプトへ… (2)
チュニジアからエジプトへ… (2)チュニジアの「ジャスミン革命」は、1月15日に始まり、あれよあれよという間に、独裁者のベン・アリ追放に成功しました。物価高に国民の怒りが高まって…という説明がなされていますが、それはその通りなのですが、物価高の原因まで遡らないと、その広がりまでは、予測できないことになります。後講釈になりますが、2つのことが考えられるように思います。ひとつは物価高の原因です。これは間違いなく、リーマンショック後の経済先進国中心の紙幣の大量バラマキ政策です。このブログでも、あちこちで触れていますが、ばら撒かれた紙幣が本国の設備投資等に回らず、途上国への投資と商品先物市場での投機や株式市場に流れ込んだことです。その結果、人間の基本的な生存に関わる穀物までもが投機の対象となって、貧しき人々を直撃したのです。実は、食糧輸入国の日本でも、食品の価格は上がっていますが、日本の場合円高がクッションの役割を果たしているため、値上がりは大変緩やかなのです。まさに円高効果さまさまなのですね。それこそ円安になったら大変です。勿論、商品市場高騰の理由には、投機のみではなく、中国やインドと言った人口大国の経済的離陸という、実需面での買い圧力も大きく作用していますから、紙幣の大量バラマキ政策が止まっても、値下がりは限られてしまうでしょうが…さて、ふたつ目の理由です。これは、私独自の主張ではなく、教えられたことなのですが、エジプトの南、ナイルの源流に位置する、スーダン内戦に、平和解決の道筋が整ったことです。この国は、長く内戦に苦しんできました。ダルフール紛争という語は、お聞きおぼえのある方も、あろうかと存じます。このスーダンで、南スーダンの分離独立が、住民投票の結果、90%以上という圧倒的な賛成で、現実のものとなりつつあるのです。内戦を繰り返していたスーダンが、住民投票で民主国家を作ろうとしている。それなら我々も…。 永年の独裁と、それが故の政治的無策の結果、放置されたインフレでを何とかしよう。こうした声が、チュニジアの革命につながり、エジプトやイエメンに波及したというのが、現在の状況のように思います。 続く
2011.01.31
コメント(16)
-
『文学界』創刊 31日の日記
クロニクル 『文学界』創刊1893(明治26)年1月31日108年前になります。日清戦争が始まる1年と数ヶ月前ですね。この日、北村透谷や島崎藤村らの手で、文芸雑誌『文学界』が創刊されました。この『文学界』は、1898(明治31)年1月まで続き、全部で58号まで発行され、ロマン主義文学の初期の旗頭の役割を果たしました。透谷と藤村のほかに、樋口一葉、上田敏、田山花袋、戸川秋骨、馬場孤蝶、松岡国男らが常連執筆者でした。20代前半の若い世代が中心で、編集メンバーでは、創刊当時25歳の北村透谷が最年長でした。その透谷は創刊翌年の1894年に亡くなっています。やがて、メンバー夫々が、各自の道を歩みだしたことで、役割を終え、98年1月をもって、解散となりました。
2011.01.31
コメント(2)
-
チュニジアからエジプトへ… (1)
チュニジアからエジプトへ… (1)2週間前、チュニジアで、1987年11月から23年余にわたって政権を担当してきた独裁者ベン・アリが、あっけなく政権を追われて追放されました。「ジャスミン革命」という洒落た名がつけられましたが、まだ事態は完結していません。というのは、追放された独裁者は、政敵による訴追を恐れ、子飼の部下を政権内に残すことで、自己の保全を図ろうと、必死になっているからです。もうしばらく様子を見る必要がありそうですね。そして、チュニジアの事態は、あれよあれよという間に、エジプトに飛び火しました。チュニジアは、古代ローマと3度のポエニ戦争を戦ったカルタゴの遺跡持つ、北アフリカの小国です。それに対し、エジプトはアラブ世界最大の、8千万人の人口を抱える大国であり、4度の中東戦争の後に、親イスラエルに転換したイスラエルとアメリカにとって、大変重要な国です。従って、エジプトでの政変、ムバラク追放という事態になれば、それはイスラエルとアメリカの中東政策の根本的再編が必要となる大事件になります。それは、中東世界の流動化と戦火のは可能性を高めるかもしれません。それは、日本を除くアジア経済の早期復調に助けられて、辛うじて小康状態を保っている日・米・欧の経済にとっても、大きな打撃となることも考えられます。こんな事情で、金曜のウォール街では、株価は急落を示しました。いったい、アフリカのアラブ世界に何が起こっているのか。何故アラブアフリカが発火点となったのか。エジプトは、そして隣接国々はどうなるのか。乏しい知識ですが、すこし探ってみたいと思います。あまり期待なさらずに、お付き合い下さい。
2011.01.30
コメント(6)
-
赤穂浪士吉良邸に討ち入り 30日の日記
クロニクル 赤穂浪士吉良邸に討ち入り1703年1月30日(元禄15年12月14日)今日は、12月14日ではありません。そうなのですが、308年前の今日こそが、大石内蔵助ら赤穂の47人の旧藩士たちが吉良邸に討ち入り、本懐を遂げた日です。12月14日は旧暦での日付、太陽暦では1月の30日です。ですから、真冬の寒さの中、大雪の日の深更だったことも、そうだろうなと実感をもって受け止められますね。ただし、大雪の討ち入りは、歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の創作で、実際のこの日は、冷え込みの厳しい星空だったというのが、真相でした。そして、深更とされる現実の討ち入りは、今の時刻で言うと、日付の替わった31日(12月15日)の午前3時から4時の間のことでした。ただし、こちらは当時の習慣が、明六つから1日が始まるとしていたことから、討ち入りは12月14日(西暦1月30日)のままと去れています。
2011.01.30
コメント(12)
-
ユーロの憂鬱 (39)
ユーロの憂鬱 (39)1月15日に(38)を書いてから、アリゾナの銃撃事件を追いかけて、つい御無沙汰してしまいました。この「ユーロの憂鬱」についても、現段階での一応の締めを記しておきたいと思います。現在ユーロは、奇妙な小康状態にあります。各国の経済力を比べれば一目瞭然ですが、ドイツ経済とギリシアやポルトガル、アイルランドの経済を同じ土俵に乗せて、1つの通貨で括ろうというのは、何度も記してきたように、やはり無理があります。経済力に問題を抱える国々にとって、つっかユーロは強すぎて負担になっています。ですから彼らをユーロの仲間にし続けるためには、経済力の高い国による支援が避けられません。逆に経済力の高いドイツにとっては、実力に比べて通貨が安く、金利も低いために、景気過熱しすぎる恐れが拭えません。では、ユーロの解体とか、ユーロ圏の縮小という事態が生まれるのかというと、どうもそうでもなさそうです。ユーロの分裂は、西欧諸国が時間をかけて進めてきた欧州ポルトガル、ギリシア、アイルランドなどのユーロ離脱は、こうした国々のデフォルトに繋がり、これらの国々の金融機関に貸し込んでいる欧州の銀行の経営危機に、直結してしまいますし、同時に長い間苦心に苦心を続けてきた、欧州統合への努力を、一挙に瓦解させてしまうことにも、繋がるからです。それはあんまりではないか。何とか続けていく道を見つけようではないか。ギリギリの局面になると、こうして妥協案が探られます。その結果、壊れそうで壊れない、不安定性を高めながらも、何とか支えあっているという、綱渡り状態が今後も続いていきそうに見えます。現実にドイツの景気についてみれば、輸出比率が40%台と、日本の3倍弱に達するドイツにとって、不安定さを増す共通通貨ユーロ安は、明らかにプラスに働きます。そのため。ユーロ不安は、欧州全体の景気の崩壊にもならないという、何とも不可思議な状態がなお続く可能性が、高そうです。今年も、ユーロ圏の状態から、眼がはなせないようです。今後もユーロのウオッチングを続けますので、何かあれば書かせて戴こうと思います。どうぞよろしく。 完
2011.01.29
コメント(8)
-
政治改革4法案成立 29日の日記
クロニクル 政治改革4法案成立1994(平成6)年1月29日もう17年経つのですね。7党連立の細川内閣の時期でした。この日、衆議院議員の選挙に、小選挙区比例代表並立制を導入することを柱とした、政治改革関連4法案が可決成立しました。小選挙区比例代表並立制の導入と、政党交付金の導入(政党助成法)を二本柱とした政治改革4法案は、中選挙区制から小選挙区制とすることで、選挙にかかる経費を少なくすることと、政党の規模(議員数)に応じて、国庫から交付金を支給することの2点で、政治と金の問題を解決することを狙って、導入が検討され、この日成立をみました。しかし、その後も政治と金を巡る問題は後を絶ちませんね。
2011.01.29
コメント(6)
-
日本国債は格下げされたのか?
日本国債は格下げされたのか?テレビは勿論ですが、今朝の新聞もまた、判で捺したように、「S&P日本国債を格下げ」と報じていました。この報道は、極めて不正確で、正しくありません。消費税を上げたい政府に協力するため(それにしては、昨夜の菅首相の発言はオソマツでした)、意図的にそう報道したのか、単なる勉強不足なのかは、はっきりしないのですが…(苦笑)。S&P社が、昨日日本について発表した格付けは、日本国債そのものの格付けではありません。即ち日本国債のデフォルトの可能性を探ったものではなく、彼らが国債の格付けとは別物としている、「ソブリン格付け」を下げたのです。「ソブリン格付け」というと、いかにも国債の格付けのようですが、国債の格付けは、基本的には外貨建て国債の場合にしか行なわれません。例外はユーロのような、多国間で流通する通貨の場合です。実際に、国債の格付けが引き下げられたのなら、債券市場で日本国債は暴落するはずです。債券市場は、株式市場と違って基本的にプロが99%を占める市場ですから、マスコミの虚言に惑わされることはない市場です。S&Pの発表後、債券市場は僅かな揺れこそ見せましたが、引けは前日比で、ほとんど変わらずでした。債券市場は、S&P社が勝手にやっている「ソブリン格付け」(各国の経済力、成長の可能性などについて、ランキングをつけるものです)で、日本の成長力に疑問をつけて、1段階引き下げただけで、日本国債のデフォルト可能性を問題にしたのではないことを、正確に見抜いていたのです。日本のマスコミとは、雲泥の差です。S&Pは、「日本のソブリン格付け」の引き下げ理由を、生産人口の減少と高齢化の進行により、経済成長率予測が年率で1%程度に留まりそうだから、と説明しています。この指摘はその通りでしょう。生産人口が減少すれば、経済成長率が低くなるのは、ある意味当然です。ただ、こうした今後の経済成長の問題と、国債のデフォルトの可能性とは全く別物です。S&Pも、日本の対外純資産残高が、世界最大であることを認めています。また、外貨・金の準備高が1兆ドルを超え、中国に次ぐ世界2位であることも認めています。その上、経常黒字が続いていることから、対外純資産が今後数年さらに増加するだろうことも、認めているのです。いったい何のために、「ソブリン格付け」を引き下げたのでしょうね。これで、デフォルトの可能性が囁かれている、ベルギーやフィンランドのドル建て国債(いずれもAAフラットです)よりも、低く格付けするとは、どうかしています。実はこの会社、倒産したエンロンに、AAの格付けをしていたなど、何かと問題があることでも、知られています。最後に米紙「ウオール・ストリート・ジャーナル」の記事を引用しておきます。「日本は経済成長率が低く、従ってインフレ率が低いのだから、日本国債を買い持ちすればいいでしょう。」
2011.01.28
コメント(10)
-
新潟少女長期監禁事件 28日の日記
クロニクル 新潟少女長期監禁事件2000(平成12)年1月28日タイトルをどうつけるべきか、今日は迷いました。11年前の今日は、事件の解決日でした。少女が誘拐されたのは、小学校4年生だった1990(平成2)年の11月13日、新潟県三条市の小学校からの下校途中でした。ですから、少女は9年2ヵ月に渡って監禁されていたことになります。少女が同じ新潟県柏崎市の加害者宅で見つけられ、助け出されたのは全くの偶然でした。少女を誘拐した犯人(加害者)宅へ、別件で訪問した同市の保健所職員が、室内にいた足が萎えて満足に歩けない女性を発見、保護したのです。その後の入院と事情聴取の結果、9年2ヵ月前に誘拐された少女と判明したのでした。衝撃的な事件でしたので、おそらく皆さんの記憶にも、残っている事件だと思います。
2011.01.28
コメント(20)
-
アリゾナの銃撃事件を考える(10)
アリゾナの銃撃事件を考える(10)ボーイング社について、少々追加させて戴きます。同社の最大の工場は、ロングビーチにあるのですが、そのロングビーチ工場の従業員数のことです。1990年当時、この工場の従業員は2万人を数えました。それが今回のレイオフの結果、従業員は7千人にまで減少するそうです。米政府やFRBが、形振り構わず市場にドル札を提供しているのですが、日本と同じで、そのお金が設備投資に回っていません。市場で資金を集めたり、銀行借り入れが可能(銀行が快く融資を承認してくれる)な企業や、市場での資金調達が可能な企業は、せっせと高利の借金の返済や、自社株買い、そしてM&Aに精を出しています。ですから、こうした企業の株価はあがります。行き場のない資金が、商品市場と共に、こうした値上がりの見込める企業の株を狙って、株式市場に流れ込みます。昨秋のQE2以降、米国株式市場が好調なのは、こうした事情によります。そして米国では、仮定の流動性資産に占める株式のウェートは、日本より遥かに高いのです。株価の好調が、昨年のクリスマスセールの好調に繋がりました。車も売れました。住宅は一時に比べ、随分安くなっているのですが、手が出ない層が多いのですね。銀行融資がOKになりませんから…。そこで、家はむりだけれど、車なら買い替えられるとか、○○なら買えるという層が、動いた結果が、クリスマスセールの好調だったと、私は見ています。12月の新築住宅販売戸数は32万戸。市場予測より2万戸以上多かったと報じられていますが、依然として低水準で、1960年当時の水準まで落ちたうえでの底ばい圏を抜けられずにいます。住宅と雇用の回復のない限り、米経済の日本化は続くでしょう。そして次第に貧困化する中産層。精神不安定に陥る人々は、おそらく増え続ける。その先にあるものは、見えるように思うのは、私だけでしょうか? 完
2011.01.27
コメント(4)
-
曙横綱に昇進 27日の日記
クロニクル 曙横綱に昇進1993(平成5)年1月27日18年前になるのですね。この日、前年の九州場所と1月の初場所で、2場所連続優勝した大関曙が横綱に推挙されました。ここに初の外国人横綱が誕生しました。それから今日まで18年、今や上位陣のほとんどが外国籍の関取に占められていますね。日本人の優勝力士がでなくなって、随分経つような気がしますね。
2011.01.27
コメント(9)
-
アリゾナの銃撃事件を考える(9)
アリゾナの銃撃事件を考える(9)アリゾナの銃撃事件に戻りましょう。パナマ運河のクルーズからお帰りになったリンダ夫人から、「事件後サラ・ベイリンのテレビへの露出が見られなくなった」と、報せて戴きました。さすがに、テレビ局もこれはまずいと思ったのでしょうね。しかし、火元のアリゾナ州議会は、事件後州法を改正(日本人から見ると改悪でしょうね)して、21歳以上の成人は、誰でも許可なしで、何処へでも銃を持込めることとしたのです。これで、学内や病院への銃の持込が、野放図に認められることになったのです。州の権限の強い米国では、州によって異なる法が施行されていることは、『19世紀のアメリカ』でも記述した通りです。そして、銃の自由所持は、今後のアメリカにとって、極めて危険なことだと、私は考えています。昨秋の中間選挙で話題となったティー・パーティは、リーマン・ショック後の経済不振で、中産階級の座から転げ落ちつつある、そんな白人層を中核とした組織です。彼らのやり場のない怒りが、政府批判となって噴出したのです。結果はどうでしょうか。その後の論調で米国景気は回復に向かいつつある。企業業績は、発表を見る限り、順調に回復しています。ですが、これで安心というわけにはいきません。企業の業績回復から、景気は回復に向かっていると、確かに言えるのですが、それが雇用の回復に結びつくことはないのです。数年前に日本でも経験したことです。金融危機を経験した日本経済は、2002年から回復基調に入り、リーマン・ショック前の2007年初めまで、戦後最長の景気回復が続きました。しかし、この間給与生活者の賃金は、上昇することはなく、低下ないし横這いを続けました。ですから、「実感なき景気回復」という語が流行ったりしたのです。同じことが今のアメリカで起きています。象徴的な例を記します。つい先日、中国の胡錦濤国家主席が訪米し、大変な額に上る商談をまとめました。その目玉が、航空機メーカーのボーイング社が受注した総額190億ドル、200機という旅客機の受注でした。ところが、大型受注で大いに気を良くしているはずのボーイング社は、そのビッグニュースの翌日に、1千人規模のレイオフを発表したのです。要するにボーイング社には、中国から受注した大量の飛行機を、利益率の低い米国内で生産する気がなく、海外生産を拡大する計画を、推進するということなのです。米国の大企業の収益の改善は、国内生産を減らして、労賃の安い海岸生産の拡大によって、齎されているのですね。ですから、企業にとっての景気回復は、雇用の拡大に結びつかず、失業率は高止まりしたままなのですね。国内数%に過ぎない、高額所得者は潤っても、中・低所得者にはそうした恩恵は及ばず、古き善きアメリカを支えてきた中産階級には、分裂と没落の危機が大きく口を開けている。今のアメリカ社会は、私にはこのように映っています。 続く
2011.01.26
コメント(4)
-
日本で最初のパーキングメーター設置 26日の日記
クロニクル 日本で最初のパーキングメーター設置1959(昭和34)年1月26日1959年は、4月に当時の皇太子(現在の平成天皇)の婚儀を控えた年でした。4月10日の婚儀の後の、都内のメインストリートでの馬車パレードは、沿道の大勢の皆さんもにこやかで、ゆったりとのどかな雰囲気に溢れていました。そうです。当時の日本は、各地で渋滞こそ起きるようになっていましたが、まだ今のような車社会ではありませんでした。しかし、都心部ではさすがに駐車スペースが不足し、長時間の路上駐車の締め出し作戦が考えられることになりました。こうして考え出されたのが、路上パーキングの構想でした。都心部の一部道路上に、パーキングメーターを備えた駐車スペースを設けて、時間でいくらという料金を徴収することで、駐車時間を短くしようというわけです。この計画は短時日の内に実行に移され、この日丸の内と日比谷の2ヶ所に設置されました。
2011.01.26
コメント(12)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (8)
アリゾナの銃撃事件を考える(8) ウイィリークスが暴露した米国の機密情報の中に、イラク戦争に関する映像もありました。武装ヘリが、報道されてはまずいと判断した現場を撮影した、ロイター通信の記者を銃撃したと話題になった場面が、その1つです。実際に武装ヘリが、ヘリからの機銃掃射で殺害したのは、ロイターの記者だけではなく、多くのイラク市民をも、位置的に銃撃したものでした。しかも、この銃撃の犠牲となった負傷者を助け、自らの乗用車で病院に運ぼうとしていた民間人にも、機関銃による一斉掃射が浴びせられていました。見るものが、眼を背ける残忍な映像がそこにありました。それは、イラク戦争が不正義の戦争であることを、余す所なく雄弁に暴いている映像でした。元々イラク戦争は、ありもしない「大量破壊兵器」をあると偽って、ブッシュ前大統領が、国連の反対を押し切って、勝手に始めた戦争でした。ですから、それは当初から大義名分のない戦争でしたが、国民に嘘をついて始めた戦争は、戦争の現実を国民から隠すことにしか、継続が困難な戦争に、成り果てていたのですね。こうした事実が、次々に国民の眼に触れて、反対運動が強まっては困る。だからウィキリークスのような存在は、その経営者もろとも消してしまうに限る。こういう姿勢が読み取れます。それはそうですよね。仮定の話ですが、もしイラク戦争の開幕前に、ウィキリークスが誕生していて、湾岸戦争やアフガン戦争に関する、米兵の残虐行為や、戦争の捏造計画が暴かれていたら、アフガンやイラクでの戦争に、国民の支持は得られず、イラクやアフガンの国民を地獄に落とすようなことは、なかったでしょうから…。そして、現在の米国の殺伐とした雰囲気は、イラクやアフガンからの帰還兵によっても、増幅されているのです。 ザビ
2011.01.25
コメント(4)
-
ブット首相出産 25日の日記
クロニクル ブット首相出産1990(平成2)年1月25日21年前のこの日、パキスタンのベナジル・ブット首相(出産時36歳)が女の子を出産しました。現職首相の出産は、世界初のことでした。彼女は、元首相で父のアリー・ブット氏が創設したパキスタン人民党(PPP)の2代目党首として、88年の選挙に勝ち、首相の座についていました。その後、政権を追われたり、首相として再起したりと、波乱の人生を送りますが、3度目の首相への返り咲きかと思われた2007(平成19)年12月27日、イスラマバード郊外での選挙集会において、反対派のテロにより暗殺されました。54歳でした。彼女はイスラム圏で最初の女性首相として知られますが、汚職体質にまみれており、残念ながら、あまり高い評価は与えられていません。
2011.01.25
コメント(10)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (7)
アリゾナの銃撃事件を考える (7)ところで、ウィキリークスのアサンジ氏は、現在も英国で拘束されたままです。拘束理由は、「スウェーデン当局から、○犯罪容疑で引渡しを要請されている」というものです。報道によれば、スウェーデン当局に、アサンジ氏と○交渉を持った女性から、「○行為に際して、アサンジ氏が○○○○○を装着してくれなかったから、彼を○○罪で告訴したい」という、申し出があったというのです。これだけのことで、英国当局はアサンジ氏を逮捕し、今なお拘束しています。しかも、アサンジ氏が英国当局に出頭し、逮捕拘束されてから、かなりの日数が経っていますが、未だにスウェーデン当局から、正式な控訴状は届いていないのです。これは、明らかな人権侵害に見えます。ウィキリークスが公開した「機密文書」やイラク戦争の映像で、米国の威信が大きく傷つけられたとしても、それは意図的な捏造による名誉棄損ではありません。秘密にしておきたかった、自らにとってまずい、そして不利になる事実を暴露されたことに対して逆上し、逆恨みをしているに過ぎません。昨日も記しましたが、ウィキリークスは機密情報の提供を受けて、その真偽を確認した上で、少しづつそれを公表しているに過ぎないのですから…。スウェーデンも語るに落ちましたね。明らかに米国に頼まれて、アサンジ氏の身柄を確保し、出来るなら、彼の身柄を米国に引き渡そうとしているのでしょう。地下のノーベルが嘆いているでしょうね。 続く
2011.01.24
コメント(4)
-
ザ・タイガース解散コンサート 24日の日記
クロニクル ザ・タイガース解散コンサート1971(昭和46)年1月21日1960年代後半は、グループサウンズの全盛期でした。ブルー・コメッツ、スパイダース、タイガース、テンプターズなどなど、次々に人気グループが登場、今も歌われるヒット曲が数多く誕生しました。タイガースにはジュリーとトッポ、スパイダースにはマチャアキとジュン、そしてテンプターズにはショーケンと、人気のヴォーカリストも揃っていました、しかし、グループ・サウンズの絶頂期は短く、60年代の終わりと共に、急速にGSブームは下火となり、中心メンバーたちも、個人として活動するようになり、解散するグループも多くなりました。こうしてザ・タイガースも、1970年末に解散を表明、丁度40年前の今日、武道館で催された解散コンサートを最後に、解散しました。個人的な好みで言えば、タイガースの曲では、トッポが独特の高音でメいーン・ボーカルを務めた「花の首飾り」が、お気に入りです。
2011.01.24
コメント(12)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (6)
アリゾナの銃撃事件を考える (6)オバマ大統領が、"capture or kill" と口走り、CIAが暗殺リストに載せているアン・ワル・アラウキ容疑者の父親は、「息子を暗殺しても良いとする、客観的基準」の開示を求めて、米国の裁判所に提訴しているのですが、政府もCIAも、今日まで何の回答もしていません。ウィキリークスによる、米国の外交文書の暴露問題についても、米国政府や議会の対応には、首をかしげざるを得ない発言や行動が、多々あります。創始者のジュリアン・アサンジ氏に対し、堂々とテレビで「アサンジを始末しろ」と叫んでいる議員が、何人もいることです。ウィキリークスが入手した外交文書は、同社が盗み出したものではありません。内部告発者であるブラッドリー・マニング氏から、提供を受けたものです。ですから、ウィキリークス社や、責任者のアサンジ氏に、窃盗罪を適用することすら無理なのです。アサンジ氏とウィキリークスは、提供された情報を少しづつ、公開する作業を進めているに過ぎません。これはまさしくテレビや新聞、雑誌などのメディアが、日常的に行なっていることと同質のものです。ウィキリークスから情報提供を受け、それを紙面に掲載した報道機関も多々あります。イギリスのガーディアン、ドイツのシュピーゲル、アメリカのニューヨーク・タイムズなどが該当するのですが、こうした報道機関は、お咎めなしで、何故ウィキリークスとアサンジ氏のみを攻撃するのでしょうか。しかも、窃盗容疑で逮捕しろではなく、「殺してしまえ」なのです。裁判にかけても有罪に出来る自信はない。しかし、彼とウィキリークスは邪魔で危険だ。だから始末してしまえ。こういう発想が透けて見えます。だからこそ、国会議員という公人が、マスコミを通じて、白昼堂々「アサンジを暗殺しろ」と叫んでも、何の咎めも受けないと言えましょう。現在のアメリカは、ここまで倫理的に腐敗してしまっているのですね。私は、この事実が残念でなりません。 続く
2011.01.23
コメント(10)
-
「ゴキブリホイホイ」発売 23日の日記
クロニクル 「ゴキブリホイホイ」発売1973(昭和48)年1月23日アース製薬の「ゴキブリホイホイ」、ご存知ですよね。当時好感度no,1と言われた由美かおるをCMに起用し、大ヒットした商品です。今でも関連商品の売れ行きは好調で、殺虫・防中関連商品でのアース製薬のシェアは、50%近いと言われています。実はこのアース製薬、ゴキブリホイホイ発売の3年前、1970年に会社更生法を申請し、一度倒産しています。この会社を買収し、再建を引き受けたのが、大塚製薬でした。こうして大塚製薬の傘下に入ったアース製薬は、ゴキブリ捕獲器の開発に社運をかけ、除虫菊の成分から、ゴキブリ誘引剤を取り出すことに成功したのです。この発見が、誘引剤で誘い込んだゴキブリを、粘着剤で動けないようにして、箱ごと捨てる「ゴキブリホイホイ」の誕生に繋がりました。「ゴキブリホイホイ」は他社製品に比べて、捕獲力が高く、しかも誘引剤であるため、殺虫成分を含まず、薬剤の使用に問題のある小児や小動物のいる家庭にも歓迎され、爆発的大ヒットになりました。勿論アース製薬の経営再建も、ここに軌道に乗りました。
2011.01.23
コメント(18)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (5)
アリゾナの銃撃事件を考える (5) パナマ運河のクルーズからお帰りになった、リンダ夫人はご存知だと思いますが、ブッシュ大統領は、オサマ・ビン・ラディンを”capture or kill"と叫んでいました。「生け捕りにしろ、抵抗するなら殺してもかまわん」と訳すと上品過ぎるでしょうか。ともかく、あまり品が良いとは言えない表現で、その抹殺を命じていました。9,11事件がビン・ラディンの命令に基づくものとする、明確な証拠は今日現在明らかにされていませんから、彼に対する "capture or kill"という命令は、超法規的で恣意的な処刑命令になりますから、これは国際法に違反する命令でした。そして実は、オバマ大統領もまた、ある人物に対して、"capture or kill"と、ブッシュ前大統領と同じ表現で、「殺してしまえ」と発言しているのです。その人物とは、アン・ワル・アラウキという米国生まれのイスラム聖職者です。アラウキ氏は米国籍を持ち、イエメンを拠点に活動する人物です。そしてCIAは、彼を生死を問わない追跡対象者のリストに加えています。そしてCIAは、アラウキ氏がこのリストに加えられた最初の米国民であることも、明らかにしています。CIAは、その根拠として、彼がクリスマスに起きた航空機爆破未遂事件と、フォート・フッド基地での乱射事件に関わりがあることを、示唆しています。しかし、これも諸侯は示されていません。そしてあろうことか、こうした曖昧な状況のなかで、オバマ大統領までが、アラウキ氏を「殺しても構わない」と発言しているのです。証拠不十分の状態での暗殺許可指令は、専門家筋から、国際法は勿論、米国の国内法にも抵触する可能性が指摘され、合法性に疑問が出されているといいます。こうした事実を踏まえてみると、今回の事件でのサラ・ベイリンやジェシー・ケリーの言動を問題視して追求すれば、いずれその矛先が、自身にも及んでくる可能性が、残っていたのです。オバマ大統領としては、そうした展開だけは避けなければならず、事件を、その背景を含めて徹底追及することを避け、国民の結束を呼びかけるという、ありきたりの内容にとめざるを得なかったのでしょう。 続く
2011.01.22
コメント(8)
-
血の日曜日 22日の日記
クロニクル 血の日曜日1905(明治38)年1月22日106年前のことです。明治38年ですから、日露戦争の最中。戦争の相手国だったロシア帝国の当時の首都ペテルブルグで起きた惨劇のことです。当時のロシアは、ギリシア正教に近い、ロシア正教を国教としていて、西暦とは少し異なるロシア暦を採用していました。西暦の暦から13日を引くとロシア暦に、ロシア暦に13日を加えると西暦になります。レーニンを指導者とするボリシェヴィキ(後のロシア共産党)が権力を掌握したロシアの革命を十月革命と言ったり、十一月革命と言ったりするのは、前者がロシア暦を基準に叙述しているのに対し、後者は西暦を基準に叙述するからの違いで、どちらも正しいことになります。ややこしいですね。で、血の日曜日事件は、西暦でいう今日1月22日に起きましたから、ロシア暦では1月22日のことになります。20世紀初頭のロシアは、フランスからの借款を頼りに工業化を進めていましたが、日露戦争当時は不況に喘いでおり、そこに戦争の負担が重なって、貧民の暮らしはどん底状態にありました。そんな民衆たちは、この日ロシア正教会の司祭ガポーンの指導の下に、この日自分たちの苦しみを訴えに、ツァーリ(皇帝)の下へと請願行進を行なったのです。民衆は、ツァーリを信頼し、ツァーリに直接訴えれば何とかしてもらえると。信じていたのです。今の窮状は、悪い官僚やツァーリ側近が、嘘の報告を繰り返し、ツァーリが実情に気付かないようにしているせいだ。こう考えていたのです。そのため、ガポーンの打ち出したツァーリへの請願行進は、貧しい民衆の心を捉え、この日の行進には、近在の村々を含めて、10万人以上の民衆が参加したのです。こうして雪の冬宮前広場は、群集で埋め尽くされます。武器を持たない素手の人々の集まりでしたが、あまりの大群衆の出現に、恐怖心に襲われた守備隊は、隊長の命令と共に、無抵抗の民衆に一斉射撃を浴びせたのです。雪の冬宮前広場は、血で染まり、大勢の犠牲者を出したのです。この事件の様子は、ロシア各地は勿論、広く世界に報じられ、ロシア各地では、次第に抗議行動が広がり、ツァーリに対する民衆の盲信が崩れるきっかけとなったのです。この血の日曜日事件をきっかけとする、ロシアにおける革命情勢の進展(最終的には失敗に終りますが、第一次ロシア革命と呼ばれます)は、ロシア政府をして、日本との戦争の継続は困難との認識に導きます。その結果が、アメリカ西海岸ポーツマスでの、日露交渉の受諾に繋がりました。この血の日曜日事件がなかったとしたら、日露戦争の帰結は、また違ったものになっていたように思われます。
2011.01.22
コメント(4)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (4)
アリゾナの銃撃事件を考える (4)前回に記した米国の州財政の状況を考えると、アリゾナでの銃撃事件は偶発的なものではなく、今後似たような財政状況にあって、住民サービスを大幅に縮小している諸州で、続発する可能性を秘めています。それ故に、こうした犯罪を強く非難し、銃撃を教唆する宣伝を繰り返した共和党保守派の議員や政治家たちの言動に、枠をはめる強さが、米国の政治と司法に求められると、私は考えます。否、私だけでなく、一般の日本人であれば、大多数の方がそう考えるのではないでしょうか。ところが米国は違うのです。アラバマ州議会が、この期に及んで、なお銃規制を緩めようとしていることは、第2回に書きました。問題はノーベル平和賞まで受賞したオバマ大統領にあります。彼は1月12日に、アリゾナ州立大学で開かれた6名の死者への追悼式で、大略次のように述べたのです。彼は、事件の背景とされる過剰な政治対立に触れ、「今回の事件が、新たな分裂を招くようなことがあってはならない」と、国民の結束を呼びかけた上で、事件は狂信的個人の犯行であって、それを理由に共和党、特に最右派のティー・パーティの選挙戦術や政治路線を、問題にするのは誤りであるとし、「一瞬立ち止まって、対話が互いを傷つける方向にではなく、問題を解決する方向に向かっているかどうかを、確認する必要がある。」と述べたのです。一般論としては尤もに聞こえますが、これで犠牲者の家族や友人、ギフォーズ会員議員やその支持者が納得できるでしょうか。きれいごとでお茶を濁した発言のように、私は受け止めました。良く考えるまでもないのですが、対立候補、対立陣営を口汚くののしり、暗殺を示唆するメッセージを、インターネットやテレビなどで流し続けた特定人物を、真正面から非難し、批判の嵐を加えなければ、相手は益々付け上がり、類似のメッセージを流し続け、第2、第3の犠牲者を生み出すでしょう。平和の使途のはずであるオバマ大統領のメッセージが、何故このように心に残らないアピールに留まるのでしょうか。 続く
2011.01.21
コメント(10)
-

ルイ16世処刑 21日の日記
クロニクル ルイ16世処刑1793(寛政5)年1月21日フランス革命200年の1989年は、日本では昭和から平成に移行した年、国内的にはバブル景気に浮かれ、何人ものバブル紳士が、そうとも知らずに束の間の我が世の春を謳歌していました。そして世界では、ベルリンの壁崩壊に代表される東欧革命の年として、ソ連圏とソ連の影響力とが、音を立てて崩れ落ちていった年でした。今日取り上げるのは、200年以上も昔のことになったフランス革命からです。218年前のことになります。丁度日本では、松平定信の寛政の改革に対する庶民の怨嗟の声が高まり、夏には彼が失脚する年に当たっています。そんあ時でした。フランス革命が本格化してから3年半のこの日、国王ルイ16世が、革命広場(現在のコンコルド広場)のギロチン台に引かれ、処刑されたのです。ルイ16世の処刑直後の光景を描いた、当時の絵です。前にも掲げましたが、再掲します。国王処刑のいきさつについては、2007年に連載した「フランス革命」のシリーズのうち、no,33~36(07年8月13日~15日掲載)を、ご覧下さい。
2011.01.21
コメント(10)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (3)
アリゾナの銃撃事件を考える (3) ギフォーズ下院議員の襲撃事件は、アリゾナ州で起きました。彼女はアリゾナ州選出の議員ですから、当然といえば当然なのですが、そう割り切ってしまっては先が見えません。ここで、リーマンショック後のアリゾナ州の状況を検討してみましょう。最近日本のマスコミも少しづつ取り上げるようになってきたのですが、米国の財政状況は、中央政府だけではなく、州財政もまた極端に悪化している州が増えています。私も昨年カリフォルニア州の置かれた大変な状況を、少しだけ記しました。日本の場合も中央政府だけでなく、地方自治体の財政状況もひどいことになっているのは、北海道夕張市の例以後、かなり明るみに出されてきました。米国も似たような状況にあるのですが、1つ日本とは決定的に違っている点があります。それは中央の財政と州の財政が、互いに完全に独立している点です。地方交付税とか、中央からの補助金というシステムは、米国にはありません。これは現在休載中の「19世紀のアメリカ」のシリーズの序章に記したことですが、合衆国建国のいきさつに原因があります。出来るだけ地方即ち州の権限を侵さない、緩やかな連邦制を目指すという合意でスタートしましたから、財政自主権は州にあり、州の権限を侵さない範囲で連邦政府の徴税権が認められたのが、米国の租税制度でした。ですから、財政難に陥った州は、中央政府による救済に期待を寄せることは出来ず、自助努力で財政難を解決しなければならないのです。そこでどうするか。それが大変ドライなアメリカ的やり方なのですが、出来ないから仕方がないとばかりに、住民サービスその他、お金の掛かることは、次々に縮小または廃止しているのです。学校の先生、警察官、消防士、清掃作業員などを、バサバサと削り、児童や生徒は学年ごとに日替わりで登校するため、1人の子どもが受ける授業は週に2日だけといった状況になっています。街路にはゴミが溢れ、警官不足による犯罪の増加と続きます。それだけではありません。年金などの社会保障も大幅に削られています。さらには州議会や州庁舎といった州の資産も次々に売却し、売却先からリース契約で借り受けて、業務を遂行する体たらくなのです。もちろん、病院や医療も例外ではありません。銃撃犯のロフナーも、アリゾナ州の精神医療サービスに対する予算が、大幅に削られたがために、精神科医によるカウンセリングが「受けられなくなっていたというのです。信頼する医師と面談することも出来ないことから、不安心理を募らせたロフナーは、テレビやネットを通じた悪魔の呼びかけに、大きく心を揺さぶられたであろうことが、推察できます。リーマンショック後の米国の現状が、今回の事件の底流として横たわっている。このように思えてなりません。 続く
2011.01.20
コメント(4)
-
大和運輸「宅急便」サービスを開始 20日の日記
クロニクル 大和運輸「宅急便」サービスを開始1976(昭和51)年1月20日丁度35年になるのですね。この日、大和運輸(現在はヤマト運輸)が「宅急便」サービスを開始しました。クロネコヤマトの宅急便の誕生です。大和運輸は、三越や松下電産の専属配送業者でした。上得意を持っていたため、他社が構想道路網の整備を追い風に長距離輸送に進出した際に出遅れ、業績不振に陥りました。このままではまずいと気付いた新社長の小倉昌男氏は、個人を相手に、小口貨物を沢山扱うことで、利益を得ようと大口中心の発想を転換、「電話1本で集荷に伺う・1個でも家庭へ集荷に出向く・翌日配達」を合言葉に、営業を展開。大成功を納めたのです。今では、誰でも知っている宅急便ですが、サービス開始の初日、35年前の1月20日の集荷数は、11個だったそうです。良くここまで伸びましたね。
2011.01.20
コメント(22)
-

新年の餅つき
新年の餅つき今晩は。私の住む川崎市には、子ども文化センターという川崎市独自の子どものための施設があります。その施設も、ここ15年ほど、財政難を理由に、様々な変遷を遂げてきているのですが、折角の子どものための施設は、何とか残そうと地元もいろいろ協力して、今日まで何とか存続してきています。その子ども文化センターで、今日は餅つきが行なわれました。地元の旧家から餅つきの諸道具一切(蒸篭や竈から、火をたく雑木まで)を提供して戴き、町内の役員や有志が、職員と協力して釜番から、餅つき、キナコや海苔、アンコロなどのお餅の製作まで、一切を手伝うのです。10時半から火を熾し、11時からつき始め、昼前は自主保育グループの親子連れや、近所の保育園児たちが、餅つき風景を見がてら、お餅を食べにやってきます。19日の水曜日は、近隣の2つの小学校が、いずれも4時間で授業終了。子ども達もお餅つきに参加しやすいのです。午後1時になると、大急ぎで下校してきた子ども達がやってきます。去年も参加した子達は。楽しかったことを覚えているのでしょう。早く来ると、いっぱい杵で搗かせてもらえることを知っているのです。この子達は10回づつ、搗くことが出来ました。1時半を回ると、川崎市独自の学童保育施設のワクワクプラザの子ども達が、集団でやってきます。60人を越える子ども達を、4グループに分け、1人5回づつ子供用の杵で、餅を搗きます。みんな張り切って頑張りました。子供用でも杵は重いので、上級生以外は、みんな杵をもちあげて搗くのが一苦労でしたが、どの顔もとっても嬉しそうでした。
2011.01.19
コメント(14)
-
日本航空会社更正法申請 19日の日記
クロニクル 日本航空会社更正法申請2010(平成22)年1月19日あれから丁度1年になるのですね。日本航空と子会社2社が、この日会社更生法を申請して倒産しました。あれから1年、現在なお再建に苦しんでいますね。国鉄は分社化した民営化で、本州3社は黒字化し、株式上場も果たしましたが、さて日航はどうでしょうか。JRとは環境が違いすぎます。JRは夫々に独占的な路線を持つ国内企業です。日航の場合、世界の航空会社がライバルですから、こうしたライバル、時には格安航空会社との競争に耐えるコストパフォーマンスを実現する必要がある上に、国内にもANAというライバルがいます。私には、民主党に拝み倒された、稲盛会長が気の毒に見えてなりません。
2011.01.19
コメント(8)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (2)
アリゾナの銃撃事件を考える (2) 問題は、サラ・ベイリンに留まりません。アリゾナ州の選挙区で、民主党のギフォーズ候補と大接戦を演じた共和党の候補は、ジェシー・ケリーという若者でした。彼はイラク戦争への従軍経験を持ち、そのことを恰好の宣伝材料として、共和党候補にのし上がった人物でした。選挙用ポスターに、銃を持って立っている自分の姿を大写しにして用いていることが、そのことを明白に物語っています。そのケリー候補は、「オレと共にM16自動小銃を手にして、ギフォーズを消せ!」と、何度も呼びかけていたというのです。同じアリゾナ州選出の同僚議員が、そう語っています。証言者を探せば、大勢出てくるでしょう。銃撃犯のロフナーは、昨日記した通り、重度の精神不安定に陥っていた青年でした。現在全米各地で、こうした若者が増えているのですが、アリゾナ州はその中でも、目立って多い州のひとつです。州の保安官の1人は、こうした事実を踏まえて、次のように語っています。「精神的に不安定な人は、この国で普通に使われている、レトリックの影響を受けやすい。」それは疑いのない事実だ」と。こう見てくると、サラ・ベイリンも、ジェシー・ケリーも、誰かが実際にギフォード議員を銃撃することを、密かに期待していたであろうことが、容易に想像できます。これが日本ならば、未必の故意による殺人並びに殺人未遂事件での立件を視野に、警察が動いているでしょう。それが米国ではどうでしょうか。亡くなった6人の内の1人は、奇しくも9年前の9/11事件当日に生まれた9歳の少女でした。近くのスーパーにギフォーズ議員が来るというので、彼女を見るために、近所の方と一緒に出かけて、命を落としています。 この事実が報道され、全米から哀悼の意が、アリゾナの彼女の両親の下に届けられています。それにもかかわらず、アリゾナ州議会は、銃規制をさらに緩め酔うとしているのです。元来アリゾナ州は、米国内でも銃規制の緩い州の代表格なのですが、それをさらに緩め、「大学などにも、自由に銃を持ち込めるように…」しようという案が、共和党中心に検討されているというのです。ここには、今回の銃撃事件を反省し、再発防止を真剣に考えようという姿勢は、微塵も見えないように思えます。 続く
2011.01.18
コメント(12)
-
熊沢天皇登場 18日の日記
クロニクル 熊沢天皇登場1946(昭和21)年1月18日焼け跡が各地に残る、敗戦後の混乱期のことです。敗戦の年が明けた1月1日には、天皇の人間宣言が、各紙の一面トップで大きく取り上げられ、天皇制の雰囲気がなお色濃い、日本国民を驚かせて間もない頃でした。この日、名古屋で雑貨商を営む熊沢寛道さんの、「自分は南朝の子孫で、南朝こそが日本の正統の皇位継承者である」とする主張が、新聞各紙で大きく取り上げられ、また国民を驚かせました。各紙は彼を熊沢天皇として、紹介したのです。彼は、前年11月にGHQに、自己の主張を記した嘆願書を出しており、それに眼をつけた米誌「ライフ」の記者が、彼にインタビューした記事が、「ライフ」に大きく取り上げられ、日本の各紙が「ライフ」に追随した結果が、この日の記事に繋がったのでした。子供の頃の、小中学校での歴史の授業では、彼のことが語られましたが、戦中の授業では、南北朝の騒乱は、教科書からも抹殺されていましたから、国民は隠されていた天皇家の騒乱を、ここから学んだのですね。逆賊とされてきた足利尊氏の再評価も、これからでした。
2011.01.18
コメント(10)
-
アリゾナの銃撃事件を考える (1)
アリゾナの銃撃事件を考える (1)米国南部アリゾナ州での銃乱射事件、眼を覆うような事件でしたが、米国社会に巣食う根深い問題を提示しています。ブログ仲間のマダム・リンダが、カリブ海のクルーズ中でお留守なのが残念ですが、後日議論に加わって戴きましょう。私が最も言いたいことは、こんな米国が果たして民主国家で自由の戦士なのかという点にあります。まるで、、非民主的なテロ国家そのものに見えるからです。事件は、地元トゥーソンのコミュニティ・カレッジの学生で、精神不安定を理由に停学処分を受けていた学生(つまり、学内で事件を起こす可能性があるから、しばらくカレッジに来てはいけないとされたのですね)が起こしました。同州選出の民主党のガブリエル・ギフォーズ下院議員が瀕死の重体、会場にいた同議員の支持者など6名が死亡という悲惨な事件でした。ギフォーズ議員は、昨年秋の中間選挙で、共和党の相手候補との激戦を制して、僅差で勝利し、1月からの新議会での活動を開始したところでした。その新議会で、彼女は選挙戦中の衝撃の事実を明らかにしています。彼女は新議会で、合衆国憲法の修正第1条にある「表現の自由」の部分を読み上げ、選挙中に行われた自らに対する脅迫の事実を、明らかにして、厳しく非難したのです。選挙期間中に、彼女の選挙事務所が銃撃されて粉々にされたり、従を所持した男が事務所に乱入して、居合わせた運動員を脅迫したりしていたのです。 同じく選挙区は異なりますが、同じアリゾナ州の民主党下院議員候補、ラウル・グリハルバ候補の事務所でも。同じような事件が頻繁に起き、ついには同所の事務所を閉鎖する事態も起きていました。昨秋の中間選挙は、そうした殺伐とした空気の中で行なわれ、選挙後もそうした空気が残っているのです。そして、前共和党副大統領候補だったサラ・ベイリン元アラスカ州知事の選挙事務所は、昨年の中間選挙の際にウェブ上で、激戦が予想される選挙区にライフルの「標的マーク」である「照準線」を記した米国地図を、公開していました。ギフォーズ下院議員の選挙区にも、当然「照準線」が合わせられていました。しかもそれだけではないのです。「撤退せずに再装填だ。弾を込めなおせ!」を政治スローガンにしていたのです。まさに、サラ・ベイリン自身が、暗殺を仄めかしていたのです。本気で実行するとは思わなかったで済むことでしょうか。この点は後で考察しますが、ギフォーズ議員の暗殺を暗示していたのは、実はサラ・ベイリンに留まらないのです。ギフォーズ議員の対立候補だった、ジェシー・ケリーという若者もまた、より直接的に、暗殺を訴えていたのです。 続く
2011.01.17
コメント(6)
-
民撰議院設立建白書 17日の日記
クロニクル 民撰議院設立建白書1874(明治7)年1月17日昨日、どんど焼き後の打ち上げの席で話が出たのですが、今年100歳を迎える方々は、明治44年にお生まれの皆さんです。年の初めに来年の話は気が引けますが、話の運びでお許しいただくと、来年はいよいよ大正生まれの方が100歳を迎えられることになるのですね。1912年は、明治45年兼大正元年ですから、考えてみれば当然なのですが、思えば私の中学・高校時代は、1955年4月~61年3月まででしたから、100年前は黒船登場以後の幕末の混乱期でした。「明治は遠くなりにけり」ですね。今日取り上げた「民撰議院設立建白書」の提出、今年からすると137年も前の話になります。そうなんです。かつての100円札の主、板垣退助(彼の「板垣死すとも自由は死せず」って言葉、この人は紙幣の顔になる価値のある人だと、思ったものです)や後藤象二郎、江藤新平ら8名が、連名で政府に国会開設を願う意見書を、提出したのです。彼らの主張の根拠は、当時「天賦人権説」と呼ばれていたルソーの社会契約説にありました。その具体的な内容は、専制政府を批判して、天皇と臣民一体(君民一体)の政体を作ることを主張したもので、士族や豪農・豪商ら一定の教育を受けた平民に参政権を与え、議会を開設することを主張したものでした。政府は時期尚早と回答したのですが、この建白書に賛同する意見書が、多数提出され、自由民権運動の活発化に繋がってゆきました。
2011.01.17
コメント(10)
-

どんど焼き
どんど焼き15日の小正月を1日過ぎてしまいましたが、今日は地元の氏神さまの社の近くで、どんど焼きが行なわれました。社の広場は、手狭なため、ご近所の方の休耕田を毎年拝借しています。午前中に役員が総出で賽の神の祠を作ります。およそ、2時間をかけて完成した祠です。午前中に準備を整え、1時から始まりです。地元の子ども達には、女性役員たちが上新粉を捏ねて作ったお団子とみかん、そして飲み物を提供するため、子供連れ、親子連れの参加も増えています。皆さん、取り外したお飾りや書初めなどを持参して、祠と一緒に燃やします。役員の挨拶後、お神酒を戴いて、いよいよ火入れです。写真は今年の当番役員の皆さんです。火が入ると、年末依頼、日本全国のなかで、ここだけ雨とも雪ともご縁がなく、晴れた日の続いている南関東ですから、アッという間にご覧のように燃え上がります。お飾りや書初めなども、一緒に燃えました。午前中は、時々強い風が吹き、このままでは火勢が強くなりすぎると心配されたのですが、幸い昼頃から風も弱まり、消防団にお願いして、近くまでポンプ車に出動していただいて、滞りなく実施することが出来ました。火勢が弱まり、熾きができると、いよいよダンゴを焼く番です。賽の神の火で焼いたお団子を食べると、1年病気をせずに元気で過ごせるという言い伝えによるものです。それで、おダンゴの提供もするのです。しかもお団子を刺して焼くための竹竿も、毎年役員たちが、近くの竹薮から切り出して、貸してくれるのです。さあダンゴ焼きが始まりました。風が軽く回るため、煙があちこちにたなびいて、皆さん煙をよけるのに必死でした。小学校の先生方も、児童や父母と一緒に団子を焼いていましたが、火の熱さと煙に悩まされていました。で、後半は、長老たちに教えられて、ブロックを借りてお団子を刺した竹竿を置き、お団子が焼けるのを待ちました。焼きあがるとダンゴを抜いて、竹竿を待っている方に渡して、次の方が焼くのです。全員のおダンゴが焼けたところで、火を消して後始末。ご苦労会に移ったのは、寒さの増した4時半頃でした。私は今回も勿論写真係。今年は2月の節分祭も鬼の役は免除されています。そうそう、どんど焼きの氏神さまは、地元に3箇所ある小さな社で、行なわれます。節分や獅子舞に登場する神社は、そうした小さな社を束ねる大きな神社で行なわれるのです。地域の永年の慣行ですね。
2011.01.16
コメント(20)
-
Jリーグ初代チャンピオン決まる 16日の日記
クロニクル Jリーグ初代チャンピオン決まる1994(平成6)年1月16日昨年は、4年に1度のサッカーワールドカップ、南アフリカ大会での日本チームの活躍に沸きました。プロサッカーリーグ、Jリーグを頂点とする育成システムの成果が、ようやく現れてきたようで、嬉しいことでした。さおのJリーグ、1993年に発足、参加10チームで1年目がスタートしました。チーム数がまだ少なかったので、前期、後期の2部制として、夫々が全チーム2回総当りの18試合で優勝チームを決め、最後に年間チャンピオンシップを行なって、総合優勝チームを決める方式をとりました。こうして、94年の1月に入って、前期優勝チームの鹿島アントラーズと、後期優勝のヴェルディ川崎によって、チャンピオンシップが戦われ、17年前のこの日、ホーム・アンド・アウェー方式の戦いの2試合目が行われました。結果は2試合合計3対1で、ヴェルディ川崎が初代チャンピオンに輝きました。そのヴェルディ川崎、プロ野球方式に固執する読売グループが、Jリーグに対する横槍を拒否されて、つむじを曲げて手を引いた結果、弱小チームに成り下がり、東京ヴェルディとなった現在は、その存続すら危ぶまれています。常に上位で大活躍している鹿島アントラーズとは、天と地ほどの差がついてしまいました。残念です。
2011.01.16
コメント(8)
-
ユーロの憂鬱 (38)
ユーロの憂鬱 (38)共通通貨ユーロとEUの抱える問題点のあれこれを記してきました。なんだか終わりのない右往左往を見物しているようにも思えるのですが、ユーロの今後はどうなるでしょうか。共通通貨ユーロは、間違いなくかなりの無理を抱えています。ドイツとギリシアやポルトガルで、同じ通貨が使われるのです。同じ通貨ですから、ドイツとギリシア、ドイツとポルトガルで、ECB(欧州中央銀行)が定めたたった一つの政策金利が適用されているのです。ですから、ユーロの加盟国は、為替変動に対しても、国ごとの経済情勢の変動に応じて、きめ細かく金利を調整するなどの、金融政策による対応や調整を、行なうことが出来ないのです。ドイツでは、その経済的実力からして、常に通貨が安すぎ、金利が低すぎることから、景気が過熱してインフレが生じる恐れを抱えています。逆にギリシアやポルトガルは、経済的実力からして不相応に、通貨が強すぎて、金利が高すぎることから、景気が一段と後退する危険性が色濃く残っています。こうした矛盾を抱えているのが、ユーロなのです。こうした矛盾は、最近良く言われるようになった、ドイツマルクがユーロから離脱するか、ギリシアやポルトガル、アイルランド等の通貨を、ユーロから切り離すか、この2つのどちらかを実行しない限り、解決することはありえないでしょう。しかし、そうすることは、今まで続けてきた欧州統合に向けて、営々と築きあげてきた努力を、全て無に帰すことに繋がります。それゆえ、この決断を下すこともまた、容易なことではないのです。 続く
2011.01.15
コメント(4)
-
双葉山敗れる 15日の日記
クロニクル 双葉山敗れる1939(昭和14)年1月15日72年前の今日は、大相撲1月場所の4日目でした。前日まで69連勝を続けていた横綱双葉山にとって、この日の一番は70連勝のかかった一番でした。そしてこの日双葉山は安藝ノ海の外掛けに敗れ、古来稀なりの70連勝には届かなかったのです。勝利した安藝ノ海は出羽の海部屋の新鋭で、双葉山とは初対戦で、巡業中の稽古の経験もなく、取り口を全く知られていなかったことが幸いしたとも言われていますが、出羽の海部屋あげての打倒双葉山の作戦で、投げにきた時に足を狙えと、教えられていたと言います。最近、横綱白鳳の63連勝が話題となりましたが、双葉山以前の連勝記録は、横綱谷風の63連勝と、奇しくも白鳳とタイの連勝記録でした。双葉山の連勝記録は、小結だった1936(昭和11)年1月場所の7日目に始まります。前日はこの場所全勝優勝を飾った横綱玉錦に敗れています。この場所9勝2敗で関脇に上がり、以後この日の敗戦まで負けしらずの連勝を続けたのでした。当時は年2場所、1場所11日間の興行でしたが、36年5月場所11戦全勝、翌年1月場所も全勝と続くと、双葉山人気が盛り上がり、同年5月場所からは、13日興行に伸びたのです。ですから、同年5月そして38年の1月、5月と13戦全勝を続け、66連勝として、39年1月場所を迎えたのでした。まる3年にわたって、連勝を続ける緊張感に耐えたのですから、やはり不世出の大横綱と言えるのでしょうね。ところで、双葉山に勝利した安藝ノ海ですが、彼は勝って驕らず、親方や先輩から、あの双葉関に勝ったオマエも、負けて話題になるような力士にならなければ、双葉関に失礼になると諭された教えを守って、稽古に励み、4年後の1943(昭和18)年1月場所後、照国と共に横綱に推挙されました。ところで、その後双葉山と安藝ノ海と8度対戦していますが、双葉山の8連勝に終っています。以上、小学生時代に、オヤジに何度も聞かされた話です。東京大空襲で焼け出されるまでの我が家は、当時の両国国技館の近くにあり、呼び出し太郎さんのお宅の近くだったとか。オヤジは相当な相撲狂だったのです。
2011.01.15
コメント(10)
-
ユーロの憂鬱 (37)
ユーロの憂鬱 (37)昨日記したように、EU加盟諸国の金融機関の連鎖は、闇に包まれている部分も多いのですが、とりあえず公表されている部分、並びに公表はされていないけれども周知されている部分を、ここに記してみますと、次のようになります。バルト3国、エストニア、ラトヴィア、リトワニアの3国に対する融資では、スウェーデンの金融機関が突出しています。東欧のうち、西欧世界と接するチェコ、スロバキア、ルーマニア、ハンガリー等に関しては、オーストリアの融資が目立っています。そして、そのオーストリアの金融機関には、ドイツとイタリアの銀行が大量に貸し込んでいます。そして、ポーランドに関しては、ドイツの銀行が最大の貸し手となっています。こうした点は、BISが発表する「国際与信統計」からも、確認することができます。同じように、アイルランドとギリシアについては、イギリスの与信が図抜けていますし、スペインとポルトガルは、いくつもの国から融資を受けていますが、地理的に近いフランスがの融資が最大となっています。そして、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、イタリア、スウェーデンといった国々の金融機関同士の繋がりが、どうなっているかという点になると、複雑すぎて詳細は分らないというのが、正直なところになるのです。ですから、EU加盟国のどこかで、国家が支えきれずに大手金融機関のデフォルトが発生すれば、それが原因で各国の金融機関が連鎖的に倒産する、破綻の連鎖が起きかねないのです。 続く
2011.01.14
コメント(4)
-
文学座分裂 14日の日記
クロニクル 文学座分裂1963(昭和38)年1月14日文学座は、1937(昭和12)年に岸田國士、久保田万太郎、岩田豊雄の3名を発起人として設立された、日本新劇界の名門劇団です。俳優座や民芸と共に三大新劇団とも称されます。その文学座で48年前のこの日、芥川比呂志を筆頭に、文学座の中堅・若手劇団員29名が劇団に退団届を提出し、英文学者の福田恆存と共に劇団「雲」を設立し、脱退者全員が参加することを表明しました。この集団脱退は、日本の演劇界始まって以来の大事件として、マスコミの注目を集め、その後に脱退劇を巡る、様々な報道がなされました。ただし、テレビや夕刊紙の普及以前のことですから、週刊新潮などの報道も、決してセンセーショナルなものではなかったのですが…。報道によると、脱退劇は、全て隠密裏に進められ、文学座幹部の中村伸郎や杉村春子らは、当日になるまでこの集団脱退に、全く気付かなかったそうです。この集団脱退の背景には、ベテランと中堅・若手陣とのズレがあり、彼らに大きな不満が蓄積していたことがあったようです。脱退した29名の中には、芥川比呂志、高橋昌也、加藤和夫、仲谷昇、小池朝雄、名古屋章、神山繁、三谷昇、岸田今日子、文野朋子、加藤治子ら、その後も演劇やテレビ、映画などで活躍した人たちが含まれていました。また文学座は、この集団脱退のあった同年の11月に、正月公演に決まっていた三島由紀夫の戯曲 『喜びの琴』の上演を、思想上の行き違いを理由に中止しました。このことをきっかけに、同劇団の幹部・中堅の矢代静一、松浦竹夫、中村伸郎、北見治一、賀原夏子、丹阿弥谷津子、南美江、村松英子ら14名が、再度同劇団を集団で脱退するという事件に見舞われました。
2011.01.14
コメント(6)
-
ユーロの憂鬱 (36)
ユーロの憂鬱 (36)ドバイショックを引き金とした、第3次BIS規制の導入延期は、イギリス金融機関のドバイへの巨額貸付と、その不良債権化を明るみに出しました。巨額の不良債権の存在は、当然該当する金融機関の存続を危うくします。実は、こうした巨額貸付を欧州や米国の銀行は、その多くが抱え込んでいるのです。しかもそうした巨額貸付は、アメリカの銀行よりもヨーロッパの銀行の方が、数多く抱えていると考えられています。EU加盟国のメガバンクは、東欧や北欧、南欧のみでなく、ロシアや中東、さらには南米やアジアにまで触手を伸ばし、多額の資金を貸し付けているのです。彼らは何故、そんなに欲張って融資を拡大しようとするのでしょうか。それは、欧州の巨大金融機関の資産規模が巨大化し、1国のGDPの規模を遥かに凌駕する規模に達しているからです。そのような巨大銀行が破綻したとしたら、国有化によって救済しようにも、資金が足りませんから不可能になります。頼りは国際金融界も協調融資しかありません。そしてもう一つ、リーマンショックで明らかになったことは、金融機関同士の取引が、網の目のように複雑に絡み合って、どこがどこに繋がっているのかが、誰にも分らなくなってしまっているということでした。デリバティブ取引の普及の結果、コンピューターに計算させた複雑な仕組みが、こうした結果を導いたのです。そして欧州の場合、EUという国境を超えた統一市場が存在し、金融機関の国境を超えた合併なども、数多く行なわれています。そうしたメガバンクが、単一の金融市場で競争し手いるのです。金融システムのシステミックリスクを、計量しようとしても、何処まで正確に計量できるかは、かなり疑わしいといわざるを得ないのです。事実ECBが昨春(2010年春)実施した金融機関のストレステストで、正常と診断されたアイルランドの銀行は、半年後の10月末には、格付け機関によって、破綻懸念先(あえて我々の馴染みの言葉で表現しました)に分類されているのです。 続く
2011.01.13
コメント(6)
-
日劇ダンシングチーム初公演 13日の日記
クロニクル 日劇ダンシングチーム初公演1936(昭和11)年1月13日丁度75年前のことです。前年9月から選ばれてショーダンサーとしてのレッスンに励んでいた、日劇ダンシングチームのメンバーが、この日初舞台を踏んで、デビューしました。演目は「ジャズとダンス」。日劇ダンシングチーム(NDT)と名乗ったのは、6月の第4回公演の時からです。1977(昭和52)年4月公演をもって、定期公演を終了、81年2月の日劇の閉館と共に解散しました。歴代のメンバーには、谷桃子、丹下キヨ子、北原三枝(石原裕次郎夫人)、根岸明美、中田康子など、各方面で活躍した方たちがおりました。
2011.01.13
コメント(10)
-
ユーロの憂鬱 (35)
ユーロの憂鬱 (35)スイスのバーゼルに本拠を置くBIS(国際決済銀行)は、各国の中央銀行の集合体で、グローバル金融に関する規制監督の総元締めです。ですから、BISにとって個別の金融機関に対する自己資本規制の強化、並びにそのための体制整備は、何をおいても譲れない一大関心事なのです。そのBISが、ドバイショックを受けて、2012年からの導入を予定していた、金融機関に対する第3次自己資本規制の実施を、当分の間延期すると発表したのです。例によって日本の新聞は、経済専門紙の日本経済新聞でさえ、曖昧な表現で事実を報じたに留まり、その原因に迫る迫真のレポートは、対に出ませんでした。日経新聞は、12月16日の1面で他社に先駆けて報じたことで、僅かに面目を施したに過ぎませんでした。速報は、それを肉付けする第2弾、第3弾でのより深い分析記事に裏付けられて、初めて輝きを増すものなのですが…その点海外メディアはさすがでした。欧米に限らず、インドやシンガポールの新聞なども、BISによる延期措置が、ドバイ・ワールドに絡んだ決定であることに、当初から踏み込んで報じていました。そこでは、現在の金融危機の状態のなかで、自己資本規制を強化すれば、金融機関の貸し出しが益々萎縮するという理由付けと共に、イギリスの金融機関が、ドバイワールドなどドバイ関連の貸出し債権の不良化で大きく傷つき、規制のクリアが難しくなっていることに、配慮した措置である旨が、きちんと書き込まれていました。BISが、何よりも大切にしている国際金融界の秩序維持、そのために必要な規制の強化という大方針を、一時的にでも見送らざるを得なかったのですから、ことは重大です。ドバイ問題の影響は、これほどに大きかったのです。 続く
2011.01.12
コメント(4)
-
大相撲の実況放送始まる 12日の日記
クロニクル 大相撲の実況放送始まる1928(昭和3)年1月12日83年前のことです。勿論テレビはありませんから、ラジオでの実況放送です。日本ラジオ放送が始まったのは、この3年前の1925(大正14)年の3月22日のことでしたから、およそ3年の経過で、大相撲の実況中継が始まったのですね。前年1927年に、東京と大阪の相撲協会の話し合いがまとまり、両団体がが同時に解散して、単独の大日本相撲協会が発足したことが、実況放送に繋がったようです。場所は、1月と5月に東京両国で、3月と10月は大阪で開かれることになり、83年前の今日が、初場所の初日だったのです。さて、この実況中継の開始に当たって、大相撲史に残る改革が実施されています。それが幕内4分の立会いまでの制限時間です。実はこの規定、この1928年の初場所から導入されたのです。今までは、無制限でした。理由は、実況中継の時間には限りがあり、限りある時間内に横綱の取り組みまで、全てを終らせる必要に迫られたからでした。横綱の取り組みまで、全てを時間内に放送できるなら…というのが、NHKが出した実況放送の条件だったのです。
2011.01.12
コメント(18)
-
ユーロの憂鬱 (34)
ユーロの憂鬱 (34)チェコ中央銀行のハンブル副総裁は、以下のように発言しました。ユーロとEU内途上国の関係に潜む問題点を、とても的確に捉えています。「自国通貨は、金融危機にあたって、一種のエアバックのような働きをしている。ハンガリーやバルト諸国など、中東欧でユーロ寄りの政策をとる国や、ユーロに固定された相場を持つ国、さらにはユーロ建て債務を多く抱える国などで、より深刻な危機に立ち至っていることが、それを証明している。」金融危機勃発後の様々な動きのなかで、北・中・東欧諸国のユーロ熱はや、ユーロへの期待感は、広い範囲で薄らいだことは否定できません。そして、ユーロ圏やEUへの揺さぶりは、ユーロの外からもやってくることにも、警戒が必要です。UAEを構成する6つの首長国のひとつドバイ政府が、注目を集めたのは、2009年の11月末のことでした。ドバイの政府系持ち株会社ドバイ・ワールドが、資金繰りに窮していることが明らかになったのは、2009年の11月末のことでした。11月30日にドバイ・ワールドは、推定590億ドルの債務のうち、傘下の不動産開発会社ナギールなどの保有分、260億ドルについて、、返済を繰り延べる可能性を示唆したのです。アラブ世界のオイルマネーをはじめ、世界各地から資金を集めて、人工島に豪華なリゾートマンションなどを建設する、ドバイ・マジックが喧伝されて間もなくのことでしたから、ドバイショックは、たちどころに世界を駆け巡りました。そんな報道のなかで、注目すべき報道が2つありました。1つはドバイ向け債権の最大の保有者が、イギリスの金融機関だったという事実です。ドバイ政府は、宣言後ほどなくして、RBS,HSBC,ロイズなどを中心とする債権団と協議をはじめ、凹面は隣国であるアブダビ首長国の資金支援によって、最悪の事態に陥ることを回避しつつ今日に来ています。この状態は、問題が解決したことを意味するわけではありません。とりあえず時間稼ぎをしたに過ぎないのです。第2、第3の爆弾が各所に埋め込まれているのです。そしてドバイ情勢をウォッチしていて気付いたもう一つの情報は、2012年導入予定のBIS規制の導入延期が発表されたことです。この問題は、明日記すことにします。 続く
2011.01.11
コメント(8)
-
中国に日本大使館設置 11日の日記
クロニクル 中国に日本大使館設置1973(昭和48)年1月11日38年前になります。前年の1972年に田中角栄首相(当時)と大平正芳外相らが訪中、日中の国交正常化が実現しました。両国で国交正常化に関する協定書を批准し、この日、日本での中国大使館と中国での日本大使館が、同時に設置されました。中国からは陳楚駐日大使が、日本からは小川兵四郎駐中国大使が、初代大使として同時に着任したのは、3月29日でしたから、大使館設置の約2ケ月半後のことでした。なお小川初代中国大使は、後に首相となる宮沢喜一代議士の叔父さんに当たります。
2011.01.11
コメント(8)
-
ユーロの憂鬱 (33)
ユーロの憂鬱 (33)東欧諸国の中で、チェコだけは他国と異なった行動を取りました。チェコも当初はユーロの導入を目指して、ユーロ圏入りを切望していました。当初は、2010年のユーロ圏入りを目指していたのです。ところがリーマンショック後の2008年12月には、、財政赤字を理由に加盟目標時期の延期を発表したのです。その後もチェコ政府と中央銀行は、「ユーロの導入を急がねばならない理由はない。」と主張して、加盟時期の目標設定を見送り続けているのです。特にチェコ中央銀行の総裁は、「現在のチェコ経済の現状からすると、ユーロへの加盟は、チェコ経済にとってマイナスに働く可能性が高い」とまで、述べています。チェコの通貨コルナは、1997年に完全な変動相場制に移行したのですが、リーマンショック後の外資の流出によって、大きく売り込まれてコルナ安となりました。その結果、ユーロにリンクしているがゆえに、自由に自国通貨安にもって行くことが出来ない国々とは違って、輸出主導で経済の回復を図る可能性を、手に入れたのです。チェコの大統領自身も、「ユーロ圏が現在抱えている、成長率の鈍化や生産性の低下といった問題の大半は、ユーロの導入に問題があったのではないか」と、発言しています。これは、欧州統合が、本当の意味で欧州全体のためになっているのかという、根本的な問いかけです。通貨統合が通貨主権の喪失に繋がることを嫌っての、ユーロ導入に反対の国もありました。イギリス、スウェーデン、デンマークなどがは、この立場でした。それに加えて、チェコのように、通貨統合が欧州にとって、本当にプラスなのかと自問する声も出てきているのです。 続く
2011.01.10
コメント(0)
-
徴兵令施行 10日の日記
クロニクル 徴兵令施行1873(明治6)年1月10日138年前のことです。この日明治政府は徴兵令を施行しました。前年12月28日に「徴兵告諭」が出されてから、僅か2週間後のことでした。徴兵令では国民皆兵の原則が貫かれ、旧支配層である士族中心の志願兵制を主張は、避けられました。欧米列強の兵制に倣った軍の整備こそが、列強による日本の植民地化を防ぐ道に繋がると考えられたのです。同時に士族中心の志願兵制の主張者(=保守派)への配慮として、薩摩・長州・土佐の3藩の士族から、天皇の身辺警護にあたる御親兵が選抜されました。徴兵令の結果、数え年20歳の男子は、3年間兵役に着くことが定められたのですが、当初は多くの例外規定が設けられていました。即ち、体格が基準に達しない者、病気の者など、当然と思われる事情から、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「代人料(270円)を支払った者」、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」なども、徴兵を免除されたのです。
2011.01.10
コメント(8)
-
自殺の名所三原山 9日の日記
クロニクル 自殺の名所三原山1933(昭和8)年1月9日78年前になります。この日伊豆大島の三原山の火口から、2名の女学生が友人の立会いを受けて、投身自殺しました。友達の自殺を止めない友人って何なんだと、私などは大いに不満なのですが、この自称友人たちは、友達の自殺の報を、警察のみでなく新聞社などにも語ったのでしょうね。この事件がきっかけで、以後三原山は自殺の名所となってしまい。この年だけでなんと994名もの投身自殺者が出る騒ぎとなりました。大島の人たちからすると、迷惑この上ない話でした。
2011.01.09
コメント(16)
-
ユーロの憂鬱 (32)
ユーロの憂鬱 (32)今世紀に入ってEU入りした東欧諸国は、EUの補助金を得てインフラ整備を進めてきたのですが、さらに1歩進めて、共通通貨ユーロの導入を目指して、次々にユーロ圏への加盟許可を得ようと、努力してきました。現在、加盟が認められた国は、スロバキアとスロベニア、そして今年1月1日に加盟を認められたバルト3国にの1つエストニアの3カ国だけです。ラトビア、リトワニア、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアの7カ国は、まだユーロ圏入りの基準を満たすことが出来ずにいます。現在のユーロ圏入りの基準は、次の5項目です。1、過去1年間の消費者物価上昇率が、同上昇率の最も低いユーロ圏3カ国の平均を、1,5%以 上、上回らないこと2、財政赤字は、対GDP比3%以内であること3、公的債務残高は、GDP比60%以内であること4、金利は、過去1年間の長期金利が、消費者物価上昇率の最も低いユーロ圏3カ国の平均金利 を、2%以上は上回らないこと5、為替は、2年間独自に切り下げを行なっていないこと。並びに欧州通貨制度の為替相場メ カニズム(ERM2のことです)の通常の変動幅(上下に15%以内)を守ること物価、財政赤字、公的債務残高、金利、為替の五つの条件を守ることによって、経済構造を他のユーロ加盟国と並べるところまで、引き上げてもらおうとしたのです。リーマンショックが起きたのは、各国がこうした努力をしているときでした。そこへ発生した金融危機によって、どの金融機関も一斉に手元資金を確保するために、融資の引き上げに動きました。日本で、不動産価格が暴落し、資金手当ての出来なくなった不動産投資ファンドが、次々に倒産したのも、このためでした。当然資金力の弱い、北・東欧の国々からは、外資は真っ先に手を引きました。投資する際は、ドルやユーロを現地通貨に変えて投資しますが、この動きは比較的なだらかに続きます。しかし引き上げる時は、ヨーイドンで横並びに、一斉に引き上げます。当然今度は現地通貨をドルやユーロに転換します。このため、各国の通貨は短期間に強烈に売られます。まさに売りたたきにあったようなものです。通貨価値の大幅な下落は避けられません。さらに、こうした国々は、金利の低いユーロ建てで、融資を受けていました。韓国の個人が金利の低い日本の円建てで住宅ローンを組み、リーマンショックによる円高ウォン安で、支払い不能に陥ったのと、同じ現象が起きたのです。自国通貨安で、こうした国々の債務は、大幅に膨れ上がってしまったのです。 続く
2011.01.08
コメント(4)
-
ベルが鳴るベルが鳴る… 8日の日記
クロニクル ベルが鳴るベルが鳴る…1912(明治45)年1月8日99年前ですから、来年は100周年なんですね。エッ、「何のことか分らん」ですか。ですからベルなんです。列車の出発を告げる、あのベルのことです。流行歌(この言い方も古くなりましたね)に良く出てくる別れの場面の歌詞にありますよね。あの出発を告げるベルの第1号が、99年前のこの日、あの「上野はおいらの心の駅だ…」の上野駅で、日本で始めて鳴り響いたのです。で、発車ベルというと、私にとってはこの曲なんです。春日八郎のデビュー曲「赤いランプの終列車」です。白状しますと「ベルが鳴る ベルが鳴る」は、ここから盗りました。 > 白い夜霧の 灯りに濡れて 別れせつない プラットホーム ベルが鳴る ベルが鳴る さらばと告げて 手を振る君は 赤いランプの終列車 <
2011.01.08
コメント(12)
-
ユーロの憂鬱 (31)
ユーロの憂鬱 (31)財政統合の問題に戻ります。この問題を突き詰めていくと、結局は1つの政府の問題に行き当たります。EUが1つの政府を持つことになれば、ギリシアやアイルランドの問題もEU政府の責任になりますから、夫々の財政赤字問題は、EUの統一財政上の赤字に転嫁されますから、ギリシア政府やアイルランド政府の悩みは、解消されることになります。しかしながら、ここにはいくつもの問題があります。、まず財政上の火消しが必要な国は、ギリシアとアイルランドに留まらず、スペインやポルトガル、さらにはイタリアが控えていますし、バルト3国や東欧の国々も大きな火種を抱えています。これだけ大きな火消しをするだけの財政資金は、EUにはありません。つまり共倒れが必至なのです。こうした現実を脇に置いたとしても、自国の税金からの持ち出しになるドイツやフランス、オランダらの国民は、自分の支払った税金が、他国のために使われることを受け入れるでしょうか。そんなことは御免だと大騒ぎになることは必定です。選挙の怖い政治家が、こうした国民の強い反発を無視して、政治統合や財政統合を推進することは考え難いですね。そして最後に、財政負担から解放される国々はどうでしょうか。財政負担から解放される代償に、自国の財政自主権を放棄しなければならないとすると、唯々諾々としてこの契約に応じるでしょうか。それではあまりに犠牲が大きすぎると、あの手この手で抵抗することは、間違いないでしょう。そうまでするくらいなら、EUやユーロという巨大ロボットのバーツであることをやめ、勝手気ままに振舞う道を選ぶ可能性の方が高そうです。永久に財政自主権を失うよりも、一時は辛くても、思い切ってデフォルトする道を選び、自国通貨を大幅に切り下げて、輸出主導で再建を図る。南米や98年のアジア通貨危機に際してのアジア諸国の取った道です。こうしたせめぎあいが今も続いています。なぜなら、EU政府の統合財政が誕生したとしても、その体制下で、本当に財政困難国の(例えばギリシアの)悩みは解決するのでしょうか。ギリシア国民の納めた税金以上の額が、当初はギリシアに投入されるでしょうが、将来はどうなるか分らないのです。自分たちの納めた税金が、自分たちが納得のいくように使われているかどうか分らないのに、馴染みの薄いEU政府に税金を納める気になるでしょうか。こうした抵抗感は、どの国でも強いように思われます。 続く
2011.01.07
コメント(8)
-
「もしもし、こちらニューヨーク」 7日の日記
クロニクル 「もしもし、こちらニューヨーク」1927(昭和2)年1月7日84年前の出来事です。「もしもし、こちらニューヨーク」と妙なタイトルをつけましたが、実は84年前の今日、ニューヨークからロンドンへ、史上初めて、太西洋を越える国際通話がかけられたのでした。これが、国際電話の事始でした。それにしても、「もしもし、こちらニューヨーク」といきなり呼びかけられたロンドンの方は、さぞ驚いたことしょう。
2011.01.07
コメント(4)
-
ユーロの憂鬱 (30)
ユーロの憂鬱 (30)ですから、ユーロ圏諸国やイギリスなどは、ECBやEUによる支援の前提として、ギリシアに大幅かつ大胆な財政赤字削減策の導入を要求しました。当然増税や年金支給年齢の引き上げ、公務員給与のカットに人員の削減なども含まれますから、ギリシア国民は強く反発します。それが分る故に、ギリシア政府もあの手この手で抵抗したのですが、EU諸国の支援なしには、デフォルトが確実なのですから、最終的には従わざるを得なかったのです。しかし、これで問題が解決するわけではありません。ギリシアに半年遅れて、昨年11月~12月にかけて再び問題になったアイルランドのケースが、良い見本なのです。既に指摘したことを繰り返すと、アイルランドはギリシアに先駆けてIMFやEUに支援を求め、要求された緊縮政策を忠実に守っていたのです。求められた処方箋の通りに経済を運営した結果、支援の成果が上がらずに、再び危機を迎えた姿がそこにあったのです。即ち、経済が大きなダメージを受けているときに、財政赤字の削減を優先して増税や緊縮財政を実行すれば、当然国民は生活防衛のために、節約志向を強めて消費を縮小します。雇用と所得の落ち込みという二重の危機が、そこにはあるのです。企業もまた過剰生産を恐れて、設備投資を控えると同時に、過剰設備の廃棄を進めます。この結果、増税にも関わらず、税収の落ち込みが大きいために、増税の効果は期待したほどには伸びないのです。日本の諺にある「虻蜂取らず」状態です。その上ギリシア政府は、受けた融資に対する利払いの義務を負います。その利子は市場金利を参考に決められますから。かなり高い利子を払わなければならないのです。デフォルトの可能性を市場に指摘された国の国債は、信用を失いますから、相当高い金利を提供しないと、誰もリスクをとってくれません。さすがにIMFやECBもむき出しの高利を要求するのは気がひけたのか、市場金利よりは2ポイントほど下げたのですが、それでも5ポイント台です。ギリシアは、EUの支援で借換えは出来ましたが、以前よりも高い金利の支払いに悩まされることになったのです。支援で現時点での破綻は免れました。しかし、ギリシア経済の将来が、保障されたわけではないことに、注意が必要なのです。菅首相、ユーロ圏の状況を、何処まで学んでいるのでしょうね。まるで財政破綻だけが見えて、増税や緊縮財政の弊害は見えない、特殊なメガネをかけているかのような発言をしていますね。これじゃぁ、支持率はまた下がるでしょう。 続く
2011.01.06
コメント(6)
全62件 (62件中 1-50件目)