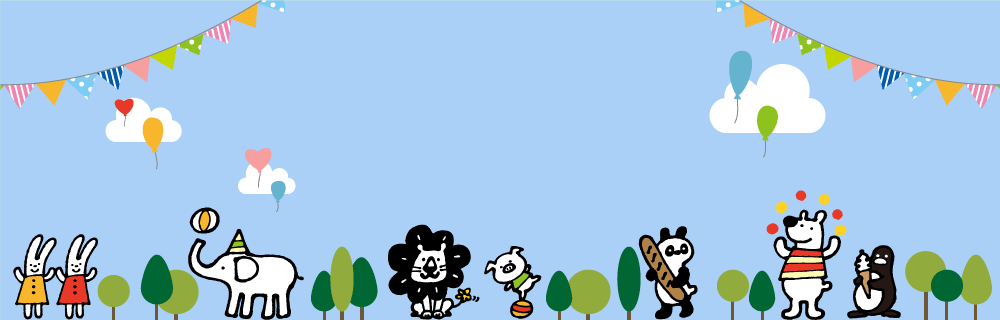2011年07月の記事
全83件 (83件中 1-50件目)
-
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (4)
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (4)1871(明治4)年、明治政府は廃藩置県を断行しました。版籍奉還後、新政府は次なる方針が固まるまで、旧藩主を知藩事に任命して、奉還された「所領」の管理を一任していました。そのため「廃藩置県」までは、実質的には何も変っていなかったのです。そんな中で、中央集権体制の確立という大義名分のために、「廃藩置県」を断行したのです。最初はともかく実施をということで、北海道を除く、沖縄までの諸藩を、全て県に置き換え、(そのため、1871年の施行当初は、3府302県もありました。3府は東京、大阪、京都です)そこに中央政府が任命した県令(現在の県知事です)を派遣したのです。当然旧藩主の知藩事は失職、当然藩士たちも失業です。これは大騒ぎでした。新政府は、中央政府の方針を全国に行き渡らせることが目的ですから、県令には、少数の例外を除いて、旧藩とは関係のない人物を派遣しました。ですから、藩が県に変っただけに見えても、内部は大変革だったのです。県の数も、次々に整理され、同年晩秋にかけて72県に整理され、その後も漸次統合されて、1876(明治9)年には35県にまで減少しました。これでは、県の範囲が広すぎると、今度はいくつか分県され、1889(明治22)年には、3府43県とほぼ現在並となったのです。しかし、現在の地方自治を見ても、県令(県知事)だけ抑えても、それで中央の命令が地方の隅々までに届くわけではありません。広い圏域をいくつかに分け、さらに末端の村々にまで、中央政府の意向を染み渡らせるためには、さらにいくつかの工夫が必要でした。少し遅れますが、こうして整備されたのが、187(明治11)年の郡区町村編成法と、区の多くを市に改めた1888(明治21)年の市町村制の導入でした。この制度の巧妙なところは、県令と郡長は中央政府から派遣されるのですが、市町村長については、地元の推薦に基づき地方の信望厚き名望家を、任命していることです。即ち名望家たちに、新政府に不満を持つ地元住民たちの説得を押し付けているわけです。地元住民は、日頃世話になっている地元名士の言うこととなると、耳を傾けないわけには、行かないのです。こうして明治政府は、「廃藩置県」の実行をもって、封建体制からはっきりと縁を切ったのです。そのことのよりはっきりした決着は、1873(明治6)年の地租改正によって果たされるのですが、その前に、もう少し触れたいことがあります。 続く
2011.07.31
コメント(2)
-
公務員のスト権、団体交渉権を禁止 31日の日記
クロニクル 公務員のスト権、団体交渉権を禁止1948(昭和23)年7月31日この日、政府は政令第201号を公布、直ちに施行し、国家公務員及び地方公務員の争議権、団体交渉権を禁止しました。この月23日に、マッカーサーは芦田均首相に書簡を送り届け、(1)公務員の団体交渉権・争議権の否認 (2)逓信関係官庁の郵政と電信電話への分割 (3)鉄道及び専売公社の公共企業体化 (4)国家公務員法の全面的な改正 などを求めました。政府がこのマッカーサー書簡に対応して、実施したのが政令第201号でした。それは、この時期、日毎に勢いを増しつつあった、労働運動を抑え込むことを狙ってのことでした。
2011.07.31
コメント(6)
-
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (3)
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (3)版籍奉還とは、「版図」(土地を指します)と「戸籍」(土地に暮らす人々、人民を指します)を返還することです。封建制度の下では、国王はその配下に対して、その功績に応じて「所領」を分配したり、配下になった武将が元々保持していた「所領」の継続支配を認めたり(これを「安堵」と言います)します。配下は、その見返りに国王に対する忠誠を誓います。この「所領」とは、単なる土地を指すのでなく、その土地で働き、生活している人民を含んだ言葉(専門用語で概念と言います)です。この関係は洋の東西を問いません。例外は、封建社会を経験しなかった米国だけと言って良いでしょう。ルイ14世時代のフランスも、エリザベス1世時代のイギリスも、康熙帝時代の中国も、そして徳川幕府体制の日本も同じです。徳川将軍が国王にあたり、大名や旗本が領主に当たります。そして大名もまた、上位の家臣に「所領」を与えます。家老や奉行等、石高表示の禄を受けている家臣は、「所領」を拝領して生活し、家の子・郎党を養います。何俵何人扶持という禄を受ける家臣は、「所領」は拝領できずに禄米の支給を受けました。さて、明治維新の結果として、新政府が成立したのですから、新政府の長となった明治天皇は、薩長連合やその支持グループに担がれた結果であったとしても、新生日本の支配者となったのですから、旧来の方式としては、日本全国の「土地」と「人民」の支配者となったのです。実は徳川幕府から権力を奪取した後に、どのような支配体制を構築するかは何も決まっていなかったのです。 それでも、ともかく旧来の幕藩体制とは違った支配をするぞという姿勢は、示す必要があります。 こうして実行されたのが、版籍奉還でした。土佐、薩摩、長州など、新政府の樹立に功績のあった諸藩を先頭に、諸大名が明治天皇に「土地と人民」をお返し申し上げたのです。これを受けて、明治天皇と天皇の政府が、返還された全国の所領を、功臣たちに気前良く分配したとしたら、日本はなお封建体制を続けることになったのです。しかし、それはありえませんでした。幕藩体制と同じようなシステムを続けたのでは、日本の植民地化を防ぐための諸施策を実現するための前提、即ち中央集権体制を実現することが出来ません。 ですから、新政府は返還された「所領」をそのまま預かり、功臣たちに一切「所領」を分配することをせずに、2年後の明治4(1871)年に廃藩置県を断行したのです。この間、旧武士の士族たちには、過去の所領や家禄に応じて、秩禄と呼ばれる現在で言う年金のようなものが支給されたのです。 財政厳しき中、大変な負担でしたが、士族の叛乱を防ぐためには、必要止むを得ない措置でした。 続く
2011.07.30
コメント(4)
-
自衛隊機と全日空機衝突 30日の日記
クロニクル 自衛隊機と全日空機衝突1971(昭和46)年7月30日あれから40年ですか。そんなに経っているのですね。この日、午後2時3分頃、岩手県の雫石町上空で、千歳発羽田行きの全日空機に、航空自衛隊松島派遣隊所属のF86Fジェット戦闘機が衝突、全日空機は空中分解して乗員・乗客162名が全員死亡する事故が起こりました。全日空機は指定された高度と空路を守っており、自衛隊機が民間機の使用空路に紛れ込んだために生じた100%航空自衛隊に責任のある事故でしたが、原因を作った自衛隊機の2人の乗員はパラシュートを使って脱出、命を取りとめただけに、遺族や世論の怒りは、凄まじいものがありました。当然のことながら、自衛隊の軍事優先、安全軽視の体質が問題視され、自衛隊への批判が集中、責任をとって防衛庁長官以下、統合参謀本部議長ら自衛隊幹部が辞任することとなり、航空管制法も抜本的に改正される騒ぎになりました。
2011.07.30
コメント(20)
-
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (2)
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (2)日本資本主義の特徴を綴ることは、後半の課題とさせて戴き、先ずは明治政府の諸政策を見てゆきましょう。前作、黒船来航に記したように、幕末・維新期の日本政府は、西欧列強による植民地化をいかに防ぐかという大きな課題を負っていました。そして、幸運にもそのための時間がある程度与えられたことも記しました。明治政府は、この与えられた時間を上手に生かし、見事に植民地化の危機を切り抜け、日本を近代資本主義国家にのし上げることに成功しました。明治政府がそのために唱えたスローガンが、富国強兵と殖産興業の2つのスローガンでした。そしてこの2つのスローガンを、見事実現することに成功しました。その辺のいきさつを見て行きたいと思います。列強という日本の植民地化を狙う敵から、自国を守るためには強力な軍隊を持つことが必要です。そして強力な軍隊を持つためには、敵と同等の近代的兵器で武装する必要があります。この敵の中には、死の商人と呼ばれる武器商人がいて、武器を売ってくれます。長崎の観光名所グラバー邸の持ち主だったグラバーは、まさにその代表的人物でした。しかし、彼ら死の商人が所有する武器は、本国では二番煎じの武器なのです。軍事大国が売却する武器は、決して自国の軍隊を困らせるような最新鋭の武器ではありません。自国の軍隊が安心して優位にたてる、本国ではスクラップ化される運命にある武器を、高額で売りつけるのです。それを見抜いた明治政府の俊英たちは、自前の軍需工場を建設することの重要性に気付き、そのために国を豊かにしなければならないことを承知していたのです。では、どのように国を豊かにするのか。それには、産業を盛んにすること、即ち殖産興業しかないこと、資本主義社的生産システムを発達させるしかないことを、見抜いたのです。そして、そのための手を着実に打っていきました。しかし、こうした政策を実現するためには、まずそのための前提条件の整備が必要です。それは、中央政府の命令が地方の隅々にまで達する中央集権体制確立の問題です。徳川幕府の下で、長く続けられてきた幕藩体制のままでは、中央の命令は地方に届きません。そうした二重三重の権力構造を温存したままでは、敵の思う壺に嵌まるだけです。中国政府の実行した、洋務運動や変法自強運動が成功しなかったのは、その前提となる中央集権体制が確立できなかったからでした。明治政府はその轍を踏まず、先ずは中央集権体制の確立を優先したのです。それが、1868(明治2)年の版籍奉還と1871(明治4)年の廃藩置県でした。 続く
2011.07.29
コメント(6)
-
沖縄の米軍機、南ヴェトナムを爆撃 29日の日記
クロニクル 沖縄の米軍機、南ヴェトナムを爆撃1965(昭和40)年7月29日この日、沖縄の嘉手納米軍基地を飛び立ったB52爆撃機30機が、南ヴェトナムを爆撃しました。このB52爆撃機の根拠地は、米国のグァム基地でしたが、同地がハリケーンに襲われたため、前日に沖縄に避難していたものでした。ハリケーンを避けて飛来していたとはいえ、沖縄からヴェトナム戦争の前線に、直接出撃したのは、始めてのことでした。未明に発信したB52は、お昼過ぎには嘉手納基地に再び姿を現しましたが、沖縄米軍は行き先を公表しませんでした。日本国民が事実を知ったのは、サイゴン(現ホーチミン市)からの外電によってでした。国務省は、「沖縄基地の米軍機のこのような使用は、日本政府との事前協議の対象にならない」との談話を発表しました。日本政府も翌日、「日米安全保障条約上は問題がない」との談話を発表しますが、一方で「しかし日本国民の感情を無視したものだ」と不快感を表明、米側に善処を要望しました。当時沖縄は米国の占領下にありましたから、沖縄の米軍機が直接南ヴェトナムでの戦闘に加わったということは、沖縄が報復攻撃を受けることもありうるということに繋がります。このため、野党は一斉に抗議の声をあげ、琉球立法院もまた超党派で抗議の決議を行いました。ヴェトナム反戦運動と、沖縄返還運動が多いに盛り上がるきっかけとなった出来事でした。当時は現在に比べると、平和主義と反戦運動が広く国民の共感を集めていた時代でした。
2011.07.29
コメント(4)
-
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (1)
明治政府の功績と日本資本主義の特徴 (1)黒船来航のシリーズを終えたところで、明治政府の功績にも言及しておきたくなりました。それは、日本資本主義の発達並びに特徴の問題と、密接に関わりがあります。そこで、戦前の、とりわけ明治期の日本資本主義いついても、記させて戴きます。最初に断ってきますが、明治維新は日本型のブルジョワ革命(市民革命)だと、私は考えています。それは、フランス革命が代表する革命とは、かなり様相が違います。しかし、これは、19世紀後半という時代の様相によることろが大きいのです。何よりも版籍奉還と廃藩置県の実行によって、封建領主による土地専有の体制をぶち壊し、地租改正によって、個々人の土地所有を認めた政治権力が、封建的な政治権力であるはずはないのです。明治維新は日本型の近代革命でした。革命によって、旧支配体制はひっくり返されました。だからこそ、家柄や血筋に囚われない、門閥が意味を持たない、新しい政治的、社会的、経済的に全く新しいシステムが構築されたのです。だからこそ、明治政府の中枢部には、家柄、血筋に関係なく、維新の功臣がキラ星のごとく立ち並び、互いに切磋琢磨しながら、列強による植民地化の危機に立ち向かったのです。明治期には、キラ星のごとく、多くの人材が登場します。「革命の10年は、平時の100年では及ばないほどの仕事が行なわれ、人材が登場する」と言われます。それは明治維新においても同じなのです。そして、維新の功臣たちは、出自や門閥が意味を成さない、実力のみで人を評価することの重要性を、肌で感じて承知していました。ですから、明治の功臣の2世、3世で、親の仕事を世襲で引き継いだ人物は、見当たらないのです。このことは、このブログでも何度か触れてきましたが、大久保、木戸、伊藤、山縣らの子孫は、誰一人後継者になっていないのです。実力さえあれば、国家の将来に貢献する仕事が出来る。こう信じられることは、若い人材にとっては、この上なく幸せなことです。だからこそ、彼らは頑張った。そして、こうした体制を築くことが出来たのは、明治維新が革命だったからこそ、遠慮会釈なく、旧体制を破壊することが出来からなのです。 ザビ明らかに現在との大きな違いが、そこにありますね。
2011.07.28
コメント(6)
-
続・米国原爆実験に成功 (12)
続・米国原爆実験に成功 (12) 戦後の国際政治と言えば、すぐに冷戦の語が浮かんできます。しかし、冷戦が本格化するのは、中国の社会主義化がほぼ確実視されるようになった1949年からです。米国が日本の再軍備を求めるようになった時期と、ほぼ同時です。ですから、1945年の時点で、米国が日本を社会主義封じ込めの最前線にしようと、意識していたという事実はありません。それでは、何故日本を占領したかったのか。それは、日本の地理的位置にあります。日本は、日本海を挟んで、中国とソ連に国境を接しています。それだけに、自国の安全を考えると、ソ連としても手に入るものなら、手に入れたい島国です。逆に米国にとってはどうか。当時米国は、中国の内戦は、蒋介石の国民党が勝利するものと、何の疑いもなく信じ込んでいました。それゆえ、社会主義封じ込めの最前線は、国民党の中国が務める。これが米国の考えでした。当時の米国は、日本が再度軍事大国にならない様に、徹底的に日本の民主化を進めることしか、念頭になかったのです。ただし、べ国にとって1つだけ譲れない線がありました。それは、日本がソ連の占領下に入ることでした。そうなったらどうなるか。日本は米国を睨むソ連の最前線の基地になります。ハワイをはさんで米本土まで一直線です。そうなると、真珠湾攻撃の悪夢が再現されるかもしれません。それはなんとしても避けたい。日本に、ソ連の基地を作らせるわけに行かないという米国の思惑が、ソ連の参戦を挟む時期を選んでの、ヒロシマとナガサキへの原爆投下に繋がりました。いわば、ヒロシマとナガサキは、政治ゲームの生贄とされたのですね。 完
2011.07.28
コメント(6)
-
第一次世界大戦始まる 28日の日記
クロニクル 第一次世界大戦始まる1914(大正3)年7月28日97年前ですか。間もなく100年経つのですね。この日、オーストリアはセルビアに宣戦布告し、対セルビア戦争に踏み切りました。丁度1ヶ月前、ボスニアの首都サライェヴォで、皇位継承者夫妻がセルビア人の民族主義者の手で暗殺されたオーストリアは、開戦の10日前から突然強硬路線に舵を切り、7月24日には、最後通牒を突き付けておりました。しかも回答期限は2日後の26日という途方もない要求でした。セルビア側は何とか期限までに回答をまとめたのですが。オーストリアは直ちに回答を拒否、駐セルビア大使にベオグラードからの退去を命じ、国交を断絶、この日の宣戦布告と開戦となったのでした。セルビアを後見するロシアは、直ちに軍に総動員令を発し、独・墺国境に兵を集め始めます。これを受けてドイツは8月1日にロシアに宣戦を布告、独・露も交戦状態に入りました。ドイツは翌2日には、フランスに侵入、独・仏間にも戦端が開かれました。これを受けてイギリスも直ちに対独開戦を決定、28日の開戦から僅か1周間で、戦争は列強の参加する国際戦争に発展しました。このため、オーストリアがセルビアに宣戦を布告したこの日をもって、第一次世界大戦が始まったと説明されます。
2011.07.28
コメント(7)
-
続・米国原爆実験に成功 (11)
続・米国原爆実験に成功 (11) 米国の思惑は、見事に当たりました。ポツダム宣言の受諾を渋っていた日本が、8月9日以降、手のひらを返すようにポツダム宣言の受諾に傾いたのは、実際にはソ連参戦の衝撃によるものでした。この点は、昨日紹介した『木戸幸一日記』に明らかです。しかし、ソ連参戦の前後に米国が投下した2発の原爆の衝撃は、決定的でした。その結果、そソ連を含む連合国は、連合国による対日占領について、米国主導の占領とすることに、一言も異議を挟まず、まるで既成事実であるかのように承認したんです。こうして、米国による対日占領が開始されたのです。アメリカは何故日本を占領したかったのか。最後にこの点を記します。実は日本の植民地であった朝鮮半島には、米国は何の関心も示しておりません。日本のポツダム宣言の受諾表明を受け、米国は朝鮮半島の占領行政をソ連と分担する検討に入るのですが、対日方面軍司令部も、国務省のアジア部局も、積極的に関わろうとはしなかったのです。こうして、朝鮮半島問題は、後にケネディ・ジョンソン政権の国務長官を務めたラスク大佐に丸投げされたのです。ラスクは、半島中央部までをソ連軍の管轄地とすることで、早期合意を目指し、適当な山脈や河川が見当たらないことから、北緯38度線を境界とする案に、思い至ったと、後に回想しています。それほど、朝鮮半島に関心を示さなかった米国が、原爆を投じてまで、日本の占領に拘ったのです。そこには、どんな理由が隠されていたのでしょうか。 続く
2011.07.27
コメント(6)
-
田中角栄前首相逮捕 27日の日記
クロニクル 田中角栄前首相逮捕1976(昭和51)年7月27日35年前のことです。この日、東京地検は、ロッキード事件に絡んで田中角栄前首相を逮捕しました。取調べの結果、8月16日に受託収賄罪と外為法違反の2つの容疑が固まったとして、起訴しました。この事件は、2月に米国でロッキード社の幹部、コーチャン副首相の証言によって、問題が暴露され、米国発で日本のマスコミの注目を浴び、それから検察が動くという、珍しい手順で暴かれた事件でした。事件の特異性から、対中関係の改善を米国の意向を無視して積極的かつ素早く進めるなど、戦後米国の意向を無視した初めての首相の登場に危機感を持った米国が、今後の首相となる人達への警告の意味も込めて、積極的に暴露したのではないかという、うがった見方をする人達もかなりの数に上りました。
2011.07.27
コメント(14)
-
黒船来航(41)
黒船来航(41)最後に残ったのが、西欧最大の植民地大国イギリスと、ナンバー2のフランスです。英仏両国は、インド並びに北米大陸で、植民地獲得競争を繰り広げ、やがて1900年前後には、アフリカ大陸の植民地化でも激しく争うことになる、まさに犬猿の仲の両雄でした。そんな関係ですから、日本との関係においても、互いに先を越されてはならじと、激しいつばぜり合いを点火したのです。古い時代の日本史の教科書には、当時のフランス皇帝ナポレオン3世(1852年~70年のフランスは、第二帝政の時代でした)から贈られた乗馬服をまとって、これまた贈られた脚の長いアラブ産駒に跨った徳川幕府最後の将軍慶喜の、にこやかな写真が良く載っていました。御記憶のおありの方も多いと思います。そうなんです。フランス公使ロッシュは、江戸の幕府と京都の朝廷を担ぐ薩長連合を天秤にかけ、幕府の勝利を予測して、幕府との関係強化を本国に具申していたのです。ナポレオン3世から慶喜への贈り物は、ロッシュの示唆によるものでした。ロッシュは幕末の動乱は、幕府が勝利すると身ていたのです。これに対してイギリス公使パークスは、京都の朝廷と連携する薩長連合の勝利を予測し、薩長連合との関係の強化にかけていたのです。結果は薩長連合の勝利による、明治新政府の登場に繋がったのですから、パークスの読みの方が当たっていたことになります。ところで、幕末維新期のイギリスは、なお中国での利権の拡大に目を奪われており、日本への関心は、相対的に低かったのです。1850年代から60年代のはじめにかけて、中国各地は、太平天国の叛乱に悩まされていました。西欧列強は当初是々非々の態度を貫いていたのですが、アロー戦争の勝利によって、慎重から大幅な譲歩を取り付けると、態度を変えて清朝擁護に舵を切ったのです。その先端にいたイギリスは、しばらくは中国での利権の拡大に釘付けにされ、日本への進出はしばらく後回しとなったのです。イギリスからも、時間が確保できたのです。フランスはどうでしょう。肩入れした徳川幕府は消滅しました。ロッシュは函館戦争に協力すべきと解きましたが、それは途中で頓挫しました。そして1870年、あの普仏戦争となったのです。ナポレオン3世のフランスは、ビスマルクの下で周到に対仏戦の準備を整えたプロイセンに完敗したのです。その結果、1871年1月プロイセン中心のドイツ帝国が成立しました。そしてフランスは、祖の語しばらくは、敗戦の痛手を癒し、対独復讐の炎を燃やして、対外侵出よりも、強大化した隣国への対応に忙殺されることになったのです。明治新政府が誕生し、古くからのしがらみを断ち切った新生日本は、しばらくの間虎視眈々と日本の植民地化を狙う大国が、1つとして存在しないという、まさにたぐい稀なる幸運に恵まれたのです。明治政府は、こうして与えられた時間を上手に生かし、短期間に日本の国力を充実させ、資本主義化を推進して、植民地化を防ぐことに成功した。こういうことになりましょうか。 完
2011.07.26
コメント(6)
-
続・米国原爆実験に成功 (10)
続・米国原爆実験に成功 (10) スチムソンやトルーマンらの主張が、実は意図的に触れられていないこと。それが、8月8日から9日にかけてとされていたソ連参戦です。ソ連軍の満州侵入によって、日本軍は北方から大きな打撃を受けます。そして、南カラフトを席捲しての北海道上陸や、ウラジオストーク港を利用して、越後から北陸にかけての大軍の上陸となれば、日本軍がなお持ちこたえるのが難しいことは、容易に推測できることです。事実、天皇側近の内大臣木戸幸一の日記に寄れば、ソ連参戦が明らかになった8月9日朝、天皇に呼ばれた木戸は、「ソ連が参戦したとなれば、戦いの終息を急ぐ必要があると思う。この点鈴木首相と十分話しあってほしい」と、指示されたというのです。天皇は、日本がソ連に占領されれば、天皇制は否定され、日本の天皇制が滅びる危険を察知して、講和を急ぐ意向を示されたのです。広島への原爆投下については、何も話さなかった天皇が、ソ連参戦時には短時間で自分の意志を表明したのです。当時アメリカは、日本の国内事情を丁寧に分折していました。そこから、「原爆投下やソ連の参戦がなくても、通常の空爆を強化するだけでも、日本は確実に年内中に降伏するだろう」とい主張する人たちもいたのです。アメリカ戦略爆撃調査団報告」はその1つです。それでも原爆は8月の6日と9日に投下されました。それは明らかに、「ソ連の参戦以前に日本に決定的ダメージを与えること」であり、あるいは「国際世界におけるソ連参戦の印象を薄め、日本の降伏は原爆投下によると、世界に信じさせること」にあったのです。アメリカ政府は、ソ連の参戦に日本の指導層が大打撃を受けるであろう事を知っていました。だからこそ、参戦前に日本に決定的なダメージを与え、日本を降伏させたのはアメリカであるという印象を、世界に広めておくことが必要であると判断していたのです。原爆投下は、まさに日本に対する占領権の確保を目的に、実施されました。私はこのように考えています。
2011.07.26
コメント(10)
-
ポツダム宣言発表 26日の日記
クロニクル ポツダム宣言発表 1945(昭和20)年7月26日ベルリン郊外のポツダムで、この月17日から会談中だった米・英・ソ3国のうち、米・英2国は、中国の蒋介石には電信で知らせて了解を採り、なお交戦中の日本に対する降伏勧告と、降伏条件を米・英・中3国の名で発表しました。一緒に会談中のソ連の名がないのは、日ソ間には交戦状態がなかったからでした。中国の蒋介石は、会談の席に中国代表を招かず、電信での通告で同意を求める米・英のやり方に不快感を表明しましたが、宣言の内容そのものには同意を表明したのです。さて、このポツダム宣言の内容ですが、前文で日本の軍国主義者のこれ以上の抗戦の無益を説き、日本は破滅か理性的な降伏で国土の全面的な焦土化を防ぐかの二者択一に迫られていることを指摘し、以下の条件を提示しています。(1)日本の軍国主義の除去、(2)平和で安全な新秩序が構築されるまで、連合軍による占領を受け入れること、(3)カイロ宣言による領土制限の受諾(明治以降の戦争で獲得した領土のうち、交戦状態にないソ連(旧ロシア)から獲得した南部樺太を除く全領土の返還と朝鮮の独立承認を求めた宣言)、(4)日本軍の武装解除と兵士の復員、(5)戦争犯罪人の処罰、(6)民主化の徹底と基本的人権の確立、(7)再軍備の禁止そして、占領中も占領軍に依る直接統治を行なわず、日本人に依る政府を認める間接統治方式をとることも匂わせていました。日本固有の領土の割譲が要求されていないこと、賠償請求のないことなど、降伏条件としては、当時の戦況からして極めて緩やかな内容であることが、良く伝わってきます。これは、2月のヤルタ会談における、ドイツ降伏後3ヶ月以内に日ソ中立条約を破棄して参戦するという、米ソの密約の期限が迫り、ソ連の参戦が目前に迫っているという状況を踏まえ、米国が戦後の対ソ関係を考慮して、日本を自陣営に留めることを目指していたからです。しかし、戦局の不振にいらだち追い詰められていた当時の軍首脳部は、ポツダム宣言に込められていた米国のサインを冷静に受けとめる能力がありませんでした。軍部は、戦犯の処罰という項目に拘り、この戦犯に天皇が含まれるのか否かという点に拘り、天皇の処罰なしの確約が得られない限り、ポツダム宣言を受諾出来ないとする姿勢を貫き、国民に対しては、宣言の内容を発表すると共に、「政府はこれを黙殺する」との談話を発表しました。連合国はこれを拒否と受けとめ、対日攻撃を続けました。ソ連参戦を出来れば避けたかった米国も、日本の頑なな態度から、日本降伏の決定打がソ連の参戦であったという印象が広まるのを怖れ、完成したばかりの原子爆弾の投下を決定しました。そしてソ連も参戦し、長崎に2発目の原爆が投下されました。ソ連軍は怒涛の勢いで満州に展開した関東軍を蹴散らし、朝鮮半島の北部にまで達します。日本がようやくポツダム宣言を受諾して降伏したのは、こうした事態が進んだ後でした。軍首脳の自己保身と、冷静に彼我の力関係を分析する能力の欠如(つまり無能!)、そして天皇に近い政治家の軍部と対決しても事態を打開しようという強い政治的意志と責任感の欠如が、ポツダム宣言発表後の事態の推移の中に見てとれます。こうした無能な軍人や政治家の誤った判断の結果、日本は原爆の被害とソ連に抑留された人々の苦難を産み、そして朝鮮半島の人々は今日なお南北分断の悲劇の中に置かれ、そして子どもを拉致されて苦悩する親たちもいる状況が残っているのです。私は、大都会を中心とする米軍の空襲や原爆の投下に対し、今でも強い憤りを覚えますし、米国政府に対し、例え対米関係を一時的にこじらせたとしても、こうした住民虐殺に対し強く抗議し、日本国民に対する謝罪を要求すべきだと考えます。そして同時に、当時の軍人や政治家の戦争責任をしっかり追究して、彼らの自己正当化発言発言を許すべきではないと、考えています。
2011.07.26
コメント(8)
-
黒船来航(40)
黒船来航(40)日本にとっての第2の幸運は、当時の世界情勢にありました。今まで記してきたように、日本は米国を選んで、粘り強い交渉の末に、1854年に日米和親条約を、4年後の1858年に日米修好通商条約を結びました。そして、最恵国待遇を主張して、米国と同等の条約締結を要求してきた、イギリス、フランス、ロシア、オランダとも、付き合いの長いオランダのアドヴァイスを下に、同様の条約を締結しました。1870年代に端緒を持ち、1900年前後の時期に頂点に達する帝国主義の時代には、やや早いのですが、1850年代と共に、西欧列強が植民地獲得競争の時代に入っていたことは、間違いのないところです。そうした状況のなかで、日本はこの危機を堂々と切り抜けました。アジアで植民地化を経験しなかったのは、日本とタイだけでした。このうち日本の場合、江戸時代の経済発展が重要な意味を持ち、そこに資本主義発展の萌芽があったからこそ、明治政府の殖産興業政策がうまく機能したことは、大いに強調すべきと事柄です。そこに、世界情勢が日本に時間的余裕を提供してくれたのです。 まず、日本と開国条約を結んだアメリカです。御存知のアメリカ社会を2分した大規模な内戦、南北戦争は1861年に始まり、4年の長きに渡って続けられました。この間は勿論、その後1880年頃まで続いた再建の時代を含めて、米国の外への膨張には、ブレーキがかけられていたのです。次にロシアです。ロシアも米国と並んで、日本との開国条約の締結に熱心でした。そのロシアですが、日米和親条約の締結を挟む時期に、黒海から地中海への進出を目指して、オスマン帝国領への侵出を目指し、英仏両国とクリミア戦争(1853年~56年)を戦い、惨敗したのです。その結果近代化の遅れに気付いたロシアは、1861年に開始する農奴解放をはじめ、大改革と呼ばれた改革の時代に入ったのです。こうして、ロシアの体外発展にも、大きなブレーキがかかっていたのです。オランダは元々、日本の植民地化という野心を持ちませんでしたから、残るはイギリスとフランスです。 続く
2011.07.25
コメント(4)
-
続・米国原爆実験に成功 (9)
続・米国原爆実験に成功 (9) 米国の主張を、もう少しみてみましょう。原爆投下時の陸軍長官スチムソンは、1947年2月に、対日戦争を回想して、次のように記しました。「1945年の7月前半、日本を撃ち破るための米軍の戦略は、まだ原子爆弾の使用を含んでいなかった。当時はまだ、原爆実験が行なわれていなかったからである。」「だから我々の計画は、夏から秋にかけて、海上と空中の封鎖を強化しつつ、さらに猛烈な空襲を行なった後に、11月1日に九州南端に上陸する予定であった。これに続いて1946年春に、九十九里あたりへ上陸する手はずを整えていた。」「この作戦計画を最後までやり遂げることになったとすると、大掛かりな戦闘が、1946年後半まで続くと、我々は予想していた。」「このような作戦では、米軍だけでも100万人を超える戦死者、戦傷者を出すだろうという報告を、私は受けていた。」以上がスチムソンの回想です。6月に決着した、僅か3ヶ月弱の沖縄での地上戦で、どれほどの死者が出たかを知る者にとっては、この説明はそれなりに説得力を持っているように、思えるところがあります。しかし、この回想にも、おかしなところが2つあります。何よりも、何故原爆投下が8月の早い段階だったのか。この文章は何も説明していません。九州への上陸予定は11月です。ならば、9月いっぱいは、封鎖と猛烈な空爆で日本人の戦意をくじき、それでもなお日本の交戦意欲が衰えず、このままでは多大な犠牲が避けられないと判断してからでも、原爆投下は遅くなかったはずです。それに、原爆実験前に紹介しましたが、日本を含む各国の軍人を原爆実験に招いて、その威力を見せ付けて、暗に降伏を促す方法も、実験が成功した今ならば、何もためらうことなく、実行できたはずです。そうしたことは何もしていないのです。トルーマンやスチムソンの説明は、明らかに後付の説明に過ぎないことは、明らかです。では、彼らの本音は、どこにあったのか。 続く
2011.07.25
コメント(2)
-
毒入りカレー事件 25日の日記
クロニクル 毒入りカレー事件1998(平成10)年7月25日あれから13年ですか。この日は町内会のボランティアをしている者には、忘れられない事件の起きた日です。和歌山県園部で起きた、夏祭りの振るまいに用意されたカレー鍋に青酸化合物が混入され、毒入りカレーを食べた4人の方が亡くなった、いいえ殺された事件です。会場近くの民家のガレージを借りてご近所総出でカレーを作り、会場へ運ぶまで交替で番をする、一種の炊出し訓練にもなりそうな、共同体慣行の名残でもあるような行事に、水を指す悪質な行為でした。見張り番の人達は、悪意を持って毒物を混入しようとする人を見張るのではなく、匂いに惹かれてちょっとお先にお毒見をと、考えるいたずら好きな子ども達対策だったに違いありません。まさかそこに毒を入れるなんて…この事件の影響で、この年の秋祭りでは、飲食物の提供を見あわせる町会も多く、各地に多大な迷惑を及ぼしました。犯人は年末に逮捕されましたが、この事件は子どもどころか、親世代の人達の幼児化が進み、精神発達が未熟なままで、身体だけが大人になってしまった、未熟児的大人が多くなっていることを、改めて印象付けました。この事件は、そうした善悪の判断、公共空間と私的空間の区別、行為の社会的影響などについての判断が出来ない「人間」の起こした象徴的な事件でした。この種の事件は、日本社会が失ってしまった社会の規範力の再構築なくして、解決しえない問題であることは確かですね。
2011.07.25
コメント(8)
-
続・米国原爆実験に成功 (8)
続・米国原爆実験に成功 (8) 米国は何故、日本に原爆を投下したのか。そしてそれは何故、開発実験の成功から1ヶ月も経たない8月の6日と9日だったのか。最後にこの点を検討したいと思います。この件に関する米国の公式見解は、以下のようになります。1946年、K,T,コンプトン博士は、以下の文章を発表しました。「私は、原子爆弾の使用が、アメリカ人と日本人の数十万人、いやおそらくは数百万人の命を救ったという、強い信念を持つに至った。原子爆弾を使用しなかったとしたら、戦争がなお多くの日数を要したであろうことは、疑う余地がないからである。」と。この文章に対し、原子爆弾の投下を最終決定したトルーマン大統領は、コンプトン博士に手紙を送り、彼の分析は大変公平な情勢分析であると褒め称え、さらに「あなたの論文に示された結論と、私が到達した結論とは本質的に同じである。」と、書き送ったのです。こうして、原爆投下は、多くの米国人と日本人の命を救ったという、アメリカ側の公式見解が出来上がったのです。この見解は、次の2点を含んでいます。1、原爆を投下すれば、日本は敗北するだろう2、原爆を投下しなければ、戦争はさらに続き、双方合わせて数百万人の死者が出るだろうだから、広島・長崎の30万人以上の死者は、数百万人の人々の命を救った犠牲者である。この2つの論点は正しいでしょうか。もう少し、アメリカ側の主張を見てみましょう。 続く
2011.07.24
コメント(6)
-
東京教育大学、筑波への移転を決定 24日の日記
クロニクル 東京教育大学、筑波への移転を決定1969(昭和44)年7月24日この日、東京教育大学(現在の筑波大学)の評議会は、政府が推進を決定していた筑波研究学園都市への移転を決定しました。この構想については、移転を承諾すれば、旧式の設備を一新でき、しかも大型の研究用機材を大量に新規購入できることに魅力を感じた理工学系の教員が概ね移転推進派となり、人文、社会科学系の教員の多くは、人事等で国家管理色が強まることを嫌って、移転反対を強く主張するなど、学生をも巻き込んで学内を二分する大問題になりました。この年1月には東大安田講堂を占拠した全共闘派の学生を、機動隊が排除するなど、全国的に学生の反乱が続いており、東大闘争以後も、各地の大学でのストライキや授業ボイコットが続き、全国学園闘争と称された事象は、なお衰えをみせていませんでした。当時は、そんな時代環境にありました。それゆえ、移転反対派の学生たちは、移転を決定した評議会の議事録の公開や移転賛成の根拠の公開を求めて、ストライキや全学封鎖を繰り返し、一時は騒然たる空気に包まれましたが、70年代に入って全共闘運動の退潮と共に、移転へ向けてのスケジュールが進むことになりました。しかし、移転反対派の教授陣の多くは、民主的手続きを踏んでの移転決定手続きが採られないことに抗議して辞職の道を選び、文系の名物教授の多くが、他大学に転籍する事態を招きました。こうした事情から、移転後しばらくの間、筑波大学は文系スタッフの確保に四苦八苦する状況が続きました。
2011.07.24
コメント(10)
-
黒船来航(39)
黒船来航(39)日本の幸運の第1は、その地理的位置にありました。日本は西欧列強から最も遠い極東の島国でした。西欧人にとっては、日本に至るまでに、豊かな自然に恵まれた魅力的な島々が各地にありました。インド然り、マラッカ然り、現在のインドネシア然り、インドシナ半島然り、そして中国です。私は、もし日本の地理的位置が、もっと南に下がっていたら、どうだったろうかと考えると慄然とします。幕末の日本及び日本人にとっても、仰ぎ見る大国であった隣国中国が、1840年~42年にかけてのアヘン戦争で、逢えなく大敗したことを目の当たりにした日本人のショックは、実に大きかったのです。ペリーの艦隊に中国語の通詞として加わった羅森が、黒船を訪問した日本の教養ある人々の間で、一番人気だった事実は、以前指摘しました。この事実は、アヘン戦争以後の幕末の段階でも、多くの日本人にとって、中国がなお憧れの対象だったことを、はっきりと示しています。その中国を、簡単に打ち負かす西欧列強の軍事力。これは戦って勝てる相手ではない。中国敗北のショックが大きいだけに、時の支配者である徳川幕府は、そのことをしっかりと学習し、もし開国を迫られた場合は、戦わずに交渉によって道を開くことを、申し合わせる時間的余裕を持つことが出来たのです。まさしく、日本はその地理的位置によって、西欧列強への対応の仕方を学習する時間を、確保することが出来たのです。 続く
2011.07.23
コメント(2)
-
続・米国原爆実験に成功 (7)
続・米国原爆実験に成功 (7)目視投下は、天候が悪ければ実行できません。8月5日の夜、広島上空は晴れ渡り、きれいな星明りとなりました。この広島に午後9時半頃に、空襲警報が発令されました。たった1機のB29が飛来したのです。偵察に来たのです。同機は、明朝の天気は良さそうだという報告を、テニアン基地に送りました。テニアン基地では、この報告を受け、深夜午前1時過ぎに3機の観測機が出発しました。エノラ・ゲイら3期編成の本隊は、その約1時間後に基地を出発しました。原子爆弾を積み込んだエノラ・ゲイ号と、計測機器やカメラなどを積み込み、科学者やカメラマンを乗せた2期の観測機という構成でした。この日広島市の天候は、雲が多いものの晴れていました。第1目標広島への投下に、迷う余地はなかったのです。広島に到着したエノラ・ゲイ号は、午前8時15分17秒、何も知らない人々の上に、「リトルボーイ」と名付けらえれた原子爆弾を投下したのです。爆発が起きたのは、投下から43秒後のことでした。投下から7年後、「中国新聞」は、独自の総力取材を行い、同年7月25日付けで、原爆による被害は死者だけでも282,000人にのぼると発表しました。翌1953年4月の広島市役所の調査では、死者26万人、行方不明者66,700人、重傷者5万1千人、継承者10万5千人と発表されました。当時の広島市の家屋、76,327戸のうち、70,107戸が被害を受け、うち5万5千戸は全焼しています。1つの地方の中核都市が、一瞬にして壊滅したのです。 続く
2011.07.23
コメント(10)
-
自衛隊潜水艦釣り舟と衝突 23日の日記
クロニクル 自衛隊潜水艦釣り舟と衝突1988(昭和63)年7月23日この日午後3時半過ぎ、三浦半島の横須賀港の沖合いで、海上自衛隊の潜水艦「なだしお」(2200トン)と、大型の釣り漁船「第1富士丸」(154トン)が衝突しました。第1富士丸は僅か1分足らずで沈没し、通りかかったタンカーとなだしおが乗員・乗客48名の救助にあたり、19名を救助しましたが、うち1名は同夜死亡、29名は行方不明となりました。4日後の27日、第1富士丸は海底から引き上げられ、行方不明者全員の遺体が収容されました。夏休みに入った直後の事故でしたから、親子連れの乗客も多く、船室に留まっていた乗客のほとんどが、急の沈没に脱出の間もなく、船内に閉じ込められて水死した様子が、次々に明らかになりました。死者30名という大事故でした。事故の原因は双方の衝突回避行動の遅れによる、初歩的ミスとされましたが、救助にあたったタンカーの証言から、衝突直後になだしおが機敏に救助にあたらなかった事実や、回避行動の遅れを隠蔽するために、航海日誌を改竄していた事実が明らかにされ、自衛隊に対する風当たりは強くなりました。そのため、1ヶ月後の8月24日、当時の瓦防衛庁長官が事故の責任をとって、辞職することになりました。また、東京湾の船舶航行が超過密状態で、危険がいっぱいの状態であることも明かになりました。
2011.07.23
コメント(8)
-
続・米国原爆実験に成功 (6)
続・米国原爆実験に成功 (6) そこから、米軍の原爆投下作戦は、慌しく動き出しました。7月16日の実験に先立って、第20空軍509爆撃隊に属する15機のボーイングB29爆撃機が、中部太平洋のテニアン島に配置換えになりました。15機は全機そろって尾部に黒い円を黒い矢が貫いているマークをつけていました。C・ルメー将軍指揮下の15機は、日本本土への原爆投下作戦を受け持つ部隊でした。そして、実験成功から僅か10日後の7月26日朝、重巡洋艦インディアナポリス号は、「ポテトチップの缶くらい」の小さな鉛の円筒に入ったウラン爆弾を積んで、テニアン島に到着したのです。原子爆弾がテニアン島に到着する1日前の7月25日、スチムソン陸軍長官の承認を得た一通の命令書が、対日作戦を指揮するアーノルド空軍司令官の下に届けられました。そこには、次のように書かれていました。「第20空軍509爆撃隊は、本年8月3日頃以降、天候が目視爆撃を許す状況になり次第、可及的速やかに最初の特殊爆弾を、次の目標の一つに投下すべし。目標は、広島、小倉、長崎、新潟」と。8月2日頃から、西日本の天候は、台風の影響を受けて、不安定な日々が続きました。8月6日以前は、目視爆撃のできる条件はなかったのです。かくして、運命の日は6日となったのです。 続く
2011.07.22
コメント(2)
-
日本基督教連盟軍国主義に協力を表明 22日の日記
クロニクル 日本基督教連盟軍国主義に協力を表明1937(昭和12)年7月22日この日、日本基督教連盟は「時局に関する宣言」を発表、軍国主義の国策に協力することを表明しました。この日の約2週間前に当たる7月7日、盧溝橋で日中両軍が衝突し、日中戦争が始まっていました。日本の軍部は戦争の拡大によって、華北から華中一帯を占領する計画を立て、統帥権の独立を楯に、政府の命令を無視して戦争拡大路線をひた走ります。そうした目論みの下、信者数がそこそこ多い宗教団体に対し、国策に協力するよう圧力をかけてきたのです。基督教連盟もまた他の宗教団体と同じように、残念ながら軍部の圧力になすすべなく屈服し、国策への協力を表明したのです。基督教会の多くもまた、一定の戦争責任を免れない存在となったのでした。
2011.07.22
コメント(10)
-
黒船来航(38)
黒船来航(38)勿論、日米修好通商条約は、日米の交渉によるもので、戦火を伴っていませんから、領土の割譲や賠償金の支払いもありません。そこには多額の賠償金の支払いによる国富の流出もありませんし、領土の割譲による政治的な怨念も生まれることはありませんでした。もっとも、こうした形での国富の流出や政治的怨念に無縁であったことが、やがて日清戦争を契機に、日本が列強に移行すると、敗戦国や植民地民衆に対する苛酷な要求の押し付けによって、植民地民衆の草の根の抵抗に、苦しめられることには繋がっていくのですが…。ともかく、幕末から明治初期にかけての日本の政治支配層の判断は、実に当を得た適切な判断だったことは間違いありません。この適切な判断が、日本の危機、欧米列強による植民地化の危機から、日本を守ったことは、間違いのないところです。他には、いくつかの歴史の女神が齎した幸運が作用しているのですが、その幸運を現実に生かしきる力のある政府が、当時の日本に存在したことは間違いありません。最後に、歴史の女神(=クリオ)の微笑みとは何かを、簡単に振り返ることにしたいと思います。後数回、お付き合いをお願いします。 続く
2011.07.21
コメント(4)
-
続・米国原爆実験に成功 (5)
続・米国原爆実験に成功 (5) また話は前後します。原爆実験成功に約1ヶ月先立つ6月18日、ホワイトハウスで対日作戦が検討されました。正副大統領に三軍の長が揃い、「九州侵攻作戦」の適否が検討されたのです。沖縄戦での日本軍の激しい抵抗で、多数の死傷者を出した記憶が生々しかったことから、九州上陸作戦となると、犠牲者がさらに大きく膨らむことが予測されました。マーシャル参謀総長は「これは憂鬱な数字ですね。しかし、戦争には手軽で血を流さない勝利などないのです」と発言しました。スチムソン陸軍長官の重大発言が飛び出したのは、この後でした。彼は、「何か他の手段によって、ある種の成果をあげたいものだ」と語ったのです。この発言は、完成が近付いている原子爆弾の対日投下を示唆した発言でした。米国政府の公式見解、「原子爆弾の投下は、数十万いや数百万に及ぶかもしれない、アメリカ人並びに日本人の命を救ったのだ」という見解は、ここから生まれました。この見解が後に作られた、巧妙な言い逃れであることは、この連載の最後に記すことにして、先を続けます。この会合から半月経った7月3日に、広島等への爆撃を禁じる命令が出されたことは既に記しました。では、具体的な原爆投下作戦は、どのように進行したのでしょうか。 続く
2011.07.21
コメント(6)
-
「上を向いて歩こう」の誕生 21日の日記
クロニクル 「上を向いて歩こう」の誕生1961(昭和36)年7月21日誕生から今年でちょうど50年なんですね。故坂本九ちゃんの代表作として知られる、「上を向いて歩こう」が初めて、披露されました。といっても、まだ九ちゃんが歌ったわけではありません。この曲は、50年前の今日開かれた、作曲者の中村八大さんのリサイタルのために書かれた曲で、この日初めて演奏されたのです。作詞はコンビの永六輔氏でしたが、この時点では、レコーディングの話は出ていなかったのです。坂本九によるレコーディングは秋に行われ、10月に発売がとなりました。レコード発売と時を同じくして、この曲はNHKの人気番組『夢で逢いましょう』の10月~11月の今月の歌として紹介され、61年11月~62年1月の3ヶ月間レコード売り上げのトップを独走する、爆発的な大ヒットとなりました。
2011.07.21
コメント(12)
-
黒船来航(37)
黒船来航(37)昨日に続き、中国が強いられた敗戦条約である天津条約や北京条約と、日本が結んだ交渉条約である日米修好通商条約との相違点を記します。第3に、外国軍による内政干渉の問題があります。中国では、開港した各港に、イギリス軍艦の自由入港が認められていました。何かあればイギリスは、自国艦船を派遣して、砲艦外交に訴えることが出来るようになっていたのです。これに対し対日条約では、外国艦船の寄港は、薪水の補給に限られ、砲艦外交を展開することは認められていませんでした。第4に、関税の問題です。関税行政に関して、日本は僅かに自主権を確保していましたが、関税自主権についての理解を欠いたがゆえに、迂闊にも関税自主権を主張し、確保することの重要性に思い至らず、敗戦中国の締結した条約と同じく、関税自主権を失っていました。この点は、欧州資本主義の後発組であるドイツ、ロシア(1917年まで)、イタリアが、いずれも「保護関税」を設けて、世親資本主義国に対抗したのに比べ、明らかに不利な状態にありました。しかも、既にお伝えしたように、安政条約は条約の期限を明記していないという欠点を持っていたがゆえに、この不利益を交渉によって解決するためには、多くの困難を伴ったのです。しかし、日本側の不利益はこの点に留まりました。第5に、アヘン条項を見ましょう。中国ではアヘンの取引は、イギリスのごり押しで合法とされていました。日本では当然のごとく厳禁で、アヘンの禁輸、見つけ次第の没収が明記されていました。第6に、居留地での外国人の自治権の問題です。中国では上海の租界など、各地に中国政府の支配が届かない地域がありました。しかし、日本では外交人居留民の自治機関は、実質的な形成を見ることがなかったのです。横浜の事例を紹介しましたが、日本側が先手を打って、各国別に線引きした居留地を提供し、居留民全体を招いた歓迎宴を催すなど、相互関係が円滑であったがゆえに、居留民にとって、自治機関の必要性を意識させるような、居心地の悪さが存在しなかったからなのです。 続く
2011.07.20
コメント(4)
-
続・米国原爆実験に成功 (4)
続・米国原爆実験に成功 (4)7月16日に行われた実験の様子を記します。この日午前5時30分、ニューメキシコ州アラモゴーゴールドの砂漠地帯に作られた高さ30mの鉄塔の頂上で、その場にセットされていた実験用の原子爆弾が、大爆発を起こしました。実験は成功したのです。濃い紫とオレンジの光に縁取られたかのような火の球は、直径1600mほどに膨れ上がり、上空12000mに達するキノコ型の原子雲となって立ち上りました。当時の米陸軍の推定で、爆発の威力は、TNT火薬にしておよそ2万トンに相当するとみなされました。勿論実験用の鉄塔は、跡形もなく崩れ落ちていました。爆発の直後、実験を見守った軍人の1人は、実験を指揮したグロービスの問いかけに、「戦争は終った」とうめくように語ったと、当のグロービス自身が証言しています。原子爆弾が、遠からぬ日に、日本に投下されることを、この軍人は知っていたのでしょう。原子爆弾の恐るべき威力を目の当たりにした軍人が、思わずそうしゃべったであろうことが、推測されます。では、米軍はどのように原子爆弾の対日投下を決めたのでしょうか。この点は、何段階かに渡って重層的に決められていったことが、現在では明らかになっています。 続く
2011.07.20
コメント(4)
-
マクドナルド日本上陸 20日の日記
クロニクル マクドナルド日本上陸1971(昭和46)年7月20日40年前のこの日、日本マクドナルドのハンバーガーレストラン1号店が、東京の三越銀座店内で産声をあげました。手頃な価格と、調理に時間のかからない、すぐに口に出きるお手軽さが受け、瞬く間に若者の間に支持を広げたことはご存知の通りです。ファーストフードの隆盛はマクドナルドによって準備されたと言っても、言い過ぎではなさそうですね。それから40年、同業態の店を含めると、いったい何店の店が日本にあるかも、分からなく釣堀のね、
2011.07.20
コメント(12)
-
黒船来航(36)
黒船来航(36)アヘン戦争の敗北に始まり、その後の敗戦の都度、中国(当時は清)が西欧列強に締結を強いられてきた諸条約と、1858年に結ばれた安政条約、日米修好通商条約とは、冷静に比較してみると、類似面よりも相違面の方が大きいのです。そこでは、1858年の天津条約や1860年の北京条約の方が、明らかに従属性、不平等性が強いのです。その点を少し具体的に記してみましょう。第1に、キリスト教の布教問題を挙げると、中国では原則自由で、宣教師は中国国内の通行の自由と、中国官憲の保護が得られることになっています。安政条約には、こんな規定はありません。 日本との条約相手国の宣教師は、布教は認められますが、任地には制限があり、日本官憲に届け出て、布教並びに居住の許可を得る必要がありました。第2に、内地旅行権の問題です。中国では、全国各地どこにでも出かけることが出来ました。しかし、日本では、開港した5港の居留地並びに周辺の定められた範囲を除けば、旅行の自由はありませんでした。商業活動は、居留地内でしか行なえず、旅行も定められた遊歩地内に」限られていました。有名な生麦事件も、横浜居留地の外国人に認められた遊歩地での出来事でした。日本政府に雇われ、その許可を得たものだけが、行動の自由をある程度許されたのです。従って、不平等条約の象徴とされている治外法権は、日本では、実質的な問題となることは、ほとんどなかったのです。むしろ、現代の沖縄における米軍人の犯罪の方が、よほど治外法権の観点からすると、大きな問題だと私は考えています。 続く
2011.07.19
コメント(2)
-
続・米国原爆実験に成功 (3)
続・米国原爆実験に成功 (3)原爆実験の行われた7月16日、陸軍長官スチムソンは、17日に始まるポツダム会談に備え、大統領トルーマンと共に、ドイツに向かっておりました。スチムソンとトルーマンは、ポツダムの宿舎で、暗号電報により、実験成功の報告を受けました。ドイツ時間で、昼をまわった頃のことです。暗号電としたのは、敵側に情報が漏れることを警戒しての、当然の措置でした。電文は以下の通りです。「医師無地帰着。生まれた男の子は活発で、目の輝きは、統治からハイホールドまで達し、鳴き声は、小生の農場まで達した。」送信者は、J.L.ハリソン。原子力政策を束ねる委員会で、スチムソンの補佐役を務めた人物です。この報告を受けたスチムソンは、ただちにイギリス首相チャーチルを訪問、1枚のメモを手渡しました。壁に耳ありを警戒したのです。メモには「赤ん坊は、満足に生まれた」とだけ、記されていました。チャーチルもまた無言で頷いたのみで、2人は、すぐに別れました。男児の誕生は、核兵器実験の成功を意味し、医師とは、原爆計画担当部隊の指揮官を指していました。「目の輝き」は広島の生き残った子ども達が「ピカッ」と名付けて畏れた閃光をさします。それゆえ、鳴き声は当然、「ピカッドン」の「ドン」を指します。ハイホールドは、実験の行われたアラモゴールドから400kmの距離にありましたから、閃光は400km先でも確認されたことになります。またハリソンの農場までは、およそ88km程度とされていますから、100km近く先でも、聞こえたということになります。核兵器の誕生、即ち何10万人もの命を一瞬にして奪い、その後も奪い続ける悪魔の兵器の誕生を、赤子の誕生に例えるとは…。私には、こうした神経はとても理解できません。 続く
2011.07.19
コメント(10)
-
日本もボイコットしたモスクワ五輪開幕 19日の日記
クロニクル 日本もボイコットしたモスクワ五輪開幕1980(昭和55)年7月19日この日、第22回目の近代オリンピック、モスクワ五輪が開幕しました。モスクワ五輪については、前年79年12月27日に始まったソ連軍のアフガニスタン(以下アフガンと略記)への侵攻に抗議して、英国、中国、西独(当時)、日本などが、ボイコットを表明、参加を見合わせました。この結果、五輪出場を目指して、厳しい練習に明け暮れていたアマチュアの選手達、とりわけ80年前後が選手生活のピークであった、マラソンの瀬古選手など、当時の代表選手たちが、泣きをみることになりました。ソ連のアフガン侵攻から、1ヶ月も経たない1月の中旬に、人権外交というスローガンを掲げた米国のカーター大統領が、ボイコットを表明、対米従属を国是と考える日本にとっては、ボイコットに追随する以外の選択肢は、事実上無くなっていたのです。スポーツが政治に従属している事実が、余す所なく映し出された、考える事の多い出来事でした。
2011.07.19
コメント(8)
-
祝!なでしこジャパン優勝
祝!なでしこジャパン優勝こんにちは。今朝は9時に起きました。ほぼ毎朝通りでした。「果報は寝て待て」主義の我が家は、昨夜は一番遅かった娘と私も、3時には就寝。空気としては、決勝まで出たこと、ドイツ、スウェーデンを連破して、ワールドカップの決勝戦のピッチに立っただけで大満足。疲れもたまっているだろうし、善戦敢闘してくれれば十分、そんな空気でした。ところがでした。驚きました。起床してリビングに下りていくと、先に起きていたワイフが、珍しくこの時間にテレビを見ています。「おはよう」も言う前に、いきなり「なでしこ、勝ったわよ!」の一声。「エッ!」新鮮で嬉しい驚きでした。90分は1:1。先制されて追いつき、そして延長もまた1点づつとって、追いつき。2:2でPK戦へ。驚きました。善戦し、敢闘してくれればは、彼女たちに失礼でした。彼女たちは本気で勝つ気でした。逆に追い上げられ、追いつかれたアメリカは、負ける気がなかっただけに、追われた時の心のコントロールが難しかったのでしょう。ビデオ映像ですが、PKに出てくる選手にオーラが感じられませんでした。負けの経験の乏しいものが陥るワナでしょうか。流行語になった「想定外」の事態に、アメリカは沈みました。そうは行っても、日本選手は4本中3本のpkを決め、アメリカ選手は1本しか決められなかったのです。2本のPKをしっかりセーヴしたキーパーの海堀さん、見事でした。沢選手得点王とMVPおめでとうございました。この快挙がきっかけとなって、日本における女性の社会進出が、さらにすすむことになることを、私は熱く期待しています。現在の経済のデフレ傾向。少子化で、若い人たちや中堅世代への所得移転が十分に進まないことに、大きな原因があります。その点は、家庭に滞留している主婦層をの社会復帰、共働きを当然とする社会風潮をさらに前進させることでしか、解決は難しいでしょう。女性が働きやすい環境の整備こそ、急ぐ必要がありますね。
2011.07.18
コメント(14)
-
光化学スモッグ発生 18日の日記
クロニクル 光化学スモッグ発生1970(昭和45)年7月18日この日、午後1時頃、東京杉並区堀の内の立正高校で、40数人の生徒が突然吐き気などを訴えて倒れ、近くの病院に運ばれました。都公害研究所は、新種の公害の可能性が考えられるとして、調査に乗り出し、光化学スモッグの発するオキシダントと、高湿度の中で発生した硫酸の微粒子による、世界初の複合汚染が原因と発表しました。発生地附近は、(1)急に気温が上がった(2)天気が良く紫外線が強かった(3)風が弱く空気が澱みやすかったと、被害の出やすい条件が揃っていたことも指摘されました。この発表を受け、東京都を中心に全国の大都市では、観測態勢を強化し、オキシダント濃度が一定量を越えた場合に、住民に対して屋外に出ないように呼びかけるなどの対策を進め、学校に対しては屋外での体育や部活動などを、一時的に休止するように求めるなどの対策を講じました。自動車の排ガス規制が強化されるようになるのも、この時以降のことです。今ではお馴染みの光化学スモッグ注意報や光化学スモッグ警報の発生、41年前のことだったのですね。
2011.07.18
コメント(8)
-
黒船来航(35)
黒船来航(35) 二字漢語は、やがて中国へ里帰りします。日清戦争後、日本への中国人留学生の来訪が始まります。彼らは、この新造の二字漢語で、欧米の新概念、新知識を吸収します。こうした二字漢語が、やがて彼らの手で、漢字の母国=中国へ持ち帰られたのです。現代中国語に見られる、日本語と共通する二字漢語の多くは、ここに起源を持っています。ペリー来航を簡単に記す積りが、思わず長くなりました。最後に、徳川幕府が結んだ2つの条約と、当時の中国や後の朝鮮が結ばされた条約との違いを対比して、終わりにしたいと思います。我々の中学・高校の時代の歴史では、「徳川幕府の結んだ安政の諸条約(日米修好通商条約並びに、最恵国待遇によって英・仏・露・蘭と結んだ同内容の条約です)は、不平等条約であり、関税自主権はなく、治外法権も認めている」と、教えられてきました。関税自主権はなく、この点では明らかに不利でしたが、治外法権は、実はほとんど問題とならず、事実上認めていないに等しいのです。その他の点でも、実は違いが大きいのです。 続く
2011.07.17
コメント(6)
-
続・米国原爆実験に成功 (2)
続・米国原爆実験に成功 (2)米国が初の原爆投下実験に成功した7月16日から、約1ヶ月半前の6月1日に遡ります。この日スチムソン陸軍長官を委員長とする「原子力利用のための委員会」と名付けられた、原爆使用のための委員会は、以下の3ヶ条からなる計画を、トルーマン大統領に提出し、その承認を得たのです。提案は以下の通りでした。1)原子爆弾は、速やかに日本に投下すること2)民間建造物に取り囲まれた軍事施設を目標とすること3)爆弾の性質については、無警告とすること以上の3点です。この決定に至るまでに、委員会の内外で、様々な意見が戦わされたことが、今では明らかになっています。当初は、日本の軍人を含む諸外国の軍人を、オブザーバーとして招いて、原爆実験を国際的デモンストレーションとしてはどうかとか、原子爆弾(新兵器)の恐るべき威力の一部を打ち明けて、対日警告とし、定めた期日までに降伏しなかった時にのみ、使用したらどうかと言った案などが、検討されました。しかし、こうした案については、もし実験が失敗したらどうするのか。絶対に成功するとはいえないではないかという声が多数を占め、また原爆を摘んだ飛行機が狙い打ちされないかとか、投下候補地を悟られて、そこへ捕虜達を送り込まれる危険があるのではといった声があがり、結局無警告での投下となったのです。そして原爆実験成功の約2週間前の7月3日、統合参謀本部は、マッカーサー、ニミッツ、アーノルドの陸海空3軍の対日総司令官に対し、京都、広島、小倉、新潟の4都市への爆撃を厳禁する通達を発しました。この命令には理由は付されていませんでした。しかし、3司令官は、当時の対日攻撃の中心が、主要都市への爆撃を追え、地方の中核都市への空爆と艦砲射撃に移っていた事情を踏まえ、この命令が、新型爆弾の投下候補地を示していることを理解したのです。このうち、京都はスチムソン長官の強い反対で候補地から外れ、方向が離れる新潟は補欠に回され、新たな候補として長崎が加えられたのです。 続く
2011.07.17
コメント(10)
-
「もはや戦後ではない」
クロニクル 「もはや戦後ではない」1956(昭和31)年7月17日この日発表された経済企画庁の『経済白書』は、副題を「日本経済の成長と近代化」として、日本経済の回復に対する自信をそれとなく示していたのですが、本文では、前年昭和30年中盤からの景気回復と物価の安定、そして金融緩和を綜合して「数量景気」と名づけ、日本経済は昭和20年代後半の特需依存型の景気回復を脱し、正常で安定的な成長軌道を歩み出しているとの判断を示し、「もはや戦後ではない。......回復を通じての成長は終った。今後の成長は近代化によって、支えられる」として、今後の経済成長への自信を背景に、バラ色の展望を示しました。「もはや戦後ではない」は、年度後半の大流行語となり、流行語大賞がこの時期に存在していたとしたら、間違いなくダントツで授賞しただろうと思われる勢いで、国内各層に浸透していきました。朝鮮戦争の休戦後、特需を失った日本経済は、深刻な不景気に見舞われ、一時的に元気をなくしていたのですが、前年(昭和30年)秋から、アメリカの景気回復による輸出の好調に支えられて、景気は回復傾向を示し始め、30年の貿易収支は5億ドルの黒字となり、それに加えて空前の米の大豊作が重なり、好景気にも関わらず、物価は非常に安定した状態にあったのです。この見通しの発表と、バラ色の空気は国民の気分を明るくし、翌32年にかけての、「神武景気」と呼ばれた好景気に繋がりました。神武景気後の後退期を経て、池田内閣の所得倍増政策を起点とする、高度経済成長期に連なって行きました。
2011.07.17
コメント(8)
-
黒船来航(34)
黒船来航(34)漢字2文字で1つの単語とすることが、当時は新鮮に映ったと、昨日の最後に記しました。当時は、中国語でも二字単語は例外でした。中国古典を綴った古典語以外では、稀にしか見られなかったのです。当然中国語をお手本とする日本語でも同じでした。簡潔な二字単語は、新しい概念を盛り込むのに適していました。今日われわれが日常的に使っている「政治」「経済」「文化」「文明」「銀行」などは、この時期に新造漢語として生まれたものです。日本人による最初の英和辞典として、1873(明治6)年に出版された、柴田昌吉と子安峻(こやすたかし)と共著『英和字彙(じい)』には、この二字漢語の原則が大々的に採用されていました。造語の方法は二通りありました。ひとつは中国古典にある単語の意味転換で、「革命」「民主」「経済」などが該当しました。もうひとつは、全く新しい漢字二文字のの組み合わせで。「哲学」「蒸気」「通信」「電気」などがそうでした。現代日本語で使われる二字漢語の多くは、こうして幕末から明治20年頃までに、一斉に造語されて、使われるようになったのです。 続く
2011.07.16
コメント(4)
-
続・米国原爆実験に成功 (1)
続・米国原爆実験に成功 (1)米国の核兵器製造計画は、1940年に研究計画をスタートさせたドイツに遅れ、1942年に開始されました。名高い「マンハッタン計画です」この研究計画は、大掛かりなもので、機密保持も大変厳重でした。しかも、研究拠点は広い米国の東西南北に分散され、計画の全貌を知るものは、ホンの僅かな幹部に限られていました。最初の原爆実験が行われたニューメキシコ州には、ロス・アラモスにニューメキシコ爆弾研究所が置かれました。テネシー州のオークリッジには、巨大なガス拡散工場と電磁工場が置かれていました。この町は、町そのものが兵器工場を母体として生まれたのですが、のち「原爆の町」と呼ばれることになりました。そして西海岸のカナダとの国境に位置するワシントン州ハンフォーどには、デュポン社の加わった、原子炉を備えたプルトニウム分離工場が建設されました。こうした各地の研究の進行状況は、全て首都ワシントンの陸軍省オフィスの一郭に」ある、目立たない小さな部屋に集められました。ここが「マンハッタン計画」の本部だったのです。この部屋には、小さいけれども極めて厳重な金庫が備えられ、そこに計画の全貌と進捗状況が一目で分かる極秘書類が入っていました。本部の課員は、全員暗号名で呼ばれ、相互に名前も知らなかったというエピソードも残されています。分かっているのは、責任者の准将が、「99」と呼ばれていたことだけです。「マンハッタン計画」は、当時のお金でおよそ20億ドルを使い、最大時には54万人もの人々を、登録雇用していたと言われます。54万人というのは、米国史上最大の作戦と言われた、ノルマンディ上陸作戦の1,5倍に当たる人数です。こうした物量作戦の末に、クロニクルに記したように、66年前の今日7月16日、米国は原爆実験に成功したのです。そして、実は米国は、原爆実験に成功する前から、近い将来の新兵器の開発成功を確信して、対日投下を決めていたのです。 続く
2011.07.16
コメント(8)
-
米国原爆実験に成功 16日の日記
クロニクル 米国原爆実験に成功1945(昭和20)年7月16日この日、米国はニューメキシコでの大気圏内核実験を行いました。離れた観測地点から閃光のきらめきが確認され、史上初めての原子爆弾の製造に成功したことが確認されました。トルーマン大統領には、「赤子は正常に生まれた」という暗号で知らされたのですが。大統領はただちに、日本への投下準備に入ることを指示したのです。その結果、実験成功の21日後には広島に、24日後には長崎と、製造から1ヶ月足らずで、2発の原爆が投下されたのです。最初に投下あり気だったことは、疑う余地がありませんね。
2011.07.16
コメント(10)
-
黒船来航(33)
黒船来航(33) 福沢が衝撃を受けた言語の問題に戻ります。幕末から維新にかけて、西欧文明の吸収に、日本の将来の進路を定めた、幕府や新政府の要人たちは、世界規模で汎用度の高い言語が英語であることに気付きました。中国語やオランダ語は、次第に国際的に通用する言語の地位を失っていったのです。こうなると、英語の修得が急務となります。どのように英語を学習すべきか。留学生の派遣は勿論ですが、それは次世代の人材の養成が狙いです。さしあたって今をどうするか? 先ずはオランダ語との構文の類似性に着目して、オランダ語と比較することで、構文の理解を深めました。前述した下田追加条約に付けられたオランダ語の訳文が、ここで大いに役立ったのです。しかし、近代西欧文明は、次々に新たな発明を生み、その都度いくつもの新しい単語を生み出します。この単語の理解には、オランダ語の知識は役に立ちませし、当てはまる単語は出てこないのです。1823年完成の、モリソンの『華英・英華辞典』が参考にはなりましたが、それ以降に次々に生まれた新しい造語は、カヴァーできませんでした。そんな頃に香港で出版されたのが、ロプシャイドの『華英・英華辞典』全4巻でした(出版1865~69年)。この辞典は、イギリス人が中国語を理解するために作られた英語の辞書ですが、この第4巻が英華辞典となっていて、漢文の素養が十分ある日本人にとって、英語学習の恰好の教材となったのです。そのため、この辞典は大量に日本に輸入されたのです。英語の修得を目指す気鋭の若者達に、どのくらいもてはやされたかは、海賊版の出版で、大きな利益を得た人物も出たことを紹介すれば十分でしょう。羅布存徳(ロプシャイド)原著/井上哲次郎贈訂『英華字典』がそれです。特に、ロプシャイド辞典の漢字2文字で1つの単語とする訳法が、とても新鮮に写ったようです。 続く
2011.07.15
コメント(8)
-
円高は日本経済に打撃か?
円高は日本経済に打撃か?新聞の間違い その2日経新聞は、他紙と違って経済紙です。その日経新聞にすら、円高で日本の輸出産業は大打撃を受けると平気で報じています。この報道は間違っています。ただ間違いと知りつつ「ウソ」をついているようには思えませんので、間違いと気付かずに、そう信じているのではないかと、私は疑っています。経済評論家と称する人たちの中にも、そう口にしたり、書いたりしている人たちが多いですから…。事実を指摘します。ここに記すことは、2010年(つまり昨年)の財務省統計に載っていたものです。昨年の日本企業の貿易決済の通貨建て比率を見ますと、輸出のドル建ては48%、円建ては42%です。輸入では、ドル建ては71%で円建ては23%です。貿易においては、商品を購入する側、つまり輸入して代金を支払う側は、弱い通貨での決済を求めます。当然輸出する側、代金を受け取る側は強い通貨での決済を求めます。貿易においても、支払いは手型になります。1ヵ月後が期限とすれば、今1ドル80円のドルは、その頃には75円に下がっているかもしれないのです。ですから、ドル建てにしておけば、80円の支払いでなく、75円の支払いで済みます。ご承知の通り、昨年は対ドル、対ユーロで大幅な円高が進みました。それなのに、円建て輸出の比率が、ドル建てに追いつきそうな勢いなのです。輸入については、日本企業に不利な円建ては23%に留まっています。さて、そうはいっても、日本製品の輸入は、相手国にとって、高いものにつくことは事実です。ドル建て輸出の比率が増えても、輸出総額が減っていれば、円高打撃論は正しいということになります。しかし、昨年の輸出総額は、史上最高でした。つまり、円高は日本の輸出企業に打撃を与え、不況に直結するという考え方は、正しくないのです。円高で資源高を吸収することで、日本経済は助かっているのですね。大震災は、さすがに堪えたようですが、経済界は予想より早く、回復しつつあるようです。問題は市井の人々の暮らしの再建です。円高不況論は、信じない方が良いように思います。
2011.07.15
コメント(8)
-
ニクソン訪中発表 15日の日記
クロニクル ニクソン訪中発表1971(昭和46)年7月15日ちょうど今年で40年です。この日、米国のニクソン大統領が翌年5月までに中国を訪問して、朝鮮戦争以来険悪な関係のままだった米中関係を改善するため、毛沢東主席と会談する旨が、米中両国で同時に発表されました。仕掛け人はキッシンジャー大統領補佐官でした。ニクソン大統領は就任と同時に、ハーバード大学の国際政治学者キッシンジャーを大統領補佐官(2期目は国務長官)に任命、ヴェトナム戦争の集結に向けての国際関係の再構築を委ねました。キッシンジャーは、ヴェトナム戦争の集結には隣国中国の協力が不可欠と判断、中ソ対立の現状から米中関係改善に脈ありと考え、1949年以来親密な関係にあった台湾政府との関係を、微妙に調整してシグナルを送り、遂に中国首相周恩来から、隠密裏の中国訪問を歓迎する旨の連絡を受けたのです。当時米中関係の改善は、国際政治上の大事件でしたから、なおどうなるか分からない交渉の行方を考えれば、隠密行動は米中両国にとって、当然のことでした。こうして彼は公式にはヴェトナムを訪問、戦地を視察するとして、軍用機で香港へ飛び、車で広州入りし、そこから北京へ飛んだのです。時に7月9日のことでした。周恩来首相との数日に及ぶ会談の結果、中ソ対立に悩み、ソ連の攻撃を警戒する中国もまた、米中関係の改善に異論はなく、まさに「敵の敵は味方」を地で行くように、冒頭で記した翌年5月までのニクソン大統領の訪中が、決定したのです。慌てたのは、就任以来中国敵視政策を取り続け、中国の国連復帰を妨害し続けてきた佐藤内閣でした。あせり狂った佐藤首相は、あらゆるチャンネルを通じて中国へ接近しようとしたのですが、「佐藤内閣相手にせず」といなされ、目的は達成できず、沖縄返還を見届けて、翌72年6月に退陣することになりました。当時の美濃部亮吉東京都知事が71年8月の訪中時に、周恩来首相に宛てた佐藤首相の親書を託され、周首相との会談時に手渡そうとして、「これはなかったことにしましょう」とやんわりと受け取りを拒否されたのも、佐藤首相の焦りを示す一幕でした。当時美濃部知事も二期目の任期中で、選挙戦ではストップサトウと佐藤内閣との全面対決を掲げて圧勝していただけに、後日明かになったこのエピソードは意外感を持って受け取られたのですが、その点について美濃部氏は、日中関係の改善は急務であり、人を選り好みすべきではなく、判断は周首相にお任せすれば良いと考えたと、答えていたのが印象に残り、いまだに覚えています。
2011.07.15
コメント(8)
-
黒船来航(32)
黒船来航(32)一方、日本からも、海外へ出かけた人たちがいました。留学生としては、薩摩や長州などの下級武士や、西欧文明への好奇心に駆られた諸藩の若者たちが、イギリスやオランダ、アメリカなどに密航という形で出かけています。伊藤俊輔(のち博文)、井上聞多(のち薫)、上州安中藩の新島襄など、多彩な人材が海を渡っています。海外事情に疎い勢力による攘夷の動きは、致命傷になる前に、1863年の薩英戦争と、64年の下関砲台の攻撃という、局地的出来事で終わりを告げました、こうした攘夷の動きの終息には、海外に密航した藩士たちが、海外事情をつぶさに見学して、国力の違いを実感して、攘夷論がいかに愚かであるかを実感し、反論を開国に切り替えることに尽力したことが、力を発揮したのです。政府が派遣した海外視察団も、知識を世界に求め、外国で見聞したことを、大変有効に使いました。幕府が最初に派遣した海外使節団は、1860年に日米修好通商条約の批准書を交換するために、米国に渡った遣米使節団でした。2年後の62年には、遣欧使節も派遣されています。この2つの使節団に、同行した1人が福沢諭吉でした。彼は中津藩出身の旧幕臣であったことと、小藩の」出身であったために、明治政府には加わらず、新島襄らと共に、ジャーナリスト、教育者として活躍する道を選びました。外国での知見を生かした、『西洋事情』や『文明論之概略』などの彼の著作が、明治の若者に強い影響力を持ったことは、皆さんも御存知の通りです。 続く
2011.07.14
コメント(0)
-
おかしいぞ「日経新聞」!
おかしいぞ「日経新聞」!本日の「日本経済新聞」朝刊の1面に、「場当たり政策で国は衰退」と題する、編集委員実哲也氏の署名記事が載りました。「日経新聞」ばかりではないのですが、このところの新聞各社の記事には、「原発擁護」と受け取れる記事が目立ち、これでは、政府や電力各社の御用新聞まがいではないかと、不安に思っていたのですが、今日の実氏の記事は、ひどいものでした。「投資や雇用の計画が立てにくくなったのが、1番困る」という、経営者の声を最初に紹介して、彼はこう続けます。「福島第1原子力発電所の事故を受けて、多くのメーカーが関西などへの生産シフトを表明したのは僅か2ヶ月前のこと。気がついたら電力不足が最も深刻なのは関西圏になりつつある。来春にも全ての原発が止まる可能性を誰が想定できただろうか。」と。関西圏の普通の生活者が慌てるのなら分かります。しかし、まともな企業経営者や、実氏のような大新聞の編集委員が、この事態を全く想定しなかったというのは、果たして本当でしょうか。私は、この文章は真っ赤なウソだと指摘します。第1に、フクシマの事故が発生した直後であれば、事態の拡がりや収束への見通しが不明でしたから、関西圏への影響が読めなかったというのは、認めても良いかと思います。しかし、事故から1ヵ月後の4月半ばまでには、事故の長期化と影響の拡大、損失補てんと補償で、東電の屋台骨が揺らいでいることは、誰の眼にも明らかでした。企業経営者の最大の任務は、企業の将来のために世界と日本の今後を見通し、その見通しの下に、短期・中期・長期の企業戦略を練ることと、次代の経営者を育てることの2点にあります。世界と日本の今後の動向を見通せないような経営者がいれば、その企業は衰退に向かい。やがて競争に敗れて消えていきます。ですから、世界レヴェルの競争にしっかり耐え、利益を稼ぎ出している企業の経営者は、当然のこととして、原子力発電のウエートが9電力の中で飛びぬけて高い、関西電力が電力不足に悩まされるかもしれないということは、見通せて当然なのです。フクシマ危機の長期化、原発に対する世論の目の硬化や不安感の増大。世論の批判を無視できない政界の動き。この程度のことが予測できない、ヤワな経営者が世界規模の競争に耐えられるはずがないことは、すぐに分かります。まともな経営者は、早くからこの事態を予測していた。ただし、固く口は閉ざしていたのでしょう。さて、大新聞の編集委員の実氏です。彼も長く企業経営者を取材してきた記者の1人です。ですから経営者の資質も知っているでしょうし、マスコミ人として、事故の長期化が世論の批判を強め、日本の原発体制が揺らぐ事態が起こることは、予測したでしょう。ですから彼は、「来春にも全ての原発が止まる可能性を」想定できる立場にいたのです。それを、シャーシャーと「誰が想定できただろうか」と書くのです。自分も、企業経営者も、祖の可能性を知っていたのに…です。実氏と日経新聞は、「原発がないと大変なことになる。停電が発生するかもしれないし、節電要請はもっと強まるかもしれない。それ以上に企業の海外流出が続いて、日本の雇用は脅かされ、失業が増えて凄い不況になるかもしれない」と、読者を脅すことで、原発容認に世論を誘導しようと企んでいるのでしょう。私はそう読みました。冒頭の「投資や雇用の計画が立てにくくなった」は、菅内閣の瞑想による、復興計画立案の遅れに対する批判とも、読めますから、ただちに電力問題にかかるわけではありません。最後に、署名記事の日経を槍玉に挙げましたが、他紙も日経と大同小異であることを付言しておきます。
2011.07.14
コメント(18)
-
東京スカイツリー起工式 14日の日記
クロニクル 東京スカイツリー起工式2008(平成20)年7月14日3年前のこの日、東京スカイツリーの起工式典が行なわれました。東武鉄道が本社に隣接する貨物駅跡地を提供し、その地に建設されています。完成前の現在、既に新たな観光名所となっており、まさに東武鉄道は「損して得とれ」を地でいったといえましょう。東京スカイツリーの建設目的は、東京都心部の超高層ビルの増加によって、東京タワーからの送信が電波障害を生じるようになったため、TV各局が代替施設の建設の必要を痛感したことにありました。ですから当初は、地上デジタル放送のために、建設が計画されたわけではなかったのです。ところが、建設計画案作成期間中に地上デジタル放送が次第に普及し、2011年7月24日には地上アナログテレビ放送が終了となることが決まったため、地上デジタル放送用の電波塔になりました。現在の竣工予定は2012年2月。その後試験放送などを経て、2012年5月22日に開業の予定と、東武鉄道から発表されています。事業主体は東武鉄道が筆頭株主の「東武タワースカイツリー株式会社」。事業費は約500億円。このために、同社は500億円のユーロ債のCBを発行して資金調達を行いました。発行後に円高=ユーロ安が進行しましたから、同社はかなりの為替差益という恩恵を受けられます。施行は大林組が担当しています。
2011.07.14
コメント(6)
-
牛乳と牛肉
牛乳と牛肉中部大学の武田邦彦先生のブログに、こんな記事が載っていました。「チェルノブイリでは原発から少し遠いところの牛乳を飲んだ子供たちから大量の甲状腺がん がでました。このことがあるので、私も牛乳については慎重に調査をしていましたが、どう も危険なようです。 事故直後は、北海道産の牛乳は北海道産でしたが、今では、福島、茨城、千葉の牛乳は大量 に西日本に送り、そこで、「汚染された牛乳」と「綺麗な牛乳」をまぜて、ベクレルを規制 値以内に納めているという情報もあります。 つまり、政府が「規制値を下回ったものを拒否するのは風評」と言い、それにのって業者が 「混ぜてベクレルを下げる」ということもなされるでしょう。 もちろん、政府も業者も「罪の意識」がありますから、発表しませんし、マスコミの調査も 隠されているようです。悪いことをしているという気持ちはあるのです。福島などの牛乳に ついて多くの人が不安に思っているのですから、出荷する時にはバッチ(一つのタンク)毎 に測り、それを公表すれば、むしろ牛乳の販売も順調にいくと思います。データを隠せば隠 すほど、事態は紛糾するでしょう。 牛乳は産地が限定された少し高めの牛乳を買ってください。」(7月11日のブログ)牛肉については、7月9日のブログにこうあります。 「2011年7月9日、牛肉に放射性物質が2000ベクレルも検出されました。 2000ベクレルというと、一日100グラムの牛肉を食べると1年で内部被曝を1.5ミ リシーベルト程度浴びます。 私は4月に各地のデータを見ていましたら、その時点ではまだ肉類には放射性物質が取り込 まれていませんでした。7月に入って牛肉に放射性物質が入ることを予測できず、すみませ んでした。…… 牛肉の汚染は私の予想よりかなり早かったのですが、汚染されたと分かった限りは、出来る だけオーストラリア産の牛肉を求めた方が良いと思います. 牛肉が汚染されているということは福島、関東の牛肉、豚肉、鶏肉、卵は全部、注意した方 が良いでしょう。代謝速度は、動物の大きさのルートですから、ウシとブタが5倍違うとす ると、ブタの方が2倍速く汚染されることを示しています. 残念ですが、福島やその近郊の酪農家の方は、肉類の生産を一時、中断し、状況を見られる ことが大切と思います.」政府と東電は、事実を隠蔽し、隠蔽しきれなくなると、渋々「実は…」と公表することを繰り返してきました。そしてマスコミもまた、そうした政府や東電の味方をしているようです。その間に、国民の、とりわけ子ども達や若い人たちの被爆が進んできました。とりわけ問題なのが、食品その他、今までは危険としてきた数値を、此のくらいなら問題ないと、根拠も不十分なままに、国民を言いくるめようとする態度です。明らかに政府とマスコミは、産業界や生産者の立場を守ろうと(それはおそらく、生産者への補償が、天文学的数値に跳ね上がることを警戒してのことでしょうが)、国民の被爆に目を瞑ることに決めたようです。マスコミもひどいですね。中国産食品から規制値を超えた有害物質が出た時の、危険だ信用ならないという大合唱と、なんたる違いでしょうか。別に私は、大合唱をわるいというわけではありません。大合唱をするなら、同じ基準で規定を超えた放射性物質が検出された食品についても、同じように危険だ排除せよと、キャンペーンを張るべきであり、それを救済せよという知事や政府を糾弾するのが、節度あるマスコミの態度のはずです。政府もマスコミも、地方自治体も信用ならないことは、はっきりしていますね。
2011.07.13
コメント(8)
-
黒船来航(31)
黒船来航(31)幕末の横浜の経験は、明治政府にも継承されました。イギリスやアメリカばかりでなく、フランスやドイツからも、「お雇い外国人」と呼ばれた一群の人々が、日本にやってきました。政府のみでなく、民間でも外国人を招いたり、雇ったりという動きが続きます。彼らは、各種の技術指導や知的ノウハウの伝授に勤しみ、日本の「近代化」に大きな足跡を残しました。その分野は、政治、法制、産業、財政、教育、文化、技術、医学などなど、多岐に渡りました。明治初年から22年までの統計によれば、当時日本を訪れた「お雇い外国人」の総数は、2,299名、国籍別では、最多がイギリスの928名となっています。イギリスに次いでは、アメリカ、フランス、中国、ドイツの順になっています。分野別に見ますと、工部省関係が749名と最多であり、なかでも都市のインフラ整備に関連する事業の関係者が、目立ちました。鉄道、船舶、工作機械、電信、灯台などの設計、建設など、各地で引く手あまたの状態が続きました。こうした「お雇い外国人」たちは、知的好奇心が強く、飲み込みの早く、その上礼儀正しい日本人に好感を抱き、自らの技術や知的ノウハウを、惜しげもなく伝授したのです。 続く
2011.07.13
コメント(4)
-
母子手帳使用始まる 13日の日記
クロニクル 母子手帳使用始まる1942(昭和17)年7月13日この日、厚生省(現厚生労働省)は妊産婦手帳規定を実施に移しました。これが現在の母子健康手帳の原型ですから、母子健康手帳の利用開始は、戦時中のこの日だったことになります。私の生まれる3ヶ月少し前のことです。この政策は、まさに「生めよ増やせよ」政策の一環として、人口の増加を図るために、妊産婦に栄養食を優先的に配布するため、そして出産用品を確実に配給することを狙いとして、立案されたそうです。まだ、物不足が目立つ時期ではないのですが、将来における物不足を、厚生省が読んでいたとすると、そう読んだ人物は、端倪すべからざる慧眼の持ち主ですね。
2011.07.13
コメント(6)
全83件 (83件中 1-50件目)
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 福袋2026🔹MLB ロサンゼルス・ドジャ…
- (2025-11-16 19:23:16)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 639.開いてごらんよ その眼を 視えな…
- (2025-11-17 00:00:15)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「イマドキではない」19歳女優 ビキ…
- (2025-11-17 00:30:05)
-