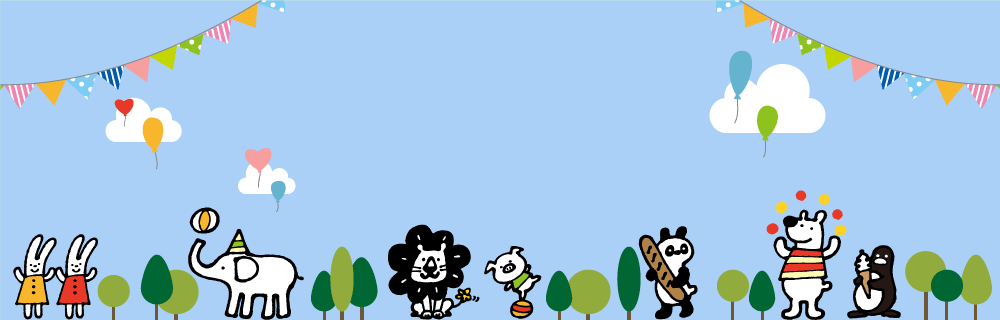2019年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
改正大店法施行 31日の日記
クロニクル 改正大店法施行1992(平成4)年1月31日27年前のことです。大規模小売り店舗法の改正法が、この日施行されました。旧来の法は、小売店保護の名目で、出店には既存の商店街の同意を採り付けることを義務付けておりました。そのため、延べ床面積、営業時間、営業日数(年間の休日日数など)の枠をはめられる為、大手スーパーなどが出店を断念するケースも少なくないなど、大型店の出店が厳しく制限されていたのですが、この改正によって規制が緩和され、スーパーや大規模小売り店の出店競争が激化することになりました。 とりわけ、駅前の繁華街などでは、駐車スペースの確保が難しく、車で来店するなら駅前よりも、交通渋滞が少なく、駐車スペースも広くとることが可能な、郊外型店舗が各地に誕生し、駅前商店街の顧客が激減することにもなりました。 小規模店なら小規模店のメリットを生かした、独自の販売・集客戦略を練ることもなく、駅前という立地に安住し、規制に守られてぬくぬくとしていた古くからの商店街は、この結果大きな打撃を受けました。 大型店との共存の道を探らず、出店を防げれば良い式の、厳し過ぎる制限を出店希望の大型店に課して、郊外に追い遣った咎めが出た報いのように見えました。大型店イジメの結果が、郊外型店舗にお客を吸い取られる結果を招いたと言えましょう。 そこで、今度は性懲りもなく、大型店の郊外立地を制限してもらい、駅前に大型店を誘致出きるように、大型店の郊外出店を規制してもらおうというのが、最近の動きなのですから、あきれます。 護送船団(最もスピードの遅い船に合わせてスピードを調整し、船団として行動、進行する方式です)方式と呼ばれるのですが、早い船は足踏みよろしくスピードを落とし、遅い船に合わせて進むのです。ここに進歩が生まれると期待する方がどうかしています。 かつて、デパートの誕生期(西欧で1870~80年代、日本では20世紀20年代でしょうか)に、時代の波を理解できない、古くからの商法にアグラをかいていた商店は、いくつも淘汰され、時代の波に飲み込まれてゆきました。 同じ運命を辿るか、再生を果せるかは、他力本願よろしく、再び規制の力を借りようとするのではなく、歯を食いしばって新しい成長の道を見つけ出そうと、商店街が知恵を絞ってチャレンジしていくか否かに、かかっているように思うのです。こう考えるのは、わたしだけでしょうか。
2019.01.31
コメント(8)
-
南ヴェトナムでテト攻勢 30日の日記
クロニクル 南ヴェトナムでテト攻勢1968(昭和43)年1月30日ヴェトナム戦争の最盛期の話です。ついこの間のような気がしてならないのは、年齢のせいでしょうか、もう51年も前になるのですね。この日はヴェトナムの旧正月(テトと呼ばれます)でした。この日を期して、南ヴェトナム解放民族戦線と北ヴェトナムの連合軍が、南ヴェトナム中部の諸都市に、同時多発的な一斉攻撃を仕掛けました。準備万端を整えた上での一斉攻撃に、南ヴェトナム政府軍は一溜りもなく、米軍もまた守勢に回らざるを得なくなりました。 翌日には、攻撃は首都サイゴン(現在ホーチミン市)市内と、古都フエにおよび、一時はアメリカ大使館を占拠する勢いを示しました。急遽米海兵隊などが増派され、大使館の奪回には成功しましたが、解放戦線軍と北ヴェトナム軍の精強さと、組織的訓練の行き届いた様子は、世界に衝撃を与え、世界世論も圧倒的な南ヴェトナム支持に傾いたのでした。
2019.01.30
コメント(7)
-
アラビア石油 29日の日記
クロニクル アラビア石油1960(昭和35)年1月29日 丁度、安保改訂反対闘争の年のはじめでした。59年前のこの日、アラビア石油がクウェート沖のカフジ油田を掘り当てました。それは、日本企業による、初めての海外での油田開発の試掘成功でした。カフジ一帯は、サウジとクウェートの中立地帯です。そしてカフジ油田は、カフジ沖合い(ペルシャ湾の一廓です)の海底油田です。アラビア石油は、ここで40年間創業して、石油を採掘する権利を得たのですが、その権利は40年後の2000年に失効してしまい、現在はサウジ・アラムコの関連会社が、石油の採掘を担当しています。それでも40年間の採掘の間に、二度の石油ショックがあって、原油の値段が大きく居所を変えましたから、アラビア石油、随分と儲けることが出来たようです。
2019.01.29
コメント(9)
-
春闘始まる 28日の日記
クロニクル 春闘始まる1955(昭和30)年1月28日 春闘が形骸化してかなり時間が経ちますが、春闘の語は今に残り、「三丁目の夕日」とは違った意味で、郷愁を感じる方も多いと思います。 本日は、その春闘の始まりの話です。64年前のことです。GHQの戦後改革の1つに労働組合の結成の自由、労働者の団結権の承認などがありました。この観点から労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法も作成され、労働者は団結権のほかにも、団体交渉権、争議権を獲得していました。 労働者のナショナルセンターも組織され、1時期「総評」が大きな力を持ちました。その総評に属する、炭労、私鉄総連、電機労連など6単産が、この日「春季賃上げ共闘会議総決起大会」を開いたのです。この春季賃上げ闘争を略して春闘と呼ぶようになったのです。しかし最近の労組、すっかり元気がないですね。賃上げについて、首相が経済団体に要請するなんて、本末転倒もいいところです。
2019.01.28
コメント(6)
-
ヴェトナム和平パリ協定調印 27日の日記
クロニクル ヴェトナム和平パリ協定調印1973(昭和48)年1月27日46年前のことです。この日、南北ヴェトナム政府・南ヴェトナム臨時革命政府の3外相とアメリカ国務長官の4者によって、ヴェトナム戦争の終結と、平和の回復に関する和平協定が正式に結ばれました。この協定の最大のポイントは、「調印から60日以内に米軍がヴェトナムから撤退する」と定めた一項にありました。ヴェトナム戦争は、仏領インドシナ(ヴェトナム・ラオス・カンボジャ)の独立を目指す民族解放戦争に際し、植民地の維持を狙った宗主国フランスが、ホー・チ・ミンを指導者とするヴェトミン軍との戦いに敗れ、三国の独立を認めて撤退した後に、ヴェトミン軍と仏軍の引き離しのために、2年間の暫定的な軍事境界線と定められた北緯17度線の南側(ここが南ヴェトナムと称されたのです。北側が北ヴェトナムとされました)に、フランスに替わってアメリカが進出、アメリカの傀儡政府を作って、南部ヴェトナムの引渡しを拒否したことが遠因となって始まった戦争です。 1956年の引渡し拒否から3年、59年から組織化が始まった南ヴェトナム解放民族戦線の活動は、年を追って活発となり、62年に入ると、もう米軍の支援なしには、南の傀儡政府は生き延びることが不可能な状態になりました。米国は軍事顧問団という名目で米軍を投入、辛うじて反共親米の南ヴェトナム政府を支えている状態に陥ったのです。ここに米国は自ら作った不人気な傀儡政府に見切りをつけ、次々にクーデタを実行させては、何度も政権の交代を図りました。しかしいずれもうまくゆかず、遂にはトンキン湾事件として知られる、北ヴェトナム魚雷艇による米海軍艦船への魚雷攻撃という、偽の事件をでっち上げて(この事実は、数年後アメリカのマスコミの手で、米軍による捏造、自作自演であったことが明かにされました)議会の賛成を取りつけ、北ヴェトンムへの北爆と、南ヴェトナムへの海兵隊の投入という、本格的な軍事介入に踏み切ったのでした。 こうしてヴェトナム戦争は、アメリカの戦争に変質を遂げました。宣戦布告なき本格戦争が始まったのです。しかし、ジャングルに潜った解放戦線とのゲリラ戦は、文明化された生活に慣れた米軍兵士には無理でした。ジャングルで電気をつけ、大きな音で音楽を流していては、ゲリラの恰好の餌食になってしまいます。しかし、死の恐怖と戦いながら夜の闇にじっと潜んでいることは、文明生活に慣れた米兵には耐え難いことでした。兵士はマリファナに活路を見出すしかなかったのです。いつしか慢性化したマリファナの吸引は、運良く米国へ帰還した兵たちによって、米国内にガン細胞よろしく、広まってしまいます。その間、米軍の大量投入にも関わらず、軍事情勢は悪化の一途を辿ります。こうして万策尽きた米国は、和平協定という形を整えて、自ら介入した戦争に、自ら幕を引くしかなくなってしまったのです。かくしてパリ和平協定は、事実上米国の敗北宣言だったのです。
2019.01.27
コメント(5)
-
初の疎開命令下る 26日の日記
クロニクル 初の疎開命令下る1944(昭和19)年1月26日75年前のこの日、内務省は、改正防空法に基づく初の疎開命令を、東京と名古屋に対して発動しました。この命令に基づき指定地域内の建造物の強制取り壊しも行われましたが、そうした行為も空しく、その後も日本の防空能力の欠如を見透かして、激しさを増す一方だった米軍の空爆によって、東京、名古屋、大阪、神戸といった大都市は、徹底した空襲によって焼け野原となり、多くの市民が焼き殺されるという、大虐殺の憂き目を見たのでした。
2019.01.26
コメント(8)
-
陸軍大将宇垣一成に組閣の大命下る 25日の日記
クロニクル 陸軍大将宇垣一成に組閣の大命下る1937(昭和12)年1月25日 82年前のことです。前年の2.26事件後、軍部の政治介入は強まり、とりわけ前年5月18日に公布された、陸・海相の現役武官制(陸軍大臣と海軍大臣は、現役の大将・中将から出すとの決まり)の復活により、軍部は意に染まない内閣には、大臣を送ることを拒否することで、その存在を否定することが出来る強大な権限を手に入れました。いよいよ軍部独裁の環境が整ってきたのです。 実際、2.26事件後に組閣した広田内閣は、実質的に陸軍の意向を最大限に尊重することで、辛うじて命脈を保っていたのです。そこへこの日の4日前に、衆議院において政友会議員による痛烈な軍部批判と、それに対する寺内陸相の反駁とで議場が大混乱に陥る事件が起きたのです。衆議院の即時解散を主張して辞任をちらつかせる寺内陸相を説得できなかった広田内閣は、23日に総辞職するに至りました。そして、この日陸軍大将の宇垣一成に組閣の大命が下ったのですが、宇垣が陸軍内反主流派であったことから、軍部は組閣に反対し、後任陸相を出すことを拒否したのです。そのため、後任の陸相候補は次々に入閣を拒否、万策尽きた宇垣は、遂に29日、組閣を断念するに至るのです。軍部の横暴が、遂に首相人事にまで及んだことを示す、一幕でした。日中・日米戦争の敗北に至るストーリーは、この辺りから、いや、もう少し前から始まっていたように、思えてなりません。
2019.01.25
コメント(8)
-
元日本兵横井庄一さん発見 24日の日記
クロニクル 元日本兵横井庄一さん発見1972(昭和47)年1月24日 47年前のこの日、グァム島のジャングルで、元日本軍軍曹横井庄一さんが保護されました。横井さんは,この日川エビを獲っているところを現地の人に見つかり、保護されたのです。1945年8月15日のポツダム宣言の受諾による、敗戦の受け入れ(なぜマスコミは、この降伏による敗戦を終戦と言い替えるのでしょうね?)を知らず、1人ジャングルで27年も生き延びてきた横井さんは、この時56歳でした。グァム島のジャングルで、果実やイモ類、魚や川エビ等を食べ、マンゴーの葉から衣服を作るなどして自給自足生活を送っていたそうです。健康チェック後、2月2日に帰国。帰国時の第一声「恥ずかしながら、横井庄一,ただ今帰って参りました」でした。この「恥ずかしながら......」はこの年の流行語となり、以後、郷里の名古屋に落ちつき、サバイバル体験を生かした講演活動を行なって、各地で人気を集めました。1997年82歳で死去。
2019.01.24
コメント(11)
-
NHK初の国会中継 23日の日記
クロニクル NHK初の国会中継1952(昭和27)年1月23日67年前ですから、勿論テレビなどはありませんし、存在を知る人っていたのかなぁ?という時代の話です。この日、NHKがラジオ第一放送で、史上初めて衆議院本会議の模様を実況中継しました。今の退屈な国会論戦は、見る人なんているんだろうか?って感じになりますが、この時代は珍しさもあって、結構人気になったようです。 麻生財務相の祖父、吉田ワンマンの時代でした。
2019.01.23
コメント(12)
-
イギリス労働党政権獲得 22日の日記
クロニクル イギリス労働党政権獲得1924(大正13)年1月22日95年前のことです。この日、イギリスでは、イギリス労働党のマクドナルドを首班とする、初めての労働党内閣が誕生しました。この時は1年足らずの短命に終ったのですが、この経験をしっかり生かして、1929年から35年まで6年半の長期政権を見事に実現し、保守党との二大政党時代を気づき上げました。日本の民主党、イギリスの政治史や政治思想は学んでいたのでしょうが、せっかくの生きた教材を生かせなかったのですね。
2019.01.22
コメント(6)
-
ロンドン海軍軍縮会議 21日の日記
クロニクル ロンドン海軍軍縮会議開催1930(昭和5)年1月21日89年前のこの日、ロンドンで米・英・日・仏・伊5ヶ国が参加して海軍の軍縮会議が幕を上げ、数か月の激論の末、以下のような条約がまとまりました。 1、主力艦の建造停止を5年間延長する2、主力艦の保有率を英米の15に対し日本は9とする3、米・英・日3国で補助艦協定を結び、日本は総量で米国の69,7%とする。潜水艦保有は、各国同じとする。この条約に対し、軍部・右翼は強く反対しましたが、浜口内閣は国民の支持を背景に、反対論を抑えて調印にこぎつけました。当時、日露戦争に際して発行した外債(25年債)の借り換え期限が迫っていたことから、米英と良好な関係を保つ必要性を強調することで、国防費の削減を含む緊縮予算を組むことの必要性を訴えた作戦が、功を奏したのです。
2019.01.21
コメント(8)
-
大和運輸「宅急便」サービスを開始 20日の日記
クロニクル 大和運輸「宅急便」サービスを開始1976(昭和51)年1月20日43年前になるのですね。この日、大和運輸(現在はヤマト運輸)が「宅急便」サービスを開始しました。クロネコヤマトの宅急便の誕生です。 大和運輸は、三越や松下電産の専属配送業者でした。上得意を持っていたため、他社が高速道路網の整備を追い風に長距離輸送に進出した際に出遅れ、業績不振に陥りました。このままではまずいと気付いた新社長の小倉昌男氏は、個人を相手に、小口貨物を沢山扱うことで、利益を得ようと大口中心の発想を転換、「電話1本で集荷に伺う・1個でも家庭へ集荷に出向く・翌日配達」を合言葉に、営業を展開。大成功を納めたのです。 今では、誰でも知っている宅急便ですが、サービス開始の初日、39年前の1月20日の集荷数は、11個だったそうです。良くここまで伸びましたね。
2019.01.20
コメント(11)
-
インディラ・ガンディー首相誕生 19日の日記
クロニクル インディラ・ガンディー首相誕生1966(昭和41)年1月19日インディラ・ガンディーは、独立インドの初代首相、ジャワ・ハルラル・ネルーの娘です。ネルー首相は、日本の平和憲法を高く評価し、日本が非同盟主義をとることを望んでいました。それは適わぬ夢に終ったのですが、日本の子ども達の像を見たいという希望を受け入れ、日・印平和条約の締結後に、上野動物園に、アジア像というビッグなプレゼントを贈ってくれました。このアジア像はネルー首相の最愛の令嬢の名をとり、「インディラ」と名付けられたことは、ご存知の方も多いと思います。さて、1964年5月末、東京五輪の4ヶ月半前、ネルー首相は急死します。後任首相も2年後に急死し、ここにインド国民会議派は、ネルーの血を引くインディラ・ガンディーを首相に推したのです。こうして、53年前の今日、インディラ・ガンディー女史は、第3代のインド首相の座に就いたのです。ネルーの著書、邦訳名『父が子に語る世界歴史』(みすず書房刊 全6巻)は、ネルーが獄中から、当時10代の娘インディラに、世界の歴史を語ったものです。
2019.01.19
コメント(7)
-
ドイツ帝国誕生 18日の日記
クロニクル ドイツ帝国誕生1871(明治4)年1月18日148年前のことになります。日本ではこの年廃藩置県が断行されています。そんな年のことでした。前年の晩夏に始まった普仏戦争(プロイセン<普>とフランス<仏>の戦争)に勝利したプロイセン宰相ビスマルクは、この日占領中のヴェルサイユ宮殿鏡の間にて、プロイセン王ウィルヘルム1世の、ドイツ皇帝への戴冠式を行い、併せてドイツ帝国の誕生を宣言しました。 明治維新に遅れること3年、ここにようやく統一ドイツが誕生し、1861年登場の統一イタリア、68年に誕生した日本の明治政府と合わせ、後の第二次世界大戦でトリオを組む3カ国が、後進資本主義国としての歩みを、ほぼ同じ時期に始めることになりました。
2019.01.18
コメント(8)
-
民撰議院設立建白書 17日の日記
クロニクル 民撰議院設立建白書1874(明治7)年1月17日1912年は、明治45年兼大正元年ですから、考えてみれば当然なのですが、思えば私の中学・高校時代は、1955年4月~61年3月まででしたから、その100年前は黒船登場以後の幕末の混乱期でした。「明治は遠くなりにけり」ですね。 今日取り上げた「民撰議院設立建白書」の提出、今年からすると145年も前の話になります。そうなんです。かつての100円札の主、板垣退助(彼の「板垣死すとも自由は死せず」って言葉に、この人は紙幣の顔になる価値のある人だと、思ったものです)や後藤象二郎、江藤新平ら8名が、連名で政府に国会開設を願う意見書を、提出したのです。 彼らの主張の根拠は、当時「天賦人権説」と呼ばれていたルソーの社会契約説にありました。その具体的な内容は、専制政府を批判して、天皇と臣民一体(君民一体)の政体を作ることを主張したもので、士族や豪農・豪商ら一定の教育を受けた平民に参政権を与え、議会を開設することを主張したものでした。 政府は時期尚早と回答したのですが、この建白書に賛同する意見書が、多数提出され、自由民権運動の活発化に繋がってゆきました。
2019.01.17
コメント(8)
-
パーレビ国王亡命 16日の日記
クロニクル パーレビ国王亡命1979(昭和54)年1月16日40年前の話です。1978年秋以降、革命情勢が日増しに強まりつつあったイランで、この日遂にパーレビ国王が亡命を決断、エジプトに出国しました(後病気治療名目で、米国が亡命を受け入れました)。ここにイランの王政は崩壊し、イラン・イスラム革命は勝利に向けて大きく前進しました。2月1日には、革命派の精神的支柱だったホメイニ師が、亡命先のパリから15年振りに帰国、国民各層の熱狂的歓迎を受けました。2月11日には、革命派による勝利宣言が行われ、ここにイラン革命は成就しました。
2019.01.16
コメント(9)
-
UFJ銀行誕生へ 15日の日記
クロニクル UFJ銀行誕生へ2002(平成14)年1月15日17年前の今日、三和銀行と東海銀行が合併して、UFJ銀行が誕生しました。90年代のバブル崩壊を受け、金融機関の自己資本が痛み、大手銀行の合併を含む合従連衡が盛んに行われるようになり、さくら銀行(前身は太陽神戸三井銀行)と住友銀行が合併した三井住友銀行、富士・第一勧銀・興銀が合併したみずほ銀行、そしてUFJ銀行と東京三菱銀行が、4大メガバンクと言われましたが、やがて、UFJは東京三菱との合併を選び、現在は三菱東京UFJ銀行となっています。
2019.01.15
コメント(9)
-
文学座分裂 14日の日記
クロニクル 文学座分裂1963(昭和38)年1月14日 文学座は、1937(昭和12)年に岸田國士、久保田万太郎、岩田豊雄の3名を発起人として設立された、日本新劇界の名門劇団です。俳優座や民芸と共に三大新劇団とも称されます。その文学座で56年前のこの日、芥川比呂志を筆頭に、同座の中堅・若手劇団員29名が劇団に退団届を提出し、英文学者の福田恆存と共に劇団「雲」を設立、脱退者全員が参加することを表明しました。この集団脱退は、日本の演劇界始まって以来の大事件として、マスコミの注目を集め、その後に脱退劇を巡る、様々な報道がなされました。ただし、テレビや夕刊紙の普及以前のことですから、週刊新潮などの報道も、決してセンセーショナルなものではなかったのですが…。 報道によると、脱退劇は、全て隠密裏に進められ、文学座幹部の中村伸郎や杉村春子らは、当日になるまでこの集団脱退に、全く気付かなかったそうです。この集団脱退の背景には、ベテランと中堅・若手陣とのズレがあり、彼らに大きな不満が蓄積していたことがあったようです。 脱退した29名の中には、芥川比呂志、高橋昌也、加藤和夫、仲谷昇、小池朝雄、名古屋章、神山繁、三谷昇、岸田今日子、文野朋子、加藤治子ら、その後も演劇やテレビ、映画などで活躍した人たちが含まれていました。また文学座は、この集団脱退のあった同年の11月に、正月公演に決まっていた三島由紀夫の戯曲 『喜びの琴』の上演を、思想上の行き違いを理由に中止しました。このことをきっかけに、同劇団の幹部・中堅の矢代静一、松浦竹夫、中村伸郎、北見治一、賀原夏子、丹阿弥谷津子、南美江、村松英子ら14名が、再度同劇団を集団で脱退するという事件に見舞われています。
2019.01.14
コメント(9)
-
共通一次試験始まる 13日の日記
クロニクル 共通一次試験始まる1979(昭和54)年1月13日40年前になります。この日と翌14日の2日間に渡って、第1回目の共通一次試験(現在のセンター入試の前身)が全国で実施されました。出願者341,874人、実際の受験者327,163人にのぼるマンモス受験でした。受験生は各試験場で一斉にHBの鉛筆を持ち、マークシート方式の試験に挑みました。 この共通一次試験は、過熱する一方の受験競争に巻き込まれた高校教育の正常化をめざすとう意気込みで、鳴り物入りで準備されたのですが、予備校や受験業者が、自己の存在の生き残りをかけて、受験生の自己採点結果をコンピューターで集計、分析して独自に合否を事前推定するなどして、2次試験の出願に影響力を及ぼすことを防げなかったため、高校や大学のランク付け、大学間、高校間の格差はかえって激しくなるという結果を生んだのでした。その上、受験科目が増えたために、受験生の負担は以前にも増して厳しくなり、偏差値重視の弊害もまた改善されるどころか、以前に増して激しくなり、過熱する一方の受験地獄の弊害は益々強まる結果となったのでした。その結果、考え、理解し、自分の脳の引出しにしっかりしまい込むために、考えるヒントとして脳に染み込ませるのではなく、とりあえず詰込んでおく式の、ハウツー的な暗記教育全盛の時代が訪れます。袋に詰込み過ぎれば破裂しますから、破裂を避けるには、先に詰込んだものを、袋の反対側から逃していかなければなりません。一夜漬で詰込んだことは、試験が終ればほとんど忘れてしまっているのが良い例です。覚えていたのでは、翌日の試験科目を覚える隙間がないのですから…。こんな経験が皆さんにもあると思います。 ここに共通一次試験施行後の受験競争の過熱、詰込み教育の全盛の中で、自ら学ぶ姿勢を身に付けるチャンスを失った気の毒な若者達の多くは、能動的な思考訓練の欠如から、常に受け身で教えられることを待つだけの、受動的な姿勢ばかりが目立つ若者になってゆきました。大学世界で「目の光る、活きの良い学生が少なくなった」といったような嘆き節が聞かれるようになるのは、共通一次試験導入の4~5年後のことでした。この考える力の喪失傾向に歯止めをかけないと、将来大変なことになるという思いもあって、導入されたのが、反詰め込み教育ともいうべき、「ゆとりの教育」だったのですが、教育現場の消化不良もあって、十分な実践期間もとらずに、再び1度破綻した詰込み教育に戻そうとする、現在の政府及び教育再生会議の方向は、益々マイナスの方向に進んでいくように思えてなりません。考える力、そして感じとる力、論理的に思考し、豊かに想像をめぐらせる時、何故と発問して、自ら考え解決する能力が獲得でき、かつ他者の傷みをわが事として甘受しうる想像力も身につきます。現在養うべきは詰込む能力ではなく、この思考力と想像力であるはずですから……。
2019.01.13
コメント(6)
-
不良債権は76兆円 12日の日記
クロニクル 不良債権は76兆円1998(平成10)年1月12日あれから21年も経ったのですね。21年前のこの日、当時の大蔵省は全国146の銀行が、自己査定の結果として報告してきた、97年9月末現在の不良債権総額は76兆円で、貸し出し総額の12.6%に当たると発表しました。しかし、この数字は、あくまでも銀行自身の自己査定の結果に過ぎず、銀行の実態を表すには、極めて不十分なものでした。実際、この年6月に大蔵省から分離独立する金融庁が、その後に監査を実施した結果、不良債権への分類の変更を迫った債権が、次々に明るみに出てきたことは、ご存知の通りです。各行が正常債権に分類していた債権の中に、実際には不良債権に分類すべきだった債権が、数多く隠されていたのです。この自己査定は、前年の拓銀や山一証券の破綻を受けて、実施されたものだったですが、この年秋には日本長期信用銀行が、暮には日本債権信用銀行が、破綻認定を受けて一時国有化されることになった事実も、ご存知の通りです。どこまで続くぬかるみぞ!といったところでしょうか。先送りを重ねに重ねてきたのですが、遂に万策尽きて……厚化粧の裏の素顔が透けて見えた一瞬だったと言えましょう。
2019.01.12
コメント(6)
-
「期待される人間像」とは? 11日の日記
クロニクル 「期待される人間像」中間草案発表 1965(昭和40)年1月11日54年前のことです。文部大臣の諮問機関,中央教育審議会(会長森戸辰男)は、この日「期待される人間像」についての中間草案を発表しました。1963(昭和38)年6月、荒木文相(当時)が、「戦後出来た無国籍の教育基本法に筋金を通したい」と,大変物騒な動機を語って物議をかもした末に、諮問を受けた中央教育審議会(以下中教審)は、古色蒼然たる委員構成の下で、それでも紆余曲折の議論を続けた末に、この日中間草案を発表しました。 そこでは、わが国の次代を担う青年が今後どうあるべきかについて、「たくましい日本人」「正しく日 本を愛する人」であることを求め、 1、技術革新の時代に相応しい能力の開発 2、日本の使命を自覚した真の日本人 3、自我を自覚した健全な民主主義を などと提唱しました。 この日、私は西洋史に関する卒業論文を提出して、研究室でゼミ仲間と談笑中にこのニュースに接し、「それでは平和憲法の精神を世界に発信する、平和の使徒を大いに増やす事にするのが一番だな。連中 さぞ困るだろうな」とシニカルに笑い合ったことを覚えています。 この草案及び12月の答申はともに、全体として抽象的なのですが、極めて保守色が強く、その後も折り に触れて蒸し返されてきました。その結果が2006(平成18)年の教育基本法の改悪に繋がりました。 きれい事を並べるだけで具体的でない安倍首相の言行と、いかに良く似ているかに注目していただく と、安倍氏の古さも良くわかるのではないでしょうか。如何ですか。 形容詞は内容を明確にするためには不要なケースが多く、政治家がこれを使う場合、内容の乏しさを誤 魔化すために使われるケースが多い事に、留意する必要があります。 正しくとは何を指すのか、愛するとは何なのか、極めて主観的で受け手によって解釈は多様に分かれて しまいます。各方面から様々な批判が寄せられたのは当然でした。 一例として、1960年の安保条約の改定審議の際に、十分な質疑と誠実な回答もせずに、反対する野党を 国会に警察官を導入して、力づくで排除したうえで、単独で強行採決した政党の態度が、健全な民主主 義なのか(当時「民主主義を守れ」のスローガンが、どれだけ安保反対運動を強化したか、計り知れな いほどでした)という批判が、朝日や毎日の投書欄に、毎日のように載せられたことを記しておきましょう。 12月の政府発表でも、答申への賛成は30%弱に留まっていました。
2019.01.11
コメント(6)
-
徴兵令施行 10日の日記
クロニクル 徴兵令施行1873(明治6)年1月10日146年前のことです。この日明治政府は徴兵令を施行しました。前年12月28日に「徴兵告諭」が出されてから、僅か2週間後のことでした。 徴兵令では国民皆兵の原則が貫かれ、旧支配層である士族中心の志願兵制の主張は避けられました。欧米列強の兵制に倣った軍の整備こそが、列強による日本の植民地化を防ぐ道に繋がると考えられたのです。 同時に士族中心の志願兵制の主張者(=保守派)への配慮として、薩摩・長州・土佐の3藩の士族から、天皇の身辺警護にあたる御親兵が選抜されました。 徴兵令の結果、数え年20歳の男子は、3年間兵役に着くことが定められたのですが、当初は多くの例外規定が設けられていました。即ち、体格が基準に達しない者、病気の者など、当然と思われる事情から、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「代人料(270円)を支払った者」、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」なども、徴兵を免除されました。
2019.01.10
コメント(7)
-
自殺の名所三原山 9日の日記
クロニクル 自殺の名所三原山1933(昭和8)年1月9日86年前になります。この日伊豆大島の三原山の火口から、2名の女学生が友人の立会いを受けて、投身自殺しました。 友達の自殺を止めない友人って何なんだと、私などは大いに不満なのですが、この自称友人たちは、友達の自殺の報を、警察のみでなく新聞社などにも語ったのでしょうね。この事件がきっかけで、以後三原山は自殺の名所となってしまい、この年だけでなんと994名もの投身自殺者が出る騒ぎとなりました。 大島の人たちからすると、迷惑この上ない話でした。
2019.01.09
コメント(7)
-
ベルが鳴るベルが鳴る… 8日の日記
クロニクル ベルが鳴るベルが鳴る…1912(明治45)年1月8日107年前になります。エッ、「何のことか分らん」ですか。ですからベルなんです。列車の出発を告げる、あのベルのことです。流行歌(この言い方も古くなりましたね)に良く出てくる別れの場面の歌詞にありますよね。あの列車の出発を告げるベルの第1号が、107年前のこの日、あの「上野はおいらの心の駅だ…」でお馴染の上野駅で、日本で始めて鳴り響いたのです。で、発車のベルというと、私にとってはこの曲なんです。春日八郎のデビュー曲「赤いランプの終列車」です。白状しますと「ベルが鳴る ベルが鳴る」は、ここから盗りました。 > 白い夜霧の 灯りに濡れて 別れせつない プラットホーム ベルが鳴る ベルが鳴る さらばと告げて 手を振る君は 赤いランプの終列車 <尤も最近はベルではなく、おしゃれなチャイムになりましたから、若い方にはわからないかもしれませんね。メロンさんやアミさんは知らないかもしれませんね。
2019.01.08
コメント(9)
-
民放各社深夜放送を中止 7日の日記
クロニクル 民放各社深夜放送を中止1974(昭和49)年1月7日45年前のことです。この年、石油ショックの影響から、電力節減が強く要請され、ビルのネオンやライトアップの自粛に続いて、この日、民放TV各社が一斉に深夜放送の中止に踏みきりました。16日には、NHKも午後11時での放送中止に踏み切り、TV各局の足並みが揃いました。許認可権を握る郵政省(当時)の要請によるものでした。しかし、この後も原油不足は解消せず、夏には、銀行・証券などの金融機関やデパート・スーパー・病院などの冷房の設定温度を28度とするなど、石油火力が中心だった電力消費の削減策が進められました。 経済団体の協力を得て、オフィスビルでも室温の28度の設定は徹底されたのが、いかにも日本らしい風景でした。 当時はなお、家庭のエアコンは普及にいたっておらず、そのため、28度の設定にも大きな不満は出なかったように記憶しています。
2019.01.07
コメント(5)
-
高見山入幕 6日の日記
クロニクル 高見山入幕1968(昭和43)1月6日51年前になるのですね。この日発表された大相撲初場所の新番付で、高見山が新入幕を果たし、外国人力士として、初めて幕内に入りました。 元横綱前田山の高砂親方に熱心にくどかれ、1964年にハワイから高砂部屋に入門、4年足らずで入幕を果たしました。入幕2場所目、横綱佐田の山に勝利したのですが、佐田の山はこの高見山との一番に破れたことで、引退を決意したと引退会見で語っています。 幕内最高位は関脇、1972年の名古屋場所で13勝2敗で幕内優勝を飾っています。引退は1984年の5月場所後、16年97場所の幕内在位は、当時の最長記録でした。大関の魁皇が2009年九州場所で98場所となって、25年振りに高見山の記録を更新しました。 高見山は、日本人以上に日本人的な義理と人情を大事にする人柄や、ケイコに打ち込む姿などから、世代を超えて幅ひろい人たちに愛され、丸八真綿など数多くのCMにも出演していました。 今や大相撲は、外国人力士で持っているのが実情ですが、その先鞭をつけたのが、高見山の活躍でした。そして彼をスカウトした、当時の高砂親方の慧眼が光りますね。
2019.01.06
コメント(8)
-
「プラハの春」はじまる 5日の日記
クロニクル 「プラハの春」はじまる1968(昭和43)年1月5日51年前になりますね。「プラハの春」我々世代には懐かしい言葉です。この「プラハの春」を主導した中心人物が、チェコスロヴァキア共産党のドプチェク第一書記でした。この日1月5日は、この日開かれたチェコスロヴァキア共産党中央委員会総会において、スロヴァキア共産党第一書記だったアレクサンデル・ドゥプチェクがノヴォトニーに代わって、チェコスロヴァキア共産党第一書記に就任した日なのです。 彼は、「人間の顔をした社会主義」を合言葉に、情報公開の徹底、自由な発言の奨励など、17年後にソ蓮共産党のゴルバチョフ書記長が推進したペレストロイカに近い政策をとったのです。ドプチェクの存在とチェコの新方針が、広く世界に知れ渡るのは4月頃でしたが、「プラハの春」と称されたチェコスロヴァキアの試みが、始まったルーツを辿ると、51年前の今日に至るのです。この「プラハの春」は、東欧社会主義の事実上の監督者であるソ連共産党の眼からすると、危険なものに写り、やがて8月20日からのワルシャワ条約機構軍の軍事介入によって踏み潰されて行きました。 ワルシャワ条約機構軍の中核は、言うまでもなくソ連軍でした。ソ連軍介入の畏れは、6月はじめ頃から意識されており、6月27日に発表された有名な2千語宣言は、社会主義における自由な言論と複数政党制の必要を訴えた文章として、知られています。この宣言はまた、4年前の東京オリンピック女子体操で大活躍し、チェコの名花と歌われたチャスラフスカさんや、1956年のヘルシンキ五輪で、5,000m、10,000m,マラソンの長距離3種目の全てで優勝し、人間機関車の名をほしいままにしたザトペックさんが、署名者に名を連ねていたことで、大変な注目を集めたのでした。
2019.01.05
コメント(9)
-
軍人勅諭発布 4日の日記
クロニクル 軍人勅諭発布1882(明治15)年1月4日137年前のことです。この日「軍人勅諭」が発布されました。 「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」で始まる、全編天皇が直接軍人たちに語りかける調子で貫かれた、天皇による訓示の体裁をとっていました。 軍人は、日々この軍人勅諭を暗唱し、唱えることで、次第に勅喩の精神が軍人の心を支配するようになっていきました。教育勅語(明治23年制定)で子どもの心を支配し、さらに勅諭で念を押したといえましょう。マインドコントロールの古典と いえましょう。
2019.01.04
コメント(4)
-
日米繊維協定締結 3日の日記
クロニクル 日米繊維協定締結 1972(昭和47)1月3日47年前になります。この年の前年にあたる1971年8月15日が有名なニクソンショック。米国が金・ドル交換停止を発表し、1ドル=360円体制が崩れるきっかけになった日でした。そして年末にスミソニアン協定が結ばれ、1ドル=308円になったように、ドルに対して各国通貨が切り上げられて、一応の小休止となりました。こうした国際経済上の大問題の根底にあったのが、米国の貿易収支の大幅赤字でした。当時米国の最大の貿易赤字国は日本でしたから、日本の安値輸出が、米国へ失業を輸出していると批判されたのです。特に米国の繊維業界が死活的な打撃を受けていたことから、日本の繊維製品の輸出が、槍玉に上げられました。これがその後、様々な分野に波及した,日米貿易摩擦の第一段でした。日本の繊維業界も、地場の中小企業が多い業界です。円切り上げの際にも、地元選出の代議士を超党派的に突上げ、猛烈な陳情攻勢をかけました。この時も大変な騒ぎとなって、ロングラン交渉となったのですが、47年前のこの日、遂にワシントンでの交渉が妥結したのです。 繊維製品の対米輸出の、年間伸び率を一定以下に抑える内容でしたから、現状維持ないし、現状より削減を主張していた米側も、大きく譲歩した内容になっていましたので、秋に大統領選挙を控える時だっただけに、米側もかなり思いきった譲歩で、交渉をまとめたと見ることができました。それでも国内の繊維業界や、業界拠りの族議員達は、5月に沖縄返還を受けることになっていたことから、「政府は糸で縄(沖縄のこと)を買った」と、政府批判を繰り返しました。 今では、米国業界の非難の矛先は、すっかり中国に移っていますね。
2019.01.03
コメント(7)
-
ボーナス事始 2日の日記
クロニクル ボーナス事始1876(明治9)年1月2日ボーナスの期限というのは、調べてみると意外と古いのですね。人によっては、江戸時代の商店が奉公人に配った盆と正月の休暇の際の「仕着せ」を起源とする方もありますが、これはカウントしないことにしました。すると、明治初期、今から143年前に、三菱系の三菱商会(当時)が、従業員に「賞与」として供与し、以後夏と暮に支給すようになったのが最初の例として出てきます。その後、三菱系中心に広まりますが、戦前では広く広がることもなく、額も月給の半月分程度でした。それが、日本企業のほぼ全体を網羅し、支給額も給与の1ヶ月とか、2か月分になったのは、戦後のインフレ期に高まった労働運動の中で、生活防衛のためとして、強く目標として要求されてからでした。
2019.01.02
コメント(9)
-
EEC(欧州経済共同体)設立 1日の日記
クロニクル EEC(欧州経済共同体)設立1958(昭和33)年1月1日 現在のEUの前身EEC(欧州経済共同体)が、61年前の今日産声をあげました。 加盟国は、フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグの6ヶ国でした。その後EECは、65年に経済のみでなく政治や文化の統合をも目指す、欧州共同体(EC)となります。この時点での加盟国は、まだ6ヶ国のままでした。イギリス、デンマーク、アイルランドの3カ国がECへの加盟を認められ、加盟国が9ヶ国となったのは、73年のことでした。次いで、81年にはギリシアが、86年にはスペインとポルトガルが加盟を認められ、EC加盟国は当初の2倍の12ヶ国となりました。93年には欧州連合条約が成立してEUが誕生、95年にはオーストリア、フィンランド、スウェーデンの3ヶ国の加盟が承認され、加盟国は15ヶ国に膨らみました。2004年5月には、旧東欧圏を中心に一挙に10ヶ国(リトアニア、ラトヴィア、エストニア、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、マルタ、キプロス)の加盟が認められました。さらに07年には、ルーマニアとブルガリアの加盟が承認されて27ヶ国となり、14年7月にはクロアチアの加盟が承認され、現在のEU加盟国は28ヶ国となっています。 多すぎ、大きすぎると、まとまりをとるのは、大変ですよね。常に不協和音を奏でていたイギリスは、EU脱退を決めながら、うろうろしていますし、独仏のリーダーシップも、怪しくなりつつあるようで、うまく乗りきっていけるのか、ここ数年が勝負の時のように思えます。ただ揺り返しはありますが、19世紀中頃までに確立した国民国家体制も、どうやら賞味期限を過ぎたようにも見え、世界は大きな転換期を迎えつつあるようにも思えます。さて、今年は多少でも先の展望が見えてくると良いのですが、まだしばらくは難しいのでしょうね。そんな気がします。
2019.01.01
コメント(7)
全31件 (31件中 1-31件目)
1