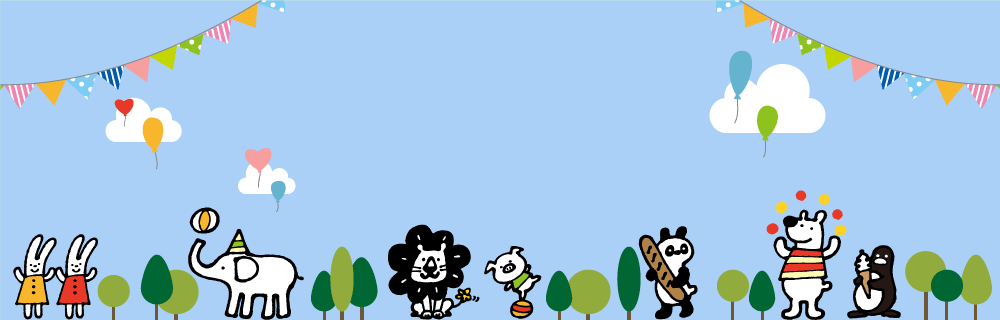2011年12月の記事
全84件 (84件中 1-50件目)
-
米国の新聞とピューリッツァ(4)
米国の新聞とピューリッツァ(4)ピューリッツァのこうした努力と企画力で、読者の支持を得、『ワールド』紙は発行部数を伸ばしました。そうなると、同業他者もまた、新しい新聞経営のモデルとして、ピューリッツァ張りの、読者参加企画を次々と打ち出すようになりました。何のことはないピューリッツァモデルの模倣です。日本でも、今日では新聞社が主催したり、共催する形での、さまざまな催しが増えていますが、その源流を辿ると、どうやらピューリッツァに行き着くようです。ピューリッツァはまた、リベラリストとしても知られ、あらゆる権力に媚びない立場から、『ワールド』紙の論説に健筆をふるい、近代ジャーナリズムの確立に努めました。1783年に、彼が『ワールド』紙を買収した当時、同紙の発行部数は公称で2万部、実売部数で1万5千部程度だったのですが、1892年の発行部数は37万4千部に達し、ニューヨーク最大の新聞となったのです。しかし、好事魔多しの例えどおり、ピューリッツァは90年代に入ると眼病を患い、90年代の後半には、経営の第一線からは身を引いてしまいます。そんなピューリッツァの名を不朽のものとしたのは、引退後の彼が、ジャーナリズムの将来を憂えて、若い新聞人の養成のためにと、コロンビア大学に新聞学科と新文学大学院を設けるための必要資金を寄付し、その資金の一部を優れた報道に対する顕彰とすることまで指定したことにありました。新聞学の一講座ではなく、学科の寄贈ですから、寄付金も半端ではありません。ピューリッツァの報道に関する熱い思いが伝わってきますね。おなじみのピューリッツか賞も、こうして制定され、1917年以降、毎年優れた記事を配信した記者個人や新聞社が表彰されるようになり、今日に受け継がれているのです。 完追記本年の更新は、ここで終了です。御愛読、激励有難うございました。明年もよろしくお願いします。 ザビ
2011.12.31
コメント(0)
-
丸の内に三菱1号館竣工 31日の日記
クロニクル 丸の内に三菱1号館竣工1894(明治27)年12月31日107年前の丸の内は雑草生い茂る錬兵場の跡地でした。この地にこの日、日本で最初のオフィスビルとなる、赤レンガ造り地上3階、地下室ありの三菱1号館が竣工しました。4年前に同地を購入した三菱は、「丸の内建設計画」を立案、1892年1月に1号館の建設に着手、ほぼ3年を費やして、この日竣工を迎えたのです。設計はイギリス人建築家のコンドルと、彼の弟子の日本人曽禰達蔵でした。面白いのは、ビルの賃貸区分で、フロア毎に貸し出す形式ではなく、建物を縦割りにして、夫々に出入り口を設ける棟割長屋形式が採られていたことです。イギリス風の赤レンガ造りであることに加え、明治政府の殖産興業政策の成果で、産業革命の始期にさしかかっていたこともあって、このビルは人気を呼び、入居希望が殺到しました。三菱の思惑は見事に当たったというわけです。この後、1911(明治44)年までに丸の内にはレンガ造りの三菱ビルが18棟建設され、いずれも満室の盛況でした。丸の内オフィス街と、三菱村の誕生秘話で、今年のクロニクルを終えることにしました。
2011.12.31
コメント(18)
-
米国の新聞とピューリッツァ (3)
米国の新聞とピューリッツァ(3)「自由の女神」像の台座建立の募金活動は、結果として『ワールド』紙の発行部数を伸ばす上でも、大いにプラスとなりました。この経験からピューリッツァは、読者の興味をそそる読者参加型の優れた企画が、発行部数を伸ばす武器となることを学びました。この後、『ワールド』紙の紙面には、読者参加型の企画が次々に掲載されました。その中で、大ヒットとなったのが、筆名をネリー・ビリーとした婦人記者をして、世界一周早回りの旅に出し、読者に彼女が何日何時間でニューヨークに戻ってくるかを、予測してもらう企画でした。皆さんも御存知の『80日間世界一周』は、1872年にロンドンで出版され、大ベストセラーとなった作品です。『ワールド』紙の女性記者ネリー・ビリー嬢の旅立ちは、80年代の末でしたから、船や鉄道で廻れるところは増えています。しかし、汽船や汽車のスピードも上がっています。それゆえ、読者の話題は、彼女はジュール・ヴェルヌの小説の主人公フォッグ卿の記録を塗り替えることが出来るかどうかに、集中したのです。ピューリッツァは、電信を利用して、彼女が送ってくる記事を紙面に載せ、読者の興味をそそることも忘れませんでした。そのため、『ワールド』紙が企画した時間当てクイズの応募は、10万通を超える大当たりとなったのです。応募締め切り後も、今日は彼女は何処まで進んだのか。帰国は何時になりそうかと、読者の興味はさらに高まり、ニューヨーク子の話題を独占したのです。結局ネリー・ビリー嬢は72日と6時間11分14秒で世界一周を達成し、フォッグ卿の80日を大きく更新して、旅行を終えたのです。 続く
2011.12.30
コメント(2)
-
マーシャル・プラン終了 30日の日記
クロニクル マーシャル・プラン終了1951(昭和26)年12月30日マーシャル・プランとは、1947(昭和22)年の6月2日に、アメリカ合衆国国務長官のマーシャルが発表した、ヨーロッパ経済の復興計画を指します。第二次世界大戦終了後の世界は、東西ドイツや東欧を巡って米ソの対立が目立ち、アメリカは、東西に分割された西ドイツの経済復興を急ぎ、ここに西ドイツ地域の再生とイギリス・フランスなどの復興を測る必要が生じたのです。実行されたマーシャル・プランは、西ドイツの目覚しい経済回復に繋がり、西ドイツ経済の力強い復活が英・仏などの経済に好影響を与えるなど、アメリカの期待以上の成果を生みました。こうして、開始から4年半余のこの日、マーシャル・プランは所期の目的を達成して、終了することとなったのです、アメリカのヨーロッパへの経済援助は、総額で120億ドルに達したと言われます。ちょうど60年前のことです。
2011.12.30
コメント(6)
-
独立国家共同体(CIS)活動開始……30日の日記
クロニクル 独立国家共同体(CIS)活動開始1991(平成3)年12月30日ちょうど「20年前ですね。12月21日にカザフスタンのアルマ・アタで,その創設を宣言した独立国家共同体(CIS)が、この日活動を開始しました。その結果、ソ連邦は公式にその役割を終え、ソ連邦の崩壊は、もはや後戻りできないものとなりました。
2011.12.30
コメント(6)
-
米国の新聞とピューリッツァ (2)
米国の新聞とピューリッツァ (2)南北戦争が終わり、軍務を解かれて失業者となったピューリッツァは、たちまち路頭に迷いました。しかし、彼にはツキがありました。兵士仲間に教えられて、ドイツ移民の多いセントルイスに遷ったのが、運のツキはじめでした。何とセントルイスで、新聞記者になることが出来たのです。駆け出し記者としての懸命の働きで、小金をためた彼は、1878年にセントルイスでポスト・ディスパッチ紙を創刊して成功します。事業欲にも目覚めたピューリッツァは、全米一の大都会ニューヨークへの進出を目指します。こうして83年、ワールド紙を買収して、念願のニューヨーク進出を果たしたのです。ピューリッツァの新聞作りの要諦は、社会種を重視しながらゴシップ記事に流れず、お堅い政治新聞とも、ゴシップ記事中心の芸能新聞とも距離を置いた、新しい大衆紙を目指したことにありました。こうして、中等教育を受けた新興の中産階級をターゲットとした、ピューリッツァの狙いは的中し、「ワールド」紙は、彼の経営参加によって、発行部数を大幅に伸ばすことに成功したのです。そのピューリッツァの武器は、読者参加型のイヴェントの多用にありました。代表的な例を二つだけ上げることにします。その第1は、今では米国の象徴となっている「自由の女神」像の建立問題です。女神像は、米国の独立100周年を記念して、パリっ子たちによって寄贈されたものです。1875年に組織された、パリの仏米協会の会員が、米国の独立100年の記念にと寄贈を思い立ち、像の完成が遅れ、100周年には間に合わなかったのですが、1884年にニューヨークに届けられた仏米友好の像なのです。しかし、像は届けられましたが、台座がありません。台座は米側が用意し、完成させる予定でしたが、ところが財政難のために、台座を作るための経費が議会で否決されてしまい、米側は像を建てることが出来ず、像はニューヨークの港に置かれたままとなったのです。1783年に「ワールド」紙を買収して、ニューヨークに進出したピューリッツァは、港に置かれたままの「自由の女神」像を見て、自分の経営する「ワールド」紙で、大々的な募金キャンペーンを行なうことを、思い立ったのです。「独立戦争に協力し、義勇軍を派遣して共に英国と戦ってくれた、フランスの友人たちが、浄財を集めて贈ってくれた「自由の女神」像が、ニューヨークの港に横たえられたままになっている」「大衆諸君の新聞である「ワールド紙は、諸君に訴える。諸君の力で「自由の女神」の台座を作ろうではないか。そのための資金を募集したい。ただし高額の寄付はお断りだ。5セント、10セントの寄付は大歓迎だ」このピューリッツァの呼びかけは、大反響を巻き起こし、短期間に10万ドルを超える寄付金を集めたのです。応募者数は12万人を超えていました。こうして、今や世界遺産にも登録されている「自由の女神」像は、米仏友好のシンボルとして、ニューヨック港の出入り口に設置されたのです。 続く
2011.12.29
コメント(2)
-
日経平均史上最高値 29日の日記
クロニクル 日経平均史上最高値1989年(平成元)年12月29日22年前になります。年初に昭和が平成に切り替わった年です。大納会のこの日、東京証券取引所の日経225平均株価が、38915円87銭という史上最高値で引けました。 87年10月のNY市場のブラックマンデーの衝撃を僅か2ヶ月で克服した東京市場では、翌88年12月には日経平均が未踏の3万円台に突入する活況を呈し、特定金銭信託やファンドトラストという聞きなれない言葉を連発しながら、日経平均株価は5万円まで上げるという、根拠のない神話が信じられるユーフォーリァ現象を呈し、この日史上最高値を記録して終えました。 翌90年の大発会の始値は、この値を200円も下回る38712円88銭でした。これが、90年代どころか、今日まで超えることが出来ない、その後の最高値になろうとは、神ならぬ身に分かろうはずはありません。4月には3万円を大きく割り込みました。その後はしばらく戻して3万円台を回復しますが、7月以降再度急落、10月には、20221円86銭と半値近くまで値下がりしたのです。第1段の底は92年8月の14309円41銭、95年7月に再び14400円台、そして3年後の98年10月には12800円台、こうした下げを繰り返して、世紀の替わった2003年4月の7607円88銭まで、13年間に渡って下げ続ける大きな後遺症を残したのです。高値からの下落率80.45%、2割弱に落ち込むという大暴落劇でした。株価と地価のスパイラル、崩壊した土地神話にしがみ付き続けた先送りのツケ、護送船団方式という政治の保護にアグラをかき続けた銀行・デパート・スーパー・土建業などを中心とした内需系企業と政治の無策が傷を大きくしたことも事実ですが、バブルは必ず崩壊し、得た果実よりも大きな傷を残すという事実は、しっかりと受けとめておく必要があります。日本の失敗を見ていたはずの欧米世界が、2006~07年頃から日本とほとんど同じようなバブルの崩壊に苦しみ、先送りのツケに苦しみ続けている様子を見ると、何とまぁと、呆れてしまいます。そんなわけで、世界経済の混乱は、なお当分は続くのでしょうね。来年も気を引き締めてことにあたりたいと考えている年末です。
2011.12.29
コメント(2)
-

特別養護老人ホームのお餅つき
特別養護老人ホームのお餅つき毎年暮れの28日は、町内の特別養護老人ホームのお餅搗きに、ボランティアで出かけます。青天に恵まれた今年も出かけました。搗くのは僅かに5臼ほどですが、お年寄りが喉につかえさせないよう、餅は一番小さいビーダマサイズに千切り、ゴマやアンコ、辛みなどにつけるのが大変ですから、時間をかけて、ゆっくりともち米を蒸かすので、結構時間はかかります。最後の2臼は、入所のお年寄りの希望者や、職員の方にも搗いてもらうのですが、これが好評で、昔とった杵柄の皆さんが、順番に搗きにきます。こんな感じです。最初は、お1人で搗ける方です。頑張っていらっしゃいます。続いて、介護士さんとご一緒に車椅子の方です。もうお1人車椅子の方ですが、この方は左半身に麻痺が残り、左手が利きませんので、右手1本で、介護士さんとご一緒です。「昔はいっぱい搗いたのよ」と嬉しそうでした。素敵な笑顔でしょう。最後は、満を持しての介護士さんたちです。半日のもちつき大会の一齣でした。
2011.12.28
コメント(18)
-
学校身体検査事始 28日の日記
クロニクル 学校身体検査事始1888(明治21)年12月28日明治21年のことですから、123年も前ということになりますが、この日文部省は、翌明治22年から、毎年4月に、学校で学生・生徒・児童の活力検査を実施するよう、訓令を発しました。活力検査とは、当時の用語で、健康調査のことです。ここに、内科、歯科の健診を含む、身長、体重、胸囲、座高をはじめ、握力、背筋力、肺活量などの身体検査が、はじめられることになったのでした。学校での4月の健診、明治時代から続いているのですね。
2011.12.28
コメント(6)
-
カラーテレビの実験局開局 28日の日記
クロニクル カラーテレビの実験局開局1957(昭和32)年12月28日54年前のことです。この日、NHKと日本テレビが、カラー放送の実験局を開局しました。 日本でのテレビの本放送が始まって(当初は1日4時間の限定放送でした)まだ4年、家庭へのテレビの普及もまだ限られていた頃です。日本シリーズや大相撲、力道山のプロレス等の中継があると、テレビを備えた界隈のお金持ちの家に、近所の子供達が(なかには大人も)上がり込んで、見せてもらっていたものでした。そんな時代でした。映画こそ総天然色が謳われましたが、テレビのカラー化など、夢のまた夢の世界だったのです。 因みに、国内のテレビ普及率が、ようやく100万台の大台に達するのが58年5月(受信拒否の先ずない時代でしたから、NHKの受信契約数での判断です)でしたから、なおテレビよりもラジオの全盛期で、同年11月にラジオの受信契約は1,481万世帯に達しています。それでも、ようやく本格的な上潮に乗りつつあった日本経済の好調もあって、テレビの普及は60年代から急加速します。 そうした中、1960年9月にはカラーテレビの本放送が始まり、各テレビ局は一部の番組をカラー放送に切替えたのです。この頃には、テレビの放送時間も大幅に増え、朝6時から夜11時頃まで放送されたのですが、新聞の番組欄の冒頭にカラー放送番組には、cと記されるようになったのです。 カラーテレビの普及期は、東京オリンピックと重なります。「オリンピックをカラーで見よう」というコマーシャルを、何度も何度も流していたことが、今でもつい最近のことのように、思い出されます。
2011.12.28
コメント(6)
-
米国の新聞とピューリッツァ (1)
米国の新聞とピューリッツァ (1)昨日掲載した「新聞と広告」の絡みで、フランスに次いで新聞が大いに発達した、米国の事情を紹介します。今日の米国新聞、最近はちょっと元気がなく、政府の後追い的な記事が多く、ちょいと心配ですが、今日の米国新聞界の育ての親は、何と言っても、ピューリッツァ賞でお馴染みの、ピューリッツァその人です。ピューリッツァ賞は、新聞人として成功したジョゼフ・ピューリッツァが、優れた新聞人の養成と、その励みとなるようにとの願いを籠め、その遺言に基づく基金で創設されたのです。1911年に死去したピューリッツァの遺志を生かした寄附講座として、1912年にコロンビア大学に新聞学科と新聞学大学院が設けられ、さらに1917年スタートで、優れた記事を描いた新聞記者などを顕彰する、ピューリッツァ賞が設けられたのです。このピューリッツァ氏が、米国のジャーナリズムをフランスの新聞と並ぶ、一流の新聞に育て上げた功労者でした。ジョゼフ・ピューリッツァは、1847年4月にハンガリーで生まれました。軍人を志したのですが、視力の不足から身体検査で不合格となります。失意の彼は、たまたま米国の内戦の噂(これが南北戦争{1861~1865年}です)を聞き、ほとんど無一文に近い状態で米国に渡り、首尾よく北部軍にもぐり込んだのです。しかし、やがて戦争は終わり、ピューリッツァは失業したのです。 続く
2011.12.27
コメント(0)
-
傾斜生産方式を決定 27日の日記
クロニクル 傾斜生産方式を決定1946(昭和21)年12月27日今から65年前、戦後の焼け跡があちこちに残る時代の話しです。政府は、この日の閣議で、経済復興をどう進めるかに関して,傾斜生産方式を採用する事を、正式に決めました。敗戦、とりわけ米軍の空爆によって、軍需産業を中心に、日本の工業地帯は大きく破戒されており、事実上ゼロからの復興でしたから、1度に全産業の復興を目指す事は、現実問題として無理でした。そのため、あらゆる産業に関連する基幹産業を中心に、少ない外貨を割当、まず基幹部分の復興を目指し、次いで周辺に広げると言う、2段階、3段階の手順で復興してゆくプランが採用されたのです。こうして、当時は国内資源として豊富に採掘された石炭採掘→電力→鉄鋼の順で、政府による支援が行われたのです。このうち石炭は、産業の黒いダイヤと呼ばれ、筑豊・常磐・夕張などの産炭地は活況に沸きました。その1つ、夕張市の最近の惨状、感懐深いものがありますね。
2011.12.27
コメント(4)
-
ソ連軍アフガンに侵攻 27日の日記
クロニクル ソ連軍アフガンに侵攻 21979(昭和54)年12月27日42年前のこの日、アフガニスタンで親ソ連派のクーダタが発生、クーデタ派の要請を受けたとしてソ連軍は直ちにアフガニスタンへの侵攻を開始しました。アフガンでは、前年4月に親ソ派政権が誕生、土地改革など社会主義寄りの政策をとったのですが、これに不満を持つイスラム系勢力が反政府活動を続け、この年9月に親ソ政権を打倒、民族主義色の濃い政府が誕生していたのでしす。それだけにこの日の親ソ派のクーデタは、ソ連の丸抱えによるものと推測されました。イスラム系に多い民族主義諸勢力はジハード(聖戦)を合言葉に山岳地帯でゲリラ戦を展開、大軍を展開できない山中のゲリラ戦で、圧倒的なソ連軍の武力を無力化してゆくことに、次第に成功して行きます。10万人に及ぶ兵力を展開してなお、情勢の悪化を防げず、消耗しきったソ連軍は、10年後、ゴルバチョフ政権の下でアフガンから撤退することになります。当時「アフガンは、ソ連にとってのヴェトナムだった」と言われ、ソ連社会主義崩壊の原因の一つに数えられました。ところで、ソ連軍撤退後のアフガンでは、諸勢力の権力争いで国内が混乱し、血みどろの闘争を展開したのですが、この混乱を収拾したのが、徹底的に汚職と腐敗を排除したイスラム原理主義勢力のタリバンでした。タリバン政権にも問題はありましたが、ソ連侵攻後、20年以上に及んだ戦乱と社会的混乱を収拾し、アフガンに平和と民衆生活の安定を齎し、庶民の支持を得ていた政府だったことは確かです。9/11を理由にアメリカはこのタリバン政府を倒し、再びアフガンを治安劣悪で安心して生活できない地にしてしまったのです。日本では、カルザイ政権のプラス面のみが、誇張して伝えれていますが、カルザイ政権の安定した支配領域は首都カブールとその近在のみに、限られています。しかも汚職にまみれたカルザイとその側近たちに、国民の支持はゼロに等しいのが現実です。財政難に陥った米国は、イラクから撤退しアフガンへの関与も最小にしたいために。現在のアフガンにはNATO軍が展開しているのですが、そのNATO軍も年末には撤退します。米国は、アフガンに足を獲られ、ソ連と同じ失敗を犯しつつあるように見えます。
2011.12.27
コメント(6)
-
新聞と広告
新聞と広告 24日のクロニクルに、貯古齢糖(チョコレート)の発売に、新聞広告が活用されたことを記しました。そこで、ここでは新聞広告の起源について記してみます。それはフランスでのことになるのですが、お読みいただければ幸いです。新聞の発行は17世紀頃のドイツにその起源を持っています。しかし、新聞が社会的に認知されるのは、フランス革命期のことになります。フランス革命期には、数多くの新聞が発行されますが、その全てが不定期刊行物で、発行部数も数百蕪が限度でした。 最初の本格的日刊新聞は、フランスの新聞王と称された、エミール・ド・ジラルダンが1836年7月に刊行した「ラ・プレス」紙です。「ラ・プレス」は始めて紙面に広告を掲載して販売価格を下げることに成功したのです。料金をを安くすることで、発行部数を伸ばす戦略を採ったのです。彼はまたアレクサンドル・デュマやウジェーヌ・シューといった、売れっ子作家の小説を新聞に連載する新機軸で話題を集めました。こうして「ラ・プレス」紙は売上を伸ばしていったのですが、ニュースの迅速な収集がまだ困難な時代でしたから、売上の伸張にも限度がありました。1848年二月革命直前の時期で、当時発行されていた日刊紙25紙合わせての総売上は、15万部そこそこだったと記されています。本格的な全国紙の登場は、鉄道輸送の発達によって、パリで印刷された新聞を素早く地方都市でも販売することが可能になった1860年代になってからのことです。明治維新直前の時期です。 ナポレオン3世が帝政の自由化政策(一般に自由帝政と呼びます)を採った事もあって、新聞発行も自由化された頃です。1863年創刊の「ル・プチ・ジュルナル」紙は、予約購読に基礎をおかず、街頭での販売や駅売りを基本として、値段を他紙の半値の1スー(5サンチーム、日本円にして50円くらい)にし、政治的主張には一切加担せずに、三面記事を大きく扱うといった安価な大衆情報紙を装って成功し、帝政末の69年(明治2年)には30万部を売上げ、20世紀初頭には、発行部数100万部を達成する勢いを示しました。同紙に対抗した「ル・プチ・パリジャン」紙も1890年(明治23年)に50万部、第1次大戦直前の1913年には130万部超の発行部数を記録しました。 状況は英・米・独でも同じでした。フランスに5年程度の遅れで、ほぼ同じような道を歩きました。こうして、ラジオの登場以前の段階では、広告が伝える内容を含めて、新聞が大都市の情報を地方へ伝播する役割をになっていたのです。
2011.12.26
コメント(6)
-
ソ連邦消滅 26日の日記
クロニクル ソ連邦消滅1991(平成3)年12月26日丁度20年になりますね。この日、ソ連最高会議はソヴィエト連邦の消滅を宣言、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、地上からその姿を消しました。この年8月19日、ソ連共産党保守派がクーデタを起こし、ゴルバチョフ書記長兼大統領を軟禁しましたが、ロシア共和国大統領のエリツィンらが反対、クーデタは僅か4日で失敗に終りました。この事件によって、共産党の権威は完全に失墜、エリツィンはロシア共和国内における共産党の活動を全面的に禁止し、ゴルバチョフも8月24日にソ連共産党中央委員会に自主解散を要求、党資産の全面接収に踏みきりました。こうして共産党は事実上消滅するにいたりました。その後、既に独立を宣言していたバルト3国に続いて、ウクライナやベラルーシなどが続々とソ連邦からの独立を宣言、12月21日には、バルト3国とグルジアを除く11共和国の首脳がCIS(独立国家共同体)の結成を宣言、ソ連邦存続の道が絶たれました。ここにいたって、ゴルバチョフソ連邦大統領は辞任を決断(25日)、この日のソ連邦消滅宣言に到りました。社会主義が一世を風靡した1つの時代が、ここに終了をみ、長く歴史に刻まれる1日となりました。
2011.12.26
コメント(14)
-
最初のプロ野球チーム発足 26日の日記
クロニクル 最初のプロ野球チーム発足1934(昭和9)年12月26日77年前のこの日、日本初のプロ野球チームとして大日本東京野球倶楽部の創立が発表されました。 選手は、沢村栄治、スタルヒン、三原脩、水原茂等19名での発足でした。同年11月に、正力松太郎読売新聞社主の招きで、べ-ブ・ルース等全米大リーグ選抜が来日しました。3年前の前回の来日では早稲田・慶應ら東京六大学の選手らが善戦したのですが、その後学生とプロとの試合が禁止されたため、今回の来日では、急遽社会人選手で全日本選抜チームを編成、対戦することになったのです。 試合は日本チームの全敗に終りましたが、結果としてプロチーム編成の機運が高まり、この日東京巨人軍の前身、大日本東京倶楽部が発足することになったのです。 しかし、1チームでは試合は出来ません。翌1935(昭和10)年12月10日に大阪タイガースが、さらに36年に入ると、1月、2月の間に名古屋、東京セネタース、阪急、大東京、名古屋金鯱と7チームが揃い、37(昭和12)年から、7チームと変則ながら、正式に公式戦が始められたのです。 正力松太郎氏がプロ野球の生みの親とされるのは、この辺の事情によるのですね。因みに最初のシーズンは春と秋の2シーズン制、春季はジャイアンツが、秋季はタイガースが仲良く制したようです。なるほど巨人・阪神戦は伝統の一戦になるわけですね。
2011.12.26
コメント(4)
-
原発問題から ~ フクシマダイイチと鳩山元首相 ~
原発問題から ~ フクシマダイイチと鳩山元首相 ~鳩山由紀夫元首相、首相としては期待はずれで、宇宙人と渾名されましたが、科学者としては有能な方だったようです。事情はこれから記しますが、私は彼を見直しています。標題に掲げましたように、フクシマダイイチの大事故について、仲間の議員たちと共に、独自の調査を続け、その成果をイギリスの科学誌”Nature”(『ネイチャー』)に掲載したのです。『ネイチャー』は世界的な権威を誇る学術誌で、掲載審査が厳しいことでも知られています。鳩山元首相は、政府や原子力安全・保安院、さらには東電の原因究明委員会とは距離を置く、独自の調査チームを結成、政府のチーム(「Aチーム」)と距離を置くために、自ら「Bチーム」と名付けて、調査活動を続けてきました。その成果を、鳩山氏と平良智之民主党衆院議員の連名で、『ネイチャー』誌に投稿、掲載となったのです。鳩山氏らは、そこで、「事実関係を明らかにするためには、あらゆる可能性について証拠と反証を収集し、それらを公開しなければならない。」と自分達の立場を鮮明にし、「最悪のシナリオが現実になってしまったのかどうか」を、検証しようと努力したことを、明らかにしています。そして、最悪の事態に対応するための計画を策定するために、再臨界の可能性を調べ、3月の大爆発が核爆発であった可能性が高いことを突き止め、さらに溶融した燃料が格納容器の底を突き破り、海に流れて環境汚染を引き起こす危険性を、追求しています。そして鳩山氏らは、自らの「Bチーム」が東電関係の資料の入手に、いかに苦労したかの事実を挙げ、世界の科学者の叡智を結集するために、東電関係の全ての資料をオープンにする必要を訴え、少なくとも「フクシマダイイチ」原発を国有化する必要を、強く訴えています。この部分の記述を一部引用します。「情報がオープンな形で収集されるために、福島第一原子力発電所を国有化しなければならない。事実は、どんなに困難なものであっても、国民に知らせなければならない。さらに、政府にこの事故の検証と補償を行う義務があることからも、国有化は不可避である。」とし、さらに「Bチームは、8月に東京電力に対して原発のマニュアルを請求したが、それを入手するだけでもたいへんな苦労をした。これは、事故の情報がどのように規制されているかを示す一例である。東京電力は当初、委員会にマニュアルを提出することを拒否した。9月にようやく提出したときには、多くの語句(カギとなる温度や実際の手順)が黒く塗りつぶされていた。東京電力は、それらが自社の知的財産であると主張したのである。東京電力が全マニュアルを公表したのは6ヶ月も経過してからであった。」ここに記された「黒く塗りつぶされた」資料の写真は、『ネイチャー』誌の紙面に掲載され、広く世界の科学者の知るところとなっています。12月15日に刊行された『ネイチャー』誌に、この論文が掲載されたことで、政府も東電も情報隠しを続けることは、かなり厳しくなったことは間違いありません。第2、第3の追求の火の手にあがってほしいところです。『ネイチャー』誌の論文については、http://www.natureasia.com/japan/nature/specials/earthquake/nature_comment_121511.php で読むことが出来ます。
2011.12.25
コメント(8)
-
ヴェトナム軍カンボジアに侵攻 25日の日記
クロニクル ヴェトナム軍カンボジアに侵攻1978(昭和53)年12月25日33年前のこの日、ヴェトナム政府軍が国境を超えてカンボジアに侵攻、28日にかけて、カンボジア東部で激戦を展開しました。その後、有利となったヴェトナム軍の後押しを受けて、翌79年の1月11日に、親ヴェトナム派共産党によって、カンボジア人民共和国の成立が宣言されました。75年に成立したポル・ポト派中心の政権は、中央を追われましたが、根強い抵抗を続け、それにシアヌーク派、右派のロン・ノル派までもが加わり、カンボジアは、内戦に突入することになりました。ポル・ポt派による都市住民の大量虐殺が明らかになるのは、それから1年ほど後のことでした。
2011.12.25
コメント(2)
-
大正天皇崩御 25日の日記
クロニクル 大正天皇崩御1926(大正15)年12月25日85年前のこの日、午前1時25分、葉山の御用邸で病気療養中の大正天皇が、逝去されました。48歳でした。少年時代から病弱で、即位後も健康にすぐれず、1921(大正10)年からは、皇太子(後の昭和天皇)が摂政を務めていたのですが、この年秋から気管支炎と肺炎を患い、葉山の御用邸で療養中でした。12月に入って病状が悪化、宮内省(現宮内庁)は15日に「天皇陛下御異例」を発表して、国民に病状を発表、快癒を祈る国民は遊興を自粛し、歌舞伎座や帝国劇場などが、相次いで興行を中止したほどでした。新聞各社はこぞって号外を発行、その日の内に、皇太子殿下の即位が公にされ、若槻内閣は、新元号を「昭和」と発表したのでした。余談になりますが、このため、昭和元年は5日しかありません。私の最年長の従姉妹は、たまたま1926年の12月26日生まれなものですから、同級生達と会うと、「私は大正なのに、あなたは昭和なのよね」と羨ましがられたと、今でも半分嬉しそうに話します。確かに昭和と大正では、ぐっと響きに違いがありますね。ところで、近年大正天皇研究はグンと進み、再評価の機運が高くなってきています。原 武史『大正天皇』(朝日選書)2000年刊がお勧めです。
2011.12.25
コメント(8)
-
金正日死去(5)
金正日死去(5)金正日総書記の死が突然だっただけに、一部に毒殺説なども流れましたが、その後の動きを見る限り、「北朝鮮」国内に動乱の様子は見られません。内部に混乱の徴候が見られないことから、毒殺説は的外れといわざるを得ません。金正日総書記の死でストップしていますが、昨年の天安艦事件と延坪島(ヨンビョンド)砲撃事件で冷え切っていた朝鮮半島の南北関係は、11月頃から急速に関係改善に向かっていました。李明博政権は、対「北朝鮮」宥和政策をとらず、南北対話を拒否する姿勢をとり続けてきたのですが、ソウル市長選の敗北以後、この姿勢を転換して南北対話を推進する姿勢を示し、南北や米朝の対話が進められてきました。その結果、来年の早い段階で、六カ国協議(南北に米中露日を加えた6ヶ国)を再開し、韓国は何らかの成果を得ることを、「北朝鮮」は日米らによる経済制裁の解除と、経済支援を得ることで、国内の経済危機を脱することを目指すことを、双方で合意する手はずが、ほぼ整っていたようです。中国や米国の発表やニュースを、注意深く見ている限り、若殿金正恩を支える叔母夫婦は、経済制裁の解除を甥の手柄にして、支配基盤の安定を目指す路線をとろうとしているように、見えます。勿論、すっかり安心というわけではありませんが、今のところ、突然「北朝鮮」が強攻策に出る可能性は、低いように思います。
2011.12.24
コメント(8)
-
消費税法案成立 24日の日記
クロニクル 消費税法案成立1988(昭和63)年12月24日23年前になりますが、この日の参院本会議で、当初税率を3%と定めた消費税導入法案が、25時間ものマラソン審議で、ようやく成立しました。当時健在だった社会と共産党は、時間切れを狙って徹底した牛歩戦術で抵抗しましたが、この日未明大型間接税を導入する「消費税」法案は可決成立しました。財政再建の旗印の下に、大型間接税導入計画を最初に打ち出したのは、79年の大平内閣が提案した「付加価値税」構想でした。この構想が潰えた後、中曽根内閣が導入を計画した「売上税」もまた、野党や国民各層の激しい反発を受けて、陽の目を見ませんでした。3度目の正直で、ようやく税率を3%とした消費税が日の目を見たのです。導入は翌89年の4月1日。97年4月には、税率が5%に引き上げられて、今日に到りますが、消費税の導入でも、さらには5%に税率を引き上げても、一向に財政状況は好転せず、悪化の一途を辿っているのが現実です。野田内閣もまた、マスコミを巻き込んで「待ったなしの財政再建」を主張して、消費税率の引き上げを画策していますが、今の政治家と財務省が予算の配分権と執行権を握っている限り、私は財政再建は覚束ないと睨んでいます。こう考えますから、現状での消費税の引き上げに、私は強く反対しています。
2011.12.24
コメント(4)
-
本邦初のチョコレート発売を予告 24日の日記
クロニクル 本邦初のチョコレート発売を予告1878(明治11)年12月24日明治は遠くなりにけりですね。もう133年も前のことになります。この日、東京は両国若松町の米津風月堂が本邦初の貯古齢糖(チョコレート)を明日から販売する旨の販売広告を、なかよみ新聞に掲載しました。この広告は大評判となり、翌日25日には、同店前に大行列が出来たと記されています。これもまた、文明開化の一齣でしたが、いったいどんな味の貯古齢糖だったのでしょうね。タイムスリップして食べてきたいような気がしませんか。
2011.12.24
コメント(14)
-
金正日死去 (4)
金正日死去(4)「北朝鮮」の核・ミサイル問題については、専門家の見方は真っ二つに割れています。静岡県立大学の伊豆見 元氏は、北朝鮮が「核開発を手放すことはないだろう。」とした上で、「来年2月から3月にかけ、米韓合同軍事演習が実施される。毎年、行われている演習だが、北朝鮮に口実を与えるかもしれない。北朝鮮は核抑止力を強化しなくてはならないとして核実験を行う可能性もある。」とし、来春は要注意としています。これに対し、韓国延世大学の武貞秀士客員教授は、金日成主席の時と同様に、喪に服する機関が必要だとする立場から、「カリスマ性が重視されてきた金総書記の喪に服する期間は重要だ。華々しい核交渉などは慎む時期が1~2年続かざるをえない。新しい政策の展開は、金日成氏が死んだときと同じで、萎縮する。核実験やテポドン1、2号など長距離ミサイルの実験もそうだ。これらは祝い事であり、目立った動きはできないだろう。」としています。武貞氏はさらに、「韓国への挑発行為も、延坪島(ヨンビョンド)攻撃のような大きな形は考えにくい。可能性はゼロではないが、少ないように思う。」と語っています。ともかく、金正日総書記の死去から数日立ちましたが、いまだにクーデタとか民衆蜂起といった情報はありませんから、すぐに何かが起きるといった情勢にないことは、間違いありません。しばらくは、様子見が正解のようです。
2011.12.23
コメント(8)
-
東京タワー完成 23日の日記
クロニクル 東京タワー完成 1958(昭和33)年12月23日 今やすっかり東京スカイツリーに話題を取られてしまったようですが、『三丁目の夕陽』に出てくるように、我々世代にとって、東京タワーは一種特別のものです。そうです。53年前の今日なのです。12月23日は、この年11月27日に正田美智子さんとの婚約を発表した皇太子(現天皇)の誕生日でもあります。ちょうどその日に合わせたのでしょうか、この日東京港区芝公園内に建設中だった東京タワーが完成しました、高さ333mは、パリのエッフェル塔を抜き、当時世界一。 東京にある7つのテレビ局(NHK2局に民法5局)の発信、中継の拠点として使用されたのですが、テレビ時代のシンボルとして、東京の新名所になりました。そしてまた、成長の道を歩み出した日本経済の躍進を示すシンボルでもありました。
2011.12.23
コメント(10)
-
教育基本法の見直しを… 22日の日記
クロニクル 教育基本法の見直しを…2000(平成12)年12月22日11年前の今日、首相の諮問機関として鳴り物入りで成立した教育改革国民会議は、会議をリードした香山委員の提言をベースに、教育基本法の見直しを森首相に提言しました。この日の会議の結論を受け、小泉、安倍両首相の下でも継続した教育改革国民会議は、文部科学省や中央教育審議会と縄張り争いを繰り広げつつ、いくつもの提言を提出しました。そこでの議論の特徴は、教員の自発性や専門性、そして教育の対象者である学習者(児童や生徒)の個別具体的な状況に照らしての教材や指導案作りの努力(教育プランの開発)を無視した、上からの押し付けにありました。問題の多い、教育基本法の改正は、2007年の参院選前の6月に成立してしまったのですが、実際の教育再生は、個々の教員による学習者の個性に合わせた教案や教材つくりに、即ち個々の教員の熱意とやる気にかかっています。残念ながら、現在の教育改革の議論には、最も大切なこの観点が、すっぽり抜け落ちてしまっています。この点、私は残念でなりません。
2011.12.22
コメント(6)
-
ルーマニア革命始まる 22日の日記
クロニクル ルーマニア革命始まる1989(平成元)年12月22日フランス革命の開始から200年目にあたる1989年は世界史的な出来事の多い年でした。6月の天安門事件、ポーランド、ハンガリー、チェコ、ブルガリアと相次ぐ東欧諸国の政変と自由化の進展、このブログでも取り上げたベルリンの壁崩壊……そして12月初旬の米ソ首脳のマルタ会談による冷戦終結宣言の発表。こうした一連の動きの総仕上げが、東欧で最後に残ったチャウシェスク独裁体制のルーマニア革命でした。22年前のこの日、ルーマニアで革命が始まりました。早朝から首都ブカレストで市民のデモが始まり、次第に人数を増して、正午前には数10万人の規模に達しました。午前11時過ぎ、チャウシェスク大統領は戒厳令を発し、国軍に治安回復を命じましたが、国軍兵士は命令を拒否、その大半がデモ隊側に就きました。勢いを得たデモ隊は、共和国広場を占拠して、共産党本部に殺到、放送局を含む主要機関を手中に収めるに到りました。ここに頑強を誇ったチャウシェスク政権は崩壊、ヘリコプターで官邸を脱出した大統領夫妻は、まもなく捕らわれの身となり、非公開の軍事裁判で死刑を宣告され、25日夫妻とも銃殺されました。ここに東欧革命の連鎖は一応の終結を見ました。
2011.12.22
コメント(10)
-
NHKスペシャル<「メルトダウン」 ~福島第一原発あのとき何が~>を見て
NHKスペシャル <「メルトダウン」 ~福島第一原発あのとき何が~>を見てご覧になられた方も多いでしょうか。18日の日曜日夜9時過ぎから放映された、NHKのシリーズ原発、「メルトダウン」~福島第一原発あのとき何が~、当日時間がなく、録画しておいたものを、見終えたところです。これが公共放送なのでしょうか。実にひどい番組でした。呆れました。民放と違って、東電や東電系列からスオンサー料をもらう必要などないNHKが、何故こんな東電に都合の良いような番組を作ったのでしょう。政府とグルになったのでしょうか。ここまで報道の自主規制が進んでいるとすると、日本はどこかの独裁国家と同じになってしまいます。それほどひどい内容でした。いくつか問題点を挙げておきます。1、1号機のオペレーションルームにいた11人に、全ての責任があると言いたげな構成になっ ていますが、操作ミスをメルトダウンの原因とするためには、先ずもって全ての配管経路が 地震で破壊されていなかったことが確認されている必要があります。その確認は、全くなさ れていません。そんな段階でNHKは、11人を犯罪者にしかねない番組製作態度をとったの です。これは公共放送にあるまじき態度です。2、当時の枝野官房長官の会見が出てきますが、この会見にタイムスタンプが全くありませ ん。その結果、会見の時系列が分からなくなっています。その結果、一種の内容操作を行な ったような効果が、数箇所で生まれています。これは検証番組での事実上の情報操作煮あた り、絶対にやってはいけない行為です。時系列の分かっているものは、ちゃんとタイムポイ ントを入れるべきです。簡単に出来ることなのですから…。3、4人の学者が登場しますが、人選がひどい。4人が口を揃えて、「誰も予測しなかった。 想定外の津波で全て壊れた」といわんばかりです。そして「メルトダウンなど、誰も想定し てな かった」と語ります。ここまでくると、専門家も大嘘つきとなります。 震災翌日3月12日の海外の新聞は、電源喪失から3時間半くらいで、メルトダウンが始ま ることを、専門家の話として掲載しています。当然、日本の専門家も同じことを語っている のですが、国内の新聞は報じなかったのです。 番組のナレーションは、そうした全うな主張は全てなかったことにして、番組の構成に都 合の良い主張をしてくれる人だけを登場させて、済ませています。明らかな偏向番組がこう して作られました。NHKの行為は、報道の倫理に照らして、許されないものだと、私は考えます。
2011.12.21
コメント(8)
-
続々・金正日死去
続々・金正日死去昨日の記事を修正します。金正日の葬儀が28日に行なわれることは、「北朝鮮」の公式発表ですから、間違いがありません。葬儀委員長が誰になるか、当日にならないと分からないと書きましたが、1994年の金日成の葬儀の際も、葬儀委員長を誰にするか決められず、葬儀委員長なしで、喪主の金正日中心に葬儀が行われたそうです。金日成の葬儀では、外国の弔問団を受け入れて、盛大な葬儀が行われたのですが、今回は、外国の弔問団は受け入れない方針なので、今回も葬儀委員長なしで、葬儀が行なわれるだろうというのが、「北朝鮮」研究者の共通理解であることを、確認しました。不確実なことを記して失礼しました。次に、軍の動静についてです。この点については、数少ない日本の「北朝鮮」研究者の見解がおよそ一致しているようですので、いかに紹介させて戴きます。「北朝鮮」では、軍人は特権階級で、一般の兵士も特権のおこぼれに預かり、上官に対する忠誠心は非常に強い集団となっています。しかも、軍人は国民の20人に1人を占めています。家族を含めると、おそらく国民の4分の1に達するでしょう。この軍人たちが、場合によっては特権を失うことにもなりかねない、クーデタに踏み切るかといえば、その可能性は低いと考えざるをえません。軍は国民の不満を抑える体制派ということでしょうか。こう考えると、当面は内部対立を封印して、若殿を支える集団指導体制をとる可能性が高いように思えます。以上、専門家の見解を紹介させて戴きました。明日は、核とミサイルに関する見解を紹介させて戴きます。
2011.12.21
コメント(8)
-
日本郵船「八坂丸」撃沈 21日の日記
クロニクル 日本郵船「八坂丸」撃沈1915(大正4)年12月21日 96年前のことです。この日、地中海を航行中の日本郵船所有の「八坂丸」が、ドイツの潜水艦Uボートによって撃沈されました。前年7月28日に開始された第1次世界大戦に、日本は日英同盟を理由に8月8日に、早くも参戦を決定、同月23日、ドイツに宣戦を布告して参戦しておりました。 ドイツは優勢なイギリス海軍の海上封鎖により、物資の輸入が滞り、劣勢に陥っていた状況を打開しようと、完成したばかりの潜水艦Uボートを投入、15年5月には、イギリスの豪華客船ルシタニア号をアイルランド沖で撃沈、国際的非難を浴びていたのですが、劣勢にあせる軍部は、今度は日本の客船を撃沈するに至ったのです。このドイツは、国際非難覚悟で、17年2月から無制限潜水艦作戦を決行、アメリカ合衆国の参戦を招くことになります。
2011.12.21
コメント(10)
-
TPPとISD条項 ( 10)
TPPとISD条項 (10) 日本側の問題とは何か。それは野田内閣の交渉姿勢にあります。TPPの特徴のひとつは、TPP協定は、参加国に全参加国との間で平等に、最恵国待遇を持ち合うことが基本です。この明白な事実を承知していながら、野田内閣は、アジア諸国等との関係において、ISD条項を結ぶことは、「相手国との紛争を国際調停や裁判にかけることが、法的に保障されるので、日本にとって有利である」として、積極的にISD条項を結ぼうとしているのです。ちょっと待ってくれと、言いたいのはここです。アジア諸国とISD条項を結べば、それはただちに最恵国待遇として、米国との関係にも適用されるのです。これは危険極まりないことは、カナダやメキシコの例で明らかです。世界銀行は、米国の都合で動く機関です。米国経済が資本主義の世界経済に恩恵を施している時期には、適度に資本主義の発達しつつあった国々にとって、そこに不都合はありませんでした。しかし今は違います。世銀とセットになって語られ、こちらは欧州から専務理事が選ばれるIMFと共に、新興の工業諸国によって、改組の要求が突きつけられているのは、このためです。ですから、米国とのISD条項は結ばないことが必要です。韓国の李明博政府は、米韓FTA協定の締結に際し、サムスンやヒュンダイの利益を優先してISD条項の受け入れを決断、野党の激しい反対を受け、遂に国会での強行採決という手段に訴えて、強引に米韓FTAを批准しました。会議場に催涙ガスが播かれて話題になったあの事件です。韓国は、1対1の交渉で米国に押し切られたのですが、日本は多国間のTPP交渉ですから、豪州などと連携して、米国に対抗する手段があります。しかも経済力は韓国よりも格段に強く(今も実質青天井のスワップ協定を結んで、韓国ウォンの底割れを未然に防いであげています)、多額の米国債の保有国ですから、経済交渉では米国より強い立場にあるのです。それを生かさずに、自らISD条項を受け入れる愚は、避けるべきでしょう。 続く
2011.12.20
コメント(6)
-
続金正日死去
続金正日死去金正日総書記の葬儀は、28日に行なわれるようですね。そういう発表がありました。問題は、葬儀日程と共に発表された、葬儀委員会の名簿です。確かに、後継と目される3男の金正恩の名が、トップに読み上げられました。しかし葬儀委員長が誰かは、発表されませんでした。葬儀委員会のトップに名はきましたが、それで葬儀委員長が約束されたわけではありません。ワンマン社長が、後継指名をせずに逝去した会社などでは、誰が社葬の葬儀委員長を務めるかが、後継争いのポイントになります。「北朝鮮」のような国では、指名はあっても、それが浸透してない場合は、同じことが起こります。28歳の金正恩の場合、喪主になることは確実でしょうが、果たして葬儀委員長になれるのかどうかは、先ず最初の試金石になりそうです。若い彼が、古参の親戚縁者や父の側近、軍の幹部らを抑えて、葬儀委員長の座を射止めるのは、そう簡単なことではなさそうです。先ずは、葬儀がどういう形で実施されるかが、最初の抑えどころとなりそうです。
2011.12.20
コメント(12)
-
米軍施政下のコザ(沖縄)市で反米暴動 20日の日記
クロニクル 米軍施政下のコザ(沖縄)で反米暴動1970(昭和45)年12月20日41年前のこの日、米軍政下の沖縄はコザ市(現沖縄市)で、大規模な反米暴動が起きました。暴動のきっかけは、この日午前1時過ぎに市内の路上で起きた米陸軍医療隊員による交通事故でした。隊員運転の車輛が市民をはねたのです。幸い怪我は軽傷で済んだのですが、事故処理にかけつけた憲兵隊員が、怪我人をそのままにして加害者を連れ去ろうとしたところから、事故を知ってかけつけた市民と対立するところとなったのです。いかにも事故処理の仕方がまずかったのですね。日頃から、米軍兵士の横暴に鬱屈した感情を持っていた市民の複雑な感情が爆発したのは、自然の成行きだったと言えましょう。 応援要請を受けた憲兵隊は20人を派遣、群衆が投石すると威嚇射撃で応戦したものですから溜まりません。市民に銃を向けるとは何事と、激高した5千人に達する市民が、米軍車輛、嘉手納基地内の小学校・雇用事務所などに放火する騒ぎとなりました。 米軍は催涙ガス弾を使用し、双方合わせて約80人の負傷者を出し、市民20人が逮捕・連行される騒ぎとなりました。 68年11月の、最初の主席公選で当選した、屋良朝苗主席は激しく米軍に抗議し、参議院では、米兵犯罪に対する裁判権を日本側に移管すべしとする決議が採択されるなど、沖縄を巡って日本国内の反米感情は大きな高まりを見せ、事件の結果、本土復帰運動は最高潮に達しました。
2011.12.20
コメント(4)
-
金正日死去
金正日死去今晩は。午後からは金正日死去のニュースで持ちきりだったですね。職場でインターネットのニュースを見て知りました。今後の確実なことは、葬儀の日程以外には何もないのですが、「北朝鮮」(正式名称朝鮮民主主義人民共和国」)の政治体制が大きく動揺することは間違いないでしょう。私が何故そのように考えるか、祖の理由だけを先ずは記しておきます。それは、「北朝鮮」の建国以来の指導者であった、父金日成主席から金正日総書記がどのように権力を掌握したかです。マスコミは、1994年7月8日の金日成主席の死去と同時に、最高指導者の地位に着いた金正日が、その後3年にわたって喪に服したと語っていますが、変化の激しい国際政治の現実のなかで、まして国際的な立場の極めて脆し「北朝鮮」で、最高指導者が3年間も喪に服するなどということが、出来るわけがありません。94年に権力を継承したとされる金正日が、総書記の地位に着いたと発表されたのは、1997年の10月8日でした。金日成死去の3年3ヶ月後です。これは極めて摩訶不思議な事実で、息子が父の権力を継承することに、「北朝鮮」労働党内部や軍内に、かなり強力な反対勢力があり、長期に渡る権力闘争が行なわれていただろうことを示していると、私は考えています。死去した金日成も、息子の権力掌握の困難を意識していたのでしょう。彼は亡くなる20年近く前の1970年代後半に、自分の後継者が金正日であることを示し、「それは、息子だからではなく、党内で最も優れた指導者であるからだ」と、見え透いたことを発言しています。こうして金正日は、1974年には、33歳で政治局入りし、80年には政治局常務委員都なり、その後もトントン拍子に出世して、80年代半ばには、中央軍事委員会書記にも就任して、軍内での地歩も固めていました。これだけの機関をかけ、慎重に準備を進めてきた金正日後継についても、金日成死去後に3年3ヶ月の権力闘争が必要だったのです。27歳と、政治家としてはまだヨチヨチ歩きがやっとの金正恩に、果たして親父譲りの権謀術数が可能なのでしょうか。国内が政治的に未熟で、エリートの層の薄い国では、若い指導者が登場し、活躍することがあります。春に大きな政変のあった、エジプト共和国の英雄ナセルは、確かに30歳前から大きな活躍をしています。しかし、独裁国家とされますが、「北朝鮮」の国民は政治的経験は積んでおり、労働党や軍部の派閥や権謀術数は、その一部を知るだけでも大変なものがあります。しかも金正恩が後継と発表されたのは、昨年の秋ですから、権力継承の準備も緒に就いたばかり、実際はほとんど手付かずというのが現状でしょう。これで、無事に金正恩体制がスタートできると、皆さんはお考えになりますか?私は、それは難しいのではないか。これから朝鮮労働党内部と、軍部のなかで激しい権力闘争が起きるのではないかと、考えています。その過程で危険な冒険主義的行動が飛び出さないといいのですが…。権力闘争で敗色濃くなったグループの、一発逆転を狙った冒険主義的行動が、一番危険です。その点を注視する必要がありそうです。
2011.12.19
コメント(10)
-
第一次インドシナ戦争始まる 19日の日記
クロニクル 第一次インドシナ戦争始まる1946(昭和21)年12月19日65年前のことです。この日、フランス軍が、ヴェトナム軍に攻撃をかけ、ここに1954(昭和29)年5月に、フランス軍の拠点ディエンビエンフーが陥落するまで7年半に及ぶ、第一次インドシナ戦争が開始されました。ヴェトナム、カンボジア、ラオスのインドシナ3国は、19世紀の80年代以降、フランスの植民地とされてきましたが、1941年7月末から、仏領インドシナに日本軍が進駐、支配下においてきました。その日本は1945(昭和20)年8月15日に、ポツダム宣言を受諾して降伏しました。その時、主に米軍の力でドイツ軍の占領から開放されて1年しかたっていないフランスに、植民地占領軍を再派遣するするだけの力はなかったため、現地の日本軍は、ホー・チ・ミンらのパルチザンに武器・弾薬を渡して降伏したのです。ここに、ヴェトナム軍の編成を見たのですが、翌46年のこの日、ようやくこの地に派遣された部隊が、ヴェトナム軍との戦闘の火蓋を切ったのでした。
2011.12.19
コメント(2)
-
竹やりでちょいと突き出す2分5厘 19日の日記
クロニクル 竹やりでちょいと突き出す2分5厘1876(明治9)年12月19日135年苗の話です。三重県飯野郡(伊勢)の一部で18日に始まっ地租改正に反対する農民一揆は、この日伊勢地方全体に広がり、各地で区戸長の家屋敷をはじめ、支庁、警察、学校、郵便局などを襲撃しました。学校が入っているのが、いかにも当時らしいのですが、貧農たちにとって、6歳~10歳(当時の義務教育は4年間です)の子供達が立派に労働力だったことを示すエピソードです。この伊勢暴動は、地租改正の規準米価算定をめぐる(高めに設定すれば、地租は高くなります)県当局と農民の対立が爆発したものでした。同じ事情は各地にあり、西日本では,岐阜,愛知、堺(大阪)に、東日本では茨城,栃木などに拡大、全国化の兆しさえ見せ始めました。ここに政府は、多発する士族叛乱と農民一揆に挟撃されることを怖れて、農民層への譲歩を決断(何よりも、徴兵制に基づく兵士の中核が貧農だからです)、77年1月に地租を地価の3%から2.5%に引き下げました。「竹槍でちょいと(どんと突き出すという言い方もあります)突き出す2分5厘」と当時話題になりました。この地価ですが、当時において地価は土地が生み出す収益(この場合は米に換算した収穫高)の過去3年間の平均を20倍した額でした。平均利子率を5%で計算したのですが、当時は日本でも地価の計算に収益還元法を用いていたことが、ここから分かります。この方法は1810年代のプロイセン農民解放や、1860年代のロシアの農奴解放など、農民に有償で農地を分与する際に採られた方法で、日本も同じ方式を採用したことが分かります。土地バブルに踊り、夢破れた後で、明治の先例に戻りまたぞろミニバブルに踊ろうというのも何とも学習能力に欠けています。開いた口が塞がらないのは私だけでしょうか。話しを戻します。こう見てくると、3%は年間収益の6割、2.5%でも5割となりますから、農民の負担は極めて高く、一揆が起きるのも当然だったという感じを受けます。
2011.12.19
コメント(6)
-
日本の国連加盟実現 18日の日記
クロニクル 日本の国連加盟実現1956(昭和31)年12月18日55年前のこの日、国連総会は、日本の加盟を全会一致で承認、日本は80番目の国連加盟国となりました。1933(昭和8)年に国際連盟を脱退してから、23年振りの国際社会への復帰でした。日本は1952(昭和27)年にサンフランシスコ講和条約の発効で、占領状態を脱した直後から、国連への加盟を希望していたのですが、ソ連との間に平和条約が締結できず、国交も回復しない状態が続いたために、国連加盟に必要なソ連の理解が得られず、参加できない状態が続いていました。吉田内閣は、日ソの国交回復を急がなかったため、状況は改善しなかったのですが、54(昭和29)年に誕生した鳩山内閣は、日ソの国交回復に政治生命をかけるという、鳩山首相の強い決意で、この年10月に国交を回復、これが決め手となって、総会に先立ち新規加盟国について、総会への議案提出権を持つ安全保障理事会の採決で、議案の拒否権を持つソ連も賛成に回り、念願だった国連加盟が、ようやく実現したのです。
2011.12.18
コメント(4)
-
スミソニアン合意なる 18日の日記
クロニクル スミソニアン合意なる1971(昭和46)年12月18日あれから40年ですか、1971年は、ニクソンショックに揺れた年でした。月、翌年2月に中国を訪問するとの発表で、日本の政界に激震を起こし、約1ヶ月後の8/15には、金・ドル交換停止を発表して、戦後のブレトン・ウッズ体制(金とドルをリンクさせた金・ドル本位制)の終焉を告げ、世界に衝撃が走りました。各国が状況の落ちつくまで、為替市場を閉鎖した中、日本のみが1ドル=360円の管理為替相場の維持を狙ったのか、市場を開き続け、各国の投機業者に手持ちのドル売りと円買いの好機を与え続ける愚を犯したのです。しかし大勢に抗し難く、数ヶ月に及ぶ交渉の結果、この日、ワシントンのスミソニアン博物館で開かれていた先進10ヶ国蔵相会議において、ドルの大幅切り下げによる多国間通貨調整に合意、辛うじて固定相場制を続けることになりました。円は対ドルで16.88%の引き上げとなる、1ドル=308円に切り上げられることになり、20日から新レートが適用されることになりました。当時のマスコミの論調は、産業界の声を代弁したのか、輸出が大打撃を受け、大不況が到来するとの大合唱でしたが、これで輸入品が安く買える、必要な洋書が買いやすくなるからと、円高大歓迎だった私などは、もっと切り上げれば良いのにと、お気楽なものでした。ところでスミソニアン合意はつぎはぎの一時的なものに過ぎず、アメリカ経済にはドル中心の固定相場を維持する体力は既に無く、1年2ヶ月後の73年2月には、円は早くも277円を記録し、この値を始め値として、2/14から現在に繋がる変動相場制に移行したのです。この間、今日までの変遷で感じたことは、自国通貨が高く評価されることは、即ち国家の経済力の強さを示すものであり、基本的には良いことだ。円高は誇るべきことだと「いうことです。その証拠に100円を切るどころか、70円台に入っても、ちゃんと日本経済は持ちこたえているではないですか。来年には60円台突入があるかもしれません。
2011.12.18
コメント(4)
-
TPPとISD条項 ( 9)
TPPとISD条項 (9) 「米国と日本が関税同盟を結成し、自国が蚊帳の外になるのはまずい。」こう考える国が数多くある。日本のTPP交渉への参加表明は、アジアの国々やカナダにこのような焦りを呼んだようです。「日本がTPPに加わるなら、わが国も…」と考えた国が続々と名乗りを上げたのです。これは米国にとって願ってもないことでした。米国は、輸出で稼ぐことで、失業率を改善したいのです。TPP交渉への日本の参加表明は、米国にとって、大変喜ばしい反応波及効果を持ったのです。こうなると、米国としては、日本にぜひともTPPに参加してもらわないと困ることになります。日本が不参かなら、不参加の国も多くなります。国外市場は広いほうが良いですから、日本が強気の交渉を貫けば、米国の譲歩を引き出すことは、十分可能であるように、私は考えています。しかし、ここにも問題があります。 続く
2011.12.17
コメント(2)
-
ペルー大使公邸人質事件発生 17日の日記
クロニクル ペルー大使公邸人質事件発生1996(平成8)年12月17日もう15年になるのですね。15年前のこの日、ひとあし早く平成天皇の誕生日を祝うパーティが、ペルーの日本大使公邸で開かれておりました。ペルーの名士や日本関係者らが集う中、反政府ゲリラ、トゥパク・アマル革命運動(MRTA)所属の14名のゲリラの襲撃があり、多数の参会者が人質となる事件が発生しました。人質との交換で拘留中の仲間の釈放が要求されました。体調の悪い方など、1部の人質は解放されましたが、それでもなお72名の方々が、人質生活を余儀なくされたのでした。日本政府は人質の人命を最優先するとことを、強くペルー政府に要請、アメリカ政府は人質に犠牲が出ることなど厭わず、強硬突入でゲリラを掃討することで、人質を解放することを求めました。 当時のペルーにとって、日米両国は共に重要な援助国であったため、ペルー政府が両国の顔を立てるために打てる手は解決の先送り、時間稼ぎしかないことは、予測される筋書きでした。 少し頭を使えば,この現実は想像出来ることでしたが、当時の日本のメディアは、すぐに解放しうるものという立場からの論調に終始し、事態を冷静に判断する事が出来ずに、情緒的判断を下す事しかしませんでした。 結局、事件が解決したのは、発生から127日後のことでした。ほとぼりの冷めた頃、ゲリラの油断を見澄ましての、強行突入による解放でした。日本人人質には死者はなかったのですが、ペルー人人質1名と突入した特殊部隊の隊員2名、ゲリラ14名と、合わせて17名の死者がでたことは、忘れずにいたいものです。
2011.12.17
コメント(12)
-
TPPとISD条項 (8)
TPPとISD条項 (8) 現在の米国中心のTPP交渉に、日本が加わることの利益は、日本よりも米国にとってはるかに大きいのです。日本の輸出企業の多くは、日米貿易摩擦や1970年代以降の円高の継続で、とっくに対米侵出を果たし、対米輸出関税がゼロのメキシコにも進出しています。ですから、TPP不参加の実害は、ごく僅かなのです。逆に実質的に日米FTAに近いとされるTPPに、日本が参加するメリットは、米国にとっては、対日輸出を増やす良いチャンスになります。輸出増によって、雇用の改善に繋げたいオバマ政権は、何としてもTPPに日本を引き込みたいと、あの手この手を尽しているのは、このためです。日本にとってのメリットは、日本がTPPに参加することで、対日輸出の面で米国(対日輸出関税がゼロまたは低率になります)に比べて不利になるライヴァル国が、TPPに加わるか、対日FTAの締結に積極的になることです。中国やカナダにその徴候ははっきり出ていますし、アジアの国々の姿勢も、対日貿易で不利益を蒙りたくないと、変わってきています。これはTPPがさらに拡大し、太平洋に面する国々のほとんどを網羅する、大ブロックに成長する可能セを示しています。これは米国にとっても、大きなプラスです。まさに日本サマサマと言えましょう。日本のおかげで参加国が増え、米国商品が無関税かそれに近い形で輸出できる国々が増えるのです。ですから、米国にとって日本は手放したくない国なのです。この足元に付け込まない手はありませんね。 続く
2011.12.16
コメント(2)
-
バングラデシュ誕生 16日の日記
クロニクル バングラデシュ誕生1971(昭和46)年12月16日今日が、誕生から40年目の記念日なのですね。私の学生時代の世界地図にはバングラデシュという国はなく、インドの東西に別れて、東パキスタンと西パキスタンと呼ばれた2つのパキスタンがありました。しかし、やがて東西の折り合いの悪さが目立つようになり、この年71年には完全分離による独立を求める東パキスタンと、そうはさせまいとする西パキスタンの争いが勃発、東パキスタンはバングラデシュ独立戦争を起こしたのです。ここにパキスタンの弱体化を望むインドが介入し、12月3日に第三次印パ戦争が勃発したのです。この戦争はインド優勢のうちに進み、この日西パキスタンが東の独立を認めたことで終結しました。そして、この日の内にバングラデシュは独立国として、誕生しました。しかし、ガンジス川の流れに沿うバングラデシュは、なおアジア並びに世界の最貧国の一つとして、苦しんでいる状態にあります。
2011.12.16
コメント(2)
-
日本橋白木屋で本邦初の高層ビル火災発生 16日の日記
クロニクル 日本橋白木屋で本邦初の高層ビル火災発生1932(昭和7)年12月16日79年前のことです。この日、日本橋の白木屋百貨店(居酒屋の白木屋ではないですよ…)で日本で初めての高層ビル火災が発生、日中のことでしたから、大勢の来店客が高層階の窓から飛び降りるなど、大変な惨事になりました。死者14名、重軽傷者130余名と報告されています。 この時期は、まだ夫人の肌着は長襦袢が一般的で、今日のような肌着は着用されておらず、そのため婦人客の多くが飛び降りるのをためらったために、被害は余計に婦人層に集中したことが指摘されています。その結果、この事故の副産物として、以後婦人下着(特にズロース)が急速に普及するようになったと指摘されています。 ところで、白木屋は戦後,昭和30年代に乗っ取り屋の横井英樹氏の株買占めにあい、やがて、東急の傘下に入り、東急日本橋店と名を変えましたが、バブル崩壊後の不況期に売上げ不振から閉鎖されました。
2011.12.16
コメント(14)
-
TPPとISD条項 (7)
TPPとISD条項 (7) FTAは自由貿易協定と訳され、貿易自由化の到達点のように言われますが、ちょっと視点を変えてみると、全く別の風景が見えてきます。我々はともすると、FTAの当事国の視点或いは日本なら日本の視点でのみ、この問題を考えがちです。ですが、今A国とB国がFTAを結んだとします。これをc国やD国、E国から見るとどう見えるでしょうか。A国とB国の間だけは、関税障壁は取り払われているか、大変低い関税率になっていますが、2国以外の国との貿易は、相変わらず元の関税のままです。C,D,Eの国々にとって、A国とB国の周囲は高い関税障壁で囲われてしまっているのです。1929年に始まる世界恐慌の時代に、イギリスやフランスが植民地・従属国と自国とを糾合して、周囲を関税障壁で囲んだブロック経済と、FTAは同質のものなのです。2国や3国の間だけを囲うのが違っているだけです。TPP(環太平洋パートナーシップ協定)は、これを10ヶ国で、日本が加わると11ヶ国出実行しよう、貿易のみでなく、もっと幅の広い経済的連携を目指して、非関税障壁をも撤廃してしまおうという計画ですから、まさにかつてのブロック経済の拡大版そのものです。ということは、ブロックに加わらないと、ブロック内の国との貿易において不利になることを意味します。日本が参加を表明する以前の段階では、TPPに消極的ないしは否定的だった中国や東南アジアの国々、1度は参加を断念したカナダなどが、日本が交渉参加を表明した途端に、今までの態度を転換して、TPPへ参加の意欲を表明し始めたのは、まさに対日貿易で不利益を蒙るのは避けたいという意志の表れなのです。世界の国々にとって、日本との貿易はそれだけ重要な意味を持っているのです。 続く
2011.12.15
コメント(2)
-
ウルグアイ=ラウンド合意 15日の日記
クロニクル ウルグアイ=ラウンド合意1993(平成5)年12月15日18年前のこの日、ガット(関税・貿易一般協定)のウルグアイラウンドが、ようやくのことに合意に達し、日本はコメの部分的市場開放に踏み切りました。「コメ市場は開放しない」と言い続けてきた日本政府と農林水産省(当時)は、当初の関税率は200%や300%でも認めると説得され、工業製品の関税率の引き下げで、最も利を得る立場から拒否し続けるわけにいかないと、ようやく重い腰をあげたのでした。そしてその数年後後、高い関税率を維持するなら、最低限度の米輸入を義務付けられる年限に達し、工業用に利用するか、倉庫に積んでおくしかない米を、お金を払って輸入するという馬鹿げた政策をとるようになり、今に至っています。倉庫の保管料も嵩むのですが、長期の保管で黴の生えた事故米を、工業用として超安価で買い入れ、それを煎餅などの加工食品会社に横流しして儲けていた業者が登場、社会問題になったのは、皆さん御存知の通りです。
2011.12.15
コメント(4)
-
全国の製糸業者一斉休業へ 15日の日記
クロニクル 全国の製糸業者一斉休業へ1929(昭和4)年12月15日米国発の世界恐慌が始まった82年前のことです。この日から、日本全国の製糸業者は2週間の一斉休業に入りました。中小の業者を含めて、全国の業者が一斉に休業するのですから、業界団体の力で出来ることではありません。商工省(現在の経済産業省)の音頭取り、強力な指導で実現したものです。 米国発の世界恐慌は、10月末に姿をあらわにしたばかりでしたが、世界的な生糸相場の下落はとどまるところをしらず、この日からの一斉休業入りとなったのでした。年末年始の正月休暇を経て、1月4日に生産は再開されますが、生糸相場は回復せず、05年4月には、家族主義的経営で知られたカネボウ(8年前に話題になったあのカネボウです。当時鐘淵紡績)までが、大幅な賃金削減に(実質23.6%の削減と報じられました)踏みきりましたが、解雇でなく賃下げで対応するのは、さすがカネボウ、超優良企業の名に恥じないと評価されたと言いますから、当時の経済状況の深刻さが偲ばれます。
2011.12.15
コメント(6)
-
TPPとISD条項 (6)
TPPとISD条項 (6) リーマンショック後の米国経済は、長期不況の呪縛に絡められ、簡単には抜けられない状況にあります。南欧諸国の財政危機から、ユーロ圏の危機に世界の眼が集まっていますが、この危機は、リーマンショックを含む米国経済の危機が、ユーロ世界にまで拡大したものに外なりません。決して米国の状況が大きく改善したわけではないのです。財務省とFRBがタッグを組んで、あれだけ湯水のように、市場にドルを垂れ流しているにも関わらず、辛うじて底割れを防いで、長期横這いを続けている。米国経済はこんな状況にあります。この現実を一番明確に示しているのが失業率です。第二次大戦後しか調べていないのですが、第二次大戦後の米国で、失業率が7%を越える状態が2年以上続いているのは、サブプライムショックに始まる今回だけです。今回の不況では、サブプライムローンの危機が顕在化した2006年後半から、失業率は7%を越え、それが現在も続いているのです。クリスマス商戦の出足が好調で、商店が軒並みパートの売り子を増やした効果で、11月は失業率が改善したそうですが、それでも失業率は8,6%なのです。現在の米国は、まさに90年代の日本と同じ、長期不況の泥沼にあります。当然、この状態で国内の消費が大きく改善するとは考えられず、オバマ政権もFRBも、海外市場の開拓によって、米国の雇用を改善しようと考えたのです。米国がTPPに突然熱心になった背景は、ここにあります。つまり米国はかなり焦っているのです。攻め手がないわけではないのです。 続く
2011.12.14
コメント(2)
-
石橋湛山総裁誕生 14日の日記
クロニクル 石橋湛山総裁誕生1956(昭和31)年12月14日 55年前のことです。この日行われた自由民主党総裁公選において、石橋湛山氏が第2代総裁に選ばれました。 前年11月15日に、自由党と民主党が保守合同成し遂げ、鳩山一郎民主党総裁兼首相が初代総裁に就任しました。鳩山総裁は日ソ国交回復を花道に辞任することが確実視され、後任には旧自由党総裁にして、当時自民党副総裁の緒方竹虎氏の就任が確実視されていました。ところが緒方氏がこの年1月28日に、急性心不全のために急死されたため、総裁レースは混沌とした情勢になったのです。ここに後継総裁レースは混沌とし、岸信介、石橋湛山、石井光次郎(シャンソン歌手の石井好子さんは、ご令嬢です)の3氏の争いとなりました。総裁レースは、札束乱れ飛ぶ猛烈な票の奪い合いの中、週刊誌の命名したニッカ(2つの陣営から金をもらう議員)、サントリー(3派全てから金を受け取る)の語が流行する中、この日早暁、石橋、石井両派の会合で2,3位連合の密約が結ばれたのです。資金力に勝る岸氏優位の情報の中、両派は激しい2位争いを演じて票を伸ばし、第1回投票で1位となった岸氏の票は、過半数には届きませんでした。こうして2位となったた石橋氏との決戦投票が行われ、石橋氏が岸氏に逆転勝利して、第2代自民党総裁に就任したのです。しかし石橋氏は首班指名を受け、閣僚も任命し、内閣をスタートさせましたが、病に倒れて国会での所信表明演説に立つことが出来ず、2ヶ月で辞意を表明、札束飛び交う総裁選への世論の批判も強かった事から、岸氏への禅譲を発表したのです。こうして57年2月に岸内閣の誕生を見るのです。警職法改正案(後廃案)の上程や60年安保の混乱を招き、超重要法案の安保改訂案の強行採決など、日本憲政史に悪名を残した岸内閣はこうして誕生しました。
2011.12.14
コメント(2)
-
民事再生法成立 14日の日記
クロニクル 民事再生法成立1999(平成11)年12月14日12年前のことです。97~98年の金融危機の余韻が残り、大型倒産の噂が耐えない頃のことです。そんな中のこの日、民事再生法が参院で可決成立しました(施行は、翌年4月1日)。この法は、全債権者の合意を必要とした和議申請(和議法)に代わる、再建型の倒産処理手続きを定めたもので、経営責任を厳しく問わないところから、経営者が選択しやすい反面、経営者のモラルハザードを助長するとして、マイナス面も指摘され、評価は二分されました。
2011.12.14
コメント(4)
-
TPPとISD条項 (5)
TPPとISD条項 (5) 世界銀行傘下の裁定機関は、米政府や米企業の手前勝手な主張を認める機関です。公平な判断など、ハナから期待できません。日本の健康保険制度、国民皆保険制度が、米国の保険会社にとっての参入障壁になっていると認定し、その廃止を命じる判断が出される可能性は、否定できないのです。牛肉を含む農産物の規制撤廃は、買う買わないの選択権が我々にありますから、消費者にとっては選択の幅が広がるだけで、実害はありません。実は米国産の方が、日本産よりも安全なものも沢山あります。国産牛乳は成長ホルモンの使用を禁じられておらず、その表示義務もないのですが、米国では発がん性との関連して、使用表示義務が科されていますから、米国産牛乳の方が、日本産よりも安全だという具合に…。食品や薬品ではこうしたこともありますが、医療保険を巡っては、日本にプラスになることは何もありません。要するにISD条項については、純粋に公平な裁定機関を見つけ、そこの判断を仰ぐのない限り、結ぶべきではないと私は考えています。世銀傘下の裁定機関は、米国寄りの判定に偏っていますから、裁定機関から外すのでない限り、ISD条項は受け入れるべきではありません。実際にオーストラリア政府は、ISD条項の導入は拒否する姿勢をとっています。米国以外との関係に有利だとしても、米国との関係でのマイナスは大きすぎます。オーストラリアと組んで、ISD条項抜きのTPPになるのであれば、私はTPPへの参加に賛成ですし、交渉次第で米国が折れる可能性は十分あると考えています。明日は、その辺を記そうと思います。 続く
2011.12.13
コメント(4)
-
地方公務員法公布 13日の日記
クロニクル 地方公務員法公布1950(昭和25)年12月13日61年前のことです。日本政府(吉田内閣)は、この日地方公務員法を公布しました。この法は、地方公務員と公立学校教員の政治活動並びに争議行為を禁止するもので、国会審議でも揉めましたが、その後も長く、働く者の基本的人権との整合性を巡って、大きな政治的、思想的な争点となりました。スト権を巡って、ストの度に大きな争点になったのですが、80年代以降、ストらしいストが見られなくなり、何時の間にか、あれだけ喧喧諤諤と賑やかだった問題も風化してしまいました。今や無風ですが、それがよいことなのかどうかは、判断の分かれるところです。
2011.12.13
コメント(2)
全84件 (84件中 1-50件目)