[加藤周一] カテゴリの記事
全62件 (62件中 1-50件目)
-
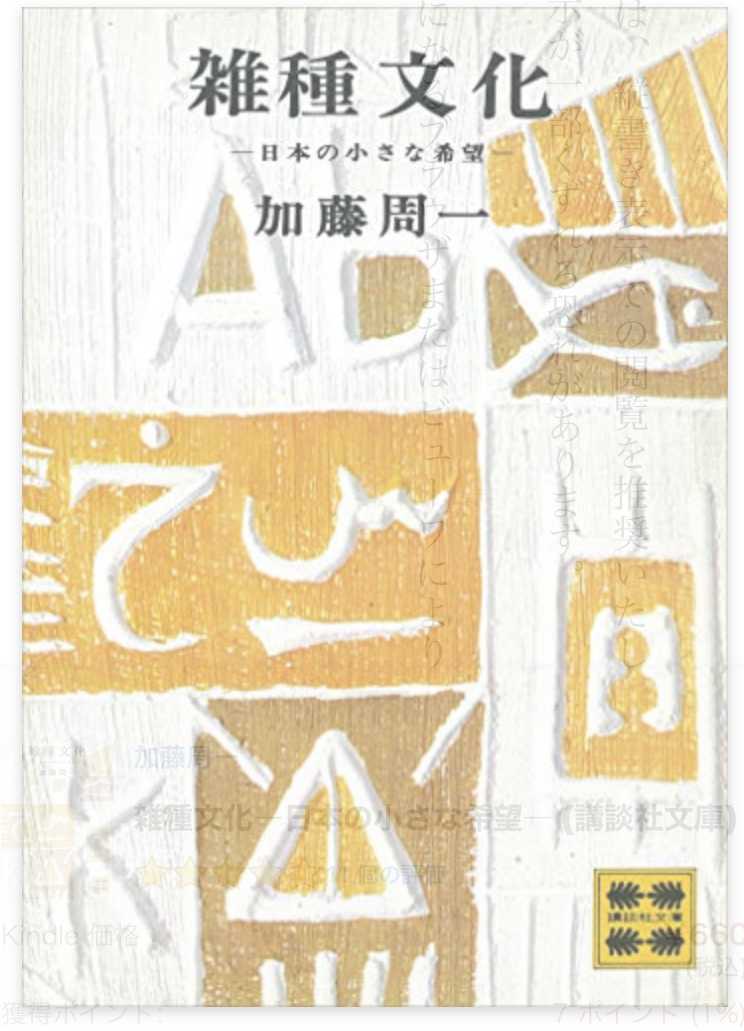
書評 加藤周一の「雑種文化」
「雑種文化 日本の小さな希望」加藤周一 講談社文庫加藤周一という「知の巨人」がいた。現代日本に「思想家」という冠をかけ得る人がいるとすれば、私は先ずこの人を挙げなくてはならないと思っている。思想家とは(1)その思想が生涯に於いて首尾一貫していること(2)その思想が独創的で且つ社会に多大な影響をもたらしたこと。コレを、私は「思想家」の定義にしている。よって、思想家とは、テレビに出ている(東大出の)有象無象のコメンテーターのことではない。思想家とは、竹中平蔵のようなマヌーバーのような理論で以って政界に(ひいては日本社会に)多大な(悪)影響を与えたような人物でもない。よって、吉田松陰は思想家ではあるが、その弟子の何人も政治家ではあったが遂には思想家たり得なかった。木戸孝允然り、伊藤博文ならば尚更。また、いっとき戦後思想界を牽引したと言われる丸山真男と清水幾太郎のうち最後まで自らの思想を進化させていった丸山は思想家だが、安易に保守に寄り添った(転向した)清水は思想家ではない。反対に一般的には無名だが、戦中戦後を通じて日本的唯物論を論じた古在由重は重要な思想家である。閑話休題。没後13年。これから日本思想史に位置付けが始まる加藤周一の代表作を再読した。かと言っても、本書は加藤周一の論文集であり、日本の雑種性を正面から論じた文章はごく短い。また、私は幾つかずっと疑問があった。そのことを含めて、この機に探ってみたい。「日本文化の雑種性」(「思想」1955・6)⚫︎「伝統的な日本」と「西洋化した日本」で分けて考えると、「日本文化の特徴は、その2つの要素が深いところで絡んで容易に抜け難いところ自体にある。←これが加藤周一の「雑種文化論」の概要である。なんだ、当たり前のことじゃないか、と考える人は多いだろう。加藤周一がこれを堂々と論じてはや半世紀以上。誰もが堂々と言えるようになったことが、改めてこの論文の影響性のひとつかもしれない。もちろん加藤周一は「西洋化」だけを問題としていない。「神ながらの道」があった古代に「仏教化した日本」も同じように、「二つの要素が深いところんで絡んで」いるのは、私たちが日々実感するところだろう。⚫︎ キリスト教圏の外で、西欧の文化がそれと全く異質な文化に出会ったら、どういうことがおこるか、それが日本文化の基本的な問題である。←雑種化は多くが認めることになった。実際加藤以前にもそのことを論じた人はいた。では、雑種化そのものは、未来の日本にどういう意味を持たせたら良いか?という問いかけをしたのは加藤周一の「独創」だった。そのためには、加藤周一は、もう一編文章を書いて寄稿する必要があった。「雑種的日本文化の希望」(「中央公論」1955・7)西洋文化が日本に入って雑種化した時に、何が残って何が残らなかったか、それが雑種化の「意味」のひとつになると加藤周一は言う(戦後民主主義の不可逆性)。もう少し具体的に言うと西洋伝来の民主主義という考え方、『「社会科教育を受けて成長した子供」「選挙権と教育を含めて原則上の男女平等を得た女性」「土地を得、得たことを当然と考えはじめている農民」「訓練された組織労働者」「戦前よりも世界情勢に敏感になった知識人」』これらのことは「ものの考え方や感じ方の変化がおこって容易にもとに戻らぬものがあるだろう」と加藤周一は分析している。←それから67年が経った。このうち「組織労働者」だけは大きな後退が起きた。しかし、戦前までは後退してはいない。「子供たち」はまた別のステージに上がっているだろう。非キリスト教的世界でのヒューマニズムの発展が、文化の面、特に思想・文学・芸術の面でどういう形を取り得るかという見通しを立てることは、この当時の中国・インドの問題ではなく、日本の問題であった。加藤周一は、そこに日本の雑種性の「小さな希望」を見出している。近代的合理主義の背景に、「プロテスタンティズムの倫理」を日本に求められないとすれば、何がその思想を支えるのか。朱子学にしろ、実存主義にしろ、日本人の民衆の根に降りはしなかった。マルクス主義「のみ」が、「西洋伝来のイデオロギーを日本の大衆の道具に使おうとした」。しかし外国で既に出来上がった型を輸入したために「日本の特殊性に応じたイデオロギーの型を生む」には至っていない。という。「それ」はどうしたら生むのか。以降、いろいろと述べているが、実は「日本の特殊性に応じたイデオロギー」「小さな希望」は何処にあるのか。遂には具体的には語らなかった気がする。ただ、雑種文化だからこそ、優れたものを生み出す可能性がある。そのことまで言及した人は、加藤周一だけだったことは強調するべきだと思う。1974年「文庫版あとがき」‥‥私がここで言おうとしたのは、現代日本の文化の雑種性に積極的な意味を認めようではないか、ということと、対外的には、排他的でもなく、外国崇拝でもなく、国際社会のなかでの日本の立場を、現実に即して、認識しようではないか、ということであった。1974年、加藤周一は既に「日本文学史序説」を著し始め、日本文化の姿の全体を明らかにしようとした。しかし、「現実に即して」どういう「日本の特殊性に応じたイデオロギー」を用意するのが、国際社会での生きる方向なのかは、遂には著さなかったように私は思う。←それで良いよね。いま、「特殊なイデオロギーがないこと」もしかしてそれこそが日本の生きる方向なのかと、これを書きながらふと思った。あ、「ずっと思っていた疑問」について、展開できていないですよね。なんか、ぐだぐだした文章になっています。昨年の夏から書き始めて、途中放り投げ、また書き始めたので、こんな感じになっています。つまり、今回再読してもハッキリわからなかったんです。かつて高校生の時に梅棹忠夫「文明の生態史観」で、日本の地政的な立場がアジアよりも西欧的な文明化への道を歩もうとしている、という「わかりやすい説」に私は影響されました。大学時代に加藤周一はそれを明確に批判した文章を読み、生態史観を卒業しました。小松左京の「未来学」を読んで、じゃあ日本の未来の青写真はどうなのか、と青臭い青年は未来が気になって仕方なかったのも、この頃です。マルクスの「共産党宣言」を読んで、「日本型の革命」は何なのだろう?と思ったのも、この頃です。柳田國男は「日本人の本性は事大主義である」という。そんな日本人の何処に希望があるのか?と思い、民俗学の講師と夜を徹して討論したのもこの頃です。その中で、「いま・ここ」主義の日本の文化を、国際的視野と歴史的知識で眺めながら半世紀論じ尽くした加藤周一の言説に、その「回答」があるのではないかと、ずっと約40年間思ってきた私です。加藤周一の著作に手をかけて登って眺めてみたら、未来を見渡すことができるのではないか?有為な若者だった私も、少しは何か役に立てることができるのではないか?とずっと思っていた。青年老い易く学なり難し。むしろ、終わりが見えてきた。あと10年で、形を作りたい。未だよくわからない。もう少し再再読してみたいと思う。
2022年01月18日
コメント(1)
-

日本のドラッカー?いえ「心学」は靖国派の雛形です「都鄙問答」
「都鄙問答」石田梅岩 加藤周一訳・解説 中公文庫 この春、突然「日本の名著」シリーズに入っていた加藤周一訳・解説の「富永仲基・石田梅岩」(1984)の半分が文庫本になった。何故今なのか?何故本来加藤が好きだった富永仲基ではなく、こちらの方を復刊したのか。 帯を読めば、編集者は本気で現代に石田梅岩を再評価させたいと思っているようだ。もしかしたら、渋沢栄一ブームを見越してのことかもしれない。 曰く 「ウェーバー、ドラッカーよりも200年早い経営哲学」 「起業家必読」 「生産と流通の社会的役割を評価、利益追求の正当性を説いた商人道の名著」 とのことである。 石田梅岩1744年没。中百姓次男として生まれる。11歳で丁稚奉公、商家としては成功しなかったが、「心学」を唱え(1738「都鄙問答」)、死んでその教えは隆盛し、商家のみならず大名家老が修行するに至り、19世紀から幕末にかけてあらゆる階層に浸透した。 確かに、「心学」の全面的な現代語訳は他にないだろうし、親切丁寧な加藤周一の解説も現代に貴重だろう。確かに、私も加藤周一の隠れていた名論考がリーズナブルにポケットに入るようになったのは貴重だと思う。しかし、編集者は気がついていただろうか?本書は、かなり厳しい「石田梅岩批判」なのである。心学の特徴を全面的に紹介することは、同時に心学の持つ理論的な矛盾を突くことになるのだ。 加藤周一の論理展開は、少し専門的でかなり緻密なので出来うるならば手に取って読んで欲しい。申し訳ないけど、私は関心部分のみ感想を述べたい。因みに、加藤解説→翻訳本文の順番に読むことをお薦めする。 ⚫︎梅岩は儒教の古典の章句を引いて、商家の日常の具体的な例に即して語った。それが今までの儒家とは違った。 ⚫︎梅岩は問答を行った。本書で学者が(私流の解釈です→)「真理は不可知なのだから、孟子が性善説を言うのは、善でもあり悪でもあるということと同じことじゃないですか?つまり孟子のいう天(真理)は何とでも解釈できるのではないか」と質問すると、梅岩は「キチンと古典を読め」「天はある。それは修業しなくては得られない」と答えて一蹴している(106p)。なかなか突っ込んだ質問が多くて面白い。←もっとも、加藤は「だから大事な部分は全て悟りに集約されて、論理の飛躍、矛盾は無視されている」と根本的な批判をしている。つまりトンデモ宗教(学問)なのだが、問題はこれが幕末の保守層に多大な影響を与えていることだろう。 ⚫︎「神儒仏トモニ、悟ル心ハ一ナリ」は、梅岩においては三教一致の主張ではなく、「悟ル心」から見れば、神・儒・仏の一致、不一致などは、二次的な問題に過ぎないという意味の感慨ではなかったか。この典型的な日本人は、天地自然と自己との一致という経験を支えとしながら、現世において、与えられた集団の中で、いかに生くべきかという問題に専念したのであり、その経験から出発して概念的な建築をつくり、そうすることで現世を、または自己の所属する集団を、超越しようとはしなかった。 ⚫︎現実の中で義理と人情が対立するときは、義理の方が優先させれることが多かった。(略)日本人が自己の内部と外部の世界との緊張関係に究極的な解決を望むときには、梅岩流の解決に近づくことが多いようである。(←義理と人情を秤にかけりゃ義理が重たい渡世の掟) ←それでも解決しない時には、加藤周一はマルクス主義の教条主義、あるいは本居宣長の「神ながらの道」を選択するだろうという。どちらも、結局大きな失敗をした。とくに、超国家主義は本居宣長流を継承したが、説明つかなくて破綻した。現代、「日本会議」や靖国派などの超国家主義がこれと同じ概念構造を持っているように思えるのは、私の穿ちすぎだろうか?政府閣僚の圧倒的多数が「日本会議」の信者になっているのは偶然だろうか?
2021年08月15日
コメント(0)
-
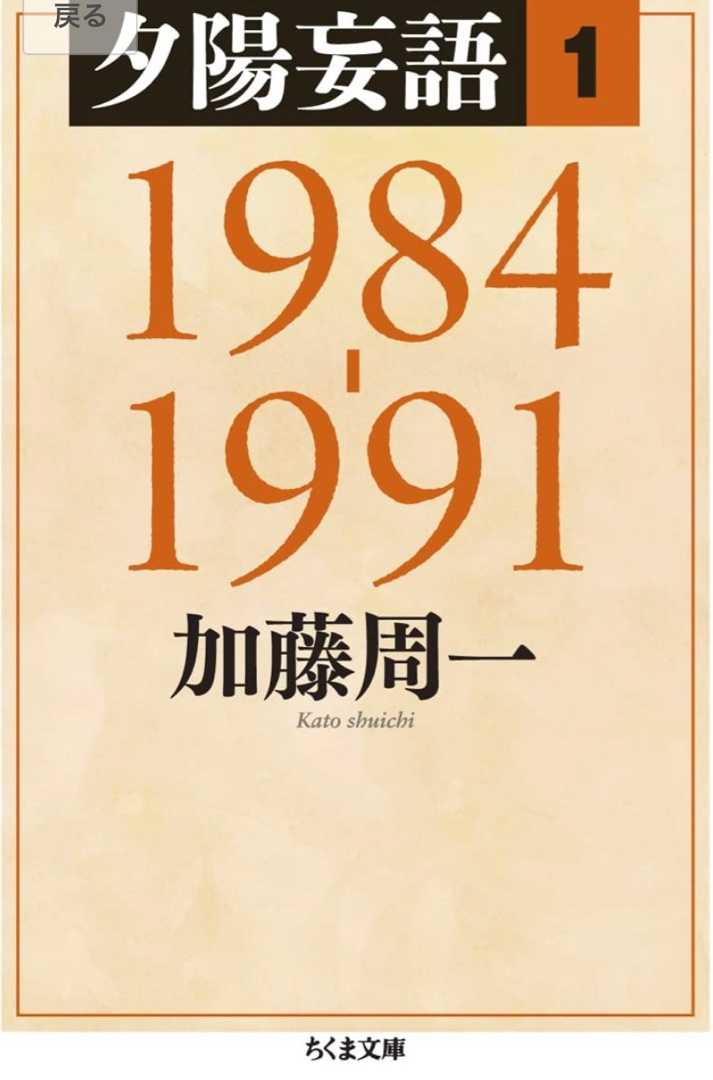
加藤ならば、どうコメントしたか「夕陽妄語1」
「夕陽妄語 1」加藤周一 ちくま文庫 加藤周一は、昭和・平成をまたがり「日本を代表する知性」と呼ばれていた。その加藤が、50年代から数えると約50年以上「時評」を描き続け、08年に自らの死亡によって終わるまで延々と書いていたのだから、時評に並々ならぬ情熱を持っていたのは間違い無いだろう。自らを「非専門の専門家」といい、文学評論家の枠に収まらない批評活動をしていた全体像が、このまとまった「夕陽妄語」全3巻(84年ー08年)の中にあるだろう。これはそのうちの一巻目。 話題は文学はもちろんのこと、文明遺跡、演劇、音楽、映画、国内と国際政治、歴史一般に及ぶ。古今東西の総てのイシューを関連つけて、一つの説得力ある言葉を提示する。実は、私に最も影響を与えている思想家である。それに、加藤周一論をまとめることは私のライフワークなのだ(別の言葉で言えば、約35年間まとめ切れていない)。 当然「夕陽妄語」は、単行本時点で一度読んでいて、所蔵している。というか、月一度の朝日新聞掲載時点で一読している。今回取り寄せたのは、一覧の便利さということもある(この文庫本 1は朝日新聞社版3冊を合本している)。それ以上に現代に、もう一度読んでおきたかったからである。 加藤周一不在の、12年間。いったい何度「彼ならば、この混迷の日本と世界に、どうコメントしただろうか」と思ったことか。安倍政権の暴走、トランプの登場、パンデミック、等々。 加藤周一の文は、元医者らしく、病状を細かにつぶさに観察した後に、文学者らしく物事の本質を表現する言葉を見つけ出す。現代に「夕陽妄語」を読むことは、十分に意味のあることだった。「どうコメントしたか」その回答は、此処にあったからである。 以下その視点で、マイメモとして感銘受けた部分を載せる。そういう位置付けなので、興味ある部分だけお読みください。 ・敦煌を見学すると、時間・空間の解放性が特徴である(釈迦涅槃像の過去仏と未来仏、そして国際性)。一方、日本の法隆寺の時空は「今・此処」に向かって収斂する。(84年9月) ←加藤の日本文化論の中心をなす「いま・ここ」論の、最も早い時期のまとまった考え。 ・45年の夏は軍国日本の終わりだった。85年の夏は軍国日本の復活の年として記憶されるかもしれない(GNP1%枠外し、公式参拝、機密保護法案)。(85年9月) ←中曽根時代の話だが、思えば新軍国日本の中興の祖として安倍時代は記憶されるのかもしれない(非核三原則外し、第一次内閣時代の教育基本法改悪、共謀罪・安保法制)。加藤のいうように、何れも共通の特徴がある。(1)提案者が政府・与党(2)説明がよく見ても不分明、わるくみればすり代えであること(3)違憲の疑いが強いか、少なくとも憲法の背景にある価値観と矛盾する行動・政策・法案であること。‥‥政府の行動規範は30年経とうとまるきり変わっていない。加藤周一は戦後40年の85年の夏に明確に危機感を覚えていた。その時から、国民が国会を10万人以上で包囲する(15年安保法制)まで30年を経なければならなかったのである。 ・いかん、ちょっと詳しく解説しないと意を尽くせない。上記の解説も説明不足だろうと思う。書き出せばキリがない。以下は項目だけ載せる。 ・日本ナショナリズムの可能性(86.3) ・いじめの分析(86.5) ・南京大虐殺に関して「歴史の見方」(86.8) ・白馬は馬にあらず。(87.1) ←そう、白馬は馬ではないんですよ。えっ?わからない。でも政治家は、このように誤魔化すんです! ・野上弥生子日記の1937年盧溝橋事件について書いたことは、「50年前の世界での常識、日本国内での極めて少数意見であった」(87.5) ・日本における「反ユダヤ主義」の生まれる5点の背景(87.6) ←これは、そのまま日本の中国・韓国・北朝鮮観と一致する。 ・「化けて出てくれ」(87.8) ←加藤の幽霊論の嚆矢 ・井の中の蛙論である。歌麿の春画、元号論、貿易摩擦、対中、対ソ政策に関連して述べる。(87.11) ←特に、江戸時代の規範は、閨房の中にまで及ばない。という指摘に「おゝ今もだ!」と思った。 ・宣長について。宣長が晩年写経を繰り返し、墓も神道墓の他に仏式墓を作ったのは何故か?(88.3) ←加藤周一の晩年の入信問題とリンクするのではないか? ←加藤周一は「歴史の複雑な二面性を問題にする条件」とは「勇気ある理性」と答えている。蓋し至言なり。 ・「黒い穴」(88.10) ←アメリカからの帰国途中の思考。西洋思考と日本思考との比較。悲しいほどに何も変わっていない。 ・1988年の思い出に加藤は高畑勲「火垂るの墓」を選んだ。(88.12) ・天皇の死去を「崩御」とはもちろん書かなかったが、「逝去」とは書いた。ほとんどはタイについて書いて、最後の行でそのことに触れた。(89.1) ・激動の89年の終わりに、加藤周一は政権交代を望んでいる。その可能性があったからだろう。それは、90年代型の政権交代ではなく09年型の政権交代ではあったのだが。(89.12) ・90年初めの総選挙では、自民党が多数を取った。そのことへの違和感を加藤周一は、3点に分けて解説する。思うに、現在でも充分通じる分析。(90.4) ・此処での加藤の「外交の季節」を読めば、この30年間北東アジアでの平和外交(ソ連・中国・朝鮮半島・日本・米国を含む集団的安全保障機関が機能し、地域の非核戦力化と経済的な協力関係が発展すること)が進まなかったのは、日本の責任が非常に大きいとわかる。(90.6) ←「ソ連の脅威」がなくなれば「日本の軍備拡大」の理由がなくなる。←しかし、「北朝鮮の脅威」を唱えて無くならなかった。 ←朝鮮半島に何もできない理由を2つあげている(1)国交を持っていない(2)過去の植民地政策について、韓国側から要求されての「謝罪」ではなく、自発的に、南北朝鮮の人民の大多数が納得しうるような責任の取り方をしていない。 ←加藤はこれからは「外交の季節」がやってくる。そのための障害の大部分は国際情勢ではなくて、日本側の習性や惰性であり、それを変えることは困難だろう。と喝破する。 ←ホントその通りになった。「しかしその困難は、決意さえすれば乗り超えられるはずのものだから、あまり悲観的でもない」←加藤さん、30年間決意できていないんですよ。 ・野間宏追悼文、情と理に溢れて名文。(91.1) ・「湾岸戦争」総括。米国の一国超大国化。後半、その下での日本の対米追随について2点の欠点を書く。 (1)「米国追随」を「国際協力」と呼ぶのは、私にはシニカルな冗談のようにしか聞こえない。「国際的孤立」、特にアジアから、を招くだろう。 ←加藤周一さん、30年間その言い替えは日本では、通用しているんですよ。悲しいことに。思ったほどには西欧からの国際的孤立は招かなかったけど、アジアへは自ら進んで孤立していきました。 (2)「反動として反米感情のたかまる可能性」 ←加藤周一さん、日本人は結局そんなに賢くありませんでした。韓国では2000年代に反米感情が大きく高まったのと対照的です。(91.3) ・「湾岸戦争」を「史記」的に表現。知的に咲(わら)うなり。(91.8) ・木下順二「巨匠」評。(91.9) ・ソ連解体について(91.12)
2020年12月01日
コメント(0)
-
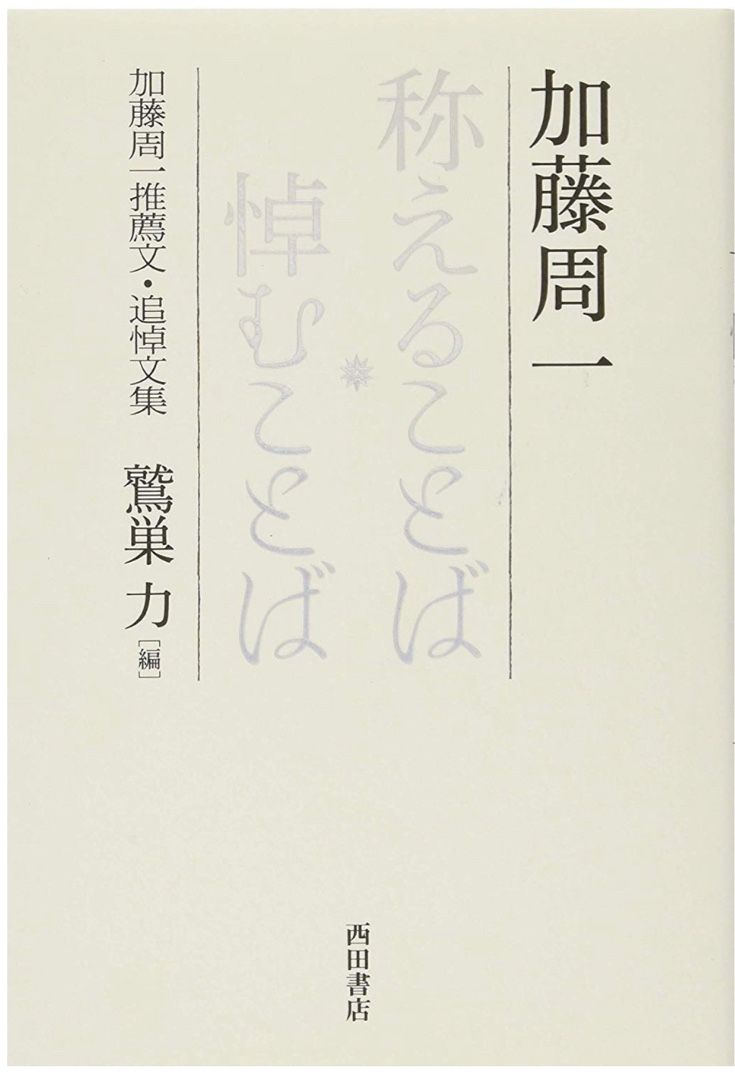
加藤周一の自画像『称えることば 悼むことば』
『称えることば 悼むことば』加藤周一 鷲巣力編 西田書店 他をして自らを語らしむ。加藤周一の書物への推薦文も、友人の弔文も、結果的には自画像になっていたと私は思う。2008年12月5日、日本の知性は、そのひと頭分低くなった。10年を過ぎて、少しその幻影を追ってみた。 自己の感受性に忠実に生きるということ。夢想家だけが、帝国主義戦争の本質を見破れるだろう。(『片山敏彦著作集』1971) その仕事は、近代日本の散文の基礎を築くことであり、全く独創的な一つの文学形式を生みだすことであった(いわゆる史伝)。しかも科学者としては、衛生学の技術を輸入し、実験科学の精神を説き、思索家としては、儒家の伝統に従って、超自然的な絶対者をではなく天下国家の現在と将来を考え、儒家とは異なり、単に政策ではなく社会構造そのものに思いを致した。仕事は多方面に渡り、業績は、何れをとっても、群を抜く。(『鴎外全集』1971) いま日本の思想家を、その独創性、対象の包括性、論理の整合性、影響の拡がりによって測り、五指を屈するとすれば、たとえば仏家に空海・道元、儒家に徂徠・白石、国学に宣長をみるだろう。(『荻生徂徠全集』1972) 中村真一郎に三善あり。第一は、天下の政事に係らぬことである。故に安んじて風雅の道に遊ぶことができる。第二は、書を読んで古今東西の文芸に渉ることである。したがって文壇一時の流行を文芸の大道と心得ることがない。第三は、その文章が明快で、おどろくべし、読めばその意味がはっきりとわかることである。思わせぶりの美辞麗句の落ちついて考えれば何のことかよくわからぬ深刻さがないのは、けだし当代文苑の奇観というべきだろう。(中村真一郎『この百年の小説』1974) この人々は、単に気分に従って生きたのではなく、考えて自己の生涯を択び、常に大勢に順応したのではなく、しばしば少数意見に徹底し、近代日本の発展を、単純な成功物語ではなく、激しい批判の対象としても捉えていた。(『日本人の自伝』1980) 大江健三郎は何故抗議をするのか。(略)それはおそらく平和であり、樹木であり、生命の優しさでもあるだろう。たしかにそれこそは、もし文学者が語らなければ、誰も語らないだろう壊れ易いものである。(『大江健三郎同時代論集』1980) 二葉亭四迷は、いやだから首相の宴会には行かない、といった人である。「このいやといふ声は小生の存在を打てば響く声也」。そのことと、彼がロシア文学の中で、ツルゲーネフばかりでなく、ガルシンやゴーリキを訳したこと、また小説を書いて同時代の日本の一市民の日常生活を、その条件を超えようとする願望との関連において描いたこと、さらに日本語の散文を日常的な話し言葉に近づけた(一致させたのではない)こととは、密接に係っていたにちがいない。(『二葉亭四迷全集』1981) 日蝕がいつ起こるかは正確に知ることができるが、革命がいつ起こるかはわからない。しかし日蝕よりも革命の方が、われわれの生活に大きな影響を与える。自然科学と社会科学とでは、予見可能性と共に扱う対象の性質が違う。その方法はどう違うか。社会科学的の広大な領域を見渡して、およその見当をつけるためにこの講座は役立つだろう。(『岩波講座 社会科学の方法』1992) ーーーーここに至るまで、未だ全体の1/4ほどからしか抜書きしていない。何処を抜書きしても、恐ろしいほどにその著者の本質を突き、怖いくらいに加藤周一自身を語っているようにしか思えない。たった200-800字ほどの文の中に、加藤周一ほどに10数巻に渡る全集の本質を閉じ込める力量を持つ評論家を、現代日本において私は知らない(誰かいたなら教えて欲しい。しっかり読んで批評させて頂きます)。 「悼む」文章は「称える」よりも比較的長いが、長くても10ページほどに過ぎない。その中に人物を簡潔に的確に纏めて余す所がない。いや、ほとんどはもっと短く纏める。私は40年前に朝日新聞で「福永武彦の死」を読んだ(1979.8.15)。1800字程の文章の中に、未だ読んだことのなかった福永武彦の全てと、限りない友情が詰まっていた。加藤の尊敬するサルトルの弔文、青年時代の師匠林達夫への弔文・弔辞、その他さまざまな友人たちへ捧げる文章。加藤周一ほどに友情を大切にする文学者を私は知らない。 いかん。だんだん、だらだらした文章になってきた。切ります。(文字総数1801)
2020年01月07日
コメント(0)
-

大阪と加藤周一への旅2-1 加藤周一生誕100年記念国際シンポジウム
9月23日(月)2日目。朝の散歩兼朝食のため6時半に出る。宿は西本願寺の真ん前だ。台風の影響は、幸いにもほとんどない。京都らしい建物も物色する。西本願寺前の消防団は、以前も写真に撮ったかもしれない。結局、モーニングをやっている喫茶店は、片鱗さえもなかった。京都は、パンが名物のはずなのに、モーニング文化がない。ファミリーマートの店内で食べる。カードが使えるのが嬉しい。8時半出発、205番バスで衣笠校前で降りて10分ほど歩く。講堂に着いたら、9時半から18時半まである、加藤周一生誕100年記念国際シンポジウムの連続講演は既に始まっていた(会場内写真不可なので、載せられません)。一番手は奈良勝司氏「近代日本の体外観と西洋理解」。頭が悪いので、難しい。加藤周一論ではなくて、江戸時代から明治維新にかけての国民意識の型を述べた。おらが村の中の1番意識(武威)と帰属集団の中で我をはらずに勤勉に努める(通俗道徳)が、現代まで残っている。知識人は個として孤立する(加藤周一)。というような意味だったかどうか自信がない。2番手は中国人の孫歌氏「対談における加藤周一」。1番むつかしかった。竹内好や丸山真男との対談記録を駆使して、なんかいろいろ言っていた。昼休み中に、加藤周一文庫に行こうとしたら休みだった。それはないでしょ!これを楽しみにしていたのに!講堂地下で、丸山真男文庫共同の「<おしゃべり>から始まる民主主義」という展示をしていた。確かに2人は対談の名手ではあったが、あまり大きな感慨はなかった。青春ノートの資料集、高かったし、カードは使えなかったが、約800円近く値引きしていたのもあり、遂に買ってしまった。この旅で本代は13200円にも及ぶ。嗚呼!午後一番手は、池澤夏樹氏「『日本文学史序説』を読む」。喋り慣れていることもあって、1番理解出来た。幾つか重要なことを言っていた。私なりにまとめてみる。加藤周一と初めて会ったのは、父親(福永武彦)の葬儀の時だった。次が1969.8.7の反核シンポジウム、次の対談をした時(2003)に、「あの人のことがわかるようになった」。←これは想定外の遅さだった。理系出身、外国生活が長い、リベラルと加藤周一と生き方が似ているので、もっと前から影響を受けているのかと思っていた(だって加藤周一の親友、福永の息子なんですよ!)。ずっと、あのノンポリの吉田健一から影響を受けていると告白していたのを不思議に思っていたが、少し納得した。池澤夏樹は、日本文学全集を編む時に、加藤の日本文学史序説の「はじめに」部分から、教わった。他にも丸谷才一、吉田健一、中村真一郎の批評家を準拠した。加藤周一は、文学史を書く時に外国文学と比較し相対化する。それは一休宗純を述べる時にイギリスのジョン・ダンを引き合いに出すかの如くであり、狭い比較ではない。そして、客観性を担保する。加藤周一のいう日本文学の特徴は以下の通り。・文学が哲学をも代行する(一休宗純)。・「具体的、非体系的、感情的」で抽象性を欠く(ソクラテス・プラトンは出てこない)。・時代を超えて統一性が著しい。・新しいものの追加とゆるやかな変化、建て増しを繰り返す(長歌→和歌→連歌→俳諧→短歌)。・最初から叙情詩(古事記)叙事詩(万葉集)劇(猿楽)物語、随筆、評論、エセー全て揃っていた。日本語で書かれた文学史として、こんなに長く続いているのは、中国を除いて無いのではないか。・細部に意を注ぎ、全体を見ない。・求心的傾向。京都、江戸、東京。・文学者とその帰属集団との密接な関係(文壇とか)池澤夏樹は、これに加えて、近代以前は・恋愛・性愛の重視(武勲の話はほとんどない、セックスか権力争い)・自然への視線(成る・生るVSつくる)・弱者への共感(勝ち負けの話になると、負けた方に心を寄せた)・平安期までは女性の活躍(応仁から樋口一葉まで)現代は文学が1番ジェンダーが進んでいる。序説への批判・序説は人文地理的考察から始めてもよかったのではないか?何故「建て増しの繰り返し」で済んできたからと言えば、同じ民族で済んで来たから日本の特性としては、島国であること、大陸との距離があること、異民族から独立を保てた「自然災害さえ我慢すれば侵略はなかった」、中緯度のモンスーン気候、キリスト教世界観とは違う「成る・生る」という動詞が基本の世界観質疑応答より・池澤夏樹のいう文学特徴の中で、異民族からの独立は1945年から保てなくなったと思うが、文学の特徴も変わったのではないか?「変わったと思う、弱者への心の寄せ方も変わったと思う」池澤氏は、明治時代に変わったという認識だった。←これはとても重要な指摘である。私は、弥生時代の倭国統一も、維新の戦争を経ない統一も、弱者への視線を重視する日本人の特性が影響している、という仮説を立ているが、日本人がアジア侵略に向かったのは、その特性が崩れたから、という言い方が出来るかもしれない。現代の韓国報道も、近代以前ならば決して起きないことだったのかもしれない。自明のことではあるが、文学史とは、即ち思想史なのである。次は李成市氏「韓国から見た「雑種文化論」」である。韓国にも雑種文化的特性はある、というおおまかに言ってそんな話だったと思う。面白くなかった。娘のソーニャ・カトー氏が短い挨拶をした。これが良かった。(あくまでも私的まとめです)ヨーロッパ連合に対して英国離脱等内から壊されようとしている。日本も韓国に対する植民地的な考えが起きている。父はなんと言うか?どんな答えをするか?どんな質問をするか?と考えてしまう。理想と理性の精神が失われようとしている。次の加藤周一が現れるのを見逃さない様に目を開こう。次の加藤周一が必ず現れると確信しています。この前の李成市氏の講演への質疑応答で、あいも変わらず、韓国を植民地化したことの真偽や、併合中で良いこともしたと言う事を、臆面もなく質問した人がいたので、余計によかった。この後のシンポジウムは欠席した。それに参加していたら、今日中に帰れなかったかもしれない。また、あくまでもアジアの中の雑種文化論を語る大きなテーマは、私的には合わなかった。アジアの中でどのように平和に生きていけるのか、それを探る講演にしてもらわないと、私には合わない。これのために京都に来て1日潰したのだが、うーむ、イマイチだったと言うべきか。鈍行で倉敷に帰る。家に着くと、11時近くになっていた。10123歩
2019年10月07日
コメント(0)
-

アーカイブス加藤周一の映像 1
アーカイブス「加藤周一が残した言葉」2009.3.NHkより永田誠さんの奮闘によって、加藤周一映像のYouTubeが多くUPされている。ここに載せるのは、一番初めに載せるに入門編として適当だ。短くポイントを押さえているだろう。亡くなる半年前に撮影したNHkの追悼番組を映して、それを見ながら姜サンジュなどの言葉を載せている。すでに癌は全身に転移していて、身体は衰えているが、表情は非常に鋭い。10年前の語りではあるが、まるで安倍一頭政治の今を見据えて、「現代をどのように見たらいいのか」ということを語っているかのようだ。ここで加藤が言っているのは「教養を持て」ということだ。このあと世の中を席巻するポピュリズムをこの時点で、根本から批判している。なかなかこういう映像までチェックできないのだが、少しずつ紹介していきたい。
2019年02月13日
コメント(1)
-

加藤周一の娘の寄稿文
加藤周一の娘ソーニャさんの寄稿文by「図書」12月号なんとか、手に入れた!題名は「夕陽妄語(とドイツ語のその言葉)」。ソーニャ・カトー文、高次裕翻訳。内容は、立命館の加藤周一文庫開館記念講演の内容を大幅に膨らませたもののように思えた。あの時、聞きそびれていたことや、曖昧だったことも随分明らかになったような気がする。新しく知ったこともあった。以下、私的に「おおっ」と思ったことをメモする。・(私は)この家系で加藤という名を継ぐ最後の者なのだ。←つまり、家系的には加藤家は絶えるということなのか?最初の奥さん(京都の人?)との間に子供はいたのか?矢島さんとは子供はできなかったのか?いかん、いかん!下世話な感情です。・←ウィーンとの奥さんとの関係が、これを読む限り、何故別れたのか、一向にわからない。・パリでの加藤周一との共通の故郷として、パンテオン広場にある、ルソー像、ゾラ像と向かい合い、ヴォルテール像のすぐ隣のホテルを挙げた(←1度行ってみたい)。・加藤周一のお気に入りの場所(ソーニャさんの定点)。クリュニー美術館の「貴婦人と一角獣」ブランクーシーの彫刻「接吻」(←1度行ってみたい)。・ソーニャさんは、20代にヨーロッパ情報の加藤周一への通信員だったという自覚。←それは当然あり得るだろう。我々とは違い、そういう「生の声」を発信する友人は加藤周一にたくさんいただろう。それが彼の判断を正確なものにしていただろう。・ソーニャさんは「(加藤周一が)政治家になることが、ひとつの選択肢としてあったのか」と思っていたようだが、日本人の読者でその選択肢があり得ると思う人は先ず居ないだろう。・どうやらソーニャさんにとっても、加藤周一のキリスト教洗礼はショックだったようだ。「父は最期の時は一人の人間だったということだ。」ということは、この行動は、娘に相談していないということなのだろう。あゝそうだ。ごめんなさい。2018年12月は、加藤周一没後10年、命日のある月でした。もう10年。はや10年。・「制定から72年間を経過した憲法第9条保持のために戦う者として、私の父は今日でもまだ知られているか」ことあるごとに彼女はそう学者や学生に問い、返答は曖昧で「日本の社会には、そもそも平和の象徴となる人物がいない」と聞いたそうだ。落胆しているソーニャさんに言いたい。少なくとも私は、9条の会で加藤周一の果たした役割は、誕生から立ち上がり運動まで導いた役割は、9人の中で1番重く、決定的だったと思っているし、9条改憲を2018年末のギリギリのタイミングで、またもや退けたことは、9条の会の存在なしには語れないことであり、よって、日本の平和に果たした役割は、とてつもなく、非常に大きい。と心から思っています。2018年12月読了
2018年12月27日
コメント(0)
-
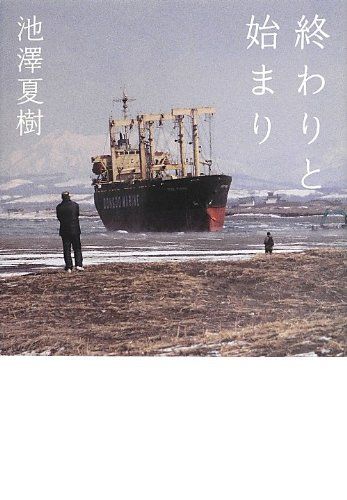
「終わりと始まり」池澤夏樹は加藤周一の後継か
「終わりと始まり」池澤夏樹 朝日新聞出版社2008年の末に亡くなった加藤周一の「夕陽妄語」に代わり、2009年4月から池澤夏樹の連載が朝日新聞紙上で始まった。 私はその前後に20年近くとっていた新聞購読を中止したので、このエッセイを読んだ記憶がほとんどない。本格的に加藤周一連載の後継に落ち着くことも、実は幾分疑っていた(それまでは暫定的に大江健三郎の連載があった)。あれから10年近く経って、既に二巻目が出ているこの本の第一冊目をやっと読んだ。池澤夏樹は加藤周一の後継であると思っていたわけでもなく、期待していたわけでもない。それでもやはり新聞後継連載のエッセイを読んでみるのが怖かったのだろうと推察する。題名の意味が不明だったが、加藤は漢詩から採ったが、池澤は「さりげないものがいいと思って」外国人の詩から採ったことが、今回知れた。いい詩である。2年後に詩の内容が現実(震災)に追いついたのは、偶然である。読んでみると、池澤夏樹は多くの点で違っていた。文学よりも、旅の話が生き生きと語られる。ともかく池澤夏樹は「行動的」である。被災地に何度も通った。加藤も震災後神戸に訪れているが、その比ではない。もちろんだから優劣をつけるわけでもない。最新のマンガや映画の内容を何度も俎上に載せる。古典を大切にしていた加藤とかなり違う。日本に帰って住んだ土地である沖縄と北海道の話題が多くを占め、「戦後日本文学の1番大事な作家」と評価する石牟礼道子氏の関係か、水俣の話題も多かった。3.11の後からは、少なくとも2年間の2/3は震災関連話題で占める。古今東西の遠くに広がらず、比較的身の回りの話題が多いというのは加藤周一のそれとは違うだろう。しかし、教養はやはり古今東西に広がっており、社会を批判的に見る目は比較的鋭い。イサム・ノグチが好きだから、政治の話をしないわけではない。むしろ積極的にしている。これらは「夕陽妄語」の伝統に似るだろう。加藤周一は私にとっては、仰ぎ見る大先生だった。池澤夏樹は大学で演習のお世話になっている先生のような気がする。学ぶべき所は多いが、時々は「それは違うでしょ」と言いたくなるのである。ともかく、読み継いでいきたいと思った。2018年9月読了
2018年09月18日
コメント(0)
-
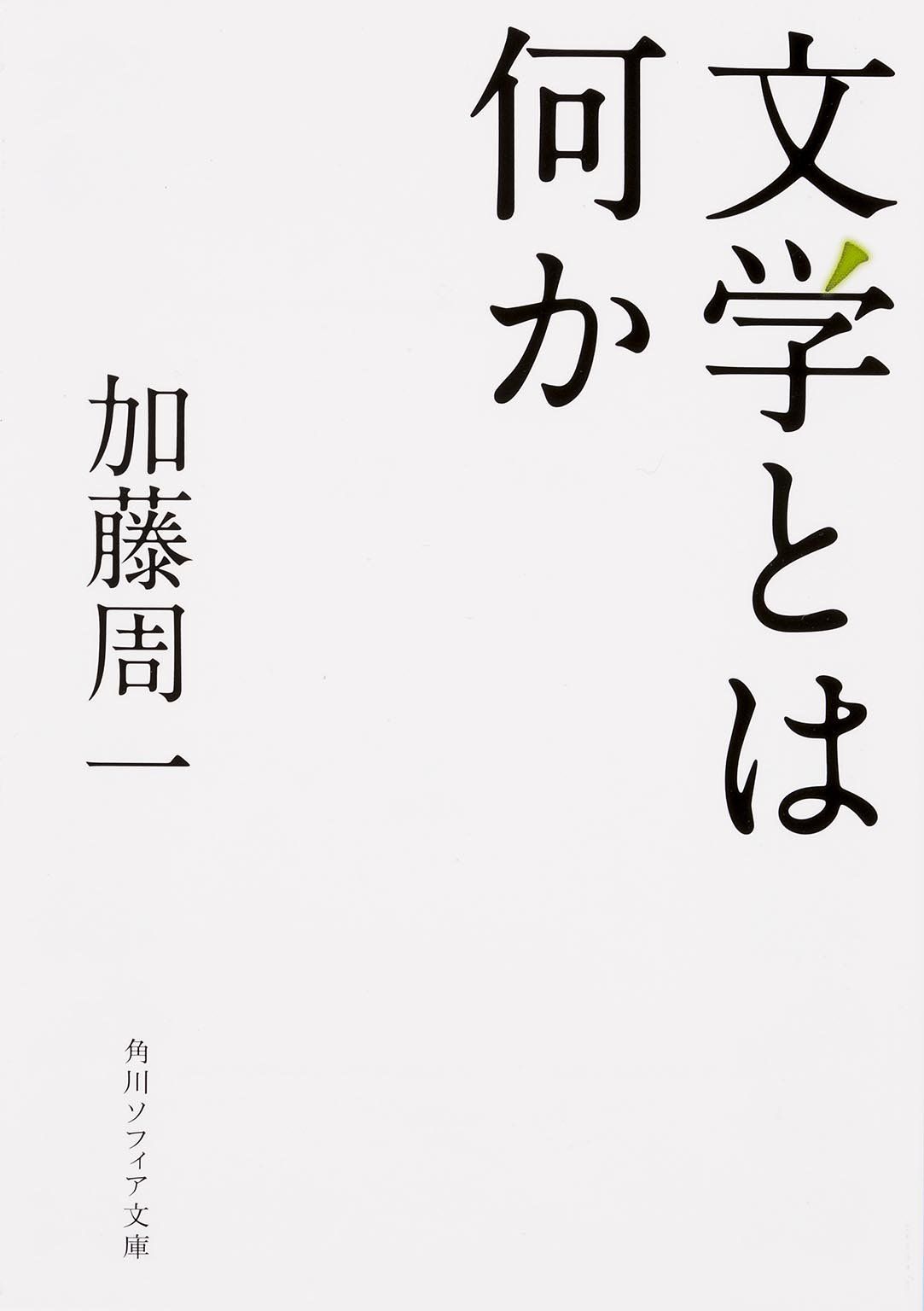
加藤周一「文学とは何か」の池澤夏樹の解説を批評する
「文学とは何か」加藤周一 (解説・池澤夏樹)角川ソフィア文庫この本には「思い出」も「想い」もあるが、それを今は展開出来ない。今回は特にこの文庫本のために書き下ろされた池澤夏樹の解説について、私の感想を書きたい。旧版「文学とは何か」は1950年に角川新書として刊行された。少し読みやすくして1971年に新版を角川選書として出している。今回はおそらく新版はそのままに解説だけを付け足してソフィア文庫の中に組み入れたようだ(2014年7月初版)。何故か加藤の著作集に入っていないこの文学入門が、安く簡単に読めるのはたいへん喜ばしいことだと思う。さて、池澤夏樹の解説だ。何故それに注目するのか?朝日の「夕陽妄語」が、加藤周一の死を以って終わったあとに、それを引き継いだのは池澤夏樹の連載だった。池澤夏樹は加藤周一の後継者なのか?加藤周一ファンとしては半分納得し半分訝った。外国生活が長く、古今東西の教養を持ち、社会的発言もまともな彼は後継者に相応しかったかもしれない。しかし、2014年11月から始まった個人編集の日本文学全集に、友人の中村真一郎や父親の福永武彦はあるのに、この巻に相応しく、個人的にも親しいはずの加藤周一が2人の巻に入っていなかったのに、先ずは私は「おや?」と思った。もっとも、それだけならば私は「加藤は評論家だから」と思ったかもしれない。「吉田健一」に一冊を充てた時に解説を書いて、池澤夏樹は「(自分の文学観は)主に評論家の吉田健一と丸谷才一に依っている」とあった。びっくりした。何故、よりによってあの究極のノンポリの、社会意識がゼロの吉田健一が入るのか。私はこの一冊を読み通すことが出来なかったので、その内実は未だわからない。ただ、池澤夏樹はこの解説においてこう書いている。(文学とは何か、という問に答える本として)池澤夏樹は他に3冊の本を挙げる。石川淳が『文学大概』を書いたのは43歳。吉田健一の『文学の楽しみ』は55歳。丸谷才一の『文学のレッスン』は85歳の時だが、『文学とは何か』を書いた時に加藤周一は31歳だった。若い分だけ覇気があり、無謀であり、勇猛だった。(197p)先ず最初に、先の御方よりもこの文学入門が劣るかのように書いているのである。先ず構成がよくないと手厳しい。文学とは何かを論じるに、「客観的な方法」から入っているのは、間違いだと断じる。しかし言うまでもなく文学はまずもって主観の装置だ。それは加藤だってよく判っている。普遍的な文学の定義を求めて客観に走ったが、そこから主観の方へ少しづつ戻る形で議論は進む。(198p)そこから、各論には感心する所があると言って、流石に「解説」なので褒めて終わるのであるが、「ホントは褒められた本じゃないんだよ」と言外に書いているようで、私はむっとしている。ちょうどこの頃は、池澤夏樹が文学全集を編んでいて、おそらく吉田健一や丸谷才一を集中して読んでいた最中だと思うので、余計このような書き方になっていたのだと思う。もちろん、「文学は主観の装置だ」という池澤夏樹の意見に異論はない。だからと言って、論理がグルリと回っているからと言って、老獪な評論家と並べて貶めるようなこの解説はどうかと思う。ホントに池澤夏樹は加藤から影響を受けていないのか?吉田健一を規範にした池澤夏樹は、吉田健一ならば決して書かなかったような社会批評を、解説の最後に付け足している。誠実な批評家は自国の文学に対して厳しくなる。(略)この本が刊行されたとき、日本はまだ敗戦の空気の中にあった。それを終戦と言い換えて済ませるわけにはいかないと加藤は考えた。それが「日本近代文学の不幸」という部分に表れている。そして、戦争が敗北に終わってから69年後の今、この本が書かれてから64年後の今、加藤がこの本に盛ったと同じ批判を日本の社会に向けなければならない。「孤立しないためには、個人主義が個人的にではなく、社会的に徹底させられる必要がありましょう」というのはそういう意味である。(202p)池澤夏樹の(あえて言う)自分の父親にさえやっていない「加藤軽視」は、もしかしたら自己への「批評が厳しくなった」現れなのかもしれない。2018年5月読了
2018年05月08日
コメント(0)
-

京都旅1-1 加藤周一文庫
9月9日朝、新幹線に乗った。遅い2日のみの夏休み(実質は1日半)のために京都に行く。本当は、去年正月の島根行きのリベンジを計画していたのだが、日曜日午後の野暮用を思い出したので、新幹線1時間の処に急遽変更した。目的は何か。これも約1年間の願望だった立命館大学図書館内にある「加藤周一文庫」を尋ねる、それのみである。本来ならば1日あれば済む。でも1年間行けなかった。こんな機会がないとずっと行けないままだ。 京都は思い出の地だ。38年前、私はふたつの大学を受験するために、当時同志社の学生だった、兄貴のほとんど穴倉の下宿に10日間ほど泊まっていたことがある。受験と受験の間に、私は思いつく限りの京都観光を独りで回った。もちろん寂しくはなく、とてつもなく面白かった。私の生涯で、5ー6回は「世界が広がった」経験をした時があるが、間違いなくこの時はその一つだったと思う。私はその時に日本史と日本の美術に出会った。それはそのまま、その直後に出会う加藤周一の数々の著作を理解する手がかりになっただろう。 京都駅前から立命館大学行きのバスに乗る。 二条城。 バスの車窓から見ると、戦災にあっていない京都の町並みは、しかしほとんど千年の都の面影さえ観ることができない。古いものを遺さずに無秩序に街づくりをするのは、外国人にとって理解不可能だろう。台湾と似ている。あそこはせいぜい200年ぐらいの歴史しかないが。加藤周一は、そのことに異議を唱え少し運動をしたが、焼け石に水だったようだ。 立命館大学に着いた。新館の図書館のなんと立派なことか。 受付で、所定事項を書いて(免許証などの証明書は必要)加藤周一文庫の見学の許可をとる。写真撮影は不可なので、パンフの表紙だけを載せる。 1948年ごろの日記が展示されてあった。また、加藤周一の愛用の机と、寛ぐ時の椅子などを見る。それらを新調せずにずっと使い続けていたらしい。確かに悪いものではないが、もっと機能を上げようという気持ちを持たなかったのだろうか?鷲巣氏は、そこが加藤周一たる処だと指摘する。 加藤周一文庫の二万冊の蔵書は、圧巻であり、その一部と雖もその内容は歴史の中の古典全集はもとより、かなりマイナーな岩波文庫新書を揃えている。様々な外国情報も網羅する。NHK歴史ドキュメント、周恩来語録、人民日報資料集まである。小田実・自立する市民、三池争議資料集、中国石窟のシリーズ、安部公房短編集、池澤夏樹の各本、もちろん中村真一郎の各本、80年代の雑誌文化評論、みすず、丸山真男手帖、古いユリイカ、等々等々。森羅万象の全てに興味があり、私の蔵書の10倍近くを持っていた。 ひとつ気になったのが、蔵書の一冊(と言っても確かめたのは数冊のみ)たりとも、書き込みが無いのである。新品同様の本も、ボロボロになった古い本も無いのだ。加藤周一がノート魔だったのは知っている。ノートをとりながら、本を読んでいたのは十分に考えられる。しかし、加藤周一は移動の際も必ず本を持ち歩き読んでいたと何処かに書いていたと思う。付箋紙の無かった昔から、ノートをとりようがない昔から、彼はどうやって本の内容をまとめていたのか。頭がいいのは良く知っている。しかし、せめて線を引いた方が「合理的」なのではないか? ともかく、質はもとより、量だけでも追いつかないか?という予想は簡単に砕け散った。 予想を若干超えて、やはり加藤周一はすごかった。という感想しか出てこなかった。鷲巣氏の、ノートを分析した、加藤周一研究が早く出ることを祈る。 終わって、立命館国際平和ミュージアムに行った。これで3度目。常設展示の図録を買う積りだったが、やめた。3度目となると、瑕疵も見えてくる。 コンサートもできるような、大きい一階エントランス。火の鳥が飛んでいる。 珍しい展示では、厭戦を煽る手紙や、トントントラカリの替え歌で厭戦をうたっていた。高地らしいが、庶民のささやかな抵抗があるのを見れて嬉しかった。 B29迎撃用ロケット燃料精製装置。 本来、鉄製の精密機械である。それを陶器でも作れるという日本人の器用さ、ここに極まれり。戦争の愚かさ此処に極まれり。 全体的にはバランスよく展示している。しかし、である。現代情勢に言及しているのは、イラン戦争まで。ISはもとより、戦争法をめぐる日本の情勢に一切触れていないのは、はっきりいって片手落ちだろう。 昼食は近くの中華店で、北京定食。
2017年09月11日
コメント(0)
-

加藤周一の射程「世紀末ニッポンのゆくえ」
「世紀末ニッポンのゆくえ」インタビュアー小尾圭之介 ミオシン出版文教大学情報誌に連載されたインタビュー集。1997年、ちょうど20年前の本である。お目当てはもちろん巻頭の加藤周一。日本の「システム」についての、私にとっては自明の、しかし多くの読者には新鮮で鋭い指摘が続くインタビューだったろうと思う。加藤は20世紀日本の成功の要因を支えた「工業化」を更に支えたのは、一定の条件があったからだという。それは日常生活に犠牲が少なかったこと。日常生活の様式の変化は少なかった。また、天皇制官僚国家を民主主義の犠牲の上につくることに成功した。しかし、「一般に、少数意見を内部に抱えている国•団体は、状況が変われば、今まで少数意見だったものが多数意見になって、別の方向に進むことが出来るのですが、日本では、少数意見を排除してしまうことで能率は高めたが、必要な方向転換もできないようになったと思います」(15p)「明治以来の日本は集団主義で一億一心、団結して与えられた目的を達成することはできるが、方向転換能力がないために必然的に失敗します。この100年に成功も失敗もあって、戦後もその気質が続いていると思います。しかし、今、それが隠されているように見えるのは、戦後がアメリカの占領下から始まったからでしょう。現在は法的に独立し、内政面では占領は終わりました。しかし、外交政策と軍事面ではだいたいアメリカに従っていますから、アメリカの準保護国的状況、実質的には半独立国です。」(17p)半独立が何故続いているのか。一つは、アメリカが解放軍として、軍事型官僚国家から解放したから、歓迎した。一つは、日本の国民性。現実を直視しない。衣食足りて心理的に政治から遠ざかる。「寄らば大樹の陰」もあった。一つは、鎖国の影響。国際情勢を客観的に見ずに、絶えず日本との関係においてだけ見る。最近では、冷戦が終わると同時に、ドイツは基地問題に反応した。日本はしなかったし、今もしていない。(19p)21世紀への展望を聞かれて加藤周一は「南の犠牲で繁栄する北」という構図を変えなければならない、と解く。1996年11月の段階では、これはあまりにも預言的だった。曰く。「経済力、軍事力は北にかなわないとなると、南のアイデンティティーを守るためにできることはテロリズムだけです。これは絶望的な暴力です。希望を与えることがテロへの唯一の対策です。そういうことに日本がいくらかでも貢献することが望ましいと思います」(28p)しかし現実はそうではなく、アメリカの腰ぎんちゃくに成り下がっているのはご承知の通り。国家間の同盟の問題や、科学技術問題特に原子力発電などのエネルギー問題でも文化的アイデンティティーでも預言的発言をしているのだが、割愛する。改めて、加藤周一の視線の届く距離は長いと思った。2017年3月31日読了
2017年04月07日
コメント(0)
-

加藤周一 その青春と戦争
(知人のメーリングリストから拝借。赤旗の記事らしい)録画していたETV特集の「加藤周一 その青春と戦争」をやっと観た。素晴らしかった。幾つかの小さな発見と、何よりも加藤の瑞々しい文章と、それを読む学生の瑞々しい感性に触れて愉しかった。死後数年経ってお菓子の缶に保存されていた1937年(17歳)から1942年(22歳)までの、評論や日記、詩などを書いたノートが見つかり、それを学生やいろんな人が読みながら、紹介してゆくというものでした。全体的な感想を云えば、池澤夏樹が言うように、「加藤周一は最初から加藤周一だった。観察者であり、分析者だった。論理的に生きて行こうという"決意"がある」ということになる。しかし、学徒出陣の一年前にノート執筆を已めた加藤の中に、理不尽な死を前に何とかして世界を理解しようとする心が、揺れながら書かなくてはならないという気持ちも併せて観て取れる。論語を模した自叙伝や、後の三題噺を彷彿させるような「東京」という短文、等々。ここにはホントにその後の加藤周一を予見させる文章に満ちている。驚くのは、何処を切っても加藤周一なのに、文章そのものをこの後の分筆活動で「切り貼り」することは一度も無かった、ということ。加藤周一はフランス文学「チボー家の人々」を自ら一部翻訳する。そこには、ヨーロッパの街の中、第一次世界大戦の直前にもかかわらず、人々が平和に無邪気に生きている様子が描かれるだろう。加藤周一は書く。「歴史は繰り返す。1940年はいかに1914年に似ていることか。現代は何度絶望したら許されるのか。」加藤がそう書いたその一年後に太平洋戦争が始まった。歴史は繰り返す。2016年はいかに1940年に似ていることか。現代は何度絶望したら許されるのか。現在95歳の加藤周一の妹の久子さんを、初めて見た。久子さんは、当時叔父の軍人岩村清一(ロンドン軍縮会議にも出席)の影響が強かっただろうという。叔父も戦争には負けると思っていて、戦争には反対だったらしい。加藤周一の同級生の貴重な"生き残り"山崎剛太郎氏も登場。それと同時に、加藤周一がよく言及していた中西哲吉氏の写真も出てきた。今回、加藤が亡くなる直前のメモも紹介される。加藤周一はその親友のことをだいたいこんな風に書いていた。「私は戦争で2人の親友を失った。もし彼らが生きていたならば、日本もが再び戦争の道へといくことを許しはしない。私は親友を裏切りたくない。憲法9条には親友の願いが込められている」中西は池澤夏樹によれば、加藤周一よりも優秀だったかもしれない、という人だった。立命館の学生が加藤周一の青春ノートを真剣に読み込んでいて、嬉しかった。加藤周一を「古代に"逃避"している」とか「傍観者」とか、学生特有の性急な言葉を使いながら、基本的に加藤周一を理解していたように思う。最後のまとめ部分で、加藤周一から学んだ感想を述べて一人の学生の言葉が印象的だった。「歴史は繰り返すのは、"人の弱さ"かもしれないけど、それを乗り越えることがあるとすれば"人の力"かもしれないと思う。そのように生きる力は、"人をつなぐ"ことだと思う」がんばれ。がんばろう。ちょっと急がせますが、再放送のお知らせです。ETV特集「加藤周一 その青春と戦争」8月20日(土)午前0時〜1時(金曜日の深夜)http://www4.nhk.or.jp/etv21c/2/また、ツイッターの「加藤周一文庫」からの情報です。本日のETV特集「加藤周一 その青春と戦争」で扱われる加藤の「ノート」は、インターネット上で全文を公開しています。番組を見て関心を持たれた方は、ぜひこちらもご覧ください。trc-adeac.trc.co.jp/WJ11C0/WJJS02U…15:41 - 2016年8月13日
2016年08月19日
コメント(2)
-

加藤周一文庫開設記念講演会
加藤周一文庫開設記念講演会が昨日立命大であった。以下はホームページでのお知らせのコピー2016年4月、立命館大学は衣笠キャンパスに新たに平井嘉一郎記念図書館を開館し、その中に「加藤周一文庫」を開設しました。本文庫の意義を広くご理解いただくため、「加藤周一文庫開設記念講演会」を開催します。◆加藤周一文庫◆加藤周一現代思想研究センター2016年5月7日(土)13:45〜17:10講演1:「加藤周一 −世界を見つめた旅人」講師:ソーニャ・カトー講演2:「加藤周一さんを再読する」講師:大江健三郎氏表彰式:ソーニャ&シュウイチ・カトー スカラシップ表彰式会場:立命館大学衣笠キャンパス行きたかったが、仕事があって京都行きは早々に諦めていた。そしたら、Ustreamでライブ中継してくれることになった。大江健三郎さんの講演は途中で席を立たざるを得なかったが、貴重な話を聞くことが出来た。先ずは立命大吉田学長は「我々はいま時代の岐路に立っている。だからこそ、加藤周一を再読する意味がある。」と挨拶。加藤周一自選集その他を編集した鷲巣力氏(研究センター所長でもある)が司会を勤めた。鷲巣氏は、5年間加藤周一文庫開設のために準備してきたらしい。ソーニャ・カトーさんの話は、私なりにまとめると以下の通り(聞いたのをメモしているだけなので、話の全てでもないし、正確かどうかわかりません。よろしくお願いします)。私の父の眼差しについて話したい。私の父は、二つの世界の旅人でした。私は生後間もなく加藤周一とヒルダ夫婦との養子になりました。父は日本人でいっとき一緒に暮らしていましたが、その後はウィーンの私と母とは、別々に暮らしていた。父は時々ウィーンに来た。父が日本からプレゼント持ってくるのが楽しみだった。特におせんべい。私はその缶に宝物を入れ、それもまた宝物にしました。母は私が11歳の時になくなりました。その時ほど悲しそうな父を見たことはなかった。救えなかったことを悲しんでいた。年に一度お互い訪問するのが常になった。初めて日本に行ったのは17歳。80年代終わりの頃、三週間の日本滞在は蒸し暑さにびっくりした。父の習慣を見、テニスをする父の姿を追いかける、それだけで幸せだった。続く何年か間に絆が強くなった。政治的、芸術的なやり取りをした。2人のお気に入りの街はパリでした。私にヨーロッパを教えてくれたのは父なのです。ヨーロッパの歴史について開眼させてくれたのも父でした。何処へ行ってもヨーロッパの考察を巡る旅になりました。私の思い出の中の父はいつもヨーロッパ人。でも、父がどれほど日本人であったか、年をとってわかった。亡くなって父が二つの世界を行き来する旅人だとわかった。人間に対するアプローチも深く見聞きする前に調べてました。17歳の時成田で別れをいう時、抱擁した。その後はそれが習慣になった。公の場でも変わらない愛情表現が、周囲を戸惑わせた。残念なことに私は一度も日本語を習わなかった。ドイツ語が二人の秘密の言葉になりました。父のヨーロッパが私のヨーロッパになったように、父のドイツ語が私のドイツ語になりました。我々2人の人生に政治が重要な役割を果たした。私の人生に政治が重要なものになっていた。加藤の名前を一生たずえるのは、重要なことです。父の病気が重くなり、日本の家に行った。人生で最もつらい、最も大切な旅になりました。その時から、日本との結びつきが強くなりました。長男のマチアス14歳には、シュウイチというセカンドネームがついている。鷲巣「サプライズです。もう一人のソーニャを紹介したいと思います。カナダ・バンクーバーの大学で教えていた時の学生、ソーニャ、アンゼンさんです」ご紹介に預かりましたアンゼンです。1960年代のカナダの学生です。初めて加藤周一に会った時にヒルダさんと親しい人になった。養子を迎える時に名前がソーニャと聞いた。2002年ごろ、加藤周一が東京でソーニャさんの写真を持ってきて、「貴方が名付けだよ」と言われた。貴方のように、といわれた。今ごろ⁉ 無責任だ、と思った。その後、彼女と文通した。会った途端に一生の付き合いと思った。必ず日本で会おうといった。今回それが実現してとても嬉しい。加藤周一先生との関係。私は四年生のフランス文学の学生だった。文学のコースの先生は、加藤周一先生。その時の感激はまだ覚えている。それで日本文学者になった。いつまでも恩師です。教えからインスピレーションを受けたのは私だけではない。世界中数千人いることでしょう。短い詩を読みたい。(原文は英語、うまいことメモできなかった)ふいに思い出す先生の棺に収められたのは論語、聖書、カントそして、永遠に読み続けたいという願望ありがとうございました。私にとってはずっと謎だったことがひとつ明らかになった。加藤周一とヒルダさんは離婚したのだと思っていた。別居はしたが、少なくとも憎しみあって別れたのではなさそうだ。死別したのだ。まるで森鴎外の舞姫だ。よくわからないこともまだ多い。質疑応答でいくらか出たのだろうか。大江健三郎は体調がすぐれない中で講演してくれたようだ。全部聞けなかったので、ちくま文庫「言葉と戦車を見すえて」を高く買っていて「戦後の名著、世界的な名著といっていい」とまで言ったことをメモしておく。
2016年05月08日
コメント(0)
-
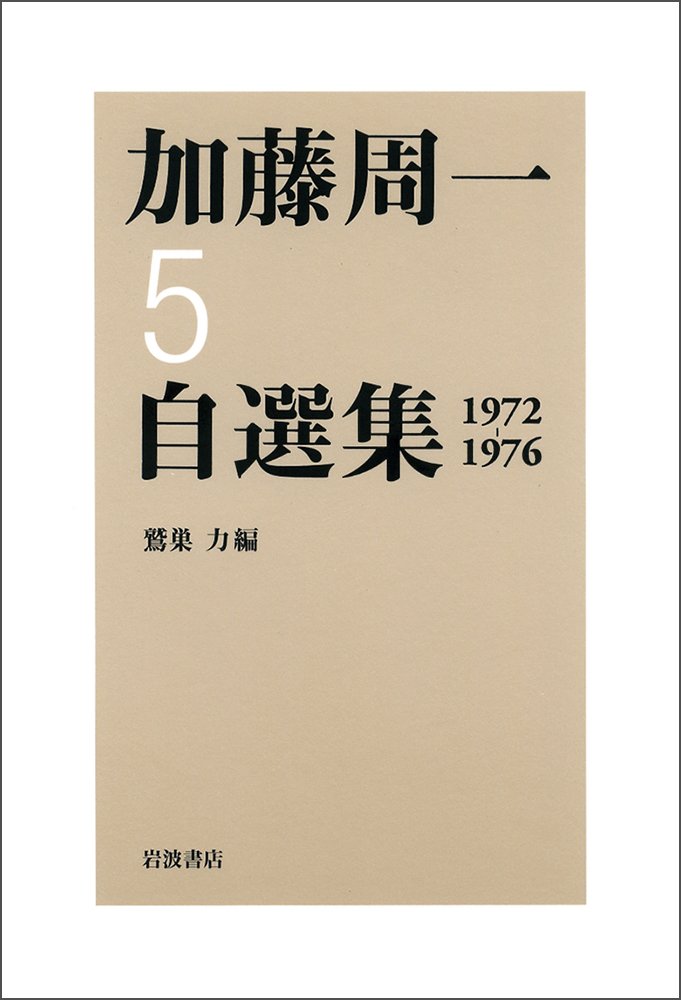
「鉄斎覚書」の覚書 「加藤周一自選集5」
兵庫県立美術館の鉄斎展を観に行く下準備として、とりあえず「加藤周一自選集5」(岩波書店)の「鉄斎覚書」という小文を繙く。加藤周一は鉄斎を「19世紀末から20世紀初めにかけて、日本の絵画は、ただ1人の鉄斎によって、記憶されることになるだろう。」(112p)と最大級の賛辞を寄せている。そのことを確かめに行くのが、今回の鑑賞の最大の目的である。たった3頁の文ではあるが、何時もの如く緊密に書かれている。ホントは全文を写しとった方が、私の学習にも良いのではあるが、ブログの性格上それはできない。よって、この一文を私なりにまとめてみるという少し無茶をやって私の覚書としたい。(略)しかし鉄斎の画業は、また大いに「文人画」の伝統的な枠を超えていた。時に緑、褐色などの淡彩を用いたが、またしばしば眼にも鮮やかな濃彩の画面をつくった(たとえば青緑、朱、青など)。前者の例には清荒神清澄寺蔵『古仏○図』、後者の例には『寿老分昇図』をあげることができる。(略)筆法は書にならって「気韻生動」の強い線を引くことがある。しかしまた墨をぼかしてその明暗により色彩的効果(「ヴァルール」)を生ぜしめる妙味もある。そこまでのところは大雅にもあり、木米にもあった。一転してその色彩効果が抽象的表現主義の見事な画面に及ぶのは、鉄斎において独特である。たとえば清澄寺蔵『水墨清趣図』の画面中央、家屋と人物の上および右の部分。風景を半鳥瞰的視点から描くのは伝統的である。『聖者舟遊図』(清澄寺蔵)の鳥瞰的視点は異例に属し、前述の『古仏○図』で下から見上げているのはさらに独特の構図であろう。(略)鉄斎はありとあらゆる様式で、ありとあらゆる対象を描いた(日本の伝統的な材料・題材・様式の範囲内で)。(略)多くの様式を併用したのは、先に鉄斎、のちにピカソ、けだし、天性の画家の途方もない表現欲があり、一個の様式に盛り込めないほどの多面的な世界があった稀有の例に違いない。鉄斎のもう一つの特徴は、ゴッホやルオーのように(またその他多くの画家のように)、その絵が成熟し、晩年にいたっていよいよ輝きを増したということである。(略)(110-112p)追記(略)鉄斎の芸術の歴史的な意味は、一時代の社会的変化が急激で、広汎であればあるほど、高度の芸術的達成は伝統的な芸術の枠組みの中でのみ達成される、ということに要約されるかもしれない。伝統的な芸術は、鉄斎にとっては、文人画とその材料・技術・題材であった。彼は決して油絵具を用いず、印象派の技術は採らず、裸婦を題材にしなかった。それにも拘らずーではなく、おそらくそれ故に、その伝統的な枠組みの中で、彼自身の、微妙に新しい様式を創り出すことができたのである。(略)(113p)○は合という字の下に龍。つまり、注目すべきは以下の部分である。色彩。抽象表現。構図。題材。晩年においての成熟度。これ等は確かに2ー3の絵を観てもわかるはずもないことだ。今回の大展覧会がまたともない機会である所以だろう。加藤周一は自分で実物を観ないでは、決して批評文を書かない人だった。ところが、その美術批評は文字通り古今東西に及ぶ。だからこそ、鉄斎とピカソとの類似性を指摘することができる。おそらく、明後日鑑賞して来ます。
2016年04月26日
コメント(2)
-

加藤周一「夕陽妄語」災害の責任
加藤周一の単行本未収録の「夕陽妄語」である。 いわく「災害の責任 2008/6/21(土) 朝日新聞朝刊」。胃がんで休載する最後から二番目のエッセイである。すでに病状は大きく進行していて、その一か月後に遺言ともいえるテレビ収録をすることから、医師である加藤にも死の覚悟ができつつある、あるいはできていたころだと思う。その時になぜこれを書いたのか(かなり大きく写真を載せたので見にくければ拡大して全文を読んでほしい)。直接のきっかけは、この記事が掲載される一週間前に非常に大きな地震がおきた。平成20年(2008年) 6月14日 マグネチュード7.2 「岩手・宮城内陸地震」 死者 17人 不明 6人負傷者 426人 住家全壊30棟 住家半壊146棟など 震度6強 実は恥ずかしながら、今回調べて初めてこの年にM7.2という今回と同等、阪神大震災クラスの地震が起きた事に気が付いた。完全に忘れていた。この三年後に東日本大震災が起きるなどとは、その当時岡山に居る私などは想像できていなかった。加藤周一はこの大地震をうけて、「天災」のあれこれについて考えたわけではなかった。明確にその後近いうちに(それは3年後かもしれないし、数十年後かもしれない)起きるであろう「大震災」の「責任」について考え、さらには天災のようにやってくる「戦争」に対する「責任」について述べたのである。その慧眼恐るべし。本当に恐ろしい。話の展開は、病気のせいかいつもの切れ味はなかったかもしれないが、その内容については、古今東西のあらゆる人間の現象に詳しく、物事を千年単位で見ることのできる稀代の人物の面目躍如たる文章であった。今記事をアップしようとして、この「災害の責任」と同じように、すこし記事の意図するところをあまりにも省略しているのに気が付いた。私の言いたいのは、当然今回の熊本地震のことではない。これからありうるであろう、南海トラフ地震のことであり、これからありうるであろう天災のようにやってくる「戦争」あるいは「戦争準備」について、我々ができることだ。具体的には、戦争準備のために年間5兆円を使うよりは地震準備あるいは今回の地震被害復興のために数兆円を使う方がいいだろう、ということである。さらに言えば、原発は速やかに停止、一刻も早く廃炉に向けて舵をきるべきだう、ということである。
2016年04月21日
コメント(2)
-

加藤周一「しかし、それだけではない。」
「しかし、それだけではない。」小森陽一対談集2 シネ・フロント社 他にも興味深い対談はあるのだが、ドキュメンタリー映画「しかし、それだけではない。加藤周一幽霊と語る」を撮った桜井均との対談に、多くの学びがあったので、その紹介を最優先する。まだ映画は観ていない。観るべきだと切実に思った。買うしかないのか⁉ 小森陽一 いま夢幻能とおっしゃいましたけど、複式夢幻能の場合、旅をしている法師なり、歌を詠む人なりが、まずその土地の人、現実に存在していると思われる人と出会って、いろいろ語らっていると、実はその人はすでに亡くなった、非常に深く重い過去を抱えていた誰かの霊であって、その後はその霊が自らを語り始めていく。それが複式夢幻能ですが、この映画全体はそういう形式を、結果としてなのかもしれませんが、入れ子状に組み込んでいます。幽霊と加藤さん、加藤さんと私たち、という具合に。(12p) 桜井均2004年に「9条の会」の呼びかけ人になられた。あのとき、もしかしたら中西さんに「加藤、今だ、行け」というふうに背中を押されたのかなと、僕は勝手に思ったんです。 小森陽一 私もそう思いました。つまり、霊の「乗り移り」というか、戦後ずっと加藤さんは中西さんの幽霊と対話をつづけていたんだと確信しました。(18p) 桜井均 (2006年東大駒場での講演会の)最後の方で「船が沈んでいくときに何を思うかというときに、残った人たちが十分生きてくれることだ。それには平和じゃなけりゃ生きられないでしょ。戦争やって何をするんですか。なんのために戦争するんですか」と強く言うところがあります。あれは最初、中西さんの話をしているんです。南方で船が沈んでいくときに中西さんがそういうことを思っただろうと。ところが途中から完全に中西さんと加藤さん自身が重なって「私」と言っている。 小森陽一 ある種の憑依、あるいは憑霊ですね。(22p) 今まで、ここまで中西哲吉という敗戦数ヶ月前にフィリピン沖に沈んだ加藤周一の友人のことが、形を持って現れたことはなかったと思う。加藤周一を語る上で重要な人物だとは思っていたが、どのように重要なのかはこれでハッキリわかった気がした。いや、小森陽一と桜井均に加藤周一の霊が憑依して、語らせたのか。 しかしそれだけではない、他にも重要な指摘が続く。 小森陽一 非常に文学的に重要なことを桜井さんはおっしゃったと思います。つまり、「今=ここ」というのが、一方では日本的現世主義というか、神道には教義がなくて今この瞬間に祝詞をあげればそれでいいというおさえ方がある。その態度は過去を切り捨て水に流し、未来も考えず、この場だけ辻褄をあわせればいいということにも一方ではなる。だけどそれとは逆に、過去を全部「今=ここ」に引き寄せているがゆえに、この瞬間に未来全体に責任をとるという自覚のもとに行動するという「今=ここ」主義もあるわけです。加藤さんの姿勢、たぶん「9条の会」の呼びかけ人になったときの決断は、後者の「今=ここ」主義だったのだと思います。(略)そうすると、そういう点でも「日本文学史序説」を今の桜井理論で読み直す必要がありますね。(略)石田梅岩の心学を論じているときも、彼は庶民むけには現世ご利益主義みたいになるけれど、自然観はすごく深い、と加藤さんはおっしゃっる。あの矛盾した言い方を解く大事なヒントをもらった気がします。 桜井均 加藤さんの場合、いつもわかんないですよね、今日はどっちだったんだろうと。 小森陽一 その両方を一緒に考えてらっしゃるのでしょうね。何度もそういうことがありました。(33p) 桜井均 僕はドキュメンタリーを作ってきたものですから実証主義的なところがあって、数えてみたら「しかしそれだけではない」という言葉が「夕陽妄語」で25回以上出てくるんです。他にもいっぱい出てきます。 小森陽一 (「夕陽妄語」を手にして)この付箋のところですか。 桜井均 そうです。そこを読んでいくと話がそこから急転直下、きりもみ状態で深まっていくんです。だから反語の「しかし」じゃないんですね。ただ「それだけではない」と言えばいいんだけど、語呂として「しかしそれだけではない」と言っている。(略)一回断定して、もう一回相対化するという、もう一つの眼があるんですよね。(略)もう一個の目で見ると、そこにいろんな人の想念がある。そこには、いくつもの一回性があって、言っておかなければならないことや人がたくさんいる。 小森陽一 加藤さんは、理不尽な死に方を強いられた一人ひとりのことを思っていらした。映画の中でも「なんど謝ればいいんですかというけれど、死んだ人みんなに謝らなければいけない」とおっしゃっていて、固有名を持った死者の一人ひとりが大事なんだということを加藤さんは強調されています。そういう思いにぐっと入ったときに「しかしそれだけではない」が出てくる感じですね。 桜井均 いつも自分を相対化しながら「もっとあるんだぞ」という感じなんですよね。中西さんの話はレストランなんかでしない方がいい。これだけは許せないんだと、ほんとに興奮して机を叩くんです。バーンとね。そうすると周りのお客さんがびっくりしちゃうわけです。あの顔で怒るわけですから。 小森陽一 ほんとに怖いですから、加藤さんの場合。 桜井均 実は実験で二回ぐらいやってみたんです(笑)。すると、条件反射的に机を叩くんですよ。 小森陽一 それがつまり、加藤さんの友人に対する記憶の身体化の在り方なのですね。(37-40p) 桜井均 若い人の中に、そういう人が結構いるわけです。そういう人がこの映画のどこで反応するかというと、先ほど触れた「橋渡し」のところなんです。加藤さんが「どんなちっぽけな人間でも、この世界に意味を与えることのできるのは自分なんだよ」ということをおっしゃっるでしょ。あそこに反応する若い人が意外と多いんです。(略) 小森陽一 そうだと思いますね。つまり、自分の中に独自の価値体系を持たずに、すべてまわりから評価されるだけ。とりわけ日本の点数競争だけの学校社会的な成績主義の中だけでしか自我形成ができていない。中味のない数値だけだから焦燥感をかきたてられる。だけど、どんなに焦燥感にかられながらやっても、所詮は他人の評価だから、全然自信にはならないわけですよね。その逆転現象が、ある時期まで流行った「自分探し」です。その言葉に騙されて、せっかく正社員で入社したのに、突然辞めてフリーターになってしまう。1990年代から若者たちが「自分探し」をさせられてきたとすると、「世界に意味を与えることのできるのは自分自身の意識だ」という加藤さんの言葉は、自分を一気に外へ開かせる力を持っています。さらに次の瞬間、もっと自分が問われることになる。世界に意味を与えられるかというと、簡単ではない。非常に鋭い問いかけになっていると思いますね。 桜井均 それを言って加藤さんは去っていくんです。(40-41p) 私も「序説」の読み直しと、「妄語」の中の「それだけではない」をもう一度読み返す必要を感じた。この対談(2010年)の概要は知っていたのだが、その全容は価値が全く違うものだった。やはり概要は概要だった。 加藤周一はたった5分間の「那智瀧図」のために根津美術館に赴き断っていた美術品に対するコメントを言う人だった。ガラス越しにではなく、直に絵を見るために苦労を厭わない人だったのだ。概要を知るということと、全文を読むということと、直に話を聴くということと、直に対話するということは全くレベルが違うんだということを再認識した。もはや直に話を聴いたり対話することは叶わない。ブログに書く場合は、全文を読んだ時に限ることを改めて決意する。 2015年4月23日読了
2015年04月27日
コメント(2)
-

なぜ若者はあんなに怒っていたのか?
昨晩、テレビで池上彰の「戦後70年をキーワードでとく」(題名うろ覚え)というたぐいの番組をしていた。昨日の池上彰繋がりでつい見てしまった。 その中のキーワードの一つ、「学生運動」「1968年のころ、なぜ若者はあんなに怒っていたのか?」という流れの解説があった。 日大闘争、東大闘争などを簡単に解説したあと、コメンテイターたちが感想を言い合っていたが、言っていること自体はあまり間違っていないと思った。 室井佑月「(ホステスとして)飲みにきた人に聞くと、『よくよく考えると女にもてたかったから』と言っていた(笑)」 池上彰「世の中が豊かになった。格差を変えたかった。当時の学生は、エリート意識があった。世の中をよくしたいんだ。でも客観的には独りよがり。」 当時学生だったおじさんたちの言葉「模索することが、エネルギーだった」「社会にたいする怒りを出すことに誇りを持っていた」「当時の学生はよく議論していた」「思想からはいった」 番組の基調はひとえに「現代の若者にはとても見られないことだよね」ということのみだった。 アジ演説があった。「学生さんたちがんばれ」という空気もあった。 1968年新宿騒乱。駅周辺に集まる二万人の写真。これが最近の国会前の原発集会のような写真になっていた。しかし、おそらく1968年の方が若者密度が高い。 若者はどこに行ったのか。単に集会に誘われただけの若者は「いちご白書」の世界に移った。就職活動。「もう若くないさ、と髪を切ってきたよね」 そして「たった一つの事件で熱が冷めた。」浅間山荘事件。それに続く内ゲバの悲惨さ。あれで皆が「引いた」。と池上彰は解説する。事実としてはその通り。しかし、政府とメディアがそれを後押ししたことには触れない。 番組は「若者の怒り」は「世相」であったというまとめに終始していたと思う。 伊集院光「いま無関心が多い。中間がいい」 室井佑月「みんな世界の平和願っているのに」 というコメントもあったが、そこは全然深められない。私は池上彰の番組は、結果的には現状追認の保守を助ける番組だと思う。しかし「学生運動は怖いから関わるな」という昔の意見を少しづつ変えていく力には、なったとは思う。 原発問題、戦争立法問題、貧困格差問題。産学協同問題。1968年当時の問題はさらに深くなって我々の目の前にある。それを打開する道はどこにるのだろうか。 そのヒントはやはり加藤周一にあると私は思う。 『テロリズムと日常性』(加藤周一 凡人会 青木書店)のなかで加藤周一は次のようなことも言っている。 加藤周一は「日本の学生運動は生き甲斐主義で、権力に対する反発に終始してしまった」と総括する。 加藤は現状打開の可能性をひとつの「行動」の中に見る。 『小さなグループがいくつか連携して、具体的な問題をひとつ解決する。そういう流れをだんだん広めていって、地方行政を動かすような規模になって、ある程度社会的な力を持つ…ということがあり得るんじゃないか。』 大きな目的を掲げるのではなく、まずは行動しようといっているのだ。それは世界の戦後(フランスの五月革命、チェコスロヴァキアの『プラハの春』、アメリカの黒人運動)を見ていていた加藤が提言する「世界の教訓」である。 と、同時に「部分から全体へ」という日本的文化の特徴を活かした、「日本らしい」運動の仕方でもある。 9条の会は、そういう運動の一つとして有効だろう。ただ、それに固まってはいけない。と私は思う。 私が事務局をしている「平和委員会」の活動も、そういう運動の一つだろう。労組の活動もそういう運動の一つだろう。原発反対の金曜日行動もそういう運動の一つだろう。 このような運動に、若者も参加して欲しい。一部では動きが出ている。一部だけだが。 これらの運動が 「ひとつの課題を解決する」ようになることが重要なのである。 原発稼働を阻止しているのはその一つの現れだろう。 →「自治体に影響を及ぼすようになる」 そういう段階はまだかもしれない。 いま世の中は全体として、危機的状況にはあるが、まだ綱引きの状況にあると私は思う。
2015年03月31日
コメント(0)
-

「『羊の歌』余聞」余聞
『羊の歌』余聞 (ちくま文庫)[本/雑誌] (文庫) / 加藤周一/著 鷲巣力/編 鷲巣力は全集的な「自選集」の他に幾つかこのような短編集を編んでいる。この本は、主に加藤周一が自分周辺を書いたり語ったりした文章を集める。それは同時に学者の加藤周一が文学者に変貌する時でもある。加藤周一の散文はそれほど魅力的であるとわたしは思う。 鷲巣力は、「加藤周一が加藤周一になっていくうえで、戦争体験が大きな意味を持ったが、もう一つ大きな影響を与えたのは、抒情詩の読書体験である」(338p)と述べる。抒情詩体験については、マチネ・ポエティクを紹介した時に一部書いた。戦争体験については、展開を始めるとこの小さな文章では書き切らない。 ただ、「私が小学生だった時」(「夕陽妄語」2006)に出てくるこの一文は、加藤の意図を離れていろんな感想が吹き出てきたので、ちょっと紹介したい。 たしかに小学校には「いじめ」もあった。教師の権威と力は圧倒的であったから、教室ではなかったが、校庭や通学の途中にそれはあった。病気がちの子どもで、腕力に乏しかった私は、いじめる側にまわったことはないが、いじめられる側にまわったことはある。私には自衛の工夫が必要であった。 教師や親たちに助けを求めることはできない。私は同級生の中でも腕力のいちばん強そうな子供に接近し、その暴力による保護を求めた。その代わりに教室で教師から質問され彼が窮地に陥ったときには、秘かに解答を彼に手渡した。そのことに気づかない教師もあり、気づいても黙認していた教師もある。 そういう取引は中学校ではさらに徹底した。私は今でも日本国の外交姿勢を見ると、小学校での私の「いじめ」対策を想い出す。(157p) 念のために注釈を加えると、加藤は小学校時代の「いじめ」対策を日本国外交に援用するのが良いと主張しているわけではない。しかし間違っているといっているわけでもない。 私の感想は、だから、加藤の「いじめ」対策ケース(以下「加藤ケース」と云う)は、日本国外交姿勢のミニチュアモデルとして極めて使いやすいと感心したことにある。 ●小学生に加藤ケース以外により良き方法はあっただろうか。 (1)9条憲法を持つように、綴り方の時間に有効な「宣言」をしたらどうか。宣言にも依るだろうが、効果があるようには思えない。 (2)戦後大国と軍事同盟を結んだ国のように「腕力の強そうな子供」と戦争を仕掛けて、安定化を目指すのは?それでもし成功しても、加藤が得たかったものは一切手に入らないだろう。特に穏やかな時間は。 (3)1人で勇気を持って交渉に出掛ける?しかし、それが出来なかったからいじめられたのである。 加藤の周りには、既に暴力が蔓延していた(級友や教師の権力)。この「周り」の改変がない限り、彼が「いじめ」から脱する「根本的な有効な手だて」はないのではないか。加藤周一は秘かに、その改変の力の源泉を母親から貰った「愛」に求めているようだ。さて、現実世界では何に求めればいいのか。 2015年3月21日読了
2015年03月26日
コメント(0)
-
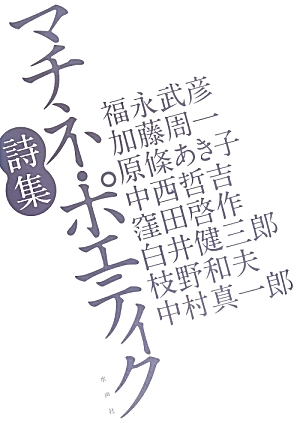
死を意識した青年たちの「マチネ・ポエティク詩集」
「マチネ・ポエティク詩集」福永武彦・加藤周一・原條あき子・中西哲吉・窪田啓作・白井健三郎・枝野和夫・中村真一郎 水声社 戦前において唱えられた日本の詩の「厳密な定型詩」の運動は、結果から云えば失敗だったらしい。しかし、その日本文学史においての位置をわたしは、検討する能力がない。 それら同人たちの中で、福永・加藤・中村が巣立っていることの意義も、わたしは検討する立場にない。 ただ、長い間この詩集は絶版状態で、その全貌は不明なままだった。ここに重要な詩評を併せて復刊成ったことの意義は大きいだろう。 福永武彦の詩の厳密さは理解出来る気がするが、加藤周一や他の人の定型具合は、わたしにはわからない。その効果、または詩の全体的な素晴らしさも、よくわからない。 ただ、加藤周一の「さくら横ちょう」などを読むと、未だに昭和歌謡として歌われているらしい、ことなどを聞くと、韻を踏む定型詩の日本の歌詞に与えた影響の幾ばくもあったのかもしれないと思うだけである。 その加藤はマチネ・ポエティクについて、その始めた理由をのちにだいたい以下のような理性的な分析を施している。 一つ、何人かが「万葉集」の読書会に参加していて、規則化された詩の押韻の可能性に興味を持った。 一つ、幾人かがボードレールたちの反ロマン主義、反自由詩の方法論に興味を持った。 一つ、九鬼周造の日本語押韻の理論と試作を頼りにしていた。 一つ、戦中の時代に「おそらくのこり少ないと思われた人生の最後の時」を神に祈ることの代わりに、クロス・ワード・パズルを解くように「他にすることがなかった」。(「中村真一郎、白井健三郎、そして駒場」より) マチネ・ポエティクのほとんどに、いやすべてに、理論的な詩群がない。それは偶然なのではなく、死を意識した青年たちの死ぬ前に人のとる道だったのかもしれない。 あの理論派加藤周一でさえ、全てこんなにも少女趣味的な詩ばかりを残している。 「さくら横ちょう」 春の宵 さくらが咲くと 花ばかり さくら横ちょう 想出す 恋の昨日 君はもうここにいないと あゝ いつも 花の女王 ほほえんだ夢のふるさと 春の宵 さくらが咲くと 花ばかり さくら横ちょう 会ひ見るの時はなかろう 「その後どう」「しばらくねえ」と 言つたつてはぢまらないと 心得て花でも見よう 春の宵 さくらが咲くと 花ばかり さくら横ちょう 2015年3月20日読了
2015年03月25日
コメント(4)
-

9条の会の弱点「憲法9条新鮮感覚」
「憲法9条新鮮感覚 日本・ドイツ学生対話」加藤周一+浅井イゾルデ 桜井均編 花伝社 加藤周一は93年に日本とドイツを比較して「戦後の世代にも戦争責任はある」という考え方を述べた。しかし、それはあくまでも自覚的な平和運動家だけに知られており、一般常識にはなっていない。世の中には依然として「生まれる前の戦争のことで、どうして国が何度も謝らなくはならないのか」という頓珍漢なことをいう人たちが多くいる。いや、却って増えているというのが現状である。 それはすなわち、日本の平和運動の欠点の現れでもあるだろう。その欠点と直接結びついているかどうかは精査が必要だが、この本の冒頭言で加藤は9条の会の「弱点」をふたつ挙げている。 一つ、国際的協力の面はまだ極めてせまい。9条改憲は本来国際問題でもある。 一つ、9条の会に集結している方々の構成員に問題がある。老人が多く、若者が少ない。 この指摘に、私は目を開かされた思いがした。死せる加藤周一生ける我々をさらに走らす。 この前ドイツのメルケル首相が日本にきたとき、エネルギー問題や歴史認識問題で、安倍には耳が痛いことを言ったらしい。しかし、本当はもっとドイツとの対話が進んでいたならば、メルケルを9条の会の全国討論集会に呼んでシンポを開くことが出来たかもしれない。もしそういう「幅広い運動」が出来るようになれば、9条の危機は回避されるだろう。 加藤周一が亡くなったのは、2008年12月だった。1-3月に不調を訴えて胃癌が発見されて、夏に最後の力を振り絞って1968年の革命のことについて話をしたのだ。それは民主化の国際的な運動であり、若者の運動だった。この本は2008年4月に刊行されている。まさに準備段階のときに加藤に、病魔が忍び寄っていたのである。その本が「若者たちの」「日独学生対話」であったことはすごいと思う。 残念ながら、学生たちの議論は、まだ一般常識の範囲を超えてはいない。理論としても、行動レポートとしてもみるべきものはなかった。しかし、試みそのものは、例えようもなく貴重である。 2015年3月18日読了
2015年03月24日
コメント(2)
-

今こそ必要「戦争責任の受けとめかた」
「戦争責任の受けとめかた ドイツと日本」加藤周一著 編集・国民教育文化総合研究所 アドバンテージサーバー発行 加藤周一の戦争責任論については、「戦後世代の戦争責任」(かもがわ出版)などの普及版があるので、広く世に知られている。しかしそれより少し前に出版された本書は、現在では絶版となって手に取ることはなかった。初めて読んでみて、重なる所は当然多いがこちらはひとつひとつドイツと比較して、結果的かなり突っ込んだ議論になっている。 加藤の考え方は以下のものだ。聞いたことがあるかもしれないが、今こそ繰り返し主張しなければいけない時だと思う。 戦時下のさまざまな犯罪は、あるいは戦争自体は、日本の社会、文化が生み出したものです。(略)1945年以来、たしかに日本の歴史的社会的文化的条件は大いに変わりました。しかし、まったく変わったわけではない。問題は何が変わり、何が持続しているかということです。南京虐殺を生み出した社会的文化的条件からの離別、戦前の日本社会との断絶に、だれが努力しているか、だれがそうしようとしているか、ということです。それはいまの日本人全体の問題です。(略)残念ながら戦後の日本では、かつての日本の社会的文化的条件を 突き崩してゆこうとする実際的な作業や努力がない。少なくともそれはきわめて希薄です。そしてそのことにこそ、日本人全体の責任がある。(8p〜9p) 我々はいま、その責任のツケを払わなくてならない立場に立とうとしている。そんないまだからこそ、ここの議論の詳細に少し耳を傾けるべきだと思う。 ●ドイツでは「頽廃芸術展」や「大ドイツ展」などをしている。日本ではなぜ戦争を賛美した戦時中の絵画の展覧会が開かれないのか。なぜ「禁演落語大会」が開かれないのか。能の「蝉丸」、「大原御幸」も抹殺された。歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」の「せまじきものは宮仕え」が禁止された。 ●「なしくずし」に国外で戦線が拡大していくと同時に国内でも体制がファッショ化する。不思議なのは、80年から90年代にかけて言論や思想や政党の主張でも10年前あるいは5年前とまったく逆の言論や主張になって、それに対する弁明や転換の根拠が明示されなかった。しいてその根拠を探れば大勢がそう動いているから。かつては「時局」が使われた。いまは「現実」という言葉が使われている。(←現代にも当てはまる) ●個人としても、戦争犯罪(捕虜虐待や従軍慰安婦)になぜ加わったのか、拒否できなかったのか。そのことを深く考えてみる必要がある。戦後の日本国憲法や労働基準法でも、労働者の意思に反する労働の強制を禁じているのですが、「現実」はそうはなっていない。 ●日本人の手による戦争裁判はひとつもない。(←それから20年後の現代でも同様である) 2015年3月11日読了
2015年03月23日
コメント(2)
-

【悲報】9条の会の聖地消滅
4月24日東京に来た序でに、9条の会の「聖地」に行こうと思った。しかし、たどり着くと其処は消えていた。 2009年11月11日、2010年2月17日の私のブログで私が二回に渡って探索した結果、加藤周一さん行きつけの喫茶店は上野毛駅前の「ル・サフラン」で間違いない。しかも、後で小森陽一さんの証言があったのだが、加藤周一さんと小森陽一さんはここの二階で初めて9条の会の話をしたのである(最初の言い出しは加藤であり、小森が事務局を引き受けることで、この会はスタートした)。だとしたら、この喫茶店が戦後の支配層の改憲戦略を戦略でもって止めた大運動になった「聖地」でなくて、なんであろうか。 私は二回目の訪問の時に、店の主人から「ええ!いつもここを利用してくださっていました。いつもミルフィーユを頼まれていたんですよ。寂しくなりました」との証言を得ていた。しかし、その時ミルフィーユは品切れだったのだ!私はいつか再訪することを誓っていたのだが、貧乏が祟りこんなに遅くなってしまった。そうして、やっと来ると「ル・サフラン」はなく、次の新しい店の改装工事をしていたのである!工事関係者が「前の店は畳んでしまった」と言っていたので、私は永遠に加藤周一が好んだミルフィーユを食べ損なったということになる。これが悲報でなくて、なんであろうか。 正当な聖地とミルフィーユは永遠に消え、今は「9条の会誕生跡地」という場所だけが残ることになった。場所は駅前のローソン横、ケーキ・パン・デリ「ラ・フェエゾン(予定)」である。 悲報はもう一つある。写真は載せることが出来ないが、加藤周一さんの旧宅は取り壊されて新しい住宅地になっていた。仕方ないことではあるが、寂しかった。 万が一ということを考えて、駅前にもう一つある喫茶店「カフェ・アンバール」で珈琲を頼んだ。ミルフィーユは置いてなく、当然二階もなかった。美味しかったが、高かった(500円)。
2014年04月26日
コメント(2)
-

『加藤周一における「時間と空間」』を読む
「加藤周一における「時間と空間」」ジュリー・ブロック編著 かもがわ出版二つのシンポジウムの記録を加藤周一の著作をフランス語で翻訳したジュリー・ブロックが編集した本である。八割は外国研究者の報告の翻訳という労作なのだが、如何せん深いものは無かった。唯一良かったのは、加藤の最後の肉声を撮り、映画まで作ったNHKの桜井均氏だけだった。また、貴重な矢島翠さんのインタビューもあったので、何が書いているのか緊張したのだが、ほとんど新しいことは語っていなかった。唯一びっくりしたのは、出会いはわりと早かったこと、一緒に暮らし始めた時期が確定したことである。桜井均の講演より加藤さんは、日本の大勢順応主義、現在主義を生涯批判し続けました。「過去のことを水に流し、明日は明日の風が吹く」として、現在をあいまいに拡大し、責任を決してとらない日本人の態度、これを悪しき「今=ここ」主義と定義します。加藤さんは、これとは正反対に、過去の責任を現在に引き受け、未来の責任も現在に引き寄せ、意識を現在に集中し「今やらなければ」という思いで、多くの人々のところに足を運ばれたと思います。これが大勢順応主義、悪しき現在主義の対極にある、加藤さん流の「今=ここ」主義だと思います。(160p)加藤さんは、ギリシャのテオ・アンゲロプロス監督の「永遠と一日」という映画が好きでした。死期が迫った老詩人が、アルバニアから越境してきたストリートチルドレンを助けます。なぜその少年を助けたのか?彼が老人の目の前で警官に取り押さえられそうになったからで、老人にとって目の前のたった1人の少年の命が問題なのです。「永遠と一日は同じ重さである」、「一日の中に永遠をみなければ人生に意味はない」と加藤さんは言います。日本語で「永遠」という言葉は、「永い」という文字と「遠い」という文字を含んでいます。長い「時間」の連なりと、遠くまで広がる「空間」。つまり、意見を変えない遥な死者と、遠い異国の理解者と語ることは、「今=ここ」に意識を集中するものにしか出来ません。はるか昔の死者や遠くの国の理解者に希望を繋ぐという話を加藤さんはよくしました。信濃追分のベンチに刻まれたラテン語「In tera pax…(地には平和を…)」は、絶望的な戦中の加藤さんにとって、この村に少なくとも1人、自分と同じように平和を願う人間がいる、これはまさに「永遠」からのメッセージだったのです。死に直面した実朝、アルバニアの少年の命を救う老詩人、両者に共通するのは、限られた生の最後における「決断」です。そして信濃追分のラテン語は、絶望的な世界に「意味」を与えることの「希望」の象徴です。晩年の加藤さんから、私はジャーナリズムが「決断」の仕事であり、世界に意味を与えることができるという「希望」を教えられました。(165p)矢島翠、加藤周一を語る(2009年4月)矢島は共同通信に入って二年ホノルルにいた時に加藤周一と知り合ったらしい。一緒に暮らし始めたのは1969年から。「昔のことはあまり知らないけれど、ただ戦争にはずっと反対だったことは確かですね」「(日本の最も変わらない点は)天皇制でしょ。(笑)まあそれから、物事の細部ですね。ディテールに注目して、それを大変美しく表現するという。そういうことは日本人はいまでも、じゃないかなあ(笑)、変わらないことだけど。その代わり、物事を大局的にみて、そしてとくに世界のなかに置いてみて判断するということは、あまり得意じゃないということも変わっていないんじゃないかしら。」2012年10月18日読了
2012年10月31日
コメント(0)
-
未曾有の危機の中で加藤周一に学ぶ
小森陽一さんが3月26日、名古屋哲学セミナー主催で「未曾有の危機の中で加藤周一に学ぶ - 「日本文学史序説」の思想―」という講演をしていた。西川さんという方が、その講演録をメモしてくれているのでその大要を読んだのだが、重要なことを言っていると思えたので、メモしたい。講演録のメモに対する感想なので、群盲象をなでる如しではあるが、方向性はもらったような気がしたのである。大要は読んでもらうとして、ここに書かれていることに刺激を受けた。「自然大災害を恨んだりしていない被災者たち。現実の中から元気を奮い立たせようとする被災者たち。困難な状況の中で、生き抜こうとしている被災者の意識は、かってその全てが、天皇制と言う特異な装置によって翻弄されてきましたが、今こそ、我々は、これを掴みなおし、変えていくことが出来ると考えています。もう一度、加藤周一氏が、「九条の会」設立を決断された生き方を学ばなければならないと思います。今こそ、日本人の此岸性、死者を通して、生きている我々が、立ち上がる時を迎えなくてはならないと思います。死者の記憶と会話して、今をどう生きるか、我々にとって、今こそ重要です。」日本人の中の土着思想はともすると、時の支配層に利用されてきたのですが、「変えていく」契機はあるというのです。「日本の文学と造形美術、工芸作品には日本的思想表現が見える。日本的表現とは、具体的であり、非体系的であり、感情的表現であり、日常目に触れる対象を美的に表現してきた。従って、ここでは世俗的な変化を好み、体系的、論理的なものを、日常的なものの中に取り込み、実践的、具体的に日常に即して、個別的な現場を重視するのが日本文化であり、部分から全体を作るのが日本文化である。日本語は、持続的文化の新旧交代ではなく、古いものを受け入れ、これを新しいものと共存させていく。これは短歌の世界にも見ることが出来る。日本文学の歴史は、多様な形を保っている。この特質が、社会構造に結びつく時、先ず極端な保守性として表れ、天皇制はこれを利用してきた。しかし、一方、日本文化は、新しいものを、ドンドンと取り入れる特色も持ち、例えばそれが、新技術の採用、新型消費財の登場・新語乱造にも発揮されている。日本文学と、美術表現の優れた面を支えているのは、2重構造であり、表意文字と表音文字の意識的使い分けもその一つとして指摘される。」原発ムラの構造的な把握は日本人の苦手とするところかもしれないけれども、身近な放射能から「命を守る」という一点で、「ひとつになろう日本」ということは、ありえるだろう。部分から全体へ。
2011年04月23日
コメント(17)
-
「加藤周一が語る」憲法を活かすということ
昨日の続きです。小森「加藤さんは2007年11月の第二回全国交流集会で、今までは九条を変える、明文改憲ををすると言ってはばからない安倍政権のような単純な政権に対し、広範な一致点で九条を守ろう、といってきた。(略)けれども福田政権に替わって、理屈も扱い方も慎重になった。そうしいう中で九条を「守る」だけでなくて、「生かす」運動に転換していかなければならないし、それは長丁場のうんどうになるだろう、こうおっしゃいました。(略)」加藤「はじめに、二つの動詞、「守る」と「生かす」とが、どう違うかということですが、まず「守る」ほうは、今小森さんが言われたような、名文が憲法に書かれているのだから、その条文を変えないということで、ことに一項、二項を変えないのが「守る」でしょう。(略)非常にハッキリしていると思う。だから、スローガンとして生きると思う。 ところが「生かす」のほうはそうではないと思います。どういう政策を採るか、いくつか選択肢があり、その中のひとつをとるとき、今度の政府は少なくともそれが唯一の生かす道だとはいわず、いくつかある生かす道のひとつだというだろうと思います。それに対してわたしたちは「そうではない。それはいくつかある憲法を生かす道のどれにも属していない。あなたの提案している政策はどういう意味でも憲法を生かすことことにならない。憲法の精神を殺すことになるんだ」、ということをいわなくてはならない。(略)仕方ないですね。相手が変われば、こちらも変わらないわけにはいかない。だから、憲法についての考えをそもそも細かくし、それをあらかじめ内面化することが必要です。一人でするのは大変だから、みんな集まってお互い助け合いながら、理論的に整理することが必要です。つまり「憲法九条は変えたくない、守りたい」と言ったら、「しかし、解釈をもっと自由にする必要があります」という反応がきたときに、それを反駁し、反論する理屈をやはり考えなくてはならないということです。しかるべくよく勉強して、毎日の積み上げでもってしっかりした理屈をもっているように進んでいかなくてはいけないと思う。それが私のいう、単に守るのではなくて生かす必要があるということ、精神を生かすことなのです。」→この発言の背景としては、福田内閣の当時の情勢があったわけだが、その後民主党政権が誕生し、憲法問題が一時期後景に押しやられた現在いよいよ現実的な課題となっている。民主党政権がついに解釈改憲をタイムテーブルにのせてきたのである。この九条の会がこの数年、憲法を語る会を企画し、一見憲法とは関係ないようなテーマや人物も呼んできているのは、まさにこの加藤周一の問題意識を受けてなのではないだろうか。「憲法についての考えをそもそも細かくし、それをあらかじめ内面化することが必要です。一人でするのは大変だから、みんな集まってお互い助け合いながら、理論的に整理することが必要です。」ほんとうに大変だけども、昨今の海兵隊抑止力論が出たときに、沖縄だけでなくて、日本全土で草の根学習会ができるような、そんな力量を私たちは持っておかなければならない。言うは易く……。加藤「(北朝鮮問題について)私は経済封鎖しないほうがいいと思います。経済封鎖は中途半端です。平和的に解決するというのが、憲法の精神なのだから、それで押し通すべきだと思います。経済封鎖をやれば、それで足りなければ武力封鎖ということになるわけです。あるいは、経済封鎖をして本当に有効に働かせるつもりならば、必要に応じて武器を使わざるを得ないというようなことになる。たとえば、今言っていた臨検です。臨検して相手が抵抗してきたらどうするのですか。(略)初めから武力を使うことを念頭に入れながら圧力を加えるというようなことをすれば、本当に使わなくてはならなくなる可能性が高いと思います。」→たとえば、北の脅威がゼロということはないと思う。しかし、そのためにやれ核兵器を持てとか、経済封鎖だとかという発想は「現実的ではない」と私は思うのです。加藤「今日本は分かれ道にいる、というスローガンがありますね。(略)どちらをとるかということは決めたほうがいい。そうしないと実行することが困難です。いま勉強して反対だったら、できるだけ憲法の精神に反する道は歩きたくないという。戦争は嫌いだと言わないで、日本が戦争を始めたり、戦争に参加するような道を開くことに反対だという。主語は日本国であり、そして、今すぐ戦争をするかしないかが問題ではなくて、戦争へ繋がっていく道をとるかとらないかが問題であることに気づくことですね。(略)見逃してはならないのは、やはりなし崩しということ。変化が小さいから見逃していいのではなくて、小さい変化にこそ注意すべきだと私は思います。」→ここは、非常に大事なことだと思う。(2008年4月対談)加藤「戦争準備で大切なことが二つある。一つは武器を持つこと。その結果、軍産体制ができる。しかし、武器だけでは戦争は絶対にできない。(略)すくなくともある程度まで多くの国民が戦争を支持しなければ、戦争はできない。」加藤「(宣伝で気をつけること)戦争が正しいんだという信念。または錯覚、あるいは狂気、哲学。ともかく精神的なもの。(略)私が警戒するし、好まないのは「富士山は日本一の山」のあとに「世界の人が仰ぎ見る」ということ。(略)「日本一の富士山」まではファシズムではないけれども、「世界の人が仰ぎ見る」にはある錯覚があり、価値観の押し付けがあります。だから「世界の人が仰ぎ見る」が始まったら危ない。戦争準備ということを警戒したほうが言いと思います。」→このあたりの加藤のまなざしは、すでにあと10年スパンで気をつけることを言っているのだと思う。それから二年立った。あと、八年、われわれは戦争の芽に敏感でなければならないと思う。もちろん、気がついている人は既に気がついている。法律の改悪?有事立法は既に成立している。国民投票法は既に成立している。タブーは?教育基本法改悪は既になった。批判的な組織は?朝日新聞は九割がたもう駄目だ。組合は30年以上前からがたがただ。小選挙区制で反対政党は10年以内に0か1になるかもしれない。なし崩しということ。けれども、まだ希望はある、きっと。
2011年04月18日
コメント(2)
-
「加藤周一が語る」日本外交の弱点
「加藤周一が語る」聞き手小森陽一 九条の会編集このパンフは九条の会から取り寄せて読ませてもらいました。二回の対談があり、最後は2008年4月26日であり、この直後に胃がんが発見されているから、実質最後の対談本だといっていいのかもしれない。(加藤周一の絶筆は夕陽妄語七月掲載分、最終発言はETV特集)だが、しかし、ここにも遺言といっていい発言が多くあり、読んでよかった。ランダムに紹介したい。(2007年12月1日の対談)小森「問題の整理をします。ほとんどのマスコミが論評していない(大連立を話し合った)小沢・福田密室会談の意味、それは、いままで日本の歴代政権があいまいにし続けてきた対米関係を重視するのか、それとも国連を重視するのか、この二者択一に関して、小沢一郎ははっきりと、対米よりも国連の安保理の決議を重視するという意見に踏み込んだ上で会談がもたれたことにある。」→正直、大連立構想に対してこの視点を私は持っていなかった。加藤氏の慧眼に敬服します。この時点でここまでハッキリしていたことは重要です。なぜならば、鳩山が2010年1月突然ころりと意見を変えたのは、まさにこの点に関してアメリカから「恫喝」に近い要請があったからだろうと想像できるからです。現在の「小川叩き」はまさにここに関係しているだろうと私は思います。国連重視案の是非は置きます。2011年春に突如起こった「大連立」の意味はまったく違います。いまや、民主、自民共に「対米従属」の立場は同じ。これにTPPがなれば、みごとに米国の属州化は完成でしょう。加藤「(「テロとの戦争」からの軌道修正について)はじめはかなりの国がイラク征伐をした。だけど、その戦争を支持していた国はだんだんと減ってくる。(略)どうしてそうなるかというと、大衆が反対だから。だから、大衆の反対が世界政治をかえるということのひとつの非常に鮮やかな例が、今われわれの眼前で起こっているということになると思います。」→これが10年スパンで考えたときの世界史の流れです。日本にいるとなかなか見えてみえてこない。日本は極めて例外的な動きをしているのでなおさらです。加藤「日本の外交の弱みは、日英同盟の頃から、つまり明治から、いつも孤立することへの恐怖です。だから何とかしてその孤立を破りたいという感じが非常に強い。たぶん日本外交の要のひとつは、孤立を破ることだと思います。ところが、あるときには成功し、あるときには成功しないわけですが、こと最近はあまり成功していません。今の日本は、確かにアジアの国々から孤立している。日本は中国や韓国の若者が一番あこがれる国ではありません。いくら日本の政府でも、そのくらいのことはもちろん知っていて、アジアで孤立していることは感じていると思います。ただし、その全部に匹敵するくらいの強力なボスがアメリカで、アメリカに頼っていれば、たとえその周りの連中がいくら日本嫌いでも、それからトラブルにになっても、いざというときにアメリカが助けてくれる。(略)ところが、そのアメリカが変わるときがくると、本当に孤立するわけで、日本にとって不幸なことになると思います。(略)日米関係は日米一体であるといっても、そんなに一体ではない。日本側はそう思っているかもしれないけれど、米国側は別に一体だと思っていない。(略)彼らは、そういうことで外交政策を決めません。それは文化の違いであって、鶴の恩返しなどと日本では言うけれど、アメリカの恩返しはそう期待できないだろう、と私は思います。」→ジャイアンとスネオの関係のような、心理学の面からこれからの処方箋をかけるかもしれません。この指摘は、もしかしたらかなり予言的かもしれません。実際、アメリカはいつでも日本を切るでしょう。日本はそれができない。自公民がやっている限りでは。小沢のときにその可能性はありましたが、アメリカ財界、自公民、マスコミが全力を出して潰してしまいました。見事なもんでしたね。
2011年04月17日
コメント(2)
-

丁丑公論私記 2011 (下)
「丁丑公論」の「緒言」は次のように始まる。「およそ人として我が思うところを施行せんと欲せざる者なし。即ち専制の精神なり。故に専制は今の人類の性といふも可なり。人にして然り。政府にして然らざるを得ず。政府の専制は咎む可らざるなり。 政府の専制咎む可らずといえども、これを放頓すれば際限あることなし。又これを防がざる可らず。いまこれを防ぐの術は、唯これに抵抗するの一法あるのみ。…… 近来日本の景況を察するに、文明の虚説に欺かれて抵抗の精神は次第に衰頽するがごとし。いやしくも憂国の士はこれを救ふの術を求めざる可らず。抵抗の法一様ならず、或いは文を以ってし、或いは武を以ってし、又或いは金を以ってする者あり。今、西郷は政府に抗するに武力を用ひたる者にて、余輩の考えとは少し趣を殊にする所あれども、結局その精神に至りては間然とすべきものなし」。つまり、日本社会において「権力の偏重」が起きれば、必ず「抵抗の精神」が起きるのだ、このチェックアンドバランスが大切だと福澤はいっているわけです。福澤は西郷の武力による抵抗の仕方には異論があったようなのですが、それについてはここでは解説しません。ここで注意したいのは、暴力による抵抗の是非の一般理論でも、その1877年当時における歴史的な意味でもない。むしろ福澤をして「抵抗の精神」の必要を痛感せしむるに至った当時の状況そのものである。「近来日本の景況を察するに、文明の虚説に欺かれて抵抗の精神は次第に衰頽するがごとし。」この一句、今もし「文明」の語に換えるに「グローバリゼーション」の一語を以ってすれば、そのまま140年後の今日にも通用するだろう、と私には思われる。現在の日本の状況は、小選挙区制施行より引かれた二大政党制の弊害いよいよ大きくなり、一方の政党である自民党の質問内容を見れば、基本政策はまた同じ。小沢一郎が四面楚歌の中に立ったのは、そういう状況のなかにおいてであった。渡辺治が民主党政権直後に分析したように、民主党には三つの立場がある。グローバリゼーションの推進を掲げる前原等のいまや民主党主流派、従来の自民党体質である地方利益を代表する小沢一郎の派閥、そして小泉政権の被害を背負った庶民の立場を代表して前回衆議院選挙で当選した新人議員たち。米国と利益を同じにする民主党主流派の議会内反対勢力を潰そうとするならば、先ずは米国の利益とは違う方向に行く小沢一郎を敲くに越したことはないだろう。ここを敲けば、新人議員の多くは機能不全に陥るか、こちらに寝返ざるを得ない。小沢一郎が反対勢力としての機能を失えば、政府の専制に対抗できるのは、おそらく共産党、社会党のみといって過言ではないだろう。ここを孤立化させれば、社会党は与党との提携を求める傾向がある。孤立化した共産党の「抵抗」は怖るべき者ではないだろう。1877年に妥当した議論は、2011年にも通用するだろう。すなわち「政府の専制咎むべからず」しかし「これを放頓すれば際限あることなし」。ゆえに「抵抗」が必要だということである。議会制民主主義のわが国では国会内「抵抗」勢力の問題は重要である。しかし、問題はそれだけでない。保守党政府の政策の内容は、国民の大多数の利益を反映していない。国民の利益とは何であるか。第一に平和。再びアジアの大陸に凍死し、南の海のもくずと消え、一瞬に核の熱に蒸発するのは、明らかに国民の利益に反するだろう。第二、この国の住みよさ。住むに家あり、仕事場からはリストラされる心配もなく、生活に応じた賃金をもらい、安全な食物を摂取し、子供は明るく学校に行き、医療は必要を受けることができ、暮らすに十分な年金は保証されており、地震水害で怯えることもない。第三に生きがい、働きがい、自分自身に対する誇り。これは社会への所属感だけでなく、社会の決定への積極的参加、またその社会の目的とするところに自己の価値の反映を見出すことのできる可能性の意識を、意味するだろう。……およそこのようなことが国民の利益とはいえないだろうか。もしそうであるならば、軍備拡張止むことなく、世界で一番危険な沖縄の基地を沖縄内でたらいまわしにするどころか、日米共同いよいよ増し、アジアの緊張を高めることは、おそらく平和を脅かし、国民の利益に反することだろう。また、グローバリゼーションの掛け声の下に進められてきた産業のあり方は、あきらかにこの国を住みにくくさせる。平均賃金は下がり、リストラの合法は野放し、住むに家なき人は若年層に広がり、TPPを待つまでもなくさらに食物の安全、医療保険、年金、自治財政の破壊は進んでいる。われわれはこれらの推進を巧妙な世論操作の元に注意をそらされてきた。他方、国の進路を定める政治上の決定は、いよいよ与党・大企業・官僚機構の上層部に集中する。一般大衆の「参加」の意識は、薄れざるをえない。しかも企業の中では、目的のわからぬ機械の、歯車のひとつとしてしか自分を感じることができない。人はパンのみにて生くるものに非ず。これでは自分自身に対して誇りを持つことはできないだろう。国民の利益は必ずしも国民がはっきり意識するものではない。多数の利益と多数の意見との間には、くいちがいがある。そのくいちがいを狭めることが、世論の操作に抵抗することだろう。その担い手は、大企業の内よりも、小企業の従業員や小売商、婦人層、あるいは派遣社員などの非正規労働者などから起こるとすれば起こるであろう。そのような抵抗の組織ほど、今日、日本の民主主義を救うために大切なものはない。一人ひとりの個人が、大衆の意見に従うばかりではなく、大衆の利益全体を見極めることが、急務の中の急務となる。それこそが福澤の言う「一身独立して一国独立する」ということの中味だろう。1877年に「丁丑公論」を作った福澤諭吉は、薩長土政府の専制に対する抵抗の精神を説いた。当時の日本は、議会もなく、強大な産業もなかった。140年後の今日、もし福澤をして世にあらしめたならば、何というであろうか。おそらく「官」に対する抵抗ばかりでなく、今や「官」と一体化した与党と大企業との専制に対する抵抗をといたことだろう。また抵抗の必要を、憲政の常道、武士の意地として強調するばかりだけでなく、内政外政両面にわたって今日の権力がゆるがせにしてきた日本国民の重大な利益の擁護を、当面の急務としたことであろう。「丁丑公論」の福澤は、西郷が権力を握っても、軍国主義の危険はなかったろう、と論じた。そのとき日本の武装は、到底「征韓」の用に堪えるものではなかった。しかし現在、もし福澤が「公論」を書けば、専制に対する充分な抵抗の組織されぬ限り、反対政府側からではなく、政府側から、軍国主義の復活の怖れも大きいと論じたかもしれない。‥‥‥以上の論文は、実は加藤周一氏の「丁丑公論私記」(1970)の剽窃である。しかし、そのままの書き写したのではなく、2011年現在の情勢にあわせて変えた部分がある。よって、文章の責任は、私にあるのである。なぜ、このようなことをしたのか。大きく変えたところは二点。「公明党の言論弾圧事件」を「小沢一郎の政治とカネの問題」に摩り替えた。また、「近来日本の景況を察するに、文明の虚説に欺かれて抵抗の精神は次第に衰頽するがごとし。」この一句、今もし「文明」の語に換えるに「グローバリゼーション」の一語を以ってすれば、そのまま140年後の今日にも通用するだろう、と私には思われる。と、書いたところ、じつは「グローバリゼーション」のところには「GNP 」の文字が入っていた。あとは、その変えた部分に従って現代状況の部分を変えただけで、文の構成そのものはほぼ加藤周一氏そのままである。ただし、そのまま写すにはブログとしてはあまりにも長い論文なので、三分の二ほど省略した。よって、公明党言論弾弾圧事件や現代情勢の部分は氏の論文のほうがはるかに詳しい。なぜこのようなことをしたのか。そのような大幅な変更があったにも拘らず、1970年当時の論文がそのまま現代にも通じるということを証明したかったからに他ならない。それが証明できたならば、当然、1970年におきたことは、1877年にも起き、2011年にもおきたことを証明するだろう。また、それぞれの年代での「抵抗の精神」のあり方が、まったく変化せずに、われわれに求められていることも、証明するだろうと思われたからである。そのことは、われわれに「時代の変化で変化しない一定の指針」を示すのではないか、と思ったからである。原文は加藤周一自選集4(1967-1971)より採った。
2011年02月26日
コメント(15)
-
丁丑公論私記 2011 (上)
加藤周一氏亡くなって二年、漸くいちファンに過ぎない私の許枕にも立ってくれた。彼は何故か漢文で「胸底有拙文」と謂う。謹んでこれを公表したい。「丁丑公論私記 2011」1877年(明治10年丁丑)、西郷隆盛が城山に討ち死にし、西南の役が終わって後、天下の世論は西郷を非難し、屍に鞭打ってやまなかった。そのとき福澤諭吉は「丁丑(ていちょう)公論」を書き、西郷を弁護した(しかし福澤はその稿を秘蔵し人に示さなかった。世間がその内容を知ったのは、1901年2月、福澤の死の前後、「時事新報」の連載による)。福澤は、なぜ西郷を弁護したのか。維新の功より「古今無類の忠臣」とされていた西郷は、維新後10年、西南の役が起こるや、たちまち「古今無類の賊臣」とされ、新聞紙上の論説は、ことごとく彼を罵詈誹謗して、その状あたかも「西郷に私怨あるものかと疑はるる程」であった。福澤は、これが事実の反するとし「後世子孫をして今日(明治10年)の実況を知らしめ」るために、「丁丑公論」を作ったのである。しかしそれだけではなかった。西郷に対する世論は、明治10年に豹変した。しかし世論が豹変したのは、それがはじめてではなかった。幕末において薩長は徳川への逆臣とされていたのである。それが維新で変わった。福澤はあらかじめ、そういうこともあったから、西郷のことにもこだわったのである。この「豹変」は時を隔てて、1945年を境にして「神聖にして侵すべからざる天皇」が「人間天皇」になり、「聖戦」が「侵略戦争」にもなった時にもおこっただろう。1877年の福沢の感懐の背景は、またおおいに2011年のわれわれをとりまく状況に似ている。去年から今年にかけて、天下の新聞テレビは小沢一郎のいわゆる「政治とカネ」問題をいっせいに攻撃するということがあった。日頃役者や人気歌手の私事の報道に専念してきた週刊雑誌さえも、決然起こって「政治腐敗」を糾弾するがごとく、その状あたかも、福澤流に言えば、小沢一郎にも「私怨あるか」のごとくであった。不幸にして「政治とカネ」問題は、わが国において新しいことではなく、また小沢一郎に限ったことでもない。たとえば、政権党や野党が企業献金を受け入れて、企業に有利な法律や政策を通したり、それを黙認するようなことがなかったか(それはおそらくあるだろう。もしなければ、財界の懇談会が政党の政策を自らの利益と比べて通信簿をつけるというようなことも起きないだろう)。マスコミの場合は、政府より金をもらい、それによって報道の偏向はなかったか(それもおそらくあるだろう。もしないというのならば、官房機密費が公になったときに、そのことに無視を決め込んだのが、ほとんどの報道機関であったということにはならないだろう)。政治家個人の法律に触れるような所得隠しもなかったろうか(これもあったことが指摘されている)。そういうことがあったときに、世の報道機関、世間の耳目挙げて、政府・与党・野党・報道機関・大企業の「政治とカネ」問題を糾弾してやまず、数ヶ月間、巷に批判の声が満ちたであろうか。決してそうではなかった。一方に、政権党、野党、政治家、大企業の制度カネにまつわる腐敗があり、他方に一政治家の政治とカネを巡る疑惑があるとしよう。今日のわが国の政治腐敗は、前者は後者の100倍にするに違いない。前者は政府・野党・大企業・の非、後者は一政治家の非。前者の100倍の非に沈黙して、後者の100分の一の非を弾劾してやまないのは、なぜであるか。「大勢に従」ったジャーナリズムにとって、政治腐敗はつまるところ、口実以上のものではなかったのだろう。福澤が1877年の西郷批判について見破っていたのは、そういうことだろう。それはその時代に限らず、その人に限らない。
2011年02月25日
コメント(2)
-

加藤周一の追記あるいは小さな希望
加藤周一自選集(4(1967ー1971))「日本の美学」(「世界」67年11月号)という小論の要点については、省略する。いつか詳論したいと思っている「日本その心とかたち」や「日本文化の時間と空間」でこの小論の「動機」はさまざまに形を変え壮大に演奏されるからである。ここでは、それから11年後に書かれてたこの小論の追記の文章(「著作集12」78年11月)について言及したい。このように加藤は書いている。水墨画と朱子学における「日本化」の方向のこのような一致は、美学的問題ではなく、世界観の問題である。そのいずれの場合にも、芸術家や思想家を動かしていたのは、世界への好奇心ではなく、当事者の内面の欲求であった。目標は、世界の構造理解ではなく、わが「心」の質の改善であった。外部から内部へ、社会から自己へ、客観から主観へ向かうこのような関心の集中は、おそらく二つの条件-社会の構造の長い安定と、歴史過程への参加の小さな可能性―に深く係わっていたはずである。そういう条件は、日本では、数世紀にわたる鎖国の平安時代後期と江戸時代に、備わっていた。社会的変化が急激で、その過程への参加の可能性が開かれていると知識人たちが感じた短い時期、たとえば明治維新の直前と直後、第二次世界大戦の直後には、知識人や芸術家の関心が、人生いかに生くべきかよりも、社会や歴史はいかにあるべきかへ向かった。しかしそれは例外的な時期の例外的な現象にすぎない。ここで加藤は珍しく日本変革の可能性について書いている。たとえそれか「例外的な時期の例外的な現象」といおうとも、である。加藤はかつて「雑種文化 その小さな希望」のなかで、純粋な国粋化も西欧化も失敗に終わった、希望は日本の雑種性そのものの中にある、と言う意味の「希望」を書いた。以降、加藤が明らかにしてきたのは、日本の「人生いかに生くべきか」に向かう日本人の特性ではあったが、最終的にはいつも「平和」な日本であり、「民主と平等」が同時に実現している社会であったと私は思っている。そうではない社会が現実に続いていて、その変化の可能性が大きく開かれたのが「68年」なのではなかったのだろうか。しかし、加藤が夢見たのはあくまでも「プラハの春」であり、「全共闘」の68年には限定的な評価しかしていなかったと私は認識している。そうだとすれば、「明治維新の直前と直後、第二次世界大戦の直後」の状況は、加藤が感じていた「雑種文化の小さな希望」が実現する限られた時期だったのではないか。私はとりあえず、そのように仮定を立ててみたい。だとすれば、現在2010年はどういう時代か。「社会的変化が急激で、その過程への参加の可能性が開かれていると知識人たちが感じ」る時代ではないだろうか。はっきりそうだとは言い切れないが、以前よりは随分とそういう状況になっていると私は感じている。社会的変化は急激である。それはリーマンショックがたった一日で日本に押し寄せてきたことからもわかるが、たとえば象徴的なのがアメリカのテレビドラマ「24トゥェンティフォー」である。アメリカ全土を揺るがすテロ事件が次々と起こるある意味荒唐無稽のドラマではあるが、90年代ならば何ヶ月もかかるような事件がたった24時間以内で完結するというのは、ひとえにアメリカ全土に張り巡らされた情報網があるからである。だからあのドラマの主人公は一応不死身の捜査官ジャック・バウワーではあるが、本当は前半はCTUの情報エキスパートのトニー・アルメイダ、後半は クロエ・オブライエンなのである。階級的な力の成熟は無いが、情報社会の成熟がともかくも「変化」のスピードだけは上げている。「社会変化の過程への参加の可能性が開かれている」と知識人(そもそも加藤亡き後知識人っているのか?)と市民は感じているかどうか。これは、確かに懐疑的である。しかし近年の政権交代、全住民規模の基地反対運動、九条の会の広がり、等々状況は変わってきている。たとえば、韓国の03年のインターネット大統領選みたいなことが日本で起きれば、それは決定的になるかもしれない。それは確かに「小さな希望」かもしれないが、とりあえず、インターネット選挙元年の今年、社会はいったいどこまで「開く」か。「参加」がひとつのキーワードかもしれない。
2010年05月12日
コメント(25)
-

「加藤周一自選集4」覚書
加藤周一自選集(4(1967ー1971))岩波書店やっと自選集4を紐解きだした。とても今年中に全巻(10巻)までたどり着きそうには無い。2-3年越しで加藤周一の再読を試みることになりそうだ。この巻は1967年(「朝日ジャーナル」に「続羊の歌」の連載を始めた年)から、1968年のプラハの春を挟み、1971年(初めての中国訪問)までの21編を収める。冒頭二編目の「日本の美学」はコロンビア大学の講義の成果であり、二年前の「源氏物語絵巻について」の全面的な展開である。すなわち「日本文化における時間と空間」ににたどり着く、基本概念がここで提示されている。解説の鷲津力氏は、「加藤の執筆展開法はヴァーグナーの楽劇作曲法を連想させる」と書いている。最初は小さく単純な曲想として示される。その後その動機は複雑に変奏され、他の動機と組み合わされる。やがて「指輪」の末尾を飾る「神々の黄昏」のさらに最後は「ヴァルハラの動機」「ジークフリートの動機」などなど多数の指導動機が組み合わされて壮大な響きで全曲を閉じる。すなわち、「源氏物語絵巻について」から「日本の美学」を経て、「日本における芸術思想の展開」「日本文学史序説」「日本その心とかたち」「日本文化における時間と空間」に活かされて行くのである。加藤が初めからそれを意図していたら、凄いだろうが、たぶん偶然そうなったのだろう。私に私だけの「単純な曲想」はあるのだろうか。この巻は同時に今までもっとも世界情勢について書かれた巻になった。後に加藤が何度も言及する「68年」が含まれているからである。やはり鷲津氏が加藤の問題意識にあわせて、68年の出来事を網羅してくれている。後にこれを使うと思うので、抜書きしたい。全体の動き1月 南ヴェトナム解放戦線と北ヴェトナムによる「テト攻勢」3月 米軍の「北緯20度以北の北爆停止」発表5月 パリで和平会談8月 ソ連は「プラハの春」を戦車で踏みにじる。10月 中国では文化大革命の嵐。劉小奇失脚。12月 毛沢東による近衛兵の農村下放始まる。学生、労働者の「世直し」の動きアメリカ4月 キング牧師暗殺。反対運動ますます激しく。6月 ヴェトナム即時撤退を主張したケネディの暗殺。 ヴェトナム反戦運動ひるまず。 ヒッピーズ、スチューデントパワー、ブラックパワーヨーロッパ3月 パリ大学ナンテール校の学制改革反対運動5月革命 学生と労働者によるゼネスト3月 ワルシャワ、検閲制度に対する学生運動5月 西ドイツ、67年からの非常事態法に反対する運動でゼネスト。日本でも学生運動はさまざま「世直し事はじめ」(68年「世界」8月号)の再読が必要であるとつくづく感じた。もちろんプラハの自由化とソ連の介入を詳論した「言葉と戦車」(「展望」11月号)も。鷲津氏は「プラハの春は加藤の見果てぬ夢だったのである」と言っている。その「夢」とはなんだったのか。民主と自由、言葉と戦車、世界と日本、若者と老人、最後の遺言のようなテレビ出演も含めて、加藤の「68年」の意味をもう一度捉えなおす必要はあるだろう。と、この本を読む意気込みを書いてみるが、なかなかまとめる時間を持てないで要る。
2010年05月11日
コメント(7)
-
97年加藤周一『夕陽妄語』より
モンテヤマサキさんがコメント欄で、13年前の加藤周一の「夕陽妄語」の文章「選挙の季節」を紹介してくれた。「全く驚くべき文章です」とモンテヤマサキさんは言う。同感である。けれども、今この時期にこの文章を拾ってきてくれたモンテヤマサキさんの慧眼にも驚く。今この時期とは、どんな時期か。ひとつは、文章冒頭に述べられている英国労働党による政権交代は、まさに今日、英国保守党に変わった。ひとつ時代が巡った、ということである。ひとつは、日本の政権交代について言及しているが、「政権交代」ということの意味を鮮やかに示し、普天間問題の観るべき座標をも示しているように思えること。ということで、その文章を紹介したい。「選挙の季節」(朝日新聞97年6月加藤周一『夕陽妄語』)今年1997年の5月から6月にかけては、英国の総選挙(5月1日)で労働党が圧勝し、フランスの国民議会選挙(5月25日・6月1日)では社会党が勝って、共産党や緑の党と併せて議席の過半数を獲得した。その結果英国ではトニー・ブレア首相の労働党内閣が保守政権に代わり、フランスでは保守党のシラク大統領の下でジョスパン首相の左翼連合政権が成立した。それより早くイタリアでは、すでに戦後長く続いたキリスト教民主党の時代が終わり、左翼民主党(元共産党)を中心とする中道左派政権が交代していた。来年のドイツの総選挙でも、社会党勝利の可能性があるだろう。ヨーロッパは保守党の時代から社会党の時代へ移りつつあるようにみえる。もちろん選挙の争点も、勝敗の理由も、国によってちがう。しかし各国に共通の条件もある。第一に1990年代の初めソ連の崩壊と共にまき起こった「自由市場万歳」の大合唱が終わった。その頃気の早い男は『歴史の終わり』という本さえも書いたが、終わったのは歴史ではなく、自由市場・規制緩和・福祉切り捨てで万事めでたいという楽観主義であった。保守党の採った政策は、ある時には景気を刺激し、ある時には不景気を克服しなかった。しかしどこでも常に、失業問題を解決せず、福祉を後退させ、貧富の差を拡大した。行く先に光がみえなかったから、人心は保守政権を離れたのである。第二に、ヨーロッパの議会民主主義の国には、有力な反対党があった。したがって選挙を通しての政権交代が可能であった。社会党政権が今後どの様に、どの程度まで、困難な問題の解決に成功するかはわからない。独仏を中心にしていえば、失業問題の解決と国際競争力の維持と、財政赤字の削減を、同時に実現することは、容易でないだろう。しかし国民は選挙によってその意志をあきらかにし、――その意志が常に合理的であるとはかぎらないが――、政治に圧力をかけることができる。この第二の条件は今の日本にはない。各種保守党の間に離合集散はあるが、保守政権に対してのあきらかな反対党は、共産党以外にない。しかし共産党の議席は少なく、孤立しているので、さしあたりの役割は批判政党のそれに止まる。この国の有権者が「保守政治不信」といわず、「政治不信」というのも、そのことのあらわれであろう。そこには深い諦念がある。第一の条件についていえば、日本の政治的状況は、ヨーロッパの現状に一周り後れているように思われる。日本では1990年代の後半に、相変わらず、市場開放や規制緩和や自由化を目標として「改革」を唱えている。その「改革」が実現する頃には、世の中が変わって、自由市場は弱肉強食の修羅場であり、そこから人間を救いだすためには政府の介入が不可欠だということになっているかもしれない。しかし世の中はヨーロッパだけではないし、選挙が行われているのもヨーロッパ諸国だけではない。最近イランの大統領選挙(5月23日)では、宗教上の権威者(アヤトラ)が推した候補者に大衆的人気のあるモハメッド・ハタミ氏が圧勝し、インドネシアの総選挙(5月29日)では逆に与党が大勝した。カナダの総選挙(6月2日)の結果は、与党自由党が後退しながらオンタリオで勝って過半数を維持し、改革党が西部で、新民主党が「プレーリー」で進出した。メキシコの総選挙もこれに続き(7月6日)、制度的革命党が68年間独占してきた政権の交代がおこるかもしれない、といわれている。これらの選挙では、ヨーロッパ諸国の選挙でよりも、争点のちがいが大きい。たとえば『朝日新聞』(1997年6月4日)のオタワ特派員(上治信悟氏)も指摘したように、カナダの総選挙は地域対立を直接に反映した。殊に西部を背景とする改革党の進出は、おそらく強硬な対ケベック政策を意味し、したがって他日ケベック側の独立運動の人気を増大させるだろう。そういう分裂傾向はイランやメキシコでは目立たない。しかし争点のちがいよりも、制度のちがい、あるいは議会と議会外の勢力との力関係のちがいが、選挙結果の政治的意味づけに大きな意味をもつだろう。たとえばインドネシアの国会議員は千人。その半数は政府が選び、残り半数のなかでも75人は軍隊が選ぶ。選挙されるのは425人である。選挙の意味は、すべての国会議員が選挙される国の場合とちがう。たとえ反対党の「デモ」に対して軍隊と警察が催涙弾やゴム弾を使わないとしても。イランでは誰が大統領になっても政策に大きな変化はなかろう、という説がある。大統領の権限は、宗教的指導者たちによって、著しく制限されているからだ、という。私はその説の当否を知らない。しかし一般に、選挙された議会(または大統領)と議会外の政治勢力との関係には、さまざまの場合があり得ることを知っている。たとえば昔軍国日本では(殊に1936年以後)、選挙によって成立した衆議院が、国家の意志決定に演じる役割は、きわめて限られていた。やがて政党は解散し、議会は軍部を中心とする政府の政策を「翼賛」する機関にすぎなくなる。今日の日本では、議会内に強力な反対政党がないので、政権交代を通じ、政策の根本的な転換を実現することができない。しかし少なくとも制度上は、軍国日本の場合とはちがって、選挙を通して国民が反対政党を活性化する可能性が残されている。イタリア国民はすでにそうした。メキシコ国民もそうするかもしれない。長く続いた一党支配は、ロシアで崩壊しただけではなく、議会民主主義的な資本主義国でも崩壊したし、崩壊しつづけるであろう。日本国民はいつそうするのだろうか。つまるところ、それは国民の意志の問題である。私は遠い外国の、――東京からみればすべての外国は遠い――相次ぐ選挙の報道を読みながら、私自身が生まれて育った国の現状を顧み、とりとめもない思いに耽る。欧米の流行に敏感なこの国は、いつ社会民主主義の活性化に眼を向けるだろうか。沖縄にはいつ独立運動がおこって、ケベックのそれに呼応するだろうか。冷戦の枠組みのなかで半世紀以上も維持されてきた外国の軍事基地は、いつ「たらい廻し」から縮小へ向かうだろうか。独仏関係に似た日中間の信頼関係は、いつほんとうに築かれるだろうか。そしていつ震災の町では大企業の再建よりも、被災した住民の、殊に貧しい市民の、生活と福祉の保証が優先されるようになるだろうか。昔の歌の文句にもいう、「答は空吹く風の中にある・・・」(以上引用終わり)世界を見る、ということはどういうことなのか。ひとつのお手本を示していると思う。日本の「政局」がどうなろうと関係ない、少なくともヨーロッパで、北アメリカで、南アメリカで、何が起きているのかそれを見据えた上で日本の問題を見ることが必要なのだ。そうえすれば、この文章のように1997年の時点で、2010年どころか、2020年の日本の課題も語ることが出来るのだろう。私見ではあるが、英国は「労働党不信」で政権交代をするのではないだろう。「政治不信」でするのだ。だから本来単純小選挙区制度を早々に取り入れた英国で第三党が伸びるという現象が起きているのである。>日本の政治的状況はヨーロッパの現状にひとまわり遅れている。まさにそのとおりであって、「ひとまわり」というスパンは13年であったのか、と今思っているところである。しかし、このままでいくと、「ひとまわり」のスパンは20年ぐらいに延長されるかもしれない。日本における「政権交代」はべつに社会民主主義政党でなくてもいいと思う。しかし、リーマンショックでも失業者がすぐにホームレスに直結するような日本でなくなること、その程度のヨーロッパ水準は日本ではまだ実現していない。>冷戦の枠組みのなかで半世紀以上も維持されてきた外国の軍事基地は、いつ「たらい廻し」から縮小へ向かうだろうか。この水準に至るにはまだまだかかりそうだ。ギリシャの政党は日本の保守党と同じように最低である。けれども、ギリシャ国民は「怒る」ことを知っている。ギリシャの暴動は株価の下落だけが問題なのではない。公務員の削減や昇給凍結、年金の削減や受給年齢の引き上げ、付加価値税の引き上げ等々。まさにあの保守政権が提案することは日本の未来の姿だ。日本国民は「怒る」ことが出来るのだろうか。
2010年05月07日
コメント(7)
-

「九条の会」と加藤周一
冥誕小森陽一は「九条の会を発案されたのは、加藤周一さんであった」とはっきり書いている。(「冥誕」のなかの「加藤周一さんと九条の会」)。加藤周一が小森陽一を説得して事務局長に担ぎ上げたのは、慧眼であったが、まだなぜ小森が選ばれたのか、詳しい経緯はわからない。おそらく2001年秋から発足していた「憲法再生フォーラム」という勉強会で若くて行動力のある小森を知ったのだろう。2003年秋、加藤は自宅近くの喫茶店の二階で小森と九条の会の構想を語る。(朝日新聞09年9月)その喫茶店はほぼ間違いなく、上野毛の「ル・サフラン」である。だとすれば、後世日本の平和に決定的な影響を及ぼした「九条の会」の誕生を演出した喫茶店としてここは歴史的名所となるかもしれない(笑)2001 9.11事件起きる。 秋アメリカのアフガン侵攻 小泉「テロ対策特措法」 11.20「憲法再生フォーラム」共同代表 加藤周一、杉浦泰雄、高橋哲哉2002 ブッシュ一般教書演説「テロとの戦争」イラク戦争を準備2003 3.20 イラク戦争始まる 小泉「武力攻撃事態対処法」 イラク特措法による自衛隊の戦場への派遣 「集団的自衛権の行使」「明文改憲」へ着々と地ならし2004 4月第一週「読売新聞」世論調査65%が「憲法を変えたほうがいい」そういう流れの中で、加藤さんは研究者の集まりを持つだけでいいのか、このままの形態でいいのか、模索していたらしい。小森は述べる。 今誰かが明文改憲に反対する運動を、広範な市民に呼びかけなければ手遅れになる。しかし、現状において政党や労働組合のどこかが呼びかけても本当の意味で広がりのある運動をつくることはできない。そうであるならば、知識人が知識人として、個人の立場から、憲法を守り、生かす運動を呼びかけるべきだと判断されたのである。その加藤周一さんの決断を、私は大江健三郎さんへお伝えし、そこからあの九人の「九条の会」の呼びかけ人のつながりが始まったのであった。 加藤さんは「九条の会」の運動を次のように位置づけた。既に多様な形で存在する「九条を護ろうとする人たちの運動」をお互いに「横の連絡」を取り合い、「ネットワークを創りたい」。その「相互連絡の手伝い」、「有効な連絡が出来るようにする」(2004年6月10日の「記者会見」での発言)のが、「九条の会」の運動であると。最初から、加藤周一は明確な「戦略」を持っていたということがわかる。日本はたしかに外国のように何百万人ものデモ行進を行うような横断的な横の連絡組織はない。しかしながら、市民の一人ひとりの政治的な学習能力は大きいし、小さな集団の中での結束力は非常に高い。小さなコミュニティは無数にあるのが日本の市民運動の特徴である。もしそれらの無数のコミュニティを横につなげることが出来たならばどうだろう。小泉によって水をあけられていた運動を、もしかしたら戦後で唯一「戦略的に市民運動が政府の戦略に勝った瞬間」になるかもしれない。 加藤がだいぶ以前からその構想を持っていた証拠に青年との学習会の記録「テロリズムと日常性―「9・11」と「世なおし」68年」(2002)ですでに加藤周一は質問に答えてこのように言っているのである。『小さなグループがいくつか連携して、具体的な問題をひとつ解決する。そういう流れをだんだん広めていって、地方行政を動かすような規模になって、ある程度社会的な力を持つ…ということがあり得るんじゃないか。』「改憲」派が多数であるかのように報道する、マス・メディアのキャンペーンの中で、心の中で思っていても、それを他者に向かって自らの意見として「明示する機会」を持たなかった多くの人々が、講演会に足を運ぶことでまず沈黙の意思表示をし、呼びかけ人の講演の言葉に励まされ、それに応答するように「アピール」への賛同を口にし始め、その「意見」を自分の生活圏の中で「明示」することで、草の根の「九条の会」が結成されていく。と、小森は「九条の会」の大きくなった経緯を説明する。06年6月10日の「九条の会全国交流集会」で加藤さんは「九条の会は、日本で唯一の、そして、世界でも珍しい、ことに平和運動に関しては、明らかに例外的に珍しい組織です」と語った。そして「勢いに乗ってください」と呼びかけた。らしい。どのように珍しいのか、もう少し詳しい分析はほしいところであるが、かつて「言葉と戦車」(1968)で加藤がプラハの春がソ連の戦車で潰されていくのを見たときにそれでも「小雨に濡れたプラハの街頭に相対していたのは、圧倒的で無力な戦車と、無力で圧倒的な言葉であった」といったように、知識人として言葉の持つ力を21世紀の初めに証明したひとつの試みであったことは確かだと思う。
2010年04月04日
コメント(28)
-

加藤周一の人柄あるいは「冥誕」
冥誕かもがわ出版加藤周一の追悼集である。先に市民の追悼集を読んだばかりで、確かそのとき私は「今はあまり読む気がしない(その多くはすでに読んでいるから)」と書いた。こういう知ったかぶりが私の悪い癖で、私の知らない追悼文がここにはたくさん載っていて、いろいろと学ばされた。反省したい。たとえば水村美苗さんは「加藤さんは単に与え続けただけではない。ご自分から何一つ相手に求めないという決意が、その人格の芯にあり、その上で与え続けたのです」という。加藤が死んで聞こえてくるのは、思った以上の人格者だったということ。それは最晩年に協会で洗礼を受けたということに関係しているのだろうか。それとも、この場合は加藤のフェミニストたるところが発揮されたのであろうか。水村さんは「ご老齢になっても、手荷物ひとつ私に預けようとなさらなかった」と書いている。あの老男女が二人で歩いているとき、手荷物を巡っての会話のやり取りが目に浮かぶようである。確かにジェントルマンたるもの、ご婦人に手荷物を持たせるなどとは言語道断とはいえ、80歳を過ぎた高名な作家がなかなか出来ることではない。前進座の演出家香川良成さんが言うには、戯曲の第二作を要望したところ、「明朗敢闘大和魂」(仮題)を提案したと言う。渡辺一夫の「敗戦日記」にも書いている、彼が「明朗敢闘大和魂」と渾名した隣家の主人を中心にした一家の話らしい。川口の町工場の一家の、戦中・戦後の日本、大陸ごろ、学者、市町村長、特高、陸軍将校、闇屋、不動産屋、米軍、慰安婦、近所の女たちが絡み、現実と夢が交差し、ファンタスティックな文明批評的作品=無責任の体系批判的作品になるとのことだったそうだ。これはもし実現していたら、加藤周一の総括的作品になったかも知れず、つくづく実現できていない前進座のプロデューサーとしての責任が問われる?出来事であった。普段着の加藤周一について、鷲津力さんはこのようなことを書いている。「88歳になっても加藤さんと会えば、おしゃべりはいつも三時間から四時間に及んだ。その間はほとんど加藤さんがしゃべっていた。」「だが、いわゆるグルメ指向ではない。高級レストランに入ることを拒みはしなかったが、街中のファミリーレストランに入る事も嫌がらなかった。どんなレストランに入っても、気さくにあるいは貪欲に、たとえ短くても店員と言葉を交わすことを常としていた。」けだし、誰にでも出来ることではない。小森陽一の九条の会に関する文章は重要である。そのことは項を改めて書く。
2010年04月01日
コメント(0)
-
萬斎の決意あるいは「野村万蔵の芸」
『加藤周一自選集3』より「野村万蔵の芸」(1965「図書」2月号)野村万作が「私の長男の萬斎が(この文章を)読みまして、自分は加藤先生の本を読んで刺激を受けて、狂言の道に進む気になった、と狂言師になった動機を聞かれるとよくそう答えていました」と書いていて、(「現代思想 総特集加藤周一」のなかの「加藤周一先生と親子三代」)どんな文章だったのかを今回確認させてもらった。野村萬斎(1966-)は確かにまだ若手の狂言師に過ぎない。しかしながら、その才能は本物だ。映画「陰陽師」において、彼がスクリーンの中に出てくるだけで画面が妖しくなったので、びっくりしたという経験がある。安倍晴明は狐の妖怪の落とし子であるという伝説があり、萬斎のふと見せるしぐさがなんと狐に見えるのである。将来恐るべし、率直にそう思った。そしてこの文章を読んでみて、なるほど、と思った。思いっきり挑発的な文章である。狂言とは何か、という分析的な言葉はほとんど無い。わずかに加藤がドイツの演劇人のために野村万蔵に頼んで衣装もつけずに一曲踊らせたときのドイツ人の評「言葉はわからぬが、いずれ動きと同じように、よほど様式化された言葉に違いない。これほど型の定まった様式化された芝居を演じて、あれだけ写実の妙を見せるのは、実に偉大な芸である」だけである。ほかのところでは、加藤が言っているのはただ一点だ。狂言が芸術だから、万蔵の芸がすばらしいのではなく、万蔵が現代の「名人」だから、狂言が芸術になっているに過ぎない。加藤は戦前は歌舞伎、戦争中は能楽、戦後は狂言を「発見」したという。名人の時代は過ぎ去るものである。六世万蔵(1898-1978)の時代が過ぎ去れば、加藤は狂言を見なくなるのだろうか。野村万蔵が名人だから、芝居とは何かという当方の考えも定まってくるのだ。その芝居が新しいか、古いかというようなことは、芝居を芝居にする決め手では決してない。芝居を芝居にするものは、新しさとか古さとかを忘れさせてくれるもの、すなわち人間精神の遂に時代を超えようとするものである。そしておそらく、これは芝居にかぎったことではない。私は芸術については確かなところから出発したいと考えるのである。加藤は生涯、自分の目で見て、耳で聞いたものしか論評はしなかった。
2010年03月27日
コメント(2)
-
幽霊と語る、あるいは「三題噺」
加藤周一の『三題噺』(ちくま文庫)を買った。加藤周一自選集3にすでに三つの噺のうち二つは載っているし、「加藤周一の書いた加藤周一」に一つの作品だともいえる「あとがき」の収録されているので、いまさらという感も無きにあらずだったが、ひとつの単行本として読むことで「映画館で映画を見るような」ライブ感を味わえた。まあ、趣味の世界ですね。この本は、石川丈山、一休、富永仲基という三つの人生を「小説」として描くことで「日常的」「官能的」「知的」の徹底した三つの人生を描こうという試みである。加藤周一自ら言うように3人を「ありえたかもしれない三つの可能性」として描いたものである。「逃げ得なかった私の望みは三つあり、三つしかなかった。そして私は旅の空の下でたまたまその望みを託して語るに足る三人の事物に出会った。」(「あとがき」)私は三つしかなかった、とは思えない。しかしそれはまた別のところで。発見はいくつか。「解説」で鷲津さんは石川丈山を描いた「詩仙堂詩」の文体について、加藤が詩仙堂でたまたま出会った老人と「対話」するという形式で進むことに注目してこう言う。「亡霊が老人として登場し、対話を交わすという趣向は一体どこからヒントを得たものだろうか。一つの可能性は能楽だろう。能楽には亡霊が登場する作品が数多くあるが、加藤は能楽に学生時代から親しんでいた。」もう一つは芥川の影響か、と書いているが、私は1番目のほうだと思う。能楽はたしかにそのような構成で話が進むことがおおい。つまり「夢幻能」。亡霊や神仙、鬼といった超自然的な存在が主役(シテ)であり、常に生身の人間である脇役(ワキ)が彼らの話を聞き出すという構造。そこから豊かな世界が広がるのである。そして今回加藤の遺言ともいえる映画の題名は「しかしそれだけではない。加藤周一幽霊と語る」であった。私はまだこのドキュメントを見ていないが、幽霊とは、ひとつは加藤の友人で戦火に消えた中西であることは間違いないだろう。加藤は常々、友人が果たせなかったこと、友人が許さなかったであろうことを自分はしたくない、と語っていた。加藤が一貫して戦争反対を「アプリオリ」に貫いてきたのは、この経験からであった。加藤の長期エッセイ「夕陽妄語」にも、老人や高校生がよく出て来る。もしかしたらあの高校生は前私が言っていた加藤の息子ではなくて、中西だったのかもしれない。そんなことも思ったのでした。幽霊と語っていた加藤周一が、今現在では幽霊の位置にある、それだけでも非常に魅力的な映画ではある。岡山で上映してくれないのだろうか。自選集3に載っていない「仲基後語」に丈山、一休、仲基の三人のまとめみたいなものが書かれている。加藤の分身ともいえる記者は「繰り返すことの出来るのは言葉だけだ」という仲基の言葉を受けて「言葉だけが偶然に抵抗することが出来るということでしょう。一回限りの経験のなかにもし永遠を見ることが出来なければ、永遠というものは無いでしょうね。一休宗純はそれを感覚的な情愛の世界に見たのでしょう。石川丈山はそれを日常生活の末端に見たのでしょう。」という。それに対し、仲基に「しかし反応は次第に鈍くなる」ので感覚的なものが永遠の意味を持つのだろうか、と反論させている。加藤は言う。「感覚的な反応が次第に弱くなっても、その反応が人生に持つ意味は変わらない」。すると仲基は「(私に)もし倦きない生活がありうるとすれば、それは考える生活だけだ」と言わせている。加藤にとっての「一回限りの経験」はもちろんひとつには「戦争」であったろう。しかし、65年に書かれたこのとき、二度目の離婚と、矢島との新しい恋が影響しているのではないかという気がしてならない。別のところで、加藤は文学と科学の違いを「反復できるもの」と「一回限りの経験」だと書いている。(「文学の擁護」)加藤が文学を擁護するのは、知的な加藤が一回限りの経験である「情愛」「日常」「思考」を大切に思っているからに他ならない。それは私たちにとってもやはり同じなのだろうと思う。―いや、まったく怪物ですよ。―何が?―あなたがですよ、すべて純粋なるものは怪物です。加藤は仲基に対して言う。私たちは加藤に対して言うだろう。
2010年03月26日
コメント(10)
-

ある日本文化についての発見あるいは『「源氏物語絵巻」について』
「加藤周一自選集3」より「源氏物語絵巻」についておそらく1964年末、加藤周一は上野毛の五島美術館において「源氏物語絵巻展」に出会い、大いに興奮し、彼はその直後、重大な日本文化に対する「型」の仮説を立てるに至った。結論から言えば、それはやがて「日本文化における時間と空間」に結実する。加藤周一は源氏物語絵巻に何を見たか。一言で言えば、「多くの直線による画面の分割法の繊細微妙極まるところの無い洗練」を見たのである。建物の部分の直線によって画面をいくつかの空間に分割し、その空間に人物の色を配する工夫は、「源氏物語絵巻」だけのものではない。しかしここには、たとえ一本の短い垂直線でさえ、微塵も左右に動かすことの出来ない厳しさがある。(略)おそらく物語と質と造形的な絵画の質とを結び付けて考えることは出来ないだろうが、文化の構造の中で関連はあるだろう。(略)私見によれば、「源氏物語」の眼目は「時間」である。(略)そのなかで季節が変わり、治世が変わり、世代が交代し、人が生まれ、育ち、恋し、苦しみ、老いて、死んでゆき、過去が現在になり、現在が未来を含む「時間」の流れそのものに他ならなかった。(略)されば一方には「源氏物語」の「時間」があり、他方には「源氏物語絵巻」の「空間」があった、ということができる。(略)その一方の時間は、終末論を含まない具体的で現実的なこの世の時間である。物語は永遠を考えなかったから、時の流れに敏感であることが出来た。(略)他方の空間は、合理主義的な均斉を含まない感覚的で微妙な日常世界の空間である。「絵巻」は、左右相称や黄金分割を無視したから、空間の構造に無限に敏感になることが出来た。私は源氏物語絵巻を直接見たことが無い。よって、加藤のこの判断をなんとも言うことはできない。ここには、加藤の「発見」に対する率直な喜びの言葉が入っている。そしてその「発見」は日本文化、ひいては「我々とはなにものか」ということを考えるに置いて非常に重要なことを示唆していると私は思う。
2010年03月19日
コメント(0)
-
加藤周一の信仰あるいは「親鸞」
「加藤周一自選集3」より「親鸞」ずっと前にこの文章を読んだときには、ただただ感心した。日本において初めて「神がいる」つまり彼岸思想を打ち立てたという意味で、法然、親鸞は決定的だったということを述べた。文章なのである。(法然と親鸞において)日本の精神は、はじめて、決定的に、超越的な彼岸思想に徹底した。思想的にその道を開いたのは、法然である。その意味で、1500年以上の日本仏教思想史の中から、もしただ一人を挙げろとすれば、まず法然を挙げる必要があろう。しかしその思想的革命から引き出すことの出来るすべての人間的結論を引き出したのは、主として13世紀前半に活動した親鸞であった。ともすれば、彼岸ではなく、「此岸」に陥る日本人の思想において、この思想家は特別であり、またその限界を知ることで、日本の思想の限界も知ることになるのである。ということを私に教えてくれた非常に刺激的な文章だった。そこまでは今までの理解だった。今回は、まったく違う見方でこの文章を読むことになってしまった。加藤周一がなくなってしばらくたったころ、私はMLで加藤周一が亡くなる直前(08年7月ごろ)上野毛のカソリック協会で洗礼を受けたのだということを聞いた。(洗礼名はルカ)びっくりした。加藤さんはずっと無神論者なのだとばかり思っていた。この論文の直前に加藤さんは「余は如何にして基督信者とならざりしか」という短文を書いているが、これは加藤さんの心情吐露というよりか、日本人一般論を書いたものだから、後で考えれば、加藤さんの真情はついに分かってなかったのではあるが、なんとなく「理性の人」加藤さんは「宗教には走らない」と思っていたのである。そういう考え方は「理性ある人は宗教に走らない」と考えることと同じことで、もちろん間違った考え方であると「理性」では知っていてもである。ところが今回、この論文でこのような文章を見つけた別の言葉で言えば、それでも人を信じるのは、だまされる覚悟をするのと同じである。だまされぬためには、信じないほかは無い。信じなければ、人格と人格の接触はおこらないだろう。つまるところ人間関係も二者撰一の形で現れる。二者撰一の根拠は、理性的にはありえないから(理性的にありえるのは確率の計算だけだ)、一種の賭けである。(略)念仏して、浄土に行くか、地獄に行くか、知れたものではない、といった後で、たとえ地獄に行くとしても、「いずれの行もおよびがたき身なれば」、後悔することはないという。これはもちろん親鸞の「歎異抄」の「たとひ法然聖人にすかされまひらせて、念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからずさふらふ。」ということの解説ではある。ここで「賭け」という言葉を使っているのに注目したい。この項の注で、加藤周一はこうも書いている。パスカルは言う。神があるのか、ないのか。どちらが本当らしいか。「理性はこれを決定することが出来ない」。神とわれわれを隔てる無限のかなたで、「賭けが行われる」。表が出るか、裏が出るか。「神がいるという表を取って損得を考えよう。二つの場合がある、もし勝てばすべてを得、負けても失うものは無い。それならば躊躇わずに、神がいるという方へ賭けるのがよいだろう」たとえばこの論法のおおいに親鸞に似ているのを見るべきである。(略)宗教の宗教性は超越者に集中する。超越者と人間の関係は、信仰という行為に集約される。その信仰という行為の根拠は、一種の「賭け」である。たとえ法然上人が間違っていて地獄に落ちても後悔することはないと親鸞は言い、たとえ神がいると賭けて間違っていたとしても失うところは何も無いはずであるとパスカルは言う。信仰の本質を突き詰めると、親鸞たらずとも、また仏教徒たらずとも、Gredo quia absurdumへいくようである。Gredo quia absurdumてなんだろう。(たぶんフランス語だと思う)誰か教えてくれませんか。要は、加藤周一の理性は、パスカルに同調しているとも読める。あるいは、まだ迷っているようにも見える。加藤さんが死んだとき、棺には「論語」とカントの「実践理性批判」そして「聖書」が入れられたという。結局私はまだ加藤の振興の意味に付いてまだ語るべきものを持ち合わせていない。これからも、加藤さんの最後の選択である、「洗礼」の意味について考えていかなければならないのははっきりしている。
2010年03月17日
コメント(2)
-
加藤周一自選集3
自選集第三巻は1960年カナダのヴァンクーヴァーのブリティッシュ・コロンビア大学に赴任した年から1966年「羊の歌」の連載を「朝日ジャーナル」で始める年までの著作21編を収めている。編者の鷲巣力氏はこの中の特に「三題噺」が加藤周一の大きな転換点だったと述べる。「研究者や文学者・思想家が自らの「核」をつくりあげるとき、研究対象に向かって没頭できる時間と空間が必要である」それが加藤にとってコロンビア大学だったらしい。「三題噺」にはひとつには、加藤のありえたかもしれない自分の三つの側面が書かれている。それは「羊の歌」を準備しただろう。ひとつは、文学史研究の「定点」を築き上げる上で「橋頭堡」になったことで、それは「日本文学史序説」を準備した。ひとつは、ここにいたって、加藤の文体が完成する。「要するにヴァンクーヴァーで「加藤周一は加藤周一になった」のである」今回特に注目したのは、「三題噺」の各編以外には、「親鸞」(1960)、「源氏物語絵巻」について(1965)、「野村万蔵の芸」(1965)、「サルトルの知識人論」(1966)である。余裕があれば詳論したい。
2010年03月14日
コメント(0)
-

東京彷徨3 加藤周一邸
小さな旅だけど、旅は気づきの連続である。ちょっとした親切がうれしいo(^-^)oホテル三番館では、出るとき思いがけない雪の天気に(おそらく客が忘れていった)ビニール傘を持たせてくれた。大泉学園駅前のカフェNOVELでは、一人用の机に着いたら「広いほうが落ち着くでしょう」ともう一つくっつけてくれた。「気遣い」が日本のサービスなのだとつくづく感じた。一方、韓国の場合はそういう親切は無いけれども、ヘルプを出すと徹底的に助けてくれる。旅人にとっては、どちらも嬉しいが、どちらかという韓国の方がいいかな。上野毛駅で降りて加藤周一旧宅まで歩いていく。歩いて10分もないところにそれはあった。予想に反して木造家屋ではなく、コンクリート制の2階建て。表札には「加藤・矢島」とある。これはイメージ通り。わりと大きな家であるが、驚いたことに二世帯住宅になっていた。2階に住んでいる人の名前は全く見当が付かない名前であった。でもよかった。矢島翠さんは一人暮らしになっていないことだけは確かだからである。庭はよく見えなかったけど、欅みたいな木が見えた。イギリスのガーデンのようではなかったが、緑があってほぼイメージ通り。これ以上うろうろしていると「不審者」になってしまうので退散した。幹線道路から約50メートルほど。閑静とは言えないかもしれないが、この落ち着いた住宅地であの膨大な評論の多くを書いたのだと思うと感慨深い。前にも寄った喫茶店「ル・サフラン」でケーキセットを頼む。今月のケーキはキャラメルサレです。おかみさんに聞いた。「加藤周一さんをご存知ですか」「ええ!いつもここを利用してくださっていました。いつもミルフィーユを頼まれていたんですよ。寂しくなりました」今日はミルフィーユは品切れだったらしいので食べることは出来なかったが、やっぱりここが行きつけの喫茶店だった。ウィキよりミルフィーユの写真を拝借。やはりなんと言っても加藤周一の好みの菓子はその名を「ナポレオン・パイ」との愛称でも親しまれたフランスを代表するケーキだったのである。その後駅前のワイン酒屋「ビンテージ」で若い御主人に同じ質問をしたらさすがに名前さえ知らなかった。「30年前の著作にワインの話をしていたというがあったんです。ワインを置いてあるのはここしかないので」私は聞いた。「うちは一年半くらい前に開店したんです。もう閉めたけどそれまでに酒屋はひかり屋というのがったみたいです」(モンテヤマサキさんの情報によると、酒屋はスリーエフに店替え、パン屋は駅前のローソンに変わったらしい)そうか!あのパン屋も酒屋も、もうないのか。でもわかってよかった。本当はこのあと国立博物館に寄って国宝土偶展に行こうと思っていたがタイムアウト、帰路についた。満足のいく旅でした。加藤周一さんは、2008年夏、「どうしても語り伝えたいことがある」と体調不良を圧して話をされた。それはその年の死後ETV特集で放映され、文庫「私にとっての20世紀」に付記された。私にとっての20世紀最後の収録は上野毛のこの自宅でなされた。加藤さんの話は、新自由主義経済の破綻の先に、不安定な「生」を強いられている今日の若者たちが「異議申し立て」する可能性まで及んだ。最後の最後に、このように言っている。この社会というのは変わらなきゃいけない。どう変わるのかは、誰にもわからないんだろうけど、しかし、ともかく変わる必要があるんですね。(略)ただChangeと言って、それが一種のラウンドスラングみたいな効果を持ったのはどうしてなんだろうと考えないとね。ただ、言葉だけの問題じゃなくて、あれだけの反応を引き起こすことが出来るのは、それはやッぱりどこかで深い現実に触れているからですよね。それはただ口先だけの宣伝、単なる宣伝技術の問題だっていうんじゃないと思うな。やはりどこかでアメリカ人の感情の深いところに触ったんですよ。だから、なんだかわかんない。たぶんオバマも知らないだろうと思うけど‥‥‥。最後の最後は繰り返しの言葉も多く、加藤さんらしい「切れ」はなかった。しかし「オバマも知らない」ところで「深い現実に触れている」というのは、その後の一年と少しのオバマの政治が(悪い意味で)証明した。加藤さんは最後の最後まで「鋭い」人であった。上野毛の加藤邸に続く道、霙に変わった小雪は生垣に静かな呟きを落としていた。
2010年02月17日
コメント(11)
-
「加藤周一自選集2」
「加藤周一自選集2」岩波書店自選集の二巻目である。加藤がフランス留学から帰ってきて「日本文化の雑種性」を書いた直後から「戦争と知識人」を書き、やがて二回目の外国移住を始める直前までの四年間の著作を集めている。(1955-1959)編集者の鷲巣力氏は加藤のフランスの留学は「ヨーロッパを発見し」「日本文化と比較する視点を持った」ことで画期だったと述べる。この本に載せている単行本初出は、英語義務教育の無駄を説いた「信州旅日記」のみ。しかし、加藤読みの新しい視点をもらうという意味では色々な発見がある本ではあった。もう仕方が無い。自選集10巻をそろえざるを得ないだろう。
2010年02月03日
コメント(4)
-

『漢字・漢語・漢詩―雑談・対談・歓談―』
漢字・漢語・漢詩一海知義 加藤周一 かもがわ出版表題から分かるように、漢語に対する造詣が深い二人の談論風発、侃侃諤諤(けんけんがくがく)の『漢字の将来性、日中の漢字文化の違い、論語の意義』などを語った対談である。肩のこらない対談である。しかし1500円はさすがに高い。注目すべきは、中国語訳と韓国語訳の載っている『漢字文化圏の未来』という対談。同じ漢字文化圏として、もっと戦略的に教育を整えたらどうかという、拝聴に値する議論である。お互い筆談出来るぐらいの教育をしたらどうかという提案である。一海先生曰く「中国古典を読めるような力を持つ必要は無いのであって、筆談が出来るような日常会話を漢文にして、意見の交換が出来るぐらいの漢文力でいいのです。日本人がいう『おはよう』(好天)、漢文では何というか。そんな簡単なしかし、必要な日常的な語彙を含んでいる『日漢辞典』が必要ではないでしょうか。」皆思如何?
2010年01月28日
コメント(4)
-

「私にとっての加藤周一」その二
私にとっての加藤周一昨日の続きです。市民の加藤周一をはじめて見たときの第一印象は割と共通している。まきひろみさんはこう言う。「壇上に現れた氏は、足元危なげな老人に見えた。しかし語りだすと、しだいに聴衆を圧倒していった。「このお歳だし、無理もないか」とタカを括っていたら、とんでもない老人だった。鋭い眼と的確な言葉、百科全書的世界を融通無碍に飛ぶ頭脳に呪縛された。」 しかし、中国新聞記者で学生の時に加藤周一の講義に出ていたという道面雅量さんの文章に私は思わず涙する。ほんとそうなのだ、と思う。「(略)学生の自由な意見や問いを歓迎した。教壇にうつぶせるようにして耳をすませ、いつも最後まで聞いた。奇抜でも筋道が通った意見には、嬉しそうにやり取りをした。思い込みの強い意見には、そう考える根拠を問い、十分でなければ「ふむ。ほかに」と次の学生を指した。学生は発奮した。」道面さんは加藤周一のサルトルの追悼文のなかで次のくだりが忘れられないという。「世には多くの心温かき人がある。また少なからず考える人がある。しかし心温かき人が必ずしも考える人であるとはかぎらない。いわんや、考える人の心が温かいことは、むしろ稀である」加藤さんは自分は「考える人」だという強い自負を持っていたと思う。だが、「心温かき人」については、そうではないからそうありたい、と思っておられた気がする。それがこの文章を書かせていると思うのだ。しかし、まさにそのような心こそ、「温かい」と言わずしてなんと言うべきか。加藤先生、心温かくしかも考える、稀にも稀な―。 岐阜県の豆腐屋で白沙会会員の弓削智裕さんはこのように励まされたという。「半分冗談だ、と前置きされながら、「トーフイズム」の学説を披露された。明治以降の急速な近代化、工業化を支えたのは、天皇制と豆腐だ、という「学説」。 煮られて良し、焼かれても良し、冷奴でおばんざいで、酒の肴で、それこそ老若男女に愛でられる、豆腐。なんといっても歯がなくても食べられるのがよい。さらに安い。気取らず、背伸びせず、常に庶民の滋養を満たすに足る。豆腐の滋養は維新の混乱から富国強兵を目指し歩き出した庶民に、最も安価に、しかも効率的にエネルギーを与えた。「尊王」による思想動員と滋養に富む豆腐によって、庶民の能動性を引き出し、近代化を達成したという。」いま弓削さんは「九条豆腐」を売り出しているという。 不登校をしていた時期、父親に連れられて通った京都。山本美穂子さんは加藤周一は今もいつも見守ってくれているという。「先生はよく孔子の牛の話もされました。弟子が、一頭のかわいそうな牛を助けたところで他にも多くのかわいそうな牛がいるのだからと言うと、その一頭は私の前を通ったから助ける、と孔子は答えたと言います。ひとつの命を助ける情がなければ、たくさんの命を助ける行動にはつながらないというのです。 その話を聞いた時、「ああ、私は加藤先生にとって一頭の牛だったのだ」と、深い感動を覚えたことがありました。人の命を、それも多くの命を救いたいと願った加藤先生は、目の前の一頭を助けることに尽力を惜しまれなかった。偶然にも私は先生の前を通り、ちゃんと歩けるまでに助けていただきました。」
2010年01月19日
コメント(4)
-

「私にとっての加藤周一」その一
私にとっての加藤周一かもがわ出版が加藤周一の一周忌に合わせて、追悼本を二冊出している。一冊は有名人の追悼集。「冥誕』。今はあまり読む気がしない(その多くはすでに読んでいるから)。もう一冊、加藤周一が晩年京都でいわゆる「サロン」として楽しんでいた白沙会の人々と、かもがわHPで募集した市民の追悼文の文集「私にとっての加藤周一」が出ている。一読、28人の文をよみながら、ここに「私」がいる、と思った。私の周りでは、もちろん私が一番加藤周一をよく読んでいる。けれども、日本中には本当に無数の加藤周一ファンがいるのだということがよくわかった。できうる限り抜き書きしたい。元教師の国方勲さんは「はだしのゲンはピカドンを忘れない」(岩波ブックレット)の生徒の読書感想文集を100人ほどに送る。思いもかけず、91年に面識は一切ない加藤周一から返事が届く。「(略)なさっているお仕事の意味は決定的に大きいと私は考えます。もちろん限界はあります(生徒の人数)。しかし、私たちは、私たちにできることの限界まで、やるべきことをやるほかはないでしよう。私自身は大いに勇気づけられました。ここに確かな手ごたえがあると……それ以上何を望むのかと。御礼まで。―心からの御礼まで。加藤周一」このあと、他の人の追悼文のいずこからも出てくるのですが、有名無名を問わずに、加藤周一は一人ひとり真剣に相対するのです。ヴァイオリニストの松野迅さんは言う。「加藤周一氏の講演に接するたび、その論理の明瞭さも相まって、私は非常に西洋的な話術だと感じてきた。私が西洋音楽を学習してきた故にそう捉えるのかもしれないが、テーマが分析的に「第一に……、第二に……」と提示され、語尾を濁さない日本語は、主題、展開、再現を形づくる西洋音楽の〈ソナタ形式〉を確認するようだった。展開部と再現部の表現が自由自在で、予想を超えた即興的魅力は『居酒屋の加藤周一』を彷彿とさせた」加藤の文章は美しい、とだれもが言う。科学者の明瞭さと文学者の情熱や詩心を併せ持っているからだと私は思っていたが、なるほど、留学先で血となり肉となった西洋音楽だったのかもしれない。会社員の瀬戸さんは言う。「加藤さんの著作から学ぶことは多い。しかし、加藤さんの生きざまからも、おおいに学ぶことがあると思っています。ひとつは、「できるだけ自由に生きてみせる」ことを意識されていたと思います。集団主義の強い日本において「ここまで自由に生きることができる」という事例を身をもって示されたのです。」また、ガラス作家の高澤そよかさんは言う。「あるとき、晩年の氏に直接質問する機会を得て、自由を貫き通すことの秘訣をおたづねした。当時勤め人だった私にとっては、切実だったのだ。高い代価を支払い、社会への影響力を犠牲にして、自覚的に選択した自由人という生き方であることを、氏は教えてくださった。」これに関して(というわけでもないのですが)、白沙会の中心的な発起人の井上吉郎氏がこの本でこのような証言をしていた。「僕は、1993年、96年、2000年の三回、京都市長選挙に立候補している。加藤さんにも推薦してもらおうと、お願いにあがった。 先生は訴えに耳を傾けてこう言われた。自分はこれまで、選挙にあたって政治家を推薦したことが一度だけある。それは宮本顕治さんで、参議院選挙だった。宮本さんとは『展望』の対談で一回だけあった(1949年、臼井吉見編集長)。結果、良いことも悪いこともあった。良いことは宮本さんが当選したこと。悪いことは中国が入国を認めなかったこと。そんな事を語って、自分は一つのことを一回しかしないことにしている。そう言う加藤さん、僕の望みはかなえられなかった」井上氏のエピソードは「高い代価を支払い、社会への影響力を犠牲にして」ということの一つの例だと思う。加藤周一は、サルトルの思想を、フランスの抵抗的文学者たちの実践を、日本においてはいかに実現できるかをいつも考えていたように思う。決して組織には属さないと決めた加藤周一の、しかし日本における『世直し』の可能性をどこに見ていたのか。晩年はその一つの答えだったように思う。白沙会の山本晴彦氏(山口民報編集長)は言う。「加藤先生は日本文化の構造的特徴を『今・ここ』主義だと鮮やかに浮き彫りにし、歴史への無関心・無反省と大勢順応主義に鋭く警鐘を鳴らしづけてきた。ひとつの与件としての『今・ここ』主義を無視するのでなく、事実として見据えて相対化し、そこに埋没しない個人の確立こそが〈未来の洞察と歴史への共鳴〉にとって決定的だと説いた。弁証法を借りれば、『今・ここ』主義即自を『今・ここ』主義対自ととらえ直すことである。「一般的に起こりにくい」としても、まさに加藤先生が生涯をかけた如くに『今・ここ』主義からの〈脱出〉をめざす知的・思想的営為を聊かも休まず、そしてまた先生が晩年最大の情熱を注いだように草の根の小さな実践的努力〈九条の会〉を積み重ねる―もし何かが起こりえるとすれば、その中にこそ現状追従と歴史無視を乗り越える本質的変革の可能性は芽吹くのであろう」「自分は一つのことを一回しかしないことにしている。」晩年に始めた組織的政治的行動の意味ははかりなく大きい。長くなったので二回に分けて紹介する。
2010年01月18日
コメント(2)
-

『現代思想』総特集加藤周一
『現代思想』臨時増刊7月号 総特集加藤周一実は加藤周一を単独で評論した本は極端に少ない。片手で数えることができるくらいである。そういう意味で、やっと出てきた特集本なのだ。今現在加藤周一を語れる人間がここに登場している人達とあと数人であるということは認識しておいていいだろう。単独で加藤氏について本を書いた海老坂武、成田龍一、矢野昌邦も当然出でいる。本を編集したり番組を編集した鷲巣力、桜井均、九条の会で晩年親交厚かった小森陽一の発言も重要である。その他の人達もまだ読んでいないが、重要な指摘があるような気がする。じっくりと読んで生きたい。とりあえず、小森陽一と成田龍一の対談で重要だと思ったところをメモする。(私的メモです。分かりにくいと思います。申し訳ありません。)『加藤周一を読むために』成田 加藤さんは戦後に三つの主題、つまり天皇制批判と戦争責任の追及、そして原爆の問題を抱え発言していったのだと思います。小森 出発点の天皇制批判と連動した大勢順応主義的な知識人に対する批判の文章の中で、本当に戦争を恐ろしいものとして経験したのは庶民、民衆なのだ、だからそこからもう一度こえをあげなければならない、ということを明確にしています。実際の人生の歩みからすると、フランスに行って認識を獲得したと見えるけれども、しかし現実の日本のかかわり方で言えば、いかにしてもう一度人民の中から知識人が声を上げるのかという課題は、その時点その時点できわめて意識的に加藤さんが追求していたということが、まさに現状に対する処方箋となりうる論点だったのだと思います。小森 60年6月に加藤さんがどうして外に出たのか、その直接的な原因について、私も結局聞くことが出来ませんでした。なんどもお酒を飲みながらお尋ねしても、そこはやはり語られなかった。しかし論理的な枠組みでいえば、50年代の後半に加藤さんが主張されていた問題、すなわち、それは憲法より日米安保条約が優位に立ってしまうような状況の中でいったいどういう道を選ぶべきなのか、それからもうひとつ、核兵器問題が米ソの冷戦だけでなく保有国が広がっていこうとしている状況の中でどうするのか、という二点の問題はやはり戦後の加藤さんの出発点をきちんと引き継いだ形での議論なのだけど、その加藤さんの議論を担う政治勢力が現れなかったという問題が私は非常に大きいと思います。成田 同感です。(略)加藤さんはこのあと「日本的なるもの」の考察へと、ぐっと集中していくわけですね。ということは別の言い方をすると、新たな担い手を日本の伝統の中から探り出していこう、再発見していこうという営みを開始したということが出来るかもしれません。60年のときに、何故外に出たのか。小森さんの言うように当時の日本の政治状況に嫌気がさしたのか、それとも二番目の奥さんと別れたショックか(いつごろ離婚したのか、不明なのです)、そのあたりはこれからの研究課題でしょうか。60年に外国に行くことで、大学紛争に巻き込まれずに済んだ加藤は丸山真男らが被った傷を追わなかったことで独特の位置を占めることになったと成田さんは言います。そのあたりは新鮮な視点であって面白いものでした。※この対談で6月の加藤周一をしのぶ会の様子を小森さんが報告しているのですが、奥平康弘さんがどのような話をしたかというところで「木下順二の『巨匠』という芝居を見たときに、こんな難しい芝居を普通の日本人が見ているのかと感動された加藤さんを例に出しながら」と言っており、これは最近その会の報告書が出たので確認できたのだが、『審判』(東京裁判を扱ったもの)の間違いです。編集者もそこまではチェックできなかったようです。小森さんでさえ、そのような間違いをするのだと、少しほっとしました。ちなみに、奥平さんの言いたかったことは『普通の民衆がこんな難しい演劇を会場が満員になるほど見に来る。民衆は決してタモ神みたいな「わかりやすさ」に騙されない。まだ日本の将来はまんざらでもない、と加藤さんは言いたかったのだろう』ということでした。
2009年12月15日
コメント(0)
-

加藤周一のこころを継ぐために
ふと気がつくと、加藤周一の命日(12月5日)を過ぎていました。12月4日に岩波ブックレット「加藤周一のこころを継ぐために」が出版されました。この本は今年6月2日に行なわれた九条の会の講演会「加藤周一の志をうけついで」を元に解説を加え、加筆したものである。加藤周一のこころを継ぐために一番重要だと思ったのは、夫人の矢島翠(みどり)さんの「加藤周一のこころを継ぐために」という挨拶である。全文ではないが、その半分近くを抜粋したい。物書きというのは、大体においてエゴイスティックなものでございます。いま自分がしている仕事、あるいはこれからしようとしている仕事、それこそが一番大事なことなんだという気持で、読んだり書いたり話したりする、そこに重点を置くものです。けれど、加藤の最晩年には、大きな事件が次々に起こって、彼にとってもむしろ実践活動の方に比重が移るようになりました。それはとても大きな変化でした。ですから本当に、たとえば小田実さんなら当然なさったかもしれないけれど、加藤がよくこれだけ動くようになったものだ、と横で見ていて感じておりました。(略)そのような(9.11テロからアフガン、イラク戦争のような)状況を見ていて、加藤が強い危機感を持ったことが感じられました。つね日ごろ、日本の憲法こそは人類の理想の先取りだと信じておりましたから、どうにかしなければならない、と考えるようになった。昔の敵国であるアメリカの言いなりになって、その戦争の支援を始めるようなことは、なんとしてでも阻止しなければならないと考え、皆様に呼びかけて、5年前の2004年6月に「九条の会」が発足したわけです。(略)加藤の人生は、それ以降大きく変わっていきました。物書きのエゴイズムから抜け出し、-と言ってもよいと思いますが-、九条の会を広める運動を始めます。しかも、その運動も、石造りの堅い、しっかりした三角形のピラミッドではなく、既成の組織に決して乗らず、一人ひとり生きて、暮らして、物を考えている、そういう人たちが手をつないでゆるやかなネットワークをつくる、というものでした。その最初の狙いは、現在の九条の会の運動において、まず達成できたのではないかと思います。その狙いの達成したあと、それをどうやって生かしていくか。権力側は、もう憲法改正を既成事実であるかのように話しています。そして、改憲手続法である国民投票法は、小泉政権のあと安倍政権時に強行採決によって成立しており、2010年の5月から施行されます。それをあたかも既定路線のように、すぐにも国民投票が行なわれるかのように政府は宣伝しています。そのような状況を、きちんと落ち着いて見極めながら、人類の理想である憲法をどう生かしていくか。このゆるやかなネットワークの中で、どう根づかせていくか、考えていかなければなりません。日本で生まれた新しいネットワークのかたちは、世界の人々の共感をよび集めながら、地球をおおうまでに広がっていく可能性を持っている。日本の政局の動きに一喜一憂してばかりを恐れるよりも、これまでは考えてもみなかった明日の憲法のありかたに、希望をつなぐことはできないでしょうか。-加藤はという言葉が、きらいでした。1960年生まれの私は、80年から国政にかかわりだしたので、まだという経験が無い。だから半分の人生だったと言っていい。むしろ、アメリカ、政府、大企業の戦略を感心することしきりであった。しかし、初めてという希望が生まれている。20世紀日本が生んだ最高の「知識人」の最後の「戦略」はそう簡単に逆転できないところまで来ている。「巨匠」は死ぬ間際に最後の「闘い」に打って出た。木下順二の演劇「巨匠」では「青年」がそれを受け継いでいる。
2009年12月07日
コメント(2)
-

「天皇制を論ず」加藤周一自選集より
加藤周一自選集(1(1937ー1954))より第二弾です。加藤周一の「天皇制を論ず」は、戦後最も早い時期に現れた天皇制批判の文章である。掲載は東京大学内のある財団法人「大学新聞」1946年3月21号であった。「不合理主義の源泉 問題は天皇制であって天皇ではない」の表題のあとにこの題名がついている。筆名は荒井作之助。話はずれるが、この東京「大学新聞」は戦前から現代までずっと刊行し続けられている、独立採算で会社組織になっているおそらく唯一の大学新聞である。私が作っていたような大学新聞とは中身も部数も影響力も違う。時代が下って、かつて映画「精神」の監督の想田和弘もここの編集長をしていたらしい。あまりもの激務に一時統合失調症にかかった。それで新聞社をやめたわけである。これが彼をして「精神」を撮らせた動機にもなっている。その「大学新聞」に加藤周一は明確に断じる。「天皇制は何故やめなければならないのか。理由は簡単である。天皇制は戦争の原因であったし、やめなければ、又戦争の原因となるかもしれないからである」加藤は天皇制廃止の理由を述べた後に廃止反対論の無意味なことを示していく。非常に論理的な文章である。筆名荒井作之助。「(疎開先の)追分で世話になった農民の名前をそのまま筆名とした」らしい。実在した農民の名前を筆名としたのは、「虐げられてきた農民の立場で天皇制を論じたかったのだろう」と編者の鷲巣氏は言う。支配者層は、降伏か抗戦かを考えたとき日本人民の命を考えたのではなく、ひとり天皇の地位についてのみ考えた。廃止すれば(天皇の地位の)混乱が起きるという意見に対し、加藤は「戦争を迎えるのは沈黙をもってし、天皇制の廃止を称うに混乱を以ってする者は恥を知れと云いたい」と書いた。穏やかで理性的な加藤の文章の70年の著作の中で、もっとも激烈な言葉がここに書かれている。戦争に対する怒り、それが加藤周一の出発点だった。そしてそれは生涯変わらなかった。今回初めて収録された、同じ筆名で書かれた「天皇制について」という文章がある。(「女性改造」1946年6月号)天皇制とは封建体制そのものである、とその根本を説明し、天皇制を支持する「国民感情」が根強くあることを認めながらも、この文章ではとくに女性たちに対して分かりやすく情熱的に訴える。「面を起こそう」「あなた方を真に美しくするものは、理性と勇気、時と場合によっては屈せざる反抗の精神である」
2009年11月17日
コメント(3)
-

「正月」加藤周一自選集より
加藤周一自選集(1(1937ー1954))自選集1より私が自ら選んで(^^;)いくつかをコメントしたい。なお、この自選集「木下杢太郎の方法」に加藤周一は「このような歴史的人物(木下杢太郎のこと)を称ぶには敬称を省くのが敬意を表する所以だと思うから、旧師の一人を称ぶに私は敬称を省く」と書いている。それに習い、私も加藤周一を語るにこれからは敬称を省きたいと思う。1938年(昭和13年)旧制一高時代文芸部の雑誌「校友会雑誌」に加藤は三篇小説を寄稿しているらしいが、その一篇が「正月」である。高校生になった「私」が小学時代から親しくしている恩師を訪ねる、という内容の小編である。この恩師「秋元先生」は「羊の歌」に描かれる小学四年のときの担任「松本先生」に違いない、と解説の鷲巣氏は言う。「よく事実を見なければならない」ことを生徒に教え、加藤氏はその人柄を好み、その知識を敬っていた。学校のこと等を少し話したあとで、私は想出した様に最近大学を辞職された某教授のことに触れた。すると先生は、国の方針と意見がちがえば仕方がない、という意味のことを簡単に言われた。それは、現在、この国の社会的傾向に対する種々の立場の問題を含んでいるはずであった。のみならず教育と云う点にあらわれたそれ等の立場の問題として、必然的に私たちの関心を要求するはずであった。―すくなくとも、仕方ないと云う答以上のものを望んでいた私は肩透かしを喰わせられた様な気分を味わった。感じたことは二つ。ひとつは、この「最近大学を辞職された某教授」は東京大学教授矢内原忠雄氏(親友矢内原伊作の父)の1937年12月の辞職を示しているのに間違いない。だから次の年の正月の話題としてはまったく普通であった。しかし、いかに高校生の書く小説といえども、非常に大胆だとは思う。あきらかに「私」は某教授の辞職に批判的である。そういう小説を発表し、当局が目をつければ学生加藤周一にはいろいろと不便なことがおきるだろう。小説はそういうこともある程度覚悟した上で書かれている「落ち着き」があった。そこに居るのは、18歳にしてすでに自立した一個の社会的な青年の姿である。ひとつは、自分の成長と、社会の矛盾、そしてそのバランスをすでに客観的に書くことが出来るところまで成長している、早熟な文学青年だという点である。この小説は掌編ということもあったが、まとまっていて、読み応えがあった。(私には漱石の影響を感じたが、確信はない)このときの社会状況と、青年(少年?)加藤周一の思想変遷はもう少し綿密に研究する必要があるのかもしれないが、今はその余裕がない。
2009年11月15日
コメント(0)
-

「加藤周一自選集1」より
加藤周一自選集(1(1937ー1954))9月より岩波書店から加藤周一自選集の刊行が始まった。すでに平凡社から「加藤周一著作集」24巻がでており、「加藤周一セレクション」も平凡社文庫から出ている。では、なぜ「全集」ではなく、「自選集」なのか。私は大いに疑問を持っている。もうこれで「全集」の出る目は八割以上なくなった。編集方針は第一巻の「刊行にあたって」に詳しい。編集会議は2007年夏より始まったらしい。初期には加藤周一本人が積極的にかかわっている。加藤氏はこれによって、「70年余の「著作活動の軌跡」をたどり、かつ自分自身を「定義」する選集として編む」ことを望み、読者のためにも著作集やセレクションと違う編集方針で編むことを望んだらしい。よって、今までとは違い、基本的に発表年代順に著作が並ぶ。他の方針として、ひとつ、著作に限定して収め、対談や講演などは収めない。ひとつ、安く手に入る代表作「羊の歌」「日本文学史序説」「日本その心とかたち」「日本文化における時間と空間」は割愛する。ひとつ、既刊の評論集や著作集に収録されなかった著作からも、加藤氏を定義するに必要な著作を収めるように努める。ひとつ、加藤氏が執筆を切望していた「鴎外・茂吉・杢太郎」に関連する著作を多く集めるように努める。ひとつ、外国語著作は収めない。全集でない以上、それらの編集方針は当然だろうと思う。そうでないと、当然全10巻という範囲では収めることは出来なかっただろう。けれども、これだけの説明では「なぜあの重要な著作が選から漏れているのか」ということの説明にはなっていない。たとえば、初期の代表的な評論集「1946文学的考察」からは三篇しか収録がなくて、「1945年のヴェルギリウス」は洩れている。私はこの中の「予言者カッサンドラの悲しい運命こそは、歴史に於ける理性の役割を、実に鮮やかに象徴するものであろう。」という言葉に大きな意味を感じているものである。カッサンドラという言葉を加藤周一は後々も使っていく。預言者としての知識人の役割を最初から意識していたことの現れであったはずである。このことは、加藤周一を「定義」するうえで重要なことではないのか。また、50年発表の小説「ある晴れた日に」も洩れた。もちろんこれは、岩波現代文庫から最近刊行されたからであろう。よって納得している。この年の重要な文学評論で長く絶版になっている「文学とは何か」も洩れている。加藤氏の最初期の全般的な文学評論であり、これこそ加藤氏を「定義」するために自選集に入れるべきだった。何が問題だったのか、編者の鷲巣力氏にはぜひとも明らかにしてもらいたいと思う。それでも、この自選集は面白かった。この自選集によって初めて目にすることの出来た著作があったからである。17歳のときのあまりにも専門的な映画評や18歳のときの小説「正月」。あるいは、日本で最初期の天皇制批判「天皇制を論ず」の直後に書かれた1946年6月の「天皇制について」。あるいは、初めてのサルトル論51年「ジャン・ポール・サルトル」を読むことが出来るのは喜びであり貴重である。もちろん、もう気がついていると思いますが、私の加藤周一に関する記事は、一般の人の関心とは少しずれていて、いつかはモノにしたい「加藤周一論」のためのメモ書きのようなものなので、他の人が読んでおそらく、この自選集への不満や「喜びであり貴重である」感情は生まれないだろうということも自覚しています。加藤周一に関しては、少しミーハー的な文章にならざるをえないのですが、ご勘弁ください。まあ、私のブログは半分以上はこれだけではなくて、考古学関係やらミーハー的な「不親切な文章」なのです。鷲巣「刊行にあたって」でこのように書いています。加藤氏の著作は、文意は明瞭、視点は斬新である。かつ美しく、精確な文で表現される。詩人の魂と科学者の方法を兼ね備えた稀有な作家であった。加藤氏はまた終生変わらず、少数者として矜持を保って発言し続け、弱者を理解する姿勢を崩さなかった。大言壮語を嫌い、語るときはつねに声低く語った。これらはまさに「加藤周一の精神」の表れである。私もまた、そう思う。せっかくなので、以後「自選集1」から幾つか文章を選んでコメントしたい。
2009年11月13日
コメント(0)
-

上野毛彷徨
東京にこの前行きましたが、「加藤周一が書いた加藤周一」の感想で書いたとおり、加藤周一の居宅を訪ねて、上野毛を徘徊したのです。上野毛の呼び名を駅の人に「上野毛(うえのもう)行きのの電車はこちらでいいのですか」と尋ねたぐらいに良く知らない私です。何度も聞きなおした末にやっと「ああ上野毛(かみのげ)ね」と教えてくれました。居宅情報は「加藤周一著作集15」の「あとがき」にこのように書かれている。しかし、住めば都である。私の家の近くには五島美術館があって、焼き物の逸品を備えるばかりでなく、また名古屋の徳川美術館と共に現存する「源氏物語絵巻」を二分して蔵することは、人のしる通りである。駅前にパン屋があり、「モンテ・ヤマサキ」という。「モンテ」はすでに「ヤマ」だから、いささかくどい名前にちがいないが、その店に座る太ったおかみさんには、泰然として迫らない風格がある。また酒屋のおかみさんとは、ブルガリア産のぶとう酒の安くてコクのあるやつを、値切って買ったときから知り合いになった。(1979.11.20)分ったこと。ひとつ、パン屋のモンテ・ヤマサキを探すこと。ひとつ、五島美術館の近くである。インターネットで地図を調べて印刷して持っていったわけです。駅前に交番があることは分かっていましたから、まずはそこでダメ元で「評論家の加藤周一さんのお宅は知っていますか」「番地は?電話番号は?」不審者だと思われなかったのは嬉しいのですが、やっぱりおまわりさんは名前さえ知りませんでした。「知らないのです。それでは、パン屋のモンテ・ヤマサキは知りませんか?」電話帳を引いてくれましたが、ありませんでした。なにしろ30年前の文章です。もう畳んでいるのかもしれません。お巡りさんは親切にもゼンリンの地図も見せてくれました。「加藤なんて家はたくさんあるから分からないだろう」「そうなんです」なんとなく五島美術館の近くに「加藤」と書いている家を見つけました。そこを目指して行きました。閑静な住宅街です。外国人の家族が散歩しています。イメージぴったり。これはモンテ・ヤマサキではなく、目に付いたおしゃれなパン屋さん昭和40年前後に建てていると思うので、庭付きの木造の家だと思うのです。ところが、行ってみると、目指す加藤家の表札は名前が違うし、家は新しいし、中から小さい子供の声さえします。《でも、もしかしたら子供さんの代に名前も変えて改築しているかもしれない》と思い直し、写真だけ撮りました。結局違ったのですが…。五島美術館に行って見ました。ちょうど「伝えゆく典籍の至宝」展をしていました。江戸時代の文人の写本ならびに原本が展示されています。加藤氏が生きていたならば、必ず見に来ただろう内容です。庭も昔の資産家らしい凝ったものでした。ダメ元で少しお年を召した売り子さんに聞いてみました。「加藤さんなら、駅の向こう側に住んでおられると聞いたことがあったわ。どこかははっきりしないけど」やっぱり顔見知りでした。そして、まったく見当違いのところを探していたようです。駅の周りを探してみましたが、見つかりませんでした。前にどこかの文章に小森陽一さんが「ご自宅の近くの喫茶店の二階で話を聞いた」と書いていたような気がします。周りを回ってみて、二階のある喫茶店はこの「ル・サフラン」だけです。上がってケーキセットを頼みました。その日のケーキのうちいちばんフランスらしいケーキであるシャルロット・ポワールを頼みました。なんとも濃厚なクリームが入っていました。ここに間違いないと思います。五島美術館お勧めの食堂のチラシがあったので、そこに書いてあった「さくら庵」という東京の典型的な蕎麦屋に入り、野菜掻揚げ丼と蕎麦のセットを頼みました。濃い口醤油のだし汁、そば粉は北海道から取り寄せて手打ちをした白く細い麺の本格派です。おいしゅうございました。もうまったく日も暮れました。あきらめて岡山行きの新幹線に乗ったのでした。行きかう人、特にお年を召した女性、みんな加藤氏の妹のような顔立ちでした。蕎麦屋もそうですが、上品なパン屋や喫茶店、ビンテージという名のワイン酒屋、中華食堂、豆腐の惣菜や、銭湯、上品でしかも庶民的な、加藤氏の住む町にふさわしい処でした。
2009年11月11日
コメント(8)
-

「ある晴れた日に」銃後における人間性の圧殺
ある晴れた日に岩波現代文庫 加藤周一8月15日の正午、天皇の放送を聞き終わって外へ飛び出した土屋太郎は、一晩を眠らずに過ごしたので、一瞬めまいを感じた。晴れあがった真昼の空は青く、巨大な入道雲がぎらぎらと輝いている。盛り上がり、わきあがり、膨張し、途方もないエネルギーをみなぎらせて、天頂に届く雲。太郎は雲を見た。自分はここに生きていると思い、未来に向かってひらかれていると感じ、身体の中に、かつて知らなかった希望と力が溢れるのを意識した。この小説を見たのは初めてではない。すでに「加藤周一著作集」13巻に入っていて、読もうと思えば読めたのである。けれども、途中で挫折した。小説的には成功していないと思う。一生懸命小説を書いているという感じがして、すらすらと読めなかったのである。心理描写のくどいところもある。いまから60年前の1950年、加藤周一は友人の中村真一郎や福永武彦のようには小説を書くことが出来なかった。そのことが、彼をして日本有数の文学評論家に変えさせたのかもしれない。ところが、文庫本になったことを契機に改めて少し無理をして読んでみるとこれがなかなか「面白かった」。「序」を書いている渡辺一夫も言っているが、「近代戦争の銃後における人間性の圧殺に対する抗議証言にもなるという点で、忘れがたい印象を残」しているのである。何人かの典型的な人間が登場する。主人公土屋太郎や友人関哲哉の姉あき子、あき子の疎開先信州に暮らす画家やその友人吉川、あるいは大学教授の五十嵐は戦争に批判的で、そしてそのことを自由にいえないことに精神的な圧迫を感じている。その信州の田舎にも水原という人の精神に土足で入り込む憲兵がいる。渡辺一夫でさえ、自殺を考えていた(「敗戦日記」)ということなのだから、あの時代にあって、批判精神を保ち続けることが以下に大変なことかなのは今の想像以上なのだろう。あるいは、太郎の東京の病院の医者の同僚に対して太郎は「火傷の治療法については、綿密な論理を繰り整然と語ることの出来る男が、なぜ沖縄の運命については簡単な論理さえも冷静にたどることが出来ないのだろう」というようなことを感じる。一方では、あき子や画家や教授とは職業が違うのにもかかわらず、共通の言語で語ることの喜びがある。もう一人の女性が登場する。ユキ子は看護婦であるのと同時に医者である土屋に淡い恋心を抱いている。彼女は「健康な」皇国女性として登場する。空襲のときに土屋とユキ子は(精神的な)決定的別れを経験する。それらの会話を重ねていく中で、一種の戦争場面のない戦争小説が出来あがっているのである。この本の収穫は渡辺一夫の「序」がついていることであった。実は渡辺は加藤のことを「星菫派の一人」と書いている。加藤は星菫派(戦争中リルケなどを楽しみながら、一方で戦争を容認していた人達)を厳しく批判していた張本人で、渡辺一夫もそれを知っていたはずなのに、なぜそう書いたのか、大きな疑問なのであるが、それはここの記事の趣旨ではない。
2009年11月09日
コメント(0)
全62件 (62件中 1-50件目)











