2004年04月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
「生きている兵隊」 【石川達三】
生きている兵隊(伏字復元版) (著者:石川達三|出版社:中公文庫) 南京攻略戦前後を描く小説。 ノンフィクションではなく、あくまでも小説である。 主人公は階級の低い兵士たちであり、日本軍が組織的にどういうことをしたかということを描いているのではなく、戦場において、人間はどのように考え行動するのか、というのを描いている。 例えば、主要な登場人物の一人近藤の内面描写、「彼のインテリゼンスは戦場と妥協していたのである」(p88)、「近藤はまた彼の感受性の上にぴたりと蓋をしめて戦場と妥協した」(p98)などが印象に残る。 また、従軍僧が、出征前は、敵の戦死者も弔ってやるつもりだったのに、戦場ではその気になれず、積極的に中国人を殺す。 ことさら、日本軍の残虐行為を描こうとしているわけではなく、「これが現実だ」ということ淡々と描いており、おそらく実際にこうだったのだろうと思わせる内容なのだが、だからこそ軍にとっては都合が悪かったのだろう。 「倉田少尉の刀では敵の壕までとどかない」(p130)の「刀」は「力」の誤植か?
2004.04.26
コメント(0)
-

「こんな親が問題児をつくる」 【相部和男】
こんな親が問題児をつくる一万人の非行相談から( 著者:相部和男 | 出版社: 講談社文庫) 相談所を営む著者は、少年院で12年間カウンセリングをするうちに、少年院に入る前の段階で非行の火を消すべきだと考え、保護観察の分野に移り、25年の経験を経て、保護観察になる前の段階で手がけるべきだと思うようになったという。 「できたら少年院には入れたくないという持論をもっている」(p164)とも書いている。 何度も書かれているが、母乳ではなく人工栄養で育った子供は、母親との間に充分な関係が築かれず、それが原因になることがあるという。具体的な事例としてあげられる子供の多くが「人見知りをしなかった」という。また、非行に走った子どもと親が、決まったように飯粒をお椀に残すというのも興味深い。 子供の非行の原因となる親のタイプを、「手抜き型」「ホイホイガミガミ型」など12に分類しているが、ここまで分類されていると、どれにも当てはまらない親というのはいないのではないかと思う。 「子供のタメにならない教師」も10タイプあげているが、親が原因であることの方がずっと多い。 「カウンセリングの実際」という章もあるが、具体的なカウンセリング内容については触れていない。文章だけで、中途半端に受理解されるのを避けるためだろうか。 もっと一つ一つの事例を具体的に書いて欲しい所だが、それをしたのでは一冊にまとまらないだろう。 豊富な経験と知識のある人だとは思うのだが、「登校しないまま形だけは中学を卒業したが、自閉症となり、家から一歩も外に出ようとしなかった」(p132)という文章には驚いた。中学卒業後に自閉症になるわけがない。引きこもりと混同しているようだ。 親というものは、「字のとおり木の上に立って見ることのできる人が本当の親である」(p220)というのもいただけない。 サマーヒル学園の例が何度も出てくるが、タバコを吸い始めたばかりの子供は、自由な雰囲気の中におくと殆ど自らタバコを吸うことをやめるが、「タバコがすでに病みつきになっている者はやめられない」(p76)そうだ。依存症には対処できないわけだ。 非行に走った子供と直接会うことも多く、相手に信頼されているようだ。しかし、無条件に子供を肯定しているわけではない。非行から立ち直らせるということは、子供の今の状態を変える、ということであり、子供の側から言えば、今のあり方は良くない、と言われるということである。 それでも信頼されるためには、親近関係の維持が必要であり、親子の間ならなおさらその親近関係が必要なのだが、それが容易ではないからこそ非行が多いのだろう。
2004.04.20
コメント(0)
-
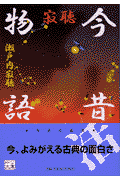
「寂聴今昔物語」 【瀬戸内寂聴】
寂聴今昔物語(著者:瀬戸内寂聴|出版社:中央公論新社) 瀬戸内寂聴が、『今昔物語』の中から面白いと思ったものを随意に口語訳したもの。 全体の構成などは特に考えていない。 全部で45話。 仏教説話もあるが、生々しい男女の関係を描いたものも多い。原典にそういうものが多いのか、それとも著者の好みか。 瀬戸内寂聴の本を初めて読んだが、文章は読みやすくわかりやすい。
2004.04.16
コメント(0)
-
「中国怪奇小説集」 【岡本綺堂】
中国怪奇小説集(著者:岡本綺堂|出版社:光文社文庫) 「青蛙堂奇談」(『影を踏まれた女』所収)と同じように、一人ずつ話すという趣向。 六朝の『捜神記』から清の『閲微草堂筆記』まで時代順に並ぶ。 岡本綺堂の広範な読書量の一端を窺うことができる。 岡本経一の解説によると、初版は1930年、総ルビ付で出たという。 その時のルビによるものなのか、「[門<虫]」を「みん」、「姚」を「ちょう」と読ませるなど、本来の音読みとは違う読みがほどこしてあるものが目立つ。 『夷堅志』の「餅を買う女」は、女の霊が水飴を買いに来る話とオダマキ型の合体。 『池北偶談』の「[口+斗]蛇」の[口+斗]は「叫」の誤植ではないだろうか。 『子不語』の「狗熊」の「虎[亡+おおざと]」の[亡+おおざと]は「邱」の誤植か。
2004.04.11
コメント(0)
-
「影を踏まれた女」 【岡本綺堂】
影を踏まれた女(者:岡本綺堂|出版社:光文社・光文社文庫) 「青蛙堂鬼談」の12編と、「近代異妖編」3編。 当代の話もあれば江戸時代の話もある。 もっとも怖いのは「異妖編」の「寺町の竹藪」。合理的な説明は全くない。 それがかえってこわい。「あたし、もうみんなと遊ばないのよ。」という台詞が何を意味するのか全く説明されず、勝手にあれこれ想像するしかないのだが、その台詞の向こうに深い闇が想像されるのだ。 印象に残ったこと。 「彼は土地の新聞社に知人があるのを幸いに、○○教の講師兄妹のあいだに不倫の関係があるということをまことしやかに報告した。」(p56)「不倫」という語の本来の用法である。 「満洲の土人は薬をめったに飲んだことがないので」(p120) 「満州」ではなく、ちゃんと「満洲」になっている。またここの「土人」も、「土地の人」という本来の意味で用いられている。 「この時代には江戸のなごりで、御新造《ごしんぞ》という詞《ことば》がまだ用いられていました。それは奥さんの次で、おかみさんの上です。」(p169) これは「黄いろい紙」という話の一部だが、初出は大正14年。その頃には、「奥さん」「御新造」「おかみさん」の順位がわからなくなっていたわけだ。 「むじなをその芸妓になそらえて予譲《よじょう》の衣《きぬ》というような心持ちであったのか」(p177) これも「黄いろい紙」。山本周五郎の「よじょう」のもとにもなっている予譲の故事、明治大正には広く知れ渡っていたらしい。たしか、下町の神社にその故事を記したものがあったはず。それでなじんでいたのだろう。 「むかしから丸年《まるどし》の者は歯並みがいいので笛吹に適しているとかいう俗説があるが、この喜兵衛も二月生れの丸年であるせいか、笛を吹くことはなかなか上手で」(p184)の「丸年」、意味を調べたが分からなかった。 「七尺《しちしゃく》去って師の影を踏まずなどと支那でもいう。」(p263)を見て、「三尺」の間違いではと思って調べたら、もとは七尺だったようだ。 「おせきがとつかわ[#「とつかわ」に傍点]と店を出たのは」(p265)の「とつかわ」が分からなかったが、「あわてて」という意味だった。
2004.04.07
コメント(0)
-
「南方熊楠 森羅万象を見つめた少年」 【飯倉照平】
南方熊楠 森羅万象を見つめた少年( 著者: 飯倉照平 | 出版社: 岩波書店・岩波ジュニア新書) 熊楠の青年期を中心にした伝記。 著者の文章は平易ながら、内容や引用は高度なので、中学3年以上ぐらいでないと理解できないのではないか。 読むと、常に出口の見えない情況にあってもがき苦しんでいたようだ。 絵も字もうまく、勉強に努力を惜しまない。しかし、努力の結果として自分が何を残せるのか、何を残したいのか、それが自分にも分からなかったのではないか。常にイライラした気持ちでいたのだろう。 熊楠はなんとローラ・インガルス・ワイルダー(大草原シリーズ)と同い年だが、同じ時代とは思えないほど違う世界に住んでいる。盲人用の大学もあったほどだから、都市部では教育環境は整っていたはずだが、熊楠の少年時代の方が、ローラの少女時代よりも教育環境は恵まれている
2004.04.02
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- お勧めの本
- 「海のてがみのゆうびんや」海で迷子…
- (2025-11-16 19:10:04)
-








