2004年07月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
「雄呂血」 【監督・二川文太郎。1925年】
1925年 寿々喜多呂九平脚本・二川文太郎監督 オリジナル、つまり、板東妻三郎版。久しぶりに見た。BSで放送された活弁付きのもの。 声は入らないので、役者は身振りと表情だけで状況がわかるように演じなくてはならない。 心中を説明する字幕と活弁の助けはあるのだが、複雑な話なのに、表情だけでも何となくわかるくらいわかりやすい演技。 正義感の強い武士が、周囲に誤解されてならずもの呼ばわりされるようになり、人を助けようとしたのに、捕り方と大立ち回りをすることになる。主人公にも短慮なところはあるのだが。 初恋の女性とその夫を助けることはでき、その二人は陰ながら手を合わせる、ということで、観客には幾分かの救いは与えられるのだが、主人公には全くない。 善人面の悪人と、悪人に見らえてしまう善人。ああ、なんという運命のいたずらか。 それにしても、この映画、作られたのが大正14年。 映画というものが広まってまだそんなに時間はたっていないはずなのに、もうこんなに屈折のある映画を作っていたのだ。 いつの時代でも、すぐれた創作芸術家というのはいるのだ。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.07.24
コメント(0)
-
さすが産経新聞!
白骨温泉で、入浴剤を混ぜていたという事件についての、「産経新聞」の「産経抄」というコラム。「しかし、だからといってそれで健康を損なう害があるわけではない。和歌山県の白浜でオーストラリアから白砂を運んでいる例もある。涙ぐましい企業努力といっては言い過ぎだが、頭から湯気を立て目の色を変えてケシカラヌというほどのことではあるまい。」だって。 さすが産経新聞! 「嘘をついてはいけない」などという子供のようなことは言わないのだ。 金儲けのためなら多少のことは許される、というわけだ。
2004.07.15
コメント(0)
-

「免疫革命」 【安保徹】
免疫革命( 著者: 安保徹 | 出版社: 講談社インターナショナル) 新潟大学教授が書いた本。これまでの対症療法を否定し、人間が本来持っている治癒力を引き出すことを主張する。 著者の考えに従った治療での、進行性のガンも治癒率は高いそうだ。 免疫の仕組みや白血球とはどういうものかという専門的な説明が大部分なのだが、流し読みなのであまり頭に入らない。 そもそも病気の原因は何かというと、ストレスがもっとも大きな原因だという。 生活を改め、ストレスをなくしていくことで病気にかからなくなり、病気になっていても治癒していくのだそうだ。 かと思うと、現代人はリラックスしすぎていて病気になったりもするそうな。 何しろ「心のもち方が体調をつくる」(p266)ということで、クヨクヨするのがよくないというのだ。しかし、「そうか、クヨクヨするのがよくないのか、じゃあクヨクヨするのはやめよう」などといってクヨクヨしなくなれる人は、最初からクヨクヨしないだろう。 クヨクヨしまいと思ってもクヨクヨしてしまうからクヨクヨするのだ。 読んでいて強く感じるのは、「医学は宗教に近い」ということだ。 患者の精神への働きかけが重要なのである。 「民間療法でも、自分が治ると信じられるものに自己責任でとりくむことは、免疫活性につながります」(p133)という。信じる者は救われる、ということだ。
2004.07.14
コメント(0)
-
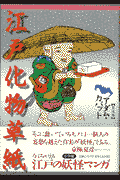
「江戸化物草紙」 【アダム・カバット】
江戸化物草紙(著者: アダム・カバット|出版社:小学館) 著者はアメリカ生まれの日本文学研究者。 15歳の時に英訳の『源氏物語』を読んで日本文学の虜になり、日本に留学、大学院の時から泉鏡花の幻想小説を専門に研究し、今では日本の大学の教授になっている。 江戸時代の、化け物を題材にした草双紙5種の紹介が中心。 草子の紙面を全部載せているので、全体のイメージがよく分かる。 取り上げられているのは、北尾政美(きたおまさよし)・画の『夭怪着到牒(ばけものちゃくとうちょう)』のほかはいずれも十返舎一九作の『妖怪一年草』(勝川春英・画)、『化物(ばけもの)の娵入(よめいり)』(勝川春英・画)、『信有奇怪会(たのみありばけもののまじわり)』(十返舎一九・画)、『化皮太鼓伝(わかのかわたいこでん)』(歌川国芳・画)。 どれも画が凝っていて面白い。『妖怪一年草』は人間界の年中行事のパロディになっていて、花見ならぬ「穴見」、お釈迦様の誕生を祝うのに対して「お逆さま」の誕生を祝い、月見をせずに「闇見」をするといった具合。十返舎一九の絵のうまいのにも驚く。 ほかに、山口昌男や小松和彦、京極夏彦らの考察もある。 ただ、京極夏彦は、「江戸化物草紙の妖怪画」で、柳田国男による、妖怪は零落した神の姿である、という定義を「現在でも妖怪を定義する条件として一般にも広く用いられている」と述べているが、これは小松和彦は否定しており、民俗学研究者に聞いても、現在でもそのまま通用しているわけではない、ということだった。
2004.07.11
コメント(0)
-
「トキワ荘の青春」 【監督・市川準。1996年】
1996年 カルチャア・パブリッシャーズ。監督・市川準。 恥ずかしながら、こういう映画があることを知らなかった。 トキワ荘については、ゆかりの人々が思い出を描いてまとめた「トキワ荘物語」も読んだし、藤子不二雄の「まんが道」も読んだ。 その昔、NHKで放送されたドキュメンタリーも見た。取り壊し前にかつての住人が顔を合わせるというもの。 しかし、それでもわかりにくい。主役の本木雅弘が寺田ヒロオだということはすぐわかる。見ていると、髪型も似せているし、顔も面長に見えてくる。 ところが、ほかの登場人物の区別が付きにくい。 最初に、事実に基づいたフィクションだと断っており、話の展開上、実話とは異なる部分も多い。それで面白くなるならそれでもいいのだが、面白くなっているとはいいがたい。 途中、アニメ一本でいくことにする、と言ってトキワ荘を去ったのは鈴木伸一のことだと思うが、この映画だけでは何がなんだかわからない。マンガから離れていった人もいる、ということを示すエピソードか。 売れて忙しくなっていく人もいる一方で、編集者に引導を渡されれる森安なおや、自ら筆を折る寺田ヒロオ。テーマは挫折した青春なのか。 1950年代(たぶん)の風景の写真や、曲をさかんに取り入れているところをみると、その時代を描きたかったのか。 あれこれ盛り込まず、寺田ヒロオのことだけ描くなり、寺田の目を通して見たほかの漫画家の姿を描くなり、焦点を絞ればよかったのではないか。 つげ義春が出てきたことだけは驚いた。交流があったとは知らなかった。 森安なおやのマンガが出てきたが、タケノコを背負った娘の話で、これは読んだことがある。ほかには、ロシアのスキー場の話しかしらないが、叙情的で、洗練された感性の持ち主だった。 思えば、寺田ヒロオや森安なおやは手塚治虫の影響は受けなかったのだろう。それが良かったのか悪かったのかはわからない。二人はもっと早く生まれていれば、漫画家生活が続いたのではないかと思う。 最後の場面で、寺田ヒロオが背番号ゼロの野球少年に「ありがとうございました」と礼を言われるのは、別れの言葉なのだ。 と、いろいろなことを考えながら見た。 不満に思うところは多いのだが、こういう映画を作るという志は買う。トキワ荘の青春(1996) - goo 映画楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.07.09
コメント(0)
-

「考証風流大名列伝」 【稲垣史生】
考証風流大名列伝(著者:稲垣史生|出版社:新潮文庫) 時代考証家の語る風流大名あれこれ。 「考証」とはついているが、厳密な時代考証によって実像を明らかにしようというのではなく、「こんな大名がいたんだよ」という軽い読み物にしてある。 小説仕立ての逸話紹介というところ。 鍋島藩の化け猫騒動などは、俗説を紹介し、実際のところを述べ、考証といえば考証だが、荒唐無稽な俗説を紹介することの方に筆を費やしている。 茶道誌「淡交」に連載したものだそうで、茶器や茶室に関わる話が多い。 しかし、序章で「茶室が密談には誂《あつら》え向きなので、政略は多くそこで練られたと聞いた。」「本書に出る大名の、多くが茶道の名手なのはそのためである。」(p15)と書いていながら、柳生宗矩の章では、戦国武将が茶道に励んだのは、「耽美《たんび》・平静の極致心理の希求からである。」「密議をこらし、或《ある》いは隠密《おんみつ》に密命を下す場所などとするのは見当はずれも甚だしい。」(p161)とはどういうことだ。 山本博文の解説は役に立つ。 史料の信憑性を綿密に考察するよりも、話が面白ければどんな史料でも積極的に活用しているという。 稲垣史生は杉浦日向子の師であり、三田村鳶魚の弟子である。 島津の「お由羅騒動」をもとにした直木三十五の「南国太平記」について、「江戸の権威三田村鳶魚翁《えんぎょおう》がその事実をつかみ、心を躍らせて書こうとしていた矢先、当時、日の出の勢いの作家直木三十五が、どこで取材したか、いち早く歴史小説として書き」(p209)とあるが、三田村鳶魚の「大衆文芸評判記」では、三田村鳶魚の発表した文章をもとに書いたように思われる。
2004.07.06
コメント(0)
-
「闇の左手」 【アーシュラ・K.ル・グイン】
闇の左手(著者: アーシュラ・K.ル・グイン /小尾芙佐 | 出版社:ハヤカワ文庫) 実に久しぶりにSFを読んだ。 有名な作品であることは知っていたし、家にはあったのだが、手に取る機会がなかった。 作者が構築した独自の未来史の一部で、最初は何が何だか分からなかったが、惑星「冬」の政治的な面については結局なんだかよく分からなかった。 こういうことを考えついて、破綻なく長編を書くということ自体が想像を絶する。
2004.07.05
コメント(0)
-

「スリーピー・ホロウ」 【監督・ティム・バートン。1999年】
1999年 アメリカ。監督・ティム・バートン。 たまたま家にあったビデオを巻き戻したらこれが録画されていたので見てみた。 最近全く洋画を見ないので監督も主演もどういう人なのか知らない。知っていたのはクリストファー・リーだけ。いやあ、久しぶりに見たなあ。 話は伝奇物だった。科学的・合理的な捜査を主張する若き捜査官が、スリーピー・ホロウという村での連続殺人事件捜査のために派遣されて……という話で、結局科学的な謎解きはないまま、首のない騎士の呪い、それを利用した魔女の仕業ということで、「合理的」に説明されてしまう。 謎は解明され、ヒロインは救われ、こうして科学的・合理的な19世紀を迎えたのだ、ということなのだが、現代には起こりえない事件なのだろうか。そんなことはないと思うのだが。 いつも曇り空で、森にはいると枯れ木ばかりで、しょっちゅう雷鳴がとどろき、おどろおどろしさ満載。雰囲気は出ているが暗い場面が多いのでわかりにくかったのが残念。 首なし騎士が斧をヒュンヒュン振り回すのが、カンフー映画のようだった。 ヒロインを演じた女優は小柄で、子供なのかと思ったが、一人前の娘であるらしい。顔立ちは役にぴったりだった。DVDが出ている。
2004.07.04
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- 読書
- ミーちゃんと行く 磐座の旅 香川・…
- (2025-11-16 21:53:59)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-







