2004年02月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
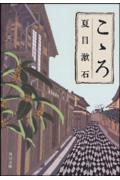
「こゝろ」 【夏目漱石】
こゝろ(著者:夏目漱石|出版社:角川文庫) 前に読んだのは二十年以上まで、大まかなところ以外はすっかり忘れていた。 「先生」と出会った時のことを語った文章ですでに「先生が亡《な》くなった今日になって」(p15)とあり、読者には、この「先生」はいずれ死ぬのだ、ということが提示されている。 小説の中での「現在」は、主人公が列車の中で手紙を読んでいる時であるようだ。 以前は、なんとなく、「私」は「K」を失うことをおそれて「お嬢さん」に求婚したのかと思っていたが、読み直すとそうではない。純粋に「お嬢さん」を自分のものにしたかったのだ。 内容もさることながら、言葉が興味深い。 その代表が「寂しい」。 「ちっとも寂《さむ》しくありません」「うちほど寂《さむ》しいものはありません」(p23) 「家《うち》はまた寂《さみ》しくなる」(p112) 「寂《さむ》しいからもっといてくれ」(p115) 「時とするとまた非常に寂《さみ》しがった」(p116) 「無人で寂《さむ》しくって困るから」(p158) 「無人で寂《さむ》しいから」(p169) 「一人で寂しくってしかたがなくなった結果」(p256) という具合で、「さみしい」「さむしい」はあっても「さびしい」はないようだ。最も、どこまで漱石自身がルビを振ったのかはわからないが。 「その言葉の耳ざわりからいうと」(p45)では「耳ざわり」が「耳障り」とは違う意味で使われている。 主人公は漱石と同じく、近代的自我を持ち、前近代的な自我の持ち主とは合わない。 「父の無知から出る田舎《いなか》臭いところに不快を感じだした。」(p94) 「私は田舎の客がきらいだった。(中略)私は子供の時から彼らの席に持するのを心苦しく感じていた。」(p99) 「学問をさせると人間がとかく理屈っぽくなっていけない」(p100)という父親の、主人公への不満は自我のありかたの違いによるものだ。 「私は兄に向かって、自分の使っているイゴイストという言葉の意味がよくわかるかと聞き返してやりたかった。」(p128)というところに、自分と同じように教育を受けた兄が、前近代的な自我の持ち主であることへのいらだちがあらわれている。 「ページさえ切ってない」(p173)は、洋本は袋とじになっていて、自分で切らなくてはならなかったということだろう。 「持ってきよう」(p191)は江戸弁か。 「自分の愛人とその母親」(p241)の「愛人」は現代とは意味が異なる。
2004.02.27
コメント(0)
-

「身体の文学史」 【養老孟司】
身体の文学史(著者:養老孟司|出版社:新潮社・新潮文庫) 解剖学者が、独自の観点から近現代の文学について語る。 養老孟司の文章は、新聞などで見る時評のようなものは分かりやすく面白いのだが、この本は何だか観念的なことが多くわかりにくかった。 例えば、「芥川は漢文を古典としない世代だ」というようなことはよく分かる。しかし、「若い芥川は、漱石の内省的な心理主義をさらに拡張し、身体そのものを、心理主義で規定される近代文学の領域に取り込んだのである」(p49)などという文章になると理解できない。 書名にあるように、文学における「身体」というもののありようを問題にすることが多いのだが、それがよくわからないのだ。 筆者は、自我は脳の機能でしかないと割り切っている。 例えば、「意識化された自我などというものは、たかだか千五百グラムの脳の、それもそのごく一部の機能に過ぎない。」(p182)と言い切っている。 その他、強く印象づけられた箇所。 『古事記』に「豊葦原水穂国」という表現があるが、これは、大陸の自然を知る人の表現に違いない。(p112) 「解剖していれば、私の口の中には人体の切れ端くらいは飛び込む。それを飲み込んだからどうかといえば、どうでもないのであって、無意識に人間を食ってしまう側から見れば、意識的に人間を食うことがなぜ興味の対象であるのか、そこが根本的に私には不明なのである。」(p151) 戦後、身体の型が失われ、若者が電車の中で足を広げて不格好に坐るのは、身体を持て余しているのである。(p180) また、明治になって発展・普及したものは、江戸時代にすでに需要があったものなのだ、という指摘も面白かった。
2004.02.26
コメント(0)
-

「物語の体操 みるみる小説が書ける6つのレッスン」 【大塚英志】
物語の体操 みるみる小説が書ける6つのレッスン(著者:大塚英志 |出版社:朝日新聞社) 副題の通り、小説を書けるようになるための具体的なレッスン。 専門学校で教えた体験などをもとに、非常に具体的に書かれている。 ただし、読めば書けるようになると言うものではない。「示された方法にしたがって本人がちゃんとヒンズースクワットなり素振りナリをやってくれなくては小説のための「体力」は身につかない」(p156) たとえば、「カードを使って〈おはなし〉のプロットを100個作」る(p41)というトレーニングをしなくてはならないのである。 専門学校では、途中で脱落する学生が多かったそうだ。 ところで、小説の書き方を教えるためには、そもそも小説とは何か、ということを理解していなくてはならない。この本は、「小説とは何か」「物語とは何か」ということを解明する本でもある。 途中で、著者は大学で民俗学を学んだと述べている。それで、「なるほどそうだったのか」と理解できた。 たとえば、昔話の研究をするなら、類話との比較検討などで、物語の構造に目を向ける必要が出てくる。もともと、物語の構造に目を向ける勉強をした人なのだ。 例えば、「彼ら(=梶原一輝の主人公たちは)は物語の構造に破れた主人公たちだったとさえ言えるでしょう」(p94)などという表現に、それが現れている。 インターネットの小説サイトでの経験に符合する点も多かった。 例えば、まんがを描く才能が五つぐらいに分裂してきている、という話で、その中の一つに、「物語世界の設定やバックグラウンドのディテールを構築し、埋めていく技術」というのを挙げている。(p123) ほんとうにこういう人がいるのだ。「設定」ばかりを細かく作り上げ、肝心の物語作りまでいかない。 また、「創作する読者、創作する受け手」の大量発生を予感していたというようなことも書いている。(p209) まさにそうなのだ。数多くの小説サイトがあることからもわかるように、世の中、「読みたい人」より、「書きたい人」の方が多いのではないかとおもうくらいだ。 同じページに「ある文芸誌が休刊した時、その雑誌の最後の新人賞の応募作がその雑誌の実売数を上回っていて」という噂が紹介されているが、おそらく事実だろう。 二年前に、ある出版社の人と話した時に、「読みたい人より書きたい人の方が多いのでは」と言ったら、その通りだと言われたことがある。「本を出したい」という人が多いだけでなく、出せば売れるものだと思いこんでいるそうだ。 自分は人の書いたものは読まないし買わないが、自分の書いたものは読んで欲しい買って欲しいという人ばかりが増えているのでは、本が売れるわけはない。 と、小説の書き方から離れたことまで考えさせる本だった。
2004.02.25
コメント(0)
-
「白虎隊」 【中村彰彦】
白虎隊(著者:中村彰彦|出版社:文春新書) 著者は史家ではなく作家である 栃木県生まれで、会津の人ではないが、『筆者は会津藩を「賊軍」とは考えない」(p11)と、その姿勢を明らかにしている。 書き方は、資料を綿密に調べ、諸説の誤りを指摘して実像を明らかにしながらも、想像力を駆使して合理的な解釈を求めており、なぜ篠田儀三郎が指揮を執ることになったか、どのようにして飯盛山にたどり着いたか、どのように自刃したのか、説得力がある。 士中二番隊が携えていたのは旧式銃ではなく新式のものであったことを始めて知った。 落城後の白虎隊士、会津藩士についても筆は及んでいる。 佐川官兵衛は西南戦争で戦死したのだった。 以下、印象に残ったこと。 飯沼貞吉がのどを突いた時のことを回想した文章。(p157) p158からの「十九士の横顔」で、自刃した隊士の生い立ちなどが語らえれている。母親の名は、「たみ子」「さだ子」「すぐ子」と「子」の付くものが多い。 籠城中、薩摩軍にとらえられた隊士がいたが、大切に扱われ、放免してくれた、という話(p186)は、薩摩にも武士道があったことを物語る。 容保は、落城の際に書いた文章で、会津藩領民をさして「国民」と書いている。(p196)当時はまだ「国」とは、それぞれの藩のことだった。 自刃から七ヶ月、遺体の埋葬が許されていなかった。新政府軍の非道の象徴だ。(p217) 最後は、その後、白虎隊がどのように知られていき、受容されたかが語られるのだが、その直前の「秘められた真実」(p224)がもっとも印象に残った。 自刃した隊士の遺体から刀や金品を盗んだ地元民がいた、というのだ。 飯沼貞吉もその被害にあったらしい。 しかし、飯盛山の盗賊については、これまでの資料はいっさい触れていないという。(p232) その理由を「地元民に金品を漁られたとは信じたくない。そんな哀切な思い」にあると想像しているが、おそらく、著者も、会津出身だったら触れないのではないだろうか。
2004.02.20
コメント(0)
-
「江戸の見世物」 【川添裕】
江戸の見世物(著者: 川添裕|出版社:岩波新書) 籠細工からラクダ、象、軽業、生き人形と、見世物あれこれ。 寺社と結びついて持ちつ持たれつであったとは初めて知った。 最近読んだ「大江戸奇術考」は、奇術のテクニック、つまり、演じる側に焦点を当てていたが、これは、見世物としてどうなのか、という点が重視されている。 また、これも最近読んだ「安政大地震」では、とても見世物どころではなかったように思われるのだが、この本を読むと、軽業の見世物が大好評なのだ。しかも、天才軽業師は、明治維新を待たずして渡米し、興行を打って、アメリカで客死している。 何もかも知らないことばかり。 先行研究に頼らず、一から資料を調べ直しており、信頼が置ける本である。
2004.02.18
コメント(0)
-
「元禄御畳奉行の日記(尾張藩士の見た浮世)」 【神坂次郎】
元禄御畳奉行の日記(著者:神坂次郎|出版社:中公新書) この本が出た時、ずいぶん話題になって興味は抱いていたのだが、なぜか手に取らずにいた。 すべてが現実であるだけに、理念化された江戸時代ではない、生の江戸時代を感じることができる。 明るい筆致で紹介してはいるのだが、人の死ぬ話が多い。 切腹する勇気もなく食あたりで死ぬ方法をとる、滑稽にも見える「ところてん自殺」もあれば、心中がはやったり、貧窮のための自殺が続いたり。 男女の仲をめぐる騒動も多い。 元禄十六年からの年半だけで、京、大坂だけで九百余人の心中事件があった(p131)とは驚きだ。 元禄といえば忠臣蔵だが、日記には素っ気ない記述しかない。まあ、そんなものだろう。日本中が沸き立った事件だったとは思えない。 討ち入りの時は、江戸では大評判だったとは思うが。 さて、日記を残した朝日文左衛門。四十五歳で没するのだが、原因は酒。とにかく酒を飲まずにはいられない。しかも、今風に言うなら勤務中でも酒を飲む。まさに酒毒にあたっての死である。 この本は、日記本体である『鸚鵡籠中記』から、著者がおもしろそうなところだけ抜き出し、解説を加えているわけだが、とにかく朝日文左衛門というのは記録魔だったことがわかる。 これを読んで思い起こすのは「藤岡屋日記」だ。もっとも、藤岡屋の場合は、自分には直接関わりのないことを記録しているのだが。 とにかく、記録する、ということは、彼一人の特質ではなく、日本文化の一つなのではないかと思う。 戦争中、アメリカ軍は、日本兵が残した手帳に、克明な日記が書き付けてあるのを解読し、日本軍の動きを知ったという。 この読書録自体も似たようなものだ。 インターネットでも日記サイトは多い。己の行動を書き記そうとする本能のようなものがあるのだろう。
2004.02.17
コメント(0)
-

「大森界隈職人往来」 【小関智弘】
大森界隈職人往来(著者:小関智弘|出版社:岩波現代文庫) 大田区で生まれ育ち、ずっと旋盤の仕事をしてきた男の回想録。 町工場というものを通して、町のあり方まで目を向けている。「さすが職人」と感心するような心の持ち方をしている。 文章は非常にうまい。凝った文章もある。文芸同人誌に参加していたくらいだから、文章を読むことも書くことも好きなのだろう。 もっとも感心した文章。「町工場を渡り歩く職人は、ゆるやかな渦を巻いて流れたが、どこかの杭にひっかかっては新しい技能を身につけ、工場世界についての見聞をひろめて、また杭を離れた。」
2004.02.14
コメント(0)
-
「江戸怪談集(下)」 【高田衛】
江戸怪談集(下)(著者:高田衛|出版社:岩波文庫) 『諸国百物語』『平仮名本・因果物語』『新御伽婢子』『百物語評判』の四種。 『諸国百物語』の「江州、白井介三郎が娘の執心、大蛇になりし事」(p52)は、女が蛇に化生し、人間に化けて男と結ばれ子供を産むという、異類婚姻譚と、女が執念によって蛇になると言う白蛇伝の混合。 「賭づくしをして、我が子の首を切られし事」(p80)は、小泉八雲の怪談に似たようなのがあった。 『百物語評判』は、世の怪異を論理的に解釈しようとしているのが興味深い。 「是れたまたま其の石の、人がたちに似たるを以て、名付けたるべし。疑ひ給ふべからず」(p338)と怪異を退けているものもあるが、「垢ねぶりも、其の塵垢《じんこう》の気の、つもれる所より、化生し出づる物なる故に、垢をねぶりて身命をつぐ。必然の理たるべし」(p345)と、怪異の発生するのが当然と解釈しているのもある。 雪の結晶が六角柱であることは幕末になってから知られたのかと思っていたが、『百物語評判』に「雪は六出《ろくすい》と云ひて、かならず六かど侍る。(略)雪は純陰の物なれば、老陰の数、六なる故、かならず六出《むつかど》あり」(p362)とあった。 解説によれば、この本は、貞享三年(一六八六)開板だそうだ。 こんなに古くから知られていたとは新知識。
2004.02.12
コメント(0)
-
「記憶を消す子供たち」 【レノア・テア】
記憶を消す子供たち(著者:レノア・テア。吉田利子・訳|草思社) 恐ろしい本である。ほとんど山岸涼子の世界。 記憶の不思議、トラウマの影響に驚くが、アメリカの家庭は一体どうなっているのか、恐ろしいほど。アメリカでは、子供が普通に幸福に育つなどということはめったにないことになっているのではないかと思われるほどだ。 また、恐ろしいのは、自分もまた、子供への虐待を続けた父親と同じ人間なのだから、同じことをする可能性が自分にもある、ということだ。 悪い奴が読んだら、子供は記憶を消すのだから、やっても大丈夫だ、と考えてしまうのではないか、というのも不安だ。
2004.02.06
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










