2004年11月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

プロ教師の見た教育改革 【諏訪哲二】
プロ教師の見た教育改革(著者:諏訪哲二|出版社:ちくま新書) 教育改革に対する評価というよりは、そもそも学校とは何か、学校を生み出した「近代」とは何かを論じる部分が長い。 なぜなら、学校の存在の前提を正しく認識せずに学校教育を語ることができないからだ。そして、前提を誤解したまま教育を語る人が非常に多いからだ。 読んでいると、名句がちりばめられた本のように思えてしまう。「理屈さえ立てれば現実がよくなるという近代的信仰にはまず眉に唾をつけておこう。」(p12)「子どもは見ずkら学ぶものであるとおとなが語るとき、子どもが学ばない、学ぼうとしない可能性を一切考えていない。」(p24)「極端に言うと、文科省、教育委員会、管理職たちのあたまにあるのは、授業のことだけである。」(p70)「高校は、途中で罷めたがる生徒を慰留し、手とり足とりして卒業させようとする。」(p76)「ジャパンローカルの知的主体たちは、普遍や真理は必ずどこかに在り、それもかなり手近に在るように錯覚している気配がある」(p164) この本を読むと、産経新聞も朝日新聞も同じ勘違いを土台としてものを言っているにすぎないように思える。自分は「近代」の体現者であり、「普遍や真理」を自分はみつけたと思いこんでいるのだ。 人間を右か左かに分類してしまわないと気が済まない人は、こういう本を読んだらどう思うのだろうか。 誤植発見。「家そこでは庭や地域の教育力なるものは」(p194)は、「そこでは家庭や……」の誤植と思われる。楽天フリマから現金5万円プレゼント
2004.11.30
コメント(0)
-

「ゴジラ対メカゴジラ」 【監督・福田純。1974年】
ちょうど30年前の映画だ。 いきなりアンギラスが登場して、あれあれと思っていると、アンギラスはゴジラに見せかけたメカゴジラの強さを見せるためだけの出演。ゴジラがアンギラスの敵を討つことを決意する場面が欲しかった。 今回は沖縄が決戦の場ということで、オープニングの音楽は沖縄民謡風。 時代劇でよく見る睦五郎がブラックホール第3惑星から来た侵略者のボス。宇宙人なのに葉巻を吸ったりブランデーらしきものを飲んだり。その手下の一人が草野大悟。 さらにお約束の平田昭彦。 そして、インターポールの岸田森。岸田森がかっこいい。 沖縄ご当地の伝説の怪獣「キングシーサー」がゴジラと一緒にメカゴジラと戦うのだが、これがあんまり強くない。「キング」ってなんで英語で名前が付いてるんだ。さらに、キングシーサーを目覚めさせる歌がまるっきりムード歌謡で沖縄の旋律じゃないのが残念。 「メカゴジラ」というアイディアは秀逸。楽天フリマから現金5万円プレゼント
2004.11.29
コメント(0)
-

三大怪獣 地球最大の決戦 【監督・本多猪四郎。1964年】
これもだいぶ前に見たはずなのだが、「金星人」と怪獣の戦いの場面以外はすっかり忘れていた。 王女が飛行機に乗って……という場面。確かにこれは「幻魔大戦」で、ルナ王女がベガと出会うシーンに似ている。 この映画に影響を受けたのだろう。 なお、この映画、最後の別れの場面は「ローマの休日」を思わせる。 それはさておき、話の中身だが、見終わってよく考えると変なのだ。 並大抵でない異常気象に見舞われている、ということだったのに、それはどこかへ行ってしまっている。異常気象が原因でキングギドラが来たわけでもないようだし。 怪獣が力を合わせてキングギドラを撃退し(といっても、キングギドラはゴジラに石をぶつけられて逃げ帰ったようにしか見えないのだが)、めでたしめでたしだが、南の島へ帰ったモスラはいいとして、のこったゴジラとラドンはどうなったのだ。日本中で大暴れかもしれないではないか。 もっとも印象に残るのは、モスラがゴジラとラドンの間に入って協力を求める場面。怪獣は怪獣同士で言葉が通じるのはいいとして、ゴジラとラドンは、「知ったことではない」だの「お前が先に謝れ」だの言い合ってなかなか協力しない。これは当時の国際情勢が反映されているのではないだろうか。 まだまだ「戦争」が身近な時代だったのだ、ということを思わせる。楽天フリマから現金5万円プレゼント
2004.11.28
コメント(4)
-
寒気《さむけ》
日曜日から寒気がする。 日曜日の朝、起きた時に寒気がして、熱を測ったら36.9度。11時まで横になっていたら36.6度になったのでプロレス観戦に。 月曜日、やはり熱は平熱ながら寒気がするので、午前中に近所の医者へ。扁桃腺が赤くなっていると言われ、注射をされ、薬をもらって出勤。 火曜日は勤労感謝の日で休み。少しは体調がよくなっていたので、外出もした。 水曜日。やはり寒気。熱はない。仕事に行くが、退勤間際には、「明日は出勤できないかも」と思う。 木曜日。予想的中。熱は平熱だが、寒気がしてならない。休暇を取って終日横になる。 金曜日。やや持ち直して出勤。どうにか仕事をこなす。 今日。やはり寒気。昨夜は風が強かったせいか熟睡できず、何度も目が覚める。今朝は6時前に目が覚めてしまう。 一度起きてから10頃横になり、少し寝る。午後も1時間ほど寝る。寒気は変わらず。 どうしたんだろう。
2004.11.27
コメント(0)
-
ZERO ONE……
「橋本、ゼロワンの活動停止を発表」ということだ。 ついに来たか。 旗揚げから3年9ヶ月。途中までは順風満帆のようだったのに。 大量離脱後、経営難に陥った全日を尻目に、テレビ東京の放送も始まり、外人選手の発掘にも成功し、話題作りはうまくいっていたようだったのに。 正直なところ、橋本に三冠を持って行かれたころは、全日はZERO ONEに吸収されてしまうのではないかと心配したほどだった。 おそらく、話題の華やかさとは違って、経営は常に不安定だったのではないかと思う。 週刊「ゴング」に、会社側の中村氏のインタビューが載ったとき、レスラーの感覚と経営者の感覚は違う、橋本は経営者としての感覚が甘い、というようなことを言っていた。 橋本はこれから肩の手術をするという。成功を祈る。 破壊王として復活し、負債を清算し、星川の回復を見届けて欲しい。 「古巣新日本は、橋本の復帰を大歓迎!」と言うが、自分だけ安定した道を選ぶことはないだろう。新日に復帰するとしたら、金を稼いでZERO ONEの負債返済のためだろう。 「武藤驚き「言葉が見つからない」」という記事もある。一時はZERO ONEと全日の交流は盛んだったのに、最近はさっぱりだった。これも、橋本が経営から手を引いたためだったのだろうか。最強タッグに、大谷・大森組などが参戦してもおもしろかったのに。 間違っても分裂して小さい団体に分かれたりしないように。ただでさえ団体乱立でかえって地盤低下を起こしているのだから。 また、団体存続のための無理は禁物。 第2の荒井社長(FMWの)を出すようなことになってはいけない。
2004.11.26
コメント(0)
-

「少年時代」 【監督・篠田正浩。1990年】
小説「長い道」を藤子不二雄A(安孫子素雄)がマンガ化し、その二つを原作として映画化されたもの。製作・企画は安孫子素雄。 東京の子どもが一年間富山に疎開したときの思い出。 学力も腕力も群を抜く級長や、そのいいなりの子ども、敵対する子ども。子どもの身勝手さ、残酷さが描かれているのが珍しい。「子どもは純真だ」「地方の人は純朴だ」などという現実を無視した思いこみで作られた話ではない。 この映画の優れている点は、常に主人公の子どもの視点から世界がとらえられていること。 子どもには、大人の理解を超えた子どもの世界があるのだ。その世界の物語であり、大人が問題解決に乗り出したりはしない。今の「学園ドラマ」が、決して生徒を主人公にせず、教師を主人公にするのとは大違い。 お約束として、富山の美しい自然も登場する。風景が美しいほど、子どもの残酷さが際だつ。 もう一つ感心するのは、子役が皆、達者なこと。 繊細な主人公、屈折した精神を持つ級長、陰湿な同級生、腕力だけの同級生。どれも人を得ている。 これは、戦争中という特殊な時代にのみ生まれる物語ではない。「子どもの世界」という点で、時代を超えて普遍性を持つ物語である。だからこそ、現代の人間が見ても理解できるのだ。 これを見て、かつてNHKで放送された少年ドラマシリーズの「ユタとふしぎな仲間たち」を思い出したのは私だけではあるまい。 また、宮沢賢治の「風の又三郎」にも通じるものを感じる。 この話独特のものがあるとすれば、それは、子どもたちが「物語」に飢えている、という点だ。 読書好きで話もうまい主人公に連続語り物(たとえば講談や浪曲のようなもの)として語らせ、それを聞いて楽しむ。無理にでも話させようとする。これが戦争中の実態だったとは思わないが、妙に現実味があった。
2004.11.25
コメント(0)
-
二つの忠臣蔵
今季、二種類の忠臣蔵が放送されている。 一つはテレビ朝日の「忠臣蔵」、もう一つはNHKの「最後の忠臣蔵」。どちらも見ているが、どちらも不満を感じる。力の入れ具合に志は感じるのだが。 まず、「忠臣蔵」。 オーソドックスなようでいて、微妙にずれている。 寺坂吉衛門が吉田忠左衛門ではなく大石家に仕えている、というのが変。また、元服前から「主税」と呼ばれているのも誤り。(元服前の松之丞)。 出演者が豪華ではあるのだが、若い人が少ない。わかい時代劇役者を育てるのによい機会なのだから、未熟であっても、将来のために若い人を起用して欲しかった。 「最後の忠臣蔵」 四十七士の中でもっとも興味のる寺坂吉衛門が主人公ということで期待して見始めた。 ところが、忠臣蔵が中心ではなく、寺坂の個人的な問題が中心になってしまっている。忠臣蔵において寺坂がどのような役割を果たしているのか、ということが重要なわけで、もちろんそれを描きもしているのだが、それが些末なことに見えてしまう。 なぜ、不満を感じるのか。それは、見ている自分の中に「忠臣蔵はこうだ」「寺坂吉衛門はこうだ」というイメージがあり、それとずれているからなのだ。 こちらの一方的な思いこみにあわないからと入って不満を言われたのでは、番組を作っている方としては迷惑だろうが、視聴者というのは勝手なものなのだ。
2004.11.24
コメント(0)
-
「新選組!」 第46回「東へ」 (11月21日放送)
残すところ、今回を入れてあと4回。 幕府側は、慶喜の逃亡で市中を失い、敗北が決定的に。 京で隊士たちと関わりを持った人たちが総登場。 寺田屋の女将に助けられ、捨助は晴れて仲間入り。 八木ひでは子供ができたというわけではなかったようだ。 原田左之助が、清に渡って盗賊に、と言ったのは、明治になってから左之助は大陸で馬賊になっているという噂が流れたのを生かしている。なるほど、自分で言っていたということにしてあれば話が自然になる。 斉藤一が、土方に「新選組はあんたが作った」と言う場面があったが、斉藤が土方には心服していることがこのせりふで表されている。 また、土方が近藤と沖田の前で近藤周斎(というより田中邦衛)のまねをしてみせるのは、土方はこの二人にだけ心を開いているということを示している。 かつて対立していた佐々木と、仲間だった山崎の死が、これからの運命を物語る。 見せ場の一つは、勝海舟が慶喜を罵倒するところ。野田秀樹がいかにもそれらしい。 しかし、勝海舟って、その昔、同じ大河ドラマで渡哲也(途中で病気降板して松方弘樹)だったんだよなあ。同じ人間とは思えない。 谷周平はまだ一緒にいるような描き方だったけれど、どう処理するんだろう。
2004.11.23
コメント(0)
-
世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦
後楽園ホールに行ってきた。 自分の体調が悪くて集中できない部分もあったのだが、おおむねいい興行だった。 客は満員。 livedoorに記事3本。「健介一家対RO&D戦が5対5に」 試合開始前のRO&DタイムでTAKAが要求していたものが、メインの試合のあとで決定。自然なストーリー作りに努力しているのが感じられる。「波乱!武藤がMUTAに負けた…」 スティール、MUTAに武藤と西村というくせ者揃いの試合。MUTAが毒霧からシャイニング・ウィザードで武藤から3カウントを取ってしまった。客席は不満。「天山全日乱入、夜は逆に乱入された」 天山の登場は全く迷惑。 試合開始前に来て「川田さんの試合を見せてもらいます」というくらいの挨拶をすればいいのに。 小島も乱入なんかしちゃだめよ。 詳しい観戦記を作成中。 ここからどうぞ。(観戦記用に持ち込んだノートパソコンのバッテリーが途中で切れてしまって、最後の3試合が詳しくないのが心残り)
2004.11.22
コメント(0)
-

「怪獣総進撃」 【監督・本多猪四郎。1968年】
前にも見たことがあるのだが、ほとんど覚えていなかった。 時は20世紀末、怪獣たちは小笠原諸島に作られた「怪獣ランド」にあつめられ、人間の管理のもと、平和に暮らしていた。ところが、キラアク星人が、その怪獣ランドを破壊し、怪獣たちに各国の都市を襲わせる。 小笠原、月、富士山麓を舞台に繰り広げられる、キラアク星人と地球人との戦い、そして、宇宙人に操られる怪獣たちの運命は。 最後は、怪獣たちが人間の指揮下に戻り、キラアク星人の野望を砕く。 ゴジラ、ミニラ、ラドン、モスラの幼虫、アンギラス、バラン、バラゴン、ゴロザウルス、マンダ、クモンガと怪獣オールスター出演に、敵役としてキングギドラが花を添える。 さしものキングギドラも地球の怪獣によってたかってやられては勝てないのであった。 これで解決かと思うとまた困難な情況が生まれ、と、話がよくできていて見せ場たっぷり。 富士山麓での怪獣たちの戦いをアナウンサーが実況中継しているのがいい。 音楽は伊福部昭。威勢のいい曲で話にぴったり。 また、昔の方がいいな、と思ったのが、軍隊のメカ。 最近の「ガメラ」などとは違う。昔は、ミサイル車や戦車などミニチュアを作っていたものだ。それがまた特撮好きの心をくすぐっていた。 ところが最近は自衛隊が協力してくれるものだから、本物が出てきてしまう。 そりゃあ、本物の方が迫力はあるが、やはりミニチュアがカチャカチャ動いてくれた方が、特撮映画らしくていい。 検索したら、フリー百科事典「ウィキペディア」に「怪獣総進撃」という項目があって詳しく解説されていた。 好きで詳しい人というのはいるものだ。
2004.11.21
コメント(0)
-

「ゴジラVSヘドラ」 【監督・坂野義光。1971年】
いやあ、ビックリ。まさに怪作、奇作、傑作。 オープニングに怪獣が出たかと思うと、タイトルバックは、「♪水銀 コバルト カドミウム」と、小林旭でも歌わないようなストレートな歌詞の主題歌を、若い女性(麻里圭子という人のようだ)が、赤を基調としたサイケデリックなバックの前で歌い、汚れきった海が映る。 公害問題が大きくなり、ヘドロが問題になっていたのでヘドロを吸収して巨大化したヘドラが登場したわけで、「かえせ 緑を青空を」と歌うのも無理はない。変化に富んだ凝った曲で労働歌のようなメロディの部分もある。 どういうわけか現れたヘドラは、どういうわけか現れたゴジラにやっつけられてしまう、といえば簡単のようだが、随所に遊びがある。 アニメーションで女性が二人すれ違うと、その顔が重なった部分が黒くなり、その形が、ヘドラによる被害地域の図に重なる、という具合。 人間がやっとの事で工夫した装置は役に立たず、なぜかその使い道を理解したゴジラが利用してくれる。 おまけにゴジラは、自分の吐く息で空を飛ぶ! 話には聞いていたがこうやって飛んだのか! ヘドラを倒してめでたしめでたしかと思うと、最後に別なヘドラの存在を示唆して終わる。 いやあ、ぶっとんだ映画だ。 監督は、これが初監督作品で、次に「ノストラダムスの大予言」を撮っただけ。どういう人なんだ。 柴俊夫が柴本俊夫という芸名で出ていた。
2004.11.20
コメント(0)
-
新選組実録 【相川司・菊池明】
新選組実録(著者:相川司/菊地明|出版社:ちくま新書) 浪士隊から箱館戦争まで、あしかけ7年の新選組の動きを描く。 新選組の歴史だけでなく幕末の歴史も説明しなくてはならないので忙しい。 まず「なるほど」と思ったのは、新選組はもともとは攘夷のために働こう等していたのであって、市中見回りは本意ではなかったこと。池田屋事件などによって、否応なくそういう仕事が中心になってしまっていくのだ。 土方たちは京に上ったら上ったきりではなく、隊士募集のために江戸に戻ったりもしていたのだった。 各種の手記・聞き書きなどを駆使しているが、資料による食い違いなどもあり、たとえば、離脱は許されたのか許されなかったのかもよくわからない。 読んでいておもしろかったのは、京都時代よりもむしろ、甲州攻略失敗後。 近藤勇が斬首となったのは、土佐藩が強硬に死刑を求めたからで、その理由は坂本龍馬を新選組が暗殺したことにあった。その誤解がなければ生きながらえた可能性も高かったようだ。 永倉たちは袂を分かち別行動になったのに、土方が会津に行った頃には、永倉たちもいたらしい。 土方は途中から仙台に向かったが、会津に残った斉藤一とは顔を合わせたのだろうか。 終盤は主に土方のこと。 榎本武揚と一緒に箱館へ向かい、奮戦。 p218に引かれる「函館戦記」によれば、土方は「必破に終わる」と知りながら戦っている。生き延びてはあの世で近藤に合わせる顔がないということもあるだろうが、土方として大義を貫いたわけだ。「益」よりも「義」なのである。 島田魁のように、最後まで行動をともした人たちは、土方の人柄をしたってのことらしい。 文章は平易だが、「帰宅途中の天神橋で駕籠を襲って内山を殺害したとされる」(p39)という文章は不満。歴史研究書であるのだから、どこのだれによってそう「され」ているのか明記してほしい。
2004.11.19
コメント(0)
-
一緒に・・・ 【MAX】
思い立って床屋へ行ったら、有線で音楽が流れていた。 そのうちに流れてきたのがこの曲。ああ、冬が近づいたからなあ。 この曲で紅白も出たんだっけ。 カップリング曲の「POWDER SHADOW」も佳作。 MAXが気になるようになったのは、まだスーパーモンキーズだった時代。「夜もヒッパレ」が好きでよく見ていた。 レギュラーで出いてた彼女たちは、安室奈美恵のバックダンサーのような扱いだった。 後ろの席にいることが多く、時々しか画面に映らなかったがいつもニコニコしていた。 その後、MAXとして少しずつ売れ出し、ほかの歌番組でも見るようになった。感心したのは、とにかくいつも笑顔でいること。ほかの歌手が歌っているときも、ノリのいいところを見せて、場を盛り上げようとしていた。 画面の隅でもとにかく笑顔というのは三波春夫以来だった。 メンバーで一番好きだったのはミーナ。 ただし、一番きれいな顔をしているのはレイナだと思う。 リナは話がわからないところがあって、一方ナナはしっかりしたところがあった。 「うたばん」で夢判断をしたとき、ナナは、グループでも一人でも仕事ができるようにならなくてはならない、と言っていたのが印象に残っている。 そして。周知の通り、ミーナは結婚、出産。 休養に入ってしばらくは、3人がソロ写真集を出していたりしたが、アキという新メンバーを加えてまた4人で活動するようになった。 別にアキに対して含むところは何もない。途中から入ってよくがんばっていると思う。 しかし、MAXとしてはミーナの復帰を待っていてほしかった。子持ちアイドルとして話題にもなったろうし、女性ファンの応援も得られただろう。 アキをそのまま残し、5人グループになってもよかったのに。 志村けんの番組に出たときに、「メンバー変わったの?」と聞かれて「はい、変わりました」と答えていたときにはがっかりした。 ミーナは二人目を妊娠中だという話もある。 彼女が幸福ならそれでもいいが、惜しい、という気持ちもある。
2004.11.18
コメント(0)
-
めだか 【フジテレビ】
公式サイト 第1回からずっと見ている。 このドラマで一番いいのはスピッツの主題歌だ。 ドラマの内容は、というと、定時制高校が舞台というのは、めずらしくはあるが、結局教師が主人公になってしまっているのが残念。 学園ドラマって、生徒が主人公にならなくちゃいけないんじゃないの? 昔はそうだったと思ううんだけど。 第6回で、生徒が昔の同級生に脅されて、という話の時、結局、事件そのものは解決しないで終わってしまったのは不思議だった。 主人公を演じるミムラという人のことはまったく知らなかった。ミムラとカタカナで書かれるとムーミンを思い出すが関係ないのだろうか。 「新選組!」の原田左之助こと山本太郎や、これも「新選組!」に出ている小日向文世など、出演者は多彩な顔ぶれ。 中でも気になるのが泉谷しげる。フォーク少年だった人間としては見ずにはいられない。泉谷しげるにあわせて作ったような役を演じている。(フォーク少年だったからスピッツの歌に引かれるのか?) 公式サイトをみたら、浅野ゆう子は灰谷健次郎に習ったことがあるそうだ。へえ~。
2004.11.17
コメント(2)
-
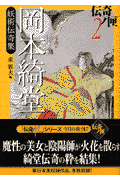
岡本綺堂妖術伝奇集
岡本綺堂妖術伝奇集(著者:岡本綺堂/東雅夫|出版社:学研M文庫) 妖女の登場する「玉藻の前」「小坂部姫」「クラリモンド(翻訳)」 いずれも独特の美意識によって書かれたもので、単なる正と邪、光と闇の戦いという話ではない。 世を乱し人を滅ぼそうとするものの美しさが描かれている。 「小坂部姫」では「天守閣」ではなく「天主閣」と表記している。 キリスト教の影響によって、教会をまねて造られたという説を最近読んだが、その名残か。 「まだまだ不幸が仕足らいで」(p415)は「不孝」の誤植。 戯曲「平家蟹」「蟹萬寺縁起」「人狼」「青蛙神」 いずれも怪異譚。歌舞伎と同じで、特に謎が解き明かされる、という訳ではなく、不思議な話は不思議なまま終わる。「青蛙神」は「猿の手」の本案だが、それとわからないほど独自性を持っている。 短編小説「青蛙神」「蟹」「五色蟹」「木曽の旅人」 いずれも読んだことのある話だが、文章に読ませる力があるので、新鮮な気持ちで読める。 随筆「江戸の化物」「高座の牡丹燈籠」「舞台の牡丹燈籠」「小坂部伝説」「怪談劇」「温泉雑記」 怪談の考証や、怪談にまつわる思い出話。知識の広範さを知ることができる。 「舞台の牡丹燈籠」の終わりに「巴里《パリ》にはバジン・テアトル(芝居風呂)などと洒落た名前を付けた湯屋もある。」とあるが、パリにも銭湯があるのだろうか? 関連資料「木曽の怪物」「蓮華温泉の怪話」 小説「木曽の旅人」の原話。こういうものを資料として採録してあるのはありがたい。(「玉藻の前」だけの感想はここ)
2004.11.16
コメント(0)
-
ミゼット・プロレス
昨日の「たったひとつのたからもの」に関連して、障害者の社会的認知という面から。 私は一度だけミゼット・プロレスを生で見たことがある。全女の地方での興行で。東京ではやらないらしい。大田区体育館に見に行ったとき、ミゼット・レスラーは、スタッフとして働いていて、試合はなかった。 もう8年ぐらい前のことなので記憶はおぼろげだ。 基本的にはお笑いなのだが、掌打や膝十字など、流行の技も取り入れていて感心した。 試合後は、顔見知りらしい若い客に、後かたづけのアルバイトを依頼したりしていた。 もう30年ぐらい前のことだろうか。 一時期、テレビにミゼット・レスラーが出ていたことがある。お笑い番組で、いじられる役で笑いを取っていた。 正直なことを言うと、障害を笑うようでいやな気持ちがした。そう思ったのは私だけでなく、世の中からそういう声が挙がり、やがて出なくなってしまった。 大人になり、プロレスに興味を持って、関連する本や雑誌をいろいろ読んでいるうちに、ミゼット・レスラーのインタビュー記事に出会った。衝撃だった。 彼らは、テレビ出演に大きな期待を寄せていたのだ。自分たちが社会的に認知される機会だと思って、喜んで笑いを取っていたのだ。 それなのに、「良心的」な声がその機会をつぶしてしまった。私も、実際に投書したりしたわけではないが、同じことを思っていたのだから、機会をつぶした側の人間だ。 テレビから消えたからと言って障害がなくなるわけではない。むしろテレビは積極的に登場させて、ふつうの存在だという雰囲気を作り出して行くべきなのだ。 ことさら障害者を取り上げる必要はない。自然に画面に登場させてほしい。 ミゼット・プロレスのことを思うと、ジャイアント馬場さんのことが思い出される。人並みはずれて体が大きい、ということは、プロレスラーとしては大きな武器だった。 しかし、子供の頃から、体が大きいということでの苦労もあったはずだ。中学で、履けるスパイクがないからと野球をあきらめていた時期もある。好奇の目で見られることもあったろう。 雑誌のインタビューで、取材者と並んで立って、体の大きさを強調するような写真を撮りたいといわれると、断っていた。 馬場さんには馬場さんにしかわからない思いがあったことだろう。
2004.11.15
コメント(0)
-
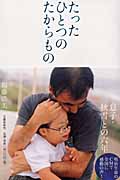
たったひとつのたからもの
10月26日に放送されたものだが、やっと見た。 ダウン症の我が子と生きた6年間。実話を元にしたドラマ。 もちろん、ドラマだから、現実よりはきれいに描いてあるのだろう。ドラマよりもっともっと困難なことがあったのではないだろうか。 ダウン症の子をほんとうにダウン症の子が演じている。 1歳、3歳、6歳と三人の子が出演している。この子たちがすごいのだ。演技をするという意識はおそらくないのだろう。リアルな迫力がある。 ダウン症の子どもたちの施設も登場し、たくさんのダウン症の子どもたちが画面に映る。成長し、働いている人も登場する。 視聴率はよかったそうだ。こういうドラマが、社会的認知のきっかけになればいい。世の中にはダウン症というものが存在し、決して珍しいものではない、ということだけでも知られるといい。 メディアから隠して存在しないことにしてしまうのではなく、その存在を当たり前のこととして受け入れていくようになってほしい。 テレビ番組の公式サイトもある。
2004.11.14
コメント(0)
-
想い出が多すぎて 【高木麻早】
日刊ゲンダイの「あの人は今こうしている」で高木麻早が取り上げられていた。懐かしい。 ポプコン出身でモデルもしているということだった。 代表曲は「ひとりぼっちの部屋」だが、「想い出が多すぎて」もヒット。 あのころは、「フォーク」に分類されていたが、今にして思えば無理がある。 そもそもポプコン出身者はフォークという意識はなかったのではないだろうか。 自分で曲を作って歌う、ということをフォーク歌手以外はほとんどしていなかったので、フォークと呼ばれただけのことだろう。 ユーミンも最初はフォークになっていたが、途中から「ニュー・ミュージック」になった。ジャンルわけしようとしても既成のジャンルにあてはまらないので、彼女のために作られたジャンルだったといってもいい。 今はもう無理にジャンルわけをすることはない。 自分で曲を作っていようがいまいが「Jポップ」だ。「演歌」というジャンルがあるにはあるが、さほど境目は感じられない。 もちろん、フォーク歌手、演歌歌手という存在がなくなったわけではない。 そういえば、「シンガーソングライター」という言葉もあったが、今では死語のようだ。 検索したら、高木麻早の公式サイトがあった。現在の写真もある。そうそう、こういう目の人だった。
2004.11.13
コメント(2)
-
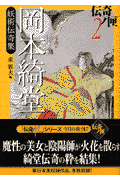
玉藻の前 【岡本綺堂】
岡本綺堂妖術伝奇集(著者:岡本綺堂/東雅夫|出版社:学研M文庫)所収。 岡本綺堂の伝奇小説。 かつて天竺や唐土で世を乱す元となった魔女の魂が少女に乗り移り、少女はやがて魔性の女となる。 その一方で、少女の幼なじみの少年は陰陽師の弟子となり、魔物を退散させようとする側に立つ。 しかし、妖術使い通しの戦いが描かれているわけではなく、幼なじみを恋しく思う男女の葛藤や、世を乱そうとする怨念の暗黒美が中心。独特の美意識によって書かれた小説なのだ。 光と闇の戦いなどという図式化された話ではない。 こういうものを出版しておこうという志はありがたい。 もとは歴史的仮名遣いのもので、それを現代仮名遣いになおしてある。「御利益がなうでか」(p8)というところ「なうでか」ではなく「のうでか」にすべきだろう。「玉藻の前」だけの単行本もある
2004.11.12
コメント(0)
-
最強タッグ+新日の迷走?
まずは、「最強タッグ優勝だ!本間&諏訪間が新技」。新人としてデビューからまもなく、いきなり大抜擢の諏訪間と、やっとのことで初出場がかなった本間。まずは話題作りで貢献。 見ていて気持ちのいい戦いを期待する。 さて、川田VS天山の三冠戦になるはずだった新日の大阪ドーム大会。 「天山、3冠戦延期に激怒!何がハッスルだ」 そりゃそうだろう。プロレスファンの掲示板を見ると、天山だけじゃない、三冠戦めあてにチケットを買ったファンだって怒っている。昨日発売のプロレス雑誌にだって天山の意気込みが紹介されているし、新日の広告でも三冠戦になっている。 こういうの詐欺じゃないの? と、あれこれ迷走しているように見える新日だが、経営は安泰らしい。昨日の記事だが、「新日が中間決算報告、通期で黒字2億円!」だそうだ。あれだけ選手がいれば、ギャラだけでも大変な額だろうに。 ギャラといえば、「ドロ沼…猪木祭報酬支払いで新日が訴訟」によれば、猪木祭での、永田裕志、安田忠夫2選手のギャラ合計額は、3300万円だそうだ。
2004.11.11
コメント(2)
-

樋口一葉(内山理名)
11月1日に、新札発行を記念して放送されたのをやっと見た。 24年という短い人生のおわりの10年ほどを描いている。 話が忙しくなかったのはいいが、エピソードの羅列のようになってしまっていて、環境や内面の変化の掘り下げは足りないように見えた。 まあ、樋口一葉という人はどういう人だったのかを紹介するドラマとしてみればよくできている。 フィクションの部分はそう多くはあるまい。 一葉に関しては、伊藤整の「日本文壇史」で読んだことぐらいしか知らない。 半井桃水(永井大)との関係は、実際はもっとドロドロしたもので、半井はもっとダメダメな男だったのではないかと思う。 主演の内山理名は、最初は「一葉にしては健康的だな」と思っていたが、寝込んでからは、ちゃんとやつれて見えたのがさすがだった。実際にやつれる必要はない、やつれて見えればいいのだ。演技なのだから。 妹役の前田亜季も好演。 母親がかとうかずこ。すっかりおばさんになってしまったなあ。「なんとなく、クリスタル」(原作は今や長野県知事の田中康夫)でデビューした時は、柳宏の最先端を行く若い女という雰囲気だったのに。 調べてみたら、「ガメラ3 邪神《イリス》覚醒」で前田亜季の姉の前田愛の母親役をやっていた。(見たのだが印象に残っていなかった) 父親や役は野口五郎。こういう役をやる年になったのですなあ。 追記: 「ガメラ3」で、かとうかずこは前田愛の母親役ということだが、両親は昔、ガメラとギャオスの戦いで死んだことになっていて、しかもその回想シーンでは妹の前田亜季が娘を演じていた。つまり、その時も親子の役だったのだ。
2004.11.10
コメント(4)
-

南条範夫さん逝く
作家の南条範夫さんが亡くなった。 訃報記事 96歳だったそうだ。 南条範夫さんのさんの小説を初めて読んだのは、NHK大河ドラマの原作として書かれた「元禄太平記」だった。 私は放送中はちゃんと見ていなくて、年末に放送された総集編を見たらおもしろかったので、お年玉で原作を買ったのだった。ドラマとは違いがいろいろあって、仲でも男色の話には驚いた。 思えば、それが、忠臣蔵に興味を持ったきっかけだった。 ご冥福をお祈り申し上げます。 「元禄太平記」 原作の小説は残念ながら絶版状態。 ドラマは総集編などが出ている。
2004.11.09
コメント(0)
-
どうせ終わるなら…
NHKの「新選組!」 大政奉還からが長いのである。 昔は、大政奉還で終わったのだと思っていたが、実は駆け引きの一つでしかなかったのだ。 慶喜が徹底的に困った将軍なのがいい。 さて、新選組はというと、幕府がなくなった以上、頼るところがない。土方が金の分配をさせるのは、先行きの見込みがないのを見越してのことだろう。 これからあとは、出世や金のためではなく、誇りのために戦うのだ。徳川家のためであったり、仲間のためであったり、隊士それぞれに思いはあるだろうが、利益のために命をかけるのではない、というのが重要。 みんなが、そろいもそろって総司のところに朝鮮人参を持ってくるあたり、それぞれ死を覚悟していることを暗示している。 これからは隊士の死、離別の連続になるわけだ。 いやだなあ。新選組全盛のところで、みんなで宴会でどんちゃん騒ぎ、なんてところで終わって欲しかった。 宴会の最後に全員そろって記念撮影、なんて感じでさ。 シャッターの音がして画面が写真の映像になって終わるの。みんな笑顔で。 そうでなければ、一同が宴席に着いたところで、近藤勇がカメラ目線で、「新選組はここで終わります。今まで見てくれてありがとう。誠の旗はこれからも皆さんの心の中で生き続けます」とかなんとか言ってカメラが引くと、スタジオに作った座敷で、出演者もスタッフも入り交じって大宴会。 せっかくコメディタッチで作ってきたのに、主人公が死んで終わるのは残念。
2004.11.08
コメント(0)
-

七輪生活
一月ほど前、近所のホームセンターで七輪を買った。 金属製ではなく、土を焼いて作ったもの。 けっこうあちこちにある。 私が子どもの頃は、ただ円筒形のものだったが、口の開いているのもある。それを買った。 こういう形のもの。 子どもの頃、冬になると、七輪でジンギスカンを食べていた。(年に一度ぐらいだけど) 冬の寒い時に、庭先で食べた。 それを思い出し、ジンギスカン鍋を探したら、これはなかなか見つからなかった。ホームセンターを三軒回って見つけた。 さあ、庭でジンギスカンだと思ったら、こんどは羊の肉が見つからない。私が育った田舎町でも手に入ったものなのに。ジンギスカンがブームらしいというのに。 仕方がないので豚肉・牛肉で焼き肉。 小学三年の息子は喜んだ。 それいらい、毎週休日には庭で七輪を使った昼食。 羊の肉を見つけてジンギスカンも食べた。 網焼きもした。 今日は、ずっと前に買ったままのアウトドア用調理セットのフライパンで焼きうどん。テフロン加工のフライパンは焦げ付かないから便利。一度に調理できる量は少ないけれど、少しずつ食べては調理というのも楽しい。 焼きうどんの作り方は簡単。 肉と野菜をいためて麺を入れ、めんつゆをかけて麺をほぐして蓋をして待つ。 野菜は、モヤシ、玉ネギの薄切りのほかに、キノコがいい。シメジなんかが食べやすい。 めんつゆはかけすぎないように。味が足りないのは後で足せるけれど、しょっぱくなったのを薄めることはできないから。こういうのがあると便利。 昼間からビール(実は発泡酒)を飲みながら外で食べる。 子どもも喜ぶ。火を使う、ということが重要なのだ。 本能を刺戟するようだ。 通信販売でもあるだろうと思って探したら、「七輪」で検索すると、金属製のものがたくさんヒットする。 「木炭コンロ」で検索した方がいい。 一度、たこ焼きに挑戦してみたが、これは失敗。炭火は火力の調整が難しくて、焦げてしまった。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.11.07
コメント(2)
-
川田激怒+世界タッグ
「川田激怒!3冠戦への新日扱いに」 そりゃそうだ。ダブル・メインイベントというわけでもなく、3冠戦の後に2試合もある。 他団体から来てもらうんだから、礼を以て遇するということをしなくては。内部の戦いが重要だ、というのなら、わざわざ全日から来てもらうことはない。 「天山、夢の4冠狙う!」というのが、天山個人のわがままだというのなら、天山が全日に出てくればいいだけのこと。「川田のパートナーは長井」 長井がやっとアジアタッグを手に入れたということで、長井に正式決定。 夢の続きを見せてくれ。 長井よ、団体の枠を超えて呼び寄せた川田の期待に応えてくれ。
2004.11.06
コメント(2)
-

「ニッポン無責任時代」 【1962年。監督・古沢憲吾。主演・植木等】
「無責任」シリーズ第1作。 同じ頃、日活では無国籍アクションでドンパチやっているのだ。時代の勢いというものを感じさせる。 今見ると、植木等が主演で、クレージーキャッツが出ていること以外にほとんど見るべきところはない。 先日見た「エノケンの近藤勇」のような工夫も計算もない。ほとんどアイドル映画である。出演者のオーラだけで見せる映画だ。 こういう映画がヒットした、ということ自体が、その時代を象徴している。 峰岸徹(この時は峰健二)がお坊ちゃんの大学生役で出ていた。 DVDかビデオが出ているのではないかと思って調べたが、出ていないようだ。
2004.11.05
コメント(4)
-

「阿弥陀堂だより」 【2002年。監督:小泉堯史】
主演は寺尾聰と樋口可南子なのだが、94歳の老婆を演じる北林谷榮が圧巻。阿弥陀堂での一人暮らしが実にリアル。 1911年生まれだから、91歳の時の作品。尊敬に値する。 都会で暮らしていた、売れない作家の夫と、仕事に励んでいた女医の夫婦。 妻が疲れ果ててしまったこともあり、無医村となっていた夫の故郷の村に移り住む。 村人に受け入れられ、中でも、阿弥陀堂に一人住むおうめ婆さんの生き方に触れて穏やかな気持ちになっていく。 親しくなった女性の病気や、夫の恩師が末期ガンであることなど、いくらか出来事はあるが、しずかに時がすぎていく。 1年かけてじっくり撮影されたものらしく、美しい四季の風景が時の流れを示す。 「谷中村」というおそらくは架空の村が舞台。撮影は主に長野県飯山市で行われたそうだ。 非常に丁寧に、良心をもって作られた佳作である。 風景が記録してあるというだけでも価値は高い。 こういう映画を見て、自分も田舎で暮らしてみたい、自然の中で暮らしてみたいと思う人も多いだろう。 実際、田舎暮らしにあこがれて、退職後引っ越したりする人もいる。 しかし、現実にはこの映画に出てくるような土地で暮らすのは困難が多い。商店も少ないし、不便なことが多い。 移り住んだものの、地域社会のつきあいの煩わしさに耐えかねて都会に舞い戻る人もいる。 田舎暮らしに傷ついて、都会に出てきて癒される人も多いのでは。 私自身は地方育ちだが、シャワー付きトイレとブロードバンドのないところには住みたくない。 原作の小説がある。阿弥陀堂だより(著者:南木佳士|出版社:文春文庫) ダウンロード販売もある さらに関連本も。ラ・メモワール・ド“阿弥陀堂だより”
2004.11.04
コメント(0)
-
「女次郎長ワクワク道中」 【監督・斎藤寅次郎。1951年】
笠置シヅ子主演のミュージカル時代劇。 踊りは余り無いが、出演者が歌う歌う。 見合いさせられるのを嫌がって、家出した娘(笠置シヅ子)と若旦那(キドシンと配役に出ていた。木戸新太郎という人)が、実は見合いの相手だったとは知らずに出会い、意気投合。清水の次郎長を追う一派や旅の一座と出会ったり、と、お約束満載のてんやわんやの道中をくりひろげる。 で、笠置シヅ子なのだが、娘役とはいっても、1914年生まれなので、この年37歳! とてもそうは見えない。 垂れ目で庶民的で、終わりの方だけちょっと見た妻は「サザエさんにそっくり」と言っていた。 笑いを取るのは横山エンタツと伴淳三郎(配役では伴淳となっていた)。 50年以上前の映画の方がエネルギーがある。 どうしてこういうことを考えつくのだろうと思ったが、考えてみれば、歌舞伎だって、随所に歌と踊りが登場する。むしろこれが伝統的なのかも。 こういう映画を作るのは難しいだろうが、せめて2時間ドラマで作れないだろうか。歌って踊るミュージカル時代劇。難しいのかなあ。笑いをとるのって大変だし。作り手によほどの技量がないと成功しないよなあ。
2004.11.03
コメント(0)
-

夜回り先生
10月27日にTBSで放送されたものを今日になって見た。 原作者の水谷修さんのことは、NHKのETVで放送されたのを見て知った。 ドラマの内容はETVで放送していた講演の内容と重なる。信じられないほど悲惨な現実が世の中にはある。 新聞の紹介記事をよんだところでは、妻子のことは原作には出てこないそうだ。理解ある妻子の支えというのは定石ではあるが、このドラマの場合は不要だったのでは。 主人公が関わった子供たちの話をもっと描いてほしかった。 それはそれとして、ドラマではあっても迫力はあった。 必ずしもハッピーエンドにはならないのが現実なのだ。深く関わっていながら、自殺されてしまう。 これが学校で関わっているこどもの自殺だったらどうだろう。 おそらく、「なぜ防げなかった」と、非難囂々だろう。 ETVで見たときも、ドラマで見たときも、「これは重要だ」と思ったのは、「愛の力で依存症を治すことはできない」ということだ。 薬物依存症は、愛の力では直せない。医学的な治療が必要な病気なのだ。 世の中には、愛の力で問題が解決できると思っている人がいる。 世の中、そんなに簡単ではない。 夜回り先生
2004.11.02
コメント(0)
-
スタンハンセン登場!
「スタンハンセン登場!カズハヤシ、世界ジュニア王座防衛」 おお、ハンセン元気だったか。よかった。膝の具合がかなり悪いのではないかという噂もあったが、NOSAWAを蹴散らしたりして元気なところを見せてくれたようだ。 全日を支えてくれたハンセン。来てくれてありがとう。 「魂のラリアット」を読んでその人となりを知ってますます好きになった。元気でいてくれ。 もう一つ。 「川田がケアを下し3冠8度目防衛」 激闘だったようだ。 ケアと川田、二人の全日生え抜き同士の対決なのだ。 川田にとっては辛勝、ケアにしてみればあと一歩というところ。これは見たかったな。 ハンセンの姿も見たかった。ちょっと、行けばよかった、という気もする。
2004.11.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1










