2004年05月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
「ハートブレイク・キッズ」 【小林信彦】
ハートブレイク・キッズ(著者:小林信彦|出版社:新潮文庫) 23歳のフリーライターを主人公とした小説。 全くの偶然から、高級マンションで若い男と一緒にいなくてはならなくなって……という出会いから3ヶ月間を描く。 非常に軽い書き方で、作者が顔を出して遊んでみたりしている。 途中、主人公の売り出そうという話があるところで、「あ、これは『極東セレナーデ』だ」と気づいたのだがほかの要素もあったのだ。 小森収という人が、解説を書いていて、「小林信彦の小説の様々な定跡のパッチワークみたいだ」と指摘している。まさにそうなのだ。さすがに解説を頼まれるだけのことはある。 『夢の砦』『紳士同盟』などの要素に気づかなかった。 主人公は映画評論家であり、登場人物が映画をめぐって話す場面もある。全体に映画を意識した小説で、おそらく、いろいろな映画の要素を意識して持ち込んでいるのだろう。冒頭もそうだし、偽物の麻薬捜査官かと思ったら本物だったなどというところもそう思わせる。 解説によると、これは女性雑誌「JJ」に連載されたものなのだそうだ。おお、小林信彦が「JJ」に連載を持っていたとは。 特に、主人公が、自分ではそうは思っていないけれど、回りから美人だと評価されている点など、言われてみると、女性読者を意識した書き方だ。 なお、ハートブレイクというのは失恋のことではなく、東京育ちの者の故郷喪失感というようなことのようだ。
2004.05.27
コメント(0)
-

「共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち」 【メロディ・ビーティ/村山久美子】
共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち(メロディ・ビーティ/村山久美子)共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち(メロディ・ビーティ/村山久美子) 「共依存症」という言葉を初めて知った。 そもそも共依存症とは何か、というと、それがよくわからない。 他人の世話にとりつかれ、自分を失ってしまい、相手のために何かしているようでいながら実は相手を支配しようとしているという症状があるのだが、阿それは表面的なことで、本人が自覚していない心の奥底に潜む心理状態であるようだ。 薬物やアルコールの依存症の人と一緒に暮らしている人がなりやすい。 著者はかつて薬物依存症であり、自分も共依存症であり、自身の体験や、カウンセラーとなって見聞した事例を豊富にあげている。 各章の初めには、誰かの言葉がおかれているが、「感情を抑えるたびに、胃に点数が加算される……」(p227)は大いに同意できる。 共依存症から脱却するための具体的な方策もいろいろあるのだが、そのまま日本では通用しないのある。 例えば、「私たちは、神に依存することもできる。神は私たちのそばにいて、気にかけてくれる」(p188)、「怒りが恨みに転化する前に、聖職者などに話すのもいい」(p257)などがそうだ。 共依存症者は相手のために何かしようとしながら振りまわされ、自らを傷つけていく。考えてみると、学校の教師というのは、共依存症者であることを回りから強制されているようなものだ。 しかし、心が愛情で充たされているというわけではない。 「共依存症者のほとんどは、心の中で何百回も相手の葬式に参列しているはずである」(p266)ということだ。
2004.05.17
コメント(0)
-
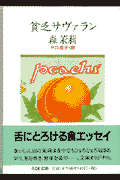
「貧乏サヴァラン」 【森茉莉】
貧乏サヴァラン(著者: 森茉莉 | 出版社: 筑摩書房・ちくま文庫) 食べ物に関するエッセイを集めたもので、森茉莉の、「上等なもの」への熱意にあふれている。育ちがいいだけあって、「上等なもの」=「高価なもの」ではないのがいい。 自分の主張をストレートに書いているのもあって、その内容には感心させられた。「だいたい、(粋)のスパルタ教育がなくなったということは、親たちに自信がなくなって、息子のやることも、服装(「なり」とルビ)も放任になったことなので、自信のない親は、口を出さないことが、理解のある親だとでも思っているより仕方がないのである。」(p59)「父親の言葉を丸呑みにしてそのまま、ぬうと育った私が賢い子供でないことは認めるが、貧乏が書かれていなくては、(生活がない)、という思想はおかしい。金のある生活も<生活>である。(p115)「彼は商館の小僧から一代で身代を築いた人であったが、そういう人にしては漢字も出来たし、字も立派であった。私の父とはすべてにくい違った考えの持主であったのは当然だが、それはかれの罪ではなく、秀れている方向が異なっていたのに過ぎない。」(p125) ただこの本、手紙を除いては、いつ書かれたものなのか明記していないのが残念だ。
2004.05.12
コメント(0)
-

「ムーミン谷の彗星」 【トーベ・ヤンソン /下村隆一】
ムーミン谷の彗星(著者:トーベ・ヤンソン/下村隆一|出版社:講談社文庫) 解説によると、1946年に書かれたものを1968年に書き改められたものだという。 シリーズとしてはムーミントロールたちがムーミン谷に住み着いてから最初の話ということだそうだ。 偶然ながら、「ムーミンパパの思い出」を先に読んだが、時間軸では、次にこれを読むのが妥当なわけだ。 スニフは最初から一緒にいて、冒険の途中でスナフキン、スノーク、スノークのおじょうさんに出逢う。 スナフキンはギターではなくハーモニカが得意で、すのーくのおじょうさんには名前はない。 冒険譚ではあるのだが、この夜の終わりが来るかもしれないという時に、どのような精神でそれを受け止めるのかという心理的な面に重点が置かれている。 「ムーミンパパの思い出」もそうだったが、哲学的なのだ。 北欧の児童文学ではこういう理屈っぽいのが一般的なのか、あるいは、特殊なシリーズだから人気があるのか。 そのあたりは全く分からない。 不思議な世界である。
2004.05.10
コメント(0)
-
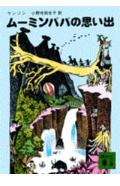
ムーミンパパの思い出 【トーベ・ヤンソン/小野寺百合子】
ムーミンパパの思い出(著者:トーベ・ヤンソン/小野寺百合子|出版社:講談社) 最近、スナフキンの父親のことを知って、確認のために読んでみた。 たしか、3度アニメ化されていて、最初の2度は同じ設定になっていた。これが印象に残っていて、ずいぶんムーミンの世界を誤解していたのだ。 3度目のテレビ東京でのアニメ化は原作に近かったようだ。 さて、スナフキンのことなのだが、原作のファンには常識なのだろうが、なんと、ミイの異父弟なのだ。スナフキンの父親はヨクサルという。ミイの父はでてこない。 最後まで読んでさらに驚いたのは、ヨクサルもミイの母親もまだ生きているのだ。冒険を続けていてずっと子どもたちをほったらかしにしているのだ。 北欧と日本の風土の違いというのはあるにせよ、登場人物の考え方は新鮮だ。 精神的自立を目指す話なのである。これ、童話ではあるが、大人のために書かれたのではないだろうか。
2004.05.07
コメント(0)
-
チャンバラもどき 【都筑道夫】
チャンバラもどき(著者:都筑道夫|出版社:文藝春秋) 「捕物帳もどき」の後を受ける連作短編集。 第1話で、前作とこれが、作者の祖父の速記記録をもとにしたものだった、ということにしている。第1話では作者が聞き手だが、第2話からは祖父が聞き手になっていて、祖父は登場しない。 聞き書きという体裁はもちろん「半七」を連想させる。 鞍馬天狗、座頭市、丹下左膳、木枯らし紋次郎、眠狂四郎、藤枝梅安となりきり、最後はまた鞍馬天狗が顔を出すという趣向。 老人の一人称で、昔のことを知らない人に話す、ということで、随時解説が入る。小説という形の、幕末から明治初期の江戸東京案内になっている。 解説(矢田省作)が、作者に直接聞いた話を色々紹介していて興味深く、役に立つ。いい解説だ。 都筑道夫が大佛次郎の文体模写で小説を書き始めたなど、全く知らなかった。こうなると、大佛次郎も読まなくてはならない。 作者は、これを書くために、「調べに調べて、どの一行も出典あり、というくらい、気を入れた」という。たしかに非常に濃厚で雑多な情報が詰め込んである小説で、それが多すぎるくらいなのだが、解説の結びにある作者の言葉で納得できた。「おまけ#[「おまけ」に傍点]のたくさんついているのが、好き」なのだそうだ。 まさにおまけたっぷりの小説である。
2004.05.06
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










