2004年03月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
「白髪鬼」 【岡本綺堂】
白髪鬼 岡本綺堂怪談集(著者:岡本綺堂|出版社:光文社文庫) 「青蛙堂奇談」(『影を踏まれた女』所収)に続く怪異譚集。 当代の話もあれば江戸時代の話もある。 このうち「西瓜」は、ほかの何かで読んだ記憶がある。 怪談なので合理的な説明はされない。 どの話も、偶然と言えば偶然、必然と言えば必然と言えるような事が起こるのだが、どうやってこういう話を考え出したのだろうか。 中国の筆記あたりに着想を得た物もあるのだろうが、岡本綺堂の筆にかかると、いずれも、日本に土着した物語となる。 もっとも印象に残ったのは表題作よりも「妖婆」だ。やはり江戸時代物がいい。 解説は都築道夫で、これがまたよく出来ている。 実作者としての経験からの解釈あり、考証あり。 なんとなく読み流してしまった所も、都築道夫は気に留めていて、「停車場の少女」に出てくる「電報をかける」という表現、「白髪鬼」で「酉の市」と書いて「とりのまち」と読ませている所、「一の酉」ではなく「初酉」となっているところなど、岡本綺堂が江戸人であることを示す例としている。 ところで、本の題としては「白髪鬼」、副題が「岡本綺堂怪談集」となっているが、目次の前のページには、「近代異妖編」とある。もとはその書名で出ていたらしい。
2004.03.31
コメント(0)
-

「あかね空」 【山本一力】
あかね空(著者:山本一力|出版社:文藝春秋) 書き下ろし長編で、直木賞受賞作。 去年(2003年)にテレビドラマ化されたのを見た。 妹おきみの視点から描いたもので、安心してみていられるできだった。 永吉が赤井英和、おふみが浅野ゆう子だった。 小説を読んでみると、テレビではよくわからなかったところもよくわかる。(あたりまえだ) 傳蔵は、テレビでは迷子になったということだったが、迷子札があったはずなのに、変だなと思っていたら、原作ではさらわれていたのだ。これなら理解で期す。 永吉が江戸に出てきたところから、子供たちだけで店をやっていくところまでの三十年近くの話。 人情話ではあるのだが、同じ出来事が家族それぞれにとって違う意味を持っており、互いに誤解しあっていることで葛藤が生まれる。 悪いやつというのが一人しか出てこない。 文章は変に凝ったところはなく、非常に読みやすい。 一気に読んだ。 どんなものを着ているか、ということをその都度ちゃんと書いているが、読むこちらに知識がないので絵としては浮かばない。 ドラマの配役を当てはめて読んでいた。 江戸の風俗の解説などはないのがかえっていい。 「六ツ(午前六時)」「五尺五寸(百六十六センチ)」「一寸(約三センチ)」というように、時間と長さにだけ説明がついている。
2004.03.23
コメント(0)
-

「はじめての言語学」 【黒田竜之助】
はじめての言語学(著者:黒田竜之助|出版社:講談社) 言語学を一つの科目としてとらえ、どのようなものなのか入り口から中をのぞくという姿勢の入門書。 おもしろく読んだが、さて、言語学とは何か、ということがわかったかというとそうはいかない。 印象に残ったのは、著者の姿勢として、批判するときは、名を出さないこと。 「蒲焼き」の語源を民間語源で説明してしまっていることを取り上げ、「アルファベット」の説明では「見事なまでに役に立たない」とやっつけているのは、明らかに岩波書店の「広辞苑」だと思われるのだが、「某社の大型国語辞典」としか書かない。 「びっくり! 日本語の起源」(p196)では、大野晋のタミル語起源説を取り上げているが、ここでも「国語学の大御所」というだけで名前は出していない。 「信じられないような音韻対応を発明し、言語学を勉強した人はみんなビックリしたが、ご本人は自信満々であった。」ということだが、著者は1964年生まれだから、発表された時はまだ中学生ぐらいだろう。これは後で知ったことだろう。 興味深いのは、「真面目なインド言語学者が何人か反論していた。でもこういう真面目な意見は面白くないのか、マスコミはあまり取り上げなかった。」というところ。 問題はこれなのだ。旧石器時代の遺跡の捏造がずいぶん大きく取り上げられたが、あれだって、ずっと前から疑義を提示していた学者がいたのに、それをとりあげず、新発見、大発見と持ち上げてきた人達がいたから捏造が続いたのだ。マスコミが捏造を誘発した面があるだろう。 以前は見ていたが、「外国語学習メカニズムについて特集したのを見たら、その荒唐無稽《こうとうむけい》さにあきれかえってしまった」(p197)という番組は「特命リサーチ」だろうが、これも番組名は出ない。 「《母国語認識》などという不正確な見出しをつけていたのはうちで購読しているM新聞だけであった。そんな判断もできない人が新聞記事を書いているとは真に不思議である。」(p239) ここでは「毎日新聞だろうな」と察しは付く書き方をしている。 気になるのはその後の部分だ。 人は誰でも、自分の専門にかかわることなら、不正確な書き方がしてあれば「変だ」と思うが、それ以外は新聞に書いてあることを鵜呑みにしてしまうのではないだろうか。とにかく、新聞は疑ってかかるに越したことはない。 「《ハングル語》というのもわたしには抵抗がある。ハングルとは文字の名称である。日本語のことを《ヒラガナ語》と呼ばないように、韓国・朝鮮語にそういう名称を与えるのは変だと思う。」(p32) 言語学者でなくたって変だと思う。なぜ「ハングル語」がまかり通っているのか不思議だ。こういうことろは声を大にしてもらいたい。 一方、言語の名称と言うことに関しては、「言語に名称を与えるのは政治と歴史であり、言語学では判断できない。」(p177)と明確に述べている。事はそう簡単ではないのだ。
2004.03.20
コメント(0)
-
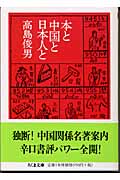
「本と中国と日本人と」 【高島俊男】
本と中国と日本人と(著者:高島俊男|出版社:ちくま文庫) その昔、雑誌「東方」に連載されたものをもとにまとめた本で、『独断! 中国関係名著案内』と重なる部分もある。 書評であったり、著者のエピソードを語るものであったりして、語り口に工夫があり、いずれもおもしろく読める。自分も読んでみようという気になるのも多いが、読む気にならないのもある。それでも、紹介する文章自体はおもしろいのだが、著者の芸のすぐれていることがわかる。 読者に対して親切な作りで、各編の末尾に、読者が知らないのではないかと思うようなことがらについて、【ことば、ことがら】というコーナーをつくって説明している。 例えば、「花形記者から権助に」(p134)の「権助】とは何だろうと思っていると、ちゃんと説明している。 あとがきによると、中国が変化したので内容が時機遅れになったものは割愛したそうだが、そういうのも全部収録し、詳細な索引を付けて出して欲しいものだ。 日本において、どのように中国が語られていたか、という貴重な記録になったはずだ。
2004.03.18
コメント(0)
-
「パレアナの青春」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
パレアナの青春( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社:角川文庫 )" 『少女パレアナ』の続編。 ベタな通俗小説になってしまっているのだが、それでも面白い。 それまで全く登場していなかった一家と関わりを持ったり、途中であっという間に六年たって、パレアナが二十歳になってしまったりして、物語はどんどん進む。 続編というよりも、これは『少女パレアナ』と分けられない、一つになったものなのだ。 おそらく、作者は、『少女パレアナ』を書いているときから、最後にはこうなる、というのが、頭にあったのだろう。 『少女パレアナ』に比べれば、伏線のはり方が甘いが、それでも、一体どうやって決着をつけるのだろう、という興味で読み進まずにはいられなかった。 訳文で気づいたこと二つ。 「おまえの舌(した)にはついていかれないよ」(p37)。初版は1962年。「いかれない」という表現は今は珍しくない。訳した当時は不自然ではなかったのだろうか。裕次郎の「赤いハンカチ」に「いかれたものを」という歌詞があり、聞くたびに引っかかるものを感じていたのだが、どうやら、広く使われていたらしい。 「患家先(かんかさき)」(p194)。初めて見た言葉だ。患者の家、という意味なのだが、英和辞典にはこういう言葉が載っているのだろうか。
2004.03.17
コメント(0)
-

「少女パレアナ」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
少女パレアナ改版( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社: 角川文庫) 子どもの頃に、子ども向けの文学全集で読んだことがあったが、たまたま家にあったのでちゃんとしたものを読んでみた。 大人の目で読んでみると、大衆小説のつぼを心得ていて、話の展開が実にうまい。 貧困から裕福へ、かたくなな親族、と、『小公子』や『秘密の花園』などのパターンを踏襲し、主人公の明るさで周囲のものが救われていく、というハッピー・エンド。叔母の昔の恋人は誰か、など、あとで考えると、ちゃんと伏線が張ってあったのに、ついだまされてしまった。 作者は、子どもの時から作家になりたいと思っていた、という人ではないそうだが、物語とはどういうものかがよく分かっている人だったのだろう。 出版されたのは1913年で、すでに開拓時代ではないのだが、西部と東部というのはだいぶ異なるらしい。それもまた、主人公とまわりの人物とのギャップになっているようだが、そこはよく分からない。 読んでいて、何かに似ている、と感じたが、何に似ているかといえば、『非凡なる凡人』と、『富士に立つ影』の「主人公編」の主人公だ。特に、物語としてもおもしろさから言えば、『富士に立つ影』に似ている。 こういうものを読むたびに感じるのは、翻訳の難しさだ。 児童文学、ということで、ですます調で訳してあるのだが、「懇望(こんもう)していた」などという言葉が出てきたりする。 また、訳されたのが40年近く前であり、言葉遣いが随分違う。
2004.03.15
コメント(0)
-
「漱石の思い出」 【夏目鏡子/松岡譲】
漱石の思い出(著者:夏目鏡子/松岡譲|出版社:角川文庫) たしか十年以上前に一度読んでいるのだが、ほとんど忘れてしまっている。 また、その間にいろいろほかの本を読んでいるので、ほかで得た知識とあいまって「ほう」と思うこともあった。 成立過程は巻末の「編録者の言葉」に詳しい。 漱石の死後十年がたち、晩年に漱石のもとに出入りしていた松岡譲が、未亡人に話を聞いてまとめたもの。 「家庭における漱石」「妻の見た漱石」、つまり、作家としてではなく、家庭人としての実像である。 漱石に幻想を抱いている人からは批判もされたらしい。 親しく出入りしていながら、漱石の一面しか知らなかった人も多かったろう。 解説で、次男の夏目伸六が、小宮豊隆の『夏目漱石』を評して、「著者のこの消化不良と頭の悪さとが」と述べている。 家庭での姿のみ見ていたものとしては、はたから見ていたものの書くものには、腹立たしい思いさえしたことだろう。 関係のない話だが、この次男の伸六という名、「俺たちの旅」のグス六と同じだが、「俺たちの旅」はそれを知っていてあの名をつけたのだろうか。 結婚前の逸話として、漱石が、ありもしない縁談を断ったと言って怒った話(p10)が語られている。今なら、人格障害か、統合失調症というところだ。 ロンドン時代も、「だれかが監視しているような追跡しているような、悪口をいっているような気が」(pp108)したそうだ。 脳を病んでいる夫・父を持つ家族も大変だが、本人も苦しかったろう。 泣きやまない末子に、「皆にいじめられ、そのうえ父からもかわいがられなかった」(p309)自分を重ね合わせてあやすところなどは哀れである。 以下、印象に残ったところ。 「新し橋のところの丸木|利陽《りよう》で写真を撮《と》って送り」(p19) 新橋の間違いかと思ったら「新し橋」という地名があったのだ。 夫人は朝寝坊で「時々朝のご飯もたべさせないで学校へ出したような例も少なくありませんでした。」(p34)明治でも朝寝坊の人はいたのだ。 「藤島さんののが」(p45)、「また例ののが」(p139)はそれぞれ、今なら、「藤島さんのが」「例のが」というところ。 「一人ののが二人ふえて」(p329)というのもある。「いったい夏目は生家のものに対しては、まず情愛がないと申してもよかったでしょう。あるものは軽蔑《けいべつ》と反感ぐらいのもので」(p47)と、漱石の長じてからの態度を語ってから、それまでの生い立ちが語られる。 漱石の一番上の兄に、樋口一葉との縁談があった。(p51) 漱石は、徴兵免除のため一時、北海道に籍を移していたことがあった。(p63) もし軍隊にいたらそれこそ発狂してどうにもならない状態になっていたのではないだろうか。 鈴木三重吉はもとは子供嫌いだった。(p192) 修善寺での大病の時、ワラブトン(p225)に寝ていた。 三三九度の練習で「座敷に二人が向かい合って坐っていると」(p271)とある。今なら横に並ぶところだが、江戸の風習がまだ残っていたようだ。 大阪での入院中「便所が西洋式になっておりまして、水で流すようになってるのですが」(p275)西洋式がそのまま持ち込まれていた世界もあったのだ。 大阪から帰った後痔の手術をしているが、「翌年になってもまだ膿《のう》が出たりして」(p277)ということで、痔瘻だったようだ。 「駄洒落《だじゃれ》や皮肉をかっ飛ばして」(p279)の「かっ飛ばす」は江戸弁か。 通夜僧が「何でもかっかじめるような話をいたします」(p285)の「かっかじめる」も江戸弁か。 「菊五郎はたしか長谷川時雨《はせがわしぐれ》さんがお連れになって」(p323)。ほう、長谷川時雨とも交際があったのか。江戸の人同士、話が合ったのかもしれない。森茉莉は確か長谷川時雨から何かもらったことがあったはず。文人同士、広くつきあった人なのだろう。 教師としての漱石。「おれはできない生徒にはどこの学校でも仇敵《かたき》のように思われたもんだが、そのかわりできる生徒からは非常にうけがよかったもんだ」(p340)
2004.03.12
コメント(0)
-

「恋人たちの森」 【森茉莉】
恋人たちの森(著者: 森茉莉 | 出版社:新潮文庫) 初めて森茉莉の小説を読んだ。 文章は凝りに凝っていて軽く読み流すことはできない。 点の打ち方も独特で、「変わった科目の教授だったということで、あった。」「肖像が自分に物を言うような気分のすることもあるように、なった。」「激しいものを潜めている顔を、していた。」という具合。 「ボッチチェリの扉」「恋人たちの森」「枯葉の寝床」「日曜日には僕は行かない」の4編。 「ボッチチェリの扉」はおそらく実体験がいくらかまじっているのではないかと思われる、ある家族を描く小説。由里《ユリア》が部屋を借りている家の家族にまつわる話で、由里は女性に対して厳しい目を向けている。同性だからこそ敏感に感じる女の嫌な面も描いているのだが、文章が凝っているので嫌みを感じさせない。 「恋人たちの森」以下3編は、中年にさしかかった男(文筆業や大学教師で金持ち)と、まだ少年らしさをのこしている若者の恋愛。 「恋人たちの森」は年上の男の死によって世界は終わり、「枯葉の寝床」は二人の死によって永遠を手に入れる。「日曜日には僕は行かない」は、女の死によって二人の世界が続く。 3編とも、金には不自由しておらず、高級品を買える境遇で、洋風の生活をし、身なりにも気を遣う。しかし、「愛」というのはそれとは次元の異なるところで価値があるわけだ。 これはユーミンの世界ではないか。 彼女の歌う「純愛」は、「金で買える物はすべて手に入れられる状態における愛」だと感じるのだが、一脈通じる物がある。 何を着ているか、どこで食事をするか、どんなタバコを吸っているか、ということを詳しく書くことによって、世界にリアリティがもたらされており、風俗小説とも言えるだろう。 男同士の恋愛というものには全く興味がないので、正直なところ理解できない小説集だった。 「僕じゃ少し役不足だね」(p102)は、誤用なのか、本来の意味で使っているのか。
2004.03.08
コメント(0)
-
「江戸商売図絵」 【三谷一馬】
江戸商売図絵(著者: 三谷一馬 |出版社:中公文庫) 江戸の商売あれこれを、資料からの模写で示し、簡単な説明と、その商売にまつわる川柳を載せている。 絵の出典も明記してあり、丁寧な作りに感心する。 江戸を通しての商売もあれば、一時期だけあったものもある。 「米搗き」など、杵を担いで歩き、呼び込まれて仕事をする、という、流しの米搗きもあったという。 読んで楽しく資料としても役に立つ本だ。
2004.03.06
コメント(0)
-
「江戸のおしゃべり 川柳にみる男と女」 【渡辺信一郎】
江戸のおしゃべり 川柳にみる男と女(著者: 渡辺信一郎|出版社:平凡社・平凡社新書) 川柳を原典から引いて解釈を加え、江戸時代の人々の生活をかいまみようという本。 あやとりの説明など、言葉の解釈がくどく思われる点もあるが、面白く、江戸の人の息づかいが感じられる。 それでも残念に思う点はある。 例えば、「獣肉と野菜を混用した薩摩汁に代表されるように、中国や南方の食文化の影響からか、獣肉を多食するとされる」(192ページ)のように、主語を出さずに「される」を使っているところがある。 また、三田村鳶魚の『江戸字引』を引いて、「リャンコ 二の唐音。本拳の語に二をリャンという、大小さしたるを指す、リャンともいえり。武士をののしる言葉。」 というのを引いて終わらせている。この場合の「唐音」とは、漢字音の「漢音・呉音・唐音」の「唐音」ではなく、中国語での発音という意味だろう。したがって、「二」の唐音とするのは正しくはない。「両」の唐音と言わなくてはならないはずだ。 あとがきによれば、「唯一、現代の本で引用したのは、三田村鳶魚の『江戸字引』のみである。」という。原典主義は尊敬すべきことだが、「二」をリャンというかどうかは、中国語の辞書を引いてみればわかるはず。惜しい。
2004.03.02
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月3日分)
- (2025-11-17 00:21:38)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 185
- (2025-11-16 21:29:24)
-







