2004年08月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1 >
-
そっくりさん
浜口京子選手とえなりくん。-輾転反側-
2004.08.31
コメント(0)
-

マリアのうぬぼれ鏡 【森茉莉】
マリアのうぬぼれ鏡 ( 著者:森茉莉 | 出版社:ちくま文庫) 森茉莉のエッセイから抜粋した森茉莉語録。 「贅沢」「食い道楽」「幸福」「恋愛」など十一項目に分類してある。 明治生まれで、また、言葉をいろいろと選んで使う人なので「かいなで」「茄子《なす》や胡瓜の古漬けのかくや」など、知らない言葉が出てくる。このうち、「かくや」はわからない。混ぜご飯の具などの「かやく」のことか。 語られている内容もさることがながら、言葉が気になる。 「夏の半襟は朝のあまり高くないのをたくさん買って、掛け流しにする(一度ですてること)。」(p21)。これと同内容のことが127ページにも出てくるが、そちらでも「かけ流し(一度で捨てる)」と説明がしてある。 最近問題になっている温泉問題で、さかんに「かけながし」という言葉が出てくる。お湯を循環させずに、浴槽からあふれた分を捨ててしまい、常に新しい温泉が供給されている状態をいうのだが、これは温泉用語ではなく、昔からあった表現だったのだ。 「言葉は暖《あった》かっぽいし」(p162)。最近よく聞く「ぽい」言葉。森茉莉も使っていたのだ。 語られているのはほとんどが自分の内面にあることで、外部に目を向けることは少ない。 「日本のジャーナリズムはいつもそうである。大騒ぎするが直ぐに忘れる。」(p196)などというのは例外的だ。 ただし、他人に厳しい目を向けないわけではない。「マリアを現在取り巻いている日本庶民は」(p200)で始まる一段アドは、成り上がり庶民への罵倒である。森茉莉にとっては労働を崇高なものと見るなどというのはもっとのほかなのだ。彼女が愛した人々は「働かなくてはならないから働いているのであって、決して勤労を誇っていない。」という。 こうして他人を批判はするが、見下しているわけではない。自分とは違う価値観に生きる人として遠ざけるだけだ。「間違った誇が多い。例えば小さい例が、他人を馬鹿にすることを自分が賢い証明のように思うような事がその一つだ。」(p237)と言っている。 この「誇り」というのは森茉莉を支える重要な要素だったのではないだろうか。「自分に誇りのある親の子供はコンニャクにはならないんどえある」(p238)というところにも見て取れる。別段、鴎外の娘であることを鼻に掛けているわけではない。鴎外のことは美しい思い出として心の中に常にある。 小説家としての鴎外を見る目は案外冷静だ。 「鴎外は翻訳と批評と戯曲を書くのは巧かったが、小説は理屈で、つまり頭で書いているので詰まらなかった。」(p119)とまで言っている。漱石の小説は好きだという。「鴎外にとって不幸なのは鴎外を好きな人は漱石も愛すが、漱石が好きな人は鴎外はきらいの場合が多いらしいことである。」(p118)だそうだ。 「インきの汚点」(p71)、「たとへようのない」(p151)は誤植と思われる。
2004.08.30
コメント(0)
-
「危ぐ」「進ちょく率」
いずれも新聞記事の見出しにあった語。 県民の反発を危ぐ 矛盾対応で米軍迷走と 宮城県の財政再建プログラム 進ちょく率73.3% どちらも、一瞬意味が分からなかった。 「危ぐ」は「あやうぐ」とでも読むのかと思ったが、そんな言葉は聞いたことがない。 考えれば「危惧」「進捗率」だな、とはわかる。なぜこんな表記をするのか。 おそらく「常用漢字に入ってない」というのが理由なのだろうが、だったら「拉致」は「ら致」と書くか、というと、今ではこぞって「拉致」と書いている。 一貫性がない。 「常用漢字」にない字を使うな、というのではない。逆だ。 「危惧」「進捗率」と表記した方がわかりやすいだろう。なぜこんな表記をするのだ。 かえってわかりにくい。 こんな表記をするくらいなら、言葉を工夫して漢字だけで書ける語を用いればいい。 「危惧」ではなく「懸念」、「進捗率」ではなく「達成率」という語を使えば漢字で書ける。もちろん意味は全く同じではないが、意味は通じる。 少しは工夫しなさいよ。-輾転反側-
2004.08.29
コメント(0)
-
少しは頭を使えよ
相変わらず産経新聞が朝日新聞を意識して独り相撲。 28日の産経抄。 朝日の言うことが気になってならないらしい。しかも、自分が言っていることが矛盾していることに気がつかない。 「アテネ五輪は日本選手の健闘で日の丸・君が代のラッシュになったが、スタンドの日本人はみな国際的礼節を守り、他国の国旗・国歌にもきちんと敬意を払っていた。つまり都教委のめざすような教育がほどこされれば、まずまず“安心”していいのである。」と、結んでしまっている。自分が何を書いているのかわからないらしい。 これから都教委が目指す教育というのは今までは行われていなかった教育だろう。だからこそ話題になるのだ。 つまり、今、アテネ五輪で「国際的礼節を守り、他国の国旗・国歌にもきちんと敬意を払っていた」人たちというのは、これから都教委が目指す教育を受けていない人たちということになる。その人たちが、むしろ産経新聞が求める日本人になっているというわけだ。 ということは、都教委の目指す教育を否定し、従来の教育が正しいと主張しなくてはならなくなるではないか。 少しは頭を使えよ。
2004.08.28
コメント(0)
-

「H.G.ウェルズのSF月世界探検」 【監督:ネイザン・ジュラン。1964年】
アメリカ映画。レイ・ハリーハウゼンの特撮もの。特撮場面を作るためにこの映画が作られたのだろうが、意外や意外、話がよくできている。 原作は子供の頃に読んだ記憶がある。しかし、原作通りでは1964年という時代には作れない。そこで、その当時の現代の宇宙飛行士が月に到着したら、すでに1899年に人類が到達していたという証拠があって……ということで、原作の話になる。 人間の造形が深いのが印象に残る。月の生物の動きは、シンドバットものと同じ。 なぜ登場人物の一人が盛んに咳をしているのかと思っていたら、ちゃんと意味があるのだった。 外来の病原菌によって絶滅するというのは、西洋人が各地に病気をまき散らした経験からすぐに考えつくことなのだろう。 DVDがでている。
2004.08.27
コメント(0)
-
謎の「ジェンダー・フリー」
「ジェンダーフリー」教育現場から全廃 東京都、男女混合名簿も禁止という記事を読んで、世の中には不思議なことを考える人たちがいるものだ、と思って、東京都の教育委員会のサイトを見に行った。 このことについては、「男女平等教育について」というページで触れている。 別段、男女混合名簿を禁止するというわけではないらしい。面白いのは「東京都教育委員会は、これまで学校における出席簿等の名簿について、望ましい男女共同参画社会の実現に向けた取り組みの一環として、男女混合名簿の導入を推進してきた」のだそうだ。 自分で推進してきておいて禁止というわけにはいかないよなあ。 ついでに、上の記事では、「男女混合名簿導入にも影響を与えており、東京都内では今年4月現在、小学校81%、中学校42%、全日制高校83%で、男女混合名簿が導入されている。」のだそうだ。 教育委員会が推進しても、抵抗していた学校も少なくないわけだ。それで処分者が出ているという話も聞かないから、「男女混合名簿はやめろ」といわれても従わなくたってかまわないのだろう。 上に引いた記事や教育委員会の言っていることを読むと、ジェンダー・フリーに基づく男女混合名簿は「男らしさ」「女らしさ」の否定につながるからいけない、ということらしい。 ここまでくると宗教だね。どうして男女混合名簿にすると男らしさや女らしさがなくなるのかさっぱりわからない。 世の中に性別というものがある以上、性差はなくならないだろう。 それに「ジェンダー・フリー」という言葉がなくなったからといって、男が男らしくなり、女が女らしくなるとも思えない。 それともなんですかね。山咲トオルやKABA.ちゃんのような「男らしくない」男性タレントは、「ジェンダー・フリー」とやらが生み出したものなんですかね。 むしろ、テレビ局に「男らしくない男性タレントは使うな」と要求すべきだろう。 「ジェンダー・フリーは和製英語で言葉として間違っているから使わない方がいい」というのならわかるのだが、そういうわけではないらしい。 自分たちで勝手に作り上げた「ジェンダー・フリー」という亡霊相手に独り相撲を取っているようにしか見えない。 はたから見ると滑稽なだけだが、本人は大まじめなんだろうね。-輾転反側-
2004.08.26
コメント(0)
-
柔道で昇進
金の阿武教子選手に「総監賞詞」授与 今までなぜかオリンピックではメダルが取れなかった阿武選手が金メダル、ということでご同慶の至り。 しかし、この記事の最後にある、「阿武選手は同日付で巡査部長から警部補に昇進した。」というのが納得できない。 昇進したくて柔道に打ち込んでいたわけではないだろうし、昇進よりも名誉を望む人なのでは。 偉業をたたえるのはいいが、柔道は職務ではないはずだ。 職務ではないことで昇進とはどういうことだろう。 民間企業で働いているほかの競技の選手たちが、メダルを取ったからといって昇進しているとは思えない。 昇進させるなら、注目を浴びることなく地道に職務を遂行している人たちに目を向けよう。-輾転反側-
2004.08.25
コメント(0)
-
おめでとう! 浜口京子選手
もう10年以上前のこと。新日本プロレスの中継番組である「ワールドプロレスリング」に、なぜか、引退から復帰したものの、首が思わしくなく半引退状態だったアニマル浜口のコーナーがあったことがある。数回だったと思うのだが。 アニマル浜口が、娘と、簡単なトレーニング法を紹介するコーナーで、タオルを使って二人でするトレーニングなどもあった。その時に彼女を初めて見た。まだ小学生だったのではないだろうか。 トレーニング後、娘のついでくれたビールを、熱く語りながら飲んだりしていた。 その後、レスリング選手として頭角を現し、今日に至るわけだ。世間は「アニマル浜口の娘」として見るし、父親としてはユニークな父親なので、いろいろな思いを味わったことだろう。 今回のオリンピックでも、応援席のアニマル浜口にカメラマンが群がっているのを見て不快に思った。応援する姿を写そうというのではなく、面白い映像がとれないかなあという下心ばかりが感じられた。 闘将・アニマル浜口は、常に人を引きつけることを意識し、自分だけでなく周りも熱く燃えさせようとする男だ。おもしろおかしく取り上げないで欲しい。 注目されていただけに、準決勝で敗れたときには、大きなショックを受けただろう。ひそかに心配していたのだが、銅メダルを取って笑顔を見せてくれてほっとした。 おめでとう! よくやった!
2004.08.24
コメント(0)
-

「あの子を探して」 【監督・張芸謀。1999年】
貧しい村の小学校が舞台。教員が親の看護のため一ヶ月留守にする。その間の代用教員として雇われてきたのは13の少女。教員は、退学する生徒が多い、一人も減らさなければ10元出すという。原題は「一個都不能少」で「一人も減らすことができない」という意味。 そもそもこの少女、目当ては謝礼の50元であって、子供が好きなわけでもなければ教育熱心でもない。 ところが、どちらかというと問題児の男子が親の借金を返すために町へ働きに行ってしまい、このままでは生徒が減ってしまうと、連れ戻しに行こうとするのだが……。 全体にドキュメンタリータッチで、主人公を含め、登場人物には、プロの俳優はほとんどいないそうだ。子どもたちの表情も暮らしぶりもリアリティがある。小学校に寄宿している子どもたちまでいるが、現実にこういう学校はあるのだろう。 ほとんど金もなく町へ出た少女が、男の子を捜し回る内に親切にされたり冷たくされたり。むしろ、冷たくされることの方が多い。 いわば子供が子供を捜すのだからうまくいくわけはないのだが、そこはドラマだから、ちゃんと話は丸く収まる。 たとえば、2本のコーラをみんなで分け合って飲むときの子どもたちの作り物ではない表情や、村と町の生活の格差に圧倒される。これじゃ、みんな町へ行きたくなるよね。 しかし、貧富の差や、教育問題がテーマというわけではない。社会的な映画ではない。 監督はきっと、こういう物語を描きたかっただけなのだ。 自分が描きたかった物語にぴったりの風景、子どもたちを得ることができて傑作を作ることができたのである。 DVDがでている。あの子を探して(1999) - goo 映画
2004.08.21
コメント(0)
-
「眠る男」 【監督・小栗康平。1996年】
1996年 脚本=小栗康平、剣持潔。監督=小栗康平 群馬県の人口200万人突破を記念して制作された映画なのだそうだが、群馬が舞台らしいというだけで、映画の内容とは関係がない。 「風景」を描く映画だ。群馬県各地で撮影したと思われる風景の迫力が印象に残る。 山岳地もあるが、駅前、商店街、そういった生活の場もまた画面のほとんどをしめる。人間は小さいことが多い。 タイトルの眠る男は、山で事故にあって以来眠り続けている男で、寝ているばかりで何かするわけではない。その男の友人だった役所広司が主人公といえば主人公。 眠り続けていても起きて生活していても時間は流れ、昔の自分が予想していなかったような自分になる。 いいも悪いもない。 スナックで歌っているのがインドネシアの女性で、この女性が最後に、死んだ眠る男の魂と出会ったりするのだが、この女性の意味は全くわからない。 役所広司が、山の頂上で、ブロッケン現象を見るところまではいいが、「人間は大きいんかねえ、小さいんかねえ」と声に出すのはかえって冗舌に思えた。眠る男(1996) - goo 映画
2004.08.20
コメント(0)
-
「料理人」 【ハリー・クレッシング】
料理人(著者:ハリー・クレッシング /一ノ瀬直二|出版社:ハヤカワ文庫) おそらくイギリスと思われる国の田舎町に自転車で現れた男コンラッド。 名家に住み込みの料理人として雇われ頭角を現していく。 料理を通じて主人一家、もう一つの名家をコントロールするようになる。 といっても金銭的な野心があるわけではない。両家を実質的に我がものにし、富を手に入れるが、結局何をするかというと城にこもって延々とパーティを開くという結末。 料理を作ること、食べることにとりつかれた人間たちの物語でもあるのだが、グルメ小説ではない。旧家乗っ取りの成り上がり小説でもない。 何とも言いようのない不思議な小説なのである。 コンラッドが人々を操っていく様は見事だ。 主人一家の体重をコントロールし、じゃまになりそうな執事は病気にして追い出す。 料理の力で主人の娘も手に入れる。 主人はそれまで執事の仕事だった飲み物の調合に、その妻はテーブルセッティングや皿洗いに、息子はコンラッドの弟子として料理に、それぞれ嬉々として取り組むようになり、常にコンラッドの指示を仰ぐ存在になってしまう。 訳者あとがきによると、これは悪魔物の一つなのだそうだ。 人間の欲望を刺激し、人間を意のままに操る。悪魔とはそういう存在であるらしい。 一箇所誤植発見。「喚起設備の貧弱」(p145)は「換気設備の貧弱」だろう。
2004.08.19
コメント(0)
-
「私の美の世界」 【森茉莉】
私の美の世界(著者: 森茉莉 | 出版社: 新潮社・新潮文庫) 森茉莉が、何を好み何を嫌うかについて書いた文章を集めたもの。 こまごまとした日常生活にかかわる事柄もあれば、「反ヒュウマニズム礼讃」のような、社会批評の文章もある。フランスでの生活を懐かしむ余りか、西欧に較べると日本はダメだ、という論調が目につくが、少なくとも自分の頭で考え、自分の感性に基づいて判断している。 例えば、「事故死をした人間の遺族は、すべてジャアナリズムの演出通りに動いているので、水で死んだ人々の遺族が最後に船の上から花束を投げて、悲しげな表情で、水面を見つめる、という、どこか拵えもののような光景がその度に展開する。」(P167)などは、報道の本質をついている。 金が入ったらそろえたいものの中に、半七捕物帖があったが、やはり本物、という気がするのだろう。岡本綺堂の書いた芝居も好きらしい。 意外に感じたが、長谷川時雨から絵葉書をもらったことがあるという。与謝野晶子について書いた文章の中に、「やはり偉物(えらもの)だった長谷川時雨(しぐれ)」と表現してある。鴎外の交際範囲に長谷川時雨もいたわけだ。 森茉莉のように、一人で、自分の思いのままに(経済的には思いのままではないようだが)暮らしていると、自分の世界の中で生きることができる。それで彼女の感性を損なわれずにいたのだろう。 「貧乏サヴァラン」の「マリアの幻は、現実以上の現実なのだ」(P37)という文章に、森茉莉の生活が凝縮されている。
2004.08.18
コメント(0)
-
「いつでも夢を」 【監督・野村孝。1963年】
町工場で働きながら定時制高校に通い、今の生活から抜け出すことを夢見る浜田光夫。 孤児だったが、引き取られた先の医院の仕事を手伝い、これも定時制に通う明るい娘、吉永小百合。 トラックの運転手で、浜田光夫と、吉永小百合を張り合うきっぷのいい若者、橋幸夫。 これまた非常に「時代」というものを感じさせる映画だった。 定時制だというだけで入社試験を不合格にされる浜田光夫。今でもこういうことはあるだろう。それでも気を取り直して前向きになるわけだが、差別そのものは消えないわけで、問題の解決にはならないのだが、それを精神的に乗り越えてしまう映画なのだ。 定時制の教室で、労働法についての授業をしているのも印象的。 貧しいのが当たり前、それでも希望を持って生きていこう、きっといい日がやってくる。 40年後の今、貧しさからはだいぶ脱却できたとは思うが、精神的にはあまり希望のもてない世の中になってしまった。 橋幸夫と吉永小百合の歌う主題歌は知っているが、この映画、とにかく歌が出てくる。 浜田光夫も橋幸夫も歌う歌う。 ここまで明るいとかえって不自然だが、これが自然に見えた時代だったんだなあ。いつでも夢を(1963) - goo 映画
2004.08.14
コメント(0)
-
「上を向いて歩こう」 【監督・舛田利雄。1962年】
主役は坂本九と浜田光夫。鑑別所からの集団脱走から始まる。どうも、鑑別所と少年院が混同されているようなのだが、この当時はこうだったのかも。 脱走後、坂本九は保護司のもとで地道に働き、浜田光夫はドラマーにあこがれて裏社会に足を踏み入れる。 いくら地道に働いたって、鑑別所からの脱走という罪は消えないはずだが、その点はいいかげんで、刑事も別に捕まえようとしないのは謎。 ヒロインは吉永小百合と渡辺トモ子。 浜田光夫が入り込んだ世界で顔役になっている高橋英樹は、実は大学受験をめざしていて……と人物造形は複雑。 主人公二人は互いのためを思いながら誤解が生まれたり。 それぞれつらい過去を持ち、一人ぼっちだったが、手を携えて歩いていこう、新しい世界が待っているという明るい終わり方。 歌を歌う場面が多いのは当然だが、最後はみんなで、新しい競技場の横を、「上を向いて歩こう」を歌いながら歩くのだ。主要人物はそれぞれのパートがある。 歌に合わせて日本各地の労働風景が流れたりして、高度経済成長を象徴するような映画だ。 石川進(昔はQちゃんと言えばこの人だったのだ)が出ていて懐かしかった。上を向いて歩こう(1962) - goo 映画
2004.08.13
コメント(0)
-

「銀座の恋の物語」 【監督・蔵原惟繕。1962年】
きちんと全部見たのは初めてかもしれない。 物語の筋よりも「銀座」であることが重要なのだ。 働くのも銀座なら、住むのも銀座の裏通り。まだ薄汚れた安アパートがあったのだろう。 裏世界のギャングたちも、みんなコートを着て帽子をかぶり、おしゃれなのだ。 同じ日活映画でも、地方が舞台になると、いかにも地方のチンピラといった服装になるのとは大違い。 ヒロインが交通事故にあった後どうしていたのかは、全くわからない。 デパートで働くとなれば住民票ぐらい要求されるだろうが、まだ戦争を引きずっている時代で、その点はおおらかだったのだろうか。ヒロインの両親も空襲で死んでいるし。 主人公は、才能はあるのだが、実に身勝手な男だ。自分の都合しか考えていない。 だからこそ、当時としては「新人類」とでもいうべき新しい世代の象徴になれたのだろう。 気になるのは、男がみんなやたらとタバコを吸うこと。しかも、マッチ棒をところかまわず捨てる。 吸うのが当然、という時代だったのだろう。 DVDが出ている。銀座の恋の物語(1962) - goo 映画楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.08.12
コメント(0)
-
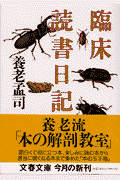
「臨床読書日記」 【養老孟司】
『臨床読書日記』。著者:養老孟司。出版社:文春文庫 『文學界』に連載された読書禄。専門分野の本はほとんど取り上げていない。 アメリカのミステリが好きらしく、「アメリカの推理小説、法廷小説、警官小説のたぐいは、一年に百冊の桁数をよむではないか。」(p130)という。 読んだことのない本ばかりが登場するが、それでも面白い。 随所に顔を出す著者の考えが面白いのである。 そういうところだけ集めて名言集ができる。 たとえば、・日本という社会は、ほんとうに意見や感想の多い国である。事実より意見や感想が多いのは、そのほうが、日本型共同体の生活にとって、重要だからであろう。(p15)・「思ふ存分に金をひつたくる」のあたりでは、ほとんど笑うほかはなかった。明治維新以来、現在に至るまで、一貫して追及されたわが国の戦略は、ほとんどこれだけだったかもしれないからである。(p17)・(日本の新聞は)記事に客観性がない。記者の主観で書いている。(中略)事実をただ平叙しないで、自分の意見を、なんとか潜り込ませようとする。(p36)・科学の話題が、本当はこういうふうに面白くなるものだというのは、よくわかっているのだが、それをつまらなくしているのは。この社会の常識である。科学の世界にも世間の常識はどんどん浸透する。面白いことをするよりは、役に立つことをする。・英語の新聞だけを一年読み続けて、突然日本語の新聞を読んだら、報道にこんな主観的表現をしていいのかと感じる。これは私だけの体験ではない。(p115)という具合。 脳の専門家であり、脳の働きの面から、「日本語を読むときの脳の使い方は、マンガを読むときと同じ使い方なのである。それだけのことである。それが日本のマンガ文化を裏づけている。」(p26)という。日本人がマンガ好きという現象だけをとりあげて批判しても説得力はないわけだ。 なお、「アルファベット型の文字と、いわゆる象形文字、世界にはこの二つの型の文字がある。」(p23)は疑問。アルファベット型の文字でももとは象形文字だったものもある。表音文字と表意文字という方がよい。
2004.08.11
コメント(0)
-

「江戸三〇〇藩最後の藩主 うちの殿さまは何をした?」 【八幡和郎】
江戸三〇〇藩最後の藩主 うちの殿さまは何をした? ( 著者: 八幡和郎 | 出版社: 光文社 ) 幕末から明治にかけて、武家社会でどのような動きがあったのか、各藩はどう対処したのか、すべての藩について述べている。 最近の江戸時代見直しブームの中で、地方分権が進んだ時代だったかのような印象も受けるが、筆者は、「江戸時代に、日本は藩という三〇〇の地方自治体に分かれていて、充実した地方分権が行われていたなどというのは、まったくの嘘である」(p34)と否定している。 著者は、明治維新を必然的なものとし、それに抵抗したのは無駄なことであり、無用の犠牲のもととなったと考えているようだ。 桑名藩のところで、「養子の殿さまが実兄に従い迷走したので藩士に多くの犠牲を出したのだが、殿さまの方は楽しく余生を送っているのだからいい気なものである。明治になって、尾張、会津、一橋、桑名の四兄弟で撮った写真が残っているが、私などこれを見ると腹立たしく感じる。」(p109)とまで書いている。 松平春嶽についてよく書いたものを読んだことがなかったが、この本では「幕末の名君である」(p133)と高く評価している。 奥羽戦争については、「状況をいちばんよく知る立場にあったはずの会津のわがままが、他藩を専科に巻き込んだ責任は大きいと感じる」(p206)そうだ。 会津藩士の行動については、「この不器用で、無用の犠牲を生んだ、しかし、ある意味で純粋な会津藩士の生き方」(p199)と一定の評価を与えているが、容保の資質については否定的だ。佐幕派を否定してもいいのだが、「新撰組などによる厳罰主義も、その是非はともかくとして、後難を考えれば危険な行動であった」(p200)というのには首を傾げる。「その是非はともかくとして」とはどういうことだ。是非など考えず、自分たちが犠牲にならないように立ち回るのが当然ということなのだろうか。 読んでいると、著者の立場が一貫しているのはわかる。いわば「損得史観」とでも言うべき考え方で、後のことを考えて損をしない生き方をするのが当然という立場で書かれている。 西国諸藩については、「西日本人的な現実主義でもって、各藩では新しい上青に敏感に反応し、朝敵とされたようなところも冷静な対処で大事にならないように立ち回るのに成功したといえるだろう。」(p334)と書いているのだが、こう書かれると、西日本の人はかえってうれしくないのでは。 著者はもともとは通産省の官僚だったひとなのだ。損得史観になるのは当然か。 明治に入ってからの各藩への処遇についてもふれている。「宮城県」や「福島県」など、江戸時代の有力な藩の名が県名にならなかったのは、明治政府が悪意でそうしたのではない、また、会津が斗南に移ることになったのも、会津自身が選んだことだ、という。しかし、猪苗代か斗南かどちらかを選べと迫ること自体、敗者への圧迫ではないのだろうか。 人材についてもかつての朝敵だった地域出身者が要職についている。 「自分の地元が発展しないのは戊辰戦争のせいだ」というのは通用しないということをくどいほどに述べている。 著者の考え方に疑問を感じる点もなくはないのだが、「おわりに」はいい。 まず「歴史小説は真実でない」という自明のことが理解されていないという。「著名な政治家すら、もっぱら司馬遼太郎などの小説を愛読書とし、その知識で歴史を語りがちである。」(p372)というのは、まさにその通り。「正しく歴史を知りたければ歴史小説はよまないほうがよい」とまで言い切る。 そう言われても、歴史そのものより歴史小説の方が面白いから読みたくなるんだが。 さて、この本は歴史を知ること以外に、観光案内として役に立つ。 各藩の城下町が今どうなっているか、かつての城跡がどうなっているかについて触れている。遺稿がほとんど残っていないところについてはそう書いているし、元のものと異なる城が建てられているところではそのことも指摘している。もちろん、ほめているものもある。たとえば、播磨龍野藩のところで、最後に「本丸御殿が立派に復元されていて一見の価値がある」(p315)と付け加えている。 観光資源としての価値を見いだしているのである。さすが通産省官僚。
2004.08.03
コメント(0)
-
南方熊楠
先日、NHKの「その時歴史が動いた」で南方熊楠を取り上げていた。 興味深かったのは、神社合祀、森林伐採が「国益」にかなうという理由で推進されていたこと。 現代でも、大義より「国益」第一の人たちがいる。 「国益にかなう」という理由でイラク出兵を是とする人たちは、明治時代に生まれていたら、神社合祀を押し進め、森を破壊したのだろう。 なお、熊楠の「神社合祀に関する意見」はここで読むことができる。
2004.08.02
コメント(0)
-
「雄呂血」 【監督・二川文太郎。1925年】
1925年 寿々喜多呂九平脚本・二川文太郎監督 オリジナル、つまり、板東妻三郎版。久しぶりに見た。BSで放送された活弁付きのもの。 声は入らないので、役者は身振りと表情だけで状況がわかるように演じなくてはならない。 心中を説明する字幕と活弁の助けはあるのだが、複雑な話なのに、表情だけでも何となくわかるくらいわかりやすい演技。 正義感の強い武士が、周囲に誤解されてならずもの呼ばわりされるようになり、人を助けようとしたのに、捕り方と大立ち回りをすることになる。主人公にも短慮なところはあるのだが。 初恋の女性とその夫を助けることはでき、その二人は陰ながら手を合わせる、ということで、観客には幾分かの救いは与えられるのだが、主人公には全くない。 善人面の悪人と、悪人に見らえてしまう善人。ああ、なんという運命のいたずらか。 それにしても、この映画、作られたのが大正14年。 映画というものが広まってまだそんなに時間はたっていないはずなのに、もうこんなに屈折のある映画を作っていたのだ。 いつの時代でも、すぐれた創作芸術家というのはいるのだ。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.07.24
コメント(0)
-
さすが産経新聞!
白骨温泉で、入浴剤を混ぜていたという事件についての、「産経新聞」の「産経抄」というコラム。「しかし、だからといってそれで健康を損なう害があるわけではない。和歌山県の白浜でオーストラリアから白砂を運んでいる例もある。涙ぐましい企業努力といっては言い過ぎだが、頭から湯気を立て目の色を変えてケシカラヌというほどのことではあるまい。」だって。 さすが産経新聞! 「嘘をついてはいけない」などという子供のようなことは言わないのだ。 金儲けのためなら多少のことは許される、というわけだ。
2004.07.15
コメント(0)
-

「免疫革命」 【安保徹】
免疫革命( 著者: 安保徹 | 出版社: 講談社インターナショナル) 新潟大学教授が書いた本。これまでの対症療法を否定し、人間が本来持っている治癒力を引き出すことを主張する。 著者の考えに従った治療での、進行性のガンも治癒率は高いそうだ。 免疫の仕組みや白血球とはどういうものかという専門的な説明が大部分なのだが、流し読みなのであまり頭に入らない。 そもそも病気の原因は何かというと、ストレスがもっとも大きな原因だという。 生活を改め、ストレスをなくしていくことで病気にかからなくなり、病気になっていても治癒していくのだそうだ。 かと思うと、現代人はリラックスしすぎていて病気になったりもするそうな。 何しろ「心のもち方が体調をつくる」(p266)ということで、クヨクヨするのがよくないというのだ。しかし、「そうか、クヨクヨするのがよくないのか、じゃあクヨクヨするのはやめよう」などといってクヨクヨしなくなれる人は、最初からクヨクヨしないだろう。 クヨクヨしまいと思ってもクヨクヨしてしまうからクヨクヨするのだ。 読んでいて強く感じるのは、「医学は宗教に近い」ということだ。 患者の精神への働きかけが重要なのである。 「民間療法でも、自分が治ると信じられるものに自己責任でとりくむことは、免疫活性につながります」(p133)という。信じる者は救われる、ということだ。
2004.07.14
コメント(0)
-
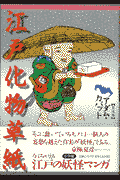
「江戸化物草紙」 【アダム・カバット】
江戸化物草紙(著者: アダム・カバット|出版社:小学館) 著者はアメリカ生まれの日本文学研究者。 15歳の時に英訳の『源氏物語』を読んで日本文学の虜になり、日本に留学、大学院の時から泉鏡花の幻想小説を専門に研究し、今では日本の大学の教授になっている。 江戸時代の、化け物を題材にした草双紙5種の紹介が中心。 草子の紙面を全部載せているので、全体のイメージがよく分かる。 取り上げられているのは、北尾政美(きたおまさよし)・画の『夭怪着到牒(ばけものちゃくとうちょう)』のほかはいずれも十返舎一九作の『妖怪一年草』(勝川春英・画)、『化物(ばけもの)の娵入(よめいり)』(勝川春英・画)、『信有奇怪会(たのみありばけもののまじわり)』(十返舎一九・画)、『化皮太鼓伝(わかのかわたいこでん)』(歌川国芳・画)。 どれも画が凝っていて面白い。『妖怪一年草』は人間界の年中行事のパロディになっていて、花見ならぬ「穴見」、お釈迦様の誕生を祝うのに対して「お逆さま」の誕生を祝い、月見をせずに「闇見」をするといった具合。十返舎一九の絵のうまいのにも驚く。 ほかに、山口昌男や小松和彦、京極夏彦らの考察もある。 ただ、京極夏彦は、「江戸化物草紙の妖怪画」で、柳田国男による、妖怪は零落した神の姿である、という定義を「現在でも妖怪を定義する条件として一般にも広く用いられている」と述べているが、これは小松和彦は否定しており、民俗学研究者に聞いても、現在でもそのまま通用しているわけではない、ということだった。
2004.07.11
コメント(0)
-
「トキワ荘の青春」 【監督・市川準。1996年】
1996年 カルチャア・パブリッシャーズ。監督・市川準。 恥ずかしながら、こういう映画があることを知らなかった。 トキワ荘については、ゆかりの人々が思い出を描いてまとめた「トキワ荘物語」も読んだし、藤子不二雄の「まんが道」も読んだ。 その昔、NHKで放送されたドキュメンタリーも見た。取り壊し前にかつての住人が顔を合わせるというもの。 しかし、それでもわかりにくい。主役の本木雅弘が寺田ヒロオだということはすぐわかる。見ていると、髪型も似せているし、顔も面長に見えてくる。 ところが、ほかの登場人物の区別が付きにくい。 最初に、事実に基づいたフィクションだと断っており、話の展開上、実話とは異なる部分も多い。それで面白くなるならそれでもいいのだが、面白くなっているとはいいがたい。 途中、アニメ一本でいくことにする、と言ってトキワ荘を去ったのは鈴木伸一のことだと思うが、この映画だけでは何がなんだかわからない。マンガから離れていった人もいる、ということを示すエピソードか。 売れて忙しくなっていく人もいる一方で、編集者に引導を渡されれる森安なおや、自ら筆を折る寺田ヒロオ。テーマは挫折した青春なのか。 1950年代(たぶん)の風景の写真や、曲をさかんに取り入れているところをみると、その時代を描きたかったのか。 あれこれ盛り込まず、寺田ヒロオのことだけ描くなり、寺田の目を通して見たほかの漫画家の姿を描くなり、焦点を絞ればよかったのではないか。 つげ義春が出てきたことだけは驚いた。交流があったとは知らなかった。 森安なおやのマンガが出てきたが、タケノコを背負った娘の話で、これは読んだことがある。ほかには、ロシアのスキー場の話しかしらないが、叙情的で、洗練された感性の持ち主だった。 思えば、寺田ヒロオや森安なおやは手塚治虫の影響は受けなかったのだろう。それが良かったのか悪かったのかはわからない。二人はもっと早く生まれていれば、漫画家生活が続いたのではないかと思う。 最後の場面で、寺田ヒロオが背番号ゼロの野球少年に「ありがとうございました」と礼を言われるのは、別れの言葉なのだ。 と、いろいろなことを考えながら見た。 不満に思うところは多いのだが、こういう映画を作るという志は買う。トキワ荘の青春(1996) - goo 映画楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2004.07.09
コメント(0)
-

「考証風流大名列伝」 【稲垣史生】
考証風流大名列伝(著者:稲垣史生|出版社:新潮文庫) 時代考証家の語る風流大名あれこれ。 「考証」とはついているが、厳密な時代考証によって実像を明らかにしようというのではなく、「こんな大名がいたんだよ」という軽い読み物にしてある。 小説仕立ての逸話紹介というところ。 鍋島藩の化け猫騒動などは、俗説を紹介し、実際のところを述べ、考証といえば考証だが、荒唐無稽な俗説を紹介することの方に筆を費やしている。 茶道誌「淡交」に連載したものだそうで、茶器や茶室に関わる話が多い。 しかし、序章で「茶室が密談には誂《あつら》え向きなので、政略は多くそこで練られたと聞いた。」「本書に出る大名の、多くが茶道の名手なのはそのためである。」(p15)と書いていながら、柳生宗矩の章では、戦国武将が茶道に励んだのは、「耽美《たんび》・平静の極致心理の希求からである。」「密議をこらし、或《ある》いは隠密《おんみつ》に密命を下す場所などとするのは見当はずれも甚だしい。」(p161)とはどういうことだ。 山本博文の解説は役に立つ。 史料の信憑性を綿密に考察するよりも、話が面白ければどんな史料でも積極的に活用しているという。 稲垣史生は杉浦日向子の師であり、三田村鳶魚の弟子である。 島津の「お由羅騒動」をもとにした直木三十五の「南国太平記」について、「江戸の権威三田村鳶魚翁《えんぎょおう》がその事実をつかみ、心を躍らせて書こうとしていた矢先、当時、日の出の勢いの作家直木三十五が、どこで取材したか、いち早く歴史小説として書き」(p209)とあるが、三田村鳶魚の「大衆文芸評判記」では、三田村鳶魚の発表した文章をもとに書いたように思われる。
2004.07.06
コメント(0)
-
「闇の左手」 【アーシュラ・K.ル・グイン】
闇の左手(著者: アーシュラ・K.ル・グイン /小尾芙佐 | 出版社:ハヤカワ文庫) 実に久しぶりにSFを読んだ。 有名な作品であることは知っていたし、家にはあったのだが、手に取る機会がなかった。 作者が構築した独自の未来史の一部で、最初は何が何だか分からなかったが、惑星「冬」の政治的な面については結局なんだかよく分からなかった。 こういうことを考えついて、破綻なく長編を書くということ自体が想像を絶する。
2004.07.05
コメント(0)
-

「スリーピー・ホロウ」 【監督・ティム・バートン。1999年】
1999年 アメリカ。監督・ティム・バートン。 たまたま家にあったビデオを巻き戻したらこれが録画されていたので見てみた。 最近全く洋画を見ないので監督も主演もどういう人なのか知らない。知っていたのはクリストファー・リーだけ。いやあ、久しぶりに見たなあ。 話は伝奇物だった。科学的・合理的な捜査を主張する若き捜査官が、スリーピー・ホロウという村での連続殺人事件捜査のために派遣されて……という話で、結局科学的な謎解きはないまま、首のない騎士の呪い、それを利用した魔女の仕業ということで、「合理的」に説明されてしまう。 謎は解明され、ヒロインは救われ、こうして科学的・合理的な19世紀を迎えたのだ、ということなのだが、現代には起こりえない事件なのだろうか。そんなことはないと思うのだが。 いつも曇り空で、森にはいると枯れ木ばかりで、しょっちゅう雷鳴がとどろき、おどろおどろしさ満載。雰囲気は出ているが暗い場面が多いのでわかりにくかったのが残念。 首なし騎士が斧をヒュンヒュン振り回すのが、カンフー映画のようだった。 ヒロインを演じた女優は小柄で、子供なのかと思ったが、一人前の娘であるらしい。顔立ちは役にぴったりだった。DVDが出ている。
2004.07.04
コメント(0)
-

「赤穂浪士」 【大仏次郎】
赤穂浪士(上)赤穂浪士(下) 忠臣蔵もののもはや古典的小説。 単純に、吉良を悪とし、恨みを晴らすというのではなく、武士が武士らしくなくなり、権力ばかりがものをいうようになってきた社会に対して異議を唱えるのが討ち入りの目的となっている。 「亡君が御一個として天下に示そうとなされた御異議を、一団体を作って全身全力を挙げて叩《たた》き付けるのである。」「われわれの存在そのものが、天下、御公儀に向けての反抗、大異議だからである」(下巻)という内蔵助の言葉がそれを物語っているが、あまりにもあからさまな書き方だ。 刃傷沙汰の直接の原因は、吉良が、賄賂の少ないのを恨んで内匠頭に非道な仕打ちをしたためということになっていて、強いて言えば吉良が悪役なのだが、上杉家の千坂、色部といった人物はお家を守るために身命を賭した人物として描かれ、善悪の対立というだけの話にはなっていない。 本筋と平行したところに、蜘蛛の陣十郎、堀田隼人、お仙という人物も登場させて話をふくらませ、武士同士の争いなど知ったことではないという価値観も描いているのだが、どうもそのせいで焦点がぼやけてしまっているように見える。 気になる寺坂吉右衛門は、吉良家へいく途中で姿を消した、と吉田忠左衛門が説明するだけ。この小説の中ではそれだけで済まされている。 書かれたのは1927年から翌年にかけてだそうで、おそらく新鮮な忠臣蔵だったのだろうが、今日から見ると、特に目新しいところはない。この小説をきっかけに新しい忠臣蔵がどんどん書かれ、世界が広がっているからだろう。 断絶騒動の時期に、堀部安兵衛が赤穂にいたように書かれているが、彼は江戸藩邸で働いたことしかなかったのでは。 武林唯七を「この支那人の子孫は無謀なくらい勇敢だった」(下巻)とある。彼が中国人の孫であることは、昔から有名だったらしい。 知らなかった言葉。 「骨灰である」粉みじんという意味。
2004.06.30
コメント(0)
-
「〈超〉読書法」 【小林信彦】
〈超〉読書法(著者:小林信彦|出版社:文春文庫) 「本は寝ころんで」の続き。 「週刊文春」以外のものに発表されたものも含む。 「本は寝ころんで」に続くのは第3部の「狂乱読書日記」なのだが、「本は寝ころんで」とは雰囲気が違う。 前作では「目が点になる」「点目」という表現が何度も出てきたが、これには1度しか出てこない。 そしてこちらは、怒りが根底にある。 書かれたのが1994年から1996年までで、阪神大震災、オウム真理教と、絶望的な気持ちになる事件が続いていたのである。 小林信彦は、「今」を記録することに熱心だ。 「文庫版のためのあとがき」に「阪神大震災とオウム真理教事件によって、読書人の気持が一変《いっぺん》するという時代の転換点を、数々の書評を通じて、リアルタイムで描いたことで、この本は一つの立場を主張できるように思いました。」(p292)と明確に書いている。 あの時期の「今」、あの時期に何が起こっていたかを記録した本なのである。 途中、ある人物を、やけに持ち上げているな、と思ったが、これについても、「文庫版のためのあとがき」で「判断ミス」と正直に書いている。
2004.06.10
コメント(0)
-
「ベスト・オブ・ドッキリチャンネル」 【森茉莉】
ベスト・オブ・ドッキリチャンネル(著者: 森茉莉 | 出版社:ちくま文庫) 森茉莉のテレビ評。1979年から1985年にかけて書かれたもの。 文庫に収められているのは一部なので、松田優作や小林旭について書いた文章があったら読んでみたいとは思うが、かといってそれをさがすために全集の文章全部に目を通す気はしない。 長嶋茂雄が森鴎外に似ているというのはどうかと思うが、森茉莉がいうのだからそうなのだろうか。また、当時は全く無名だった内藤剛志を高く評価しているのは慧眼である。 好き嫌いがはっきりしていて、それが基準なのだから、他人がどういおうが関係ない。自分の好みを押し通すだけ。悪く書かれた方は、反論のしようもない。 森茉莉の記憶違いを指摘したはがきが来たりすると、「私なぞに葉書を書く暇に一枚でも、半枚でも文章を書いて見たらどうだろう。そうすれば、文章を書く苦労が解るだろうから、他人(ひと)の書いたものに何(なん)のかのと文句をつけるようなことはしなくなるだろう。」(p279)などと書いている。これでいくと、俳優に「自分で演技をしてみれば、他人の演技に文句をつけるようなことはできなくなるはずだ」と言われたら言い返せないし、そもそも批評というものが成立しなくなってしまうはずなのだが、森茉莉はそういう世俗的な論理は超越してしまっているからこそ面白いのである。
2004.06.05
コメント(0)
-

「國語元年」 【井上ひさし】
NHKで1985年に放送されたドラマ「國語元年」を最近再放送で見直し、興味を持って読んでみた。 「国語事件殺人辞典」「花子さん」「國語元年」の三編収録。いずれも、言葉の虜になった人間の話。 最初の二編は、いずれもやや理がかちすぎ、説教くさくさえある。 解説(扇田昭彦)によると、作者自身も失敗作と思っているそうだ。 「國語元年」は、まずテレビ脚本を書き、それから舞台用に書き直してる。 テレビを見た時から、関西の言葉を話す人がいないな、と思っていたが、舞台用では、ちよ(テレビでは下町出身。島田歌穂だった)が、河内出身になっている。 テレビ版の主人公ふみは、舞台版では出戻り女ということになっていて、さらに語り手は修二郎に変わっている。 テレビ版も舞台版も、それぞれ面白い。 主人公は、伊沢修二に先立つこと七年、「小学唱歌集」を編んだばかりということになっている。それに収められている歌というのが、舞台版にはいろいろ出てくる。楽譜も載っている。南郷清之輔は実在の人物だったのかと思ったが、それらもすべて作者の創作。 言葉にとりつかれた人間は、幸福になれないという話ばかり。 客観的に、「全国統一話し言葉」を人為的に作り出そうとせず、自然に誕生するのを待て、と言う虎三郎の姿勢が印象に残る。(これは新潮文庫版の感想。現在は絶版。中央公論文庫で表題作を収めたものが出ている)國語元年(著者:井上ひさし|出版社:中公文庫)
2004.06.04
コメント(0)
-
「ハートブレイク・キッズ」 【小林信彦】
ハートブレイク・キッズ(著者:小林信彦|出版社:新潮文庫) 23歳のフリーライターを主人公とした小説。 全くの偶然から、高級マンションで若い男と一緒にいなくてはならなくなって……という出会いから3ヶ月間を描く。 非常に軽い書き方で、作者が顔を出して遊んでみたりしている。 途中、主人公の売り出そうという話があるところで、「あ、これは『極東セレナーデ』だ」と気づいたのだがほかの要素もあったのだ。 小森収という人が、解説を書いていて、「小林信彦の小説の様々な定跡のパッチワークみたいだ」と指摘している。まさにそうなのだ。さすがに解説を頼まれるだけのことはある。 『夢の砦』『紳士同盟』などの要素に気づかなかった。 主人公は映画評論家であり、登場人物が映画をめぐって話す場面もある。全体に映画を意識した小説で、おそらく、いろいろな映画の要素を意識して持ち込んでいるのだろう。冒頭もそうだし、偽物の麻薬捜査官かと思ったら本物だったなどというところもそう思わせる。 解説によると、これは女性雑誌「JJ」に連載されたものなのだそうだ。おお、小林信彦が「JJ」に連載を持っていたとは。 特に、主人公が、自分ではそうは思っていないけれど、回りから美人だと評価されている点など、言われてみると、女性読者を意識した書き方だ。 なお、ハートブレイクというのは失恋のことではなく、東京育ちの者の故郷喪失感というようなことのようだ。
2004.05.27
コメント(0)
-

「共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち」 【メロディ・ビーティ/村山久美子】
共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち(メロディ・ビーティ/村山久美子)共依存症 いつも他人に振りまわされる人たち(メロディ・ビーティ/村山久美子) 「共依存症」という言葉を初めて知った。 そもそも共依存症とは何か、というと、それがよくわからない。 他人の世話にとりつかれ、自分を失ってしまい、相手のために何かしているようでいながら実は相手を支配しようとしているという症状があるのだが、阿それは表面的なことで、本人が自覚していない心の奥底に潜む心理状態であるようだ。 薬物やアルコールの依存症の人と一緒に暮らしている人がなりやすい。 著者はかつて薬物依存症であり、自分も共依存症であり、自身の体験や、カウンセラーとなって見聞した事例を豊富にあげている。 各章の初めには、誰かの言葉がおかれているが、「感情を抑えるたびに、胃に点数が加算される……」(p227)は大いに同意できる。 共依存症から脱却するための具体的な方策もいろいろあるのだが、そのまま日本では通用しないのある。 例えば、「私たちは、神に依存することもできる。神は私たちのそばにいて、気にかけてくれる」(p188)、「怒りが恨みに転化する前に、聖職者などに話すのもいい」(p257)などがそうだ。 共依存症者は相手のために何かしようとしながら振りまわされ、自らを傷つけていく。考えてみると、学校の教師というのは、共依存症者であることを回りから強制されているようなものだ。 しかし、心が愛情で充たされているというわけではない。 「共依存症者のほとんどは、心の中で何百回も相手の葬式に参列しているはずである」(p266)ということだ。
2004.05.17
コメント(0)
-
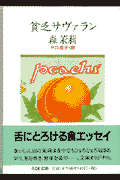
「貧乏サヴァラン」 【森茉莉】
貧乏サヴァラン(著者: 森茉莉 | 出版社: 筑摩書房・ちくま文庫) 食べ物に関するエッセイを集めたもので、森茉莉の、「上等なもの」への熱意にあふれている。育ちがいいだけあって、「上等なもの」=「高価なもの」ではないのがいい。 自分の主張をストレートに書いているのもあって、その内容には感心させられた。「だいたい、(粋)のスパルタ教育がなくなったということは、親たちに自信がなくなって、息子のやることも、服装(「なり」とルビ)も放任になったことなので、自信のない親は、口を出さないことが、理解のある親だとでも思っているより仕方がないのである。」(p59)「父親の言葉を丸呑みにしてそのまま、ぬうと育った私が賢い子供でないことは認めるが、貧乏が書かれていなくては、(生活がない)、という思想はおかしい。金のある生活も<生活>である。(p115)「彼は商館の小僧から一代で身代を築いた人であったが、そういう人にしては漢字も出来たし、字も立派であった。私の父とはすべてにくい違った考えの持主であったのは当然だが、それはかれの罪ではなく、秀れている方向が異なっていたのに過ぎない。」(p125) ただこの本、手紙を除いては、いつ書かれたものなのか明記していないのが残念だ。
2004.05.12
コメント(0)
-

「ムーミン谷の彗星」 【トーベ・ヤンソン /下村隆一】
ムーミン谷の彗星(著者:トーベ・ヤンソン/下村隆一|出版社:講談社文庫) 解説によると、1946年に書かれたものを1968年に書き改められたものだという。 シリーズとしてはムーミントロールたちがムーミン谷に住み着いてから最初の話ということだそうだ。 偶然ながら、「ムーミンパパの思い出」を先に読んだが、時間軸では、次にこれを読むのが妥当なわけだ。 スニフは最初から一緒にいて、冒険の途中でスナフキン、スノーク、スノークのおじょうさんに出逢う。 スナフキンはギターではなくハーモニカが得意で、すのーくのおじょうさんには名前はない。 冒険譚ではあるのだが、この夜の終わりが来るかもしれないという時に、どのような精神でそれを受け止めるのかという心理的な面に重点が置かれている。 「ムーミンパパの思い出」もそうだったが、哲学的なのだ。 北欧の児童文学ではこういう理屈っぽいのが一般的なのか、あるいは、特殊なシリーズだから人気があるのか。 そのあたりは全く分からない。 不思議な世界である。
2004.05.10
コメント(0)
-
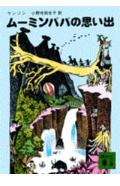
ムーミンパパの思い出 【トーベ・ヤンソン/小野寺百合子】
ムーミンパパの思い出(著者:トーベ・ヤンソン/小野寺百合子|出版社:講談社) 最近、スナフキンの父親のことを知って、確認のために読んでみた。 たしか、3度アニメ化されていて、最初の2度は同じ設定になっていた。これが印象に残っていて、ずいぶんムーミンの世界を誤解していたのだ。 3度目のテレビ東京でのアニメ化は原作に近かったようだ。 さて、スナフキンのことなのだが、原作のファンには常識なのだろうが、なんと、ミイの異父弟なのだ。スナフキンの父親はヨクサルという。ミイの父はでてこない。 最後まで読んでさらに驚いたのは、ヨクサルもミイの母親もまだ生きているのだ。冒険を続けていてずっと子どもたちをほったらかしにしているのだ。 北欧と日本の風土の違いというのはあるにせよ、登場人物の考え方は新鮮だ。 精神的自立を目指す話なのである。これ、童話ではあるが、大人のために書かれたのではないだろうか。
2004.05.07
コメント(0)
-
チャンバラもどき 【都筑道夫】
チャンバラもどき(著者:都筑道夫|出版社:文藝春秋) 「捕物帳もどき」の後を受ける連作短編集。 第1話で、前作とこれが、作者の祖父の速記記録をもとにしたものだった、ということにしている。第1話では作者が聞き手だが、第2話からは祖父が聞き手になっていて、祖父は登場しない。 聞き書きという体裁はもちろん「半七」を連想させる。 鞍馬天狗、座頭市、丹下左膳、木枯らし紋次郎、眠狂四郎、藤枝梅安となりきり、最後はまた鞍馬天狗が顔を出すという趣向。 老人の一人称で、昔のことを知らない人に話す、ということで、随時解説が入る。小説という形の、幕末から明治初期の江戸東京案内になっている。 解説(矢田省作)が、作者に直接聞いた話を色々紹介していて興味深く、役に立つ。いい解説だ。 都筑道夫が大佛次郎の文体模写で小説を書き始めたなど、全く知らなかった。こうなると、大佛次郎も読まなくてはならない。 作者は、これを書くために、「調べに調べて、どの一行も出典あり、というくらい、気を入れた」という。たしかに非常に濃厚で雑多な情報が詰め込んである小説で、それが多すぎるくらいなのだが、解説の結びにある作者の言葉で納得できた。「おまけ#[「おまけ」に傍点]のたくさんついているのが、好き」なのだそうだ。 まさにおまけたっぷりの小説である。
2004.05.06
コメント(0)
-
「生きている兵隊」 【石川達三】
生きている兵隊(伏字復元版) (著者:石川達三|出版社:中公文庫) 南京攻略戦前後を描く小説。 ノンフィクションではなく、あくまでも小説である。 主人公は階級の低い兵士たちであり、日本軍が組織的にどういうことをしたかということを描いているのではなく、戦場において、人間はどのように考え行動するのか、というのを描いている。 例えば、主要な登場人物の一人近藤の内面描写、「彼のインテリゼンスは戦場と妥協していたのである」(p88)、「近藤はまた彼の感受性の上にぴたりと蓋をしめて戦場と妥協した」(p98)などが印象に残る。 また、従軍僧が、出征前は、敵の戦死者も弔ってやるつもりだったのに、戦場ではその気になれず、積極的に中国人を殺す。 ことさら、日本軍の残虐行為を描こうとしているわけではなく、「これが現実だ」ということ淡々と描いており、おそらく実際にこうだったのだろうと思わせる内容なのだが、だからこそ軍にとっては都合が悪かったのだろう。 「倉田少尉の刀では敵の壕までとどかない」(p130)の「刀」は「力」の誤植か?
2004.04.26
コメント(0)
-

「こんな親が問題児をつくる」 【相部和男】
こんな親が問題児をつくる一万人の非行相談から( 著者:相部和男 | 出版社: 講談社文庫) 相談所を営む著者は、少年院で12年間カウンセリングをするうちに、少年院に入る前の段階で非行の火を消すべきだと考え、保護観察の分野に移り、25年の経験を経て、保護観察になる前の段階で手がけるべきだと思うようになったという。 「できたら少年院には入れたくないという持論をもっている」(p164)とも書いている。 何度も書かれているが、母乳ではなく人工栄養で育った子供は、母親との間に充分な関係が築かれず、それが原因になることがあるという。具体的な事例としてあげられる子供の多くが「人見知りをしなかった」という。また、非行に走った子どもと親が、決まったように飯粒をお椀に残すというのも興味深い。 子供の非行の原因となる親のタイプを、「手抜き型」「ホイホイガミガミ型」など12に分類しているが、ここまで分類されていると、どれにも当てはまらない親というのはいないのではないかと思う。 「子供のタメにならない教師」も10タイプあげているが、親が原因であることの方がずっと多い。 「カウンセリングの実際」という章もあるが、具体的なカウンセリング内容については触れていない。文章だけで、中途半端に受理解されるのを避けるためだろうか。 もっと一つ一つの事例を具体的に書いて欲しい所だが、それをしたのでは一冊にまとまらないだろう。 豊富な経験と知識のある人だとは思うのだが、「登校しないまま形だけは中学を卒業したが、自閉症となり、家から一歩も外に出ようとしなかった」(p132)という文章には驚いた。中学卒業後に自閉症になるわけがない。引きこもりと混同しているようだ。 親というものは、「字のとおり木の上に立って見ることのできる人が本当の親である」(p220)というのもいただけない。 サマーヒル学園の例が何度も出てくるが、タバコを吸い始めたばかりの子供は、自由な雰囲気の中におくと殆ど自らタバコを吸うことをやめるが、「タバコがすでに病みつきになっている者はやめられない」(p76)そうだ。依存症には対処できないわけだ。 非行に走った子供と直接会うことも多く、相手に信頼されているようだ。しかし、無条件に子供を肯定しているわけではない。非行から立ち直らせるということは、子供の今の状態を変える、ということであり、子供の側から言えば、今のあり方は良くない、と言われるということである。 それでも信頼されるためには、親近関係の維持が必要であり、親子の間ならなおさらその親近関係が必要なのだが、それが容易ではないからこそ非行が多いのだろう。
2004.04.20
コメント(0)
-
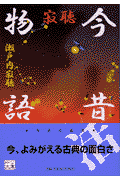
「寂聴今昔物語」 【瀬戸内寂聴】
寂聴今昔物語(著者:瀬戸内寂聴|出版社:中央公論新社) 瀬戸内寂聴が、『今昔物語』の中から面白いと思ったものを随意に口語訳したもの。 全体の構成などは特に考えていない。 全部で45話。 仏教説話もあるが、生々しい男女の関係を描いたものも多い。原典にそういうものが多いのか、それとも著者の好みか。 瀬戸内寂聴の本を初めて読んだが、文章は読みやすくわかりやすい。
2004.04.16
コメント(0)
-
「中国怪奇小説集」 【岡本綺堂】
中国怪奇小説集(著者:岡本綺堂|出版社:光文社文庫) 「青蛙堂奇談」(『影を踏まれた女』所収)と同じように、一人ずつ話すという趣向。 六朝の『捜神記』から清の『閲微草堂筆記』まで時代順に並ぶ。 岡本綺堂の広範な読書量の一端を窺うことができる。 岡本経一の解説によると、初版は1930年、総ルビ付で出たという。 その時のルビによるものなのか、「[門<虫]」を「みん」、「姚」を「ちょう」と読ませるなど、本来の音読みとは違う読みがほどこしてあるものが目立つ。 『夷堅志』の「餅を買う女」は、女の霊が水飴を買いに来る話とオダマキ型の合体。 『池北偶談』の「[口+斗]蛇」の[口+斗]は「叫」の誤植ではないだろうか。 『子不語』の「狗熊」の「虎[亡+おおざと]」の[亡+おおざと]は「邱」の誤植か。
2004.04.11
コメント(0)
-
「影を踏まれた女」 【岡本綺堂】
影を踏まれた女(者:岡本綺堂|出版社:光文社・光文社文庫) 「青蛙堂鬼談」の12編と、「近代異妖編」3編。 当代の話もあれば江戸時代の話もある。 もっとも怖いのは「異妖編」の「寺町の竹藪」。合理的な説明は全くない。 それがかえってこわい。「あたし、もうみんなと遊ばないのよ。」という台詞が何を意味するのか全く説明されず、勝手にあれこれ想像するしかないのだが、その台詞の向こうに深い闇が想像されるのだ。 印象に残ったこと。 「彼は土地の新聞社に知人があるのを幸いに、○○教の講師兄妹のあいだに不倫の関係があるということをまことしやかに報告した。」(p56)「不倫」という語の本来の用法である。 「満洲の土人は薬をめったに飲んだことがないので」(p120) 「満州」ではなく、ちゃんと「満洲」になっている。またここの「土人」も、「土地の人」という本来の意味で用いられている。 「この時代には江戸のなごりで、御新造《ごしんぞ》という詞《ことば》がまだ用いられていました。それは奥さんの次で、おかみさんの上です。」(p169) これは「黄いろい紙」という話の一部だが、初出は大正14年。その頃には、「奥さん」「御新造」「おかみさん」の順位がわからなくなっていたわけだ。 「むじなをその芸妓になそらえて予譲《よじょう》の衣《きぬ》というような心持ちであったのか」(p177) これも「黄いろい紙」。山本周五郎の「よじょう」のもとにもなっている予譲の故事、明治大正には広く知れ渡っていたらしい。たしか、下町の神社にその故事を記したものがあったはず。それでなじんでいたのだろう。 「むかしから丸年《まるどし》の者は歯並みがいいので笛吹に適しているとかいう俗説があるが、この喜兵衛も二月生れの丸年であるせいか、笛を吹くことはなかなか上手で」(p184)の「丸年」、意味を調べたが分からなかった。 「七尺《しちしゃく》去って師の影を踏まずなどと支那でもいう。」(p263)を見て、「三尺」の間違いではと思って調べたら、もとは七尺だったようだ。 「おせきがとつかわ[#「とつかわ」に傍点]と店を出たのは」(p265)の「とつかわ」が分からなかったが、「あわてて」という意味だった。
2004.04.07
コメント(0)
-
「南方熊楠 森羅万象を見つめた少年」 【飯倉照平】
南方熊楠 森羅万象を見つめた少年( 著者: 飯倉照平 | 出版社: 岩波書店・岩波ジュニア新書) 熊楠の青年期を中心にした伝記。 著者の文章は平易ながら、内容や引用は高度なので、中学3年以上ぐらいでないと理解できないのではないか。 読むと、常に出口の見えない情況にあってもがき苦しんでいたようだ。 絵も字もうまく、勉強に努力を惜しまない。しかし、努力の結果として自分が何を残せるのか、何を残したいのか、それが自分にも分からなかったのではないか。常にイライラした気持ちでいたのだろう。 熊楠はなんとローラ・インガルス・ワイルダー(大草原シリーズ)と同い年だが、同じ時代とは思えないほど違う世界に住んでいる。盲人用の大学もあったほどだから、都市部では教育環境は整っていたはずだが、熊楠の少年時代の方が、ローラの少女時代よりも教育環境は恵まれている
2004.04.02
コメント(0)
-
「白髪鬼」 【岡本綺堂】
白髪鬼 岡本綺堂怪談集(著者:岡本綺堂|出版社:光文社文庫) 「青蛙堂奇談」(『影を踏まれた女』所収)に続く怪異譚集。 当代の話もあれば江戸時代の話もある。 このうち「西瓜」は、ほかの何かで読んだ記憶がある。 怪談なので合理的な説明はされない。 どの話も、偶然と言えば偶然、必然と言えば必然と言えるような事が起こるのだが、どうやってこういう話を考え出したのだろうか。 中国の筆記あたりに着想を得た物もあるのだろうが、岡本綺堂の筆にかかると、いずれも、日本に土着した物語となる。 もっとも印象に残ったのは表題作よりも「妖婆」だ。やはり江戸時代物がいい。 解説は都築道夫で、これがまたよく出来ている。 実作者としての経験からの解釈あり、考証あり。 なんとなく読み流してしまった所も、都築道夫は気に留めていて、「停車場の少女」に出てくる「電報をかける」という表現、「白髪鬼」で「酉の市」と書いて「とりのまち」と読ませている所、「一の酉」ではなく「初酉」となっているところなど、岡本綺堂が江戸人であることを示す例としている。 ところで、本の題としては「白髪鬼」、副題が「岡本綺堂怪談集」となっているが、目次の前のページには、「近代異妖編」とある。もとはその書名で出ていたらしい。
2004.03.31
コメント(0)
-

「あかね空」 【山本一力】
あかね空(著者:山本一力|出版社:文藝春秋) 書き下ろし長編で、直木賞受賞作。 去年(2003年)にテレビドラマ化されたのを見た。 妹おきみの視点から描いたもので、安心してみていられるできだった。 永吉が赤井英和、おふみが浅野ゆう子だった。 小説を読んでみると、テレビではよくわからなかったところもよくわかる。(あたりまえだ) 傳蔵は、テレビでは迷子になったということだったが、迷子札があったはずなのに、変だなと思っていたら、原作ではさらわれていたのだ。これなら理解で期す。 永吉が江戸に出てきたところから、子供たちだけで店をやっていくところまでの三十年近くの話。 人情話ではあるのだが、同じ出来事が家族それぞれにとって違う意味を持っており、互いに誤解しあっていることで葛藤が生まれる。 悪いやつというのが一人しか出てこない。 文章は変に凝ったところはなく、非常に読みやすい。 一気に読んだ。 どんなものを着ているか、ということをその都度ちゃんと書いているが、読むこちらに知識がないので絵としては浮かばない。 ドラマの配役を当てはめて読んでいた。 江戸の風俗の解説などはないのがかえっていい。 「六ツ(午前六時)」「五尺五寸(百六十六センチ)」「一寸(約三センチ)」というように、時間と長さにだけ説明がついている。
2004.03.23
コメント(0)
-

「はじめての言語学」 【黒田竜之助】
はじめての言語学(著者:黒田竜之助|出版社:講談社) 言語学を一つの科目としてとらえ、どのようなものなのか入り口から中をのぞくという姿勢の入門書。 おもしろく読んだが、さて、言語学とは何か、ということがわかったかというとそうはいかない。 印象に残ったのは、著者の姿勢として、批判するときは、名を出さないこと。 「蒲焼き」の語源を民間語源で説明してしまっていることを取り上げ、「アルファベット」の説明では「見事なまでに役に立たない」とやっつけているのは、明らかに岩波書店の「広辞苑」だと思われるのだが、「某社の大型国語辞典」としか書かない。 「びっくり! 日本語の起源」(p196)では、大野晋のタミル語起源説を取り上げているが、ここでも「国語学の大御所」というだけで名前は出していない。 「信じられないような音韻対応を発明し、言語学を勉強した人はみんなビックリしたが、ご本人は自信満々であった。」ということだが、著者は1964年生まれだから、発表された時はまだ中学生ぐらいだろう。これは後で知ったことだろう。 興味深いのは、「真面目なインド言語学者が何人か反論していた。でもこういう真面目な意見は面白くないのか、マスコミはあまり取り上げなかった。」というところ。 問題はこれなのだ。旧石器時代の遺跡の捏造がずいぶん大きく取り上げられたが、あれだって、ずっと前から疑義を提示していた学者がいたのに、それをとりあげず、新発見、大発見と持ち上げてきた人達がいたから捏造が続いたのだ。マスコミが捏造を誘発した面があるだろう。 以前は見ていたが、「外国語学習メカニズムについて特集したのを見たら、その荒唐無稽《こうとうむけい》さにあきれかえってしまった」(p197)という番組は「特命リサーチ」だろうが、これも番組名は出ない。 「《母国語認識》などという不正確な見出しをつけていたのはうちで購読しているM新聞だけであった。そんな判断もできない人が新聞記事を書いているとは真に不思議である。」(p239) ここでは「毎日新聞だろうな」と察しは付く書き方をしている。 気になるのはその後の部分だ。 人は誰でも、自分の専門にかかわることなら、不正確な書き方がしてあれば「変だ」と思うが、それ以外は新聞に書いてあることを鵜呑みにしてしまうのではないだろうか。とにかく、新聞は疑ってかかるに越したことはない。 「《ハングル語》というのもわたしには抵抗がある。ハングルとは文字の名称である。日本語のことを《ヒラガナ語》と呼ばないように、韓国・朝鮮語にそういう名称を与えるのは変だと思う。」(p32) 言語学者でなくたって変だと思う。なぜ「ハングル語」がまかり通っているのか不思議だ。こういうことろは声を大にしてもらいたい。 一方、言語の名称と言うことに関しては、「言語に名称を与えるのは政治と歴史であり、言語学では判断できない。」(p177)と明確に述べている。事はそう簡単ではないのだ。
2004.03.20
コメント(0)
-
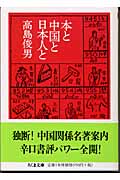
「本と中国と日本人と」 【高島俊男】
本と中国と日本人と(著者:高島俊男|出版社:ちくま文庫) その昔、雑誌「東方」に連載されたものをもとにまとめた本で、『独断! 中国関係名著案内』と重なる部分もある。 書評であったり、著者のエピソードを語るものであったりして、語り口に工夫があり、いずれもおもしろく読める。自分も読んでみようという気になるのも多いが、読む気にならないのもある。それでも、紹介する文章自体はおもしろいのだが、著者の芸のすぐれていることがわかる。 読者に対して親切な作りで、各編の末尾に、読者が知らないのではないかと思うようなことがらについて、【ことば、ことがら】というコーナーをつくって説明している。 例えば、「花形記者から権助に」(p134)の「権助】とは何だろうと思っていると、ちゃんと説明している。 あとがきによると、中国が変化したので内容が時機遅れになったものは割愛したそうだが、そういうのも全部収録し、詳細な索引を付けて出して欲しいものだ。 日本において、どのように中国が語られていたか、という貴重な記録になったはずだ。
2004.03.18
コメント(0)
-
「パレアナの青春」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
パレアナの青春( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社:角川文庫 )" 『少女パレアナ』の続編。 ベタな通俗小説になってしまっているのだが、それでも面白い。 それまで全く登場していなかった一家と関わりを持ったり、途中であっという間に六年たって、パレアナが二十歳になってしまったりして、物語はどんどん進む。 続編というよりも、これは『少女パレアナ』と分けられない、一つになったものなのだ。 おそらく、作者は、『少女パレアナ』を書いているときから、最後にはこうなる、というのが、頭にあったのだろう。 『少女パレアナ』に比べれば、伏線のはり方が甘いが、それでも、一体どうやって決着をつけるのだろう、という興味で読み進まずにはいられなかった。 訳文で気づいたこと二つ。 「おまえの舌(した)にはついていかれないよ」(p37)。初版は1962年。「いかれない」という表現は今は珍しくない。訳した当時は不自然ではなかったのだろうか。裕次郎の「赤いハンカチ」に「いかれたものを」という歌詞があり、聞くたびに引っかかるものを感じていたのだが、どうやら、広く使われていたらしい。 「患家先(かんかさき)」(p194)。初めて見た言葉だ。患者の家、という意味なのだが、英和辞典にはこういう言葉が載っているのだろうか。
2004.03.17
コメント(0)
-

「少女パレアナ」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
少女パレアナ改版( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社: 角川文庫) 子どもの頃に、子ども向けの文学全集で読んだことがあったが、たまたま家にあったのでちゃんとしたものを読んでみた。 大人の目で読んでみると、大衆小説のつぼを心得ていて、話の展開が実にうまい。 貧困から裕福へ、かたくなな親族、と、『小公子』や『秘密の花園』などのパターンを踏襲し、主人公の明るさで周囲のものが救われていく、というハッピー・エンド。叔母の昔の恋人は誰か、など、あとで考えると、ちゃんと伏線が張ってあったのに、ついだまされてしまった。 作者は、子どもの時から作家になりたいと思っていた、という人ではないそうだが、物語とはどういうものかがよく分かっている人だったのだろう。 出版されたのは1913年で、すでに開拓時代ではないのだが、西部と東部というのはだいぶ異なるらしい。それもまた、主人公とまわりの人物とのギャップになっているようだが、そこはよく分からない。 読んでいて、何かに似ている、と感じたが、何に似ているかといえば、『非凡なる凡人』と、『富士に立つ影』の「主人公編」の主人公だ。特に、物語としてもおもしろさから言えば、『富士に立つ影』に似ている。 こういうものを読むたびに感じるのは、翻訳の難しさだ。 児童文学、ということで、ですます調で訳してあるのだが、「懇望(こんもう)していた」などという言葉が出てきたりする。 また、訳されたのが40年近く前であり、言葉遣いが随分違う。
2004.03.15
コメント(0)
-
「漱石の思い出」 【夏目鏡子/松岡譲】
漱石の思い出(著者:夏目鏡子/松岡譲|出版社:角川文庫) たしか十年以上前に一度読んでいるのだが、ほとんど忘れてしまっている。 また、その間にいろいろほかの本を読んでいるので、ほかで得た知識とあいまって「ほう」と思うこともあった。 成立過程は巻末の「編録者の言葉」に詳しい。 漱石の死後十年がたち、晩年に漱石のもとに出入りしていた松岡譲が、未亡人に話を聞いてまとめたもの。 「家庭における漱石」「妻の見た漱石」、つまり、作家としてではなく、家庭人としての実像である。 漱石に幻想を抱いている人からは批判もされたらしい。 親しく出入りしていながら、漱石の一面しか知らなかった人も多かったろう。 解説で、次男の夏目伸六が、小宮豊隆の『夏目漱石』を評して、「著者のこの消化不良と頭の悪さとが」と述べている。 家庭での姿のみ見ていたものとしては、はたから見ていたものの書くものには、腹立たしい思いさえしたことだろう。 関係のない話だが、この次男の伸六という名、「俺たちの旅」のグス六と同じだが、「俺たちの旅」はそれを知っていてあの名をつけたのだろうか。 結婚前の逸話として、漱石が、ありもしない縁談を断ったと言って怒った話(p10)が語られている。今なら、人格障害か、統合失調症というところだ。 ロンドン時代も、「だれかが監視しているような追跡しているような、悪口をいっているような気が」(pp108)したそうだ。 脳を病んでいる夫・父を持つ家族も大変だが、本人も苦しかったろう。 泣きやまない末子に、「皆にいじめられ、そのうえ父からもかわいがられなかった」(p309)自分を重ね合わせてあやすところなどは哀れである。 以下、印象に残ったところ。 「新し橋のところの丸木|利陽《りよう》で写真を撮《と》って送り」(p19) 新橋の間違いかと思ったら「新し橋」という地名があったのだ。 夫人は朝寝坊で「時々朝のご飯もたべさせないで学校へ出したような例も少なくありませんでした。」(p34)明治でも朝寝坊の人はいたのだ。 「藤島さんののが」(p45)、「また例ののが」(p139)はそれぞれ、今なら、「藤島さんのが」「例のが」というところ。 「一人ののが二人ふえて」(p329)というのもある。「いったい夏目は生家のものに対しては、まず情愛がないと申してもよかったでしょう。あるものは軽蔑《けいべつ》と反感ぐらいのもので」(p47)と、漱石の長じてからの態度を語ってから、それまでの生い立ちが語られる。 漱石の一番上の兄に、樋口一葉との縁談があった。(p51) 漱石は、徴兵免除のため一時、北海道に籍を移していたことがあった。(p63) もし軍隊にいたらそれこそ発狂してどうにもならない状態になっていたのではないだろうか。 鈴木三重吉はもとは子供嫌いだった。(p192) 修善寺での大病の時、ワラブトン(p225)に寝ていた。 三三九度の練習で「座敷に二人が向かい合って坐っていると」(p271)とある。今なら横に並ぶところだが、江戸の風習がまだ残っていたようだ。 大阪での入院中「便所が西洋式になっておりまして、水で流すようになってるのですが」(p275)西洋式がそのまま持ち込まれていた世界もあったのだ。 大阪から帰った後痔の手術をしているが、「翌年になってもまだ膿《のう》が出たりして」(p277)ということで、痔瘻だったようだ。 「駄洒落《だじゃれ》や皮肉をかっ飛ばして」(p279)の「かっ飛ばす」は江戸弁か。 通夜僧が「何でもかっかじめるような話をいたします」(p285)の「かっかじめる」も江戸弁か。 「菊五郎はたしか長谷川時雨《はせがわしぐれ》さんがお連れになって」(p323)。ほう、長谷川時雨とも交際があったのか。江戸の人同士、話が合ったのかもしれない。森茉莉は確か長谷川時雨から何かもらったことがあったはず。文人同士、広くつきあった人なのだろう。 教師としての漱石。「おれはできない生徒にはどこの学校でも仇敵《かたき》のように思われたもんだが、そのかわりできる生徒からは非常にうけがよかったもんだ」(p340)
2004.03.12
コメント(0)
-

「恋人たちの森」 【森茉莉】
恋人たちの森(著者: 森茉莉 | 出版社:新潮文庫) 初めて森茉莉の小説を読んだ。 文章は凝りに凝っていて軽く読み流すことはできない。 点の打ち方も独特で、「変わった科目の教授だったということで、あった。」「肖像が自分に物を言うような気分のすることもあるように、なった。」「激しいものを潜めている顔を、していた。」という具合。 「ボッチチェリの扉」「恋人たちの森」「枯葉の寝床」「日曜日には僕は行かない」の4編。 「ボッチチェリの扉」はおそらく実体験がいくらかまじっているのではないかと思われる、ある家族を描く小説。由里《ユリア》が部屋を借りている家の家族にまつわる話で、由里は女性に対して厳しい目を向けている。同性だからこそ敏感に感じる女の嫌な面も描いているのだが、文章が凝っているので嫌みを感じさせない。 「恋人たちの森」以下3編は、中年にさしかかった男(文筆業や大学教師で金持ち)と、まだ少年らしさをのこしている若者の恋愛。 「恋人たちの森」は年上の男の死によって世界は終わり、「枯葉の寝床」は二人の死によって永遠を手に入れる。「日曜日には僕は行かない」は、女の死によって二人の世界が続く。 3編とも、金には不自由しておらず、高級品を買える境遇で、洋風の生活をし、身なりにも気を遣う。しかし、「愛」というのはそれとは次元の異なるところで価値があるわけだ。 これはユーミンの世界ではないか。 彼女の歌う「純愛」は、「金で買える物はすべて手に入れられる状態における愛」だと感じるのだが、一脈通じる物がある。 何を着ているか、どこで食事をするか、どんなタバコを吸っているか、ということを詳しく書くことによって、世界にリアリティがもたらされており、風俗小説とも言えるだろう。 男同士の恋愛というものには全く興味がないので、正直なところ理解できない小説集だった。 「僕じゃ少し役不足だね」(p102)は、誤用なのか、本来の意味で使っているのか。
2004.03.08
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1 >











