2004年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
学習障害児、養護学級で授業も
という記事が目にとまった。 数年前にADHDを知り、調べてみたら、自分が子供の頃にぴたりと当てはまる。「ああ、俺はADHDだったのか!」と思ったが、その後いろいろ調べたり、インターネットで専門のサイトを見たりしているうちに、簡単にそう思いこんではいけないと思うようになった。 世の中、自分がADHDだと思いたがる人(たいてい大人)が多い。ほんとうにADHDで困っている人からすれば不愉快だろう。 さて、この記事だが、「埼玉県教育局は29日、学習障害(LD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)のある小中学校の児童・生徒が、教科ごとに通常学級で学ぶか、養護学級や養護学校で学ぶかを選択できる制度を、今年度中にも実施する方針を固めた。」という。 障害を持つ子供が普通学級に通学することが理想のように考える人たちは反発するだろう。 しかし、専門家のいない学校に通って、適切な支援を受けられないままいるのと、養護学校などで必要な支援が受けられるのと、どちらが本人の将来にとって有益だろう。 普通学級に通って、なおかつ専門家の支援が受けられるようにすればいい、という人もいるだろうが、現実には無理な話だ。障害を持つ子供と同じ数だけの専門家がいるはずはない。 普通学級にいても、学校にいる間はまだいい。 卒業してからどうなるのだ。就職は? 今は、何かというと「学力低下」を問題にし、学校の成績がよくないのは悪いことだ、と考える人が多い。そんな情況の中で普通学級にいるのは、学習障害児にとっては苦痛だろう。 「障害があっても、子供を養護学校へ行かせるのはよくない」と考える人もいるらしい。そういう人は、養護学校への差別意識を持っているのではないだろうか。 高校進学で考えてみればいい。普通科の高校に行く人もいれば、商業高校へ行く人もいれば、工業高校へ行く人もいる。そもそも高校へ行かない人もいる。 それと同じように、養護学校へ行く人もいれば、そうでない人もいると考えることはできないのだろうか。
2004.09.30
コメント(0)
-

現代文の朗読術入門 あなたを磨く話しことば 【杉沢陽太郎】
現代文の朗読術入門(著者:杉沢陽太郎|出版社:日本放送出版協会) 著者は元NHKアナウンサー。 入門書ではあるが、声の出し方のような基本の部分については、あまり触れていない。 そういった個々の訓練から朗読に入っていくのではなく、朗読の全体像から個々の問題に入っていくのである。 第一章「数から意味へ」、第二章「音のことばとしての日本語」は文章論、日本語論になっている。 現代文は、「明治以後に作られた、欧米語を移し植えたような文体」(p17)ということで、日常会話の言葉とは別に、文章語としての現代語があり、それを朗読するには、非常に意識的な作業を行わなくてはならないのだ。わかりやすく読めばいいというものではない。 第六章「『伊豆の踊子』を読む」では、いきなり「朗読は演奏である」という小見出しが立ててあり、演出が必要であるということが、具体的な例とともに示される。 もちろん、人によって演出は異なるわけで、同じ作品でも朗読者によって違う味わいを持つことになる。 実際にNHKのアナウンサーが解説・朗読したCD付き。 「あとがき」に、吉川英治は、徳川無声による『宮本武蔵』の朗読がいやで、「あれは私の作品ではない」と言っていたというエピソードが、朗読の難しさを語っている。
2004.09.29
コメント(0)
-

谷原章介(伊東甲子太郎)って
この人、この「新選組!」で初めて見た人だと思っていたが、最近になって、前に見たことがあるのを思い出した。 「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」だ。田中美里と、口ではいろいろ言いながら協力する天才発明家の役。 なんだ、あの人だったのか。全然印象が違う。 「新選組!」では嫌なやつ。若いのにうまい。こういう嫌なやつを下手な役者がやってはつまらなくなる。 敵役は達者な役者でなくては困るのだ。 公式サイトを見たら、素顔の(当たり前だ)写真があった。
2004.09.28
コメント(0)
-
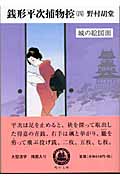
銭形平次捕物控(四) 城の絵図面 【野村胡堂】
銭形平次捕物控(4)城の絵図面(著者:野村胡堂|出版社:嶋中文庫) 「くるい咲き」「兵糧丸秘聞」「人魚の死」「美女を洗い出す」「城の絵図面」「黒い巾着」「大盗懺悔」「十手の道」「どんど焼き」「十七の娘」の十編。 銭形平次を四冊続けて読むとどっぷりその世界にはまりこんでしまう。全く関係のないテレビを見ていても、その辺から八五郎が出てくるんじゃないかと思ってしまう。 話は、江戸初期に設定されている初期のものが多い。また、めずらしく武家がらみのものが目立つ。 なんと言ってもこのシリーズのいいのは、巻末に野村胡堂の随筆が収録されていることだ。 この巻では「捕物小説について」。とは言いながら、探偵小説全体について述べている。 『探偵小説の「偵」の字が制限文字なら、「たんてい小説」と仮名で書いても宜いではないか」とあるが、当用漢字のせいで「推理小説」となったのではないことは、小林信彦が書いている。しかし、そう信じている人が多かったのだ。
2004.09.27
コメント(0)
-
土方・ケア・小島
25日の後楽園大会。・土方 第3試合で、3カウントをとられた土方がリングに残っていたところを見ると、おそらく石川の登場は予告されていたことなのだろう。 決着をつけるはずが2連敗。心中忸怩たるものがあるだろ。 石川は何のために来たのか。「全日の」土方と試合→和解→共闘とつながっていくのか。 元気出してくれ。明るい土方が見たい。・ケア 最後、TAKAの持ち込んだ椅子は有効だったのかなあ。 結局、椅子には当たらなかったようなように見えた。 ハワイにおいてきたはずの三冠ベルトをかざして見せ、次のチャンピオンは俺だ、ということだが、川田の壁は厚い。しかし、川田だけが頂点にいるのではリング上の物語が続かない。 こちらは先が読めない。・小島 とにかく、川田の次は小島が全日を引っ張って行かなくてはならないのだ。 川田とは正反対の陽性のレスラーだが、内面は悩みがちなタイプではなかろうか。 もし、ケアが三冠ベルトを巻くことになったら、挑戦者として名乗りを上げるだろう。 しかし、三冠戦の前に、最強タッグリーグがある。パートナーは? カズ? 常に新しいテーマを観客に提示して物語を作って行かなくてはならないのだから、プロレスラーは大変だ。 平井や荒谷も、もっと積極的に物語り作りに加わっていって欲しい。平井と奥村の抗争なんて、全日ファン好みだった。ああいうのでもいいから。
2004.09.26
コメント(0)
-
全日本プロレスの試合順
9月25日の後楽園大会。 ほう! と思ったのが試合順。 武藤社長の試合が休憩前だった。 タッグマッチで、タッグ・パートナーは西村。対戦相手はLOVEマシーンズ。(これ、考えてみると嵐改めLOVE・マシーン・ストーム以外は新日育ち) この顔合わせで休憩前なのだ。 武藤社長、この路線を続けていけば、かつての馬場さんの域に達することもできるかも知れない。 武藤社長の固定ファンは多い。引退などされては営業に響く。休憩前に「明るく楽しく新しい」プロレスを提供するポジションへの移行を考えているのではないだろうか。 もう一つ。 健介ファミリーの中嶋の試合が、健介のシングルマッチの後に組まれていた。天龍と組むから、ということもあるのだろうが、驚いた。健介の試合に、すぐ後に試合する中嶋がセコンドにつくわけにはいかないし、中嶋の試合のセコンドが、試合したばかりの健介というわけにもいかない。 中嶋独り立ちへの一里塚。 メインは小島のシングルマッチ。 川田も言っていたように、次の世代で全日を背負って立つのは小島しかいない。武藤社長が、将来を見越しての試合順だろう。 ここで内部から、「次期エースは小島じゃない、俺だ!」というレスラーが出てくると盛り上がるのだが。 大会の観戦記は、ここ。まとまり次第順次アップ。
2004.09.25
コメント(0)
-

「緋牡丹博徒 お竜参上」 【監督・加藤泰。1970年】
藤純子(今は寺島純子。寺島しのぶのお母さん)主演のシリーズもの。名前は聞いていたが見るのは初めて。シリーズ第6作で、第1作が1968年。調べたら、このあたりはほとんど毎月のように出演映画が封切られている。看板女優だったのだ。 さて、映画の方は、というと、おそらく大正と思われる時代を舞台にした任侠もの。 浅草六区で芝居をしている一座と、六区を仕切る親分(嵐寛寿郎)率いる鉄砲一家が善玉。探していた娘(自分の娘ではない)と出会い、その親分のもとに身を寄せるが、浅草をねらう鮫洲一家(親分は安部徹)が魔の手を伸ばしてきて……。 藤純子が若くてきれいなのはもちろん、菅原文太も若い。 礼をする時に、藤純子は、正座して頭だけ深く下げる(深くうなずくような感じ)のが不思議だった。腰から折るような礼はしないのだ。当時の風俗だったのか、彼女だけそういう特徴を持たせたのか。 みんなやくざ者ではあるが、不正は許さないという正義感なのだ。こういう映画をみてやくざにあこがれる人もいただろうが、むしろ、暴力団の無法を抑制する効果があったのではないだろうか。不正をはたらくやくざって、とにかくかっこわるい、という世界なのだ。 さて、気になる時代設定だが、凌雲閣がある、ということは1923年の関東大震災以前。冒頭に救世軍が出てくるので、1985年以後ということになる。 なお、この映画のDVDが出るそうだ。
2004.09.24
コメント(0)
-

「忍者ハットリくん・ザ・ムービー」 【監督・鈴木雅之。2004年】
どんなものかと見に行ったら結構よかった。 実写版の忍者ものって久しぶりだ。 オープニングは、洋画風。SHINGO KATORIとローマ字で出る。 ケンイチとの出会いのところはさらりと流して、甲賀の悪者との対決がメイン。 よく考えるとケンイチって、ハットリくんがきたから危ない目にあっちゃうんだけど、そんなことは見ている間は考えない。 ケムマキがいい奴なので驚いた。 目の見えないミドリという少女の設定はよく考えたものだ。目が見えないのだから、姿を隠しているハットリくんの存在に気づくし、ケムマキがハットリくんと同じにおいだと感じるのも自然。 ハットリくんは故郷へ帰るからいいけど、みんなの前で忍者であることを明かしてしまったケムマキはどうするんだろう。今の仕事を続けるわけにもいかないだろうし。 ハットリくんは姿をさらすが、ケムマキはみんなに見えないところで……というふうにしてやらなくちゃ。 見ていて、東映で作った「伊賀野カバ丸」を思い出した。こちらもアイドル映画だったけど、JAC総出演で、コミカルでありながら、東映の忍者の伝統を受け継いでいた。 この「ハットリくん」は東宝のアイドル映画の伝統を受け継ぐものだ。 こういうのでいいから、実写の忍者ものをもっと作ってくれないかなあ。
2004.09.23
コメント(0)
-

2010年
1984年。アメリカ。監督・ピーター・ハイアムズ 原作は言わずと知れたアーサー・C・クラーク。 この映画を見るのは2度目。 2度目にしてやっと話の全貌が理解できた。 そういうことだったのか。なぜHALが混乱したのか説明されている。“発見能力を与えられている”というよりは、“人間的な感性を与えられている”のだ。 自分が犠牲になることを承知の上でディスカバリー号を発進させるところなど、泣かせる。 映画では、「すばらしいこと」がおこって、国同士の争いなんかどうでもよくなるわけだが、現実はそうなりそうもない。ソ連は2010年を待たずして崩壊してしまったが、アメリカは次々に敵視する相手を見つけている。 クラークの「地球幼年期の終わり」のように、人類の理解を超える存在に触れるようなことがあれば、地球は一つになれるだろうか。 おそらくそうはなるまい。「国益」ばかりにとらわれ、他国を出し抜こうとしたり、大国に追随してみたりと、醜い争いが展開されるような気がする。 映画は非常に大がかりなおとぎ話だ。 DVDも出ている。
2004.09.22
コメント(0)
-
堺雅人(「新選組!」の山南敬助)
この人のことは、「新選組!」を見るまで全く知らなかった。 いつも微笑をたたえた知性的な表情で、温厚そうな口調。 山南にぴったりだと思ってみていた。 微笑を絶やさないのは、そういう役なので意識してそうしているのだとおもっていた。 ところが、日曜日の相撲中継にゲストで呼ばれていたのをみたら、なんと、もともとそういう顔立ちなのだ。 山南を演じているときは、見た目では年齢不詳だったが、普段の姿はいかにも若い役者、という感じで長めの髪。 調べたら1973年生まれだそうだ。 細身に見えていたが、切腹の場面で着物をはだけたのを見たら、鍛錬された筋肉質の体だった。そこでまた感心。 「新選組!」は、主な隊士に、いかにもそれらしい役者を当てていて、演じていると言うより、その役者そのままで入り込んでいる。 近藤に香取慎吾を、というのは脚本家の意向だそうだが、ほかのキャストにも脚本家の強い意向が働いているのではないだろうか。 役者に合わせて書いているのではないかと思われるほどはまっている。それでいながら、実際の新選組の隊士も、きっとこういう人だったのだろうと思わせるところがたいしたもの。
2004.09.21
コメント(0)
-
やっぱりアキラはかっこいい!
アキラ(と言っても大友克洋ではない。小林旭)を取り上げるというので、昨日、「いつみても波瀾万丈」を見た。 前後編2回に分けての放送だったのだが、残念ながら前編は見逃した。 見ての結論。 やっぱりアキラはかっこいい! いい時もあれば悪い時もあり、苦労もしてきたのに、明るい表情でさらりと語る。さすが「銀幕のスター」だ。 「渡り鳥」シリーズと「流れ者」シリーズはほとんど見た。歌も好きだ。 アキラの歌には名曲が数々ある。第1は何だろう。「ギターを持った渡り鳥」「さすらい」「口笛の流れる港町」などもいいが、「恋の山手線」はアキラにしか歌えない歌だ。「アキラのダンチョネ節」「アキラのズンドコ節」も捨てがたい。 「熱き心に」はいい歌ではあるが、ひっかかるものを感じる。「唇に触れもせず」など、今でも一人の旅を続ける渡り鳥が、浅丘ルリ子を思っているのかな、と思わせるのだが、どうも阿久悠らしさが出過ぎていてすんなり入ってこない。 作曲した大瀧詠一はアキラの大ファンだそうで、曲はなじんでいる。 懐かしくて、アキラのCDをレンタルショップで借りてきた。「小林旭全曲集」というタイトルだが、「自動車ショー歌」は入っているのに「恋の山手線」が入っていないのは残念。
2004.09.20
コメント(0)
-
照英はプロ野球スト「大正解」
ということだ。 照英といえば「水戸黄門」の鬼若。今年に入って、「新選組!」の島田魁。 どちらも根っからの善人の役。この人、体は大きいが、顔は見るからに善人そうで、「これじゃあ、悪役はできないな」と思わせる。 プロ野球のストライキについて「大正解」とは思い切ってよく言った。 芸能生活を考えれば、どの企業がスポンサーになるかわからないのだから、「残念です」とかなんとか適当なことを言ってすます方が無難なはずだが、そうしなかった。 偉いぞ! 今回のストライキ、三大紙の社説を読み比べると、読売だけが選手を悪く言っている。そりゃそうだわな。経営者側なんだもの。経営者のごり押しが通用しないような世の中になっては困るわけだ。 全国紙ではないが、「労働組合」などと名前が付くとそれだけで毛嫌いしそうな産経までもが選手に同情的。 「球団を手放したい」という企業がいて、「球団を経営したい」という企業がいるのだから、何の問題もなく各リーグ六チームで来季もやっていけそうなのに、いったい何が障害になるというのだろう。 オーナー側には、球団数を無理矢理にでも減らし、数年後にはなにかしようという陰謀がある、と思われて当然。 陰でこそこそ動いてる連中は、責任を感じるべし。
2004.09.19
コメント(0)
-
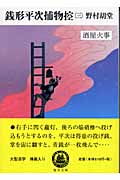
銭形平次捕物控(三)酒屋火事 【野村胡堂】
銭形平次捕物控(三)酒屋火事 (著者:野村胡堂|出版社:嶋中文庫) 「欄干の死骸」「酒屋火事」「血潮の浴槽」「地獄から来た男」「傀儡《くぐつ》名臣」「謎の鍵穴」「南蛮秘法箋」「竹光の殺人」「死の矢文」「人肌地蔵」 三巻目だが、まだまだ初期の作も入っているらしい。「南蛮秘法箋」は、由井正雪の乱の記憶も新しい時期、という設定。 小説として練りが足りないような作もあったが、いずれも「銭形平次」として楽しめる。 作者は救いのない話は嫌いだということだが、どうしても殺人が出てきてしまう。また、犯行の動機は男女の横恋慕が多い。やはり恐ろしいのは人の心だ。 巻末の「随筆銭形平次」は「捕物小説は楽し」。この随筆が収録されていることでこの文庫の価値が高まっている。 はっきりと、『私の「銭形平次捕物控」は「半七捕物帳」に刺戟《しげき》されて書いたもので」と書いてある。「岡本綺堂先生」とも書いている。半七を評して、「探偵小説としては淡いものだが、江戸時代の情緒を描いていったあの背景は素晴らしく、芸術品としても、かなり高いものだと信じている」とある。まさにその通りである。 半七に着想を得ながらも、探偵小説の面を重視し、また、江戸情緒よりも、あえて犯人を捕らえずに済ませてしまうような人間味を重視したところに銭形平次の独創性があり、価値があるのだ。
2004.09.18
コメント(0)
-
モモが結婚、来年1・7で現役引退
おお! 中西百重が寿引退! 倒産状態の全女を支え、キッスの世界というユニットでCDを出したりして人気を集めていたが、「昨年7月に全日本女子を辞めたときから、引き際を考えていた。もう体がボロボロで100%の試合が披露できなくなったから」ということだそうだ。 女子プロレスはハードだ。10年ぐらい前に、アジャ・コングは「いつか死人が出ると思いながらやっている」と言っていたが、その言葉通り、試合中のダメージがもとでなくなったレスラーもいる。 体が軽い分、首から上にダメージを与える技を使いやすく、危険だ、ということを馳浩も指摘していた。 百重も限界を超えて戦っていたのだろう。 納見佳代じゃなくて中西というところが意外だったが、寿引退大いに結構。 引退した後にもいろいろな道があるというところを見せて欲しい。 格闘家になるもよし、タレントになるもよし、飲食店経営でもいい。引退したら終わりではない。そこから新しい人生が始まるのだ。
2004.09.17
コメント(0)
-
魔界倶楽部解体
ということだそうだ。 正直なところ、新日には全く興味がないので魔界倶楽部そのものはどうでもいい。 気になるのは長井の動向だ。最後まで魔界倶楽部のメンバーだったが、これで所属グループはなくなった。 これも、全日復帰への布石だろうか。そうあってほしい。 「俺だけの王道」の興行で言った「夢の続き」を見せてくれ!
2004.09.16
コメント(0)
-
四十肩
痛いのである。 最初になったのは3年前の夏。 8月の後半、右肩に違和感があるなと思っていたが、9月に入って動かすと痛むようになってきた。 ちょっと動かしても痛い。腕が上がらない。 噂に聞く四十肩かと整形外科に行くと、首や肩のレントゲンをとった上で、四十肩とのお墨付きをもらった。(正式な病名はナントカ炎といっていた) 貼り薬をもらい、時間がたつのを待つしかない。 痛いからと言って動かさないでいると固まってしまう、というので、無理矢理にでも動かすように、と言われたが、左手で右手を持ち上げただけでも激痛が走って動けなくなるくらい痛い。 冬になっても治らない。冷えるとよけい痛い。 寝ていて、寝返りを打っただけでも激痛で目が覚めてしまうくらい。 炎症を起こす物質が間接にたまっているのだ、ということで、医者は、ビールなら一日2本まで、日本酒なら2合までは飲んでいいという。血行をよくするため。 しかし、そんなに飲んでいては肝臓が持つまい。 長いこと苦しんだが3年目になってだいぶ軽くなってきた。 やれやれと思っていたら、なんと今度は左肩が痛み出した。これまた四十肩だ。 右肩の経験があるので、できるだけ動かすようにしている。炎症を起こす物質を散らさなくては。 さて、四十肩の原因だが、『免疫革命』という本を読んだら、体を横にして寝る人がいるが、下になっている方が四十肩になるとあった。 言われてみると、ずっと右を下にして寝ていた。 右肩が四十肩になってからは、それをかばうために無意識のうちに左側を下にして寝ていたのかも知れない。 意識して仰向けでねるようにしているが、仰向けでも左手の角度によっては肩が痛む。 先は長い。
2004.09.15
コメント(0)
-

銭形平次捕物控(二) 八人芸の女 【野村胡堂】
銭形平次捕物控(2)八人芸の女 (著者:野村胡堂|出版社:嶋中文庫) 挿し絵入りで、「原画所在不明のため印刷物より復刻しました」とのことだ。オリジナルの姿を復元しようと、これも良心的だ。 「庚申横丁」「一枚の文銭」「大村兵庫の眼玉」「綾吉殺し」「招く骸骨」「赤い紐」「二服の薬」「八人芸の女」「雪の足跡」「お民の死」の十編。このうち「赤い紐」はほかの本で読んだ記憶がある。 初期の作品らしく、寛文二年(一六六二)というと「ツイ一昨年」という表現(p74)というのがある。 いずれも面白いが、ミステリとしては、謎解きに必要な材料が読者に提供されているとはいいがたい、という面で欠点はある。しかし、そんな欠点なぞそんのその。面白い。 では、何が面白いのか? これが難しい。 江戸情緒というのは確かに大きな魅力の一つだ。しかし、「半七捕物帖」とは異なる。 岡本綺堂はいわば江戸の残滓のなかで育った人間であり、野村胡堂は後から江戸を学んだ人間である。しかし、江戸を外から見た野村胡堂の方が、誰にでもわかる江戸らしさを描き出しているようだ。 あとは何か。 平次と八五郎の人間性だろう。ハードボイルドとは遠いところにいる、濡れた完成の持ち主。事件の解決よりも、関係者の抱える問題の解決を重視する。 では、結局、人情話のおもしろさなのかというとそうでもない。 これは、「銭形平次」というジャンルの小説なのである。
2004.09.14
コメント(0)
-

ヒデキ、壮絶闘病記「あきらめない-脳梗塞からの挑戦-」
実は、私の弟も40歳前に脳梗塞で入院したことがある。 幸い、奇跡的に回復し、ほとんど後遺症もないようだ。原因はタバコ。ほかに考えられない。仕事がきつかったのかと思ったが、本人に聞いたらそれほどでもなかったらしい。 入院して数日後に見舞いにいった。その時は、点滴を付けたまま歩き回ったり、普通に話しをしたりできたが、入院の翌日はそんなことはできなかったらしい。 話をして驚いたのが、意識が戻るとタバコが吸いたくなったということ。吸っていいかどうか看護婦さんに聞いてきてくれ、と奥さんに言ったそうだ。完全なニコチン依存症である。 若かったので経過もよく、その病院ではそこまで回復できたのは史上二人目、というくらい回復できた。 おかげでタバコもやめることができたが、血液をサラサラにする薬というのを今でも飲み続けている。 悪いことは言わない。タバコをお吸いのみなさん、やめておきなさい。あなたとあなたの家族のためです。(記事はここ)
2004.09.13
コメント(0)
-

「禁断の惑星」 【監督: フレッド・マクラウド・ウィルコックス。1956年】
SF映画の傑作として名前だけ知っていたが、初めて見た。 なるほど、こういうものだったのか。 他の惑星での冒険という面もあり、露出の多い服装の美女ありで、古典SFのお約束的面を持ちながら、潜在意識の生み出した怪物という、非情に観念的なものを取り上げている。 どうしてこういうことを考えついたのだろう。 話の内容もさることながら、宇宙船やロボットのロビー、秘密施設の構造など、そのデザインが公正に与えた影響は大きい。秘密施設の入り口の構造など、単純な開閉ではなく、複数の扉が回転するようにかみ合ったりする。 デザインのほか、最も後世に影響を与えたのは音ではないだろうか。 キューンキューンという不安定な響き、これが強く印象に残る。 今でも、宇宙というとこういう音が流れるのは、この映画の影響ではないかと思う。 そりゃあ、視覚的には、古くさい感じはする。しかし、1956年にここまで到達していたことが、後のSF映画につながっていくわけだ。少なくとも内容は少しも古びていない。テーマの普遍性、永遠性の面では最高峰だ。 DVDも出ている。
2004.09.12
コメント(0)
-
ウルトラマンのイデ隊員は今
あの人は今こうしている ベテラン俳優の二瓶正也さんという記事。 あれ? 何年か前にも取り上げてなかったっけ。 言わずと知れた「ウルトラマン」のイデ隊員。 天才エンジニアで発明家で大活躍だったが、屈折したキャラクターだったのだ。 「ウー」が登場した回(第30話「まぼろしの雪山」)では、「自分も早くに母親を亡くした」と、みなしごの少女に同情していた。 ピグモンが、ジェロニモの危機を教えに来てくれた時(第37話「小さな英雄」)では、「どうせウルトラマンが来てくれるんだ」と投げやりになってしまい、ピグモンの死を招いてしまった。 もう一つ。「ジャミラ」が登場した回(第23話「故郷は地球」)。 実験の失敗を隠すために見殺しにされた科学者の末路を知り、その墓碑を無言で見下ろす。 画面はイデ隊員の顔のアップで、画面の外から「イデ」と隊員たちが呼ぶ声が聞こえてくるラストシーン。 なお、この時のジャミラの墓碑にかかれた年で、「ウルトラマン」は未来の話として作られていたことがわかるのだ。たしか没年が1996年だったと思う。 二瓶さんを最後に見たのは、「劇場版ウルトラマンコスモス」だった。 元気そうでなにより。わたしもうれしい。
2004.09.11
コメント(2)
-
小説上杉鷹山(下) 【童門冬二】
小説上杉鷹山(下) (著者:童門冬二|出版社:学陽書房)(読んだのは単行本。1983.6.15初版。1994.3.10四十四刷) 改革には、成功もあれば失敗もある。だいぶ時間がたっているようなのだが、改革が始まってから何年たったのかはわかりにくい。 具体的に財政がどれぐらい好転したのかもわからない。 二組の男女の縁談はどうなったのかも結局わからない。 あくまでも藩主に従う者もいれば、よどんだ世界にはまっていってしまう者もいる。その点は現実的だが、これは史実に基づいているわけだ。 書きぶりは、上巻に続いて、現代的な意味を持たせようとする。「現代風にいえば、勤務をフレックス・タイムにし、管理系の机仕事人間に、生産現場に行って、現場体験をしろ、かれらの苦しみを知れ、ということだ。」(p170)という具合。 同じ時期を描いても、小説としては、長谷川伸の「上杉太平記」の方が面白かったな、と不満を感じながら読んだのだが、「あとがき」を読んで評価が変わった。 「この小説の母体は、山形新聞に連載したものである。最初百五十回とう約束が、倍近く延びた。地元の人の関心が高かったためだという。」とある。 なるほど、そうだったのか。地元の人のために書かれたのならこれでいい。基本的な知識を持ち、一定のイメージを描いている読者を相手にして書いているのだから、くだくだしい説明はいらないのだ。 とくに米沢の人たちは、この本が売れて喜んだことだろう。 気になった表記。 「とんでもございません」(p75)は誤り。「とんでもない」の「ない」は「せつない」「はかない」の「ない」と同じなので「ございません」に置き換えることはできない。 「関東平野を横断し、福島から、米沢へ急行した。」(p213)江戸から北上したのを「横断」とは妙。南北方向なので「縦断」。 (松平定信の寛政の改革と、水野忠邦による天保の改革は失敗したが)「鷹山は、その轍を踏まなかった。」(p260)「轍を踏む」は「戦陣と同じ過ちを犯す」ということ。寛政の改革も天保の改革も鷹山の改革より後なので、この表現は使えない。
2004.09.10
コメント(0)
-
少しはお役に立てるかと
「PC小知識」というページを作っています。 私自身が困った経験に基づく事例がほとんど。 お役に立てれば幸いです。
2004.09.09
コメント(0)
-

小説上杉鷹山(上) 【童門冬二】
小説上杉鷹山(上) ( 著者: 童門冬二 | 出版社: 学陽書房 ) 一時ずいぶん話題になった本。今頃になって読んだ。 今は文庫しか出ていないらしいが、単行本で読んだ。 財政破綻状態にあり、藩を返上してはどうかという話まで出ている状態で、養子として迎えられ十七歳で藩主になった上杉治憲が、家臣の心をつかみ、藩を立て直していく過程が描かれている。 文章は読みやすくわかりやすい。 しかし、読んでいて、「はたしてこういうのを小説というのか」という気持ちが起こってくる。もちろん小説であることに間違いはない。しかし、登場人物が何かするたびに、それにいちいち現代的な意味を持たせるのが気になる。 例えば、「農政の専門家を核にして、それぞれところを得させた特別作業班《プロジェクト・チーム》を発足させようというのである。」(p27)、「いまの経営行動のパターンに合わせれば、……」(p47)という具合。 治憲が取り立てた改革チームと、頑迷な守旧派の対立、改革の象徴である炭火が広がっていくさまなど、わかりやすいことこの上ない。みすずと佐藤文四郎の恋もお約束。 おそらく、これを読む人は現代のビジネス社会を生き抜くのに役に立つと思って読むのだろう。作者も明らかにそれを意図している。 作者は長く東京都の職員として行政に携わった人だそうだ。「組織」というものについてはいろいろな経験を積んでいることだろう。しかし、この小説が現代において、実利的な面で役に立つのか、というと疑問を感じる。作者もまた、現在の東京都の経済的破綻を招いたうちの一人であるはず。 やはり、小説は小説として楽しみたいものだ。 表現で気になったところ。 「隗《かい》(いいだした人)より実行せよ」(p47)。誤りではないが、本来の意味とはずれがある。 「ことばが的を得ていることを告げた。」(p137)。「的を射る」の誤り。 NHKでドラマ化されたもののビデオが出ている。
2004.09.08
コメント(0)
-
って言うか
以前から気になっていた「って言うか」。 何か話があって、それに対して「って言うか」だろう、と思っていた。 ところが今日になって、自分もそれと同じようなことを口にしていたのに気づいた。 「そう言えば」だ。 何が「そう言えば」だ。それまでの話題と全く関係のないことを言い出す時に使っているではないか。 「って言うか」と同じだ。
2004.09.07
コメント(0)
-
発達障害者:「支援法」臨時国会で提案へ
早期発見、国の責務--超党派議連という記事があった。 おそらく、発達障害の子を持つ親からの働きかけや、海外での支援教育のあり方の報道などのちからがあってのことだろうと思う。 テレビで紹介されたのを見るだけでは、どこまで欧米では成功しているのかはわからない。 失敗例は取り上げないだろうし。 ただ、興味深く思うのは、発達障害を持った子が、顔も名前も出して取材に応じ、番組の中で取り上げられていることだ。 日本の、ある教育法で成功している小学校がテレビで紹介されたとき、クラスの一人の子だけ顔にぼかしが入っていたことがあった。 ほかの子は顔を出しているのに、その子だけぼかしが入っているので、かえって目立ってしまう。おそらく、何らかの障害を持った子なので、保護者の意向でそうしたのではないかと思った。 記事によると、「乳幼児健診などによる早期発見」をめざすということだが、現実には、障害を持っていると診断されても、それを受け入れず、支援を拒否してしまう保護者が多いのではないだろうか。 障害を持っていても、養護学校ではなく地域の普通学校に通っている、という話が時々新聞で紹介される。障害を持っていることをほかの子供や保護者に明らかにしたうえでそうしているのだろう。それを否定する気はない。 ただ、そうすることは、一方では養護学校を否定することにつながっていくのではないかと思う。 将来就職することを考えると、養護学校に通った方がいい、という話も聞く。 世の中には様々な障害がある。 もっと広く認知され、隠す必要がなくなって欲しい。支援を受けるのは特別なことではないという考えが広まれば、支援が受けやすくなるだろう。
2004.09.06
コメント(0)
-
土方隆司
神奈川・横浜文化体育館 また石川に敗れてしまったか。残念。本人も悔しいだろう。 二人の因縁は、土方がバトラーツを離れ、他団体に参戦しようとした時、石川が邪魔をしたことから始まっているらしい。 俺だけの王道で決着をつけるはずだったのだが、大出血のためレフェリーストップで負けになってしまった。 今回こそ決着をつけるはずだったのに。 土方が全日にフリー参戦し始めた頃から、応援していた。 キックの音がよく響くのがいい。タッグマッチでコーナーに控えている時には盛んに声を出して盛り上げていた。 いろいろ大変で落ち込んでいた時、『王道30周年ファン感謝ツアー』・後楽園ホールを見に行ったら、試合前に登場して入団の挨拶。それで気分がよくなり、試合も好試合が続いて明るい気分になったものだった。 負けるな土方! これからだ!
2004.09.05
コメント(0)
-
ディスレクシア
という言葉を初めて知った。最近NHK教育テレビで放送された番組を見て。 文字の認識がうまくできず、読み書き、計算に困難をきたすのだという。 イギリスでは早くからその存在に気付いていて、ディスレクシア専門の教育方法も研究・実戦されているということだった。 番組では、ディスレクシアの子供がどのような教育を受けているか紹介されていた。 こういう番組を見ると、自分のことを考える。 私は小学校の1年生の時、カタカナの「ミ」を左右反対に書いていたのを覚えている。いわゆる鏡文字だ。 自分の書いた「ミ」と、他の人の書いた「ミ」がどこか違う、ということは感じるのだが、どこが違うのか長い間気がつかなかった。 また、ずっと悪筆で苦労している。「丁寧に書きなさい」とずいぶんいわれたが、精一杯丁寧に書いても、他の人のような字にはならないのだ。 ペン習字も3回やってみた。中学生の時、大学生の時、30歳過ぎてから。しかし、それで悪筆が治ることはなかった。 大人になってからは、これは脳の機能の問題なのだろうと考えるようになった。 LD(学習障害)というものが話題になり、「悪筆はLDの一つで、書字障害というのだ」とことを聞き、「ああ、そうだったのか」と腑に落ちた。 特に30歳を過ぎてからペン習字に挑戦したとき、「どうやら、字形の認識に問題があるらしいぞ」と自分で気付いた点もあった。 だからといって悪筆が治るわけではない。困ることにかわりはない。 話を番組に戻すと、ディスレクシアの有名人も紹介されていた。俳優のトム・クルーズがそうで、彼は脚本を読んで理解することができず、他の人に読んでもらって覚えたという。 見終わって、LDとどこが違うのだろうと思って調べたところ、このページによると、「ディスレクシアは医学用語であり、特異的学習障害は教育用語である。」ということだった。 イギリスでは人口の10%、日本では4%がディスレクシアだということで、なぜ差があるのか、番組では説明がなかった。漢字も仮名も使う日本語の方が認識しやすいのだろうか。 2日の読売新聞に、字読めない「失読症」、英語圏と漢字圏で原因部位に差という記事があった。これと関係するのだろうか。
2004.09.04
コメント(0)
-
黒木瞳と岡田准一
黒木瞳&岡田准一主演純愛映画パリで撮影 | Excite エキサイト : ニュース 黒木瞳と岡田准一って、何年か前、「おやじぃ」というドラマで親子だった。父親は田村正和で、姉が広末涼子。 うーむ。こういのって、演じる人の気持ちとしてはどうなんだろう。 まあ、歌舞伎だと、実の親子で、親子だけでなく、夫婦や恋人や仇同士を演じたりするわけで、プロの俳優ならちゃんと気持ちは切り替えられるのだろう。 知人に、21歳の男がいる。茶髪で耳にピアスをして、外見はまるっきりそのへんのあんちゃん。芸能人の話になったとき、その男が「岡田准一はかっこいいと思う」と言っていた。 岡田准一は、へえ、そうなんだ。男からも「かっこいい」と思われるアイドルであるらしい。-輾転反側-
2004.09.03
コメント(0)
-
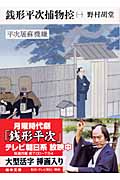
銭形平次捕物控(一) 平次屠蘇機嫌 【野村胡堂】
銭形平次捕物控(1) 平次屠蘇機嫌 ( 著者: 野村胡堂 | 出版社: 嶋中書店 ) 十編収録。このうち「花見の仇討」は読んだ記憶があるはずなのだが肝心の所は何も覚えていなかった。 事件があり、謎解きがありと、おきまりの捕物帖なのだが、人情話の面に重点が置かれている。犯人が明らかになっても平次が許してしまう話もある。 近代の法治ではそれではまずいわけだが、いわば情治の世界なのである。 この本、今年の四月にテレビ朝日でテレビ化されたのを出版されたもの。全十巻で毎月一巻ずつ出すと、帯にある。 正直なところ、今までこの出版社の存在を知らなかった。 底本を明記してあり、巻末に「随筆銭形平次」を収録してあるあたり、本を出す姿勢はなかなかいい。 こういう本は、ある時に買っておかないとすぐに消えてしまう。全巻そろえたいものだ。 「攪乱」に「こうらん」とルビが振ってある(p264)あたり、底本を尊重しているのだろう。ただし、ところどころにでてくる「大跛者」という語にはルビがない。おそらく底本ではルビがついているのではないかと思う。 こういうところを変えてしまったりせず、巻末で「不適当な語句・表現が見られますが、本書が成立した時代的背景と著作の内容とに鑑み、また著者他界のことでもあり、原文のままといたしました」と断っている。 断らなくても、「銭形平次」を読むような人なら察することとは思うが、断りを入れるのがルールのようになっているのだろう。
2004.09.02
コメント(0)
-
ワープロさんありがとう
31日に放送された(再放送らしい)「プロジェクトX」、「運命の最終テスト」~ワープロ・日本語に挑んだ若者たち~ を見た。 東芝が最初に開発し、小型の普及機も出していた。三遊亭円窓がCMに出ていて、古典落語を記録するのに使っているということだった。 普及期が出始めた頃からワープロが欲しくてたまらなかった。しかし、手が出ない。40万以上したのではないか。 結局、2年近く待って、シャープの「書院」を買った。文字が、32ドットできれいだったのが決め手。 30万円近くしたと思う。今ではとうてい手が出ない。 その後、早い時期からパソコンを使うようになり今日に至っているが、後発のメーカーが東芝が切り開いた道を歩いてきた成果を存分に利用させてもらっている。 東芝がワープロや日本語変換のシステムで特許をとって独占していたら、ここまで普及するにはもっと時間がかかっていたかもしれない。 番組の中で少し触れられていたが、ワープロの開発に並ぶ東芝の功績はノート型パソコンの開発である。軽量小型で、デスクトップ並みの性能。ダイナブックの初期の方の発表会を見に行って、小さいのにロータスが入っているというので驚いた。 これも、CPU、キーボード、液晶画面の一体型を意匠登録でもして他社がまねできないようにしていたら、今日のPC普及はなかったのではないかと思う。 正直なところ、PC関連で東芝の製品を買って使ったことはない。 しかし、感謝はしている。 ありがとう、東芝!-輾転反側-
2004.09.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 185
- (2025-11-16 21:29:24)
-
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3
- (2025-11-14 13:43:41)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-







