2014年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
若菜 上 -72-
大殿がそのお二方の様子をご覧になって、「上達部の座が、ひどく端近ではありませんか。こちらへいらっしゃい」と、東の対の南面にお入りになりましたので、皆そちらにおいでになります。兵部卿の宮も居ずまいをお直しになりおん物語をなさいます。上達部以下の殿上人は簀子の間に円座を敷いて座ります。若い人々は、格式ばったものではありませんが、様々な箱の蓋に椿餅、梨、柑子のような物を取り交ぜてありますのをふざけながら食べます。上達部は魚介の干物でお酒を召し上がります。衛門の督はひどく思いに沈み、ややもすると桜の花に目を止めて思いに耽っています。大将は事情を知っていますので、『御簾からほのかに見たおん方を思い出しているのであろう』と思っていらっしゃいます。『だが一方ではひどく端近にいらした事を、はしたないとも思うであろうな。それにしても、こちらのおん方ならばそのように不用心な事はなさるまい。さればこそ父上は、世間から言われるほど宮様をご寵愛なさらないのかもしれぬ』と合点がいきますので、『やはり、内にも外にも心配りが足りなく幼稚なのは、可愛らしいようではあるけれど安心できないものだな』と、見下げた気持ちになるのでした。衛門の督は、そのような女三宮の欠点に考えが及びませんでした。思いがけず物の隙間からほのかに宮様を拝見したにつけても、『以前から思いこがれていた気持ちが叶うかもしれぬ』と嬉しくてたまらず、女三宮の事が頭から離れないのでした。
May 30, 2014
-
若菜 上 -71-
几帳の脇から少し奥に入った所に、袿姿で立っていらっしゃる女君がいます。階から西へ二間の東端ですので、遮る物もなくすっかり見えるのでした。表着は紅梅襲でしょうか、その下には紅や紫の濃い色薄い色が幾重にも重なり、その違いが華やかで、まるで草紙の小口のようです。その上には桜襲の織物の細長を着ているようです。先の方まであざやかに見える御髪は糸を縒りかけたように靡いて、裾のほうが房やかに切り落とされている様子はたいそううつくしく、身の丈より七・八寸ほど長く伸びていらっしゃいます。たいそう細く小柄ですので、お召し物の裾が長く余っていて、その姿つきや髪のかかっていらっしゃる横顔は、何とも言いようのないほど上品で可愛らしいのでした。夕日の淡い光の中ですのではっきりせず、奥が暗いような気がするにつけてもひどく物足りなく残念なのでした。お付きの女房達は、花が散るのなどお構いなしに蹴鞠に熱中している若君達を見ようとして、丸見えになっている事に気付かないのでしょう。猫がひどく啼きますので、それを振りかえってご覧になった面もちやしぐさなどがおっとりしていて、衛門の督は『若くて可愛らしい人だな』と思うのでした。大将も気付いて『これはまずい』と、御簾を直しに近寄ろうとなさるのですが、それも反って軽率な行為のようにお思いになって、ただ気付かせるために咳払いをなさいます。すると、やっと奥へお入りになりました。とはいうものの、大将とて女三宮をもっと見たいとお思いでしたから、たいそう飽き足らないお気持ちでいらしたのですが、あちらで猫の綱をお放しになったので御簾が下りてしまい、思わずため息が出るのでした。大将にもましてすっかり女三宮に魅せられてしまった衛門の督は、胸がいっぱいになって、『あれはどなたなのだろうか。女房たちの中で一人だけ目立つ袿姿から見ても、また女房とは思えないご様子から推しても、宮様に違いあるまい』と、ひどく気になるのでした。さりげなく振舞っているのですが大将は、『衛門の督は、はっきり見たに違いない』と、心配になるのです。衛門の督はやるせない気持ちの慰めに、猫を招き寄せて掻き抱きますと、女三宮の移り香がたいそう香ばしくて、可愛らしく啼くにつけても恋しい方に思いなぞらえて懐かしく感じるとは、いかにも好色めいてはいないでしょうか。
May 28, 2014
-
若菜 上 -70-
あまり格好のよろしくない、ばたばたと無作法な遊びですのに、それが優雅に見えますのは場所柄や人柄によるのでした。風情あるお庭の木立に霞みが立ちこめ、色とりどりに咲き続く花の木や萌葱色の芽の蔭に、つまらぬ遊びではあるのですが上手下手の技を競い合い「我こそは」と自慢顔をした中で、ほんのお付き合いで加わった衛門の督の足技に及ぶ人はありませんでした。たいそう上品で控えめな衛門の督が、無作法にならないように身だしなみに気を配り、それでいて蹴鞠に熱中している様子は面白いのです。人々が寝殿の御階の間に面した桜の木陰に寄って、蹴鞠に夢中になっていますのを、大殿も兵部卿の宮も高欄に出てご覧になります。 たいそう熟練した技なども見せて、蹴り続く回数も多くなるにつれて、身分の高い人たちの服装も乱れ、冠の紐も緩んでしまいました。いつもは冷静沈着な大将の君も、ご身分の割に夢中になっていらっしゃるように見えます。それでも他の人より若く上品で、やや糊気の失せた桜襲の直衣に、指貫の裾の方を少しばかり膨らませて、心持ち引き上げていらっしゃるのですが、軽々しいようには見えません。優雅な打ち解け姿に桜の花が雪のように降りかかりますので、見上げて、たわんだ枝を少し折り取って、階段の中ほどに腰をお掛けになりました。そこへ督の君がおいでになり、「桜の花がずいぶん散りますね。桜を避けて吹けばいいのに」と、仰せになりながら女三宮のお部屋を横目で見ますと、女房たちはいつものように締りのない様子で、御簾からこぼれ出た袖の端や透いて見える衣装の色合いなどが雑然としていて、まるで佐保姫に手向ける幣袋かしらんと思われるほどです。御几帳はだらしなく片隅に寄せてあり、人の気配も近く、世馴れているように見えます。そこへ小さなかわいらしい唐猫を少し大きな猫が追いかけて御簾の端から走り出てきましたので、女房たちが右往左往する気配や衣擦れの音で大騒ぎしている様子が聞こえます。猫はまだよく人になついていないのでしょうか、逃げないように長い綱をつけていましたので、それが物に引っかかってしまいました。猫が逃げようとして引っ張るうちに女三宮の御簾の横端をすっかり引き上げてしまったのですが、それに気づいて直す女房もいないのです。柱のところにいた女房たちも唐猫に気を取られて御簾を直すどころかうろうろするばかりです。
May 25, 2014
-
若菜 上 -69-
三月のうららかなある日、六条院に兵部卿の宮と衛門督が参上なさいました。大殿が対面なすっておん物語などなさいます。「暇な暮らしではこの季節がとくに退屈ですね。公私ともに用事がないので、何をして過ごしたものやら」と仰せになって、「今朝大将が来ていましたが、どちらにいますか。所在ないから大将に小弓射させて見物しましょう。小弓の好きな若い人たちもおいでですし。大将は帰ってしまいましたか」と、傍人にお聞きになります。「丑寅の町で、大勢で蹴鞠を見物していらっしゃいます」と申しますので、「蹴鞠は騒々しく跳び回るが、それでも意外におもしろく気の利いた遊びだね。こちらに参るように」と仰せになります。若い君達のような人々ばかり大勢いるのでした。「毬をお持たせになりましたか。どなたがおいでかな」と大将に仰せになります。「誰それが大勢参っております」「それでは、皆でこちらへいらっしゃい」ちょうど明石女御が若宮をお連れ申して内裏にお帰りになった頃ですので、寝殿の東おもてはひっそりと人目につかない場所になっていました。鑓水の流れが行き逢う広々とした所に、蹴鞠をするのにちょうど好い場所を捜して皆が立ちました。太政大臣のご子息たちは頭の辨、兵衛の佐(すけ)、大夫の君など年長の者も幼い者も、皆人並み以上に上手に毬を蹴ります。次第に日が暮れて行くのですが「風も吹かず、蹴鞠に恰好の日だ」と面白がり、辨の君もじっとしていられず加わりますので、大殿は、「辨官でさえ抑えきれないようですのに、上達部でも若い衛府司たちはどうして遊びに参加なさらないのでしょう。私が若い頃は、無作法な遊びとしてできなかった事を残念に思ったものですよ。とはいえ毬を蹴る格好は、身分の高い人の遊びとしては、ひどく軽々しいものではありますね」と仰せになりますので、大将も督の君もみな庭にお降りになります。何とも言えぬ桜の花影を散歩していらっしゃる夕映えのそのお姿は、たいそう優美なのでした。
May 14, 2014
-
若菜 上 -68-
こうした事を大将の君も、「なるほど完璧な女君というものは、なかなかいないものだ。それにしても紫のおん方は父上の北の方となられて長いけれど、お心構えやお振舞いに落ち度がなく落ち着きのあるご本性で、その上気立てがやさしく、他の人にも気使いをし、自分自身の品位も保ち実に奥ゆかしくいらっしゃることよ」と、かつて見た面影を思い出されるのでした。大将の北の方には、『可愛い』とお思いになるお気持ちは深いものの、打てば響くような才覚のない人ですので、かつてあれほど恋しかったお気持ちも今では失せて、慣れるに従って気が緩み、かつまた六条院に暮らしていらっしゃるおん方々のご様子がそれぞれに趣があってうつくしいので、心ひそかに関心を寄せているのです。まして女三宮は高いご身分でいらっしゃいますのに、父・大殿は格別ご愛情が深いようでもなく、ただ世間体を繕っているようにしか見えませんので、殊更大それた気持ちというのではありませんが『お姿を拝見する機会がないものか』と思っていらっしゃるのでした。衛門の督の君も、いつも朱雀院に参って親しくお仕えした人ですので、大切にかしづいて女三宮をお育て申されたお気持ちを逐一拝見していて、婿選びをなさった頃から希望を申し上げ、朱雀院におかれても『身の程知らずとは思召さず』と聞いていたものの、予期に反して源氏の院と結婚なさった事をひどく残念に思い、胸が痛むような気持ちになりますので、なお思い切る事ができないのでした。それで、その頃から親しくしていた女房からのたよりで、女三宮のご様子などを聞き伝えては、それをはかない慰めにしていたのでした。「紫の上のご寵愛には、やはり負けていらっしゃる」との世間の噂を伝え聞いては、「畏れ多いことではあるが、私と結婚していたらそんな思いはおさせ申さなかったであろうに。もっとも宮様という高い身分に、我が身はふさわしくないが」と、いつも小侍従という女三宮のおん乳母を責め立てて、「世の中は不定だから、いずれ大殿が出家をなさった折には、宮様を妻として迎えたい」と怠りなくうろつき回っているのでした。
May 11, 2014
-
若菜 上 -67-
大将の君は、かつて女三宮とのご結婚について考えないでもありませんでしたのに、こうして近い所に住んでいらっしゃいますので、冷静ではいられません。お世話なさる際にうまい口実を作っては度々参上なさいますので、自然に女三宮のおん気配やご様子も見聞きなさいます。父・大殿は上辺の儀式は厳めしくご立派に、世の例ともなるほど大切になさるのですが、たいそう若く、鷹揚でいらっしゃるばかりで、際立って奥ゆかしいところが見えません。お附きの女房なども経験豊かな年配の者は少なく、年若い美人でただもう華やかに振舞い、風流好みの者ばかりが数知れぬほど多く集まってお仕えしています。悩みのないあたりでいらっしゃるとはいいながら、何事にも穏やかで気持ちを抑えている者は心の内をはっきり見せませんので、人知れず悩みを抱えているとしても、本当に楽しそうに屈託なく暮らしているように見える者たちと一緒にいると、周りに引きずられて同じ雰囲気や調子に合わせるものですけれども、明けても暮れても幼稚な遊びや戯れに熱中している女童の様子などをご覧になりますと、大殿にはお気に召さないのですが、御自分のお気持ちだけで一方的に世の中をご覧にならないご性分でいらっしゃいますので、『こういった事をしたいのであろう』と大目に見てお諫めになりません。ただ女三宮ご本人の行儀作法についてだけはよくお教えになりましたので、少しは大人らしくおなりなのでした。
May 10, 2014
-
若菜 上 -66-
そして明石の上に、「あなたはいくらか物の道理を分かっておいでのようですから、大変よろしい。対の上と親しくなすって、明石女御の御世話も同じ気持ちでなさいませ」と、そっと仰せになります。「私に仰せくださらなくても、本当に例のない御方とよく存じ上げておりますので、明け暮れお噂しては感謝申し上げております。私を目ざわりな者とお思いになりお許しがなかったなら、こんなにまで私に目を掛けてくださるはずがございませんのに、きまりが悪いほど人並みにお扱いくださいますので、反って恐縮いたしております。物の数でもない身でありながらそれでも生きておりますのも世間体が悪く、明石女御のおんためにはたいへん辛く恥ずかしゅう存じますが、私の失策をいつもかばってくださいまして」と申し上げます。大殿は、「あなたのおん為ではないのでしょう。ただいつもお傍でご様子を拝見できない気掛かりさに、あなたにお任せしているのでしょうね。あなたも又、女御を独占して親だという態度をあらわになさらないからこそ、万事が穏やかに無難に運ぶので私も安心できて嬉しいのですよ。つまらない事柄でも道理を弁えないひねくれた人は、人との付き合いの上で当人はもちろん、周囲の人にまで迷惑をかけるものです。しかしあなたがたはどちらも直すべき所がないように思われますので、私は安心しているのです」と仰せになるにつけても明石の上は、『ほんに。私はよくぞここまで卑下してきたものだわ』とお思い続けになるのです。大殿は対へお帰りになりました。明石の上は、『対の上へのご情愛ばかりが深まるようね。ほんに対の上も、他のおん方々には比べられないほど万事の才覚を身に付けていらっしゃるのですもの、ご情愛深いのもお道理だわ。宮のおん方へは表向きの御世話ばかりがご立派でいらっしゃるけれど、めったにお渡りにならないのは勿体ない事ではないかしら。お二方は同じ皇族の血筋ではいらっしゃるけれど、一段高いご身分でいらっしゃる女三宮は、ひどくお気の毒ね』と蔭口をおっしゃるにつけても、『そんな高貴なおん方々と交わりを持つ私の宿縁は、たいそう立派なものなのだ』とお思いになるのでした。身分の高い女三宮でさえご自分の思い通りにならない世の中ですのに、ましてご自分などお付き合いできる身分でもありませんから、今では恨めしいと思うことさえないのでした。ただ、山に籠ってしまった父・入道の事を思いますと、しみじみと悲しく気掛かりなのです。尼君もひたすら「極楽浄土で再会しよう」との一言を頼みとして、後世を思いやりつつ寂しく庭を眺めていらっしゃるのでした。
May 9, 2014
-
若菜 上 -65-
そして、「この願文には、別にまた、私が添えて奉るべき願文がございます。私の趣意は、そのうちお話し申しましょう」と、明石女御にお話しになります。そのついでに、「今はこうして昔の事情をお分かりになったでしょうけれど、紫の上のお気持ちを疎かにお考えなさいますな。もとより切っても切れない夫婦や親子の間柄ではまだしも、継母が継子に同情を寄せ、あるいは優しい言葉をかける事さえめったにないものです。まして実母がこうしてあなたに付き添うてお世話なさる様子を見ながらも、始めの頃の気持ちと少しも変わらず、以前にもましてあなたを深く大切にしていらっしゃるのですよ。昔のたとえにも、『継母というものは、上辺は継子を大切に世話するが、下心は分からない』とあります。継子が知ったかぶりの邪推をしますと賢いように見えますけれども、表裏のない素直な気持ちで慕っていたなら、邪険な継母のほうも『この子をどうして憎めようか』と、仏罰を受けそうで改心する事もあるでしょう。前世からの敵同士は別として、互いに行き違いが多々あったとしても、どちらか一人憎む心のないときには、自然に仲直りするようです。また、それほどでもない事に難癖を付け、愛敬がなく人を嫌う性癖のあるのは、可愛らしさがなく、同情する価値がないように思います。それほど多くはありませんが、私が人の心のあれこれを見た限りでは、趣味の良さを始めとしてそれぞれにある程度の心違いはあるようです。人は各自に得意な点があって、取柄がないのでもありませんが、そうかといって我が妻を本気で選ぶのは難しい事です。ただ、心に癖がなく好ましいことにかけては対の上だけでしょうね。この人こそ素直で穏やかな人と、私は思います。立派な人であるとしても、あまり締りがなく頼りないのもひどく残念なものですが」と、紫の上の事ばかり仰せですので、もう御一方の宮様の事は想像に難くないのです。
May 7, 2014
-
若菜 上 -64-
「年とともに世の中の有様を知るようになりますと、私にとっても不思議に恋しく思い出される入道の人柄ですから、ましてや深い契りを結んだ夫婦の仲では、どんなに感慨無量でしょうね」とお話しなさいますので、この機会に明石の上は『夢の話についても、思い当たる事がおありかもしれない』と思い、「何ともあやしい梵字とか言う筆跡ではございますが、お目に留まる節も混じるかと存じます。上洛いたしました際には『これが最後』と別れて参りましたが、やはり肉親の情は残るものでございます」と、体裁よくお泣きになります。大殿は文箱をお取りになって、「立派な文字ではありませんか。しっかりしていらっしゃるのでしょう。筆跡だけでなく、何事につけても有識者というべき人ではあったけれども、処世術だけが欠けていたのでしたね。入道の先祖の大臣はたいそう賢明で、世にも珍しい忠誠心を尽して朝廷にお仕えなすったのに、その間に何かの間違いがあって、その報いで子孫が滅びたなどと世の人が言うようですが、女子の家系ではあってもこうして女御に御子が生まれたのですから滅びたわけではなく、これもまた入道の多年にわたる仏道修行のご利益なのでしょう」と、涙を拭いながらお読みになります。『入道という人は不思議なほど偏屈で、訳もなく高い理想を抱いていると世間の人も非難し、また私自身もしてはいけない結婚をしてしまったと後悔したものだが、全ては前世からの約束事であったのだ』とお悟りになったのですが、将来がはっきりしないのでどうなる事かと心配して過ごしてきたのでした。『しかし入道は夢を信じていたからこそ、一途に私を婿に望んだのだ。私が無実の罪でひどい目に会い、須磨や明石にさすらったのも、ひたすらこの女御一人をもうけるためであったのだ。さて、入道はどのような願を立ててめでたい夢を見たのかしらん』と知りたくなって、心の中で拝みながら願文をお取り出しになります。
May 6, 2014
-
若菜 上 -63-
慌てて文箱を隠すのも間が悪く、そのままにしていらっしゃいますと、「何か仔細がありそうな箱ですね。あなたに思いを掛けた人が長歌でも詠んで、封じ込めたような感じがしますよ」と仰せになります。明石の上は、「何と嫌な事をおっしゃる。お若い宮様を迎えて若返りなすったせいで、私など意味のわからないような御冗談が時々出て参りますのね」とにっこりしていらっしゃるのですが、何やらしんみりと考え込んでいらした様子がはっきり分かります。大殿が不審に思って首を傾げていらっしゃいますので面倒に思って、「明石の入道が密かにいたしておりました御祈祷の巻数や、まだお礼参りを果たしていない祈願などがありましたものを、『機会があれば大殿にお目に掛けた方がよろしくはないか』と、送って参ったのでございますが、今はまだその時期ではございませんので、お開けにならずともよろしゅうございましょう」と申し上げますので、『なるほど、深い事情があったのだ』とお思いになり、「あの後、どんなに修行なすってお暮らしだったでしょうね。長命で、長い間仏道修行を積んだ功徳もきっと大変なものであったろう。世の中の名僧や高僧を見ても、煩悩や迷いが深いせいであろうか、学問があるというだけのことで、入道にはとても及ばないでしょうね。いかにも悟りが深く、それでいて風情のある人柄でした。聖者ぶった顔はしていないけれど、心の奥底ではすっかり極楽浄土に住んでいると見えたものです。まして今では心にかかる『ほだし』もなく、解脱しきっているのでしょうね。私が気軽な身であるなら人目を忍んで明石の浦に行き、もう一度入道に会いたいものです」と仰せになります。「今ではもう、住んでいた所も捨てて、鳥の音も聞えぬ山奥に入ったと聞きました」「さらばその文箱は遺言というわけですね。文を通わしていますか。尼君はどんなお気持ちでしょうね。親子の仲よりも夫婦の縁では、また悲しさも格別でしょうから」と、涙ぐんでいらっしゃるのでした。
May 2, 2014
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- チェンマイに佇む男達 寺本悠介の場…
- (2025-11-20 10:06:55)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-
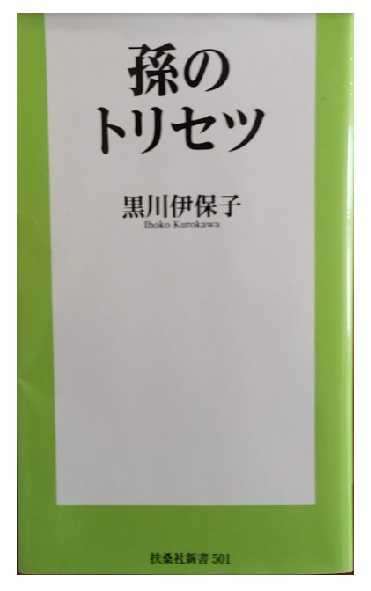
- 最近、読んだ本を教えて!
- トリセツを超えた祖父母の指南の書
- (2025-11-20 12:56:25)
-







