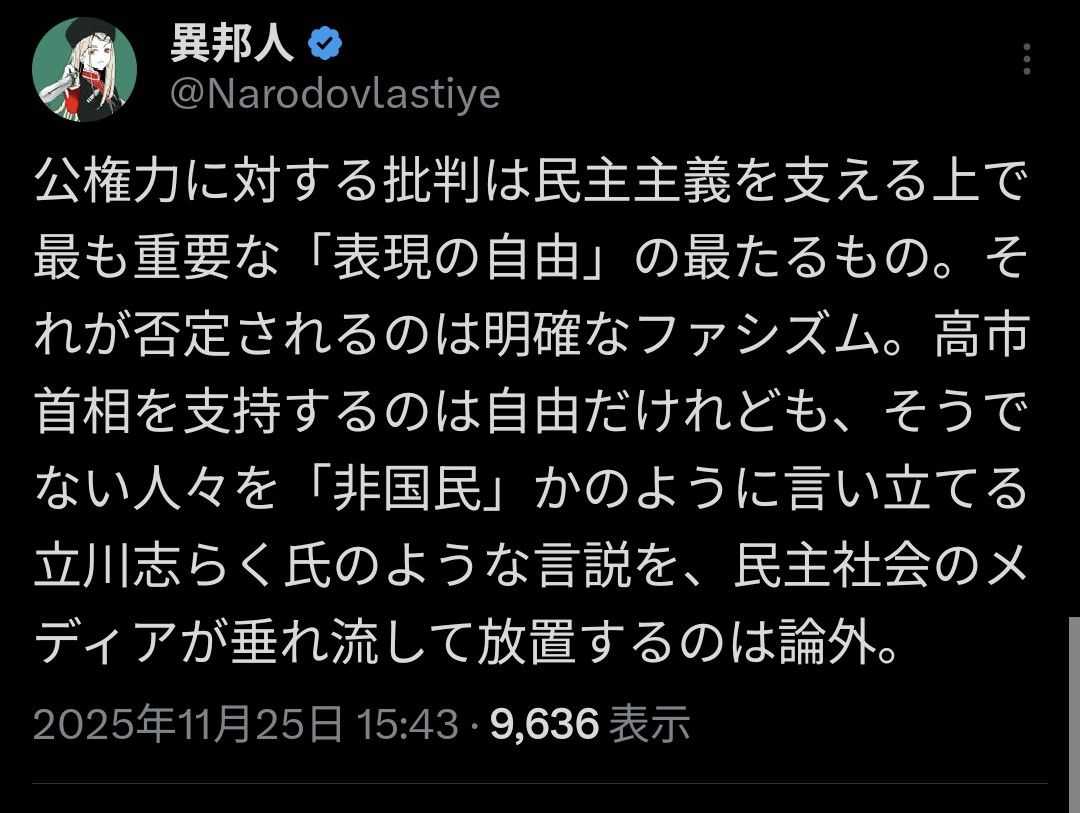2012年07月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
恰好いい篆刻文字♪
京生まれだから固い漢字よりも角の取れたひら仮名を本来は好むのですが、篆刻の字となると俄然、漢字特有の味に酔ってしまい勝ちです。 この日記で一度話題にした篆刻に関する本「中国遊印200選」高畑常信著(日貿出版社)のページを繰っていると、どの標語を余生の友に選ぼうかと迷ってしまいます。 栖神静楽・・・心をやすめ静かに楽しむこと。栖の字が梅に似 ていて住所と錯覚する効果、それに字ヅラが 宜しい。 詩仙心雑・・・詩に高尚で通俗的でない心を表現する。面白 い言葉ですが、凹版になっているので残念。 浩乎自得・・・深く自分から心に悟る。4つの文字のバランス が宜しい。 小蓬莱・・・・蓬莱山は父の好んだ思想。少し遠慮した小蓬莱 の字の並びが意匠的。 日慎一日・・・毎日毎日、きょう一日を大切にする。日という文 字が二度出てくるのすが、間、空白の多い字づ ら。 生気遠出・・・万物を生長発育させる気が、とどまることなく 発生する。字の並び、意味も良好。 大象無形・・・大きな象(カタチ)には、きまった形が無い。実に 面白い篆刻文字。 父が遺してくれた印鑑用の四角柱の大理石2本は、俳句の知人Kさんに、星子を篆刻文字で彫って頂きました。向日町の公民館で、年に2度ある展示会に、色紙や短冊に押印したいと思っています。
2012.07.31
コメント(0)
-
夢二の「思い出ぐさ」♪
わが家には父の遺した夢二に関する書物が沢山あります。残念ながら本物の肉筆ものは無いのですが、どの作品も私たちの胸に沁みわたる抒情が感じられます。 掲題の「思い出ぐさ」は昭和42年5月30日、龍星閣から発行された二重ケース入りのものです。こういう場合、父は新聞の切抜きを一緒に保管しているのが常でして、”情感通う浮世絵 竹久夢二 思い出ぐさ”という見出しで、<ユニークに明治・大正の情緒を描き、哀詩をうたい、当時の若い人の夢を燃やし、あこがれのマトとなった竹久夢二が、明治44年から大正9年にかけて、全盛期の10年間に「月刊夢二絵ハガキ」(つるや書房版)として描き続けた400余点のうち、326点の作品群をアート紙に収録した愛蔵本。>などと紹介しています。 最初の絵ハガキは、黒っぽい着物で、テーブルに頬杖する女性「朝」。2番目は「水鏡」で小さな池畔に座り込み、二の腕白く髪を整えるの図。日本髪を結ったカラフルな「春」、蛇鱗もようの浴衣の後ろ髪、無地の団扇が印象的な「夏」収穫物の籠を小脇に抱えた「秋」、大胆な柄の炬燵に粋な日本髪、かんざしを直している「冬」歌舞伎紙屋治兵衛の「紙治」、「きられ与三郎」、「め組の辰五郎」、小唄集1から”よしや今宵はくもらばくもれ とても涙でみる月を”の「よしや今宵は」”山路とおれば茨がとめる 茨はなしゃれ日が暮れる”小唄集3の「山路とおれば」”丁とはらんせ もし半でたら 私を売らんせ 吉原へ”の「丁とはらんせ」”ムスメなにするあんどのかげで かあいとのごのオビくける”の「ムスメなにする」「髪のほつれは」・・・髪のほつれは枕のとがよ それをおまえに うたぐられ 荒海ぢや うき世ぢや ゆるしゃんせ 「逢いにきたれど」・・・逢いにきたれど戸はたヽかれず 歌の文句でさとらんせ「そのふたり」・・・そのふたり 理想のかしや みてあるき「白状を」・・・白状を娘は乳母にしてもらひ 実にいじらしい娘の仕草が描かれています 解説は例によって、夢二の研究家・長田幹雄さんが7ページに綴っておられます。全380ページに及ぶ愛蔵本なのです。
2012.07.30
コメント(0)
-
秀吉公と茶室♪
大山崎には重要文化財が沢山ありますが、千利休が作ったとされる「待庵」は国宝に指定されています。子どもや団体の拝観は対象外で、”駅前にある妙喜庵”宛、事前の往復ハガキでの予約が必要とされています。利休について書物を繰っている中で、秀吉公の黄金の茶室の件があったので、少し引用します。 <1586年9月、秀吉は宮中の小御所に黄金の茶室を持ち込み、天皇や親王方に手づから茶をたてました。吉田兼見は日記に前代見聞の見事さと記しています。それから4年後の九州名護屋城の茶会でこの茶室で雑煮を食べ、茶を飲んだ宗湛は、茶室から道具類までが黄金づくしだったと書き残しています。 {金の御座敷のこと、平3畳なり。柱は金を延べて包み、敷居も鴨居も同前なり。壁は金を長さ7尺ほど、広さ5寸ほどずつに延べて雁木にしとみ候。 縁の口に4枚の腰障子にして、骨と腰の板は金にして、赤き紋紗にてはりて、畳表は猩々緋、へりには金襴ー萌黄小紋・・・(宗湛日記)}> 何かの催し物で一度、この黄金の茶室を見たことがありますが、明るい場所で見れば、なるほどけばけばしいものですが、仮に大山崎にある”待庵”の内部を黄金づくしにしても、採光が充分では無いので、それほど派手ではないのかも知れません。 (参考図書:「京のかくれ話」の児島孝氏の一文)なお、”妙喜庵・待庵”等、大山崎の観光については、「大山崎ふるさとガイドの会」のホームページをご覧ください。
2012.07.29
コメント(0)
-
2度結婚?清少納言♪
平安期の女性の場合、生没年代や本名を知ることは難しく、紫式部が藤原宣孝と結婚していたことは判明していますが、そのライバル清少納言に至っては昔の学者は独身者と思い込んでいたようです。 しかしいろんな系図を探っている内、”清少納言の子”というものがあったので、子供がいる以上、亭主もいたに違いなかろうということで、その名は橘則光。清少納言より少し上の位の中流官僚で、その出世ぶりは左衛門尉(サエモンノジョウ)・・・警視庁の局長クラス修理亮(シュリノスケ)・・・宮中の営繕を司る役の次官遠江介・・・・・・・・副知事クラスという具合です。彼とは早くに結婚し、男児を設けていますが、同居という形はとって居なかった模様。2度目の結婚は彼女が中年過ぎの頃で、かなり年上の藤原棟世(ムネヨ)がその人で、摂津守や山城守を歴任した人物。 或るとき、藤原斉信(タダノブ)が清少納言の才女振りに嫌気して、「蘭下花時錦帳下」という白楽天の詩の一節を使いに持たせ寄越しました。この続きは「蘆山雨夜草庵中」なのですが、少し工夫して、「草の庵を誰かたづねん」と添え、”そんなことをおっしゃっても、廬山雨・・・の一句をお答する人などおりませんよ”と、とぼけました。その手紙を見て、斎信や周りの公家たちは、”やられた、この女、ただ者じゃないぞ”と感心し、それ以降はすっかり少納言のファンになってしまったということです。 この評判を聞いて、夫の則光は、さっそく彼女の元を訪れ、あの時は俺も傍にいて鼻高々だった、自分の出世より嬉しく感じたと述べています。この時期、少納言・則光は少し上の公家たちから”いもうと・せうと(兄)”と呼ばれていたようで、同居しない二人がからかわれていた節があります。 清少納言はその後ますます有名になり、ともすればいろんな貴族が押しかけてきますので、こっそり誰にも告げないで秘密の家に里下がりしていると、斎信さまから「お前は何処へいったのか、せうとなら知っているだろう、教えろ」と迫られ往生したと則光は打ち明けます。この秘密の場所を知っていたのは夫の則光と公卿の藤原経房(ツネフサ)だけでしたが、経房も、その場に居合わせながら知らん顔。経房さまと目が合ったりしたら笑い転げそうで、目の前の若布(ワカメ)ばかり、がむしゃらに食べていたよと漏らします。やはり夫婦ですね。(参考図書、「日本夫婦げんか考」永井路子著、枕草子など)
2012.07.28
コメント(0)
-
三川合流の模型♪
一昨日、昨日の2日間、大山崎歴史資料館の3階では、17人の児童たちを集めて「三川合流の模型を作る!」の学習と工作があって、私たち”大山崎ふるさとガイドの会”からも20名ほどが子供たちの工作に付き添いました。ここ数年間の企画は以下の通り。「立札をつくる!合戦から大山崎を守った立札」(平成18年)「JR山崎駅をつくろう!」 (平成19年)「”蘭花譜”の版画を刷ろう!」 (平成20年)「武将のかぶと・よろいをつくろう!」 (平成21年)「幕末の大砲模型をつくろう!」 (平成22年)「飛び出す!設計図を作ってみよう!ーーお茶室の起こし図」 (平成23年)小用で参加できなかったのは、立札と大砲の年度だけで、蘭花譜の時は、愛らしい少女とのツーショットが掲載されました。今年の写真は上級生の少年と会長。 奈良から流れ来る木津川、琵琶湖を出発点とする宇治川、亀岡の大堰(オオイ)川が嵐山を越えて桂川となって、この三川が時代と共に大工事によって変遷しながら合流する光景を、明治22年ごろの三川合流図(これは高学年用)現在の三川合流図(これは1~3年の低学年用)の2種類で、予め資料館の職員さんパートさんが川を彫って下さった板に、瓦を敷くときに使う粘土を張り付けながら堤防や山などの起伏を作り、浅草海苔のような深緑のパウダー(粉)を降りかけ固着させ、2ミリほど彫り込まれた川に紺色や緑色の塗料で色塗りを施したあと、15分ほどで硬化の始まる”モデリング・ウォーターを塗り付けてテカらせます。 私が担当したのは、小学1年生の女の子ふたり、もう一人の女性ガイドさんも担当。一人は数の加減で上級生用の旧図が割り当てられていました。もうひとりは現代の図でかなり景色は違うのですが、鈴羽・郁美のふたりは大の仲良し。すぐ後ろの席は、郁美ちゃんのお兄ちゃんで、彼を担当されたのが、この道ベテラン本職はだしのFさんで、ご指導よろしくお兄ちゃんの出来栄えは素晴らしい。鈴羽ちゃんと郁美ちゃんは無意識に譲り合える真の親友で、こちらは冗談を言っては笑わせながら、要所、要所の注意や時間配布のチェックなど、実に楽しく作業しました。 ふたりとも時間内にきちんと完成することができ、参加した子供たちは労作を手に、記念撮影に納まっていました。 私はこの後、出版社へ9月号の原稿持出、返す刀で、Mさん宅で、関西現代俳句協会の事務長さんや幹事さんらと、現在受付中の全国大会の作品の整理事務をしました。参加費用の現金と作品数とのチェック、整理番号取り、作品番号のナンバーリング、原本のコピー、選者への発送、9作品一挙に出された方への記念品発送、出版社から戻った印刷と原本との校正作業など3千人、2万点近い作品を管理するのは大仕事です。
2012.07.27
コメント(2)
-
漁場の開拓♪
ジャニーズ系と言っても今じゃ好い歳になられたTOKIYOのザ!鉄腕!DASH!!は自然環境を再構築する内容で、好きなテレビ番組の一つです。 上前淳一郎さんの「節約が明るい時代<読むクスリ第37巻>」(文芸春秋)に「山育ちの魚」と題したものがあります。これを要約しますと、 総工費12億円、海中に沈めた巨大ブロック5千個。海底に伸びる山脈は120m、山の高さが12m。これは長崎県平戸島沖、水深80mの平らな海底に作った人工の山です。 世界の大漁場は海底から盛り上がったような地形から成っていることに注目し、その誘因は、海流がこの山にぶつかりぶわっと湧き上がり、海底の栄養塩を海面近くへ送ることによって、 海面近くで光合成する植物プランクトンに栄養が行き渡り、よく育ちます。するとこれを食べる動物プランクトンが大量に発生し、イワシや小型の魚に絶好の環境になります。さらにそのような稚魚を狙って大型の魚も集まって来るという理屈です。実際に平戸島沖では2年後、イワシの漁獲量が6倍になり、イワシやアジの稚魚目当や巨大ブロックの壁に付着するフジツボ目当てに大型魚が集まり、 ムツ、ヒラマサ、マダイなどが驚くほど獲れるようになったようです。巨大ブロックは火力発電所から排出する石灰石を利用してコストを切り詰めたらしく、山口、島根、鳥取、兵庫なども習っているとか。 山本周五郎の「日本武道記」だったか、海浜に糞尿などを撒き苦労の末、漁場を拵えた人物の話があったように思いますが、”きっと成功させる”という強い信念が大切なのでしょう。
2012.07.26
コメント(2)
-
大相撲閑話♪
先日の大相撲千秋楽は、29年ぶりの全勝対決という圧巻でした。おおむかし、テレビに報じられる大相撲中継では、大関以上の取組になると、制限時間いっぱいの時は、会場がわ~という歓声に満ち、手に汗を握る興奮状態が心地よかったものです。 外人力士を採用した時から、良い面と悪い面が予想されていましたが、”相撲道”という精神的な面での劣化は、相撲の多様性と引き換えに負うことでもありました。 元来、相撲は神事のひとつで、神前にて力士が相撲を取る事によって、大地の魂を揺るがし、大地に生えている植物に生命力を吹き込み、豊作を祈願する意味合いがありました。つまり相撲の起源は宗教的儀礼であり、力士が四股を踏むのは、大地の魂を振り起す”魂振り”の儀式だったのです。 そういう意味合いに立てば、単に勝敗にこだわることではなく、心身ともに卑しからぬ人品が求められるスポーツでもある訳です。立ち合いについては、このブログにくどくど書き込んできましたが、NHK放送の栃・若決定戦や大鵬・柏戸戦などは、両手を着くことなく腰高のまま、ぶつかっています。この画像には驚きました。立ち合いのルールについては、何回も検討され、現在ではアマチュア相撲のように両手を土俵に着けることが必須とされるに至っています。 その方が力が出るというのが力学的見地なのですが、もし、土に両手を着けることで立ち合いが円滑に行かない(アマチュアでは問題なさそう)のなら、昔のように片手着ないしは、手振りだけで良いとする考えも無駄では無いのかも知れません。千秋楽前日の、横綱対稀勢の里戦の気まずさは回避できたのかも・・・。とは言うものの、我勝ちに飛び出すという態度や心の姿勢は、相撲が神事という観点からも戴けません。 本日只今から大山崎町の歴史資料館へ赴き、当番並びに恒例「夏休みこども歴史工作」のお手伝いを致します。子供は実に可愛い。
2012.07.25
コメント(0)
-
俳句と折紙に人生全うした男♪
凡そ1年前の8月上旬に亡くなられた高木智さんの遺作展が、京都は宝ヶ池のグランドプリンスホテル京都で開かれていて、本日午後4時で最終となります。地下1階の鞍馬の間には、高木智さんゆかりの俳句仲間や折紙のお弟子さんたちが笑顔でお迎え下さいました。 高木さんは京大卒業後、佛教大に勤務され、その間、俳句と折紙を一生のホビーになさった方でした。1967年には、日本折紙作家協会展に伎月人形等出展、7年後には荒木京さんを主宰とする「京都おりがみ会」を結成され、1993年「古典に見る折り紙」を出版、ほかに16冊の著書や「秘傅千羽鶴折形解説 復刻と解説」など5冊の共著があります。 俳句にも触れるなら1950年ごろ、京鹿子を興された鈴鹿野風呂先師に師事。「唐橋」「合宿抄」「漕手の四肢」「ベレー」「姫始」「菖蒲湯」の句集を発行する傍ら、鈴鹿野風呂記念館の図書館の守役として数多の貴重な書物や短冊・色紙などを整理・管理。数回に渡って企画展を開催、結社の俳人は元より、著名な俳人たちの来館を得て居ました。 折紙に関する収集も多大、貴重で、喜多川歌麿の「浮世忠信蔵 十一段目」や歌川豊国・国貞・芳虎たちの浮世絵18点、書籍では土佐光信の「職人尽歌合 上」や西川祐信の「傾城手管三味線 巻5」など和綴じ本や書物が43点。 作品では、黒猫を膝に抱く女を描いた竹久夢二の「黒船屋」などの色紙4点、童謡シリーズは、うぐいす、ひなまつり、嵯峨菊など10点、立体作品では、実に精巧な「弥勒菩薩」「白雪姫と七人の小人」など10点。 俳句部門では、<玉砂利を音させて掃く松の芯>この軸は服部郁史の手によります。短冊20点ほど。 夫人には、永年の看病の疲れも癒えぬまま、この一大イベントに全霊を注がれて、こんにちを迎えられました。月刊俳誌「京鹿子」の毎月の発刊に際しては、何かとご協力を賜り、ご支援して頂いております。 この度の盛会を心からお祝い申し上げます。
2012.07.24
コメント(0)
-
浴衣によせて♪
京都には古来の浴室を持つ寺があって、1つは妙心寺の明智風呂、或いは同志社大学の傍にある相国寺の浴室。さらに泉湧寺にも寛永期の浴室があります。 風呂の”風”は水蒸気を指し、”呂”は深い部屋を意味し、詰まるところ足利時代以降の風呂とは蒸し風呂のことでした。この蒸し風呂にて汗をかいた後、冷水浴や冷水で身体を拭ったりしていたので、無料で振舞われた庶民は至って清潔。しかるに平安時代の貴族は入浴の習慣が無かったから、匂い隠しに香を焚き込んでいたようです。 熱い湯気の中に身をさらすのだから火傷防止の被服が必要でした。それが”湯帷子(ユカタビラ)”で、麻の単衣の着物を着用していました。このゆかたびらの”びら”がいつの間にか略され、”ゆかた”になりました。蒸し風呂の中でのみ着用するということは本来、人目につかない下着でしたが、時代が下るに従い、浴衣と称して夏季に愛用する単衣となってきました。 もう1つ加えるなら、蒸し風呂で長時間座っていると、簀子(スノコ)の下から上がってくる蒸気が熱くなるので、持参した麻の布を尻に敷くようになりました。これが風呂敷なのです。 大阪港区の南市岡にある商店街の呉服屋さんは、銀行員時代に私が営業担当したことがあって、問屋が持参した厚味30センチ以上もある浴衣の見本帳2冊を、こちらの店主は矢継ぎ早にめくっていかれ、400生地ほどの中から、わずか3つの柄を注文して居られたのをつぶさに見て居ました。プロの仕事って、お互い真剣勝負なんだなと感心した記憶があります。気前よく注文して、売れ残こせば、それは小売店側にとって自滅することに他ならないからです。 兎も角、最近若い人の間で浴衣が手頃な和装のおしゃれとして見直され、流行している傾向にあることを喜ばしく思っている次第です。
2012.07.23
コメント(0)
-
ビックリハウス版「大語海」教訓編その12♪
本日は午後から開かれる吟行句会へ参加する為、間もなく出かけます。阪急の西院で下車、丸太町近くまで市バスに乗り、北野天満宮御旅所(御輿岡神社)、通称だるま寺で親しまれる法輪禅寺、勤王の志士30余名の墓のある竹林寺辺りを散策します。 どんな句が浮かんで来るのか楽しみです。で、本日は場つなぎになってしまいますこと深謝。大爆笑・ビックリハウス版「大語海」の訓戒編から、適宜抜き出してみました。 ちょっと花王貸してもらおうかーーー銭湯にて 注意しただけで怪我一生ーーー暴力生徒 注意!一秒遅れてます {近頃少し地球の男にあきられたところよ♪ーーーピンクレディ 智恵子は東京には「県民の日」がないと言った 違いがわかる男ならインスタント・コーヒーは飲まない〇沈黙は禁なりーーーアナウンサー 父よあなたはエラはった〇父よあなたは強がった 父替えるーーーあきっぽい母 小さな新設 大きな寄付金 小さな親切 大きな期待 妻をめとれば才だけで見目麗しからず情けなし 月とすっぽんぽんーーー野外ストリップ 妻の耳に記念物ーーーイヤリング 転載は忘れたころならバレません 溺死はくりかえす デモの貼りもの所かまわず 天は人の上に二を書いて作る 天上天下唯我独身ーーーオールドな男女 では、また来襲ーーー台風 天高くWOMAN肥ゆる秋本日はこの辺で~
2012.07.22
コメント(2)
-
暦から・・・♪
3月の中旬に藤森神社で買った京都府神社庁編の「神社暦」を今、開いています。本日21日は、みづのとひつじ、旭川神社や藤沢白旗神社、大阪津守神社、下関厳島神社などが夏祭り。旧暦で言えば、6月の3日に当たり、八白、友引、その次にかかれている「女・除」について書きますと、”女(ぢよ)”は二十八宿のひとつ。10番目の”女”は、芸能を学ぶによく、葬式を出すは凶とあります。二十八宿はもと、月が27日半弱で全天を一周するとき通過する軌道付近の28の星座であって、中国や印度等で用いられたもの。後年、これによって吉凶を占うようになったようです。角・・・棟上げ、婚姻など万事進むによし。亢・・・婚礼、種蒔、衣服裁ち吉。但し造作は凶。?(テイ)・・・婚姻、入宅、酒造、種蒔は吉、衣服裁ちは凶。といった具合で、明日は「虚除」だから、虚=衣服裁ち縫い、着初め、学問始め等よし。 今日明日とも下の字の意味を調べなくては不完全ですので付け加えますと、下の字は「十二直」といって、中国の古代から行われた暦註で、夕方北斗七星の柄が指す方位の十二支と密接な関係を持つとか・・・。建・除・満・平・定・執・破・危・成・収・開・閉の12種類。因みに本日の建は、大吉で万事良いけれど、土をうがかし、船のりは悪し。明日の除はものを捨てるのに都合の良い日。 要約すれば、本日は芸能を学ぶのに良い日で、かつ船乗りと土いじり以外は万事大吉の日。明日の日曜(吟行の日ですが)は、新しい服を着て、図書館で借りた本の内容を活かし、これまで没になった句などはすっかり諦め、捨ててしまうのが良いということのようです。 やはりこういった占いごとは直訳では難しいから、専門家によって噛み砕いて告げて貰うに限りますね。本日の拙作の付録は、悪夢という狂詩曲です。マッキントッシュで15年ほど前につくったものです。「悪夢」
2012.07.21
コメント(0)
-
清少納言&紫式部♪
紀貫之の<男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり>の書き出しで始まる土佐日記は、それまで漢字ばかりで綴られていたものを仮名文を使ったことから、後世の女流文学の隆盛に大いに影響を与えたことは周知の通りです。余談ながら、貫之直筆の日記は見当たらないのですが、藤原定家、藤原為家らの写本が約300年後に、また三条西実隆の写本が360年後に出されていたことは大山崎でのガイドの一助になります。 さて、現代はクイズ番組が相変わらず人気を誇って居て、東大卒、京大卒の張り合いや女子アナウンサーらの才女の活躍が番組に花を添えて居ます。同じようなことが平安時代にもあったようで、麻木さん風なのが清少納言だったのかも知れません。彼女は名著「枕草子」に時折自慢も含めて当時の生活ぶりを残しています。中宮”定子”に仕えた清少納言と、一条天皇のもうひとりの后・彰子に仕えた紫式部とは、なりゆきからも、双方の性格の違いからもライバルとして張り合っていたものと思われます。クイズ形式の知識と即答という点では清少納言が優位にありそうですが、それは表面的な感がしないでもありません。他方、紫式部の知識の深さは、長編「源氏物語」の至る所でさりげなく覗かせています。「源氏」の底に流れるものは”無常観”、一見華やかな王朝絵巻を描きながら、永遠の繁栄などあり得ないというのが式部の想いの中にあるものと思われます。クイズ式ならボタンを押す速さ、単語数で清少納言の勝利、しかし、記述式・論文形式なら紫式部の勝利との予測がたちます。 ただ一言つけ加えるなら、<清少納言こそ、したり顔にいみじう侍りける人。さばかりさかしだち、真字(マナ)書きちらして侍るほども、よく見れば、まだいとたへぬことおほかり>と評したり、・・・自慢たらたらの人は、あとできっと見劣りする とか、やたら風流がっているような人は、決して将来ろくなことはあるまい>などと悪口の限りを並べています。そして少納言をけなす一方で、<私なんか、一の字さえ知らない顔をしているんですから>と述べるに至っては、謙遜どころか嫌味な部分も露呈しています。 少しおっちょこちょいで、やや自慢げな少納言だけど、枕草子にみる観察力と直截的な表現力、これまた愛らしい才女と言うべきでしょうね。 本日の夕刻は、大阪上六のシェラトン都ホテルにて、茨木和生・大石悦子・吉田成子さんらの御招きで、宇多喜代子句集「記憶」の詩歌文学館賞、辻田克己句集「春のこゑ」の俳人協会賞など5名の方の受賞祝賀会に参ります。
2012.07.20
コメント(2)
-
随想・佐賀から大阪へ♪
私が佐賀市から大都会・大阪に移ったのは小学4年の夏休みでした。丁度こちらへ引っ越す頃、先だっての九州地区のように、佐賀では記録的な雨でした。当時の引越しは〇〇運輸のような便利な運送屋がなく、荷造りは自分たちでリンゴ箱に逐一詰め込む時代でした。 京都から佐賀まで来てくれた祖父がせっせと準備してくれました。祖父は丁稚から木綿問屋の婿養子になった人ですから荷造りの名人でした。黙々と働いて、一足先に祖父は京都に帰って行きました。 関門トンネルの復旧が進んでいない為、連絡船で博多・門司を渡りました。大きな船旅は初めてでしたから、甲板の上を行ったり来たりしていました。4歳の妹とうろうろしていると進駐軍に呼び止められました。 ギクっとしましたが、その兵隊さんがにこっと笑っているので止まりました。彼はバッグから今で言うマクドナルドみたいに分厚いサンドイッチを取り出して妹に渡してくれました。「You are a prety girl」そう言いながら。お礼もそこそこに両親の居る場所に駆け戻りました。あのサンドイッチの大きさが当時の国力の違いを歴然と物語っていました。 門司からは夜行列車でした。父の工夫で座席と座席を渡す板を数枚持って来ていましたので、私たち子供はよく眠ることができたようでした。 大阪の住まいは父の会社の社宅3戸の内の一つでした。20坪の敷地に4Kの間取りでした。モルタル造りの木造家屋は、佐賀のとは違っていて、近代的な住まいに思えたのでした。 やがて二学期が始まりました。小学校までは上町線と言うチンチン電車の2駅の距離で、初めて買って貰った定期券を珍しく思いました。勉強の進み具合は佐賀と比べものにならず、京都から佐賀へ行った2年前とは正反対で、クラスメイトにはさぞかし田舎者が来た写っていたことでしょう。
2012.07.19
コメント(0)
-
”京”の語源を探る♪
やっぱり本はできるだけ読んだ方が得をしますね。と言うのも、先日図書館で借りた「京のかくれ話」久田宗也監修、西村豁通編(同朋舎)の中に、”京”の語源などについて、トピックス風に解説してありました。一部拝借し、纏めますと、 「京都の意味は?」と尋ねたら殆ど「みやこ」という答が返ってくる。ならば「みやことは?」と更に追求すると、返答は明快さが無くなって曖昧になるようです。 「京」という漢字をシャープ製の漢字源で検索すると、1)みやこ、2)大きくて高い、3)数の単位で、兆の十倍、現代では兆の万倍とあります。”京”の字を分解すると上は楼閣の一部、下は小高い土台を描いたものとも書いてあります。 また「都」は”ミヤコ”であり、”宮處”或いは”御屋處”つまり皇帝の屋敷のある場所を意味します。長安(今の西安)が西京と呼ばれていたのに大して、京都の原型とされる中国の洛陽が東京と呼ばれていたことから、京には都の意味が含まれているように思えます。 中国の現首都:北京は”元”の時代は”大都”と呼ばれていたようで、それは凡そ100年弱で滅びましたが、京都は馴染んだ名に恥じず、長い歴史の中に逞しい活力を秘めながら生きつづけています。 それ故に、江戸・東京へ遷都された時の、京の人々の驚きと嘆きの深さは計り知れないものでした。平安神宮、京都博覧会、都をどり、時代祭など都人の心を慰めるものが企画・実行されたのでしょうね。
2012.07.18
コメント(2)
-
恋句に寄せて♪
黛まどか著(小学館)「恋する俳句」から適宜選び、エッセイ化してみました。 逢う為の旅に白靴揃えけり 吹田市 本田尚子 ここでいう季語は白靴。愛しい人に逢える、指折り数えて待ち続けた心の昂ぶりが最高潮に達した日、白い靴を新調した女心は可愛いものですね。 遠距離愛また逢うまでのサングラス 埼玉 長尾かおり これは通常の遠距離恋愛なのか、やや問題を秘めた恋愛なのか定かではありません。しかし、色白の、やや痩せぎすな女性の姿が浮かびますね。 祭りにはきっと帰ると云ったのに 大阪 押立眸 作者と都会に居る彼とは遠く離れて暮らしています。村の祭りは二人にとって想い出がいっぱい残っている。正月も、春先にも何度も約束した夏祭りでの帰郷が果たされず、いよいよ遠くなってしまった彼の心に、つい愚痴が・・・。 日本古来の美意識として、例えば”月”にしても、満月に近いか満月そのものよりも十六夜、立待月、居待月、寝(伏)待月という具合に、少し欠けている月の方が風情があると言わんばかりに、多くの秀歌を遺しています。
2012.07.17
コメント(0)
-
レトロとモダンのコラボ本♪
いま京都は祇園祭の一色に塗り固められ、最高潮に達する感がしています。3年ほど前に、乏しい小遣い銭を叩いて買った”レトロ”と”モダン”の入り混じった「京都スーベニイル手帖」。 その夏バージョンは女優・KIKIさんの浴衣や夏服姿と共に、京の観光地、旅館、グッズなどを紹介。少し例を挙げると、ウエスティン都ホテル京都、東福寺の方丈庭園、銀閣寺キャンデー店、とらや四条店、昭和23年オープンの喫茶「ソワレ」、堀川下立売の鳴海餅本店、350年以上前に創業の人形店「小刀屋中兵衛」宝ケ池のプリンスホテル、ぎおん萬養軒、通しか知らない古書店・アスタルテ書房、昭和2年創業の「長者湯」、河井寛次郎記念館や上賀茂の焼きもち、塩芳軒の貝づくし、半兵衛麩、太田金物店の急須など。 秋期は薮内加奈さんがモデルとして和菓子”水万寿”の工場見学や京丸団扇、三月書房、元祖八ツ橋屋、法輪寺のだるま、秋紅堂、ほうき専門店の内藤利喜松商店、二保堂茶舗、アサヒビール大山崎山荘、伏見稲荷などを紹介しています。本に綴じ込みの観光メモ、古い舞妓さんのたまご型写真、モダンな模様の千代紙、住所・電話番号入りの各店所在地地図など。若い京都ファンの女性には冬・春期の別冊も含めて、小部屋に飾っておきたい豪華本です。<追伸補足>文中、二保堂茶舗とありますが、一保堂茶舗の誤りです。>
2012.07.16
コメント(2)
-
出水の後の墓のこと♪
豪雨続きによる九州地区の被害状況は想像を絶するほどですが、父がきちんと遺してくれた新聞切抜きファイル、牧村史陽氏の「大阪史蹟地図」に興味を惹く記事がありました。数編ほどを私なりにまとめてみました。明治18年6月17日、折からの長雨に淀川が増水して枚方辺りで堤防が決壊しました。北河内、南河内のみならず、網島、桜の宮など天満川堤防から生駒山の麓まで泥水で埋まったのでした。太閤秀吉公が万が一に備えて造らせた”わざと切り(和佐登幾利)”の堤防の扱いによって、流木が暴れ、川崎橋、天満橋、天神橋、難波橋が壊れ、市内水びたしになったようです。その為、御成橋(備前島橋)の先の網島にあった大長寺、そこにあった治兵衛・小春の心中墓もろとも現在は400メートルほど先に移転していて、寺の跡地は現在、藤田美術館となっています。 さて新聞記事で面白いのは、明治の洪水以前の安永6(1777)年の「難波丸網目」という本には大長寺に鯉塚については触れているものの、歌舞伎・浄瑠璃ですっかり有名になった二人の墓は載せて居ません。ところが24年後の「葦の若葉」(蜀山人著)には、<南に行けば野田村なり、小さき流を渡りて右の方に大長寺あり、ここは網島という所なりけり。門の内に地蔵堂あり、その側に鯉塚あり(中略)その右のかたに一の石のしるしあり 釈了智・妙春信女 俗名 かみや治兵衛・きの国や小はる寛政七年丙辰に七十五回忌の卒塔婆をたつ、これは世の人浄るりに作りてかたり伝へし紙治と小春の心中せし処なり>とあって、その年には墓があったことが解ります。 一方、翌年の1802年享和2年に大阪に旅した曲亭馬琴の「覊旅漫録」によると<紙屋治兵衛が墓は大坂網島大長寺にあり、近日の大水にこの大長寺決水口にあたり墓所混乱して或るはおし流し或るは崩れたり、故に治兵衛が墓は見ずにゆかずしてやみぬ。>とありますから、たった1年の間に、治兵衛らの心中墓が流されたこと、江戸・明治期にも洪水が頻繁にあったことが解ります。参考までに以下のサイトをhttp://kajipon.sakura.ne.jp/haka/h-gizoku.htm「世界恩人巡礼大写真館」http://www2.ocn.ne.jp/~webpeco/timeinotabi.html「地名の旅」
2012.07.15
コメント(0)
-
常日頃が大事という話♪
これは今から8年も前、母がまだ元気に暮らして居た頃に、このブログに載せたものです。< 日頃の行いって大事だなぁ~って思った話です。 実家で二泊して朝の散歩の道すがら、いつも大きな黒ぶちの犬(バーニーズ)を連れている愛くるしい顔のお嬢さんと口を聞きました。少し話をしていると、彼女のお宅はこの境内の真後ろ。「〇〇という家です」と仰った。「じゃ~私の実家の傍ですね?△△という家ご存知ですか?」と尋ねたところ、「はい、知っています。」それから亡父の話に移りました。 「私、お父様から化学方程式を沢山教えて戴きました。化学の先生ですね?」と仰るので二度びっくり!・・・「いいえ、親父は国語の先生でした。」「ええ~っ!化学のこと詳しく教えて戴いたので、てっきり化学の先生かと思っていました。」 それからワンちゃんの話やご近所の話などして、私は散歩を続けました。実家に帰宅して朝食を摂りながらこの話を母にしたところ、母もそのお宅のことを詳しく知っていました。 90歳に近い祖母さんの居られることや二姉妹のことなど・・・。まぁ、近所の散歩途上に逢ったのですから知り合いであってもおかしく無いのですが、 亡父がこのお嬢さんたちに笑顔で接し、心の中を占めていたという事実がクローズアップして来たのです。誰にも優しく・・・という信念を貫いた亡父の生前の行いを垣間見たのでした。 内弁慶という言葉がありますが、そうでは無くて、家庭内では亭主関白(勿論優しい時は優しいのですが)、雷親父であった亡父が、世間では仏さまのような柔和な人柄であったことが、俳句がらみの人だけに限らず、全ての方々に向けられていたということでした。 不肖の倅ながら父の血筋を、ある程度は受け継いでいます。亡父ほど自己中心では無いにせよ、七つの顔を持つところなど、そっくりなのです。 ”生前の日頃の行いの大切さ”を身に染みて感じた本日のお散歩でした。> ここに登場したバーニーズ犬は今も元気で、朝のゴミ出しの折など、吠えていることがありますが、”コール、コール”と名前を呼んであげると、彼も猶更、呼応して吠えるのでした。
2012.07.14
コメント(0)
-
世の中の歪♪
毎日のように不幸で腹立たしいニュースが報じられていますね。戦後の日本は驚異的な復興を遂げました。それは輝かしいことではありますが、同時に「時を大切にする」ことを手放して来たのだと愚考しています。戦後から20数年までを顧みると、アメリカ的な資本主義が日本人の胸中に入り込み、伝統的な日本古来の価値観を根底から覆す部分も一部では蔓延って来ていました。 職人さんの技術が落ちて来た。外人力士制度を導入した相撲界では、禅にも似た”道”というものを棚上げにして来たので、”立ち合い”の呼吸合わせが複雑化して<勝てばそれだけで良い>に近い反エチケット的な風習が大勢を占めています。 話を今回の学校不信に転じますと、所得倍増に続いて核家族が一戸の単位になりつつあって、昔の道徳的な価値観が廃れていく一方で生じている現象と思われます。 昔は子供に大きな夢を抱かせてきました。大きくなったら何なる?総理大臣や大将などが主流。ところが今や小学校高学年の頃から、具体的な進路、競争に勝つ為の教育中心に変化して来ているのです。だから自分たちの甘い汁ばかり考える一部の官僚、政治家、そして学校の体制にも。責任を取ろうとしない卑怯者ばかりが上位に陣取ってしまっているのです。 もう一点付け加えると、北野武さんは世界的に評価されている偉人ではありますが、彼がテレビ画面において、ひょうきん族以来の”いじめ的振舞”を今なお継続していますね。成人した大人なら少しは手加減しますが、小中高校生には・・・・。その悪習が職場においても・・・。 人を押しのけても自分だけが有利な立場になるよう、そのノウハウ、技術ばかり磨いて来た人たち。大津の学校は氷山の一角、きっと日本全土の公立学校でも同じように、教育委員会という権力だけ一人前の一掴みの人々によって、歪曲した命令系統に屈服しているのでしょう。 時を大切にするこころ、自然を大切にするこころ、自分以外の人々を大切にするこころ、親や祖父母を大切にするこころを絶やしてはなりません。
2012.07.13
コメント(4)
-
にいにい蝉が鳴き出した♪
テレビでも報じていましたが、数日前から”にいにい蝉”が鳴き始めています。梅雨の晴れ間に覗く太陽の力加減をみると、もう真夏が舞台の袖に控えている様子が解りますね。この梅雨どきは、まるでオセロの駒のようにはっきりとした裏表が垣間見えるのです。 子供の時分には、にいにい蝉の鳴く期間や、油蝉が謳歌している日数が今より長かったように思います。ところが、ここ5、6年はと言えば”熊蝉”の独断場の感がします。熊蝉は子供心に、蝉の王者と尊敬していましたが、最近その威厳はとみに衰え、町のごろつきのように、歓迎されず、、尊敬されず、疎まれる存在になってしまったともさえ。温暖地域としての日本が、猛暑日の続く亜熱帯地区、熱帯に近いような気候に変化しつつある中、節電に勤めなければならい上に、暑苦しい熊蝉の大音響を聞かされて居ては堪りませんね。 植物に目を転じますと、一時大変蔓延っていた”檜扇”がはっきりとした色合いの花をつけていて、他の庭草花と束ね、仏壇の供華として家内は選んでいます。この檜扇はね、根っこが丈夫で、球根が土中に増え続ける生命力の強い植物です。リフォーム前のこの寝室の場所に檜扇王国を作っていたことを思い出します。 この家購入当初一面にあった芝生が消えゆく時の流れにそって、一時廃れていた”捩花・文字擦草”が愛らしい色合いで、天に向かって伸びている様は、本当に平和。必ずしも同じ場所に出る訳ではなく、安全な場所を選んで顔を出すようになっています。今年も大好きな捩花を見ることができ、幸せの真っ只中にいるような日々です。
2012.07.12
コメント(0)
-
肩書って、大したことはない♪
男女を問わず人間は欲の塊で、成人するにつれ社会的地位や肩書きへの欲求も大きくなっていくように思います。私は都市銀行に居ましたので、先輩や同僚、後輩たちの出世欲をつぶさに見てきました。 そんな環境下にあって、出世ということにそれほど興味が無かったのは親譲りなのかも知れません。 父は勤務時間中は最大の努力を払うけれど、企業の犠牲者になる積りはいささかも無く、帰宅後の余暇を如何に過すかということに注力していたように思います。 それは多岐に渡る趣味の多さ、知識の豊富さに裏づけされていました。星座・数式・古文・俳句・演劇・歌舞伎・宝塚歌劇・舞踊(都をどり他)・落語(漫才)・美術・デザイン・歴史・美食・和菓子・・・・数え上げても際限が無いくらい。 ところで企業人が退職し、傍系の関係会社で再び肩書のある名刺が使えるのはせいぜい十余年程度だから、六十五歳を超えた頃から肩書きのついた名刺は使えなくなってしまうと、その人物に威光や力感が無くなってしまうように感じることが多々あります。寧ろ、その御夫人の方が社交的でパワフルに生活していらっしゃることが多いように思います。 私は大した肩書きも無かったから、退職後の悲哀感など皆無で、自由人になれた喜びを噛み締めていました。・・・そう、人生は肩書きが取れた老後(六十五歳)からが、真の力比べなのかも知れません。
2012.07.11
コメント(2)
-
駕ガを枉マげる♪
先日紹介した矢沢永吉おっと矢沢永一著「教養が試される341語」から、幾つか拾ってみました。1)駕ガを枉マげる=枉げては無理にでもとか、強いての意 味。貴人の乗る牛車が車駕。 百人一首の<春過ぎて夏来にけらし白妙 の衣干すてふ天の香久山>と詠まれた持 統天皇(天武天皇の妃)は、未曾有の水 飢饉に際して駕(ガ)を枉(マ)げて葛 城山の役行者を訪れ、降雨の祈祷を求め られた事から、貴人が身分の低い者を強 いて訪れるのが本義。2)忌諱(キキ)に触れる=タブーを侵したり禁令を破る事。 古代ギリシャの哲人ソクテスは理不尽な 法によって死刑を言い渡され「悪法と言 えども、法には従わねば」と、自ら毒杯 をあおった。また、中国の老子も「自分 が生きていくためには、国の禁令=忌諱 に触れずにおくべき」という言葉を残し 悪法に逆らって死ぬような愚挙を冒さず 身を守る心がけが大切であると説いた。3)正鵠を失わず=ぴたりと的(マト)をついた指摘、表現、 または術策の事を掲題のように表現。 古来、弓場には的の中心に”正(みそさ ざい)”か”鵠(白鳥)”が描かれてい た。出来得るなら、正鵠を失わない意見 をこのブログにも遺したいなあ。4)驥尾に付す= 驥=一日に千里を走る駿馬の事。「驥足 を展(ノ)ぶ」は、優れた人がその才能 を思う存分発揮する事。驥尾=駿馬の尾 っぽ。ゆえに<優れたリーダーに従えば 凡人でも事を成し遂げる>の意味。 大阪の橋下グループが日本の施政をそっ くり変えて下さるのか?本日はこれまで。久しぶりに付録の拙作。雑音があってお耳障りでしょうが・・・。”追悲録”
2012.07.10
コメント(0)
-
アンテナこそ個性発揮のみなもと♪
ブロードウェイのタップ・ダンス。50人が同じ振りをして観客にパワーを贈ります。一方、サーカスのピエロも、暗い生活とは裏腹のコミカルな演技で客を惹きつけています。 人を感動を与えるには、先ず、自分自身が感動する飛び切り上等なアンテナを持って置かなければ、伝える「ネタ」が育ちません。どんな些細な事柄でも見逃さない貪欲で冴えのある触覚(通常の人が見落とす材料)が必要となります。 であっても、一つ仕入れたから、それで足りると言う訳には行きません。いろんな「ネタ」を自分なりに繋ぎ合わせて一つの作品を作ることで個性という宝を手に入れる訳です。 ところで舞台人にとって要求されるのは、表情や声や身ぶりで人の関心を抱き込むことだから、ショー・ダンスをしている人(例えば木の実ナナさんなど)は、宵の明星のように瞳を輝かせていらっしゃる。 たった二つの瞳であっても、顔の表情と全身の表情だけで、人々を楽しい国へと誘うのです。 本来、人間の成長は受身から覚え始めるのですが、受身だけでは一人前として育ちません。 受身の間に知り得た知識や感動を、今度は伝える側に立って行動しなくては進歩しません。僅かな経験・知識を元手に、相手に伝える術(すべ)を実体験から学んでいく人が成長が速いのでは? 仕入れてはそのアレンジの仕方に気を配ること。美味しい料理も仕込みの良否が鍵を握りますね。一旦爆発的に売れっ子になった芸人やタレントが1年経たずしてテレビ画面から消えるのは、世に出るまでの「ネタ」の収集不足、或いは「ネタ」があっても、その応用が下手で、瞬時の受け答えに活かすことに不器用すぎるから・・・。 舞台人は稽古を積み重ねることによって、先ずは安全圏内の演技を披露することが出来ましょう。 此処までは誰もが、その努力によって約束されているようですが、その一歩先を踏む域に達するには、その色づけ、味付けとなる日々のアンテナ・触覚・感性の精度が大いに左右するものと思われます。 奇術師のマギーさんは中学を卒業して東京に出、奇術の勉強を始め、漸く場末の舞台に立たれたそうな。不器用なりに精一杯努力し続け腕を磨いておられたのですが、観客には一向にウケませんでした。 ところが、舞台で「自分は不器用なんですよ」と本音を口に出したところ、お客様がどっと笑って下さった。それ以来お客さんの心を掴むことが出来たと回顧して居られました。不断の稽古をベースとして個性を加味して行くこと、それが観客を虜にするのかも知れませんね。
2012.07.09
コメント(2)
-
これは贅沢、見事な小冊子♪
以前にも書いたこの小冊子「鴻」は、やはり銘書の仲間に挙げても良いと思われます。 拙文ながら部分的に再び載せますと <こけし作家の筆で和紙に書かれた「鴻」という小冊子1号から14号(17年5月28日)。 発行人は茶室「鴻」の主、渡辺 鴻という方で、こけしを中心とした郷土玩具の収集家です。 記念すべき第1号の内容は、齋藤松治(高湯温泉)のこけし紹介。また遠苅田の長老:佐藤茂吉の手紙を披露。 続いて木ぼこの鑑別というコーナーでは、本田鶴松、本田亀寿、本田久男、四亀健康らを紹介。・・・中略・・・ 父の貰っている第1号の限定品Noは159号、表紙はこけしの筆画。2号は秀一の筆(限123番)で2号から編集後記があります。 4号は佐藤広喜の筆でNo61番と言った具合で、表紙絵の見事さ、内容の濃さ、どの号をとっても、 こけしの収集家には垂涎の出そうな贅沢品と思えます。これはわが家の家宝の1つとして代々残して行かねば・・・。 参考までに以下のHPは如何でしょうか?「木人子閑話(17)」
2012.07.08
コメント(0)
-
「ベルサイユの薔薇」想い出の記♪
アスコム社発行の「ベルばらと私」を読み始めると、一番手の榛名由梨さんから順に汀夏子、鳳蘭、安奈淳、松あきら、瀬戸内美八・・・と演じた折の想い出記が続いて掲載されています。各人がそれぞれの立場で役づくりに苦労された訳ですが、その要点をまとめてみました。 榛名さんの場合、一番手だから先ずは頭髪その他を池田理代子さんの原作に近いように工夫されました。眉毛の端と端の場所から角度まで似せて描くとか、演出者・長谷川一夫さんの「目の中星(☆)飛ばしや!!」という冗談がでるほど真実味を帯びた化粧を披露されたところ、みなさん感動されたそうな。 印象のある記事は、<そもそも、「はじめ舞台に出てくるときは”榛名由梨”で出てこい」って先生が言うわけ。オスカルではなくて榛名由梨で登場しなさい。いわゆる男役の榛名でよい。しかし演じていく途中からオスカルとしての女の気持ちになっていけということだったのよね。>女として生まれながら男として育てられたオスカルの役づくりは、通常の男役とは微妙に違うところが難点のようでした。 オスカル役を諦めていた汀さんには、宝塚歌劇団としての続演が決まり、幸運が回って来ました。また、余りにも大柄な鳳蘭さんは、オスカルは不自然なので王妃を救おうとした貴公子フェルゼンの役、1975年たまたま海外公演が重なっていたので、海外公演組を選ばず、国内に残っていたらオスカル役が転がり込んできたというラッキーな安奈淳さん。彼女は舞台と私生活とをはっきり分けるタイプだから、オスカル役も地のままで演じようと自然な気持ちで演じられたようです。 いろんな失敗談が盛られていて、例えば地方公演では体育館だったので、昼間の公演は暗転部分の着替えが丸見えだったり、演技の流れが最高潮のときに〇〇さま、お母様が外でお待ちですという呼び出しが何回もスピーカーから流れ、舞台が台無しに・・・だとか・・・。 ベルばらQアンドAでは、タカラヅカとは? 「ベルばら」といえば?今の私からオスカルへのメッセージは? 同じくアンドレへのメッセは?フェルゼンへのメッセは?生まれ変わったらもう一度タカラヅカに入る?好きなセリフは?女心として惚れた男役は? 苦労した役は? もう一度やりたい役は?という質問に対して、かなり個人差のある回答がありました。 しかしいずれにも共通することは、宝塚という厳しい世界で鍛えられたことや教え込まれたこと、苦労したことや涙あふれる喜びが、その後の彼女らの人生や生き方の指針、基礎となっているということでした。
2012.07.07
コメント(2)
-
失くした筈のノートが・・・♪
私たちの青春時代には歌ごえ喫茶が流行り、一方でロカビリー、そしてグループサウンズなども流行っていました。手軽に音楽を楽しむには、ピアノやギターがあればいい、という訳で、独身時代はクラシック・ギターを買いました。5本の指を駆使するアルペジオも時には奏でましたが、専らコードをリズムで奏でる程度。それでも自分の伴奏で気ままに歌うのだから、爽快な気分になっていたことを思い出します。 或る日を境に、この楽しみが分断されました。そう、大切な和音コードを付した歌詞ノートが見当たらなくなっていたのです。向日町の家から、リフォーム後の当地へ転居した際に、いずれかの段ボール箱に納まったまま見えなくなっていたらしいのです。それが、先日見つかりました。文具の極東の、少々上等な大学ノートには、36程の横線が入っています。曲の題名を一番上のところに、1番から3番までの歌詞を(自分としては)丁寧に書き、アルファベット大文字のゴム印を使って、AMとかDM、E7、E、F、C、D7、G、G7などのギターコードを赤色スタンプで押印。これさえあれば、自分が伴奏者を兼ねながら、好きなように歌うことができたのでした。釧路の夜、ラヴユー東京、湯の町エレジー、湖畔の宿、雲に乗りたい、小さな日記、禁じられた恋、ある日突然、スワンの涙、<童話、桜の園、思い出の旅情、あおぎりの歌、かわいい人、エメラルドの月>異国の丘、上海帰りのリル、有楽町で逢いましょう、今は幸せかい、坊や大きくならないで、東京の人、君は心の妻だから、初恋の人、恋の季節、夕月、受験生ブルース、真夜中のギター、昭和ブルース、GREEN FIELD、空に星があるように、<テレビのアンテナほか、クレハホームソング多々>のべ140曲以上が網羅されている大切なノートです。ギターの弦を支える器具が一部壊れているので、中古品でも良いから、近々買い求め、心のリフレッシュに努めたいと思っています。
2012.07.06
コメント(2)
-
いよいよ祇園祭♪
7月に入ると1カ月もの間、京の人気スポット、祇園八坂神社のイベント・祇園祭の行事が続きます。2日には市役所の市議会議場において、恒例の巡行順がくじ引きで決められました。しかし、従来の観念を覆すような試みが行われていて、先の祭は長刀鉾の先頭と船鉾の最後尾、後の祭グループは北観音山の先頭、南観音山の最終ぐらいは常識として知っていましたが、結論として、先の祭、長刀の1番、蟷螂山の4番、5番の函谷鉾、21番には放火鉾、22番の岩戸山そして最終の船鉾はくじ取らずの固定順位、またあとの祭グループでの1番(通番24番)は橋弁慶山、続いて北観音山、29番目の南観音山、そして、今年から加わる大船鉾(唐櫃)が後の祭の最終且つ全体の最後尾の33番となる固定の順位として、くじ引きをしない山鉾となっています。 くじ引きでの1番を引いたのは郭巨山いわゆる二十四孝の釜掘山、次いで霰天神、通算6番には油天神山、綾傘鉾、占出山、そして大きな図体の月鉾、10番目が孟宗山、太子山、木賊山、鉾では4番目の菊水鉾、伯牙(琴割)山、四条傘鉾、芦刈山、鶏鉾、白楽天山、山伏山、恋愛のご利益・保昌山という順位、あとの巡行グループの1番くじ(通算26番)は鈴鹿山、不自然な格好した浄妙山がこれに続き、黒主山、南観音山、鯉をかたどった鯉山、八幡山、役(エンノ)行者山そして初お目見えの大船鉾となりました。後祭の橋弁慶山は従来の北観音山に代わって、実に140年ぶりに先頭順位で巡行します。町内の喜びはいか程か・・・。 任意の山や鉾の名前から検索されますと、You Tubeの画像が楽しめます。父は山鉾町の生まれ、育ちでしたから、7月になると祇園祭モードになる人でした。物置には、祇園祭に関する書物や切抜き、グッズなどがまだ残したままにしています。京都新聞誌上では、祇園祭の特集欄を設けていただいています。
2012.07.05
コメント(3)
-
憂さ解消?ビックリハウスNo11♪
昨日そして本日は月刊俳誌内の投稿句集の校正作業で終日本部務めです。今し梅雨とて、鬱陶しい日が続きますが、例によって、大爆笑・ビックリハウス版「大語海」の教訓編(ス~タ)の抽出例にて憂さを払拭して下さい。〇スター新春かくし子大会 捨てるカミあれば、拾うヤギあり〇住まいは木から〇せまいながらも楽しい厠(カワヤ) 狭い日本そんなに太ってどこへ住む せまい日本、だから急げばはやく着く〇せまい日本、寝返り打ったら海へ落ち〇銭湯を知らない子供たち 背に腹をかえようとして腸捻転 青年よ大志たことを言うだけ言えよ 線路は続くよここまでは 〇損な女のひとりごと たらちねの母を背負いて一本背負い 田がために稲はなる 太平洋ひとりボッキ 棚も木からできる 助けたい人、わらをも投げる 食べ物を粗末にすれば、仏さまのバッチが当たる〇只今の包装で見苦しい点がありましたことお詫びします(アルバイト嬢)本日はこの辺で~
2012.07.04
コメント(0)
-
やさしい京鹿子(草)♪
わが家から長岡天満宮の境内までほんの数分、母と起き伏ししていた頃は早朝の散歩コースでした。八条ケ池の手前には店がふたつあって、ひとつが同じ住宅街でも店を出しておられる「花子」さんの店。 最近は喫茶や貸部屋なども併営しておられ、グレープフルーツを漬けた清涼水を無料にしておられます。月末の土曜日に、その花屋さんで”京鹿子(草)”を数株、販売しておられたので、さんざん迷った挙句、1株購入、玄関先に植えました。私の所属する俳句結社の名前がこの可憐な鹿の子絞りの花に由来しています。 父の生前にも、またリフォーム前の庭にもありましたが、工事の加減で結果的に枯らせてしまいました。リフォーム後の新居から6年、大好きな”百日紅”と”京鹿子”が揃い、また同じく淡いピンクの捩花も近々、顔を出してくれそうなので、やっとこ思いが叶ったような気分です。参考までに、いつも覗かせて頂いている”季節の花300”さんのサイトをつけておきます。下野・下野草(高原に咲く)よりもやさしさが違うのです。「季節の花」
2012.07.03
コメント(0)
-
六月の拙句♪
結婚以来、家内はいつもトイレに一輪挿しを飾ってくれています。盆栽の世界観も一輪挿しの世界も、ひとつの小宇宙ですから、俳句の世界に通じるのです。ここ数日は擬宝珠の淡い紫いろがこころを癒してくれます。 さて6月の拙句の一部は以下の通りです。〇父の日の三十余冊の古日記〇父の日を忘ることなき長女なる◎薔薇を剪る忽ち両袖直(ヒタ)濡るる〇呂川越え律川を越え青楓 この句は三千院ちかくの風景を詠みました。△薄暑はや鉄の匂ひのまち堺 大阪支部句会に参加、副主宰から特選にしていただき、短冊もいただきました。◎南宗寺三好列墓の草いきれ〇誘蛾灯かすかに水の音のする 路面車のフリー切符や夏帽子 訝しき秘史のある寺梅雨に入る 墓碑二つ庄兵衛吉べゑ青梅風 夏草や武人茶人の眠る寺 夏芝やはるか向かうに利休の井 このほかありますが、現代俳句協会の全国大会への出句協力の責がありますので、公には出来かねる状態です。もうすぐ一番好きな花、捩花(文字擦草)が咲きます。首を長くして、その日を待っています。
2012.07.02
コメント(0)
-
瓶生花と小野妹子♪
先日、本居宣長の”あぶり出し”の件で本文をまとめて掲載した日置昌一著「ものしり事典」には予期しないような事柄が述べてあるので非常に退屈しません。掲題のように、生花に小野妹子が登場するなんて思いもかけませんでした。花の小枝を手折って瓶に挿し、室内に飾り自然の美を取り入れた風習は既に平安期の文献にあるようですが、この瓶生花は元来、仏への供華から始まっており、仏教の伝来とセットで小野妹子が関わっていた模様。 武家社会の鎌倉期になると、(人を殺める)無常観から野辺の草花にまで心を寄せるようになりました。室町時代、銀閣寺で著名な足利義政の頃、相阿弥真相が華道に秀で、村田珠光の茶道と時を同じくして元服の花、出陣の花、祈祷の花、三具足の花などという形式を固めて行き、(文献としては谷川流が古いものの)その伝を受けた六角堂の執行・池坊専応が池坊流派を興すに至りました。秀吉の時代には茶人として名を成した千利休は、茶道と一体化した華道家として注目するに値する人物でした。 再び時代を遡ると、嵯峨・大覚寺において、平安期に嵯峨天皇が臨幸され、境内にある菊島に小舟でお渡りになり、枝ぶりのよい菊をひと株おとりになって花器にお飾りになった。華道でいう、天地人三才のありさまを見事に表現なさったとか。これをきっかけに大覚寺では、華道としての免許を天皇から授かった由。 千利休、細川三齋(忠興)、古田織部(重勝)、小堀遠州(政一)、近衛信尹といった茶人はこぞって、華道にも優れていました。のちに広口の花器も出ましたが、いずれも銅製のもの、明治時代になって初めて陶器の花器が出ました。
2012.07.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1