2012年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
火事を待つ木♪
米国のニューヨークでは自然の猛威の前に大変な事態になっていますね。上前淳一郎さんの「読むクスリ(20巻)」から見つけた掲題の”火事を待つ木”というのはオーストラリアの話でときどきニュース番組等で目にする光景ですね。 コアラの好きなユーカリの林が山火事になった時には、何週間もかけて燃え続くようです。あのユーカリは油を多く含んでいるので、実は大変燃えやすい木。南半球のオーストラリアでは1~3月にかけての夏場に吹く風は威力があり、空気も乾いているので樹木同士が擦れることで自然発火します。それ故、異常乾燥期には戸外での一切の火の使用を禁じています。トータル・ファイア・バンという法律が発動され、放送されます。タバコのポイ捨てやバーベキュウ、ゴミの焼却など一切駄目で、違反したら2年の禁固刑。 ところが、火事をお蔭で、ユーカリ林に混在するアカシアは子孫を残して行くのだそうです。種子はインゲン豆のような形の固いサヤに入っていて、少々の事では種子が外へ出られないのですが、大火事のお蔭で、火に炙られて種子が弾け、地上に落下。大火事が雨や消火によって消えたあと一斉に発芽する仕組みになっているようです。一方、地下にしっかり根を張るユーカリは、幹が黒焦げになっても平気の平左で新芽を出し、燃えカスを栄養分として育ちます。 本日の拙作は、少し派手な曲、京都祇園には祇園会館があります。今はお笑いの吉本興業が使っていますが、昔はここに”京都マハラジャ”がありました。そこへ2、3度足を運んで同じように踊りながら、私もマハラジャ用の曲3つにチャレンジした次第です。実に単調ですが、昔はこんな感じでしたよ。ディスコギャル
2012.10.31
コメント(0)
-
たばlこ占い♪
旧・日本専売公社の小冊子に「たばこマナーー読本」があって、掲題の記事が書かれています。 <ライフコンサルタントの浅野八郎氏の見解では、たばこを手にするとき、個人差が一番あらわれるのは、親指と人さし指の動作で イ)親指をアゴにあてて伸ばして吸う人 →男性的でねばり強く、かつ頑固なタイプ ロ)指先で軽く持つ人 →やや女性的ながらも神経こまやかな心配りのできるタイプ ハ)指の奥にはさむ人 →スタミナ満点、活動的で社会性も十分なタイプ ニ)掌で口を覆うようにして吸う人 →寂しさをカモフラージュしている内気なタイプ ホ)逆にてのひらを外に見せて吸う人 →開放的で世話好きなタイプ一方、たばこの消し方から判断すると a)灰皿の端に軽くあてて灰を落とす人 →他人に対する思いやりがあり、 感情を抑えることのできるタイプ b)逆に灰皿に押し付けて消す人 →決断力に富んだ行動派 c)煙を消さずにおく人 →自己本位で周囲の事を意に介さないタイプ d)吸殻を同じ長さに並べておく人 →カネのやりくりがうまく、注意力に富むタイプ う~ん 解るような解らないような・・・。間もなく大阪俳人クラブの吟行大会の開催の為、家を出ます。司会進行役です。 本日の拙作はオーロラをテーマに曲にしました。不協和音が多いのと、全般的にやや単調なこと、禁じ手である平行4度進行を使っていますが、 宇宙規模の気象、オーロラーの雰囲気をお伝えできるンならお慰み。”オーロラ幻想編”
2012.10.30
コメント(2)
-
ユダヤ人の知恵♪
先月中旬に逝去された樋口廣太郎さんはアサヒビール中興の祖と崇められた人物で、私たち「大山崎ふるさとガイドの会」がご案内する山荘美術館の”琅玗洞”には樋口さんの墨痕が彫られています。 樋口さんの話によると、欧州でユダヤ系の金融関係者と会ったとき、親しくなると彼らのご先祖の墓に案内する習慣があって、歴史的に迫害を受け続け、無念のうちに亡くなった人々の墓前に連れて行くのだそうです。<わたし達は残虐なものを見たり、聞いたりしていますが、見ないよう、聞かないように心がけています。>と彼らは言ったそうな。日本にある”三猿の教え”にも似た対応の在り方で、それを彼らは目休め、耳休め、頭休めと表現しているようです。見ないようにしたり、聞かないようにすることで、ストレスを溜めないようにし、怨念を超越して生きて行こうという国民性が出来ているようです。 ところで樋口さんの話の本題に戻れば、視界に見える余計なものを見ない工夫をして、美しいものだけを見る訓練をしたのだそうです。それを教えて下さったのが、あの東山魁夷画伯。魁夷画伯と同乗の車で名神高速道路を走っていたとき、窓越しに比叡山が綺麗に見えるのだけれど、沿道に林立する照明灯の柱が何度も景色を遮るので、「台無しですねぇ」と漏らしたところ、「柱は目の前から消してしまえばいいのですよ」と平然と仰ったそうな。要は半年ぐらい練習すれば、余計なものは目に映らないとのこと。大層苦労した結果、樋口会長も、9カ月目ぐらいから目の前の邪魔なものが見えなくなったということです。 本日の拙作は軽井沢の雰囲気を曲にしてみました。 「軽井沢にて」
2012.10.29
コメント(0)
-
変った町名・名古曾町♪
郵便番号616-8405は何とも優雅な名前の右京区・北嵯峨名古曾町。 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞えけれ九条家に主流を握られ祖父・実頼、父・頼忠同様、正二位権大納言どまりながら「一条朝の四納言」と称された藤原公任の和歌に出てきます。近くには大覚寺があり、九月には龍頭舟、鷁首舟を浮かる大沢池があり、名こその滝はここに注いでいました。奈良の旧勢力に嫌気して京に都を移された桓武帝の意志を継がれた嵯峨帝と兄の平城帝との確執を経て、安泰、強力、永遠をイメージする地として嵯峨の字を充てられた証拠が諡号や別院の名にあります。 また「枕草子」では清少納言が<野は嵯峨野、さらなり>と綴り、平安京の政治力、富、華麗のすべてが嵯峨野に集約されていると評した美しいところ。先述の大沢池には、水が幾筋にも岐れて傾斜地を走るという”多岐(滝)”が注いでいた。この滝を作ったのは百済河成その人で、官人ながら画家でもあった。「今昔物語」によれば、<河成は世にならぶものなき絵師で、滝の石もこの河成がたてた>とあるように、滝殿といえば何処そこの滝でなく、嵯峨院の滝と限られるほど著名であった。 嵯峨上皇が亡くなり、貞観十八年(八七六)に嵯峨院が大覚寺にあらためられ、その後しばらく滝殿の水は大沢池に注いでいたものの、十一世紀半ばには水勢が衰え、 褪せにけるいまだにかかる滝つ瀬の 早くぞひとは見るべかりけると後拾遺和歌集に赤染衛門が案じたように、やがて嵯峨院の滝は涸れてしまった。この世をばと権勢を読んだ藤原道長の嵯峨遊覧のお供をしたのが藤原公任で、冒頭の和歌を詠んだと言われている。後年、大覚寺の滝殿の石組みが解体され、藤原冬嗣の邸「閑院」に移され、あとかたも無くなったという。現在堀川通に面した京都国際ホテル辺りが「閑院」に当る。さて本日の拙作は、”追悲録”です。音が割れてお聴きくるしいでしょうが・・・。
2012.10.28
コメント(2)
-
茶会は旅籠にて♪
昨日は午前中には歯の治療、すぐ昼食を済ませ一路、大山崎中央公民館前に集合。招待客は少人数と思いきや、江下大山崎町長はじめ、30余名が続々集まり、近くにある川崎家を訪いました。 会場となった川崎家は「高槻屋」と号し、参勤交代の諸大名が宿泊した由緒ある旅籠だったところ。江戸後期の「浪花講定宿帳」には、向日町の「富田屋」などと併記される優良旅館だった由。一昨年のプレ国民祭、昨年の国民祭(国体の文化版)の”大茶会”を出発点とする「友あそび」という茶道サークルのご尽力で、後続の30名を含め60名が参集、ガイドの会もと会長のF氏、N氏らを含め、着物姿の男女も多々見受けられ、優雅な雰囲気に。茶会のお菓子(饅頭)は京菓子舗「老松」さんの手によるもので、この日の講演会も社長・太田 達氏の日本古来の信仰と宴を源とする文化がコラボしているという趣旨の「信仰 宗教都市京都」がテーマでしたが、話術に長けておられ、寸暇も飽きさせることのない自由闊達に、話があっち飛びこっち飛びの展開でした。時々クイズ形式で茶会客に問われ、正解者には、ご持参の菓子や記念グッズを自ら手渡しされました。 ラッキーなことに、羊羹の話が面白く閉じた瞬間、<よう考えたら・・>と言いましたら、それが上出来?老舗・老松さんの茶席菓子集の綺麗なトランプを下さいました。わが家には父が集めたトランプが、かなり処分したにも拘わらずまだ沢山ありますが、今度は私のものとして残すことになりました。 参考までに「老松」さんのHPを。 さて本日の拙作付録は、ギター曲の一例です。”GUITARその1”
2012.10.27
コメント(0)
-
一つの林檎を絵に描けば、・・・♪
生きるって事は食べて寝てさえ居れば果たされるものの、人間的でありたいと思えば、存外に難しいものですね。価値観や倫理観については一概に言えない部分があって、簡単に片づけられないものを含んでいますね。 丸い食卓の上に一つの林檎を置き、10人が輪成りに腰掛けてその林檎を写生したとして、呈示された作品が同じ絵になるかと言えば、そうではありませんねぇ。 絵の上手、下手は別としても、画用紙に描かれる林檎は、やはり10通りの林檎になってしまいます。倫理や善悪の基準は、その時代によって刻々と変化して行きます。美、つまり美人の典型も時代によって、様々に変遷して行きます。 例えば、個人的には、近い将来、再び濃いめの眉が流行するような予感がしています。当初は誰かの手によって、人為的に美の基準が変えられて行きます。細い眉毛の良かった時代、太い眉毛が流行った時代、細身で華奢な女がもて囃された時代。巨乳で無ければ人では無いように見られがちだった時代。 世の中に流されるか、自己を主張を貫くのかは各個人の自由に委ねられます。 先入観や噂はさておき、全ての事を白紙の心で一旦受け入れ、自分の物差しで世の是非を判断して行きたいと常々思っています。ゆめゆめ、噂や氾濫する情報だけで判断の基準にはすまいと思っております。 本日の拙作は、ピアノ曲です。Pre For HIROMI
2012.10.26
コメント(0)
-
珠玉の名言集 ♪
半藤一利さんの「この国のことば」(平凡社)は机上に立てておきたい程の名著の一つです。大山崎の歴史資料館には行基(聖武天皇から菩薩号を下賜)ゆかりの銅塊が6個保存されています。数年かけてその銅塊を分析した結果、東大寺の大仏さんと全く同じ成分であることが判明。おそらく大仏建立に献身的に寄与した事への褒賞品なのかも知れません。 前口上が長くなりそうなので本論に入りますと、日本最初の大僧正に任じられても行基さんは何の表情一つ変えなかったとされるほど謙虚な人物だったようです。 <山どりのほろほろと鳴く声きけば 父かとぞ思ふ母かとぞ思ふ 行基菩薩>行基さんが永眠されたのは、天平21(749)年2月2日、享年80だったとか。 続いて、俳句の大家・芭蕉翁が鑑真像を見て詠まれた句は <若葉して御めの雫ぬぐはばや はせを> 鑑真さんの偉いところは、日本から懇請されて日本への渡海を何度もチャレンジされたのだけれど度々海上で遭難、失明する傷も負われましたが、6度目にやっと日本の地に着かれたそうな。それは754年1月16日の事で、大仏開眼の2年後。捨て身の鑑真さんに翁も共感されたものと思われます。 桓武天皇は旧体制の奈良に嫌気され、長岡京、そして平安京に遷都を果たされましたが、その折に出された名文が、<山河襟帯、自然に城を作(ナ)す。・・・・よろしく山背国を改めて山城国となすべし。また子来の民、謳歌の輩、異口同辞、号して平安京という> 玄武・白虎・青龍・朱雀という四方の地形が”四神相応”に即していたから千年以上も都であり得たのかも知れません。 本日の拙作は、ミサの席において一番最初に歌われる曲Kyrieです。 主よ憐み給え(キリエ エレイソン クリステ エレイソン)と繰り返し歌うもので哀調ある曲です。 学生時代の4年間、社会人になってから今日まで、いろんな作曲家のKyrieを歌って来ました。 ”主よ憐み給え”を何度も繰り返し想っていると自然に流れ出たメロディです。 終章で半音上げ、転調しています。「Kyrie」
2012.10.25
コメント(0)
-
万福寺の魚ばん(かいばん)♪
亡父の新聞切り抜きに恰好の日記材料を見つけました。それは宇治・黄檗山万福寺の斎堂前の、天井から吊り下げられた木製の魚で、球を咥えています。 約3百年前、隠元禅師が開山したときから、斉堂の前に吊るされ、食事の”時”を告げるために叩かれたもので、魚の形をしていますが、鯉でも鮒でも良いそうです。 口に咥えた球は108つの煩悩を意味するようです。魚という字と木偏に邦という漢字(カイバン)を叩くのはインドの高僧の故事に従っていて、減罪を祈念するのだそうです。 さて本日の付録は「反省」です。両親への反発心で親許を離れ、ひとりで住んでみたものの世の中そんなに甘くはないと感じた若い娘の心境を歌にしました。”反省”1)ひとりになって 初めて分かった 人の温もり 見た目だけで選んだ 過去の男 不誠実と屈辱と そして悲しさだけを 残して行った 会いたくなんかない 道ですれ違っても 知らん顔しよう だけど淋しさだけは どうしよう 2)家庭を捨てて 初めて感じた 親の気遣い 喧嘩腰で通した 過去の対話 愚かさと幼さと そして気まずさだけを 残して去った 謝りたくはない 心すれ違っても 歩み寄りは無理 だけど親子の絆 どうしよう 3)社会に触れて 初めて気づいた 世間の常識 自分だけの自由は ほんの少し 身勝手さと気侭さと そして優越感を 手にしただけ 独立したけれど 思ったほど良くない 将来性ゼロ こころ傷める不安 どうしよう
2012.10.24
コメント(0)
-
秋の千草♪
庭の彩は、ほんの数日間で大きく変わっていきます。玄関側の北庭を彩るのは杜鵑(ホトトギス)の赤むらさきの斑点花。天鵞絨いろの帽子を付けたままのものはこれから裂けて咲きます。物置の手前には、五月を謳歌した山吹が黒っぽい実をつけています。鬼門にあたる所は南天の実が、これから赤く色づくのでしょう。この付近の自転車置き場にも杜鵑。 道路側の西庭は水引草、殆どが紅色。大葉蛇の髭にはまだ緑色の実がいくつも上に連なっています。花水木の実はすっかり落ちてしまいました。根が傷みだした夾竹桃は衰退し、代わってこぶりだった錦木が私より丈が大きくなっています。これからの紅葉が楽しみです。 南面には酢漿草(カタバミ・オキザリス)のピンク色も見事ですが、庭の至る所に石蕗の花が咲き始めました。この花が灯った後には寒い寒い冬将軍のお出まし。まるでカンテラの灯のように庭中が照らし出されます。まだ咲き続ける酔芙蓉。12月になったら白の夾竹桃も、この酔芙蓉も植木屋さんい丸坊主にされてしまいます。母のイメージに近い桜の大樹は、いよいよ鮮やかな紅葉が始まるのです。ヒヨドリの夫婦が時折メタセコイアに止まり、縄張り宣言などするのです。本日の付録は「直美の不幸」 1. 私の人生狂った あいつに抱かれた あの夜 初心な女の性サガが 目覚めた あの夜 一流大学 真面目に卒業して 今じゃ儚ハカナい 浮き草よ ゆらゆら揺れる 笹の舟 ふわふわ浮かぶ 流れ雲 あヽ あヽ とてもやりきれない 2. あいつがやくざと知らずに 世帯をもって 暮らした 何の疑い持たず あいつと暮らした その内不意に 家を空ける日続いて 暮らし貧しく なるばかり 仕事を探し 夜の街 お酒と煙草 覚えたわ あヽ あヽ 子供がかわいそう 3. それでも 時々帰って 金だけ盗っては 出て行く 無理に抱いては 亭主面ヅラして 出て行く いつまでこんな 生活続くか不安 遠い田舎に逃げようか ゆらゆら揺れる 心です 強い女に なりたいの あヽ あヽ 生きるって辛いのね 歌詞とメロディを同時に照らし合わせようという奇特な御仁が居られましたら、 別途インターネットをダブルクリックして戴き、曲名のボタンを押して戴ければ、歌詞をみながら曲をつかんで頂けます。
2012.10.23
コメント(0)
-
魚道(ギョドウ)の話 ♪
魚の多くは春から夏にかけて産卵するようですが、鮭などの様にこれから遡上するものも。日本の河にはダムが沢山ありますが、落差の大きい場所では魚が遡上し易いように階段式のものがあります。数年前、俳句の知人のお誘いで岐阜県の薄墨桜を観に行った折、近くの川に敷かれた魚道を見て、感動しました。 上前淳一郎さんの「読むクスリ 20巻」には”魚が上る階段”と題して、海で育った若鮎が、川を上る際に、人間が取水のために作った堰やダムが多くなって、遡上が思うように捗りません。そこで魚のために作られたのが魚道で、ダムとほぼ同じくらいに魚道の歴史は古いのです。階段式の場合、落差が大きすぎると、魚とて上り切れません。そこで考案されたのが”らせん式魚道”。円筒形のビル内に緩やかにつけられた螺旋階段をぐるぐる回りながら上がるという寸法。円筒形の立体駐車場みたいなビルを川岸に建て、魚を誘い込めば、あとは魚の習性で楽に遡上できるという訳です。北海道には鮭、鱒用に、10メートルものらせん魚道が有るようです。興味ある方は、魚の遡上という検索でtubuを拾ってご覧遊べ、痛々しいほどに段差をものともせずチャレンジする魚たちの姿に胸を打たれますよ。<本日の付録は、はわが作品としては平成10年ごろの遅いもので、18トラックをフルに使った交響詩”悪夢”です。>悪夢
2012.10.22
コメント(0)
-
爽快!天王山ウォーキング♪
8月の下旬から、洋間に太陽が少しずつ入り込むことに家内は気づいていました。今年は9月に入ってもいっこうに暑さは納まらず、そして洋間の床板に容赦なく陽の領域が広がって来ました。 先日、尾道、鞆の浦に旅しましたが、対潮楼(福善寺)の広間に、冬至と夏至に入り込む図がありましたが、週に2回のゴミ出しの折にも、東側の家並みにかかる太陽の位置が、刻々と変って行きつつあることが判ります。太陽系の惑星たる地球の一角を占める日本、唐辛子のような形をしていますが、北端は択捉の北緯45.33’ 南端は沖ノ鳥島の北緯20.25’東端は南鳥島の東経153.59’ 西端は与那国島の東経122.56’と結構幅があります。先だって、経済的領域のことをテレビで報じていましたが、単なる領海と大いに異なって、経済的領域で言えば、日本は海に囲まれているので、世界有数の広い領域を持つ大国と言えなくも有りません。 話がとんだ所に移ってしまいましたが、京都府の南端、大山崎町にある”天下分け目の天王山”のウォーキング、昨日は雲ひとつ無い好天に恵まれ235名もの参加を得ました。サントリービール工場には予約数ちょうどの200名様をご案内できました。最近のご年配者はとてもお元気で、山麓を廻るコースよりも天王山の山頂を経て小倉神社そしてサントリーに至る登山コースの方が圧倒的に多く、7キロの道のりを元気に歩かれた由。私の受け持った山麓コース旗番号No19の内訳は、ご夫婦4組を含む10名様。この西国街道は歴史上の人物、菅原道真、藤原道長、信長、秀吉、前田利家と言ったお歴々が間違いなく通られた道。そう言う歴史所の人物と一体感をお持ちになってお楽しみ下さいと最初に挨拶して、合間のガイドはしょっちゅう笑い転げて戴くような語りに終始、写真等も見て頂きながら笑顔でお別れ頂きました。本日の付録は拙作の歌をお聴き下さい。「荒野」
2012.10.21
コメント(2)
-
今月2度目の借出し書 ♪
なるべく偏らないように意識しているのですが、或る程度、自分好みの本を借出すことに・・・。1)「頭の体操 第5集」多湖 輝著(光文社) わが家には父の遺したこのシリーズがほぼ有る筈で、物置から探し出すのが面倒で借りました。2)「この国のことば」半藤一利著(平凡社) 飛鳥・奈良期、京都王朝期、源氏・平家期、鎌倉・南北朝期、戦国期、江戸(前・後)期、幕末・維新期、明治初期、明治・19世紀終りの各期の流行語(歌も含む)3)月刊誌「京都」本年3月号(白川書院) 古地図、古地図で京を歩く。特集の中に、「道標」をめぐる欄があって、何気なく歩いている道路でそういう碑見つける楽しさは格別です。4)「安田里美一代記」鵜飼正樹著(新宿書房) 最近はすっかり見ることがなくなった祭どきの境内での見せ物。子供の頃、大きなニシキヘビに触れた記憶が生々しく・・・。5)「読むクスリ 20巻」上前淳一郎著(文芸春秋) いつもの愛読書で、この日記を埋めるときに重宝します。丸写しは著作権に関わりますので、極力まとめてから・・・。 さて、本日はボランティア・ガイド「大山崎ふるさとガイドの会」の一員として、好天の中、秋の「天王山ウォーキング」に参加します。事前の全体打合せ会議に出席していませんでしたので、参加総数(おそらく250名)は存知ませんが、予約組の3番手で出発辞令を受けています。毎度の事ですが、本日は道中大いに笑っていただき、にこやかなお顔でお帰り願うつもりです。<本日の付録>はフルート曲です。「フルートの為の試作」 メロディ以外のバック音がテンポを刻むような聞え方がするのは、 各音符の1つ1つ毎に< >の命令を施していない所為です。 パソコン・ミュージックを教えて下さった三重堀さんは、まるでオーケストラの前に座って聴いているような 臨場感を漂わせる”丁寧な譜面入力”を心がけていらっしゃいました。
2012.10.20
コメント(0)
-
にべもないってぇ?
にべもなく〇〇されたとか言う”にべ”。愛想が無いとか、冷たくという意味合いになりますが、このにべは実は魚の名前からきています。魚偏に免れるの免を付けた字が、魚のニベ・。昔は日本の近海でよく捕獲できた魚ですが、白身で塩焼き、似付けても旨いとのこと。この魚の話題はもう一つあって、浮袋からねばっこいニカワが採れるので、強力接着剤の原料にも。これもニベと呼ばれています。 長塚節の「土」には「勘次もお品も其時互に相慕ふ心が鰾膠の如く強かった」という用法があるようです。これを否定形に使った例が「デートの誘いをにべもなく断る」など。 古くからの用法ながら、お互い自分の殻に閉じこもって他人との強いつながりを求めない現代の若者に、似て居ますね。 本日の付録は「みれん雪」 貴方が残した 胸乳の痕(あと)が 出湯の中で 見え隠れ 今夜別れの 今夜別れの みれん雪 追いかけましょうか 諦めましょうか 運命(さだめ)の糸よ ほつれ髪 窓に冷たい 窓に冷たい みれん雪 貴方に添えない 淋しい夜は 心の中で 泣いている 明日も続くか 明日も続くか みれん雪 この作品は既にお亡くなりになった京都のプロの作詞家から仕事中に「みれん雪」というテーマで書いてみないかと電話があって、急いで書いたものです。何度も書き直しました。”出湯の中で 見え隠れ”のみ褒めて貰いました。 「みれん雪」
2012.10.19
コメント(0)
-
時代祭の歴史♪
京都の三大まつりと言えば、5月の葵祭(古典で言う祭はこの祭のこと)、梅雨の真っ只中に行われる祇園祭、そして桓武帝による遷都の記念日である10月22日に行われる時代祭。昨日の句会の席で句友から時代祭招待観覧席の切符を頂戴しましたので、その歴史を振り返ってみたいと思います。基礎知識はインターネットから簡単に入手できますので、ここにくどくど書く必要もありません。 毎年出版される小新聞紙ほどの説明書を参考に綴っていきますと、明治維新によって東京に首都が移り、天皇のお住まいまでも東京に移され、心の中が空白になってしまった京都市民を鼓舞させる催しとして、遷都千百年の記念祭の一環として、初回は10月25日に、延暦文官参朝式、延暦武官出陣式、藤原文官参朝式、城南やぶさめ式、織田公上洛式、徳川城使上洛式、それに園部地区弓箭組、丹波から山国隊などが行列。この催しは大層好評を博し、天聴にも達したようで、爾後、継続的に挙行されました。その後、神幸祭をも加え、ご鳳輦、神宝、調度品なども豪華絢爛となり、事業は平安講社に委ねられました。大戦前後の空白を経て昭和25年には7年ぶりにし復興、婦人列の参加を得て、さらに雅やかになりました。手元にある情宣紙には、法人個人合わせて970ほどの協賛会員が掲載されています。華麗な列の構成人数は、先頭の名誉奉行から最後尾の弓箭組まで数えきれないほどのスケールになっています。 本日の付録は交響曲です。”十字軍の遠征”
2012.10.18
コメント(2)
-
「Spider Girl」 ♪
14日の日曜と15日の月曜にかけて、大学時代のグリー(無伴奏男声合唱)クラブの同期生の1泊旅行(琵琶湖畔)。今回は月曜日が対象になりましたので総勢13名でしたが、急逝したA君に黙祷を捧げ、K君が持参して来て下さった遺影を前に、日曜の夕食後も懐かしい愛唱曲をハモったり、昔話に花を咲かせ、12時前まで和やかに語り合いました。明けて翌朝は近江八幡の城下町や八幡堀界隈の散策、続いて貸切の舟にて西湖辺りを遊覧。 その折、昔わたしが作った曲を聴いていただけるチャンスが無かったので、ここ数日はMACで作った曲を、添えてみたいなと思います。押し付けはわが主義にに反しますのでスルーして戴いても一向に構いません♪ 「Spider Girl」 1)いかす男ナンて 居ないわ 時々居るけど年寄 つまんなーい つまんなーい ハートぐうっと掴んで 放さない魅力を 持ってる男に キスしてキスして 取り憑く 甘えて甘えて 拗ねる そんな素敵な男を 網を張って待ってるのよ Wao! 2)どんな男も わたしに 狙われたらもう最後よ 恐いよ 恐いよ 大きなどんぐり瞳で 悩殺パンチを見舞うわ見舞うわ キスしてキスして 取り憑く 甘えて甘えて 拗ねる わたしのペースのスタート 逃れられない蜘蛛の糸よ Wao! 3)飽きさせない程 いろんな キャラクターあるのよわたしに バラエティ バラエティ だから退屈しないよ 波乱万丈の人生 送れる送れる キスしてキスして 取り憑く 甘えて甘えて 拗ねる 訳も解らない女 それがわたしって言う訳なの Wao!「Spider Girl」 昨日はクラシックをお聴き頂きましたが、本日はガラッと変ってポップスにしました。
2012.10.17
コメント(0)
-
小春日和のような人♪
家と地続きのお隣さんは元阪神タイガースの代表を務めた方でしたが、母が亡くなるひと月ほど前にお亡くなりになり、今は奥様が元気に暮らして居られます。 毎週或る曜日にはお稽古ごとでお友達やお弟子さんが集まれるようで、その日は賑やかな人声が絶えません。私が高校3年、一家が大阪から新興住宅地となった此処へ越して来た当時は、 入学前のお子さん二人が居られたので、私より一廻りぐらい年上と推測していますが、当時も今も、小春日和のような微笑みが印象的な奥さんです。 十数年来、お庭の日当たりの良い場所を畑にされ、大根や葱などいろんな野菜を自家栽培なさっています。ときどきその畑で獲れた新鮮な野菜を裏木戸からお持ち下さいます。わが家内も菜園には憧れていて新婚当初の借り住まいように、ゆくゆくは畑も作りたいと思っているようです。 近所には貸し農園も多々あるのですが、夏場の手入れなどを考えると自宅から離れた畑仕事は敬遠したくなります。我ら夫婦の寝室十畳ほど増築した影響もあって、畑を作るには幾つかの植木を犠牲にしなければなりませんので、躊躇しているところです。 何はともあれ、隣人の奥さんは女神のような優しい御方。 できるだけ小春日和の人でゐやう 星子人生の良きお手本がそばに居られるので、我ら夫婦も一歩でも近づきたいと念じつつ・・・・。(本日の付録)100曲ほどMACで作った中で一番気に入っている曲です。リズムトラックは使用していませんが、五線譜を10以上同時に使用しています。 「懊悩」 哀しいときに聴いていただくと返ってすっきりしていただけるかも?
2012.10.16
コメント(0)
-
69年代(昭和44年)の流行歌♪
物置を整頓していたら月刊雑誌「平凡」の付録、’69年度9月号「夏のオール・ヒット」曲集が出て来ました。勿論、私の”華の独身?”時代です。当時のヒットチャートに列挙されている歌手は 森進一(港町ブルース)、いしだあゆみ(ブルーライト・ヨコハマ)、ピンキーとキラーズ(涙の季節)、由紀さおり(夜明けのスキャット)、橋幸夫(京都・神戸・銀座)、水前寺清子(にんげんどっこの唄)、カルメン・マキ(時には母のない子のように)、高田恭子(みんな夢の中) クール・ファイブ(長崎は今日も雨だった)、佐川満男(今は幸せかい)、黛ジュン(雲にのりたい)、小川知子(恋のなごり)、ヒデとロザンナ(粋なうわさ)・・・・。69年8月新譜からは星空のロマンス(ピンキー)、デートの日記(由美かおる)、池袋の夜(青江三奈)、いいじゃないの幸せならば(佐良直美)、人形の家(弘田三枝子)、もうすぐ陽がのぼる(吉永小百合)・・・。 69年上半期のトピックスから 青江三奈の「長崎ブルース」は238万枚、レコードを並べれば東京から岡山近くまで、売上高は8億8千万円。また売れっ子は森進一、いしだあゆみだったそうな。 昭和43年12月。黛ジュンが「天使の誘惑」でレコード大賞、ピンキーが「恋の季節」で新人賞、佐川満男の「今は幸せかい」のヒットが少々遅れ、”ちょっと遅かったのかい”で紅白歌合戦には出場できず。 グループサウンズの全盛期が過ぎ、それでもタイガース(青い鳥)、テンプターズ(純愛)、オックス(スワンの涙)は健在。 新三人娘の小川知子は、恋人と騒がれたレーサーの福沢幸雄氏の突然の事故死を「夜のヒットスタジオ」で知らされ、悲しみの涙を隠さなかった純情さがファンの心を打って「初恋のひと」が大ヒット。いしだあゆみ、黛、知子の全盛時代を作ったとか。 フォークソング流行の兆しが見えたのもこの頃で、夜明けのスキャット、ビリー・バンバンの「白いブランコ」、マイケルズの「坊や大きくならないで」、トアエ・モアの「或る日突然」、森山良子の「禁じられた恋」などがヒットし始めました。 今日(コンニチ)演歌界の大御所である北島三郎も「仁義」「加賀の女」などで実力が認められました。このほか、伊藤ゆかり「知らなかったの」、奥村チヨ「恋の奴隷」、キング・トーンの「グッド・ナイト・ベイビー」、はしだのりひこ「風」、ズー・ニー・ブー「白いサンゴ礁」、チータの「365歩のマーチ」、箱崎伸一郎「熱海の夜」、藤純子「緋牡丹博徒」、和田アキ子「どしゃぶりの雨の中で」、新谷のり子「フランシーヌの場合」、岡林信康「チューリップのアップリケ」、ブルーベル・シンガーズ「昭和ブルース」・・・・。 もう遠い、遠い昔の流行歌を話題にしてみました。過去はすべて美しく感じてしまいます。浜辺に落ちているガラスの欠けらのように、時が角を削って行くんですね・・・。
2012.10.15
コメント(0)
-
握手が朝の挨拶?
ドイツ人の特徴と言えば、先ず朝の挨拶、しかもそれは握手で始まりますから、職場などでは大変、兎に角顔を合わせたらお互いに目を見つめ合いながら握手し、グーテン・モルゲンおはようと挨拶するらしい。この握手なる仕草、今では各国に浸透しつつありますが、元来、彼らはゲルマン民族の流れ。手に武器を持っていない証拠を示し合う為に行ってきた風習がそのまま名残となっています。 同じ部屋にいる全員と必ず握手するのだから・・・その日初めて見かけたら、相手が電話中でも、打合せ中だろうと、必ず近寄ってきて手を差し出すのだそうだ。国民性が日本に似て律儀だから、握手に手は抜かないから、時として大きな手に包まれる時突き指などもしかねません。突き指しない工夫として、こっとも負けじと強く握り返すのがコツらしい。国民性とは言え、握手に要する時間を仕事・作業に回せば、もっと彼らの生産性が上がるとも?さて、本日の付録は小学5生の時に作った曲、歌詞も殆どできていました。長調と短調を繰り返してみました。 いざない 1小粋な 娘さん こんにちは 今日は 一緒に 歌おう あの歌を エ~エ あの歌を 2澄ましたお嬢さん こんにちは 今日は 一緒に 登ろう あの山へ エ~エ あの山へ 3素敵な お姉さん こんにちは 今日は 一緒に 踊ろう 公園で エ~エ 公園で いざない
2012.10.14
コメント(0)
-
義父が理想像♪
家内のこれまでの人生の中で一番楽しかったのが、おそらく少女期、乙女時代ではなかったかと思います。その訳は、日曜の都度、家族で釣りに出かけたり、近郊で遊んだり、旅に出ていたという話をちょくちょく耳に入れていましたので。旅行での入浴は家族風呂に一緒に入っていたということから家風が推し量れます。 私が家内と見合いしてこれでOKという段階になった頃、職場にお誘いの電話があって、義父は昼飯時に近くのスエヒロのステーキを何度となく馳走して下さいました。結婚してから此の方、義父の怒った顔にお面したことがありませんでした。 外見的に優しい紳士はあっても、玉葱の芯まで優しくて紳士的な人という方には滅多にお会いできませんが、その例外として義父の存在を挙げることができます。社内の社員から敬愛もあつかったであろうことが容易に想像できる人柄でした。 数年前、相思相愛の義母の死から二年数ヶ月で義父も後を追ったことになります。一歩でもこの父に近づきたいと思う齢に達して参りました。 小春日のやうな人との一日かな 星子
2012.10.13
コメント(0)
-
待宵の小侍従♪
大山崎の名刹:宝積寺の仁王門を少し上ったところには”待宵の鐘”がありますが、大晦日の晩には善男善女が並んで除夜の鐘を撞きます。この梵鐘の願文は、 「天下泰平、国土安穏、特庄内安全、十方旦那諸人快楽(ケラク)也」と小文字で彫られていますが、鐘の名の謂れは石清水八幡宮別当の娘:待宵の小侍従に因んでつけられています。 彼女は平安末期の近衛天皇の皇后多子に仕えた女流歌人で、恋人が来るのを”待つ宵”と、”後朝(キヌギヌ)の別れ"とのいずれに趣が深いかを問われた時の歌が 待つ宵に更行かねの声きけば あかぬわかれの鳥は物かは(新古今) と詠んだことから、恋う男性の訪れを待ちわびる女性の恋情をこの鐘に託して後々、待宵の鐘と呼ばれるようになったとか。小侍従は恋の歌の名手だったので、恋の成就に効果がありますよと私たちガイドが説明しますと、女性の皆様は悉くワァーと歓声を上げて下さいます。 数年前、長岡京の図書館で小侍従の詠んだ歌集の資料を入手しました。百首を超えますが、 君こふとうきぬる玉のさよ更けて いかなるつまに結はれぬ覧(千載) 朝ごとにかはる鏡の影みれば 思はぬかけのかひもなきかな(千載) 思ふあまりみつのかしはにとふことの 沈むにうくは涙成けり(続古) 今こそは逢夜にあふと見し夢を いはぬにいむと思ふあはすれ なからへはさりともとこそ思ふつれ けふを我身の限成けり 今こそは絶はてぬとも君ゆへに とまる心は身をもはなれし こうして一部を鑑賞してみますとかなり一途な性格で、思われた男も、或る時は嬉しく、或る時は重すぎて辟易していたのではないかとも愚考する次第です。しかし色恋沙汰は女性の方がお上手で、思わせぶりな詠み方に徹した小侍従に人気が集まったことに納得。
2012.10.12
コメント(0)
-
沖縄では女性側からプロポーズ?
今から数年も前のことですが、NHKの教育テレビ谷啓さんの「美の壺」を録画しておいたら、沖縄特集で陶器、螺鈿、シーサーなどに続いて、織物の話がありました。 沖縄では女性の方から男性へプロポーズをするようです。ティーテジという紅花で染めた手ぬぐいを好きな相手に渡し、その女性を気に入った男性は舶来のビーズで拵えたブレスレットを女性に渡してOKの合図をします。すると女性はいよいよ真心を込めて機織り機を使って男性用の帯をつむぎます。その紋様は藍染色に五つの白四角紋様と、四つの角紋様。その心は・・・・(五イ)つの世(四ヨ)も私を可愛がって下さいね。或いは幾久しく愛して下さいね。 (皆様にお願い)私の所属するボランティア・ガイド大山崎ふるさとガイドの会は毎月内容を更新しています。特に行事などを載せている歳時記欄をご覧下さい。
2012.10.11
コメント(0)
-
京の震災・火災歴♪
建都以来、京都はいろんな災害に遇っているようで す。陽明文庫には重要文化財の「宮城図」が所蔵されていて、村上天皇から白河天皇の御世1世紀余りの間に起きた内裏の焼亡年月日(15回も)が記述されています。 また鴨長明の「方丈記」には安元3年(1177年)に起きた最大級の火事(別名、太郎焼亡)の情況を詳述しています。続いて起きた翌年の火事は次郎焼亡と命名された由。 文禄5年(1596年)に起きた大地震は醍醐寺80代座主直筆の「義演准后日記」に詳しく記されていて、伏見城、大仏殿、東寺を初め、この時代を象徴する建造物の多くが倒壊し、山崩れ、道路破損などもあったようです。 近世の火事では寛文13(1673)年、宝永5(1708)年、享保15(1730)年、そして天明8(1788)年発生のものは、いずれも2日間にわたる大火事で被害甚大であった模様です。 文政13(1825)年7月の地震は余震を伴いながら翌年まで続いたとあり(まるで東北大震災そっくり)御所の築地がことごとく壊れ、二条城の石垣も崩壊したようです。死者も多く、心機一転を図って年号を天保と改元されるほどでした。 北野天神縁起(国宝)には、人間界(火宅)の様子が描かれていて、鎌倉時代の消火風景や逃げ惑う人々がリアルに描写されています。本願寺火災図では、寺宝を担ぎながら走る僧の姿や、燃える屋根が落ちかけ瓦などが飛び散る光景が描かれています。 (参考資料:京都市歴史資料館編集・発行「特別展図録」昭和60年5月8日)
2012.10.10
コメント(2)
-
戦国時代の瓦版??
乱世をスクープ!「戦国史新聞」日本文芸社(1300円)、編者:戦国史新聞編纂委員会、発行者:阿部林一郎 という面白い図書を借りてきました。通常の新聞と同じ造り、形式になっているものです。そっくり転用します。 見出し(事件の顛末)<羽柴軍驚異の大返し>”仇討ちを実現させた外交手腕” <本能寺の変が起きた6月2日、織田軍の軍団長は、いずれも京都から遠く離れた場所にあった。柴田勝家は越中、羽柴秀吉は備中、滝川一益は上野、さらに織田家の盟友、徳川家康は数人の家臣を連れ、堺見物の途中で、畿内は軍事的な真空地帯となっていた。 諸将が引き返してくるまでの時間を利用し、畿内における勢力を確立する、というのが、明智光秀の反逆後の戦略だった。事実、柴田勝家は上杉軍に手こずり、徳川家康は三河に帰国するのが精一杯。 滝川一益に至っては、北条軍に大敗を喫し、上野から伊勢長島に逃げ帰る始末だ。摂津で待機していた丹羽長秀と神戸信孝(信長三男)も、明智軍との衝突を避けており、明智光秀の予定どおり十分な時間稼ぎが可能なはずだった。 しかし、備中高松の羽柴秀吉だけは例外で、6月3日に変の報を受けて以来、迅速に兵をまとめ、6日に高松を出発。1日に30~40キロを進むという強行軍で、12日には富田に到着し、翌13日には明智光秀と雌雄を決した。ちまたでは羽柴軍の行軍速度が大きく取り沙汰されている。 だが真に注目すべきは、変を知った翌日に和睦交渉を成功させ、その直後に撤兵を開始した、羽柴秀吉の転進の速さだろう。中国情勢に詳しい関係者の談話によれば、 毛利家は撤兵開始以前に織田信長の死を知ったと言われるが、羽柴軍は背後を脅かされことなく帰還した。北陸の柴田勝家が、上杉軍の追撃を用心するあまり出遅れた状況を考えると、 羽柴秀吉は毛利家を巧妙に懐柔したと推測される。外交交渉の巧拙が、撤兵の成否を左右した事実は注目に値する。> 1582年(天正10年)版のこの新聞には、ほかに、<わずか12日間の天下 「山崎にて明智軍敗れる」(山城=1582年6月13日)や <「織田家後嗣は嫡孫三法師」”柴田勝家派は面従腹背の姿勢か”>や記者の目のコーナーでは「清洲会議の明暗」 ほかに、「天正遣欧使節、ローマにて出発す」の見出し・記事が書かれていました。 この新聞には明智光秀が襲撃されただろう竹薮小道の写真や、丹羽長秀の人物画、秀吉が三法師を肩に乗せている絵、故織田信忠や織田信雄の人物画、天王山の戦いでの突破口を開いた池田親子の人物画まで載せてありました。 ガイドの時、このように、現代風に説明するとお客さんにも親しみを覚えて貰えるかも知れません。ガイドの勉強は楽しいなぁ~♪
2012.10.09
コメント(0)
-
ふうせんかづら♪
父が愛したこの庭には、いろんな草花や樹木があって、家内が毎日のように手入れをしているものの、その年ごとの出来、不出来、咲き映えの良否がないわけでもありません。知識不足による例としては、月下美人の水遣りの仕方が理に適っていなかった為、今年は花芽が一つしか着きませんでした。柿の樹は、リフォーム時にガレージを作ろうかと思い、一旦地面すれすれで伐ったけれど、ガレージ案は取止めたのでそのままにしていたら、再び幹が出て今や数メートルの大木に成長しているけれど、実の出来栄えはよろしくありません。 きのうの例会の帰りがけ、編集相棒のI氏から、酔芙蓉の種が獲れたら少し分けて下さいと言われ承諾しました。白い花が夕方には薄紙で拵えたポンポンのように桃色に染まり、ふつか後には赤紫色のまま、地に落ちてしまいます。花部分を捥ぎ取ると下には蕾の形をした種部分が黄緑色のままついています。はて?これを干せば良いのかな。 ふうせんかづらは、ご近所ながら亡くなったSさんから頂いたのか、向陽俳句会の方から頂いたのか今となっては記憶にないのですが、わが家では数か所で見ることができます。この種を家内の親しい方のお分けしたところ、その方の庭のぐるりを囲む状態になっていて、通行人から素敵ですねと声をかけて貰えるので、ご主人が亡くなった今も、心が少し陽気になるといって喜んでおられるとか・・・。昨日の例会の兼題だった鶏頭は一年草だから、毎年種を蒔かないといけないようですね。
2012.10.08
コメント(0)
-
秋のみやびに浸る♪
秋の気配が日増しに濃厚になるにつれ、落ち着きを取り戻して来た感が致します。 秋を彩るものは多々ありますが、一番ポピュラーなものは所謂”秋の七草”。 七種類の名前を覚える方法を思いついてから、すらすら言えるようになりました。 「お好きな服は?」→女郎花、薄、桔梗、撫子、藤袴、葛、萩。 源氏物語の手習いの巻には、垣根のあたりに植ゑてあります撫子もおもしろく、 女郎花、桔梗なども咲き初めてゐるのでしたが、色々の狩衣姿の若い男共を大勢連れて、・・・ と書かれていたり、みのりの巻には紫の上の御歌 おくと見る程ぞはかなきともすれば かぜにみだるゝ萩のうはつゆ また桐壺の巻では桐壺帝の 宮城野の露ふき結ぶ風のおとに 小萩がもとをおもひこそやれ やどりぎの巻では中の君の 秋はつる野辺のけしきもしのすゝき ほのめく風につけてこそ知れ 夕霧の巻では一条御息所の 女郎花しをるゝ野辺をいづことて ひと夜ばかりのやどをかりけん あげまきの巻の中宮大夫の 見し人もなき山里の岩がきに こゝろながくもはへる葛かな そして藤袴の巻には夕霧の おなじ野のつゆにやつるゝ藤袴 あはれはかけよかごとばかりも などの歌が添えられてあります。少しは雅の世界に浸っていただけましたか?
2012.10.07
コメント(0)
-
憑き物の世界♪
先日このブログに5冊の借出し書を記しましたが、その内1つが小説家・佐藤愛子さんの「私の遺言」。この本を借りる時、大好きな佐藤さんの本だから、本の半ば以降の頁をパラパラと繰って決めたのですが、何とよくよく内容を見れば、あの世とこの世の狭間の霊に取り憑かれた苦心談なのでした。黄金いろに輝いた衣装を纏い、金色の髪と明るい光彩を放っていらっしゃる三輪明宏さんに助けて貰われた話なのです。 <人が死ぬと「あの世」へ行く。この世は三次元世界、「あの世」は四次元世界で、そこには物資も時間も空間も距離も重力もない。波動の上下によって厳格な縦割制度が作られていて、まず霊界があり、その上に幽界、更にその上に霊界、神界と上がって行くのが四次元世界である。 人が死んで肉体が消滅すると幽体が残る。幽体はエーテル体で(それは人が生きている時、オーラとして肉体の形に添って輝いている)、ひとまず幽現界へ行く。一般に死後49日間は死者の魂はこの世にいるといわれるが、これが幽現界である。「あの世」とは幽現界の上の幽界で、そこへ上がったことを「成仏した」というのだ。(中略)・・たいていは49日を過ぎても幽現界に留まっているという。幽現界から幽界へステージを上げ、そこで霊界へ上がる心境に達すると自発的にエーテル体を捨ててアストラル体となって霊界へ上る。 幽現界(現世と幽界の間)は現世での執着物欲などを引きずったままの世界である。そのためになかなか幽界へ上れず、死者の大半はここにいるといわれている。> こういった調子で、言葉で言い表せない超常現象や幽霊の存在を具体的に説明しておられる。私もむかし、お隣の家からオレンジ色の火の玉が窓から浮遊し、やがて猛スピードで天へと駆け上がっていったのを目視しました。それから2日後にお隣のお婆さんが亡くなられたのを不思議に思ったいます。
2012.10.06
コメント(0)
-
どっちを評価する♪?
上前淳一郎さんの「読むクスリ」を参考に書かせて頂きますと、中国の「十八史略」の西漢宣帝の項に、 或る人の家の竈に真っ直ぐな煙突が立ててあり、その下には薪が積んであったのを、「これでは火の粉が落ちて火事になるので、煙突を曲がったものに取り換え、薪もほかへ移しなさい」と助言した客があったのに、無視して居た為、後日、薪から火が出ましたが、村人が駆けつけ火を消した為、大事には至りませんでした。主人はお礼に牛を殺し、酒を振舞ったのでした。 それを見て一人が言いました。「先日、煙突を曲げ、薪を移せと助言した者の意見を聞いていれば、火事もおこらず、ましてや牛をつぶしたり酒を振舞うことも無かったろうに。消火をした人々だけが持て成しを受け、助言者に何の礼もないとは・・・」 織田信長は部下の教育や使い方に秀でていたようで、彼を一躍有名にした桶狭間(田楽狭間)での戦では、敵将・今川義元に一太刀浴びせた者や馬乗りになって彼を仕留めた者の評価よりも、今川の本隊が桶狭間で休憩しているという情報を持たらせた簗田政綱の方を武功第一人者と評価したようです。(注・桶狭間の戦については歴史学者の中でいろいろ論議されていますが、私見では、このままの説を支持) 衆議院の選挙がいつになるのか不透明ながら、1票の重さ、責任を踏まえた上で投じたいものですね。
2012.10.05
コメント(0)
-
お座敷と足袋の裏 ♪
或る省庁のお役人が職員の教養講座に当時60過ぎの名妓・美智奴姐さんを呼んだそうな。会議室に6、7枚の畳を敷いてお座敷風に設え、100人もの職員の前で、若い頃の苦労話やをどりへの苦心談などを語って貰ったあと、椅子を片づけた畳の上で、加賀鳶という舞を踊って貰ったそうな。事後の労いの語らいに、「今日の畳は、足袋の裏が全然汚れませんでした。今どきはそんな座敷は数える程なんですよ」とお褒めの言葉をいただき、彼は驚いたと言います。美智奴姐さんの話では、昔の料亭では、座敷で白足袋の裏が汚れないよう、拭き掃除が行き届いていたけれど、近頃は畳が良くても廊下を歩いただけでも足袋裏が黒く汚れることも多々あるとのこと。日舞では再々足を上げる所作があるので、足袋の裏が黒いと客への礼を逸するから、今回は有難かったという次第。 美智奴姐さんの舞台となった畳を徹底的に磨くように指示したのは、総務課長さん。何でも彼は地元の旧家の育ちだから、客への心遣いを幼い頃から躾けられていたそうな。こういう些細なことにも気配りをするところが日本の文化なのでしょうね。 本日の付録はお座敷に因んでmacで作った歌です。「京暦」円山公園の枝垂れ桜と篝火、鴨川と杜若(カキツバタ)、嵐山の紅葉、カットしていますが雪の鞍馬を歌っています。リズムの付け方に問題ありです。一日に20曲ほど、ぶっつけ本番での録音ゆえ、ひどい出来ですがご容赦のほど。
2012.10.04
コメント(0)
-
秋って、いいなぁ♪
季節の移り変わりは、空の色や風の音、そして空気の匂いでも感じ得ますね。多感な少年期の2年間を九州は佐賀市内で過ごしましたので、暮れゆく原っぱを吹き抜ける風の触感でも秋を知りました。そう、あの秋は蜻蛉、ヤンマと対峙していましたっけ。小石をハトロン紙に包んだものを2個用意し、2つを細糸でつなぎ、頭上を遊泳するヤンマに向って抛り投げると、何かと寄ったトンボに絡みつきます。胴体を跨いだ格好のこの小道具の重さに堪えかねてトンボは落下。胸の白いメスだとそれを釣竿のような竹の先っちょに結び、遊泳させていると、今度はオスが寄って来るので、捕虫網で捉えます。オスがメスに絡んだ一瞬の勝負が面白くって、時の経つのも忘れてしまいます。正に、小椋桂さんの <疲れを知らない子供のように、 時が二人を追い越してゆく・・・>の世界でした。 現実に戻って、 出窓の前のススキはもうじき絮が遠い旅に出かけることでしょう。 昨日の恋の名残の酔芙蓉は紅く縮み、今朝目覚めた恋は清く真っ白。 風船蔓の殆どが柿渋色に老けながら、透明な風に揺れています。 溝から石垣にかけて、真っ青な蔦には赤い小粒の実が三つ四つ。 もうすぐ花水木が紅葉する中、赤い実が沢山生まれ出ましょう。 暗くて寒い、嫌な冬への先導者・晩秋はほんとうにつれない恋人。 黒っぽい大きな背中(セナ)を見せながら、夕闇の街灯に消えゆく・・・。付録は晩秋をイメージして作曲した交響曲です。”秋夜”風の音、静けさ、そしてやがて到来する冬将軍の足音を感じていただけたら・・・。
2012.10.03
コメント(2)
-
秋だ、恋しよう♪
秋は或る意味、しっとりとした恋の季節。そこで、黛まどか著「恋する俳句」(小学館)の例句から3つ選び、私なりのコメントを。逢う為の旅に白靴揃えけり 吹田市・本田尚子 ここでいう季語は白靴。愛しい人に逢える、指折り数えて待ち続けた心の昂ぶりが最高潮に達した日、白い靴を新調した女心は可愛いものですね。 遠距離愛また逢うまでのサングラス 埼玉・長尾かおり ここでは普通の遠距離恋愛なのか、やや問題を含めた恋愛なのか定かではありません。色白で、やや痩せぎすな女性の姿が浮かびますね。 祭りにはきっと帰ると云ったのに 大阪 押立眸 作者と彼とは遠く離れて暮らしています。村の祭りは二人にとって想い出がいっぱい残っている。正月も、春先にも何度も約束した夏祭りでの帰郷が果たされず、いよいよ遠くなってしまった彼の心に愚痴が・・・。 心だけの清い憧れ、ときめきなら、ひそかに、いくつでも恋する自由はあると思います。
2012.10.02
コメント(0)
-
月見の思い出♪
台風17号の上陸で昨夜は松尾大社や長岡天満宮の名月会はどうなったのでしょう。数年前の名月の夜は、京都は嵯峨・広沢池畔にてすき焼きを賞味させて戴きました。以下当時の様子を再び掲載しますと、 <総勢十二名が言いたい放題のジョーク飛び交う和やかな雰囲気の中、上等な牛肉の美味に酔い痴れました。 ”もうこれ以上食べきれません”状態で「澤乃家」を後にして一行は真っ暗闇に近い広沢池の周りを半周し、枝ぶりの良い松の木の傍から名月を仰ぎました。 やっぱり兎が存在しています。九月の月見は大概雨降りが多く、今夜のように雲一つかからない見事な月を観られたことは何という幸運なことでしょう。 すき焼きを戴いている時に耳元まで届いた笛(尺八)の音は、実は百数十メートルも離れた東屋から聞えていました。琴の音は傍では大きなボリュームなのですが遠くまでは及ばないようで、笛の音の方が通りが良いということを知りました。 岩鼻やここにもひとり月の客 向井去来 広沢池畔にはそこそこの月見客が居られましたが、私はそれらの人々をみんなシャットアウトし、或る一人だけが漫然と月を眺めている処に自分も加わったような設定をしながら楽しみました。 十五夜では無かったので足許は暗く、広沢池を進む舟も闇に包まれてしまいます。月と正反対の方角にある愛宕山の威容は月光を浴び鮮明に見えていました。 風雅にして贅沢な一夜を経験させて戴きました。いつか家内と来ようと思いました。帰宅すると仏壇前の台にはススキや萩がきちんと供えてありました。> この項に登場した「澤乃家」へは、今年の初夏、家族ぐるみで訪れました。付録は月に因んだ拙作です。 「さようなら」
2012.10.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 株主優待コレクション
- クリレスから株主優待が届きました♪
- (2025-11-26 00:00:09)
-
-
-
- ひとり言・・?
- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…
- (2025-11-22 22:12:52)
-
-
-
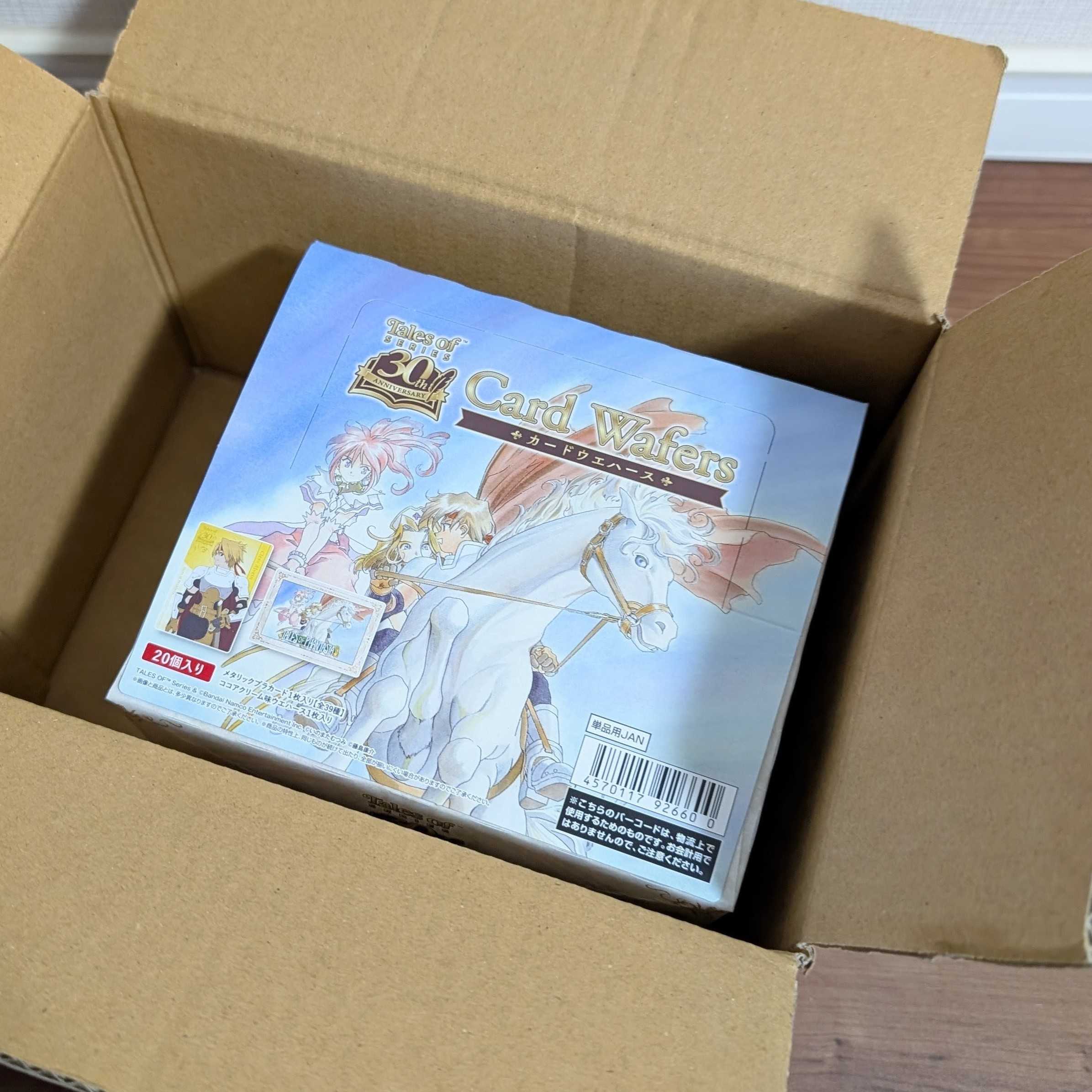
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…
- (2025-11-25 21:50:38)
-







