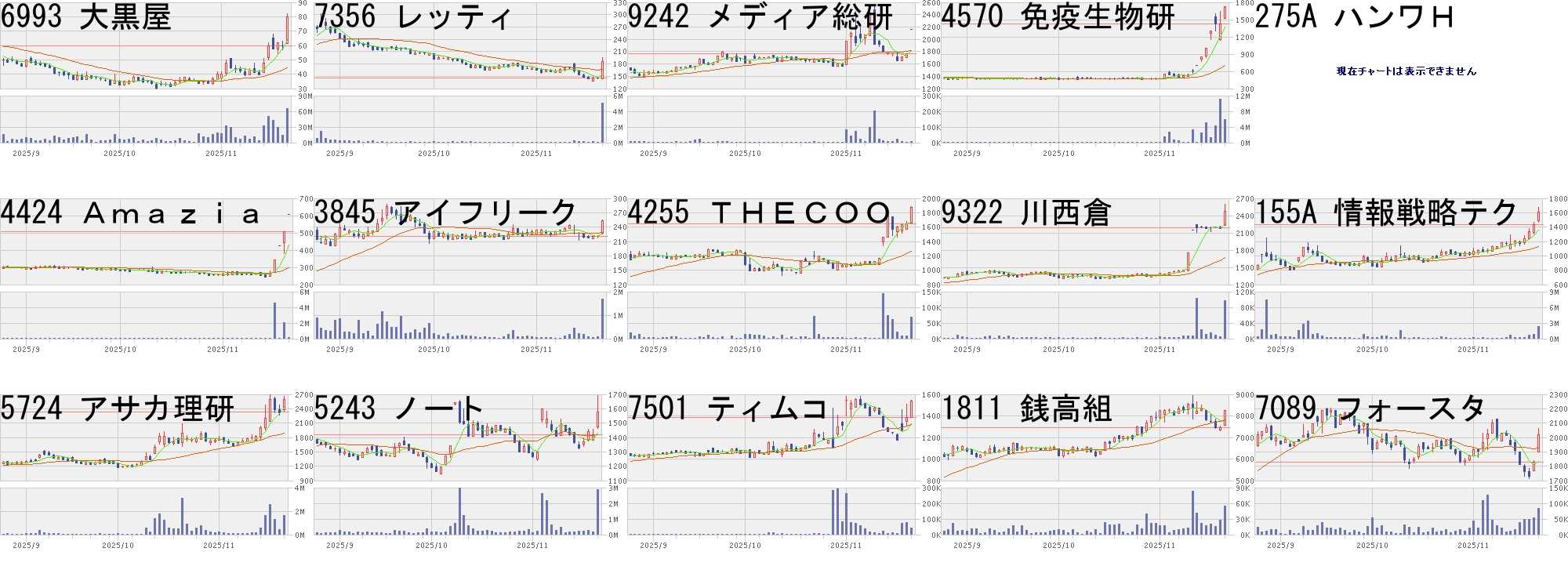2012年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
新・遊びの博物誌より♪
朝日新聞による1980年2月16日の日曜日から始まったと思われる「新 遊びの博物誌」は、最終回(69回)の坂根巌夫編集員のコメントから察するに、後年、単行本として発刊されたものと思われます。残念ながら第5回目の発行ペンダントの分からしか父の切抜きは残っていませんが、科学的に工夫された斬新的な作品が主流を占めます。例えば、”スケープゴート”なる置物は、引っ張っても、握りつぶしても2、3分立てば元の形に戻るマスコットで、上役を殴らずにこれをとか、妻(夫)を苛めずにこれを、息子の耳をひっぱらずにこいつの耳をなどのキャッチフレーズで大人気になったようです。なお、切抜かれた新聞の裏には<巨人の角投手の乱調で連勝が12でストップした記事や、マッケンロー×コナーズのテニス決勝戦のニュースが>面白いのは”聴く時計”と題するもので、指先で触れると電子音にて時刻を知らせる「オードクロン」。楽譜の説明まで付いていて、1時23分ならラ、ミミ、ラララ。2時丁度ならララ、ミミミそして休符。3時ゼロ3分ならラララ、休符、ラララいずれも4分音符です。ほかに惑星運行音を電算機で再現したCDや、”さかさ文字”。ひみつやゆめという平仮名が描き方によってトランプのように上下いずれも一緒。さかさま文字も工夫次第でOK。こんにゃくのように表裏の無いオブジェ。そして世界を凌駕したマジックキューブ。立方体の万華鏡。テレビでお馴染みとなった老後の顔を予想する”エイジ・マシーン”。艶やかな美女をめくったら骸骨に絵が変る山東京伝作の”本朝酔菩提”(1809年作)0~9のサイコロの目を利用して描いた人物画。この辺の切抜き裏面は「国公立大共通一次試験問題」 このように、切抜きのすべてを掲載したいほど、面白い記事満載のシリーズでした。
2012.04.30
コメント(0)
-
ポスターの魅力♪
歌は世につれ世は歌につれと申しますが、歌ばかりでなく、テレビのCM、そしてポスターも折々の時代を映しているように思います。今、ここに一冊のカタログがあって、「ベルエポックの巴里展」と題する19世紀末のフランスにおけるポスター作品を集めたもので、1982年京都は高島屋の6階ホールにて、読売新聞大阪発刊30周年(今なら60周年)を記念した催し物で、カタログ製作者は株式会社アート・ライフでした。 その発刊書に挟んである父が残した京都新聞の切り抜きでは、<パリに集まっていた芸術家たちが、産業や興業界の要請に呼応し、C・M分野に独自の美を築いたものだ。・・・いかにも爛熟した甘美の情緒と装飾性を備え、ベル・エポック(最も良き時代)の雰囲気を今に伝える。 ミューシャ、グラッセ、ティリらアール・ヌーボーの画家、ポスターの父とされるシェレ、ロートレック、ドニー、ボナールらナビ派の画家、ウイレットらモンマルトルに生きた画家らの作品約90点である。> 日本にも竹久夢二を初めポスターなどに秀逸な作品を残した作家が多く居て、いつぞやテレビの「開運!何でも鑑定団」では、大正ロマン漂う麦酒のポスターやその他の作品が一点當り数万円の値がついていました。 田圃の真ん中や村の板づくり壁や電信柱などに張り付けてあった「白元」や「髪の素」など白と紺色の組合せの琺瑯製の看板・・・いろんな金属板が戦前・戦後の風物詩であったことも併せて、懐かしく想い起こされて来るのです。
2012.04.29
コメント(2)
-
加茂・賀茂・鴨?
京都人でありながら、いつもあやふやさに困る鴨、加茂、賀茂の使い分け。「賀茂御祖ミオヤ神社」の通称は「下鴨神社」で下賀茂神社とは書かないようです。一方、「賀茂別雷ワケイカズチ神社」の通称は「上賀茂神社」で、上鴨神社とは書きません。京都を代表する川と言えばカモガワなれど、上賀茂神社の辺りを流れているのは”賀茂川”で、下鴨神社の南のデルタ地区で高野川と合流してからは、「鴨川」に変ってしまいます。 平安時代に下って朝廷から伊勢神宮につぐ崇敬を受けました。但し、祭礼や奉幣、行幸は2つの神社はいつも同日に行われる仕来りになっています。つまり鴨でも賀茂でもよろしいが、賀茂が一般的。この地に勢力を張っていた「カモ」氏にまつわる名称と言えましょう。
2012.04.28
コメント(2)
-
漢字あれこれ♪
<犬は古くから家畜として飼育されて来ましたが、その用途は3つで、口先の尖ったものは猟犬、よく吠えるものは番犬、そして体の肥えた種類は食用に供されました。>遠藤哲夫さんの「漢字の知恵」の一文です。さらに、牛や羊などと共に犠牲としても用いられ、”献”は古来、ご先祖の御霊に犬をお供えとして捧げたことの証とも。”伏”は人のそばに犬がつき従い、腹這いになる形から、ふせる・かくれるの意味を含みます。また”臭”の字の”自”部分は人間の鼻の象徴で、鼻と犬との合成漢字と言えますね。器はお供えの容器に犬の生き血で清めていた犬にまつわる字ですが臭同様、犬が大に変っています。 犬が漢字部首の偏として使われる時は、”?”の形をとります。犯罪の右側や、氾濫の右の字はわくを破って出るという意味があるので、人の道から外れる意味合いも理解できますね。 一方、猫などは鳴き声から、苗ミアオと結合、狐も瓜のクワ・コン。音ではないケースには、狸、狼、猪、狢(ムジナ)、?(イタチ)、獺(カワウソ)。狆は多民族を蔑視した字ですが、日本では愛玩犬の”ちん”に使っています。”獨”の音符の蜀は目の部分をことさら開いたアオムシの象形で、木の葉に取り付いて離れないから、”独”の字は独り立ちの意味と、孟子の「老いて子無きを独と曰う」から、頼る者はなくてひとりきりで居る状態の意味合いも。
2012.04.27
コメント(0)
-
不調な4月の句作♪
俳句に初めて接したのは昭和36年の5月、野風呂先師が拙宅にお越し下さった時でした。京鹿子の古老・西村十七星さん親子、妹と妹の友人も加わって確か7人での句会。父がこの地に新居を構えて間もない時で、近所を散策、たけのこ工場を見学したりしました。 湯気満ちるたけの子工場暗き中 こんな句を詠みました。野風呂翁からのプレゼントは 工場を見たけのこを見て俳句のい 野風呂だったような・・・。その後大学3年ぐらいから俳誌に投句、翌年から例会に参加し、かなりの月数を経て、 遊び居る子らの柔髪に東風伝ふ の句が先生の選に入りましたので、星子の雅号を頂戴しました。それから病気長期入院によるブランクを経て、すばる没翌年の春から再び結社に入りました。 さて句作は易しくもあり、難しくもありって、それが魅力の一面です。今月は不作の月? 隠沼の一隅明かる夕山吹 花祭題目をどりもご奉納 山吹や姫の祟りの池と聞く 表鬼門うら鬼門とて濃やまぶき 鶏冠井(カイデ)より稚児行列の花まつり 夜桜やふたりの鼓動合ってゐる 普段着も一張羅なり啄木忌〇花一輪かそけくあんぬ啄木忌〇祇園から白川沿ひを花曇り 尊王の東湖の刻書木下闇〇風光る唐津の浜の古砲台〇竹秋や隠れ古刹の歓喜天 うぐひすや句縁を希ふ金福寺 白川通いちやう新芽の愛らしき 尼御前は一人静と寂び給ふ 大原やひねもす桜蕊の降る 胴だけの灯籠石や藤枝垂るこのほか数句ありますが・・・。
2012.04.26
コメント(0)
-
京の石碑・陵墓めぐり♪
一昨日はガイドの会の物知り博士Kさんの案内で京の道しるべや陵墓を見て回りました。 さて四条から新京極通りを北へ上り、蛸薬師辺りで寺町通と河原町通とを見比べると河原町通向って低くなっていることが解ります。Kさんの解説では、寺町通の西側は店が立ち並び、東側は寺の境内だった。境内の東側は鴨川の川原地だったから土地が低くなっています。この新京極通も三条に差し掛かるとぐっと高くなっています。それは三条大橋の東西の道筋だから三条通は高い場所にある訳です。 河原町通の信号を渡り、1つ手前の道を鴨川に向って歩きますと、これは牛が引っ張る荷車道で、橋を渡る人は肩に俵1つ分、馬は背中に俵2つ分乗せ、この重さまでは大橋を渡ることが出来ますが、それ以上の俵を積載する牛荷車は、橋よりの低い通りを橋と並行に進み、川水に浸かりながら鴨川を渡った訳で、それは図録にも載っています。また一俵の重量(60キロ)への工夫と言えば、人が使う長杖の上部分は板状になって居て、塀にもたれる時、杖の板にするすると俵を下ろし乗せ、休憩したのだそうです。三条大橋の1番目の擬宝珠には洛陽三条・・・の増田長盛の銘があり、次の擬宝珠には刀傷が残っています。 更に東に向かい、白川橋を渡った橋の袂に石碑があります。これは京都最古の道標。延宝6(1678)年、「京都無案内の旅人の為に之を建つ」と彫られています。此処から少し南に下がった露路を東に入ると、明智光秀の首塚があって、長存寺殿明窓玄智大禅定門と刻した石碑もあります。青蓮院横から粟田神社へ参る道は旧東海道のようで都ホテルにぶつかる為、途中で石段を下ります。 山科に抜ける大通りには昔の車道の轍(ワダチ)跡の筋がくっきり残る石を幾つも壁にはめ込んであります。天智天皇山科陵・諸羽神社を経て東海道を下る道中、「五条の別れの道標」があります。宝永5(1707)年の建立で、大津方面から京をめざす旅人は、ここで左に折れ、渋谷・滑石越えへ出る近道を選んだようです。「右は三条通り」「左ハひがしにし六条大仏、今ぐまきよ水道」と刻まれています。渋谷越えの道を選んだのは、洛中では碁盤目でも、この地点では道は斜めに延びている故。この日のフィナーレは、十禅寺、そして人康(サネヤス)親王の墓詣ででした。仁明天皇の第4皇子は28歳の時眼病から失明されました。琵琶琴の祖として崇められています。 今朝よりは悲しき宮の秋風や また逢坂もあらじと思へばという小野小町の和歌は、この皇子の逝去を悼まれたものとされます。
2012.04.25
コメント(0)
-
男のおしゃれ♪
先日家内が図書館から成美堂出版編の「お父さんのおしゃれ事典」というお洒落な本を借りてきました。副題には、”年齢を重ねた今こそ挑戦!”だとか、”オフスタイルのコーディネート術”が添えられてあります。またその文言の下に、グレイ、ブラック、黄土色のジャケットが3つ並べてあって、それぞれのジャケットの下には、薄い黄土色、グレイ、そしてダークグレイ色のズボンが3つ配されてあって、各3通りの組み合せとなる点線が上下斜めに配してあります。第1章は、定番を着こなす・組み合せで印象を変える。とあって、古き良きグレンチェックの復活・茶のチェックを若々しく・懐かしのアイビーテイスト・これぞツイードの質感・ハウンドスーツを大胆に着回す・カントリージャケットの典型やブレザーの着こなしは自分の感性を信じてなどという見出しで具体的に説明してあります。第2章はNew T・P・O ちょっとしゃれてちょっと気取ってのテーマに沿って、ミュージアムへ・ショッピングへ・レストランへ・仲間との語らい・散歩を楽しむ・・・という具合に目的にあった服の着こなしを伝授してあります。第3章は、基本のおさらい 由来を知り着こなし上手の第一歩をとあり、着こなし上手にみせる5つのパターン(この項には、趣味の良さや、年齢を超えたコーディネートや遊び心、落ち着いた大人のムード)など、また手持ちのアイテムで、とか、基本のおさらい。最終章の表題は、迷わない選び方 どの服に合わせるかを思い浮かべ判断するとあって、事細かにアドバイスが書かれてあります。テレビの昼の番組で、千円コース、2千円コース、5千円コースに分けながら、それぞれに3つの色を決め、早い者順に色を埋めてゆき、ダブった後順位の人は無効となり、4人のうちの最後に残った人が4人分のお買いもの代金の全額を支払う番組があります。最後は3つのコースの買い物を身につけて披露します。コーディーネートの力量・センスの良否がテレビ画面に移されますので、4人の女性の焦ること焦ること。 亡父は非常にお洒落でしたし、高級なものを買わなくても、いろいろ工夫して着こなす人でした。残念ながら父とはサイズが合わず、むしろ義父の形見や叔父の形見の一部を愛用しています。そう言えば、学生時代、母方の祖父の背広はクラシックながら上等でしたので、学生服の代わりに愛用していました。 家内は母や彼女の母の形見を沢山持って居ますので、お出かけの恰好と言えば、母の服、義母のスカート、弟の嫁(故人)のバッグなどのコーディネートで楽しそうです。
2012.04.24
コメント(0)
-
地元の孟宗タケノコ♪
寒い期間が長かったものだから、乙訓(オトクニ)地区のタケノコは生育が遅れがちでした。それでも今月の2週目辺りから、長岡天満宮近くの店や駅舎付近では、朝採りのタケノコが人気を呼んでいます。3月に長姉から”いかなご”のくぎ煮を2ケース頂いておりましたので、お礼に、地元の筍を送ることにしました。少し雨が止んだ折をみて、自転車で太鼓山という地名の竹やぶ道に出しておられる店であれこれ検討しました。やや小ぶりのものはキロ千円、中ぐらいのものはキロ千五百円、真っ白ながら太目のものはキロ千八百円。あれこれ迷い、中ぐらいのを3千円ほどで買いました。家に帰ってからの早速、家内は大きな鍋で煮詰め、灰汁抜きをします。当地のものは掘りたてならヌカは不要とのことですが、念のため、ヌカ入りで1時間半。お店の奥さんが御負けに、小さい筍を3つ添えて下さいましたので、2つは姉への付録、1つはわが家で食することに。午後の曇天のなか、家内は自転車でサントリービール工場近くの宅急便屋へ持参、発送依頼してきました。 タケノコの名産地であるここ長岡(含む向日市、大山崎)では、いろんなお店の採り立て筍を食べ比べることができます。庭には”木の芽(山椒の芽)”も食べごろの程良い大きさになっていますので、これこそ、地産地消と言えますね。 乙訓に棲みたけのこのお大尽 星子注)大尽=大臣
2012.04.23
コメント(4)
-
ビックリハウス版「大語海」教訓編その4♪
ビックリハウス版「大語海」の教訓編”お”の続きです。若干私なりに手を加えています。では、ゆっくりお楽しみ下さい。お客様は髪さまざまですーーーー床屋オーケストラがやっと来たーーー田舎町おこし 煮つけ たき火 団子ーーー桃太郎の好物お供えあれば嬉しいなーーーご先祖さまお楽しみは これ?身体?「お茶飲まない?」このひとことで2児の父老いては子に知ったかぶる老いてなお参観ーーー教育ママ恩を肌でかえす・・・ ありゃりゃ思いきり避けんで下さい・・・ブス同盟おどけの顔も三度までーーー二流お笑いタレントお店できないのが残念です・・・過疎地お肥満なら着てよね♪ーーーLLサイズおじいさんは山へしばかれに、おばあさんは川で円タクにのりました。お代官さま 俺 ゲイでごぜぇますだ ざっとこんなところで御座います。
2012.04.22
コメント(0)
-
今夜のおかず♪
現在使っている電子辞書は2台目ですが、<生活1>の項の9番目は「今日の夕ごはん」。その親切ぶりは、料理の写真から調理時間、カロリー数値、秘伝の隠し調味、食材から作り方まで懇切丁寧に説明されていて、おまけにあと一品まで足してあります。 1日はアスパラのお肉巻+キャベツとツナの和風サラダ。 2日は、いかと絹さやの中華炒め+チンゲン菜とひき肉のスープ。 3日は牛肉と新じゃがのカレー煮+レタスの海苔サラダ。 4日はこんにゃくと豚肉のおかず煮+たけのこの酢みそがけ。 5日はキャベツ入りカルボナーナそして一品はにんじんとレーズンのサラダ。こういう具合で、本日21日は、ひと口しょうが焼きと長いものもずくがけ。本日は、関西現代俳句協会の理事会に出席します。翌日22日は修学院方面での吟行句会。続いて月曜日は9時過ぎ地元出発の洛中(新京極から蹴上ほか)ウォーキング。火曜日は向日町での句会。25日は5月2日本番への下見ガイド。27日の午前は結社の俳誌の発送、引き続き、夕方から大阪俳人クラブの常任理事会で司会役、そのあと宴会があります。翌28日は大阪俳人クラブの俳誌の発送事務。29日は京都俳句作家協会の吟行俳句大会。一昨日は結社の俳誌の最終稿、大阪俳人クラブ誌の最終稿同時に終えました。ほんとうに忙しい日々が続きます。
2012.04.21
コメント(0)
-
藤原定家の歌あそび♪
織田正吉さんの「絢爛たる暗号ーー百人一首の謎を解くーー」の一節に、”定家の言語遊戯趣味”として、彼が30歳の折、藤原良経の求めに応じて「いろは」47字を頭に詠み込んだ文字鎖の一例を挙げられています。それは字数を取るから省かせて貰いますが、素性法師の<今こむといひしばかりに長月の有明の月をまちいでつるかな>を頭とした例を一部紹介しますと、いかならむ外山の原に秋くれて あらしに晴るる峰の月かげまだきより暮れゆく秋のをしければ いづるもつらき長月の月声よわる虫のなくねの友がほに 風もすくなきならの葉がしはむすびける契りもつらし秋の野の すゑ葉の霜の有明のかげ年のうちはよしただ秋のなからなむ こころもたへず人もうらめしこういう具合にあと29首の歌がならべてあります。また「なもあみたふつ」(南無阿弥陀仏)として詠み揃えた例として、七十路のむなしき月日かぞふれば 憂きにたへける身のためしかなももしきに匂ひし花の春ごとに そむきし世をなほぞ忘れぬ天つ風をとめの袖にさゆる夜は 思ひ出でても寝られざりけりみをつくしいかに乱れて蘆のねの 難波のこともつらきふしぶしたましひもわが身にそはぬなげきして 涙ひさしき世にぞふりにしふみみむと草の蛍に道とへど 仰げば高きあとをやは知るつかへこし道をばかへている月の 山の端したふるしるべたがふなこのほか、漢詩の韻あわせのように、和歌の末尾の韻をあわせる歌の群れや、一字百首、一句百首など手の込んだものを多く詠んでいます。
2012.04.20
コメント(0)
-
物語性とリフレイン効果♪
北村英明著の「たのしい作詞のしかた」は間もなく図書館に返却しなければなりません。そこで、”物語性”や”感情の強調のときにリフレーンはその力を発揮する!”という項目を拙作から確かめてみようと思います。<物語性>・・・・・「直美の不幸」 1)私の人生狂った あいつに抱かれた あの夜 初心な女の性(さが)が 目覚めた あの夜 一流大学 真面目に卒業して 今じゃ儚(はかな)い 浮き草よ ゆらゆら揺れる 笹の舟 ふわふわ浮かぶ 流れ雲 あヽ あヽ とてもやりきれない 2)あいつがやくざと知らずに 世帯をもって 暮らした 何の疑い持たず あいつと暮らした その内不意に 家を空ける日続いて 暮らし貧しく なるばかり 仕事を探し 夜の街 お酒と煙草 覚えたわ あヽ あヽ 子供がかわいそう 3)それでも 時々帰って 金だけ盗っては 出て行く 無理に抱いては 亭主面(づら)して 出て行く いつまでこんな 生活続くか不安 遠い田舎に逃げようか ゆらゆら揺れる 心です 強い女に なりたいの あヽ あヽ 生きるって辛いのね 曲はこのようになっています。直美の不幸 またリフレインをつかった曲の例としては、演歌風のもの 「男の背中」 彼は今夜も 飲みに来た 何をしている 人なのか 白いカウンターの右端に 足を組んで ただひとり お愛想云っても 頷くばかり 背中に哀愁 漂わせ 女の胸を 女の胸を えぐる淋しさ 持って来る 独り住まいか 家持ちか 何を思って 飲んでるの 歌も歌わず 何時までも 長い指には 銀の輪が 話相手など 要らないように 背中に哀愁 漂わせ 女の胸を 女の胸を 燃やす淋しさ 持って来る 彼の来ぬ日は 気にかかる 今日でこのまま お別れか いつもの席が 空いている 胸にぽっかり 風の道 会えなくなるのか やきもきさせる 背中が語った 話してた 女の胸を 女の胸を 泣かす淋しさ 置いて行これは私が歌っています。男の背中
2012.04.19
コメント(0)
-
断わり文句の裏がわ♪
清水義範さんの「日本語がもっと面白くなるパズルの本」から抽出しました。若干文章は私流に替えていますが、”お見合いのお断わり文句”の裏側に秘める意味の考察です。1)先方がお地味なので → いかにもケチそうなので・・・2)お派手でいらっしゃるから・・・ → あの娘、どんな躾けをされたんだか・・・3)うちには立派過ぎて 男性側からの場合 → 学歴や家柄を鼻にかける生意気な女だから 女性側からの場合 → 学歴や家柄は肯定できても、真面目すぎて4)家風が合わないようで → 当人はまあまぁだけど、あの親じゃねぇ~兎角こういうことの様ですから、ご用心召されましょうぞ。
2012.04.18
コメント(2)
-
こんなことも♪
京都・高島屋の画廊での”シャガール展”がいよいよ最終日となるので出かけることにして、それまでに先日持ち出した月刊俳誌の空白部分への補充や編集後記などを急いで書き上げ、出版社にFaxしてからでかけたのですが、空白の一つは9行25文字部分。空行をいれて <待つということについて> 竹久夢二は<まてどくらせどこぬひとを宵待草のやるせなさ>と謳いましたが、私達はいつも何かを待っています。その対象物がはっきりしている場合もあれば、サミュエル・ベケットの戯曲「ゴドーをまりながら」のような漠然としたものへの期待・不安感も。 またもう一か所の穴埋めサイズは12行×18文字。これは囲いを入れて、 ”風について” <誰が風を見たでせう ぼくもあなたもみやしない>クリスチナ・ロセッティのこの詩は昔「コドモノクニ」という絵本に載っていました。また李白の<秋風吹不盡 總是玉關情>子夜という女性が兵士として駆り出された夫のことを気遣いながら砧を打っている情景を詠んだ詩ですが、いずれも深いですね。 万全を期して、こういう穴埋めの短いものを即座に書いて送るのも、編集のしごとです。
2012.04.17
コメント(2)
-
愛馬・銀輪のこと♪
家内も私もそれぞれ愛馬ならぬ自転車を持っています。表題の銀輪を広辞苑で引けば、<1.銀製または銀色の輪。2.転じて、自転車>とあります。ですから5.7.5という限られた文字数で表現する俳句には、ンの字を他の字と一括して勘定できないでもない銀輪の方が、自転車よりも場合によっては便利な単語と言えないでもありません。 ところで、この自転車を購入した理由は、寡婦の母が独り住む当家までは阪急電車で1駅先にあり、いよいよ小まめに面倒みる必要があった為、電動自転車の方が足への負担が軽減されるという面がありました。初めて電動自転車に乗った折の感想と言えば、漕ぎ出した時の瞬発力の凄さ、そして坂道を楽々走れることでした。 ・・・そんな吾らの愛馬も、リチウム電池の能力が低下、自民党・公明党による政府が国民にバラまいた2009年の定額給付金、子供たちからもそれを貰って電池のみ新しいものに替えましたが、如何せん、高額だったリチウム電池は、交換後もそれほど持久力の期待できるレベルではありませんでした。自転車を購入した当時の電池の生命力は1週刊から10日ほどの充電サイクルでしたが、新品に交換した2代目のリチウムは当初から1週間もたせる程度でした。あれから数年の現在、もう2代目リチウムもよれよれの状態です。遅かれ早かれ、毎日充電しないと使えない日がくることでしょう。 本当は健康の為に歩けばいいのに・・・重いもの提げて駅から1キロの道、丘を登るのは少し辛いから・・・。駅前近くの一角に、自転車を1年間有料で個人的に置かせて貰うようにもなったので、宥(ナダ)め賺(スカ)しながら、この愛馬と付き合っていく積りです。
2012.04.16
コメント(0)
-
「大語海」教訓編その3♪
ここ数日の雨や風に、庭地は桃色の絹を敷いたような落花ぶりです。こちらの庭にある風流な植物として”一人静”があります。もう少し日が経てば、”二人静”も。義経と吉野で別れたものの頼朝・政子の前で舞わされ、その後行方知れずとなった静御前の舞姿のイメージ。http://www.hana300.com/hitori.html 一人静http://www.hana300.com/futari.html 二人静おそらく父が指導していた俳句の何れの方から頂戴したものと思えます。 さて本日も「大語海」の教訓編の”え、お”から抽出しました。少しだけ笑って下さい。 縁の下の地から文字・・・古代遺跡 栄華ってほんとにいいもんですね(故・水野氏) エルサイズのはら (えっ?ベルサイユじゃないの?) エサを動物に与えないで、ください私に・・・飼育係 演技が悪い つまりNG え~い ひかえい ひかえい・・・メモ 親は泣くとも子は育つ 親子三人見ず知らず 親の血をひく兄弟よりも、輸血の血をひく義兄弟 親馬鹿も使いよう 親ひとり小太り 親分!台風一過の殴り込みです 親方火の車 おまえと俺とは動悸の息切れ (歌)お前を嫁に貰う前に、行っておきたいトコがある→キャバクラ? お父さんお母さん先立つものをお送り下さい お父様、お母様、殺気立つをお送り下さい 鬼はぁ外、ふくわぁ~術 (歌)俺より先に逝ってはいけない・・・夜の関白宣言 男はつらよ・・・寅さん? 男は40になったら顔に赤面もつな まだまだいっぱいありますが、本日はこの辺でお開き~。
2012.04.15
コメント(0)
-
作詞の指南書♪
先日図書館で借りた北村英明さんの「たのしい 作詞のしかた」によれば、<詞を見るポイントとして>イ)情景が浮かび上がってくる詞であるか?ロ)ドラマの状況はすぐわかるか?ハ)主人公の気持ちは伝わってくるか?ニ)新鮮な素材、表現があるか?ホ)詞のテーマは感動的で、共感をさそうか?の5項目を挙げ、例題をいくつか添えておられます。stepとして書かれていることも列挙すれば、訴えたい熱い想いーーーそれがテーマだ!詞は1つの人生を浮かびあがらせることでもある!とか、詞には起承転結をつけ、メリハリをつけてまとめあげる!1番での的確なドラマ設定が作品のカギをにぎる!詞の映像表現はバツグンの効果をあげる!とか、感動を呼び起こす作品は魅力的な主人公の心情がものをいう! それは片想いや孤独感とか恨み、生き様など さて、それならば、「しぐれ茶屋おりくの部屋」の左側下方のfreepage list欄にある拙作は、どの程度のものなのでしょう?
2012.04.14
コメント(0)
-
腰痛三日目ながら、あれこれ♪
わが庭の椿の満開のことや樹齢50年の桜のことには触れましたが、もうひとつ忘れて居ました。玄関のドアを開けた正面には、やや薄色のすみれ(菫)が無数に蔓延っています。南の庭には濃いめの紫色した別種のスミレも咲いています。玄関へといざなう石段横にも、左右に蘇芳が色づき始めました。腰痛は相も変わらず癒えませんが、そんな中、昨日は句会に参加、精記用の用紙や選句用の用紙を私が配布する役目なので止むを得ませんでした。テレビで報道される昨日の祇園・大和大路の事故の影響で、帰路の市バスは東大路三条から迂回する運行となり、原稿と再校の読合せの約束時間を20分以上遅れをとりました。車内から連絡を入れましたので、相棒の方も根気よく待って下さって居ました。本日はガイドの会の広報委員会を休めさせていただき、披講担当でもある地元の句会へ出席のあと、追加原稿及び修正後の百数十ページの校正分を出版社あて持参します。 腰は身体の要に相当する部分、不格好な姿で歩かないで済むよう、一刻も早く治ることを念じています。 では、今から本日用の句作と、校正の仕事に着手致します。
2012.04.13
コメント(2)
-
VIVA大山崎ふるさとガイドの会♪
大山崎町は京都・大阪の接する所にあって、西国街道・山陽道も走っていますから、古くからの要衝の地でもありました。中世、シソ科の”荏ごま”の油を大量生産できる道具を開発したことによって、畏き辺り、政権庁とのつながりも強く、その象徴である「離宮八幡宮」は西の日光と称される程栄えた所でもありました。 私たち”大山崎ふるさとガイドの会”は”アサヒビール大山崎山荘”(古くは大正・昭和期の大山崎山荘)の誕生と時を同じくする平成8年に発足した地域観光ボランティア団体です。昨日、24年度の総会が開かれ、町長を筆頭に町議会議長、教育長、商工会長ら10余名のご来賓の得て、粛々と行われました。23年度の大きな足跡と言えば、1)年間ガイド実施人数が1万1千人を超えたこと2)国民文化祭のイベント”戦国大茶会”を成功に導いたこと(ガイド全員参加)3)宝積寺と山荘とをつなぐ里道を階段化する補修工事4)出前ガイド5)ガイドマニュアルの増補改訂そのいずれもについてご出席願った行政から謝意を頂戴いたしました。 総会というものは円滑にことが運ぶよう万全の体制で臨むものの、いくばくの不安材料が無くもありません。今回の議長に指名され、若干のユーモアも織り交ぜながら、7つの議案を無事承認していただけることができました。実はこの日、持病の「ぎっくり腰」を再発しましたので、痛みをこらえながら大役に臨んだ次第でした。この時ほど会員の皆様のご協力、ご支援をありがたく感じたことがありませんでした。 その後、宴会に入り、50数名が逆コの字形に組んだ4つのテーブルを囲んで、一言ずつ自己紹介など。昨日は生憎の雨天でしたが、安堵感とともに帰路につきました。
2012.04.12
コメント(2)
-
京のお地蔵さん あれこれ♪
「新選京都名所図会」シリーズで著名な竹村俊則さんの「京のお地蔵さん」には、 頭に髪を束ね合掌しておられる花崗岩の洗い地蔵を皮切りに、清水寺本堂内の勝軍地蔵、清盛のドラマにも登場される崇徳院の崇徳院地蔵(聖護院近く)、允恭天皇皇后の御妹ぎみ”弟姫”の衣通姫(ソトオリヒメ)地蔵(東山仁王門近く西方寺内)や、身をもって、強欲な男の目を覚まさせなさった釘抜地蔵(千本上立売の石像寺)、清盛公が馬に乗って通りかかると急に馬が立ち止り一歩も動かなくなった場所を掘られたら出てこられた駒止地蔵は六条河原で処刑された人々の御霊を慰める為に建立されたものが、鴨川の氾濫で行方知れずになっていたお地蔵さん。四条通新京極の角にある染殿地蔵さんは、弘法大師が”十住心論”を説かれた場所で、また、藤原良房の娘・明子(アキラケイコ)は文徳天皇の皇后となられ、このお地蔵さんに願掛け、清和天皇を産まれたので、安産祈願。ご本尊は2メートルもある裸形立像ながら目にすることはできません。夢窓国師が”苔寺の庭”を作られた折、ひとりの異形の僧が大きな石を心の儘に動かし、仕事がはかどりました。四条から来たとう僧に、お礼として国師の袈裟をお譲りなさった。後日所用で四条住心院(この寺のこと)に立ち寄り、染殿地蔵の戸帖を開けてご覧になると、国師の与えられた袈裟を着て居られたので、この染殿地蔵の化身と解ったのだそうです。 洛東では16体、洛北6体、洛中はさすがに多く34体、洛西15体、洛南の10体、合わせてざっと70ものお地蔵さんを紹介してあります。こういう本も1冊本棚に欲しいものですね。
2012.04.11
コメント(2)
-
墓参と花見♪
母への墓参と花見を兼ねて家内と昼過ぎから出かけました。先に大丸にてコーヒー豆を買い、仏光寺にある皇族からの御手植えの枝垂れ桜を見、寺では母と祖母の卒塔婆を書いて貰い、わが家の墓で合掌。本家や分家の墓にも合掌。最近の強風の影響か、数枚散在する別のお墓の卒塔婆は本来の場所に戻しておきました。 河原町五條では、北から伸びてきた寺町通が五條の手前で斜めに分断されています。仏教書専門の古書店には短歌の短冊が売られていました。江戸期のものを大学の教授らが買われるようです。わが家にも古い和歌の短冊がありますので、次回の墓詣の折に引き取って貰うよう手配しました。家内が路地ばかり選んで歩きますので、それに従っていると路地から高瀬川へ降りることもできました。高瀬川沿いの桜は、夜にはライトアップがあるようです。恵比寿神社を詣でた頃から雨がポツポツ。コンビニでビニール傘を買い、家内と相合傘。白川沿いの喫茶店は月曜で休み、この辺りの桜は一部散り始めているものもありました。公の施設は殆ど休館でしたが、偶然ながら今月初めにオープンした喫茶でケーキセットで休憩。それから再び京の町中を歩きました。裁判所の桜もこれからが楽しみ。結局、高島屋まで戻り食堂専門街で中華の夕食。 きのう、2万2千歩を超える散歩で購入した土産と言えば、80歳のお婆さんが作られた飴玉2袋、豆政の”クリーム五色豆”、同じく”すはまだんご”。この州浜団子は家内がずうっと買おうと思っていた品ですが、偶然その豆政に通りかかってゲットしたものでした。
2012.04.10
コメント(0)
-
敬語こそ日本文化の誇りのひとつ♪
敬語・謙譲語・丁寧語というものは、その国の民の知的水準を表す物差しなのでは無いでしょうか?最近テレビ番組の司会者もゲストも、或いは街頭でマイクに向かって話す言葉には敬語も無ければ丁寧語も使われて居ないように感じます。ましてや隣国の国家放送の物々しい語り口の耳障りなこと。 その点日本語は語彙が沢山ありますので光景の描写や意見・感情の表現に不自由しないという利点があります。そういう優れた国に生を賜りながら、妙に言葉を無理遣り切り詰める若い人達の表現力の乏しさ、日本よりも歴史の浅い、文化的に優れているとは思えない国の価値観に染まっている現状を哀しく思います。 他人(ヒト)との付き合いの中で相手を大切にする気持ちは、尊敬語・謙譲語・丁寧語を使い分けることによって伝わることでしょう。そしてそのことは逆に、自分の存在を燻し銀のような好印象を与える効果もあります。 また敬語を使えば相手との軋轢は生じることも無さそうであるし、居心地の良い雰囲気の中に相手を置くという相乗効果もありそうです。 親からきちんと敬語を教えて貰っていない人々が教壇に立っているこんにち、教師に限らず、敬語の正しい使い方を再度身に着け、ごく自然にそれが使える水準に回復し、次世代の者にきちんと引き継いで行くのが私たち日本人の務めではないでしょうか。
2012.04.09
コメント(2)
-
「陰陽師列伝より その1」♪
志村有弘さんの「陰陽師列伝」には、これまで知らなかった闇の風習などが書かれて居て、わくわくします。 人の寿命を司る神である”泰山府君”に因む「泰山府君の祭」は陰陽道の重要な修法のひとつで、あの世から死者の魂を呼び戻す術のひとつとして陰陽師の間で行われていたそうな。日本では平安時代、安部晴明がこの祭を取り仕切り、現在も安部一族が続けているようです。泰山府君のほか、冥道諸神(冥界の神々)をも祀り、天皇や諸侯の延命長生を願う祭を「天ちゅう地府祭」もあって、中世では貴族からの要望が多く、陰陽師たちの大きな収入源になっていたそうな。1002(長保4)年11月には、三蹟で著名な藤原行成が安部晴明に、泰山府君の祭を行わせていたことが、彼の日記”権記”に記されていて、行成は使いの者に<晴明どのに泰山府君の祭の謝礼を届けさせ、米2石5斗、絹5帖。自らも鏡、硯、筆、刀を贈る>とあり、この年は、寿命の延長の祈願文が13通と多かったから張り込んだようです。また、藤原有国という晴明と同年代の官僚が、その父親に従って豊前(福岡東部・大分の一部)に在住した折、急逝した父の為に、泰山府君の祭を行い、蘇生させて話が、鎌倉説話集の「古事談」に残されているとか・・・。
2012.04.08
コメント(2)
-
4月初旬の5冊♪
3月の下旬に5月号用の原稿類を持ち出して居て、それを印字した初校が4日着。翌日の木曜に読合せを終え、昨日、一部追加の原稿も添えて校正済みのものを出版社に提出。これで気分が楽になりました。結社の5月号(1450冊)は今月27日に発送予定です。 一方、俳句結社の多くで構成する団体の機関俳誌4月号(月末発送予定)の初校も到着。いずれ読合せを。さて4月に入って最初の図書は、日記に載せ易そうな本を借出しました。1)「言技を楽しむ辞典」真藤建志郎著(講談社) 副題が<笑いの諺(コトワザ)詞華集(アンソロジー)>とあって、いろは順に古来のことわざが面白おかしく書かれています。2)「陰陽師列伝」志村有弘著(学習研究社) 日本の歴史を紐解くに当り、”闇”やら”呪い”をマスターしておく必要があります。陰陽師を通して日本の歴史を反芻しましょう。3)「たのしい作詞のしかた」星野哲郎監修・北村英明著(成美堂出版) むかし、ソニー作詞通信教育を1年受けたことがあります。作詞も俳句も論文、挨拶文もすべて基本的な共通項がありますね。そのお勉強。4)「京のお地蔵さん」竹村俊則著(京都新聞出版センター) 名著「京都名所図会」で有名な竹村さんの手になる案内書。お地蔵さんは子供の守り本尊。地獄の閻魔大王の本地仏とも。京都の散策の1つとして、地蔵めぐりというのもお薦めです。5)「本能寺の変四二七年目の真実」明智憲三郎著(プレジデント社) 光秀公の側室の子”於寉丸(オヅルマル)の後裔が、明田(アケタ)と姓を変え、明治10年に復姓を認められたようです。本能寺の変が謀反でなかったことを7つの疑問から解き明かす書です。脳味噌に4月の新風を通すのも一興かと・・・。
2012.04.07
コメント(0)
-
「大語海」教訓編その3♪
一昨日に2つか3つの花が開き、いよいよわが家の桜も盛りに向うことでしょう。それにしても今年の冷えはしつこいですね。ながらく控えていました全国から応募されたトンチ作品「大語海」の教訓編の”ウ”から。 馬の耳にイヤリング〇打てばヒビいく 運だめし 今日はどうかな 赤信号 嘘も方言では通じません 上野発の夜行列車降りたら着いた〇生めばみな子 運転中、運転手に淫らに話しかけないでください〇生みの親よりおだての親 「産む」を言わせない少しは笑っていただけましたか?本日の拙作は長閑な春のイメージ「たんぽぽ」皆様のお力で、ぐっと暖かい春を呼び寄せて下さいな。
2012.04.06
コメント(0)
-
谷崎潤一郎の恋文♪
一昨日の朝刊に、芥川龍之介の晩年の書簡や菊地寛らの書簡が宇都宮にある重要文化財・「岡本家住宅」にて見つかったニュースが掲載されていましたが、1989年7月刊行の「美食倶楽部」(筑摩書房)という谷崎潤一郎の文庫本に挿されていた新聞の切抜き。父が鉛筆でH3.9.25と書き添えた見出しは、「一代の力作 谷崎の恋文発見」とあります。 <谷崎が2度目の妻となる古川丁未子(トミコ)に送った求婚の手紙が大阪市内で見つかった。昭和6年1月20日消印の速達封書で、原稿用紙4枚にペン書きで次のような熱烈な文句が続く。「私はあなたの美に感化されたいのだ。あなたの存在の全部を、私の芸術と生活との指針とし、光明として仰ぎたいのだ。私は私の中にあるいい素質を充分に引き出し、全的に働かしたいのだ。(注略)若いし幸いにしてあなたが来てくだされば後世に輝くやうな作品を遺すことが出来ると信じる。そしてその功績と名誉とは、私のものでなく、あなたのものです。・・・(略) 谷崎44歳、前年春には最初の妻・千代を佐藤春夫に”譲り”世間を騒がせた。丁未子は文芸春秋社勤務の23歳。ふたりはこの年4月に結婚し関西に住む。が、谷崎は丁未子以前から知る松子(今年2月没)との交際が深まり、2年で破局を迎えた。そして、大阪の豪商の妻だった松子と昭和9年に正式結婚、生涯を共にした。> 丁未子は谷崎からの手紙類を仲人に託し、仲人は顔見知りの婦人記者に託した。その夫の”長岡京市”在住の林光夫氏(81)が、このほど谷崎文学研究会の場に持参し初めて公開した。というようなことが載っています。 さて本書は「病蓐の幻想」「ハッサン・カンの妖術」「小さな王国」「白昼鬼語」「美食倶楽部」など大正時代の8編から成っていますが、最初の「病蓐の幻想」というのは、神経衰弱な人物をモデル(ほぼ谷崎氏に近い)に使っています。虫歯が昂じて、その不安から、地震への恐怖に話は移り、話の大部分が地震に集中しています。谷崎当人は、汽車に乗ったとき、目的地に着く前に必ずやというほど、決まって、列車衝突への妄想から途中下車する恐怖症の持ち主だということを父から聞いたことがあります。今回、丸1年以上も経つのに東北の皆さんが再々直面しておられる震度5ほどの地震、谷崎銃一郎氏は、その恐怖のあまり、気を失うか、心臓発作であえかなくお成りなのかと想うばかり・・・。
2012.04.05
コメント(0)
-
さくらと母と?
きのう、本部の野風呂会館にて8人の仲間と校正作業に専念して居ましたので、それほど強風を感じませんでしたが、家に独り残された家内は、ほんの数秒の違いで嵐へと豹変した風の勢いに、最低限の隙間にして雨戸を閉め、家中の戸締りを確認し、地面を揺さぶるような物音に独り耐えて居たようでした。日付が変り、先ほど庭に下りて被害等の確認をしましたが、椿の花はしっかり枝に付いていました。雪柳が白い花をほころばせ、沈丁花が満開、黄水仙も元気に群がって咲いています。また父が丹精込めて育てた椿は、数えてみると49株がそれぞれ個性的をひそやかに主張しています。洋間から見て南面のやや左寄りを占める桜の大木は、無数の蕾をつけ、今日、あすにでも咲き始めることでしょう。この桜とは当地に引っ越して来て以来の仲間。桜の大樹には”さくらの精”が宿っているような。そして母亡きあとは、この桜を見るたび、母のことを想うのでした。 庭を占む寿樹なる桜母在(オハ)す 星子
2012.04.04
コメント(0)
-
あちらの漢字との比較♪
今、わが家の庭は椿が一斉に花をつけ、和風の雅を醸し出しています。本日も校正作業のため、間もなく家をでます。日本語倶楽部編の「字源の謎にこだわる本」を参考に、日本と中国のおもしろ漢字比較をしてみましょう。娘 →中国ではお母さんの意味らしい。切手→手を切ること。汽車→自動車、因みにバスは公共汽車、公共車or巴士。 では汽車は「火車」と書きます。汽水→サイダー、そして汽油→ガソリン。火紫→マッチ。打字機→タイプライター。品質→品格、人柄。脚気→水虫。通夜→徹夜。手紙→ティッシュペーパー。従って「信」と書けば手紙になります。 トイレットペーパーは「衛生紙」。料理→処理。だから「菜」なら料理の意味になります。野菜=山菜。生体→楷書のこと。縁故→理由。便宜→安値。発火→立腹だから愉快ですね。看病→診察となってくると医師みたいで誤解を招きそう。では最後に、「毎度有難、御馳走様」と紙に書いて渡したら、中国人は慌てて荷造り。<たびたび災難があります。はやく逃げて下さい>の意だって。
2012.04.03
コメント(0)
-
桜花に寄せて♪
きょう明日と月刊俳句誌の俳句集欄の校正作業にだかけますので、やや手抜きとなりますが、ちょうど5年前の2日の日記を再度掲載させていただきます。 <来る日も来る日も6畳の間から硝子越しに庭の老木に「寒くて気の毒だね・・・、慌てて咲かなくても好いから・・・、でも暖かい陽射しになったら頼むよ」と励ましの言葉を贈っています。 それでも本日(2日)、強い雨脚を幾たびか浴びながらも、我が家の老桜が開花しました。昨年は母と一緒に観たのに・・・・。桜と言えば父が亡くなった6年前、父が教鞭を取らせていただいていたミッション・スクールの庭の大木を、シスター直々のご案内で見せて戴きました。 まだこの目で観てはいませんが、岐阜県根尾村の”薄墨桜”と酷似しているのではなかろうかと思うほど、赤みが薄れていますが、広いお庭に両手を広げた恰好の老桜は まるで数年前逝ってしまわれた4世井上八千代さんの舞姿を彷彿させるものでした。現5世八千代さんは亡父の教え子の一人でしたが、今や祇園を初め京の雅を伝える宗匠になられました。京を愛し、舞踊を愛する私にとって嬉しい限りです。>今年はまだ開花の兆候は見られませんが、その分、椿や沈丁花や水仙やら・・・。
2012.04.02
コメント(0)
-
5班の皆様ありがとう♪
昨日の水辺のガイドは風雨の中、不思議に雨だけのハンディでしたので、初志貫徹を地でゆきました。先ずは5番目の出発組となられた5班のお客様10名に弁当、水筒の準備の確認と全員ビールを試飲されるかどうかの意思確認を致しました。資料館のガラス越しに見える駐車場を見やれば、吹き殴りの雨が降っている状態でした。あとが閊(ツカ)えていましたので、止む無く資料館の自動扉を出るには出ましたが、雨のかからない資料館の軒下で、お客様に晴れのお膳立ての出来なかった”天候の詫び”を入れてから、ローギア、セコンド、トップギアという歩行速度の私案の符牒を説明しました。6.5キロの長道中ですので、進行具合との兼ね合わせで時間調整の良否がカギを握ります。路傍の立て看板を覚えておいて下さい、説明は後ほどと言い置き、先ずは妙喜庵・国宝待庵(利休)の傍を通り、JR山崎駅の軒下で明治維新から10年、刀を所持しなくなって僅か10年ほどで鉄道が走ったという日本民族の、先人たちの能力の凄さを説明。雨模様の中、駅近くの公営駐輪場地下にもぐり、此処に古代の”山崎駅”のあったこと、離宮八幡の今昔などを写真で説明。関戸明神、離宮八幡を簡単に説明したあと、強い風が収まったようでしたので、水辺のガイドを提供することにし、急いで171号線を渡り、河の土手へと移動しました。 後でわかったことですが、風雨に直面した他のチームは安全策を採り、171号線の手前で戻り、山麓コースに切り替えたのだそうです。私たち5班は風に吹かれることもなく、”山崎の渡し”などを見て、堤防の上の道を歩き、淀川河口より36キロの石碑、三川合流の碑も見て、天王山の姿、石清水八幡の姿も見て、蕪村の<菜の花や月は東に日は西に>のモデル地、西条八十の「青い山脈」の歌詞について、服部良一は京・大阪を往復するうち、この風景からメロディを思いついた話など。”狐の渡し跡”にて小休憩、すぐ所定の食事場所近辺で食事を摂ることにしました。名神高速路の高架下でしたが、嬉しい奇跡の感情、この日初めて乾いた地面を見たのでした。後はうまく時間通りにことが運び、1時半の試飲の時間に余裕をもって到着しました。昨日は荒れ天候のもと、104名のお客様が参加して下さいました。どうやら、私たち5班の12人(お客10+ガイド2)だけが、当初予定通りのコースを完遂できたようです。私を支えて下さった5班の皆様、旗持ちをして下さった仲間、ありがとうございました。次の大きな行事は5月第3土曜日19日の”春の天王山ウォーキング”です。どうぞ、この催しにもお越し下さいね。お礼かたがた、ご報告まで。
2012.04.01
コメント(4)
全30件 (30件中 1-30件目)
1