2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年09月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-

ぶどう「甲斐路」
秋は果物も美味しい季節ですね。画像は私には今期初めて食べたぶどう。いただいたもので品種は分からないけれど美味しかったです。ぶどうは好きなんですが、小粒のだと食べるだけで疲れてしまうのは私だけでしょうか?(^_^;)ちょっと大きめの粒のものだと楽しみつつ、食べられるように思います。先日山梨に行った時には、ぶどう園にぶどうがたわわに実っていました。山梨といえば甲斐路という種類が有名ですね。■甲斐路ぶどう■この品種は10月半ばまで食べごろなのでまだ間に合います。薄い赤い色が綺麗で、糖度も抜群です。甲斐路といえば、JR中央本線にも「かいじ」という特急があります。もちろん「甲斐路」のことだと思うんですけど、この前八王子で駅のホームのアナウンスを聞いていたら、アクセントが頭の「か」についていて気になりました。1.「^か _い _じ」2.「_か ^い ^じ」やっぱり2.だと思うんですけどね…細かいですか?(笑)
Sep 27, 2005
コメント(6)
-

Contrex
只今、3箱目に突入しました。Contrexと言えば、硬水のミネラルウォーターの代表格。カルシウムやマグネシウムを多く含んでいるので、体に良いと聞いてはいましたが、以前は日常的に飲むにはちょっと高価でした。最近楽天で安く買えるようになっているので、1.5Lを箱買いしています。軟水と違って飲み始めは、味に馴染まなかったんですが、近頃では随分慣れて、すっかり美味しいと感じるようになってきました。気が着くと一日1.5L近く飲んでいます。コントレックスのHPを見たら「ゆっくりと噛むように飲んで下さい」と牛乳みたいな記述がありましたが、すっかり喉越しを楽しみながらビールみたいにゴクゴク飲んでました…。硬水といえば、よくお通じによいと言いますが、私の場合、それに関して特に影響は感じませんでした。とにもかくにも、美味しく感じるようになってしまったので、ないと寂しくなりました。牛乳でなくても、カルシウムが補給できるのは嬉しいですので、しばらく続けるつもりです。Contrexコントレックスcourmayeurクールマイヨールhydroxydaseハイドロキシダーゼvitologattiヴィトロガッティ■超硬水ミネラルウォーター■いろいろ集めてみました。左から硬度1551mg/L、1612mg/L、1505.75mg/L、1677mg/L。ハイドロキシダーゼは微炭酸、ヴィトロガッティは微発泡性です。どのみち、軟水のような美味しさはないので、口に合うものを選べばいいのではないでしょうか。
Sep 26, 2005
コメント(10)
-

器を使う前に
先日また新たに和食器を購入しました。陶土や釉薬の具合にもよりますが、土物の場合は使う前にしなければならないことがあります。粉引きや貫入の入ったもの、焼締の器の場合、吸水性があるためにシミができ易いので、それを防ぐために煮沸します。米の研ぎ汁を使うと、糠が隙間を埋めるそうなのですが、ただ煮るだけでも、汚れをつきにくくする効果があるそうです。ということで、すぐに使いたい気持をぐっとこらえ、この処理をしてからデビューさせることにしています。琺瑯の大きい桶に入れて煮ること40分。そのまま冷まし、しばらく漬けておきます。その後軽くすすいでよく乾かしてから収納します。使う前にも、染みができやすいものはちょっと前から水に浸しておきます。水を含ませておくことで、汚れが染み込みにくくなるんだとか。焼締の器はしっとりとして色にも深みが出ます。器によってはもっと気軽に使える物もありますが、こんな風に手をかけて使う器は使ううちに味がでてきますし、また愛着も湧いてくるというものです。最近は黒い器を購入することが多くなっています。料理も映えるし、汚れも目立ちにくい。洋食器とは違って、質感や色が物によって全然違うので、面白いというのもあります。今回も大きなお皿は黒いのにしてしまいました♪
Sep 25, 2005
コメント(6)
-

そばがき
先日手に入れた、無農薬栽培国内産そば100%のそば粉。まずはシンプルに味わってみようと、「そばがき」を作る事にしました。考えてみれば大人になってから食べた覚えがありません(^_^;)小さい頃に、父が時々作ってくれたそばがきは…確か、そばの粉を熱湯で直接練ってそのまま醤油や鰹節かなんかかけてワイルドに食べていたような気がします。作り方に自信がなかったので、調べてみますと、そば粉を練る時に、 1.湯を注いで練る2.水を混ぜてから火にかけ加熱しつつ練り上げるという方法に大きく分かれているようでした。その後に湯通しするのは共通です。私は簡単そうな2.の方法で作りました。水で溶いたそば粉を、火にかけて絶えずかき混ぜていくうちにどんどん固まってくるのでだんだん力が要るようになってきます。程よく練り上がったら火からおろし、適当にまとめて沸かした湯に投入。出来上がったそばがきは、お湯をはった器に入れて、そばつゆや薬味を添えるのが王道らしいのですが、私はそばつゆを張った中に入れてみました。浮いているのは岩海苔です。さっぱりしていて、食欲のない時などにも良さそうです。そば粉でガレットやお菓子というのもよいのですが、たまにはこんな懐かしい素朴な食べ方もいいもんですね。次は、更に直球で、まだやったことがないそば打ちにでもチャレンジしてみましょうか(笑)
Sep 24, 2005
コメント(6)
-
バンド合宿
ほぼ一年振りにバンドに参加してきました。学生時代にはいろいろバンドを組んでおりまして、その仲間の中には今でも付き合いが続いている人が結構います。このバンドの友人は地元に帰ってしまっているので、近県とはいえども、行けば立派な小旅行コース。頻繁に行くのはさすがに難しいんですが、それでも声をかけてくれるので、行ける時には参加するという感じになっています。友人が地元で組んでいるバンドにその時だけ飛び込むという形です。今回は合宿という形で、プチホテルで行いました。メンバー全員酒飲みなので、着いたらすぐに日のあるうちから、借りたホールでバーボンを飲みながら演奏。夕食はフルコースとワイン、更にその後またすぐにワイン飲みながら演奏…と深夜までずっと酒&演奏浸り(笑)途中で合流したメンバーの奥様もこれまた酒&音楽好きで皆で大いに盛り上がりました。翌日は仕事だったので、朝ごはんも食べずに早朝に失礼したんですが、仕事場に迎う途中で、仕事キャンセルの連絡がありました。…早くに分っていたらもっとゆっくりできたのに…。まあ、人生こんなもんでしょう(^_^;)楽しい時間はあっという間に過ぎて行きますね。演奏で発散して、心の底から思いきり笑ってリフレッシュすることができました。音楽は聴くのもいいですが、やっぱり自分が演奏する方が楽しい。聴く音楽はジャンルのこだわりがありますが、演奏するとなると、どんな音楽でも楽しいと感じるのが不思議です。今回は久しぶりにピアノを長時間弾いたので、筋肉痛になりそうです。きっと2日後くらいにくるんだろうな…。(練習中のギターも少し弾きましたよ♪)
Sep 23, 2005
コメント(10)
-

オリエンタルハヤシドビー
また懲りずにオリエンタルシリーズから、今回は、『オリエンタルハヤシドビー』です。中味は粉末タイプのルー。これで5~6皿分です。薄切りの玉ねぎと、薄切り肉を炒めて煮込み、火を止めてルーを投入するだけ。カレーよりも材料が少ない分更にシンプルです。味はハヤシライスというよりも、まさに「ハヤシドビー」です(笑)良く言えば、旧き良き時代の懐かしい味。私の祖母はハヤシライスは作ってもらった記憶はありませんが、もし、祖母が作ればこんな味になりそう…そんなイメージです。…一生懸命言葉を選んでみましたが、え~と、そんなわけで、ちょっと仕上げに味を足した方がいいと思います。私は醤油・ウスターソースを少々隠し味に入れたのですが、これでちょっと味が締まります。作る時の注意としては、カレーと同様、ルーを入れる時ダマにならないよう、一旦火を止めてから、少しずつ振り入れては混ぜ、を繰返すようにして丁寧に溶かすことでしょうか。しかし、ずっと気になってるんですが、「ドビー」ってどういう意味なんでしょうね?オリエンタルシリーズは、カレー類共々、どうもこの懐かしい味に惹かれて、リピートしてしまうのでした。過去の関連日記も合わせてご覧下さい。「オリエンタルマースカレー(箱)「オリエンタルカレーレトルト」「オリエンタルカレー」***********後日補足。「ドビー」について。その後山ぶきさんのご要望にお応えして調べたところ、どうも「ハッシュドビーフ(hashed beef)」が「ハヤシライス」となる過程の名前らしいです。hashedはハヤシドになったけど、ライスはまだついてなくてbeefが残っているけど、ビーフのフは取れてしまったみたいな…。こんな説明で分かります?私も理由が解ってスッキリしました。
Sep 22, 2005
コメント(4)
-

Michel Camilo Live
東京オペラシティコンサートホールで行われた、ミシェル・カミロのライヴを観に行ってきました。以前Blue Noteでのライヴが初めてで、観るのは2回目になります。今回はコンサートホールだったので、ちょっと距離感はありましたが、その代わりに(と言うのも何ですが、)盛り沢山の内容、そしてチケットも安くて満足のいくプログラムでした。Part1はソロをたっぷり、Part2は上原ひろみさんとのデュエット、Part3はストリングスアンサンブルと共に自作の組曲の演奏という構成。彼のパワー溢れる早弾きの超絶テクニックもさることながら、ラテンのノリが素晴らしい。しかし、あんまりすごい力で弾きまくるので、さすがのスタンウェイも調律がどんどん狂ってくる始末。彼の血管も切れるんじゃないかと心配になりました。炸裂する超絶パワー&技巧で、会場は興奮の渦。しかしソロは殆どの曲が同じようなテンションなので、すごいのは分かりますが、私はちょっと食傷気味になってきました…(^_^;)観た直後の今なら彼のものまね一発芸がいくつかできると思います。(もちろん形だけで演奏は別です…笑)どっちかというとPart2のデュオの方が、掛け合いの妙味や、2人のグルーヴの重なりとかが聴けて、私には面白かったです。上原ひろみさんは、オスカー・ピーターソンの来日公演の時前座の演奏を聴きましたが、あの時はPAがひどくて可哀想でした。今回はプレイ中のうなり声がちょっと気になる他は(笑)良かったです。Part3は今回初演の、カミロ氏作曲の組曲。ジャズ・ラテン系のノリに共演のストリングスアンサンブルの方々がどれほど乗るのか、ちょっとハラハラする場面もありましたが、こういう作り込んだ演奏には、アドリブとはまた別の魅力がありますね。7時開演で終演は10時。休憩も入れて約3時間、カミロ氏の様々な魅力をたっぷりと楽しめるコンサートでした。Blue Noteの時は出入り側の席だったのでハイタッチまでしてもらったんですが、実は、私この方のCD持ってないんです…。■ミシェル・カミロ■画像は、左がグラミー賞「最優秀ラテン・ジャズ・アルバム賞」を受賞した"Live at the Blue Note"、右が"Why Not!"。カミロの作曲した"Why Not!"は彼のレコーディングより先にマンハッタン・トランスファーが歌ってグラミー賞に輝いています。上のリンクから楽譜まで検索できます。楽天ブログに、上田力さんのブログを発見上田力「クロス・トーク」ミシェル・カミロも取り上げられてます→久々にミシェル・カミロへお説教!!どうもできたてのホヤホヤらしいです。
Sep 21, 2005
コメント(9)
-
出待ち
この日は滅多に出来ない経験をしました。友人が誕生日ということもあり、彼女が夢中になっている俳優さんが出演しているミュージカル観劇に行ったのです。ミュージカルが苦手な私も音楽が主体に進行していくので楽しむ事が出来ました。流れ上終演後には出待ちにも付き合いました。かなり人気のある役者なので待つファンは多く、世代的には冬ソナファン位。つまりそれなりに大人なんですが、いざ本人が出てきた途端阿鼻叫喚の有り様。その変わりように私は思わず後ずさりしました(-o-;あの場で冷めてるのは辛いもんです。貴重な体験でした。※メール更新後 修正しました。
Sep 20, 2005
コメント(4)
-

レポート提出
夏期レポートをすっかり溜めてしまっていました。あわてて取り組んで、3教科分、なんとか締切りに間に合いましたが、またやってしまったなと(^_^;)記憶を辿れば、小学校の頃からギリギリ派。いい大人になった今でもあまり改善していない自分に呆れます。あまり時間がありすぎると、あれもできる、これもできるといたずらに時間ばかりかかって焦点を絞ることができず、満足の行くものができたためしがない、なんて思ってしまうんですけど、結局はやらなければならないことを後回しにするための単なる言い訳に過ぎませんね…。また、結局はこうやって間に合わせてしまうことで、ますますこの傾向に拍車をかけてるんだとも思います。というわけで、今反省モードです(-_-;)そういえば、映画「Back to the Future」シリーズの中で主人公のマーティも、何度も同じ失敗をしていました。「chiken!!」(憶病者)と言われるとカーッとなって、見境のない行動をとってしまい、その結果会社を解雇されたり等々の窮地に陥るというものです。確か、3作目では、やっとそれに気付き克服していたと思いますが、映画を観ながら、なんでまたそれくらい我慢できないのか…とハラハラしました。マイケル・J・フォックス/バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3他人からみれば、どうしてそんなことができないのか?というようなくだらないことだったりするんですけれどね。本人にとってはなかなか抜けだせない習癖というのがあるものです。あれ、これも自己弁護モードになるかな?(^_^;)皆様には、なかなか克服できない課題というのはありますか?
Sep 19, 2005
コメント(2)
-

蓋物の和食器
洋食器も勿論好きで、実際良く使っているのですが、この数年、どうもハマっているのが和食器。磁器と陶器、どちらにも良さがありますが、陶器は、使っている土や釉薬によって様々に質感が違うので、各々に独特な味があって、ついいろいろ集めたくなってしまいます。おかげで我が家の少ない食器収納スペースは、まずいことになりつつあります…。さて、その中から今回はちょっとよそゆきな感じの蓋物に鰻丼を盛ってみました。つい沢山食べてしまいがちな丼物も、このくらいの小さな器にこぢんまり入れるとなんとなく雰囲気で満足できてしまいます。本当は木の芽なんかあると格好いいんでしょうが、これだけでもグレードアップしたような気分。丼には小さいけれど、茶わん蒸しには大きくて品のないことになりそうな微妙な大きさの器は、やはり何か惣菜を盛り付けるのがスタンダードな使い方なんでしょうが、鰻丼と同様、牛丼でも親子丼でも、小盛りの丼として使うと意外とハマるというのが、発見でした。
Sep 18, 2005
コメント(4)
-
らくらくホン
親がようやく携帯を持ちました。母は以前から携帯電話を欲しがっていたのですが、「そんなもの、なくてもいい」と父に切り捨てられて、購入は延び延びになっていました。ところが、先日父の方から私に携帯電話を買ってきてくれないかという珍しい展開に。というのも、祖母の看護のために毎日病院に通っている母を見て、これは持たせてやった方が日々の連絡も楽になるに違いないとようやく思ったらしいのです。う~ん、愛だなぁ(*^^*)思い立ったらせっかちな父の要請にすぐさま契約して参りました(笑)父は、やはり小林桂樹のCMで、ツーカーが気になっていたようですが、メールは最低読むだけでもできると「私が」ありがたいことなど諸事情からdocomoのらくらくホンにしました。いざ携帯を手にして母はどんな具合かと思えば、今迄マニュアル嫌いで、自分で買った高価な圧力鍋さえ使わなかった母が、※関連日記「イベリコ豚を圧力鍋で」今回は首っ引きで、みるみるメールをマスターしました。(どうも初日は遅くまで夢中になっていたらしい)メルアドの登録など少しだけ手伝いましたが、既に絵文字まで活用しています。時々、メールのキャラクターが実物のイメージと違う人っていませんか?母の場合、絵文字のせいかメールになると急に可愛くなるのが結構笑えます。しかし、ちょっといじってみると、「らくらくホン」は操作を簡略化するために、単純な機能だけを前面に、複雑な機能は奥の階層にまとめて入っていたりしてかえって分かりにくかったりします。初めて使うのがこの機種ならば、問題ないんでしょうね、きっと。母は、このことで「マニュアルを読む」ことに目覚めたらしく、その後家のFAX電話にも新たな機能を発見し、感激して報告してきました。「電話番号を登録しておくと、携帯みたいに選ぶだけで電話がかけられちゃうのよ」「…いや、今はみんなそういう機能があるんだよ(^_^;)」「そうなの?(驚き)」しばらく楽しい展開が見られそうです。
Sep 17, 2005
コメント(2)
-
女性専用車両雑感
出来てからずいぶん経ちましたが、女性専用車両というものに今日初めて乗りました。普段は乗り換えの都合や、空いているか否かだけで乗る車両を決めていますので、別に避けていたわけではなく、当たらなかっただけです(笑)乗ってみると女性ばかりというのは何とも不思議な感覚ですね。普通は男女比でいったら大体男性の方が多いわけですから…。この車両の存在の是非は別として素直な感想としては2つ。1.男臭くない(当たり前ですが)まだまだ暑いこの季節、体臭はやはり気になります。特に男性に多いように思いますので、随分と軽減されますね。逆に女性は、香水・化粧の香りがキツい人が多い場合には、それが重なって「匂い」ではなく「臭い」に発展する可能性も考えられますが…(^_^;)2.座席が満席でもきつくない今回特に感動しました。男性は身幅が大きい人が多いので、横型の座席1列に設定された人数が全部座ってしまうと、それだけでキツキツになりますよね。それに加えて、足癖が悪い人が多いのも男性で(きちんとしている人ももちろんいますけど)身幅以上に開脚して座る人ってよく見かけます。あれが更に場所を取るんですね。そんなに短い足を無理して広げんでも…(^_^;)と思う人もしばしば。女性でも恰幅のいい人が沢山揃った場合はその限りではないと思いますが、まあ、そんなことが起こる確立は低いと思いますので(笑)女性ばかりだと、座席がゆったりしていていいなぁと単純に思ったというわけです。…と言ってもいつもわざわざその車両を狙って乗るなんていうマメなことはできないと思いますが…。賛否両論ある女性専用車両、そんな素朴な理由で、まんざら悪くもないなと思いました。
Sep 16, 2005
コメント(6)
-

豆乳ゼリー
この頃日記のテーマがすっかり、インテリアから逸れてますが、毒を食らえば皿まで、ということで懲りずに参ります(笑)今回は「超」がつく簡単レシピです。まさに「猿でもできる」、というのに近い領域で恐縮ですが、気に入ってよく作っているものをご紹介します。名前はなんとしたらいいのか思いつかなかったんで、ストレートに『豆乳ゼリー』としてみました。と言っても、私の場合は副菜的な位置付けになっています。では、作り方を。【材料】豆乳 500cc ゼラチン5g 水めんつゆ 好みでワサビ 万能ネギ 柚子こしょうなど【作り方】ゼラチンはその製品の規定の方法でふやかし溶かしてから豆乳と合わせて良く混ぜ合わせ、容器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。…これだけです(笑)ゼラチン5gで固まる量は300mlまでと箱に書かれていたりしますが、掟破りに液の量を増やしますと、ゆるゆるのゼリーになります。(と言ってもこれ以上増やした時のできあがりは保証しません)スプーンなどですくって器に盛って、私はめんつゆをかけ、薬味を添えて、卵豆腐風に食べていますが、考えてみれば、それ自体には素材の味以外ついていないので、心太(ところてん)と同様に黒蜜をかけたりするとデザートとしてもいけそうですね。器や盛り付けに工夫すればオシャレなメニューにすることも可能です。実は、このレシピは父から教わりました(笑)どうもゴルフ仲間から聞いてきたらしいですが、重宝してます。「猿でもできる」レシピ、またそのうちアップいたします。
Sep 15, 2005
コメント(6)
-
再利用ジンジャーケーキ
あれ?もしかして私の日記に甘い物が登場するのは初めてかもしれません(笑)以前の日記で、自家製ジンジャーエール作りをアップしました。その後に残った、甘くてスパイシーな生姜のシロップ漬けの処遇に頭を悩ませていたのですが、よく遊びに行くゆ~かりptusさんのところの日記『炊飯器でジンジャーケーキ』を見て閃きました。ゆ~かりさんはジンジャーパウダーを入れてらっしゃったんですが、同じ様に生姜スライスもケーキの中に入れてしまえばいいなと。ということで、私も炊飯器ケーキに入れてみることにしました。このケーキのいいところは、ホットケーキミックスを利用するので余程のことをしなければ失敗がないということです(笑)炊飯器ケーキはもう何年も前から度々作っています。当初は中味までうまく火が通らず、試行錯誤を繰り返していたんですが、うちの炊飯器の場合、2回分まるまる炊飯すればいいことが分かったら、途端に上手くいくようになりました。基本はホットケーキミックスを普通にパンケーキを焼く割合で合わせて、後は好みの中味を足せばいいんです。というわけで、今回の中味です。1.生姜のシロップ漬けを細かくきざんだもの。2.干しナツメの紹興酒漬け(干しナツメを砂糖と紹興酒でひと煮立ちさせてから瓶に詰めて寝かしたもの)を粗くきざんだもの。3.2.の漬かっているシロップ少々。3.以外は結構たっぷりいれました。両方とも甘く味がついているので、あえてシロップ以外の甘味は足しませんでした。紹興酒ってどうよ?と思ったんですけど、もともとシナモンとクローブ風味がついたスパイシーな生姜と合わさってなかなかいい感じに。スパイスの効いたフルーツケーキのイメージで組み合わせて正解でした。欲を言えば、ナッツ類を何か足したらもっと良かったかなと。オリエンタルな感じを追究するなら、松の実なんかいいかもしれませんね。次回は試してみようと思います。さて。他には何に利用できるでしょうか。飽くなき探究は続く…。
Sep 14, 2005
コメント(10)
-
セルフいいことbaton♪
久々にバトンが回ってきました。最近復活しつつある、☆vanilla☆さんからです。日記の題材は日々悩みの種なので、こういうお題をいただくのも楽しいものです。ありがとうございます。では『いいことバトン』です。1.【その日あったいいこと】その日ってやっぱり今日のことでしょうか?いつもと同じような1日でしたが、この「いつもと同じような」事自体がいいことなんだと思います。今日を無事に元気に過ごせたこと、仕事もなんとかこなせたこと、誰かの喜ぶ顔が見られたこと、そして仕事の後のビールも旨い…。特にドラマチックなことがあったわけではありませんが、ビバ!何の変哲もない1日!!(笑)優等生的なつまらん答えで申し訳ないです。2.【数ヶ月以内にあったいいこと】いろいろありますが、一番はこれかな。子供だった頃から知っている知人が、成長し結婚したこと。アバウトな人生を送っているのを、ハラハラ見てきましたが、ちゃんと足を地に付けて、愛する人を見つけたことにあたかも母のように感動しております。3.【こんなことがあったらいいこと】6月に入院した祖母がまた歩けるまでに快復すること。あれから、また大変な状況になっているので…。あ、それに月並みですが、宝くじ当たったらいいなぁ。ここは次々に浮かんできちゃってキリがないですね。4.【次にバトンを回す人・5人】ええと、受け取ってくださる方、募集中です。日記のテーマに行き詰まった時なんかに如何ですか?(笑)セルフサービスでいきたいと思います。普段は目先の懸案事項にばかり目が向いていたりするので、「いいこと」って意外とあらためて意識することって少ないのかも。こういう視点、なかなか新鮮でした。「いいことバトン」、なかなかよい企画ですね(^_^)
Sep 13, 2005
コメント(6)
-
ソーミンチャンプル
まだ残暑厳しい日が続きますね。あまり食欲が湧かなかったので、久々に沖縄料理、ソーミンチャンプルを作りました。「ソーメン」でなく「ソーミン」なのです。簡単すぎてレシピというのも何なくらいなんですけど…。【材料】 素麺 万能ネギ 塩 胡椒 油あればもやし・ニラなど野菜類。これまたあれば、ツナ。もちろん好みの肉類でも可。【作り方】素麺を硬めに茹でて水で洗った後、塩をまぶし味をつけておきます。フライパンに油をひき、野菜やツナを入れるならあらかじめ炒めてから素麺を投入。手早く炒めて胡椒で味を調えて盛り付け、万能ネギを散らしてできあがりです。手早く炒めたいので、塩を予め素麺にまぶしておくのがコツですね。のんびりしているとだんだん素麺から粘りがでてベタベタしてしまうんです。野菜やツナなどなくても、最低ネギがあれば味が成立します。あんまり具を入れすぎないでシンプルにした方が、かえって私は好きです。彩りから万能ネギが欲しいところですが、長ネギをみじん切りにしてもどうにかいけます。つまり、ネギ系の薬味の他は塩・胡椒の味のみで素麺を炒めるだけで(胡椒を入れないというレシピもあります)なんだか美味しくなる不思議なメニューです。ちょっと濃いめに味をつければ酒の肴に♪(酒はもちろん泡盛で♪♪)素麺を炒めるってこちらの発想にはないんですけど、油で炒めてもあっさりしていて、食欲の無い時にもぴったりです。
Sep 12, 2005
コメント(4)
-
投票はしたけれど
仕事から帰ってから急いで行ってきました。今回は悩みに悩みました。どこの政党の政策ややり方を見ても首をかしげる所があり、心からこの政党に、この候補者に、と託せるような気分にはとてもなれませんでした。それでも、なんとか投票し終わって、長い間詰まっていたものがやっと出た(失礼)という感がある一方、まだ出きってないような(さらに失礼します)という気分も否めない。開票速報が進んでますが、自民圧勝の気配ですね。今回の選挙は争点についていろいろ言われてきましたが、何と言っても、政治に対する国民の関心が高まったというところに意義があったように思います。これで結局、自民が続投することになっても、こういう気運だけは失われないで欲しいと思います。
Sep 11, 2005
コメント(4)
-

ワカモレでテキーラ
前日は沖縄料理でしたが、ここのところ実はずっとメキシコ料理が食べたかったのでした(笑)ということで、念願の♪メキシコ料理店へ。写真はワカモレとシーザーサラダ。(携帯のカメラがまだ使いこなせてないのがバレバレの画像です…汗)シーザーサラダってメキシコで生まれたメニューだったんですね。初めて知ったので、敬意を表して頼んでみました。ワカモレに使われているアボカドは完熟した柔らかい果肉を潰した中に、若いまだ固めの果肉が刻んで入れてあります。他にタコスも注文しました。チリコンカン、ワカモレ、サルサ、ハラペニョ、サワークリーム他、いろんな具を好みで組み合わせて包んで食べます。本当はもっといろいろ食べたかったんですけど、これでお腹いっぱいでした。飲み物は最初はメキシコのビール、初めての銘柄にしてみましたが、いい加減な私は名前を忘れました…。写真に写っているビールは友人が飲んでた方です。ちょっと味見させてもらったら、深い味で美味しかったです。私が飲んでいたのは、コロナに近いさっぱりした感じでした。その後テキーラに切り替え、幾つかの銘柄を頼みました。テキーラにも熟成したものと、若いものがあって、全然味が違います。最初はショットグラスでストレートで。本当は、これを一気に空けるのが向こう風なんだそうですが、さすがにやりませんでした。翌日が仕事でなければやるんですけどね(笑)初めてのお店でしたが、この日は当り♪メキシコ料理、満喫できました。前日のやるせなさも、テキーラのお陰で吹き飛びました。そうそう、うちにもテキーラがありましたっけ。知人から、美味しいからといただいたものです。時々飲んでますが、やっぱりメキシコのメニューで飲むべきですね。■Cuervo クエルボたち■左から、クラシコ、ゴールド、レポサド、アネホ、リゼルヴァ。我が家のクエルボはレポサドです。リゼルヴァはとてもよいお値段です(^_^;)熟成期間、方法、原材料の割合などによりランクがあります。テキーラも奥が深いんですね。上のリンクでクエルボファミリーが検索できます。
Sep 9, 2005
コメント(14)
-
残念な生オリオン
この日は、久々に会った仕事仲間と飲みに沖縄料理屋へ。生のオリオンビールを初めて飲みました…こないだずぼらでgo!さんにコメントいただいたところだったので、期待したのですが、冷え方が足りない上、注ぎ方も今ひとつ。料理も種類はありましたし、不味くはないんですが、納得のいく質のものは少なく、これまた期待外れ(^_^;)値段が安いわけでもないのに…です。メジャーになって増えた沖縄料理屋ですが、好きな物で期待が大きいだけに、余計に残念な気分で帰ってきました。(携帯更新)*************************後程補足。それでも泡盛はしっかりいろんな種類を飲んできました(笑)
Sep 8, 2005
コメント(4)
-

ミニロボット
CUBE CAM-08二足歩行のできるミニロボットです。別に何か役に立つというものではないんですが、あったら楽しいなぁと、密かに狙っています。上の画像はCAM-08で身長20cm。複雑な機構で、首・腕を振りながら完全ニ足歩行するそうです。リモコンで前進・後退・停止などがコントロールできます。さらに半完成状態で届くので、仕上げの組み立てを自分でするという楽しみが残されているというわけですね。特別な工具なども要らずに十数分くらいで組み立てできるそうです。そして下の画像が、弟分のCAM-10。こちらは身長10cmと小柄で、リモコンこそついていませんが、二足歩行をちゃんとします。動きも前進だけですが、兄のCAM-08の1/10の価格が嬉しい。このくらいなら試しに買ってみたいなという気にもなるものです。ロボットというと何か魅かれてしまうのは何故でしょうね。遥か昔、ジャイアントロボっていう番組がありましたっけ。「行けっ、ジャイアントロボ!!」とか主人公の少年が腕時計みたいな送信機かなんかに叫んで、巨大ロボットを操縦するやつです。(近年どうやらアニメ化された模様)鉄人28号から始まり、その後も巨大ロボットを操るアニメや漫画が続々と登場して人気を集めていますね。ガンダムシリーズなんてその最たるものでしょう。商品ページを見ると「少年心をくすぐる」という文句がありましたが、そうか、私の中の少年心が疼くんでしょうか?(笑)CAM-10こちらは白以外のカラーもあります。
Sep 6, 2005
コメント(2)
-

モロヘイヤのスープ
旬を過ぎてしまいましたが、モロヘイヤって皆様どのように食べてますか?おひたしもいいんですけど、たまには目先の違う物をと探していたら、当然ですがモロヘイヤの故郷、エジプトのレシピが沢山ヒットしました。どうもモロヘイヤというと、このスープが代表的なようなので、この夏作ってみました。作り方はごくシンプル。鶏ガラのスープの中にモロヘイヤの葉を細かく刻んだ物を煮て、別にニンニクとスパイスをバターで炒めて香りを出した物を合わせる…そして味付けは塩・こしょうだけです。スパイスはコリアンダー(粒)が結構入ります。粉末ではなくできれば粒のをすりつぶした方がいいようです。私も気長に乳鉢ですりつぶしました。一緒にニンニクもすりつぶせということでしたが、面倒なのでニンニクプレスで細かくしてから合わせました。これを多めのバターできつね色になるまで炒めるのですが、ここが味のポイントになるわけですね。コリアンダーというのはあの独特の匂いのする香菜の種です。好き嫌いが大きく分かれる葉とは全然違い、砕くと爽やかな香りがただよいます。更に炒めるとグンと香りが立ってくるのです。スープの中に香ばしいスパイスをジュッっと合わせて少し煮込み、味を整えるともうできあがりです。どんな味なんだろうとわくわくしながら一口、今迄に経験したことのない味ですが、美味しかったです。コリアンダーシードが効いています。スパイスひとつ加わるとこんなに変わるんですね。本場だと、かなりの量の油を加えるらしいんですけど、そこまでしない方が日本人には良さそうです。私はこちらのレシピを参考に作りました→ぐうたらの星さんのレシピ「エジプト人直伝の味!モロヘイヤスープ」モロヘイヤのスープのレシピはネットで結構ヒットしますが、コリアンダーの生葉を使っているのが殆どの中、シードだけを使うのは珍しいようです。■コリアンダーシード(ホール)■
Sep 5, 2005
コメント(2)
-

自家製ブルーベリー
母が庭で育てたブルーベリーです。そろそろ今期最後の収穫だと思うんですけど、お裾分けをもらいました。春先にはやはり庭で実ったレモンをたくさんもらってジャムを作りましたが、(※詳しくは自家製レモンでマーマレードの日記に)さすがにブルーベリーはそんなに量がないので、このまま生で食べました。ジューシーで甘くて美味しかったです。ブルーベリーに含まれるアントシアニン色素が目に良いのは有名ですが、抗酸化作用や、コラーゲン合成を促進するなど他にも体によい働きをしてくれるんだそうです。アントシアニンは体内に入ってから約1日は効果が持続するそうですのでできれば毎日1度は摂りたいところです。生ブルーベリーは買うと高価だし、季節が終わると手に入りにくくなりますから、冷凍かドライか缶詰め、ジャムなどが手軽そうですね(^_^;)■冷凍ブルーベリー■■ブルーベリー缶詰■■ドライブルーベリー■■ブルーベリージャム・ソース■
Sep 4, 2005
コメント(2)
-

冬瓜で
大好きな冬瓜を使ったレシピです。先日の「スイカの皮」日記で、山ぶきさんとのコメントのやり取りの中でこの冬瓜が出て来たので取り上げてみました(笑)そこで冬瓜は何に似てるかということになり、結局は皮がプリンスメロンぽいということになりましたが、それより実際はもっと緑が濃い感じですね。中味も色が違うだけで、これまたプリンスメロンぽいと思うのですが、この点にはご賛同いただけませんでした(^_^;)…閑話休題。夏が旬なのに、冬の瓜と書く「冬瓜」は丸のままなら、冬まで保存がきくということからの名前なんだそうですね。白い果肉の部分は、それ自体は淡白ですが煮込むとスープや出汁の旨味をいっぱいに吸い込んでそれは美味しいのです。一緒に煮込んでもいいんですが、今回は少し凝って肉味噌を別にかけるやり方にしてみました。簡単ですけど、一応作り方を。冬瓜は種を取り皮を剥いて一口大に切ります。それを好みの出汁の中で煮て、そのまま煮汁ごと冷まし、粗熱が取れたら、冷蔵庫で冷やします。肉味噌は豚・鳥など好みの挽肉で。中華鍋に油を熱し、豆板醤を炒めて香りを出したら生姜・にんにく・長ネギのみじん切りも加えて炒めます。挽肉を加えて火を通したら、戻した干し椎茸のみじん切りも投入。鳥がらスープを少し加えて、醤油、砂糖、あれば紹興酒やオイスターソース等で味を整え、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけてできあがりです。これを冬瓜にかけていただきます。冷たい冬瓜と温かい肉味噌の取り合わせも良いですし、冬瓜も温かくして、というのもありです。これですと中華風ですが、1.肉味噌の味付け2.冬瓜を煮込む出汁(スープ)の組み合わせを変えれば応用がいろいろ利きますね。まだ冬瓜で作りたい物があるのですが、もうそろそろ時期が終わる頃でしょうか。冬瓜楽天で買える冬瓜たちです。形は長いけど、プリンスメロンに似てません?(笑)
Sep 3, 2005
コメント(4)
-
真夜中の蝉
このところの日記は、「この夏を振り返って」というようなテーマが続いていますが、今回もです(笑)夏らしく暑い日が多かったせいか、毎日のように蝉の声がしました。冷夏ですとこうはいきませんよね。早朝、日の出前でも薄日が挿すともう鳴き始めていました。蝉の中ではツクツク法師の鳴き声が一番好きです。ちゃんとイントロとエンディングがあるところなんかシビれますね。しかも、イントロの後、本編になるとちゃんと2拍子になっています。もっと分析すると強拍にアクセントが置かれていたりして、非常に音楽的です(笑)以前はレアな感じだったのに、今年は何故か我が家の周囲はツクツク法師だらけでした。いくら好きでも、そればっかりになると少し有り難味が薄れますね(笑)次はミンミン蝉だったような気がします。しかも夕暮れ時には、ミンミン蝉の声は止み、見事にツクツク法師だらけになってました。夕暮れといえば「ヒグラシ」のイメージですが、そこまで山深くないところなのでさすがに聞こえません。夕暮れとツクツク法師、なんだか変な取り合わせな気がしますが、いいんでしょうかね(^_^;)最近、蝉の地域分布などが、気候の変化によって変わっているというらしいですが、これもそれと関係あるんでしょうか。…そういえば、以前異常に暑い夏の時も蝉がとても元気な年がありました。その時は、夜中に窓辺でミンミン蝉に鳴かれてちょっと困ったことがあります。電気がついた窓辺は明るいから勘違いでもしたんでしょうか。しかもかなりの大音量です。真夜中の蝉の声って静かな中にとても響くので大迷惑。ただ、ちょっと元気がなく鳴き声が断続的ではありました。翌朝、ベランダに出てみると蝉が一匹死んでいました。これが昨夜の蝉なのだとしたら、最後に一声鳴きたかったのかも…とちょっと切ない気持になりました。日本の夏には蝉の声って欠かせないですね。暑くなくてもあの声を聞くだけで夏の記憶が蘇ってくるくらい、夏と切っても切り離せません。今年はまだ頑張っているようですが、そろそろ蝉の声も聞き納めになりそうですね。
Sep 2, 2005
コメント(6)
-

カピ(シュリンプペースト)で
暑い日が続いたためか、スパイシーなアジアの料理が恋しくなりました。タイ米もあったので、カピを使って炒飯をつくることにしました。カピは塩漬けの小エビを発酵させたタイの調味料です。イタリアで言えばアンチョビみたいな存在でしょうか。買ってはあったものの、実際に使ってみるのは初めてでした。蓋を取るとロウみたいな物で更に表面が覆われているので、それを取り除くと…。話には聞いていましたが、クサいです(^_^;)開けただけでキッチンに匂いというよりは臭いが広がります。でもこういうの、まんざら嫌いではありません(笑)ではすごく適当ですけど作り方を。【材料】ご飯(できればタイ米)玉ねぎ 何か野菜(私はレタスとコーンでした)カピ 砂糖(本当はパームシュガーなんでしょうが)ナンプラー好みでレモン、卵【作り方】1.フライパンに油を熱し、カピを投入します。カピは硬いので、なかなか炒まらないし跳ねるので、ここで玉ねぎのみじん切り(大きめ)を投入し一緒に炒めた方が落ち着きます。この油で炒めることによって臭いが香ばしい香りに変化します。そして砂糖をここで少々。2.ご飯を投入。この他に私は冷凍コーンも彩りに入れて良く混ぜます。(できる方はあおってください)さらに私はレタスを細切りにしたものも入れ軽く合わせた後、ナンプラーを鍋肌から回し入れて混ぜて出来上がり。3.別に半熟の目玉焼きを作って上に載せる&レモンを絞るとなお旨いです。いい加減でも美味しくできるので味をしめ、その後何回も作っています。塩味と旨味はカピとナンプラーで充分です。ポイントはカピを油できちんと炒めることと、砂糖を使うところでしょうか。レモンで酸味を加えるとさらに味が引き立ちます。本当はライムがいいのかもしれませんが、テキトーなメニューなのでお好きな物を。これひとつですごくアジアな感じになるカピは癖になりそうです。ちょっとコツがつかめたので、これからいろいろと応用して使っていきたいと思います。カピたち日本で見かけるのは中央のタイプが多いと思います。私が使っているのもこれです。
Sep 1, 2005
コメント(4)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- 収納・家具・インテリア情報
- 部屋にぴったり!四角のサイドテーブ…
- (2025-11-17 21:22:40)
-
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- 今年仲間入りしたクリスマス雑貨☆
- (2025-11-18 10:58:41)
-
-
-
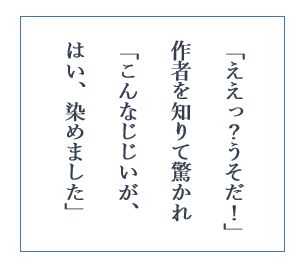
- 日記を短歌で綴ろう
- 〇☆〇作品展 短歌5首
- (2025-11-17 07:50:40)
-







