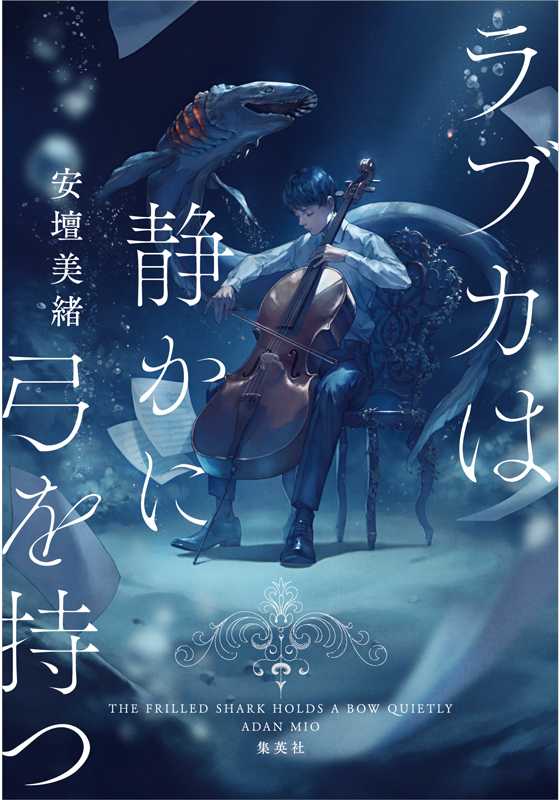2015年04月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

【菅谷城】 都幾川までの道
「都幾川(ときがわ)」『菅谷城の南』のほうに、大きな川が流れてる。『都幾川』っつってな。 延長 3,420キロメートルもある、一級河川なんだと。『菅谷城』は、この『都幾川の左岸』に出来た、『河岸段丘』っつう、丘のようになった小高い場所に 築かれた城だったんだな。 でな。『菅谷城の南廓』んとこから、『都幾川』へ通じる道が、あんだよ。 やっぱし。城と川って、重要なつながりさあんべ? 距離さ近ければ、掘の替わりにもなるし。 水量が豊富な川なら、船着き場さこしやることも、出来る。 そして、生活用水に使ったり、おトイレ代わりにもなるw。 お米さこしゃるにも、水は重要だし、な。 と、いうことで。 近くに川があんならば、見に行きたくなっちゃうんだよね。 だもんで、『都幾川』へ通じる道に行ってみた。 入口は、曲がりこんだようになっててな。 廓の上からじゃ、わかんなかったんだけど。 降りてみたら、こんなんなってた。 うお~、急だ~。も、もどろうかな・・・。 いっきにテンション下がっちまった。 だって、おっかなかったんだもの。 左右は、木が生い茂って、景色さめ~ないし。 川の姿も気配も感じない。 おまけに、この階段。 一段ごの幅が、高い。 つ~か、これ、ほんとに階段け? 一段ごとに、飛び降りるかんじ。 普通の階段だと、3段分ぐらい、あったど! 足さくじいたら、どうすべ~。 いや、冗談じゃなくってな。 本気で、危なかったんだど。 少し降りたところで、水がめ~た。 ん~。川にしちゃ、細いな。 きっと『都幾川』に通じてる、小川だな。 どっからきてんだろ? きょろきょろ。 周りさ見ても、ちょっとわかんないな。 っつうか、辺りは藪がいっぱい。 この先、ちゃんと『都幾川』に通じてんのか、心配になってきたな~。 で、結果さいうと。 ここで引き返してきました。 ん~。理由はやっぱし、この先の道がどうなってんのか わかんなかったから、かな。 あとは、帰り道の心配。 さっき、飛び降りるように降りた階段。 飛び降りた、ということは、 帰りは、よじ登らなくちゃなんないわけで。 それさ、考慮すっと 体力、もちそうになかったんだ。 後で聞いた話だと。 この先、『都幾川』んとこにゃ、『船着き場』があった、 って噂もあんだって。 ほほう。 その話がほんとだったら、『菅谷城』は『船着き場』がそなわった城、ってことになんだな。 この急激な坂道も、『船着き場と菅谷城さ繋ぐ道』だった可能性も、でてくんど。 な、なるほどな。 そういうことなら、道が急激なカーブさしてることにも、 意味さでてくんな。 もし、こっから敵さ侵入しようとしたら、急なほうが疲れるし。 曲がってるほうが、入り込みにくいど。 お、もしかしたら、廓んとこの降り口がわかりにくかったのも、 敵が入りにくいように、わざと曲げた仕掛けだったのかもしんないな。 ・・・なんてふうに考えたら、急激な坂道も、 太もも上げの運動の、連続になった階段も、 ちっとは楽になんべかな? 次くるときは体力付けて、『船着き場』まで往復すんど~!************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.29
コメント(0)
-

【菅谷城】南のだんだん廓
「南廓」 さあ、どんどん奥さ進んでみよう。『本丸跡』を背中に、西の方向へいくど。 この辺りは木が茂っていて林の状態。 道があっから歩きやすいけど、 横は崖だかんな。 おふざけは厳禁だど。 振り返ると おお~崖だ。いや『切岸』かな? あの上が『本丸跡』だど。 離れてみっと、高さがよくわかるな。 3メートルは軽~く、あんじゃないかな。 ほぼ垂直の土壁。 登ってみようという気さえ、起きないや。 敵さんも、この壁さみたら、戦意喪失しちゃうべな。 崖に見とれながら、さらに進んで行く。 崖の壁をぐるっとまわりこむと、 お。開けた場所にでたど。 おお~! なんか、すごいもんが、ある~! だんだんだ~。 すご~い。こういうの、大好き~。 背中が、うずうずしてくるよ~。 もっと近くでみてみよう! うんうん。 間違いなく、段差になってる。 これは、自然に出来た地形じゃないよね。 人が手えを加えたもの、だべな。 んじゃ、これも城の遺構なんだべか? ええと。落ちついて観察してみんべ。 まずは位置。 ここは『本丸』の西のほう。 で、だんだんの上んとこ。 なんか見覚えさあるな、と思ったら、『二の廓の端っこ』だ。『忠魂碑』あったとこから南の方向さいくと 崖になってたんだけど、そこにあたるみたいだべ。 へ~。上から覗いたときにゃ、広場みたいなとこはめ~たけど。『だんだん部分』は、気がつかなかったな。 ま、怖くて真下が見れなかった、ってせいもあっけどなw。 文章じゃ説明しにくいな。 んじゃ、らくがき地図で、見てみんべ。 だいたい、この辺。『南廓』ってとこだな。『菅谷城』ん中じゃ、南の一番端っこにあたるとこ。 なるほど。目の前に広がるスペースは、『廓』っていってよさそうな広さだな。『本丸』よりは小さいかな。 だども、1件ぐらいの建物はこしゃれそうだな。 だけんど『だんだん部分』は、せまそうだど。 まだ遠くてわかんないけんど。 建物はこしゃれないだろうな~。 人はどうだろ? 立てるスペースぐらいあっかな? あそこにずら~っと武士が並んだら・・・ ひな壇みたいw。 いや、冗談は、おいといて。 攻撃すんにゃいい高さだけんど、敵側からも攻撃し放題、 に、なりそうだど。 ん~。他にどんな使い道があっかな? あ、案内板があった。なんか、解説が書いてあるど。『だんだんの謎の答え』も書いてあっかな? ええっと。『なんのために造られたのか、謎です』だって。 研究者の間でも、まだわかってないのか~。 残念。 だども、わかんないんなら、好きに想像しても、いいんだよね? さあて、もし城主だったら、このだんだん。 どういう風につかうかな。 ふふふ。よい頭の運動に、なりそうだど。 《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.25
コメント(0)
-

【菅谷城】 土塁と堀を乗り越えて
「南の掘り」『本丸の南』にゃ抜け道があったw。 土塁と土塁の間に、下さ向かい道があったんだよ。 一旦下で止まって、さらに下ってるみたいだど。 ん~。この形。おもしろいね~。 むこっかわに小さい土盛なんかもあって、 まるで『堀底』みたいだど。 注意しながら、底まで降りる。 あ、やっぱし『堀底』だ。 これは西の方向。 ここさず~っと進んでいけば、『二ノ郭の忠魂碑』があった辺りに、でんじゃないかな。 みごとに、まっつぐだな~。 だども、ちょっと浅い。 土塁さ混ぜても2メートルあるかなぁ・・・。 簡単に渡れそうだけんど、いいんかな? 反対側。東のほうは・・・お、いいね。『本丸の土塁』があるおかげで、堅固にめ~るど。 こっちもまっつぐだけんど、どこさ続いてんだべな? あの先は『生門跡』があって、崖になってたはず。 崖に落ち込んでんだべか。 ふうむ。見てみたい・・・けんど、危なさそうだな。 時間もないし、今回はやめとこ。 実はこのあと、博物館さいく予定でな。 閉館時間が近かったから、いそがなくっちゃなんなかったんだ。 しかし、この『堀』も、謎だな~。『本丸の北』にゃ、『馬出』だの『横矢掛かり』だの、 大層な仕掛けで守られてるってのに。 こったら浅くて、まっつぐで、 敵が攻めてきたら、ど~すんだべな? ん~、こっちから敵は来ない、ってことなんかな? だから、『掘』も簡単なものなんだべか。 道は、まだまだ続いてる。先さいったら、謎が解けっかな? じゃ、どんどんいくべ。 お、こりゃすごい。『堀』さ越えたら、違う城みたいだど。 いきなり、自然いっぱい、って雰囲気になってきた。 そして、『堀』から下の広場まで、 結構な角度と傾斜で下ってっと。 そして、木々の隙間から、下さ覗いて、またびっくり! 山だ~。そして、足元は・・・崖だ。たぶん。 や。木が邪魔で、はっきししないけど。 崖、だど思う。 もしかして、『生門跡』の下とおんなしぐらい高いんかな。ここ。 ほほ~う。な、なるほど、な。 この先がどんなふうになってんのか、わかんないけんど。 この『崖』を登って、城に入りこむのは、むりそうだ。 今歩いてる道も、散歩用にこしゃった道みたいだし。 上さ登るルートは、他になさそうだど。 ということは。 こちから直接『本丸』に入れないってこと、だな。 だから、『本丸の南側の掘と土塁』は、規模が小さいのか。 へ~。でもな。そんだったら。 わざわざ『掘』さこしゃること、なかったんじゃね?『土塁』だけで、十分防御の役にたったんじゃないかな。 それとも、『南の堀』をこしゃったのは、 防衛以外になんか、別の理由があったんだべか? 気になる『堀』だな~。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)【楽天ブックスならいつでも送料無料】今日から歩ける!超入門 山城へGO! [ 萩原さちこ ]価格:1,404円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.21
コメント(0)
-

【菅谷城】 生門跡のその先は?
「生門跡」『菅谷城の本丸』。 南のほうさ歩いてみた。 おや? 南っかわは、『堀』になってんだ。 なんだか車道みたい。 ほんとに『堀』なんかなぁ。 確かめるために、『堀』にそって、進んでみたど。 あ、『土塁』もあるど。 んじゃ、ここも城の遺構なんだな。 いままで見て来た『堀や土塁』と、規模が全然違うけど。 なんでだべ? ええと確か。城を築く場合。 敵が攻めてくる方向の守りが、頑丈になんだよね? すると『菅谷城』の場合。 城の北の方向から、敵が攻めてくんのかな? 南のほうから、来ないから、こったら『低い土塁』なんだべか? ん~なんだろね。 多少は崩れちまったとこも、あるようだけんど、『本丸の北の土塁』とくらべっと、高さは半分ぐらいしかないよ。 さらに進んでいくと、 あ、ここ。『本丸虎口』んとこからめ~た、『土塁のとぎれたとこ』だ。 あれ、ここって近くでみっと、不思議な形さしてんな。 道が『土塁の横』さ回り込んで、奥に続いてるべ。『土塁』が崩れて隙間が出来た、って雰囲気じゃないな。 あきらかに、わざわざ隙間さ作ったようにめ~るど。 まるで『虎口』みたい。 だども、まだ、断言はできないど。 城によっちゃ~、あとの時代になってから、 通行するために、『土塁に穴』さ開けっちまうことが、あっかんな。 ここの場合、どうかな? 勢い込んで『土塁』さ周りこんだ・・・ら、おおっと!『土塁の先』は崖だった。 後で調べてわかったんだけんど。 どうやらここは『生門跡』、っていわれてる場所なんだと。 これは『生門跡』の北側の、崖の写真だど。 藪と林で下さめ~ないな。でも、そうとう深そう。 10メートル以上、っつったら、大げさかな~。 だども、体感はそんぐらいに感じたよ。 ここはいったい、なんなんだ?『門』ってことは、どっかに通じる道があるはず。 だども、現場にゃそんな痕跡は、なかったど。 下のほうに目をこらすと、 写真じゃわかりづらいけど、川かな? 水が流れていたど。 横に空き地みたいな場所が、あるような・・・ないような・・・ ん~、昔はあそこさ通じる道が、あったんかな~。 さっぱりわかんないんで、『縄張図』さひっぱりだしてきた。 ええと。どうやら『生門跡』の東の崖先に、『細長い廓』のようなスペースが、あるみたいだな。 でも『廓』っつうより『見張り用の小さな空き地』みたい。 それに『小さな空き地の部分』だけ、城から突き出てるみたい。 ふうむ。もしかしたら、 昔は『崖を繋ぐ橋』が、あったんかもしんないね。 そして崖の向こう側にあったのは、『東を見張る場所』。 見張り台のような役目をしてたんだべな。 残念ながら、今は橋もないし、崖の向こう側がどうなってんのか、 ちょっとわかんないんだけど。 もし、今も残ってんなら、登ってみたいな~。 東の先からめ~る景色は、どんなんだべか? 昔と同じ景色が、め~るかな?《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)【楽天ブックスならいつでも送料無料】今日から歩ける!超入門 山城へGO! [ 萩原さちこ ]価格:1,404円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.17
コメント(2)
-

【菅谷城】 降参
「本丸の西側」 今回は『菅谷城の本丸の西側』さいってみるど。 遠くからみてもよくわかる。『でかくて角ばった見事な土塁』があんだ。 お、これなんだ? 足元に、土の山があるよ。 こりゃ、『モグラ穴』だな、きっと。 もぐらが穴さ掘ったときに、邪魔っけになった土を外にほっぽると、 こんな穴になんだって。 ・・・にしても、数が多いぞ。10個以上、あったんじゃないかな。 地面が穴だらけ、って感じだったよ。 もぐらたたきの板みたいw。 ふんづけちゃうのも、なんなんで。 脇さ避けてこ。 お、ありゃなんだ。 真ん中へんに、『石碑』さあるど。 これは『菅谷城の本丸跡を示す石碑』だな。 うん。『本丸』にゃ、これがなくちゃ。 ここだけちょこっと、林が残ってんだな。 まばらな木が、ちと寂しいよ。 寄り道ば~りしてないで、さっさと奥さいくべかな。 そして、やっとこ、『本丸西の端っこ』についた。 おお~、みごとに・・・切株だらけ~w。 どうやら整備中みたいだね。『土塁』だろうが、『廓』だろうが、木はどこにでも生える。 木にとっちゃ~、急斜面も角っこの折れ目も、通用しないんだね。 だども人間にゃ、一見ゆるやかそうにめ~る斜面が難関で。 登れやしないんだな~。 振り返ってみると『本丸虎口』と『土塁』がめ~た。『本丸の北側』は、こんな感じ。 3メートルに届くんじゃないか、 って高さの『土塁』が壁になってる。 防備は万全。だね。 でも、『土塁の上』にゃ、木が生えてる・・・。 人間は防げても、自然の植物やモグラは、防げないんだなぁ。 山城の場合。 他にもいろんな動植物がいて、城さ侵入しようとしてたんだろうね。 熊とか、鹿とか、猪とか。 蛇なんか、簡単に入ってこれそうだよ。 蔓植物なんか、はびこってきたら、駆除たいへんだろうね~。 遠い場所さ戦にいって、帰ってきたら、 蔓植物に城さ占領されてた、なんて。 ちょっと想像して、笑っちまったよw。 冗談はおいといて。 実際は、どうしてたんだろうな。 城を管理する、担当者がいたのかな。 動物駆除の専門家とか? で、とらえた猪は夕食に・・・って・・・ だみだ。考えがコメディーマンガみたいになってきた。 今日はこの辺で、やめとこ。************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.13
コメント(0)
-

【菅谷城】 城主不明にゃわけがある
「本丸」『菅谷城の本丸』は、 東西、約150メートル 南北、約60メートル あんだって。 東西に長い形さしてんだね。 で、今気になってる『横矢掛かり』は、『本丸の北側』にあんだ。『横矢掛かりの土塁の上』からみっと、下がどんなふうにめ~るんかな。 たのしみだね。 んじゃさっそく。中さ、はいってみんべ。『本丸の東側』。 ひろ~い。周囲は土塁で囲まれてんど。 だども一か所、くぼんだとこがあんね。 なんかありそうだど。後でいってみんべ。『本丸の西側』。 ありゃりゃ。切株だらけだど。 この辺は林になってたんだな~。 これから整備すんのかな? 外っかわからみたときにゃ、もっと小さくめ~たけど。『二ノ郭』からじゃ、半分しかめ~なかったんだな。『本丸の虎口』は北っかわにあんだけど。 ちょうど『本丸の真ん中』あたりにくっついてるみたいだね。 いんや、ちょっと東側のほうが広いべか? 大きな屋敷も作れそうな、広さがあんな。 ここにゃ、強力な大名が暮らした屋敷があったんだべか。 こないだちょこっと紹介した『畠山重忠』さん。 この人は『菅谷城』を築いたっていわれてるけど。 この場所に住んでいたかどうか、証拠はないらしい。 それどころか、どんな大名が『菅谷城』にいたのか、ってことも、 わかってないらしいんだ。 戦国時代の城の場合。 戦争用に築かれた城なんかじゃな。 何人かの武将が、代わる代わる後退で 城に詰るってことが、あったらしいど。『城将』っていってな。『城主』の命令で、他から派遣されて、城を守ってる武将なんだと。『城主』と違って、自分の城っつうよりも、 主人から預かった城って感じでな。 勝手に他にうつったりできないし。 仕事さぼってたら、職務怠慢で切腹! なんてことに、なっちゃうんだと。 うわっ。大変だな。 で、こういう『城将』がいた城ってのは、 領地の境目とか、『主人の城主がいる城』から遠い 重要拠点になりそうな場所なんかにあってな。 環境が過酷な場合が多いんだと。 だもんで、場所によっちゃ~しょっちゅう『城将』が変わる。 合戦があるとこなんかだと、 何人もの『城将』が、同時にいたこともあるらしいど。 だもんだから、いったい誰が城を治めていたのか、なんて わかんなくなっちゃう場合が、多いんだと。 『菅谷城』の場合は、どうだったんだべな。『多くの城将』が滞在した、前線基地だったんだべか。 それとも、資料が紛失しちまっただけで、『大きな権力を持った大名』が暮らしてた城、だったんだべか。『本丸』にゃ、大名屋敷さこしゃるぐらいの広さはある。 大名の住居用、って可能性は、あるよね。 しかし、前線基地を思わせる、『馬出』や『横矢掛かり』の仕掛けもある。 あ、そうだった。『横矢掛かり』。 これを確認しないとな。『土塁の上』からじゃ、下の様子がどんなふうにめ~るのか 確かめにきたんだっけ。・・・あれ?『土塁の上』にゃ、登れないんだ? え~。つまんない。 でも。落ち着いてみっと、『土塁の斜面』は急だし。 外側の高さは堀底から、7~9メートル近くあるらしい。 残念だけんど、落っこちて怪我するよりは 登れないほうがいいんかもな。 登れるような、階段もないし、な。 ふ~ん。じゃ、ここさ守る武士は どうやって登ったんだべな?『横矢掛かり』から矢を射るにゃ、 上に登んなくっちゃ、射れないべ? それとも櫓のような建物があって、 土塁の上から突き出て、矢が射れるようになってたんかなぁ。『菅谷城』。まだまだ謎が、いっぱいだ。 研究者のかた。頑張って謎さといとこれね~。 たのしみにしてるど。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)【送料無料】 「城取り」の軍事学 築城者の視点から考える戦国の城 / 西股総生 【単行本】価格:1,620円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.08
コメント(2)
-

【菅谷城】 土橋の上から
「横矢掛かりの仕掛け」 さあ。さっそく『菅谷城の本丸』さ、侵入すんど。『左右を守る土塁』。いいね。 そして足元の『土橋』。これも、いいね~。『土橋』って好きなんだ。 ここの『土橋』は、幅もあるしがっちりしてて歩きやすいな。 堀底に向かって、伸びていく傾斜がね。 好きなんだな~。『土橋からみた、横矢掛かり』だど。 お。ほんとに、真正面だ。『横矢がかり』のたいらな面が、『土橋』のほうに向いてるど。 む・む・む。 これじゃ~、弓矢で狙い撃ち、確実だな。 それに、今気がついたんだどもな。『横矢掛かり』の上から狙える場所って、『土橋の上』だけじゃ、ないみたいだね。 堀の向こう。『二ノ廓』のほうまで、見張れるようだど。 あ、あそこもめ~る。 縄張図で確認してみたら、『馬出の門』も、『横矢掛かり』の真ん前だよ! こんな感じ。 一度に3方向狙えるよ! おお!すごい! とくに『馬出』と、連携してっとこっ。 敵さんにしちゃ、やっとの思いで『馬出の門』を突破してきたのに。 また弓矢で、撃たれちゃうんだから、 たまったもんじゃないだろうけど。 守るほうからしたら、にんまり。 だね。 ん~。やっぱし。 一か所からみただけじゃ、わかんないもんだな。 あっちこっちの角度からみて、やっとわかることもある。 や~。おもしろいな~。 おっと。『横矢掛かり』にみとれて、反対側さ、忘れてた。 『土橋の反対側』も、『深い堀』が続いてるど。 こっちのほうが深くめ~るな~。 両側が高くなってるせいかな? どこまで続いてるか、気になるとこだけど。 まずは『本丸の中』と『横矢掛かりの裏っ側』が、先だな。 今度こそ。『本丸』さ侵入だど~。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)【楽天ブックスならいつでも送料無料】今日から歩ける!超入門 山城へGO! [ 萩原さちこ ]価格:1,404円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************
2015.04.04
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1