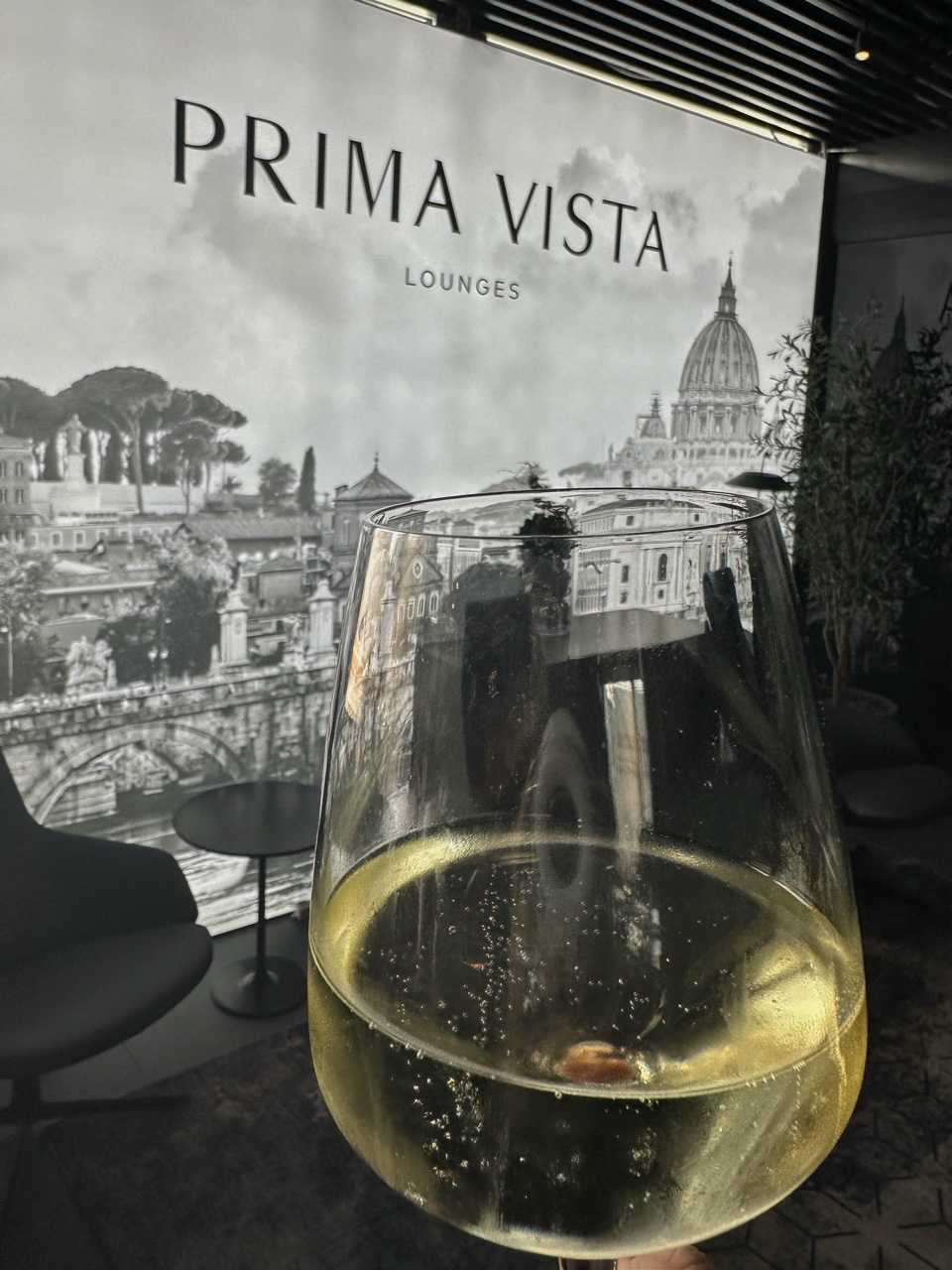2008年01月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

食べ終わってからが、本当の食事なのだの巻
中国の人たちはおしなべて歓待好きだ。 学生たちの家族は言うまでもなく、学校外で知り合った人も例外なく、そうだった。 歓待の印として、まずご馳走を振舞ってくれる。 酒を飲むように勧めてくれる。 どこかに行く時に交通費を全部出してくれる。 おみやげをたくさん持たせてくれる。 特に食事については、ふんだんな量が出てくる。 (もっとも、これは中国人が食欲旺盛だということもあるのだろうが) ホーム・ステイをするたびに、学生のおかあさんが三度三度、食事の準備をしてくれた。 ある日の昼ごはんが終わった後、学生のお母さんがこう言った。「夜は何を作ろうか」 普段は知らないが、私がいた時は、どの家でも5皿か6皿、或いはそれ以上の料理が出た。 それらのおかずプラス饅頭(マントー:小麦粉の蒸かしたもの)かお粥である。 或いはお粥を食べた後で、饅頭が出てくる。 饅頭とは中身のない肉まんのようなものだが、もっと重量感があってずっしりしている。 大きさは大人の握りこぶしよりちょっと大きいくらい。 5皿のおかずを食べれば、それだけでお腹いっぱいになる。 更に饅頭とお粥(丼になみなみと)である。 食事が終われば、動けないくらい、体が重くなる。 滞在3日目の昼ごはんにこういう料理が出た。 「大盤鶏」という料理。 鍋というか入れ物の大きさは直径が45センチくらいの大きなもの。 この中に鶏が一羽まるごとぶつ切りになって入っている。 そしてじゃがいも。 それらを、いろいろな香辛料で煮たもので、この地方では大層なご馳走だという。 鶏は学生のおじいさんが放し飼いにしながら、自分で育てたもの。 だから身がしっかりしていて、皮もぷるんぷるんしていた。 じゃがいもも味がしっかり染込んで、ほくほくした歯応えがあった。 おいしかった。 とてもおいしかった。 だから、たくさん食べた。 勿論、饅頭と一緒にである。 中に鶏の首から先(つまり頭)が入っていたが、それはさすがに遠慮した。 だが、爪というのか足先というのか、それは食べた。 多くの中国人は、この部分がおいしいのだという。 ……で、食べ終わって、すっかりお腹いっぱいになっていた。 十分に堪能した。 すると、そこに学生のお母さんが乾麺を持ってきた。 「大盤鶏」の残ったスープ(というかスープとラー油)で麺を煮て食べるのだそうだ。 というわけで、ラーメン丼にいっぱいになるぐらいの麺を食べた。 これもおいしかった。 ……もうこれ以上は入らない、というまでになっていた。 と思っていたら、またまたお母さんが乾麺を持ってやってきた。 「遠慮しないで、食べて」「さあ、どうぞ」「おいしいですよ」 家族たちが揃って、私を見ながら言う。 ……で、食べた。 というか胃にぎゅうぎゅう詰めに押し込んだ。 こんな食事もあった。 これは学生が通った高校を見学に行った時の食事。 買い物に行くという両親と学生、運転手役のいとこ、学生の友達、そして私で食べたもの。 手前の麺が開封の名物。 羊の骨から取ったスープに香辛料やラー油がはいっている。 そして丼の中には芝麻醤が溶け込んでいて、濃厚なゴマの香がする。 これもおいしかった。 こういう料理を食べることも、中国を旅する楽しさの一つ。 日本の中華料理店のメニューには、まず載っていない。 特に田舎では、素朴で温かい、人情そのもののような料理のめぐり合うことができる。 ただ、お腹が空いている時に食べれば、もっとおいしかっただろうな、とも思う。 さて、明日からは遼寧省に10日ほど滞在する。 天気予報を見ると、瀋陽では最低気温がマイナス20度を超える日が続いている。 寒い地域だが、せめて心が温まるような交流をしてきたいと思っている。 というわけで日記はしばらくお休みします。 では明日、行ってきます。
2008年01月22日
コメント(14)
-

中国の農村で雪かきをしたのだの巻
開封から帰ってきた。 学生の家での3泊4日のホーム・ステイが無事終了。 今回泊まらせてもらった学生の家は開封といっても、市内ではなく、県部。 中国の行政単位は省・市・県の順。 市の中に他の市があったり、県がいくつもあったりする。 市が日本でいうところの「県」で、県は日本でいう「町」にあたる。 学生の家を訪ねるのは、去年が2軒で、これが3軒目。 いずれも河南省内なので、他の省、まして都会部のことはわからない。 でも、中国の家はだいたいこんな感じ。 家の回りはコンクリート(或いはレンガ)の壁で囲まれていて、入口に門がある。 門を入ると、すぐ右側に台所があり、正面はこうなっている。 青い扉の向こうが居間であり、客間であり、食堂を兼ねた部屋。 中はこんな感じ。 今回の学生の家は、これまでの中で最も大きい。 それでも家の中には暖房は練炭火鉢が一つだけ。 それで湯を沸かし、料理に使う。 シャワーもない。 シャワーをする時は、どこか共同シャワー場へ行く。 水そのものがとても貴重なのだ。 日本のように蛇口をひねればすぐに温かい湯が出てくるなんて、ここでは考えられない。 でも不便だという感じはない。 これが普通の生活なのだ。 実は、私のホーム・ステイ期間中、学生は何をしようかといろいろと考えていたようだ。 彼女が通った学校を訪ねて、恩師と話をしたり。 開封市に行って、古い名所を見物したり。 有名な小籠包を食べたり……と。 しかし、それがすべてダメになった。 なぜかというと……。 大寒波が到来して、大雪が降ったから。 雪が積もることが滅多にない河南省で、一面、真っ白な景色が出現。 しかも日中でもずっと氷点下だったから、道路がすっかり凍結。 交通機関がマヒ状態になってしまった。 で、何をしたかというと、これ。 雪かき! ただ、日本の雪みたいに水分が多くないので、とても軽い。 軽い上に、わずかの風で、フワッと散っていく。 日本では、冬になると雪かきをよくやったものだが、中国で雪かきとは。 でも、これもいい経験。 むしろ観光地めぐりよりも、楽しかった。 学生も、その両親も、雪のために外に出られないことを残念がっていた。 だが、私にとっては、こういう経験ができたことの方が嬉しかった。 何より嬉しかったのは、お父さんたちとたくさん話ができたこと。 一緒にお酒も飲んだ。 お酒を飲みながら、話をした。 初日は話が弾まなかったが、2日目、3日目と、冗談を言い合えるまでになった。 食事を終わると、お父さんは必ずタバコを勧めてきた。 実は3年前に禁煙したのだが、お言葉に甘えて、吸わせていただいた。 それでも1日1本という、自分の中での原則は貫いた。 食後の一服はやっぱり、うまい! この先、もうタバコを吸うことはないだろうけど。
2008年01月21日
コメント(15)
-

冬の散歩道。。
起きたら一面の雪景色。 気温は氷点下なので、道路はカチコチに凍っている。 私の故郷に比べると降雪量はどうってことはない。 が、新郷で雪が降るということが珍しい。 既に故郷に帰った学生たちからも「雪が積もってますよ」というメールが次々に届いた。 今年は例年に比べて寒い冬を迎えている。 学生たちが試験期間に入ってからは、専ら読書三昧だった。 「三国志」(吉川英治)を全8巻読み終わり、その後、大沢在昌「闇先案内人(上下)」、横溝正史「夜歩く」、半村良「産霊山秘録」と読破した。 横溝正史は学生だった頃、30数冊読んだが、「夜歩く」は読み逃していた中の一冊。 「闇先案内人」は曲阜からの帰りの列車の中で立ったまま読み終えた。 大沢在昌ならやっぱり「新宿鮫(毒猿、無間人形)」「天使の牙」が一押し。 以前は、「三国志」の中で誰が好きか問われたら、いつもこう答えていた。 呂布! そう答えるたびに、相手からは怪訝な顔をされていた。 呂布は決して英雄でもないし、むしろ悪役として描かれることが多いからだ。 だが悪役とはいっても董卓らとは全然違う。 呂布の圧倒的な強さ、そして子供のような単純さ。 そういう部分に憧れていたのだ。 だが、今回、吉川英治の「三国志」を読み終わってみると、やはり彼だな。 諸葛孔明! 特に吉川英治の作品では孔明に多くのページを割いている。 そして創作も多い。 だから、なのかもしれないが、孔明には惹かれた。 天才的軍師と形容される孔明が、時に見せる人情と規律との葛藤。 頼れる者がおらず、孤軍奮闘せざるえない、孤独感と焦燥感。 天才が垣間見せる、そういう人間的な部分に惹かれた。 ああ、もっと読みたかった。 この冬休みは曹操が都を置いた許昌を旅する。 劉備が関羽と張飛を連れて、孔明を迎えにいった「三顧の礼」の舞台は襄樊。 ここからは列車で12時間ぐらい。 春になったら是非、訪ねてみたい。
2008年01月17日
コメント(16)
-
冬の旅。。
試験が終わり、学生たちが一斉に帰省を始めた。 ほとんどは河南省の出身者だが、それでも汽車で7、8時間というのはざら。 先ほど、遼寧省に帰る学生たちを見送ってきたが、彼らは20時間かけて家に帰る。 しかも自由席。 自由席といえば聞こえはいいが、要するに席がないということ。 満員の列車の中で座ることもできずに夜を明かす。 中国での移動は、まさに体力勝負だ。 私も去年、南陽まで夜行の「無座」で行ったが、8時間立ちっぱなしだった。 学生を送って、部屋に帰ってきたら、T先生と学生が立ち話をしていた。 あれっ、と思った。 なぜなら、T先生は昼前に、学生と一緒に、彼女の故郷に行ったはずだったからだ……。 聞けば、列車は人がいっぱいで、乗ることができなかったという。 この学校がそうであるように、中国じゅうの多くの学校で冬休みが始まり、学生が移動を始めてからだ。 そして再度、夜8時の列車に乗ることにしたのだそうだ。 8時の列車に乗れば、目的地に着くのは深夜3時。 冬休みに入って、まず学生たちの移動が始まった。 春節が近くなると、これに大人たちの移動が加わる。 中国の人口は世界の4分の1を占めているが、それがこの時期、一斉に移動を始める。 私は明後日(18日)から開封に行く。 学生の家に泊まって、家族の人たちと語りあい、酒を飲みあって、農村の生活を満喫する。 そうすれば、観光旅行だけでは見えないものが見えてくる。 内陸部のしかも農村だから、外国人が訪れるようなところではない。 去年もそうだったが、私が村を訪れる初めての外国人になるはずだ。 どんな出会いがあるか、どんな経験ができるか、楽しみ。
2008年01月16日
コメント(16)
-

曲阜散策。。
旅の中でも、私が好きなのは街歩き。 観光地巡りもいいが、街の中を散策するのも楽しい。 特に中国は、日本では見ることができない情景に出会うことが多い。 下の写真は曲阜の市場。 肉や魚が、ドスンと積まれたり、ぶら下げられたりしている。 下の写真は裸に剥かれた鶏。 生きたままの鶏を売っている店もある。 新鮮といえば、これ以上ないほど新鮮。 生きた鶏を何羽か足を結んで自転車にぶら下げて帰っていく人もいた。 この他にも羊、豚などの肉屋さんがたくさん。 「狗」と書かれた店があるが、これは犬の肉のこと。 犬の肉は食べればおいしいそうだが、まだ食べたことがない。 食べたいとも思わないけど。 でも食事として出てくれば、食べる。 こちらは飲食街。 あちこちの店から温かそうな湯気が立ち上り、賑やかな声が響いている。 見ているだけで、温まりそうな感じがしたものだ。
2008年01月15日
コメント(10)
-

曲阜行。。
曲阜は寒気の中にあった。 「曲阜」という街の名には曲がっている豊かな丘という意味がある。 中国の古代、春秋戦国時代に魯の国が置かれたところで、800年間、都として栄えたという。 そして何より、孔子の故郷として名高い街である。 その曲阜を訪ねてきた。 夜11時57分に夜行列車で新郷駅を出発。 駅には、夜でも、こんなにたくさんの列車が発着している。 夜行列車とはいっても、日中もずっと走り続けている。 始発から終点までが60時間なんて列車もある。 曲阜駅に着いたのは朝の5時半。 まだ外は真っ暗。 しかも、ローカル駅の曲阜では、即座に駅舎の外に出され、構内で時間を潰すこともできない。 というわけで、三輪タクシーに乗って、市内へ。 その三輪タクシーが契約をしている(らしい)ホテルへ直行し、そのままチェックイン。 ☆が1つあるかないかの、ぼろいホテルだったが、暖を取りながら、しばし休憩。 ホテルから歩いて5分のところにこんな城壁。 これらの城壁は外部からの敵の侵入を防ぐためのもの。 孔廟の中には、観光客の姿はまったくなかった。 観光シーズンでもなく、特にこの日は寒かったからだろう。 城壁の周りの堀の水が凍っていたほどだ。 以下は孔廟の写真。 孔廟とは伝統的大学の総本山で、北京の紫禁城、泰山の岱廟とともに中国三大宮殿建築の一つ。 ▲孔廟奎文閣(創建1018年) ▲屋根の上にはいろいろな動物が。 ▲大成殿(創建1018年) 皇帝の宮殿のみに施される皇宮建築様式が取り入れられている。 このことからも孔子がいかに敬われていたかがわかる。 孔廟を出ると、こんな看板が。 「すぐ孔府だ」「1500メートルとすぐ孔林だ」って……。 孔府は孔子の子孫が暮らしていた邸宅。 孔林は孔子一族の墓苑。 ▲これが孔子の墓。 後ろに見える土まんじゅうの中に孔子が眠っている。 孔林の中はとにかく広い。 孔子は紀元前500年ぐらいの生まれで、その後、現在まで2500年間にわたって系図が辿れる。 これって、すごいことだと思う。 写真を見てもわかるように、観光客の姿はほとんどない。 とにかく寒い日で、手袋をしている手がかじかむほど。 口は回らないし。 というわけで、昼ごはんは、熱くておいしいものを食べることにした。 それは、また明日。
2008年01月14日
コメント(12)
-
師曰く。。
今夜の夜行で曲阜へ行く。 曲阜は、私が住んでいる河南省の隣にある山東省の街。 新郷からは列車で5時間くらい。 最近までは日本人にあまり馴染みのない街だった。 しかし、先日、福田首相が訪れたことで、日本人にも知られるようになった。 孔子の故郷として知られ、多くの名所がある。 世界遺産にも登録されている。 初めは1人で行くつもりだったが、同僚のI先生が同行することになった。 2人なら食事代やタクシー代が半分になる。 まあ、問題は、あれだな。 雨! 中国に来てから、どこかに行くたびに、必ず雨が降る。 確率100%! 曲阜ではどうかな。 今の様子だと、雨ではなく、雪が降りそうだけど……。 雪が舞う、孔子廟もきっときれいだろうな。 ……なんて負け惜しみ言っちゃったりして。
2008年01月11日
コメント(10)
-
死ぬほど。。
とても嬉しいことを、中国語で「高興死了」といいます。 日本語に訳せば「死ぬほど嬉しい」です。 実は、一昨日、死ぬほど嬉しいことがありました。 まだ死んではいません。 しかし、嬉しさはずっと続いています。 他の人から見れば、きっとどうってないことです。
2008年01月10日
コメント(14)
-
こっそり、ひっそり。。
今週から試験ウィーク。 3年生たちが、時々、質問にやって来る。 曰く……、 「寝転ぶ」「寝そべる」「寝転がる」の違いは何か? 「もはや」「すでに」はどう違うのか? 「ひっそり」「こっそり」「そっと」の使い分け。 など。 これは「総合日本語」という授業で出てきた類義語の中の一例。 学生たちに使い分けを説明しながら、なんだかなあ、と思っていた。 「総合日本語」というのは、日本でいう「国語」のような授業。 だから担当は1、2年生は中国人教師だが、3年生と4年生は日本人の「国語」教師。 先日、ある学生と話をしていた時に、こんな質問を受けた。 「もし先生が『総合日本語』の先生だったら、どういう授業をしますか?」 『総合日本語』の担当は、日本で『国語』担当の教師という原則がある。 だから、私など間違っても、その授業を担当することはない。 というわけで、あくまでも「もし」という仮定でだが……。 週に3回ある『総合日本語』の授業のうち、2回は読解や文法、単語などの説明に費やす。 まあ、それでも笑いが出て、活気のある面白い授業はするけど。 そして残る1回は、毎週違う授業をする。 例えば、覚えたばかりの類義語を使ったショート・コント大会。 「こっそり」「ひっそり」「寝転ぶ」「寝転がる」などは格好の題材になりそう。 または、敬語を覚えた時は「面接」「社長と秘書」などの設定でロール・プレイ。 或いは、単元の内容に関するディスカッション。 細かい単語や文法ではなく、単元全体の感想などをお互いに話しあう。 端的に言えば『総合日本語』は教科書を読む授業。 だが、それに縛られる必要はないと思う。 目で読んで、全部を暗記しようとしても、それはなかなか難しい。 目で読み、口で話し、耳で聞いて、体を動かして覚える。 そこに多少の笑いを持ち込めば、楽しいだけではなく、単語や文法の定着もはかれる。 『総合日本語』の授業をしながら会話が上手になってもいいじゃないか、と思う。 そして単語や文法といった細かいことだけではなく、単元全体を眺めることもあってもいい。 まあ、そんなことを答えた。 そして、もし私が『古典』の担当なら……。 学生たちに、台詞は全編、古語の『古典ドラマ』をやらないかと提案してみたい。 中国人学生たちの、古語によるドラマ。 なんだか面白そうだな。 でも、そんなチャンスないだろうな。
2008年01月07日
コメント(16)
-
崩壊の前日。。
今、私は曲がりなりにも中国で日本語教師をしている。 そのきっかけは、日本で中国人研修生たちに日本語を教えたことにある。 研修生とは、日本の工場で働く労働者のこと。 私はある協同組合の設立にかかわり、その後、一人で事務関係の仕事をしていた。 正業は新聞記者だったから、二足のわらじを履いて、ひどく忙しい毎日だった。 組合を設立し、研修生たちを受け入れ、彼女らに日本語を教える仕事も受け持った。 研修生たちの本分は工場で仕事をすることにある。 日本の受入れ企業もそれを期待している。 だが、彼女らは仕事をする一方で、日本語の習得にも積極的だった。 毎年、日本語能力試験はほぼ全員が受験し、そしてほぼ全員が2級に合格した。 1級に合格した者も多い。 彼女らは仕事を終えた夜中、寮で日本語を勉強していた。 または朝、早く起きて、教科書を開いていた。 当時、私が教えていた研修生たちの中には、中国に帰国後、日本語の教師や通訳として活躍している者が多数いる。 JITCO主催の「外国人研修生日本語作文コンクール」にも毎年、多数応募していた。 毎年、必ず入選者がいた。 全国でも十指に入る優良組合としての認知も受けていた。 他の組合からは「どうして?」とその秘訣を聞かれるようになった。 JITCOから、日本語教育について取材を受けたこともあった。 組合の運営から手を引いたのが4年前。 その後は、研修生たちが来日時に1か月だけ、日本語を教えるだけになった。 その後の組合の崩壊は早かった。 そして遂に先日、研修生の受入禁止という罰則をくらったそうだ。 違反行為が数々発覚し、度重なる改善指導にもかかわらず、違反を続けていたという。 「違反」とは給与や待遇、生活状況などの規則違反のこと。 近年は、日本語能力試験への受験者も年々少なくなっていた。 レベルの低下も著しかった。 合格点にはるかに届かない低得点ばかりだった。 作文コンクールへの応募も減った。 こちらのレベルも目を覆うほどになっていた。 組合を設立するまでの苦労を思うと、崩壊はあっけないほど速い。 口幅ったい言い方をするようだが、日本語を教えることができる人はいても、日本語に興味を持たせる教え方ができる人は多くない。 興味を持たせなければ、教えた日本語は、次から次へと忘れていく。 そして、最も重要なことは、その興味を持続させてやること。 あらためて、そんなことを考えた、年の初めだった。 marinさん: メッセージありがとうございました。 とても励まされました。 返事を出したかったのですが、うまく送信できません。 今日の日記で、返事に代えさせてください。
2008年01月05日
コメント(10)
-

号泣!
本日2回目の日記。 別にどうって話題ではないのだけど……。 中国で最大のイベントは春節。 だから正月はそれほど重要視されていない。 そいうわけで、新年の気分がしなかったのだが、テレビを見ていたら、新年気分になった。 CCTV5(スポーツ専門チャンネル)で、こんな番組をやっていた。 「30人31脚」! どこかで見たことがある番組。 勝っては喜びを爆発させ……。 負けては号泣。 どこの国でも子供は同じだなあ。 この日は「天津」の学校ばかり出ていた。 (zhuoziさん、見ましたか?) 明日は「上海」が舞台になるそうだ。 これ、多分、新年特番。 ついつい最後まで見てしまった(笑)。
2008年01月03日
コメント(12)
-

「日本晴れ」。。
今年の元旦は、この地方には珍しいくらいの「日本晴れ」でした。 いつもは空が濁って、太陽が赤く見えるのですが、この日は眩しい太陽が出ていました。 夜は、これも珍しく空には星が出て、学生と星を眺めながら散歩をしていました。 元旦と言っても、こちらでは普通の日曜日と変わりがありません。 1月2日からは、通常の授業がありました。 こんな感じです。 学生たちは授業に出ているか、空いた教室で自習をしているかです。 私はといえば、毎日『三国志』を読んでいますが、それももうすぐ読み終わります。 なんだか寂しい感じがします。 もっと読みたい、と思います。 以前は、純文学もけっこう読んでいましたが、専門は広義のミステリーでした。 推理小説(本格、スリラー、古典)、冒険、、アクション、海外翻訳小説ばかりでした。 最近になってから歴史小説を読むようになりました。 広大な中国のど真ん中で、いにしえを舞台にした大長編小説を読む。 これも大いなる幸せです。
2008年01月03日
コメント(7)
-
学生優先で。。。
新年好! 明けましておめでとうございます。 ……と言っても、正月らしさはどこにもありません。 門松もないし、注連飾りもない。 晴れ着姿の女性もいなければ、初詣に向かう家族連れの姿もない。 テレビで新春特番もないし、雑煮を食べることもない。 それでも、まあ新年です。 学生に会えば「明けましておめでとうございます」と挨拶をしてくれます。 メールもたくさん来ました。 朝早くから着信音が鳴っていました。 全部で50通ぐらい、届いたでしょうか。 その全部に返事を出しました。 中国で新年を迎えるのは、去年に続いて今年が2回目。 同じことの繰り返しじゃ進歩がない。 新しい1年は昨年以上に充実した年にしたいと思っています。 まだ知らない中国を知りたい。 行ったことがない所に行きたい。 食べたことがないものを食べたい。 知り合っていない人とたくさん知り合いたい。 最大の目標は、学生たちの日本語能力を向上させること。 特に「会話」! 自分の中国語能力はその後のことだな。 ……って、言い訳ですが(笑)。 皆様のこの1年が幸多い年となりますよう、お祈りしております。
2008年01月01日
コメント(10)
全13件 (13件中 1-13件目)
1