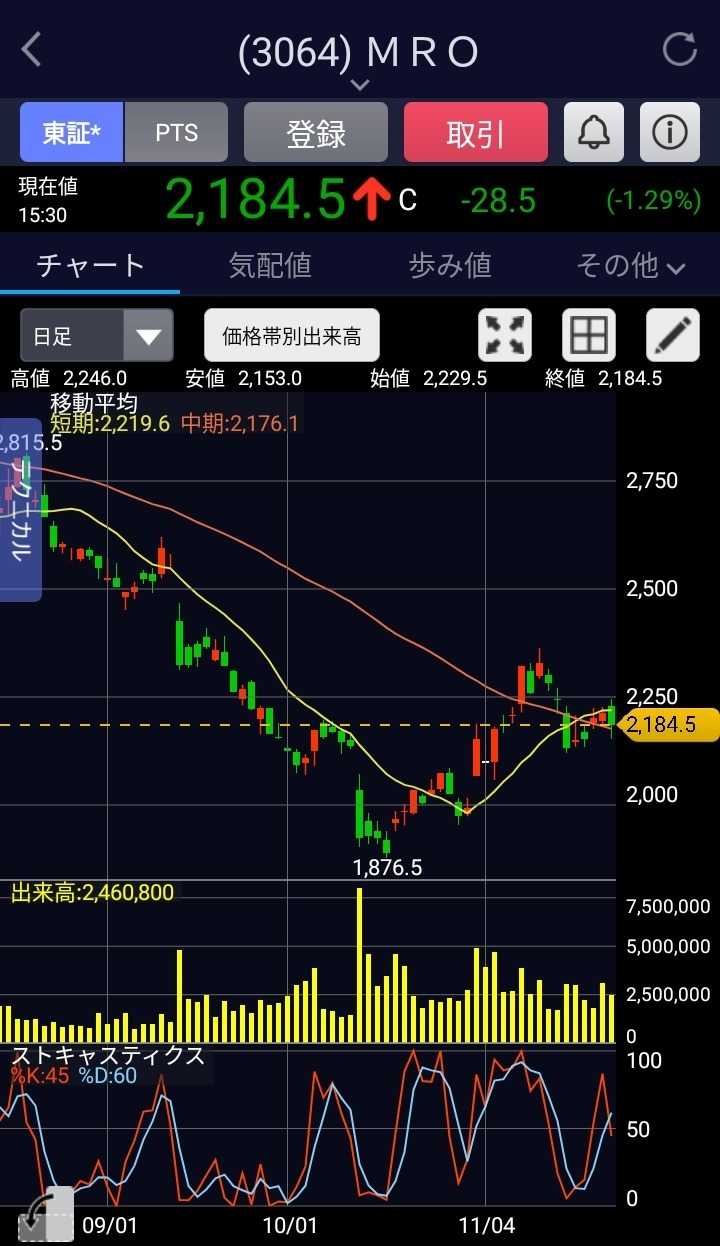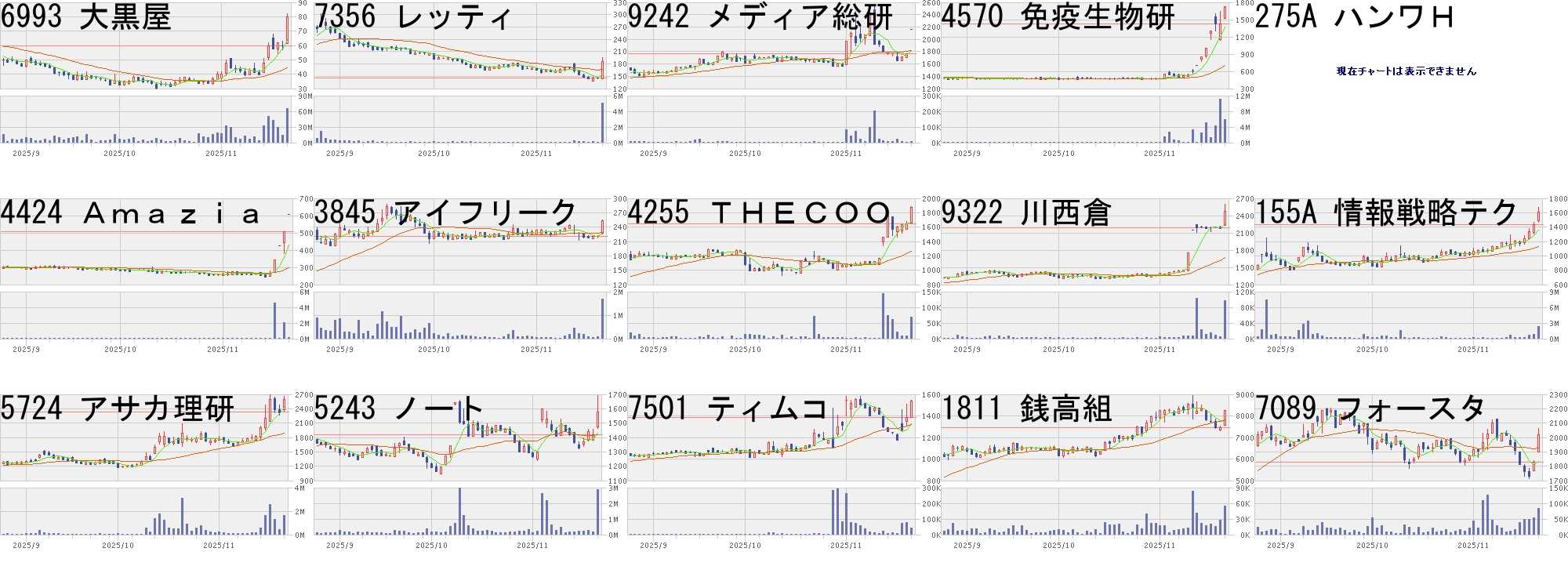2012年09月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
台風
台風17号が日本に接近しつつあります。数ある災害の中でも、気象災害はある程度事前予測が可能で、特に台風はいつ頃どの辺りにやってくるということが、あらかじめだいたい分かっています。従って、地震などと違ってある程度の準備が可能なのですが、それでも毎回必ず人的な被害が生じてしまいます。※※ただし、有史以降の台風で日本における人的被害が最も大きかったのは、伊勢湾台風の5000人で、万の単位に達する死者を出した台風は、日本では記録されていません。その限りでは、地震や火山噴火(去年の東日本材震災を始め、万単位の犠牲者を出した例が数多くある)の方がより深刻な災害とも言えるかも知れません。とはいえ、今回の台風は非常に規模が大きい。現在(29日午後11時)の中心気圧は940ヘクトパスカル。これは、とんでもなく強力な台風です。もっとも、最近は地球温暖化のせいか、強力な台風が増えているようで、940ヘクトパスカルという数値も、それほど珍しくなくなっているような気もしますが。問題は、明日の午後9時時点(東海地方付近に上陸する公算が大きい)の予想気圧が、まだ950ヘクトパスカルもある、ということです。気象庁のサイトに上陸時(直前)の中心気圧が低い台風ベスト10が載っています。これによると、観測史上、上陸時の気圧が最も低かったのは1961年第二室戸台風の925ヘクトパスカルで、第10位タイが945ヘクトパスカルとなっています。今回もと950ヘクトパスカルで上陸すれば、観測史上15位ということになります。(ただし、統計開始以前の参考記録として、1934年室戸台風の911ヘクトパスカルと、ついで1945年枕崎台風の916ヘクトパスカルがある)しかも、それぞれの台風の上陸地点を見てください。いずれも九州か和歌山か高知です。東海地方で950ヘクトパスカルで上陸する台風というのは、前例があるかどうかは私は知りませんが、かなり稀有な例であることは間違いないでしょう。上記は関東を基準にしての話ですが、沖縄では最大瞬間風速61.2メートルを記録し、これは観測史上3番目だそうなので、関東を基準にしなくても、やはり観測史上に残る強力な台風ということになるのかもしれません。明日の夕方は、あまり家の外に出ないことにします。それにしても、昔住んでいた実家は、窓に雨戸がありましたが、今は窓に雨戸のない家が増えている気がします。我が家もそうなのです。昔の家より窓ガラスは厚く、網入なので昔の家とは同列には言えませんけれど、気分的には、台風の時にはガラス窓には雨戸がほしい気がします。もっとも、関東はこの夏少雨傾向のため水不足気味なのですが、ひょっとするとこの台風によって水不足が解消するかもしれません。利根川水系の貯水量の推移を見ていると、結構な土砂降りの雨のように見えてもなかなか貯水量が増えないのに、台風一個来ただけで、わずか2~3日で何千万トン、下手すると1億トンも貯水量が増えたりします。その意味では台風は恵みである、とも言えなくはありません。日本に台風が来なかったら、水害は減る代わりに、もっと頻繁に渇水に苦しむことになりそうです。自然災害には、たいてい、被害と恵みが表裏一体になっているものです。追記結果的には、予想より若干西よりの地点で台風が上陸(紀伊半島)したため、台風が関東付近に接近した時点では、そこまで記録的な気圧ではなくなっていました。ちなみに、利根川水系の8ダムの貯水量は、一昨日(9/30午前0時現在)の時点では1億5200万立米あまり、それが丸2日近く経過した今日(10/1)午後11時現在は1億8600万立米。ほんの40時間ちょっとで、3400万トンほど水がたまった計算です。取水制限は解除されるだろうか。
2012.09.29
コメント(0)
-
やっぱり、自民党内で快く思っていない人は多いようです
「安倍さん、今度はいつ投げ出すの?」 自民県議ツイートに批判殺到自民党に所属する来代(きただい)正文徳島県議(66)が、党総裁に返り咲いた安倍晋三元首相を批判し、持病を揶揄(やゆ)する内容の書き込みを短文投稿サイト「ツイッター」に書き込んでいたことが28日、分かった。全国各地から批判が殺到、来代県議は謝罪した上でツイッターを閉鎖した。来代県議は26日、自身のツイッターに「安倍総裁さん、今度はいつやめる、いや、何時投げ出すんですか!?今度の理由は下痢から便秘ですか?」などと投稿。その後、ツイッターやネット掲示板などに来代県議を非難する書き込みが相次ぎ、27日には県議会事務局などにも抗議が殺到したという。来代県議は「地方の声を無視された腹いせに、新総裁の悪口を言ったらおこられました。新総裁に地方の切り捨てがないようお願いと、失礼をおわびします」と釈明の書き込みをして、ツイッターを閉鎖した。---昨日の記事でも少し紹介しましたが、党員投票と間逆の結果に対して、不満に思っている人は多いようですね。まあ、私から見れば、石破は、安倍より「ほんの少しマシ」にしか過ぎないのですが。まあ確かに、「今度の理由は下痢から便秘ですか?」は、同じ政党にいる人間に対してぶつける言葉としては、あまり品がよいとは言えないことは確かでしょう。ところで、昨日紹介した読売新聞の記事によると、安倍は「首相辞任後は、健康食品のおかげで症状は改善に向かったという。09年末に国内で発売された新薬が効き、現在は「ほぼ完治した」と安倍氏は語る。」のだそうです。「健康食品」は薬じゃないので、それで病気が治るなんてことは、常識的に言って考えがたい。一方、「09年末に国内で発売された新薬」というのは、更に検索してみると、こんな記事に行き当たりました。安倍氏を救った“奇跡の新薬”安倍氏は2年前から、09年12月発売の「ゼリア新薬工業」の新薬「アサコール」を常備薬としている。同社によると、完治は難しいが抗炎症作用が働き下痢などの症状を抑える効果があるという。安倍氏の事務所は「飲んでいる限りは大丈夫」と強調している。---症状を抑える、つまり対症療法の薬というわけです。安倍自身が「ほぼ完治」と言っている言葉とは裏腹に、薬を開発した側は「完治は難しい」と言っている。つまり、薬や、まして健康食品で病気が治ったわけではなく、プレッシャーがなくなったから治った、いや治ったわけではなく症状が抑えられている、ということなのでしょう。プレッシャーがかかる場面では、再発の可能性が高いんじゃないかと思えるんですね。
2012.09.28
コメント(4)
-
強い日本よりも
政権奪還へ全力尽くす…自民・安倍新総裁自民党新総裁に選出された安倍晋三元首相は26日午後、党本部であいさつし、「(自らの)経験、責任をしっかりと胸にきざみ政権奪還に向け、皆様とともに全力を尽くす」と述べた。安倍氏は、「この3年間、野党のリーダーとして大変なご苦労をされ、自民党を守って頂いた谷垣禎一総裁に心から感謝したい」と語った。その上で、5年前に首相を辞任したことに触れ、「総理を突然辞任する結果になり皆様に本当にご迷惑をおかけした」と陳謝した。安倍氏は、「政権奪還することは私たちのためではない。自民党のためでもない。日本を取り戻す、強い日本を作る、豊かな日本を作る、そして日本人が日本に生まれたことに幸せを感じる、そういう日本を作る」と訴えた。---党員投票では、石破157票対安倍84票という大差が付いていたそうですが、国会議員だけの決選投票で大逆転だそうです。石破がよい、とは言いませんが(原発推進派だし)歴史認識に関しては、石破は安倍に比べれば遙かにマシというものです。もっともなって欲しくない人物が次の首相の最有力候補になった、というのは、私にとって実にがっくりする話です。それはともかくとして、「日本を取り戻す、強い日本を作る、豊かな日本を作る、そして日本人が日本に生まれたことに幸せを感じる、そういう日本を作る」と言っているそうで。強い日本、ですか。私の知る限り、日本が(相対的に)もっとも強い国だったのは、太平洋戦争の直前から戦時中までです。それはしかし、日本人のほとんどが不幸に陥った時期でもあります。現在の北朝鮮なんか、相当無理して強い国を目指していますが、国民はとても不幸としか思えません。強い国であることと国民が幸せなことは、まったくイコールにはならないように思います。(ここで言う強い国というのは、軍事面や対外関係という意味です)国家や組織においてもそうですが、個人においても、強い(腕力や他者への態度が)人が幸せかというと、あんまりそうは思えないのです。私は、日本が、できるだけ多くの国民が幸せであると感じる国であってほしいと思っています。何をもって「幸せ」と感じるかは人それぞれです。ただ、その前提条件となるのは、まず平和な国であることです。日常的に死の危険に怯える生活を「幸せ」とは言い難いですから。そして、大半の国民が、ある程度は豊かであった方がよい。豊かであればあるほど幸せである、とは言えませんが、あまり貧しいのは不幸である、ということは言えます。そして、もう一つは未来に向けた希望があること。希望の中身は、人それぞれですし、そんなたいそうなものでなくてもよいのですが、希望のないところに幸せな生活はなかなか難しい。それにしても、「強い日本」を呼号する安倍晋三自身が、どの程度「強い」のかは、きわめて疑問の残るところです。前述のとおり、人間は強ければ幸せってものではありませんけれど、そうは言っても、体調を壊したと言ってあんな形で政権を投げ出して、しかも投げ出したとたんに体調回復というのだから、精神的な弱さを露呈しています。安倍の主義主張に私は反対ですが、そのこと以上に、近い将来起こるかも知れない東海/東南海/南海地震の際に、安倍が首相の座にいることを危惧しますね。そんな災害の真っ最中に、「総理は持病が再発して・・・・・・」なんてのは、話になりませんから。安倍新総裁、山登ってアピール「持病ほぼ完治」自民党の安倍新総裁は2007年9月、持病の潰瘍性大腸炎の悪化で、首相を辞任した過去がある。同年7月の参院選で自民党が惨敗、臨時国会で代表質問を受ける直前の辞任劇だったため、「政権投げだし」と厳しい批判を浴びた。首相辞任後は、健康食品のおかげで症状は改善に向かったという。09年末に国内で発売された新薬が効き、現在は「ほぼ完治した」と安倍氏は語る。毎年、東京の高尾山に登るなど健康回復をアピールしている。(以下略)---どう考えたって、症状が改善したのは、健康食品のおかげではなく政権を投げ出してプレッシャーが消滅したからとしか思えないんですけどね。「山登ってアピール」っていう、その登った山が、高尾山。それに、この記事にはありませんが、安倍の公式サイトによれば、丹沢の大山にも登ったことがあるようです。高尾山に大山・・・・・そりゃ、どちらも良いところですよ、とくに高尾山は私も大好きで、ほぼ毎年のように登ります。だけど、あれを「山に登った」と言うかね。ちなみに、高尾山は標高599m、登山口の高尾山口は189mなので、標高差410m。大山は標高は1251mあるけれど、ケーブルカーの終点が700mなので、標高差は551m。まあ、ハイキングですね。私は、大山は一度だけ登ったことがあります。冬でした。途中から激しい降雪になって、下りは新雪の中を歩きました。ケーブルカーを使わなかったので、バス停からの標高差は800m以上あったのですが、登山道は緩やかで歩きやすかったので、そんなにきつかった記憶はありません。健康回復を山登りでアピールするというなら、槍や穂高、とまでは言いませんけど、せめて富士山くらい登ってみせればいいのに。余談ですが、このサイトによると、富士山に登った首相経験者は、橋本龍太郎・小渕恵三・菅直人の3人、それに今回自民党総裁の座を追われた谷垣禎一も登っている。
2012.09.27
コメント(6)
-
弱腰外交という勘違い
日台の船が互いに放水 緊迫の尖閣上空ルポ尖閣諸島をめざす台湾からの漁船団を上空から朝日新聞社機で取材した。魚釣島の周辺海域で、台湾の漁船団と巡視船が、日本の巡視船と攻防を繰り広げていた。午前7時半前、尖閣諸島・魚釣島の西約30キロの海域。船首や船尾、ブリッジを台湾の旗や横断幕などで飾り立てた台湾の漁船団を見つけた。小型の漁船が30隻以上。複数のグループに分かれ、数キロ四方に広がって進んでいた。針路は、魚釣島のある東方向だ。「漁船団を守る」として同行する、海岸巡防署(海上保安庁に相当)の巡視船も数隻見えた。日本の海上保安庁の巡視船が漁船団を取り囲むように並走していた。---台湾は「親日」の国だといわれます。私自身は台湾に行ったことがない(というか、中国にも行ったことがない)ので、話に聞いているだけですが、実際に台湾のことをよく知る人の多くがそのように言っているので、おそらく間違いではないのでしょう。しかし、日本に対する「好き嫌い」の問題と、領土問題は同列ではない、ということなのでしょう。日中間で対立している尖閣諸島の領有権問題に、台湾もまた乗り出してきています。台湾、と言っても、「中華民国」つまり中国を代表する正当な政権であるという建前からの領有権の主張ですから、突き詰めれば「中国のものだ」と言っているわけです。馬政権の尖閣対応に野党も「弱腰」批判 台湾日本政府による沖縄県・尖閣諸島(台湾名・釣魚台)の国有化で、台湾の馬英九政権の対日配慮が、与党・中国国民党だけでなく、最大野党・民主進歩党の一部からも「弱腰」との批判にさらされている。日台漁業交渉再開に向けた抑制姿勢が、内政では与野党に攻撃材料を与えているかっこうだ。(中略)しかし、国民党の立法委員(国会議員に相当)は17日、日中間の争いだけが注目され「われわれ(台湾)は存在しないかのようだ」と指摘。民進党立法委員も「釣魚台はわれらの領土」「(馬政権は)まるで傍観者で、非常におかしい」などと批判を強めている。日本では国民党に比べ親日イメージの強い民進党だが、尖閣に関しては民進党所属の宜蘭県長(知事)が「(台湾の旗を掲げて)上陸したい」と発言するなど強硬派もおり、8月に香港の活動家らの抗議船の台湾寄港を拒否した馬政権では、内に対する姿勢の見せ方に苦慮している。(以下略)---「日本では国民党に比べ親日イメージの強い民進党だが」という一文には失笑しました。だって、そういうイメージを振りまいた当事者の一人が産経新聞でしょう。まあ、でもそういうことなんですよ。先日、香港の活動家が尖閣諸島に上陸して、即刻逮捕されて強制送還になりましたが、彼らもまた、中国(大陸)の意を受けた活動家というわけではなく、むしろ正反対、つまり反中国共産党の活動家であったそうです。実際、日本ではほとんど報道されていませんが、彼らが上陸した際には、中国の国旗(五星紅旗)と台湾の「国旗」(晴天白日地満紅旗)の両方を掲げていました。私は、尖閣諸島は日本の領土だと思っているし、国有かも基本的には賛成(より正確に言えば、やむを得ない)なのですが、この状況を見ると、国有化するにしてもタイミングがあまりに悪かったのではないかという気がしてなりません。ネットウヨク系の人たちは、ロシアも敵、中国も敵、韓国も北朝鮮も敵だと、日本は周りを敵に囲まれていると叫びたがるわけですが、その「敵」の一員に、これまで彼らが「味方」だと言っていた台湾も加わることになるわけです。でも、あえて言うなら、そんなに回り中が敵だらけというのは、本人自身に問題があるということではないかと思います。少なくとも、国対国の関係ではなく個人対個人の関係で考えれば、「俺の周りの連中は、みんな俺を憎んでいる敵ばかりだ」なんてのは、たいていは本人自身に何らかの問題があるからですよ。産経新聞あたりを代表例にして、領土問題について「弱腰外交は怪しからん」と叫ぶ人たちがいます。弱腰外交だから中国が尖閣諸島の領有を主張する、弱腰だからロシアのメドベージェフ大統領が北方領土に上陸した、弱腰だから韓国の李明博大統領が竹島に上陸した、というわけです。挙句の果てに、自民党の石原伸晃に至っては「自民党政権なら李明博大統領は竹島に上陸しなかった」とまで放言している。ちょっとでも頭を働かせれば、日本が強硬な態度をとればロシアや韓国の大統領が竹島、北方領土への上陸を取りやめる、などということがあり得ないことは分かるはずです。強硬な態度を示せば引くくらいなら、最初から領土問題になどなっていないのです。むしろ逆に、相手側も引けない立場にある時は、こちらが強硬な態度を取れば取るほど、相手側もより強硬な態度になるに決まっている。それが「争い」というものの基本でしょう。だいたい、日本自身が、中国がどれだけ強硬な態度をとっても「では尖閣諸島は中国に割譲します」などとは、絶対言わないではないですか。まして、「自民党政権なら」なんてのは論外もいいところです。国有化自体はやむを得ないとしても、それをこのタイミング(柳条湖事件の記念日を間近に控え、日中国交回復40周年も間近に控え、しかも中国国内では次の国家指導者を決めようとしている)で、大々的に発表するのは、やはりあからさまに挑発的だったといわざるを得ないようです。勿論、中国側のずいぶん挑発的な行動に出てはいるにしても、です。領土を守ることと、相手国にけんかを売ること(または、売られたけんかを安易に買うこと)を混同してはいけません。
2012.09.25
コメント(2)
-

今年も福島県川俣へ
毎年10月の3連休に福島県川俣町で開催されている、日本最大のフォルクローレの祭典、「コスキン・エン・ハポン」に、今年も行くことになりました。昨年は演奏せずに飲んだくれ、もとい、他人の演奏を聞くだけのために行ったのですが、今年は、あるグループから助っ人の依頼がかかり、出演者として参加することになりました。コスキンで演奏したのは、2000年が最後だったと記憶しています。(ひょっとすると1999年だったかな)それ以来だから、実に12年ぶりの演奏ということになります。助っ人の依頼をいただいたのは、広島のグループです。存じ上げている方ではありますが、一緒に演奏するのは初めてです。さて、どうなることやら。それにしても、東京からだって、福島は決して近くはない距離ですが、広島から福島は遠い。去年のステージです↓私自身は、去年はこんなことばっかりやってました↓私が毎年参加していた1990年代当時は、このイベントは土日の2日間の日程で、出演グループが100を少し超える程度でした。しかし、毎年のように出演グループが増え、初日の終演時間が、1992~3年頃は深夜2時頃だったのに、それがどんどん伸びて、私が最後に出演した頃には、出演グループが130くらい、初日の終演が朝7時にもなり、完全徹夜イベント状態。一度初日のトリで演奏したことがあるのですが、そのときは確か深夜3時半くらいだった記憶があります。12時過ぎにはメンバー全員泥酔状態だったのですが、出番が来たころには酔いもさめて、ちゃんと演奏していました。いや、演奏していたつもりですが、自分がそう思っていただけかも。そのときは、私も20代から30代はじめ頃、まだ若くて無理が利きました。今はとても同じことはできません。↓19年前の演奏。私は左から二番目でギターを弾いています。当時25歳ですよ!そのため、10年ほど前に体育の日が月曜に固定されたときから、日程が3日間に延びています。しかし、今年のタイムスケジュールを見ると、3日間日程でも終演予定時間は夜中の1時頃になっています。予定より時間が押す可能性が高いので、実際の終演は2時頃かなあ。出演グループ数は188というから、ずいぶん増えてしまったようです。さすがに、どんなに増えても4日日程にはできないので、そろそろ規模が限界に達しつつあるようです。私の印象では、世間一般にフォルクローレを演奏するグループがすごく増えているようには思えないのですが、コスキンに参加するグループだけは増加の一途というのは、なぜなんでしょうかね。---話は違いますが、去年はある団体から放射線測定器を借りて、もって行ったところ、毎時0.6マイクロシーベルトという数値が出ました。あれから1年、今年は測定器を持っていく必要はなさそうです。というのは、文部科学省のモニタリングポストの計測点の一つに、川俣中央公民館があるのです。文科省モニタリングポスト 川俣中央公民館の数値2012年09月23日22時50分時点の測定値は、0.571μSv/hとなっています。うーーん、去年の数値(0.6μSv/h)から、まったく減っていません。これを年間に換算すると、5mSvになります。私は日帰りで行くだけだから特に気にしませんが、そこに住んでいる人、特に子どもにとっては、これは怖い数字です。それにしても、1年間たって、もう少し減衰していると予想していたのですが、放射線量はぜんぜん減っていないですね。
2012.09.23
コメント(2)
-
3000メートル峰
Wikipediaによると、日本には3000m峰が21座ある、ということになっているそうです。(どこまでをひとつの山とみなし、どこからを別の山とみなすかは人によって定義が違うので、数え方によってはもっと多い数になる)先日、日本最高峰の富士山に登った後、改めて、3000目ートル峰の一覧を見てみたら、1位から9位まで登っていることに気がつきました。番外 チャカルタヤ山 5395m 2001年12月(日本じゃないけど)1位 富士山 3776m 2012年9月2位 北岳 3192m 1993年7月他計5回3位 奥穂高岳 3190m 2000年10月4位 間ノ岳(南ア) 3189m 1997年8月と1999年8月5位 槍ヶ岳 3180m 1995年8月と2000年7月6位 悪沢岳 3141m 2001年7月7位 赤石岳 3120m 2001年7月8位 涸沢岳 3110m 1999年5月と2000年10月9位 北穂高岳 3109m 2009年9月10位 大喰岳 3101m 未踏以下、登ったことのある3000m峰だけをピックアップすると13位 荒川中岳 3083m 2001年7月14位 御嶽山 3067m 2012年8月15位 西農鳥岳 3051m 1997年8月と1999年8月16位 塩見岳 3046m 1998年7月18位 仙丈岳 3033m 1992年7月他計3回そして、Wikipediaの記事で独立峰とみなしていない3000m峰5つのうち小赤石岳 3081m 2001年7月荒川前岳 3068m 2001年7月 中白峰山 3055m 1993年7月他計3回農鳥岳 3026m 1997年8月と1999年8月の4つは登っています。結局、3000m峰で未踏なのは、南アルプスでは聖岳(3013m)だけ。北アルプスではまだ沢山残っていますけど、私の力で上るのが難しそうな山はなさそうです。強いて言えば、前穂高岳が一番難しいでしょうが、奥穂や北穂と比べてどうなんだろう。あとは、技術的に難しい山はありません。体力さえあれば登れる。というわけで、日本の3000メートル峰完登を目指すのも一興かな、なんてね。ただし、Wikipediaの記事で独立峰とみなされていない山の中に、とんでもないのがひとつあります。ジャンダルム(3163m)です。私の技術ではとても無理。だから、ジャンダルムも含めての3000メートル峰完登は、できそうにありません。それにしても、こうやって3000メートル峰のリストを見ると、実に富士山だけが飛び抜けて標高が高く、2位以下がどんぐりの背比べであることがよく分かります。特に2位の北岳から5位の槍ヶ岳までは、13メートル差に4つの山がひしめいている※。そう考えると、富士山というのは日本の中で、ある種異様な山であることが分かります。※2位の北岳は、数年前測量をやり直すまでは、標高3192mとされていました。3位の奥穂高岳とは、たった2mの差だったのです。奥穂高岳の山頂には、超巨大で立派なケルンがあります。これは、高さ2メートル以上の立派なケルンを作って、奥穂高を日本第2位の山にしよう、という魂胆があったのだと聞いたことがあります。が、その努力は無まったく駄に終わりました。なぜなら、山の高さは人工建築物は除外して決めるからです。なお、富士山が現在の高さになったのは、地質学的にはきわめて最近のことです。現在の富士山である「新富士」の火山活動が始まったのは今から11000年前。それまでの富士山(古富士)の標高は3000メートルに届くかどうか、という程度で、つまりその頃は富士山もまた、「どんぐりの背比べ」の中の1峰に過ぎなかったわけです。11000年前というのは、丁度最終氷期が終わった直後の時期に当たります。それ以前の古富士山は、今より低いとはいえ3000m前後の標高なので、それなりに高山植物が分布していたでしょうが、氷期が終わった後の激しい噴火によって、山頂付近の植生は完全に破壊され、独立峰であるために近隣の山から高山植物が分布を広げてくることもなかったため、現在のように高山植物の貧弱な山になったのだと思われます。一説によると、最終氷期(今から約2万年前)の日本最高峰は現在第4位の南アルプスの間ノ岳だったといわれています。間ノ岳の山頂部に大きな山体崩壊の痕跡が見られるからです。この崩壊が起こる前は、今より数十メートル程度標高が高かったとすると、奥穂高より北岳より高い計算になるし、その頃の富士山は3000メートルあるかないかの山だったからです。間ノ岳の山頂部にはカール(山岳氷河の痕跡)もあるので、その頃には氷河もあったはずです。それにしても、「動かざること山の如し」なんていいますが、実際は全然そんなことはなくて、山はとてもよく動くものだ、ということがよく分かります。
2012.09.22
コメント(4)
-

山体崩壊と火山泥流
もう半年以上前ですが、富士山が噴火した場合の危険性について、記事を書いたことがあります。富士山は噴火するかそのときの私の結論としては、富士山はいつ噴火しても不思議ではないけれど、噴火による人的な被害はそれほど多くはないだろう(昨年の東日本在震災ほどではない)、ただし、日本の東西を結ぶ大動脈に被害が及ぶ可能性があるので、その場合は、経済的な被害は深刻かもしれない、というものです。ただ、この記事を書いた当時は、ひとつ考慮していなかった条件があります。それが、今日の記事のタイトルである「山体崩壊」です。山体崩壊とは、読んで字のごとく、山そのものが崩れ落ちてしまうことです。噴火だけでなく、地震が原因で起こる場合もあります。噴火を原因とする山体崩壊の起こった典型的な山がこれです。福島県の会津磐梯山です。猪苗代側から見ると、このように整った成層火山の形に見えます。しかし、反対側の裏磐梯から見ると。中腹から下がざっくりと抉り取られていることが分かります。この噴火は今から124年前、1888年に起こり、477名の犠牲者が出たそうです。このとき噴火による土砂崩れが長瀬川を埋め尽くしたことで生まれたのが、桧原湖など裏磐梯の湖沼群。富士山の場合も、噴火そのものはともかく、それによって山体崩壊が起こってしまうと、これは相当の被害が出る可能性があります。しかも、最近の調査で富士山の直下に活断層があると考えられるようになっています。地震でこの活断層が動けば、仮に噴火がなくても山体崩壊が起こる可能性がある。現在、火山の噴火はおおむね事前に予知できますが、地震はなかなか予知できないのは周知のとおりです。世界的に見ると、地震を原因とする山体崩壊としては、ペルー・アンデスのワスカラン(6768m、ペルーの最高峰)の例が有名です。1970年のアンカシュ地震で、ワスカラン北峰が氷河もろとも崩壊、50kmも離れた麓のユンガイの町は、当時の人口約18000人のうち、生存者がわずか300人(Wikipediaスペイン語版による。英語版によると、生存者92名)という大惨事になりました。もうひとつ可能性があるのは、積雪期に噴火した場合、雪が解けて泥流となって谷を流れ下る危険です。火山泥流(ラハール)と呼ばれます。1985年、コロンビア・アンデスのネバド・デル・ルイス火山が噴火した際は、山頂付近の氷河が溶けて麓まで一気に流れ下り、23000人の犠牲者が出ました。この火山泥流は、100km近い距離を流れ下っています。(アルメロは約40kmの位置)富士山には氷河はありませんが、11月から6月までは積雪があります。太平洋側に位置する山なので、積雪量は日本海よりの高山に比べればそう多くはありませんが、それでも4月頃にはだいたい2メートルくらいにはなります。これが噴火によって一気に解けて泥流となった場合、大変な被害が想像されます。むしろ、溶岩などは流れ下ってきたとしても速度は遅いので、逃げる時間の余裕があります。火砕流や火災サージは、猛スピードだし、高温なのできわめて危険ですが、富士山の場合は、ハザードマップから判断する限り、人口密集地にまで火砕流が届く可能性は低そうです。一方、火山泥流や、山体崩壊による岩雪崩は、時速100kmを超えるような猛スピードで、かつ御殿場市や富士市の人口密集地に迫る可能性があります。それらのことを考え合わせると、富士山の噴火(宝永噴火や貞観噴火クラスの規模)による人的被害を「たいしたことはない」と書いた先の記事は訂正の必要があるかもしれません。富士山のハザードマップ
2012.09.21
コメント(0)
-
お互いにこんなことをやり合っていても、何も解決しない
中華料理店へ投石相次ぐ…中国系企業入居ビルも18日深夜から19日朝にかけ、福岡県志免町や福岡市博多区で、中華料理店や中国系企業が入るビルに石が投げ込まれ、ガラスを割られる被害が4件相次いだ。県警は、反日デモに不満を抱いた犯行の可能性があるとみて、器物損壊容疑で捜査している。県警によると、18日深夜、志免町で1軒と博多区で2軒の計3軒の中華料理店で窓ガラスが割られた。さらに、19日朝、中国系企業が入る博多区博多駅前3の雑居ビル1階の玄関ガラスが割られているのが見つかった。志免町では、犯行直後に現場から逃げる数人が目撃されていた。県警は一晩のうちに被害が相次いだことなどから、同一グループによる犯行の可能性もあるとみている。県内では17日、在福岡中国総領事館に火の付いた発炎筒2本が投げ込まれる事件が発生。県警が政治団体構成員の男を威力業務妨害容疑で逮捕した。---「中国に抗議」なぜかロシア大使館前で放火 容疑者逮捕東京都港区のロシア大使館前で軽乗用車を炎上させたとして、警視庁は17日、自称自営業容疑者を建造物等以外放火容疑で現行犯逮捕した。「尖閣問題での最近の中国の対応に抗議するためにやった」と供述しているが、なぜロシア大使館前で火を付けたのかについては話していないという。麻布署によると、容疑者は17日午前9時10分ごろ、港区麻布台2丁目のロシア大使館前の路上で、自分が乗ってきた軽乗用車に花火を投げ入れて車を炎上させた疑いがある。車内には灯油のような液体が入ったポリタンクがあったという。 ---神戸の中華学校で放火か 校門付近で炎、警察警戒中19日午前2時40分ごろ、神戸市中央区中山手通6丁目の神戸中華同文学校の校門付近で、鉄製門扉の下から炎が上がっているのを警戒中の兵庫県警生田署員が見つけた。火はすぐに消え、けが人はなかった。発見当時、灯油のようなにおいがしたといい、放火の可能性があるとみて調べている。同校は中国や台湾の華僑の子らが通う各種学校。署によると門扉は約2メートル四方の扉2枚の観音開きで、中央下側から炎があがっていた。学校は当時、無人だった。同校は1899年に「神戸華僑同文学校」として創立。小学部6年、中学部3年の一貫教育校で、日本人を含む約700人が通う。尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した2010年9月にも、「生徒にけがをさせるぞ」などと書いた脅迫文が送られ、「報復するぞ」との脅迫電話がかけられた。同校によると、今年に入ってから被害や嫌がらせはなかったという。県警は、香港の活動家らが尖閣諸島に上陸した今年8月以降、パトロールの回数を増やして警戒していた。 ---中国での反日暴動も酷いものですが、向こうを張って、日本で同レベルのことをやっている連中もまた、酷いものです。何度も書くように、尖閣諸島は日本の領土であると私も確信していますが、それはそれとして、中国人に対してこのような迫害行為を行うと、何か事態が解決したり好転したりするのでしょうか。もちろん、これは、まったく同様のことが日系企業などに対する略奪暴行に走った中国人についてもいえます。しかも、中国側は、駐日大使が「事態悪化の責任は中国側にはない」とまで言ってしまった。その伝で言えば、一連の日本側の排外活動だって、「自体悪化の責任は日本にはない」といえるでしょう。だけど、売り言葉に買い言葉、やられたらやり返せとばかりにこういう行為がエスカレートしていけば、最後には戦争になってしまいます。日中が戦争になれば、中国の「愛国青年」たちや、日本の石原慎太郎みたいな手合い、ネットウヨク連中は、自尊心を満たされて大喜びかもしれません。しかし、その代償はとても大きい。すでに中国側では、日系企業で働いていた多くの中国人が、失業の危機にあります。日本側も、やがて似たようなことになる。それでもいいのだと、何があろうと徹底的に中国と(日本と)ことを構えるべきであると、日中双方とも国民の大多数が思っているなら、もう解決の手段はない。行き着きところまで行き着くしかありません。でも、多分そうではないはずです。ネット上で威勢のいい強硬派が、実際には世論の多数派ではありません。(中国でも同様)であれば、国中がこういう排外主義に引きずられるようなことだけはねなんとしても避けなければなりません。
2012.09.19
コメント(2)
-
領土問題は難しい
日本が抱える領土問題は、尖閣諸島、竹島、北方領土の3つです。このうち、尖閣諸島は日本が実効支配しており、それに対して中国が反発しています。一方、竹島は韓国が、北方領土はロシアが実効支配しており、それに対して日本が反発しています。つまり、尖閣諸島問題と竹島/北方領土問題では、状況がちょうど正反対になっているわけです。3つの領土問題のうち、竹島に関しては、私はちゃんと調べていない(調べる気力がわかない)ので、よく分かりません。日本に返還される可能性は皆無であるという現実だけははっきり分かっていますが。尖閣諸島に関しては、たびたび書いているように、これは日本の領土であり、中国側の言い分は間違っていると私は思います。→「固有の領土なんてものはない」しかし、逆に北方領土に関しては、日本側の主張には説得力がありません。→「不法占拠ではない」分かりやすく整理すると、いわゆる北方四島のうち、歯舞と色丹は本来日本の領土だから返還要求する権利がある。しかし、国後と択捉は、明らかにサンフランシスコ平和条約で「すべての権利、権原及び請求権を放棄」した千島列島の一部であり、日本政府自身も、いったんはそのように認めていたにも関わらず、後になって前言を翻して「国後択捉は放棄していない」という詭弁を述べているだけなのです。でも、ほとんどの日本人は、日本政府の公式見解にしたがって、ロシア(旧ソ連)が北方領土を不法占拠していると思っている。やはり、各国とも、対立する問題に関しては「自国はすべて正しい、相手国の言い分はすべて間違っている」と言うのですが、実際には自国のほうが間違っている、ということもままあるのです。これは、中国も日本も、おそらくロシアも同じことです。ところで、竹島に韓国の大統領が上陸した際には、日本は国際司法裁判所に提訴という挙に出ました。国際司法裁判所は、あくまでも相手国の同意があってはじめて審理がなされるので、韓国が同意しない以上審理はされません。一方、尖閣諸島問題に関しては、日本側は「尖閣諸島に領土問題はない」と言っています。これは、言い換えれば「国際司法裁判所に審理を委ねるつもりなどない」という意味です。ある意味では当たり前なのです。領土紛争において、実効支配をしている側は、国際司法裁判所の審理に委ねて得になることなどないからです。実効支配が認められれば損得なし、いささかでも相手国よりの審判が出れば、損にしかなりません。逆に、実効支配していない側は、どういう審判が出ても失うものがありません。したがって、韓国が竹島に関して、日本が尖閣諸島に関して国際司法裁判所への提訴を拒否するのは、損得勘定の上で当然の話です。が、日本政府は竹島について国際司法裁判所に提訴してしまいました。さて、もし中国側に国際司法裁判所への提訴を求められたら、日本側はどうするつもりでしょう。(現実に、中国がそのような策をとるかどうかは分かりませんが)竹島について国際司法裁判所に提訴してしまったばかりです。竹島は提訴する、でも尖閣諸島の提訴は認めない、というのは、あまりに露骨なダブルスタンダードですから、応じざるを得なくなる可能性が高まるような気がします。(私自身は、国際司法裁判所の審判に委ねてもいいのかな、という気はしていますが)竹島について国際司法裁判所に提訴した日本政府、そしてそれを支持したネット上の「愛国者」たちは、そこまで計算に入れて行動した(賛同した)のでしょうかね。
2012.09.18
コメント(2)
-
自分で自分の首を絞める行為
私が富士山に登っていた間に、日中関係は緊迫の度を増し、中国では反日デモが頻発し、それが暴動化して手が付けられない状況になっているようです。暴徒乱入、無言で破壊・放火…工場再起不能「まるで強盗団だった」山東省青島で15日、日系のスーパーや工場を襲ったデモ隊を目撃した中国人男性は、こう声を震わせた。襲撃されたパナソニックグループなどの工場は、一夜明けた16日、放火ですすけた建物や、壊された機械類が無残な姿をさらしていた。複数の目撃者らによると、15日午前11時ごろ、デモ隊は、郊外にあるジャスコ黄島店内で破壊、略奪を開始。1時間後、リーダー格の男が「次は保税区だ」と叫んだ。外資系の工場が集まる保税区には、パナソニックグループの電子部品工場など日系企業が入居している。ジャスコを出たデモ隊はまず2キロ先の日系工場を襲撃した後、午後2時頃、さらに2キロ先のパナソニック工場に到着。3、4階建ての建物数棟が立ち並ぶ工場は、スタッフ全員が避難し、無人だった。群衆は最も大きな建物に乱入、1階に火を放ち、機械類も壊した。火は2階に燃え広がった。隣の工場労働者は「3万人はいた。これだけの人間が道路を埋め尽くす光景は初めてで、とても抗議運動とは思えなかった」と振り返った。日系企業を狙うデモ隊はさらに、約300メートル先の自動車部品工場を襲撃。警官隊が六、七重の隊列を敷いて侵入を食い止めようとしたが、人数ではるかに上回るデモ隊はやすやすと突破。工員ら数百人には目もくれず、無言で破壊、放火に及び、十数分後には別の工場へ向かった。自動車部品工場管理職の中国人男性は「うちは再起不能。ほかの工場も含めて、これで数万人の失業者が生まれるが、中国人がやったことだ」とやりきれない表情だった。---記事にもありますが、「日系企業」と言ったって、そこで働いている日本人は幹部だけで、大半の従業員は現地の中国人です。つまり、「反日」の名目で実際は中国人自身の首を絞める行為を行っているわけです。反日デモ:「たたき壊すのが愛国なのか」…山東省青島市青島イオンは、地元学生への奨学金支給や緑化事業などの社会貢献でも知られる。「中国共産党のためでも日本政府のためでもなく、現地の人に喜ばれる企業になれればと地道に事業に取り組んできた。ただ反日と叫んでたたき壊す行為が愛国なのか。間違っている」。折口社長は声を荒らげた。(以下略)---「たたき壊す行為が愛国なのか」まったくそのとおりとしか言いようがありません。<駐日中国大使>尖閣事態悪化、日本を批判中国の程永華駐日大使は16日、毎日新聞の書面インタビューに答え、日本の尖閣諸島(中国名・釣魚島)国有化に抗議する反日デモが拡大していることについて、「日本政府の違法な島購入は、中国人民の憤りを引き起こしている。事態を放っておけば、両国の各分野の交流、協力がさらに大きな打撃を受ける」と日本政府の対応を厳しく批判した。その上で、領有権問題を「棚上げ」した過去の日中の合意に立ち返り、「領土紛争を交渉で解決する軌道に戻る」ことの必要性を訴えた。尖閣国有化について、大使は「両国民の利益に合致せず、事態悪化の責任は中国側にはない」と指摘。尖閣問題は「中国の領土主権に関わるだけでなく、歴史問題に関わり、非常に敏感」との認識を示した。(以下略)---確かに、一連の騒動のきっかけが尖閣諸島の買収問題だったことは歴然たる事実です。しかし、いくらなんでも、だから日本に責任があるということにはなりません。「中国人民の憤りを引き起こしている」というのが事実としても(何度も書くように、私は尖閣諸島は当然日本の領土であると思っていますが、仮にその点を措いたとしても)、だからこのような暴動が許されてよい、ということにはなりません。憤りがあれば何をやっても許される、と受け取られかねないような発言を、仮にも大使ともあろう立場の人間がする、というのはあまりに常軌を逸しています。これでは、石原慎太郎や在特会と同レベルといわざるを得ない。もうひとつ気になるニュース超党派国会議員団の訪中、中国側が延期申し入れ日中国交正常化40周年の記念行事に出席するため、超党派の国会議員ら約30人が26日から予定していた北京訪問が延期されることになった。中国側が、日本政府による尖閣諸島(沖縄県石垣市)の国有化を理由に延期を申し入れた。訪中団団長を務める野中広務元官房長官が12日、明らかにした。野中氏によると、同日午前、招待していた中国共産党側から、「こういう状況なので見送りにさせてほしい」と連絡があったという。訪中団には、野中氏のほか、民主党の仙谷由人政調会長代行、自民党の古賀誠元幹事長、太田昭宏前公明党代表らが参加。26~28日の日程で訪中し、記念行事などに出席する予定だった。---野中広務は、以前「南京事件71周年 12・13集会」で講演したときのことを記事に書いたことがあります。彼を含めて、ここに名の挙がっている政治家それぞれの政策や主張に対しては、必ずしも前面賛同ではありませんが(というか、私は公明党は嫌いだし、仙谷由人も好きじゃない)、それにしても中国との友好関係をある程度は重視している議員の訪中団を、中国側から拒否したわけです。ということは、日中友好を願う立場の人間すら、日本人という属性によって拒否するということになるわけです。これでは、対話もなにも成立しません。正直なところ、日中友好を願ってきた人間の一人として、今の状況はあまりに絶望的です。中国側にも日本側にも、好んで事を荒立てたい連中がいる。事を荒立てて相手を叩くことが「愛国」「国の誇り」だと思っている人たちの言動ばかりが派手で、国全体がそれに振り回されてしまっている状態に対して、それを食い止めようとする力は、あまりにも無力です。が、それでも私は言いたい。そうやって日中が互いに対立を深めて、得られるものはいったいなんなのでしょうか。底の浅い自尊心を満たす代償として、失うものがあまりに多いとしか私には思えません。
2012.09.17
コメント(4)
-

日本最高峰、3776m
実は、昨日今日と1泊2日で富士山に登ってきました。かれこれ20年くらい山登りをしていて、富士山だけは食指が動かず、これまで登ったことはありませんでした。なぜかというと、私は、高山植物の豊富な山が好きなのに富士山には高山植物が乏しいからです。それなのに、今になって富士山に登る気になったのかはなぜかというと、遠くない将来に噴火があるかもしれないからです。本当にそうなるかどうかは神のみぞ知る、ですが、決して低い確率ではないと思われます。そうなると、噴火の規模次第で、山の形や標高が今とは変わってしまうかもしれません。ならば、富士山が今の形を保っている間に、一度は登っておこうか、という気になりました。富士山には登山口が4つあります。富士吉田口(河口湖口)・須走口・御殿場口・富士宮口です。いろいろな条件から考えて、私は須走口から登って富士吉田口に下りることにしました。なぜ須走口かというと、この登山道は樹林帯の登りが長く続く(つまり、比較的植生が豊富)からです。須走口のバスの出発地は小田急線の新松田駅なんですね。富士山に登るのに、小田急線で出かけることになるとは、予想していませんでした。須走登山口は標高2000m、亜高山帯針葉樹林のど真ん中あたりに位置します。確かに深い森の中で、なかなか雰囲気のいいところです。そして、9月にもかかわらず、まだ点々と花が咲いていました。一番目に付いたのが、これです。トリカブトです。名前は、誰もが聞いたことがあるでしょう。こんなきれいな花が咲きますが、猛毒であることは周知のとおりです。歩き始めたときはどんより曇り、一時は雨までぱらついて、最悪の天気と思っていたら、そのうちに雨も上がり、雲が多いながらも日差しも出てきました。ただ、富士山のふもとには陸上自衛隊の東富士演習場があるんですね。土曜日だというのに、ここで砲撃訓練をやっていて、ずっと発砲音がするのです。樹林帯で雨がぱらついていたときは、一瞬雷かと思いましたが、音が違うので、すぐ自衛隊の演習と気が付きました。機関銃の連射音まで聞こえてきた。山登りに行って発砲音を聞くのは、正直あまりいい気持ちのするものではありません。止めろ、と言えるような筋合ではないけれど。森林限界を超えた7合目あたりです。ここまでくると、目に付く植物はほとんどオンタデばっかり。で、午後3時半頃、この日の宿泊地である本八合目(海抜3370m)に到着。須走登山口からの標高差は1370m、11時半頃出発したので、所要約4時間、1時間あたり390m。荷物が比較的軽いことを考えると、まあまあのペースかな。山小屋の前から。湖は山中湖ですね。まさしく絶景です。「当機はただいま高度3370mを飛行中です」って感じ。この景色だけでも、登ってきた甲斐があるってものです。イワヒバリ。日本の高山帯に生息する鳥としてポピュラーなのは、イワヒバリとカヤクグリ、それにライチョウの3種です。このうち、ライチョウは富士山には生息しませんが、イワヒバリとカヤクグリは富士山にもいます。(当初「カヤクグリ」としましたが、改めて写真を検討すると、イワヒバリのようなので訂正します。)宿泊した山小屋の名前は書きません。富士山の山小屋の一般的状況は知っていたので(それも、今まで富士山に食指の動かなかった理由のひとつ、かな)、こんなものだろうと予想していたとおりです。それ以上でも、それ以下でもなかった。日帰りも検討したけど、5合目で前泊するならともかく、東京を朝出ての日帰りはちょっと難しい。山小屋が不満ならテント泊にしたいところですが、富士山は幕営禁止なのでそれができないのが残念です。基本的には宿泊料金が高すぎ食事のボリュームがなさ過ぎトイレ1回200円は高すぎですね。いずれも、下界の一般的な宿泊施設との対比ではなく、南北アルプスや八ヶ岳など他の山域の山小屋との対比での話です。これらの山域の山小屋はヘリで荷揚げしているのに、富士山は山頂までブルドーザーで荷揚げしていますから、ヘリを使うよりは経費が安く上がるはずなんですよね。ついでに、宿泊者が非常に多かったので、布団1枚に2人のすし詰め状態でした。ただし、これについては他の山域の山小屋も同様なので、やむをえないところです。もっとも、わざわざすし詰めとわかっている山小屋に泊まるなら、テント泊にさせてくれと言いたいところですが。ただ、従業員の応対などは決して悪くありませんでした。二日目、つまり今日は、最初の予定では山小屋の前でご来光を見て、それから山頂を目指そうと思っていました。ところが、大半の宿泊者が、山頂でご来光を見ようと、朝3時前から出発準備をはじめるのです。周りが騒々しすぎて、寝てらんない。私も予定を変更して、頂上でご来光を見ることにしました。3時40分頃、真っ暗な中をヘッドランプを頼りに山小屋を出発。小屋の玄関の温度計は、摂氏4度でした。山頂まで続くヘッドランプの行列がすごい。私一人がヘッドランプを消しても、充分明るいんじゃないかって思ってしまいました。実際には、ヘッドランプを消しはしませんでしたが。しかし、あの暗闇の中、ヘッドランプの明かりだけを頼りに、何千人もの人が山頂を目指して、よく転倒して怪我する人が出ないものです。いや、けが人は時々出るんだろうなあ。行列が時々渋滞するので、待ち時間もそれなりにありました。本8合目から山頂までの標高差は400メートルくらいなので、前日の私のペースから言えば1時間程度のはずですが、実際は1時間半かかってしまいました。おかげで、体力的には余裕がありました。山頂です。久須志神社の鳥居。ここでちょうど夜明け。5時10分前後だったでしょうか。東の空に雲があるので、太陽が出ているのかいないのかよく分かりませんが、一応ご来光。ここで、ひとつ発見がありました。山頂にはテントが何張かあったのです。そうか!9月に入ると山頂の山小屋や売店はみんな閉まるので、監視の目はなくなるのです。つまり、今の時期は山頂なら幕営可能なんだ。登っている間は感じませんでしたが、山頂に着くとやはり風は強い。高さと早朝という時間帯を考えれば、当然の話ですが。風の強さ自体は予想の範囲内でしたが、予想を超えていたのは、風にあおられて砂が巻き上げられること。私は出発から山頂まで飲まず食わずで、山頂で朝食を食べたのですが、顔もても、ザックの中も、口の中も、あっという間に砂まみれでした。ところで、富士山の「山頂」は火口の外輪山すべてを指すことになっているのだそうです。つまり、外輪山に到達すれば、最高峰である3776mの剣が峰まで行かなくても、「富士山の山頂まで登った」ということになるそうです。が、私個人としては、剣が峰に登らずして「山頂まで行った」というのは、いささか抵抗があるので、そのまま剣が峰を目指すことにしました。駿河湾と、その向こうは伊豆半島だと思います。前日の山小屋の前からの景色もすばらしかったけど、夜明け直後の山頂からの景色は、神々しさも感じます。目指す剣が峰です。2004年に閉鎖された気象庁の富士山測候所があります。山頂火口です。深さが200mくらいあります。この噴火口が再び火を噴くことが、あるんでしょうか。(前回1707年の宝永噴火は、この山頂火口ではなく、中腹の宝永山からの噴火でした)剣が峰に着きました。ここも、記念写真を撮ろうとすごい人の列でした。影富士。やっぱり、頂上でご来光を見るという選択肢を選んで正解でした。影富士は、夜明け直後でないと見えないですから。結局、外輪山を1周(お鉢めぐり)して、7時過ぎに下山を始めました。8合目付近から山頂方向を振り返って見ました。植物がまったくない。このあたりから下は、オンタデなど多少の高山植物があるのですが、山頂から8合目あたりまでは、まるで月の山か火星の山か、というくらいに植物がありません。で、この後はひたすら下り下り下り。富士山の主要な登山道は、登りと下りが分離されているので、登ってくる人とすれ違うことはありません。砂礫の下山道を下っていくと、砂埃が舞い上がります。山頂ですでに砂まみれでしたが、更に顔、手、口の中が砂まみれに。9時半過ぎには富士吉田口の五合目に着きました。朝からずっと快晴だったのに、五合目に着いたら、あっという間にガスが広がってきて、どんより曇りに。これだから山の天気は分かりません。でも、かなり幸運でした。バスを待つ間、お中道の遊歩道を少し歩きました。富士山の山頂に行ったのは初めてですが、五合目は以前にも来たことがあり、この御中道は歩いたことがあります。高校生の頃だから、30年高く前の話。で、足元にコケモモの実がなっていたので、撮影しました。食べてもおいしい実(ブルーペリーの親戚筋ですから)ですが、まだ熟しきっていないので、きっとすっぱいに違いないし、そもそも国立公園内で実を取ってしまうわけにもいきません。「富士に一度も登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿」という言葉がありますが、分からなくもありません。でも、今回登った須走口から7合目あたりまでなら、植生も豊富だし、また来てもいいかな。それに、いつかは雪の時期に登ってみたいものです。ただし、私の雪山能力では厳冬期はとても登れないので、ゴールデンウィークあたりね。それも、山頂までは無理かな。そうそう、外国人登山者がかなり多かったです。南北アルプスや八ヶ岳でも外国人登山者はいますけど、富士山は群を抜いて多い印象です。やはり日本を象徴する山と、国際的にも思われているということなんでしょうか。欧米系の人が多かったですが、韓国人(多分)もいました。話している言語は英語が圧倒的、ついでフランス語も多かったですね。
2012.09.16
コメント(4)
-

グルーポ・ノルテ・ポトシ
グルーポ・ノルテ・ポトシの初来日公演に行ってきました。過去に来日したフォルクローレ・グループはたくさんありますが、その中でもおそらくもっともディープな演奏を見せるグループだと思います。何しろ、ボリビアのポトシ北部の音楽だけを演奏するグループですから。フォルクローレに興味のない人が見たら、「ポトシ北部?何それ?」って感じでしょうけど、これがまた好きな人にとってはたまらないのです。ポトシという町の名前自体は、世界史に詳しい方なら聞いたことがあるかもしれません。かつて銀鉱山で栄え、莫大な量の銀をヨーロッパにもたらした街です。銀は植民地時代の間に枯渇してしまいましたが、その後錫によってもう一度この街は栄えます。この地域は、アンデスの弦楽器「チャランゴ」の発祥の地と目されています。現在のチャランゴはナイロン弦を張っていますが、もともとは、スチール弦が使われていました。鉱山の町が発祥の地だったからかもしれません。そして、現在でもこの地域にはチャランゴの祖先筋に当たる楽器がたくさん残っています。今回来日したグルーポ・ノルテ・ポトシ(日本語に訳せば「北ポトシ・グループ」という、何のひねりもない名前です)は、この地域のフォルクローレを演奏するグループとしては、代表格と言ってもいいでしょう。実は、1994年にボリビアのラパスで、コンサートを見たことがあるのです。あれから18年経って、まさか日本で見ることができるとは、思いもよりませんでした。それも、直前まで行けるかどうか分からなかったので、前売り券を買っていなかったのですが、会場の労音大久保会館(R’sアートコート)に着いて「当日券を」と言ったら、何と「最後の1枚です」と。ひぇー、危ないところだったけど、ラッキーだったかも。あまり広くない会場ですから、満員になってしまったようです。演奏は、すばらしかったです。北ポトシの演奏(歌は特に)は、癖が強いので、好みは分かれるのですが、このグループの演奏は、それほど癖は強くない・・・・と、思います。それにしても、来日コンサートの日程を見ると東京/R's アートコート(新宿区大久保1-9-10)9月14日(金)18:30開場 19:00開演9月15日(土)13:30開場 14:00開演福島/福島市音楽堂大ホール(福島市入江町1-1)9月16日(日)栃木/足利市民プラザ 小ホール(足利市朝倉町264)9月17日(月・祝)17:30開場 18:00開演北海道/富良野演劇工場(富良野市中御料)9月22日(土)13:00開場 13:30開演コンサートの場所も、なかなかディープだなという気がします。彼らの音楽の故郷であるポトシの街です。実際にはこの街から少し北に行ったリャリャグアというところが、彼らの本当の故郷ですが、さすがにそこまでは私は行ったことがありません。写真右の山は「セロ・リコ」日本語にすれば「宝の山」と呼ばれ、その上のほうにパイラビリ鉱山という鉱山があります。海抜4400メートル。私は、ラパスから夜行バスでこの街について、その足で鉱山見学ツアーに参加したら、そのあと猛烈な高山病になりました。ボリビアには3回行きましたが、あんなひどい高山病はそのときしか経験がありません。その後5400mのチャカルタヤ山に登ったときも、高山病にならなかったのに。狭い鉱山を、腰をかがめながら(そうしないと頭がつかえるので)2時間くらい登ったり降りたりしたせいなのだと思います。その高山病の時の頭痛は強烈でした。もともとあんまり頭痛と縁のない人間なので、生まれてこの方、あんなすさまじい頭痛は経験したことがなかった。あれより痛い頭痛は、もう脳内出血くらいなんだろうなあと思います。幸いにして、ホテルでぶっ倒れて一晩(というか、午後3時頃から翌朝8時頃まで)寝込んでいたら治りましたけど。夜中まで、何度も痛みのせいで目が覚めたというのに、朝になったらすっかり痛みがなくなっていたのが不思議です。それで、「治った治った」と、その日一日ポトシの街(街自体も4000mくらいあって、しかも坂だらけ)を歩き回って、その夜の夜行バスでラパスに戻ったのです。病み上がりの人間のスケジュールとしてはかなり無謀でしたが、何事もなかったのは、やはり若かったからでしょうか。---話はまったく変わりますが、労音大久保会館は、新大久保からコリアタウンの少し先にあります。日韓関係の緊迫化で、このあたりのお客さんも急減、というような話もありましたが、人通りもお客のいりもかなり多いように見受けられました。このあたりを通るのは10年ぶりくらいなので、直前との比較でどうなのかは分かりませんけれどね。
2012.09.14
コメント(2)
-

続・堤防について考える
一昨日の記事で、田老の防潮堤について書きました。話は変わって、東海地震の想定震源域のなかに建設されている浜岡原発は、危険性が高いということで、現在防潮堤の建設工事が進められています。その高さは18メートルと報じられています。普代村で津波を防ぎきった15.5メートルの防潮堤より更に高いから、これで安全とは、必ずしもいえません。浜岡での想定津波波高は最大19メートルとされています。建設中の防潮堤より高いのです。しかも、津波は陸上に上がると最大波高以上まで遡上します。たとえば、東日本大震災では、40メートル以上の最大遡上高を記録しています。それらの条件を考えると、想定される最大規模の津波が押し寄せた場合、高さ19メートルの防潮堤を超える可能性がかなり高いと思われます。その場合、防潮堤はどうなるでしょうか。建設中の防潮堤は「地中に埋めた鉄筋コンクリート製の基礎構造物の上に、鋼鉄製たて壁(縦12メートル、横12メートル)を設置し、海面からの高さを18メートルにする」という構造だそうです。(共同通信のサイトより)写真で見ると、田老の新防潮堤よりもっと幅が薄いように見えます。田老の旧防潮堤は(津波には乗り越えられたけれど)破壊されなかったのに対して、新防潮堤は木っ端微塵に破壊された、ということは前回記事に書きました。その新防潮堤より厚みの薄いこの防潮堤が、巨大津波に対してどれだけの抵抗力を発揮するのか、かなり心もとない気がします。しかも、土台は砂丘の軟弱地盤です。この防潮堤が津波の力に耐えられなかった場合、背後の原発は、津波の水だけでなく、押し流されてきた防潮堤の残骸の激突をも受け止めることになるのです。田老の新旧の防潮堤に挟まれた地域では、コンクリート製の建物であっても、ほとんど破壊を免れることができなかったことも、先の記事に書いたとおりです。田老の巨大防潮堤は、津波を食い止めることはできなかったけれど、それでも津波の侵入を約6分間程度遅らせることができたそうです。だから、避難者の時間稼ぎの役には立ちました。しかし残念ながら原発には足が生えていないので、防潮堤が多少の時間稼ぎをしても、何がどうなりようもありません。そこで働く従業員の避難の時間稼ぎには役立つでしょうが。こうしてみると、やはりどう考えても「防潮堤を作るから浜岡原発は安全だ」とは言えないことが分かります。それでもないよりはマシではあります。想定より津波の規模が小さければ、防潮堤で津波を防ぐこともできるでしょうから。しかし、想定される最大規模の津波が来た場合は、この防潮堤で被害を防ぐことはできないと考えるべきだと思います。
2012.09.13
コメント(0)
-
堤防について考えてみた
福島原発事故の政府事故調査委員会の委員長になった畑村洋太郎の「未曾有と想定外-東日本大震災に学ぶ-」(講談社現代新書)を読んでみました。ちょっと首を傾げるような部分もあるのですが、なるほとほ、と思う部分もありました。それは、宮古市田老(旧田老町)の巨大防潮堤についての話です。三陸海岸の津波対策の象徴とも言える田老の巨大防潮堤は、1960年チリ地震の津波を完全に防ぎ、被害を出さなかったことから一躍有名になりましたが、それから52年後、去年の震災の巨大津波を防ぐことはできず、防潮堤は木っ端微塵に破壊されてしまった・・・・・・と、思っていたのですが、詳細に見ると、全部が木っ端微塵に吹き飛ばされたわけではなかったのだそうです。実は、田老の防潮堤は、ごく大雑把に言うと、上から見てX字型の配置になっていたそうです。最初に建設されたのは、内陸側で、中央部が海に向かって突き出し、両脇がおくに引っ込んでいる形(市街地>海)に建設されました。盛り土の外側をコンクリートで固めたもので、工事は1938年から1958年まで行われたそうです。したがって、チリ地震で名をはせたのは、この旧防潮堤だった、というわけです。その後、この旧防潮堤の外側に、1962年から新しい防潮堤が建設されました。新防潮堤は、旧防潮堤の外側に、旧防潮堤とは逆に中央部が市街地に向かって引っ込み、両端が海に向かって突き出している形(市街地<海)に建設されました。こちらは、全部コンクリートで建設されたそうです。そのため、盛り土の旧防潮堤は厚みがあるのに対して、全部がコンクリートの新防潮堤は厚みがない。旧防潮堤>と新防潮堤<の中央部は接合していたので、全体としてみると、X字型になっていたわけです。で、新旧どちらの防潮堤も、今回の津波自体はいずれも防ぐことができず、乗り越えられてしまっています。ただし、木っ端微塵に吹っ飛ばされてしまったのは新防潮堤だけで、旧防潮堤は、津波に乗り越えられはしたけれど、防潮堤自体は壊れなかったそうです。津波で壊れなくても、乗り越えられてしまえば同じ、というわけでは必ずしもないようです。というのは、新防潮堤の内側(旧防潮堤の外側)では、住民に対して死者行方不明者の割合は1割に達したのに対して、旧防潮堤の内側では、死者行方不明者の割合は5%以下だったというのです。理由はいろいろあるでしょう。旧防潮堤の内側の方が高台に近いので逃げやすかった、ということもあるかもしれません。しかし、他に2つの要素があったようです。まず、津波は、水が押し寄せるときも怖いですが、引き波も猛威を発揮するといわれます。しかし、旧防潮堤は壊れなかったので、その内側では、引き波はゆっくりだったそうです。それに対して、その外側は引き波が強烈だったそうです。新防潮堤が木っ端微塵に壊れてたため、引き波を阻むものがなかったからです。そして、もうひとつの要素は、旧防潮堤の内側では、破壊を免れた鉄筋コンクリートの建物が多少はあるのに対して、外側では鉄筋コンクリートであっても、破壊を免れた建物がほとんどない(同書の写真を見ると、ビルがたった一つだけ残っている)ことです。引き波が激烈だったことと、破壊された防潮堤それ自体が凶器となって建物を破壊したからでしょう。鉄筋コンクリートの建物の屋上に避難しても、旧防潮堤の内側では助かっても、外側では助からなかったであろうことは想像が付きます(同書では、そこまでは言っていませんけど)。それに付随して、旧防潮堤の内側では、使者の遺体はほとんど発見されているのに対して、外側では引き波にさらわれて多くが行方不明のままなのだそうです。では、なぜ旧防潮堤は破壊を免れ、新防潮堤は木っ端微塵だったのか。二つの理由が指摘されています。ひとつは、旧防潮堤は盛り土の外側にコンクリートをかぶせた物で、厚みがあった(当時の技術ではそれしか作れなかった)のに対して、新防潮堤は、全部コンクリートの「壁」(厚みが薄く縦長の構造)だったこと。防潮堤では防げないほどの巨大津波を前にすると、旧防潮堤のほうが、壊れにくかったのかもしれません。そしてもうひとつは、旧防潮堤は>型に対して新防潮堤は<型だったという点です。新防潮堤は、津波を真正面から受け止めて、跳ね返そうという建築思想、旧防潮堤は、津波の勢いをすこしでも横に逃がして、かわそうという建築思想です。残念ながら、超巨大津波という自然の猛威に対しては、現在の技術をもってしても、それを真正面から受け止めてはじき返すというのはきわめて困難(※)です。津波の勢いを削ぎ、かわすという建築思想は、津波を完全に食い止めることはできないけれど、結果的に見ればそちらの方が被害をより軽減できる、ということになるようです。※もっとも、岩手県の譜代村は、田老をも上回る超巨大堤防を築いて、あの巨大津波をすら防ぎきりました。ただし、普代村の巨大堤防は、2つの地区でそれぞれ長さが155mと205mだそうです。総延長2400mの田老の防潮堤より、ずっと規模が小さい。予算の制約を考えれば、小規模の防潮堤なら高くできても、大規模な防潮堤では難しいでしょう。もうひとつ、その普代村の防潮堤は高さ15.5mです(田老は10m)。普代村では15.5mの防潮堤で津波を防ぎきることができたけれど、田老では津波の波高はもっと高かったので、おそらく15.5mの防潮堤でも津波を防ぐことはできなかったでしょう。
2012.09.11
コメント(0)
-
相変わらず愛国無罪な人たち
フジテレビ前の日の丸破った疑い=「頑張れ日本! 」会員ら書類送検―警視庁フジテレビが東京都港区の本社前に掲揚していた日本国旗の一部を破ったとして、警視庁公安部は10日、暴力行為処罰法違反容疑で保守系市民団体「頑張れ日本! 全国行動委員会」会員の会社員の男(32)=足立区=ら3人を書類送検した。いずれも「国旗を引っ張ったのは事実だが、破るつもりはなかった」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は昨年9月19日夕、「本社前の国旗が汚れているので交換しろ」との要求にフジテレビが応じないことに腹を立て、旗を無理やり引きずり下ろそうとして一部を破った疑い。団体はその後、代わりに自分たちが持参した新しい旗を掲揚した。当日はフジテレビに対し、韓国ドラマの放映数が多いなどとして、約1200人で抗議デモをしており、終了後も国旗の件で抗議を続け、トラブルになったという。---在特会系ネットウヨクの無軌道暴走ぶりは当ブログでも何回も取り上げて批判していますが、相変わらずですね。日の丸を大事にしろと言っている人間が、日の丸を破ってどうするんですか。その理由が「汚れているから」(別のソースによると「ボロボロだから」)って、なんなんでしょうね。そもそも、他人が掲げている旗を強引に引き摺り下ろして、自分たちの旗に付け替えるって、その行動自体が(たとえ破らなかったとしても、です)すでに常軌を逸している。もう論理も何もあったものではない、ただその場の感情と集団心理に任せて暴走しているだけでしょう。ボロボロだから怪しからん、などという理屈を持ち出すなら、旧日本軍の軍旗なんて、軒並み「怪しからん」のですよ。何しろ、旗の本体はボロボロになって、周囲の房だけが残っている旗ですからね。このときの様子をYouTubeで検索すると、動画がいっぱい出てくるんですが、もうあえてリンクは貼りません。見ていて、ただバカバカしいだけですから。こういう連中が語る、いや騙る愛国心だの日本の誇りだのというのは、底が浅すぎて話になりません。正直言って、「尖閣買取寄付」にお金をつぎ込んだのがこういう連中ばかりだったとしたら、愛国詐欺も「石原慎太郎、でかしたぞ」って言いそうになってしまいますよ。
2012.09.10
コメント(6)
-
容易に想像のつく話(尖閣諸島) 追記あり
石原知事無念、尖閣地権者に「翻弄されたかも」「翻弄されていたのかもしれない」。東京都の石原知事は7日の定例記者会見で、尖閣諸島(沖縄県石垣市)の購入を巡る埼玉県の地権者との交渉を、自嘲交じりに振り返った。石原知事は4月に購入計画を発表してから、一貫して「地権者は都が買うことに同意している」と語っていた。地権者が都を袖にして国と売買契約を結ぶことになり、石原知事はこの日の会見で、「こちらはちゃんと覚書も用意して、話をしようと(地権者に)言うんだけど、だんだんと狂っていった。お互い納得する形で決着したいと考えていたんだけど」と無念さをにじませた。「個人的な友情の話もしたが、地権者の利害損得もあるでしょうから」と、地権者に配慮をみせながらも、「今ひとつ何を考えているか分からないところがあります」とも語った。一方、購入資金として全国から都に寄せられた14億7000万円を超える寄付金の使途については、「もうちょっと時間をもらいたい」と述べ、地元の漁業者のための施設整備に充てたい考えを重ねて強調した。その上で「政府が代わって、あそこにちゃんとしたインフラを造るということになったら、ちゃんと上陸もして、都の責任で調べる」と同諸島の再調査に意欲を見せた。(2012年9月8日08時53分 読売新聞)---尖閣諸島を東京都が買い取るという話については、以前記事を書いたことがあります。そのときに書きましたが、地方自治体である東京都が、都民の生活とはほとんど関係なく、しかも千数百キロもはなれた他県に属する一離島を買い取るというのは常軌を逸した行動です。で、結局のところは国が買い取るという結果に落ち着いたそうで、まあ落ち着くところに落ち着いた、というところでしょう。どう考えたって、東京都が買い取るよりはるかに筋が通っていますから。こうなることは、ある程度は予測ができたことです。先月末に、都が尖閣諸島に上陸申請をした際、国は許可しませんでしたが、その理由は上陸についての地権者の同意書がなかったためだと報じられています。都の尖閣上陸不許可 政府回答文書 外交的配慮は否定藤村修官房長官は二十七日午後の記者会見で、東京都から提出を受けた沖縄県・尖閣諸島の上陸許可申請に対し「尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理のためという賃貸の目的を踏まえ、上陸を認めない」と文書で回答したことを明らかにした。藤村氏は都による尖閣諸島の購入方針に関し「必ずしも見通しが立っているとは認識していない」との見解を示した上で、不許可の理由を「都の上陸の必要性を判断する状況にないことが大きな要素だ」と説明。都の申請に尖閣諸島の地権者の同意書が添えられていなかったことも明かし、不許可と判断した一因になったとした。(以下略)---上陸への同意書を出さないという時点で、都に上陸させる気はなく、従って、おそらく売る気もないのだろうということは想像がつきます。石原側は口頭で同意を得たなどと言っているようですが、公の申請書類で「同意書はありませんが口約束で同意してもらっています」なんて話がとおるわけがないのです。「個人的な友情の話もした」などと石原は記者会見で口走ったそうですが、阿呆かと思いますね。十数億とか二十億という額の売買契約の話が、個人的友情で決められるわけがないでしょう。結局のところ、都の提示した購入価格より国の提示した購入価格の方が高い、ということなのかも知れませんが、かりにそうだったとして、少しでも高い金額で買い取ってくれる方に売る、というのは商取引の基本原則ですから、そのことを非難するいわれはありません。地権者が「今ひとつ何を考えているか分からないところがあります」とも言っているそうですが、このような取引で、最初から手の内を明らかにしないのはごく当たり前の話です。むしろ、最初から手の内をオープンにしてしまっている東京都(石原知事)側が、異常なだけの話です。尖閣諸島を購入する、というよりは「愛国心発露ショー」を演じたいのが本音だった、というところなのでしょうが。そんなんで、取引がまとまるはずもありません。副知事の猪瀬直樹が、ツィッター上で今夜9月7日、尖閣地権者の栗原氏が石原知事に会った際、「国に売ってすみません」と謝った。謝ったではなく誤った、だね。民主政府と栗原氏は許せない。政権が変わったら船だまりをつくればよいが、そうなると自民党総裁選に条件をつけることになる。 などと叫んでいますが、自分たちの失態を棚に上げて、売り主を批判するなど筋違いも甚だしい。いい面の皮は、十四億七千万円も集まったという寄付金の送り主たちです。下駄を履く前に寄付を募ってしまうから、購入できないのに寄付だけが集まってしまうという事態になってしまった。結果的に見れば、石原が尖閣諸島購入に名乗りを上げたこと、買い取り金額が決まる前に募金を集めて、その金額が膨らんだことによって、買い取り価格のつり上げに貢献したと言ってもいいでしょう。しかも、石原はこの寄付金を、最初は「国に渡す」と言ったものの、すぐに前言を翻して「国に渡さない」と言い出しています。こうなると、寄付金集めは詐欺行為とすら見えます。愛国詐欺ですね。言うまでもなく、私は寄付などしていませんし、寄付したのが「愛国者石原様にお金を貢いでうれしい!」というような愛国マゾヒストばかりなら、私が口出しするような問題でもないのでしょうが。以前の記事でも指摘しましたが、新銀行東京は大赤字で経営危機、オリンピック招致は失敗(次はどうか分からないけれど)、銀行への外形標準課税は強行して裁判で敗訴、カジノ構想は法的問題をクリアできずに中止、後楽園での競輪復活も反対が多くて断念、など石原がトップダウンで決めた政策は、軒並み失敗。だから、今回も多分そうなるだろうと思っていたら、案の定でした。細部の検討を行って、実行可能な政策か否かを慎重に見極めて、実行したからには確実に成功させる、という面の能力が、この人にはまったく欠けている、ということなのでしょう。追記読売新聞9月6日付の報道(ネット上にはアップされていないようです)によると、もともと政府は2年前から尖閣諸島買収の交渉をしていたものの、これまで上手くまとまっていなかったようです。これが事実なら、「都が買おうとしたものを政府が横取りした」どころか、実際は正反対で「国が買おうとしていたものを都が横取りしようとした」ということになります。そうだとすると、そもそも話しの最初から、都知事は地権者の価格吊り上げ作戦の片棒を担いだ、ということになります。やっぱり愛国詐欺のにおいがぷんぷんです。
2012.09.09
コメント(2)
-
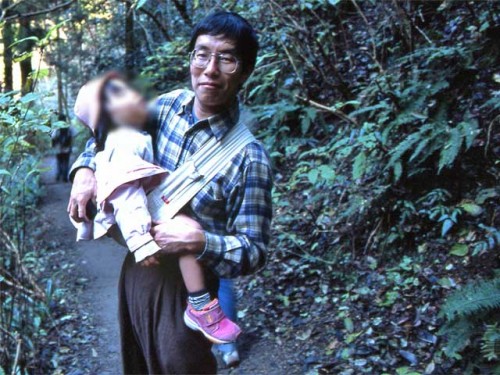
ベビーカー論争
電車ベビーカー論争にギャルモデル「子供優先車を検討して」今年3月、東京都と首都圏の鉄道会社24社が貼り出した1枚のポスターがある。そこにはこんなキャッチコピーが書かれている。〈赤ちゃんを守るのは、みんなの思いやりです。〉このポスターは、“赤ちゃんを育てやすい環境作り”のキャンペーンの一環だったが、都営地下鉄・バスを運行する東京都交通局には批判的な声も寄せられた。「車内でベビーカーに足をぶつけた」「ドア脇を占領されて、手すりが使えなかった」他の鉄道会社や都にも、「ベビーカーをたたもうというポスターを作ってほしい」「ポスターがあるから、厚かましい利用者が出てくる」などの声が寄せられたという。インターネット上では、「母親に注意を促すべき」「いやいや、周囲の人に促すべき」などの意見がいまだ飛び交う。女性セブンの取材にも、こんな意見が。「乗降口側にベビーカーを置き、子供に関心を払わずに携帯をいじっている母親がいた。周囲に気配りなく、邪魔だった」(52才・公務員)「連休の混み合う車内で、両親が子供を抱っこして座り、ベビーカーは荷物を乗せたまま広げていた。混んでいるとき、荷物は膝の上、ベビーカーはたたむべき」(46才・会社員男性)一方、2才の子供を育てている母親(32才・会社員)からはこんな意見も。「ベビーカーで寝てしまった子供を起こしてたたむとなると、ギャン泣きされてかえって迷惑がかかる。病院に連れて行くときなどは混雑している電車に乗らざるをえないこともあります。経済的にもマイカーなんて無理だし、頻繁にタクシーに乗るわけにもいかない。でも、やっぱり舌打ちされたりするとへこみます。個々の事情もあると、理解してほしい」ちなみに、ギャルママモデルでママサークル連合の総代表・日菜あこさん(28才)は、こう話す。「今は、“ママなんだから外出を控えろ”という世の中ではなく、特に小さい子供が複数いたら、ベビーカーなしの移動は考えられません。もちろん、混雑しているときには電車を見送ったり、ラッシュの時間をずらすようにしています。大勢で出かけるときは、別の車両に乗り分けたり。若いと厳しい目で見られるので、かえってみんなちゃんとしている人が多いと思います。でも、子供がぐずったらと冷や冷やします。気を使っているつもりでも、必ずしも周囲の目が温かいとは限りません。子供優先車やベビーカースペースも検討してほしい」---我が家がベビーカーを使っていたのがいつごろまでだったか、正確には覚えていませんが、1歳半くらいまでではなかったかと思います。それまでは、鉄道駅でエレベーターのありがたみなんて、感じたことは一度もありませんでしたが、子どもをベビーカーで連れ歩くようになると、やっぱりエレベーターのありがたみを実感します。それでも私は男だから(そんなに腕力のある方ではないとはいえ)、ベビーカーを抱えて階段を昇降したりエスカレーターに乗ったりもできましたが、女性だと腕力的に困難かもしれませんね。私自身は、ベビーカーを電車に乗せるとき、基本的には畳んではいませんでした。もちろん、遠距離の場合は別ですが。もちろん、私が子どもを連れて出かけるのはほぼ休日に限られるので、ラッシュアワーにベビーカーを電車に乗せたことはありません。確かに、ラッシュアワーにベビーカーを電車に乗せるのは避けるべき、というか、物理的にちょっと難しいでしょう。ドアを塞ぐような形でベビーカーを置くことも、できるだけ避けるべきとは思います。でも「車内でベビーカーに足をぶつけた」「ドア脇を占領されて、手すりが使えなかった」なんてのは、どうなの?と思います。車内でぶつかることがあるのは、何もベビーカーに限った話ではないだろうし、「ドア脇を占領され」たと言っているそのあなたがドア脇に立てば、やっぱり他の人からは「手すりが使えない」ということになるわけで。私も、ベビーカーで電車に乗るときは、極力ドア脇にベビーカーを置くようにしていました。一番乗降客の動線を比較的妨げにくい(他人に迷惑をかけにくい)場所だからです。現在でも、楽器(管楽器ケースとギター)を持って電車に乗るときは、空いていればドア脇に荷物を置くようにしています。ただ、私の場合は、抱っこ紐を使うようになってからは、すぐにベビーカーを使わなくなりました。駅でエレベーターを求めて大回りしたり、ベビーカーを抱えて階段を昇り降りするよりは、子どもをおんぶまたは抱っこする方が、圧倒的に楽だからです。抱っこ紐は、背中に回せば簡単におんぶ紐になります。子どもの体重は、その頃で12~3kgだったのかなあ。テント山行の荷物よりは軽い(体感的には、同じ重さの山の荷物よりは重く感じましたが)し、両手がフリーハンドにできるので、ごく普通に街中を歩くことができます。挙句の果てに、子どもをおんぶしたまま笛の練習2時間とか、一度高尾山に子どもをおんぶして登ったことがあります。4歳目前の頃だったので、体重は17~8kgあったのかな。もう、子どもも8歳(もうじき9歳)なので、今は昔、という感じですけれどね。幸いにして、私の音楽の練習にだけは、今も子どもはついてきてくれます。余談が長くなりましたが、小さい子どもを連れて外出することには、多かれ少なかれ困難が伴うし、周囲への迷惑が皆無というわけにはおそらくいきません。周囲への迷惑が多少なりとも小さくできるような努力は払うべきですが、かといって、「子連れの迷惑は許さない」ということになると、子どもを連れて出かけるな、ということになります。少子高齢化が言われている今、子どもを持つと肩身が狭くなるような環境を作ってどうするんだ、と私は思いますね。もちろん、程度というものがあることは言うまでもなく、どんな迷惑行為も許されると言いたいわけではありませんけど。---話はまったく変わりますが、この記事を書いていて、不意に思い出したのですが、去年の夏は節電でエスカレーターの運転休止が結構ありました。そのことをさして、「節電は弱者にやさしくない」(だから原発を動かせ)という趣旨の発言を、どこかで見たことがあります。どのサイトだったかは忘れてしまいましたが。それを読んだとき、なんだかなーと思った記憶があります。エレベーターは弱者のための移動手段ですが、エスカレーターは弱者のための移動手段ではありません。これは、実際に小さい子どもを連れて外出すれば、体感として即時に理解できることです。私は力任せにエスカレーターにベビーカーを乗せましたけど、自分で言うのもなんですが、これははっきり言って推奨させざる行為です。というか、実は危ない。まして、車椅子をエスカレーターに載せるのは、物理的に無理です。また、よちよち歩きの幼児にとってはエスカレーターの乗降はとても危険です。親がガードしないと転倒の危険性がかなり高い。老人や身体障害者の場合も同様のはずです。つまり、エスカレーターは弱者のための移動手段ではなく、強者が楽をするための移動手段なのです。(ここで言う強者というのは、純然たる肉体的機能の面のみの話です)だから、私の記憶している範囲では、昨夏、駅や商業ビルなどのエスカレーターの運転停止はかなり大規模に見られましたが、エレベーターの運転停止は(皆無ではありませんでしたが)少なかったはずです。そのあたりは、節電にあたってある程度は考慮されていたわけです。はっきり言って、エスカレーターは大半が止まったって構わないと私は思っています。そのくらいは歩け、と。歩けない人に必要なのはエレベーターであって、エスカレーターではない。
2012.09.08
コメント(8)
-
「もんじゅ」は絶対廃炉にしなければならない
「もんじゅ廃炉、とんでもない」 石原知事が視察東京都の石原慎太郎知事は6日、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)を視察した。政府の新エネルギー政策で核燃料サイクル見直しが取りざたされる中、「廃炉はとんでもない話。絶対にしちゃいけない」と述べた。石原知事は、日本原子力研究開発機構職員の案内で、原子炉上部や中央制御室を約1時間半かけて回った。終了後、知事は自身が初めて参院選に出た時から高速増殖炉に関心があったことを明かし、「あれから数十年、半ば挫折に近くなってきて残念」と語った。「もんじゅ」の長期運転中止について記者団に問われた石原知事は、「誰がつくった手続きか知らないが、そういったものを簡略化、スピードアップするのが政治家の責任」と批判した。今後の原発新設については「半分本気で東京に造ったらいいよ」と語った。----高速増殖炉「もんじゅ」の問題点については、以前にも記事を書いたことがあります。実質7ヶ月間の運転で大きな事故が2回ですから、非常に効率の事故発生率です。通常の原発だって危険ですが、高速増殖炉の根本的な問題は、冷却材にナトリウムを使っているという点です。金属ナトリウムは空気や水に触れただけで発火します。つまり、何らかの事情で冷却材が配管から漏れ出すと、それだけで火事になってしまうのです。事実、1995年に、「もんじゅ」はナトリウム漏れによる火災事故を起こしています。このとき発火の原因になったナトリウム漏れは、原子炉本体ではなく二次冷却系からのものなので、放射能漏れはありませんでしたが、鎮火までに2時間以上を要し、鋼鉄の床が高熱で解け落ちていたことが後で分かっています。地震でもなんでもないときに起こったナトリウム漏れでも、これほど鎮火に手間取るのです。一応、原子炉は窒素を充填した部屋に置かれているので、漏れ出しても発火はしない設計になっているそうです。しかし、二次冷却系はそうではありません。だから火災事故が起きた。「平時」の火災事故でさえ、鎮火に何時間もかかっているのに、地震で混乱状態のときに火災が起きたら、事態はかなり絶望的に思えます。仮に直接的には原子炉内のナトリウムが漏れなくても、二次冷却系のナトリウムが発火して、それが鎮火しなければ、原子炉本体にも危機が及ぶでしょう。水をかけて消すことができない、というのは、なかなかに決定的な問題です。冷却材が漏れ出すリスクがどの程度あるか、という点も問題です。福島第一原発の事故でも、東電の公式見解によれば、津波によって始めて事故が起きたということになっていますが、地震の直後から配管からの水漏れがあったという証言があります。新潟中越沖地震でも、柏崎仮羽原発で冷却水の水漏れはありました。その他にも冷却水漏れ事故は(あってはならないことではありますが)時々起こっているのが現状です。それらの冷却水漏れ事故が、高速増殖炉だと、そのまま火災事故に直結してしまう可能性が高いのです。恐ろしいといわざるを得ません。だから、原発先進国で地震のない国であるフランスでさえ、高速増殖炉からは撤退しました。地震のある日本で、こんな軽水炉以上に危険な原発がトラブルなしに維持なんて、人類の能力を超えると私は思います。そんな「もんじゅ」を廃炉にするな、早く動かせと我らが都知事は言うのです。滅茶苦茶な話です。何があっても、「もんじゅ」だけはは動かしてはいけない。他の原発は動かしていいというわけではないけれど、特にもんじゅは危険すぎます。そして、それを動かせと公言する石原慎太郎も、やはり危険すぎます。
2012.09.06
コメント(4)
-
改めて、原発に未来はない
再処理稼働へ 「原発ゼロ」は青森への背信だ(9月5日付・読売社説)日本は、原子力発電所から出る使用済み核燃料を再利用する「核燃料サイクル」政策の実現を目指している。日本原燃が青森県六ヶ所村に建設してきた再処理工場は、その要である。稼働へ向け、大きなヤマ場を越えた。1993年に着工し、2兆円以上の建設費が投じられてきた。高レベル放射性廃棄物を安定保管するため、ガラスで固める工程が最終試験段階で難航していたが、ようやく試運転に成功した。政府の安全確認などを経て完工する。ウラン資源の有効活用や放射性廃棄物の減少に貢献する施設である。早期の稼働が求められる。懸念すべきは、政府・民主党の「脱原発」論議の迷走だ。再処理工場を稼働させられるかどうか、それ自体が問題になってきた。政府のエネルギー・環境会議で有力選択肢に浮上している「原発ゼロ」になれば、使用済み核燃料の再利用の道は閉ざされ、工場を動かす意味がなくなる。再処理工場に全国の原発から搬入された約3000トンの使用済み核燃料は行き場を失うだろう。青森県は、日本原燃と交わした覚書を踏まえ、工場を稼働させない場合は、すべてを各電力会社が引き取るよう求めている。そうなれば、各地の原発は戻された使用済み核燃料で満杯となり、交換用の新たな核燃料を持ち込む余地さえなくなる。これでは、立地自治体も、原発を再稼働することに同意はすまい。将来の「原発ゼロ」どころか、直ちに混乱しかねない。青森県の三村申吾知事は先月、政府に対して「現実的に実行可能な方針」を示すよう求める要望書を提出し、「原発ゼロ」に疑問を呈した。核燃料サイクルについても「資源に乏しいわが国を支える重要な政策」と述べた。政府・民主党が安直に「原発ゼロ」政策に転換しないよう、クギを刺したものだろう。当然の見解表明と言える。政府は、青森県に誠実に対応すべきだ。再処理技術は、核拡散に敏感な米国が日米原子力協定で日本に特別に認めた権利でもある。この権利が「原発ゼロ」で失われる。無論、これまで培ってきた原子力の技術が衰退し、新たな人材も育たなくなる。使用済み核燃料を、厳しい管理の下で確実に再利用することは軍事転用を封じるのに役立つ。中国、韓国などは原発利用を拡大している。「原発ゼロ」は日本の発言力を低下させるだけだ。---「脱原発は非現実的だ」と叫んでいる原発推進派が、その実どれだけ非現実的か、ということがよく分かる文章です。「原子力発電所から出る使用済み核燃料を再利用する「核燃料サイクル」政策の実現を目指している。」とありますが、核燃料サイクルはすでに破綻しています。先送り主義の結果としての核燃料サイクル何故、このときに撤退しなかったのか「夢の核燃料サイクル」を実現するはずの高速増殖炉は、とても実用化できるような代物ではありません。それなのに再処理によってプルトニウムの在庫が増え続け、仕方がなくはじめたのがプルサーマル、つまり通常の軽水炉にプルトニウムを混ぜた燃料を使うことです。ところが、日本が抱えているプルトニウムは、プルサーマルで使いきれるような分量ではありません。だから、再処理をやめない限り、プルトニウムはどんどんたまっていく一方です。「再処理工場に全国の原発から搬入された約3000トンの使用済み核燃料は行き場を失うだろう。」ともありますが、使用済み核燃料が行き場を失うのは、早いか遅いかの問題に過ぎません。数日前の記事に書きましたが、六ヶ所村の再処理工場の貯蔵施設は、3000トンの収容能力に対して、すでに97%が埋まっています。これ以上使用済み核燃料を受け入れる余地は、ほとんど残っていない。それに対して、各原発の燃料保管プールは、合計20630トンの保管容量に対して、残り容量は6400トン程度だそうです。原発が通常どおり稼動している場合、年間で全原発合計1000トン程度の使用済み核燃料が発生するので、今までどおり原発を稼動させるとするなら、あと6年分しか空き容量はないのです。再処理工場が稼動したら、何かが解決するのでしょうか。何も変わりません。使用済み核燃料から、新たに生成されたプルトニウムと燃え残りのウラン235を抽出するのが再処理工場ですが、そのあとにはもちろん危険な高レベル廃棄物が残ります。高レベル廃棄物は(再処理前の使用済み核燃料も同じですが)毎時1500シーベルトという猛烈な放射能を帯びています。人間がしがみついたとすれば20秒、1メートル離れていても8分で、100%致死量に達します。50年経っても、放射線量は1/9にしか下がらず、実質的に無害になるのは数千年後とも10万年後とも言われます。で、高レベル廃棄物の最終処分場がまだ決まっていないのは周知のとおりです。地層処分、つまり地中深くに保管するわけですが、受け入れる自治体はありません。再処理工場のある六ヶ所村も、最終処分地になることは激しく拒否しているので、上記の社説にあるように再処理工場が稼動しない場合は使用済み核燃料を各電力会社が引き取るという取り決めになっているわけです。世界的に見ても、最終処分場が決まっている唯一の国はフィンランドで、それ以外の国はどこも決まっていません。あの広い米国ですら決められない(いったんはユッカマウンテンに決まったが、白紙に戻された)のだから、狭くて人口密度の高い日本で容易に決められるわけがありません。残念ながら、もうすでに高レベル廃棄物は存在するので、最終処分場はどこかに作るしかありませんが、そうそう簡単に決まらないのは明らかです。先に、今までどおりに原発を稼動したら6年分しか燃料貯蔵プールの空き容量はないと書きました。仮に半分だけ稼動(つまり、原発15%案)としても12年分です。今から12年以内に最終処分場が決まり、工事も完了し、高レベル廃棄物の受け入れが始まっている可能性は、果たしてあるのでしょうか。私には、とても無理のように思えます。どう考えたって間に合わないでしょう。まして6年は論外です。上記の社説にあるように、燃料貯蔵プールがいっぱいになれば、もうそれ以上新たな核燃料を原子炉に入れられないのですから、原発は稼動できなくなります。否応なく原発ゼロになります。なお、核燃料プールの空き容量は各原発ごとに差があり、3年以下の残り容量しかない原発も相当数あるようです。まあ、こっちの原発からあっちの原発へと使用済み核燃料をやり取りすれば、ある程度均等化できるかも知れませんが。というわけで、「トイレのないマンション」である原発は、すでに排泄物の置き場がなくなっている状態で、今までどおり原発を稼動したいといったって、近い将来そんなことは不可能になるのです。そのあたりについては、読売新聞はいったいどう考えているのでしょうか。最終処分場については頬かむりで、ただ原発を動かせというほうが、脱原発派より、はるかに非現実的です。
2012.09.05
コメント(2)
-
どういう根拠の政府試算だか 追記あり
再生エネ普及に50兆円=原発ゼロで光熱費倍増―政府試算政府は4日、「エネルギー・環境会議」(議長・古川元久国家戦略担当相)を開き、将来の原発依存度をゼロにする際の課題と克服策を議論した。2030年にゼロとする場合、太陽光や風力など再生可能エネルギーの普及に約50兆円の累積投資が必要と試算。また、原発の使用済み核燃料の扱いで関係自治体の理解を得られなければ、「即時原発ゼロ」になる恐れがあると指摘した。枝野幸男経済産業相は会議出席後の記者会見で、使用済み核燃料の扱いは関連施設が立地する青森県の理解なく変更できないと強調。その上で「(原発を)即時ゼロにする政策を取ろうとは思わない」と述べた。古川担当相は会議終了後、中長期的なエネルギー政策の方向性を示す「革新的エネルギー・環境戦略」を週明けまでに政府として策定する見通しを示した。試算によると、30年の発電量に占める原発依存度をゼロにする場合、電気代を含む家庭の光熱費は、月額最大3万2243円となり、10年実績(1万6900円)比ほぼ倍増する。原発の使用済み核燃料の扱いで青森県などの理解と協力が得られなければ「即時原発ゼロ」の恐れがあると指摘。電力供給量の約3割が失われるほか、火力発電による代替で燃料費が年間約3兆1000億円増加するとした。再生可能エネルギーの普及拡大に向けた課題として高い発電コストや送電線の整備を挙げた。古川担当相は会議で、エネルギー政策に関する国民の意見について「過半の国民は原発に依存しない社会を望んでいる」とする検証結果を報告した。 ----試算の根拠が示されていないので、内訳も何も分からないのですが、どうも変な試算だなと思います。そもそも、この「家庭の光熱費」の定義はどうなっているのかなと考えてみました。計算の根拠になるのは、おそらく総務省の家計調査だと思われますので、その統計数値をいろいろ調べた結果、2010年の2人以上世帯の光熱費から水道代を引いた金額を12で割ると、16903円になるので、おそらくこの数値が「10年実績(1万6900円)」の根拠ではないかと思われます。統計資料のエクセルシートはこちらもしそうだとすると、「光熱費」のうち、正味の電気代は月9850円になります。それ以外は、ガス代(都市ガスとプロパンの合計)約5500円、灯油代約1500円、上記の数字には(おそらく)含まれない水道代が5050円くらい、となります。今問題になっているのは、あくまでも原子力発電をどうするか、なのですから、ガス代や灯油代、もちろん水道代は関係ないはずです。もちろん、原発の代替を火力発電で行えば、天然ガスや石油の消費が増えるので、価格が高騰し、つられてガス代と灯油代も値上げする、ということはあり得ます。でも、政府の言う「2030年に原発0%」は、原発の代替は再生可能エネルギーということになっており、火力発電は増やさない、ということになっています。※2010年の発電割合は、原発26%で、再生可能エネルギー(水力)10%、火力発電64%です。原発ゼロの場合は、の発電割合の想定は。再生可能エネルギー35%、火力65%ですから、火力発電の割合は1%増えるだけです。ただし、電気使用量の絶対量は2010年より少ない(省エネをより進める)前提なので、火力発電の絶対量は2010年より少ない。つまり、原発ゼロでもガスや灯油の消費量はほぼそのまま(あるいは微減)であるはずなのです。にもかかわらず光熱費の合計が3万2243円ということは、電気代だけが約25000円になる、ということです。現状の約2.5倍です。発電コストのうち、65%の火力と10%の水力(再生可能エネルギーの一部)の部分は現状と変わりません。それなのに電気代が2.5倍に上がるというのが事実なら、残る25%部分のコストが7倍に跳ね上がる、という計算になります。どう考えてもあり得ないでしょう。太陽光発電の買い取り価格が1KWあたり42円で高い、ということが騒がれていますが、いろいろな企業が太陽光発電に参入しているということは、この単価で利益が出るということです。家庭用電気の平均単価は1KWあたり24円といわれているので、42円は確かに高いのですが、それでも2倍にもなりません。もちろん、買取価格42円という数字は、未来永劫続くものではありません。太陽光発電の初期費用は最近急激に下がっており、おそらく今後も下がるので、それに伴ってコストも更に下がるはずです。風力発電は、太陽光より更に発電コストが低いとされます。地熱発電も、初期費用はかかりますが、発電コストはかなり安いようです。それらのことを考え合わせると、原発ゼロで光熱費が月3万2千円というのは、とても信用に足る推計ではないように、私は思います。投資額50兆円というのも同様です。たとえば、太陽光発電については、造成されたまま使われずに不良債権化していた工業団地用地に、続々と設置されていると報じられています。土地はすでに造成されていて、送電線も整備されているのに使われていない工業団地用地が、1億5千万平方メートル(150平方キロ)もあるというのですから、それを使わない手はありません。追記 FNNニュースの報道によると原発をゼロにした場合、火力発電に切り替えることで、原油やLNG(液化天然ガス)の輸入が増え、2030年時点に、2人以上の家庭で、電気料金だけでも月額最大2万0,712円に、光熱費全体では最大3万2,243円となり、2010年のおよそ2倍になるとの試算が出された。とのことです。なるほどね。これは、ものすごく詭弁的な論法です。なぜなら、前述したとおり、原発ゼロのシナリオでは、原発の分は再生可能エネルギーに置き換えるから、火力発電のシェアは増えないという前提になっているからです。その前提の上で、再生可能エネルギーはコストがかかるから電気代が上がる、という話であったはずです。それなのに、「火力発電に切り替えることで、原油やLNG(液化天然ガス)の輸入が増え」るから電気代が(ガス代や灯油代も)値上げする、というのです。いつのまにか、原発の分は火力発電に置き換える話に摩り替わっている。それならば、石油とガスの価格上昇分だけを見込めばいいのであって、再生可能エネルギーのコストがどうとかは考える必要はないはずです。
2012.09.04
コメント(6)
-
追加燃料費の怪
この夏結局は大飯原発の2基が再稼働しただけで電力供給は間に合ってしまいました。おそらく、大飯原発再稼働がなくても何とかなっただろうと思います。関西電力単独ではともかく、他社からの融通も含めればね。そうしたら、原発推進派は、今度は燃料代がかさむという、カネの話にすり替えるのです。典型例としてご紹介するのは、例によって池田信夫です。昨年と今年だけで5.4兆円の国富が流出し、電気代は2割ぐらい上がり、企業は日本から出て行く。「毎日80億円以上をドブに捨てて何が得られるのか」と質問した石油や天然ガスを輸入してその代金を支払うことを、池田語では「(お金を)ドブに捨てる」と言うらしいです。すごい言語感覚だなと思いますね。それはともかく、2年間で5.4兆の燃料代と聞くと、確かにもの凄い金額だって気がしますね。では実態はどうなんでしょうか。上記池田の記述のソースは、政府の需給検証委員会の報告です。(P.44-45)なるほど、昨年実績で追加の燃料費が2.3兆円、今年の予測で、燃料費が昨年横ばいとして3.1兆円、燃料費が上昇した場合は3.4兆円という数字が記載されています。しかし、これはすべてが原発停止によるコスト上昇ではなく、原油価格上昇による分も含まれています。注記に書かれているように、2010年は1バーレル84ドル/1ドル86円(つまり1バーレル7224円)、2011年は1バーレル114ドル/1ドル79円(つまり1バーレル9006円)という計算です。円ベースで見て、2割以上原油価格が上昇しているわけです。逆に、今年に関しては、別のソースによると財務省の貿易統計によると、11年度のLNG輸入量は8318万3000トン。代替の火力発電用燃料の需要が引き続き旺盛なことから、輸入量は6.5%増加する。また、石炭の輸入量が500万トン、石油が430万キロリットル、それぞれ増加する見込み。同研究所は、関西電力大飯原発3、4号機が運転を再開し安定的に稼働することを予想の前提条件としている。一方で、原油価格が下落していることから12年度の化石燃料の輸入額は22兆6000億円と、前年度比5000億円減少する。しかし、輸入額は輸出額を3.8兆円上回り2年連続の貿易赤字になる見通しだ。試算の前提として、12年度の原油輸入価格を11.39ドル安の1バレル当り103ドル、LNG輸入価格を1トン当たり45セント高の825ドルとしている。 とのことです。つまり、去年と比べて原油価格は下がっており、従って化石燃料の輸入金額は去年より減るというのです。それにも関わらず、上記の試算は、原油価格が横ばい、または上昇のケースしか想定していません。とはいえ、それらの条件を考慮してもなお、電力会社にとって、原発停止による追加の燃料費が莫大だ、ということは分かります。燃料費が前年比で5割以上も増えているんですからね。価格上昇分を割り引いて考えても、相当の負担増だということは分かります。でも、それは電力会社にとっての負担増でしかありません。それをあえて「国富が流出」と表現するなら(そのような表現をするのは、池田だけではなく、原発推進派はおおむねそういう表現をしたがります)、国全体で考えなければなりません。日本国全体としてみれば、上記の引用文にあるように、化石燃料の輸入費は年間22兆円にもなります。それに対して、原発停止による追加燃料費の2.4兆円(実際は価格上昇による追加費用も含まれる)は、全体の1割程度です。従って、原油価格が1割も変動すれば、追加燃料費の問題など吹っ飛んでしまう、その程度の話です。私も、今後未来永劫原発が止まった分は化石燃料で代替すればよい、とは思いません。地球温暖化の問題が消えてなくなったわけではありませんから。化石燃料に依存するのは、再生可能エネルギーに取って代わられるまでの「つまぎ」であれば良いのです。それに、原発が止まった分をすべて化石燃料で代替する必要はないのです。節電によって消費電力が減っています。東京電力管内について言えば、一昨年と比べて、900万KWから1000万KW最大電力が減っています。これは、東京電力がかつて持っていた(廃炉になった福島第一原発1~4号機も含めた)原発の総出力(1730万KW)の半分以上に相当します。震災前だって常時すべての原発が稼働していたわけではない※ことを考慮に入れれば、7割くらいに相当するかも知れません。※原発は1年ごとに3ヶ月間の法定点検を行わなければなりませんし、それ以外にも、東電に関して言えば、2007年7月の中越沖地震で緊急停止した柏崎刈羽原発は、去年の震災の時点でも7機中4機しか再稼働していませんでした。これらの条件を考え合わせれば、電力会社には申し訳ないけれど、その程度の燃料費は仕方がないでしょと言うとかありません。電気料金の値上げも、それによって原発稼働が回避できるならやむを得ないと私は思っています。電気料金は値上げせず(あるいは値下げして)原発稼働するのと、電気料金値上げして原発全廃するのを比較するなら、私は迷わず後者を選びます。
2012.09.03
コメント(0)
-
8月は終わったが
あっという間に8月が終わり、夏もほぼ終わってしまいました。この8月、東京は猛暑でしたね。7月は気温が低く、エルニーニョ現象の発生も報じられていたことから、この夏は猛暑にはならないと私は予想していたのですが、残念ながら外れてしまいました。東京(千代田区大手町)の8月の月平均気温は29.1度でした。これは、一昨年(29.6度)と1995年(29.4度)に次ぐ、観測史上3番目の記録です。最高気温が35度を超える猛暑日は6日あり、最高気温は8月17日の35.7度でした。東京電力管内の電力消費量が最高を記録したのは8月30日(最高気温35.6度)で、5078万KWでした。一方、去年の最大電力は8月18日(最高気温36.1度)4922万KWだったので、最高気温が0.5度低いのに電力は150万KWほど多い、ということになります。今年の8月30日も昨年の8月17日も木曜日であり、昨年は大工場の土日シフトによって約100万KWの節電があったそうですが、今年は土日シフトとは行われていません。また、去年は電車の間引き運転もありました。間引き運転の節電効果ははっきりとは分かりませんが、このソースによると、東電管内の鉄道関係の消費電力は夏のピーク時に150万KW、うち運行関係が8割(120万KW)とのことなので、ピーク時に2割間引き運転したとすれば、節電効果は24万KWということになります。間引き運転も、今年は関東では行われていません。この二つの要素を除くと、昨年比で20~30万KW程度の増ということになり、ほぼ誤差の範囲といえるでしょう。そう言えば、エスカレーターの運転停止も、今年は見かけませんでした。私の勤務先も含めて、職場や商業施設の冷房温度も、去年よりは心持ち低めに設定されているような気がしないでもありません。そう考えると、世間一般の節電への取り組みは、去年ほどではないのかも知れません。しかし、結果として去年を上回る猛暑(最大電力を記録した日に限っては去年の方が暑かったけれど)にも関わらず、電力需要は昨年比で微増程度で収まっています。一昨年の最大電力は7月23日の5999万KW(最高気温は35.7度)ですから、そこから比べると、依然として大幅減であることは確かなのです。その結果、東京電力管内では、原発が一基も稼働せずにこの夏を乗り切ることができました。人間の文明的な生活には電気は必要不可欠ですが、大量に使えば使うほどよい、というわけでもありません。私は、将来的に原発を全廃すべきだと思っているのですが、原発への賛否はひとまず措くとしても、電気を、ひいては資源エネルギー全般をより大量に消費するという方向性は、どう考えても持続可能ではありません。石油も石炭も天然ガスも、もちろんウランも有限の資源であり、そう遠くない将来必ず枯渇するものですから。無理な節電もまた長続きしませんが、現状程度の節電は、今後も永続的に行っていく必要があるだろうと私は思います。ちなみに、我が家の場合、7月と8月の電力消費(家庭用ですから、検針日間の合計しか分かりませんが)は、7月165KWh 8月250KWhでした。昨年比で7月は大幅減、8月も微減です。もちろん、昨年だって一昨年からは25%以上減っているのですが、2年越しで計算すると、7月は2年前の45%減、8月は3割減です。ただし、去年と比べて何か特別な節電対策を新たに始めたわけではありません。7月は冷夏だったこと、8月はじめに冷蔵庫が新しくなって、冷蔵庫の消費電力が減ったことが原因なのでしょう。なお、我が家では、一昨年に消費電力が最大を記録した月は9月で、420KWh以上でした。去年は、ほぼその半減でしたし、今年9月の消費電力がどうなるかは分かりませんが、去年より大きく増えることはないでしょう。我が家の場合、課題は冬場です。今年1・2月も大幅に節電したのですが、金額ベースでは、節電分を帳消しにするくらいガスの消費量が激増しまいました。もちろん、この冬が大変な厳冬だったことも一因ではあるのですが、去年の1月もかなり寒い冬だった(1月の平均気温は昨年5.1度、今年4.8度)ので、それだけが理由ではありません。エアコンとガス暖房の両方がある部屋は、エアコンを一切稼働せずガス暖房だげを使ったのですが、両者併用する方がトータルの光熱費は安く上がるのかもしれません。もう一つ、、うちのガスファンヒーターはすでに18年以上使っています。ガスファンヒーターの寿命が一般にどのくらいか知りませんが、古くなると燃費が悪くなるとかあるんでしょうか。今まで故障したことはないので、特に考えたことはないのですが、そろそろ替え時なのかなあ。
2012.09.02
コメント(0)
-
エネルギー政策は密室談合で決めるべき、ということでしょうか
エネルギーと原発 世論で基本政策決めるな世論に耳を傾ける努力は大切だが、エネルギー問題のような国の基本政策が世論によって決められるルールを確立させてはならない。高度で冷静な政治判断こそが優先されるべきだ。2030年の原発比率など日本のエネルギー構成について、寄せられた国民の意見を分析した有識者による検証会合(座長・古川元久国家戦略相)が「少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる」とする見解をまとめた。この見解は、これから政府が着手する国の中・長期的なエネルギー問題と温暖化対策の方向性を定める「革新的エネルギー・環境戦略」の策定作業の本質に影響を及ぼしかねない内容だ。検証会合の見解を“お墨付き”として、デモに代表される反原発の時論に迎合し、「原発ゼロ」を軸とする新戦略の構築に傾斜するのは禁物だ。そうした迎合は、日本の発展に終止符を打つ行為に他ならない。国の存続と繁栄に安定したエネルギーが必須であることは、歴史が示す自明の理である。次の選挙で世論の逆風を受けるとしても、エネルギー安全保障の重要性を有権者に説いて、国の将来を確かなものにしてゆくことが、政治家の責務である。再生可能エネルギーの発電能力は、原発に比べると格段に小さく、不安定だからだ。そもそも政府が実施した意見聴取会やパブリックコメント(意見公募)、討論型世論調査は、準備不足で問題点も多い。意見聴取会で電力会社の社員の意見表明の機会を奪ったことなどにより、脱原発派が勢いを得た感がある。政府の調査では、新聞社などによる世論調査より「原発ゼロ」の回答率が高い。政府の調査そのものが脱原発ムードを醸し出した可能性が疑われる現象だ。こうした不確かな調査をよりどころに、エネルギー計画の策定を急ぐのは短慮に過ぎよう。皮相的な原発の好悪論にとどまらず、原発をなくした場合の経済や文化への影響までを視野に入れた議論の深化が必要だ。有識者の検証では、20代以下の30%強が「原発維持」の意見であることが注目された。政府は約20年後のエネルギー構成を考えている。若い世代の意見に重みを置いて検討することも重要だ。----例によって惨傾新聞、いや産経新聞の叫びです。「エネルギー問題のような国の基本政策が世論によって決められるルールを確立させてはならない。高度で冷静な政治判断こそが優先されるべきだ。」というのは、すばらしい理屈です。世論がどうであろうが、そんなものは無視して「高度で冷静な政治判断」をしろ、というのです。しかし、原発を推進してきた人たちの言ってきたことやってきたことは、「高度」でも「冷静」でもないように、私には思えます。産経新聞なんかが、まさしく代表例ですが。そもそも、「高度で冷静な政治判断」を行う主体は誰なんでしょうか。政治家か高級官僚か、ということになるのでしょう。政治家は選挙を通じて世論の洗礼を受けますが、選挙で選ばれるわけではない高級官僚が、世論を無視して密室談合で国の基本政策を決めるのだとすれば、それはもはや民主主義とは言えません。「国の基本政策」が民意で決まらないのだとしたら、選挙はいったい何のためにやるんですか、国民のガス抜きのための人気投票ですか。しかも、同じ文章の中で、「20代以下の30%強が「原発維持」の意見であることが注目された。~若い世代の意見に重みを置いて検討することも重要だ。」と言うのです。「国の基本政策を世論で決めるな」と言った同じ口で、「若者の世論で決めろ」というのですから、ダブルスタンダードもいいところです。つまり、要約すれば「自分たちに都合の良い世論には従え、都合の悪い世論は無視しろ」と言っているようにしか見えません。そもそも、30%強というのは半分以下の数字なので、「20代以下でも原発維持は少数派」という結論しか導き出しようがないように思えるのですが、産経脳には、30%強が多数派に見えるんでしょうか。ちなみに、この数字の根拠は、何とニコニコ動画のアンケートだそうです。「国家戦略室」がニコニコアンケートをソースに持ち出すとは、いささか脱力してしまいます。私もニコニコ動画にアカウントを持っていますけど、ニコニコアンケートを「世論調査」と呼ぶのは、あまりに無理があります。なお、ニコニコアンケートの結果詳細は、こちらに資料があります。確かに、「原発維持」派が20代と10代で相対的に多いことは事実ですが、それでも「即時廃止」と「徐々に減らしていきいずれは全廃」の合計が6割を超えているのですから、まともな読解力があれば「若年層でも脱原発派が多数」という結論になると思われます。当ブログで何度も書いているように、私も、「全原発を即時廃止」というのは無理だと思います。が、2030年といえば今から18年後ですから、その程度のスパンで考えれば原発全廃は可能だし、逆に2030年の時点で原発をこれまでどおりに維持し続けることなど不可能なのです。これについては、以前にも書いたことがありますが、今後運転再開不可能な原発が相当数あるのに対して、新規設置はきわめて困難ですから、どう考えたってこれまでどおりの原発依存度を維持することなど、できるはずがないのです。それに加えて、もう一つの問題があります。核廃棄物の問題です。これについても以前記事を書きましたが、高レベル廃棄物を最終的にどこに貯蔵するかは、まだ決まっていません。六ヶ所村の再処理工場(まだ本格稼動していない)の貯蔵施設はすでにほぼ満杯です。各原発の核燃料貯蔵プールには、行き場のない使用済み核燃料が大量に保管されていますが、これも近い将来満杯になります。そうなると、原子炉内の核燃料が燃え尽きても、取り出して保管する場所がない。雪隠詰め、文字どおりの「トイレのないマンション」です。そうなると、物理的に原発の運転が不可能になります。それまでの猶予期間は、早い原発ではあと数年、余裕のあるところでも十数年です。この現実を正視すれば、脱原発以外の選択肢はないと私には思えるんですけどね。
2012.09.01
コメント(2)
全23件 (23件中 1-23件目)
1