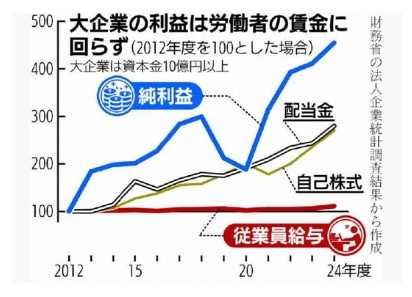2012年11月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
何でこんなことが炎上の原因になるのか理解できません
辻希美 平日に子供を夢の国に連れて行きネット上で非難殺到11月12日の月曜日、元モーニング娘。の辻希美さんが、「最近、希空とママの二人の時間がなかなかなかったので、今日は1日青空をバァバにお願いして希空と二人きりでデートに行って来ます」とブログに書きました。「この計画は2週間前位にし始めたんだケド、その時希空にどこに行きたい!?と聞いたら『〇〇ー〇〇〇』と言っていたので今日は電車に乗って夢の国へ行って来ます」と続けたワケですが、これが「娘の幼稚園を月曜日に休ませた」と2ちゃんねるなどで炎上したのです。私自身は「学校は休んではいけない」という厳格な親に育てられただけに、今回炎上させている方々の気持ちも分かりますが、ただね、いちいち赤の他人のことを批判する余力があるんだったら、お前の子供のことをもっとかわいがってやれ、と思うわけです。辻チャンのことを叩く人ってオレはバカだと思う。「ウインナーが多い」とか自宅のベランダでプールに入れてあげたら「区営プールくらい入れてやれ」とか。寛容性がますます失われていく社会になるんですかね。つーか、他人の人生にイチイチ構うよりもお前とお前の周囲を幸せにしろ、と思いますね。---さかもと未明の奇行は、非難を浴びるのも当然だと思うのですが、それにたいして、この記事の出来事は、いったい何故非難を浴びなければならないのか、私には理解できません。着陸直前の飛行機内でシートベルトを外して走り回る、という行為は、他の乗客に大迷惑をかけ、危険を及ぼす可能性もある行為ですが、自分の子どもを平日にディズニーランド(かどうかは定かではありませんが)に連れて行くことで、いったい誰に迷惑がかかったり、危険が及んだりするんでしょうか。しかも、幼稚園ですよ、小学校とは違って、義務教育じゃないんですよ。私自身だって、子どもが幼稚園のときは、平日に休ませて旅行に行ったりしたことは、何回かはありますし、それが悪いこととはまったく思いません。もちろん、小学校に入ってからは違います。小学校を遊びのために休ませたことはありません。もっとも、仮に小学校を休ませて遊びに行ったのだとしても、「私ならそんなことはしない」とは思うけど、だからといって、別に誰に迷惑をかけているわけでもないんだから、そんなに集中砲火を浴びせるような悪事とは思えないのです。みなさん、よっぽどお行儀がよくて、道徳的な聖人君子ばっかりなんですねえ。
2012.11.28
コメント(4)
-
「国防軍」大好き人間は軍事を知らない
「国防軍」 平和と安全守るに必要だ 民主党は見解を明確にせよ安倍氏は国防軍とする理由について、「日本の中では自衛隊は軍隊ではないと答弁している。憲法9条の1項、2項を読めば軍を持てない印象を持つ」と述べた。一方、武力紛争時の傷病者や捕虜などの保護を定めているジュネーブ条約を挙げて、「政府は(自衛隊が)軍隊としてジュネーブ条約上は認識されているものと思うと答弁する」とし、国際的には軍隊だと認めていると指摘した。「もし捕虜になったときに、ジュネーブ条約上、軍であればちゃんと待遇される。そうでなければただの殺人者だ」と説明し、「こんな詭弁を弄するのはやめるべきだ」と強調した。---例によって産経新聞の、しょうもない社説ですが、社説そのものの内容もさることながら、そこで引用されている安倍の発言は仰天モノです。「もし捕虜になったときに、ジュネーブ条約上、軍であればちゃんと待遇される。そうでなければただの殺人者だ」なんですか、この解釈は。安倍は肝心のジュネーブ条約を読みもせず、でたらめなことを書いているようです。もしジュネーブ条約を読んでいれば、こんな滅茶苦茶な解釈は出てきません。問題の、ジュネーブ条約第4条(捕虜)の条文は、このようになっています。第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員(2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。 (a)部下について責任を負う一人の者が指揮していること。 (b)遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。 (c)公然と武器を携行していること。 (d)戦争の法規及び慣例に従って行動していること。(3) 正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの(4) 実際には軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、たとえば、文民たる軍用航空機の乗組員従軍記者、需品供給者、労務隊員又は軍隊の福利機関の構成員等。但し、それらの者がその随伴する軍隊の認可を受けている場合に限る。このため、当該軍隊は、それらの者に附属書のひな型と同様の身分証明書を発給しなければならない。(5) 紛争当事国の商船の乗組員(船長、水先人及び見習員を含む。)及び民間航空機の乗組員で、国際法の他のいかなる規定によっても一層有利な待遇の利益を享有することがないもの(6) 占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、正規の軍隊を編成する時日がなく、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執るもの。但し、それらの者が公然と武器を携行し、且つ、戦争の法規及び慣例を尊重する場合に限る。B 次の者も、また、この条約に基いて捕虜として待遇しなければならない。(1) 被占領国の軍隊に所属する者又は当該軍隊に所属していた者で、特に戦闘に従事している所属軍隊に復帰しようとして失敗した場合又は抑留の目的でされる召喚に応じなかった場合に当該軍隊への所属を理由として占領国が抑留することを必要と認めるもの。その占領国が、その者を捕虜とした後、その占領する領域外で敵対行為が行われていた間にその者を解放したかどうかを問わない。(2) 本条に掲げる部類の一に属する者で、中立国又は非交戦国が自国の領域内に収容しており、且つ、その国が国際法に基いて抑留することを要求されるもの。但し、それらの者に対しては、その国がそれらの者に与えることを適当と認める一層有利な待遇を与えることを妨げるものではなく、また、第八条、第十条、第十五条、第三十条第五項、第五十八条から第六十七条まで、第九十二条及び第百二十六条の規定並びに、紛争当事国と前記の中立国又は非交戦国との間に外交関係があるときは、この条約の利益保護国に関する規定を適用しないものとする。前記の外交関係がある場合には、それらの者が属する紛争当事国は、それらの者に対し、この条約で規定する利益保護国の任務を行うことを認められる。但し、当該紛争当事国が外交上及び領事業務上の慣習及び条約に従って通常行う任務を行うことを妨げない。C 本条は、この条約の第三十三条に規定する衛生要員及び宗教要員の地位に何らの影響を及ぼすものではない。---捕虜として保護の対象となるのは、軍と軍人にかぎっさてはいないのです。民兵隊、義勇隊、組織的抵抗運動団体、軍に随行する軍属、民間商船・飛行機の乗組員、さらに、敵の接近に当り、正規の軍隊を編成する時日がなく、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執るものまでが、この条約において捕虜として保護の対象となることが明記されています。したがって、自衛隊が、「軍隊」を名乗っていようがいまいが、ジュネーブ条約の対象となることはまったく明白で、疑いの余地がありません。もちろん、過去の戦争においてジュネーブ条約(あるいは、その前身であるハーグ条約)が常に守られてきたかといえば、必ずしもそうではない現実はあります。たとえば、南京事件がそうです。現在でも、世界各国の紛争のたびに、ジュネーブ条約に反する捕虜の虐殺や虐待が報じられていることは事実です。が、それは「自衛隊か軍か」などということはまったく関係がない。「自衛隊」という名称だとジュネーブ条約が守られず、「軍」という名称なら守られる、なんてことがあるわけがないのです。ジュネーブ条約を読みさえすれば、安倍のような仰天解釈が出てくるはずがないので、従って安倍は条約を読んだこともないのでしょう。ジュネーブ条約という名前を出すなら、せめてその条文くらいは読んでおくべきと思うのですが、安倍にそういう考えはないのでしょうか。あまりにバカすぎると思わざるを得ません。もっとも、読んで内容を知っているのに、こんなことを言い出しているとしたら、これはまたとんでもなく悪質なデマゴギーということになりますが。
2012.11.27
コメント(9)
-
ポビュリズム?
民主党政権に対して浴びせられる定型的な批判の一つに、「ポピュリズム」という言葉があります。高校無償化や子ども手当などの「バラマキ」と呼ばれる政策にそのような批判が浴びせられることが多いようです。時には、脱原発政策(民主党がどこまで脱原発に本気かは、疑問の余地が多々ありますが)すら、ポピュリズム呼ばわりされることがあります。※私自身も、子ども手当には賛成ではありませんがちなみに、ウィキペディアによるとポピュリズム(英: populism)とは、一般大衆の利益や権利、願望を代弁して、大衆の支持のもとに既存のエリートである体制側や知識人などと対決しようとする政治思想または政治姿勢のことである。日本語では通常は大衆主義や人民主義などと訳されるが、一部では「大衆迎合」などの政治学上は不正確な訳も使われている。最近は、もっぱらこの「不正確な訳」の方が、時事用語としては主流になってしまった感がありますけれど、元々は、必ずしもそのような批判的文脈でばかり使われる用語だったわけではありません。ラテンアメリカ諸国では、アルゼンチンのペロン政権、メキシコのPRI(制度的革命党)、ペルーのAPRA(アメリカ革命人民同盟)、ボリビアのMNR(民族革命運動)などなど、ポピュリズム(スペイン語ではポプリスモと呼ぶ)的な政党が数多く政権に付きました。特にメキシコのPRIは、結党から71年間与党の座にあり続けました。これらポプリスモ的な政党は、資本家に対しては資本主義を、労働者に対しては社会主義を説くような、首尾一貫しない矛盾した政策を主張したり、バラマキ的な大衆迎合政治を行うという側面も確かにありました。しかし、その一方で、ラテンアメリカ各国を曲がりなりにも近代国家に発展させ、「一つの国、一つの国民」という国民意識を醸成するという功績もあったのです。※※ラテンアメリカ各国は、19世紀初めに形の上では独立しましたが、白人と先住民族は同じ国に住んでいても、お互いに別世界の住民同士で、「同じ××国民」という国民意識と呼ぶべきものは、ほとんどなかったのです。その垣根が取り払われ、ある程度「統合された一つの国」になったのは(今も、日本ほどは統合された一つの国にはなっていないけど)20世紀半ば頃の話。とりあえず「不正確な訳」ではありますが、ポピュリズム=大衆迎合主義という仮定で話を続けることにします。前述のとおり、「脱原発はポピュリズムだ」と主張する人たちがいます。仮にそうだとして、では「原発を続けろ」と言っている人たちはどうなのでしょうか。「事故の危険があろうが、高レベル廃棄物の行き場がなかろうが、電気がないと困るから、とにかく原発を続けろ」という主張は、これもまた立派に大衆迎合主義の一種でしかないように思えます。同じく、口先だけ勇ましい対外強硬論のオンパレードもまた、これまた大衆迎合主義の一種であるようにしか、私には思えないのです。自民党が、政権公約として防衛大綱・中期防を見直し、自衛隊の人員・装備・予算を拡充憲法改正で自衛隊を国防軍と位置づけるなんてことを主張しています。この財政難の時代に、どこから自衛隊予算増の財源を持ってくるんでしょうか。赤字国債でしょうか。と考えれば、これもまた大衆迎合主義の一種であるとしか思えません。後先考えず、ただ強硬論を振り回すのは、一見カッコよさそうに見えるけど、それもまた大衆迎合主義の一種でしかないように、私には思えます。
2012.11.26
コメント(6)
-
福島のがんリスク、明らかな増加はない、というものの
福島のがんリスク、明らかな増加見えず WHO予測報告東京電力福島第一原発事故の被曝(ひばく)による住民の健康影響について、世界保健機関(WHO)が報告書をまとめた。がんなどの発生について、全体的には「(統計学的に)有意に増える可能性は低いとみられる」と結論づけた。ただし、福島県の一部地域の乳児では、事故後15年間で甲状腺がんや白血病が増える可能性があると予測した。報告書は近く公表される。福島第一原発事故による健康影響評価は初めて。100ミリシーベルト以下の低線量被曝の影響には不確かな要素があるため、原爆やチェルノブイリ原発事故などの知見を参考に、大まかな傾向を分析、予測した。WHOはまず、福島県内外の住民の事故による被曝線量を、事故当時1歳と10歳、20歳の男女で甲状腺と乳腺、大腸、骨髄について、生涯分と事故後15年間分を推計した。その線量から甲状腺がんと乳がん、大腸がんなどの固形がん、白血病になるリスクを生涯と事故後15年間で予測した。成人で生涯リスクが最も高かったのは福島県浪江町の20歳男女。甲状腺がんの発生率は被曝がない場合、女性が0.76%、男性は0.21%だが、被曝の影響により、それぞれ0.85%、0.23%へ1割程度増えると予測された。他のがんは1~3%の増加率だった。 ---見出しは、「発ガンリスクに明らかな増加はない」とありますが、本文を読むと、「福島県の一部地域の乳児では、事故後15年間で甲状腺がんや白血病が増える可能性がある」とあります。リスクの増加がないというのは、実際には成人に限っての話に過ぎないようです。それも、浪江町の20歳男女は、発ガンリスクが1割程度増える、という見込みだそうです。この数値、リスクをどう受け止めるかは、人それぞれでしょう。ただ、チェルノブイリの事故と比較して、留意すべき点が二つあるように思えます。第一に、事故によって放出されてしまった放射能の総量が、チェルノブイリの数分の一であった、ということです。したがって、深刻な汚染にさらされた土地も、それに比例してチェルノブイリの事故よりは狭い。(ただし、汚染地域の人口密度は、チェルノブイリより福島のほうが高そうな気がします)第二に、チェルノブイリの事故では、旧ソ連当局は当初事故の存在を秘匿していたという事実です。スウェーデンなど国外で高濃度の放射能が検出されて、もう隠しようがなくなった時点で、やっと事故が公表され、住民の避難が開始されました。避難の遅れは、せいぜい1日か2日程度のことではあったのですが、その時点ですでに、大量の放射能が撒き散らされてしまっていたのです。それに対して、福島の事故では、幸いなことに原発から放射能が大量に撒き散らされる以前に、近隣住民が避難しています。福島第一原発の正門付近の放射線量は3月12日4時00分 0.07 μSv/h(正常範囲)同日4時30分 0.59 μSv/h同日7時40分 5.1 μSv/h同日15時29分 1,015 μSv/h(1号機北西敷地境界付近)同日15時36分 1号機で爆発という経過をたどっているのに対して、避難指示は3月11日20時50分 半径2km以内に避難指示同日21時53分 半径3km以内に避難指示3月12日5時44分 半径10km以内に避難指示同日18時25分 半径20km以内に避難指示となっています。大量の放射能が降り注ぐ以前に10km圏内に避難指示が出されており、1号機爆発の3時間後には非難範囲が20km圏内まで拡大されています。実際には、避難指示と同時に全員避難できたわけではないでしょうが、原発から約5kmの富岡町に住んでいた北村俊郎氏の「原発推進者の無念」(平凡社新書609)によると、大渋滞のため避難にかなり時間がかかっていますが、その日の夕方には避難所にたどり着き、その時点で避難所は満員だったとのことです。菅政権の震災対応にはいろいろと批判がありますけれど、原発周辺住民の迅速な避難に関しては(菅の功績か、当時官房長官だった枝野の功績かはともかく)よくやったといえるのではないかと思います。もしも原発周辺からの住民の避難が行われなかったり、遅れたりした場合は、住民の頭上に大量の放射能が降り注ぐことになっていたはずです。発ガンリスクの評価も、まったく違ったものになっていたでしょう。そうならなくて済んだのは、不幸中の幸いと言うべきでしょう。
2012.11.25
コメント(0)
-
世界最大級の地震はM10
世界最大級の地震はM10前後世界で起こりうる最大級の地震について、地球の大きさや地形から、最大でマグニチュード10前後の規模が考えられるという分析結果を東北大学の専門家がまとめました。この分析結果は、21日に都内で開かれた地震の専門家の会合で、東北大学大学院の松澤暢教授が報告しました。それによりますと、地球の大きさや巨大地震を起こす可能性のあるプレート境界の断層の長さなどから、考えられる地震の規模は最大でマグニチュード10前後だとしています。マグニチュード10は去年3月の巨大地震の32倍の規模で、これまで知られているなかで世界最大の1960年に南米チリ沖で起きたマグニチュード9.5の地震を上回ります。例えば、北アメリカからカムチャツカ半島、そして、日本の南にかけての海溝沿い8800キロの断層が20メートルずれ動くとマグニチュード10になるとしています。松澤教授は、こうした地震が起こると、揺れの長さは20分から1時間ほど続き、揺れが収まる前に津波が来て何日も続くことが考えられると指摘しました。そのうえで「マグニチュード10が絶対、起こると考えている訳ではない。東日本大震災でマグニチュード8クラスまでしか起こらないと思っていたらマグニチュード9が起きたので、僅かでも可能性があるならば、どういうことが起こるか事前に理解しておくことは必要だ」と話しています。---M10、ほとんど想像もつかない世界です。近い将来に起きる可能性が高い、というわけではないものの、地質学的には、そのくらいの地震が起こりうる、というわけです。記事には「去年3月の巨大地震の32倍の規模で、これまで知られているなかで世界最大の1960年に南米チリ沖で起きたマグニチュード9.5の地震を上回ります。」とありますが、具体的には、M10.0だとすると、チリ沖地震の約5.5倍という計算になります。揺れの長さは20分から1時間ほどって・・・・・・これまた想像を絶する世界です。去年の東日本大震災も、揺れの持続時間がすごく長いと感じました。実際に、気象庁の発表によると、震度4以上の揺れの持続時間が、東京千代田区の気象庁で130秒、福島県いわき市では190秒だそうです。ほかに、本震並みに揺た余震がありました(ゆれた時間はさすがに本震より短かったけれど)。阪神淡路大震災では、揺れの持続時間が10秒から20秒だったそうです。関東大震災でも、東京で感知された揺れの持続時間は30~60秒程度とか。それらと比較し果ても、東日本大震災がいかに桁外れな地震だったかわかります。ちなみに、震度4以上と言う限定でなければ、地震の後相当長時間(1時間かそれ以上)微弱な揺れが続いていたように体感しています。震度で言えば1程度でしょうけど。東京での揺れが2分10秒の東日本大震災ですらあんなにすさまじいのに、揺れの時間が20分から1時間となったら、どういうことになるのでしょうか。東京は震度5強程度で、倒壊した家屋もほとんどありませんでしたが(というか、東日本大震災全般に、揺れによって直接倒壊した家屋は少ない)いくら5強でも、20分も1時間も揺れ続けたら、共鳴現象なども加わって、倒壊家屋が続出するんじゃないかと思います。我が家の場合、家具の転倒防止用つっかえ棒のおかげで、本棚の転倒は免れた(ただし、本はたくさん落下した)のですが、地震の後、つっかえ棒はいずれも大きくずれていました。おそらく、後さらに何分か揺れ続けた場合、つっかえ棒が外れて、本棚は全部倒れたでしょう。地震の後、つっかえ棒には全部滑り止めシートをかませましたが、どの程度効果があるでしょうね。高層マンションなどでは、東京でもあの地震で家具が全部転倒したという例は少なくなかったようです。で、揺れが続いている間に津波の第一派というのは、これは逃げられないだろうなと思います。しかも、近海からの津波、フィリピン沖からの津波、千島列島からの津波、カムチャッカからの津波、フィリピン沖からの津波、アラスカ沖からの津波・・・・・・最大波高は、いったい何十メートルになるんでしょうか。100メートルとかなったりして。東京湾は、比較的津波の被害を受けにくい地形ですが、M10ではさすがにダメかもしれません。当然、被害を受けるのは日本だけではありません。M9.5のチリ地震では、日本に波高6mの津波が来ています。M10となったら、ロシア沿海州、中国、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、アメリカ大陸の太平洋岸などにも、猛烈な津波が押し寄せることになります。さすがに、この規模の地震に対して防災対策といっても、人間の力でできる対策は限られているかもしれません。M8、M9クラスの地震は、多分予見しうる将来に再び襲ってくることがあるはずで、それに対する備えは必要ですが、さすがにM10クラスとなると、現代文明の存続している間に発生する可能性もそんなに高いとは言えないし(もし来たら、現代文明への致命傷になるかも知れませんが)、「ナマズさん、おとなしくしていて」と念じるくらいしか、対策もなさそうに思えます。
2012.11.23
コメント(0)
-
子は泣くもの
泣き叫ぶ乳児にブチ切れてクレーム……さかもと未明の“搭乗マナー”が物議テレビ番組などでコメンテーターとしても活躍するマンガ家のさかもと未明が雑誌「Voice」に寄せた「再生JALの心意気」と題した記事が、ネット上で物議を醸している。同記事は、さかもとが今夏に搭乗したJAL国内線の飛行機の中で起きた出来事を記したもの。記事によれば、さかもとは機内に同乗していた1歳くらいの乳児が泣き叫んでいたことに耐えられず「ブチ切れて」しまい、 「もうやだ、降りる、飛び降りる!」と、着陸準備中にもかかわらず席を立ち、出口に向かって走り始めたのだそう。そしてさらに、乳児の母親に「お母さん、初めての飛行機なら仕方がないけれど、あなたのお子さんは、もう少し大きくなるまで、飛行機に乗せてはいけません。赤ちゃんだから何でも許されるというわけではないと思います!」と告げたのだという。そして、飛行機が着陸した後もさかもとはこの一件について納得がいかなかったようで、JAL側に対応に関するクレームを入れるとともに、航空法や飛行機の現状を知るべく広報部に取材を申し込んだそう。整備中の機体などを見学しながら、広報担当者への取材を通じ、なぜ今回のようなことが起きたのかについて確認したという。記事内でさかもとは、泣き叫ぶ乳児を隔離するために防音壁のある個室を設けることは航空法の規定によりできないことや、機内での乗客マナーの周知は冊子を配布して行なっていることなど、取材して得た情報を紹介するとともに、「搭乗マナーや機体の工夫について、議論すべき余地はまだまだあるはず」「航空法や搭乗規定、機内の装備だって数十年前につくられたそのままじゃなく、改善できるところはすべき」と問題提起した。さかもとが、記事を通して最も伝えたかったのは、おそらくこの「議論すべき余地」についてだろう。「いやだなあ。みんなに『嫌なおばさん』と思われる。でも、本当にそう思うんだもの」と、複雑な思いがありつつも、問題を提起して、議論が行われることを望んでの行為だった、と読むこともできる。しかし、さかもとの意に反して、ネット上ではさかもとの振る舞いに対する辛辣なコメントが多く上がっている。「ただの『嫌なおばさん』じゃなくて『迷惑なおばさん』ですね」「これはひどい。JALの問題にすり替えられているが、要は筆者の愚痴」「うわあ…。赤ちゃんの泣き声を許容できない心の狭さにも、赤ちゃんをあやすお母さんへの気遣いのなさにも驚くが、『私のようなクレーマーのわがままを聞くな』とか『航空法を改正しろ』とか意味がわからん…」などといった批判的な意見が多数見られたほか、脳科学者の茂木健一郎氏も「さかもとさん、これはないよ。無茶苦茶」「だいたい、1歳の赤ちゃんのふるまいを、コントロールできると思っている大人がいることが信じられない」と苦言。弁護士の落合洋司氏も「気持ちはわかるが赤ちゃんが泣くのは仕方ないのでは。昔から、泣く子と地頭には勝てぬ、いうくらいで」とコメントしている。---”クレーム騒動”話題のさかもと未明、機内での違反行為について謝罪……警察に出頭していた搭乗した飛行機内でのクレーム騒動を記した記事で物議を醸していたマンガ家のさかもと未明が、同件について自身の公式ブログで言及。非難を浴びている自身の違反行為について謝罪するとともに、警察に出頭したことを明かしている。(中略)さかもとは21日付けのエントリーで、自身の記事が話題になっていることについて触れ、「わたしはモンスター・クレーマーと言われても、わたしの発信した言葉、行動、クレームが議論のきっかけにさえなっていただけたらと記事を書いたので、すこしタイムラグはありましたが、こんなに話題にしていただき、本当にありがたく思っています。作家冥利につきます」とコメント。「赤ちゃんが泣きすぎないようにする知恵や、どうしても必要があるとき以外、何歳くらいから飛行機に乗せたらいいか、赤ちゃんの安全面と周りへの配慮を含んだ常識的な親の判断規準について、広く議論したいです」と、記事で伝えたかった自身の考えを改めて示した。また、着陸態勢に入ったあとに通路に出たことについては、「批判していただき、改めて反省するところがあった」とし、「本日2012年11月21日五時、都筑警察署に出頭して、三輪慎二さんに記録作成をお願い申し上げました」とのこと。「JALの方には報告していたので、特に処罰はないのかと思っていましたが、広く世に発言する立場の人間として、自分かした過失に対しては、お目こぼしに甘えたり、芸能人だからと特権に浴したりせず、自ら身をただして、進んで相応な処分をうけなくてはいけない、それが発言者の責任だし、さかもと未明の美学だからです」との考えを示すとともに、「違反行為については本当に申し訳ありませんでした」と改めて謝罪している。---さかもと未明というのは、典型的な極右文化人の一人ですが、案の定、自身にとって「好ましくないもの」への許容度が著しく低いんだな、と思いました。その挙句に、批判を浴びたら「警察に出頭してきた」って・・・・・・、そりゃもちろん、着陸態勢に入った後でシートベルトを外して立ち上がることは、飛行機への搭乗ルールとしては失格であり、批判を浴びるのは当然ですが、社会的批判=刑事罰じゃないのに、これまた短絡的な行動。何ヶ月も前のそんな行動について、出頭された警察も困っただろうに。「お母さん、初めての飛行機なら仕方がないけれど、あなたのお子さんは、もう少し大きくなるまで、飛行機に乗せてはいけません。赤ちゃんだから何でも許されるというわけではないと思います!」これはすごい理屈ですよ。はっきりいって、赤ちゃんは泣くのが仕事、こんなことを言われたら、赤ちゃん連れたら、どこにも行けないってことになってしまいます。ただ、乳幼児に対してこういう反応を示す人は、世の中に一定数存在することも事実です。子どもの泣き声というのは、私が思うに子どもを育てた経験があるかないかで、「耐性」が変わってくるんじゃないかと思います。私自身は、うちの子が1歳9ヶ月のとき、北海道旅行で初めて飛行機に乗せました。幸いなことにあんまり泣き叫んだり暴れたりという記憶はないです。唯一、ある宿で相棒が一人で風呂に行ってしまったら、子どもが「マーマ!マーマ!」と大騒ぎして泣き叫んで、挙句の果てに叫び声とともに吐いてしまったことがありました。畳の上にでも吐いていたら、ある種の大惨事になるところでしたが、偶然にも吐いた場所が部屋の入り口のたたきだったので、おおごとにはなりませんでしたが。しかし、そういう大掛かりな旅行のときではなくて、ちょっと出かけた先で子どもが泣き叫んで立ち往生したことはいくらでもあります。だいたいにおいて、「疲れた、眠い」攻撃が始まったときですね。そういうときに、隣から「うるさい、あんたは子どもを外に連れてくるな」といわれたら、ちょっとめげますよね。幸い、面と向かってそんなことを言われたことはありませんが。北海道旅行くらいなら、飛行時間も1時間半程度なので、子どもも十分耐えられます。しかし、これが海外となると、話が変わってくるでしょう。私が過去何回かメキシコ、南米にいったとき、当然のことながら乳幼児を連れた乗客が同じ飛行機に乗り合わせていることは、多々あります。子どもが大騒ぎをするのに遭遇することも、当然あります。あれはメキシコに行ったときだったかなあ、3~4歳の女の子が、猛烈に騒いでいたことがありました。米国西海岸からメキシコ市まで、4時間以上かかるので、小さな子は退屈しないで過ごせる限界を超えています。おかあちゃんは、疲れて子どもを無視して一人でぐったり寝ていたから、なおヒートアップ。日本人の子だろうがメキシコ人の子だろうが、ぐずれば同じだということが、よく分かりました。
2012.11.22
コメント(17)
-
ヒトの知性
ヒトの知性、6千年前ピーク? 米教授「狩りやめ低下」人類の知性は2千~6千年前ごろをピークにゆっくりと低下し続けているかもしれない――。こんな説を米スタンフォード大のジェラルド・クラブトリー教授が米科学誌セルの関連誌に発表した。教授の論文によると、人類の知性の形成には2千~5千という多数の遺伝子が関係しており、ランダムに起きる変異により、それらの遺伝子は、働きが低下する危険にさらされている。一瞬の判断の誤りが命取りになる狩猟採集生活を送っていたころは、知性や感情の安定性に優れた人が生き残りやすいという自然選択の結果、人類の知性は高まっていった。---なかなか興味深い説ではありますが、ちょっと賛同はできないなと思います。「知性」というのはなかなか定義の難しいものです。単なる知能とも、知識ともちょっと違う。知能と知識と性格の総合体とも呼ぶべきものが知性であろうと思います。(もっとも、この学者は英語で論文を書いたはずですが、原文ではどういう単語なんでしょうね。日本語と英語では、微妙なニュアンスに差があると思いますので)純然たる大脳の知的能力、という意味なら、記事のようなこともあり得なくはないかも知れません(後述するように、私は懐疑的ですが)。ただ、「知性」ということになると、知識という要素も無視できません。知識は、純然たる能力ではなく、データの蓄積です。個人だけでなく、集団による知識の蓄積と継承が大きくモノをいいます。どう考えたって6000年前や2000年前より、現在の方が知識の蓄積は進んでいます。さて、では純然たる知的能力という面ではどうでしょう。知識の蓄積はその後進んでいても、大脳の能力は6000年前か2000年前頃がピークだったのでしょうか。私にははっきりしたことは言えませんが、「一瞬の判断の誤りが命取りになる狩猟採集生活を送っていたころは、知性や感情の安定性に優れた人が生き残りやすいという自然選択の結果、人類の知性は高まっていった。」というのは、どうかなと思うのです。狩猟はともかく植物の採集に関しては、一瞬の判断が命取りになるとは思えない(農耕生活と比較して、の話です)し、狩猟だって、一瞬の判断が命取りになるような獲物なんて、そう滅多にいるものではないでしょう。どうも、「狩猟採集生活=マンモスみたいな手強い相手ばかりを狩猟する人たち」というような、あり得ない前提がちらついて見えてしまいます。狩猟採集生活を送る人間集団は、現在でも皆無ではありません。アフリカ南部のサン族(いわゆるブッシュマン)とか、オーストラリアのアポリジニとか、南米アマゾンの諸民族など。この説が事実だとすれば、現在も狩猟採集生活を送っている彼らの方が、それ以外の人類の平均より知的能力が高い、ということになります。知的な能力に関して、狩猟採集民族もそれ以外の民族も、何も差はありません。能力が劣っているわけでも、優れているわけでもないんじゃないかと思われるのですが、このあたりはちゃんと検討したのでしょうかね。ずっと以前に書いたことがあるのですが、ヒトのヒトたるゆえんは、直立二足歩行を行うこと、です。ヒト以外に直立二足歩行を行う動物はいません。400万年前にアフリカにいたアウストラロピテクス、いわゆる猿人は、脳の発達から言えばチンパンジーと大差がありませんでしたが、古生物学上、アウストラロピテクスは疑問の余地なくヒトの仲間であって、猿(類人猿)ではないのです。なぜなら、アウストラロピテクスは、ほぼ完全に直立二足歩行をしていたから。つまり、ヒトは二足歩行をするようになったからヒトになったのであって、知能が発達したからヒトになったのではないのです。知能の発達は、二足歩行の後、二次的に獲得された能力です。では、ヒトの知能はいかにして発達したか。二足歩行によって前足(手)が自由になったからだと言われています。もともと、猿(特に類人猿)は手が器用で知能の高い動物ですが、ヒトは直立二足歩行によって、手が完全に自由になり、その手を最大限に使うことが、脳の発達を促したのだと考えられています。ヒトのヒトたるゆえんは直立二足歩行ですが、人類の知能の源泉は手先を使うことにあり、なのです。狩猟採集生活か農耕生活あるいは現代文明かということより、どれだけ手先を使うか、ということの方が知能の発達には影響が大きかったと思われるのです。
2012.11.20
コメント(16)
-
安倍晋三は、批判は聞きたくないらしい
フェイスブックをやっていない人はアクセス不能ですが、安倍晋三のフェイスブック公式チャンネルがあります。その11月4日の記事に、こんなことが書かれています。明日11月5日(月)朝7:40前後~TBS『みのもんたの朝ズバ!』へ生出演いたします。自民党総裁選挙直前に、やはり生でこの番組に出演させていただいたのですが、番組の中で「街の声は・・・」と称したコーナーで「安倍元首相に期待するか」と街ゆく人々にインタビューしているシーンが忘れられません。「安倍さんは結局(首相在任中に)何もしなかった!」などのコメントを取り上げ、実に八割の方々が「安倍晋三には期待しない」とのご意見でした。(その後、インターネット等を通じ、「あの報道は明らかにおかしい」「絶対に情報操作している」「親中派の安倍おろしとしか考えられない」等の意見とぶつかり、反日メディアへの抗議行動へつながり、TBSがデモ隊に取り囲まれたのは記憶に新しいと思います。)また、総裁選挙翌日の朝の報道では、みのもんたさんに「カツカレーなんて食ってる場合か!」と激しく檄を飛ばしていただきました(笑)『番組作りには本当の国民の声が反映されるべき!』との大きなうねりが起きつつあります。その意味では皆様に積極的に番組に意見を伝えることも、草の根の声を活かしていくことに繋がるのではないでしょうか。TBSもそのために視聴者センターを設けています。TBS視聴者センター(原文は電話番号記載)---要約するとテレビが「街の声」として取り上げたうちの8割が「安倍晋三には期待しない」という意見だったのはおかしい、情報操作だ、抗議しろと、言っているわけです。さて、安倍晋三に期待しない、という声が8割というのは、本当に「おかしい」「情報操作」なのでしょうか。そもそも、安倍が自民党の総裁選に勝ったときも、議員票では勝ったものの、一般党員投票では大差で負けていました。つまり、国会議員を除く一般党員の間では安倍は人気がない、という明白な事実があります。では、自民党員でもない一般国民の間ではどうでしょう。毎日新聞11月19日付世論調査野田佳彦首相と自民党の安倍晋三総裁に関し、「どちらが次の首相にふさわしいか」を聞くと、安倍氏を挙げた人が22%、野田首相20%でほぼ拮抗(きっこう)した。民主支持層の79%が首相を挙げたのに対し、自民支持層で安倍氏を挙げた人は66%。「どちらもふさわしくない」が53%に上った。---産経新聞11月19日付世論調査衆院選後に「日本のリーダーとして最もふさわしい人」では、国政進出を否定している維新代表代行の橋下徹大阪市長が15・6%で首位。2位は自民党の石破茂幹事長(13・0%)、3位は同党の安倍晋三総裁(11・9%)。維新代表の石原慎太郎前東京都知事は10・5%で5位だった。---共同通信11月19日付世論調査「野田佳彦首相と安倍晋三自民党総裁のどちらが首相にふさわしいか」は、安倍氏35・0%に対し野田首相32・1%と拮抗した。---民主党政権がこれだけ国民の支持を失っているにもかかわらず、野田と安倍のどちらが首相にふさわしいかとなると、支持率が拮抗しており、いずれも5割にはるかに届かない数字です。産経の調査では、野田の名前は出てきません(ランク外なのか選択肢に入っていなかったのかは不明)が、安倍は橋下、石破に次ぐ3位です。毎日の調査が一番わかりやすいですが、「どちらもふさわしくない」が53%、つまり安倍じゃダメだ(安倍でも野田でもダメだ、も含めて)という人がだいたい7割なので、件のテレビ番組で安倍に期待しない意見が8割というのは、おおむね世論の動向とほぼ同じと見られます。はっきり言ってしまえば、「安倍支持」で熱狂しているのはネットウヨクだけ。現実世界で安倍を支持している人は、そんなに多くはないのが現実です。ところが、安倍はその現実を直視するのが嫌なのか、報じられるのが都合が悪いからか、こうやって抗議電話を煽る。もちろん、政治家として、支持率が低いから総裁を降りますとか、この政策はやめます、なんてことはあり得ないでしょう。わたしだって、政治家じゃないけど、このブログで圧倒的少数意見だとしても、自分が正しいと思うことは主張します。だけど、支持する声が少ないという現実は現実として直視する、あるいは受け流すこともできず、テレビ局の陰謀にして抗議を煽るようでは、次の首相になる可能性が高い人物としては、あまりに肝っ玉が小さすぎるし、頭悪そうにしか見えません。(いや、頭悪「そう」じゃなくて・・・・・・)ちなみに安倍のフェイスブックの記事には、「秘書です」との書き出しで始まっているものと、そうでないものがあります。秘書ですというのは、秘書が代筆しているということでしょう。そう書かれていないものは本人が入力したのでしょうか。だとすると、件の記事は本人がアップしたということになりますが、果たして。
2012.11.19
コメント(9)
-
こういう事業こそ、仕分けすれば良かったのに
クジラの肉、もっと食べて! 在庫ありすぎ、学校給食にも売り込む政府が国策として進める調査捕鯨で捕獲したクジラの鯨肉が、個人向けの通信販売や居酒屋など外食産業のメニューとして、2013 年にも登場する見通しになった。学校給食のメニューとしても、本格的に復活する見通しだ。水産庁所管の財団法人で、調査捕鯨の実施主体「日本鯨類研究所」(鯨研)が、赤字が続く調査捕鯨の収支改善策として、新たに個人や外食産業のほか、学校給食向けに鯨肉の直接販売を始める方針を表明したからだ。■調査捕鯨の赤字解消めざす調査捕鯨の鯨肉は現在、年間の消費量に匹敵する約4000トンの在庫を抱え、鯨研は累積赤字の解消を求められている。国内の鯨肉は調査捕鯨のほか、日本沿岸で小規模に捕獲される「小型沿岸捕鯨」と呼ばれる商業捕鯨の鯨肉が一部地域で流通しているが、居酒屋や学校給食のメニューとしては一般的ではない。水産庁と鯨研は、鯨肉を個人や居酒屋、学校給食に売り込むことで在庫を減らし、安定財源を得ることで調査捕鯨を継続する考えだ。今後、一般向けに鯨肉を売り込むPR活動などが始まるという。水産庁が鯨研に委託する調査捕鯨は、鯨研が調査後に解体した鯨肉を販売し、翌年の調査経費に充てることになっている。ところが鯨研の調査捕鯨は、鯨肉の販売不振で2005年度以降、赤字傾向が続いている。鯨研は鯨肉の販路拡大で3年後の2014年度に2011年度比5%(1億4800万円)の増収を目指すほか、老朽化した調査船の省エネ化や鯨肉生産の機械化などで10億円のコスト削減も行い、3か年で3億円の黒字達成を目指す。■販路の縮小で販売不振日本はかつて資源調査の調査捕鯨でなく、クジラを販売目的の商業捕鯨として捕獲していた。ところが1982年、国際捕鯨委員会(IWC)が、シロナガスクジラなど絶滅が懸念される13種の大型鯨類の商業捕鯨を禁止。日本は1987年、商業捕鯨から撤退したが、鯨研が同年から南極海などで資源調査を目的に調査捕鯨を行っている。IWCは調査捕鯨を加盟国の権利として認めているほか、解体後の鯨肉の販売も認めているからだ。鯨研の調査捕鯨の経費は年間45億~50億円かかり、鯨研が解体後の鯨肉を販売し、翌年の調査費に充てている。鯨研の鯨肉販売額は、かつて50億~60億円あったが、近年は販路の縮小に伴う販売不振で2011年度は28億円に半減。2010年度に反捕鯨団体「シーシェパード」の妨害で調査捕鯨を中断した影響で、11億3306万円の赤字に転落した。農林水産省が赤字補填と妨害対策のため、東日本大震災の2011年度復興予算に約23億円を計上し、批判を浴びたのは記憶に新しい。■環境保護団体は「調査捕鯨」を批判このため、鯨研は鯨肉の流通経路の縮小で入手が困難となっている居酒屋など飲食店向けに鯨肉を直販し、潜在需要を掘り起こす収支改善策をまとめた。かつて学校給食などで鯨肉を食べた一般消費者向けに高級商品を開発し、カタログ通販も行う。これまで調査捕鯨の鯨肉は流通が限られ、「和牛の中級クラス並み」と高価になったこともあり、居酒屋などでは一般的ではなかった。年間100トン程度の消費にとどまる学校給食では値下げなどで200トン程度と倍増を目指す。水産庁と鯨研は、2012年12月にも始まる今冬の調査捕鯨から3カ年で収支を抜本的に改善することを目指す。IWCに加盟国の権利として認められている調査捕鯨だが、実際に行っているのは世界で日本だけで、環境保護団体は「擬似商業捕鯨だ」と批判している。これに対して、商業捕鯨再開を目指す日本捕鯨協会は「世界の鯨類が食べる海洋生物の量は世界の漁業生産量の3~5倍に上る。クジラを間引くことで人間が魚を利用することができる」などと反論している。---捕鯨に関する問題は過去に何回か取り上げたことがありますが、私は基本的に調査捕鯨反対論には与しませんし、シーシェパードなど過激な捕鯨反対派の行動も常軌を逸していると思っています。商業捕鯨が禁止になった大きな理由は、過剰捕獲による絶滅の危険ですが、少なくとも捕鯨の対象となるミンククジラに関しては、かなり個体数が回復して、絶滅の危険があるような状態ではないと言われます。(シロナガスクジラなどは依然として絶滅の危機にあるようですが)父が鯨肉を好きだったので、父の生前は年に1~2回程度は実家で鯨肉を食べる機会がありました。私も、鯨肉は嫌いじゃない。しかし、父の死後は、1回も鯨肉は食べていません。嫌いじゃないけど、そこいらのスーパーでは売っておらず、わざわざ探してきてというほどまで好きではないからです。私は、タッチの差で給食に鯨肉が出た経験のない世代です。出たのに覚えていないだけかも知れませんが。相棒は、私より1学年上ですが、給食で鯨肉を食べた世代です。改めて聞いたところ、鯨肉が給食に出たのは「小学校1年まで」とのことなので、1学年下の私が給食で鯨肉を食べた記憶がないのは、時系列的に辻褄が合います。もっとも、私は東京出身ですが、相棒は他県出身です。私の相棒は、給食の鯨肉はそんなに嫌いじゃなかったそうですが、学校給食で食べた鯨肉っていうのは「おいしくはなかった」と言う人が多いです。だからでしょうか、日本で商業捕鯨が打ち切られたのは1988年のことですが、学校給食から鯨肉が消えたのは、相棒と私の記憶が正しければそれより15年も前のことになります。私も、給食はともかく、鯨ベーコンや鯨の大和煮缶詰などは、子どもの頃どこでも売っていたし、ごく当たり前に食べていました(「大和煮」という名称も、いまや死語かもね)。しかし、正直言って鯨ベーコンをおいしいと思った記憶はありません。どう考えたって、豚肉の本物のベーコンの方がおいしい。大和煮の缶詰なんてのは、癖が強くておいしくない肉を濃い味で誤魔化すために考案されたようなものですから、どんな肉を使ったって味は同じでしょう。そう考えると、鯨肉が珍重されたのは日本人一般に動物性タンパク質が手に入らなかった時代に、やむを得ずという側面が強かったのではないかと思います。もっとも、どんな肉でもおいしさには個体差があり、同じ個体でも部位による差があります。近年に食べた鯨肉を、そこそこおいしいと思ったのは、それが比較的高級肉だったからでしょうし(自分で買ったわけじゃないから、値段は知らないですけど)、学校給食の鯨肉を多くの人があまりおいしいと思わなかったのは、何でもありの安物肉だったからでしょう。私は鯨肉の流通状況には疎いですが、在庫がだぶついているということは、比較的高値で売れるおいしい肉が優先して流通している可能性が高いと思います。そういう肉はおいしいけれど、もし鯨肉が大量流通を始め、高級でない肉も出回り始めると、たちどころに・・・・・・、ということも考えられます。結局のところ、今の時代に鯨肉は日本人にとっての必需品ではまったくなくなっており、極小の存在意義しかなくなっている、ということです。この現実は動かしがたい。たとえば米や小麦とは重さがまるっきり違います。であるなら、それを公費を使ってどこまで維持するのか、ということは問われるべきじゃないのかと思いますね。引用記事にもありますが、震災復興予算を調査捕鯨に流用なんて酷い話もありました。こういうのこそ、事業仕分けの対象にすればよかったのに、と思います。なお、上記引用文の「世界の鯨類が食べる海洋生物の量は世界の漁業生産量の3~5倍に上る。クジラを間引くことで人間が魚を利用することができる」という日本捕鯨協会の「反論」は噴飯ものでしかありません。鯨類が地球上に姿を現したのは、4000万年以上前のことです。それ以来、鯨はずっと海洋の食物連鎖の中で繁栄してきたのです。人間が大規模な捕鯨を始めたのは、たかだか数百年前の話で、鯨の歴史はそれより10万倍くらい長い。「世界の鯨類が食べる海洋生物の量は世界の漁業生産量の3~5倍」というのが事実かどうかは私には分かりませんが、事実とするなら、それこそが現在の海洋における自然な生態系のあり方でしょう。それを人間が手を加えて「こうすべき」なんてのは、全知全能の神でもあるまいし、傲慢にもほどがある。
2012.11.18
コメント(6)
-
数合わせ新党
維新、太陽と合流=新代表石原氏、代行に橋下氏―基本政策で合意日本維新の会は17日、大阪市内で開いた全体会議で、太陽の党との合流を決めた。太陽は解党し、党名は「日本維新の会」を残す。新代表は、太陽共同代表の石原慎太郎前東京都知事とし、維新代表だった橋下徹大阪市長は代表代行に就いた。また、維新の国会議員団代表には太陽の平沼赳夫共同代表が就任。松井一郎幹事長(大阪府知事)と、浅田均政調会長は続投した。石原氏は全体会議に出席し、「第三極では困る。第二極にならなければならない。小異を捨てて大同で団結し、最初の一戦を戦おう」とあいさつ。橋下氏は「石原総大将がわれわれのリーダーになったのだから、魂を込めて、あと1カ月、死に物狂いで戦っていく」と強調した。全体会議では、松井氏が太陽と合意した基本政策を報告。消費税の地方税化や道州制の実現、環太平洋連携協定(TPP)交渉参加、新しいエネルギー需給体制の構築―などを掲げた。ただ、維新が太陽との合流前に衆院選の公約として検討していた「2030年代の原発全廃」は、合意に含まれなかった。この後、石原、橋下両氏は記者会見。橋下氏は「お互いに理解を深めて、最終的にグループ全体で一つの考えになった。自民党や民主党に比べれば、はるかにわれわれの方が考え方が一致している」と強調した。---突然の衆議院解散からわずか1日、各政党の迷走が激しさを増しているようです。太陽の党は解党とのことですが、そもそも結党と報じられたのが今月14日。たった2日で解党するなら、最初から結党などしなければいいのに。ちなみに、「太陽の党」で検索しても、グーグルでは「太陽の塔」に自動修正されちゃうくらいの状態です。維新の会は脱原発、石原慎太郎は原発推進。この差はかなり大きいと私は思うのですが、「維新が太陽との合流前に衆院選の公約として検討していた『2030年代の原発全廃』は、合意に含まれなかった。」ということは、合同のために維新の会は脱原発方針をあっさり反故にした、ということなのでしょう。維新の会にとっての脱原発は、その程度の軽い主張だったようです。この数日、みんなの党、維新の会、減税日本、石原新党(太陽の党)と「第三極」の各党がめまぐるしく集合離散を繰り返し、合併と報じられた数日後に白紙撤回とか、まるっきりわけが分からない状態になっています。昨日のこの報道だって、1週間後にはどうなっているのか、見当もつきません。ただ、はっきりいえることは、いずれの党も「右派」という以外は個別の政策はバラバラだということ。前述の原発政策がその一例です。減税日本なんて党は「減税」が党名に掲げるほどの看板政策のはずなのに、その部分で政策が相容れない維新の会に一生懸命擦り寄っている。こんな各党が、大同団結の名の数あわせでひとつにまとまっても、それを野合と呼ばずして何と呼ぶのでしょうか。
2012.11.17
コメント(20)
-

ティエラ・クリオージャ 3年ぶりの演奏より
私は、現在3つのフォルクローレグループに参加しています。このうちのひとつ「ティエラ・クリオージャ」は、2009年4月以来、中心メンバー夫婦の海外赴任のため休業状態になっていました。しかしこの度、彼らが帰国。3年半ぶりに復活しました。事前練習は1回だけ、本来5人編成のところ一人欠場と、かなりキビシー条件の中での演奏ですが曲は、ボリビアのカルナバルのメドレー(サンタクルスの花~カルナバル・グランデ)です。我ながら、やっぱりサンポーニャの角度がパタパタと動いており、「正しい吹き方」になっていないな、とは思うのですが・・・・・・。この動画のスペイン語でのタイトルは、Seleccion de carnavalitosにしました。カルナバリートは、カルナバルの縮小語尾型です。実は「カルナバリート」という言葉が意味する音楽は、ボリビアとアルゼンチンでは違います。ボリビアでは、このような6/8拍子の音楽をカルナバル、あるいはカルナバリートと呼びます。元は、東部低地のサンタクルス地方の「カルナバル・クルセーニョ」から来ているようです。一方、アルゼンチンのフォルクローレでは、2拍子系の音楽を「カルナバリート」と呼びます。代表曲として「花祭り」(El Humahuaqueño)が知られています。アルゼンチンで「カルナバリート」と呼ばれるものとほぼ同じ音楽はボリビアとペルーにもあるのですが、名前はワイニョ(ボリビア)/ワイノ(ペルー)です。同じスペイン語を使っていても、国が違えば単語の意味が変わったり、同じものを指す単語が変わったりする典型です。YouTubeで単にcarnavalitoだけで検索すると、アルゼンチンでカルナバリートと呼ばれている音楽ばかりがヒットしますが、これはボリビアよりアルゼンチンのほうが大国で、YouTubeにアップされている動画もアルゼンチンのほうが多いからでしょう。
2012.11.16
コメント(0)
-
せめて、最低限の定数是正をしてから解散せよ
衆院、16日解散=来月4日公示・16日投開票―自民、定数削減に協力・政権に審判野田佳彦首相は14日、自民党の安倍晋三総裁らとの党首討論で、16日に衆院を解散する意向を表明した。首相は、来年1月召集の通常国会で衆院議員定数削減の実現を確約するよう要求。自民党も定数削減に協力する方針を決めた。政府・民主党は、首相や輿石東幹事長が出席した三役会議で、衆院選日程を12月4日公示―16日投開票とすることを決定した。2009年9月に政権を獲得した民主党は、初めて与党の立場で国民の審判を受ける。政権奪回を目指す自民、公明両党のほか、「第三極」として連携を探るみんなの党、日本維新の会、太陽の党などがどこまで勢力を伸ばすかが焦点だ。衆院選は東京都知事選と同日選となり、各党は候補者擁立や公約づくりを急ぐ。ただ、民主党内には年内解散に反対論が噴出しているほか、環太平洋連携協定(TPP)交渉参加の争点化を図る首相の姿勢に反発が拡大。小沢鋭仁元環境相が離党して日本維新の会への合流を決めるなど、解散を前に混乱が広がっている。首相は党首討論で、安倍氏に対し、「近いうちに信を問うと言ったことにうそはなかった」と強調。赤字国債発行に必要な特例公債法案の16日までの成立と、最高裁が「違憲状態」とした衆院小選挙区の「1票の格差」の是正と定数削減に協力を要請した。また、定数削減を来年の通常国会で実施し、それまでの間は国会議員歳費を2割削減するよう提案した上で、「通常国会で定数削減を必ずやると決断してもらえるなら、16日に解散してもいい」と表明した。さらに、首相は踏み込んで「後ろに区切りを付けて結論を出そう。16日に解散をする」と明言した。公明党の山口那津男代表に対しても、同様に呼び掛けた。自民党はこの後、安倍氏や石破茂幹事長らが党本部で対応を協議し、首相の提案を受け入れることで一致した。安倍氏は都内の講演で「首相の提案に全面的に協力する」と表明した。山口氏も記者会見で「解散後の国会で(定数削減を)行うなら十分合意は可能だ。努力したい」と述べた。年内解散に否定的だった輿石氏は記者団に「首相の専権事項で首相が判断したのだから、それでいいではないか」と述べた。---3年前に、民主党に大いに期待した人も、私のように、自民党よりはマシと消去法的に支持した人も、民主党に反対した人も、この3年間は「とてもがっかり」というのが現実ではないかと思います。私自身もそうです。3年前、総選挙で民主党が勝った日に、このブログで私はこう書きました。私は民主党は好きではないけれど、それでも自公政権よりは何割かマシと思っていますので、この結果は非常に喜ばしい。しかし、問題はこれからです。政権交代も大事ですが、そのあとどんな政策を実行していくのかは、もっと大事です。民主党政権になったからと言って日本が劇的に変わるとは思えませんが、多少は期待しています。多くの人々の期待に背く結果となれば、次回総選挙では民主党が今回の自民党のような結果になるかもしれません。なんだか、危惧したとおりの結末に至ってしまったようです。政権交代後どんな政策を実行したか、結果としてみれば(自民党と違うことは)ほとんど何も実行しなかったということに尽きます。高校無償化と子ども手当(現在は元の児童手当の名称に戻っている)くらいですね、実行したのは。しかも、高校無償化はともかく、子ども手当てには、私はあんまり賛成ではありませんでした。今の野田政権の現状を見れば、自民党政権時代とほとんど何も変わりません。とはいえ、その自民党は野党転落後、さらに右旋回を続け、今では極右政党と化しています。野田政権はダメダメですが、次に予想される安倍政権は、もっと悪いことになりそうです。およそ政治というものに私は何の期待も抱けなくなっています。それはともかく、野田首相がとうとう解散を決めたそうで。解散は首相の専決事項だから、首相が解散するって決めたなら、それはそれでいいのでは、と言いたいところですが、第一に定数削減には反対です。第二に、1票の格差を最低限是正してから解散すべきでしょう。最高裁からは、すでに1票の格差について、違憲という判決が出ています。それをなんら是正せずに次の選挙をやる、なんてことが許されていいのか。0増5減という定数是正措置に賛成ではないけれど、今の票の格差を完全放置したままで解散するよりはまだ、0増5減だけでもやるほうがマシです。選挙の後で定数是正を実現というのは、「もう一回憲法違反の選挙をやる」ってことです。本質的におかしいといわざるを得ないでしょう。特例公債法案は16日までに可決成立させるそうですが、それができるなら0増5減も早く成立させろと言いたいですね。
2012.11.14
コメント(14)
-
案外その程度なのか
ガラケーの割合66% エルネットは12日、「宅ふぁいる便」ユーザーを対象に「携帯電話に関するアンケート」を行い、最も使用頻度の高い携帯電話は全体の65.9%が「フィーチャーフォン」で、33.4%が「スマートフォン」と回答し、まだまだフィーチャーフォンが主流を占めていることがわかった。この調査は同サービスのユーザー、男女446人を対象に実施。最も使用頻度の高い携帯電話の種類が「フィーチャーフォン」と回答した人に、スマートフォンに興味があるかどうかを尋ねたところ、「(興味が)ある」は全体の70.1%、「(興味が)ない」は29.9%となった。さらに「スマートフォンに切替える時期を決めているかどうか」では、「いいえ(切替え時期を決めていない)」66.0%、「スマートフォンには切替えるつもりはない」22.8%、「はい(切替え時期を決めている)」11.2%と回答。興味はあっても、実際に切替えるとなると、話は別のようだ。切替える時期を決めていない理由では「使いこなせるかがわからない」、「今の携帯がまだ使える」、「料金が高い」などが、切替えるつもりがない理由では「パソコンで十分」や「必要な機能は今の携帯で十分」、「料金が高い」などが挙がった。(以下略)---販売台数でスマートフォンが従来の携帯を超えたのは去年7月、現在ではもうスマホのシェアは8割前後に達しています。が、しかし、販売台数はそうでも、世の中一般での普及割合は、まだ従来の携帯が2/3を占めているそうで。もっとも、私自身の体感としては、通勤電車内で携帯をいじっている人の中でのスマホの割合は1/3より多そうな感じはします。半分を超えている気がします。もっとも、電車内で携帯をいじっているというのは、ある程度使用頻度の高いユーザーでしょうから、世間一般の平均よりスマホの割合が高い、という可能性は考えられます。実は、私自身も従来型の携帯を使っています。私は今の携帯をもう4年使っていますが、あと1年くらいは使い続けるだろうなあ。わが相棒なんか去年夏に新しい(従来型)携帯に変えたばかりなので、まだまだあと3~4年は使い続ける見込みです。確かに、従来型の携帯は機能が限定されます。いつだったか、山の上からフェイスブックに書き込みをしたら、涸沢の「涸」の字が変換できないんですよ。辞書に入っていないのです。どれだけ単語不足の変換ソフトだよ、と思いました。仕方がないから、「から沢」と書き込むしかなかった。でもね、山の上から本格的な長文の書き込みをするわけでなし、その程度の不都合なら、たいした不便とはいえません。何しろ私は携帯をおおむね2週間に1度しか充電しません。それで不都合がない程度にしか、携帯を使っていないのです。まず、携帯からインターネットに接続するのは山か旅行のときだけ。普段はメールのみで、携帯電話代は一番安い料金プランの基本料金(家族割で2000円以下)で納まっています。ただ、山からフェイスブックに3回か4回書き込みをしたら、それだけでその月の携帯電話代が2600円に上がり、びっくりしましたが。そんな私がスマートフォンを持っても、多分宝の持ち腐れ。何人かの人に聞くと、だいたいスマートフォンは毎日充電しないと保たないようですね。ひどいと1日1回の充電でも間に合わないようですが。せめて、1週間くらい電池が保ってくれないと、私には使いにくくて仕方がない。でも、1年後には従来型携帯に機種更新したくても、選択肢がない、という状況も考えられます。私が携帯を買い換えるのは、バッテリーがヘタって電源の持続時間が明らかに短くなったときなのですが、バッテリーがヘタったのでスマホに買い替えたら、もっとバッテリーが持たなくなった、というのでは笑い話になってしまいます。※そうそう、最近私は、旅行や山登りのとき以外は腕時計をしなくなってしまいました。時計のないところで時間を確認するのは携帯。そのために携帯の画面を確認することは、時々あります。
2012.11.13
コメント(4)
-

反原発1000000人大占拠
本日、いや日付ではもう昨日ですが、「反原発1000000人大占拠」に参加してきました。といっても、諸般の事情により途中で帰ったのですが。経産省前です。これも経産省前。このとき、3時半頃だったかな。まだ雨は降り始めたかどうかというくらいで、傘は必要ないくらいでした。経産省前から、反対側の財務省前を撮影。向こう側にも人が集まっています。日の丸を掲げて集会に参加する人。反原発集会の度に日の丸を掲げて参加する人は何人か見かけます。今回は気付いた範囲では二人だけでした。逆に、日の丸を掲げて反原発集会を非難攻撃する在特会系の連中も、今日は見かけませんでした。エイサー隊。財務省前です。反原発集会とはまったく無関係(人が少ないところを狙って撮りました)ですが、都心の紅葉もだいぶきれいになってきので。もう少し天気がよければねえ。国会前。だいぶ雨脚が強くなってきました。国会前に向けて角を曲がるところ。トロンボーンを吹いていました。国会前、といっても、まだ国会まではだいぶ距離がありますが、これ以上前には進めません。時刻は4時過ぎくらいだったかな。かなり激しい雨になりました。ここに5時頃までいて、都合により引き返しました。5時過ぎ、もう真っ暗だけど、まだまだどんどん人が集まってくる。というか、むしろこれからの時間が国会包囲の本番なのでしょうが。100万人大包囲と言っても、100万人は集まっていなかったと思いますが、どのくらいの参加者数だったんでしょう。首相官邸、国会、経産省、財務省、文科省、厚労省、外務省、東電本店、Jパワー本社などに分散しているので、全体でどれだけの参加者がいたのかは分かりません。おそらく、私が帰った5時より後の時間のほうが本番なので、その時間のほうが人が多かったんだろうと思います。東京だけでなく、今日は全国46都道府県で一斉に集会を開いているとのことでした。何で先に帰ったかと言うと、家で夕飯食べると約束したのがひとつ、そしてもうひとつは、帰りに某楽器店に寄って、新しい譜面台を買いました。これまで、フォルクローレでは譜面台を使うことはほとんどなかった(たまに歌詞カードを置く用に使うくらい)のですが、フルートのワークショップに行くようになると、譜面台が必要。いつも相棒の譜面台を借りていたのですが、これが重くて、折りたたんでもデイパックに入れられるぎりぎりくらいの長さです。そこで、もっと軽くて、小さくたためる譜面台を買ってきました。値段は4000円弱くらいでした。
2012.11.11
コメント(3)
-

ここまでは、非難に当たらないかも・・・・・・
遭難後、登山ツアー強行 旅行社、中止要請聞かず中国の「万里の長城」で3人が遭難死したツアーを主催したアミューズトラベル(東京都千代田区)が、事故後に登山を含む別のツアーを強行したことがわかった。観光庁が中止を要請したが、「ベテランガイドもいるから大丈夫」と説明し、8日に出発した。問題のツアーは、ペルーとボリビアを12日間で巡る。ペルーのマチュピチュ遺跡の近くにあるワイナピチュ山への登山がある。アミューズ社の日程表では11日に片道2時間程度で登る。標高は3千メートル近く、「一般の観光ツアーではなかなか訪れません」などとうたっている。標高2千メートル近い遺跡周辺を約6時間トレッキング(山歩き)する行程もある。アミューズ社によると、参加者は60代を中心に首都圏などの男女7人。万里の長城の事故後に参加の意思を確認したところ、キャンセルは出ず、ツアーが中止になることを心配する声の方が多かった。同社は会見などで、「南半球はこれから夏。トレッキングは険しい道ではなく、晴れていれば半袖のTシャツでもできる。同じツアーは50回以上やった」と説明した。日本から添乗員1人が同行し、トレッキングでは現地ガイド2人がつくという。---こんな危険な旅行会社がまだ登山ツアーをやるのか、と言いたい気持ちは私にもあるけれど、参加者が依然として参加を希望しているツアーを、出発直前に中止というのは、難しいだろうなというのは分かります。新規募集はとんでもないけど。問題のワイナピチュというのは、この山です。向こう側に見える山です。私自身は登っていませんが、「登山」というほどのものではないような。標高3千メートル近くとありますが、実際の標高は2750mほどのようです(資料によって標高に食い違いがあるので、正確かどうか分かりませんが)。熱帯での3000メートルですから、この高度で雪が降ることはありません。マチュピチュの入り口になるクスコの街(インカ帝国の首都でもあった)は、標高3400mほどで、マチュピチュ(標高2400mほど)には、むしろ山を下っていくかたちになります。クスコは今や人口50万近い大都市で、空港もあります。山の険しさも、尾根を歩く限りはそんなに困難そうには見えません。(登った経験がないので、あくまでも印象です)↓の北アルプス・北穂高岳(登山道は奥側の尾根に付いている)と比較して、登山道部分の斜度はそんなに差がありそうには見えません。なお、片道2時間とありますが、マチュピチュからの標高差約350メートルとすると、普通の足なら1時間程度、健脚ならそれ以下だろうと思います。「一般の観光ツアーではなかなか訪れません」というのは事実ではあるけれど、クスコからの日帰りツアーではその時間が取りにくいだけであって、特別に困難だからというわけではありません。むしろ、もし単独で行くとしたら、「標高2千メートル近い遺跡周辺を約6時間トレッキング(山歩き)する行程」こっちの方が怖いです。ただし、怖いといっても気象条件や山の険しさの問題ではありませんよ。クスコからマチュピチュまでウルバンバ川沿いに約80kmをトレッキングする人も少なくありませんが、日本の山は単独行で歩く私も、ペルーで何泊もの単独行は尻込みします。このあたりでおっかないのは、自然より人間なんだから。ただし、怖いのはあくまでも単独の場合で、団体なら人数の力があるので、まず心配の必要はないでしょう。せっかくなので、マチュピチュのその他の写真も。なお、この当時は一眼レフはもっておらず、確か小学生の頃から使っていた、レンズ固定式でズームもないカメラに普通のネガフィルムを入れて撮影していました。1989年10月下旬です。以前に何かの記事で紹介したことのある写真のはずです。ふもとの鉄道駅。マチュピチュ遺跡までは、もの凄いつづら折れの車道をバスが登っていきます。
2012.11.10
コメント(12)
-
何故、こういう失態を引き起こすのか(一部訂正)
女性の居住市読み上げ=昨年6月、男逮捕時に捜査員―失態に「憤り」・神奈川県警神奈川県逗子市で、男が元交際相手の女性を刺殺し自殺したとみられる事件で、県警が昨年、女性への脅迫容疑で容疑者(40)を逮捕した際、手続きに基づき、逮捕状に書かれていた女性の結婚後の姓や自宅住所の一部を読み上げていたことが9日、分かった。同容疑者が女性の自宅を割り出す手掛かりになった可能性があり、県警逗子署は経緯を調べている。同署によると、容疑者は昨年6月1日、今回の事件で死亡した女性(33)に「殺す」などと書いたメールを送ったとして、脅迫容疑で逮捕された。その際、捜査員は逮捕状に書かれた結婚後の名字と、少なくとも住所の「逗子市」を読み上げたという。同容疑者からストーカー行為を受けていた女性は、同署に相談した際、自分の結婚後の名字や住所を教えないでほしいと要望していた。しかし、逮捕後、女性が検察側とやりとりをした際、同容疑者が自分の新姓を知っていることを告げられ、県警に連絡。同署は陳謝し、防犯カメラの設置など対策をアドバイスしたという。---ストーカー行為による逮捕であり、被害者側から結婚後の名字や住所を教えないでほしい旨の要請が出ていた(仮に、要望が出ていなかったとしても、当然の話でしょう)にも関わらず、わざわざそれを逮捕状に書いて知らせてしまうというのは、まったく話にもならない大失態と言うしかありません。※当初、「読み上げたことがけしからぬ」と書きましたが、逮捕状は本来容疑者から求められれば、提示する義務があるようです。ということは、読み上げたことが問題ではなく、逮捕状にわざわざ新姓と新住所を記載してしまったこと自体が問題だということになります。以前にも、似たような例があって、当ブログでも記事を書いたことがあります。そのときは、加害者の両親が、被害者に謝罪するつもりで被害者の連絡先を警察から聞き出したという事例で、一応は(本人の主観では)善意から出た行動だったので、それ以上の事態には至りませんでしたが、今回は被害者の殺害という事態に至ってしまったのだから、最悪としかいいようがありません。結果的には、脅迫メールなんか無視して警察には何も言わず、黙ってメールアドレスを変更でもしておいたほうが、警察に相談して犯人を逮捕してもらうよりも安全だった、ということになっているのが現実です。これでは警察の意味がない。記事によると、住所を少なくとも「逗子市」までは読み上げたそうです。そこで中断したとするなら、被害者の住所を読み上げるのはまずい、ということを知ってはいたのでしょう。にもかかわらず、何で読んじゃったのか。「市」くらいまでなら大丈夫だと思ったのか。甘い、甘すぎるというものです。「大阪市」とか「横浜市」くらいの巨大都市ならまだしも、逗子は人口6万人にも満たない小さな街です。そこまで住所が特定できてしまった場合、その先の住所が特定される危険性は飛躍的に高まります。何しろ、この犯人はこの時点で無職だったようだから、調べる時間だけはいくらでもあったのです。報道によると、この犯人が被害者に対して付きまといを始めたのは6年前。警察が警告していったんは収まったものの、2010年に被害者が結婚すると、再び嫌がらせメールが始まった、ということです。つまり、犯人は、被害者が結婚したことを知っていた、ということです。その時点で4年も前に分かれた元彼女の結婚の事実を調べ上げて嫌がらせメールを送るほど、妄執に凝り固まって手の施しようのない人間です。そんな人間が、標的の住む市(さほど大きくもない)の名前を知ってしまったら、こんな事態を招く危険が高い、という程度のことが、どうして分からなかったんでしょうか。それにしても、もしも私がこの被害者の立場(あるいはその夫の立場)だったとしたら、一も二もなく引っ越しますね。持ち家だったら経済的な面でそう簡単に引っ越しできないとしても、犯行現場はアパートと報じられています。賃貸住宅だとしたら、犯人が執行猶予で釈放されたと知ったら、直ちに引っ越します。こういう妄執人間に住所を知られてしまったら、残念ながら解決策はそれしかないでしょう。
2012.11.09
コメント(9)
-
それでもまだ、「もんじゅ」を動かす気か
「もんじゅ、13年度中に運転再開」 原子力機構が方針高速増殖原型炉「もんじゅ」の今後の研究計画を策定する文部科学省の作業部会が8日開かれ、もんじゅを運用する日本原子力研究開発機構は、2013年度中にもんじゅの運転を再開して性能試験に入れるとの見通しを示した。原子力機構によると、設備点検を来年夏前に終了。再開に向けて機能を確認し、さらに約4カ月間かけて準備を進め、来年度中に運転再開できる見通し。40%出力試験から徐々に出力を上げる性能試験を2~3年かけて行い、その後本格運転に入るという。ただし、もんじゅの敷地内には断層があり、原子力規制委員会による調査や耐震評価などが予定されている。原子力機構は「規制委員会の対応などの状況により時期の変更はある」と説明している。---私は、「長期的な脱原発派」なので、原発全廃への筋道が明確であるなら、それまでの間に限定して原発を再稼働することはやむを得ないと思っています。しかし、脱原発への筋道がうやむやなままでの再稼働と、危険性の高い原発を再稼働することには、断固として反対です。危険性の高い原発というのは、具体的に言えば東海地震の想定震源域のど真ん中に立地する浜岡原発、あるいは活断層の上に建っている志賀原発、老朽化している原発、そして、2度も大きな事故を起こしている「もんじゅ」もその一つです。もんじゅの危険性については、以前の記事に書いているので詳細はリンク先を読んでくださいここにも危険きわまりない原発が「もんじゅ」は絶対廃炉にしなければならない最初は稼働開始から4ヶ月で火災事故、2度目は稼働開始から3ヶ月で炉内中継装置を炉内に落とす事故。「平時」ですら、そんな状態なのです。まして、稼働中に地震が来たらどういうことになるのか。何度も指摘することですが、一般の原子炉(軽水炉)で使われる冷却材は「軽水」つまりただの水です。それに対して高速増殖炉「もんじゅ」に使われる冷却材はナトリウムです。ナトリウムは、水や酸素に接触しただけで発火する危険物質です。発火してしまったら、それを鎮火させる手段は、燃え尽きるのを待つしかありません。せいぜい、未発火のナトリウムを抜き取ることで、できるだけ早く燃え尽きさせることができる程度です。(1997年の火災では、そのようにして鎮火させた)原子炉本体は窒素の充填してある部屋に置かれているので、そこからナトリウムが漏れ出しても火災は起こらない、という触れ込みですが、二次冷却系はそうではありません。1995年の火災は、二次冷却系からのナトリウム漏れが発火しています。二度の事故はいずれも地震とは無関係の「平時」の事故である点に留意すべきでしょう。それでさえも、鎮火・復旧には大変な労力を要しています。まして運転中に地震に見舞われたら、どういうことになるのでしょうか。柏崎刈羽原発は、2004年の新潟県中越地震と2007年の新潟県中越沖地震で大きな影響を受けましたが、幸い福島第一原発のような大事故には至っていません。しかし、いずれの地震でも、放射線を帯びた微量の水漏れが発見されています。これが水ではなくナトリウムだったら発火しているはずです。新潟県中越沖地震では、変電設備の火災が発生していますが、これとナトリウム漏れによる発火のダブルパンチとなったかもしれません。地震の混乱の中で、他にも火災が発生している中で、水では消火できないナトリウム漏れ火災を速やかに鎮火させる、というのはまず不可能なことのように思えます。いくら二次冷却系からの発火でも、鎮火に手間取れば、どんどん燃え広がって、最後は全部焼き尽くすことになってしまうでしょう。地震のない国フランスでさえ、あれだけ原発に依存していても、高速増殖炉の開発は中止しました。地震国日本がいまだに高速増殖炉の開発を続けるというのは、異常なこととしか思えません。
2012.11.08
コメント(2)
-
オバマ大統領再選
オバマ氏、激戦州制して再選決める 米大統領選6日投開票の米大統領選は、米東部時間の同日午後11時すぎ(日本時間7日午後1時すぎ)に民主党のオバマ大統領が激戦州オハイオでの勝利を確実にし、共和党のロムニー候補を破って再選を決めた。現時点で結果が出ていない州はフロリダを残すのみとなった。オバマ氏はオハイオ以外でも激戦となっていたニューハンプシャーやアイオワ、ウィスコンシン、コロラド、バージニアの各州を次々に制して勝利を引き寄せた。激しい接戦が予想されていたフロリダ州では互角の情勢が続き、7日未明にかけて集計作業を実施。開票率97%の時点で得票率はオバマ氏が50%、ロムニー氏が49%と僅差となっている。当選に必要とされた選挙人は270人。これまでに獲得した選挙人はオバマ氏が303人、ロムニー氏は206人。---私は日本人なので、当然米国の有権者ではなく、どちらの候補を支持などといっても無意味ですが、オバマかロムニーかと言えば、そりゃオバマの方がはるかに好感が持てます。ただし、4年前に比べると、魅力も色あせた感がなくもないけど。それはともかく、今の時点でもフロリダ州ではまだ勝敗が決着付いていないようですが、それを除くと、獲得選挙人ではオバマ303対ロムニー206と、一見すると大差が付いているように見えます。しかし、得票率では50%対49%という超接戦。それなのに選挙人でこんなに大差が付いているのは、言うまでもなく州ごとに勝った候補が選挙人を総取りし、全体の選挙人が多い方が勝利するという、小選挙区と同様の選挙方式を採用しているからです。ただし、すべての州が総取り方式ではなく、メイン州とネブラスカ州だけは、選挙人の一部は州全体の勝者に、残りは州内の下院選挙区ごとの勝者に割り当てるというシステムになっています。その選挙区の最多得票者だけが選挙人を獲得できる、という意味ではこれも小選挙区と同じです。もちろん、大統領は一人なので、大統領選はどこの国でも小選挙区ではあるのですが、単純な全国一区の大統領選(米国を除く大半の国の制度)では、得票数と勝敗は完全に一致しているのに対して、米国方式は、得票率と勝敗が一致しない。得票率では小差なのに獲得選挙人は大差が付くことが多いし、得票で負けた方が選挙に勝つという論外な事態すら、起こることがあります。最近の例では、2000年の大統領選(ブッシュ対ゴア)で起こったことが有名です。得票数に従ってゴアが勝っていれば、イラク戦争などという馬鹿げた戦争は起こっていなかったかも知れません。得票と勝敗の逆転現象は、しかし何も2000年が初めてだったわけではなく、それ以前も19世紀に2回起こっています。さらに、小選挙区制の発祥の地であるイギリスでも、2回起きている。まさに小選挙区(的な)制度の悪弊と言えます。日本の小選挙区比例代表並立制でも、逆転現象こそ起こっていないけど、2009年の民主党も2005年の自民党も、議席数では「歴史的大勝利」だけど、実際の得票は議席数ほどの大差が付いていたわけではありません。そのあたりの勘違いも、両党のその後の失速の一因ではないかという気もします。小選挙区制を最も優れた制度であるかのごとく思いこんでいる人たちもいるようですが、日本の例で見ても、どう考えても小選挙区が導入される以前と以降を比べれば、どう考えてもそれ以降の方が政治がおかしい。こんな欠陥だらけの選挙制度はないと、わたしは思っています。
2012.11.07
コメント(4)
-
また遭難!
万里の長城で日本人2人死亡、1人不明 大雪で遭難中国河北省張家口市懐来県にある世界遺産「万里の長城」で、日本人観光客4人と中国人ガイドの計5人が3日夜、強風と大雪のため遭難した事故で、新華社通信によると、このうち68歳と62歳の女性が死亡した。ツアーを主催した日本の旅行会社によると、3人が死亡したとの情報もある。新華社によると、76歳男性が行方不明となっている。59歳の女性と中国人ガイドは無事だった。北京の日本大使館も5日未明、4人のうち、2人の遺体が確認され、1人の安否は確認中で、1人は救出された、と中国側から連絡があったことを明らかにした。(中略)中国の通信社、中国新聞社によると、5人は北京市西部から登山し、長城付近で、遭難した。中国人ガイドが自力で下山し、警察に通報した。アミューズトラベルによると、一行は10月28日から9日間、万里の長城を計100キロ歩くツアーに参加。毎日14~16キロを5~8時間かけて歩く予定で、遭難したのは7日目だった。現場は北京市との境界に近い山地で、整備され観光地として有名な八達嶺から西南に約20キロ離れている。現場付近は、3日から「数十年ぶりの大雪」(地元メディア)に見舞われ、道路の一部が通れなくなっており、通信も切断されているという。地元当局者の話では、5人が遭難した付近の長城を訪れる観光客はあまり多くなく、道路も整備されていない。当局者は朝日新聞の取材に対し、「現場は山の奥深く、捜索は難航している」と語った。---よりによって、あのアミューズトラベル社が主催するツアーだそうです。当ブログでも何度か取り上げた、北海道トムラウシで遭難事故を起こした、あの会社です。この記事では9日間で100キロとありますが、行き帰りを除いて実際に歩く日程は7日間ということのようです。1日平均15キロ。15キロを1日だけ歩くならたいしたことはありませんが、それを7日間続けてというのは、結構きついと思います。それも、万里の長城って、写真などで見る限りは、かなり起伏のある山の中ですからね。遭難は7日目のことだそうで、疲労が相当蓄積していた可能性が考えられます。別記事によると、遭難現場付近の標高は1000メートルという話もあります。北京という街自体がかなり寒いところで、気候帯でいうと亜寒帯の一番南端にあたります。世界の天気予報で調べると、北京の今週の日最低気温は0度前後、日によっては氷点下のようです。それだけでも結構寒いのですが、標高1000メートルということは、そこから更に6度低い計算になります。いや、北京は大都市なので、ヒートアイランド現象の影響で周辺地域より暖かい可能性があります。それも考慮すれば、気温の差はもっと大きいかもしれません。そんなところで深夜の時間帯に歩けば、当然気温は確実に氷点下に決まっています。報道によると現地は数十年ぶりの大雪だそうですが、それも事前に予報されていたそうですし、北京は冬の降水量が極度に少ないので大雪が珍しいというだけで、寒さそのものはそんな記録的ではなかった可能性も考えられます。ごく大雑把に言って、日本の中部山岳で2000メートル相当の気象条件に相当する場所と思われるのですが、この時期にそんな場所で、深夜に行動するというのはどうなんでしょうか。冬山装備でならともかく、そうでなかったとすれば、常軌を逸した行動と考えざるを得ません。想像するに、予定ではそんなに遅くなるはずではなかったけれど、疲労の蓄積で、予定より行程が遅れて、深夜に至ってしまった、というところではないかという気がします。おそらくアイゼンなんか用意していないでしょうから(そもそも、登山靴を履いていたかどうかもはっきりしません。ジョギングシューズだったかも)雪で滑って足をとられて思うように歩けなかったのかもしれません。前述のとおり、大雪は事前に予報されていたそうですから、それにもかかわらず予定通り出発してしまった判断も問われます。というか、これ、3年前のトムラウシの遭難とそっくりの話じゃないですか。まったく、あの遭難事故から、この会社は何を学んでいたのか・・・・・・。それにしても、改めて山には団体ツアー旅行では登りたくないな。進むも退くも自分の判断じゃないと、こういう特攻隊ツアーにその判断を委ねるのは怖すぎます。
2012.11.05
コメント(11)
-

焼岳の写真(ボジフィルム)
先週の焼岳のフイルム写真がやっと完成したので、アップします。登り始めてすぐの撮影です。紅葉のカラマツと。同じ写真のデジカメ版はこちら↓全般に、私のデジカメよりフィルムの一眼レフのほうが、色合いが深いです。かなり登ってきたところです。同じ位置からデジカメで撮ったのは↓先ほどの写真はデジカメとフィルムの差はそれほどでもないけど、この写真ではかなりの差があります。もちろん、私はフィルムの色合いのほうが好きです。さらに登って、稜線上に出たところから。笠ヶ岳です。デジカメの写真は↓この時間帯は本当に天気がよくて、ラッキーでした。穂高連峰です。デジカメ写真は↓ですが、被写体は同じでも撮影位置が少し違います。さらに登ると、穂高連峰の先に槍ヶ岳も見えてきます。広角だと遠くてよく分かりません。アップにしてみました。ズームレンズの最大望遠が85mmなので、たいしてアップになりませんが、左端が槍ヶ岳です。中央右よりのピークが西穂高岳、右端が奥穂高岳。西穂・奥穂間が、一般コースでは日本最難関といわれる登山道です。この位置からはデジカメで撮影はしていませんので、フィルムの写真のみです。引き返す少し手前で山頂方面を撮影しました。アイゼンなしではこのあたりが限界かな、という感じです。ただ、翌々日に演奏の予定がなければ、山頂まで突撃していたかもしれません(笑)。前の記事にも書きましたが、立ち上っている白いものは、雲ではなく火山の噴気です。このあと、もう少し登って引き返しました。多分、右端に張り出している岩のあたりで引き返したように思います。このあたりでもデジカメは出していませんので、フィルムの写真のみです。展望台と呼ばれる地点まで戻ってきました。山頂をアップで。噴気がモクモクと出ていますねえ。同じ場所でデジカメで撮影した写真は↓です。やっぱり、こうやって比較してしまうとデジカメと一眼レフでは大差があります。面倒でもフィルムの一眼レフは手放せません。もっとも、私のデジカメ(Canon SX150IS)は実売価格で2万円程度。フィルムの一眼レフとレンズのほうがずっと高いので、当たり前といえば当たり前です。ただ、写真の解像度はデジカメのほうが上なんです。デジタルとフィルムの一眼レフ同士で比較したら、どうなんでしょうね。なお、フィルムのカメラはキヤノンIOS7(中古)、レンズはEF24-85mm F3.5-4.5 USM、フィルムはフジ・プロビア100Fです。
2012.11.04
コメント(11)
-
もし存在したら、考古学的大事件だけど
雪男の確率「60~70%」 西シベリアで発見の体毛イエティ(雪男)と呼ばれる謎の動物の体毛である確率は60~70%――。ロシアの西シベリア・ケメロボ州で米ロなどの研究者が昨年秋に洞窟で見つけた毛について鑑定した結果、そうした結論に達したと、ロシア国立気象大学のサプノフ主任研究員がノーボスチ通信に明らかにした。昨年秋に国際会議を開いたケメロボ州政府も10月29日、サンクトペテルブルクの研究所で毛のDNA鑑定が終わったと発表。サプノフ氏の言葉を引用し、「アザス洞窟で見つかった10本の毛は人間のものではない。哺乳類のものだが、クマやヤギ、オオカミなどの動物でもない」と伝えた。サプノフ氏は同通信に対し、「電子顕微鏡での体毛検査や核DNAの抽出を通して、60~70%の確率で、どの生物のものかを言える。チンパンジーよりはヒトに近い」と述べ、アザス洞窟で見つかった足跡も95%の確率でイエティのものといえると主張した。ケメロボ州で昨年開かれた国際会議には米国、ロシア、カナダなど5カ国の専門家が参加し、イエティの目撃証言が相次いだ洞窟や周辺の山を探索。洞窟の足跡の一つから毛が見つかっていた。一方で、一度も死体が見つかっていないなど異論もあり、論争を呼んでいる。---この話を事実だと仮定すると、イエティの正体は何でしょうか。クマの可能性が高いように思うのですが、仮に今まで未発見の動物だったとすると、その候補として可能性が高いのは、現生人類の進化の隣人であるネアンデルタール人かデニソワ人、ということになるでしょう。特に、デニソワ人は西シベリアから化石が見つかっているので、位置も一致します。それ以外のヒトあるいはサルの仲間である可能性は、著しく低いと思われます。なぜなら、シベリアという酷寒の地にすむことができる霊長類は、ネアンデルタール人、デニソワ人、現生人類に限られるからです。が、しかし、やっぱりそれって本物ですか?ってところは、いささか(というか、非常に)怪しいなと思います。「電子顕微鏡での体毛検査や核DNAの抽出」もいいけど、C14年代測定をしなくちゃ。もし、それが本当に雪男の毛だったとしても、年代測定してみたら5万年前のものでした、って可能性だってあるわけです。酷寒の地だけに、シベリアでは数万年前のマンモスの毛も発見されているのです。それに、現在知られている限り、デニソワ人は現生人類とそんなにかけ離れた風体ではなく、頭の毛を除けば、毛むくじゃらだったわけでもありません。イエティの正体がデニソワ人でも、あるいは他の何かだったとしても、何万年も生存し続けるには、それなりの個体数が必要です。最低限数十人以上はいなければ、無理でしょう。いくらシベリアは広大で人口密度も低いとは言っても、そのような動物集団が存在すれば、われわれ現生人類との接触がないはずがなく、昔からの目撃例や居住の痕跡、死体などがまったく見つからないのは、あまりに不自然と考えざるを得ません。大胆に予想するなら、問題の「イエティ」の毛の正体は(クマなどその他の動物のものではない、というのが事実とすれば)前述のとおり、本物のデニソワ人だが、体毛は数万年前のものまたは実はイエティでもなんでもなく、ホームレスが洞窟に住み着いていただけの、いずれかではないかと私は思うんですね。事実が知りたいところですが、正体が明らかになる日が来るんでしょうかね。
2012.11.02
コメント(0)
-
「在日」は誰だ
アイヌ、琉球は縄文系=本土は弥生人との混血―日本人のDNA解析・総研大など日本人を北海道のアイヌ、本土人、沖縄の琉球人の3集団に分けた場合、縄文人に起源があるアイヌと琉球人が近く、本土人は中国大陸から朝鮮半島経由で渡来した弥生人と縄文人との混血が進んだことが確認された。総合研究大学院大や国立遺伝学研究所(遺伝研)、東京大などの研究チームが、過去最大規模の細胞核DNA解析を行い、1日付の日本人類遺伝学会の英文誌電子版に発表した。アイヌと琉球人が同系との説は、東大医学部の教官を務めたドイツ人ベルツが1911年に初めて論文発表した。頭骨の分析では、狩猟採集生活の縄文人は小さい丸顔で彫りが深く、約3000年前に渡来し稲作をもたらした弥生人は北方寒冷地に適応していたため、顔が平たく長い傾向がある。総研大と遺伝研の斎藤成也教授は「ベルツの説が101年後に最終的に証明された。本土人は大ざっぱに言えば、縄文人2~3割と弥生人7~8割の混血ではないか。今後は縄文人のDNA解析で起源を探るほか、弥生時代に農耕が広がり人口が急増した時期を推定したい」と話している。---記事にあるように、これは従来から言われていた説がDNA鑑定によって再確認された、というだけの話です。日本にいつから人類が住み始めたかは判然としないものの、第四紀更新世(1万年前より古い時代)には、すでに人が住んでいたことははっきりしています。旧石器時代の日本における人類の足跡は、2000年に発覚した旧石器捏造事件によってかなり揺らいでしまい、前期・中期旧石器時代に関しては、日本に確実に人類が住んでいた証拠は消滅してしまっています。ただ、後期旧石器時代(3万年前より新しい時代)については、捏造と無関係の遺跡が見つかっているので、日本にヒトが住んでいたことは間違いない。旧石器時代人と縄文人の関係は、よくわかってはいません。旧石器時代の石器などの遺物は数多く見つかっているものの、人骨はごくわずかしか見つかっていないからです。旧石器時代人は縄文人の祖先かもしれないし、別々に渡来した別系統の民族だったかもしれません。わずかな例からは別々の系統という可能性が示唆されているようです。ただし、旧石器時代人も縄文人も単一の集団だったとは限りません。いずれにしても、旧石器時代人も縄文人も、東南アジアから北上してきた南方系の集団であることはほぼ間違いないようです。つまり、この日本列島に最初に住み着いた人々(旧石器時代人、あるいは縄文人)は、南方系だったと思われます。その後、弥生時代以降になって、新しい集団が日本に流入します。中国大陸から朝鮮半島経由でやってきた北方系の弥生人です。弥生時代の始まった時期には諸説ありますが、2千数百年前から3千年前くらいと考えれば間違いありません。弥生人の渡来もその頃に始まったのでしょう。縄文人が先住者で弥生人は後発ですが、弥生人のほうが勢力が強く、日本本土の主要部分は弥生人が占拠し、縄文人は駆逐されました。駆逐といっても、完全消滅したわけではなく、混血によってある程度の痕跡は現代の日本人にも残されています。その割合は、記事にあるように、おおむね「縄文人2~3割と弥生人7~8割の混血」という程度ではないかといわれます。しかし、後発組の弥生人は日本のすべての地域で多数派になったわけではなく、縄文人の血筋が色濃く残った地域が二つあります。それが、北海道のアイヌと沖縄、というわけです。ただし、歴史的に見れば、北海道と沖縄に限らず、東北地方の広い範囲(蝦夷)と九州南部(熊襲)に、大和朝廷に服属しない異民族が存在していたことが知られています。熊襲は古墳時代には平定されていますが、蝦夷が最終的に征服された時代ははるかに新しく、平安時代の終わり、源頼朝によってです。源頼朝が鎌倉幕府を開いた際の「征夷大将軍」という称号が「蝦夷征服の将軍」という意味であったことは、いまさら説明する必要もないでしょう。蝦夷や熊襲と、現在のアイヌ、琉球人との関係ははっきりしませんが、やはり縄文人の血筋を色濃く受け継いでいた人々であった可能性が高そうです。いずれにしても、現代のわれわれ日本人の祖先は、主要部分が朝鮮・中国から渡来した人々、一部が南方から渡来した人々と見て間違いないでしょう。朝鮮半島から、あるいは中国から朝鮮半島経由で渡来した人々は、弥生人だけではなく、それ以降も7~8世紀ころまでは絶えることがなかったようです。だから、朝鮮半島出身、あるいは朝鮮半島経由の血筋をまったく引いていない、などという日本人は、よほど近年に帰化した人(たとえばフィンランドから帰化したツルネン・マルテイとか、米国人から帰化したドナルド・キーンとか)以外は、皆無と言っていいはずです。皇后が以前に、自分たちの祖先には朝鮮からの血が入っている、という発言をしたことがあります。当然の話です。入っていないはずがない。私にも、あなたにも、安倍晋三にも石原慎太郎にも、在特会の桜井誠にも、朝鮮半島由来の血筋は、間違いなく入っています。---話は変わりますが、尼崎市の遺体遺棄・行方不明事件で連日マスコミをにぎわせている角田美代子を巡る都市伝説に、「彼女は在日朝鮮人だ」というのがあります。明白なデマです。デマ話の根拠になったのは、角田の「戸籍上の従兄弟」が李正則という在日韓国人だから、ということなのですが、わざわざ「戸籍上の」と注釈がついているのは、養子縁組によって従兄弟になっただけで、血がつながっているわけではないからです。そんなことは、マスコミで散々報じられているので、ちょっと調べればすぐに分かることです。週刊新潮や文春が彼女の生い立ちを追っており、彼女の両親の職業から、もともと名乗っていた苗字(角田は母方の苗字で、もともとは父方の苗字を名乗っていたらしい)から、若い頃の「武勇伝」から、みんな報じられています。どこにも、彼女が在日(あるいは帰化した)という痕跡はありません。それにも関わらず、一度犯人の周辺に在日韓国・朝鮮人の名を見つけたが最後、誰でも調べれば分かる、あたりまえの事実すら目に入らなくなって、ひたすら「在日の犯罪」と思い込むのが、ネットウヨク脳という奴なのでしょう。まったく救いようがない。ええ、確かに問題の角田美代子にも、朝鮮由来の血は入っているでしょうよ、前述のような意味ではね。そういう意味で、朝鮮由来の血を引いていない日本人などいません。ネットウヨクだって同じです。
2012.11.01
コメント(4)
全22件 (22件中 1-22件目)
1