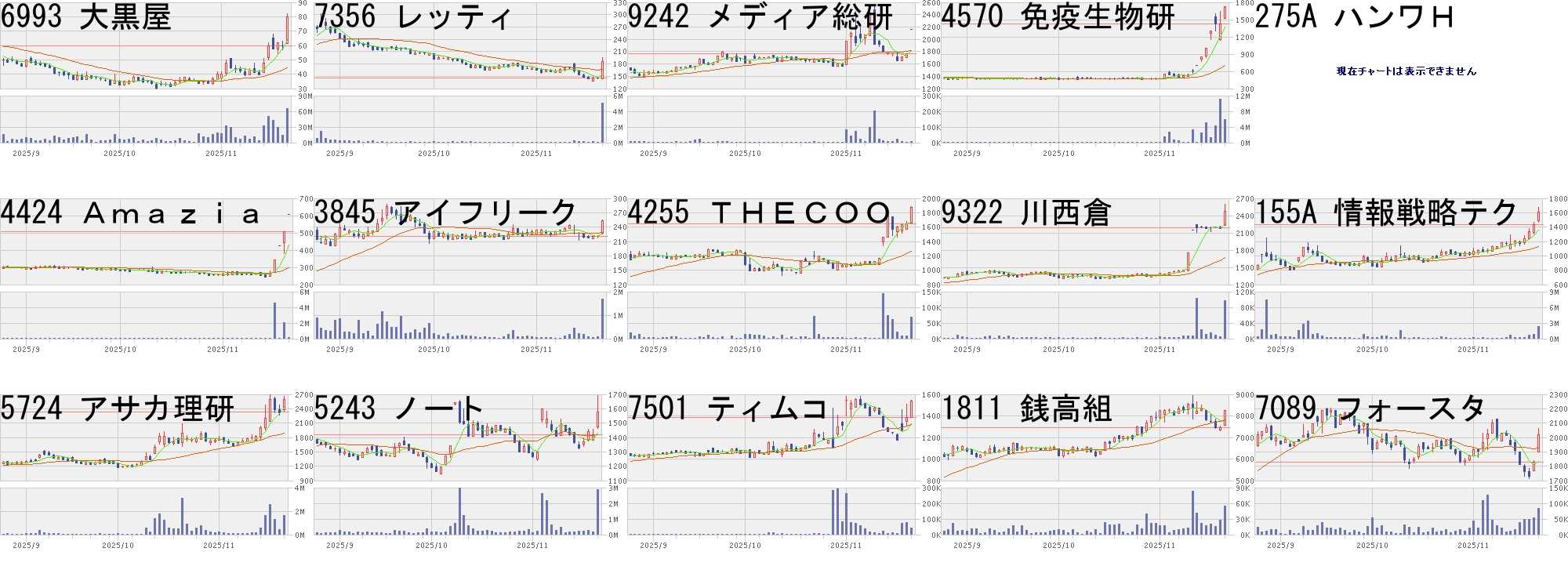2018年09月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
沖縄県知事選 玉城さん勝利
沖縄知事選 玉城デニー氏が初当選 辺野古反対派に追い風翁長雄志知事の死去に伴う沖縄県知事選は30日、翁長氏の後継として米軍普天間飛行場の名護市辺野古への県内移設計画に反対する元自由党衆院議員の玉城デニー氏が、移設を進める安倍政権が支援した前宜野湾市長の佐喜真淳氏ら3氏を破り、初当選を確実にした。政府は移設を計画通り進める方針だが、玉城氏は「あらゆる権限を駆使して阻止する」としており、今後も政府と沖縄の対立が続く。---一度も行ったことがない沖縄の知事選ですし、もちろん具体的な選挙運動に参加したわけでもありませんが、玉城さん応援していました。当選確実とのことです。うれしいです。家で、万歳三唱しちゃいます。翁長前知事の意思を継いで、辺野古への基地移設阻止に引き続き頑張ってください。与党側は菅官房長官や小泉進次郎議員、あるいは東京では対立状態にある(ことになっている)小池都知事など、大物政治家を次々と沖縄入りさせています。また、今回公明党が、国政と同様に自民党側についています。公明党は候補者を落選させることを非常に嫌うし(逆に言えば絶対に勝てるところにしか候補を立てない)、おそらくは自民党に対しても集票力の強力さを誇示して存在感を示したい、という意図もあるのだと思いますが、今回の知事選にはものすごく注力したようです。一方、玉城陣営は政党色を前面に出さないようにして、あまり大物議員の応援演説もなかったようですが、そのほうが作戦として優れていた、ということなのでしょう。今の時点では、ネット上で記事が見つかりませんが、NHKのニュースによると、出口調査では野党支持層が玉城候補に投票したのは当然として、無党派層でも玉城候補が7割くらい、そして自民党支持層でも玉城候補への投票が2割程度あったようです。また、創価学会員からも、離反者がかなりあったように報じられています。ただし、NHKのニュースでは、公明党支持層の分母が小さいため、その何割くらいが玉城候補に投票したのかは、ちょっと読み取れませんでしたが。これらの事実からは、沖縄では、自民公明支持層でも、米軍基地辺野古移設はノーという意見が一定数存在することが読み取れます。まして、無党派層や野党支持層も含めた、沖縄全体の民意は言うまでもありません。辺野古への基地移設、言い換えるなら、沖縄県内での基地のたらいまわしに対して、沖縄県民の意思は明確にノーであると、改めて示されたわけです。この事実は重い。政府は、この県民の明白な意思を踏みにじるようなことはすべきではありません。ともかく、国内の政治関係では最近珍しい、心から嬉しいと思えるニュースです。
2018.09.30
コメント(5)
-

9月の野鳥観察
まだ明日まで9月ですが、台風が接近してくる明日は、鳥を見には行かないと思うので、今月見た鳥についてのご紹介をしたいと思います。まず、9月8日船橋三番瀬海浜公園です。オオソリハシシギ左がオバシギ、右はメダイチドリアジサシ。珍しくはない鳥ですが、野鳥観察再開してから、なかなか撮影することが出来ず、やっと撮影できました。コアジサシの群れの中にアジサシがいます。頭の色が、コアジサシは側面と後頭部は黒いけれどおでこは白いのに対してアジサシは頭は全部黒、そして両者が並ぶとアジサシはコアジサシよりかなり大きいことが分かります。中央の個体と、その手前で翼に頭を突っ込んでいる個体がアジサシで、その他はコアジサシです。時々、一斉に飛び立ちます。そして9月16日葛西臨海公園です。ミサゴです。このときは4羽のミサゴが乱舞していました。ミサゴ。さらに9月22日から23日にかけての八ヶ岳(すでに一度掲載済の写真ですが)美濃戸から赤岳鉱泉に向かう途中にて、おそらくコサメビタキ幼鳥。訂正、おそらくルリビタキの幼鳥。同じくコサメビタキ(訂正、ルリビタキの幼鳥)行者小屋から美濃戸に下る途中で遭遇したキバシリ(画質があまりよくないですが)そして、今日9月29日葛西臨海公園いつでもカメラマンの人気者のカワセミです。トウネン。朝9時前頃、まだ満潮から潮が引き始めて間もない時間で、干潟は水の中でした。走したら、護岸の上の水溜りでエサを探していました。トウネン。トウネン、ミユビシギ、ハマシギは互いに似ていて区別が付きにくいのですが、ハマシギはややくちばしが長め、ミユビシギは名前のとおり指が3本で後ろ指がないことから区別が付きます。くちばしは短めで、後ろ指がバッチリ写っていますから、トウネン。(それに、ミユビシギの冬羽はもう少し灰色)ダイシャクシギ。8月に同じ場所で見たホウロクシギとそっくりで、この状態では両者見分けがつきません。しかしホウロクシギとダイシャクシギは酷似していますが、腰部と翼の下が、ダイシャクシギは白く、ホウロクシギは上体と同様の斑点が入っていることから識別できます。この写真では、翼の下面が白いので、ダイシャクシギであることが分かります。ダイシャクシギ。それにしても、でかくてくちばしの長い鳥です。ダイシャクシギ。というわけで、シギの渡りシーズンはまだ終わらないようです。今日もそうですが、週末に天気が悪いことが多いのが残念です。
2018.09.29
コメント(0)
-
こんなんでも「文芸評論家」になれる?!
『新潮45』休刊の背景~貧すれば鈍する名門雑誌の最期~月刊論壇誌『新潮45』が休刊した。大変なショックである。かくいう私は、同誌2015年9月号に初寄稿させて頂いて以来、合計8回この雑誌に寄稿させて頂いたことになる。毎回巻頭に近い位置に遇して頂き、表紙にも『古谷経衡』の名前が複数回踊った。2015年~当時の私にとって『新潮45』は権威と格式のある雑誌で、寄稿の依頼があったのは率直に名誉と感じた。~いま振り返ってみると『新潮45』は極端な二重構造を持った雑誌だった。これはどういうことか。最終号となった2018年10月号の主要連載陣は、鹿島茂(仏文学者)、瀬戸晴海(前厚生労働省麻薬取締部部長)、古市憲寿、稲泉連、福田和也、泉麻人、適菜収、保阪正康、片山杜秀、佐伯啓思、ヤマザキマリの連載漫画。今回の『新潮45』休刊で、同誌は「ヘイト雑誌だ」「ネトウヨ雑誌だ」などと散々誹謗があるが、この連載陣をみて「ネット右翼的である」と思う人はいないだろう。今回新潮社の代表取締役が声明で述べたように、「新潮45」の特別企画「そんなにおかしいか『杉田水脈』論文」のある部分に関しては、それらを鑑みても、あまりに常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現が見受けられました。 というの部分の、「ある部分」が自称文藝評論家の小川榮太郎による『政治は「生きづらさ」という主観を救えない』を指すことが明らかなように、この雑誌は特集や特別企画部分では極めてネット右翼に迎合し、当初から炎上上等の、エッヂの尖った姿勢を鮮明にしながら、雑誌後半を占めるの連載陣に至っては、「至極穏健な」寄稿で占められているという、極端な二重構造を有しているのだ。なぜ『新潮45』は、雑誌の半分がネット右翼迎合、もう半分は穏健という二重構造を内包する雑誌になったのか。それは、端的に、『『新潮45』の実売数は1万部前後が続いており、雑誌単体では赤字という状況があった。部数の落ち込みを回復したいという焦り』という報道に全てが集約されている。部数減少の回復を願う一心で、特集と特別企画はネット右翼に迎合的とする。しかし雑誌全体をその路線にしてしまうと、既存の穏健な讀物を好む定期購読者や読者が離れてしまう、というジレンマを抱えながら突進を繰り返した。---なるほど、実は「新潮45」という雑誌は、良くも悪くも私の興味を引かなくて(極右路線に走る以前から)、1度も購読したことがないし、多分書店で立ち読みしたことすらほとんどないと思います。なので、極右路線に走ったことすら、一連の騒動で初めて知った状態です。まだしも、悪い意味で興味を引く「WiLL」や「正論」は、金を払って購入はしないけれど、立ち読みくらいはしました。自分の主張に一致する本や雑誌も、もちろん読みますけど、それよりむしろ、対立する主張の本や雑誌のほうが、読むことを好む側面が、私にはあります。読むと「カチン」とは来るけれど、ある意味知的対抗心をそそられると言うのか、刺激になるのです。(そういう意味でもっとも熱心に読んだのは、WiLLでも正論でもなく、今は亡き「諸君」です)ただし、それも最近はあまり読まなくなってきました。「敵ながらあっぱれ」だった「諸君」がなくなってしまい、「WiLL」から「HANADA」が分裂して、表紙デザインも中身もそっくりな雑誌が2誌書店に並ぶようになってからは、はっきり言って食傷気味。そういう主張が世の中に、あまりに溢れかえりすぎて、表紙に並ぶ主要記事タイトル(あるいは新聞の広告を)一瞥しただけで、もうお腹いっぱいなのです。知的対抗心をそそられるより、呆れかえって脱力してしまうのでは、とても読む気になれません。この手の雑誌を手に取って中身に目を通したのは、今記憶を遡っても、一年以上前のことになるはずです。先の記事でも取り上げましたが、今回「新潮45」が休刊(雑誌コードを保持する関係でそう言っているだけで、実質は廃刊)になるにあたり、「最後のとどめ」になったのが小川榮太郎の記事であることは論を待たないでしょう(もちろん、根本的には杉田水脈の記事が原因ですが)。どう見ても、小学生の屁理屈レベルの文章、いみじくも引用記事が「自称」文芸評論家と評したような文章が、堂々と商業雑誌に掲載されるのです。では、この自称文芸評論家は、どんな経歴でどんな著作があるのか。wikipediaによれば、大阪大学文学部卒業、埼玉大学大学院修士課程修了、同博士課程単位取得満期退学。大学院の指導教官は長谷川三千子。専門は近代日本文学、19世紀ドイツ音楽。主な論文は「福田恆存の『平和論論争』」「川端康成の『古都』」などとされているが、このうち「福田恆存の『平和論論争』」は掲載元がわからないと指摘されている。1998年下期、文藝春秋の文芸雑誌「文學界」の新人小説月評を担当。私塾「創誠天志塾」では塾長を務めていた。2015年10月、「一般社団法人日本平和学研究所」を設立し理事長。2017年12月、フジサンケイグループが主催する第18回正論新風賞を受賞。だそうです。阪大卒で埼玉大の院卒、学歴は立派ですが、指導教官が長谷川三千子(典型的な極右産経文化人)というのは、「いかにも」です。で、著書は『約束の日 ―安倍晋三試論―』 幻冬舎・『国家の命運 ―安倍政権奇跡のドキュメント―』幻冬舎・『『永遠の0』と日本人』幻冬舎新書・『最後の勝機(チャンス) ―救国政権の下で、日本国民は何を考え、どう戦うべきか―』PHP研究所・『一気に読める「戦争」の昭和史 1937-1945』・『小林秀雄の後の二十一章』幻冬舎・『天皇の平和 九条の平和 ―安倍時代の論点―』産経新聞出版・『徹底検証「森友・加計事件」 ―朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪―』飛鳥新社・『徹底検証 テレビ報道「噓」のからくり』青林堂・『徹底検証 安倍政権の功罪』悟空出版共著宮崎正弘 『保守の原点 ―「保守」が日本を救う―』海竜社・上念司『テレビ局はなぜ「放送法」を守らないのか ―民主主義の意味を問う―』・足立康史『宣戦布告 ―朝日新聞との闘い 「モリカケ」裏事情から、在日・風俗・闇利権まで、日本のタブーに斬り込む!―』徳間書店・杉田水脈『民主主義の敵』青林堂いやー、タイトルを見るだけで、お腹いっぱい。古谷のいう「自称文芸評論家」という表現がよく分かります。だって、ほとんど安倍ヨイショ本と朝日新聞・リベラル攻撃本しか書いていないじゃないですか。「文芸」評論と呼びうるものが、この中にどれだけあるのか。せいぜい好意的に言って「政治評論家」でしょうし、「評論」と呼ぶには、批評対象対する客観的視線がなさすぎるので、実質的には「ネトウヨ文筆家」以上のものには見えません。それにしても、学歴は立派とはいえ、あの小学生の屁理屈並みの駄文を書く人間が、「文芸評論家」を名乗って、せっせと安倍ヨイショ本を書かせてもらって、それなりに売れるんだから、極右文化人の世界というのも美味しいよね。私も、今の仕事がお払い箱になったら、ネトウヨに転向して、売文家になろうかな・・・・・。その時のペンネームは、「ロス12」にしよう(爆)って、もちろん私にも恥と外聞と良心というものがありますから、そんなことはしませんけどね。そう思いたくなるくらい、ネトウヨに媚びを売る系の言論空間の知的退廃ぶりはすさまじいものがあります。小川榮太郎なる人物の文章を見て、つくづくそう思いました。
2018.09.28
コメント(8)
-

秋の八ヶ岳・赤岳 その3
最終回です。北アルプスも見えます。かなりうっすらしていて分かりにくいですが、穂高連峰と大キレット、槍ヶ岳です。硫黄岳。天狗岳(左が西天狗、右が東天狗)そして、八ヶ岳連峰を一望。左遠方から蓼科山、北横岳(ピークは明確には分かりませんが)、西天狗、東天狗、硫黄岳、横岳と連なります。また、権現岳と南アルプス文三郎尾根を下山と書きましたが、正しくは、ここまでは赤岳から阿弥陀岳に至る稜線で、文三郎尾根はこの分岐から始まります。山頂から分岐までは絶壁の急降下ですが、この分岐から行者小屋までの、狭い意味の文三郎尾根はさほど危険箇所もなく、スイスイ下ります。さっきまでほぼ同じ高さだった阿弥陀岳が、あっという間に見上げる高さになります。手前は中岳、奥が阿弥陀だけです。この辺りで、1回尻餅をついてしまいました。(怪我のあと、山での転倒は初めて、気をつけなくちゃ)行者小屋目前まで下山してきました。黄葉真っ盛り、素晴らしい景色でした。ただ、ダケカンバを中心に黄色い黄葉が中心で、カエデ、ナナカマドなどの紅葉はあまり多くありませんでした。数少ないナナカマドの紅い紅葉。(ナナカマドは点々とありましたが、カエデ、モミジは私の見た範囲では気が付きませんでした)行者小屋に到着。横岳の尖峰群を見上げます。小屋には赤提灯がかかってました(笑)同じく行者小屋から赤岳を見上げます。そして、ここから美濃戸に向けて、南沢を下山。この日は晴天で、日向は地面が乾いていましたが、前日までは雨とくもりだったので、森の中の土の斜面や木の根は湿っています。稜線上の岩場は、一見危険そうに見えますが、実は全然滑らない。しかし、南沢の樹林帯の下りは、いかにもツルツル滑りそうで、しかも結構な急斜面もあって(前日登った北沢のほうが急斜面は少なかったように思います)、けっこう怖い。まあ、滑っても単なる尻餅で済むとは思いますが、運が悪いと昨秋のように・・・・・(いや、何でもありません)それに、稜線上では痛くなかった足も、この辺りまで下ってくると、疲労でちょっと痛い(それが怪我後の標準状態で、歩くのに支障があったわけではありません)カラ類の混群がしきりと頭上を飛び交うのですが、樹高が高くて、どうもうまく撮影できません。唯一撮影に成功したのがこちら。キバシリでした。一応始めての撮影です。証拠写真にもならないくらいの低画質ですが。ナナカマド。この日は快晴になりましたが、それまで雨が続いていたので、沢は水量たっぷりでした。美濃戸に到着。12時過ぎていたのでここでおそばをいただきました。そして、美濃戸口に戻ってきたわけですが、ここまで人けのない場所を探していたものの、晴天の三連休中日で登山者が多く、なかなか人けのない場所は見当たらず、最後美濃戸口から登山道とは別方向の林道に入って、お約束の・・・・・・この日も練習。で、美濃戸口入浴して、バスで帰路に着きました。(本当は、生ビール飲みたかったけど、時間がなくなってしまいました)先に書いたように、怪我のあとに登った山としては、標高差、難易度とももっともハードな山でした。(もっとも、登りは標高差1400mを2日かけてます。6月に丹沢の塔ノ岳標高差1200mを日帰りで登っているので、見方によってはそちらのほうがキツイ、とも言えます)足首も、もちろん完治はしていないのですが、ずいぶん無理が利くようになりました。あとは、まだテントを担ぐ山行だけは再開していないですけどね。無雪期でも、テントを担げば荷物は15kg以上になります。正直、美濃戸から赤岳鉱泉までの北沢はテント担いでも往復できるだろうと思いますが、行者小屋までの南沢の下りは、テントを担いで転ばずに下れる自信は、まだないです・・・・・・。まあ、それは来年以降に。
2018.09.26
コメント(2)
-

秋の八ヶ岳・赤岳 その2
前回の続きです。日本で一番高い山が目の前に見えます。展望荘から山頂への登り。冬は、地蔵尾根の難易度が高く、そこから先の山頂まではそれほど困難ではない(ように感じる)のですが、雪がないと、こっちの方が地蔵尾根より厳しいかも。赤岳頂上山荘に到着。目の前に山頂です。山頂に到着。三連休の中日、天気は快晴、登山日和なので、山頂には人がいっぱいでした。海抜2899mの高さ、登山口からの標高差(美濃戸口が標高1490mなので、標高差1400m)、登山道の険しさ、どれをとっても、左足の骨折以降ではもっともハードな山登りでした。いや、ブログ上では、まだ過去形で書くには早すぎます。下山が残っているんだから。(山で、登りで遭難する人はあまりいません、私自身も含めて、事故の大半は下りで起こります)山頂から赤岳頂上山荘を振り返る。その向こうに硫黄岳が見えます。そして、下山にかかるわけです。元々、地蔵尾根を登り、文三郎尾根を下る、という計画でしたし、地蔵尾根よりは文三郎尾根の方が多少は楽なはずなので、迷わず文三郎尾根へ。もっとも、文三郎尾根は夏冬1回ずつ登ったことがあるだけで、下りは初めてなのでした。うーーむ、文三郎尾根もまた、けっこうな急降下なのでした。この岩場の通過が一番大変。一昨年の3月に登ったときは、ここはどうやって通過したのかなあ、全然記憶がないんですけれど。この辺りは、一昨年冬に登ったときの記憶は、何となくあります。2016年3月21日撮影。先の写真より少し下がった位置からの撮影と思いますが、おおむね同じ場所を撮っています。天気がよくて、岩が乾いているので、まったく滑らないので、見た目ほど危険はありませんが、そうは言っても左足首にボルトが入っていますからねえ。しかし、いつもは、手術跡が痛むのですが、落ちたら即死のところを歩いていると、何故か全然痛くないし、足の感覚もほとんど怪我の前と変わらないのです。何でだろ~~~。でも、行者小屋まで下ってくると、そこから先はやっぱり左足が痛いのです。何でだろ~~~~。正面に阿弥陀岳。足の怪我がなければ、ついでにこちらも登りたいところでしたが、今回は見送ることにしました。しかし、紅葉真っ盛りです。権現岳と、その向こうに南アルプス。同じ位置でアップ。権現岳と、その奥は左から北岳、甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳中央アルプスの山々。北アルプス。穂高連峰、大キレット、槍ヶ岳が見えますが、さすがに遠くて分かりにくいです。阿弥陀岳のアップ。横岳。さらに次回に続きます。
2018.09.25
コメント(0)
-

秋の八ヶ岳・赤岳 その1
9月22日土曜から昨日23日まで1泊2日で八ヶ岳の赤岳に行って来ました。朝、7時発の始発のあずさに乗ろうと思ったら、超満員で、自由席は座れそうにありません。そこで、1本遅らせて7時18分発の臨時列車にしたので、茅野駅から美濃戸口行のバスも1本遅くなりました。元々、天気も早い時間は天気が悪く、次第に回復してくる予報だったので、あまり早く着くメリットもなさそうでしたし。美濃戸口に11時過ぎに到着。この時間には、まだ天気はよくありませんでした。が、回復を信じて赤岳鉱泉に向けと歩き出します。もう花はほとんど終わりですが、唯一トリカブトだけはあちこちに咲いていました。アリや蜂が蜜を吸っていましたが、昆虫にはトリカブトの毒は効かないのでしょうか。標高1800mか1900mの亜高山帯林で、サメビタキの仲間らしき小鳥が飛んできたので、とりあえず撮影しました。あとで色々調べたのですが、コサメビタキの幼鳥と思われます。3年後の訂正。おそらくルリビタキの幼鳥です。尾羽が青いことを当時は見落としていました。サメビタキの仲間はサメビタキ、コサメビタキ、エゾビタキの3種がいますが、エゾビタキは日本には渡りの途中で立ち寄るだけで、繁殖していないので除外。残る2種のうち、分布域としてはサメビタキの分布域のはず(サメビタキは亜高山帯針葉樹林で繁殖、コサメビタキはそれより下の落葉広葉樹林で繁殖)なのですが、ネットで写真を比較すると、どう見てもサメビタキではなくコサメビタキの幼鳥に見えます。訂正。前述のとおり、ルリビタキの幼鳥のようです。撮影場所は亜高山帯林(写っている木はシラビソ)なのですが、落葉広葉樹林との境界からさほど離れているわけではないので、本来は落葉広葉樹林で繁殖するコサメビタキが入り込んでくることもあるのでしょう、多分・・・・・・。訂正。ルリビタキの幼鳥と思われます。ルリビタキは亜高山帯で繁殖するので、この辺りにいるのは自然です。美濃戸口を11時過ぎに出発、美濃戸が12時(昼食)で、2時過ぎに赤岳鉱泉に到着しました(ほぼコースタイムどおり)。山小屋の宿泊申し込みをして、まだ早い時間なので、中山展望台まで行って見ました。が、赤岳、残念ながらガスっていて、見えません。このあと、赤岳鉱泉近くのヘリポートでみっちり笛の練習。しかし、その写真は撮りませんでした、(本当は中山展望台で吹きたかったのですが、人が多くて・・・・・・)夕暮れも赤岳鉱泉。テントも沢山ありました。わたしもテントにしようか迷ったのですが、まだ20kg近い荷物を担ぐのは、左足が厳しいかな、初日はひょっとすると雨かも、といったことで、テントは断念しました。赤岳鉱泉の夕食。牛ステーキですよ!実は、この赤岳鉱泉はお風呂もあるのです。ただし、冬季は風呂は閉鎖です。今まで赤岳鉱泉は何回もとまったことがありますが、すべて冬で、無雪期に泊るのは初めてです。なので、お風呂も初めて入りました。山でお風呂に入れるのはうれしいです。石鹸やシャンプーはありませんが。そして翌朝、23日。快晴です!!阿弥陀岳に朝日が当たっています。登山届には、行き先赤岳と書いたのですが、赤岳に登るか、硫黄岳にするか(硫黄岳は初心者向きの山)、ちょっと迷いました。天気が悪かったら硫黄岳にしたところですが、この天気なら赤岳にgo!まず、行者小屋に向かい、そこから地蔵尾根を赤岳へと登ります。赤岳は過去に3回(途中撤退を含めると5回)登っていますが、近年は冬季ばかりで、無雪期に登るのは20年ぶりです。いきなり、はしご連続攻撃。このはしごは、冬季でも露出しているので記憶にありました。そして、急登は続く。しまった、地蔵尾根より文三郎尾根から登るほうがよかったか、と一瞬思いましたが、もう手遅れ。引き返せない、登るしかありません。(それに、文三郎尾根も大同小異でした)この辺りが一番厳しかったでしょうか。無雪期の地蔵尾根は、遠い昔に1度下ったことはありますが、登るのは初めて。なんだか、積雪期より厳しい感じがするのは気のせいか。それにしてもこんな斜面をよく冬に登れたな(それも2往復半)、と今更ながら驚いてしまいます。もちろん、足の怪我がなければ、この登りを厳しいとは思わなかったでしょうが。そして、ともかく地蔵尾根を登りきって稜線に出る(地蔵の頭)と、そこには目の前に横岳がそびえています。地蔵の頭のすぐ近くに赤岳展望荘があります。その先から、赤岳山頂を撮影。赤岳のアップです。八ヶ岳は俗に「小屋が岳」なんて言われることもあるくらい山小屋の多い山域です。撮影した場所に赤岳展望荘があって、目の前の山頂にも赤岳頂上山荘があります。阿弥陀岳もほぼ同じ高さに見えるようになりました。続きは次回です。
2018.09.24
コメント(0)
-
屁理屈にもほどがある
<新潮45>杉田氏擁護特集で社長コメント「常識逸脱した」月刊誌「新潮45」が性的少数者(LGBTなど)を「生産性がない」などと否定する杉田水脈衆院議員の寄稿を掲載し、更に最新10月号で擁護する特集を組んだ問題で、発行元の新潮社は21日、「あまりに常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現が見受けられた」と認める佐藤隆信社長名のコメントを発表した。この問題で社としての見解を公式に示したのは初めて。明確に謝罪はしていない。コメントでは「言論の自由、表現の自由、意見の多様性、編集権の独立の重要性などを十分に認識し、尊重してきた」と説明。その上で10月号の特別企画「そんなにおかしいか『杉田水脈』論文」の「ある部分」に問題があったと認め、「今後とも、差別的な表現には十分に配慮する所存です」と続けている。「ある部分」が何を指すかは明らかにしていない。杉田氏は同誌8月号に寄稿した。内容への批判を受け、最新号では擁護特集を企画。文芸評論家の小川栄太郎氏がLGBTが生きづらいなら痴漢も生きづらいなどと主張し、「彼らの触る権利を社会は保障すべきでないのか」などと書いていた。この問題を巡っては、新潮社と接点がある作家らからも「差別に加担している」と批判の声が上がり、また同社の文芸部署もインターネット上で「45」への否定的な見方を示唆するなど、社内でも異論が起こっていた。(以下略)---杉田の暴論はすでに各方面から集中砲火を浴びていますし、私も以前の記事で批判したことがあります。では、杉田は生産性が高いつもりか各方面からの批判に対して、杉田の暴論を掲載した新潮45は、杉田擁護の特集を組んだわけですが、その内容があまりに酷いので、またまた批判が起こっています。そもそも、藤岡信勝、小川榮太郎、潮匡人、八幡和郎という執筆陣を見ただけで、中身の予想はつきますが。中でも、引用記事にある小川榮太郎の「LGBTが生きづらいなら痴漢も生きづらい」というのは、凄まじく醜悪な主張です。双方の合意に基づいて2人の人間が愛し合うことに、何の問題があるのでしょうか。日本では何の法にも触れませんし、合意の元なのだから、被害者もいません※。それは、同性同士でも異性同士でも同じことです。※ただし、それをどこまで露出するか、には制約があります。かつて、公衆の面前で男女が手をつなぐだけでも、怪しからん、という時代もありました。今は男女が公衆の面前で抱き合っても、問題になりません。しかし、今でも裸の男女が、となったら、わいせつ罪になる。でも、それは同性同士とか異性同士とかは関係ない。1人でも、公衆の面前で裸で歩き回れば同じことです。しかし、愛し「合う」のではなく、愛の一方通行は、その発露の仕方には制限があります。合意でなく片方が拒絶しているのに、一方的にそのような行動に及べばセクハラであり、一定の限度を超えれば犯罪です。それはLGBTだろうが異性愛者だろうが同じことです。同性同士の場合、「婦女暴行」や「強 姦」にはならないとしても、暴行罪や強要罪には当たるでしょう。痴漢というのはまさしく、そのような行為そのものであることは、言うまでもありません。異性愛が「正常」だとしても、それをどのように発露してもよいわけではありませんし、相手の意に反して強要することは、「正常」ではないのです。LGBTにしても異性愛にしても、そのような性的な指向と、それをどのように発露するかは、別の問題であり、それを混同するのは、あえて言えば、屁理屈です。そのようなほとんど小学生レベルの屁理屈を、堂々と商業雑誌に掲載して、恥ずかしくないのか、と思います。あまりの酷さに、新潮社内部からも批判が起こり、それがツイッターなどを通じて外部に発信されているわけですが、とうとう、新潮社の社長が引用記事のとおりのコメントを発表する事態となったそうです。「あまりに常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現が見受けられた」という認識は、そのとおりでしょう。ただ、引用記事によれば「明確な謝罪ではない」とのこと。この対応もまた、分かりにくいと言わざるを得ません。第三者ではない、自社が発行している雑誌について、そのような認識を持ちうるのであれば、謝罪の言葉を入れるべきだったのではないか、と思います。
2018.09.22
コメント(4)
-
あまりに意味不明
加計理事長とのゴルフ問われ 首相「将棋はいいのか」自民党総裁選に立候補している安倍晋三首相、石破茂・元幹事長は17日夜のTBSの番組に出演し、司会のキャスターを交えてゴルフをめぐって応酬した。首相が友人の加計孝太郎・加計学園理事長とゴルフや会食を重ねていたことについて、星浩キャスターが「加計さんは、いずれ利害関係者になる可能性があった。まずかったという気持ちはあるか」などと質問。首相は「利害関係があったから親しくするというのではなくて、元々の友人」と述べ、問題ないとの認識を示した。星氏は「学生時代の友だちでも、金融庁幹部とメガバンクの頭取はゴルフをしてはいけない」と重ねて指摘。石破氏も「自分が権限を持ってる時はしない、少なくとも。あらぬ誤解を招いてはいけない。私もいますよ、そういう友人は。ですが、職務権限を持ってる間は接触しない」と首相の姿勢を問題視した。首相は「星さん、ゴルフに偏見を持っておられると思う。いまオリンピックの種目になっている。ゴルフが駄目で、テニスはいいのか、将棋はいいのか」などと反論した。---自民党の総裁選に、わたしはほとんど関心を持てません。どうせ安倍が完全に優位に立っている上に、安倍と石破の違いは、「感情的なネトウヨ」と「多少は理性的なネトウヨ」の違いでしかなく、石破だって(その歴史認識はかなりまともだとは思いますけど、それ以外の面では)支持できるような主張はあまりないからです。原発推進派だし。自民党の総裁が石破に代わったから、日本の向かう方向が目に見えて変わる、なんてことは信じ難いものがあります。なので、わたしは安倍も石破も、まったく、かけらほども支持するものではありません。両者のテレビでの討論も見ませんでした。ただ、討論の間の、安倍のあまりに挙動不審な目つきが話題になっていることはネット上の動画で知りました。たしかに、あれは挙動不審すぎる。しかし、それより何よりわたしがびっくりしたのは、この言い分です。「学生時代の友だちでも、金融庁幹部とメガバンクの頭取はゴルフをしてはいけない」に対する回答が「ゴルフに偏見を持っておられる~ゴルフが駄目で、テニスはいいのか、将棋はいいのか」というのは、いくらなんでも明後日の方向過ぎる回答です。だれも、「ゴルフ」というスポーツの是非など問題にしていない、親密すぎる関係の一環(あるいは象徴)としてのゴルフが槍玉に上がっているのであって、「テニスはいいのか、将棋はいいのか」←ダメに決まってんでしょうが、そんなこと。これで、何か反論したつもりになっているとしたら、安倍は本当に救いようのないバカとしか言いようがありません。こんなのが、かれこれ6年近く日本の首相を務め、今後も勤め続ける可能性が濃厚なのですから、残念ながら日本の進む道は暗いと思わざるを得ません。
2018.09.19
コメント(2)
-
計算が出来ない新聞記者
自衛隊OBの提言であぶり出された中国の無体に目をつぶる「日本人」の正体「ディスる」とは「相手を否定・侮辱する」という意味だとか。12年近く毎週小欄を書いているとご賛同下さる読者も多いが、時にご批判も賜る。605回目の前回も「中国をディスる記事」との反発が書き込まれた。しかし、中国の軍事費は1988年比49倍、2007年比でも3倍に膨張している。科学・先端技術開発費といった「隠れ軍事費」を含めれば、安全保障上の“超常現象”と断じて差し支えない。(以下略)---例によって、記者の仮面をかぶった政治運動屋の愚論です。軍事費が1988年比49倍、2007年比でも3倍に膨張という、その数字だけを見ると、とてつもない拡大ぶりですが、その間の経済力の拡大を無視して数字の膨張だけを非難する意味があるのでしょうか。そういう言い方をするなら、日本も高度経済成長期に、途方もない「軍拡」を行ったことになります。「1988年比49倍、2007年比でも3倍」という数字の根拠は、おそらくこちらの資料だと思われます。中国の国防費これによると、中国の公表国防費は1988年約215億元、2007年約3472億元、2017年1兆444億元とあります。これを計算すると確かに49倍と3倍になります。では、この間に中国の経済力はどれほど拡大したのか。人民元による予算額との対比なので、同じく人民元による名目GDP額(インフレ率を補正した実質GDPでは、「予算額」との正確な対比にならないので)を比べてみました。世界経済のネタ帳・中国のGDPの推移これによると、1988年の中国の名目GDPは1兆5330億元、2007年は27兆1700億元、2017年は81兆2030億元です。伸び率は1988年に対して約53倍、2007年に対して約3倍です。そう、「1988年比49倍、2007年比でも3倍」という中国の軍事費の伸びは、この間のGDPの伸びに比例したものであり、対GDP比で見れば、中国の軍事費は特段増えてはいないのです。これ以外に「隠れ軍事費」があるといいますが、それは今始まったことではなく、1088年当時も(それよりはるか以前から)ありました。もちろん、経済大国になった分だけ装備は充実してきているけど、その代わり数は大幅に減らしてきています。かつて、中国軍は総兵力400万人、今は230万人。人口比では日本の自衛隊と大差ない人数です。軍用機も、かつては4000機も保有していましたが(数は多かったけれど、どうしようもない旧式機ばかり)、それが新型機に置き換わった代わりに、1200機まで減っています。かつて航空自衛隊が、米軍のお下がりのF86戦闘機→F104戦闘機→F4戦闘機→米軍でも最新鋭のF15戦闘機と、高度経済成長に乗ってどんどん最新鋭機を導入して行った、それを中国は今やっている、というだけの話です。軍事費の伸びをGDPの伸びとの対比で考える、という、ごく初歩的な数字の取り扱いをしないから、野口だの阿比留だのといった産経の「看板記者」連中は記者のフリをした政治活動屋だというのです。中国の合計特殊出生率は日本より低く、一人っ子政策を撤廃したあともそれは回復していません。そう遠くない将来、中国も日本と同様人口減が始まるし、生産年齢人口はすでに減少に転じているとの指摘もあります。つまり、中国の経済成長もそうそういつまでも続かないし、当然軍事費の拡大も同様と見ることが出来ます。何の問題もない、とはいいませんが、「安全保障上の“超常現象”」などと言うのは、阿呆のたわごとでしかありません。
2018.09.17
コメント(2)
-
イージスアショア
イージス・アショアが吹っかけられた「高い買い物」に終わる理由防衛省は7月30日、陸上配備型の弾道ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」2基の配備費用は4664億円になるとの見通しを発表した。小野寺防衛相は昨年11月「一般的な見積もり」として「1つ大体800億円」と答弁していた。2基で1600億円程度のはずが本体2基だけで2680億円、維持費などを入れると4660億円になる。これには1発約40億円とされる迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」24発ずつ2ヵ所(計約2000億円)や一部の用地の取得、整地、隊員宿舎、教育訓練費などは含まれていない。トランプ政権の言うまま、「イージス・アショア」は安上がりと信じて、自衛隊が求めてもいない装備の導入を急遽政治主導で決めたのが誤りだったのだ。これまでも米国政府を通じた「有償軍事援助」(FMS)では当初の米側の見積もりより価格が後になって高騰するのが常だった。米国側が当初は低い見積もりを日本側に示し、政府がそれを元に採用を決めて、一部の予算が付き、後もどりしにくくなったのを見計らうように米国が価格をを吊り上げた例は枚挙にいとまがない。現在、日本の弾道ミサイル防衛は、イージス・システムと迎撃ミサイル「SM3ブロック1A」を搭載する「こんごう」型護衛艦4隻、および航空自衛隊の「パトリオット・PAC3」移動式発射機34両から成り立っている。「こんごう」型は計90発の各種ミサイルを縦に入れる「垂直発射機」を持っているが、各艦はミサイル迎撃用の「SM3ブロック1A」を8発ずつしか積んでいない。これに対して、北朝鮮が持つ核弾頭は「約12発」から「60発以上」と推定には大きな幅があるが、弾道ミサイル300発程度はありそうだ。イージス艦が破壊できなかった弾道ミサイルは「パトリオット・PAC3」で迎撃することになっている。1地点に各2両の移動式発射機を配置、首都圏と米軍基地を守る構えだ。その発射機には16発の迎撃ミサイルを入れられるが(引用者注:M902発射機の場合、1両で16発)、各々4発、2両で8発しか積んでいない。「PAC3」は不発や故障に備えて1目標に2発ずつ発射するから、4目標にしか対抗できない。イージス艦やPAC3で装備されているミサイルが少ないのは、ミサイルの値段が高いためだ。イージス艦用の「SM3ブロック1A」は1発約16億円、「PAC3」は1発約8億円だから多くは買えないのだ。「こんごう」型は1隻約1400億円、「PAC3」の発射装置は1セット約120億円だから、そのシステムの価格に対し、搭載する迎撃ミサイル数が不釣り合いに少ない。「イージス・アショアに何千億円も投じるよりは、イージス艦やPAC3が保有する迎撃用ミサイルの弾数を増やす方が合理的ではないか」とミサイル防衛関係の自衛隊上層幹部達に言うと、ほぼ例外なく「仰言る通りです」との答えが返ってくる。(要旨)---イージス・アショアの配備が問題となっています。当初の「セールストーク」では1基800億円だからイージス艦(1隻1400億円)より安上がり、と言っていたのが、蓋を開けたらどんどん値上がりした上に、なんと、ミサイル本体代(1発40億円)は別、ときたもんです。ということは、海上自衛隊のイージス艦の価格も、ミサイル代込みだと、本当はもっと高価なのか、と思いきや、こちらはなんとPAC3ミサイルは8発しか積んでいません、と。(8発だけでも300億円以上になり、それは当然艦の建造費には含まれていないのでしょうが)イージス艦の垂直発射機には、対潜ミサイルや個艦防空用の短距離対空ミサイルも搭載できますが、その対潜ミサイルも定数は16発とされるけど、全部積んでいるかどうかは怪しいし、日本のイージス艦は短距離対空ミサイルは搭載していないようです。つまり、90セル、あるいは96セルの発射機のうち、少なくとも2/3以上、下手をすると8割以上は空っぽ、というのが実態、ということです。パトリオットミサイルも、実は発射機の1/4しかミサイルを積んでいない、と。自衛隊には、「たまに撃つ、弾がないのが、玉に瑕」という川柳があるそうですが、まさにそのとおり、これでは張子の虎と言われても仕方がありません。わたしは、重武装を主張する人間ではなく、自衛隊の規模は縮小すべき(廃止ではない)と思っている人間ではありますけど、いくらなんでもこれはあまりに酷いのでは、と思います。この状態で、ミサイルという中身が入っていない器(発射装置)を増やす意味なんかあるのか、とてもあるようには思えません。イージスアショア導入などやめて、その代わり、予算の一部を、ミサイル本体の購入に(もちろん維持・整備費用にも)振り向けるべきじゃないでしょうか。イージス・アショア当初見積もりの2箇所で1600億円をミサイル購入費に当てれば40発分にはなります。そのイージス・アショアは、特に秋田で配備に反対の動きがあります。配備場所が市街地から1km未満の近距離であり、特に学校が至近距離にあるためです。イージスアショアがあると、そこが相手からの攻撃目標となり、いざというときに周囲が巻き添えになりかねないことが1点と、もう1点は電磁波の問題です。イージスシステムに限ったことではありませんが、大出力のレーダーは強烈な電磁波を出します。イージス艦は、搭載するSPY-1レーダー作動中は乗組員が甲板に出ることを禁止、港内や陸の至近距離では作動を停止しているそうです。電磁波の影響が強烈だからです。そんなものを何故市街地の至近距離に配備しようとするのか。まったく理解に苦しみます。そもそも、陸上固定式のイージス・アショアは船であるイージス艦に比べて、いかにも使い勝手が悪いものです。何らかの事情で場所を移動したくても、容易なことではないからです。船のほうが、はるかに使い勝手がよいのです。そのイージス艦は現在は6隻ですが、2隻が建造中で、近く8隻になります。それでもなお、これほどの巨費を投じてイージス・アショアを導入しようという意味が、わたしにはまったく理解できません。予算の無駄遣いとしか思えません。※もっとも、イージス艦1番艦である「こんごう」は就役から25年経過しており、あと十数年後には退役ということになりそうです。その際は、代艦ということになるのでしょうが、船体のみ新造してイージスシステム他の武装は移設、かつ船体の性能は大幅に落とせば、建造費用は大幅に安上がりになるのではないかと思います。船として高性能なイージス艦が8隻も必要とは思えないのです。弾道ミサイル迎撃に特化した「移動可能なイージスアショア」と捕らえるならば、ディーゼル機関で最大速度15ノット程度、イージスシステム以外の武装は皆無か、最低限の防御火器のみで充分でしょう。普段は海上に停泊し、悪天候のときだけ港に逃げるとか、いっそのこと、乗組員はランチで出勤という体勢にすればよいかも。
2018.09.15
コメント(4)
-
どこまでも荒廃した心象風景
座間9人殺害事件 白石被告と接見 「金払ったら話す」神奈川県座間市のアパートで男女9人を殺害したなどとして、10日強盗殺人などの罪で起訴された白石隆浩被告が11日メディアの中で初めてNHKと接見しました。被告は事件の動機などについては答えず、「金を払った相手に話をしたい。長くこのような生活になるので気前のいいところとおつき合いしたい」と述べ、接見を打ち切りました。白石被告は起訴後に接見の禁止が解除され、11日午前、メディアの中で初めてNHKと接見しました。白石被告は「金を払った相手に話をしたい。長い時間、ここに入ることになるので一番、気前のいいところに答えることにする。お金をいただいた相手には正直に話をさせていただく」と述べ、事件の動機などについての質問には答えませんでした。また、犠牲者や遺族に対する気持ちや、金銭を要求する理由について質問しましたが、「自分がどのように見られているかわかっていて流れも考えている」としたうえで、「お金をいただいてから話をする」と述べて一方的に打ち切りました。NHKは金銭の支払いには応じず面会はおよそ15分間で終わりました。---ある意味ぶったまげたニュースです。死刑制度への賛否はともかくとして、可能性の問題として、9人も殺し、しかも冤罪の可能性が微塵もないこの犯人に、死刑以外の判決が出る可能性は限りなくゼロに近いでしょう。万が一死刑にならなくても(心神耗弱とか?まあ、それが認められる可能性もないですけど)無期懲役、仮釈放の可能性はゼロ。一生刑務所から出てくる可能性はないです。(はっきり言って、出てこられても困りますけど)それなのに、そこまでして金が欲しいのかな。金を手にして、何に使うつもりなんでしょうか、というか、使えるのでしょうか?死刑囚の独房の中で。追記:独房内でも、お金をつかえないことはないようですね。東京拘置所 完全ガイド 「食べ物」は差し入れ可能?なんというか、ものすごく荒廃した心象風景・・・・・・って、そもそも9人も殺した犯人の心象風景が荒廃しているのは当たり前でしょうけど。だけど、このニュースが大々的に報じられたことによって、今後他社はこの犯人と面会して、その話を記事にすることは実質的には不可能になったでしょう。何ぼなんでも、死刑囚(になるのが確実な刑事被告人)に、犯行についての話を聞くためにお金を払いました、は許されることでありませんから。「犯人に金を払ったのか」と疑いの目を向けられかねない行動は非常に取りづらくなったでしょうね。
2018.09.13
コメント(2)
-
最高の友人、最低の公人
文大統領ツイッターに「非礼な安倍に代わってお詫びする」コメントがついた理由文在寅大統領のツイッター掲示物に書き込まれた日本ネットユーザーのコメントが目を引いている。彼らは「文大統領、温かい励ましとお見舞いをいただきありがとう」とし「安倍首相の非礼な振る舞いを心からお詫びする」などの書き込みを残した。該当の掲示物は、文大統領が今月6日、北海道で発生した震災に関連し、日本国民と安倍晋三首相に送った慰労メッセージの内容だ。文大統領は「自然災害で大きな被害に見舞われている日本国民と安倍首相に慰労メッセージを送った」とし「台風と地震で犠牲になった大阪と札幌地域の住民を哀悼の意を表する。遺族と、負傷して財産被害を受けた方々にも慰労の言葉を申し上げる」と慰労の言葉をかけた。の後、メッセージを受け取った安倍首相が文大統領のメッセージにどのような立場も明らかにしないため、一部の日本ネットユーザーが「安倍首相が欠礼を犯した」として代わりに謝罪に出た。あるネットユーザーは安倍首相のコメント欄に「文大統領の温かいメッセージにまだ返礼をしていない」とし「無礼で恥ずかしい」などと直接コメントを残したりもした。一方、安倍首相は7日、自身のツイッターに台湾の蔡英文総統とオーストラリアのスコット・モリソン首相などが残した慰労メッセージを共有して感謝の気持ちを表明していた。--- 北海道の地震に際して、韓国の文大統領からツイッターでお見舞いの言葉があったのに、我らが首相はそれを完全無視で応じているそうです。オーストラリアの首相と台湾の総統からのお見舞いツイートには謝辞を返しているのに。嫌いな奴だからお見舞いの言葉をもらっても無視する、それが通用するのは、私人間のやり取りだけです(それだって、子どもじゃあるまいし、いい大人が人としてどうかと思うけど)。社会人、公人としてのやり取りで、それはあり得ないでしょう。まして、一国の首相が!!本当にガックリする話です。親しい友人にとっては、きっと安倍は最高にいい奴なんだと思いますよ。友達への仁義に篤く、どんなことをしても守ってくれるから。そのかわり、友達以外に対しては、とことん敵対的だけど、世間一般のただの人なら、嫌なら周囲に近づかなければ良いだけですから。しかし、私人としてならよい奴かもしれないけれど、公人、まして一国の首相となったら、嫌なら近づかなければ、では済みません。自民党は総裁選の最中なので、安倍支持層の中核であるネトウヨ層へのアピールのために、韓国大統領からのお見舞いに対して無視を決め込んでいるのではないか、という指摘もあるようです。確かに、ありそうなことです。そうだとすると、ネトウヨ層という友達への仁義(と自らの総裁選勝利という政治的打算)のために、隣国の元首に対して無礼な対応をとった、友達への仁義のためなら隣国との関係の更なる悪化もいとわない、ということになります。本当に、一国の首相として、最低最悪の輩としか言いようがありません。。
2018.09.11
コメント(2)
-
喉元過ぎれば・・・・・・
震度7の「北海道地震」の大停電で体験したオール電化生活の落とし穴2018年9月6日の午前3時過ぎ。スマホの「緊急地震速報アラーム」と同時に襲った「激しい揺れ」で飛び起きました。最大震度7の北海道地震です。まもなくして北海道全域が停電に……。長時間の停電で気づいた「オール電化の落とし穴」についてお話します。6日のわが家の冷蔵庫には、調理しないで食べられるものがありませんでした。普段はパンやお菓子など、いくつかストックされているのですが、買いだめ派のわが家は、その日は買い出しの前日だったのです。家には「ガスコンロ」もありませんし、もう、最悪です!予想通り、アイスはでろでろ。肉類も解凍されてしまったのに、今すぐ調理ができないもどかしさ……。停電は北海道全域と聞いたので、すぐの復旧は無理だと判断。調理はあきらめ、すぐに食べられそうな調理済み食材を求め、信号機が止まった町へ買い出しに出掛けました。朝方に開店していているのはコンビニのみ。まずはおにぎりやパンを買っておけば、どうにか明日までは過ごせそうだと思いましたが、考えていることはみんな同じだったようです。朝の8時にして、お弁当の陳列棚はすでに空っぽでした。かろうじてカップラーメンがいくつか残っていましたが、お湯すら沸かすことができないもどかしさ。普段は当たり前にできていたことができないって、結構なストレスです。つくづく電気のありがたみを感じる出来事でした。この日一日は、とにかく口に入りそうなものを探すため、わずかに開店している店を探し回ることに。そんな中、近所の大型スーパーで「ガスコンロ」をゲットすることができました。長蛇の列に並んだかいがあります。その夜は、無事にカップラーメンを食べることができました。「頭がかゆい!」。汗っかきの娘が頭をかきだしたのは、停電した日の翌朝です。体のべたつきは「体拭きシート」でなんとかしのいだのですが、洗髪はどうしようもできません。固定電話が通じない!スマホの充電もできない!これはオール電化とは関係ありませんが、今回の震災で一番困ったことです。外部との連絡を取りたかったのですが、停電のせいで家の固定電話が通じません。結局はスマホに連絡が入るのですが、停電時フルに使われているスマホは、常に充電不足が続きます。そこは車の充電器で凌いだのですが、今度はガソリンが底をつきそうに……。どこのガソリンスタンドも、車が何十台も並んでいます。(要旨)---あまりに既視感のあり過ぎる話です。つい7年前、東京でも同じことが起こりました。北海道でも、あの時は同じことが起きなかったのかな?と疑問に思いましたが、改めて記録を調べると、東日本大震災において、北海道では震度4が最大だったのですね。津波の被害はあったけれど、おそらく停電は北海道ではほとんど起きなかったのでしょう。コンビニで真っ先に下降せずに食べられる食品がなくなったこと、その後しばらく、スーパー等で加工食品類の品薄が続いたこと、電気が切れるとガス暖房もつかえないこと、ガソリン不足で各地のガソリンスタンドに車の行列ができたこと、みんな、東日本大震災で経験したことです。震災についていろいろと思うところ災害に弱い社会 そして計画停電追記地震が起きたのは午後2時46分、その後バタバタして、いつ帰宅できるか分からない(結局、その後避難所に応援に言って一晩を明かすことになった)ので、午後7時頃職場近くのコンビニに買出しに行ってみたら、すでにパンだのお弁当だのの類は、ものの見事にすっからかんで、インスタントラーメンの類もほとんどなかったのですが、日清のカップヌードルだけが、わずかに残っていたのと、何故かケーキがあった。その日、お昼にカップラーメンを食べてしまったのです。それなのにまたカップラーメン、それにケーキとは(本来的には、わたしは甘いものが大好きですが)またすごい取り合わせの夕飯だな、とは思ったのですが、仕方がないのでそれを買いました。職場に戻って食べているあいだに、上司から避難所の応援に行くように指示されて、大慌てでかきこんだ記憶があります。というわけで、地震の瞬間私は職場にいて、しかも帰宅したのは翌日の午後だったので、自宅がその間どうなっていたかははっきりとは知らないのですが、どうやら停電にはならなかったようです。ただ、これもはっきりとは知りませんが、おそらくガスは止まったはずです。と言うのは、その6年前の2005年7月に東京で震度5を記録した地震の際は、自宅のガスが止まりました。ガスの供給は止まらなかったと思うのですが、自宅のガス配管は遮断弁が閉じ、ガスを使う際にそれを開かなければならなかったことは覚えています。東日本大震災のときも、東京ガスの供給が止まったかどうかは知らないのですが、少なくとも自宅の遮断弁は閉じたはずです。我が家はオール電化ではありませんが、電気が止まり、ガスが止まればオール電化と代わらない事態になってしまいます。ガスが復旧しても、ガス暖房と風呂釜は電気でコントロールするので電気が回復しなければ使えません。もっとも、ガスコンロは電気なしで着火するので、炊事は問題ありません。やかんでお湯を沸かせば暖房の代わりにもなるでしょう。加えて、登山道具の中に携帯ガスコンロがあり、ガス缶も4個か5個は持っています。そういえば、地震の後しばらく、登山用品店でもガス缶やヘッドランブは品薄でした。要するに、大きな災害が起きたとき、それから必要なものを買おうとしても、もうほとんど手に入らない、ということです。だから、それ以来我が家は非常食と水(2Lのペットボトル2ケース)は常に置いてあり、水に関してはそれに加えて、毎朝洗濯に風呂の残り湯を使うと、そのあとすぐに風呂に水を張ってしまいます。風呂桶に水が入っていない時間帯は、1日のうち20分か30分くらいしかないようにしています。でも、こういう対策って、地震の直後にはみんなやるのですが、だんだん忘れていくのです。まさしく喉もと過ぎれば熱さ忘れる、というやつで、わずか7年でも、結構忘却の彼方になっていたりするものです。この機会に、我が家も色々思い出さなければならないな、と思います。
2018.09.10
コメント(2)
-
泊原発を再稼動しろ、という暴論(修正あり)
前回の記事でも触れましたが、泊原発が停止中の北海道で、地震によって大規模停電が生じたことから、「泊原発が停止していなければ停電にならなかった」「泊原発を再稼動しろ」と叫ぶ人たちがいるようです。冬までに泊原発を再稼動して命を守れ例によって原発推進屋の池田信夫などが代表例です。最初にお断りしておくと、「今回のこの地震」に限定して言えば、確かに泊原発が稼動していれば停電は起こらなかったかもしれません。(修正:「今回のこの地震」に限定しても、泊原発が稼動していても停電が起こった可能性は高いようです、記事末尾に追記しました)泊原発付近では震度2程度だったということなので、おそらく設備の破損も緊急停止も起こらなかったでしょうから。しかし、それはたまたまに過ぎません。残念ながら、地震はいつどこで起こるか、現在の観測水準では事前に予測することができません。今回、結果として苫東厚真発電所の至近距離が震源だったので、苫東厚真発電所が停止したことから、大規模停電に発展しましたが、泊原発が稼働中に、その至近距離で大地震が発生することも、当然ありえます。というより、泊原発の真下には活断層があるので、そうなる可能性は低くはありません。大きな地震が一つ起これば、連動して周囲に地震が頻発する傾向がありますから、泊原発も大地震に襲われる確率は以前と比べて大幅に上昇していると思われます。地震発生時の北海道電力管内の電力需要は300万kwあまりだったようです。それに対して苫東厚真発電所の出力は165万kwで、つまり北海道の全電力需要の半分以上を苫東厚真発電所に依存していた最中に地震による配管の破損で急停止したことから、電力の需給バランスが崩れ、安全装置が働いて連鎖反応的に次々と停電が生じたようです。しかし、泊原発もまた、1号機と2号機が゛各57万9千kw、3号機が91万2千kwという、苫東厚真発電所を上回る出力を持っています。原発は出力調整ができず、また基本的には定期点検中以外は運転を停止しないので、もし泊原発が稼動していたとしても、苫東厚真発電所の代わりに泊原発が北海道内の電力需要の半分以上をまかなっている状態になっただけです。仮に原発を稼動したところで、「地域的に偏った少数の発電所に依存する」という、今回の停電の根本原因となった部分は、何も変わらないのです。したがって、その状態で、泊原発の至近距離で大地震が起きたら、やはり電力の需給バランスが崩れ、今回の事例と同様に大規模停電が生じたことは確実です。しかも、火力発電所なら燃焼を停止させればすぐに止まり、配管の破損も修理すれば済む話です。しかし、原発はそうは行かない。制御棒を挿入して核分裂を「停止」しても、核燃料は相当長期間発熱を続けることは今更説明の必要はないでしょう。そして、配管が破損すれば放射能漏れ事故ですから、火力発電所の配管破損よりはるかに深刻な事態となります。福島第一原発ほど酷い事態にはならないにしても、相当深刻な事態に追い込まれることは確実です。それを考えれば、原発が稼動すべきではない、原発を稼動することが解決策ではないことは明らかであると私は思います。ではどうすべきなのか。本質的には、泊原発にしろ苫東厚真発電所にしろ、北海道の電力需要に比べて、1基辺りの出力が過大に過ぎるところに問題があります。だから、1基止まっただけでも需給バランスが崩れる。より小出力の発電所を多数、地域的にも1箇所にかたまらないようにして稼動するほうが、今回のような不測の災害に対する備えとしては優れているのです。ところが、経済合理性という意味では、できるだけ大出力の発電所をできるだけ少数稼動させるほうが経費が削減できます。その兼ね合いが難しいところですが、北海道電力は不測の事態への備えよりも経済合理性を完全に優先したから、こういう事態になった、と言わざるを得ないでしょう。[追記]こちらの記事によると、泊原発が稼動していたとしても(なおかつ、泊原発自体が直接地震の被害を受けていなくても)、停電が防げたかどうかは、「わからない」とのことです。「30人31脚」という言葉で地震時の状況がたとえられています。確かに、泊原発が稼動していた場合(総出力200万kw)でも、残る需要100万kwあまりは、苫東厚真発電所がまかなっていた可能性はきわめて高いと考えられます。その100万kw(当時の発電量のおよそ1/3)が地震によって突然停止したとすれば、やはり電力需給のバランスが大きく崩れ、大規模停電に至った可能性が高いと考えられます。その場合、泊原発も、たとえ直接的な地震の被害がなかったとしても、巻き添えで停止せざるを得なかったでしょうし、その場合、外部電源喪失の危険性はより深刻なものだったはずです。
2018.09.08
コメント(44)
-

ああ、災害列島
今日は、先日の台風の記事を書こうと思っていたのですが・・・・・・北海道で震度7の地震、9人死亡 29人安否不明6日午前3時8分ごろ、北海道胆振地方を震源とする地震が発生し、厚真町で震度7、むかわ町と安平町で震度6強を観測するなど道内各地が強い揺れに襲われた。政府によると厚真町などで9人が死亡した。同町では大規模な土砂崩れが発生して29人の安否が不明で、救出活動が続いている。このほか道内では家屋の倒壊などに伴い、けが人は約370人に上る。地震の影響で道内のほぼ全域295万戸が一時停電し、市民生活や経済活動に大きな影響を与えている。厚生労働省の調べでは、6日午後3時時点で、349病院で停電が起きており、34の全災害拠点病院が自家発電機で対応。札幌市など33市町村3万255戸で断水が発生している。札幌市清田区の住宅街では液状化現象が発生し、道路に亀裂が入るなどの被害が出た。道教委によると、6日は小中高校など9割超の公立学校が休校した。交通機関への影響も大きく、新千歳空港の6日の発着便は、国内線、国際線とも全便欠航となった。JR北海道も6日朝の始発から全線で運転を見合わせ、札幌市営地下鉄と市電も始発から運転を取りやめた。今回の地震はマグニチュード6.7、震源の深さは37km(いずれも暫定値)と推定されている。胆振地方で発生した地震としては、統計を取り始めた1923年以降、最大規模となる。---北海道は7月に行ったばかりなので、ドキッとしました。大きな揺れを観測したのは札幌、千歳、苫小牧の周囲が中心で、今回行った阿寒湖や釧路、霧多布、昨年行った大雪山と層雲峡、上富良野はいずれも震度3だったのは不幸中の幸いです。ただ、停電の影響は北海道全土に及んでいるようです。北海道と言えば泊原発がありますが、今回は幸運にも震源が原発からは遠く、また運転中ではなかったので事故にはならなくて済んだようです。その代わり、北海道のほぼ全土で停電が生じてしまいました。そのことをもって「原発を再稼動しろ」と叫ぶ原発推進屋がさっそく現れているようですが、今回はたまたま稼働中の火力発電所が震源に近かったのでこういう事態になりましたが、原発の稼働中にその近くで地震が起これば、やはり同じことになります。もちろん、放射能を巡る事故のリスクも生じます。しかし、仮に放射能が漏れる事故がなくても、震度6の地震がきたら、原発は緊急停止するしかありません。原発が再稼動していたとしたら、電力需要の少ない深夜は、出力調整のできない原発だけを動かして、他の発電所はほとんど(あるいはまったく)停止していた可能性が高いので、その原発が緊急停止すれば、有無を言わさずすべて停電です。それにしても、本土に上陸した台風としては異例の強さと報じられた台風21号が関西を襲ったのが一昨日です。あの日は、東京も(暴風圏にはまったくかすらず、強風圏が通過しただけですが)大変な風の強さで、わたしの体感では、8月に来た台風のときより、はるかに風は強かったように思います。ただ、今回何故か、風がもっとも強かった時間帯、関東の平野部は雨が降らなかった(早朝と深夜日付が変わった後で激しい雨が降ったものの)のが、幸運でした。とはいえ、首都圏の鉄道ダイヤはかなり乱れたので、影響を受けた人も多いのではないでしょうか。わたしが職場を出て、強い風に驚いたとき、東京は暴風圏まで300kmくらい離れていたはずです。それでもあれほどの風の強さなのだから、台風直撃の関西はどれほどの事態になったかと思ったら、さっそく動画が上がっています。2013年10月に、関東でも上陸時950ヘクトパスカルほどの強力な台風が来たことがあります。あのときも強烈な台風でしたが、ここまでではありませんでした。沖縄や小笠原は別にして、本土でこれほどの台風の被害はほとんど記憶にありません。が、しかしそれによって関空が浸水して機能麻痺に陥ったのは、色々と将来に教訓を残したと考えざるを得ません。「台風の来週が満潮と重なった」と言いますが、確かに満潮には重なりましたが、小潮か、その直後くらいの時期であり、つまり干満の差がかなり小さい時期でした。※※潮の満ち引きは海水が月の引力に引かれて起こります。一方、大潮小潮は、太陽と月の位置関係によって起こります。つまり、太陽と月と地球が一直線に並んだとき(満月または新月のとき)は、太陽と月の引力が合算されて作用するため、干満の差が大きく(大潮)、一方地球を角として太陽と月が直角に位置したとき(半月)と、太陽と月の引力が相互に引っ張り合うように作用するため、干満の差が小さくなります(小潮)。それにもかかわらずあれほどの被害が生じてしまったということは、もし大潮の満潮だったら、もっと波高が低くても同じ被害が生じた、ということです。また、空港島と陸を結ぶたった1本の橋にタンカーが衝突して、交通途絶する事態となりました。あのタンカーは、航空燃料を関空に輸送したあと、付近に停泊中に台風に襲われ、碇を下ろしていても2imも流されて(走錨)橋にぶつかったということです。異例な規模の台風が来ることはあらかじめ分かっていたのに、なんであんな場所に止まっていたのか、と思いましたが、2kmも流されることまでは想定していなかったのでしょう。もっとも、走錨は一度起こると、荒天が収まるまで止めるのが難しいようなので、そのくらい流されることは想定すべきだったのかもしれませんが。そのことよりも、より根本的に陸地との連絡通路が(海路を除けば)たった1本の橋だけ、というのは、災害対策や危機管理上、いささか問題なのではないか、という気がします。同じく東京湾上の島(または中州)である羽田空港は、道路橋、鉄道橋、地下トンネル、何本もの接続ルートがあります。それに加えて、今回の北海道の地震です。地震・津波、火山の噴火、台風、長雨、残念ながら日本は本当に災害大国です。その中でも、特に今年は台風を中心に水害が多かった。しかし、これだけ短期間に連続するとは思いませんでしたが、考えてみれば、災害とはえてしてそのように連動するものです。地震と台風には直接の因果関係はありませんけど、地震と津波はもちろん連動するし、複数の地震も連動するし、地震と火山の噴火も連動する傾向があります。東京は、さいわいにも何故か繰り返し起こった水害の被害をほとんど受けませんでした。今年ここまでは、ですけど。未来永劫そのまま・・・・・・では済むはずがありませんね、残念ながら。
2018.09.06
コメント(6)
-
災害時の貴重な教訓を消し去ろうという暴挙
関東大震災 朝鮮人慰霊式典 知事追悼文なし、市民は批判1923年の関東大震災から95年となる1日、犠牲者の慰霊法要が東京都墨田区の都慰霊堂で営まれた。小池百合子知事の追悼の辞が代読されたが大震災での朝鮮人虐殺に触れず、民間の式典にも小池氏は追悼文を送らなかった。昨年に続く判断で、市民らは「惨劇を繰り返さないと誓うのが知事の役目なのでは」と批判した。法要では小池氏の追悼の辞を副知事が代読した。「災害の脅威を風化させず、東京の防災に万全を期してまいります」などと述べたが、朝鮮人虐殺には直接言及しなかった。送付は歴代知事が続けてきたが、小池氏は記者会見で「法要で全ての方々へ哀悼の意を表している」と説明していた。民間式典の主催者は「知事の判断は虐殺の史実を否定しようとする動きに結果的にくみし、首都東京でヘイトスピーチや民族差別を助長してしまう」と残念がった。法要に参列した東京都羽村市の女性は「震災から95年、その時にどんなことが起こったのか今では知らない人が多い。負の歴史にもきちんと向き合う必要がある。知事は率先して、歴史を伝える役割があるのに」と話した。慰霊堂そばでは別の団体が独自の慰霊祭を開き、「数千人虐殺も捏造(ねつぞう)だ! 日本人の名誉を守ろう」と主張する看板を掲げた。政府中央防災会議の報告書(2008年)は朝鮮人らの犠牲者数について、約10万5千人の震災死者数の「1~数%」と記述。「朝鮮人が武装蜂起し、放火するといった流言を背景に、住民の自警団や軍隊、警察の一部による殺傷事件が生じた」と指摘している。---小池知事が、朝鮮人虐殺朝鮮人虐殺を追悼する式典に式辞を送らず、震災犠牲者への追悼の辞でもそこに触れなかったのは、今年が初めてではなく、去年からのことです。昨年も当ブログでこの件を取り上げましたが、これは実に恐るべきことであると私は思います。災害は天災です。防災対策など手段を尽くすことで、ある程度は被害を局限できるとしても、人間の努力で災害の発生を完全に防ぐことは不可能です。が、流言飛語による大量虐殺は違います。これは人災であり、人間の努力で止められるはずであり、止めなくてはならないものです。ところが、当時の日本の官憲は、この人災を食い止めるための努力をあまりしなかった。これが、行き着くところまで行くと、ルワンダの大量虐殺になります。ルワンダでは、大規模災害が生じたわけではありませんが、大統領の搭乗する飛行機が正体不明の武装勢力に撃墜されて大統領死亡、という異常事態の発生がきっかけで大量虐殺が起こりました。大規模災害(や、国家を揺るがすような異常事態)の発生時に、デマが飛び交い、それが少数の人間集団に対する攻撃に結びつき、それがやがて殺戮にエスカレートする。残念ながらこれは、もっともあってはならない出来事ですが、にもかかわらず、人類の歴史上何度も繰り返されてきた悲劇です。であるならば、今後また起こるであろう大規模災害の発生時に、同じ事態の発生を繰り返してはならない、そのために最大限の努力を払うのは、防災の責任者たる行政のトップの大きな責務でしょう。当然、過去のそのような事例を反面教師として、そこから多くの教訓を汲み取るべきとであるはずです。それなのに、行政のトップが、「韓国に謝ったら負け」みたいな、実にくだらない国家意識を丸出しにして、過去の事例を直視することを避ける、そのような姿勢で、災害発生時のデマとそれによる少数派迫害を食い止めることができるのか、あるいはそもそも食い止めるべきという意思を持っているのか、きわめて重大な疑念を抱かざるを得ません。
2018.09.04
コメント(3)
-
世の中の仕組みは、科学だけでは動かない
原発推進派の池田信夫が、福島第一原発から出て、タンクに貯蔵されている汚染水(トリチウム水)をサッサと海に流せと叫んでいます。トリチウム水を止めているのは福島県漁連だマグロは汚染水より危ない池田に限らず、こういうことを叫ぶ「科学通」(自称)は少なからずいるようです。墨田金属工業日誌が、それを痛烈に批判しています。「硫黄酸化物の大気放出禁止は非科学的だ」硫黄酸化物は火山から大量に噴出される。人間活動の比ではない。硫黄そのものは生物に必須の元素である。だから工場からの硫黄酸化物も大気排出してよい。希釈のために高い煙突を立てて、その濃度以下まで希釈して排出すればよい。科学カルトがそう言い出したら馬鹿にされるだろう。公害防止の歴史や大気汚染防止の枠組みを無視している。そもそも法はそれを許さない。だが、お理工さんたちはトリチウム水でそれを言っている。曰く自然界で大量生成される。半減期は短い。人間の体内からもすぐに出ていく。そもそも体の中に何ベクレルあると思っている。そう言い出している。だが、原発からの排出物である。それを全く無視している。排出物を垂れ流しにすることは許されない。その仕組みがある。彼らのいうことは不法投棄業者の逃げでしかない。「自然で枯れ木は何トン出ると思っているのか?」とうそぶいて建築廃木材を捨てる行為を肯定するのがお理工さんである。あるいは、糞尿の海洋投棄と並べてもよい。魚介類も排出する。糞尿を捨てたところで害は少ない。昔はそうしていたし、今でも沿岸から50キロ離れれば船舶はそうできる。だから糞尿は海洋投棄してもよい。連中のいうトリチウム海洋投棄肯定はそれと同じだ。(要旨・以下略)---タイトルと書き出しがいささか逆説的ですが、要旨としては、まったくそのとおりと言うしかありません。実のところ、トリチウム水が本当に、完全に無害なのかどうかについては異論があり、確実なことはいえません。加えて、福島第一原発の汚染水は、トリチウム以外の放射性物質は除去した、ということになっていますけど、実際にはそれ以外の放射性物質も基準値を超えることが度々あるようです。その点は措くとしても、池田の、マグロは汚染水より危険、という言い分に至っては、馬鹿としか思えないものです。第一に、マグロが危険だから、別の危険な水を垂れ流してよい、という理屈はないでしょう。懲役5年の犯罪を犯した奴が許されて社会復帰しているから、俺だって懲役2年くらいの犯罪を犯しても問題ない、と言っているようなものです。第二に、マグロの水銀濃度が高くて人体に有害だとしても、マグロは食材として美味しい、という事実があります。だから食べる。「ふぐは食べたし命は惜しし」なんてことわざもあります。美味しい魚であるからこそ、危険性とのトレードオフが生じます。しかし、例えば糞尿は人体に危険なものではありません。加熱処理してしまえば、口にしても何の問題もない。だからと言って、そんなものを口にする人間はいない。口にするメリットが何もないからです。原発の汚染水を海に流すことも同じです。少なくとも環境負荷という意味で、メリットは何一つありません。そんなものをマグロの危険性と同列に論じるのは、無意味の極みです。汚染水を海に流したい、というのは、単に、そうするほうが安上がりだという政府(と東京電力)の都合でしかありません。90万トンというと莫大な量に感じますが、東京都民が1日に使用する水の量が400万トンであることを考えると、たいした量ではありません。墨田金属が「科学カルト」「お理工さん」と揶揄する連中と同様、池田も「科学的根拠が」と言いますが、世の中は科学的根拠だけで動いているわけではありません。「マグロは美味しい」にどのような「科学的根拠」があるのか、「糞尿は汚い」「ゴキブリは汚い」等々にいかなる「科学的根拠」があるのかと考えてみれば、世の中「科学的根拠」など無関係に動いていることのほうがよほど多いことが分かるはずです。それを無視して「科学的根拠」を錦の御旗に掲げても、理解も納得も得られるものではない、ということです。
2018.09.02
コメント(2)
-

7月29日の演奏
もう1ヶ月前になりますが、ティエラ・クリオージャ前回の中野区哲学堂公園での演奏を1曲だけYouTubeにアップしました。猛烈な暑さの中、汗だくでの演奏。汗で、顔もケーナもびしょ濡れで、滑る滑る。今まででも、もっともアツい演奏でした(笑)途中で3オクターブが出なくなってきて、このときは3オクターブになると力を振り絞って吹いているのでそこだけ音程がちょっと上ずっています。普段でも、基本的にケーナの3オクターブはありったけの息を使わないと出ないものですけどね。それにしても、このときは汗だくになって以降、3オクターブにてこずりました。この曲、別グループでも演奏していますが、そちらでは、わたしはケーナ副旋律、ティエラ・クリオージャでは主旋律です。そして、以前にも紹介しましたが、9月9日(日)に、再び中野区哲学堂公園で演奏します。チラシが完成しましたので、ご紹介します。さらにその先、11月10日(土)、正式な案内は後日行いますが、キラ・ウィルカのライブを行う予定です。多分、そのお店で演奏できるのはそれが最後になるかもしれません。詳細はまた後日。
2018.09.01
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1