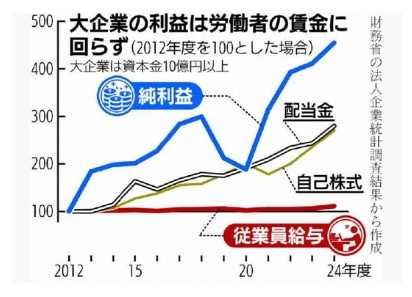2018年02月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
速くなっても遅くなる(謎)
モバイル「5G」時代へ…現在の100倍の速度世界最大級の携帯電話・タブレットの展示会「モバイル・ワールド・コングレス」が26日、スペインのバルセロナで開幕した。NTTドコモが次世代通信規格「5G」を活用したロボットを出展するなど、5Gが主役となっている。一方、韓国・サムスン電子はスマートフォンの最新機種を発表し、米アップルに対抗する構えをみせた。NTTドコモのブースでは、人型のロボットが書道をする様子が披露された。全身にセンサーを取り付けて書道をする人間の動作が、5Gの技術を生かせば、瞬時にロボットに伝わる。5Gは、現在主流の通信方式の100倍の通信速度を持つとされ、ドコモは2020年のサービス開始を目指している。---「現在の」100倍と言っても、現在の規格上の上限速度をよく知らないので、その100倍がどの程度の速度なのか分かりません。検索したところ、5G通信の規格上の上限速度は10Gbps程度を想定しているようです。一方、現在の通信規格であるLTEの規格上の上限速度は150Mbpsから75Mbpsです。なるほど、確かにその100倍です。すげー!と、言いたいところですが、規格上の上限速度と現実の上限速度は全然違ったりします。私の自宅の固定回線(フレッツひかり)は規格上の上限速度は100Mbps(今はギガビットが主流でしょうが、我が家は諸事情で上限100Mbpsの契約のままです)なので、LTEの速度は固定回線と堂等かそれより速い!ということになります。が、現実には、固定回線もモバイル回線も、規格上の上限速度なんて、出たためしがありません。この記事を書いている27日夜11時前現在、固定回線の速度は、速度測定サイトで計ると、最速で10Mbps程度という悲惨な数字になっています。ただし、空いている時間なら話は別です。この記事を校正している28日朝7時現在では、同じ速度測定サイトで90Mbpsほどの速度が出ていますから、規格上の上限の9割くらいのスピードです。一方、モバイル回線(IIJmioの格安SIM)は、規格上の上限速度は75Mbpsをうたっていますが、過去何回か測定した限り、空いている時間のもっとも速い速度でも6Mbpsしか出ず、遅いときは1Mbpsも出ません。つまり、固定回線は条件がよければ規格上の上限に近い速度が出るけれど、格安SIMのモバイル回線は条件がよくても規格上の上限速度の10分の1も出ない、ということになります。実用上は6Mbpsも出れば(固定回線での10Mbpsは言うに及ばず)FHD画質の動画を見るのにも、それほどは支障はありませんが、混みあっているときのモバイル回線では、FHD画質の動画を見るのはほとんど不可能です。格安SIMではない、ドコモ直接契約のモバイル回線ならもっと速いでしょうが、それでも実効速度が規格上限の半分に届くことすら、滅多にないでしょう。したがって、規格上の上限速度は固定回線もモバイル回線も同等でも、実効速度では固定回線の方が遥かに速い、ということになります。というわけで、5Gの規格上の速度10Gbpsをスゲー!と思うよりは、「規格上の上限速度よりも実際の速度の方が大事じゃね?」と思ってしまうのです。わたしが初めてパソコンを手にした1999年当時はまだ56Kbpsのアナログモデムの時代で、それが2001年にADSLを導入したとき、まだ規格上の上限速度は1.5Mbpsに過ぎなかった(実行速度では1Mbpsにも達していなかった)のですが、それでも革命的に速い、と思いました。それ以降、同じADSLの上位規格(下り50Mbps)、さらにはフレッツひかりに乗り換えましたが、それぞれの体感差はそれほど感じないのが現実です。もちろん、アナログモデムは言うまでもなく、ADSL1.5Mbps時代は、まだ動画をネットで見ることはなかった、ということはあります。回線の高速化に伴ってネット上のコンテンツもどんどん重たくなっていくので、規格上の上限速度がいくら高速になっても、体感的な快適さはそれほど向上しないのが現実です。もっとも、本当のところを書くと、個人的には、モバイル回線は、何しろ格安SIMですから、 コストパフォーマンス的にはさして不満もありません。むしろ不満は固定回線にあったりします。というのは、前述のとおり、フレッツひかりは、混雑時とそうでないときで、速度差が極端なのです。10Mbpsと書きましたが、ひどい時は5M以下になるときもあります。ADSLの50Mbpsの時代は、私の環境では実効速度は25Mくらい出ていました。光回線の状態の良い時よりは遅いとは言え、FHD画質の動画を見るにも問題はありませんでした。そして、ADSLは、混雑時にもそれほど速度は落ちなかったのです。どんなに遅い時でも動画視聴にストレスを感じたことはありません。一方、ひかり回線が空いている時に90M出ても、「速い」と体感するのは、動画を視聴ではなくアップロードするとき、大容量のファイルを友人とやりとりする時くらいです。その時はたしかに速いと思いますが、そんなに頻繁 いすることではありません。逆に混雑時には、いつも動画は途切れるし、重いサイトの表示は時間がかかるので、体感的にはADSLより明らかに「快適ではない」のです。戻せるものならADSLに戻したいと思ってしまう今日この頃です。現実には、物理的な回線が銅線から光回線に切り替えられているわけで、もう戻せないのですが。
2018.02.28
コメント(0)
-
憲法違反かどうかはともかく、二重国籍は容認すべき
「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。(以下略)---二重国籍をめぐる問題は、蓮舫の二重国籍「問題」の際に記事を書いたことがあります。基本的には、わたしは二重国籍は容認されるべきであると考えています。それが「憲法違反」とまで言えるかどうかは、正直に言ってやや疑念を感じますが、日本の国籍法の「二重国籍を認めない」というタテマエは、実質的には意味がないのが実態です。日本の国籍法は、日本国籍と外国籍の二重国籍について、以下のように規定しています。第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。元々日本国籍しか持っていなかった人が、自己の意思で外国籍を取得すると、日本国籍を失います。(第11条第1項)おそらく、引用記事で提訴するという方は、大半がこのパターンなのだろうと思います。しかし、自己の意思によらず外国籍を付与された人は、一定年限までに日本国籍を選択する宣言を行えば、日本国籍を失うことはありません。(第14条第1項)ひょっとすると、提訴された方の中には、この国籍選択手続きの際、外国籍を選択して日本国籍を失った方(第11条第2項)もいるかもしれません。「日本国籍を選択して外国籍を放棄する」という宣言はあくまでも日本の国内法に基づく手続きであり、そこで日本国籍を選択しても、本当に外国籍を失うわけではありません。国籍に関する権限はその国の政府にしかないのであって、日本政府に、日本以外の国の国籍を与えたり奪ったりする権限はないからです。一応は、日本国籍を選択した場合は、「外国籍の離脱に努めなければならない」という努力義務はあるものの、努力義務でしかなく、実際に外国籍離脱を求められることはありません。更に、国籍選択には経過措置があって、1985年(国籍法が改正された年)以前から二重国籍だったものは、国籍選択手続きを行わなくても、自動的に日本国籍を選択したものとみなされます。また、外国人が日本に帰化した場合も、元の国籍からの離脱は、日本国籍取得後の努力義務に過ぎません。もちろん、自己の意思で外国籍を取得した場合でも、その事実を日本の行政機関に届け出なければそれまでです。そうやって、外国籍を取得しながら日本国籍も維持している人は、おそらく海外在住者などに相当数いるのでしょう。つまり、現状は、自己の志望で外国籍を取得して、その事実をわざわざ律儀に日本政府(在外公館や市区町村役所・役場)に届け出た人、国籍選択の際にわざわざ外国籍を選択と届け出た人だけが日本国籍を失う、という運用実態になっているわけです。だったら、外国籍を取得しても黙っている、国籍選択の際には「日本国籍を選択します」と宣言だけしておくか、そもそも選択手続きを行わなければよい(運用の実態としては、期限までに国籍選択の宣言をしない二重国籍者に対して督促することもありません)ということになります。簡単に言えば、バカ正直なごく一部の人だけが日本国籍を失い、大半の人は二重国籍になっている、ということです。国籍法国粋主義者の中には、行政がきちんと調査しないのがけしからん、などと空理空論を述べるものがいますが、。そんなことは明らかに実行不可能なのです。外国籍の有無を調べる権限も能力も、日本政府にはありません。日本政府が外国の政府に対して「うちの国民の××さんがおたくの国の国籍を持っているかどうか」なんて照会したところで、絶対に回答はもらえません。主権と個人情報の問題です。逆に外国の政府が日本に対してそんな照会をしたところで、やはり絶対に回答しないでしょう。このように、国籍法の二重国籍を排除しようという規定は、まったく意味を失っているのが現実なのです。また、それによって二重国籍者が多数存在することで、何か不都合なことがあるかというと、何もないのが現実です。だったら、このような実効性のない無意味な規定は撤廃して、二重国籍を公式に容認すべきであるとわたしは思います。
2018.02.26
コメント(6)
-

今月の葛西臨海公園
今月も、12日・17日・今日25日と3回葛西臨海公園に鳥の写真を撮りに行ってきました。まず12日の分からスズガモ。まったく珍しい鳥ではなく、葛西臨海公園の沖合いに何千羽と浮いていますが、いつも沖合いにいるのであまり近い距離で撮影する機会はありませんでした。それが、何故か西なぎさの波打ち際にいたので、アップで撮影。ジョウビタキ。1月に撮影したときよりずっと近距離、かつ鮮明に撮影できました。同じくジョウビタキのメス、またはオスの若鳥。葛西臨海公園でも、他の場所でもジョウビタキは何回か見ていますが、いつもメスタイプばかりで、オスはまだ撮影できていません。オオジュリン。ホオジロの仲間です。夏羽では頭が真っ黒になりますが、冬羽では頭の模様はホオジロと良く似ています。そして17日西なぎさでスズガモの群れを撮影したら、その沖の杭の上に、白鷺が止まっていました。いや、写真を確認するとサギではなく・・・・・・くちばしを隠しているので分かりにくいですが、九分九厘クロツラヘラサギです。ヘラサギは、名前はサギですが、実際はトキの仲間です。ウミアイサ。1年前に同じ葛西臨海公園で見て以来です。この日はくもりで明るさが足りず、あまり鮮明な写真ではありません。コガモ。珍しい鳥ではありませんが、やはり今年になってからは初めて撮影しました。ノスリ。ノスリやオオタカといった猛禽類も、私が子どもの頃は、東京近郊では滅多に見ることがなかったように記憶していますが、今は冬場は珍しくありません。そして今日25日。やはり曇り空で、明るさが少々足りませんが。ビンズイ。明治神宮で1年前に見て以来です。そのときは1羽だけでしたが、今日は5~6羽いました。地味な鳥ですが、セキレイの仲間です。同じくビンズイ。葛西臨海公園の大観覧車のたもと(中央奥に観覧車の支柱が写っています)を、何故かカルガモ1個小隊が一列縦隊になってゾロゾロと前進中。どこに向かっているのかな?ハジロカイツブリ。子どもの頃は、なかなか出会うことのできなかった鳥でしたが、今は冬場の葛西臨海公園は行くたびに必ず遭遇します。ノスリが飛んでいます。オオジュリン。カワセミ。日本の野鳥の中でもトップクラスに人気があり、いつも撮影者が群がっています。今日も私以外に2人撮影している方がいました。アオアシシギ。珍しいシギではありませんが、今年に入ってからは初めて撮影しました。12日と17日は、この撮影した場所(下の池)には、シギもチドリも全然いなかったのですが、今日はアオアシシギだけがいました。アカハラ。これも珍しい鳥ではなく、1月にも撮影していますが、今日は至近距離からアップで撮影できました。ハイタカ、と思われます。シルエットになってしまっているし、遠いので確実ではありませんが。ハイタカだとすれば、一応、初めて撮影する鳥です。まあ、アリバイみたいな写真ですけど。
2018.02.25
コメント(0)
-
時間よりマシなものさしは存在しない
条件異なる調査結果を比較 厚労省働き方改革をめぐり、安倍首相が撤回した、国会答弁の基になったデータについて、厚生労働省は、条件の違う調査結果を比較していたことを認めた。安倍首相は先日、裁量労働制で働く人の労働時間について、「一般労働者より、短いというデータもある」としていた、過去の答弁の不備を認め、撤回・陳謝した。厚労省は19日、この答弁の基となった、5年前の調査のデータに関する調査結果を公表した。それによると、一般労働者の労働時間は、1カ月のうち、最も残業の長い日のデータを使う一方、裁量労働制で働く人については、単に1日の労働時間について聞いた結果を用いており、裁量労働制の労働時間の方が、短くなりやすい不適切な比較がなされていた。加藤厚生労働相は、「一般労働者と裁量労働制で、異なる仕方で選んだ数値を比較していたことは、不適切でありました。深くおわび申し上げます」と述べた。19日の衆議院予算委員会では、加藤厚生労働相がデータの不備について撤回する1週間前に把握していたことを明らかにしたのに対し、野党側は抗議して、委員会を退席するなど徹底抗戦の構え。野党6党は19日、国対委員長会談を開き、政府に対し、働き方改革法案の提出見送りを求める方針で一致した。 ---恣意的なデータを用いて「裁量労働制の方が労働時間が短い」という結論を出そうとして、それがバレちゃった、というお話です。だいたい、裁量労働制の拡大は、経済界(経営者)が要求していることです。企業経営者がどういう意図でそのような要求を掲げるのか、と考えてみればよいのです。社員の労働時間を減らしたいとか、給料をできるだけ増やしたいとか、そんな意図で彼らが裁量労働制の拡大を主張するわけがないのです。人件費を少しでも減らしたいと考えるのが大方の企業経営者です(もちろん、それを非常識な手法で強行したいとまで考える経営者はわずかであるにしても)。だから、企業はなかなか賃上げをしようとしないのです。裁量労働制の拡大も、当然そのほうが人件費が削減できると考えるから要求しているに決まっているじゃないですか。独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査では、1ヵ月の実労働時間の平均は、専門業務型裁量労働制で206.5時間、企画業務型裁量労働制で197.2時間、通常の労働時間制で185.0時間であり、裁量労働制の方が労働時間が長という結果が出ています。裁量労働制の問題点は、過去にも記事を書いたことがあります。日本でも、すでに限定された職種で裁量労働性が導入されています。その建前は、時間管理をされず労働者自身が自由に時間管理を行う働き方ですが、実際にはたいていの場合、「名ばかり裁量労働制」で、時間管理の裁量権が労働者にはないのが実態です。以前の記事でも紹介しましたが、前述の同じ調査結果によると、裁量労働制にも関わらず、専門業務型裁量制の42.5%、企画業務型裁量制の49.0%の人が「一律の出退勤時刻がある」と回答しています。要するに、半分近くは「裁量労働制」と言いつつ時間管理されているのです。現状は、裁量労働制が認められるのは、専門性、特殊性が高い、限られた職種のみです。それでもこんな実態だというのに、裁量労働の対象を広げれば、実態はまったく裁量労働ではないのに、残業手当を払わないだけの、名ばかり裁量労働がさらに増殖していくことは必至です。仕事とは他者に何かを与えて、対価をもらうのが本質です。程度の差はあっても、他者との交渉のない仕事などありえません。また、雇用-被雇用の関係においては、期日までに成果を出せば、過程は問いません、などという仕事は、世の中にはほとんど存在しません。そもそも、「成果」自体が時間と不可分である仕事が多いし、そうでなくとも、雇い主、あるいは顧客との連絡、報告、協議は絶対に必要です。となれば、裁量労働などというお題目を掲げたところで、給与所得者である限り、勤務先や顧客、同僚や上司が稼動している日時に拘束されることは、避けようがありません。成果主義、と言えば聞こえが良いものの、成果を図る共通の物差しなどありません。同じ企業の中でも、部門により担当により、成果の物差しは異なります。まして、いわゆる管理部門など、何をもって成果とするのか。競争原理至上主義者たちは、労働の対価を時間という物差しで測るのは古い、と叫びます。ですが、古い(けれども社会に定着している)、というのはそれだけ物差しとして優れているということです。確かに、時間というものさしは万能ではありません。非合理的な部分が皆無とは言いません。しかし、世の中には万能の物差しなど存在しないのです。そういう意味では、労働の対価を金銭で支払う、ということ自体、報酬の支払い方として万能とは限りません。物々交換、バーター取引の方が優れている場面も皆無ではありません。それでも、現代社会において金銭より優れた支払い方法はないので、給与の支払いは金銭によってすることが定められているのです。時間による労働量の測定もそれと同じです。万能ではないのは確かです。が、それよりマシな測定方法は存在しない以上、時間によって労働の成果を測定することが基本原則となるのは当然のことです。そうである以上は超過勤務に残業手当を出すのも当然のことなのです。裁量労働制の拡大は、そのような雇用の基本原則を破壊するものであり、人件費を安くしたい企業経営者にとってはメリットがあっても、働く人にとって、概ねデメリットの方が遥かに大きいものと言うしかありません。
2018.02.23
コメント(2)
-
高騰し続ける大学の学費
大学の学費が高騰を続ける2つの理由少子化で子どもの数が減っているのに、なぜ学費は上がっているのか――。そんな疑問を抱く人も多いだろう。事実、国立大学の授業料は、1990年の33万9600円から53万5800円へと約6割も上昇。「国立大学に入学してくれれば何とかなる」という親の期待は通用しないのかもしれない。そもそも国立大学の運営費は、国の「運営費交付金」がその多くを占める。16年度で約44%だ。この交付金が年々下がっている。04年に国立大学が法人化され、受益者負担へと政策が転換されたからだ。国の財政が厳しいことから「一定の受益者負担を求めよう」と、法人化された04年度から16年までの12年間で1470億円(11.8%)の交付金が削減されている。削減された分を授業料の値上げで賄ってきた。15年12月、文部科学省はこのまま交付金の削減が続くと、国立大学の授業料が31年度には年間約93万円になると試算を公表した。計算上の数字で実際に上げると決定したのではないと撤回したが、財政が厳しいなか、今後政府がどれだけ教育に財源を割くことができるかは難しい問題。年間約93万円とすれば、さらに約40万円の値上げを想定していることになる。そこまで学費を負担して大学に通わせる意味があるのか、という費用対効果としての疑問も生じる。国立大学の「運営費交付金」に当たる私立大学の「私立大学等経常費補助金」の支給はほぼ横ばいだが、もともと支給金額が少なく、収入の多くを学生からの学費で賄っている現状がある。一方で人件費や設備費、研究費などの経費が年々かさんでいるため、私立大学でも授業料の値上げが続いている。(要旨・以下略)---半年以上も前の記事ですが、大学の学費の高騰は我が家の近い将来にも影響の大きな問題です。まず、引用記事に補足ですが、「国立大学の授業料は、1990年の33万9600円から53万5800円へと約6割も上昇」とありますが、これは狭義の授業料のみの話です。実際に大学に払うお金は、もちろんこれだけではありません。これ以外に28万円余りの入学金があります。更に、大学によっては設備費などを取られる場合もあるようですが、すべての大学、というわけではないようです。それらを合計すると、初年度の学費は全部で80万円以上かかります。従って、もし記事のように(単なる試算に過ぎないとはいえ)授業料が93万円になったとすれば、初年度の学費合計は120万円か、それ以上になってしまいます。私は1986年当時、私大でしたが初年度の学費(入学金等一切込みの、大学に払った金額)60万円に満たず、2年目以降は40万円代半ばくらいだったと記憶しています。4年間のトータルで200万円に届かなかったはずです。当時としても私大の中では「下から何番目」という学費の安い大学で、第一志望だった某大学(合格できなかった)は、それより初年度で15万か20万高かったと記憶していますが、それでも今の国公立より安い。※自分の記憶が正確かどうか、絶対の自信はないのですが、調べてみたものの母校の30年以上も前の授業料や入学金の額は分かりませんでした。ただ、文部省のホームページに掲載されている、国立大学と私立大学の授業料等の推移によれば、1986年の私大の学費平均は、授業料497,826円・入学金241,275円です。私の記憶する学費は、これに比べて入学金は大幅に安いものの、授業料は多少安い程度です。「全国有数の学費の安い私大」という当時の評判から、おそらく大きな記憶違いはないと思われます。前述の文科省のサイトからわかることは、私の母校ばかりでなく、当時の私大の平均値でも、今の国立大より安かった、ということです。ちなみに、わが母校の現在の学費は初年度120万円くらいなので、2倍くらいに上がっています。国公立はどうかというと、前述の文科省のサイトによれば、1986年当時は授業料25万、入学金15万、合計40万円ですから、やはり今は2倍以上です。当時、世の中はバブル真っ盛り。今の世の中の所得水準は、当時よりたいして上がっていません。それなのに、大学の学費だけは2倍。そりゃ、子どもを持つ世帯は苦しくなります。その挙句に、高額の奨学金や学費ローンを借りて、卒業後に返済できなくなり、行き詰まり、自己破産という例が多発して社会問題にもなっています。江戸時代の昔から、日本は同時代の中では教育熱心な国でした。(諸説ありますが、江戸時代の日本の識字率は、もちろん今よりははるかに低いのですが、それでも世界一だった、あるいは少なくとも世界トップクラスだった、と言われます)それが日本の「国柄」であり、経済発展の原動力にもなりました(戦前の軍拡の原動力となった一面も否めないですが)。そのような日本の「地力」の原動力を放棄して、明るい未来の展望が開けるようには思えません。
2018.02.21
コメント(3)
-
ああ、ネトウヨレベルの国際政治学者
三浦瑠麗氏、ワイドナショーでの発言に批判殺到国際政治学者の三浦瑠麗氏が2月11日に放送されたテレビ番組「ワイドナショー」に出演し、北朝鮮のテロリスト分子が日韓に潜んでいると発言、とりわけ大阪が危険だとの認識を示した。これに対し、Twitterでは「根拠がない」といった指摘や、在日コリアンに対する憎悪を煽りかねないと懸念する声が上がっている。~三浦氏は朝鮮半島における安全保障問題に触れ、戦争によって北朝鮮の指導者・金正恩氏が死亡した場合、ソウルや東京、大阪に潜む北朝鮮のテロリストたちが活動し始めると指摘。中でも大阪について「今ちょっとやばいって言われていて」などと、潜伏者が多数いるとも受け取れる発言をした。(以下略)---今をときめく(笑)国際政治学者サマの、何とまあ程度の低い発言か、と驚かざるを得ません。確かに、拉致問題などを見る限り、70年代から80年代当時、日本国内に北朝鮮の協力者がいたのは、おそらく事実であろうと思います。ただし、「だからやっぱり戦争になったら北のテロリストが」と言うのは、あまりに短絡に過ぎます。第一に、70~80年代当時に北朝鮮の協力者がいた、ということと、現在もいる、ということはイコールではありません。日本国内の社会状況、政治状況がこんなに変化しているのに、工作員だけが何の変化もなく存在し続ける、と考えるのは不自然というものです。第二に、北朝鮮への協力者がいたことは事実でも、彼らが武器を用いた破壊工作を行った痕跡はありません。第三に、大阪という具体的な地名を挙げて「今ちょっとやばい」と言うことの根拠が、まったく不明確です。過去の拉致問題を見ても、圧倒的に多いのは日本海沿いの地域であり、東京やその周辺の事例もありますが、大阪(および神戸)の事例は「あることはある」という程度でしかありません。要するに、なんら具体的根拠が伺われないヨタ話に過ぎない、ということです。批判を受けると、三浦は阪神淡路大震災の際に被災地から工作員の隠匿する迫撃砲が発見された、という根拠の不明確な話を根拠に挙げて反論しているそうですが、その「被災地から迫撃砲」も、事実は「旧日本軍の迫撃砲弾が被災地から発見された」というのが真相のようです。つまり、工作員とはまったく無関係の事案です。結局、2チャンネルだのヤフーニュースのコメント欄だのにたむろしているネトウヨ連中の言っていることをそのまま引き写しているだけ、ということです。大阪という地名を挙げている辺りからもそれがうかがわれます。大阪の名を挙げることの根拠が不明確と私は書きましたが、実のところ、根拠は不明確ですが、心情は明確であるように思います。つまり、ネトウヨ連中が何かと「大阪民国」などと揶揄するその風潮に乗っかっただけだろ?ということです。治安維持の実務面では、あらゆる事態を想定して対策を講じる必要があるでしょうから、工作員の存在を想定してひそかに対策を考えること自体は、やむを得ない面はあります。しかし、万が一に備えて対策を講じることと、その「万が一」を国名を名指しして(根拠も示さず)宣伝してまわることの間には大きな差があります。そのようなこともわきまえず、差別と憎悪を助長するような無根拠なヨタ話をテレビで公言する国際政治学者、悲しくも戦慄すべき事態です。かつて、ルアンダで大量虐殺が起こったとき、それに先立って、まずラジオ局が対立する少数派「民族」に対する憎悪の宣伝を繰り広げた、という先例を、わたしは思い出してしまいます。ルワンダに見る虐殺の構図日本はもはや、その段階に至っている・・・・・・・とは、思いたくありませんけどね。
2018.02.19
コメント(2)
-

怪我以降初めての山登り
昨年11月25日に足首を骨折して以来もうじき3ヶ月、とうとう山登りを再開しました。楽しい雪山が私を待っていると、言いたいところですが、まだ足首が充分に曲がる状態ではなく、完治とはとても言えない状態で本格的冬山はさすがに無理。なので、スーパーライト級の「雪山」に登ってきました。高尾山です。実は、あの日、「高尾山から陣馬山へ縦走しようか、それともあっちの山に登ろうか」と迷って、あっちの山に登ったら、ああいうことになってしまったのです。あのとき、高尾~陣馬を選んでいたら、今頃何事もなく冬山を歩いていたでしょうね。で、一応は雪山です。高尾山口の駅前ですら、雪が残っているくらいですからね。元気なら陣馬山まで縦走したいですが、足はとてもそんな状態ではないので、今日はおとなしく高尾山頂までです。雪山、と書きましたが、実のところ表参道は完全に除雪され、道に雪はありません。金比羅台の手前、シジュウカラの群れにルリビタキ(メス、またはオスの若鳥)が混ざっていました。ルリビタキ。先日石神井公園で撮ったときより、鮮明に撮れたように思います。金比羅台からの景色。東京の街はでかい。こちらは、ケーブルカーの終点付近から撮影した東京の町並みです。都心方面を取ったつもりでしたが、スカイツリーが見当たりません。都心方面ではなかったかも。自然研究路4号路(北斜面の中腹の道)に行きたかったのですが、見てのとおり雪がカチカチに凍っています。氷の上に半ば土がかぶさっているので、それほどは滑らないのではないかという気はしますが、今は足に踏ん張りがきかないので、とても進む勇気がありません。なのであきらめて、3号路(南斜面の中腹の道)を行きました。こちらは、さすがにほとんど雪はありませんでした。日陰で数箇所凍結した雪がありましたが、土をかぶっていて、滑りやすくはありませんでした。ただ、この程度の登山道でも、今の私の足には、目いっぱいでしたけど。ヤマガラの群れに遭遇。その中に・・・・・・ゴジュウカラがいました。山頂直下、シジュウカラらしき鳥を何気なく撮影。逆光で真っ黒だったので、補正してみたら、やはりシジュウカラ・・・・・・のような頭ですが、腹の下に黒ネクタイがない。別の写真で確認。やはり腹に黒い筋はありません。つまり、どうやらシジュウカラではなくヒガラだと思われます。山頂に着きました。高尾山口駅を9時10分頃出発して、山頂着は11時25分過ぎ。つまり2時間15分くらいかかりました。鳥の撮影に時間を費やしたとは言え、怪我する前は最速45分で登っていましたから、大幅な速度ダウンです。が、今の状態でこれ以上速く歩くことはとても不可能だし、あまり速く歩くと鳥が見つけられません。ここで、高校同期の山仲間と遭遇。(彼女は別のグループで登っていて、山頂で会えればいいね、とは言っていたのですが)今日は快晴だったので、富士山がきれいでした。富士山を250mmの望遠でアップ。昼食を食べていたら、エナガの群れが飛来。近くにいたグループが、「セキレイ」と言っていました。確かに尾が長いので、セキレイに似ていないこともないですが・・・・・・。そして、ザックから突き出す謎の竹筒。いいえ、謎でも何でもありませんね。例によってケーナとサンポーニャを持っていって、山頂は人が多いので避けましたが、その少し先でこっそりと、10曲くらい吹いてきました。下りは、前述の高校同期の山仲間とその同行者と3人で表参道を下ってきました。登りより下りの方がはるかに足に負荷がかかります。高尾山の表参道といえども、今の私には登りより下りの方がはるかにきつかったです。さいわい、ひねったり転んだりすることもなく下山しました。普段なら高尾山はジョギングシューズで登るのですが、今回は登山靴。足首の上までカバーされているほうが万が一の場合により安全と思ったもので。しかし、足首に補装具をつけて登山靴を履くと、中で当たるところがあって、立っているだけで痛いのです。(実は、歩いていると痛くないけど歩いていないと痛い)なので、行きの電車の中で補装具は外してしまいました。登山靴自体が、足首をひねることを防ぐ作りなので、それで問題ありませんでした。怪我して以降、鳥の写真撮影などで3kmや4kmは毎週のように歩いていましたが、高尾山はスーパーライト級の山とは言え、表参道経由で片道約4km(往復8km)、標高差約400m、今まででも圧倒的に、もっとも歩いた一日になりました。
2018.02.18
コメント(0)
-
そこまでしてカジノを導入したいか
カジノ入場は週3回まで 政府が規制案を与党に提示政府は統合型リゾート施設(IR)内のカジノに関し、日本人の入場回数の上限を週3回、月10回までとする規制案を自民、公明両党の関係部会にそれぞれ示した。自民党からは「規制が厳し過ぎる」という批判も出た。公明党では週3回など入場回数制限の根拠を示すよう求める意見が相次いだ。政府は規制案を盛り込んだIR実施法案を3月中に国会提出したい考えだが、調整は難航しそうだ。規制案では、日本人や国内に在住する外国人を対象に、カジノの入場回数の上限を「連続する7日間に3回」か「連続する28日間で10回」とする。入場履歴はICチップ付きのマイナンバーカードを使って確認。訪日外国人旅行者には適用しない。スロットマシンやルーレット台などを設置する主要部分の面積は1万5千平方メートルまでに抑え、IR全体の3%以下とする。自民党の部会では、規制の必要性に賛同する意見がある一方、「採算性からみて面積制限が厳し過ぎる」という批判や、普及率が10%程度のマイナンバーカードを本人確認に使用することへの疑問が出た。このため、政府が修正案を検討することになった。一方、公明党は支持母体の創価学会などにカジノ解禁への慎重論が根強く、ギャンブル依存症対策基本法案が成立しない限りIR実施法案の国会提出を認めない構えだ。---以前にも記事を書いたことがありますが、わたしはそもそもカジノを合法化することには反対です。加えて、カジノを合法化しておいて、その利用に回数制限を課す、というのは、私にはまったく理解不能、意味不明です。人が暴れる毒薬を合法化するので、暴れないように足かせをします、と言っているようなもので、滅茶苦茶な話です。そもそもそのような危険性のある毒薬を合法化しなければ、足かせなどいらないわけで。週3回を超えて利用させてはいけないほどに危険なものを(実際に危険だと思います)合法化しいぇよいとは思えません。加えて、引用記事でも指摘されていますが、全国民の1割にしか普及していないマイナンバーカードを入場の条件とすることは、実質的に「日本人お断り」と言っているのに等しいものです。実質的には訪日外国人専用施設ということになります。かつて、戦前の中国には租界というものがあって、「犬と中国人入るべからず」という立て札があった-と言われます。同じようなことを、現在の日本でも行おう、ということです。それは色々な意味で差別的としか思えないことです。そんなことまでしてカジノを合法化しなけばならない理由が、わたしには理解できません。もちろん、端的に言って金儲けのため、ということは分かります。そう言っては身も蓋もないので、経済的利益のため、ですね。しかし、その経済的利益と、それによってもたらされる社会的害悪のバランスが取れているようには、思えません。人体になんらかの益のある薬なら、害悪(副作用)があってもそれをコントロールしながら使用することは意味のあることです。しかし、ギャンブルには、それを利用する人にはなんの益もない。害悪しかありません。残念ながら、人間社会においてこの害悪は必要悪、という側面は否定しません。だから、今すでに存在するギャンブルを禁止せよ、とは言いません(言っても無理なことです)。それは、逆に言えば、カジノにどれほどの害悪があっても、いったん始めてしまえば、あとからやめるのは困難を極める、ということでもあります。今から新しいギャンブル、言いかえれば新しい害悪を創設することに、なんのメリットも見出すことはできません。
2018.02.16
コメント(8)
-
その忖度は異常だ
<政府>新元号、公表時期で苦慮 保守派に年明け論も2019年5月1日の皇太子さまの即位に伴って改める新元号について、政府は事前の公表時期をいつにするか苦慮している。コンピューターシステムの改修に配慮し、今夏ごろの公表を検討していたが、伝統を重んじる保守派からは現在の天皇陛下の在位中の公表への反発がなお強い。また、政府内でも、事前公表による新元号への賛否の議論の過熱を懸念する見方もある。自民党内では9月の党総裁選後が望ましいとの声もあり、「今秋以降」との声が強まりつつある。政府が事前公表を検討するのは、元号を使用する官民のシステム改修などの時間を確保するためで、一定の周知期間を置くことを考えている。これに対し、自民党の保守系議員は最近、複数の首相官邸関係者に「早く公表し過ぎると天皇陛下に対して失礼にあたるのではないか」と働きかけ始めているという。理由の一つに、19年1月7日に陛下が自ら執り行われる昭和天皇逝去30年式年祭がある。これと合わせて政府は陛下の在位30年の祝賀行事を実施するかを検討中だ。こうした行事より前に新元号を公表した場合、国民の関心が新天皇に移り、平成の時代を振り返ったり陛下の在位30年を祝ったりする雰囲気がそがれる、との意見が保守派に強まっている。天皇1代に元号一つと定めた明治時代以降、改元と天皇の代替わりが密接に結びついたことを保守派が強く意識しているのも背景にある。安倍政権としては、固い支持層の懸念には一定の配慮が必要だ。これとは別に政府内には「早く公表し過ぎると、改元の前から新元号に関する賛否の議論が起こる」(事務方)との懸念もある。平成への代替わりの際に新元号への賛否が話題になったが、発表と改元がほぼ同時だったためすぐ沈静化した。事前公表して、新元号に不満が出た場合、祝賀ムードに水を差す可能性がある。(以下略)---29年前に、「昭和」から「平成」に改元が行われた当時、すでにコンピュータやオンラインシステムは存在しましたが、現在ほど社会に深く浸透していたわけではありません。確か、運転免許証が、改元直後は発行日・有効期間を平成に改めることが間に合わず、裏面にゴム印で平成×年と押印するという対応がとられました。当時私が持っていた免許証が、ちょうどそういうレアものな免許証でした。現在は、当時とは比較にならないくらいコンピュータが社会に普及し、なおかつ各種オンラインシステムが相互に連携し合っています。もっとも、その代わりと言ってはなんですが、役所を例外として、民間企業における元号の使用頻度は大きく下がっていると思われます。特に外国との取引がある企業は、国外では通用しない元号は使用しないでしょうし、そうでなくても、改元の度に大きな労力と経費をかけるのは避けたい、と平成の開元の際に学んだ企業は多いでしょう。役所だって、元号の使用なんてやめてしまえ、とわたしは思わないこともないのですが、残念ながら役所は法律で元号の使用を縛られているので、それはできそうにありません。それにしても、改元に際して、少しでもシステム上のトラブルを回避するには、できるだけ早く次の元号を決めて、準備期間を長く取るべきと思うのですが、そうは考えないのが「保守派」という連中のようです。「早く公表しすぎると天皇陛下に対して失礼」という言い分には、驚きを禁じえません。それをきみたちは天皇から聞いてきたのか?そんなはずはありません。天皇が退位を言い出した理由は、自身が高齢となったこと、「即位の礼」と「大喪の礼」が重なることは新しい天皇やその周囲に負担が大きいこと、など様々の理由があります。しかし、その中で、ある日突然天皇の死とともに平成の元号が終わり、翌日から新しい元号、という状況は社会に負担が大きいことも、決して小さくない理由の一つなのではないでしょうか。天皇に対して失礼、などというのは、無用な忖度というものです。というより、むしろ天皇の名を利用しているものの、実際には自分たちの個人的な思いに過ぎないのでしょう。そもそも、5月1日という改元に日付自体が、政治的な都合だけを考えて、社会的事情を考慮しないものだと言わざるをえません。普通に考えれば、予定しての改元なんだから、1月1日がわかりやすいに決まっているじゃないですか。一年に二つの元号が並存するのは、混乱の元です。または、元号などもはや役所だけのものだという前提に立てば、役所の年度の切り替わりである4月1日でもよいですが、そのどちらでもない5月1日を改元の日に選ぶのは、無用な混乱を招きたいだけとしか思えません。まあ、それらのことを強行すれば、社会全般に一層元号離れが進むだけのことでしょうけどね。前述のとおり、もはや元号を使う企業は少数派でしょうが、その少数派の企業も元号の使用から離れていくでしょう。一般社会の日常生活からも元号の使用は離れていくでしょう。正直言って、わたし自身も、仕事上は別にして、仕事以外の日常生活では、元号はほとんど使いません。使うとしても、個別具体的な何年、ということではなく、世代論、年代論としての言い方がほとんどです。昭和ヒトケタ世代とか、昭和50年代とかそういう言い方で、それもほとんど昭和以前に偏っており、平成はそういう使い方もあまりしていません。それでも、前述のとおり、役所はこの愚行に付き合わざるをえず、それによって無駄な労力と経費を使うことになるのでしょう。馬鹿馬鹿しい話です。話はまったく変わりますが、エクセルは元号に対応していますが、あれも元号が変わると修正パッチが必要になるのでしょう。私が自宅で使っているのは古くてすでにサポートが切れた版なので、何の対応もとられないかもしれません。もっとも、前述のとおり、わたしは自宅では元号は使わないので、それで困ることは特にありませんけどね。
2018.02.14
コメント(2)
-
条件が整えば訪朝は望ましい
韓国大統領の訪朝けん制=菅官房長官菅義偉官房長官は13日の記者会見で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が韓国の文在寅大統領の訪朝を要請したことについて「北朝鮮は核・ミサイルの開発を継続して行っている。北朝鮮のほほ笑み外交に目を奪われてはならない」と述べ、安易に応じないよう韓国政府をけん制した。菅長官は「8日の平壌での大規模な軍事パレードでも、昨年発射が確認された弾道ミサイルと同じタイプとみられるミサイルが4種類確認されている。それが北朝鮮の実態だ」と指摘した。ーーー韓国は日本の属国ではないので、大統領がどこを訪問して誰と会うかについて、いちいち外国からの指図を受ける謂れはないのではないでしょうかね。本来は一つの国であるべき南北朝鮮が二つの国に分かれているのは、正常な状態とは思えません。その中で両国の間で緊張緩和が図られること、そのために首脳会談が行われることは、一方的に臣従しに行く、というのでない限りは、好ましいことであって、否定すべき理由は何もないと、隣国の一国民であるわたしは思うんですけどねえ。もちろん、北朝鮮の体制はロクでもないものです。が、それが近いうちに、周囲に被害を与えずに倒れる可能性は低い以上、戦争という破局を迎えないために対話を行うことは、必要なことでしょう。それとも、「北朝鮮の脅威」を叫ぶ向きには、北朝鮮が脅威でないと困る、ということでしょうか。そもそも、思い返せば2002年に我が国の小泉首相が訪朝しているわけですが、そして、現在首相である安倍も、当時官房長官として小泉首相に随行して訪朝しているわけですが、当時北朝鮮は核開発を行っていなかった、弾道ミサイルの開発を行っていなかった、とでも言うのでしょうか。北朝鮮の行ってきたことは、確かに非道です。しかし、その非道な状況は、2002年当時と今で、それほど大きな差はありません。日本の首相が訪朝したのに、韓国の大統領が訪朝するのがけしからん、などという理屈が立つわけがありません。それにしても、北朝鮮が暴発すれば、戦火は確実に日本にも及ぶことになるにも関わらず、この政権には、あるいはそれを熱烈に支持するネトウヨ層には、そのような事態を避けなければならない、という真剣な危機意識はないのでしょうか。北朝鮮の現政権を倒せれば、日本にもミサイルの何発か落ちて、何千人か何万人かが死んでも(北朝鮮が核の使用まで踏み切れば、死者の数はもう一桁以上多くなる)構わない、とでも思っているのでしょうか。考えたくもないことですが、そうなのかもしれません。
2018.02.13
コメント(2)
-

石神井公園ルリビタキとクロジ
先週に続いて、また石神井公園に行って来ました。雪はほとんど消え、先週よりは歩きやすかったです。それに、先週よりずっと暖かかったですし。先週は出会うことができなかったルリビタキとクロジ、せめてどちらかと遭遇しないか、と期待して行ってみました。変なカモ出現。くちばしと胴体はカルガモですが、頭は半分マガモ。俗にマルガモなどと呼ばれる、マガモ(または、マガモを原種とするアヒル)とカルガモの雑種だと思われます。これも、だいたいカルガモなのですが、頭がちょっと変なので、おそらくマガモとカルガモの雑種でしょう。そして、お目当てのルリビタキ。先週は「ここによく出る」という場所で空振りだったのですが、今日は?着いたら、いきなり出てきました。メス(またはオスの若鳥)です。ただ、くもりで日差しがない上に樹林の中なので、暗い。そこに400mmのレンズを振りかざすのですから、あまり鮮明な写真は撮れませんでした。このくらいに縮小すれば、まあまあ見られる、というところです。メスは、オスよりはやや地味ですが、それでもわき腹の黄色と尻尾の青がきれいです。褐色の部分がオスだと全部青いので、一層きれいですが。明るいところで撮影できれば、更に鮮やかに写るんでしょうが・・・・・・。そのルリビタキが倒木の辺りから不意に飛び去ったと思ったら、入れ替わりにやってきたのがクロジ(オス)でした。ホオジロ科です。先ほどのルリビタキは、写真を撮るのははじめですが、見るのは初めてではありません。こちらのクロジは、見るのも初めての鳥です。前述のとおり、暗くて、手ブレ写真を量産してしまいました。手ブレしていない数少ない写真をアップしましたが、これもISO6400での撮影になってしまったため、等倍では画像がかなり荒くなってしまいました。このくらいのサイズなら大丈夫ですが。クロジ、当ブログで何度も紹介しているアオジも近縁種です。ただ、アオジはちょっと広い公園にはいっぱい渡ってきますが、クロジは少ないです。ちなみに、アオジ、クロジはいますが、アカジという鳥はいません(笑)。ヤマガラ。今日は、いきなりお目当ての鳥が出てきたし、天気もいまひとつだったので、それ以外の鳥はそんなに撮影せず帰路につきました。本日確認した鳥。カイツブリ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、キンクロハジロ、バン、オオバン、アオサギ、ゴイサギ、コゲラ(声のみ)、キジバト、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、メジロ、ヒヨドリ、ツグミ、ルリビタキ、クロジ、ハクセキレイ、スズメ、ムクドリ、ハシブトガラス。
2018.02.11
コメント(0)
-
選択的夫婦別姓制を拒否する理由などない
夫婦別姓、賛成42%、反対上回る 内閣府世論調査内閣府は10日付で「家族の法制に関する世論調査」の結果を公表し、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について賛成が42.5%に達し、反対の29.3%を上回った。世代別でみると、男女とも60代以下は賛成が多数だが、70代以上は反対が52.3%と過半数を占め、世代間の意識の違いが浮き彫りになった。選択的夫婦別姓は夫婦が望む場合には、結婚後もそれぞれ結婚前の名字を名乗ることを認める制度。平成24年の前回調査は法改正に反対が賛成をわずかに上回っていたが、今回は賛成が前回比7.0ポイント増となり、賛否が逆転した。法務省の担当者は調査結果を踏まえた夫婦別姓について「国民の意見はなお大きく割れている」としている。また、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、旧姓を通称として使える法改正は容認する」との回答は24.4%だった。内縁関係にある夫婦については同じ名字を名乗らなくても「夫婦と同じような生活をしていれば、正式な夫婦と変わらない」との回答が74.6%で過去最高となった。---我が家は、結婚する際、相棒が急性を名乗り続けたいという要望は特にありませんでした。なので特段の軋轢もなく、世間一般のたいていの夫婦と同じように、相棒が私の苗字を名乗っています。しかし、世間一般には、結婚しても苗字は変えたくないという人が、割合としては少数派でも、ある程度存在します。それは、必ずしもそういう主義主張ということではなく、仕事上の都合である場合が多いようです。少し前に、サイボウズの青野慶久社長らが夫婦別姓が認められないのは憲法24条に違反する、として提訴したことが報じられています。それで知ったのですが、サイボウズの社長は結婚に際して青野氏が姓を変えているのですね。私の周囲にも、結婚の際に夫が姓を変えた夫婦はいます。が、圧倒的にその数は少ないです。私の個人的な知り合いの中では、多分99%の夫婦が、結婚に際して妻が姓を変えています。我が家もそうなので、「これは女性差別だ」とは言いにくい気持ちもありますが、これだけの比率の差を見れば、男女の立場は対等ではないことは歴然としています。その一方で、夫婦別姓制を待ち望んでいる夫婦は、私の周囲には大勢います。実際、戸籍名はともかく、日常生活は別姓を名乗っている夫婦も何組かいます。もちろん、割合として多数派というわけではありません。妻がフルタイムの正規職で働いている場合にそのような希望が強く、専業主婦であったり、結婚に際していったん退職しているような場合は、それほど別姓への希望が強くない傾向はあるように見受けられます。(例外もあり)そのような人たちの希望をはねのける、合理的な理由はまったくないと私は思います。あくまでも、「選択的」夫婦別姓制です。前述のとおり、我が家は別姓にしたいという願望は夫婦ともにありません。全員が例外なく夫婦別姓にしろ、というのであればそれは反対ですが、希望者のみ別姓が選択できる、という制度に、どうしてこれほど反対がいるのか、私は不思議でなりません。そんなに他人の苗字に介入したいのか。と、言っても反対は3割に満たないので、あくまでも少数派です。ところが、人数では少数派でも、いわゆる保守系にそういう連中が多く(これもまた、例外は多々ありますが)、自民党は保守系を支持基盤にしているので、どうも近いうちに選択的夫婦別姓制が認められそうな様子はまったく見えません。「旧姓を通称として使用できる法改正」というのは、反対とは言いませんが、実質的な意味はほとんどないと思います。つまり、別姓反対派が叫ぶ「家族の一体感が失われる」だの「子どもへの影響」だのという夫婦別姓の「問題点」なるものは、戸籍上の表記によって生まれるものなのか?ということです。そんなわけがありません。だって、世の中のたいていの人は、自分の戸籍をそんなに頻繁に見るものではないからです。とりわけ、子どもが自分の戸籍を見る機会は少ないものです。それなのに、夫婦別姓に「家族の一体感が失われる」とか「子どもに悪影響がある」というマイナスがもし本当にあるのなら、それは、滅多に見ない戸籍などではなく、家族が日々の日常生活で名乗る苗字が理由だ、ということに、当然なるはずです。したがってこういう反対理由を掲げながら「旧姓を通称使用」なんて論は、そもそも成り立ち得ないものです。一方では、少子化の危機が叫ばれています。少子化への対策は色々あるでしょうが、結婚への障害をできるだけ少なくする、ということもその一つになるでしょう。選択的夫婦別姓制は、そういった障害の解決策の一つではあります(あくまでも、多くの問題点の一つへの対策に過ぎないので、そんなに大きな効果は期待できないにしても)。その程度のこともできないようで、少子化の解決など、できっこないとしか言いようがありません。
2018.02.10
コメント(6)
-

パソコンの電源とハードディスク交換
数日前、朝突然パソコンが立ち上がらなくなってしまいました。まったくピクリとも動かない状況から、犯人は電源だろうと見当をつけて、押入れから古い電源を取り出して、仮に換装(ケーブルだけを差し替え)してみたら、一応動いたのです。これで犯人が電源と確定したのですが、朝の忙しい時間だったし、電源をケースから外してちゃんと交換するのは面倒くさいなあ、何とかして元の電源動かないかなあ、と思って、ダメもとで元に戻してみたら、なんと奇跡が起こって(笑)、起動したのでした。それ以降数日間はとりあえず問題なくパソコンは稼動していたのですが、一度こういうトラブルがあると、次にいつ同じことが起こるか、分からない不安感が生じてしまいます。そもそも、パソコンの電源の寿命ってどのくらいなのかな、と検索したら、3年とか5年とか書いてあります。私のパソコンの電源は・・・・・・もう8年使っています。パソコン自体は3年半ほど前に組み替えましたが、電源は流用しています。こりゃ、寿命間近、というところでしょうか。それとは別に、このパソコン、OSは120GBのSSDに、データは2TBのハードディスク(HDD)に入れています。2TBという超巨大な容量(買ったときは、そう思ったのですが・・・・・・)のHDDが、もう6割くらい埋まってしまいました。動画の容量恐るべし、です。それに、電源は壊れたら買い換えればよいでしょうが、ハードディスクは壊れて中のデータが吹っ飛んでからでは手遅れなので、基本的に3~4年で取り替えるようにしています。このハードディスクも、パソコンを組み替えたときに入れ替えたんじゃなかったかな、確か。いや、よく覚えていないので、ひょっとしたら前のパソコンから流用だったかも知れませんが、いずれにしても、少なくとも3年半以上は使っていると思うので、これもそろそろ替え時かな、と思っておりました。本日、諸事情により病院に行く用事があって半日休暇を取ったので、ついでに電源とハードディスクを買ってきました。右が電源のパッケージ、左がハードディスクのパッケージです。実は、開封前に撮影することはすっかり忘れて、あとから撮影していますが。ハードディスク。4TBですよ。特にこだわりがないので、一番安いやつを買ってきました。税込9000円台でした。3.5インチベイに納めて作業するのが面倒で、この状態で旧ハードディスクからデータを移行したら、約1TBのデータを移行するのに、ほぼ4時間近くかかってしまいました。一方の電源は・・・・・・撮影する前に交換しちゃった。上の写真のケース内一番右上が電源です。これまでの電源は400Wでしたが、新しい電源は550Wもあります。正直言って、そんな容量はいらないんですけどね。ゲームはやらなくなって久しいので、グラフィックスボードも挿していないし。お値段は5000円台でした。ハードディスクとあわせて、1万5千何百円。代わりに、交換した古い電源の写真。少し前に誇りの掃除をしたのですが、それでもほこりがついています。中を覗き込んでみると、コンデンサは特に膨らんだりはしていないように見えますが・・・・・・。何しろ8年使っていますからねえ。電源からは、ヤマタノオロチみたいにケーブルが延びています。下のほうの、一番幅広ででかいソケットが、マザーボードへの電源供給ケーブル、その下に隠れている黄色いケーブルがCPUへの電源供給ケーブル。上の方でごちゃごちゃ固まっている中で、茶色のソケットがPCIexpress用の電源供給ケーブルですが、わたしはかつてのPCIボードやAGP時代のグラフィックスボードは使ったことがありますが、PCIexpressのボードは一度も使ったことがありません。だって、今はマザーボード上にあらゆる機能が内蔵されていますから。昔はLANですら外付けでしたが、今はどんなマザーボードにもLANは内蔵されています。ごちゃごちゃした中の黒いソケットは、シリアルATAとパラレルATA用の電源ケーブルです。ハードディスク、SSD、CD-ROMやDVD-ROMの電源供給用です。なお、このパソコンのケースは2005年に購入したもので、もう13年も使っています。と言っても、ケースはただの箱ですけど。中身は、電源は今回の交換で3代目、マザーボードも3枚目です。今のマザーボードも3年半になりますが、今のところこのパソコンの性能に何の不満もないので、まだしばらく使うかな。交換するとしたら、Windows10にするときでしょうね。Windows7のサポート期限は、あと2年しかないので、2年以内、ということになりますが。
2018.02.08
コメント(0)
-
どんな侵略戦争も「防衛」と称して始まる
「フルスペックの集団的自衛権」は必要だ国会で安倍首相が「第9条2項を変えることになれば、書き込み方でフルスペック(全面的)の集団的自衛権が可能になる」と答弁して、石破茂氏の提案する第2項の削除案を否定した。これに対して石破氏は「集団的自衛権を何でもやりますなんて、党として決めたわけでない」とし、第9条2項の削除が全面的な集団的自衛権の行使容認につながらないという。~常識的に考えて、自衛権に制限をかけて自国が安全になることはありえない。集団的自衛権の限定行使についての「5党合意」では「存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること」となっているが、北朝鮮からミサイルが飛んできたとき、国会で審議していて間に合うのか。---例によって、池田信夫のくだらぬ論考です。9条の改憲には、安倍の案であろうが石破の案であろうがわたしは反対です。ただ、そのことはそのこととして、集団的自衛権で「防衛」と名を冠すればなんでも認める、というのは異常なことであり、そんなことによって自国がより安全になることなどありえないと私は思います。だいたい、どんな侵略戦争も「防衛」と称して始まるものです。戦前の日本は「高度国防国家」と自称していましたが、その実態は中国に対する侵略国家でした。だから、戦後の日本は武器使用の3要件として、「我が国に対する急迫不正の侵害がある」「これを排除するために他の適当な手段がないこと」「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という厳しい条件を付してきたのです。池田は「北朝鮮からミサイルが飛んできたとき、国会で審議していて間に合うのか。」などと使い古されたデマゴギーを叫んでいますが、日本の領土に向かって飛んでくるミサイルを迎撃するのは個別的自衛権の問題であって、集団的自衛権とは関係ないし、「武力攻撃事態」であることは明らかです。しかし、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」分かりやすくいえば米国に対する武力攻撃は、「存立危機事態」には当たるでのしょうが、日本に対する武力攻撃ではありません。それに対して、「それは日本に対する攻撃だ」とみなして反撃すること(集団的自衛権の行使)を認める「平和安全法制」自体に問題があると私は思います。ましてそのようなことを「緊急だから」と国会の事前承認もなく、政権の恣意的に反撃をことが許されてよいとは思えません。そのような安易な武力行使は、国民をより巨大な危険へと陥れる可能性があります。戦前の日本を例に挙げましたが、あからさまな侵略戦争を「防衛」と称することは、何も日本の専売特許だったわけではありません。ベトナム戦争での米国のあからさまな侵略、中米・カリブへの干渉、あるいは旧ソ連のハンガリー、チェコ、アフガニスタンへの介入、これらはいずれも「自由主義陣営の防衛」「社会主義陣営の防衛」と称して行われています。世界のどの国も、「侵略は悪」という認識は共有しており、自国の振る舞いは侵略ではない、という体裁を欲するからです。現在の日本は、戦前とは違い、単独の判断、単独の軍事力で外国を侵略する能力は幸いにしてありません。その代わり、米国の判断、米国の軍事力の補完として、「集団的自衛権の行使」と称する実質的な侵略に加わる可能性が、非常に高くなってしまいました。日本政府は、およそ米国の世界戦略に公然と異を唱えたことはありません。が、それでも、集団的自衛権は違憲とされていた時代は、海外で戦争に日本が参加することだけはありませんでした。集団的自衛権が認められていたら、日本はベトナム戦争に参戦していたかもしれません。そうすれば、米軍や韓国軍のように、非戦闘員や民間人の虐殺に日本も関与する事態が起こっていたかもしれない。もちろん、自衛隊(そのような場合、もはや自衛隊ではなく日本軍という呼称だったかもしれませんが)にも多くの死傷者を出したに違いありません。あるいは、湾岸戦争や、泥沼のイラク戦争に、後方支援ではなく最前線の戦闘部隊を送っていたかもしれません。お互いに多くの戦死者を出した上に、イスラム国の主たる憎悪の対象が日本になっていたとしても、不思議ではありません。安倍の言う、そして池田がそれに追従する「フルスペックの集団的自衛権」なるものは、実際にはフルスペックの対米従属でしかありません。米国の世界戦略に、「後方支援」だけでなく、いわば弾除けとして最前線に立とう、ということです。そのようなことが、日本の「国防」「安全保障」の役に立つとは、私には思えないのです。一部の国家主義者が溜飲を下げるだけで、一般国民の平和と安全を保つことには、百害あって一利なしです。まして、そのようなことを、国会での議論すら経ずに、時の政権の独断で決めてよいはずがありません。
2018.02.06
コメント(2)
-

メジロの喧嘩は恐ろしい。
今日は午後から信濃町の「ティアスサナ」で練習だったのですが、早めに家を出て、となりの駅、千駄ヶ谷で下車して、新宿御苑に寄ってきました。実は、新宿御苑に入ったのは初めてです。(多分)お目当ては、オシドリ、トモエガモ、アオゲラ、ルリビタキでしたが、この中では残念ながらオシドリしか出会うことができませんでした。そのオシドリは後回しにして、梅の花が咲きはじめて、あちこちでメジロが飛び回っていたのですが、その中で2羽のメジロが大喧嘩をはじめました。2羽が絡み合って地上に転落、しかし、それでも激しく争っています。いったん、第一ラウンドは終了して、2羽とも飛び立って梅の木に戻ります。が左上のメジロ、激しく羽根を震わせて、まだまだ闘志満々。そして、第2ラウンド開始です。またまた2羽絡み合って地上に転落。つつき合い、というか、1羽が一方的に攻め立てる展開。いやー、チビでも凶暴です。しかし、結局第2ラウンドも決着はつかず一羽が先に飛び立ち、残る1羽も飛び立ちました。激しく争ったので、羽根が乱れに乱れています。梅の木に戻って、「フンッ」って感じ。なんか目つきが怖い(笑)そのあと第3ラウンドがあったかどうかは、時間の関係で確認しておりません。で、オシドリですが、池の奥の木陰に潜んでいてなかなか出てこなかったのですが、2回ほど出てきたので撮影。距離はかなりありました。今日は笛一式を担いでいたので、重い100-400mmではなく、55-250mmのレンズでした。なので、あまり大きくは写せませんでした。カモ類(特に淡水ガモ)のオスは全般に派手できれいですが、その中でもオシドリのオスは特に派手です。で、時系列とは反対になりますが、昨日の午前中は石神井公園に行ってきました。石神井公園は多分25年くらい前に行ったことがあるのですが、それ以来です。鳥の撮影のためにははじめて行きました。公園内はあちこちに雪が残っていて、今の足の状態ではちょっと辛いものがありました。カワラヒワの群れがいました。かつて、わたしが中学生から社会人になったばかりくらいのころは、典型的な都市鳥の一種で、まったく珍しい鳥ではなく、実家の周囲でも普通に見かけていた記憶があります。しかし、昨年野鳥観察を再開して以降は、ぜんぜん見かける機会がありませんでした。唯一写真に収めたのが、何と昨夏の北海道。それ以来2度目のカワラヒワの撮影です。そのカワラヒワの群れの中に、アトリが混ざっていました。実は、下から見上げた写真では種名が分からず、Facebookの鳥の写真のグループで聞いて、教えていただきました。カワラヒワもアトリも、アトリ科、つまり近縁同士です。(カナリアの仲間です)コゲラ。コゲラをもう1枚。ゴイサギバン。足がでかい。指にはカモのような水かきはありませんが、巧みに泳ぎます。キセキレイこちらもキセキレイ。
2018.02.04
コメント(2)
-
色々な意味で問題の根は深い
築50年「住み心地良かった」 札幌・火災の施設11人が死亡した札幌市の「そしあるハイム」の火災。関係者によると、建物は生活困窮者の就労支援が目的で、警察からの連絡などをもとに受け入れを決めていたという。居室は1人部屋で、浴室やトイレは共同、食堂もあった。家賃は月3万6千円。月2万円を追加すれば、3食付きになった。ほかに光熱費などもいるという。10年ほど前から入居している人もいれば、火災の数日前から暮らし始めた人もいた。建物に管理人がいるのは午前7時半~午後5時半。夜間は入居者だけになり、玄関の鍵は入居者がしめていたという。元スタッフによると、希望に応じて食事を提供し、病院の送迎や買い物の手助けなどもしていた。入居者は運営側で面談をするなどして決定。8年前から2年ほど住んだという札幌市東区内の男性は「8畳の部屋に住み、食事の提供も受けた。住み心地は良かった」と話す。札幌市消防局などによると、建物は50年ほど前に建てられ、2004年までは旅館として使われていた。(以下略)---また悲しい事故が起こってしまいました。火災を起こした施設は、「自立支援住宅」で、入居者の大半が生活保護受給者だと報じられています。しかし、生活保護に詳しい知人に聞いても、東京23区には、路上生活者の就労支援を行う自立支援センターというものがありますが、それとは違うもののようだし、「自立支援住宅」というものは聞いたことがないそうです。そうしたら、今朝の毎日新聞のによると、火災のあった自立支援住宅「そしあるハイム」は、法的な位置づけがあいまいで無届けだった、とのことです。厚労相は、「無届の無料低額宿泊所か、無届の有料老人ホームの可能性がある」として調査を行うということです。確かに、3食提供というところからは、実質的には無料低額宿泊所のようなものだった、と言えそうです。家賃は3万6千円だそうですが、調べると札幌市の生活保護の住宅扶助上限額は、単身世帯の場合3万6千円なので、完全にそれに合わせた額、つまり生活保護が前提の施設であることが分かります。3食提供で2万円だそうですが、他に光熱費や管理費もかかるはずです。この施設の場合どうだったかは分かりませんが、東京の無料低額宿泊所の場合は、3食提供だと、生活保護受給者の手元に残る、自由に使えるお金は1万5千円から2万円程度(法人によって差があるし、保護基準は年齢によっても違うので、それによって差が出ます)と聞いています。なお、札幌は級地区分が1級地2なので、東京23区より、生活保護基準は5千円程度低くなります(70代以上単身世帯だと、1級地1は7万4千円余に対して1級地2は6万9千円余)。その代わり、当然のことながら北海道は東京より冬季加算は高い。東京(冬季加算の区分6区)の冬季加算は2500円ほどですが、北海道(同1区)は1万2千円ほどです。法的位置づけとか、火災対策の面では色々と問題のあった施設であったことは確かだと思いますが、しかし、そういう施設がなかったら、ホームレス寸前の状況の人の住まいを確保できない、というのが現実です。しかも、多分としかいえませんが、この施設は各入所者が8畳程度の個室に住んでいたというので、東京の無料低額宿泊所(たいていは相部屋だそうで)より条件がよく、運営者と入所者の関係もかなり良好だったことが伺えます。だから、「無届だったからひどい施設だった」とは一概に言えないのです。東京だって路上生活で冬を越すのはかなりつらいはずです(特にこの冬は寒いから)。冬場だけ生活保護を受けて施設に入り、暖かくなると姿を消してホームレスになる人もいると聞きますが、北海道では、よほどの装備とスキルがなければ、冬の路上生活など生きていけないでしょう。「こんな無届の施設はけしからん、すぐに閉鎖すべきだ」なんてことを言い出しても、それに代わる、より条件のよい住居はどこにもないので、結局は入居者に路上生活をしろというも同然となってしまいます。そうでなくても、路上生活に陥る、陥りそうな人の中には、社会生活能力や対人関係に難のある人が少なくありません。知人によれば、アパートに入居しても大家や隣人とトラブルを起こして追い出されたり、施設に入っても同様のことを繰り返す人も、稀ではないそうです。そういう人の対応や、行き先探しにケースワーカーは疲弊することが多い、との話です。この施設も、きっと「ここでなければ生活できない」人がいたのだと思います。その一方で、ここでもトラブルを起こして出て行ったり追い出されたりした人も、多分いたでしょうが。一方では日本中に空き家が増えていながら、その一方では住む場所が確保できない人が少なからずいて(本人自身に一人暮らしで生活する能力が欠けている、という面はあるけれど)、なんとも非合理な話ですが、これが現実です。現実的には、この種の無届施設を少しでも無料低額宿泊所など無届ではない施設に移行させる(ために必要な設備、手続き、入所者の処遇などを整える)ように図っていくしかないのでしょう。
2018.02.03
コメント(3)
-

皆既月食
昨夜は皆既月食がありました。東京はもりの予報でしたが、実際には晴れて、皆既日食を見ることができました。足がまだ治っていないので、外での撮影はやめて、自宅の寝室の窓からの撮影です。月食の始まり次第に明るい部分が減り皆既月食直前。しかし、この辺りから暗くてオートフォーカスが効きにくくなり、ピンボケ写真を量産。皆既月食になりました。このあたりは10枚に1枚しかマトモな写真が撮れませんでした。窓から月がはみ出したところで、撮影終了しました。予報が外れてよかったです。
2018.02.01
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1