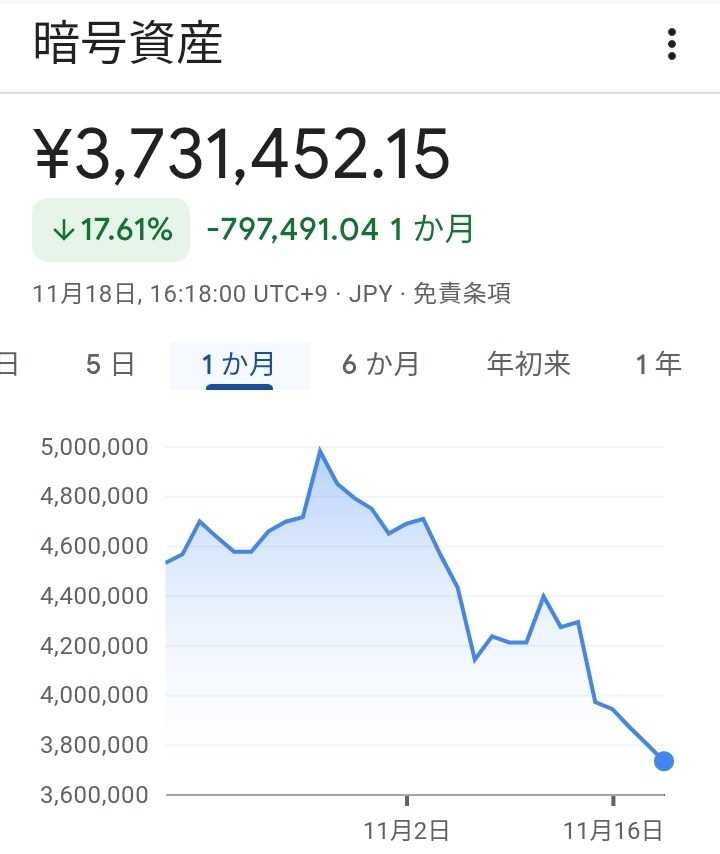2021年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

小池一子 はじまりの種をみつける(感想)
クリエイティブ・ディレクターは、企業や団体が広告宣伝を行う際に、そのビジュアル制作や広告戦略を指揮する仕事です。 依頼主からPRしたい商品やサービスの概要、あるいは広告戦略の方針を聞いた上で、どのような手法を使って宣伝すればより効果的なのか検討し、企画や戦略を練っていきます。 ”小池一子 はじまりの種をみつける”(2021年5月 平凡社刊 小池 一子著)を読みました。 日本のファッションやアート、デザインの世界で先駆的な仕事を成し遂げてきた、クリエイティブ・ディレクターの小池一子が来し方と人となりを語っています。 広告宣伝の方法には、テレビCMや新聞広告、雑誌広告、ポスターや車内広告、店頭キャンペーン、インターネット広告など、いろいろな種類があります。 これらを組み合わせながら、より広く周知できる方法を考案していきます。 広告の手法が決定すると、コピーライターやCMプランナー、アートディレクターらを集め、ポスターやCMなどの広告物の制作を行っていきます。 このときクリエイティブ・ディレクターは、依頼主に提案した通りの広告物が完成するようにスケジュールや品質の管理を担当します。 似たような職種として、アートディレクターが挙げられ、企業によっては同じ職業として扱われることもあります。 しかし、制作物のビジュアルの監修が業務の中心であるアートディレクターに対して、クリエイティブ・ディレクターはビジュアル監修に加え、広告戦略の立案にも大きく関与します。 そのため、美的センスやスタッフをまとめるリーダーシップだけではなく、広告手法に関する幅広い知識や経験が必要とされます。 小池一子さんは1936年2月6日に、教育学者の父・矢川徳光と母・民子の間に、5人姉妹の4番目として東京に生まれました。 作家で翻訳家の矢川澄子さんは、次女であり姉です。 1943年に、政治家で出版社を営む小池四郎伯父と、洋裁研究所を主宰する元子伯母の養子となりました。 1944年の小学3、4年の時に、静岡県田方郡函南村へ疎開し、父・四郎が創設した青年訓練所のコロニアル様式の住宅で暮らしました。 終戦後、父・四郎が死去しましたが、しばらく伊豆伊東に居を構え、のち東京へ戻りました。 1948年に、クリスチャン・スクールの恵泉女学園中等部に入学し、高等学校まで同学園で学びました。 1954年に、早稲田大学文学部演劇科に入学し、2年時に、英文科へ転科しましたが、在学の5年間は、学生劇団「自由舞台」にほとんどの時間を費やし、演劇に没頭しました。 1959年に大学を卒業後、姉・澄子の紹介で堀内誠一さんの監修するアドーセンターに入社しました。 同年創刊の『週刊平凡』(平凡出版、現・マガジンハウス)の連載ページ「ウィークリー・ファッション」にて、はじめて編集、執筆を担当しました。 以後、ファッション、デザインを中心に、執筆や編集の仕事が本格化しました。 久保田宣伝研究所(現・宣伝会議)でコピーライター養成講座に通いました。 1961年にアド・センターを退職し、フリーランスになり、高野勇さん、江島任さんと「コマート・ハウス」を設立しました。 1962年に編集を担当した広報誌『プワンティングインク』の創刊にアートディレクターとして田中一光さんを迎え、以後、多くの重要な仕事をともに行いました。 三宅一生さんとの出会いもこの年のことでした。 1965年にアメリカのサンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ヨーロッパのロンドン、パリ、ミラノへ初めて外遊しました。 1966年に森英恵さんの顧客向け冊子、タブロイド判『森英恵流行通信』創刊号より、編集と執筆を担当しました。 ヨーガン・レールさんを取材し、生涯の交友が始まりました。 1969年に企画、コピーライティングで「池袋パルコ」立ち上げに参加し、西武グループの広告活動に様々な提案を行いました。 訳詞を手がけたミュージカルの「ファンタスティックス」の公演が行われました。 1970年に旭化成の研究室に参画し、テレビコマーシャルの仕事にも携わりました。 1973年の冬休みに、三宅一生さん、皆川魔鬼子さんとロサンゼルスヘいき、ニューヨーク、メトロポリタン美術館で開催されていた「Inventive clothes 1909-1939」展に出合いました。 1975年にこの展示会を京都で開催すべく、「現代衣服の源流」展と題し、企画、実施に奮闘しました。 主催は京都国立近代美術館と京都商工会議所、会場は京都国立近代美術館で、アートディレクターは田中一光さん、空間は杉本貴志さん、マネキン製作は向井良吉さんでした。 同年にコマート・ハウスを退職し、米国・ハワイ大学所属機関「東西文化研究所」へ美術館学の研修のため半年間留学しました。 1976年の在米中に、「世界クラフト会議」参加のためメキシコヘ行きました。 田中一光さんからのハワイヘの電話で、東京デザイナーズ・スペースに発起人として参加しました。 ハワイから帰国後、有限会社オフィス小池を設立し、後に株式会社キチンに改称しました。 西武美術館のアソシェイトキュレーターとなり、1977年開催の「見えることの構造」、1979年開催の「マッキントッシュのデザイン展一現代に問う先駆者の造形 家具・建築・装飾」以降、数多の展覧会に参画しました。 1977年にファッションデザインを最初に美術館で取り上げた「三宅一生。一枚の布」展が西部美術館で開催されました。 1978年に三宅一生の本『三宅一生の発想と展開』の編集を担当し、青山に構えられた編集室に龍る日々であす、実施に奮闘した。 主催は京都国立近代美術館と京都商工会議所、会場は京都国立近代美術館で、アートディレクター・構成は田中一光さん、写真は横須賀功光さん、操上和美さんほかでした。 1979年に「無印良品」の企画・監修に参画し、1980年から販売が開始されました。 同年に「浪漫衣裳」展の図録を編集し、京都国立近代美術館で開催されました。 翻訳を手がけたジュディ・シカゴ著『花もつ女-ウエストコーストに花開いたフェミニズム・アートの旗手、ジュディ・シカゴ自伝』がパルコ出版から出版されまし。 1981年に、アムステルダムのアート・ディレクターズ・クラブ主催の「ジャパンデイ」でパネル・トークを行いました。 同催事のため、田中一光さんと『日本の色彩』を出版し、翌年リブロポートからも刊行されました。 ダイアナ・ヴリーランド著『アルール美しく生きて』の監修、翻訳を行いました。 1980年度ファッション・エディターズ・クラブFECを受賞しました。 1982年に演出家の渡辺浩子訳・演出のミュージカル「キャバレー」の訳詞を担当し、博品館劇場で公演が行われました。 1983年に佐賀町エキジビット・スペースを設立し、主宰となりました。 佐賀町エキジビット・スペースは、1927年竣工の「食糧ビル」の空間を1983年に再生し、2000年までの17年間、小池一子が設立・主宰した日本初のオルタナティブ・スペースです。 現在進行形のアートを発信し、森村泰昌さん、内藤礼さん、大竹伸朗さん、杉本博司さんら多数のアーティストを輩出しました。 2011年に「佐賀町アーカイブ」が3331 Arts Chiyodaに開設され、現在に至っています。 1927年竣工のかつては廻米問屋市場として栄えた「食糧ビル」の空間を再生し、1983年から2000年までの17年間、現在進行形のアートを発信した日本初のオルタナティブ・スペース「佐賀町エキジビット・スペース」です。 森村泰昌さん、内藤礼さん、大竹伸朗さん、杉本博司さん、立花文穂さんなど多数のアーティストを輩出しました。 2011年より「佐賀町アーカイブ」として、佐賀町エキジビット・スペースの活動と資料、作品コレクションを検証し、展示し、語り、学ぶ、アーカイブをショーケース化するという新しい試みをスタートしました。 1995年に、「日本文化デザイン会議95群馬」による日本文化デザイン賞授賞委員長に就任しました。 1996年に佐賀町エキジビットースペースの活動が賞され、財団法人日本文化藝術財団(京都)から第三回日本現代藝術振興賞を受賞しました。 1997年に、DNP文化振興財団主催で現代グラフィックアートセンターで開催されました、 大竹プリンティング/ペインティング」展のキュレーションを行いました。 2000年に国際交流基金主催で佐賀町エキジビット・スペース閉廊で開催された、ヴェネチア・ビエンナーレ第7回国際建築展日本館「少女都市」のキュレーションを行いました。 同年に、特定非営利活動法人AMP(Art Meeting Point)を設立しました。 2002年に食糧ビルディング解体にともない開催された、「エモーショナル・サイト展」の実行委員となりました。 2006年に70歳で武蔵野美術大学を退任し、名誉教授となりました。 鹿児島県霧島彫刻ふれあいの森の、作品・作家選定委員となりました。 2008~2009年は、ロンドンでの研修で日英を行き来する日々となりました。 2011年に、アーツ千代田3331内に「佐賀町アーカイブ」を設立し、「佐賀町アーカイブ」と題し、大竹伸朗さん、内藤礼さん、野又穫さん、森村泰昌さんの展覧会を開催しました。 2012年に三宅一生デザイン文化財団主催で21_21DESIGN SIGHTで開催された「田中一光とデザインの前後左右」展のキュレーションを行い、同時刊行の同名書籍の企画・編集を行いました。 2014年に、総合ディレクター清水敏男さんの企画で銀座四丁目名古屋商工会館で開催されました、 「いまアートの鏡が真実を映す」展の実行委員となりました。 2015年に良品計画発行の書籍『素手時然』の編集と執筆を行いました。 2016から2020年まで十和田市現代美術館館長に就任し、第68回全国美術館会議にて理事に就任しました。 2018年に、エイボン女性年度賞2017大賞を受賞し、2019年に第22回文化庁メディア芸術祭功労賞を受賞しました。 2020年に群馬県立近代美術館で開催された、展覧会「佐賀町エキジビット・スペース 1983-2000 現代美術の定点観測」の企画、キュレーションを行い、同カタログの編集、執筆を行いました。 同年に平凡社から著書『美術/中間子小池一子の現場』を出版し、良品計画から『MUJI IS』を編集、執筆し、刊行されました。 2021年に「東京ビエンナーレ2020/2021」の総合ディレクターとなり、企画展「東京に祈る」のキュレーションを行いました。 「東京ビエンナーレ」は、戦後の復興期に上野の東京都美術館で行われていた国際展で、中でも1970年、「人間と物質」をテーマにした第10回は日本の美術史に大きな足跡を残すものでした。 そこから半世紀が経ち、アートや芸術のあり方も大きく変化した今の東京で、新しいフレームや仕組みを実験する場として「東京ビエンナーレ」を2020年に始めることにしました。 著者は、素晴らしいクリェイターたちと人生で出会えたことは、もう感謝としか言いようがないといいます。 お互いに心からわかりあって、一緒にものをつくることができる関係というのは何にも代えがたいことです。 価値観が共有できる人と何かを生み出すということ、それが自分にとっていちばん楽しいことで生活の基本であるといいます。鍬と聖書が育んだ情緒/才気あふれるクリエイターたちと/衣服と美術、ものづくりの現場で/日本の社会で女性として生きるということ/はじまりの種をみつける/のこす言葉/略歴[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]小池一子 はじまりの種をみつける【中古】 歴史をつくる女たち 8 / 小池 一子, 木村 尚三郎 / 集英社 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】
2021.08.28
コメント(0)
-

婆娑羅大名 佐々木道誉(感想)
婆娑羅=ばさらは、日本の中世、主に南北朝時代の社会風潮や文化的流行をあらわす言葉で、実際に当時の流行語として用いられました。 語源はサンスクリット語で、”vajra (伐折羅、バージラあるいはバージャラ)= 金剛石(ダイヤモンド)を意味していました。 ”婆娑羅大名 佐々木道誉 ”(2021年4月 文藝春秋社刊 寺田 英視著)を読みました。 元弘の乱から建武中興の争乱が生んだ自由奔放な武人といわれ、室町幕府の要職につき守護となり権勢をふるい、入道して道誉と号し佐渡大夫判官入道といわれた、佐々木道誉の生涯を紹介しています。 平安時代には、雅楽・舞楽の分野で、伝統的な奏法を打ち破る自由な演奏を婆娑羅と称するようになりました。 身分秩序を無視して実力主義的で、公家や天皇といった名ばかりの権威を軽んじ、奢侈で派手な振る舞いや、粋で華美な服装を好む美意識でした。 鎌倉時代末期以降、体制に反逆する悪党と呼ばれた人々の形式や常識から逸脱して奔放で人目を引く振る舞いや、派手な姿格好で身分の上下に遠慮せず好き勝手に振舞う者達を指すようになりました。 室町時代初期、南北朝時代に流行し、後の戦国時代における下克上の風潮の萌芽となりました。 源氏足利将軍執事で守護大名の高師直兄弟や、近江国守護大名の佐々木道誉(高氏)、美濃国守護大名の土岐頼遠などは、ばさら的な言動や行動でばさら大名と呼ばれ、ばさらの代表格とされています。 佐々木道誉は、足利幕府草創期の不動の重臣であり歴戦の強者でもあり、若狭・近江・出雲・上総・飛騨・摂津守護でありまあした。 華道、香道、茶道、連歌、そして能・狂言まで、現代日本人の美意識の源流はこの男にあったといいます。 寺田英視さんは、1948年大阪府生れ、上智大学文学部史学科を卒業し、文藝春秋社に入社後、主として編輯業務に携わり、2014年に退社しました。 在学中から武道に親しみ、和道流空手道連盟副会長・範士師範を務めています。 佐々木道誉は佐々木高氏のことで、一般的に佐々木佐渡判官入道、佐々木判官、佐々木道誉の名で知られ、道誉(導誉)は法名であり実名は高氏です。 鎌倉幕府創設の功臣で近江を本拠地とする佐々木氏一族の京極氏に生まれたことから、京極道誉または京極高氏とも呼ばれます。 初めは、北条氏得宗家当主で鎌倉幕府第14代執権の北条高時に御相伴衆として仕えました。 1331年に後醍醐天皇が討幕運動を起こし、京を脱出して笠置山に拠った元弘の乱では、道誉は幕府が編成した鎮圧軍に従軍しました。 捕らえられた後醍醐天皇は廃され、1332年に供奉する阿野廉子・千種忠顕らと共に隠岐島へ配流された際には、道誉が道中警護などを務めました。 後醍醐帝を隠岐に送り出し帰京したのち、後醍醐の寵臣で前権中納言の北畠具行を鎌倉へ護送する任にあたります。 しかし道中の近江国柏原で幕府より処刑せよとの命をうけ、同年6月19日に具行を処刑しました。 後醍醐配流後も河内の楠木正成らは反幕府活動を続けて幕府軍と戦い、後醍醐も隠岐を脱出して伯耆国船上山に立て籠りました。 1333年に幕府北条氏は、下野の足利高氏、後の尊氏らを船上山討伐に派遣しました。 しかし高氏は幕府に反旗を翻し、丹波国篠村で反転して京都の六波羅探題を攻略しました。 この時期の道誉自身の動向については良く解っていませんが、足利高氏と道誉が密約して連携行動を取ったことを示す逸話があります。 足利尊氏、上野の新田義貞らの活躍で鎌倉幕府は滅亡し、入京した後醍醐天皇により建武の新政が開始されると、六角時信や塩冶高貞ら他の一族と共に雑訴決断所の奉行人となりました。 尊氏が政権に参加せず、武士層の支持を集められなかった新政に対しては、各地で反乱が起こりました。 1335年には、信濃において高時の遺児である北条時行らを擁立した中先代の乱が起こり、尊氏の弟の足利直義が守る鎌倉を攻めて占領した時行勢の討伐に向かう尊氏に道誉も従軍しました。 時行勢を駆逐して鎌倉を奪還した尊氏は独自に恩賞の分配を行うなどの行動をはじめ、道誉も上総や相模の領地を与えられました。 後醍醐天皇は鎌倉の尊氏に対して上洛を求めましたが、新田義貞との対立などもありこれに従わず、遂には義貞に尊氏・直義に対する追討を命じた綸旨が発せられました。 しかし、建武政権に対して武家政権を樹立することを躊躇する尊氏に、道誉は積極的な反旗を勧めていたともされます。 建武の乱では、足利方として駿河国での手越河原の戦いに参加しましたが、新田義貞に敗れ弟の貞満らが戦死しました。 道誉自身は義貞に降伏し、以降新田勢として従軍して足利方と争いましたが、箱根・竹ノ下の戦いの最中に新田軍を裏切り足利方に復帰しました。 この裏切りにより新田軍は全軍崩壊し敗走し、道誉を加えた足利方は新田軍を追い京都へ入り占拠しました。 しかし、奥州から下った北畠顕家らに敗れた足利軍は京都を追われ、兵庫から九州へと逃れました。 この時、道誉は近江に滞在して九州下向には従っていないともされます。 九州から再び東上した足利軍は湊川の戦いで新田・楠木軍を撃破して京都へ入り、比叡山に逃れた後醍醐天皇・義貞らと戦いました。 道誉は東から援軍として来た信濃守護小笠原貞宗と共に、9月中旬から29日まで補給路である琵琶湖を近江国を封鎖する比叡山包囲に当たりました。 やがて尊氏の尽力で光明天皇が即位して北朝が成立し、尊氏は征夷大将軍に任じられて室町幕府を樹立し、後醍醐天皇らは吉野へ逃れて南朝を成立させました。 道誉は若狭・近江・出雲・上総・飛騨・摂津の守護を歴任しました。 1337年に、勝楽寺に城を築き、以降没するまで本拠地としました。 1340年に長男の秀綱と共に白川妙法院門跡亮性法親王の御所を焼き討ちし、山門宗徒が処罰を求めて強訴しました。 朝廷内部でもこれに同情して幕府に対し道誉を出羽に、秀綱を陸奥に配流するように命じました。 ところが、幕府では朝廷の命令を拒絶、結果的に道誉父子は上総に配流されました。 山門に悩まされる尊氏・直義兄弟には、道誉を罰するつもりなど毛頭無かったものと推察されています。 翌年、何事もなかったかのように幕政に復帰し、引付頭人、評定衆や政所執事などの役職を務め、公家との交渉などを行いました。 1348年の四條畷の戦いなど南朝との戦いにも従軍し、帰還途中に南朝に奇襲を受け次男の秀宗が戦死しました。 室町幕府の政務は当初もっぱら弟の直義が主導しましたが、1350年から観応の擾乱と呼ばれる内部抗争が発生しました。 道誉は当初師直派でしたが、擾乱が尊氏と直義の兄弟喧嘩に発展してからは尊氏側に属しました。 南朝に属し尊氏を撃破した直義派が台頭すると、1351年に尊氏・義詮父子から謀反の疑いで播磨の赤松則祐と共に討伐命令を受けました。 これは陰謀であり、尊氏は道誉を討つためと称して京都から近江へ出兵し、義詮は則祐討伐のため播磨へ出陣し、事実上京都を包囲する構えで、父子で京都に残った直義を東西から討ち取る手筈でした。 しかし、事態を悟った直義は逃亡しました。 道誉は以後も尊氏に従軍し、尊氏に南朝と和睦して後村上天皇から直義追討の綸旨を受けるよう進言しました。 尊氏がこれを受けた結果正平一統が成立し、直義は失脚し急逝しました。 1358年に尊氏が薨去した後は、2代将軍義詮時代の政権において政所執事などを務め、幕府内における守護大名の抗争を調停しました。 この頃、道誉は義詮の絶大な支持のもと執事の任免権を握り、事実上の幕府の最高実力者として君臨しました。 婆娑羅を一身に体現したのが佐々木道誉です。 婆娑羅は何よりも誰よりも、道誉と結びついています。 道誉の家すなわち佐々木家、京極家は、宇多天皇の孫雅信王に出自し、近江を根拠地とする宇多源氏です。 鎌倉時代には、京において検非違使を務める家でもありました。 婆娑羅大名と言えば高師直や土岐頼遠の名もすぐに浮びますが、彼らが時を得顔にふるまうのは一時で、戦上手ではありますが、美意識と教養の広さ深さにおいては、遥かに道誉に及ばないでしょう。 道誉に象徴される婆娑羅とは、単なる乱暴者の所業をいうのではありません。 日本人の美意識と深くかかわる何かがそこに潜んでいます。 婆娑羅の内実は、能狂言から茶の湯、立花、聞香、連歌にまで及びます、 幅広い文化の享受者であり、庇護者であり、指導者でもありました。 本書で、南北朝という動乱と向背常なき時代を生き抜いた道誉の婆娑羅ぶりを通して、自由と狼籍の間に潜む日本人の出処進退と美的感覚を瞥見しています。 人間という社会的存在にとって永遠の難問である自由、すなわち根源的主体性の在処を垣間見る小さな足掛かりを得たいと願うといいます。 第一章と第二章は、道誉が生きた時代背景と出自についての概略です。 面倒であれば第三章の道誉の婆娑羅ぶりから読み始めて下さってもよいとのことです。 興味の赴くままにお読み戴ければ、著者としては十分満足であるといいます。はじめに 名物道誉一文字/第1章 佐々木氏の出自と家職、そして若き日の道誉/第2章 動乱の時代ー両統迭立と三種の神器/第3章 婆娑羅ーその実相と文化人道誉(妙法院焼討/立花/聞香/連歌/能狂言/茶寄合/楠木正儀と道誉/大原野の大饗宴/肖像自賛と道誉の死)/第4章 婆娑羅から傾奇へー変容と頽廃/第5章 根源的主体性と自由狼藉の間/あとがき 主要参考文献 佐々木道誉略年譜と関連事項[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 婆娑羅大名佐々木道誉 文春新書1310/寺田英視(著者) 【中古】afb佐々木道誉 南北朝の争乱を操ったバサラ大名【電子書籍】[ 羽生道英 ]
2021.08.25
コメント(0)
-

壱人両名 江戸日本の知られざる二重身分(感想)
江戸時代の身分は世襲で固定されていたといわれますが、実際には自在に身分をまたぐ人々が全国に大勢いました。 壱人両名という言葉は、江戸時代の史料に見られる、江戸時代の人々が使用したナマの表現です。 同義語として、壱人弐名、一鉢両名、一身両名などがあります。 ”壱人両名 江戸日本の知られざる二重身分”(2019年4月 NHK出版刊 尾脇 秀和著)を読みました。 一人の人間が二つの名前と身分を同時に保持して使い分け、百姓でありつつ武士でもあったりする壱人両名について、融通を利かせて齟齬を解消することを最優先した江戸時代特有の秩序冠を解説しています。 「壱」(「壹」)と「一」とは全くの別の漢字ですが、古来通用されますので、一人両名などの表記も当然混用されます。 数値の表記でも「壱」を一般的に使用し、幕府の文書でも壱人両名の表記が多いです。 著者は、最も代表的な表記であった「壱人両名」を、これらを総称する学術用語として使用しています。 ちなみに壱人両名という言葉は今ではすっかり死語で、一般の辞典には載っていません。 しかし「日本国語大辞典」(第二版)という、現在日本最大規模の辞典ともなると、「一人両名」という項目で、「一人で二つの名を持っていること」という意味が掲載されています。 百姓が、ある時は裃を着て刀を差し、侍となって出仕する-周囲はそうと知りながら咎めず、お上もこれを認めています。 なぜそんなことが、広く日本各地で行われていたのでしょうか。 尾脇秀和さんは1983年京都府生まれ、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程を修了し、京都近郊相給村落と近世百姓で博士(文学)号を取得し、現在、神戸大学経済経営研究所研究員、佛教大学非常勤講師です。 江戸時代の身分はピラミッド型の士農工商で、一生変えられないと考えられてきました。 しかし、ある時は侍、ある時は百姓、と自在に身分を変える名もなき男たちが、全国に無数にいたといいます。 江戸時代は身分制度で身動きのできない窮屈な時代だったという概念を、根底から覆すこととなるでしょう。 なぜ別人に成りすますのでしょうか、お上はなぜそれを許容したのでしょうか。公家の正親町三条家に仕える大島数馬と、京都近郊の村に住む百姓の利左衛門の二人は、名前も身分も違いますが実は同一人物です。 それは、時間の経過や環境の変化で、名前と身分が変わっだわけではありません。 大小二本の刀を腰に帯びる帯刀にした姿の公家侍の大島数馬であると同時に、村では野良着を着て農作業に従事するごく普通の百姓の利左衛門でもありました。 いわば一人の人間が、ある時は武士、ある時は百姓という、二つの身分と名前を使い分けていたのです。 江戸時代中期以降、様々な壱人両名が、江戸や京都などの都市部から地方の村に至るまで、あちこちに存在していたことが確認できるといいます。 伊勢国の、とある村の百姓彦兵衛は、別の村では百姓仁左衛門でもありました。 武蔵国のとある村に住む神職村上式部は、その村の百姓四郎兵衛でもありました。 近江国大津の町人木屋作十郎は、別の村では百姓清七でもありました。 陸奥盛岡藩士の奈良伝右衛門は、同藩領の富商・佐藤屋庄六でもありました。 幕府の御家人である河野勇太郎の父河野善次郎は、江戸の町の借家で商売を営む町人の善六でもあったなどなど。 これらは、子供の留吉が成人して正右衛門に改名したというような、時間の経過などによって名前や身分が変化し移行したのではありません。 ある時は佐藤屋庄六でありつつ、またある時は奈良伝右衛門でもあるといったように、一人で二つの名前と身分を、同時に保持して使い分けていました。 「士」であると同時に「商」でもあるなんて、絶対にいるはずのない存在ですが、現実にはそれは広範に存在していました。 壱人両名の存在は、幕府の公的な記録でも、百姓・町人らの私的な記録でも、覆しようのない明白な事実として確認できるといいます。 いつの時代も世の中は、原則や綺麗ごとや建前だけでは成り立ちません。 どんな物事にも本音と建前があり、表と裏があります。 表だけ建前だけを見たのなら、江戸時代は身分が厳格に固定されていて流動性に乏しい姿しか見えてきません。 しかし、本音と建前、表と裏の両方を見た時、壱人両名のような存在が、全く否定しようのない事実として浮かびあがってくるといいます。 数多の壱人両名の男たちは、誰もが知っている、名のある歴史上の人物ではなく。名もなき者たちです。 壱人両名というあり方に注目した時、長い期間、変わらなかったように見える江戸時代の社会、とりわけ身分の固定とか世襲とかいわれているものの、本当の姿が見えてきます。 江戸時代、一般庶民にとっての士農工商という言葉は、社会を構成する諸々の様々な職種の総称です。 この四種類しか身分・職種がないとか、あるいは士・農・工・商という四段階の階級序列だとかいう意味ではありません。 世の中は、政治をする人、食糧生産に従事する人、服を作る人、物を交易する人など、様々な職種の存在によって成り立っています。 政治もして、米も野菜も作り、魚も獲って、服も作る、などを一人でこなすことはできません。 ですから、ある程度の文明が形成された社会では、分業によって社会が構成され、人はその社会の一員として、果たすべき役割を担うようになります。 江戸時代における士農工商は、そのような社会的分業と、それによる人々の差異を当然あるべき状態とする前提のもと、一般には肯定的な意味で使われていた言葉です。 江戸時代の人々は、このような社会的分業意識に基づいて、現在自分が受け持つ役割に精勤し、その役割を次代に継承させていけば、現状通り社会は安定し、自分も、家も、国も繁栄し続けるという価値観を持っていました。 その社会の安定には、各自がその役割を果たす上での、秩序も必要不可欠となります。 特に治者と被治者、君臣・父子・夫婦・兄弟・長幼など、その人の社会的立場に基づく上下の差別も重視されました。 上位者は下位者への慈愛、下位者は上位者への敬意を求められ、その逸脱はあるまじき行為とされる社会でした。 それゆえ、その地位・役割に相応しい行動と、務めを果たす分相応の生き方が美徳とされました。 江戸時代の社会は差(たが)いと別(わか)ちがあることを大前提として、それを肯定した上に成り立っていた社会です。 江戸時代は、近現代社会とは異なる価値観や仕組みで成り立ち、人々はそれを当然として生きていました。 現代社会での差別(さべつ)という言葉は、理不尽で不当な扱いを受ける、絶対的な悪としての意味で使われます。 江戸時代の差別(しゃべつ)は、太陽と月は違うとか、犬と猫は違うとかいうような、当たり前の物事の差異や区別を意味する言葉でした。 社会的分業と分相応の意識と相まって、差別は社会を安定させる秩序そのものでもあり、ほとんど肯定的な意味でしか使われていませんでした。 江戸時代と現代とで、字面も訓みも全く同じ言葉が使われていたとしても、その意味が同じでないことも多いです。 ゆえに過去の史料に見える言葉を、現代社会の語感や意味で読みとらないよう、十分注意せねばなりません。 検討する時代においてその言葉がどのような意味で使われていたかについて、当時の価値観や社会構造に即して、その時代における意味を正確に踏まえる作業が、歴史学の研究において考察の前提として重要です。 現代人から見ると、壱人両名の状態は奇妙で面白く見えます。 名前だけでは別人ですが実は同一人物、ある時は武士、またある時は町人だなんて、事実は小説よりも奇なり、という感じがします。 ですが、別に他人を面白がらせようと思って、そんなことをしているのではありません。 そこにはどんな理由があったのでしょうか。 壱人両名を考えることは、江戸時代はどんな社会だったかを明らかにする、一つの視点ともなるのです。 事実ありのままではなく建前を重視した処理は、百姓・町人たちばかりではなく、大名が幕府に対して行う手続きにおいても慣行化していました。 例えば大名には、生前に相続者を選定して幕府に届け出ておかねばならない規則がありました。 届け出がない状態で大名の当主が死ねば相続は認められず、原則としてその大名家は断絶となります。 しかし実際はそんな状態で当主が死んだ場合、家臣や親族たちがなお当主存命の体を装って、当主が病床から後継者を届け出るという手続きを行いました。 つまり、死ぬ前にちゃんと届け出ていたという状況を建前として作り出すことで、無事に相続が認められたのです。 このほか、相続人として幕府に届け出ている長男が死んだ場合、次男を長男本人ということにしてこれとすり替えた事例があります。 また、当主が17歳未満で死去すると相続が認められないという先例上の規則を意識して、幕府に実年齢とは異なる年齢を届け出る年齢操作が、様々な事情によって常態化していました。 これらはいずれも「公辺内分」と呼ばれ、幕府には一切秘密裏に進められました。 しかしその内情は、実は幕府も承知の上であり、表向き知らない体で黙認していたのです。 真実なるものは、平穏な現状を犠牲にしてまで、強いて白日の下に曝される必要はありません。 事を荒立てることなく、世の中を穏便に推移させることこそが最優先されるべきであり、秩序は表向きにおいて守られていればよいのです。 そのように考えて、うまく融通を利かせて調整・処理するのが、長い天下泰平の期間に醸成されていきました。 これが江戸時代の秩序観なのであり、壱人両名はその秩序観に基づいた顕著な方法であったといえます。 特に非合法とされた壱人両名は、事実に即せば明らかに、支配される側の下位の者が、支配する側たる上位の者に虚偽の申告を行っている行為です。 ですが支配側が、それをうまいことやっているだけだとして黙認していることも多いです。 ただ何かしらの要因でそれが表沙汰になった場合、その事実は、上下の差別を重視する社会の秩序に反しますから、処罰せざるを得ないだけのことなのです。 江戸時代の社会秩序は、極端に言えば、厳密に守られている必要はない、ただ建前として守られているという体裁がとられていることを重視するのです。 壱人両名は、このような江戸時代の秩序観に基づきつつ、社会の秩序を表向き維持して、波風を立てず現実的に推移させる、作法・慣習の一つでした。 社会構造が国民を一元的に管理する近代国家への改変に伴って否定されて変化し、作法・慣習としての意味を喪失し、国家に不都合な偽詐として消滅させられていきました。 それは暗黙の了承下で行われていた調整行為であったがゆえに、やがて人々の記憶からも綺麗に忘れ去られていきました。 けれども、壱人両名を作り出していた本音と建前のあり方、特に建前的な調整行為を是とする秩序観は、現代社会でも変わらないものではないでしょうか。序 章 二つの名前をもつ男/一章 名前と支配と身分なるもの/第二章 存在を公認される壱人両名-身分と職分/第三章 一人で二人の百姓たち-村と百姓の両人別/第四章 こちらで百姓、あちらで町人-村と町をまたぐ両人別/第五章 士と庶を兼ねる者たち-両人別ではない二重身分/第六章 それですべてがうまくいく?-作法・習慣としての壱人両名/第七章 壊される世界-壱人両名の終焉/終 章 壱人両名とは何だったのか/主な参考文献・出店史料[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]壱人両名 江戸日本の知られざる二重身分【電子書籍】[ 尾脇秀和 ]【中古】 大系 日本の歴史(9) 士農工商の世 /深谷克己【著】 【中古】
2021.08.17
コメント(0)
-

沢村栄治 裏切られたエース(感想)
沢村栄治は1917年三重県宇治山田市生まれで、京都商業学校、現在の京都先端科学大学付属高等学校の投手として、1933年春、1934年春・夏の高校野球全国大会(当時は中等野球)に出場しました。 ”沢村栄治 裏切られたエース”(2021年2月 文藝春秋社刊 太田 俊明著)を読みました。 1934年に創設された読売ジャイアンツの前身・大日本東京野球倶楽部に投手として参加し、1937年に日本職業野球連盟の第1回最高殊勲選手に選ばれた、天才投手・沢村栄治の野球と人生を紹介しています。 1試合23奪三振を記録するなど、才能の片鱗を見せました。 1934年の夏の大会終了後に京都商業を中退し、その年の11月に開催された読売新聞社主催の日米野球の全日本チームに参戦し、5試合に登板し4試合は先発しました。 日本プロ野球史上に残る伝説の選手の一人であり、1947年彼の名を冠した沢村賞が制定され、該当者のない場合を除き、優秀投手に毎シーズン贈るとされています。 来日したアメリカ大リーグ選抜チームと静岡草薙球場で対戦したとき、ベーブ・ルース、ルー・ゲーリッグらの超一流打者に対し好投しました。 試合はゲーリッグのホームランにより1対0で惜敗しましたが、そのときの善戦の模様は今日まで語り伝えられています。 戦前のプロ野球界で、NPB史上初の最多勝利を獲得し、NPB史上初の最高殊勲選手も受賞しました。 史上2人目のシーズン防御率0点台、史上初の投手5冠に輝き、史上初のノーヒットノーラン達成など、さまざまな記録を打ち立てました。 実働5年間の通算成績は、登板試合105、投球回765と3分の1、63勝22敗、防御率1.74、奪三振554、完投65、完封20でした。 獲得したおもなタイトルは、最多勝利2回、最優秀勝率1回、最高勝率1回、最多奪三振2回、最高殊勲選手1回でした。 太田俊明さんは1953年千葉県松戸市生まれ、東京大学在学中は硬式野球部の遊撃手として東京六大学野球で活躍しました。 卒業後は総合商社などに勤務し、1988年に坂本光一の筆名でで執筆した、甲子園を舞台にしたミステリーで第34回江戸川乱歩賞を受賞しました。 2013年の定年退職を機に小説執筆を再開し、2016年に第8回日経小説大賞を受賞しました。 2020年に亡くなった野村克也さんは、著書で、沢村栄治なかりせば私もいない、と書いているそうです。 沢村栄治は日本プロ野球における、その年の最高の先発完投型投手に贈られる沢村賞に名を残す、職業野球黎明期の伝説的投手です。 その名は、野村さんの言葉を引くまでもなく、日本野球史に燦然と輝いていますが、実は沢村の職業野球における全盛期はわずか2年弱に過ぎません。 1936年から1943年の8年間で63勝22敗が、不世出の天才投手・沢村栄治の職業野球における生涯成績です。 沢村と同時期に同じ巨人軍などで活躍したビクトル・スタルヒンが、通算で303勝176敗、1シーズンだけで42勝をあげた時代に、この数字ぱ不世出と呼ばれる投手としてはまったく物足りないと言わざるをえません。 では、数字的にはこの程度の投手がなぜ沢村賞に名を残し、時代の異なる知将・野村さんをして、沢村栄治なかりせば、と言わしめる存在になったのでしょうか。 それには、もちろん理由かあり、著者はそれを書くのが、本書の目的であるといいます。 日本における野球の最初は、1871年9月30日に横浜の外国人居留民とアメリカ軍艦の乗員との間で行われた、現在の横浜スタジアム球場の試合のようです。 1872年頃に第一番中学、現在の東京大学の外国人教師・ホーレス・ウィルソンによって、学生たちの間に野球が広まりました。 1907年に初の有料試合が開催され、1908年にアメリカのマイナーリーグ主体のプロ野球チームが来日しました。 1909年に羽田球場が建設され。日本運動倶楽部が設立されました。 1920年に合資会社日本運動協会が設立され、日本のプロ野球の始まりとなりました。 次いで天勝野球団が設立され、1923年にプロ球団宣言が行われました。 1923年に関東大震災の震災被害により、日本運動協会と天勝野球団ともに解散し、日本運動協会は阪神急行電鉄により宝塚運動協会として再結成されました。 1929年に宝塚運動協会が解散され、1934年12月26日に大日本東京野球倶楽部、東京巨人軍、現在の読売ジャイアンツが設立されました。 大日本東京野球倶楽部は、読売新聞社社主であった正力松太郎さんによって設立され、正力さんが初代オーナーとなりました。 正力さんは読売中興の祖として大正力と呼ばれ、それぞれの導入を強力に推進したことで、プロ野球の父、テレビ放送の父、原子力の父とも呼ばれます。 1934年の暮れ、全日本チームを基礎としたプロ野球チーム・大日本東京野球倶楽部の結成に参加しました。 沢村が学校を中退してプロ入りしたのは、野球部員による下級生への暴行事件が明るみに出て、連帯責任で甲子園出場が絶望的になったためでした。 等持院住職の栂道節さんが、同年大日本東京野球倶楽部専務取締役に就任する市岡忠男さんに沢村を紹介しました。 等持院は京都市北区にある臨済宗天龍寺派の寺院で、足利氏の菩提寺であり、足利尊氏の墓所としても知られます。 市岡さんは、早稲田大学野球部監督、読売新聞社社員、大日本東京野球倶楽部初代総監督、日本職業野球連盟初代理事長、東京巨人軍初代代表を歴任しました。 読売新聞社は1931年にアメリカ大リーグ選抜軍を日本に招待し、全日本軍や東京六大学野球などとの対戦が組まれ、成功を収めました。 しかし、1932年に野球統制令により学生選手のプロ選手との対戦が許可制になり、実質的に興業ができなくなりました。 そこで市岡さん、浅沼誉夫さん、三宅大輔さん、鈴木惣太郎さんの4人は、野球統制令対策として職業野球チームを結成することを正力松太郎社長に働きかけ ました。その結果1934年6月9日、日本工業倶楽部で職業野球団発起人会が開かれ、6月11日には創立事務所が設けられました。 この時、市岡さんは沢村を勧誘して入団を実現させました。 沢村はプロ野球リーグが始まる前の1935年に、第一次アメリカ遠征に参加し、21勝8敗1分けの戦績を残しました。 同じ年の国内での巡業では22勝1敗で、翌1936年の第2次アメリカ遠征でも11勝11敗をあげました。 そしてプロ野球リーグが開始された1936年秋に、プロ野球史上初、昭和初、20世紀初、大正生まれ初のノーヒットノーランを達成しました。 同年12月、大阪タイガースとの最初の優勝決定戦では3連投し、巨人に初優勝をもたらしました。 1937年春には24勝・防御率0.81の成績を残して、プロ野球史上初となるMVPに選出されました。 さらにこの年は2度目のノーヒットノーランも記録するなど、黎明期の巨人・日本プロ野球界を代表する快速球投手として名を馳せました。 しかし、徴兵によって甲種合格の現役兵として帝国陸軍に入営し、1938年から満期除隊の1940年途中まで軍隊生活を送り日中戦争に従軍しました。 前線で手榴弾を多投させられたことから、生命線である右肩を痛めました。 また戦闘では左手を銃弾貫通で負傷し、さらにマラリアに感染しました。 復帰後はマラリアによって何度か球場で倒れたり、右肩を痛めたことでオーバースローからの速球が投げられなくなりました。 しかし、すぐに転向したサイドスローによって抜群の制球力と変化球主体の技巧派投球を披露し、3度目のノーヒットノーランを達成しました。 その後、応召により予備役の兵として軍隊に戻り、1941年終盤から1942年を全て棒に振り、さらにはサイドスローで投げることも出来ず、肩への負担が少ないアンダースローに転向しました。 しかし、制球力を大幅に乱していたことで好成績を残すことが出来ず、1943年の出場はわずかでした。 投手としては、1943年7月6日の対阪神戦の出場が最後で、3イニングで8与四死球と2被安打で5失点で降板となりました。 公式戦最後の出場は同年10月24日、代打での三邪飛でした。 1944年シーズン開始前に巨人からついに解雇され、移籍の希望を持っていましたが、鈴木惣太郎さんから諭されて現役引退となりました。 その後、南海軍から入団の誘いがありましたが固辞しました。 現役引退後、1944年10月2日に2度目の応召があり、同年12月2日、フィリピン防衛戦に向かうため乗船していた軍隊輸送船が、屋久島沖西方の東シナ海でアメリカ海軍潜水艦により撃沈され、屋久島沖西方にて27歳で戦死しました。 1959年に野球殿堂入り。1966年6月25日に第27回戦没者叙勲により勲七等青色桐葉章を追贈されました。 巨人は沢村の功績をたたえて、背番号14を日本プロ野球史上初の永久欠番に指定しました。 また、同年に沢村の功績と栄誉を称えて沢村栄治賞が設立され、プロ野球のその年度の最優秀投手に贈られることとなりました。 沢村はよく、ホップする快速球を投げたと言われます。 日本プロ野球における最高球速は、2016年に日本ハムファイターズの大谷翔平が記録した165キロです。 2015年に、これまでないと信じられてきた全盛期の沢村か試合で全力投球する映像か発見されました。 沢村は現代でもほとんど見られないほどの、全身の力を効率的に使った流れるようなフォームでした。 投手の球速を、投球の際の腰の移動速度と利き腕の移動速度の比から推定すると、投球映像のコンピューター解析では比率は5.38でした。 これは150キロ前後の速球を投げる現代のプロ野球のエース級の5.0を凌駕し、大谷氏の5.41に近いといいます。 当時、悪条件の中で投げた沢村が、気象条件のよいときに本来のフォームから全力投球したら、いったいどれだけ速いボールを投げたのでしょう。 いち野球ファソとして、それか知りたくて、著者は沢村栄治を訪ねる旅に出たといいます。第1章 沢村栄治と正力松太郎ー職業野球への胎動/第2章 甲子園のエースから職業野球のエースへ/第3章 ベーブ・ルースとの対決ー東京巨人軍の誕生/第4章 職業野球リーグの創成/第5章 「私は野球を憎んでいます」/第6章 戦場と球場/第7章 そしてプロ野球が生まれた[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]送料無料【中古】沢村栄治 裏切られたエース (文春新書 1300)巨人の星 第91話 栄光のピッチング(沢村栄治物語)【動画配信】
2021.08.07
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1