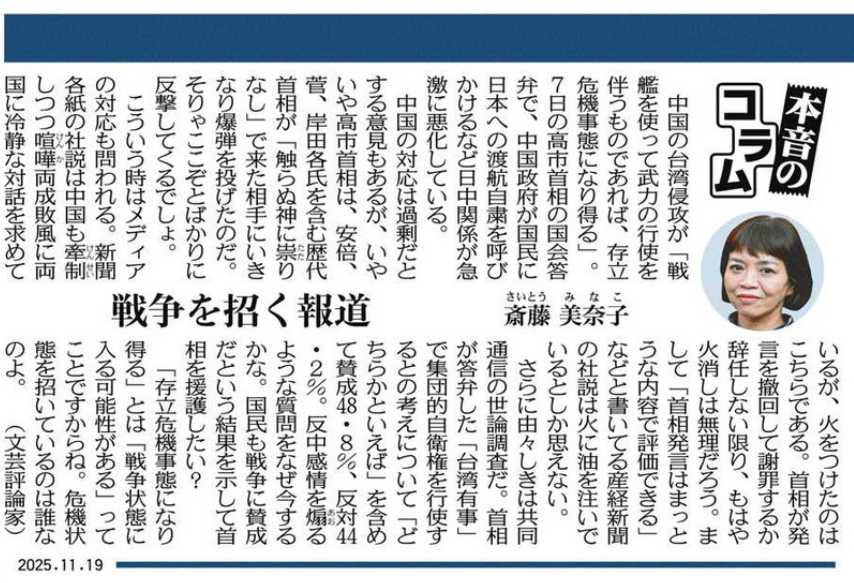2021年12月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

ジュネーブ史(感想)
ジュネーヴ(仏: Geneve)は、スイス西部、レマン湖の南西岸に位置する都市で、フランス語圏に属しジュネーヴ州の州都です。 英語ではジェニーバGeneva,ドイツ語ではゲンフGenfと呼びます。 ”ジュネーブ史”(2021年1月 白水社刊 アルフレッド・デュフール著/大川四郎訳)を読みました。 権力抗争を経ながら自由を希求してきたジュネーブについて、要塞都市から国際都市となるまでの歴史を概説しています。 ジュネーヴはスイス南西部,レマン湖からローヌ川が流れ出る交通の要所にあり、フランス語地域の精神的中心であり国際的都市です。 三日月形のレマン湖の南西側の角を取り囲むように広がり、サレーヴ山、ジュラ山脈等の山地に囲まれ、市内をアルヴ川、ローヌ川が流れています。 人口は約19万人、面積は15.93平方km、標高は375mで、チューリッヒに次ぎスイス第2の都市です。 スイスの公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4言語ですが、フランス語圏のジュネーヴでは、ほとんどの場合フランス語が用いられます。 しかし、世界都市であるため基本的に英語も通用します。 金融業が発達しており、プライベードバンクの中心地です。 また、国際赤十字,ILO,世界保健機関などの本部所在地で,国際連合ヨーロッパ本部が置かれているパレ・デ・ナシヨンがあります。 金融,商業の中心で、工業は時計,精密機械,アクセサリーなどがあります。 また、公園の多い美しい町で,モン・ブラン山の景観に恵まれ,観光地としても著名です。 12~14世紀の聖堂、15~16世紀の市庁、1559年創立の大学、図書館、美術館などがあります。 古代ケルト人の町でしたが,1世紀にローマ植民市となりました。 16世紀にはカルバン派の本拠地でした。 1815年にスイス連邦に加盟し、19世紀後半以降、急速に発展しました。 著者のアルフレッド・デュフール氏は1938年チューリッヒ生まれで、デュフール家は、14世紀以来、ジュネーヴ郊外サティニーに由来する旧家です。 中等教育の一時期をチューリッヒで就学したことを別とすれば、少年時代の大半をサティニーで過ごしました。 名門校コレージュ・ド・カルヴァンを優秀な成績で卒業し、ジュネーヴ大学法学部に進学しました。 同学部を卒業後、文学部に学士入学し哲学をも学びました。 ドイツのハイデルベルク、フライブルク両大学留学を経て、法学博士号を取得しました。 ジュネーヴ大学法学部で教歴を重ね、1980年に正教授に就任しました。 法制史の講義と研究に従事する一方、法制史研究室主任として、後進の研究者育成にもたずさわりました。 主たる研究領域は、フーゴー・グロティウス、ザミュエル・プーフェンドルフらの近世理性主義的自然法論が、18世紀スイス・フランス語圏地方の婚姻法および国制にどのように浸透していったのかというテーマです。 著者は、ジュネーヴ大学法学部在学中に聴講したポール・グッゲンハイム教授の講義に示唆され、フライブルク大学法学部留学中にハンス・ティーメ教授から直接の指導を受けています。 その後、近世理性主義的自然法論の淵源として、スペイン後期スコラ学派にまで研究対象を拡げています。 そして、2003年に定年退職し、現在はジュネーヴ大学名誉教授であり名誉法学部長です。 訳者の大川四郎氏は1959年鹿児島県生まれ、1986年名古屋大学大学院法学研究科博士課程前期課程を修了しました。 そして、ジュネーヴ大学法学部D.E.S(高等教育免状)課程を修了し、愛知大学法学部教授となり今日に至ります。 本書は、著者が母校ジュネーヴ大学法学部で長年講じてきた、「ジュネーヴ法制度史」講義か原型となっています。 例年夏学期に開講された講義では、中世から18世紀後半までの都市国家ジュネーヴにおける制度史が講じられました。 その範囲を広げ、古くは古代ローマ時代にまで遡り、近くは21世紀初頭までのジュネーヴ史をコンパクトに叙述しています。 訳者は、1991年10月からスイス政府奨学金留学生としてジュネーヴ大学法学部に留学しました。 研究テーマは、17世紀スイスを媒介としてヨーロッパ中に伝播した近世理性主義的自然法論が18世紀フランス私法学に及ぼした影響でした。 修士論文に相当する論文をまとめるにあたり、著者に師事しました。 研究を進める傍ら、著者による各種関連講義を訳者は聴講しました。 このうち、1992年夏学期に聴講した半期間の選択科目の1つが本書の原型となりました。 奨学金終了後、著者の推薦で法制史研究室の助手として一年間の任期で雇用してもらいました。 著者が本書の執筆を始めたのは、19934年頃だったと記憶するといいます。 訳者は、修士論文の口述試験を終えると、1995年4月に日本へ帰国しました。 その後も原稿執筆か続けられ、1997年にようやく本書が上梓されました。 ただちに著者の了解を得、訳者は翻訳を始めたものの、諸般の事情により、完訳を終えるまでに実に22年もの歳月を要してしまったといいます。 ジュネーヴは、カエサル「ガリア戦記」の冒頭に登場するアロブロゲス人によって築城された城塞都市に始まり、中世ヨーロッパにおける交易と金融の中心地になりました。 そして、宗教改革の牙城に始まり、現代を風靡する急進主義について開かれた都市へと発展しました。 その後、後退と発展をくり返し、現在のジュネーヴに至っています。 対内的には、度重なる権力抗争を経ながら、自由を希求してきました。 対外的には、小国ながら、周辺諸国との間で高度な外交術を駆使して、その独立を獲得し維持しようとしてきました。 その延長線上に、今日の国際平和文化都市ジュネーヴがあります。 ジュネーヴの歴史は古く、ローマ時代までさかのぼり、ユリウス・カエサルがこの地を占領し、ジュネーヴという名前を与えたといいます。 その後、神聖ローマ帝国の支配を受けましたが、1315年のモルガルテンの戦い等の独立運動の影響でハプスブルク家から離れ、1648年のヴェストファーレン条約によって正式に独立が認められました。 近世にはプロテスタントの一派である改革派の拠点となり、1536年にカトリックのサヴォイア公国から独立し、宗教改革がなされ、ジュネーヴ共和国としての宣言がなされ、ジャン・カルヴァンらによる共和政治が行われました。 ジュネーヴ革命とも称されます。 1602年、サヴォイア公カルロ・エマヌエーレ1世が、ジュネーヴ支配をもくろみ侵入しましたが、市民軍の抵抗にあい失敗に終わりました。 この事件は、サヴォイア公が侵入に使った梯子にちなんで“エスカラード(梯子)”と呼ばれま 現在のエスカラード祭はこの事件にちなんだものです。 フォンテーヌブローの勅令の後、啓蒙主義の感化を受けた神学が台頭し、カルヴァン派の正統主義にとって代わりました。 市民は市参事会を牛耳る門閥のシトワイアンとユグノー企業家のブルジョワに分裂していました。 1704年から1782年にかけて、これらに非市民労働者を加えた各勢力が三つ巴となって政権を争いました。 ユグノーが多かった時計職人がフランスでの迫害から逃れるためにジュネーブへ移住し、時計が地場産業となりました。 機械式時計に用いられるジェネバ機構は、ジュネーブにちなんで命名されました。 1781年に、ブルジョワと労働者が市民総会で間接民主制を採択しました。 翌年、シトワイアンが保護同盟を結んでいた諸勢力に要請し、ジュネーヴを包囲させました。 ジュネーヴは降伏してブルジョワが亡命し、フランスへ逃げた者はフランス革命に関与しました。 1798年には、ナポレオン・ボナパルトによりフランスに併合されました。 その後、ウィーン会議において、スイス連邦に加わりました。 このころからジュネーヴは、スイスの歴史において国際金融市場の司令塔であり続けました。 第一次世界大戦と第二次世界大戦中はスイスは中立国だったため、両陣営の外交官や亡命者が集まりました。 1960年代にファンド・オブ・ファンズのバーニー・コーンフェルドが、国際投資信託=Investors Overseas Services の本部をジュネーヴに置きました。 2017年の調査によると、世界20位の金融センターであり、スイスではチューリッヒに次ぐ2位です。 本書は結果的には、文庫本にしては珍しいほど、著しく内容が凝縮された通史となっています。 全体を通じて、重要な歴史事象の制度史的背景が立体的に叙述されています。 第二編から第三編には、カルヴァン指導下で宗教改革か導入された16世紀、啓蒙思想家ルソーとヴォルテー・ルが活躍した18世紀、赤十字運動を立ち上げたアッリー・デュナンを輩出した19世紀が記述されています。 そして、多数の国際諸機関か設置された20世紀について叙述されています。 ジュネーヴは、1848年に成立したスイス連邦よりも歴史か古く、不羈独立の共和国であることを衿持としてきました。 しかし、ジュネーヴ史はこれら4つの時代に尽きるものではありません。 なお、第二版までの本書は第三編第二章で終わっていましたが、第三版以後は終章部分か加筆されています。 ジュネーヴ気質について、コスモポリタン的な文化の下ではありながら、綿々と続いてきているのは、地元にこだわり、際立って用心深い気風であると述べています。 ここには普遍的な思想を志向する哲学者、高遠な信条を奉ずる人道主義者、新しい事に熱狂する上流社会人がいます。 その他方、冷静沈着な旧市民、そして、愛郷のジュネーヴ中心主義者もいます。 ジュネーヴ気質とは、とっつきにくく、不愛想であり邪樫です。 なお、この部分の出自は、1929年の文筆家ロベータ・ドートラ著「ジュネーヴ精神」に由来しているといいます。緒論 ジュネーヴ、その起源から司教都市成立まで/第一編 司教領としてのジュネーヴ(第一章 司教都市、封建体制、コミューンの形成/第二章 中世ジュネーヴの最盛期/第三章 政治的独立を目指すコミューンの闘いと司教領の終焉)/第二編 ジュネーヴ、プロテスタント共和国(第一章 プロテスタント共和国の出現とジュネーヴにおける諸制度の再編成/第二章 十七世紀のジュネーヴ/第三章 啓蒙主義時代のジュネーヴ)/第三編 スイスの一カントンそして国際都市としてのジュネーヴ(第一章 スイスの一カントンとしてのジュネーヴ/第二章 国際都市ジュネーヴ/終 章 ジュネーヴ伝説とジュネーヴ精神)/訳者あとがき/参考文献[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]ジュネーヴ史 文庫クセジュ / アルフレッド・デュフール 【新書】【中古】 スイス チューリッヒ・グリンデルワルト・ベルン・ツェルマット・ジュネーヴ ワールドガイドヨーロッパ8/JTBパブリッシング 【中古】afb
2021.12.25
コメント(0)
-

チキンラーメンの女房 実録 安藤仁子(感想)
安藤仁子=あんどうまさこは、日本の実業家にして日清食品創業者である安藤百福の3人目の妻です。 百福と結婚後、夫の投獄、事業の失敗、財産喪失など、度重なる不運を乗り越えて、世紀の発明と呼ばれるインスタントラーメン「チキンラーメン」が完成するまで夫を支え、その生涯を共に生き続けました。 ”チキンラーメンの女房 実録 安藤仁子”(2018年9月 中央公論新社刊 安藤百福発明記念館編)を読みました。 激動の時代に何度失敗しても諦めずに復活を果たしてきた、波乱万丈の日清食品創業者・安藤百福の妻として、夫をひたすら支えた仁子の生涯を紹介しています。 その人生は、2018年10月から2019年3月まで放送された第99作目のNHK連続テレビ小説「まんぷく」の主人公の1人、立花福子のモデルとなりました。 「まんぷく」は2017年11月14日に制作発表が行われ、インスタントラーメンを生み出した日清食品、現在の法人格としては日清食品ホールディングス創業者の安藤百福と、その妻・仁子の半生をモデルに、懸命に生き抜いた夫婦の物語でした。 主人公・仁子に関した公開資料はほぼなかったため、このドラマのために初めて親族や友人などにインタビューし、生前の手帳や日記を元に資料が作成され、登場人物や団体名を変えてフィクションとしました。 安藤百福発明記念館は大阪池田と横浜にあり、大阪池田は安藤百福発明記念館 横浜、愛称、カップヌードルミュージアム大阪池田と呼ばれ、横浜は安藤百福発明記念館 横浜、愛称、カップヌードルミュージアムと呼ばれています。 大阪池田は1999年に、池田市に「インスタントラーメン発明記念館」としてオープンしました。 2002年にはラーメン屋「麺翁百福亭」が近隣にオープンし、2008年11月末まで営業していました。 2004年に拡張新築、展示物の拡充など改装を図り、2006年には入場者数100万人を達成しました。 2008年に第6回世界ラーメンサミットが大阪で開催されるのを記念して、正面広場に建てられた安藤百福の銅像の除幕式が行われました。 2017年に、施設の名称を「安藤百福発明記念館 大阪池田」、愛称:カップヌードルミュージアム 大阪池田に改称しました。 現在、入館料は無料で、管理・運営は日清食品ホールディングス関連団体の公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団が行っています。 チキンラーメンの開発がなされた研究所の小屋が再現され、ほかにもインスタントラーメンやカップヌードルの製法と改良の歴史が模型とともに展示されています。 世界中で発売されているインスタントラーメンのパッケージの展示もあり、有料でスープの種類や各種トッピングを自分で選択するオリジナルのカップヌードルを作るコーナーがあえいます。 横浜は広く東日本や世界に向けて安藤百福の功績を伝えるため、2番目の記念館として横浜みなとみらいに建設されました。 2010年の安藤百福の生誕100周年と、1971年の世界初のカップラーメンの発明40周年を記念して、2011年に開設されたのでした。 日清食品ホールディングス株式会社と、公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団が共同運営しています。 ミュージアムのテーマは、生涯を食の創造開発に尽くした安藤百福の精神の、クリエーティブ・シンキング=創造的思考です。 発明・発見の楽しさや、ベンチャーマインドの大切さを子供たちに伝えることを目的としています。 全館、見て、触って、作って、食べる、大人から幼児まで一緒に遊んで楽しめる体験型ミュージアムとなっています。 2012年に累計入館者数100万人を達成し、その後も、毎年100万人を超える入館者数を記録し、2019年には累計入館者数800万人を達成しました。 安藤仁子は1917年に大阪市北区富田町に生まれ、1870年生まれの父親は重信、母親は1879年生まれの須磨です。 父親は福島県二本松の神社の宮司の次男、母親は鳥取藩士の娘でした。 実家の安藤家は、福島県の二本松神社の神主を務める名門で、父親は大阪で事業に乗り出す資産家でした。 子供は三姉妹で、長女は晃江、次女は澪子、そして三女が仁子です。 仁子は1929年に小学校を卒業し、金蘭会高等女学校入学に入学しました。 この小学校時代、教会の英語塾にも通い、英語を学びました。 1931年に重信の事業が失敗し、生活を支えるため14歳で大阪電話局で交換手の見習い職員となり、1年間、高等女学校を休学しました。 一家は次姉の嫁ぎ先に転居しましたが、次姉の家も生活が苦しかったようです。 仁子は1935年に18歳で金蘭会高等女学校を卒業し、両親とともに京都市伏見区醍醐に転居しました。 家計を支えるため、得意な英語と、取得していた電話交換手の資格を活かして、都ホテル、現・ウェスティン都ホテル京都に就職し、正規の電話交換手として採用されました。 1941年に太平洋戦争が勃発し、翌年25歳のとき、父親が71歳で亡くなりました。 仁子はホテルでの働きぶりが認められ、フロント係に抜擢されました。 ここで1944年27歳のとき、大阪で事業を手掛けていた呉百福と出会い、求婚を受けました。 一度は仕事の未練から断ったものの、何度もにわたる求婚の末、仁子は好意を受け入れました。 1945年に第一次大阪大空襲で百福の工場と事務所焼失しましたが、数日後、仁子は28歳で、35歳の百福と結婚し、京都・都ホテルで挙式しました。 父方の先祖に幕末の学者の安積艮斎と歴史学者の朝河貫一がいて、このことは仁子にとって生涯の誇りでした。 大阪府吹田市千里山に新居を構えましたが、戦局悪化により、百福、須磨とともに、兵庫県上郡に疎開しました。 終戦後、1946年に、疎開先の上郡から戻り、大阪府泉大津市に転居しました。 1947年に百福が泉大津の旧造兵廠跡地で製塩事業を開始し、また、名古屋市に中華交通技術専門学院を設立しました。 製塩事業では従業員として慈善事業同然に、仕事を失った若者たちを仕事に雇い、いつしかその数は百人を超えました。 仁子は母と共に、彼らの母親代わりになって、若者たちの面倒を見ました。 月に1度は誕生会を開催し、アルコールにカラメルを混ぜ、ウイスキーに似せた酒を造って誕生日を祝いました。 若者たちからは実の親以上に慕われ、小遣いの前借や、恋人とのデートのことまで相談されたといいます。 1947年に息子の宏基が誕生し、仁子は宏基の出産後の肥立ちが悪かったのですが、百福が研究の一環で材料とした食用ガエルの肉片を食べることで健康を取り戻しました。 これが栄養食品であるビセイクルの開発のヒントの一つとなりました。 1948年に、百福が泉大津市汐見町に中公総社を設立し、同時に、国民栄養科学研究所を設立し、栄養食品の開発に当たりました。 同年、百福が脱税容疑でGHQに逮捕され、巣鴨プリズンに収監され、財産没収となったため、1949年に家族は、大阪府池田市呉服町の借家に転居しました。 仁子の母の隠し金で生活しながら、巣鴨プリズンに通い百福と面会しました。 百福は処分取消を求めて提訴し、税務当局は司法取引を持ちかけましたが、百福は応じませんでした。 仁子は訴訟を取り下げるように頼みましたが、夫は頑なに応じませんでした。 収監から2年後、仁子が子供たちを連れて面会に来て、百福はその姿を見て潮時と思い、1950年に訴訟を取り下げて釈放されました。 同年、百福が中公総社をサンシー殖産に商号変更し、休眠状態を経て、後に、日清食品として引き継がれました。 1951年に百福は信用組合の理事長に就任し、仁子は西国三十三観音霊場の巡礼を開始しました。 1957年に、百福が理事長をしていた信用組合が倒産し、再び全財産没収され無一文になり、池田市呉服町の自宅でチキンラーメンの開発に着手しました。 百福が何度も麺の製造に失敗する一方で、仁子はその失敗した麺をブタの餌として販売することで、陰ながら百福を支えました。 百福はスープを完成させた後、即席麺の開発に取り掛かりましたが失敗が続きました。 しかし、仁子が、高野豆腐なら水を吸ってすぐ柔らかくなるのに、と何気なく言ったことがヒントとなり、麺に小さな穴を開ける方法を発案しました。 さらに、ある日の夕食に仁子が天ぷらを揚げているのを見て、天ぷらの表面のわずかな穴を見て、麺を油で揚げて乾燥させる瞬間油熱乾燥法を発見し、世界初の即席麺チキンラーメンを完成しました。 家族総出で製造、出荷作業を手伝い、仁子はスープ作りを担当しました。 試作品を受け取ったアメリカからは、500ケースの注文が来ましたので、仁子たち家族総出でラーメンを作りました。 その後、大阪市東淀川区田川通りに借りた倉庫を工場に改装し生産を開始しました。 大阪市中央卸売市場でチキンラーメンを一食35円で発売して爆発的にヒットし、会社の商号をサンシー殖産から日清食品に変更し、本社を東区、現・中央区に置きました。 1966年に百福が初めて海外視察し、カップヌードルのヒントを手に入れました。 1967年のアメリカ出張の帰り、飛行機の客室乗務員からもらったマカデミアナッツの容器を持ち帰り、仁子が大切に保管していました。 そのアルミ蒸着したフタが、のちにカップヌードル容器に採用されました。 呉服町の借家を出て、池田市満寿美町に転居し、1968年に母親が89歳で亡くなりました。 1971年に、百福は世界初のカップ麺カップヌードルの開発に成功し、発売を一食100円で開始しましたが、値段が高いなどの理由であまり売れませんでした。 しかし、1972年に起きた連合赤軍の浅間山荘事件の際、カップヌードルを食べる機動隊員の映像がテレビで全国中継され、これがきっかけになって売れ始めました。 1985年に息子の宏基が社長を継ぎましたが、百福と宏基は経営方針が違いから対立が多く、仁子が巻き添えとなりました。 その後、百福は娘の明美から電話で諭され、仁子に謝罪したそうです。 また宏基が仁子を思い、父の話を聞き入れ、百福もそれを受け入れ、ようやく平穏が訪れたといいます。 仁子の晩年の楽しみは、信仰の人生の集大成といえる四国八十八箇所の巡礼と、日清食品の工場に祀った観音菩薩への日々の参拝でした。 百福が目を患うと、目に効く寺を見つけては、必ず立ち寄って参拝しました。 2003年86歳のとき、石田家の、石田ゆり、いしだあゆみ、石田治子らをモデルにした、NHK朝の連続テレビ小説「てるてる家族」が放送されました。 石田家の実家は喫茶店で、仁子がよく小学校時代の子供を連れて、その店に行っていたという数奇な縁があったことから、放送では、インスタントラーメン発明の物語も放送されました。 2005年に、百福が夢をかけて開発した宇宙食ラーメンを乗せたスペースシャトルの打ち上げ成功し、野口聡一宇宙飛行士が宇宙ステーションで食しました。 2007年に百福が96歳で亡くなり、百福の死去から3年後の2010年に、仁子が百福を追うように92歳で亡くなりました。 仁子の少女期や戦中の困窮期の生涯はほとんど知られていませんでしたが、没後、遺品として寝室から1冊の手帳が発見されました。 そこに記された少女時代の思い出を土台に取材を加え、百福との結婚後のエピソード群と共に、仁子の波乱万丈の生涯をまとめ、評伝が2018年に発行されました。序章 観音さまの仁子さん/第一章 家族~両親と三人姉妹/第二章 幼少期~女学校時代の苦しい日々/第三章 百福との出会い~戦火の中で結婚式/第四章 若き日の百福~実業家への挑戦/第五章 戦火避け疎開~混乱の時代を生きのびる//第六章 解放された日々~若者集め塩作り/第七章 巣鴨に収監~無実をかけた闘い/第八章 一難去ってまた一難~仁子、巡礼の旅/第九章 即席麺の開発~仁子の天ぷらがヒント/第十章 魔法のラーメン~家族総出で製品作り/第十一章 鬼の仁子~厳しい子育て/第十二章 米国視察~カップ麺のヒントつかむ/第十三章 仁子の愛~鬼から慈母へ/第十四章 四国巡礼の旅~百福最後の大失敗/終章 ひ孫と遊ぶ~百福少年に帰る/安藤仁子の年譜/参考文献[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 チキンラーメンの女房 実録 安藤仁子 / 安藤百福発明記念館 / 中央公論新社 [単行本]【宅配便出荷】【中古】 安藤百福とその妻仁子 インスタントラーメンを生んだ夫妻の物語 中経の文庫/青山誠(著者) 【中古】afb
2021.12.18
コメント(0)
-

シルクロード 流沙に消えた西域三十六か国(感想)
シルクロードは東洋と西洋を繋ぐ歴史的な交易路であり、紀元前2世紀から18世紀の間、経済、文化、政治、宗教において互いの社会に影響を及ぼしあいました。 ”シルクロード 流沙に消えた西域三十六か国”(2021年5月 新潮社刊 中村 清次著)を読みました。 中国からタリム盆地周縁のオアシス都市を経由しパミールを経て西アジアと結ぶ、いまなお多くの謎が眠る絹の道シルクロードへの西域三十六か国の旅を案内しています。 2014年に、中国・カザフスタン・キルギスタンに残る33か所の関連遺跡や寺院などが、「シルクロード」の名で世界遺産(文化遺産)に登録されました。 シルクロードの概念は一義的ではなく、広義にはユーラシア大陸を通る東西の交通路の総称であり、具体的には北方の草原地帯のルートである草原の道、中央の乾燥地帯のルートであるオアシスの道、インド南端を通る海の道の3つのルートをいいます。 狭義には最も古くから利用されたオアシスの道を指してシルクロードといいます。 オアシスの道は中国からローマへは絹、アルタイ山脈から中国へは金が重要な交易品となっていたことから、このルートは「絹の道」あるいは「黄金の道」と呼ばれており、のちに草原の道や海の道が開けるまでは最も合理的な東西の交易路でした。 シルクロード貿易は、中国、韓国、日本、インド亜大陸、イラン、ヨーロッパ、アフリカの角、アラビアにおいて、それぞれの文明において長距離の政治・経済的関係を築くことで、文明発展に重要な役割を果たしました。 主要交易品は中国から輸出されたシルクですが、ほかにも宗教、特に仏教、シンクレティズム哲学、科学、紙や火薬のような技術など、多くの商品やアイデアが交換されました。 シルクロードは経済的貿易に加えて、そのルートに沿った文明間の文化的交易道でもありました。 中村清次さんは1939年東京都生まれ、1962年に東京大学文学部西洋史学科を卒業し。NHKに入局後、編成、番組制作を経て、1979~1981年の「NHK特集シルクロード」取材班団長を務めました。 当時この特集番組は大きな反響を呼び、芸術祭優秀賞、菊池寛賞など数々の賞を受賞しました。 2010年春まで福山大学客員教授、聖心女子大学非常勤講師を勤め、現在はNHK文化センターにてシルクロード講座の講師を務めています。 著者は週1回のラジオ30分番組「カルチャーラジオ」の6か月分のテキスト「シルクロード10の謎」を書いていますし、NHK退職後の仕事として、大学講師とカルチヤセンター教室講師とを合わせ、20年間シルクロードを研究しています。 また、人生百年時代と言われる今、80歳になったら、さらにシルクロードと仏教の研究に没頭してみようと思っていたそうです。 気が付いて我に返ったら100歳、出来るならそんな生き方で終わりたいといいます。 シルクロードという名称は、19世紀にドイツの地理学者リヒトホーフェンが、その著書においてザイデンシュトラーセン(ドイツ語:絹の道)として使用したのが最初です。 古来中国で西域と呼ばれていた東トルキスタンを東西に横断する交易路、いわゆるオアシスの道=オアシスロードを経由するルートを指してシルクロードと呼びました。 リヒトホーフェンの弟子で、1900年に楼蘭の遺跡を発見したスウェーデンの地理学者ヘディンが、自らの中央アジア旅行記の書名の一つとして用い、これが1938年に英訳されて広く知られるようになりました。 シルクロードの中国側起点は長安、欧州側起点はシリアのアンティオキアとする説がありますが、ほかにも、中国側は洛陽、欧州側はローマと見る説などもあります。 日本がシルクロードの東端だったとするような考え方もありますが、特定の国家や組織が設定したわけではないため、そもそもどこが起点などと明確に定められる性質のものではありません。 中国から北上して、モンゴルやカザフスタンの草原を通り、アラル海やカスピ海の北側から黒海に至る、最も古いとみなされている交易路です。 この地に住むスキタイや匈奴、突厥といった多くの遊牧民が、東西の文化交流の役割をも担いました。 東トルキスタンを横切って東西を結ぶ隊商路はオアシスの道と呼ばれ、このルートをリヒトホーフェンがシルクロードと名づけました。 長安を発って、今日の蘭州市のあたりで黄河を渡り、河西回廊を経て敦煌に至ります。 ここから先の主要なルートは次の3本で、西トルキスタン以西は多数のルートに分岐しています。 このルート上に住んでいたソグド人が、唐の時代のおよそ7世紀~10世紀頃シルクロード交易を支配していたといわれています。 西域南道は、敦煌からホータン、ヤルカンドなどタクラマカン砂漠南縁のオアシスを辿ってパミール高原に達するルートで、漠南路とも呼ばれます。 オアシスの道の中では最も古く、紀元前2世紀頃の前漢の時代には確立していたとされます。 このルートは、敦煌を出てからロプノールの北側を通り、楼蘭を経由して砂漠の南縁に下る方法と、当初からロプノールの南側、アルチン山脈の北麓に沿って進む方法とがありました。 4世紀頃にロプノールが干上がって楼蘭が衰退すると、水の補給などができなくなり、前者のルートは往来が困難になりました。 距離的には最短であるにもかかわらず、極めて危険で過酷なルートですが、7世紀に玄奘三蔵はインドからの帰途このルートを通っており、前者のルートも全く通行できない状態ではなかったものとみられます。 13世紀に元の都を訪れたマルコ・ポーロは、カシュガルから後者のルートを辿って敦煌に達したとされています。 現在のG315国道は部分的にほぼこの道に沿って建設されており、カシュガルからホータンまでは、2011年に喀和線が開通しています。 天山南路=西域北道は、敦煌からコルラ、クチャを経て、天山山脈の南麓に沿ってカシュガルからパミール高原に至るルートで、漠北路ともいいます。 西域南道とほぼ同じ頃までさかのぼり、最も重要な隊商路として使用されていました。 このルートは、楼蘭を経由してコルラに出る方法と、敦煌または少し手前の安西からいったん北上し、ハミから西進してトルファンを通り、コルラに出る方法とがありましたが、楼蘭が衰退して水が得られなくなると、前者は通行が困難になりました。 現在のトルファンとカシュガルを結んでいる南疆線は、概ね後者のルートに沿って敷設されており、1971年に工事が始まり、1999年に開通しました。 G314国道も部分的にほぼこの道に沿っています。 天山北路は敦煌または少し手前の安西から北上し、ハミまたはトルファンで天山南路と分かれてウルムチを通り、天山山脈の北麓沿いにイリ川流域を経てサマルカンドに至るルートです。 紀元後に開かれたといわれ、砂漠を行くふたつのルートに比べれば、水や食料の調達が容易であり、平均標高5000mとされるパミール高原を越える必要もありません。 現在のG312国道や蘭新線、北疆線は、部分的にほぼこの道に沿っています。 広大な中国の西端に、かつての「西域」、現在の新疆ウイグル自治区があり、その自治区の東端に、シルクロード史上、極めて重要な湖、ロプノールがあります。 19世紀の半ば頃から、ロシア、スウェーデン、イギリス、フランス、日本と、それぞれ目的は様々でしたが、各国が中央アジアヘ探検隊を送り出し、現地の情報を集め貴重な文化財を獲得していきました。 そうした中、20世紀の初め、スウェーデンの探検家スウェン・ヘディンが、ロプノールは1600年を周期に、砂漠の中を北から南へ、南から北へと移動するさまよえる湖だと発表しました。 その上で、今、湖に水はないが、もうすぐ水は戻ってくると予言しました。 そして1934年、ヘディンは、水の戻った湖にカヌーで漕ぎ出し、予言は的中したと発表しました。 この摩詞不思議なロプノール=さまよえる湖説は、今に至るまで、世界中のシルクロード・フアンの心を捉えて離さない物語の一つです。 そのロプノールについて、著者たちのシルクロード取材班は、取材の過程で、ある事実を知り驚愕したといいます。 当時、日本にある殆どの世界地図に記されたロプノールは、いずれも、実線で明確に形取られ、その湖面はあたかも満々と水を湛えているかのように、青々と彩られていました。 恐らく、スウェン・ヘディンの湖に水は戻ったという発言以来、地図製作者たちは、あと数百年は、湖水がここに止まると確信したのでしょう。 しかし、ヘディンの発表から45年後の1979年、取材を重ねていく中で動かしがたい確かな証拠により、湖面の何処にも水がないという事実を突き付けられました。 当時、アメリカ航空宇宙局の地球観測衛星ランドサットに衛星写真を依頼しましたが、その結果、間違いなく当時のロプノールにはどこにも水がないことがわかったのです。 実は1935年から中国政府は、文物の海外流出を防ぐため、という理由で、外国人への門戸を閉じてしまいました。 これによって、19世紀半ばから始まった、中央アジア探検家時代は幕を閉じて、以来、年を重ねるごとに、中国内シルクロードは、地上最後の秘境としての度合いを深めていきました。 「NHK特集 シルクロード」の番組制作のため、著者たちは1979年から取材を始めました。 番組は日中共同制作で、NHKとCCTVとの共同取材班でした。 訪れた地では、日本チームは何処へ行っても44年振り、或いは45年振りの外国人と呼ばれたといいます。 中国内シルクロードは、かつて「西域36か国」と呼ばれたエリアですが、それまで40数年にわたり、外国人への門戸が閉ざされていた地であり、まさに撮影するも特ダネでした。 忘れてはならないのは、番組放送を契機に中国で始まった、シルクロード分野における研究の飛躍的な発展です。 中国歴史書を中心とした従来の文献学に、考古学、言語学、人類学、仏教美術史、宗教学、更には考古学調査に必要な自然科学の分野も加わり、各学術分野の総合研究が始まりました。 しかし、いくら研究が進んできたといっても、シルクロードの範囲は広大です。 本書で取り上げるのは、東は黄河に臨む蘭州から、巨大な砂漠・タクラマカンを挟んで、西は世界の屋根といわれるパミール高原まで、の西域36か国とその周辺に限りたいということです。 シルクロードを通した、日本と中国・西域との関わりが、思いのほか深いことを示すものが幾つもあります。 まず、4世紀半ばにオアシス国家・亀茲王国に生まれた鳩摩羅什は、長安で、「金剛般若経」「法華経」「阿弥陀経」「坐禅三昧経」など約300巻に及ぶ経典を漢訳しました。 日本人は、鳩摩羅什が訳したその経典を今も読んでおり、古代シルクロードは奈良・飛鳥の法隆寺金堂の壁画や仏像などの源流を思わせる大地です。 東大寺大仏へとつながる大仏の来た道でもあり、仏教東伝の道を象徴するかのような、我が国との深い関わりを示しています。 竪笙換(ハープ)、五弦琵琶、四弦琵琶、排蕭、事築、笙、腰鼓、鶏鼓などの楽器は、いずれもシルクロードの全盛期に唐の玄宗皇帝が最も愛した亀茲楽の主役だった楽器です。 わが国でも正倉院に宝物として収蔵されていたり、今なお雅楽としてお馴染みの、優雅な音色を奏でる楽器として実際に使用されています。 他にも正倉院の宝物には、シルクロード由来の物が幾つもあり、日本がシルクロードの東端とも言われる由縁となっています。 現地を取材した際にも感じたことだそうですが、シルクロードを旅するツアーの講師として現地をご一緒した際に多くの方々が口にしたのが、不思議なことに懐かしいという言葉であったといいます。 それは日本文化の源流が飛鳥・天平文化にあり、そのさらに源流が中国にあり、特に西域だったからではないでしょうか。 トインビーが、そこで生活したいと憧れるまでに、西域の国々が繁栄したのはなぜでしょうか。そしてそれにも拘わらず、なぜ、そうした幾多の王国が、流沙の中に埋もれていってしまったのでしょうか。 これから皆さんと一緒に、シルクロードを旅するように、その遥かなる歴史の謎を一つ一つ解きあかしていきたいといいます。序章 遥かなるシルクロード/第一章 「楼蘭の美女」は、どこから来たのか/第二章 「さまよえる湖」が、もうさまよわない理由/第三章 「タクラマカン」は謎の巨大王国なのか?/第四章 絹と玉の都、ホータン王国の幻の城/第五章 建国の夢が滅びの始まり-ソグド人の悲劇/第六章 奪われた王女-亀茲王、烏孫王女を帰さずに妻とする/第七章 玉を運んで四千キロ-謎の民族・月氏の正体/第八章 楼蘭・?善王国の消えた財宝-天下一の大金持ち王の末路/第九章 仮面をつけた巨人のミイラの謎/第十章 幻の王族画家が描いた「西域のモナ・リザ」/終章 シルクロードはなぜ閉じられたのか-捨てられた敦煌/おわりに [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]シルクロード 流沙に消えた西域三十六か国 新潮新書 / 中村清次 【新書】【中古】 私の西域紀行 上 / 井上 靖 / 文藝春秋 [文庫]【宅配便出荷】
2021.12.11
コメント(0)
-

2035年「ガソリン車」消滅(感想)
自動車業界の動きが目まぐるしく、100年に一度の大変革の波がうねっています。 ”2035年「ガソリン車」消滅”(2021年6月 青春出版社刊 安井 孝之著)を読みました。 製造業における環境問題に対する活動の一つであるカーボンニュートラルに関連して、日本政府が打ち出した2035年ガソリン車の新車販売禁止について、日本の自動車産業の動向を中心に今後の業界の展望を行っています。 19世紀末にドイツでガソリン車が発明され、20世紀に自動車産業は大きく成長しました。 ガソリン車の誕生から100年以上たった今、運転手なしでもクルマが走る自動運転やCO2排出量をゼロにする電動化の開発競争が、業界を大きく揺さぶっています。 その大変革には欧米や中国の自動車メーカー、米国の巨大なIT企業も参入し、かつてない競争が進行中です。 生きるか死ぬかという言葉が、自動車メーカーの経営者の口から飛び出すほどの危機感も漂います。 そこに地球温暖化をストップさせようとする世界的な脱炭素への動きが加わり、自動車業界の競争をさらにヒートアップさせました。 日本政府も2020年秋に、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を宣言しました。 安井孝之さんは1957年兵庫県生まれ、稲田大学理工学部を卒業し、東京工業大学大学院を修了しました。 日経ビジネス記者を経て、1988年に朝日新聞社に入社し、東京経済部・大阪経済部の記者として、自動車、流通、不動産、財政、金融、産業政策などをおもに取材しました。 東京経済部次長を経て、2005年編集委員となり、2017年に退職し、現在、Gemba Lab代表、ジャーナリストで、東洋大学非常勤講師を務めています。 カーボンニュートラルは環境化学の用語の一つであり、製造業における環境問題に対する活動の用語の一つでもあります。 日本語では炭素中立と言い、何かを生産したり一連の人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量にする、という目標です。 カーボンニュートラルな植物利用と炭素量変化の流れを、持続的に繰り返すのがカーボンニュートラルです。 植物の茎・葉・根などは全て有機化合物で出来ています。 その植物が種から成長するとき、光合成により大気中の二酸化炭素の炭素原子を取り込んで有機化合物を作り、植物のからだを作ります。 そのため植物を燃やして二酸化炭素を発生させても、空気中に排出される二酸化炭素の中の炭素原子は、もともと空気中に存在した炭素原子を植物が取り込んだものです、 そのため、大気中の二酸化炭素総量の増減には影響を与えないため、二酸化炭素=炭素循環量に対して中立である言われます。 現在、地球温暖化の進行とそれによる諸影響が問題となっています。 地球温暖化の主な原因の一つとして大気中の二酸化炭素の濃度が上昇していることが挙げられ、二酸化炭素の濃度の上昇を抑えることで地球温暖化の進行を抑えようとする動きがあります。 この動きの中でカーボンニュートラルという概念が頻繁に登場するようになりました。 そして、人間活動で排出する温室効果ガスの量よりも、植物や海などが吸収する温室効果ガスの量の方が多い状態をカーボンネガティブと言います。 また、人間が何らかの一連の活動を通して温室効果ガス、特に二酸化炭素を削減した際、排出される量より多く吸収することをカーボンポジティブと言います。 戦後のエネルギー革命により石油、ガスの普及に伴う炭の需要減で山林が荒廃しました。 しかし今では、薪ストーブは暖炉とともにカーボンニュートラルの観点からも見直されています。 近年、カーボンニュートラルに近い植物由来のバイオマスエタノールなどが使われたり、持続可能性を考慮したうえで薪・枯れ草・木質ペレットなど植物由来燃料の利用が行われたりしています。 また廃棄後に焼却されて二酸化炭素を排出する一方で、吸収はほとんどない石油由来のプラスチックの代替として、トウモロコシなどを原料とするバイオプラスチックが製造されています。 2007年4月に、ノルウェーのイェンス・ストルテンベルク首相は、カーボンニュートラルを2050年までに国家レベルで実現する政策目標を打ち出しました。 国家レベルでこのような政策が決定されたのは初めての例だとされています。 また、同年12月、コスタリカのオスカル・アリアス・サンチェス大統領は、2021年までに国家レベルのカーボンニュートラルを実現する目標を発表しました。 海外においては、Nike、Google、Yahoo!、Marks & Spencer、香港上海銀行、Dellなど大手企業が、自社のカーボンニュートラル化宣言を行い、温室効果ガス削減に取り組んでいます。 日本においても、グリーン電力証書を活用した企業の温室効果ガス削減が行われています。 しかし、グリーン電力証書については、追加性の要素が不足しているとの声もあり、環境省で取り扱い方針を検討中です。 さらに、2020年10月に菅総理が所信表明演説で、2050年にカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すと宣言しました。 この宣言によって、自動車業界はカーボンニュートラル化に必要なこととして、車の使用時でのCO2排水を抑えるだけでなく、製造の段階で発生するCO2を抑え、自動車の電動化を計画しています。 それを受けて2035年に純粋なガソリン車の新車販売を禁止することが決まりました。 それ以降は国内で、HV(ハイブリッド車)やEV(電気自動車)、FCV(燃料電池車)などしか売ることはできず、新車販売市場からガソリン車は姿を消します。 世界的な脱炭素、電動化の流れの中でクルマはどう変わっていくのでしょうか、 また、テスラ、グーグル、アップル、中国企業が続々と市場参入してくる中で、日本のメーカーは競争力を維持できるでのしょうか。 日本経済を支える大きな柱である自動車産業は、今後20~30年の間、大きな変革期を迎え、事業構造を一新させなければなりません。 自動車産業に関わる550万人といわれる人たちへの影響は計り知れず、その変化は自動車産業にとどまりません。 カーボンニュートラルは私たちの生活全般を見直し、人類が200年にわたって燃やし続けた化石燃料を使わない暮らしの実現を意味します。 すべての産業と私たちの生活を大きく変える、21世紀の産業革命が起きようとしています。 ガソリン車の消滅はそのひとコマではありますが、とても重要なひとコマです。 人やモノを移動するモビリテイは、インターネットがいくら発展しても人類のリアルな生活にはなくてはならない存在です。 大変革には痛みを伴いますが、今始まったカーボンニュートラルヘの挑戦は、地球温暖化をストップし、私たちの生活のグリーン化を目指しています。 また同時に進行するクルマの自動運転は、交通事故死ゼロと高齢になっても自由にどこでも移動できる社会を実現するポテンシャルを持っています。 そんなワクワクする理想の未来への新しいカーレースが始まったのです。 2050カーボンニュートラルと自動車の電動化問題は、2020年末に降ってわくように現れました。 ですが前向きにとらえれば、自動車産業がこれまで抱えてきた二つの原罪(環境負荷と交通事故)を、100年ぶりに克服できるチャンスが到来したとみることができます。 また、今後30年にわたり再エネ発電を誘致できる地方の活性化策にもなります。 日本には技術蓄積が少ない風力発電の部品製造や組み立て・建設といった、新しい産業を生み出す力も秘めています。 自動車産業が失う雇用も少なくはないでしょうが、今後30年の間に生まれる新産業を雇用の受け皿とし、痛みを最小化する努力を続けるしかありません。 ガソリン車が消滅する日は、理想の姿へのマイルストーンであり、グリーン経済へと日本が進化するチャンスととらえたいとのことです。 2021年4月にオンラインで聞かれた気候変動サミットで、バイデン大統領は温室効果ガスを2030年までに、2005年比で50~52%削減すると表明しました。 菅首相も従来の目標値を見直し、2030年までに2013年比で46%削減すると踏み込みました。 ホンダの三部敏弘社長は、2040年までに世界で売るすべての自動車をEVとFCVにすると宣言しました。 日本メーカーが得意なガソリン車やハイブリッド車から手を引き、完全な電動化へと大きく舵を切りました。 期限を切って、完全な電動化を表明したのはホンダが初めてです。 一方、日本自動車工業会の会長でもあるトヨタ自動車の豊田章男社長は、自工会の会見で、合成燃料を普及させればガソリン車やハイブリッド車もカーボンニュートラル実現後も走ることができると、EV化一辺倒の動きに改めて釘を刺しました。 カーボンニュートラルをゴールにしたカーレースは始まったばかりで、ゴールまで目が離せない状況が続きます。 画期的なイノベーションが起きれば局面が大転換することもありますが、重要なのは私たちが目指しているのは産業や生活をグリーン化し、持続可能な地球に戻すという理想の未来という点です。 本書では、現在進行中のカーレースの現状と課題を紹介するとともに、2050年のカーボッニュートラルのゴールに向けてどのように歩んでいけるのか、どんな道がより望ましいかを考え、指し示します。 また、私たちの生活がどのように変わるのかもわかりやすく説明しています。 自動車の電動化についてEV派対反EV派といった極端な二項対立で論じる向きがありますが、この本では丁寧に論述することに注力したそうです。 新聞やテレビなどの日々の報道だけでは、自動車産業の電動化やカーボンニュートラルの本質を知ることは難しいです。 それは断片的な内容が多いからであり、本書を書くにあたって、目の前で起きている事実を大づかみに理解することを目指しました。 自動車産業の未来と私たちの暮らしの行く末の正しい姿を知りたいと思う人たちの一助にこの本がなってくれれば幸いといいます。はじめに/第1章 ガソリン車の寿命は、あと10余年?「2035年、100%電動化」の衝撃/第2章 ハイブリッド車(HV)・電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)/第3章 一歩先行く中国、米国、欧州…グーグル、アップルも参戦 EV化で後れをとる日本メーカーの秘策は?/第4章 モビリティ革命で生活・仕事が一変!電動化がもたらす、人とクルマと街の新しい関係/第5章 ガソリン車消滅は日本にとって新たなチャンス!?真の「グリーンモビリティ社会」への道/おわりに[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 2035年「ガソリン車」消滅 青春新書インテリジェンス/安井孝之(著者) 【中古】afb脱炭素サバイバル 週刊東洋経済eビジネス新書No.374【電子書籍】
2021.12.04
コメント(0)
-

職業としてのシネマ(感想)
製作された映画著作物、つまり上映興行権すなわち著作権を有するネガフィルムをプリントに複製し,これを上映興行するために興行社である映画館に一定期間貸し出すことを配給といいます。 ”職業としてのシネマ”(2021年5月 集英社刊 髙野 てるみ著)を読みました。 1980年代以降、数々の配給作品のヒットでミニシアター・ブームをつくりあげた立役者の一人である著者が、配給、バイヤー、宣伝等、現場におけるエピソードを交え、仕事の難しさ、面白さ、やりがいを伝えています。 配給業者と興行者との間に上映料の契約が結ばれますが,その値段は作品の興行価値や劇場の等級、すなわち,そのキャパシティや設備や入場料や所在地域,そして上映期日や上映期間などによって決定されます。 映画配給は外国の映画の日本国内での上映権利を買いつけ、買いつけた後、上映する映画館を決め、宣伝する仕事です。 外国の映画会社との交渉になりますので、外国語の能力が問われる場合もあります。 一人前になると、カンヌやベニスなど、華やかな映画祭に参加することもあります。 キャリアの形成は配給会社に入ってキャリアをスタートするのが一般的ですが、経験を積んだ後に自分で会社を起こしたり、フリーで活躍する人もいます。 現在のインディペンデント系の配給会社は、個人単位で始められたものが多いですが、独立には相当な知識と経験が必要です。 本書は業界で働きたい人のための映画業界入門書である一方、ミニシアター・ブーム時代の舞台裏が余すところなく明かされていて興味深い。 髙野てるみさんは1948年東京生まれの映画プロデューサー、エデイトリアル・プロデユーサー、シネマ・エッセイストです。 美大卒業後、新聞記者を経てフリーライターになり、女性誌を中心に活動し、エディターとしても関わりました。 ファッション、音楽、映画を主軸に、各ジャンルで活躍中のオピニオン・リーダーのインタビューを得意としてきました。 1985年に広告や雑誌の企画制作をする株式会社ティー・ピーオーを設立しました。 大手企業PR誌、企業記事体広告などを中心に、宣伝業務、CF 制作、イベント,講演、セミナーの企画・制作と、幅広く活動してきました。 1987年にフランス映画を中心としたヨーロッパ映画の輸入配給会社、巴里映画を設立しました。 カンヌ映画祭などで話題となった映画作品を買いつけ、話題作りをして世に出す仕事を進めてきました。 これまでに、「テレーズ」「ギャルソン!」「サム・サフィ」「ミルクのお値段」「パリ猫ディノの夜」などフランス映画を中心に配給・製作を手がけてきました。 ミニシアター系映画興行の新たなマーケットを開拓し、その後もアート作品や文化度の高い作品を世に送り出しています。 2007年4月より、文京学院大学で”アニメーション論”の特別講師も務めています。 株式会社ティー・ピーオーは、東京都千代田区に本店のある、広告・雑誌・書籍の綜合企画制作会社です。 雑誌「アンアン」「クロワッサン」「オリーブ」「とらばーゆ」「マリ・クレール」「流行通信」など、1980年代をリードしてきた多くの女性誌で、ファッション、食、旅、著名人インタビューの企画提案、制作などを行ってきました。 企業タイアップ編集企画制作や、雑誌作りのノウハウや、有名人のネットワークを活かした企業誌も企画制作しています。 また、各界で活躍中の著名人の方々の著作の企画プロデュースもし、出版・書籍の取材から執筆、編集協力も手がけています。 株式会社巴里映画は、東京都目黒区にあるフランス映画を中心としたヨ ーロッパ映画の輸入配給会社です。 日本映画の海外紹介、輸出、映画の共同製作、映画関係印刷物の企画編集、映画人の育成なども行っています。 1992年に、日仏合作作品、ヴィルジニ・テブネ監督「サム・サフィ」では、日本側のプロデューサーとなり、数多くのヒットメーキングの技を発揮しました。 新人監督作品の発掘にも注力し、ニュージーランド映画などを配給しています。 映画配給は映画産業における業務部門の一つで、単に配給と呼び、配給業務を行う企業を映画配給会社や配給会社と呼びます。 映画作品を完成させるまでが製作、エンドユーザに向けて上映業務・接客業務を行うのが興行であり、その両部門を結ぶのが映画配給です。 経済活動としてみると生産者から商品を仕入れ、小売業者に販売する卸売業にあたります。 世界各国において、その国内で製作された映画は、例外を除いて第一に国内配給が行われます。 製作者側と配給会社との間で、配給契約を結ぶことでこれが実現します。 次に、国外での配給については、製作者側が国外配給権を国内での配給会社や国外セールスを行う会社に委託する場合と、製作者側が直接セールス窓口となる場合があります。 一方、国外の作品に関して、配給会社は、自国内での配給権を買い付けて、国内での配給業務を行います。 世界各地で催される映画祭や映画見本市にバイヤーを派遣し、所望の作品を見つけて権利者と交渉します。 配給会社が買い付ける権利が、劇場公開権のほか、テレビ放映権、ビデオグラム化権といった2次・3次利用を含むオールライツである場合、配給会社が自国内のテレビ局やビデオメーカーにそれらの権利をセールスすることも可能です。 自国内に限らず、アジア、ヨーロッパ、北米といったエリアでの権利を含めて、買い付けることもあり、その場合はそれ相応の資金が必要です。 映画のセールスとは、配給会社が興行会社や個別の映画館に対して行う営業業務を指します。 通常は専門の配給会社が担当しますが、映画製作者自身が配給も手掛ける自主配給というケースもあります。 映画配給会社の仕事は大きく分けて3つあり、すでに制作されているもしくはこれから制作をする映画を買い付けること、買い付けた映画を上映する映画館を確保すること(ブッキング=営業)、映画をヒットさせるために宣伝を行うことです。 映画だけでなく、DVDや主題歌などでも収益をあげなければならないのが映画配給会社ですので、宣伝は非常に大事な仕事になります。 内容は、タイアップ、マーチャンダイジング、前売りチケットの管理、試写会やプレス試写会、完成披露記者試写会や会見、制作発表記者会見、主演男優や女優が来日したときのイベントや記者会見、舞台挨拶などなどです。 さらに、TVやラジオ、新聞や雑誌、ネットなどでの宣伝など、映画配給会社の仕事は多岐に渡っています。 著者が手がけてきたのは、映画ビジネス、洋画配給、そしてミニシアターで上映する単館系洋画配給ビジネスという仕事です。 「買い付け」た映画作品を劇場にブッキングして、観客となる皆さんに観ていただきます。 映画を配給するからには、多くの方々に知っていただく必要があり、宣伝という大仕事も手がけます。 一度でもヒットを出そうものなら、次のヒットを願って深みにハマつていくことは否めません。 ヒットとは、多くのお客さんに観に来ていただき、その作品を面白いと言ってもらうことを狙うのであって、お金持ちになるために邁進するというモチベーションとは少し違います。 お金儲けを狙うなら、これほど手がかかる面倒なことには関わらないほうがいいです。 そうして、あくまで公開される劇場がハレの場で、そこでは配給プロデューサーは不可視の存在であり、あくまで黒子です。 前作の「映画配給プロデューサーになる!」が出版されて、かなりの時間が経過しましたが、仕事内容の変化がほとんどないのには驚くばかりだそうです。 AIに取って代わられそうもない仕事かもしれません。 映画を観て楽しむ側からは、常に映画は、「キレイごと」「イイとこどり」で語られています。 大学で教えていたのは映画論であり、その素晴らしさを広く世に伝えるビジネスです。 配給の仕事については、自分から触れたことはありませんし、尋ねられもしませんでした。 世の中で映画のことが語られる場合はキレイごとであり、まずは、スターについて、カリスマ的監督について話題にのぼります。 完成した映画は、多くの人々の力の結晶で情熱の賜物。素晴らしいと感じられるように、感動できるように作られているのですから、それが観客側から観た映画というものなのですから、それで良いのです。 前もって「盛られた」宣伝によって、すでにかなり「洗脳」されて劇場へと誘われていることに気づいてもいないはずです。 だからこそ、配給という仕事、宣伝という仕事は、表立つ必要がなくていいのです。 著者は、影の存在であるところに、ささやかな誇りを感じてもいるといいます。 しかし、自分が好きな映画は、配給会社に就職しても配給できるとは限りませんので、映画が好きなら肥給の仕事はしないほうがいいといいます。 配給の仕事には宣伝の仕事がカップリングされています。 映画を買い付けてから、劇場公開までの間、ほぼこの業務は続きます。 映画文化、芸術の話を誇りをもって、映画を作った映画監督になり代わってやる仕事なのですから、売り込みに躊躇など無用です。 自社映画の宣伝の渦中ともなれば、よその映画など観ている暇もありません。 映画は観るのが一番楽しくて、送り手になるのは難しいため、映画好きほど、配給の仕事を避けたほうがよいのは、映画ファンとして好きな映画を観る時間がなくなるからです。まえがき/第1章 知られざる「配給」という仕事/第2章 配給プロデューサーは「バイヤー」でもある/第3章 配給に「宣伝」はなぜ必要かー1+1=2が不正解な仕事/第4章 「監督」は王様である/第5章 王様に逆らう「女優」と媚びない「俳優」/第6章 パンデミック時代を迎えた「映画館」/あとがきにかえて-映画は決して、なくならない[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]職業としてのシネマシネマでごちそうさま 恋と仕事と、女たち【電子書籍】[ まつかわゆま ]
2021.12.04
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1