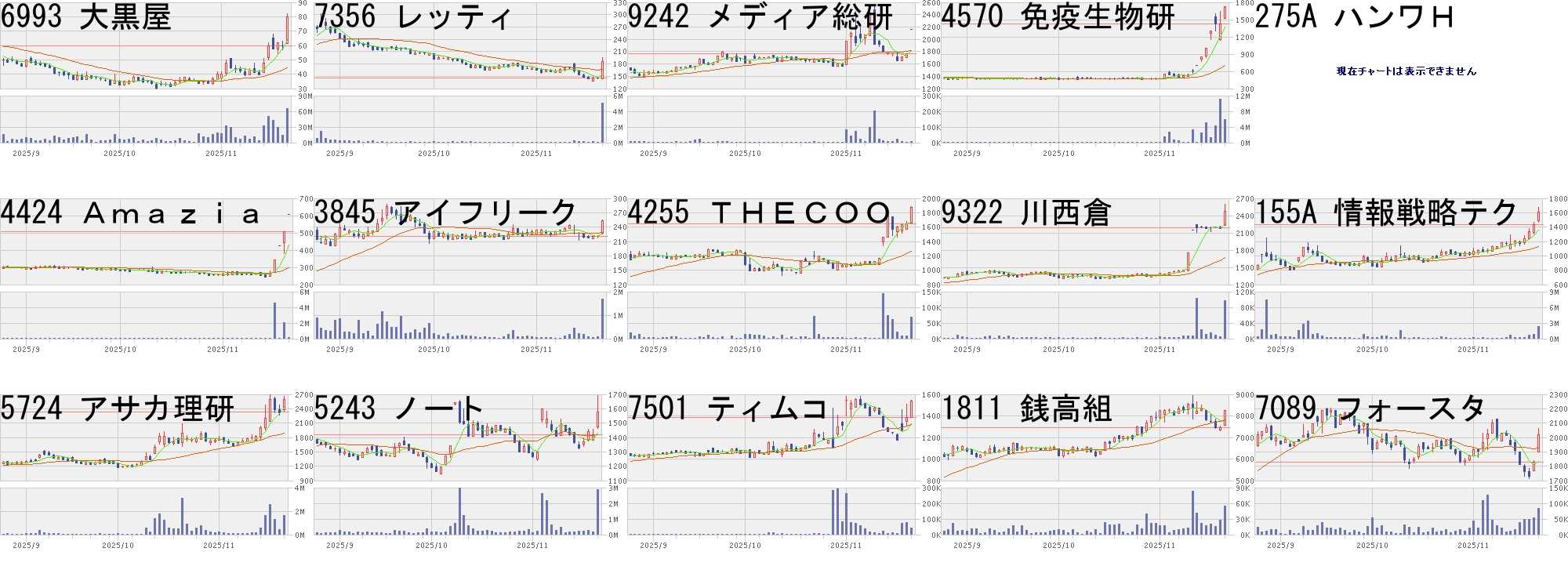2018年03月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
説教要約 1093
「キリストの復活と私たちの人生」 2018年4月1日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2017年3月14日放映「計画に現れる愛」 「キリストの復活と私たちの人生」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、1章8~11節 キリストの復活は、キリスト教の福音において最も大切で中心的なものです。しかし世の中においても、一般的な意味における復活や復興ということは、非常に重要なことではないでしょうか。それでキリストの復活および一般的な意味における復活を問わず、復活について考えてみましょう。 一、復活――それは人間本来の願望です キリストの復活はともかくとして、私たちは、一般的な意味における復活というものを切に求めているのではないでしょうか。 からだが常に健康で、若々しく、生き生きとしていることを願わない人がいるでしょうか。不老不死は人間の悲願です。科学、特に医学は、このために少しでも貢献しようとしているのであり、体育やスポーツも同じではないでしょうか。 また精神的にも生きる喜びや希望に満ちていることを願わない人がいるでしょうか。文明の発達や文化の向上は、このような心の願いの当然の結果であるということができます。 そして霊的な面において、清く正しく生きることが人の道であり、もしそこから逸脱していれば、更生しようとするのが人のあるべき姿ではないでしょうか。道徳や倫理また宗教は、このことを私たちに教えています。 このように人間は、肉体的にも精神的にもそして霊的にも、復活や復興また更生を切に求めているのです。 二、復活――それは正真正銘の事実です キリストが復活したというと、多くの人々は、「死んだ人間が生き返るはずがない」と一笑に付してしまいます。しかしルカの福音書の24章には、キリストの復活が事実であることを証明する根拠が三つ記されています。 1.第一は、死体のない墓です この箇所には、三回も墓の中には主イエスのからだが見当たらなかったことが記されています(3、23、24節)。 2.第二は、キリストの顕現です この箇所には、エマオという村へ行く途中のふたりの弟子たち(15節)とシモン・ペテロ(34節)と十一使徒(36節)にキリストが現れたことが記されています。彼らは、よみがえられたキリストを目撃した証人なのです(48節)。 3.第三は、聖書の証言です この箇所には、3回も聖書という言葉が記されており(27、32、45節)、キリストは聖書の預言の通りに死んで復活されたことを私たちに教えています。 三、復活――それは起死回生の秘訣です パウロは、アジヤで非常に大きな苦しみに遭った時、「非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ほんとうに、自分の心の中で死を覚悟しました。これは、もはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼む者となるためでした」と告白しています(第二コリント1章8、9節)。これは復活を信じる信仰です。 私たちのからだは、疲れたり、病気になったりすることがあります。しかし再び元気になったり、病気が治ったりすればよいのです。また様々な問題のために失望したり、落胆したり、挫折したりすることもあるでしょう。しかし再び立ち上がればよいのです。さらに信仰が死んだような状態になることがあるかも知れません。しかし再び生きた信仰を持てばよいのです(第二コリント4章8~11節)。 キリストは、十字架の上で死なれましたが、よみがえられた方です。聖書は、「もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです」と教えています(ローマ6章5節)。 キリストの死と復活を信じる人は、たとえ倒れても、打ちのめされても、また死んだようになっても、再び起き上がり、生き返ることができます。キリストの死と復活を信じる信仰は、私たちに起死回生の力を与え、私たちが苦しみに満ちた人生を歩んでいくために不可欠なものなのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.03.31
コメント(0)
-

説教要約 1092
「神の謙遜と人の謙遜」 2018年3月25日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年7月7日放映「神への信仰と感情」 「神の謙遜と人の謙遜」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、2章1~11節 「何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい」(3節)。 「キリストは……人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました」(6~8節)。 この前半の3節には人の謙遜について、後半の6~8節にはキリストの謙卑、すなわち神の謙遜について記されています。 一、人の謙遜について 人の謙遜について聖書は次のような三段階の謙遜を教えています。 第一段階は、身を低くする謙遜です。とかく人の世は、「出る杭は打たれる」ところです。それで人々に受け入れられるためには、「能ある鷹は爪を隠す」という謙遜なふるまいが必要になってきます。これは、自らの偉大さを自覚している謙遜です。 第二段階は、心の謙遜です。これは、「自分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であること」を認め(黙示録3章17節)、神の前に無一物で、何の良い物も持ち合わせていないことを意識することです。これは、自らの無力さを自覚している謙遜です。 第三段階は、霊の謙遜です。これは神の前に返済不能な罪という負債を背負った債務者であることを認め(マタイ一八章24、25節)、救い主の必要を意識することです。これは、自らの罪深さを自覚している謙遜で、「心(原語は霊)の貧しい者」です(同五章3節)。 二、神の謙遜について 神の謙遜について聖書は次のような三段階の謙遜を教えています。 第一段階は、人となられた謙遜です。キリストは、「神の御姿である方なのに……人間と同じようになられました」(6、7節)とは、何と驚くべきことでしょうか。 第二段階は、仕える者となられた謙遜です。さらに驚くべきことは、キリストは、人に「仕えられるためではなく」(マルコ10章45節)、かえって「ご自分を無にして、仕える者の姿をと」られたことです(7節)。 第三段階は、罪を贖う者となられた謙遜です。最も驚くべきことは、罪の奴隷である私たちを救うために、「自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負」い(第一ペテロ2章24節)罪を贖う者となられたことです。 三、救いの道について 冒頭の図は、これらのことをまとめたものです。この「V」の図において両者が接しているのは最下点のみです。キリストは、罪の奴隷となっている私たちを救うために私たちの罪をその身に負い、罪を贖うところまで降りてくださったのであり、私たちも罪を贖ってくださるキリストのところまで降りて行くなら、贖いの代価としてのキリストのいのちを受け、罪から救われることができます。 四、神の勝利と人の勝利について 神の謙遜については「この『上られた』ということばは、彼がまず地の低い所に下られた、ということでなくて、何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです」と教えています(エペソ4章9、10節)。キリストは、神の御姿である方なのに、人の姿という低い所に下られ、仕える者の姿というさらに低い所に下られ、罪を贖う者という最も低い所に下られたのです。そして贖いを信じる人に神のいのちを与えると、復活という高い所に上られ、顕現というさらに高い所に上られ、昇天という最も高い所に上られました。これが神の勝利の「V」です。 人の謙遜については、まず高慢な人が身を低くする人にまで下り、次に心の謙遜な人にまで下り、さらに霊の謙遜な人にまで下り、そこにおいて贖いの代価としての神のいのちを受けるなら、まず新しく生まれるという高い所に上り、次に罪をきよめられるというさらに高い所に上り、次に来る世において栄光のからだに変えられるという最も高い所に上ります。これが人の勝利の「V」です。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.03.24
コメント(0)
-
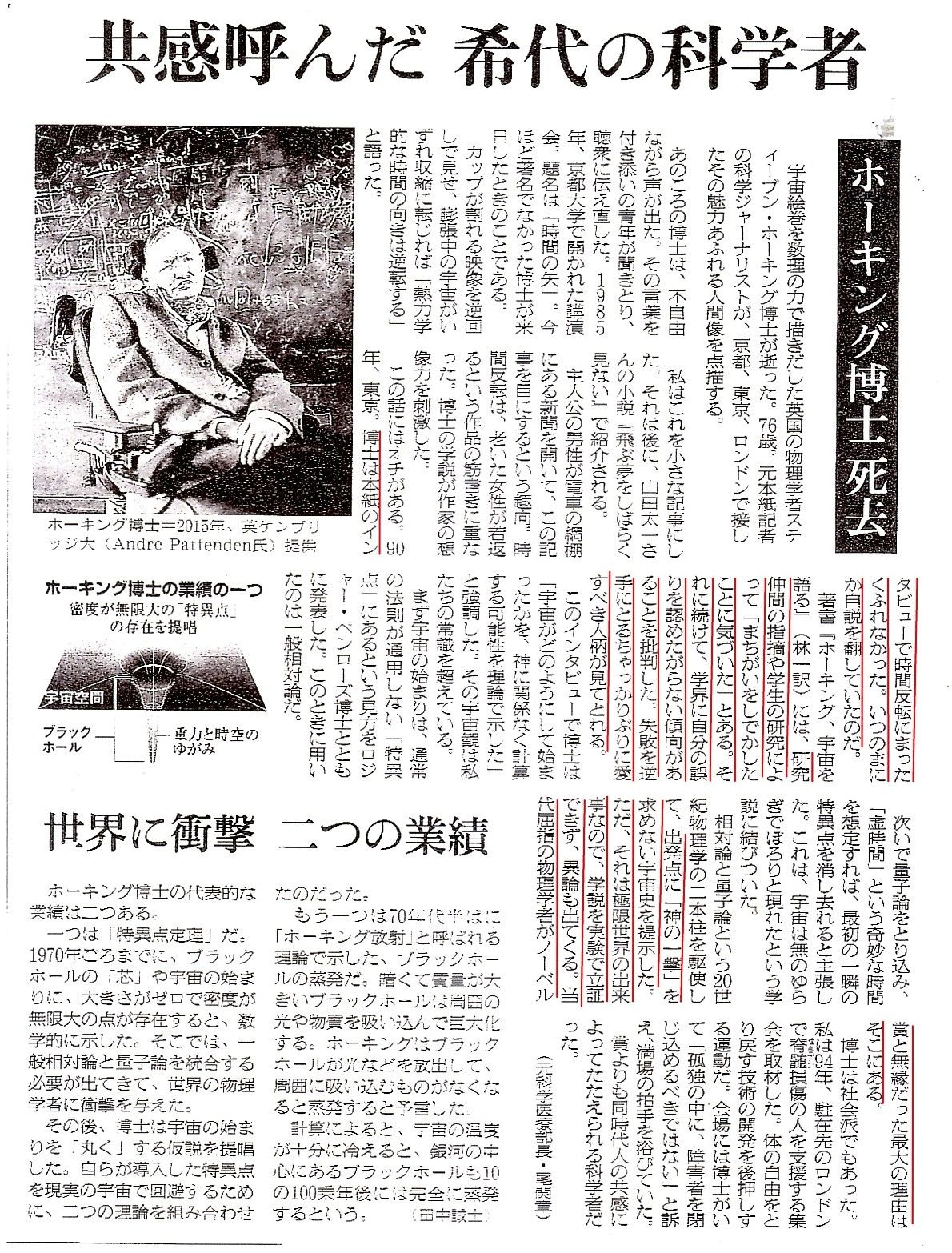
説教要約 1091
「初めに情報ありきか物理法則ありきか」2018年3月18日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年5月26日放映「神への信仰と意志」 2018年3月22日の朝日新聞の朝刊の記事です。赤線のところをお読みください。 「初めに情報ありきか物理法則ありきか」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、1章1~5節 一、初めに物理法則ありき 「車いすの天才科学者」として有名な英ケンブリッジ大のスティーブン・ホーキング博士は、「2010年9月に『ホーキング、宇宙と人間を語る』を出版し、たちまちベストセラーになりました。日本の新聞にも、ホーキングが『宇宙は神によって創られたのではなく、物理法則によって自然に作られるのだ』と書いていることに対して、欧米ではキリスト教関係者から強い反発を受けているというニュースが流れました」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』258、259頁、エクスナレッジ、2011年)。 ホーキング博士は、次のように述べています。 「この世界には完全なる法則の集合があり、現在の宇宙の状態を知ることができれば、今後宇宙がどのように発展するのかを予言することができる、という考え方です。このような法則はどの場所でもどの時刻でも成り立つべきで、そうでなかったらそれは法則ではありません。例外や奇跡もありません。神でも悪魔でも宇宙の発展に干渉することはできないのです」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』239頁、エクスナレッジ、2011年)。 ホーキング博士は、この本の出版に関して次のような謝辞を述べています。 「宇宙は偉大な設計図によって創造されました。そして本も、その設計図に従って書かれるのです。しかし、宇宙は無から生まれましたが、本は無から自発的に現れることはあり得ません。宇宙が創られるために創造主は必要ではありませんでしたが、本が出版されるためには制作者が必要です。その役割は著者だけが果たすのではありません。編集者、デザインをした人、校正をした人、図版の制作者、絵を書いた人、個人秘書、コンピューター補佐役の名前を挙げて感謝しています」(『ホーキング、宇宙と人間を語る』255~257頁、エクスナレッジ、2011年)。 二、初めに情報ありき 現代は、ITの時代です。ITとは「Information Technology」すなわち「情報技術」ということです。情報がなければ、何も考えられず、また何も動きません。21世紀になって、人類は「情報」ほど大切なものはないことがわかったのです。ところが聖書は、初めから「情報」が何よりも大切であることを教えています。 ヨハネは、「初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた」と記しています(1~3節)。「ことば」は心の表現、言い換えれば、人格を持つ者の表現です(マタイ12章34節)。 情報学者のヴェルナー・ギット博士は、この「初めにことばありき」というヨハネのことばを用いて「初めに情報ありき」という本を出版しています。すなわち「ことば」は、情報にほかなりません。 聖書は、「家はそれぞれだれかが建てるのですが、すべてのものを造られた方は、神です」と記しています(ヘブル3章4節)。 ケン・ハム氏は、「背後に知性の存在を指し示すものの例として、建物、ラシュモア山の彫刻、車を挙げ、これらは決して自然にはできません。知性のある誰かが計画して作ったから存在するのです」と述べています。 「ヒトの遺伝情報を読んでいで、不思議な気侍ちにさせられることが少なくありません。これだけ精巧な生命の設計図を、いったいだれがどのようにして書いたのか。もし何の目的もなく自然にできあがったのだとしたら、これだけ意味のある情報にはなりえない。まさに奇跡というしかなく、人間業をはるかに超えている。そうなると、どうしても人間を超えた存在を想定しないわけにはいかない。そういう存在を私は『偉大なる何者か』という意味で十年くらい前からサムシング・グレートと呼んできました」(村上和雄『生命の暗号』198頁、サンマーク出版、1997年)。 説教要約 1039 生命の設計図であるDNA 情報学者のヴェルナー・ギット博士は、宇宙には「情報」と「エネルギー」と「物質」があり、情報がエネルギー(物理法則)を造り出し、エネルギーが物質を形造ると述べています。情報がなければ、エネルギー(物理法則)はなく、エネルギーがなければ、物質は存在しません。 説教要約 1040 宇宙の設計図である神の数式 「初めに情報ありき」と「初めに物理法則ありき」のどちらが正しいでしょうか。私たちは、どちらを信じるでしょうか。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.03.16
コメント(0)
-
説教要約 1090
「心を見守れ(12)罪と負いめ」 2018年3月11日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年5月10日放映「神への信仰と知識」 「心を見守れ(12)罪と負いめ」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、6章12~14節 「私たちの負いめ(debts)をお赦しください。私たちも、私たちに負いめのある人たち(debtors)を赦しました」(12節)。 「もし人の罪(文語訳は過失、原語はあやまち)を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます」(14節) 一、「罪」と「負い目」の違い 「主の祈り」には「負いめ(debts)」と「負いめのある人たち(debtors)」ということばが記されています(12節)。「『負いめ』の原語は『オフェイレーマ』ということばで、罪(ルカ11章4節)に対するユダヤ的表現で、当然支払うべきものを支払わない、義務を果たさないことである。神にまた人に果たすべきことをしていない罪が、ここで指摘されている」(新聖書注解)。私たちは、罪をきよめられた後にも残る人間的要素というのがあります。それは「知識の不完全さ(無知)」「過失」「弱点(人間的な弱さ)」「誘惑から免れ得ないこと」です。 私たちは「うちに住む罪」(ローマ7章17、20節)が聖霊によって取り除かれて、きよめられても、これらの人間的要素のために、「神と人に果たすべきことをしていないこと」すなわち「負い目」があるのです。 二、「罪」と「負い目」からの救い 聖書は、「罪(罪の行い・心のうちに住む罪)」と「負いめ」を区別しています。罪の行いは、罪を悔い改めてキリストの十字架による罪の贖いを信じて、赦されますが、罪の行いが赦されても、心の「うちに住む罪」(ローマ七章17、20節)があるので、「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです」(ガラテヤ2章20節)と信じて、罪からきよめられなければなりません。 しかし罪をきよめられた後にも残る人間的要素のゆえに、「神と人に果たすべきことをしていないこと」すなわち「負い目」があります。「負いめ」は、厳密には「罪」ではありませんが、「神と人に果たすべきことをしていない」ので、「私たちの負いめをお赦しください。私たちも、私たちに負いめのある人たちを赦しました」と(12節)、日々祈らなければならないのです。 三、「人の罪を赦すこと」と「自分の罪の赦し」について 主の祈りの直後に、「もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます」と記されています(14節)。 「この罪の原語は、『パラプトーマ』で、神に対し、人に対して道を誤った者の罪である」(新聖書注解)。この聖句をそのまま単純に解釈するなら――たとえば射殺事件を例に挙げると――Aが私の家族を殺したので、私もAの家族を殺した場合、私が自分の家族を殺したAの罪を赦すなら、私がAの家族を殺した罪は、赦されるでしょうか。そんなことは、絶対にありません。それでは、この聖句は、どのように解釈すればよいのでしょうか。 Aが私に罪を犯した場合、それは神に対して犯したもので、しかも「律法を定め、さばきを行う方は、ただひとりであり、その方は、救うことも滅ぼすこともできます」(ヤコブ4章12節)。すなわち「人を罪に定める権威」も「人の罪を赦す権威」も私にはなく、ただ神のみ持っておられるので、私はAを神のさばきにゆだねることです。これが私にとってAの罪を赦すことになるのです。 それは、具体的に言うならば、神は「罪を悔い改めて、福音を信じるなら、あなたの罪を赦すが、罪を悔い改めず、福音を信じなければ、あなたを罪に定める」と仰せられ、私とAの両者に二者択一を迫られます。すなわち前者を選ぶなら、罪を赦されますが、後者を選ぶなら、罪に定められます。これが「もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます。しかし、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません」(14、15節)という聖句の意味なのです。 私たちは、罪を赦され、罪をきよめられても、「負い目」があるので、「私たちの負いめをお赦しください。私たちも、私たちに負いめのある人たちを赦しました」と(12節)、日々祈らなければならないのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.03.10
コメント(0)
-
説教要約 1089
「心を見守れ(11)確信と自信」 2018年3月4日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2016年2月1日放映「無意識の三要素による歩み」「心を見守れ(11)確信と自信」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、11章1~6節 「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです」(1節)。 一、自信は神に対する不信仰である 世の中において偉大であると言われる人は、ほとんどが自信に満ちた人です。「自信」とは、自分の能力や賜物を信じて、それに拠り頼むことです。ですから自信が高じれば、自負心や高慢になり、反対に自信を失えば、失望したり、落胆したり、果ては自暴自棄に陥ったりしないでしょうか。聖書は、「鼻で息をする人間をたよりにするな」(イザヤ2章22節)、「人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者はのろわれよ」と教えています(エレミヤ17章5節)。そしてキリストは、「わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです」と仰せられました(ヨハネ15章5節)。 二、信仰は確信にならなければならない 「西洋では信仰に入るか、無神論者になるかのどちらかです。ですから日本人はよく分からないのです。無神論というのは、神に絶大なる関心を持たなくては、できないのです。神を否定するのですから。ところが日本人というのは……宗教は重要であると言いながら自分は入らないのですから。……こういう統計は、西洋人は、不思議だ、不思議だと思うでしょう」(北森嘉蔵著『愁いなき神』)。 私たちは、神とその救いを信じる決心をする前に、その信じる神とその救いが確かな事実であり真理であることを知性的に理解し、納得し、承認することが必要です。 ギリシャ語には日本語において「確信(する)」と訳されることばが6つほどあります。 (1)「もし私たちが、確信(パレスィア、大胆さ)と、希望による誇りとを、終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです」(ヘブル3章6節)。 (1)「あなたがたの確信(パレスィア、大胆さ)を投げ捨ててはなりません」(同10章35節)。 (2)「私たちはキリストによって、神の御前でこういう確信(ペポイセスィス、信頼)を持っています」(第二コリント3章4節、1章15節)。 (3)「あなたがたのうちに良い働きを始められた方は……完成させてくださることを私は堅く信じている(ペイソー、説得されて確かに信じる)のです」(ピリピ1章6節、1章25節、2章24節)。 (3)「そのような信仰は……あなたのうちにも宿っていることを、私は確信しています(ペイソー、説得されて確かに信じる)」(第二テモテ1章5節)。 (3)「その方は私のお任せしたものを、かの日のために守ってくださることができると確信している(ペイソー、説得されて確かに信じる)からです」(同1章12節、ピレモン21節)。 (4)「あなたは、学んで確信した(ピストー、確証を与えられる)ところにとどまっていなさい」(第二テモテ3章14節)。 (5)「もし最初の確信(フポスタスィス、確固たる心)を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちは、キリストにあずかる者となるのです」(ヘブル3章14節)。 (5)「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信(フポスタスィス、確固たる心)させるものです」(同11章1節)。 (6)「私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、……力と聖霊と強い確信(プレロフォリア、徹底的または完璧な確信)とによったからです」(第一テサロニケ1章5節)。 エリファズは、ヨブに「あなたが神を恐れていることは、あなたの確信ではないか」と語っています(ヨブ4章6節)。これはヨブがそうであったのか、エリファズの解釈なのかわかりませんが、それは誤りです。「神を恐れていることを自分の確信にする」ことは、「自分自身に拠り頼んでいる自信」にほかならず、徹底的(完璧)に神を信じる「確信」ではありません。 聖書は、「信仰」は信じるだけでなく「大胆」に、「信頼」し、「説得されて確かに信じ」、「確証を与えられ」、「確固たる心」で、「徹底的または完璧な確信」を持つことが必要であると教えています。これこそ神が私たちに求めておられることです(ヘブル11章1、6節)。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.03.03
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1