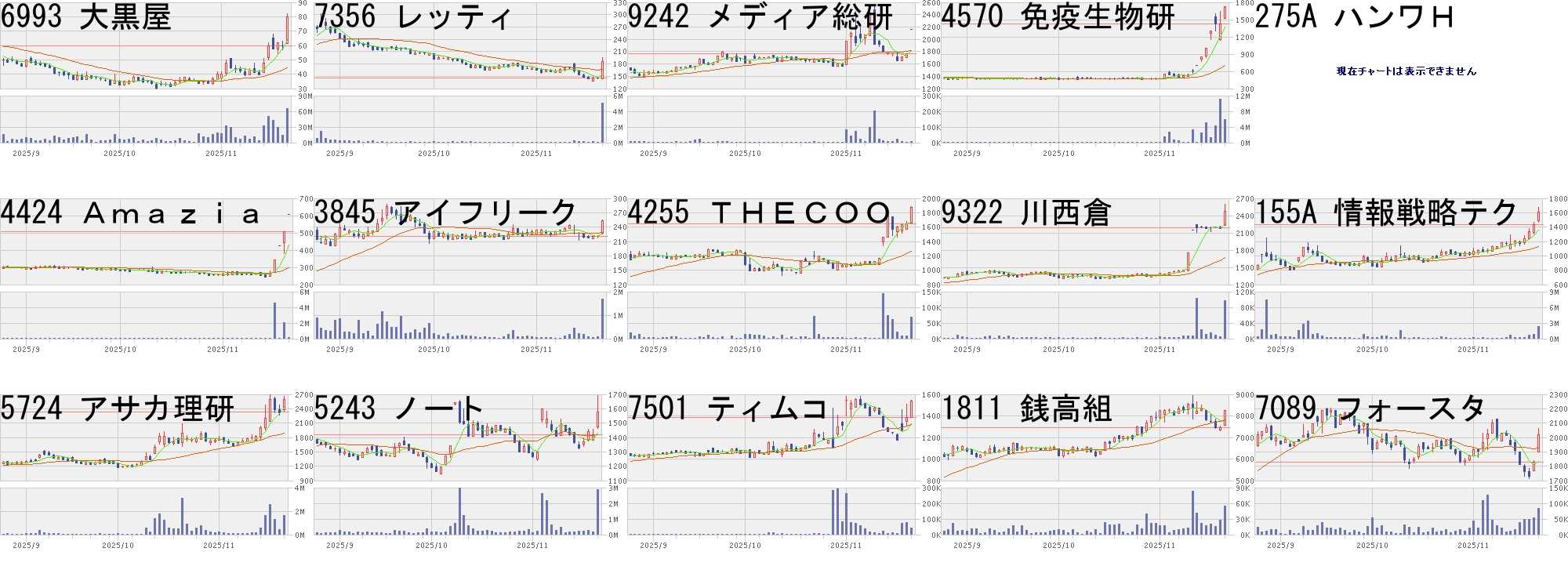2018年12月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
説教要約 1132
「大いなる事をなさる神を呼べ」2018年12月30日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年7月4日放映「真の幸福」「大いなる事をなさる神を呼べ」 甲斐慎一郎 エレミヤ33章1~9節 その名は主である方がこう仰せられる。「わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう」(3節)。 この箇所における「あなたの知らない、理解を越えた大いなる事」というのは、第一義的には、4節以下に記されているユダとエルサレムの復興と繁栄のことを指しています。しかしここでは、すべての人に当てはまる神の啓示としてとらえてみます。 一、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事が起きるのが人生です フランスの文学者が「ある赤ん坊が母親のお腹から出てくると、まわりをキョロキョロ見回し『なんだ、人生とは、こんなものか』とひとこと言って、おなかの中に引っ込んでしまう」という即興劇をつくりました。 しかし実際は「事実は小説よりも奇なり」というエマソンの言葉ように、現実の人生は、作家の空想も及ばないような意外なことが多いもので、人が一生かかっても極め尽くすことができないほど不思議な巡り合わせや複雑な変化に富んでいるものです。 聖書は「順境の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後の事を人にわからせないためである」と教えています(伝道者7章14節)。 二、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事をなさるのが神です 私たちは、新年を迎えて新しい計画や目標を立てたり、新年の希望や抱負を語ったりすると、何か新しくなったような気がします。しかし正月も終わり、通常の生活に戻ると、去年と少しも変わっていない自分を発見して、愕然とすることがあります。「日の下には新しいものは一つもな」く(伝道者1章9節)、人は、神による以外に新しくなることはできません(第二コリント5章17節)。 神は、イスラエルに「見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている」仰せられました(イザヤ43章19節)。 イスラエルの民は、何度も神にそむいて罪を犯し、神が遣わされた預言者たちの警告にも耳を傾けず、ついに敵国バビロンに滅ぼされ、生き残った者は捕虜となり、バビロンに連れて行かれてしまいました。彼らは、神に対して犯した罪の報いを受けたのです。 ところが神は、ペルシャの王クロスの霊を奮い立たせられたので、王のおふれによってイスラエル人は捕囚の身から解かれ、祖国に帰ることができました(エズラ1章)。 彼らは、「主がシオンの捕らわれ人を帰されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた」と歌っています(詩篇126篇1、2節)。このバビロン捕囚からの帰還こそ、神がなさる「新しい事」です。 パウロが述べているように、神は「私たちの願うところ、思うところのすべてを越えて豊かに施すことのできる方」です(エペソ三章20節)。ダビデは「私の時は、御手の中にあります」と記しています(詩篇31篇15節)。ブッシュネルは、「どの人の生涯も神の計画による」、「神の心の中には、すべての人のために完成された完全な計画が大切にしまわれている」と述べています。 三、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求めることこそ私たちの義務であるとともに特権です このように神は、「私たちの願うところ、思うところのすべてを越えて」、あふれるばかりの恵みを注いで「新しい事」をなさる方です。神は、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事をなさる方ですから、神のなさることはみな「新しい事」なのです。 私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求めることこそ私たちの義務であるとともに特権です。新しい年、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求め、その神に新しい事を期待して歩もうではありませんか。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.12.29
コメント(0)
-
説教要約 1131
「キリストの受肉の目的」 2018年12月23日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年7月15日放映「世を愛された神」「キリストの受肉の目的」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、2章5~18節 ヘブル人への手紙の1章にはキリストが神であること、2章にはキリストが人であることについて記されています。それでキリストの受肉の目的について学んでみましょう。 一、人間の尊厳と価値について 私たちは、人間についてどのように考え、どのようにとらえているでしょうか。 ある人は、「あなたは人を海の魚のように、治める者のないはう虫のようにされます」と神への疑惑に満ちて、悲惨な人間の姿を嘆いています(ハバクク1章14節)。 他の人は、「人とは何者なのでしょう。……朝ごとにこれを訪れ、そのつどこれをためされるとは。いつまで、あなたは私から目をそらされないのですか。つばをのみこむ間も、私を捨てておかれないのですか」と神への嫌悪に満ちて、試みられる人間の苦しみを訴えています(ヨブ7章17~19節)。 別の人は、「人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人の子とは、何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは」と神への感謝に溢れて、人間の幸いな姿を歌っています(詩篇8篇4節)。 私たちは、人間の尊厳と価値を知っているかどうかによって、これほど人間に対する考え方に違いが生じて来るのです。 神の御子が人となられたというキリストの受肉こそ、真の人間の尊厳と価値を私たちに教えるとともに、人間が神の計画と目的から決して除外されていないことを証明するものです。私たちは、このキリストの受肉のすばらしさを知る時、神への疑惑と嫌悪に満ちて、人間を惨めな者として嘆くのをやめるようになるだけでなく、人間の尊厳と価値を知って、神への感謝に溢れるようになるのです。 二、キリストの受肉の目的について 聖書は、キリストの受肉の目的について次のような三つのことを教えています。 1.第一は、罪に対する贖いのためです 聖書は、イエスが人となられたことを「御使いよりも、しばらくの間、低くされたイエス」と記し、その「イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです」と述べています(9節)。さらに「神のことについて、あわれみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のために、なだめがなされるためなのです」と記し(17節)、キリストの受肉は、罪に対する贖いのためであると教えています。 2.第二は、試みに対する助けのためです 私たちは、「狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕する所もありません」(マタイ8章20節)、「わたしは悲しみのあまり死ぬほどです」(同26章38節)、「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(同27章46節)と言われたイエスの言葉の重みをどれほど知っているでしょうか。自分は最も苦しい試みに遭っていると思ってはなりません。世の中にはもっと苦しい目に遭っている人々が大ぜいいるのであり、何よりもキリストは神に捨てられる苦しみを味わわれたのです。 聖書は、「主は、ご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです」(18節)と記し、キリストの受肉は、試みられている者たちを助けるためであると教えています。 3.第三は、死に対する勝利のためです パウロは、死は「最後の敵」であると述べています(第一コリント15章26節)。 そして聖書は、「子たちはみな血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした」と記し(14、15節)、キリストの受肉は、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放するためであると教えています。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.12.22
コメント(0)
-
説教要約 1130
「人であるキリスト(3)その痛みについて」2018年12月16日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年5月31日放映「信仰の決断」「人であるキリスト(3)その痛みについて」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、5章7節 「キリストは、人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とをもって祈りと願いをささげ、そしてその敬虔のゆえに聞き入れられました」(7節)。 先回は人であるキリストの第2回目として「その疲れについて」学びましたが、今回は第3回目として「その痛みについて」学んでみましょう。 イザヤ書53章には、「痛み(痛める)」という言葉が3回(4、7、10節)記されています。その痛みは私たちのためですが、「罪(咎)のために」という言葉も3回記され、それは痛みの内容を教えています。▽それは、刺し通される痛みです(5節)。▽それは、砕かれる痛みです(5節)。 ▽それは、打たれる痛みです(8節)。 一、痛みの種類 人間を構成している「霊」と「心」と「からだ」によって三種類の痛みがあります。 1.肉体的な痛み――からだの苦痛のことで、これは医学的に病気や怪我がいやされなければ、取り去ることができないものです。 2.精神的な痛み――心痛のことで、これは心を突き刺されるようなむごいことを言われたり、脳天を打ち砕かれるような衝撃を受けたり、打ちのめされるようなひどい目に会ったりして心が傷つくことです。これは気分転換をしたり、ほかのことで気を紛らわせたりしても、容易にいやされることができないものです。 3.霊的な痛み――自分は神のみこころを痛めたり、神を傷つけたりしているという自覚のことです。これは、私たちが神の言葉によって刺し通され、砕かれ、打たれる時に覚える痛みです(使徒2章37節、ヘブル4章12節)。 二、キリストの痛み キリストは、頭にいばらの冠をかぶらせられ(マタイ27章29節)、手に釘を刺し通されました(ヨハネ20章25節)。また平手で打たれただけでなく、むちでも打たれた(マルコ14章65節、15章15節)のです(肉体的な痛み)。 またキリストは、イスカリオテのユダには口づけで裏切られ(ルカ22章48節)、ペテロには3度も知らないと言われました(マタイ26章70~74節)。キリストの心痛は、いかばかりであったことでしょうか(精神的な痛み)。 そしてキリストは、十字架の上で、「わが神、わが神。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27章46節)と、人類の罪を負って死ぬという言語に絶する苦しみを嘗められたのです(霊的な痛み)。 キリストにとって肉体的な痛みや精神的な痛みは、この最も激しい霊的な痛みに備えるものとなったのではないでしょうか。 三、私たちの痛み 「霊」と「心」と「からだ」は、切っても切れない関係にあるため、三種類の痛みは、それぞれ大きな影響を及ぼし合っています。 1.肉体的な痛みや精神的な痛みがないと、霊的な痛みもないかのように錯覚してしまうのです。 私たちは、肉体的な痛みや精神的な痛みがなくても、御霊によって生まれ、光の中を歩んでいなければ、神のみこころを痛めているということを決して忘れてはなりません。 2.肉体的な痛みや精神的な痛みは、私たちに霊的な痛みを覚えさせるのです。 人間にとって最も大切なことは、霊的な痛みを覚えるとともに、それが取り去られることです。人間というものは、肉体的または精神的に痛い目に会わないと、なかなか霊的な痛みに気がつかないものですが、私たちは、霊的な痛みに気づく時、神に近づくことができるのです(詩篇119篇67、71節)。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.12.15
コメント(0)
-
説教要約 1129
「人であるキリスト(2)その疲れについて」2018年12月9日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年5月28日放映「父と子の交わり」「人であるキリスト(2)その疲れについて」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、5章7節 「キリストは、人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とをもって祈りと願いをささげ、そしてその敬虔のゆえに聞き入れられました」(7節)。 先回は人であるキリストの第1回目として「その渇きについて」学びましたが、今回は第2回目として「その疲れについて」学んでみましょう。 それでは、「疲れ」とは、何を意味するのでしょうか。次のような三つにまとめることができます。▽それは、足りなさの表れです。 ▽それは、弱さの表れです。 ▽それは、無力さの表れです。 一、疲れの種類 人間を構成している「霊」と「心」と「からだ」によって三種類の疲れがあります。 1.肉体的な疲れ――からだの疲労のことで、これは病気ではない限り、必要な睡眠や休息また栄養を取ることによっていやされることができます。。 2.精神的な疲れ――心労のことで、これは次のように言うことができるでしょう。(1)どうしてよいかわからない(知識的な面)。(2)どうにもやりきれない(感情的な面)。(3)どうすることもできない(意志的な面)。 これは、色々と学んだり、レクレーションで気分転換をしたり、正しい人間関係を持ったり、様々な能力を身につけたりすることによっていやされることができます。 3.霊的な疲れ――神の前における無力さのことで、これは、神を「離れては……何もすることができない」(ヨハネ15章5節)という絶対的な弱さのことです。 二、キリストの疲れ キリストは、「旅の疲れで」(ヨハネ4章6節)、休まれたことがあり、また激しい突風が起こり、舟が波をかぶっているような中でも、疲れのために「とものほうで、枕をして眠っておられた」(マルコ4章38節)こともあります(肉体的な疲れ)。 またキリストは「笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても、悲しまなかった」と言って(マタイ11章17節)、ご自分を非難した当時の人々の身勝手さや、「数々の力あるわざの行なわれた町々が悔い改めなかった」ことで(同11章20節)、どんなに疲れを覚えられたことでしょうか(精神的な疲れ)。 そしてキリストは、「わたしは、自分からは何事も行うことはできません」(ヨハネ5章30節)と言われました(霊的な疲れ)。 しかしキリストは、このように父なる神に完全に依存しておられたので、精神的な疲れも肉体的な疲れも克服して、神のみわざを成し遂げることがおできになったのです。 三、私たちの疲れ 「霊」と「心」と「からだ」は、切っても切れない関係にあるため、三種類の疲れは、それぞれ大きな影響を及ぼし合っています。 1.肉体的な疲れや精神的な疲れがいやされると、霊的な疲れもいやされるたかのように錯覚してしまうのです。 私たちは、肉体的な疲れや精神的な疲れがいやされても、神を信じ、キリストにとどまることによって霊的な疲れがいやされない限り、小さな罪にさえ勝つことはできません。 2.肉体的な疲れや精神的な疲れは、私たちに霊的な疲れを覚えさせるのです。 人間にとって最も大切なことは、霊的な疲れがいやされることです。肉体的な疲れや精神的な疲れを覚えることは、私たちに霊的な疲れを覚えさせ、それによって私たちは、神に近づくことができますが(詩篇119篇67、71節、伝道者7章2~4節、マタイ5章3~12節)、それはまた精神的な疲れや肉体的な疲れを克服する秘訣なのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.12.08
コメント(0)
-
説教要約 1128
「人であるキリスト(1)その渇きについて」2018年12月2日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2013年5月22日放映「真の生きがい」「人であるキリスト(1)その渇きについて」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、5章7節 「キリストは、人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とをもって祈りと願いをささげ、そしてその敬虔のゆえに聞き入れられました」(7節)。 人間は、肉体を持っているために、飢えや渇き、また疲れや痛みなどという独特な不自由さや不便さがあります。人としてキリストも罪を犯さなかったこと以外は、私たちと同じでした。 しかしこの(飢え)渇きと疲れと痛みは、肉体のみならず霊と心にもあるものです。それで聖書から次のような三つのことを学んでみましょう。▽人であるキリスト(1)――その渇きについて▽人であるキリスト(2)――その疲れについて▽人であるキリスト(3)――その痛みについて まず渇きについて学んでみましょう。 一、渇きの種類 人間を構成している「霊」と「心」と「からだ」によって三種類の渇きがあります。 1.肉体的な渇き――のどの渇きのことで、飢えも含めるならば飲食欲のことです。 2.精神的な渇き――心の渇きのことで、これには三つのことが含まれています。(1)知識的な満足を求めること。(2)感情的な満足を求めること。(3)意志的な満足を求めること。 これを実際的に分かりやすく述べるなら、人に理解されたい、人に喜ばれたい、自分の願いが叶えられたいという求めのことです。 3.霊的な渇き――神への渇きのことで、これは神の「みこころを行ない、そのみわざを成し遂げ」たいという求めのことです(ヨハネ四章34節)。 二、キリストの渇き キリストは、十字架の上で「すべてのことが完了したのを知って……『わたしは渇く』と言われた」(ヨハネ一九章28節)と聖書は教えています。これは、肉体的なのどの渇きのことですが、なぜこのような時に言われたのでしょうか。それは、十字架の上で私たちの罪をその身に負い、人類の罪を贖うという神のみわざを成し遂げている間は、肉体的な渇きも忘れていましたが、それが完了した時、のどの渇きを覚えられたのです。 キリストは十字架の上で神のみわざを成し遂げたいという霊的な渇きを満たすために、のどの渇きという肉体的な渇きを忘れ、また人に「さげすまれ、人々からのけ者にされ」ることによって(イザヤ53章3節)、精神的な渇きを満たすことも犠牲にされたのです。 キリストにとって最も大切なことは、霊的な渇きを満たすことであり、精神的な渇きや肉体的な渇きを満たすことは、第二、第三のことでした。これは私たちにとっても同じではないでしょう。 三、私たちの渇き 「霊」と「心」と「からだ」は、切っても切れない関係にあるため、三種類の渇きは、それぞれ大きな影響を及ぼし合っています。 (1)肉体的な渇きが満たされるならば、精神的な渇きも満たされ、さらに霊的な渇きも満たされたかのように錯覚してしまうのです。 (2)肉体的な渇きは、精神的な渇きを招き、それは霊的な渇きをも覚えさせるのです。 前者の典型的な例は、愚かな金持ちの農夫です(ルカ12章16~21節)。彼は、豊作のために肉体的な飢え渇きが満たされましたが、それによって精神的な渇きや霊的な渇きも満たされたかのように錯覚したのです。 人間にとって最も大切なことは、霊的な渇きが満たされることです。後者のように肉体的な渇きや精神的な渇きが満たされないことは、私たちに霊的な渇きを覚えさせ、それによって私たちは、神に近づくことができるのです(詩篇119篇67、71節、伝道者7章2~4節、マタイ5章3~12節)。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.12.01
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1