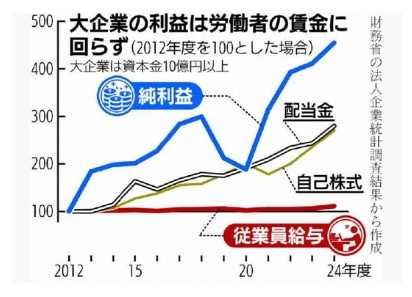2018年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

説教要約 1114
「歴史に見る七つの教会(1)」 2018年8月26日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年7月13日放映「根拠に基づいて神と福音を信じる」「歴史に見る七つの教会(1)」 甲斐慎一郎 ヨハネの黙示録2、3章 「あなたの見ることを巻き物にしるして、7つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキヤに送りなさい」(黙示録1章11節)。 私たちが一般に用いている教会ということばは、「目に見える教会」を指し、その誕生は、言うまでもなく聖霊降臨節(ペンテコステ)の時です。 しかし聖書は、それ以前にも「目に見えない教会」や「教会のひな型」を教えています。それで教会の歴史を次のような三つの時代に分けて学んでみましょう。▼聖霊降臨節以前の教会の歴史▼聖霊降臨節から主の再臨に至るまでの教会の歴史▼主の再臨以後の教会の歴史 一、聖霊降臨節以前の教会の歴史 先に述べたように聖霊降臨節(ペンテコステ)は、新約の教会の誕生日ですが(使徒2章)、その教会の前身は、すでにキリスト在世当時の弟子たちの集団に見ることができます(マタイ16章18節)。 そしてもっと時代を溯るなら「荒野の集会(エクレシヤ)」(使徒7章38節)と記されているイスラエル人の集まりも「教会のひな型」です。 しかし聖書は、教会の起源は「神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました」(エペソ1章4節)とあるように「世界の基の置かれる前から」すでに神のみこころの中にあったことを教えています。 有史以前、いや山々が生まれる前から、神は、「ご自身で、しみや、しわや、そのようなものの何一つない、聖く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせる」(エペソ1章4節、5章27節)ことを計画され、それが旧約のイスラエル人の集まりをひな型とし、新約の弟子たちの集団を前身として、ついに聖霊降臨節の日に誕生したのです。 これは何と驚くべきことでしょうか。神のご計画は、何と遠大なことでしょうか。このような教会の歴史の古さを通して、私たちは、教会こそ神のご計画の中心であることを知るのです。 二、聖霊降臨節から主の再臨に至るまでの教会の歴史 全時代の全世界における真に贖われたキリスト者の集まりである「目に見えない教会」は、「すべての霊的祝福」(エペソ1章3節)と「驚くべき神的特権」に満ちた栄光の姿です(同1章17~23節)。これに対して地上にある有形の「目に見える教会」は、外からの迫害と内からの腐敗という二つの危険にさらされながら、福音宣教のために戦い、完成を目指してうめき苦しんでいるのが現実の姿です。 この「目に見える教会」の歴史をヨハネの黙示録の2章と3章にある7つの教会の姿から見てみましょう。この7つの教会は、第一義的には、アジヤ(現在のトルコ)にある7つの地域の教会ですが、それだけでなく、ヨハネの聞いた「あなたの見た事、今ある事、この後に起こる事を書きしるせ」(同1章19節)ということばのように「将来に起こる事」すなわち聖霊降臨節(ペンテコステ)から主の再臨に至るまでの7つの時代の教会の歴史を教えているのです。 1.エペソの教会――初代教会の時代(黙示録2章1~7節) これは紀元30年の聖霊降臨節から使徒たちがすべて世を去った100年頃までの間で、教会が著しく発展した時代です。しかしこの時代の教会は、使徒たちが世を去るにつれて「初めの愛から離れてしまった」ことを教えています(2章4節)。 2.スミルナの教会――教会への迫害時代(黙示録2章8~11節) これは100年からコンスタンティヌス帝が「ミラノ勅令」によってキリスト教を公認した313年までの間で、教会が激しい迫害を受けた時代です。しかし教会は、迫害を受ければ受けるほど成長していったのであり、「殉教者の血は教会の種子である(テルトゥリアヌス)」ということばが真理であることを教えています。(神のご計画の全体「68 「歴史に見る七つの教会(1)」より転載)甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.08.25
コメント(0)
-

説教要約 1113
「欧州の国々の歴史」 2018年8月19日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年6月2日放映「心(思い)の一新」「欧州の国々の歴史」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙13章1節 政教分離で、信教の自由のある健全な国家の建設は、初代教会から現代までのヨーロッパの国々に起こった国家と教会の関係から学ぶことができます。 一、国家と対決した教会の時代――初代教会からミラノの勅令まで キリストの教会は紀元30年の聖霊の降臨の時に誕生しました。これが初代教会です。初代教会が飛躍的に成長するに従って、ローマ帝国はキリスト教を迫害するようになりました。なぜなら教会は、「国家の中の国家」のように見えたからです。これは、教会が国家と対決した時代です。「殉教者の血は、教会の種子である」(テルトゥリアヌス)ということばのように、教会は迫害を受ければ受けるほど成長し、ローマ帝国を内側から突き崩し、ついにコンスタンティヌス皇帝は、ミラノの勅令(紀元313年)によってキリスト教を公認しました。 二、国家と協力した教会の時代――ミラノの勅令からフランス革命まで ミラノの勅令によってキリスト教が公認されてから、ローマ教会が中心的な地位を占めました。ここから教会は国家と協力する時代になりました。その後、教会は西方教会(ローマ・カトリック教会)と東方教会(ギリシャ正教やロシヤ正教、日本は日本正教会)に分かれました。これが紀元1054年です。この分裂後は、西方教会であるローマ・カトリック教会は、ローマ法王の権力が世俗の王権をも圧倒するようになりました。これは、教会と国家の主導権争いを招き、国家も教会も世俗化するという弊害を生み出しました。 マルチン・ルターが起こした宗教改革(紀元1517年)が成功したのは、ルターの前に改革者が出て、犠牲となり、土壌を肥やし、空気を作ったからです。これらの人々は、宗教改革前の改革者または宗教改革の先駆者と言うことができます。この宗教改革の先駆者の中にジョン・ウィクリフ、ヨハン・フス、サヴォナ・ローラがいます。もう一つ、中世には、1,350年から1,650年にヨーロッパのおもな国々で文芸復興(ルネッサンス)が起こりました。 「文芸復興は、人生に宗教的・団体的に近づく中世のやり方の代わりに、現代的・非宗教的・個人主義的な人生観に置き換えた文化的方針の再決定の時代と定義することができよう。……神がすべての事物の尺度であった中世の神中心の世界観は退いて、人間がすべての事物の尺度となった人間中心の人生観が力を得てきた」のです(E・ケァンズ)。 マルチン・ルターによる宗教改革は、このようなカトリック教会の中で起きた宗教改革の先駆者たち、そして世俗の世界で起きた文芸復興を背景に起こったのです。近代は、霊的なものである宗教改革と、知的なものである文芸復興(ルネッサンス)によって誕生したということができます(E・ケァンズ)。 三、国家から自由とされた教会の時代――フランス革命から現代 教会は、国家が世俗化し、政治目的のために教会を利用するという弊害に気づき、「信仰の自由」と「政教分離」を求め、フランス革命(紀元1,789年)の以後からそれを勝ち取ることができました。ここから教会は国家から自由とされた時代になりました。 キリスト教の2,000年にわたる歴史において、国家と対決した教会の時代が約300年、国家と協力した教会の時代が約1,500年ですから、宗教(キリスト教)と国家が正しい関係になり、健全な国家が建設されるまで実に1,800年もの長い歳月が流れ、しかも、「信教の自由」があって「政教分離」の国家が建設されるようになった期間は、約200年です。 因みに紀元前の時代は、どの国も国家と宗教が協力した「政教一致」です。それで日本では「政治」のことを「政(まつりごと)」と言い、「まつりごと」は「祭り事」すなわち「神を祭ること」で、「政教一致」を表しています。 「政教一致」であれ、「政教分離」であれ、宗教なしに国を治めることはできず、古今東西を問わず、宗教(共産国は思想)なしに国家を建設した国は、一つもないのです。(神のご計画の全体「67 欧州の国々の歴史」より転載)甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.08.18
コメント(0)
-

説教要約 1112
「健全な国家の建設」 2018年8月12日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年5月23日放映「豊かないのち」「健全な国家の建設」 甲斐慎一郎 使徒の働き20章 「私は、すべての人たちが受けるさばきについて責任がありません。私は、神のご計画の全体を、余すところなくあなたがたに知らせておいたからです」(27節) 神の人類に対する遠大な計画は、健全な国家の建設と個人の罪からの救いという両者があります。キリストはナザレにおいて、福音は、個人を罪から救う霊的な救いであるとともに、心(知性と感情と意志)を変える精神的な救いや病をいやす肉体的な救いをもたらし、また貧しい人たちを援助する経済的な救い、さらに世の中をよくする社会的な救い、そして国家を変える政治的な救いにまで及んでいくと説教されました(ルカ4章16~21節)。 一 健全な国家を建設するためには社会の法律と倫理・道徳と神の律法が必要です 法律は、「個人の権利と利益」、「公共の福祉と安全」、「国家の秩序と平和」を守るために制定されたものです。規範には「外的規範」と「内的規範」があります。 ▼外的規範――人間の外側に表れた行為を取り締まるもので、具体的には法律です。 ▼内的規範――人間の内側の心を制御するもので、具体的には思想、信条、宗教です。 国家がどんなに優れた法律を制定しても、国民がその法律を守らなければ、犯罪が多発する暗黒な無法地帯になります。その社会の法律を守るようにさせるものが倫理・道徳であり、倫理を向上させ、道徳心を養うものは、内的規範である思想・信条・宗教、すなわち真の神への信仰であり、真の宗教(キリスト教)です。人間は罪人ですから、正しい思想・信条・宗教を持たなければ、倫理観が欠如し、道徳が退廃して、法律を犯してしまうのです。 二 政教分離で、信教の自由がある健全な国家が建設されるまでの経緯 民主主義の国家が生まれるまでは、どの国も独裁国家で、外国との戦争や国内の内乱を静めることに力を注ぎ、民は不幸でした。このような中で平和で豊かな民主主義の国家を建設するためには、キリスト教が多数派(マジョリティー)の教会、すなわち世界一の宗教になることが必要です。具体的にはローマ帝国と組んで――政教一致ですが――教育と知識を普及させ、技術が進歩するしかないのです。 そのための方法は、良くないものが沢山含まれていますが、ともかくローマ帝国は、キリスト教を公認し、キリスト教による政教一致の国家を建設し、キリスト教が多数派(マジョリティー)の教会、すなわち世界一の宗教になりました。 そのような中で、年月がかかりましたが、民主主義の三原則である「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」が養われて行き、フランス革命の後、政教分離で、信教の自由がある民主主義の国家が生まれたのです。ミラノ勅令から約1,500年の歳月が流れました。コンスタンティヌス皇帝がしたことは、ローマ帝国のため、皇帝の名誉のためであったことは、言うまでもありませんが、神は、このようなことをも用いて、将来、健全な国家が建設される過程として用いられたのです。もしミラノ勅令がなければ、キリスト教は、ただ迫害を受けるだけで、あとかたもなく消滅してしまったことでしょう。300年以上も迫害に耐えられるわけがありません。いやキリスト教だけでなく、世の国々も外国との戦争や国内の内乱を静めることばかりして、互いに殺し合い、国家も滅亡し、世界も滅亡していたことでしょう。 ローマ帝国そしてカトリック教会は、数多くの問題を抱えていましたが、神は、これさえも用いて、健全な国家、そして健全なキリスト教が生まれるのを待っておられたのです。 人はすべて罪人ですから、何の問題も罪もなく、理想的に造られていくなどということはあり得ません。数多くの問題を抱えているローマ帝国、そしてカトリック教会のなかで、少数ですが、神の人が現れて、改革していったのです。数多くの問題があっても、まずキリスト教が多数派(マジョリティー)の教会として、ローマ帝国の中で、生き残っていくしかなかったのであり、生き残らなければ、改革することもできません。政教分離で、信教の自由がある健全な国家が建設されるまでキリスト教会が誕生してから約1,800年の歳月が流れています。(神のご計画の全体「67 健全な国家の建設」より転載)甲斐慎一郎の著書→説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。
2018.08.11
コメント(0)
-

説教要約 1111
「宗教と国家の建設」 2018年8月5日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年5月11日放映「神の謙遜と人の謙遜」「宗教と国家の建設」 甲斐慎一郎 ヨハネの黙示録11章15節 「この世の国は、私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される」(15)。 一、健全な国家が建設されなければ、国民は安心して暮らすことができません 私たちは様々な生活をしています。すなわち衣食住の生活をはじめ、学生が送る学校生活、社会人が送る社会生活、そして仕事をしなくてもよい時間に行うすべてのこと、たとえば休息や保養、旅行や娯楽(レクリエーション)、趣味や運動、音楽や芸術等々の余暇の生活です。 私たちは、このような日常生活を送ることができるのは当たり前であると思っているかもしれません。しかしこれは、社会の治安が維持され、戦争のない平和な国に住んでいるからこそ可能なのです。もし社会の治安が乱れたり、外国との戦争や国内での内乱が起こったりするなら、日常生活を送ることはおろか、生きていくことさえできなくなります。私たちは、改めて健全な国家が建設されることがどんなに大切であるかを知らなければなりません。 キリストは、郷里のナザレにおいて説教をされました(ルカ4章16~30節)。その説教は「捕われ人には赦免を」「盲人には目の開かれること」「しいたげられている人々を自由にし」「主の恵みの年を告げ知らせる」というものでした(イザヤ61章1、2節)。 「捕われ人には赦免を」は政治的な救いを、「盲人には目の開かれること」は肉体的な救いを、「しいたげられている人々を自由にし」は社会的な救いを、「主の恵みの年を告げ知らせる」は霊的な救いを教えています(ルカ4章18、19節)。 キリストの福音は、個人を罪から救う霊的な救いですが、それは、心(知性と感情と意志)を変える精神的な救いや、病をいやす肉体的な救いをもたらし、また貧しい人たちを援助する経済的な救い、さらに世の中をよくする社会的な救い、そして国家を変える政治的な救いにまで及んでいくのです。 二、健全な国家を建設するためには、外的規範と内的規範の両者が必要です 「法律」は、個人の権利と利益、また公共の福祉と安全、そして国家の秩序と平和を守るために制定されたもので、人間の外側に表れた行為を取り締まります(外的規範)。その「法律」を守るようにさせるものが「倫理・道徳」であり、その「倫理・道徳」を守るようにさせるものが「思想・信条・宗教」です(内的規範)。 三、国家と外的規範、内的規範の関係には、基本的に三つのものがあります (1)国粋主義(右翼)の国家――国は法律を制定するとともに、国民を国家の意志に従わせるために思想・信条・宗教を定めます。これは政教一致です。 (2)共産主義(左翼)の国家――国は法律を制定するとともに、国民を国家の意志に従わせるために、宗教を否定し、思想や信条を定めます。これも政教一致です。 (3)民主主義の国家――国家は法律を制定するだけで、思想・信条・宗教は、国民が自由に選ぶことができます。すなわち信教の自由があり、これは政教分離です。国家は、思想・信条・宗教には一切干渉しませんが、国民は法律を守る義務があり、それを犯せば罰せられます。 この三つは基本的なものであり、実際には(1)と(3)の中間や組み合わせ、また(2)と(3)の中間や組み合わせなど様々な形態があります。 民主主義の国家が生まれる以前は、どの国も国家と宗教が協力した「政教一致」です。それで日本では「政治」のことを「政(まつりごと)」と言います。「まつりごと」は「祭り事」すなわち「神を祭ること」で、「政教一致」を表しています。 「政教一致」であれ、「政教分離」であれ、宗教なしに国を治めることはできず、古今東西を問わず、宗教(共産国は思想)なしに国家を建設した国は、一つもないのです。(神のご計画の全体「66 宗教と健全な国家の建設」より転載)甲斐慎一郎の著書 説教集2018年5月20日に出版した「神のご計画の全体」です。
2018.08.04
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1