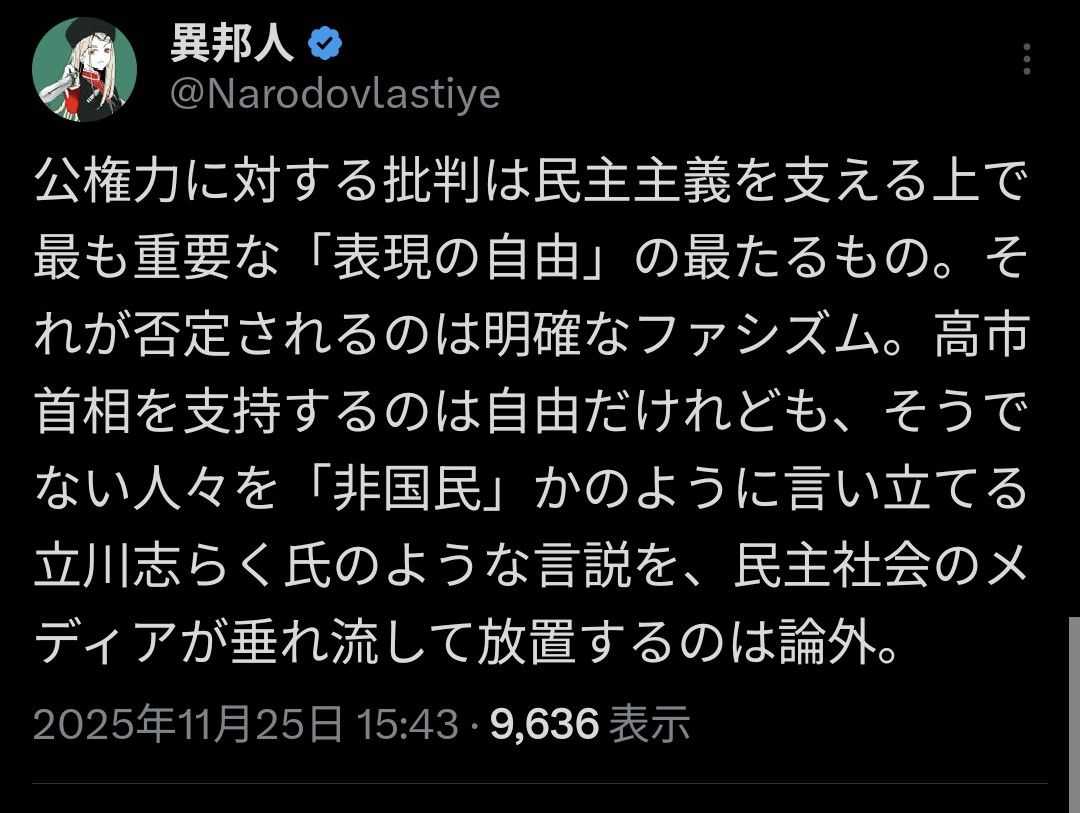2018年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約 1123
「主のことばを聞く」 2018年10月28日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2012年11月15日放映「神の愛と人の愛」「主のことばを聞く」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙10章17節 一、主のことばを聞くことのききん 2017年10月31日は、1517年にマルティン・ルターが宗教改革を行ってから500年を迎える記念すべき日です。それで聖書(主のことば)について学んでみましょう。 ききんは、人の生命を支える食物や飲物を欠乏させるものですから、人を死に至らせる恐ろしいものです。イスラエルには、ききんが多く(創世記12章10節、26章1節、43章1節、ルツ1章1節)、イスラエル人は、その恐ろしさをよく知っていました。アモスは、この「ききん」ということばを巧みに用いて、人の霊的な生命を支える食物や飲物である「主のことば」を聞くことができず、人を死に至らせる恐ろしい神の審判のことを「主のことばを聞くことのききん」(アモス8章11節)と言って、預言しました。 エリがさばきつかさとして治めていたころは、「主のことばはまれにしかなく、幻も示され」ず(第一サムエル3章1節)、また、「主が正しいと見られること」(申命記12章25節)ではなく、「めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた」ので(士師記17章6節、21章25節)、士師記の17章から21章には、読むに耐えないような醜悪で残虐な出来事が詳細に記され、まさに「主のことばを聞くことのききん」の時代でした。 二、主のことばを聞くことの大切さ 聖書は、主のことばがどれほど大切であるかについて繰り返し教えています。 1.すべてのものは、神のことばによって造られました(創世記1章3、6、9、11、14、24節、詩篇33篇9節)。 2.神が創造された以外のすべてのものも、人の心から出たことばによって造られます。 3.人の心は、ことばがなければ死にます。――人の心は、ことばによって生きているのであり、ことばがなければ死にます。 4.人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる」のです(マタイ4章4節)。――人は、神のことばを信じなければ、その心は神の前に死んでいるのであり、神のことばを信じる時にのみ、人の心は生き返り、生き続けることができます。 5.「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10章17節)。 私たちは、主のことばを聞くことによってのみ真の信仰を持つことができるのです。 三、主のことばを聞くことの祝福 ペテロは、五旬節の日に聖霊に満たされ、聖霊の降臨は、「神は言われる。終わりの日に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたがたの息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る」(使徒2章17節)というヨエルの預言の成就であると説教しました。 「幻」や「夢」とは何でしょうか。 1.「主のことばはまれにしかなく、幻も示されなかった」(第一サムエル3章1節)、 2.「主であるわたしは、幻の中でその者にわたしを知らせ、夢の中でその者に語る」(民数記12章6節)、 3.「アモツの子イザヤの幻」(イザヤ1章1節)、 4.「幻がなければ、民はほしいままにふるまう」(箴言29章18節、文語訳は黙示すなわち啓示)。 「幻」や「夢」は、神の啓示、すなわち神のことばのことです。 イエスが真の神でありながら真の人としてこの世にお生まれになったのは、十字架の死と復活によって「罪のきよめを成し遂げて……大能者の右の座に着かれ」るためであり(ヘブル1章3節)、それは、すべての人に聖霊を注がれるためでした(使徒2章33節)。 ペテロが御霊に満たされて聖書の真理がわかったように、私たちは、聖霊に満たされることによって神のことばの真理がほんとうの意味においてわかるようになるだけでなく、神と人の前で正しく、聖く、愛に満ちた生涯、すなわち主のみこころにかなった生涯を送ることができます。ですから聖霊に満たされることは、主のことばに満たされ、その主のことばによって生きることなのです。 説教集
2018.10.27
コメント(0)
-
説教要約 1122
「健全な信仰」 2018年10月21日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2012年11月7日放映「神に会う備え」「健全な信仰」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第二、1章3~14節 「神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です」(7節)。 「力と慎みとは両極端である。愛はその中間にあり、両者の結合帯また調和である」(ジョン・ウェスレー著「ウェスレー著作集2新約聖書註解下」新教出版社)。言い換えれば、力に偏れば無謀になり、慎みに偏れば萎縮しますが、愛は、両極端の二つのものを均衡と調和が取れた状態にして、両極端の過ちを防ぐのです。 健全というのは、それ自体は良いものであっても互いに相反する二つのものが均衡(バランス)と調和(ハーモニー)を保っている状態のことを言うのです。 実際生活において私たちは、この健全さに欠けるなら、純粋な動機で物事を行っても極端に走ってしまうため、自分が失敗したり、他の人に迷惑を掛けたりして、様々な問題が起きてしまいます。神は、私たちに純粋な動機である愛を与えるとともに、均衡と調和の取れた力と慎みを与えてくださるのです。 一、健全な思想や考え方――神の恵みと人間の働きの調和(9節) 9節には、神の恵みと人間の働きとが対照的に記されています。ピリピ人への手紙にも神の側の働きかけと人間の側の救いの達成について記されています(2章12、13節)。 神の恵みは、神の力の表れであり、私たちを高い所に引き上げるものですから、いわば神の理想の方向と言うことができます。これに対して人間の働きは、人間の力の表れであり、神の力がなければ、弱く罪深い人間にとって、それは私たちを低い所に引き下げるものですから、いわば人間の現実の方向と言うことができます。 神は、私たちひとりびとりにふさわしい理想の姿を求められますが、同時に人間にもその人なりの現実の姿というものがあります。ですから私たちは、人間の現実を無視して、神の理想だけを追い求めたり、反対に神の理想を無視して、人間の現実だけを肯定したりしてはなりません。神の理想と人間の現実の両者が均衡と調和を保つ時、私たちは健全な思想や考え方を持つことができるのです。 二、健全な品性や人格――喜びと悲しみとの調和(4節) 4節には喜びと涙、8節と12節には苦しみが記されています。喜びは私たちを高くし、高揚させますが、悲しみは私たちを低くし、謙虚にさせます。しかし何の悲しみもなく、喜びだけが与えられるなら、軽薄になるだけでなく、有頂天になり、ついには高慢にふるまってしまうことでしょう。反対に何の喜びもなく、悲しみだけが与えられるなら、陰気になるだけでなく、失望落胆して、ついには自暴自棄に陥ってしまうことでしょう。 神は、私たちに喜びと悲しみの両方を与えられます(ピリピ1章29節)。ですから私たちは、神から喜びが与えられたなら、遠慮することなく心から感謝することが大切です。また悲しみが与えられたなら、逃避することばかり考えず、神のよしとされる時まで耐え忍ばなければなりません。喜びと悲しみの両者が均衡と調和を保つ時、私たちのうちに健全な品性や人格が形造られるのです。 三、健全な行動や働き――大胆さと注意深さの調和(12節) 12節には神にゆだねて確信した大胆さが、14節には聖霊によってですが、自らを守る注意深さが記されています。ゆだねることは、私たちに確信と大胆さを与え、注意深さは、私たちに勤勉と責任感を与えます。しかし大胆さが行き過ぎるなら、無責任や怠慢や不注意になり、反対に注意深さが行き過ぎるなら、小心や臆病や不信仰になるでしょう。 神にゆだねた大胆さと自らを守る注意深さの両者が均衡と調和を保つ時、私たちは健全な行動と働きをすることができるのです。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.10.20
コメント(0)
-
説教要約 1121
「救いの達成に努めなさい」 2018年10月14日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2012年8月3日放映「キリスト教の信仰」「救いの達成に努めなさい」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、2章12~16節 「恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださるのです」(12、13節)。 真の救いには、常に「恐れおののいて自分の救いの達成に努める」という人のなすべき分と、「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださる」という神のなさる分との両面があります。 しかし、聖書が初めから終わりまで私たちに勧めていることは、「怠ることなく常に目を覚まして励み」、しかも「思い煩うことなく重荷を主に委ねて安息する」ことです。 この「励みつつ安息する」または「安息しつつ励む」ということを可能にする秘訣は、人のなすべき分と神のなさる分とをきちんとわきまえて、前者にのみ心を配り、後者は神に任せることです。しかしこれを反対にするなら、思い煩って焦り、心の安息と気力を失い、怠慢になるのです。 一、神の前になすべきこと 神の前において人間のなすべき分は何でしょうか。このように言われると人はすぐ「あれもしなければ、これもしなければ、あれもしていない、これもしていない」と考えてしまいます。しかし神の前において私たちの果たすべきことは決して多くありません。 聖書全体から学んでみると、第一は、神のことばによって示された罪を悔い改めて神に立ち返る「悔い改め」です。第二は、神のことばを信じて立ち上がる「信仰」です。第三は、神のことばに従う「服従」です。第四は、神のことばに従って神にすべてをささげ、お任せする「献身」です。ほかのことはみな、この四つのことについてくるものであり、私たちがこの四つのことをする時、神は私たちにほかのことをも行わせてくださるのです。 ですから私たちは、この四つのことを果たすことを忘れて、「あれもできていない、これもできていない」と言って、嘆いたり思い煩ったりしてはなりません。この四つのことを果たし、後のことは神に任せて、神が行わせてくださることをしていればよいのです。 二、自分のなすべきこと 人間は、たとえどんなに良いことをしようとも、反対にどんなに悪いことをしようとも、神の前に出られるのは、キリストの十字架のゆえに先の四つの条件を果たす時だけです。これ以外に人間は神の前に立つことはできません。しかし「それでは、さんざん悪いことをして、最後に悔い改めればよいだろう」というのは、その動機と方法において間違っていることは明らかです。 それで自分自身に対して心がけなければならない最も大切なことは、動機の純粋さと方法や手段の正しさです。これこそ人のなすべきことであり、結果は神がよいようにしてくださるのです。 結果は神のなさる分であり(箴言16章33節、21章31節)、人の力ではどうすることもできないことですから、私たちとしては、純粋な動機と正しい方法で物事を行い、結果は神に任せることが必要です。しかし良い結果のみを夢みて、動機の純粋さも方法の正しさも心がけなければ、結果が良くても悪くても、それは私たちをつまずかせ、神のみこころをそこなうことになるのです。 三、ほかの人になすべきこと 私たちは、人に対しても純粋な愛の動機と正しい方法(忍耐と謙遜と知恵)をもって接することが人のなすべき分です。その結果、ほかの人々がどのような態度をとろうが、私たちは、思い煩うことなく、神に委ねて、心を安んじていればよいのです。そして純粋な動機と正しい方法で物事を行う秘訣は、先の四つの条件を果たすことです。 このようにする時、「すべてのことを、つぶやかず、疑わずに行い……非難されるところのない純真な者……傷のない神の子どもとなり……彼らの間で世の光として輝く」ことができるのです(14~16節)。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.10.13
コメント(0)
-
説教要約 1120
「祝福に満ちた神の栄光の福音」 2018年10月7日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2012年7月23日放映「キリスト教の神髄」「祝福に満ちた神の栄光の福音」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第一、1章3~11節 テモテへの手紙の第一の1章3節から11節には、パウロのテモテに対する命令が記されています。その命令を要約するなら、「祝福に満ちた神の、栄光の福音」(11節)を自らが正しく理解し、体験するとともに、人に正しく宣べ伝えるようにということです。 一、福音の正しい理解(3、4節) 福音を正しく理解するためには、真の福音が何であるかを知るとともに、異端や偽福音がどのようなものであるかを知らなければなりません。 異端は、聖書の正しい教えに反するものや非聖書的なものすべての総称です。その代表的なものは、父なる神と子なる神と聖霊なる神は、三つにして一つという三位一体の教理や、キリストは、真の神であるとともに真の人であるという神人両性の教理を信じないものです。またそれは使徒信条を信じないものと言うこともできます。 真の福音は、人はキリストの贖いを信じる信仰によってのみ救われ、その結果、律法を守るようになるというものです(ローマ3章28、31節)。これに対して律法を守ることによって救われるという「律法主義」や、反対に救われた人は律法を守る必要はないという「律法無用主義」また聖書の啓示ではなく、主観によって神と一つになるという「神秘主義」そして目的のためには手段を選ばないという「熱狂主義」などは決して真の福音ではありません。 二、福音の正しい体験(5節) 福音の正しい体験とは、どのようなことでしょうか。パウロは、「この命令は、きよい心と正しい良心と偽りのない信仰とから出て来る愛を目標としています」(5節)と述べていますが、これこそ福音の正しい体験です。 「きよい心」とは、罪という不純物を全く含んでいない交じり気のない純粋な心ということです。また「正しい良心」とは、不正や不義が全くなく、後ろめたさとかやましさがない良心のことです。さらに「偽りのない信仰」とは、演技をしない信仰という意味で、表裏がなく、飾らず、繕わず、変装せずに、ありのままの真実な信仰ということです。 真の愛は、このようなきよい心と正しい良心と偽りのない信仰から出て来るもので、真の福音の体験は、この愛が日毎に深くなっていくことです。この真の愛こそ「きよめ」であり、もし私たちがこれ以外のものを求めるなら、福音から全く外れているのです。 三、福音の正しい実践(6~10節) 最後に福音を正しく実践し、宣教するためには、どうすればよいのでしょうか。そのためには、神の律法の目的と意義を知らなければなりません。 1.律法は、神がどのような方であり、その神のみこころがどのようなものであるかを私たちに教えるものです(出エジプト20章2~17節)。 2.律法は、人間の心を照らし、私たちの罪深さと無力さを教えて、私たちに罪の意識を生じさせるものです(ローマ3章20節)。 3.律法は、人間に救い主の必要を示し、私たちを救い主イエス・キリストのもとに導く養育係の役目を果たすものです(ガラテヤ3章24節)。 メソジストの創始者のジョン・ウェスレーは、神の「律法は、人間に向かって、あきらかにされた神の心である。……あなたがキリストに密着していようとするならば、律法に密着していなさい。かたくそれをつかんでいなさい。離してはならない」と述べています(ウェスレー説教集・中「律法の原形・性質・属性・用法」)。 私たちは、神の律法を学べば学ぶほど神のみこころを知るようになるだけでなく、律法は私たちを神のもとに追いやるとともに、私たちが神のもとから離れないように私たちを神のもとに引き留めてくれるのです。 私たちは、福音を正しく理解しているでしょうか。私たちの福音の体験は、日毎に深くなっているでしょうか。私たちは、福音を正しく宣べ伝えているでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.10.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1