2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年09月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
北京のコンサートホールをN響の演奏で見て・・・。
中国国家大劇院National Centre for the Performing Artshttphttp://www.chncpa.org/ens/●らららクラシックN響北京公演の模様を、放送されていまして、チャイコフスキー5番は、もちろんすごかったですが、ホールのすばらしい風景にも感慨深く見ていました。国家の威信をかけてつくったきっと立派なホールなのだなあと。ウィキペディアには、フランスのシャルルドゴール空港と同じ設計者で、2007年にこけらおとしになったとか。●北京のコンサートホール、私自身駐在していた1995年から1996年にかけて、数少ないコンサートを数少ない情報をもとに2か月に1回ほど行っていましたが、21世紀劇場とか、北京音楽庁とか。人民大会堂とかでもありました。アシュケナージとかアルゲリッチとか、リッカルド・ムーティとか。いろいろ印象に残っています。●http://www.chncpa.org/ens/ycgp/jmxx/2012-02-27/317844.shtml国家大劇場では、ポリーニのコンサートも近々あるようで、東京→北京・・・というように、アジアコンサートツアーを組むアーチストもきっと増えてくるのだろうと感じています。気になるチケットですが、1000RMB(人民元)から200RMB(人民元)のようで、(だいたいのレート1RMB=12円)S席12000円といったところなのでしょうか。わたしが1995年に行ったときのアシュケナージのピアノリサイタルが超S席で200RMB(当時のレートで3000円くらい)でしたので、これだけみれば、5倍くらいに物価は上がっているのかと、20年近く経ちますが、感じることとなりました。
September 30, 2012
コメント(1)
-

美味しい音楽!(所沢ミューズ キューブホール)
http://www.muse-tokorozawa.or.jp/shisetsu/cube_index.htm所沢ミューズは、何度か伺ったことありますが、大ホールでピアニストのコンサートを聴くところだとばかり思っていました。大ホール アークホール、中ホール マーキーホール、小ホール キューブホールと3つホールがあり、自分が小ホールで弾くということになりました。いろいろご尽力いただくかたのなかに、自分がいることを実感しました。●今日は、食欲の秋・・・・という季節にぴったりの、「美味しい音楽!」というものがテーマとなり、とても面白いコンセプトでありました。第1部 宴の始まり前口上 サティ 食欲のそそらないコラールモーツァルト 4手のためのピアノソナタ ハ長調 K.521より第1楽章シューマン 子供の情景より 炉辺にて・木馬の騎士ドビュッシー 前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女・アナカプリの丘ファリャ クロード・ドビュッシーの墓標銘のための賛歌ドビュッシー 前奏曲第2巻より ヴィーノの門セヴラック 古いオルゴールが聞こえるときジャコブ・ダルディアン ピアノのための小品スクリャービン 練習曲 Op.42-4、Op.42-5第2部 オードブルナポリターナ・メドレー勿忘草(クルティス)、さらばナポリ(コットラウ)、遥かなるサンタルチア(マリオ)、マリア・マリ(カプア)、チリビンビン(ペスタロッツァ)ウェーバー 舞台への勧誘アルベニス タンゴリスト 小人のおどりバッハ イギリス組曲 第3番 プレリュードアナトリー・アレクサンドロフ 2つの小品 Op.3 <ノクターン><ワルツ> 第3部 メインディッシュサティ 干からびた胎児より 「ナマコの胎児」「無柄眼類の胎児」「柄眼類の胎児」ラヴェル 鏡より 「悲しい鳥」「道化師の朝の歌」クープラン うなぎ ティク・トク・・ショックブラームス 6つのピアノ小品集 Op.118 No.1,No.2,No.4ラフマニノフ 前奏曲 Op.23-6, Op.23-12ロッシーニ ロマンチックな挽肉、 やれ、さやえんどう第4部 デザートショパン エチュード Op.10-1ドビュッシー 喜びの島湯山昭 「お菓子の世界」より、 シュークリーム、ソフトクリーム、どうしてふとるのかしら、 チョコバー、バウムクーヘン ショートケーキ、鬼あられ、ポップコーン、金平糖、甘納豆、 終曲ーお菓子の行進曲お口直しサティ アーモンド入りのチョコレートとワルツ (朗読付き)●ほんようにおなかいっぱいになりました。オードブルはオードブルで、メインディッシュはやはりメインディッシュで、デザートはお菓子の曲でいっぱいで、よかったです。プログラム構成がやっぱりいいのでしょうね。ここに至るまでのプロセスも含めて本当に感謝します。ドビュッシーは響きを楽しめて、よかったです。本当にいいホールですね。関係者のみなさまありがとうございました。
September 29, 2012
コメント(200)
-

ノアの2階
http://www.grandpiano.jp/ikebukuro.html会社がおわってから、ノアに行って1時間ピアノの練習しました。ちょっと1杯、ショットバーにいくような感覚なのでしょうか。そんな感じもしました。明日は、ピアノをまた弾く日、シューマンとドビュッシーの組み合わせは初めての日。木馬の騎士と亜麻色の髪の乙女はいっしょに弾いたら、どんなになるのでしょう。楽しみにして、がんばります。
September 28, 2012
コメント(2)
-

ぶらあぼ10月の中にあった浜松国際ピアノコンクールの小冊子。
第8回 浜松国際ピアノコンクールhttp://www.hipic.jp/今年11月に開催されます。ぶらあぼ10月号の中に冊子があり、かなり詳しく広告というか説明がありました。1991年に浜松市制80周年を記念して国際的文化事業と3年ごとに開催。8回目になるので、20年以上経つことになり、ピアニストも興味ありますが、審査委員長が日本人ということもあり、このことも興味持ちます。審査委員長の変遷第1回(1991年)安川加寿子第2回(1994年)小林仁第3回(1997年)中村紘子第4回(2000年)中村紘子第5回(2003年)中村紘子第6回(2006年)中村紘子第7回(2009年)中村紘子第8回(2012年)海老彰子審査員の顔ぶれは、第1回はダン・タイ・ソン、クラウス・シルデとかコンサート聴きにいったことのあるピアニストも名を連ねたりしています。その他、第2回・第5回は、ジャック・ルヴィエ、第3回はステファンスカ、第4回は、野平一郎 第6回は、ミシェル・ベロフ、演奏聴いたことあるピアニストの名前があったりします。http://www.hipic.jp/hipic/history/(第1回から第7回までの詳細が記載されています)今年は、審査委員長が変わるので、方向性とかも軌道修正されるのでしょうか。ショパンコンクールに2005年に優勝したブレハッチが2003年に浜松で優勝しているのですから、ひょっとしたら、そういうピアニストが現れるのかもしれません。BGM:ショパン国際ピアノコンクール(2005) 優勝者リサイタル(pf:ブレハッチ)http://www.youtube.com/watch?v=L28aSoUfp6Q30分以上ありますが、楽しめます・・・・。
September 27, 2012
コメント(200)
-
銀座4丁目のCDショップの散策・・・。
そういえば、銀座4丁目のCDショップに最近足が遠のいていたと思い、閉店時間までまだ時間があるようだったので、眺めていました。さっと眺めて目についたのが、ポリーニのショパンの24の前奏曲。若かりしころの写真のCDと最近の新譜と。録音しなおしたらしいです。ユンディ・リーのCDはベートーヴェンの3台ソナタ。ショパンとかシューマンの演奏とかしか知らないので、興味持ちました。庄司沙綾香のベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ7番・8番渋い組み合わせなので、聴いてみたくなりました。ローラン・エマールのドビュッシー 前奏曲集第1巻第2巻レコ芸特選盤ということでサンプルCD聴けました。時間なかったので、自分が練習している音と香りとアナカプリと亜麻色とミンストレルを聴いていました。音がまろやかであくせくしていない演奏が気に入ってしまいました。毎月1回くらい、何も買わなくても、ぐるっと一周することをライフワークにできたらいいなあと、あらためて感じました。 BGM:ブラームス ヴァイオリン協奏曲 Op.77 第3楽章(vn;庄司沙綾香)http://www.youtube.com/watch?v=SoeLJlnhNz0秋になったら、いつも聴いている感じがしています。この曲とこの楽章。
September 26, 2012
コメント(0)
-

オール・ドビュッシー連弾&2台ピアノコンサートに行きました。(ラーンキ・HakujuHalll)
最近コンサート情報も詳しくなくなったのですが、そのかわりに、こんなのありますがいかがですか?と言ってくださる方が増えたのも事実でありがたかったりします。hakujuhallでのラーンキ夫妻の連弾2台ピアノコンサートは直前になって知りましたが、こんなプログラムはそうそうないでしょうというもの、堪能いたしました。● デシュー・ラーンキ&エディト・クルコン ピアノデュオ・リサイタル (Hakuju Hall) (プログラム)牧神の午後の前奏曲 (モーリス・ラヴェル編 4手)6つの古代碑銘(4手) 第1曲 夏の風の神、パンに祈るために 第2曲 無名の墓のために 第3曲 夜が幸いであるために 第4曲 カスタネットを持つ舞姫のために 第5曲 エジプトの女のために 第6曲 朝の雨に感謝するために小組曲 第1曲 小舟にて 第2曲 行列 第3曲 メヌエット 第4曲 バレエ**白と黒で (2台) 第1曲 無我夢中で 第2曲 ゆるやかに、鎮痛に 第3曲 スケルツァンドリンダラハ (2台) 夜想曲 (モーリス・ラヴェル編 2台) 第1曲 雲 第2曲 祭り 第3曲 シレーヌ●ドビュッシーイヤーだからというのは、確かにあるかもしれません。ふわっとした輝いた音色での連弾や2台ピアノがつづき、知らない曲もそこそこあったのですが、うっとり感でいっぱいとなりました。名前しか存じないハンガリーのピアニストだったのですが、ずっとこれからも聴き続けたいです。小組曲の行列の3度で進行していくところ、あの美しさ加減は、耳にやきついております。弾いておられる2人が楽しそうで、仲睦まじい感じがいっぱいで、これも間近で見れてよかったです。
September 25, 2012
コメント(200)
-

らららクラシック♪で食欲の秋を堪能しました。
http://www.nhk.or.jp/lalala/ベートーヴェン フィデリオ序曲のエピソード、ワインのみすぎて、初演までに序曲の作曲ができなかったこと。特におもしろかったです。ロッシーニ、ロマンチックなひき肉という曲があるのですね。奥が深いです。シューマン、献呈(ミルテの花)ピアノの曲としてでなく、ドイツリートとして聴けてうれしかったです。バッハ、コーヒーカンタータ。いまでいうCMソングだという解説には、うなずけました。コーヒーがこんなに高価な飲み物だったとは、知りませんでした。ヴィヴァルディ、「秋」。収穫の時期にこの音楽はいいですね。http://www.youtube.com/watch?v=GIzBQA2F0E8&feature=related● 今度の週末は、こういうタイトルで、ピアノの会があって少し楽しみにしています。お菓子の曲弾いてくださる方の演奏もあったりします。わたしは美味しい曲が弾けるものをもちあわせていないので、シチュエーションをつけて、お話しにして弾くことにしました。「炉辺で木馬の騎士が亜麻色の髪の乙女と仲良くなってアナカプリの丘へ出かけて美味しいものを食べる」という設定で弾いてみます・・・・。強引な設定がどうなるかわかりませんが、とりあえずシューマンとドビュッシーの小品をかき集めてがんばります。
September 23, 2012
コメント(200)
-

スコットホール・べヒシュタイン・第21回ピアノに戯れるの会
東西線の早稲田駅から少し歩いたところ、早稲田大学の近くに、早稲田奉仕園というところがあり、そのなかの講堂(スコットホール)で第21回ピアノに戯れるの会が催され、参加しました。道中、「男なら歌え 早稲田大学グリークラブ」とかの、気合いの入ったポスターを見て、ちょっと楽しい気分にもさせられました。教会のような神聖な場所でピアノを弾かせてもらえるのは主催者の方々のおかげで、天井が高く、独特の響きのするピアノにも触れられてよかったです。夕方から4時間ほど、たくさんの方々のすばらしい演奏に堪能いたしました。私自身、ドビュッシーの前奏曲集から、亜麻色の髪の乙女、ミンストレルの2曲を弾きました。初対面の方も半分くらいいらしたのですが、弾いた曲を通じて、いろいろお話しが弾んだりしたのは、たいへんよかったです。ほとんど人前で弾いたことがない曲と、半年くらい弾き続けている曲を混ぜたときは、いろいろありましたが、いい勉強もさせてもらった感じです。ベヒシュタインのピアノ、なかなか貴重なピアノに触れた気がしています。教会の空間にとてもあっていて、気に入ってしまいました。BGM:ベートーヴェン ピアノソナタ第30番 Op.109 (pf:ペライア)http://www.youtube.com/watch?v=KGn39MXDVDo
September 23, 2012
コメント(2)
-
都電の15番
http://www.riken.go.jp/r-navi/trivia/011/r-map.html日本橋の上にまだ首都高がかかっていなかったころの、お話しを偶然伺いました。昭和30年少し前のこと・・・。茅場町から都電の15番というのが走っていて、それに乗ると、茅場町>日本橋>大手町>九段下>江戸川橋>早稲田>高田馬場に出れて、よく利用する人多かったとのこと。今でいう、東西線と有楽町線の合いの子のような路線。実際に路線図みていたら楽しくなりました。今日は早稲田のあたりに出かける予定ですが、都電の15番があれば、乗り換えなしで行ける箇所なのかと眺めていて面白くなりました。BGM: モーツァルト ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」 K537 第2楽章 (ピアノ:フリードリッヒ・グルダ)http://www.youtube.com/watch?v=llRpSkA5Sys&feature=relmfu久々にこの番号の協奏曲聴きましたが、いいですね。
September 22, 2012
コメント(0)
-
116年ぶり秋分の日9月22日
わざわざ土曜日を祝日にしなくてもいいのにと思いつつ、なぜに、今年は9月22日が秋分の日なのだろうと疑問におもっていました。http://mainichi.jp/opinion/news/20120920ddm003070151000c.html興味深い回答がありました。秋分の日=「太陽が秋分点を通過する瞬間を含む日」 ↓↓2011年9月23日 午後6時5分2012年9月22日 午後11時49分10分少々おまけしてくれたら、23日になって、次に月曜日も祝日(振替休日だったのに)と、体育の日が東京オリンピックの開会式の10月10日でなく、ハッピーマンデーで、違う日になっているくらいなのに・・・と屁理屈を言ってもしょうがないのですが、ついそんなことを考えてしまいました。● BGM:ウェーバー 狩人の合唱 (Hunter’s Chorus)http://www.youtube.com/watch?v=DXGTIHeJ8QQ&feature=related子供のころに家にレコードがあって、好きで聴いていました。ドレスデンの街並みの旅番組で聞こえてきて、とてもうれしかったです。
September 20, 2012
コメント(0)
-
日の入り17時43分
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/最近夕方暗くなるのが早くなったと思って、国立天文台のページで時間を見てみました。17時43分。その少し前にかかっていた虹が今日はきれいでした。写真を撮ろうかとおもったのですが、バスが着たので乗りました。この週末から3週間続いて、ピアノを弾くことになっているので、(早稲田/所沢/名古屋)少しの時間でも練習しようかとおもっています。それらが終わったら、少し時間を空けてということになるので、またゼロから練習する曲をみつけたりしながら、2012→2013に向かいたいですね。それにしても今年は時間が経つのが早く感じます。いいことだと思うことにします。BGM: Over The Rainbowhttp://www.youtube.com/watch?v=mKlzETes6L0
September 19, 2012
コメント(0)
-
東京アメッシュ見ています!!
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/東京アメッシュ見ています!!こういう天気の変わり目の日にしかみないですけど、会社でも家でも重宝しています。これを考えた水道局の方はえらいです。 BGM: ドビュッシー 雨の庭http://www.youtube.com/watch?v=QH2ZsZ0rwxI
September 18, 2012
コメント(200)
-
第2回ショパンアマチュア国際ピアノコンクール(ワルシャワ) Result
http://konkurs.amator.chopin.pl/index.php?DOC=zakwalifikowani_IIIネットで眺めていましたら、日本人2位、3位。といいますか、自分がピアノ再開したころ、日本のアマコン(たしか第5回だったとおもいますが)優勝されたあと、何かのきっかけから、いろいろお話しするようになった方と、ソニーピアノの会で活躍されていて、企業人のかたで趣味でピアノされている方と。私自身、10年来励みにしている方と、ということでうれしくなりました。ポーランドの本国でピアノ演奏されても外国の方に感銘うける演奏をきっとされたのだろうということで、またいろいろなことお伺いしたいです。自分が長く通っているピアノ教室でピアノ発表会でいつも一緒にでている方もポーランドまで弾きに行かれたのもよかったなあと思っています。どれだけ練習されていたかということを、伺っているので、いろいろ励みにしたいと感じております。
September 17, 2012
コメント(200)
-

日本シューマン協会の296回目の例会と渋谷ヒカリエのハチ。
今日は山手線の西側のほうに、ずっといました。 http://schumann.jpn.org/topics.html《 日本シューマン協会 第296回例会 》日 時 : 2012.9月16日(日)午後2時会 場 : スタジオ・ヴィルトゥオージ (新宿区百人町2-16-17アバンティ21)プログラム: 1)ベートーヴェン/ピアノソナタ第23番ヘ短調「熱情」Op.57 ピアノ/清水麻衣子 2)ショパン/バラード第4番ヘ短調Op.52 ピアノ/野口公子 3)シューマン/リーダークライスOp.39 バリトン/嘉山路晴 ピアノ/嘉山淳子第296回という例会の数字は、当日ご説明もいただきましたが、1973年(昭和48年)から40年近くにわたる積み重ねということもあり、大変尊敬いたします。続けることの意義をとても感じました。今日はめったに聴けないリーダークライスの声楽を聴けて、すばらしいバリトンの声に堪能いたしました。また間近でベートーヴェン、ショパンの大曲を聴けて、たいへん有意義でした例会の案内にもありましたが、シューマンの末裔の方との交流があったり、たいへん興味を持ちました。伺えてよかったです。ありがとうございました。●渋谷ヒカリエのハチ。渋谷ヒカリエに、ようやく行くことができました。中身はほとんど知らなかったのですが、8Fに文化的なフロアがあるということで、ハチと館内の表示にもありました。区の設備との融合で、この空間は粋な要素が満載で気に入ってしまいました。人形ギャラリーはめったに見れない展示があってうれしかったです。http://www.hikarie.jp/http://www.hikarie8.com/home.shtml川本喜八郎人形ギャラリーhttp://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kihachiro_gallery.htmlhttp://www.shibukei.com/headline/8556/渋谷ヒカリエの地下3Fには、地下鉄副都心線が乗り入れしていますが、もうすぐ東横線もここが駅になるようです。にぎわいも増すのでしょうね。以前、半蔵門線で広告していたHikarie。オープンしてもうすぐ半年になります。(東急文化会館の跡地です) BGM:ショパン バラード第4番 Op.58 (pf:ポリーニ)http://www.youtube.com/watch?v=f3nLd4eaRKo
September 16, 2012
コメント(7)
-

有楽町の駅前で大演説会を聴く。。。
今使っている眼鏡の枠がおかしくなったという理由で銀座界隈に出かけたのですが、出かけたタイミングが良すぎたのか、有楽町の駅前で演説会をやっていました。自民党総裁選挙の立候補者の5人の演説、1人10分ということで。せっかくなので、聴いていました。それにしても若い人たちが熱心に聴いている人多く、関心を持っている人の多さを感じました。いくら有楽町の駅前でもこの人数をくぎ付けにするくらいのインパクトはあったかとも思います。テレビで編集された一部のものより、フィルターを通さず、きちんと聴くのは、スポーツでもコンサートでも、ほかでも私自身大切にしているので、これはこれでよかったと思います。北海道選出議員かと思えば日比谷高校出身の方だったり、知らないこともわかりました。元総理大臣もいれば、元防衛大臣が2人、元外務大臣も2人いたり、含蓄深いことばもありました。演説のテンポのいい方とか、間の取り方のいい演説をを聴くと、いろいろ勉強になることもあります。新聞やマスコミの報道をみて、政治家は・・・・なんとかかんとかというのは簡単だけど、精一杯この国のためにと思っておられることはよくわかりましたので、すこしでもいい方向に向かいますよう、お祈りしたいと思います。ビルに囲まれてほどよい広さで、ここをセレクトした裏方の方は、ナイスチョイスをしたと感じました。BGM: ワーグナー タンホイザー序曲 (ショルティ指揮 シカゴ交響楽団)http://www.youtube.com/watch?v=OomkOrOl8WM
September 15, 2012
コメント(0)
-

東京駅構内、あたり一面の東急ハンズ広告//クララシューマンの誕生日の日に。
東京駅の中央線ホームから降りて、八重洲中央口に出るまで。いわゆる中央コンコースの通り、あたり一面に、全部、東急ハンズの広告が。圧巻でした。明日(9/14)オープン。大丸東京店のなか、8F,9F,10F。あまりにもきれいにそろっていて、気合いの入り具合に、ちょっと感動しました。デパートの既存店のなかに、入り込むのは、他でもありますが、楽しみであったりします。●クララ・シューマン、9月13日に193回目の誕生日ということで、WEB上でにぎわっていたみたいです。はじめてドイツを旅行した時、100マルク紙幣の肖像がこの方で、あらためてその存在を知ったわけですが、ピアノの譜めくりストを頼むお金がなく、(その当時はそれが通例だったそうです)全部覚えて弾いたおかげで、暗譜することが、そのあとの流れになったとか、19世紀の音楽普及には絶大なる貢献をしたピアニストであり、作曲家シューマンの夫人だったのだと思います。21歳だった1841年の誕生日に、ロベルト・シューマンからプレゼントされた曲がこの交響曲第4番(当初は2番でしたが、のちに書き換えて出版したため4番という扱いになっているとか)それにしても、新婚早々の誕生日プレゼントが交響曲で3週間ほどで仕上げたとか、この気合いの入り方がわたしにはたまりません。この交響曲好きなので、6月にもNHKホールで聴いたりしました。ずいぶん前になりますが、ザルツブルク音楽祭でも演目であって祝祭大劇場で聴いたこと、どしゃぶりの雨の中出向いた日だったということもありますがとてもよく覚えています。BGM: シューマン 交響曲第4番 Op.120 (全曲30分くらいです) ロンドン交響楽団http://www.youtube.com/watch?v=MT1MBEgTw_U&feature=related
September 13, 2012
コメント(200)
-

ベルギーでみたお気に入りのパリのポスター
ブリュッセルの空港で見た、パリまでタリスに乗れば1時間22分で行けるということをひとことで表したポスター(看板)苦肉の策のような感じで、こんなことしたのですが、あちらがそういうことを推進しているようなはなしは、やっぱり行ってみないとわからないと感じた次第です。●ANAも設立60年で、WEBサイトに力を入れている様子。広告の出し方ずいぶん変わってきたものだとおもって眺めています。http://www.youtube.com/ANAGlobalCH●BGM:シューマン 幻想小曲集 Op.12-2 「飛翔」http://www.youtube.com/watch?v=32AhAWKohz4ピアノ:アルトゥール・ルービンシュタイン2-3日前に読んだ村上春樹の本で、ルービンシュタインのシューマンの演奏のこと絶賛していました。この曲、いかにもがんばって弾いています・・・という演奏によくであいますが、流暢な演奏にちょっとぐらっときました。本質的なところをたくさん感じるとこんなすばらしい演奏になるのですね。
September 12, 2012
コメント(0)
-
ポーランドでピアノ弾かれる方応援します。(第2回ショパンアマチュアピアノ国際コンクール)
明日から、ポーランドで、ショパンアマチュアピアノコンクールが催されるようです。 休みも十分とれて、ゆとりがないと、とてもできませんが、テープ審査もクリアしないとこの舞台にはたてないことを知っているので本当に尊敬いたします。スケジュールhttp://konkurs.amator.chopin.pl/kalendarium.php規定http://konkurs.amator.chopin.pl/regulamin.phpコンペティターhttp://konkurs.amator.chopin.pl/index.php?DOC=Zakwalifikowani日本人は出場者40名中9名、うち4人は顔と名前が一致する方。いろいろあやかりたいことがいっぱいありますが、すばらしい演奏をされたらと思っております。BGM: ショパン バラード第3番 Op.47 (ピアノ:ラフマニノフ)http://www.youtube.com/watch?v=zl-HM_38YYg&feature=fvst
September 11, 2012
コメント(145)
-
音楽評論としての村上春樹、プーランク編は面白かった。
「意味がなければスイングはない」http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784167502096という音楽評論のエッセイは家にあったはずだったのですが、行方不明になってしまっていました。でもどっかにないかなあとずっと頭の隅に残っていました。ピアノのレッスンでプーランクのことをはじめたばかりですが、レッスンの帰りに22時過ぎても空いている小さな本屋さんで、上記の文庫本を見つけたら、帰りの地下鉄で読んでみたくなりました。ジャズのことが多いのですが、シューベルトとプーランクは単独で章立てであり、「日曜日の朝のフランシス・プーランク」という章を一気に読んでいたら、村上ワールドにすっかりはまってしまいました。ロンドンでダンスダンスダンスという著書を執筆のころ、毎日コンサートに出かけておられたらしく、ニューヨークとロンドンの客層、雰囲気、芸術を愉しむにあたってのありようの比較とか、朝に小さなホールで聴いたプーランクのこととか、アナログで聴きたいとか、プーランクとホロヴィッツは5つほどしか年が離れていなく、若いころ演奏会に取り上げていたとか。内田光子とかアルゲリッチとかが弾いたらどうなるのか、聴きたいとか。前に読んだときは、シューベルトのところしか、目がいかなかったのですが、実際、譜読みであれ、音をだしたあと、こんな世界の文章を読んで、読み終わったあたりで、自宅の最寄駅について・・・。なんておしゃれにと思いました。携帯電話もほったらかしにして、アナログの世界に浸るのもいいですね。BGM: プーランク 2台のピアノのための協奏曲 第1楽章http://www.youtube.com/watch?v=cC4kJiTHTtQ
September 10, 2012
コメント(200)
-
ウィーン国立歌劇場のコンサートがあるらしい。。。
http://wien2012.jp/index.htmlチケットが高いことがわかっているのですが、案内を見て、錚々たるメンバーが来て、引っ越し公演をしたら、いくらくらいの経費がかかるのだろうと、考えてみたくなります。日本はやはり遠い国なのだとも思ってしまいます。●ウィーンのフォルクスオーパーというオーケストラに知り合いの日本人ヴァイオリニストが団員でいるのですが、産休になったら3年休めるということを伺いました。才能のある方は働きやすいように、サポートされている国のことを尊敬してしまいます。日本ではオーケストラを減らすなど行っている某地方がありますが、この待遇のちがいはなぜ???と、根本的な文化に対する理解の差を感じずにはいられませんでした。何が豊かなのかどうなのかは、人それぞれ、国それぞれの価値感もありますが、なんでもかんでも費用対効果とかごく一部のものさしで、芸術文化スポーツなどを考えるのはすくなくとも自分は言いたくないです。そのように今日は強く思いました。●BGM: シューベルト 岩の上の羊飼い D965 (Op.post 129) (ソプラノ:エディタ・グルべローヴァ)http://www.youtube.com/watch?v=ojFA6nYl70s今回のウィーン国立歌劇場の公演で、グルベローヴァが日本に来るのが今回で最後になると、どこかに書いてありました。シューベルトの この最後の歌曲といわれる作品は、10年以上前、コンサートで聴いて、とても感動した曲です。そのことをちょっと思い出しました。
September 9, 2012
コメント(2)
-

オルセー美術館の時計台と時代考証と歴史年表をひもといて。
オルセー美術館のなかにある時計は、トレードマークになっている感じで記念品売り場にもずいぶんありました。フランスの大きな美術館がどうやってわけられているのか、以前にも調べたことがありますが、もう一度見直してみました。単に19世紀のころの展示がオルセー美術館ということではなく、はっきり区切りの目安があるということは、興味深いです。ルーブル美術館 -1848(二月革命)オルセー美術館 1848-1914(第一次世界大戦)ポンピドゥー・センター 1914- 時代背景を知っていると、眺めていてもより楽しいものだと感じるようになりました。●他に興味のある、音楽の歴史、日本史とならべてみることにしました。 バッハ 1685-1750モーツァルト 1756-1791シューベルト 1797-1828ショパン 1810-1849ドビュッシー 1862-1918プーランク 1899-1963徳川吉宗 1684-1751ペリー 1794-1858坂本竜馬 1836-1867伊藤博文 1841-1909明治天皇 1852-1912吉田茂 1878-1967似たような年次のものがわかると面白いものですね。時代が20世紀に近づけばイメージわきやすいです。今日はおもしろそうなドラマがあるので、見てみようと思っています。http://www.nhk.or.jp/dodra/dodrasp/about/index11.html BGM: スクリャービン エチュード Op.42-5 (pf:ホロヴィッツ)http://www.youtube.com/watch?v=xudZ3J4EeoQ
September 8, 2012
コメント(200)
-

キノコの木。
残暑が続くし、今日は夕方から雨だし、すっきりしないなあと思っていましたが、日本橋のデパートの入り口にある、いつも見ている大きな木にキノコがいて、なんだかとてもほっとさせられました。たった3秒であっと思わせるガーデニング担当の方、尊敬いたします。●出だしの10秒、最初の10小節・・・・、そこで聴いてもらえるようにならないと・・・・とか、相当前にいわれましたが、そんなことまで思い出してしまいました。BGM:ショパン バラード第2番 Op.38 (pf:クリスチャン・ツィメルマン)http://www.youtube.com/watch?v=MsoUIBcl7iw言われた曲まで思い出してしまいました・・・。
September 6, 2012
コメント(0)
-

各駅停車・・・来年はどちらへ。
日本の電車にはない色使いをしているものをみると、無条件にシャッターをきってしまったりします。ベルギーの空港から、街中へ走る電車はてんでばらばら。でも一定時間には必ず。そんなポリシーが気に入ったりしました。このきれいな国は、チョコレートとビールとワッフルだけで生業をなしているわけでなく、どんな国なのだろうと、母国語がなく、公用語が隣の国と隣の国の2か国語という合理性において、いろいろ感じることとなりました。●旅を終えたら、ピアノのレパートリーとかは、モデルチェンジに入る時期だったりします。去年もワイマール・ブダペストと旅をしてリストのウィーンの夜会を弾いていたのに、突然9月半ばに入って、ドビュッシーの練習するということになったりしました。今年は、旅から帰ってきてから楽譜屋さんがあいている間に会社を出ることができず、時差ボケどころではない感じでしたが、やっと夏休みの分を取り戻しつつ、モデルチェンジしようかと模索することをはじめました。ベートーヴェンでもショパンでもなく。この2人はかなり離れてみようとも思ったりしました。それにしても生誕●●年、没後●●年ということで、2006年以降追いかけていますが、思った以上にまんべんなくというか、自分のツボにはまる作品ともであったり、勉強になったり、旅をしてよけいに興味をもったり、必ずしも出向いているわけではないですが、実際の空気を感じるところに少しでもいることができたのはよかったです。ここ2年、リスト・ドビュッシーとほとんど手をだしたことのない作曲家は、弾いてよかったです。独特のピアニズムのある作品と、いわゆるドイツロマン派では、なかった音色の数々で、試行錯誤もありますが、いろいろと教えていただいたりしながら、変化していったように思います。ピアニシモでレジェロで、でもはっきり弾く、出したい音をはっきりさせる・・・そんなことは練習もまた興味深いものでした。1人の作曲家にちょっとこだわって向き合う時間を持てるのも、いいかもしれません。来年は、ずっとではないとおもいますが、自分が生まれるほんの少し前まで生きていたプーランクの作品を少し、勉強してみようかなあと思いはじめました。せっかくパリの街並みも見たことだしというのもありますし、没後50年が2013ということもありますが・・・。●このブログでは、備忘録がわりにとりあえず、 何を聴いて、何を弾いて、何を習ったかということをメモしているページがあります。最近全部かいていたらきりがないので、春・夏・秋・・・という感じですが。、http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/3001/1998年にピアノ再開して、来年で15年なのですね。ちっとも上達はしませんが、人の輪が増え続けているのには本当に感謝しないといけません。BGM:プーランク ノクターン1番http://www.youtube.com/watch?v=MRs5ctCBQRIブーニンのCDにはいっていて、この曲がはじめて存在しった曲です。アンコールで弾くにはおしゃれだなあとおもったのが第一印象です。
September 5, 2012
コメント(4)
-
ドラエモン 生誕ー100歳のたんじょうび
ドラえもんが2112年9月3日トーキョーマツシバロボット工場で製造されたとどこかに書いてありました。身長:129.3cm体重:129.3kgパワー:129.3馬力(成人男性約1293人分の力)頭の周り:129.3cm胸囲:129.3cm座高:100cm足の長さ:129.3mmネズミを見たときに飛び上がる高さ:129.3cmネズミを見たときに逃げる速さ:時速129.3km(普段は50mを15秒=時速12kmだが、例外的にアニメ第2作第2作『日食を見よう』ではある程度高空から大気圏を越えた宇宙空間までを数秒で走り切ったこともある)身長について、のび太を見下ろさない高さという設定にちょっと感動してしまいました。●自分自身かつては166cm66kgとさっと書いて、生命保険会社のおばさんを笑わせたことありますが、166cm166kgにはなりたくないとこれを見て思ってしまいました。2100年には東京の人口が半減すると、コンビニで見た新聞の見出し1面がどこかだったのをつい最近見ました。通勤電車は夏休みのような電車になるのでしょうが、ちょっとこれもさびしい感じもします。2112年には、このあいだ生誕250年とモーツァルトがいっていたように、ドビュッシーも生誕250年にたどりつくのかと。BGM ドビュッシー ベルガマスク組曲より「パスピエ」http://www.youtube.com/watch?v=zjtY8QEIkLQ
September 3, 2012
コメント(0)
-
ポピュラークラシックのコンサートを聴いて。
週末の9/1、東京建物八重洲ホールというところで、素敵な音楽を聴いていました。http://www.tatemono.com/hall/ソプラノとサロンオーケストラによる懐かしく美しい名曲ソプラノ:駒井ゆり子アンサンブル:アリオン四つ葉のクローバー嘆きのセレナーデセレナーデ金婚式出船金髪のジェニーダニューブ河の漣慕情いそしぎジェルソミーナセ・ジ・ボンケ・セラ・セラひまわり踊り明かそう●アンコールも3曲ほどあって、とても楽しめました。とても有名な映画音楽やらシャンソンやら、久しく聴いていなかった子供のころに聴いたクラシック音楽聴きました。1950年代1960年代の名曲というのは、ひょっとして、あまり語られることが少なくなったのではと、ものすごく感じました。クラシックに限らず、時代の変わり目、流れ、伝わるものとそうでないものも、気づかないままにあるかもしれない。ということを。自分自身の場合、両親がレコードを買っていたから。深夜放送とかジェットストリームなどの番組で静かなBGMをよく聴いていたこと。などから8割くらいは知っていたのかもしれません。音楽の教科書が変わったから。レコード鑑賞の曲目が変わったから。LPからCDに変わって、入っている曲が変わったから。 ビートルズ以前とそれ以降で音楽の好みが変わったから。気が付かないまま、変わっていることがあるからかもしれません。そういう意味ではとても楽しむ以外にも意義があるようなコンサートのように思え、とてもよかったです。またいろいろとこういった音楽聴きたいです。BGM:ドナウ川のさざなみ (イヴァセヴィッチ)http://www.youtube.com/watch?v=JPX_1nowjSI&feature=relatedこの曲もそうかもしれません。幼稚園のとき、家に33回転のレコードがなぜかありました。スケーターズワルツと一緒にありました。レコード鑑賞でも聴いたような気がします。いまCDショップでこの曲さがすのは予想以上に苦労するかもしれません。小学校に入ったばかりの音楽の当時の教科書思い出してみました。ストラヴィンスキーがぎりぎり生きていて、いろいろな作曲家ありましたが・・・、マーラー、プーランクなど、こういった作曲家は大人になってから知りました。いいものはもっと残るように、忘れられないようにと、なんかあってもいいのかもしれません。そんな風におもってしまいました。
September 2, 2012
コメント(3)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-
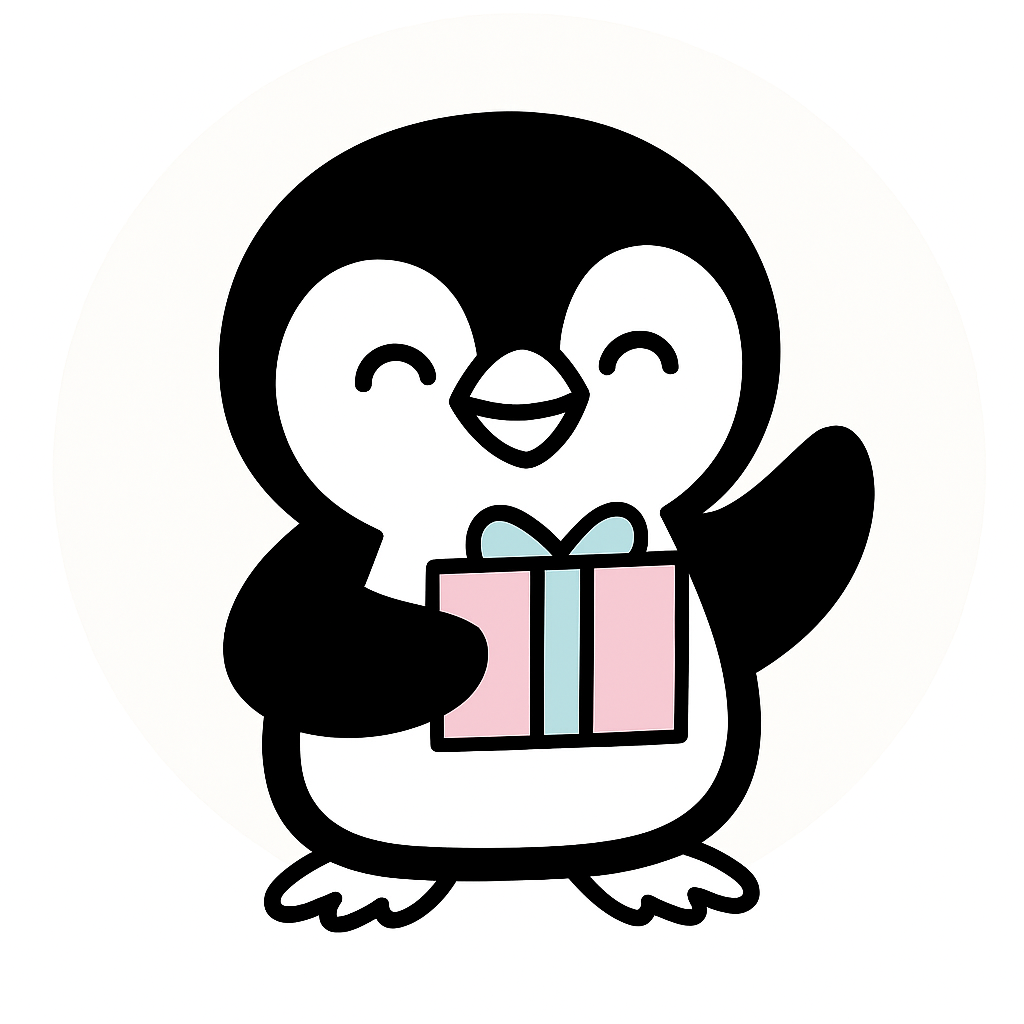
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-







