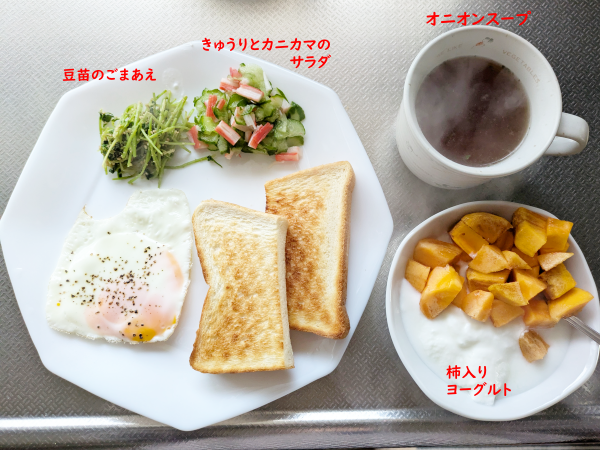2011年06月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
プレゼンとチェア
発表と司会を終えました。なんとか乗り切りました。最初に時間がタイトで4人で90分だから1人18分の持ち時間で,その後議論の時間を2~3分設けると提案しました。そのおかげですべての発表が時間内に収まりました。司会で困るのは,質問が出なかったときに何か質問をしなきゃいけないことです。最初の発表では質問をしました。それから,2番目の発表は自分自身で司会も兼ねているので自分で質問を求めました。日本ではありえないなんとも不思議な感覚です。聴衆と合わせて10人弱と少なかったのが残念でしたが,発表者自身が来ないこともあるし,司会がいないこともよくあるみたいなのでまだ恵まれていたかもしれません。このようないきなりの司会の経験は,ほかの先生方も経験されていました。そういえば日本の学会ですら司会をしたことなかった。
2011.06.30
コメント(0)
-
おもてなし
韓国学会は今日から本番です。昨晩からの本降りの雨のせいで徒歩10分程度なのにものすごく遠く感じました。折り畳みの傘も明らかに役立たず。フロントでビニール傘を売ってくれたので助かりました。それでも会場に着いた時にはズボンがびしょ濡れになりました。レジストレーションを済ませてお昼のランチョンから参加。発表会場と昼食会場も結構離れていてモールの中を行ったり来たりしました。アジア最大級といわれるモールを会場にするのはいいけれど,お互いの部屋が近くないと案内も大変です。ランチョンも豪華でした。昼からワインも出ました。ここまでまだまともに発表を聞かずにご飯ばかり食べています。それでもランチョンの前には基調講演がありました。そして映像つきで今後Economic geographyが果たさなければならない役割を世界が抱える南北格差や環境問題にスポットを当てて紹介していました。後援には世界銀行がついていて,担当者も講演しました。ソウル市副市長もあいさつしました。クラーク大学のプレジデントもいらっしゃってました。錚々たるメンバーに豪華なランチ。これでもかというぐらいおもてなしの心を感じました。
2011.06.29
コメント(0)
-

韓国学会でウェルカムディナー
ソウルに来てます。COEXで行われている学会。前夜である今日はウェルカムディナーでした。豪華な食事がフルコースで出ました。こんなおもてなしを最初から受けていいのだろうかという気分です。初対面の研究者とも名刺交換できておもしろかったです。明日からいよいよ学会発表が始まります。
2011.06.28
コメント(0)
-
明日から韓国
明日から韓国・ソウルです。韓国ではカタツムリBBクリームが流行っているようです。お土産に考えています。よく考えるとお菓子のお土産がなかなか浮かばない。。韓国のりなどはすぐに浮かびますが。2年ぶりですが,今回は観光地としてはマイナー?な江南に行きます。ほとんど観光する暇もない気もしますが,他国の研究者と交流できればと思います。そしてまた無事に帰ってくることが目標です。
2011.06.27
コメント(0)
-

ねこ
久しぶりにお隣の庭に現れたにゃんこを激写。最初は振り向いてくれなかったので喉を鳴らしてみたら振り向いてくれました。クリックすると拡大します。
2011.06.26
コメント(0)
-
ヤマザキ 白いスマイルディッシュ
ヤマザキ春のパン祭り。いつもついつい点数シールを集めてしまいます。今回の白いスマイルディッシュは大きくて使いやすそうだったのでますます。しかし今回の地震で一時休止されていました。それが再開されて6/7で終了。終了までに2枚分(48点)がたまりました。引き換え期間は6/17まででした。うっかり引き換えるのを忘れていました。そして本日あわててデイリーヤマザキに行ってきました。在庫があるのか,あったとしても引き換えに応じてくれるか心配しましたが快くお皿と交換してくれました。これまでのお皿に比べて大きくて炒め物からパスタまでたいていの料理はこのお皿で間に合いそうです。
2011.06.25
コメント(0)
-
ファーストリテイリング:震災対応「首相がブレーキ」 柳井会長兼社長、早期退陣促す
ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は23日、毎日新聞のインタビューに応じ、東日本大震災からの復旧や福島第1原発事故の対応に絡んで「政府が役割を果たしていない。(退陣表明後も居座る)菅(直人)首相は自分がブレーキになっていることを自覚すべきだ」と批判した。個人資産から10億円の義援金を出すなど、被災者支援に力を入れる柳井氏は今の政局優先の政治が我慢ならないようで「(首相が代われば)今よりは(政治は)良くなる」と菅首相の早期退陣を促した。【久田宏、谷多由】 同社は震災後、フリースや肌着など約7億円相当の商品を支援物資として被災地に送った。また、同社のグループとその従業員から計約3億8000万円の義援金を募り、柳井氏個人も10億円の寄付を決めた。 柳井氏は「事業経営とはお客様のため、広く言えば社会のためにやるということ。震災がすべてを破壊し、本当に困っている方がいるので、少しでもお役に立ちたいという気持ちだった」と振り返る。 柳井氏自ら先頭に立って被災地支援に尽力してきただけに、政治の混乱で復旧・復興が遅れかねない現状へ危機感を募らせる。柳井氏は「地方自治体の力では余りある事態なのに、政府が役割を果たしていない」と政府の震災対応を批判。一代でユニクロを育てたベンチャー経営者としての経験を踏まえ、「部下のそれぞれの役割を明確にし、進行をチェックするのがリーダーの仕事。スタンドプレーであっちこっちに飛んで行っても、何も動かない」と、原発や被災地などの現地視察を繰り返す菅首相のリーダーとしての資質に疑問を呈した。 柳井氏は、今国会の会期延長や特例公債法案の成立などを巡り、与党の民主党と自民、公明の野党がいったん3党合意しながら、菅首相が覆した騒動にもふれ、「権力の延命ばかりだ。(首相が代われば、最悪の今よりは(国政は)良くなる」と話した。毎日新聞 2011年6月24日 東京朝刊-----------------------リーダーに求められる資質はなんでしょうか。柳井氏の発言はしごくまっとうです。組織ガバナンスについてリーダーは常に考えなければならない。その大前提として組織の方向性が決まってなければいけないわけですが。そして何より決断と実行のスピードが求められます。一刻を争う事態に対して,どんなに優れたアイデアもタイミングを逃すと効果も半減,的外れになってしまう。そしてそれぞれのポジションにいる部下の役割を明確化してパフォーマンス最大化を目指す。その大前提として組織の方向性,リーダーの事業ビジョンが共有化されていなければならないわけですが。これらができないリーダーはリーダーとしての資質に欠けており,早晩組織全体がつぶれてしまいます。悩ましいのは国のリーダーとしての資質を備えた人が現れていないことです。
2011.06.24
コメント(0)
-
北東アジアの港湾競争、震災きっかけに加速
秋田港では4月から、週5便だった定期コンテナ航路を週7便に増便。従来の韓国・釜山航路に加え、一部は中国・上海まで延伸されるようになった。新潟でも県内の主要港と空港の輸出入が2~3割の伸びを示した。仙台など被災した太平洋側の港湾の機能を日本海側の港がある程度、代替した格好だ。 阪神大震災後に神戸港が低迷し、韓国・釜山港にアジアの主要港の座を奪われたのは復旧に手間取っただけでなく、世界の市場動向への対応や関連産業の勢い、価格やサービスなどの総合力で差をつけられたことが影響したとされる。 港湾をめぐる北東アジアの動きは急だ。韓国だけでなく、中国では大連や天津、連雲港などの港湾都市が競ってインフラ整備を進め、リスク分散のため工場の海外移転を検討する日本企業の誘致にも積極的だ。来年、ウラジオストクでアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を開く極東ロシアではエネルギー輸出や自動車関連の新事業などを見据えた港湾・物流施設の整備が進み、開放が遅れた北朝鮮さえもが中国との協力で日本海側の羅津港周辺(羅先市)で大規模な経済特区の建設に乗り出した。 東北の港湾の復旧・整備には周囲を見渡す幅広い視野と、地域の長期的発展につなげる戦略の策定が不可欠だ。-----------------------------------グローバル競争は震災復興を待ってくれません。阪神大震災の時に神戸港が扱っていた貨物は隣の堺や釜山港などに流れて返ってこなかったといいます。これまでなんとか維持していた国際物流拠点としての地位が今回の震災でますます凋落していきそうな勢いです。アジアの中でコンテナ船の基幹航路ネットワークに生き残るためには,ハードとともにソフト面での整備も重要です。日本の主要港湾のうち,スーパー中枢港湾が決定されました。しかし,この震災を機に東北地方の港湾のあり方を見直さないまま現状の港湾戦略を突き進めて言っていいのでしょうか。見直すとしたらどのような青写真が描けるでしょうか。東北地方というミクロなスケールで見ても,日本海側と太平洋側の港湾間競争がし烈です。日本がグローバルな港湾競争に否応なく対応しなければならない局面では,各港湾の役割をもっと明確化して投資の集中と選択を進める必要がありそうです。
2011.06.23
コメント(0)
-
ヴァンテアン・クルーズ2
本格的にヴァンテアン・クルーズの写真をアップ。乗船口は飛行機搭乗口のようです。船は一番底のDデッキから眺めた風景。奥にスカイツリーが見えます。軽食セット2100円。ボリュームはそれなりにあるしおいしかったです。さらにデザートとコーヒーがつきます。とりあえず食事を済ませて展望デッキへ。レインボーブリッジを下から眺められました。羽田空港の国内線ターミナルに近づくとひっきりなしに飛行機が真上を飛んでいきました。しかしこの日は風が強かった。今度はちょうど飛び立つところ。いってらっしゃい。大井ふ頭のガントリークレーン。なんとも壮観です。東京タワーとスカイツリーを同時に拝めました。平日だけにお客さんは少なくて展望デッキはほとんど貸切状態でした。
2011.06.22
コメント(0)
-

ヴァンテアン・クルーズ
今日は雨の合間をぬってヴァンテアン・クルーズの乗船を体験してきました。東京の竹芝からレインボー・ブリッジをくぐってお台場を抜け,羽田の国際線滑走路付近までを往復します。午前中は雨が降っていましたが,うまい具合に昼間は晴れました。乗船チケットはもらっていたので,ランチタイムに乗船し,軽食セットを追加でオーダーしました。ドイツの海運会社ハパックロイドのコンテナ船と並走したり,レインボー・ブリッジの真下を通ったり,羽田に着陸する飛行機を下から眺めたりとかなりお得な乗船コースでした。写真がみられない方はこちら。とにかく晴れてよかったです。写真アップが間に合わないので詳細は後で。
2011.06.21
コメント(0)
-
父の日は日本酒
越乃寒梅特醸酒 大吟醸を送りました。【醸造元】石本酒造【アルコール分】16度以上17度未満【原材料】米、米麹、焼酎乙【精米歩合】30%【コメント】石本酒造で蒸留し、精製した焼酎乙を使用した最高級酒です。年に2回しか出荷してないそうです。せっかくなので普段は飲まないであろう逸品をチョイス。どんな味でしょう。自分も知りません。
2011.06.20
コメント(2)
-
「健保」初の破綻、好況ドイツでなぜ
「健保」初の破綻、好況ドイツでなぜ 海外とっておき ベルリン支局・菅野幹雄2011/6/19 19:12 年率3%ペースの経済成長を続けるドイツ。「欧州の病人」とも呼ばれた長期不振を抜け、雇用や消費もすこぶる調子がいい。そんな中でひとつ嫌なニュースが市民をざわつかせている。日本の健康保険組合のモデルであるドイツの「疾病金庫」が2007年の制度改革後、初めての経営破綻に追い込まれ、「次はどこか」と疑心暗鬼が広がっているのだ。 疾病金庫は国民の9割近くが入る公的医療保険の中核だ。契約者から保険料を集め、受診時に契約者に代わって医療機関側に医療費を払う機関で、日本の健康保険組合に似ている。地域や企業、職種を単位に4月現在、155の金庫がある。 今年5月、ハンブルクに本部を置き16万8000人の契約者がいる疾病金庫「シティBKK」が事実上の破綻を宣言、7月1日の閉鎖を発表した。集まる保険料と支払う医療費のバランスが崩れて収支が悪化。義務付けられた準備金も積めず、経営改善もできずに資金繰りが行き詰まった。疾病金庫の過剰債務や支払い困難は昨年から公表されていたが、閉鎖に追い込まれるのはシティBKKが初めてだ。 契約者は別の疾病金庫に入り直す権利がある。支払い関係も新しい金庫に円滑に引き継がれ、損をするわけでもない。連邦政府のホームページもシティBKK問題のバナーを設けて平静を呼びかけている。だが、地元メディアの報道では破綻金庫の業務量が膨れあがり、6月末までの引き継ぎが思うように進んでいないとも伝えられる。心配はないと言われても、煩雑な手続きを強いられるのに変わりはない。「20を超す金庫が準備金を積めずにいる」。連邦保険庁は最近、個別名を挙げずに財政が厳しく改革が必要な金庫がさらにあると明かした。しばらく落ち着かない状況が続きそうだ。 ドイツでは基本的に契約者が疾病金庫を自由に選べる。07年の改革で、皆保険を導入するとともに、金庫間の競争を促す仕組みにした。契約者が効率よく給付をする金庫を契約者が選べば保険料が還付される可能性が増し、逆に効率が悪い金庫には追加保険料を払わねばならない恐れも出てくる。シティBKKのような金庫は若い健康な契約者が敬遠する一方、高齢で給付の多い人が残るので財政が一段と悪化、優良な金庫との優劣の差がはっきりしてしまう。疾病金庫の統合や集約なども模索されるが、そう順調ではないようだ。 破綻する金庫がある一方、公的医療保険を総括する基金では今年20億ユーロ近い剰余金が生まれるという。好況で所得水準が上がり、保険料の収入が増えた要因が大きい。 競争を促して勝ち負けをはっきりさせる制度が局所的に混乱を起こしているのは確か。だが全体では、人口の高齢化に合わせて医療保険の収支のバランスを整えないと制度が維持できなくなってしまう。 一部の疾病金庫の破綻は悩ましい現象だが、将来に向けて社会保障の制度全体を改革する試みも止められない。思い切った制度改革に踏み出せない日本にとっても、ドイツの例は考えさせられる例になるのではないか。---------------------ドイツはギルドが発達し職能別の保険組合も発達している。労働者の地位もそれなりに認められてきた経緯があるという。しかし,ここで起きていることはそうした職能別に細かく分かれた保険組合の淘汰と集約のプロセスである。どうしても医療費ニーズの高い高齢者を多く抱える疾病金庫は破たんのリスクが大きい。多くの疾病金庫の中で年齢構成や所得構成にバラつきがでていると,どうしても財政バランスの二極化が生まれる。破たんして疾病金庫同士の競争の中で起きることは何か。どうしても高まる医療費支出を抑えるために,相対的リスクの高い高齢者を被保険者からはずすことです。アメリカではそうして低リスクかつ富裕の若年層が獲得する保険者間の競争が活発です。保険者間の集約は効率的経営のためにはやむを得ない。しかし,そのなかで,高リスクとされる医療ニーズの高い高齢者をどう支えていくのか。どの国においても課題として残されているのではないか。
2011.06.19
コメント(0)
-
福祉ネットワーク―在宅高齢者の今
陸前高田市ではほとんどの医療機関が被災した。十分な医療を受けられないのが現状である。実際にどんな影響があるのか。広田半島ではほとんどの世帯で水道が復旧していない。そのなか診療所の唯一の近江医師が訪問診療を行っている。停電が続いて介護用のベッドが動かせなくなったことによって床ずれが起きている。訪問診療を続けていた20人のうち2人が亡くなった。住み慣れた場所を離れざるを得なくなった高齢者。高齢者は場所がかわるだけでも病気は多くなる。近江医師は地元の医療崩壊を食い止めるために広田診療所に赴任したのは5年前。寝たきりの高齢者がいた場合,家族は真っ暗闇の中,ライフラインが絶たれ避難所にもいけなかったという。1人の診療所の医師によって広田半島の医療は支えられている。家がある,家族がいるということで見過ごされている在宅高齢者が多いと感じる。災害時医療は,避難所医療が主体であって,わずかでも在宅医療が途切れると生命の危機につながる。家族が津波で被災したため,送迎者がおらず,通院ができなくなった在宅高齢者がいる。そうした高齢者に対して,県立陸前高田病院が訪問診療を開始した。チームには医師や看護師だけではなく,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,医療事務員なども同行することに決めた。在宅高齢者にもいろいろなニーズがある。これまでリハビリを行っていたスタッフに依頼して訪問してもらうことにした。被災者の暮らしありきの医療のあり方を考えるヒントとなる。陸前高田の地域在宅医療の取り組みは,被災地復興の重要なポイントである。
2011.06.18
コメント(0)
-

三沢勝衛
戦前の地理学者です。彼自身は諏訪中学で地理学者・教育者として活躍しました。とても参考になったので全文を書き写してみました。教科書は古墳にして,著書は墓場であるが,学会は戦場である。したがって発表論文には,時には誤謬があり,血が出るかもしれないが,生命は脈々と迸っている。心理を愛する学徒よ友よ,活きた知識を求るならば,学会とその機関誌とを斥けてはならない。―三沢勝衛の教え―由来,教育というものは,教えるのではなく学ばせるものである。その学び方を指導するのである。背負って川を渡るのではなく,手を引いて川を渡らせるのである。既成のものを注ぎ込むのではない。構成させるのである。否,創造させるのである。ただ,他人の描いた絵を観照させるだけではない。自分自身で描かせるのである。理解の真底には体得がなければならないのである。それがその人格そのものの中に完全に溶け込んで,人格化されていくところのものでなければならないのである。いつまでも長く生きているものでなければならない。したがって,地理科においても地理的考察力の訓練を重視するのである。すなわち地理的知見の開発だけではない。さらにその性格までも陶治し,自律的に行動しうるようにまで指導する。過分に感情および意志に対してまでも深い交渉を持ちかけていくべきものである。要は魂と魂との接触でなくてはならないのである。否,共鳴でなくてはならないのである。―三沢勝衛「新地理教育論」より―自律的・主体的というのが重要です。上から教えるというのではなく,ともに学ぶ姿勢が教育者にも求められるではないか。さらに,書物だけに頼っていては生きた知識が身につかないとも述べています。現実に起きていることをこの目で確かめ,考察することこそ帰納的考察につながるリアリティをもった議論となります。
2011.06.17
コメント(2)
-

牛丼チェーン店舗数比較
今日の課題は「牛丼チェーンの店舗展開」です。MANDARAという地図ソフトを使います。牛丼業界は寡占化が進み,すき家,吉野家,松屋の3チェーンで大部分のシェアを握っています。それぞれ担当のチェーンを割り当てて都道府県ごとの店舗数を地図化してもらいました。店舗数については各チェーンのウェブサイト上にある店舗検索リンクから地道に数えます。すき家吉野家上位2チェーンの店舗展開を比較すると,すき家の方が地域に偏りがなく,吉野家の方が東京,大阪など人口規模の大きい都市に店舗を集中出店させていることがわかります。これらの地図をみなが簡単に描けるようになるだけでも大きな進歩です。
2011.06.15
コメント(0)
-
一段落
お仕事が一段落しました。といっても具体的成果は何も出ていないのだけれど。それでも目の前の課題を必死になってこなしている毎日はひとまず充実している。自分が使える自由な時間が講義に割かれて限られる。その中でいかに効率的に仕事を片付けていくか。時間の管理の重要性を改めて感じています。予想外に仕事が増えることがよくあります。そういう時に限って締め切りがタイトです。しかし,そうした事態を想定外としていては,予定がくるってしょうがないです。常に予想外の仕事の負担増をある程度「想定」しておくことも大事だと感じます。そして今その想定外の仕事をこなしているのです。
2011.06.14
コメント(0)
-

32型液晶TV
32型液晶TVが3万2800円 震災の影響でテレビはいまが底値2011.05.19 07:00 ありとあらゆる激安品を見てきた流通ジャーナリストで、『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)のコメンテーターとしても知られる金子哲雄氏も「信じられない」と驚愕する事態が家電業界で起きている。それは人気液晶テレビが軒並み大幅値下がりしているといるのだ。 家電はいまが買いどき――その噂を確かめるべく、“家電激戦区”の東京・新宿周辺へ。ヤマダ電機LABI新宿東口館のテレビ売り場に足を踏み入れると、出た! 1年前に発売されたばかりのソニー「ブラビア」32型がなんと3万2800円! 10年前には「1インチ=1万円」といわれていたのが、いまや10分の1の価格となっていた。 金子さんが語る。「私も5月7日に液晶テレビを買ったばかりなんですよ。3月末のエコポイント終了の駆け込み需要を見込んでメーカー各社がたくさんテレビをつくったものの、東日本大震災後の消費自粛による影響で売れ行きがダウン。在庫が余っているので、各店舗で値下げされているんです」 製造コストから見ても原価ギリギリで、いまが底値だ。「7月の完全地デジ移行に向けて、今後アナログテレビから買い替えを進める人が増えてくる。需要が高まれば値下げしなくても売れますから、これから価格が上がる可能性も。まさに“いま”だから安いんです!」(金子さん)※女性セブン2011年6月2日号-------------------------というわけで早速横浜の家電めぐりをしました。ヨドバシカメラとビックカメラを比較しました。東芝レグザ32型に絞っていきましたが,レグザの機種は生産の絞り込みがなされていて,32型は高価格品のZ型と低価格品のA型に二極化しているとのことでした。中間価格帯のR型やH型はもう生産中止しているそうです。録画はすでにもっているブルーレイレコーダでできるので再生専用のA型に絞りました。ビックカメラでは32A1Sが34,800円でした。家の接続環境ではCATVでネット接続しなきゃいけないので,分波器が必要とのこと。追加で一緒に購入しました。届くまで3週間ほどかかります。店員さんにはいろいろと複雑な家の接続環境を説明してしっかり裏録画ができるかどうか確認しました。大変お世話になりました。
2011.06.12
コメント(0)
-
みなと寿司
今日は横浜へ。お昼時に着いたのでまずは腹ごしらえ。東急と京急線の乗り換え口の出口から出ました。すると目の前に1000円寿司ランチの看板が。迷わずに入りました。みなと寿司です。これだけ入っていてお椀+ドリンクで1000円の大漁にぎり。お得感がありました。味もかなりよかったです。ネタが新鮮でした。雨が降っていたのに昼過ぎになってお客さんが続々と入ってきました。コスパのいい店には自然と人が集まってきますね。
2011.06.11
コメント(0)
-
JINS
横浜のJINSでメガネを新調しました。これまで使っていたメガネのレンズは長年使っていただけあって細かい傷が無数についています。薄暗い部屋でかけると曇ってしまいます。度数は同じにしてもらいました。フレームは自分で選んで,レンズと合わせて4990円。なんでこんなに安くできるのか不思議です。しかも出来上がりまで30分でした。かけ心地もよくて気に入ってます。
2011.06.10
コメント(0)
-

復興格差
被災地の漁港では復興格差が生まれています。東日本大震災:発生3カ月 漁港、復興に格差(その1) 石巻の業者、塩釜に移転も 東日本大震災からまもなく3カ月。大被害を受けた岩手や宮城の水産業は復興へ動き出したが、魚の水揚げを再開した漁港がある一方、がれきの撤去も進まず、再開のメドが立たない漁港も多く、“復興格差”が出始めている。国や自治体は漁港集約も検討するが、現場の反発も強い。【永井大介、浜中慎哉】 「塩釜に客(漁船)をとられ、石巻の水産業が廃れてしまう」--。5月27日午後、宮城県石巻市の石巻商工会議所で開かれた「水産復興会議」。100人以上の水産加工業者の間に重苦しい雰囲気が漂った。 県3大漁港の石巻、気仙沼、塩釜。カツオなど200種超が水揚げされる石巻は県内最大、全国3位の水揚げ量を誇った。しかし、震災で状況は一変した。 松島が津波を防いだ塩釜は4月上旬に魚の水揚げを再開。石巻同様、壊滅的な被害を受けた気仙沼も地盤沈下した港をかさ上げし、6月中旬にカツオの水揚げを行う予定だ。 しかし、石巻では港が70センチ以上も地盤沈下。5月末になっても加工会社元社員らが腐敗したサバやサンマの廃棄に追われた。6月中旬に廃棄のメドが立てば、漁協は規模の小さい西港で小型底引き網漁船から水揚げを始めたい考え。石巻魚市場を運営する須能邦雄社長(67)は「水揚げ実績を作るのが大事」というが、水深の浅い西港に大型のカツオ巻き網漁船は入れない。 加工業者の不安は強い。復興会議メンバーで魚卵加工の丸信須田商店の須田紀一社長(53)は津波で工場設備が全壊。「土地をかさ上げし加工団地を再興するのか、内陸に移すのか、方針が決まらないと手が打てない」と嘆く。国が11年度第1次補正予算に盛り込んだ市場や加工場の支援は18億円。宮城、岩手、福島3県で分けても1県6億円。「1社当たりはスズメの涙だ」(宮城県漁協関係者) 石巻の加工業者の中には、水揚げを再開した塩釜に工場を移す動きも出始めた。石巻市水産課の勝亦睦男課長は「200社の加工業者がどんな魚もさばけるのが強み。業者が離散すれば、漁船は寄り付かない」と懸念する。毎日新聞 2011年6月8日 東京朝刊----------------------石巻の被害が甚大です。漁港間が近ければ近いほどライバル意識も強いのではないでしょうか。同じように復興が進まないのが現実。結果として被害が最小限にとどまったところが甚大なところのシェアを奪う構図になってしまっています。阪神淡路大震災でも復興格差が指摘されています。広がる復興格差 阪神・淡路大震災あす16年 阪神・淡路大震災は、17日で発生から丸16年を迎える。被災地では復興土地区画整理事業が完了する見込みとなり、人口増加が続く一方、地元経済は低迷し、地域ごとの復興格差は増している。被災者の高齢化や商店街のにぎわい回復に加え、震災で負傷した障害者への支援、借り上げ復興住宅の返還などが新たな課題として浮上している。 兵庫県によると、被災12市の推計人口は昨年10月現在、震災直前と比べて2・4%の増。ただ、10%以上増えた西宮市などに対し、淡路3市はすべて10%以上減った。1・2%増えた神戸市も、長田区だけでは22・1%減だった。 経済規模を示す域内総生産(GDP、実質)は震災前の1993年度を100とすると2009年度(速報値)は97・2で、5年ぶりに震災前の水準以下に。神戸市や西宮市などで100以上を維持したが、尼崎市(78・8)、南あわじ市(78・1)などの落ち込みが大きかった。 18地区で行われた区画整理は、新長田駅北地区(神戸市長田、須磨区)が今年3月に完了。再開発事業は新長田駅南地区(同市長田区)で継続している。【特集】阪神・淡路大震災(2011/01/16 08:00)-----------------------------西宮と淡路や神戸市長田区,尼崎などとの格差がみられます。もう少し広いスケールで見ると,神戸港が扱っていた物流量はなかなか回復しないようです。失った分は,大阪堺など周辺の港に奪われたまま戻ってこないようです。
2011.06.09
コメント(0)
-
企業情報の保存
NHK Bizスポより。企業の情報管理に新たな動きが出ている。データセンターはこれまで建物の中に保存するのが一般的だった。今日から幕張で始まったIT関連企業の展示会。コンテナ型データセンターに設置された300台のサーバー。「IIJ GIO」震災後にできたが,トレーラーに載せて移動でき,すぐに置いて開始できる。日本フルハーフはスピード感を売りにしている。インターネットイニシアティブは島根県松江市の松江データセンターパークで2台導入。消費電力は従来よりも4割カットしている。関東圏での問い合わせが殺到しているという。しかしすぐに持ち出せてしまうリスクはないか。これに対して壁を二重して保護しているという。-------------------------いろんなデータセンターの形が出てきました。リスクの場所による変化に機動的に対応しようということでしょうか。もっともリスクが低い場所に設置したとしても,その場所が当該企業にとって未来永劫リスクの低い場所であり続ける保証もない。現状で首都圏にデータセンターが集中しすぎていることは今夏とてもリスクになっています。パスワードを定期的に変更するようにデータセンターも定期的に変更するのがこれからの時代求められるということでしょうか。
2011.06.08
コメント(0)
-
久しぶりの学校
今日は結構久しぶりの学校でした。後輩や同僚たちと話をすると,悩みや不安を語ってくれます。自分もかつてそうだったように。自分の時はこうだったとしか言えないけれど,それで自分の置かれている状況を少しでも相対化できればと思って自分の経験について話します。そして話しながら自分はそうした数々の悩みを一応潜り抜けてここまで来たんだなぁと再確認することができます。これから先ももっと困難なことが待っていることでしょう。しかしこれまでだいじょうぶだったのできっとこれからもだいじょうぶ。
2011.06.07
コメント(0)
-

出た
今年初のゴキブリ。まだおとなしかったので新聞で弱らして外に逃がしました。ゴキブリが活動しやすい季節がやってまいりました。と検索したら「バルサン」を販売しているライオンが「ごきぶり天気予報(ゴキテン)」なるサイトを開設してました。地域別にみられるし,モクゴキ数も計測してます。花粉症に放射線にいろいろな予報地図が出てますがゴキも需要ありそうです。
2011.06.06
コメント(0)
-

カナダのローカルビール
トロントのお土産でローカルビールを買いました。Mooseheadというビールで1.95CADカナダドルでした。そういえばビールなどアルコール類はスーパーには売っていません。リカーショップに行かないとありません。今回は帰りのエアポートリムジン乗り場近くのKing St. WestとSpadina Ave.の交差点にあったLCBOというリカーショップに行きました。(左下に見えるのがLCBO。CNタワーが背後に見える)LCBOとは“Liquor Control Board of Ontario”の略で政府機関(オンタリオ州)直営なんだそうです。なるほど納得です。さっそくあけてみました。あっさりしています。トロントの思い出に浸りながら。
2011.06.05
コメント(0)
-
社会保障改革
消費税は現行税率5%のうち1%が地方消費税。国分4%の使途は1999年度の予算総則で基礎年金、高齢者医療、介護に限るとし、以降、毎年この3分野に充てられている。しかし財源が9.8兆円(2010年度)不足している。予算総則が定められた1999年度当初は1.5兆円の不足であった。15年度には13.3兆円不足する見込み。そこで,消費税を段階的に5%引き上げることに。そのためには同時に,社会保障の効率化・重点化を進める必要がある。具体的には,高所得者から低所得者への基礎年金の一部振り分けと支給開始年齢の引き上げ(68~70歳の案もあり),窓口負担の引き上げ(70~74歳の1割→2割)と受診時の100円負担など。これまで医療は公平性の担保を重視してきたものの,財源不足から提供すべきサービスにメリハリ・優先順位をつけていく必要があるとされる。「共助・連帯」とのキーワードがそれである。早くも段階的に上げる消費税の3%を復興財源に充てるとの議論がなされている。もともと消費税のみでは社会保障費の伸びを補いきれないため,復興財源と社会保障財源とのバランスをどうとっていくのか難しい舵取りが迫られる。そこには,明らかに消費税増税ありきの議論が展開されている。まずは社会保障費を抑えるための政策メニューをありうる限り出し尽くしてはどうか。というか,メニューについては結構出ているが,業界団体の反発が大きくて実現が難しいのだろう。たとえば,厚生年金の給付開始年齢を段階的に65歳まで引き上げた経緯があるが,これとて実現には20年を要した。開始年齢を引き上げれば,その分,企業は高齢者を継続して雇用する必要が生じるためで,経済団体は一斉に反発する。現在の民主党政権は死に体といわれている。しかし,ともかくも内閣不信任案は否決された。その今だからこそ実績を残すためにも,やるべき改革を一気に進める必要がある。長期的に影響が及ぶ社会保障費の増加について目配せしつつ,スピーディに復興予算とその財源確保が可能になるよう,できるだけ素早い対応が求められていると思います。
2011.06.04
コメント(0)
-
カナダの医療覚書
カナダでは医療制度が充実している。隣国アメリカの自己負担の高さとよく比較されます。聞いてきた話で覚えていることをまとめます。出産費用は無料。その代わり出産後1泊で退院する必要がある。歯科,眼科は有料だが高齢期には無料になる。薬剤費は有料である。その代わり,税金が13%(トロント)と高い。診察を受ける場合はFamily Doctor(かかりつけ医)を受診する。専門的な治療を受ける場合,紹介状がなければ,病院にはかかることができない。処方せんを渡されると,ドラッグストアやウォルマートなどのスーパーでも処方せんを受け付けていて処方薬をもらうことができる。代表的なドラッグストアはカナダで展開するShoppers Drug Martなどで,OTCも買える。看護師など医療従事者は正社員であっても突然解雇を言い渡される可能性がある。しかしその場合でも失業保険は出る。旅行者には医療保険は適用されず,高額な医療費を負担しなければならない。そのために海外旅行保険に加入しておく必要がある。労組のロビー活動が有効に機能していて,賃上げストはよくある。特にカナダ市交通局(Toronto Transit Commission: TTC)は市バス,地下鉄,ストリート・カー(市電)を運営しているが,賃上げストを行うと交通機関が麻痺して市民の足がなくなる。その結果として,賃上げ交渉はうまくいくことが多い。早朝から出社する代わりに退社時間は早く,ラッシュは3-6pmのようである。というわけで全般的には自国民に対する医療・福祉制度は非常に充実していて,自己負担が小さい。
2011.06.03
コメント(0)
-

トロント・ダウンタウン
トロント市内ダウンタウンには歴史的な建造物がたくさんあります。こちらは市庁舎です。1965年に建造されたそうで,デザインはフィンランド人のデザイナーによるものだそうです。すぐ隣接して1899年に建てられた旧市庁舎があります。趣があります。ブロア・ストリートとヤングストリートとの交差点には日本の渋谷を真似したという街並みが広がっていました。一角にDOLLARAMAという1ドルショップがありました。お土産になりそうなものも売っていました。ちなみにカナダではドラッグストア「Shoppers drug mart」が有名です。食料品マーケットとしてはセント・ローレンス・マーケットが有名です。1803年オープンでコーヒーから肉,野菜まで売ってます。お土産屋さんもありました。ここでお土産を少し買いました。夜は親が夜ご飯をごちそうしてくれました。串カツ。おいしかったです。
2011.06.02
コメント(0)
-
ナイアガラ
妹の旦那さんの運転でナイアガラに連れて行ってくれました。トロントからは1.5時間。途中にはワイナリーがたくさんあって,途中で試飲できるワイナリーに立ち寄ることにしました。一通り説明を聞いてお土産を買った後,別のワイナリー兼レストランで昼食。ワインととともに食事をしました。雰囲気がとってもよかったです。周辺は一面のワイン用ブドウ畑。そしてナイアガラの滝へ。カジノがあったり,ショッピングモールがあったり,完全に観光地化されてました。水しぶきがすごかったです。全部で3つの滝があるそうです。うち,2つの滝と娯楽施設はカナダが使用権?を得たそうで,残り一つはアメリカ側なんだそうです。夜は日本食レストラン(寿司屋)に行きました。トロント大学の近くということもあっていつも若い人たちでにぎわっているそうです。アボガドやサーモンをふんだんに使って見た目にもおもしろい寿司が出てきました。味はなかなかでした。スタッフは日本語が話せる方でした。街並みを歩いているとあちこちにSUSHIという看板を見かけます。それぐらい寿司は人気があるようです。
2011.06.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1