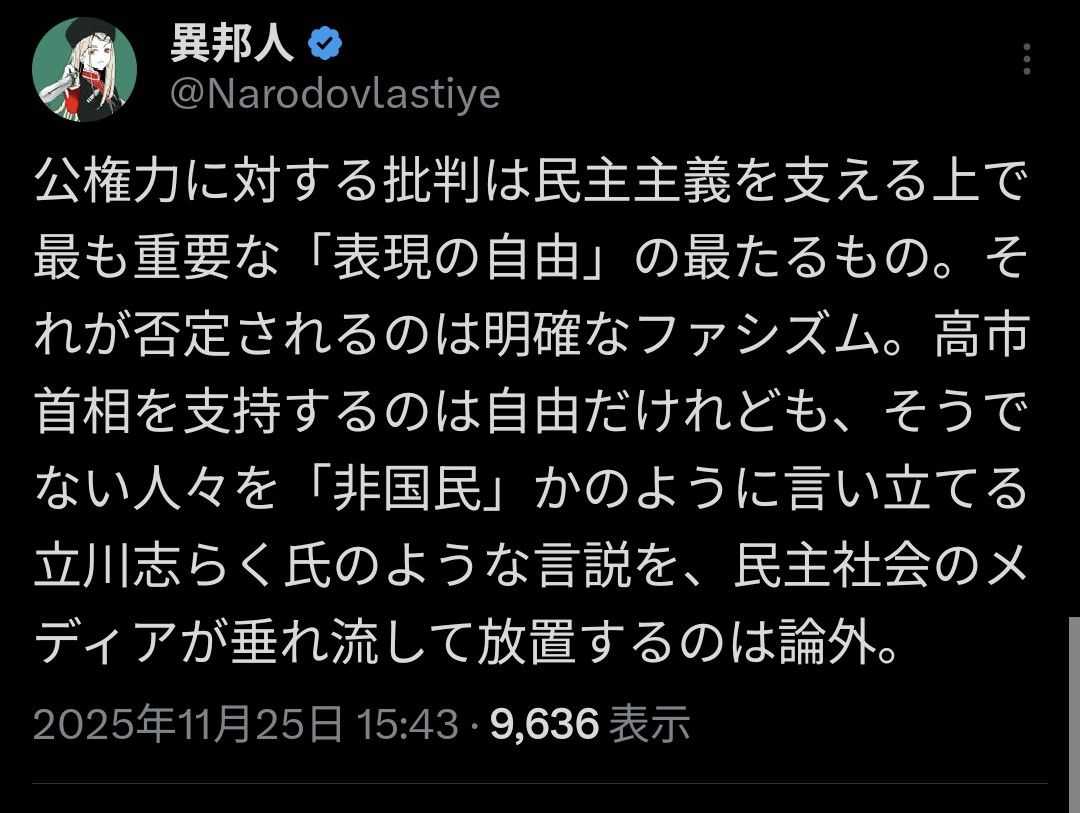2010年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
石川五右衛門その2♪
歌舞伎の「楼門五三桐(通称山門)」は、南禅寺の山門から洛中を睥睨しつつ見得を切る五右衛門の芝居で、僅か15分ほどの出し物ですが、豪華絢爛な景色、大百日鬘姿の貫禄のある演技が楽しめます。 五右衛門は、真田蔵之進という名の遠州浜松の侍という説や、忍者百地三太夫の弟子で不義を働いた石川文吾説。他に河内の石川村生まれとか、丹後の伊久知山の山城に住んでいたという説も。その山城は秀吉の命で、細川幽斎の手によって落とされ、城主石川左衛門尉秀門の次男が五右衛門で、叔母に当る菊寿さんの15代目の後裔が坂根久ニさん。坂根家系図には五右衛門の名も記されており、面長で色白、和歌と謡曲の名手とも伝えられているそうな。 さてガイドの立場で少し付け加えますと、後鳥羽上皇を祀っている”水無瀬神宮”の境内の手前、参道正面の神門には社殿に飾られた名刀”菊一文字”を盗もうとするも神威に負け、止む無く残した五右衛門の手形がありますのでご覧下さい。また五右衛門の墓は、鉾の形をした祇園閣のある大雲院にあって、参拝者に削られた墓石もご覧下さい。この寺には織田信長公・信忠公の大きな墓石もあります。わが俳句結社では毎年ここで前年の故人の冥福を祈る句会を催しています。
2010.05.31
コメント(4)
-
5冊の書♪
最近ちょっと図書館からの借り出し書が偏ってはいまいかと案じています。1)福田晃・真下美弥子「京都の伝説」(淡交社) 賀茂の神婚から京の宗旦狐まで32話を解説しています。2)NHK編「江戸・怪盗伝」 先日石川五右衛門について触れましたが、ネズミ小僧、日本駄右衛門、鬼平犯科帖など。3)NHK編「太閤秀吉天下取り」 ガイドに活かせる情報収集のため。4)峰岸純夫編集「争点 日本の歴史4巻 中世」(新人物往来社) ひょっとしたらページを繰るだけかも?5)鶴見俊輔・齋藤真爾共編「サザエさんの昭和」(柏書房) サザエさんの家族の名前に海産物が多いのは、一家が最初に疎開した場所が海の畔だったから。戦後の女性の生き様と日本家庭の変革をつぶさに示す風俗史的な漫画とも言えそうです。(拙作ご披露します。旅愁)
2010.05.30
コメント(2)
-
家内への約束手形♪
父は独身時代、そして所帯を固めてからも、俳句での旅行や社員旅行など、そこそこ旅した人物と言えるでしょうが、母は子供4人がそれぞれ独立し、孫が7人できた晩年にやっとこさ父と一緒に、或いは兄弟や数少ない友人と出かける機会を得ていたように思います。それも団体旅行は好みませんでしたので、多かったとは言えず、今から思えば、もっと旅に連れ出してあげれば良かったと後悔しないでもありませんが、どちらかと言えば受身的な性格、行動派とは逆の性格でしたので、本人自身が”清水の舞台”の心境にでもなって貰わないとそれは叶わなかったのかなとも思います。 一方、家内はと言えば、幼年期、短大時代、独身時代を通じて、家族や友人と再々旅行に行っていたようですから、何とか自由に足腰の動かせる今こそ、夫婦相揃って旅に出ることが人生設計の1つだったようで、私が父の跡を継ぐ様な恰好で俳句の世界に身を置いたことから、編集やいろんな役を預らせて貰う立場になろう等という予想外の展開に、眉を曇らせていないでもなさそうです。早く自由な立場になって家内孝行をしないと、あの世まで恨まれてしまいそうだと案じている次第です。
2010.05.29
コメント(6)
-
英邁な桓武帝と怨霊♪
上御霊神社を抜きにして怨霊のことは語れません。御霊神社の名が史書に出てくるのは貞観5(863)年のことで、六所明神、つまり怨霊神は六柱でした。それが此処では2体増え、早良親王、井上内親王、他戸(オサベ)親王、吉備聖霊、火雷神、藤大夫(藤原廣嗣)、文屋宮田麻呂、橘逸勢。いずれも恐ろしいお顔。 余談ですが、北野天満宮本殿の奥で、今も生きておられるといわれる菅原道真の御像も目を見開き、口を結ぶ憤怒顔とか。井上内親王は聖武天皇の娘、孝謙女帝の異母妹で、白壁王(光仁天皇)の妃。お二人の皇子が他戸親王。ところが稀代の策略家・藤原百川の陰謀により、井上皇后と他戸皇太子は廃され、二人を亡き者にして山部親王(桓武帝)を皇太子に推した因縁があります。祇園祭で有名な祇園社も怨霊鎮魂の神であり、牛頭天王を祀っています。スサノヲの命と習合された異国生まれの威力ある牛頭天王を祀り、より強固な怨霊の鎮魂を図り、やがて剣鉾が巨大化した為に車に乗せ、華美な装飾を施すに至ったものと思われます。(注、本稿は梅原猛著「京都発見1地霊鎮魂」(新潮社)を参考に綴りました。)
2010.05.28
コメント(2)
-
五右衛門の釜煎り♪
図書館からこんな面白い題の本を借りてきました。NHK編「江戸・怪盗伝」。これは「歴史への招待」という番組で採り上げた中の13巻とのこと。 では早速あの有名な”石川五右衛門”の真偽について話を展開して参りましょう。五右衛門と言えば”釜煎(イ)り”と来ますが、この釜は直径、深さともに2尺4寸(凡そ72センチ)だったそうで、6尺2寸の五右衛門には小さいような。但し、蓋には首や手を出す穴が開けられていたので何とも言えません。この釜は処刑後伏見城にありましたが、其の後、大和五条の代官所へ運ばれ、明治半ばには東京市ケ谷の監獄所に移され、また刑務協会の手に渡ったものの、第二次大戦のどさくさに無くなってしまいました。けれども実物の写真は保存されています。 では五右衛門は実在の人物かと言えば、徳川幕府が林羅山に命じて豊臣秀吉の伝記を編纂させ、その中には文久3(1594)年に五右衛門を捕らえ、母親と同類20人を煮殺したという記事が残っています。しかしこれは処刑から50年も経過後のことですから誰かの日記で確かめないといけません。山科言経(トキツネ)という公家の日記に<(文禄3年8月)24日丙午天晴 1.盗人すり10人子1人等釜にて煮らる。同類19人磔に懸ける。三條橋南の川にて成敗なり。貴賎群集也云々>とありますが、五右衛門の名がありません。スペイン人の貿易商人アビラ・ヒロンの「日本王国記」には五右衛門一味らしき盗賊に関する一連の文章があって、それに注釈を加えたのが宣教師ペドロ・モレホンで、<この事件は1594年(文禄3)の夏である。油で煮られたのは他でもないIxicavagoyemonとその家族>とあります。京の修道院長だったペドロは実際に三条川原まで出向き、処刑現場を見物したのではないでしょうか。 この項、まだまだ長くなりそうなので、今回はこの辺で一旦ペンを置きます。次回は五右衛門像やガイドも兼ねて書く予定です。
2010.05.27
コメント(2)
-
好きな我が作品♪
石川さゆりさんの「天城越え」や瀬川瑛子さんの「命くれない」など、女性の情念を詩にした吉岡治さんが亡くなったようです。 凡人の私には情念の詩は書けませんでしたが、ポップスや演歌、クラシックなど、折々に浮んだ歌詞やメロディを形として110曲ほど残すことができました。このメロディと歌詞については我ながら気に入っています。曲はMAC(マッキントッシュ)平成9年か10年頃に作りました。 「荒 野」男は荒野に立つ 風に吹かれて雨に打たれて 女子供を護る為に風に向かって 雨に向かって男の心 唱い上げる男は荒野に立つ 嵐の夜に吹雪の中に愛と安らぎ護る為に光る稲妻 白い巨人に益荒男魂 唱い上げる男は荒野に立つ 雲が切れ行く霧も晴れ行く 夢と現実見つめ乍ら明日を信じて 天に向かって男のロマン 唱い上げる「荒野」蛇足ながら、以下は平成4年2月7日に書いたものです。 この歌詞はおりく自身お気に入りです。おりくは本来、放浪癖を内蔵するダメ男ですが、女性よりも若干、男が早死にするのは、愚かしさを包含した「男のロマン」故かなと思っています。この人世は、男女相見(まみ)えて子孫を残し、女性は胎内に新たな命を宿し、産み出す苦痛に堪え、為に子供への情愛、思い入れは男子の及ぶところでは無い。女性には稚(いとけな)い子を育て護る本能が埋め込まれて居り、現実的な対応に機敏なることを備えつけられている。他方、男性は先述の役務を免れた穴埋めに、未知なる世界に憧れ、見えざる宝を追い求めつつ、婦女子を護る賦役を負う。世の中の男女のあるべき姿を一把絡(から)げて論じるのは無益なことなれど、男女の相違点は互いに認識しておく必要を感じる。仕事の達成に全体把握の観点に立ち、少々の犠牲は止む無しとするのが男性の物差しであり、荒削りな処置に潜む矛盾に心を寄せるのが繊細な女性の物差しでもある。この男女の相違を互いに理解しあい、埋め合わせする相性ある関係が一番望ましい男女間ではあるまいか?
2010.05.26
コメント(2)
-
政治家と落語♪
上前淳一郎さんの「読むクスリ 37巻 節約が明るい時代」の一節に見つけた小ネタです。<「落ちる話」 自民党参議院議員(注:2007年ご退任)の阿部正俊さんは、お若いころから大の落語好き。自ら編集したカセットテープが500本あって、今も朝夕欠かさず聴く。国会での質問に落語を引き合いに出して、議場を笑いで包むこともあるほどだ。同好の士が衆参両院に少なからずいることがあかってきて、「どうです、超党派で”落語党”を作りませんか」と持ち掛けるようになった。ところがだれも、うん、とは言わない。ときには、のっけからオチで応じられる。「縁起でもない。落ちる話は、持ってこないでくれ」 >( )内の注を除いて、< >内は上前さんの文章をそっくり載せています。 彼ほど落語に詳しい訳ではありませんが、わたしもあらゆる機会に落語から引用したり、ヒントを得たりしています。先日の”天王山ウォーキング”での引率に際しても”笑い”を中心に、副次的にガイドを織り交ぜますと、お客さんとの距離感が寸時に霧散、初対面のお客さん同志も1つのチーム員として連帯的な行動をとって下さいます。そして笑顔一杯のチームとなって散会に至ります。きっとこれは”笑門福自来”の一例なのでしょうね♪
2010.05.25
コメント(2)
-
ぎをん芸妓 その恵さんのこと♪
先日句友4人が打ち揃い、八坂神社石段下近くの「妹」さんにて一献傾けました。談林風とまでは行かない凡人どもの集まりですが、俳句を嗜む者同士だから、話題には事欠きません。そうこうしていると、ぎおんのその恵さんがお越しになり、みどりの御髪も美しく、お酌をして下さいました。その恵さんと席を共にするのはもう4度目ぐらいなのに、会うたびお顔が別の人に見えるものの、今回はしっかり覚えるように努めました。前回はわたしが約束の時間より遅刻して、ほんの少ししか話が出来ませんでしたが、その折は、「都をどり」期間中のお茶当番で着衣した着物のまま、来て下さっていました。少し綻びかけの年代物で恥ずかしいと彼女が言われましたが、とびきり上等なものと看立てましたのでその着物のことを褒めました。他の方は皮肉に取られたようですが・・・。今回、その恵さんは自前でそれを大幅に直(修繕)されたとのこと。良かったね。 ところで今年の都をどりは何番の組?と尋ねましたら1番組で猩々を舞ったとか。或る年代になると頻繁に舞台にでる立場になるとかで、私が観た日の2番組(この時は小愛ちゃんが上臈役・・・それは直ぐに判りました)には、西のをどり子のメンバーだった事が今、番付表で判明しました。これからも酒宴に来て頂いた舞妓はん芸妓はんらを応援しようと思っています。
2010.05.24
コメント(4)
-
日本人の質問2より♪
先日借り出した図書「日本人の質問」などはもう返さないといけませんので、折角だから本日の話題に。「仕分け人」後半戦で一躍有名になった”宝くじ”。さて江戸時代はどのようなものだったのでしょう。江戸幕府公認の催しで、豪商が後ろ盾となり、寺社の修復費用に充当されました。箱の中に入れられた木札を、坊さんが長い槍で突き寄せたとのこと。江戸時代の旅館は殿様が泊る”本陣”、裕福な人々が利用した”旅籠(ハタゴ)”、そして庶民的な”木賃宿”。さて木賃宿の”木”とは何ぞい?これは燃料となる薪のこと。問題)かたつむりのことをでんでん虫というのは何故?高橋博士 → お前の頭はどこにある?子供がつっついて頭を引っ込ませて遊びますが、おつむてんてんからてんてん虫、そしてでんでん虫へ。大桃博士 → 殻の中にに入って出て来ない。そこで「早く出よ出よ」と声をかけます。そのでよでよ虫からでんでん虫へ。矢崎博士 → 大きな貝殻を背負っていますが、何かに似ていますね。そう、オモチャのでんでん太鼓から。文珍博士 → 大阪ではぜんぜんと言うのを「でんでん」と発音します。「でんでんあきまへん」なんてね、でんでん動けへん虫やから。正解)大桃博士。 でんでん虫が活動するのは雨の日か夜。晴れた日は殻の中に閉じこもったり、草の根元に隠れて、水分が失われるのを防いでいます。生まれた時から殻がついていて最初は1巻き半しかありませんが、貝殻は体と共に成長して大人になると4、5巻きの渦に。昨日は天王山ウォーキング。子供2名を含む228人のお客様が晴れた山麓や頂上に行かれました。長岡京市にある「サントリービール 京都工場」にて出来たての生ビールを試飲されました。本日は午後から野風呂記念館で開催していた企画展の片付けに出かけます。
2010.05.23
コメント(2)
-
個性ある役づくり♪
上戸彩さん主演の刑事ドラマ「絶対零度~未解決事件特命捜査~」において、同僚でクールな警部補・高峰涼子を演じている女優さんに一言。ご本人によれば”クールな大人”の役は初めてとのことのようですが、過去の女優さんが演じてきているクールなイメージをそっくり真似ているに過ぎないような印象を受けます。モノ真似のプロは、真似る人の癖や動き、イメージを極端に引き出して演じますが、対象である本人の研究しないで、プロが真似たイメージをそのまま真似る人々が多く、それを評価する審査員の点数が甘いのも困りものです。 クールということは、何か秘密めいた過去や生い立ちがありそうな・・・と観客に思わせるような深い個性を演じる工夫をして戴きたいと思っています。鈴木京香さんは有名になられる前からチェックしていた女優さんですが、死体解剖師の役に個性を吹き込み、それが評価され、大女優としての不動の地位を築かれたように思います。要はドラマ上の人物に自分なりの強力な個性を塗り込めることが肝心なのかも知れません。
2010.05.22
コメント(0)
-
みさき公園から和歌山まで♪
と或る日、急に思い立ち、家内の両親が眠っておられる「みさき公園」の墓地にお花を手向けに出かけました。長岡天神・梅田間は株主乗車券を利用し0円、それから阪急百貨店で料理人奥村氏の彩り美(ハ)しき弁当を買い、環状線は新今宮経由、南海電車でみさき公園駅まで。墓地まではタクシーなら相当な額の距離、1時間に1本しかない送迎バスに首尾良く乗車。岬にある墓地から阪和の海の景色が一望。唱歌「みかんの花」の歌詞ぴったりの長閑な眺めでした。日当たりの良い苑内のベンチで昼食を摂り、逆方向の和歌山市へ出るや、次はバスにて”紀三井寺”に参詣。昨年開眼された金ピカの十一面千手観音さまに拝謁した後、その御堂3階から和歌浦港辺りの眺望を楽しみました。帰りはいくばくかの土産を手に、紀三井寺駅から和歌山駅経由、環状線大阪駅直通の急行にて戻り2府1県の日帰り旅を終えました。本日の拙作の曲はオーロラ(東欧編)
2010.05.21
コメント(2)
-
忽然と消えた金魚の怪♪
これまで度々登場してきた金魚の話題。今わが家には1匹しか金魚が居ません。台所の出窓に置いてある水槽の1匹が、自ら飛び出して他界。そもそもこれが怪奇現象の皮切りになるとは、予想だにして居ませんでした。1週間ほど前、庭の睡蓮鉢に飼っていた番(ツガイ)の大きい方が、”忽然と姿を晦まし”、何処を捜しても見当たりませんでした。今回は猫か烏に襲われたのかなと思いつつ落胆して居ましたが、昨日の朝、もう1匹の金魚も忽然と姿を消したのです。まさか大地震の前触れでは無いと思うものの、金網の蓋を購入するまで、金魚は表では飼えそうにもありません。
2010.05.20
コメント(8)
-
山崎の定鉾♪
室町期の公卿だった一条兼良が編んだ「尺素往来」には、<祇園御会、今年殊に結構。山崎の定鉾、大舎人の鵲鉾、処々跳鉾、家々笠鉾、風流の造山、八撥、曲舞、在地の所役、定めて神慮に叶う歟。晩頃、白河鉾入洛すべきの由、風聞に候。>とあります。山崎は荏胡麻(エゴマ)の販売権を独占することによって中世から江戸中期まで繁栄しました。自由都市としては明治維新前まで荘が存続したところでもあります。上記の資料で、その繁栄の一端が垣間見えます。 ところで、この情報は吉岡幸雄著「京都町家 色と光と風のデザイン」という美しい書物からいただきました。呉服関係の仕事で繁栄した吉田家、杉本家、野口家などの京町家のしつらえや、調度品を綺麗な写真で紹介してあるのですが、写真に添えられた説明文の美しさ、67頁以降の本文の流麗な文章と内容の濃さに、惚れ惚れしています。
2010.05.19
コメント(0)
-
写真の功罪??♪
私の幼い頃の記憶に、父に連れられ家族で出かけた折の写真のポーズ。父は姉や妹にいろんなポーズを取らせてカメラに収めていました。CMで見る、前から順に左右に分かれて顔を出すポーズは父の代から。晩年の父や母の旅行や外出時のスナップ写真を一部残しています。父の代の俳句がらみの写真やこけしにまつわる写真、都をどりや歌舞伎などものを殆ど処分しても、なお残るのは段ボール箱に2個。私の代になって、デジカメとパソコンのお蔭で、軽量なCDに残せますので大変便利になりました。ガイド関係のCD、俳句関係のCD、そして家族(主に家内中心の)のCDに分けて保存しています。これなら子供達にも負担にならない”私ら夫婦の遺物”になることでしょう。本日の付録は「反省」というポップス、しばしお耳を拝借しますが、拙作の曲をお聴き下さい。反省
2010.05.18
コメント(8)
-
祟りの思想♪
古来わが国には”祟りの思想”があって、それは哀しいかな、皇族に関するものが多くあります。先ずは長岡京・平安京に遷都された桓武帝の弟ぎみ・早良(サワラ)親王が挙げられます。桓武帝の寵臣で建都の立役者であった藤原種継を殺めたのが大伴継人・竹良に嫌疑が及び、その背後には親王があるとの事で乙訓寺に幽閉され、親王には潔白を証する余り断食されましたが、淡路への流刑の途中でご崩御、そのお怒りは怨霊となって様々な祟りをおこされたとされ、上高野の地に祟道神社を建て祀られた由。5月5日の祭では暴れ神輿のほかに、竹に白い着物をつけた幟が妖しく揺れますが、恰も亡き帝の亡霊のよう。 山崎豊子作の小説「華麗なる一族」では実の親子であるのに自分の息子を亡き父の胤と疑っていますが、讃岐の白峰に流された祟徳院は白河天皇と待賢門院との子ながら鳥羽天皇の子として扱われ、ここに葛藤の歴史が生まれました。先日、結社の吟旅のコースとして白峰の御陵に45名が訪い、祟徳院の御霊に拝し、お慰め申し上げました。柳田国男氏の説では、有能な天皇と謂えど、流罪などで怨念を残す形で亡くなった方でないと神としての条件を充たさないとされ、なるほど、早良親王、祟徳院、後鳥羽院(水無瀬神宮)の御三方の例から納得がいきます。怨霊については、またの機会に。
2010.05.17
コメント(1)
-
食パンのヘタ論議♪
私が飲み歩いた所為で、生活費に狂いが生じた時期がありました。家内が工夫を凝らして家計のやりくりをして支えてくれました。それは向日市に住んでいた頃なのですが、朝食には1斤10円の食パンのヘタ。安物の食パンなら、ヘタよりも中身の柔らかい部分の方が美味しいのですが、パン屋さんが勝負に出している上等の粉を使用した食パンの場合は、パンのヘタのごつい部分でも美味しいのです。 年金暮らしの現在はお蔭様でむしろ、その頃よりもマシな生活をさせて戴いていますが、ここ2年ほどは、長岡天神駅近くの”メサベルテ”というパン屋さんの食パンを日々購入しています。ビニール袋を持参すればカードに1ポイント押印してくれますし、月初に配られる”パンの日”の広告チラシには、30円割引券が2枚附いていますので、199円の食パンが163円と手頃な値段になります。メサベルテというパン屋さんは茨木駅2店、高槻駅、富田駅そして長岡天神の計5軒あるようで”よーいドン”でも放映されたようです。ヘタパンは5、6枚入りで30円で別途こっそり販売していましたが、最近は6枚切の袋に1枚ヘタパンを足しているようです。焼きたてのトーストにキャベツや中玉のトマト、そしてチーズを挟んで食する味は止められません。因みに長岡店がhttp://www.azalea-pierrot.org/tenpo/mesaverte/index.htm茨木店がhttp://r.tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27012316/富田店がhttp://www.mesaverte.com/news.htmlです。美味しい食パンにいつも感謝しています。
2010.05.16
コメント(6)
-
父の日記に見る双葉山♪
昭和16年1月22日の父の日記に、小三郎の靭猿のレコードについて触れていますが、それは4世野村小三郎なのか、4世吉住小三郎なのかはっきりしませんが、どうも後者のように思われます。1度目に聴いた時はそれほど良いと思わなかったらしく、再聴してその良さに気付いたようです。趣味の切手については、糊はがしを300枚ほど行ったようで午後11時までかかったことが記されています。 さて興味を惹くのは次の箇所、<けふ双葉山が前田山に負けて全勝はなし。1敗は双葉山、安芸ノ海、羽黒山の3人である。幕下十両中、双見山・豊島1敗、若瀬川2敗すべて有望>とあり、これは69連勝が途切れた年とは別で、それは昭和11年1月、前頭3枚目9勝2敗の成績を収めた場所の6日目に玉島に破れて以来、14年の9月までの連勝のことです。連勝は一旦途切れたものの、その後も強い横綱であったことがわかります。昭和12年5月の場所から従来の11日取組から13日取組に変更、また昭和14年5月の場所から、現在と同じ15日取組に変更されたようです。父の日記にある双葉山が敗れたのは13日目ですが、この場所は1敗を守り、8度目の優勝に輝いています。双葉山に関するサイトとしてお薦めするのは双葉山定次です。
2010.05.15
コメント(0)
-
漢字クイズ♪
漢字には必ず部首があります。あなたは漢字とその部首にお強い方ですか? 下のグループの中で他の4つとは異なる部首の漢字が各問ごとにあります。それを指摘して下さい。1)或・我・威・戦・戯2)商・哲・哀・尚・否3)某・桑・杏・末・楽4)群・羹・美・義・姜5)散・致・敏・敬・放随分迷いますね。では回答。1)威=女偏 それ以外はほこがまえ(ほこづくり)2)尚=さかしょう それ以外は口偏3)某=甘(カン) それ以外は木偏4)姜=女偏 それ以外は羊偏5)致=至 それ以外は ぼくにょう似ているようで違う場合や 違うようで同じ部首など 漢字の生い立ちの深遠なこと。なお本編の参考図書は「頭の良くなる漢字パズル」(頭脳強化パズル製作委員会)
2010.05.14
コメント(6)
-
10’4月の拙句♪
覚書として拙い自分の俳句を、この日記にて公開していますが、5月分として連休の間に予め書いておいた日記に、このコーナーを失念していました。遅ればせながら・・・。 円山の花のつづきや都をどり 竹秋や嵯峨と雖も知らぬ路 手を繋ぐ外人夫婦竹の秋 亀鳴くや下着のゴムの弛みがち 南座の隠り処(コモリド)奈落亀鳴けり◎末寺なる門劃を占む白木蓮 花曇り川すぢ折れて小督塚 嵐峽の滾つ瀬早も初つばめ ○パソコンの壁紙いちごの花にする 嵐電の細き踏切花ぐもり 花苺さす指先のまだ若き 戦中は内地と外地別れ霜 従軍のひめゆり学徒花いちご◎花の雨東寺の塔の黒きこと 北総門世々の剥落花の雨○八重桜ぽんぽん盛る源氏の社 石楠花や龍神ここに護り給ふ 山吹は睦弥稲荷の左座を占む 夜桜や八百屋お七のふと過ぎる 花曇り侘び寂び染めと言ふ手法○襖絵は武蔵の手なる花の雨 雨の日のモデルルームへ花楓 野水仙いつかこんな日あったよな 岡崎の薫風豊に遡上せり 粟田社の風のそよぎも若楓 粟田社の本殿昏し遅ざくら 陽春や自ら皮を脱ぐ樹など 提灯のつなぎ団子も京の春句会ごとに同じレベルの作品を5つほど揃えるのには更に更に研鑽を積まねばなりませんね。
2010.05.13
コメント(4)
-
薔薇の気品♪
まるで北国に住んでいるのかと錯覚するほど、庭を賑わせる花々の移り変わりの激しいこと。本年の最後となった牡丹の大輪は台所の出窓に活けて楽しんでいます。思ったよりも、その大きさに驚きます。鉄線の別株は濃い色を呈し、アヤメの紫には気品が漂い、その近くには愛らしい赤紫の紫蘭も咲き初め、庭石菖が例年よりも立派な姿でお目見え、名も知らぬ素朴な花も数種類かそけなく咲いています。一方、西側の歌壇には紅隈取にして渦巻き状にピンク色の匂う薔薇が一輪咲き、明後日までに3輪揃いそうです。南瓜の苗や唐辛子の苗は地植えに移さないといけません。風呂の傍の芍薬がもうすぐ咲くことでしょう。本日の拙作の曲は「伝言」。今から5年ほど前、向日町の家に住んで居た頃、家族が外出して不在の2時間ほどの寸時の間に、自作の曲をMACで流し(演奏)ながら、それに関わる演歌・フォークソング・ポップスなど自分で書いた作詞をぶっつけ本番で歌いながら、凡そ30曲ほど一挙録音したものです。歌詞を間違えたり、息遣い、リズム相違など自己採点60点ほどの出来ですが、お許し下さい。
2010.05.12
コメント(4)
-
冷泉家の歴史♪
冷泉家と言えば、藤原定家の後裔の家系だと大概の方々はご周知のことですが、そもそも「和歌の家」の象徴である御子左家(ミコヒダリケ)定家の子の為家が亡くなる時、遺言書に相当する「譲り状」を巡って、嫡流二条家の為氏及び京極家の為教(タメノリ)と後添いの母:阿仏尼の子として生まれた為相(タメスケ)の冷泉家という3つの家系が相続権を争ったのでした。幕府に嘆願する為、鎌倉へ下向した際に阿仏尼が書いた旅日記が有名な「十六夜日記」です。それから30年を経て、二条家、京極家の断絶の結果、御子左家の血筋を引く「冷泉家」として誕生しました。爾来、現在の25代目為人さんまで800年ほど続いています。余談ながら24代の為任(タメトウ)さんが某年金基金の理事長をして居られた折、私は担当銀行員として面前に居たことも。戦国の世は冷泉家にとって存亡の危機に見舞われた時代で、滋賀県の近江に疎開。6代目為広さんは駿河の今川氏や能登の畠山氏と親交を結びました。9代から12代は安土桃山、江戸初期にあたり、一時、大坂にも居を構えましたが秀吉の命により再び京に戻り、古今伝授をした家康の庇護をも受けるようになりました。この間、日本国家の宝とも言うべき冷泉家の古文書は戦火を逃れ、幕府や皇室から手厚い保護を受けました。冷泉家の住宅と定家が書いた日記:国宝「明月記」の修理には8億~9億円もの費用がかかりましたが、75%は国・京都府・京都市の負担、残りの自己負担部分が高額でしたので、バブル崩壊期ながら1億3千万円を超える寄付金が集まったようです。 参考図書:「京都冷泉家の八百年」(冷泉為人編、NHK出版)
2010.05.11
コメント(0)
-
冷やっこ♪
今年は気温の高低差が大きいので対応に難儀していますが、窓を差す光の勢いは正に夏の到来を思わせます。夏と言えば、冷奴。そこで問題です。問)冷やした豆腐を”冷やっこ”と言いますが、なぜこんな呼び方をしたのでしょうか?高橋博士→江戸時代暴れん坊だった旗本奴、江戸きっての男伊達でしたが、いずれは身を持ち崩す・・・豆腐と同じ崩れ易いところから。大桃博士→白粉(オシロイ)で綺麗にお化粧した芸者さん、色黒な芸者さんは見かけませんね。そう豆腐の真っ白なイメージが芸者さんに重なります。矢崎博士→江戸時代に身分の高い武士のお供をしていた奴さん。その着物には決まって四角い白い紋がついていました。形が豆腐そっくりなので。文珍博士→豆腐にも食べ易いサイズがあって、昔から包丁目を入れて、丁度八個に分けたから。正解は・・・・・・矢崎博士 ”冷やっこ”は、そもそもは「やっこ豆腐」と呼ばれていて、このやっことは、とりも直さず大名や武家の雑用や、出かける時の行列の供先を務めていた奴のこと。奴さんの筒袖には、大きく染め抜かれた「四角くて白い」紋がついていました。この紋に色と形が似ていることから、切った豆腐を”やっこ”と呼ぶようになりました。因みに冷奴に対して湯豆腐は「熱奴(アツヤッコ)」とか「湯奴」などと呼ばれたようです。出典はNHKテレビクイズの「日本人の質問」No2を参考に書き換えています。(本日の付録)は「Pre For HIROMI」
2010.05.10
コメント(0)
-
ちょっと面白い話♪
森光子さんが「放浪記」を2000回も演じられたことは周知の通りですが、彼女が言われた言葉の中に「公演が終るとセリフはすっかり忘れ、他の出し物に集中。次の放浪記には新たな気持ちで再びセリフを覚えます」というものがありました。なるほどなと思いました。 この年齢になると暗記物が苦手になりますが、ガイドに関しては新たな知識を覚えなければなりません。「読むクスリ37」(上前淳一郎)に「二十七士の忠臣蔵」と題してこんな内容が記されています。講談師の旭堂南海さん曰く、「講談とは所詮作り話ですが、場面ごとに人名や地名などの固有名詞を出すことで、話に真実味を持たせることができます。故に忠臣蔵を語る場合には、四十七士全ての名前を覚えなきゃなりません」原稿用紙に1行づつ名前を書いて、机の前に貼り付け、日夜ひたすら読んで暗記したそうな。ところが面白いことに義士の名前の並べ方にはいろんな流儀があって、討ち入りの表門隊と裏門隊の2グループに分ける方法や、石高(収入)による順列や好きな人物の順に並べるなど、各自創意工夫をこらすのだそうな。旭堂南陵師匠は高座での”度忘れ”への備えとして、昔懸命に暗記した原稿用紙を懐に忍ばせておけば、御守になったとか。また兵庫・岡山・広島での高座では熱烈な赤穂義士ファンの年寄り客が多いので、最初に四十七士の名の全てを立て板に水を流す名調子でぶちかますと、やんやの喝采を受け、高座が盛り上がり後がやり易くなると言う話です。 本日から松山道後温泉一泊、尾道などの吟旅です。宿泊は45名、翌日の句会は70名の大所帯となります。では、吟旅の成功と無事を祈願しながら出発致します。
2010.05.09
コメント(4)
-
09’5月の借り出し5冊♪
連休はそこそこ多忙だったことと図書館の休館日もあって、今月7日目になってやっとこさ5冊借りることができました。1)梅原猛著「京都発見1地霊鎮魂」(新潮社) 歴史上の人物と寺社仏閣との繋がりをさりげなく説いて居られます。2)(講談社)吉岡幸雄著「京都町家 色と光と風のダザイン」 著者は染色分野に秀でた方で、色彩と光と風の調和を京町家と行事などを通して説いて居られます。3)黛まどか著「京都の恋」(PHP研究所) 大文字消えて戻りし星の位置」など4)NHK「クイズ日本人の質問」グループ編「日本人の質問 2」(NHK出版) 雑学は少し覚えておくと何かの折に役に立ちそうですね。5)上前淳一郎「読むクスリ 37巻」 久しぶりに借りました。節約がテーマです。このブログにも適宜小出しする積りです。
2010.05.08
コメント(2)
-
いずれ文目か杜若♪
この季節になるとわが家ではジャーマンアイリス(ドイツ文目)と文目が賑わいを見せます。桜の花が散って寂しくなる頃に、これらが慰めてくれます。ドイツ文目の特徴は、通常のトンボと鬼やんまほどの違いほど貫禄が感じられます。近くの長岡天満宮の池畔には杜若(カキツバタ)、菖蒲、文目が咲くのですが、世間では一初(イチハツ)も含めて、毎年この季節には、それらの内、どの花だと自信を持って言えない節があります。私が再々お気に入りサイトとして利用させている「季節の花300」さんではそれらの違いを明かにして下さっています。もう一度、自分で表を拵えて、咲く時期、咲く場所、花の形、葉の筋などを比較して覚えたいと思っています。水中に咲き花の中心に白い筋模様があって葉が幅広で筋が無ければ、これは杜若。乾いた地面に咲き、花の中央に網目模様、葉っぱが細長で突起した筋があれば、これは文目。湿地に黄色の花をつけ、細長葉っぱに突起の筋があるものは黄菖蒲。幅広の葉っぱに幾筋も突起があり、とさか状のひらひらの花を乾いた土地に咲かせるのが一初。区別に躍起になるよりも、その優雅な世界に暫し浸って居たいものですね。
2010.05.07
コメント(8)
-
油断大敵あたら命を~♪
わが家の金魚は既に2度ほど、この日記の話題にしていますが、先日、思いもかけぬ非常事態が発生、台所の流し台の水はけに奇妙なものがありました。よくよく観るとそれは大切に育てている金魚の姿。出窓に置いてある立方体の金魚鉢から、勢い余って飛び出したっきり・・・命を落としていたのでした。そう先日ホテルのベッドで飛び跳ねていた子供さんが6階の窓から飛び落ちが如く・・・。そう言えば、本来、めだか飼育用に戴いた水槽に金魚を住まわせているのですが、ちゃんと透明なプラスチックの蓋がついていたのに、予備の水槽の蓋として使っていました。油断大敵、こういう事故は既に庭の睡蓮鉢からも飛び出して命を亡くした金魚が居た事例があったのに・・・。毎朝パン屑を与えたり、金魚用の餌を与えて可愛がっていましたが、細かいところまで気を使わないといけませんね。1匹になったおとなしい方の金魚が独り者になると性格が変り、能動的な動きを見せています。2匹足して3匹で飼うかどうか思案中です。対(ツイ)は今の金魚が新米を追っかけ廻して死なせることになるし、新しく2匹を足せば三角関係にもなってしまうし・・・。
2010.05.06
コメント(4)
-
誰かが縁の下役を♪
最近は早朝に散歩する習慣が無いので確かなことは言えませんが、”霧島つつじ”で有名な”長岡天満宮”では、寒い冬の朝も奉仕団の方などが本殿へ通じる石段を”無心で”掃いておられる光景を目にしました。昨日夕方から買い物に出かけ、広い通に面した歩道を自転車で通りましたが、綺麗に清掃が施されてていて、清清しい気持ちにさせていただきました。見返りを求めない”ご奉仕の精神”には頭が下がりますね。 外務省の医者としてアフリカに渡った医師が、貧しい現地の住民には医術を施せない立場にあったので、外務省を退職、夫人や家族の了解のもと、単身でアフリカに戻り、住民の病気を治しておられる美談が、2度にわたってテレビ放映されていました。彼と同じ出身校のラグビー仲間だけでなく、日本の各地から応援サポートする人々が増えつつあるようです。滅私奉公のもと、勇気のある行動、信念のある行動は人々の胸に迫るものですね。
2010.05.05
コメント(2)
-
万博あれこれ♪
上海万国博覧会がクローズアップされる毎日ですが、万国博覧会の歴史を紐解いてみたいと思います。ロンドンにて最初に開催されたのは、ルイ・ナポレオンがクーデターを挙行した1851年、日本では嘉永4年に当り、土佐漁民ジョン・万次郎が米船で琉球に護送された年でもあります。第1回目のこの万博では、入場者凡そ604万人、経費は当時の価格で約293万円(現500億?)相当額。翌々年はニューヨークで25万人の人出、’55年にはパリでナポレオン3世主導の下に開催され、560万人。文久2(’62)年のロンドン万博には、竹内下野守一行36名が日本人として初めて博覧会を見学。慶応3(’67)年のパリ万博は商業中心の展示から文化を重視する傾向に変貌、1千万人の入場を見ました。日本からも特設館を建設、出品もしていて外国奉行小栗安芸守がExhibitionを博覧会と翻訳し、福澤諭吉が「西洋事情」を書き、万博を紹介しました。このパリ博の成功が各国内での博覧会の流行の引き金になりました。明治4年、京都、西本願寺で日本最初の博覧会が開催され、以降何年にもわたって続きました。また明治7年は英国ケンシントンで世界万博、ロシアに於いても織物工業博覧会、京都では4回目の博覧会が開かれましたが、石川県金沢市で初の地方博覧会が開かれました。時代は下って明治43(1910)年、日英同盟を記念して開かれた日英博覧会は、日本が初めて企画に参加した万博で、後に大山崎山荘を建てた青年、加賀正太郎もこれを見学すべくシベリア鉄道にて出かけ、途中でヤングフラウの登頂に日本人初の成功者となりました。大正3(’14)年、東京大正博覧会が東京上野不忍池畔にて開催、経費165万円、746万人が入場。昭和15(’40)年、紀元2600年記念として東京での万博が企画されましたが、戦争色濃い国際関係悪化で中止。それから実に30年を経て大阪吹田市千里丘陵を開墾して日本初の万国博覧会が開かれたのでした。当時、銀行に勤めて3年後、桜模様に金泥入りの定期預金証書が発行された記憶が鮮明に残っています。大阪では万博40周年記念活動が盛んで、父の遺した万博グッズをガイド仲間の仲介で出品して戴いたような・・・。参考図書:浜口隆一・山口広共著「万国博物語」(鹿島研究所出版会、昭和41年発刊)
2010.05.04
コメント(2)
-
敬語等の誤使用例♪
話題の達人倶楽部編「大人の国語力が面白いほど身につく!」から、再び抽出させて戴きました。誤りがちな敬語の遣い方として「よく知っております」・・・誤りではないものの、相手が目上なら「よく存じております」「わかりました」 → 「承知しました」「おっしゃられました」・・・これは二重の敬語で不自然だから、「おしゃいました」「お食べになって下さい」・・・一見敬語を使っているようですが、食べるは品位が欠けているので「お召し上がり下さい」「ご都合はどうですか?」 → 「ご都合はいかがでしょうか?」「伝えておきます」・・・これは相手への敬意が感じられませんね → 「申し伝えます」「思わなかったです」「知らなかったです」「来なかったです」”動詞+です” これらはいずれも幼稚な表現だから「思いませんでした」「知りませんでした」などと。要は話し相手への気配り、自分が一歩下がった高さから話す姿勢が丁寧語・敬語を口にする土壌になるのでしょうね。
2010.05.03
コメント(6)
-
お供え満載の仏壇♪
わが家のお仏壇にお供えするものが少ない時は、他の部屋から仏間を経て寝室・書斎へ通る都度、寂しい気分になりますので、出来るだけいろんな菓子類や土産物、戴き物を供えるように努めています。亡くなってからの方が両親との距離が短いと言えば語弊がありますが、少なくとも亡くなって以来、父、母との距離感をそれほど感じることはありません。夫婦の日常会話に私の父母、そして家内の父母に関わる話や思い出話が何度でも頻繁に飛び出します。これほど嬉しいことはありません。哀しみという概念が無く、いつもの生活の輪の中に親が一緒だということに他なりません。本日の付録は自作、東洋の秘境です。緑生い茂る魔境をご想像下さい。
2010.05.02
コメント(2)
-
遊女その2 身請け♪
その昔、遊女が苦界から開放されるには3つのパターンがあったようです。1)年季明け・・・遊女に出る前、親元に払われた借金を客を取ることで返済することに要する時間が年季。それの完済を言います。かと言って今さら田舎・故郷には戻れません。また水の世界で働き、良い縁を探していたのでしょうか。2)身請け・・・年季明け前に馴染み客によって借金を返済して貰い、請け出されるケース。3)死去・・・本人が死んだ場合(哀しさの極み)。では、身請け証文の例をご覧下さい。 証文之事一、其方抱え薄雲と申すけいせい、未だ年季之内ニ御座候へ共、我等妻に致し度く、色々申し候所ニ、相違無く妻に下され、其上衣類夜着蒲団手道具長持迄相添え下され、忝く存じ候、即ち樽代として、金子三百五十両其方へ進じ申し候、(中略)右之薄雲若し離別致し候ハば、金子百両ニ家屋敷相添え、隙出し申す可く候、後日の為め仍て証文件の如し。 元禄十三年 辰ノ七月三日 貰主 源 六 印 請人 平右衛門 印 同 半四郎 印 遊女:薄雲は身代金350両にて源六の妻として身請けされ、以後は遊女まがいの行為、或いはそちらの場所への出入を堅く控える事を誓い、もし守らなければ、御公儀様に訴えられ、どのようにされても異存がない旨を述べ、離別した時は慰謝料の事にまで触れています。 享保20年に太夫になった高尾の場合、7年後の寛保元年には、一旦、久兵衛という者の娘として身請けされていますが、実際には1800両にて姫路15万石藩主:榊原政岑の妻となって居り、この為政岑は不行跡を理由に隠居を命じられ、藩は越後高田15万石へ移封させられています。 遊女たちは身請けされたものの、それまでの傾城ぐらしが身に染み込んで居て、何かにつけて辛かったものと思われます。 (参考図書:「遊女」西山松之助編の宮本由紀子氏担当稿)では付録の拙作です。ちょっと物悲しいメロディですが・・・。野沢菜節歌詞は下をご覧下さい♪1)なんなん 菜の花 誰 くれた 偉い坊さんが 京のかぶら はるばる運んで 植えつけた2)長閑な田舎に 灯が点いた 天道いろした 黄金の灯が 上杉殿様 国自慢3)こりゃまた 美味いぞ 良え菜じゃな 塩でちょい揉みゃ なお良かろう 銭生む宝の 土産もん
2010.05.01
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1