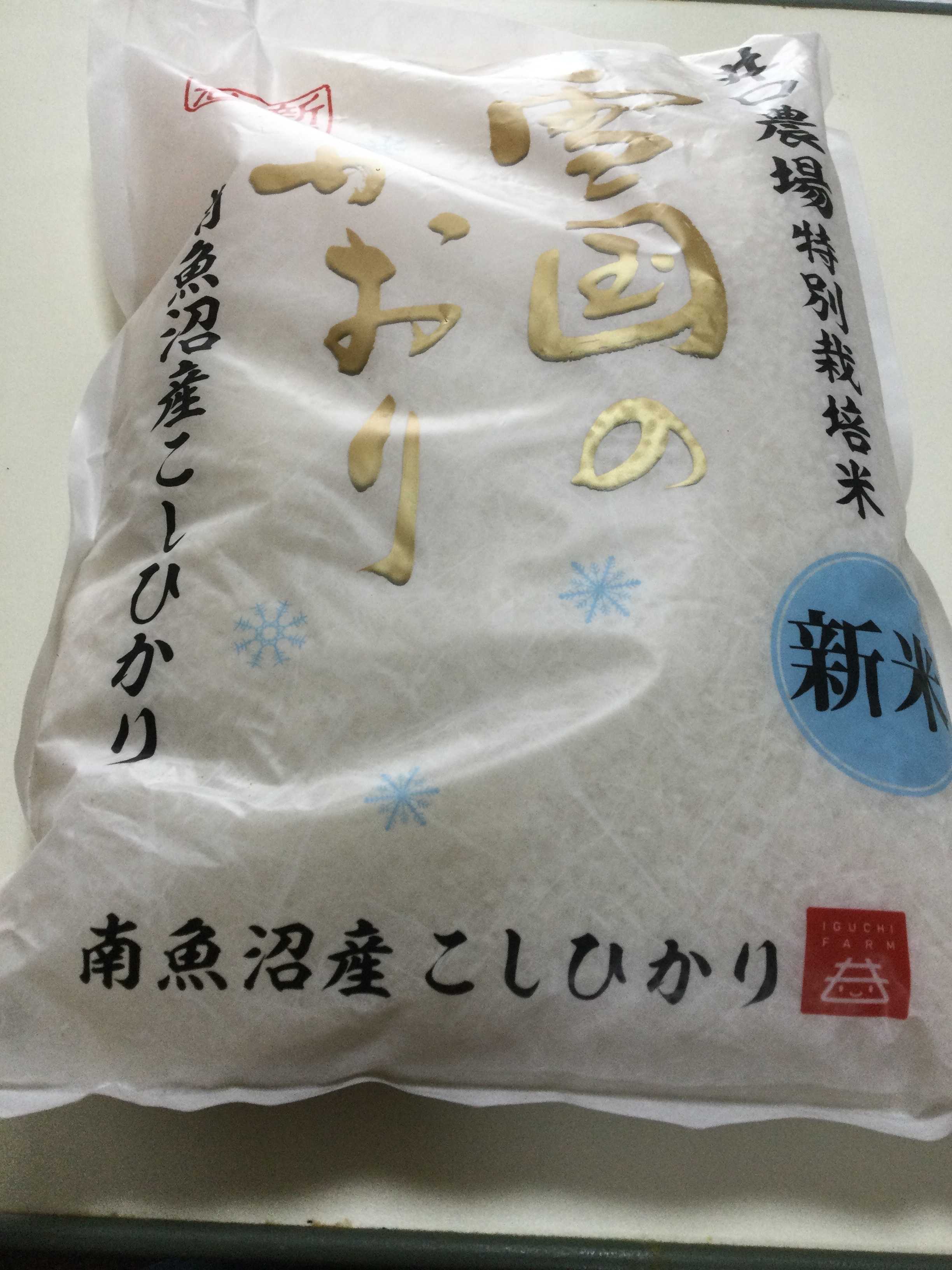2010年09月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
「戦国史新聞」(日本文芸社)より♪
自分達が生きている現代の中で、古き時代に生じた史実を伝える場合、新聞そっくりの形、或いは講談のような語り口で行えば、第三者には親密感が増して伝わり易いのかも知れません。わたしが青年だとして”お笑い界”の中で、他のライバルから突出したいとすれば、”講談そっくりの語り口”に”笑いのエッセンス”を織り込んで観客の心を掴むことでしょう。 さてさて、ここに紹介するのは、戦国史新聞編纂委員会編の「戦国史新聞」(日本文芸社)という面白い図書。通常の新聞と同じつくり、形式になっているものです。そっくりそのまま転用します。 見出し(事件の顛末)<羽柴軍驚異の大返し> ”仇討ちを実現させた外交手腕” <本能寺の変が起きた6月2日、織田軍の軍団長は、いずれも京都から遠く離れた場所にあった。柴田勝家は越中、羽柴秀吉は備中、滝川一益は上野、さらに織田家の盟友・徳川家康は数人の家臣を連れ、堺見物の途中で、畿内は軍事的な真空地帯となっていた。諸将が引き返してくるまでの時間を利用し、畿内における勢力を確立する、というのが、明智光秀の反逆後の戦略だった。事実、柴田勝家は上杉軍に手こずり、徳川家康は三河に帰国するのが精一杯。滝川一益に至っては、北条軍に大敗を喫し、上野から伊勢長島に逃げ帰る始末だ。摂津で待機していた丹羽長秀と神戸信孝(信長三男)も、明智軍との衝突を避けており、明智光秀の予定どおり十分な時間稼ぎが可能なはずだった。 しかし、備中高松の羽柴秀吉だけは例外で、6月3日に変の報を受けて以来、迅速に兵をまとめ、6日に高松を出発。1日に30~40キロを進むという強行軍で、12日には富田に到着し、翌13日には明智光秀と雌雄を決した。ちまたでは羽柴軍の行軍速度が大きく取り沙汰されている。だが真に注目すべきは、変を知った翌日に和睦交渉を成功させ、その直後に撤兵を開始した、羽柴秀吉の転進の速さだろう。中国情勢に詳しい関係者の談話によれば、毛利家は撤兵開始以前に織田信長の死を知ったと言われるが、羽柴軍は背後を脅かされことなく帰還した。北陸の柴田勝家が、上杉軍の追撃を用心するあまり出遅れた状況を考えると、羽柴秀吉は毛利家を巧妙に懐柔したと推測される。外交交渉の巧拙が、撤兵の成否を左右した事実は注目に値する。> 1582年(天正10年)版のこの新聞には、ほかに、<わずか12日間の天下 「山崎にて明智軍敗れる」>や<「織田家後嗣は嫡孫三法師」 ”柴田勝家派は面従腹背の姿勢か” >や記者の目のコーナーでは「清洲会議の明暗」ほかに、「天正遣欧使節、ローマにて出発す」の見出し・記事が書かれていました。 この新聞には明智光秀が襲撃されただろう竹薮小道の写真や、丹羽長秀の人物画、秀吉が三法師を肩に乗せている絵、故織田信忠や織田信雄の人物画、天王山の戦いでの突破口を開いた池田親子の人物画まで載せてありました。 大山崎ふるさとガイドの一員として、このように現代風に説明すると、お客さんにも親しみを覚えて貰えるかも知れません。
2010.09.30
コメント(2)
-
「新京極」某アンケート♪
今も京の歓楽地として賑わっている”新京極”は、もともと誓願寺や金蓮寺などの境内だったところ。境内では古くから参拝客相手の茶店や見世物小屋で賑わっていたようです。明治初期の京都大参事であった槇村正直氏が、ここに娯楽場を設け、商店を誘致し、首都時代の活気を取り戻そうとしたのが明治5(1872)年のこと。 昭和28(1953)年4月30日の京都新聞によると、新京極連合会の依頼に基き府能研が調べたアンケート結果が纏められています。(客層の住居地) 市内70% 府外10% 府下20%(目的) 買物20数% 遊び約50% ぶら歩12% (店の応対) 京都にしては不満が多数 親切20%(時間の過し方) 映画、娯楽場、飲食店利用 60%(利用時間帯) 午後4時半~6時が最も雑踏し、時間当り片側通行者千人に達す(印象) 低俗さを減らし、もっと上品な通りにとの意見も少なくない老年層は昔の方がもっと落ち着いていたとも。アンケートの年には連合会ではアーケード建設の準備をしていたが、その必要性を希望する意見が圧倒的に多かったとも。看板・張り出しテントや2階のスダレが埃で黒ずんでいたことや、道路に落ちている紙クズも印象が悪いようでした。 さて現代に遡りますと去年、今年は景気がよろしくないのか、昔ほどの混み合いを感じないように思います。
2010.09.29
コメント(0)
-
秋の七草♪
秋の気配が日増しに濃厚になるにつれ、落ち着きを取り戻して来た感が致します。秋を彩るものは多々ありますが、一番ポピュラーなものは所謂”秋の七草”。七種類の名前を覚える方法を思いついてから、すらすら言えるようになりました。「お好きな服は?」→女郎花、薄、桔梗、撫子、藤袴、葛、萩。 源氏物語の手習いの巻には、垣根のあたりに植ゑてあります撫子もおもしろく、女郎花、桔梗なども咲き初めてゐるのでしたが、色々の狩衣姿の若い男共を大勢連れて、・・・と書かれていたり、みのりの巻には紫の上の御歌 おくと見る程ぞはかなきともすれば かぜにみだるゝ萩のうはつゆまた桐壺の巻では桐壺帝の 宮城野の露ふき結ぶ風のおとに 小萩がもとをおもひこそやれやどりぎの巻では中の君の 秋はつる野辺のけしきもしのすゝき ほのめく風につけてこそ知れ夕霧の巻では一条御息所の 女郎花しをるゝ野辺をいづことて ひと夜ばかりのやどをかりけんあげまきの巻の中宮大夫の 見し人もなき山里の岩がきに こゝろながくもはへる葛かなそして藤袴の巻には夕霧の おなじ野のつゆにやつるゝ藤袴 あはれはかけよかごとばかりもなどの歌が添えられてあります。少しは雅の世界に浸っていただけましたか?
2010.09.28
コメント(4)
-
虫の音に寄せて♪
お盆の頃から耳にした”鉦叩”やキリギリスの声。9月も最終週となりますと、正に虫しぐれの季に当り、いろんなストリングスを聞くことができますね。それらの中で音楽的な音色は、マツムシのチンチロリン、鈴虫のリ~ンリ~ン、そこはかとなく寂しいコオロギの鳴き声。長岡天満宮八条ケ池の堤下に沿う道を歩くとき、しみじみ秋のふところの深さを思います。 コオロギの鳴き方には3種類あって、雌を誘い出す誘惑鳴き、自分の縄張りに踏み込む敵に対する警告鳴き、それに自分の縄張りを知らせる宣告鳴き。よく耳にするコロコロと寂し気に鳴いているのは縄張り宣言の口なんだそうです。驚いたことに、その縄張りの半径は4メートル、警告しても去らない敵には、時として喰い殺すこともあるとか。余り知識を増やしてしまうと、返って興醒めになってしまいますが、次のサイトは面白そう。「・・・虫の声」そして再びネットで検索して、いろんな虫の声を楽しんで下さい。本日の付録、パソコンによる自作の曲は「秋夜」です。12段もの五線譜を使って作曲しました。
2010.09.27
コメント(4)
-
山の神♪
興津要さんの「おもしろ雑学日本語」(三笠書房)の中に面白いものを見つけました。< 「山の神」 山の神通う神をばこなみじん 捨6”通う神”と言うのは、遊女が客に出す手紙の封じ目に書く文字だが、怒った女房が引き裂いた光景。このように結婚後数年を経て、うるさ型になった女房を”山の神”と呼んだ。語源その1 いろは説 それは妻を奥と言うが、<憂いのおくやま・・・>と、”山”の上(カミ)に”おく”があるから”山の神”と称したとする説。語源その2 「俚言集覧」説 この書では、上の説を否定し、”とり乱したる姿を喩えて言うなるべし”との見解。語源その3 柳田国男説 山の神は多くが女性であり、山姥の子育て伝説など、山との関係が深いと説く。語源その4 暉峻康隆説 農村で、山の神を祀るのは女性が司っていたからという説。語源その5 杉本つとむ説 山の神というのは、農民の間での女神で、十二の子を産むと言われ、神への供物であるオコゼ魚を女が食べると、生まれる子が荒っぽくなるとの伝えがあり、この妙に元気の良すぎる女房を、下々で山の神様になぞらえて、山の神と呼んだのでは?とする説。>奥さんをして、山の神という表現を耳にするとき、わたしには恐妻、嬶殿下といういうイメージを持ってしまいます。
2010.09.26
コメント(5)
-
草城が遺した収支明細簿♪
俳句結社「京鹿子」の月刊俳誌が発行されて丁度1000号になったのが平成19年の12月号。それを記念してA4版479頁の1000号記念誌が手元に届いたのが20年の5月。その実行委員会のメンバーを経て、現在は「京鹿子」誌の編集を任せて貰っています。 話は19年12月号に戻ります。表紙裏の上段には「京鹿子 収支明細簿」と書かれた大学ノートの表紙。下段にはその1頁目、創刊号の収支が左右にきちんと書かれています。1000号の1頁は高木智さんの手によって写真への説明が加えられています。そのまま載せますと、<何事にも綿密な仕事をした日野草城は、大正9年11月に「京鹿子」を創刊した時、自分の担当した3年分の経費の明細簿を、残している。それによると、創刊号は、収入の部が、岩田紫雲郎3円、田中王城、鈴鹿野風呂各5円、学生の高濱赤柿、草城、中西其十がそれぞれ1円の合計16円。支出は、印刷所支払9円50銭、送料切手1円で、残額5円50銭となっている。この創刊号は150部印刷された。>とあり、わが家にも創刊以来の月刊誌が父すばるの手によって遺されていました。現在の発行部数は10倍の1500冊程度。毎月20日過ぎから翌々月号の編集準備に着手しています。
2010.09.25
コメント(0)
-
永六輔選「一言絶句」♪
最近疲れぎみなので、安直な日記になって済みません。先ずはかくお詫びしてから、以前にも載せました永六輔さんが選んだ全国からの「一言絶句」から適宜摘みました。コメントはすべて私が挿んでいます。”一年の計は簡単に”(新田有理) あんまり欲張ると三日坊主に・・・。”人生は小説よりも愚かなり”(福島小代子) わたしなら、こう詠みたいな ”人生は小説よりも豊かなり””健康にこだわりすぎる病気です”(黒田早元) これは至言ですね。自分なりの生活リズム こそ大切なのかも。”寿命だけは控え目に生きるな 母よ”(山沖勉) お母さんの背中を見て育った子たちの率直な感想、慎ましやかな老婦人が目に浮びますね。”ボケた嫁を看取る姑”(井上三夫) 高齢化社会の側面なのかも知れません。”少しづつ親に似ながら老いてゆく”(黒子青磁) これが一番自然な流れでしょうね。”皺と汗の人生なのです シワアセなのです”(岡村治子) 額や頬に刻まれた皺は、人生の勲章なのかも・・・。
2010.09.24
コメント(0)
-
松尾社の観月祭♪
ボランティア・ガイドに属し、「大山崎歴史資料館」本日23日午前中の当番でしたので、今帰宅しました。夕方には大阪の家内の実家にて義弟の二タ七日中陰に間に合うよう出かけます。 さて昨夜は酒の神様で有名な松尾神社の「観月祭」に参加しました。5時過ぎから観月祭の神事が厳かに始められ、琴や尺八の演奏、7時過ぎからいろんな団体の和太鼓の熱演がありました。この間を利用して、お神酒やお弁当、酒饅頭などを戴きながら句作。投句(2句)の締切は8時なのですが、生憎天候がはっきりせず、望月を詠むべきか、それとも少し降りだしたので雨月か、はたまた月が出ない無月を詠むべきか迷いましたが・・・。特選3句のうち、2句は普段親しくして戴いている句友。秀逸5句にも2人の友の作品、入選10句の中に、自分の作を含めて同じ結社の方々の4句が並びました。◎まつのをの水音さても月の笛 珀眉◎ゆふるりと手水の溢る観月祭 せい子○雲の扉の開くを待ちて観月祭 照子○大前に月影となり平伏せり 公子 神楽舞ふ巫女の緋袴良夜なる 栄子 わが齢おだやかにして月仰ぐ 冨美子 ちはやぶる太古の山や今日の月 久子 覆ひ来る神名備にして無月かな 星子弁当代を含めた参加費用(予約)は2,500円。雨降りで無月に終始するのかと諦めていましたが、梢の合間から顔を出す望月、煌々と差す月光をも目に出来ましたので満足の行く催しでした。
2010.09.23
コメント(4)
-
通円良三著「橋守八百年」♪
源氏物語宇治十帖で有名な名所・宇治橋の袂で茶舗を営んでおられる通円さん。良三さんで第22代と言うから由緒の正しさは勿論、代々伝えられるお宝も相当なものと思われます。今から丁度30年前の昭和55年3月に発刊された「橋守八百年ーーーあるじ茶のみ咄ーー」には、豊太閤から下賜された釣瓶の写真が載っています。本の内容は控え目な文体ながら、通常知りえない事柄や茶にまつわる逸話などが芳醇に綴られている名著です。目次の中から興味ある見出しを拾ってみると、一休と通円、宇治七茗園と七名水、宮本武蔵と通円茶屋、御茶壺道中、太閤秀吉と宇治の橋守、大福茶の話、呂宋の壺、太閤堤の謎にメスなど枚挙にいとまがありません。また付録に載せてある茶人の花押は厚巻です。足利義政、織田信長、秀吉、細川忠興、松永久秀、蒲生氏郷、前田玄以、長谷川宗仁、尾形光琳、千道安など錚々たる人々。
2010.09.22
コメント(0)
-
彼岸花豆ちしき♪
昨日9月20日は敬老の日であり、彼岸入りの日でした。彼岸とは煩悩から脱却した悟りの境地の世界のことで、煩悩や迷いに満ちた”この世”を”此岸(シガン)”と言い、向こう側の岸(”あの世”)を彼岸と言い区分しています。彼岸の期は太陽が真東から昇り、真西に沈むので、西方に沈む夕陽を拝み、遥か彼方の極楽浄土に思いを馳せたのが彼岸の始まり。 今朝のニュースでは今年に限って秋彼岸でありながら、まだ彼岸花が咲かないのだそうです。江戸時代の農民は飢饉になると毒以外のものは何でも口にして飢えを凌ぎました。草木、花、根、昆虫、土壁に埋めてある藁さえ食べたようです。岩木山、浅間山が噴火し、数万人が餓死したと言う天明の大飢饉には、江戸幕府から全国の農民あての御触書には、藁の料理法が事細かく書かれているとか。澱粉を豊富に含む彼岸花を安易に食べてしまうと、次は人をも食らうという理由で、彼岸花は毒の花、死人の血を吸って咲く縁起の悪い花としてブレーキをかける智恵が働きました。実際には水に晒すと彼岸花の毒性は簡単に除くことができるので、現在なお全国津々浦々の田畑で植えられているのです。 行く末は格子女郎か曼珠沙華 星子
2010.09.21
コメント(4)
-
それもあり~??♪
例によってビックリハウス版「大語海」の”キ”から拾ってみました。疑心暗記・・・果たしてこんなことを覚えて何の役に立つのだろうかと思いながら、英単語を覚えること。斯親暗記・・・親に欺かれた子供が綴る暗くて悲しい日記。危険帽子・・・穴の空いたコンドーム。競技離婚・・・結婚から離婚までのスピードを競うこと。主に芸能界で流行っている。嘘弱退室・・・体の具合が悪いと嘘をついて教室から抜け出すこと。鬼走転外・・・節分の豆に追い立てられて鬼が家から逃げ出す様。気象転決・・・天気予報は下駄を投げて決めるという、気象庁の奥の手。偽矛教育・・・偽りと矛盾に満ちた現在の教育。客寒的・・・さめた目で見ること。急襲男児・・・チカン。金獲寺・・・現在の寺の実態。窮々車・・・満員電車。脚商売・・・ダンサー。全国から寄せられた駄洒落、どれも面白いですね。
2010.09.20
コメント(4)
-
先週の日曜♪
12日の日曜日、朝食の最中に家内の携帯が鳴り響き、意外に長い電話、家内の表情がどんどん曇っていきました。例の振り込め詐欺かなと思いましたが、それは香川県の坂出警察暑から。家内の弟がサークル活動の旅先で急逝したという訃報でした。甥二人は彼らが小学生の時、その母を亡くしていますので、大阪の自宅で深寝入り中の彼らは、それとも知らず、一瞬にして孤児(ミナシゴ)に。 10時頃やっと繋がった甥らに、私から3年前の葬儀の資料を探すよう指示、葬儀屋と交渉させ、彼ら二人は遺体引取り用の車に同乗させて貰い、坂出へ。私ら夫婦は新幹線で岡山経由坂出へ。葬儀用の衣裳など提げ、長男は家内の実家へ行かせ、長女はこの長岡の家で親戚からの電話応対、情報連絡詰め所としてしばし居残るよう指示。 今年の五月、俳句結社の吟旅で鷲羽山から高速路を渡ったことを思い出しつ、今度は鉄道で鳴門大橋を渡りました。坂出駅に到着後は、警察・死亡先のホテル挨拶、病院などタクシーで廻り、とんぼ帰りで大阪の実家に着いて間もなく、通夜、葬儀の段取り・・・と目まぐるしく対応しました。それにしても、病妻への看護、母親への看護、そして父への介護と病人への相続き、男児2人を育て上げ、これから自由人として楽しめるという絶頂期に命を断たれた義弟の人生・・・。 私の母が5年前、リフォーム前のこの家で心臓発作で急逝、家内の従姉妹の夫君も、その他数名が何の前触れもなく急逝しています。こういうことはありがちですので、新婚当初から家内に言い聞かせてきましたが、やはり、無常と言えましょう。 信心深い母は仏壇の前で、毎日朝夕、長い時間拝んでいました。短い時間ながらその習慣はわたしも継いでいます。仏壇の前で・・・あれや・・・これやら・・・。
2010.09.19
コメント(2)
-
切抜きの”こども風土記”♪
きのこの椅子に腰かけてしゃぼん玉を膨らませている愛らしい妖精ふたり、もう一人は同じ赤い衣裳に身を包み立ち上がったまま、しゃぼん玉を吹いています。表紙だけがこんな柄の、無地のノートに、大小さまざまのこけし模様の千代紙で包んであります。その表紙の上にさらに、赤地色した紙に、新聞の見出しを一字づつ分けて貼り付けてあります。 「こ ど も 風 土 記」(柳田国男) 誰にあげる積りだったのか、オレンジ色の画用紙の切片に、♪ の模様を貼り付け、マジックペンで書かれたことば、<昭和16年4月1日から5月27日まで朝日新聞に連載されたものの切抜きノートです。古くからあるこどものあそびを民俗学的に正しく解説した名著です。昭和24年1月に発表された戯曲「夕鶴」に出てくる鹿鹿つの何本、ねんがら、かごめかごめなどのあそびも解説してあります。> 39回で完結するこのシリーズの1番目は”鹿・鹿・角・何本”。 一人の子が目隠しをして立ち、その背後で別の子が、簡単な文句で拍子をとりながら背をたたき、その手で何本かの指を出して、その数を鬼役の子に当てさせる。英語の問ではHow many horn has the buck?”いかに・多くの・角を・牡鹿が・持っている?” このように日本語は5つと英語では6つの単語で表現しますが、ドイツは5つ、イタリアでは4つ、スエーデンやトルコでは2つの単語で囃すのだそうです。この遊びをするのは他に、スコットランド、フランス、ベルギー、オランダ、ギリシャ、スペイン、ポルトガルなど20カ国近くあると言っています。 シリーズ中、遊びの種類としてあてもの、かごめかごめ、中の中の小仏、地蔵あそび、鈎占い、ベロベロの神、ねんがらなど。また圧巻はこどもの遊びの起源を解説されている稿です。 父の新聞の切抜きは重宝できるものが多く、もう茶色に変色しかかっているものもありますが、川端康成「古都」シリーズはすべて挿絵がついているし、文豪のエッセイなども捨てきれないのです
2010.09.18
コメント(0)
-
しびれるとしびれがきれる♪
今月に入って2度ほど、木曜日の夕方7時から2時間、大山崎町の公民館2階の和室にて、”お茶のお稽古”をしています。来年の国民文化祭に備え、今年はそのプレとして大山崎の資料館、宝積寺、そして観音寺下の桜公園広場の3カ所でお茶を振舞う、その下稽古なのです。 皆さん真剣に熱心にお稽古している訳ですが、いけません、ずっと座していると膝が言うことを聞かないのです。町職員の若い男性は軽々と立ち坐りが出来ていらっしゃいますが、我等ロートルはついふらつきます。お茶請けの合間は胡坐(アグラ)でも良いと言われるものの、ついつい正座してしまいます。そして永く座っていると”しびれ”がきれます。 金田一春彦さんは「ことばの歳時記」の中で、「しびれる」と「しびれがきれる」との違いを指摘しておられます。”大言海”に拠れば、「しびれる」は、血行がとまり、全く感覚がなくなって、その部分をたたこうがつねろうが全然感じないことを言うに対し、「しびれがきれる」は、少しずつ血行が始まってくるために、ビンビン鳴っているような感じを言う。感電した時に、「しびれる」と言うのは、後者の状態に似ているから「しびれがきれる」と言う方が正しいと述べておられます。
2010.09.17
コメント(2)
-
油の神様♪
9月16日(木)付け京都新聞の20面をそのまま転載しますと、 さらなる発展祈願 離宮八幡 創建1150周年記念祭という見出しがあって、 大山崎町大山崎の離宮八幡宮で15日、「創建1150周年祭」が営まれた。製油業界の関係者や地元住民ら約120人が参列し、中世に油座の拠点として栄えた歴史を振り返るとともに、今後の発展を祈願した。 同八幡宮は859年、僧行教によって豊前国宇佐(大分県)の八幡神が勧請され創建されたとされる。嵯峨天皇の河陽(カヤ)離宮があったことから「離宮八幡宮」とよばれるようになったという。「創建1150年」に合わせ、昨年は本殿の屋根の葺き替えや拝殿の増床工事が行われた。 記念祭は供え物の油缶がずらりと並んだ本殿で、雅楽が奏でられる中、行われた。出席者は油を入れて火がともされた小皿を受け取り、正面に据えられた八足台に置き、厳かに献灯した。無病息災を願い、巫女が釜で沸かした湯に笹の葉を浸して振り撒く湯立神楽の神事も行われた。 津田定明宮司は工事に対する企業や個人の協賛に謝意を示し、「油商人発祥の地として、今後も国家の安康や国民の平穏を目指して務めを果たしたい」と挨拶した。(注、仮名部分を一部漢字に換えて掲載しました)
2010.09.16
コメント(4)
-
十一面観音♪
京都府乙訓郡大山崎町の天王山山麓にある「宝積寺」の本殿は、白蟻の被害に遭っていたので、現在床下など修復している最中ですが、ここの十一面観音さまは、聖武天皇の行幸に際して、流れていた山崎橋を架け直す工事をしている折、川の流れの勢いに、なかなか捗らない時、一人の老人が工事に加わり、水際立った働きをしてくれたお蔭で無事橋を架けることができたので、村人がその後をついていくと宝積寺の本殿辺りで姿を見失いました。そこで本殿に立っておられる十一面観音の裳裾に触れてみると、明かに濡れていました。ああ、あの老人はこの十一面観音さまの化身だったのだと村人は感謝し、爾来、「橋架け観音」と呼ぶようになりました。 ところで私が一番美しいと思う十一面観音さまは、近江の国は渡岸寺の観音さま。<鶴林寺のそれに較べると、いかにも貞観時代の豊満さ、むっくりとよくふとった足の指、右足をふみだしたひざの肉、それにくきっとひきしまったウエストのくびれ、ほどよくはりきったおなかに、美しいくぼみをみせたこのまろい腹部の、なんというあったかさ、うるわしさであろう。おもわず頬ずりしたくなるような十分の蟲惑をひそめ、見事な充実を示す腹部は、女ながらも眺め入って飽きない。>とは随筆家・岡部伊都子著「観光バスの行かない・・・」(新潮文庫)にある感想です。
2010.09.15
コメント(2)
-
急場に釘を刺す♪
今朝雨戸を開けた途端、きな臭い匂い、煙の匂いがしたので、庭に出てご近所を確かめました。別に火事では無かったようです。きっと事前に消防署の認可を得て焚き火でもされたのでしょう。枯れ葉を集めて焚き火、その中に生の薩摩芋を入れておき、ほくほくの焼芋を食べる等ということが通常は出来ないご時世になりました。 さてマクラはこのぐらいにして「火事」に関するユーモアを秋田実さんのものから3題拾いました。 540話 釘を刺す 電話のベルが鳴った。消防署員が急いで受話器を取り上げると、受話器の向うから物静かな婦人の落ち着いた声が聞えて来た。「もしもし、私共では、先だって庭に歌壇を作ったのです」「こちらは、消防署ですよ」「わかっています」と老婦人は静かな声で続けた。「この歌壇には薔薇やダリアやチューリップや、その他いろんな高価な球根を植えたばかりの処なんです」「それが一体どうしたというんです??」消防員がイライラして怒鳴るように言うと、「ですから、お宅の署員の方がお出でになった時に、私共の歌壇を荒らさないように、よく気をつけて欲しいのです。今、お隣りの家が火事です!」 541話 ちゃっかり ボーイが、ドアを激しく叩いた。「お客さん、起きて下さい。ホテルが火事です」すると部屋の中から、泊っていたスコットランド人が答えた。「よオし、分った。その代り、ホテル代は払わないぞ!」 543話 名答 映画館の経営者が自分の劇場に火災保険をかけることになった。そして契約書にサインをして加入手続きを終えてすぐ、保険会社員の方に向き直ると、たずねた。「もし私の劇場が、今夜焼けたとしたら、どういうことになりますかな?」「そうですな、今までの私の経験では、まず10年の刑というところですな」と、冷たく答えた。
2010.09.14
コメント(2)
-
ペアーの言葉探し♪
頭脳強化パズル製作委員会編「頭の良くなる漢字パズル」から。 以下の文で、<>で囲まれた言葉への対義語で○○を埋めて下さい(ここは小生の文)。1)舞踏会で、紳士は○○と華麗に踊った。2)長い間、身柄を拘束されていたが、ようやく○○された。3)今まで倹約して貯めたお金をギャンブルで一度に○○した。4)興隆を誇っていた古代文明も、時代とともに○○していった。 1)~5)のグループの漢字は、それぞれある共通の部首を付け足すと、違った漢字になります。その部首を下のa~eから選らんで下さい。1)公・毎・主・反・白2)化・秋・西・田・牙3)兄・土・鼻・垂・今4)次・有・曽・乏・加5)日・口・耳・各・活部首)a門 b口 c木 d貝 e草程よい脳の訓練ですね♪
2010.09.13
コメント(0)
-
扇風機♪
猛暑日も漸くケリが着きそうで、朝夕少し涼しく感じます。記録破りの今年のような暑さでは、生命保存の為クーラーに頼らざるを得ませんが、クーラーが一般家庭に入る前は、扇風機が大活躍していました。電気を動力とする扇風機が日本で初めて売り出されたのは明治27(1894)年のことで、輸入品でした。国内での生産が軌道にのったのは、大正4(1915)年。ところが同年7月3日の京都日報の記事では、京都市の事業部を通じて扇風機の貸し出しが始まり、100台を越えたとか、電燈用の回線を使うのは違反ゆえ、今で言うクーラー専用の回線のように、扇風機使用の為の電流引用の申し込みが500件を超え、多忙極まりないと報じてあります。とすれば、やはり京都の市民生活が余所より進んでいた証にもなります。家庭一般電気料と扇風機がらみの電気料を併せると1日当り11銭4厘の贅沢だったとか。(参考資料:岡満男「新聞と写真にみる京都百年」)
2010.09.12
コメント(4)
-
4つの人ザイ??
上前淳一郎さんの「読むクスリ」から目に飛び込んで来た表題です。評論家の坂川山輝夫さんが説かれるには、「組織には人財、人剤、人在、人罪という4つの人材があって、競争社会にあって企業を勝ち残らせるだけの技術力や専門的な能力をもった社員を1番目の”財”と分類、生きる辞典とも言うべき博学の人や職場の空気を明るく和やかにする人、要するに組織の活性剤的存在の人を2番目の”剤”と称し、賞味期限や耐用年数の切れた社員、給料を払うほどの存在価値の少ない社員が3番目の”在”、そして若い層のユニークな立案をもみ消したり、自分の若い頃の自慢話に終始するような、企業にとってマイナスになる管理職らを最後の”罪”に分類しておられます。 中高年管理職の講習会場で坂川山輝夫は、この話の後、「さて皆さんはこの4種類のうち、どのタイプですか?」と意地悪く質問されます。場内のどの管理職も「私は当然、人財、或いは人剤」という顔つきなのですが、俺が居なけりゃ会社は困るとその人達は思っているようですが、”ひょっとすると、居なきゃ~もっと会社が伸びる”。
2010.09.11
コメント(0)
-
磯田多佳と夏目漱石♪
夏目漱石が祇園の磯田多佳の仲介で、この大山崎山荘を訪れた当日の模様が、女性らしい細やかさで彼女の日記に綴られていましたので、レポートに加えました。磯田多佳は祇園の地方(じかた)の出ですが、歌人として、その才能を発揮しました。文芸芸妓と言われる所以です。彼女の許には著名な文人や芸能人がいました。漱石は言わばその代表格で、どうも二人とも頑固なところがあったようで、北野天満宮の梅花祭見物では行き違いがあったようで、漱石が気分を害したようです。漱石から多佳への書簡には、辛辣な文面もありました。また谷崎潤一郎は多佳のことを「青春物語」に詳しく書いています。彼女と親しかった文人はこの他、長田幹彦、高浜虚子、吉井勇など多士済々でした。そして67歳で没した翌年の5月に、彼女を偲んで「故磯田多佳女 追善演芸会」が多佳が女将であった「大友」の近く、源光院で開催されました。現在は祇園の新橋には「大友」は存在しません。その代わり、吉井勇の有名な「かにかくに 祇園は恋し 寝るときも 枕の下を 水の流るヽ」の歌碑が建っています。 <本日の日記は、杉田博明著「祇園の女」新潮社を参考に記述しました。>
2010.09.10
コメント(0)
-
11月借出しの図書♪
長い間、図書館を利用しませんでしたが、家内の返却期限に合わせ、本日5冊借り出しました。1)「歴史不思議物語」井沢元彦著(廣済堂出版) 壬申の乱はクーデターだったとか、大和朝廷乗っ取り!だとか、謎の美女:小野小町などなど。2)「日本史小百科 家具」小泉和子著(近藤出版社) ガイドにも、俳句を詠む材料にも好適。3)「読むクスリ 第10巻」上前淳一郎(文芸春秋) もうこれは何度でも借りています。一体第何巻を読み終わり、何巻が未読なのか管理できていませんが、この日記を書くのに便利な本です。4、5)「悦びの流刑地」「魔羅節」いずれも岩井志麻子著(集英社、新潮社) この異色の作家の強烈な世界は、小説だから面白いけれど、昔の日本の田舎の出来事なのかも? 本日はプレ京都国民文化祭として、大山崎は離宮八幡さんの境内で、定点ガイド並びに、御茶を飲まれる方々の引率、案内、誘導役を仰せつかっています。午後からは家内の実家へ行き、祖母の17回忌・仏壇前に侍ります。
2010.09.09
コメント(0)
-
江戸期、象到着時の手紙♪
この話は以前、日記に書いたものですが、しみじみとした親子の情が秋に相応しいので、もう一度載せたいと思います。 享保14年(1729年)5月、ヴェトナムから長崎を経て百日余りかけて、遥々江戸に牡象が到着しました。江戸に詰めていた各藩の藩士たちは、こぞって珍しい象のことを国許に連絡していました。水戸藩の西野稲衛門景隆という藩士の手紙が3通、私信も含めて、その写しが残されています。その中の、幼い息子に書いた手紙と奥方へのそれが、いずれも活き活きと書かれていました。 <お父さんは象という陸の上で一番大きな動物の世話役を果たしたよ。その餌の準備に苦労したけれど、お役目柄、病気除けになるというお饅頭の食い残りや、身体を拭いた布を持っています。お母さんに贈るから、お前も少し齧りなさい。そして早く象のように大きくなって、母さんを助けて上げなさい。母さんはいろいろ五月蝿いだろうが、お前だけでなくお父さんにもそうだから、我慢しなさい。男とはそういうものだ。象は子供好きだそうで、子供たちを背中にいっぱい乗せてあげるということで、実際に江戸の我が藩にも来た時、象使いがそのように象を膝まづかせたのだが、誰も乗る勇気が無かったが、お前は、その位いの勇気を持ちなさい。是非、お前を乗せたかったなぁ。殿様の前で象が披露されたのだが、無事、世話役を務め、くたくたに疲れた、その夜、父さんが象使いになって水戸まで象を連れてゆき、お前を乗せてやろうと思った所で、夢が覚めてしまった・・・。 妻への手紙には、財政厳しい折、象の餌の手配は大変だったけれど、国に残しているお前の苦労を思った。お前や子供のことがとてつも無く大切なもののように意識した。象の係りになって本当に良かった。あの象からいろいろ教えられたように思える・・・。 6月29日 おやすどの いなえもん これは海野弘(うんのひろし)氏著の「江戸妖かし草子」(河出書房新社)から抜粋した「象を見た」の一節を参考に書いたものです。海野氏は、江戸時代に詳しい作家のようで、江戸時代の豆知識を、各節ごとに附して下さっています。江戸庶民や武士や風俗習慣が手に取るように解る名著だと思います。
2010.09.09
コメント(0)
-
秋刀魚に寄せて♪
近くのスーパーへ行くと、魚コーナーには旬の秋刀魚が青刀の反りを見せて並んでいます。落語の世界では、或る殿様が目黒の農家に立ち寄ったところ、昼餉にサンマを振舞って貰いました。熱々で脂の程よく乗った旬のサンマの美味さが忘れられず、藩邸に戻ってサンマを所望しました。しかし、藩の料理人から差し出されるサンマは先ほど口にしたような活きのあるものではありませんでした。 或る日、親戚の家の御呼ばれで「ご希望の料理をなんなりと仰って下さい」と言われたので、サンマを所望されました。そちらの家老職などが考えますには、脂が多いものをさしあげて、もしもお体に触っては一大事と、十分に蒸したうえ、小骨を丁寧に抜いて、だしがらの様になった脂抜きのサンマを献上しましたので、それ程美味でなく、「サンマにしては焦げても居らず、これは一体何処から取り寄せたサンマ?」と訊ねられたところ、「日本橋河岸に御座ります」との返事に、すかさず、殿は「秋刀魚は目黒に限る」と申されたそうな。 落語の噺はそれ位にして、消防法が改正されて以来、わたし達は庭先、道路先で焚き火ができなくなりました。それが理由では無いのですが、調理器もいろいろ工夫され、煙の出ない魚焼き器がある時代になりました。子供の頃、肌色した七輪に金網を乗せ、団扇で扇ぎながら秋刀魚を焼いた記憶は遠く遠くなってしまいました。
2010.09.09
コメント(0)
-
御ン名えとせとら♪
幼名を牛若丸、遮那王と称した義経に、彼さえ知らない別の名が二つのあったことをご存知でしょうか?九条兼実の日記「玉葉」によれば、かねてより彼は義経の名乗りが、我が継嗣良経と同じであることに不満を持っていましたが、当時武威を誇る義経には摂関家の権威も通じず遠慮していました。文治元年に義経追討の院宣が下される至り、義経の名は一方的に”義行”と改名されました。忌まわしき名前を替えたものの當の義行の所在が皆目掴めないので、義行は”能隠”に通じるから露見し易いようにと、また一方的に”義顕”に替えられました。その事実が「吾妻鏡」と「玉葉」双方に記述されていて文治二年の十一月の候、義経が衣川で自刃したのは文治五年のことでした。 では女性の名前についてひとこと触れますと、太閤秀吉の正妻・北政所の幼名は”ねね”、ライバルの淀君のそれは”ちゃちゃ”。銀閣寺で著名な足利義政時代に流行ったをさな名が”ちゃちゃ”で、当時を記した「大上臈御名之事」に拠れば、貴族層のをさな名として人気のあった名が、あちゃ、かか、よよ、ちゃちゃなどが挙げてあります。やがてそれらが武家にも広がったようです。”ねね”も割りと流行った幼名で、秀吉の”ねね”宛の手紙には”おね””ね文字””おねね”等があります。北政所として出す公的な文書には貴族の正妻らしく”吉子”と記していたようですが、ねね自身が近親者に与えた手紙に”ね”と一字だけ記されたものがありますが、これは遠慮の要らない相手への用法だったとか。
2010.09.08
コメント(0)
-
モルガンお雪♪
明治37(1904)年1月26日「大阪朝日新聞」に拠れば、 <近ごろ女の果報を一身に集めたる加藤ゆきは、さる24日朝七条駅に着し、都ホテルより出迎えの馬車に新夫婦は同乗して同31番室に入りたり。花婿モルガンは多年の望みようやくかないて恋女を妻にしたるなれば、喜悦の色満面にあふれ、かたときもそばをはなれず、きげんをとりおれるさま、よその目にもいとしきほどなり。>そして翌午後3時に京を発ち、横浜港エルネンモン号に乗船、米国での結婚式に臨んだようです。これに先立ちお雪は、衣裳は河原町三条下がるの萬足屋こと岡六文にて数十点の注文をしたとか。 モーガン財閥は南北戦争の軍需景気と戦後の政府公社債などで巨万の富を築いたアメリカ屈指の財閥でしたが、1940年ロックフェラー財閥の挑戦を受け衰退した模様。此処に言うモーガンは、ジョージ・デニソン・モーガンのこと。 一方明治14(1881)年の京生れのモーガンお雪は、20歳のとき、祇園の芸妓しては破格の4万円という大金で身請けされました。アメリカ社交界では水が合わず、モルガン夫婦はパリに移り住みました。モルガンと死別した後、しばらく南フランスに居ましたが、昭和13(1938)年、京都に戻り晩年を過したとのことです。
2010.09.07
コメント(0)
-
秋に思う♪
昨年までは暗く寒い冬への序章である秋よりも、若葉艶めく希望の5月頃の方が好きでしたが、もう死することへの諦めがついたのか、感情の研ぎ澄まされる秋の方が再び好きになりそうな気がしてきました。 ところで、秋は”飽き”に通ずることから、古くは男女の情がさめて行くことに秋のイメージを被せていました。平家物語によれば、平清盛は白拍子の祇王を寵愛して止みませんでしたが、仏御前という別の白拍子にまた心奪われ、祇王を追い出そうとしました。その折、祇王が障子に書き残した歌、 萌えいづるも枯るるも同じ野辺の草 いづれか秋にあはではつべき秋(=飽き)に遭わないで果つべき=あなたも同じ運命になることでしょうの意味。 もう1つ、中国故事から拾うと、漢の武帝の寵愛を受けた班?女予(ハンショウジョ)が、趙飛燕の出現で見捨てられ、恨みの詩「怨歌行」に、その身を秋扇に例えています。そこでこんな句が浮びました。 籍だけの妻ですと言ふ秋扇ものが言い合えない夫婦になってしまったら、これほど哀れな晩年はないでしょう。夫たるもの奥さんを大切に。(注)人名の班?女予(ハンショウジョ)の女予は正しくは一字です。
2010.09.06
コメント(4)
-
ランナー=ドラマの脚本家♪
11日の名古屋市内を駆け抜けた女子マラソンは、ドラマ性に富んだレースでした。オリンピック金メダリストの野口みずきを筆頭に、渋井陽子、赤羽有紀子、尾崎好美など豪華なメンバーが勢ぞろい。最初は野口さんが積極的にタイムを上げて行かれた。これは大切なことで、今やアフリカ勢などのスピードは日本の比ではなく、国内1位を勝ち取ることも大切だけれど、世界を見据えて走っていただきたいなぁと念じながら観戦していました。当初のトップ組8名の中から徐々に遅れるランナーも。野口さんとてその例外ではなく、アナウンサーが執拗に思うくらい、野口さんの遅れを報じていました。ところが、レース後の彼女の言葉にあるように、膝の筋肉に異常があった為遅れていたものが、辛抱強く走っているうち、奇跡的に元通りに回復したということで、ここから野口さんの快進撃が始まりました。先述したように、国内1位も大切だけれど、このレースそのものの時間2時間23分台に近付けることに今回の参加者の意義があるという観点に立てば、野口さんの再度の1位、そしてスピードアップには大きな意味、貢献があったのでした。それから間もなくテレビ画面に赤いシャツ姿の外人が時々見え隠れし始めましたが、いっこうにその人物を採り上げて貰えないもどかしさが・・・。尾崎、中里のデッドヒートに割り込んで来たのが、赤色のロシアの選手・アルビナ・マヨロワシアさん。目にも明らかな速度の違い、彼女を追いかけることで記録の向上も期待できます。やがて日本のトップふたりは、互いに競り合いを始めましたが、尾崎さんの走る姿に体力の余裕が感じられ、事実、14秒もの差をつけて、尾崎さんが日本選手の一位を勝ち取られました。山下監督とのツーショットが印象的でした。 それにしても、最近稀なドラマ性に富んだレース展開。渋井、伊藤舞、野口、赤羽、宮内洋子と言った選手の頑張り、脚本の仕上げぶりに大いに感謝したのでした。
2010.09.05
コメント(0)
-
カマトトの由来♪
わたし達が時々使う言葉の中に、その由来を知らないものが沢山あります。興津要著の「おもしろ雑学日本語」(三笠書房)から面白いものを見つけました。 本題のカマトトに至るまで少々寄り道をしますが、蒲鉾は白身の魚をすり身にし、片栗粉や調味料を足し、練り上げたものを板にくっつけたものであることは周知の通りです。ところが蒲鉾は本来”竹輪”のことで、何故なら蒲の葉の形が鉾に似ているところから、最初は竹輪をさして蒲鉾と呼んでいました。嘉永6(1853)年発刊、斎藤彦麻呂の「傍廂」には、板に貼りつけた練り物に、その名を奪われたことが記述されているようです。これより前の正徳2(1712)年頃出版の「和漢三才図会」(和気仲安著)にも、竹輪が蒲鉾の源流と記されているようです。 余談はこの位にして、女性がわかりきっていることを、知らないふりして初心に見せることを”カマトト”と言いますが、この言葉は幕末頃、上方の遊里で使われたのが始まりとされています。万事承知していながら遊女が「かまぼこも魚(トト)か?」と問うたことに端を発していて、客の気を惹こうとする水商売の女性が、おぼこ娘のように見せる為の技巧的表現とされています。本日の付録は「酔いどれ女」。下の歌詞をご参照に・・・。 「酔いどれ女」1)私は女 悲しい女 夜毎むかしの いいこと振り返る 昨日は がぶ飲み 荒れ狂ってしまった どうせ昔に 戻れない そこらに転がってる 酔いどれ女2)私は女 陰気な女 悔いが身体に 仲良く居ついてる 今日はドライブ ヤケ運転しちゃった どうせ真面目に 暮らせない そこらに転がってる やくたい女3)私は女 ひねくれ女 いつも自分の 立場で甘えてる 明日はパチンコ 終了まで 打つだろう どうせコツコツ 努めない そこらに転がってる 不幸な女
2010.09.05
コメント(0)
-
野次合戦♪
森野宗明著「鎌倉・室町ことば百話」には”詞戦(コトバタタカイ)ー合戦前のパフォーマンス”という項があります。岩手県水沢市の裸祭を引き合いに、お互い悪態の限りを尽くし合う風習を述べて居られます。言わば野次合戦。「保元物語」には、後白河天皇方の大将源義朝と、その弟で祟徳上皇方に付いた為朝との間で交わされた野次合戦が描かれていて、義朝「(後白河天皇の)宣旨によって戦う者に対して抵抗するのはどういう訳?」と問います。為朝「(祟徳上皇の)院宣を受けて守っているのだ」と言い返します。 また「兄に向かって矢を引くとは運が尽きるぞ」と脅せば、「そういう兄者側は、上皇方に付いておられる父・為義に向かって矢を引いているではないか」とやり返します。 また「平家物語」には四国屋島の合戦において、平家代表・越中次郎兵衛盛嗣 対 伊勢三郎義盛の悪態応酬が描かれています。義盛「こちらの大将は清和天皇の後胤頼朝公の弟ぎみ九郎大夫判官(義経)様だぞ」盛嗣「うん 聞いたことがある。父が討たれて孤児になり、後には砂金売買商人のお供をしながら奥州まで落ちぶれて行ったあの小せがれか」義盛「無礼なことを申すな、そういうお前達こそ、木曽義仲との戦に敗れて北陸道をさまよい、物乞いをしながら逃げ帰った連中か」ざっとこんな調子で、戦に逸(ハヤ)る猛者たちもいらいらしながら、且つ笑っていたことでしょう。
2010.09.04
コメント(4)
-
灯台下暗し♪
奇跡って、滅多に遭遇するものではありませんが、現に嬉しい奇跡を体験しました。 藤原定家が編んだ「小倉百人一首」は、歌留多として意味も解らないまま、小学5年生ぐらいから親しんできました。学生時代や社会人になって数冊の解説書を読むようになり、父の遺したものを含め、10冊以上はあります。父が遺してくれたものの1つに、岩波文庫の「百人一首夕話」(尾崎雅嘉著、古川久校訂)の上巻を開いたとき、その中身の濃いさに感動しました。この日記でも1度だけ”菅家”について触れましたが、残念ながら下巻がどうしても見つかりませんでした。第一刷の刊行が昭和47年ですから、以降それほど再版されていないものと諦めながら、これはという古書店数件を回りましたが、見つかりません。いずれ岩波に頼み込まなくてはと思っていたところ、一昨日、10月号の初稿を出版社へ持参しての帰路、地元に唯1軒ある古本屋さんの中に入って探したところ、有りました、有りました。1988年第17刷発行の下巻(550円)が260円で吾が手に入ったのです。いや~こういう奇跡ならどんどん生じて欲しいものだと思った次第です。
2010.09.03
コメント(2)
-
働き者の家内♪
残暑と言うような生っちょろい陽気ではなく、酷暑の続く毎日ですが、そんな中、洗濯物を庭いっぱいに干した後は、ゴルフ場のキャディさんみたいな恰好して、家内は庭に降りたまま、長時間、庭仕事にかかります。わが家の敷地は100坪少々ですが、好きな樹木をどっさり植えた亡父の後始末とも言えそうです。、草取りだけでは済まず、樹木の枝を払ったり、落葉などの収集に余念ないようです。その結果として週2回のゴミ出しの折は、玄関近くに集積された幾つもの袋を生ゴミと一緒に出す仕事がこちらの役目。自転車の荷台に載せて2往復することも。 一方、毎日の朝食は私の仕事。仏壇にお水を供え、茶や湯を沸かしながら、コーヒーも淹れ、生野菜のサラダを用意、トーストが焼きあがる頃に家内を起こします。見合いの上、結婚した二人ですが、ま 仲は悪くない間柄だと思えるのはありがたいことで・・・。
2010.09.02
コメント(4)
-
斎藤美奈子の「男性誌探訪」♪
文芸評論家・斎藤美奈子さんの「男性誌探訪」は、2000年5月から’2年12月まで、朝日新聞社の週刊誌「アエラ」誌上で連載されたコラムで、採り上げられた雑誌は31誌。女性誌はファッション、コスメ、恋愛、結婚、料理、芸能、旅行、ダイエット、星占い・・・など、或る程度フォームが決まっていますが、男性誌はあらゆるジャンルを採り上げため、雛型を定め難い代物で、大きく分けると、a)名実一致型(最初から読者を男性に絞るもの。例 メンズファッション、紳士専用エロ誌)b)やもめサークル型(男性用と定めていないものの、結果的に男性読者が大数を占めるもの。例 釣り雑誌、鉄道マニア誌など)c)女性読者排除型(女性に嫌われそうな匂いを振り撒き、女性読者を締め出す。或る種の月刊誌・週刊誌) さて第1章の世の中を読むという侯の人気No1は「週刊ポスト」で知的パパとエロオヤジ共存雑誌。2番手が「プレジデント」研鑽・究明を主としたカラー色。3番手が、気分は社会主義的な資本主義雑誌の「日経トレンディ」。保守でオトナな日本のセレブ向きの「文芸春秋」、ご隠居の花見酒のような距離を置く「週刊新潮」、粗食を貫く硬派な経済誌「週刊東洋経済」、そしてチョコマカ生きる書生体質の次男坊的匂いのする「ダカーポ」の7誌。第2章の余暇を愉しむ(オフでも男はさぼりません)として、ナンバー、週刊ゴルフダイジェスト、サライ・・・ニュートンなど6誌。第3章のセンスを磨くコーナーでは、メンズクラブ、エスクァイア、ブルータスなど6誌。第4章の趣味に生きるでは、ヤングオート、ターザン、鉄道ジャーナル、丸(軍事雑誌)、山と渓谷など7誌。最終章の若さをことほぐジャンルでは、ホットドッグ・プレス(妄想全開、最後のナンパ誌)、週刊プレイボーイ、メンズノンノなど5誌。以上のように、異性から観る異性というものは神秘的、尊厳的、愛らしきものなのかも知れませんね。
2010.09.01
コメント(0)
全33件 (33件中 1-33件目)
1